6 / 54
Trigger Night
①始まりのとき
しおりを挟む
霞ヶ関の夜空は、上澄みだけがやけに静かだ。
この街には、見かけだけの楽園と腐敗臭のするごみ溜めが幾重にも折り重なっている。光がある場所には必ず陰ができ、その陰の中で、人は嘘を吐き、金を動かし、誰にも知られぬように“処理”をする。
榊原孝之は、そういう“処理する側”の人間だった。
警察庁警備局公安課に存在する秘匿場所・特別捜査管理部。そこは、霞が関の重厚なビルの十三階で、ぬるりとした深淵を覗き続ける役目を負った部署。
榊原はその特別捜査管理部の部長を務めるキャリア組の公安刑事であった。
特別捜査管理部の仕事は、汚れ仕事の多い公安の中でも、更に深淵に近づくような仕事だった。
無論、それは陽の当たる仕事ではない。光の届かぬ場所を這いずり回る、泥濘のような任務ばかりだった。
だが、榊原はそのぬかるみに慣れていた。
むしろ、その真っ黒なぬかるみの中以外での生き方を、忘れてしまった。
榊原は、泥に足を取られ、身動きできずにもがいている他人の姿を見るのは、嫌いではなかった。自分の掌一つで人の人生を転がす感触。搾り出す言葉一つで、目の前の人間が希望を見つけたり、絶望を噛みしめたりするその瞬間が、何よりも面白かった。
人を操る。それが、榊原孝之という男の“生き方”だった。
だからこそ。
公安が睨みをきかせる闇社会の裏側に、一人だけ“操りきれない”男の存在を聞いたとき、自分の中にじわりと興味が滲み出たのだった。
黒崎啓。
三十四歳。桃山組傘下、黒龍会の若頭。インテリヤクザという、いかにもな呼び名がぴったりと張りつく男。
生まれも育ちも東京。都内有数の進学校を卒業し、某有名大学で経済学を学び、いつしか“裏社会”に身を落とした。
その経歴には、普通では説明のつかない“歪み”がある。
なぜ一流企業に務めたり官僚になったりしなかったのか。
なぜ暴力の世界に、自ら潜っていったのか。
警察内部では、その素行について様々な噂が飛び交っていたが、榊原はどれも信用していなかった。
無意味だ。与えられた断片を鵜呑みにしても、真実には届かない。そんなことは、ずっと昔から知っている。
だから榊原は、今日、情報ではなく「現物」を見に来た。
直接会い、言葉を交わし、感情を読み、思考の癖を見抜く。それが一番早い。
────支配するには、まず知ることから始めなくてはならない。
金曜の夜。六本木の高層ビル、その最上階。
会員制の静かなラウンジで、榊原は革張りの椅子に背を預け、グラスをゆっくりと回していた。ワインは赤。安物ではないが、彼の舌には大した印象も残さない。
味などどうでもいい。
この場所は、“役者”としての衣装にすぎない。
やがて、時間ぴったりに扉が開いた。
革靴の足音が近づく。重くもなく、軽くもなく。威圧感も、媚びもない。堂々としながらも、決して人を突き放さない歩き方だった。
それだけで、榊原の中の警戒が一段階上がる。
「お待たせしました」
静かな声が響く。
その男は、ゆっくりとソファに腰を下ろした。
公安のデータで見たままの顔立ち。整った輪郭に、知性の滲む眼鏡。黒髪や艶やかで、きちんと整えられている。スーツも時計も一級品で、所作の一つひとつに、上品さがあった。
────なるほどね。君が、黒崎くんか。
榊原は黒崎に微笑みかける。いつも、どこかの誰かに向けている、人当たりの良い柔和な笑みを。
「今日は、時間を取ってくれてありがとう。黒崎くん」
声は穏やかに。目は柔らかく。
毒牙に気づかれぬよう、しっかりと隠して近寄る。
それが榊原のやり方だ。
「いえいえ。公安の方からお声がけいただいて、断るわけにはいきませんから」
黒崎も口元に弧を描く。だが、その声には妙な湿度があった。
言葉の節々に、じっとりと絡みつくような粘りがある。表面は清潔でも、その奥にうごめく何かが、じわりと滲んでいる。
社交辞令の世間話を五分十分したところで、相手の様子が少し変わった。本題に入れとやんわりと急かすように。
小さく息を吐いて、話を切り出す。
「さっそくだけど、君に聞きたいこがあってね」
榊原はワイングラスを傾けながら、静かに切り出した。
「桃山組が動かしてる新しい輸送ルート…………銃火器の密輸、かなり確かな筋から“君が鍵を握っている”と聞いてる」
「へぇ……?」
黒崎はグラスに口をつけることもなく、ただ視線を榊原の首元へ落とした。
ネクタイ。第一ボタンのわずかな開き。
露骨ではないが、目線が明確に“そこ”に向いている。
────視線がいやらしいね、君。
榊原は平然と笑みを保ちながら、黒崎の心の底を探った。
見下すでも、見上げるでもない。
なるほど。
この男は最初から、“同格”として自分を見ている。
いや────それ以上に、“自らを喰らおうとしてきる”感触すらあった。
「情報の価値は、理解しています」
黒崎はゆっくりと言った。
「だから、こちらとしても、それに見合う“対価”が欲しい」
そうくるのは想定内だ。
こちらもそれ相応のものを準備する手筈は整えている。
「そうだね。じゃあ、何を用意すればいい? こっちも情報? それとも金?」
「いえ。どちらでもありません」
ぴたり、と空気が張り詰める。
榊原は笑みを崩さず、あえて少しだけ首を傾けて訊いた。
「じゃあ、何が欲しいの?」
黒崎の目が、じっと榊原の喉を見つめた。
そして────口角を、わずかに上げて。
「身体です。────あなたの、ね」
一瞬。空気が静止した。
榊原は、グラスをテーブルに戻しながら、ふうと息を吐いた。
「…………ふふっ、なるほどね」
ゆっくりと視線を合わせ、にこりと笑う。
挑発とも、誘惑とも取れない。その中間に位置する笑みを向けてやる。
榊原は、何度もこういう交渉を乗り越えてきた。
────まったく。可愛げのない子だ。
──────だが、やはり面白い。
「その程度で君が喋ってくれるなら、安いものだよ。……黒崎くん」
にこりと笑いながら、榊原はろくに何も書いていない手帳を閉じ、グラスを持ち上げる。
「では、今日の零時。私のマンションでお待ちしています」
黒崎は一枚の紙切れを、テーブルの上を滑らせた。
そして静かに笑った。
その笑みに、榊原はまだ気づいていなかった。
それが“獲物を囲い込む側の笑み”であることに。
この街には、見かけだけの楽園と腐敗臭のするごみ溜めが幾重にも折り重なっている。光がある場所には必ず陰ができ、その陰の中で、人は嘘を吐き、金を動かし、誰にも知られぬように“処理”をする。
榊原孝之は、そういう“処理する側”の人間だった。
警察庁警備局公安課に存在する秘匿場所・特別捜査管理部。そこは、霞が関の重厚なビルの十三階で、ぬるりとした深淵を覗き続ける役目を負った部署。
榊原はその特別捜査管理部の部長を務めるキャリア組の公安刑事であった。
特別捜査管理部の仕事は、汚れ仕事の多い公安の中でも、更に深淵に近づくような仕事だった。
無論、それは陽の当たる仕事ではない。光の届かぬ場所を這いずり回る、泥濘のような任務ばかりだった。
だが、榊原はそのぬかるみに慣れていた。
むしろ、その真っ黒なぬかるみの中以外での生き方を、忘れてしまった。
榊原は、泥に足を取られ、身動きできずにもがいている他人の姿を見るのは、嫌いではなかった。自分の掌一つで人の人生を転がす感触。搾り出す言葉一つで、目の前の人間が希望を見つけたり、絶望を噛みしめたりするその瞬間が、何よりも面白かった。
人を操る。それが、榊原孝之という男の“生き方”だった。
だからこそ。
公安が睨みをきかせる闇社会の裏側に、一人だけ“操りきれない”男の存在を聞いたとき、自分の中にじわりと興味が滲み出たのだった。
黒崎啓。
三十四歳。桃山組傘下、黒龍会の若頭。インテリヤクザという、いかにもな呼び名がぴったりと張りつく男。
生まれも育ちも東京。都内有数の進学校を卒業し、某有名大学で経済学を学び、いつしか“裏社会”に身を落とした。
その経歴には、普通では説明のつかない“歪み”がある。
なぜ一流企業に務めたり官僚になったりしなかったのか。
なぜ暴力の世界に、自ら潜っていったのか。
警察内部では、その素行について様々な噂が飛び交っていたが、榊原はどれも信用していなかった。
無意味だ。与えられた断片を鵜呑みにしても、真実には届かない。そんなことは、ずっと昔から知っている。
だから榊原は、今日、情報ではなく「現物」を見に来た。
直接会い、言葉を交わし、感情を読み、思考の癖を見抜く。それが一番早い。
────支配するには、まず知ることから始めなくてはならない。
金曜の夜。六本木の高層ビル、その最上階。
会員制の静かなラウンジで、榊原は革張りの椅子に背を預け、グラスをゆっくりと回していた。ワインは赤。安物ではないが、彼の舌には大した印象も残さない。
味などどうでもいい。
この場所は、“役者”としての衣装にすぎない。
やがて、時間ぴったりに扉が開いた。
革靴の足音が近づく。重くもなく、軽くもなく。威圧感も、媚びもない。堂々としながらも、決して人を突き放さない歩き方だった。
それだけで、榊原の中の警戒が一段階上がる。
「お待たせしました」
静かな声が響く。
その男は、ゆっくりとソファに腰を下ろした。
公安のデータで見たままの顔立ち。整った輪郭に、知性の滲む眼鏡。黒髪や艶やかで、きちんと整えられている。スーツも時計も一級品で、所作の一つひとつに、上品さがあった。
────なるほどね。君が、黒崎くんか。
榊原は黒崎に微笑みかける。いつも、どこかの誰かに向けている、人当たりの良い柔和な笑みを。
「今日は、時間を取ってくれてありがとう。黒崎くん」
声は穏やかに。目は柔らかく。
毒牙に気づかれぬよう、しっかりと隠して近寄る。
それが榊原のやり方だ。
「いえいえ。公安の方からお声がけいただいて、断るわけにはいきませんから」
黒崎も口元に弧を描く。だが、その声には妙な湿度があった。
言葉の節々に、じっとりと絡みつくような粘りがある。表面は清潔でも、その奥にうごめく何かが、じわりと滲んでいる。
社交辞令の世間話を五分十分したところで、相手の様子が少し変わった。本題に入れとやんわりと急かすように。
小さく息を吐いて、話を切り出す。
「さっそくだけど、君に聞きたいこがあってね」
榊原はワイングラスを傾けながら、静かに切り出した。
「桃山組が動かしてる新しい輸送ルート…………銃火器の密輸、かなり確かな筋から“君が鍵を握っている”と聞いてる」
「へぇ……?」
黒崎はグラスに口をつけることもなく、ただ視線を榊原の首元へ落とした。
ネクタイ。第一ボタンのわずかな開き。
露骨ではないが、目線が明確に“そこ”に向いている。
────視線がいやらしいね、君。
榊原は平然と笑みを保ちながら、黒崎の心の底を探った。
見下すでも、見上げるでもない。
なるほど。
この男は最初から、“同格”として自分を見ている。
いや────それ以上に、“自らを喰らおうとしてきる”感触すらあった。
「情報の価値は、理解しています」
黒崎はゆっくりと言った。
「だから、こちらとしても、それに見合う“対価”が欲しい」
そうくるのは想定内だ。
こちらもそれ相応のものを準備する手筈は整えている。
「そうだね。じゃあ、何を用意すればいい? こっちも情報? それとも金?」
「いえ。どちらでもありません」
ぴたり、と空気が張り詰める。
榊原は笑みを崩さず、あえて少しだけ首を傾けて訊いた。
「じゃあ、何が欲しいの?」
黒崎の目が、じっと榊原の喉を見つめた。
そして────口角を、わずかに上げて。
「身体です。────あなたの、ね」
一瞬。空気が静止した。
榊原は、グラスをテーブルに戻しながら、ふうと息を吐いた。
「…………ふふっ、なるほどね」
ゆっくりと視線を合わせ、にこりと笑う。
挑発とも、誘惑とも取れない。その中間に位置する笑みを向けてやる。
榊原は、何度もこういう交渉を乗り越えてきた。
────まったく。可愛げのない子だ。
──────だが、やはり面白い。
「その程度で君が喋ってくれるなら、安いものだよ。……黒崎くん」
にこりと笑いながら、榊原はろくに何も書いていない手帳を閉じ、グラスを持ち上げる。
「では、今日の零時。私のマンションでお待ちしています」
黒崎は一枚の紙切れを、テーブルの上を滑らせた。
そして静かに笑った。
その笑みに、榊原はまだ気づいていなかった。
それが“獲物を囲い込む側の笑み”であることに。
55
あなたにおすすめの小説

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。
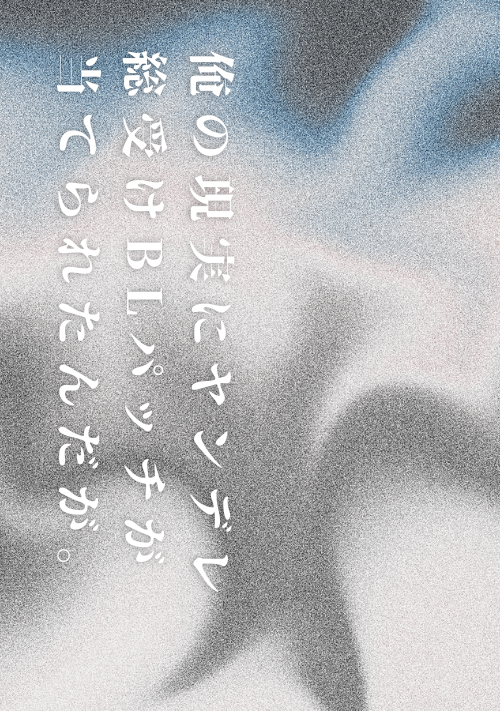

「大人扱いしていい?」〜純情当主、執務室で策士な従兄の『相性確認』にハメられる〜
中山(ほ)
BL
「ルイン、少し口開けてみて」
仕事終わりの静かな執務室。
差し入れの食事と、ポーションの瓶。
信頼していた従兄のトロンに誘われるまま、
ルインは「大人の相性確認」を始めることになる。




飼われる側って案外良いらしい。
なつ
BL
20XX年。人間と人外は共存することとなった。そう、僕は朝のニュースで見て知った。
向こうが地球の平和と引き換えに、僕達の中から選んで1匹につき1人、人間を飼うとかいう巫山戯た法を提案したようだけれど。
「まあ何も変わらない、はず…」
ちょっと視界に映る生き物の種類が増えるだけ。そう思ってた。
ほんとに。ほんとうに。
紫ヶ崎 那津(しがさき なつ)(22)
ブラック企業で働く最下層の男。顔立ちは悪くないが、不摂生で見る影もない。
変化を嫌い、現状維持を好む。
タルア=ミース(347)
職業不詳の人外、Swis(スウィズ)。お金持ち。
最初は可愛いペットとしか見ていなかったものの…?
2025/09/12 ★1000 Thank_You!!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















