24 / 28
本編
22.王弟妃と側妃の対面・後
しおりを挟む
「リオナ様……貴女は魂の蘇りを信じますか?」
唐突に、そう切り出した私へと目を細める側妃リオナ様。
私は間髪入れずに「今の私はその事を信じております」とさえ告げれば、次には驚きの表情を浮かべる側妃リオナ様の反応は当然。
なにせ、身分で人を差別する王弟妃クリスタが、「孤児の分際で……」と蔑む側妃リオナ様の元へと来訪すること自体があり得ない。
挙句、荒唐無稽な言葉さえ口にするのである。
「貴女は何を仰りたいの? とうとう『気でも違ったのか』と疑いたくなるような質問だわ」
側妃リオナ様の反応はごもっとも。
「貴女は本当にあの高慢な王弟妃殿下なのかしら?」
次には眉根を寄せて訝しむ。
ただ、彼女は初対面の頃より、素直に心情を表す性質がある。だから、私は敢えて肯定も否定もしない。
おそらく、まどろっこしいことが嫌いな側妃リオナ様のことだ。正直に思った言葉を口にするに違いない。
「王弟妃殿下……これまで私達は挨拶すらもまともに交わさず、互いの宮へと訪問することもありませんでした。いっさいの親交を持たなかった間柄では?」
「ええ、仰る通りです」
「それなのに今回の急な来訪です。王弟妃殿下、貴女の意図は何? 不可解な言葉を口にする貴女の魂胆もわからないわ」
怪しみながらも少し困惑した様子の側妃リオナ様。
本心では妹クリスタを嫌っていながらも、それでもこうして来訪を受け入れてくれる側妃リオナ様は、本来の性質が良いからだ。
人を生まれや身分で平然と差別する妹クリスタとは違い、やはり『出来たお方』だと思う。
「魂胆などありません、リオナ様。私は大好きな貴女様だかこそ打ち明けたい事がございます。よろしければ聞いて頂けませんか?」
自らを謙り、言葉を口にする私。
「……嘘っ?!」と驚愕する側妃リオナ様は言い放つ。
「まさか、あり得ない。本当に……貴女はあの高慢な王弟妃殿下なの?!」
余程に信じられないのか一瞬にして目を見開く。
「はい……とも言えますが、正直にお応えするならば実際は『いいえ』です」
「……意味がわからないわ」
「私の外見を見る限りは王弟妃ですが、中身は本人では……クリスタではありません。リオナお姉様……今すぐには信じられないかもしれませんが、私は貴女様の友人のヴィヴィアンです」
王妃時代の私がそう呼んだように、目の前の相手にも変わらずに「リオナお姉様」と呼んでみせる。
刹那、ヒュッと息を呑む側妃リオナ様がいる。
「まさかっ……」
珍しいことに、いつも冷静な側妃リオナ様の手から扇子が零れ落ちる。音を立てて床へ。
「リオナお姉様……扇子が落ちましたわ」
咄嗟に扇子を拾い上げる私は、その扇子を感慨深げに見つめる。
◇
白銀色を主にして蒼い小花が描かれた美しい扇子。この色は私の髪色と瞳を表す。
この世に2つしかない扇子は、かつて王妃であった私が「友好の証し」として側妃リオナ様へと贈った物だ。
私と揃いの扇子は特注品。
誰が贈った物であるのか明確にする為に“王妃印”が刻印され、相手の真名さえ刻んである。それは側妃リオナ様が『王妃ヴィヴィアンの大切な友人であること』を暗に伝える為のものでもある。
孤児という生まれのせいで、側妃リオナ様が見下されないようにする為の私なりの配慮でもある。
かつては先代国王レイモンド陛下の寵妃であり、今も表向きは国王キーラン様の側妃の立場を頂いているリオナ様。それでも妹クリスタのように差別する人たちは無くならない。
皆無にはならない。
だからこその王妃と揃いの扇子。
即ち、『側妃は王妃と懇意である』と遠回しに告げることで、側妃リオナ様の立場を『少しでも守りたい』との私なりの配慮。
当然、妹クリスタがこの事を知るはずがない。
「私が差し上げた扇子を今だに使ってくださっているのですね? この柄の部分にはお姉様の真名が記され、私の刻印もハッキリと彫られている。とても状態も良いし……」
今でも状態の良い扇子は、それが大切に使われていたことを物語る。
ーーーありがとう、リオナお姉様。嬉しい。
胸が熱くなる。自然と喜びの涙を流す私を食い入るように見つめる側妃リオナ様。
「これは……私には大切な宝物ですの。今となっては私の大切なお方の形見でもあるわ。とても……とても大切な物なのよ」
そう零す側妃リオナ様。
「ありがとう、リオナお姉様。これを大切に思ってくださるのが嬉しい……」
ーーーやはり、この方は私を裏切らない。
それが心から嬉しい。
◇
王家と呼ばれる世界は、外界とは一線を画する稀な環境。誰もが容易に入れる世界ではない。自分の家族ですら自由気ままには会えない。
ある意味、閉ざされた世界と言えるかもしれない。
ーーーだからなのかもしれない。
私と側妃リオナ様は同じ〈王宮〉に暮らす者同士で寄り添い合う。幸いにも気が合い、心を許せるほどに打ち解けた。
友情も深めることもできた。
私は側妃リオナ様の人となりを心から敬愛していたし、それは彼女も然り。
ーーー私の大切な友人。
側妃リオナ様は〈王宮〉においての私には、家族のような存在でもあり、もっといえば頼れる姉のような存在でもある。
彼女なら信じ難い私の蘇りの話も、きっと信じてくれるはずだと疑わない。だから、素直に打ち明けようと思った私。
ーーーきっと大丈夫。
内心ではドキドキしていながらも告げた私を実際に受け入れてくれた側妃リオナ様。すぐに人払いさえしてくれたのだ。
「貴女様が本当に私の大切なヴィヴィアン様なら事は慎重にいかないといけないわ。声は落として話しましょう。もっとも、誰の脅威にもならないはずの私を警戒する者はいないでしょうけど……」
含みのある言い方をする側妃リオナ。
その意味はのちにわかる。重大な意味を持っている。
私としても周囲を警戒するに越したことはない。
それに今回の訪問には、王弟レイモンド殿下が私の身を案じるあまり、彼の守護騎士であるルイスを護衛に付けてくれている。
彼は目立たないように物静かに待機している。まるで空気のような存在。
2人だけの席を設けてもらった私は“ある物”を持参し、側妃リオナ様へと手渡す。
おかげで私の存在は決定的なものとなり、瞬時に側妃リオナ様の腕が伸ばされ、私をしっかりと抱き締める。
「ヴィヴィアン様……貴女なのね? 本当に貴女なのね? 嗚呼っー……!」
「……はい。リオナお姉様。私ですわ。ヴィヴィアンですわ」
溢れる涙を拭い取ることさえ忘れ、私を抱き締めたまま離さない側妃リオナ様。
まるで生きていることを確実に確かめる為なのか、いっそう力がこもる。
深く、互いの体温が伝わる。
「ヴィヴィアン様、私は貴女が存在していることが何よりも嬉しいの。この世に神が存在するなら、この奇跡を感謝しないではいられないわ。貴女が生きていることが嬉しいの。ヴィヴィアン様、大好き……!」
側妃リオナ様の偽りのない言葉が心に沁みる私。
ーーーこうして私を想ってくれているお方がいる。
それがとても心強い。
どちらからともなく零れた互いの言葉が合わさる。
「……再び出逢えたことに感謝します……」
しまいには天を仰ぐ側妃リオナがいる。
◇
実は私が手土産に持参した“ある物“は金平糖。
生前、側妃リオナ様とはよくお茶をした仲でもある。だから、彼女の好む砂糖菓子を持参する私は、美しい菓子折り詰められた色とりどりの金平糖を差し出す。
これには驚嘆する側妃リオナ様。
「リオナお姉様の大好きな金平糖をお持ちしました」
「……っ?!」
その事が決定的になった事は言うまでもない。
側妃リオナ様にとっての金平糖は、先代国王レイモンド陛下に拾われた彼女が、初めて口にした甘い砂糖菓子。
元は孤児の側妃リオナ様が市井の路地で行き倒れ、食べ物さえ口にできないほどに衰弱していた当時。
「これなら食べれないだろうか?」
幼い少女が自分から口にするまで、根気よく粘り続ける先代国王レイモンド陛下。
「頼むから何でも良いから口にしておくれ。君は生きるんだ。死なせるものか……」
先代国王レイモンド陛下が、手ずから彼女の口へとそっと金平糖を含ませたのだ。
甲斐甲斐しく、自ら世話を焼く先代国王レイモンド陛下の優しさと、初めて口にした甘い砂糖菓子に命を救われた側妃リオナ様。
「私の心に深く深く沁みたの……」
それ以来、彼女は金平糖が大好き。
「どれほど豪華な食べ物より、私にはレイモンド陛下が自ら食べさせて下さった金平糖が何よりもご馳走なのよ」
ふふっ……と嬉しそうに話す側妃リオナ様。
柔らかで美しい花笑みを溢れさせる。おかげで心からの言葉だとわかる。
先代国王レイモンド陛下には、娘のような存在のリオナ様だったと訊く。ただ、側妃リオナ様の屈託のない花笑みを見る限り、心から先代国王レイモンド陛下を愛していたように思える。
当時の私はそう感じた。
ただ、そうは言っても側妃リオナ様の心の奥底の想いは誰にも推し量れない。おかげで先代国王レイモンド陛下を失った彼女が何を思い、どのような行動に出るかは……彼女にしかわからない。
唐突に、そう切り出した私へと目を細める側妃リオナ様。
私は間髪入れずに「今の私はその事を信じております」とさえ告げれば、次には驚きの表情を浮かべる側妃リオナ様の反応は当然。
なにせ、身分で人を差別する王弟妃クリスタが、「孤児の分際で……」と蔑む側妃リオナ様の元へと来訪すること自体があり得ない。
挙句、荒唐無稽な言葉さえ口にするのである。
「貴女は何を仰りたいの? とうとう『気でも違ったのか』と疑いたくなるような質問だわ」
側妃リオナ様の反応はごもっとも。
「貴女は本当にあの高慢な王弟妃殿下なのかしら?」
次には眉根を寄せて訝しむ。
ただ、彼女は初対面の頃より、素直に心情を表す性質がある。だから、私は敢えて肯定も否定もしない。
おそらく、まどろっこしいことが嫌いな側妃リオナ様のことだ。正直に思った言葉を口にするに違いない。
「王弟妃殿下……これまで私達は挨拶すらもまともに交わさず、互いの宮へと訪問することもありませんでした。いっさいの親交を持たなかった間柄では?」
「ええ、仰る通りです」
「それなのに今回の急な来訪です。王弟妃殿下、貴女の意図は何? 不可解な言葉を口にする貴女の魂胆もわからないわ」
怪しみながらも少し困惑した様子の側妃リオナ様。
本心では妹クリスタを嫌っていながらも、それでもこうして来訪を受け入れてくれる側妃リオナ様は、本来の性質が良いからだ。
人を生まれや身分で平然と差別する妹クリスタとは違い、やはり『出来たお方』だと思う。
「魂胆などありません、リオナ様。私は大好きな貴女様だかこそ打ち明けたい事がございます。よろしければ聞いて頂けませんか?」
自らを謙り、言葉を口にする私。
「……嘘っ?!」と驚愕する側妃リオナ様は言い放つ。
「まさか、あり得ない。本当に……貴女はあの高慢な王弟妃殿下なの?!」
余程に信じられないのか一瞬にして目を見開く。
「はい……とも言えますが、正直にお応えするならば実際は『いいえ』です」
「……意味がわからないわ」
「私の外見を見る限りは王弟妃ですが、中身は本人では……クリスタではありません。リオナお姉様……今すぐには信じられないかもしれませんが、私は貴女様の友人のヴィヴィアンです」
王妃時代の私がそう呼んだように、目の前の相手にも変わらずに「リオナお姉様」と呼んでみせる。
刹那、ヒュッと息を呑む側妃リオナ様がいる。
「まさかっ……」
珍しいことに、いつも冷静な側妃リオナ様の手から扇子が零れ落ちる。音を立てて床へ。
「リオナお姉様……扇子が落ちましたわ」
咄嗟に扇子を拾い上げる私は、その扇子を感慨深げに見つめる。
◇
白銀色を主にして蒼い小花が描かれた美しい扇子。この色は私の髪色と瞳を表す。
この世に2つしかない扇子は、かつて王妃であった私が「友好の証し」として側妃リオナ様へと贈った物だ。
私と揃いの扇子は特注品。
誰が贈った物であるのか明確にする為に“王妃印”が刻印され、相手の真名さえ刻んである。それは側妃リオナ様が『王妃ヴィヴィアンの大切な友人であること』を暗に伝える為のものでもある。
孤児という生まれのせいで、側妃リオナ様が見下されないようにする為の私なりの配慮でもある。
かつては先代国王レイモンド陛下の寵妃であり、今も表向きは国王キーラン様の側妃の立場を頂いているリオナ様。それでも妹クリスタのように差別する人たちは無くならない。
皆無にはならない。
だからこその王妃と揃いの扇子。
即ち、『側妃は王妃と懇意である』と遠回しに告げることで、側妃リオナ様の立場を『少しでも守りたい』との私なりの配慮。
当然、妹クリスタがこの事を知るはずがない。
「私が差し上げた扇子を今だに使ってくださっているのですね? この柄の部分にはお姉様の真名が記され、私の刻印もハッキリと彫られている。とても状態も良いし……」
今でも状態の良い扇子は、それが大切に使われていたことを物語る。
ーーーありがとう、リオナお姉様。嬉しい。
胸が熱くなる。自然と喜びの涙を流す私を食い入るように見つめる側妃リオナ様。
「これは……私には大切な宝物ですの。今となっては私の大切なお方の形見でもあるわ。とても……とても大切な物なのよ」
そう零す側妃リオナ様。
「ありがとう、リオナお姉様。これを大切に思ってくださるのが嬉しい……」
ーーーやはり、この方は私を裏切らない。
それが心から嬉しい。
◇
王家と呼ばれる世界は、外界とは一線を画する稀な環境。誰もが容易に入れる世界ではない。自分の家族ですら自由気ままには会えない。
ある意味、閉ざされた世界と言えるかもしれない。
ーーーだからなのかもしれない。
私と側妃リオナ様は同じ〈王宮〉に暮らす者同士で寄り添い合う。幸いにも気が合い、心を許せるほどに打ち解けた。
友情も深めることもできた。
私は側妃リオナ様の人となりを心から敬愛していたし、それは彼女も然り。
ーーー私の大切な友人。
側妃リオナ様は〈王宮〉においての私には、家族のような存在でもあり、もっといえば頼れる姉のような存在でもある。
彼女なら信じ難い私の蘇りの話も、きっと信じてくれるはずだと疑わない。だから、素直に打ち明けようと思った私。
ーーーきっと大丈夫。
内心ではドキドキしていながらも告げた私を実際に受け入れてくれた側妃リオナ様。すぐに人払いさえしてくれたのだ。
「貴女様が本当に私の大切なヴィヴィアン様なら事は慎重にいかないといけないわ。声は落として話しましょう。もっとも、誰の脅威にもならないはずの私を警戒する者はいないでしょうけど……」
含みのある言い方をする側妃リオナ。
その意味はのちにわかる。重大な意味を持っている。
私としても周囲を警戒するに越したことはない。
それに今回の訪問には、王弟レイモンド殿下が私の身を案じるあまり、彼の守護騎士であるルイスを護衛に付けてくれている。
彼は目立たないように物静かに待機している。まるで空気のような存在。
2人だけの席を設けてもらった私は“ある物”を持参し、側妃リオナ様へと手渡す。
おかげで私の存在は決定的なものとなり、瞬時に側妃リオナ様の腕が伸ばされ、私をしっかりと抱き締める。
「ヴィヴィアン様……貴女なのね? 本当に貴女なのね? 嗚呼っー……!」
「……はい。リオナお姉様。私ですわ。ヴィヴィアンですわ」
溢れる涙を拭い取ることさえ忘れ、私を抱き締めたまま離さない側妃リオナ様。
まるで生きていることを確実に確かめる為なのか、いっそう力がこもる。
深く、互いの体温が伝わる。
「ヴィヴィアン様、私は貴女が存在していることが何よりも嬉しいの。この世に神が存在するなら、この奇跡を感謝しないではいられないわ。貴女が生きていることが嬉しいの。ヴィヴィアン様、大好き……!」
側妃リオナ様の偽りのない言葉が心に沁みる私。
ーーーこうして私を想ってくれているお方がいる。
それがとても心強い。
どちらからともなく零れた互いの言葉が合わさる。
「……再び出逢えたことに感謝します……」
しまいには天を仰ぐ側妃リオナがいる。
◇
実は私が手土産に持参した“ある物“は金平糖。
生前、側妃リオナ様とはよくお茶をした仲でもある。だから、彼女の好む砂糖菓子を持参する私は、美しい菓子折り詰められた色とりどりの金平糖を差し出す。
これには驚嘆する側妃リオナ様。
「リオナお姉様の大好きな金平糖をお持ちしました」
「……っ?!」
その事が決定的になった事は言うまでもない。
側妃リオナ様にとっての金平糖は、先代国王レイモンド陛下に拾われた彼女が、初めて口にした甘い砂糖菓子。
元は孤児の側妃リオナ様が市井の路地で行き倒れ、食べ物さえ口にできないほどに衰弱していた当時。
「これなら食べれないだろうか?」
幼い少女が自分から口にするまで、根気よく粘り続ける先代国王レイモンド陛下。
「頼むから何でも良いから口にしておくれ。君は生きるんだ。死なせるものか……」
先代国王レイモンド陛下が、手ずから彼女の口へとそっと金平糖を含ませたのだ。
甲斐甲斐しく、自ら世話を焼く先代国王レイモンド陛下の優しさと、初めて口にした甘い砂糖菓子に命を救われた側妃リオナ様。
「私の心に深く深く沁みたの……」
それ以来、彼女は金平糖が大好き。
「どれほど豪華な食べ物より、私にはレイモンド陛下が自ら食べさせて下さった金平糖が何よりもご馳走なのよ」
ふふっ……と嬉しそうに話す側妃リオナ様。
柔らかで美しい花笑みを溢れさせる。おかげで心からの言葉だとわかる。
先代国王レイモンド陛下には、娘のような存在のリオナ様だったと訊く。ただ、側妃リオナ様の屈託のない花笑みを見る限り、心から先代国王レイモンド陛下を愛していたように思える。
当時の私はそう感じた。
ただ、そうは言っても側妃リオナ様の心の奥底の想いは誰にも推し量れない。おかげで先代国王レイモンド陛下を失った彼女が何を思い、どのような行動に出るかは……彼女にしかわからない。
80
あなたにおすすめの小説

白い結婚の行方
宵森みなと
恋愛
「この結婚は、形式だけ。三年経ったら、離縁して養子縁組みをして欲しい。」
そう告げられたのは、まだ十二歳だった。
名門マイラス侯爵家の跡取りと、書面上だけの「夫婦」になるという取り決め。
愛もなく、未来も誓わず、ただ家と家の都合で交わされた契約だが、彼女にも目的はあった。
この白い結婚の意味を誰より彼女は、知っていた。自らの運命をどう選択するのか、彼女自身に委ねられていた。
冷静で、理知的で、どこか人を寄せつけない彼女。
誰もが「大人びている」と評した少女の胸の奥には、小さな祈りが宿っていた。
結婚に興味などなかったはずの青年も、少女との出会いと別れ、後悔を経て、再び運命を掴もうと足掻く。
これは、名ばかりの「夫婦」から始まった二人の物語。
偽りの契りが、やがて確かな絆へと変わるまで。
交差する記憶、巻き戻る時間、二度目の選択――。
真実の愛とは何かを、問いかける静かなる運命の物語。
──三年後、彼女の選択は、彼らは本当に“夫婦”になれるのだろうか?

【完結】お飾りの妻からの挑戦状
おのまとぺ
恋愛
公爵家から王家へと嫁いできたデイジー・シャトワーズ。待ちに待った旦那様との顔合わせ、王太子セオドア・ハミルトンが放った言葉に立ち会った使用人たちの顔は強張った。
「君はお飾りの妻だ。装飾品として慎ましく生きろ」
しかし、当のデイジーは不躾な挨拶を笑顔で受け止める。二人のドタバタ生活は心配する周囲を巻き込んで、やがて誰も予想しなかった展開へ……
◇表紙はノーコピーライトガール様より拝借しています
◇全18話で完結予定

『影の夫人とガラスの花嫁』
柴田はつみ
恋愛
公爵カルロスの後妻として嫁いだシャルロットは、
結婚初日から気づいていた。
夫は優しい。
礼儀正しく、決して冷たくはない。
けれど──どこか遠い。
夜会で向けられる微笑みの奥には、
亡き前妻エリザベラの影が静かに揺れていた。
社交界は囁く。
「公爵さまは、今も前妻を想っているのだわ」
「後妻は所詮、影の夫人よ」
その言葉に胸が痛む。
けれどシャルロットは自分に言い聞かせた。
──これは政略婚。
愛を求めてはいけない、と。
そんなある日、彼女はカルロスの書斎で
“あり得ない手紙”を見つけてしまう。
『愛しいカルロスへ。
私は必ずあなたのもとへ戻るわ。
エリザベラ』
……前妻は、本当に死んだのだろうか?
噂、沈黙、誤解、そして夫の隠す真実。
揺れ動く心のまま、シャルロットは
“ガラスの花嫁”のように繊細にひび割れていく。
しかし、前妻の影が完全に姿を現したとき、
カルロスの静かな愛がようやく溢れ出す。
「影なんて、最初からいない。
見ていたのは……ずっと君だけだった」
消えた指輪、隠された手紙、閉ざされた書庫──
すべての謎が解けたとき、
影に怯えていた花嫁は光を手に入れる。
切なく、美しく、そして必ず幸せになる後妻ロマンス。
愛に触れたとき、ガラスは光へと変わる

追放された悪役令嬢はシングルマザー
ララ
恋愛
神様の手違いで死んでしまった主人公。第二の人生を幸せに生きてほしいと言われ転生するも何と転生先は悪役令嬢。
断罪回避に奮闘するも失敗。
国外追放先で国王の子を孕んでいることに気がつく。
この子は私の子よ!守ってみせるわ。
1人、子を育てる決心をする。
そんな彼女を暖かく見守る人たち。彼女を愛するもの。
さまざまな思惑が蠢く中彼女の掴み取る未来はいかに‥‥
ーーーー
完結確約 9話完結です。
短編のくくりですが10000字ちょっとで少し短いです。

【コミカライズ決定】愛されない皇妃~最強の母になります!~
椿蛍
ファンタジー
【コミカライズ決定の情報が解禁されました】
※レーベル名、漫画家様はのちほどお知らせいたします。
※配信後は引き下げとなりますので、ご注意くださいませ。
愛されない皇妃『ユリアナ』
やがて、皇帝に愛される寵妃『クリスティナ』にすべてを奪われる運命にある。
夫も子どもも――そして、皇妃の地位。
最後は嫉妬に狂いクリスティナを殺そうとした罪によって処刑されてしまう。
けれど、そこからが問題だ。
皇帝一家は人々を虐げ、『悪逆皇帝一家』と呼ばれるようになる。
そして、最後は大魔女に悪い皇帝一家が討伐されて終わるのだけど……
皇帝一家を倒した大魔女。
大魔女の私が、皇妃になるなんて、どういうこと!?
※表紙は作成者様からお借りしてます。
※他サイト様に掲載しております。

婚約破棄されたので、前世の知識で無双しますね?
ほーみ
恋愛
「……よって、君との婚約は破棄させてもらう!」
華やかな舞踏会の最中、婚約者である王太子アルベルト様が高らかに宣言した。
目の前には、涙ぐみながら私を見つめる金髪碧眼の美しい令嬢。確か侯爵家の三女、リリア・フォン・クラウゼルだったかしら。
──あら、デジャヴ?
「……なるほど」

あなたの愛が正しいわ
来須みかん
恋愛
旧題:あなたの愛が正しいわ~夫が私の悪口を言っていたので理想の妻になってあげたのに、どうしてそんな顔をするの?~
夫と一緒に訪れた夜会で、夫が男友達に私の悪口を言っているのを聞いてしまった。そのことをきっかけに、私は夫の理想の妻になることを決める。それまで夫を心の底から愛して尽くしていたけど、それがうっとうしかったそうだ。夫に付きまとうのをやめた私は、生まれ変わったように清々しい気分になっていた。
一方、夫は妻の変化に戸惑い、誤解があったことに気がつき、自分の今までの酷い態度を謝ったが、妻は美しい笑みを浮かべてこういった。
「いいえ、間違っていたのは私のほう。あなたの愛が正しいわ」
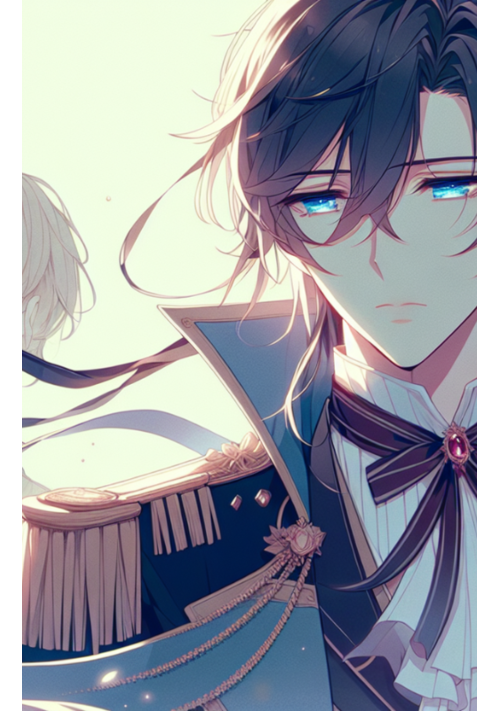
私たちの離婚幸福論
桔梗
ファンタジー
ヴェルディア帝国の皇后として、順風満帆な人生を歩んでいたルシェル。
しかし、彼女の平穏な日々は、ノアの突然の記憶喪失によって崩れ去る。
彼はルシェルとの記憶だけを失い、代わりに”愛する女性”としてイザベルを迎え入れたのだった。
信じていた愛が消え、冷たく突き放されるルシェル。
だがそこに、隣国アンダルシア王国の皇太子ゼノンが現れ、驚くべき提案を持ちかける。
それは救済か、あるいは——
真実を覆う闇の中、ルシェルの新たな運命が幕を開ける。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















