12 / 28
12
しおりを挟む
「シルビア、箸を止めろ。これは命令だ」
昼下がりの王城。
風光明媚なテラス席で、ルーカス殿下が不機嫌そうにナイフを置いた。
目の前には、一流シェフが腕を振るった豪華なフルコース。
しかし、私の手元にあるのはフォークではなく、愛用の万年筆とメモ帳だった。
「命令されても困ります。今、脳内で『王城の食材廃棄率』の計算が佳境に入っているのです」
私はメモ帳に素早く数式を書き殴りながら答えた。
「この前菜のテリーヌ、原価率は約三割ですが、盛り付けに使われている飾り野菜の廃棄量が多すぎます。これをスープの出汁に回せば、年間で金貨五十枚の削減になりますよ」
「……あのな」
殿下が深い溜息をついた。
「俺が言いたいのは、そういうことじゃない。今日は天気がいい。風も心地よい。そして目の前には美しい女(お前)がいる。……普通、ここは愛を語らう場面だろう?」
「愛? 愛で腹は膨れませんし、愛で野菜の皮は剥けません」
私はバッサリと切り捨てた。
「それに殿下、貴方様は勘違いをされています」
「なんだ?」
「私は貴方様の『恋人』ではなく『筆頭秘書官』です。就業時間内に愛を語らうのは職務怠慢、給料泥棒の所業です」
「今は休憩時間だと言っただろう!」
殿下がガチャンとグラスを置いた。
「全く……お前という奴は、隙あらば仕事を持ち込む。色気より食い気、食い気より金か?」
「当然です。金貨は裏切りませんから」
私は涼しい顔でサラダを口に運んだ。
……悔しいけれど、ドレッシングが絶品だ。これのレシピを解析して、瓶詰めにして売れば儲かるかもしれない。
「はぁ……。まあいい、お前らしいと言えばお前らしい」
殿下は諦めたように苦笑し、手元の箱をスッと差し出した。
「ほら、やるよ」
「何ですか? 新しい領収書の束ですか?」
「違う。……プレゼントだ」
殿下が少し照れ臭そうに視線を逸らす。
私は眉をひそめつつ、箱を開けた。
中に入っていたのは、透き通るような青い宝石が埋め込まれた、銀細工のネックレスだった。
「……!」
「どうだ。お前の瞳と同じ色だろう。城下町の宝石商が『最高級品が入った』とうるさいから、買ってやった」
美しい。
宝石の知識がある私でも、これほどの純度のサファイアは見たことがない。
加工技術も超一流。王国の国宝級に匹敵する代物だ。
普通の令嬢なら、「まあ素敵! 一生大事にします!」と涙を流して喜ぶ場面だろう。
しかし、私はシルビア・ランカスター。
悪役令嬢であり、守銭奴であり、プロの事務屋だ。
私は宝石を光に透かし、三秒で鑑定を下した。
「推定価格、金貨五千枚ですね」
「……」
「デザイン料込みで六千枚といったところでしょうか。殿下、まさか定価で買っていませんよね? あの店主なら『殿下価格』で二割増しにしている可能性があります」
「……お前なぁ」
殿下がこめかみをピキピキと引きつらせた。
「そこは『ありがとう』でいいだろうが! なぜ即座に査定に入るんだ!」
「職業病です。それに、こんな高価なものを頂く理由は? まさか、私の給料から天引きされるのでは?」
「されるか! ただの……その、日頃の感謝だ。それをつけて、来週の舞踏会に出ろ」
「舞踏会?」
私は手を止めた。
「ああ。隣国との国交樹立記念パーティーだ。俺のパートナーとして出席しろ」
「お断りします」
即答だった。
「私は裏方です。華やかな場所は似合いませんし、ドレスを着て愛想笑いをする時間があれば、書類を百枚処理できます」
「拒否権はない。これは『公務』だ」
殿下はニヤリと笑った。
「それに、今回の舞踏会には……お前の古巣、ランカスター王国からも使節団が来るらしいぞ」
その言葉に、私の動きが止まった。
「……王国から?」
「ああ。どうやら向こうの国王が、経済危機の支援を求めて、なりふり構わず頭を下げに来るらしい。……例のバカ王子も同行するそうだ」
レイド殿下が、来る。
しかも、私が働くこの帝国へ。
「……面白くなってきましたね」
私はゆっくりとナイフを置いた。
「つまり、私は元婚約者に対し、『貴方が捨てた女は、今や大国の皇太子の隣でこんなに輝いていますよ』と見せつける役回り、ということですか?」
「そういうことだ。最高の復讐だろう?」
殿下は楽しそうにワインを揺らした。
「俺の横に立ち、圧倒的な格の違いを見せつけてやれ。あいつが二度と、お前を連れ戻そうなどという寝言を吐けないようにな」
なるほど。
それは確かに、悪役令嬢として最高の晴れ舞台だ。
それに、私の作成した『帝国経済圏構想』を、王国の古臭い貴族たちにプレゼンする絶好の機会でもある。
「承知いたしました。その公務、お引き受けします」
私はネックレスを手に取り、首に当ててみた。
ひんやりとした宝石の感触が、戦意を高揚させる。
「ただし、ドレス代と美容代は経費で落とさせていただきます」
「好きにしろ。世界一美しくしてこい」
「もちろんです。元婚約者が腰を抜かし、マリア嬢が悔し涙で脱水症状になるくらい、完璧に仕上げてみせます」
私は不敵に微笑んだ。
「……怖いな、お前のその笑顔は」
「あら、頼もしいとおっしゃってください」
「違いない」
殿下は満足げに笑い、私の皿に肉を一枚乗せてくれた。
「食え。戦の前には栄養が必要だ」
「はい。……あ、殿下。口元にソースがついていますよ」
私は無意識にナプキンを取り、殿下の口元を拭ってしまった。
拭いてから、ハッと気づく。
これは秘書の仕事というより、もっと親密な……。
殿下が驚いたように私を見つめている。
金色の瞳が、至近距離で揺れている。
「……すまん」
「い、いえ。不潔だと衛生局から指導が入りますから。他意はありません」
私は慌てて言い訳をして、視線を逸らした。
心臓が、少しだけ早鐘を打っている気がする。
これはきっと、食後のカフェインのせいだ。そうに違いない。
「……シルビア」
「なんですか」
「やはりお前は、俺の妃に……」
「聞こえません。今はランチタイムです。私語は慎んでください」
私は強引に話を打ち切り、パンを口に詰め込んだ。
殿下は喉の奥でククッと笑い、それ以上は何も言わなかった。
テラスに吹く風が、少しだけ甘い香りを運んできた気がした。
だが、甘い雰囲気に浸っている場合ではない。
来週は決戦だ。
私は頭の中で、舞踏会の衣装予算と、レイド殿下への精神的ダメージ計算式を同時に組み立て始めた。
(待っていらっしゃい、元殿下。私が本当の『高嶺の花』であることを、嫌というほど教えてあげるわ)
私の瞳の中で、青い宝石が冷たく、鋭く輝いた。
昼下がりの王城。
風光明媚なテラス席で、ルーカス殿下が不機嫌そうにナイフを置いた。
目の前には、一流シェフが腕を振るった豪華なフルコース。
しかし、私の手元にあるのはフォークではなく、愛用の万年筆とメモ帳だった。
「命令されても困ります。今、脳内で『王城の食材廃棄率』の計算が佳境に入っているのです」
私はメモ帳に素早く数式を書き殴りながら答えた。
「この前菜のテリーヌ、原価率は約三割ですが、盛り付けに使われている飾り野菜の廃棄量が多すぎます。これをスープの出汁に回せば、年間で金貨五十枚の削減になりますよ」
「……あのな」
殿下が深い溜息をついた。
「俺が言いたいのは、そういうことじゃない。今日は天気がいい。風も心地よい。そして目の前には美しい女(お前)がいる。……普通、ここは愛を語らう場面だろう?」
「愛? 愛で腹は膨れませんし、愛で野菜の皮は剥けません」
私はバッサリと切り捨てた。
「それに殿下、貴方様は勘違いをされています」
「なんだ?」
「私は貴方様の『恋人』ではなく『筆頭秘書官』です。就業時間内に愛を語らうのは職務怠慢、給料泥棒の所業です」
「今は休憩時間だと言っただろう!」
殿下がガチャンとグラスを置いた。
「全く……お前という奴は、隙あらば仕事を持ち込む。色気より食い気、食い気より金か?」
「当然です。金貨は裏切りませんから」
私は涼しい顔でサラダを口に運んだ。
……悔しいけれど、ドレッシングが絶品だ。これのレシピを解析して、瓶詰めにして売れば儲かるかもしれない。
「はぁ……。まあいい、お前らしいと言えばお前らしい」
殿下は諦めたように苦笑し、手元の箱をスッと差し出した。
「ほら、やるよ」
「何ですか? 新しい領収書の束ですか?」
「違う。……プレゼントだ」
殿下が少し照れ臭そうに視線を逸らす。
私は眉をひそめつつ、箱を開けた。
中に入っていたのは、透き通るような青い宝石が埋め込まれた、銀細工のネックレスだった。
「……!」
「どうだ。お前の瞳と同じ色だろう。城下町の宝石商が『最高級品が入った』とうるさいから、買ってやった」
美しい。
宝石の知識がある私でも、これほどの純度のサファイアは見たことがない。
加工技術も超一流。王国の国宝級に匹敵する代物だ。
普通の令嬢なら、「まあ素敵! 一生大事にします!」と涙を流して喜ぶ場面だろう。
しかし、私はシルビア・ランカスター。
悪役令嬢であり、守銭奴であり、プロの事務屋だ。
私は宝石を光に透かし、三秒で鑑定を下した。
「推定価格、金貨五千枚ですね」
「……」
「デザイン料込みで六千枚といったところでしょうか。殿下、まさか定価で買っていませんよね? あの店主なら『殿下価格』で二割増しにしている可能性があります」
「……お前なぁ」
殿下がこめかみをピキピキと引きつらせた。
「そこは『ありがとう』でいいだろうが! なぜ即座に査定に入るんだ!」
「職業病です。それに、こんな高価なものを頂く理由は? まさか、私の給料から天引きされるのでは?」
「されるか! ただの……その、日頃の感謝だ。それをつけて、来週の舞踏会に出ろ」
「舞踏会?」
私は手を止めた。
「ああ。隣国との国交樹立記念パーティーだ。俺のパートナーとして出席しろ」
「お断りします」
即答だった。
「私は裏方です。華やかな場所は似合いませんし、ドレスを着て愛想笑いをする時間があれば、書類を百枚処理できます」
「拒否権はない。これは『公務』だ」
殿下はニヤリと笑った。
「それに、今回の舞踏会には……お前の古巣、ランカスター王国からも使節団が来るらしいぞ」
その言葉に、私の動きが止まった。
「……王国から?」
「ああ。どうやら向こうの国王が、経済危機の支援を求めて、なりふり構わず頭を下げに来るらしい。……例のバカ王子も同行するそうだ」
レイド殿下が、来る。
しかも、私が働くこの帝国へ。
「……面白くなってきましたね」
私はゆっくりとナイフを置いた。
「つまり、私は元婚約者に対し、『貴方が捨てた女は、今や大国の皇太子の隣でこんなに輝いていますよ』と見せつける役回り、ということですか?」
「そういうことだ。最高の復讐だろう?」
殿下は楽しそうにワインを揺らした。
「俺の横に立ち、圧倒的な格の違いを見せつけてやれ。あいつが二度と、お前を連れ戻そうなどという寝言を吐けないようにな」
なるほど。
それは確かに、悪役令嬢として最高の晴れ舞台だ。
それに、私の作成した『帝国経済圏構想』を、王国の古臭い貴族たちにプレゼンする絶好の機会でもある。
「承知いたしました。その公務、お引き受けします」
私はネックレスを手に取り、首に当ててみた。
ひんやりとした宝石の感触が、戦意を高揚させる。
「ただし、ドレス代と美容代は経費で落とさせていただきます」
「好きにしろ。世界一美しくしてこい」
「もちろんです。元婚約者が腰を抜かし、マリア嬢が悔し涙で脱水症状になるくらい、完璧に仕上げてみせます」
私は不敵に微笑んだ。
「……怖いな、お前のその笑顔は」
「あら、頼もしいとおっしゃってください」
「違いない」
殿下は満足げに笑い、私の皿に肉を一枚乗せてくれた。
「食え。戦の前には栄養が必要だ」
「はい。……あ、殿下。口元にソースがついていますよ」
私は無意識にナプキンを取り、殿下の口元を拭ってしまった。
拭いてから、ハッと気づく。
これは秘書の仕事というより、もっと親密な……。
殿下が驚いたように私を見つめている。
金色の瞳が、至近距離で揺れている。
「……すまん」
「い、いえ。不潔だと衛生局から指導が入りますから。他意はありません」
私は慌てて言い訳をして、視線を逸らした。
心臓が、少しだけ早鐘を打っている気がする。
これはきっと、食後のカフェインのせいだ。そうに違いない。
「……シルビア」
「なんですか」
「やはりお前は、俺の妃に……」
「聞こえません。今はランチタイムです。私語は慎んでください」
私は強引に話を打ち切り、パンを口に詰め込んだ。
殿下は喉の奥でククッと笑い、それ以上は何も言わなかった。
テラスに吹く風が、少しだけ甘い香りを運んできた気がした。
だが、甘い雰囲気に浸っている場合ではない。
来週は決戦だ。
私は頭の中で、舞踏会の衣装予算と、レイド殿下への精神的ダメージ計算式を同時に組み立て始めた。
(待っていらっしゃい、元殿下。私が本当の『高嶺の花』であることを、嫌というほど教えてあげるわ)
私の瞳の中で、青い宝石が冷たく、鋭く輝いた。
163
あなたにおすすめの小説

「君は完璧だから、放っておいても大丈夫」と笑った夫。~王宮から私が去ったあと「愛していた」と泣きついても、もう手遅れです~
水上
恋愛
「君は完璧だから、放っておいても大丈夫だ」
夫である王太子はそう笑い、泣き真似が得意な見習い令嬢ばかりを優先した。
王太子妃セシリアは、怒り狂うこともなく、静かに心を閉ざす。
「左様でございますか」
彼女は夫への期待というノイズを遮断し、離縁の準備を始めた。
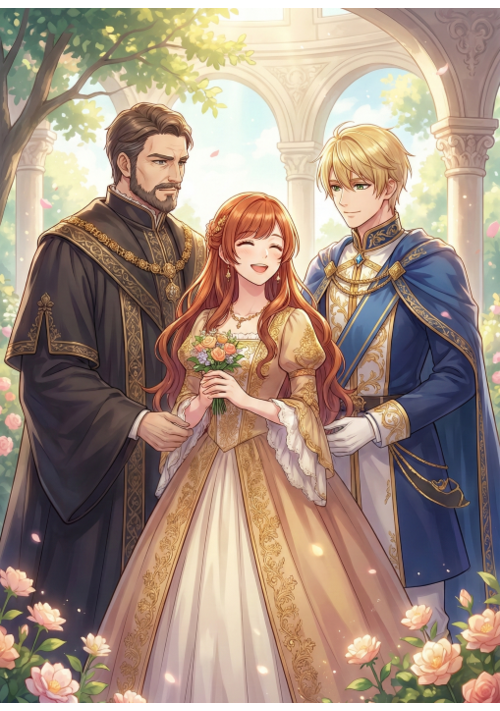
処刑された悪役令嬢、二周目は「ぼっち」を卒業して最強チームを作ります!
みかぼう。
恋愛
地方を救おうとして『反逆者』に仕立て上げられ、断頭台で散ったエリアナ・ヴァルドレイン。
彼女の失敗は、有能すぎるがゆえに「独りで背負いすぎたこと」だった。
ループから始まった二周目。
彼女はこれまで周囲との間に引いていた「線」を、踏み越えることを決意した。
「お父様、私に『線を引け』と教えた貴方に、処刑台から見た真実をお話しします」
「殿下、私が貴方の『目』となります。王国に張り巡らされた謀略の糸を、共に断ち切りましょう」
淑女の仮面を脱ぎ捨て、父と王太子を「共闘者」へと変貌させる政争の道。
未来知識という『目』を使い、一歩ずつ確実に、破滅への先手を取っていく。
これは、独りで戦い、独りで死んだ令嬢が、信頼と連帯によって王国の未来を塗り替える――緻密かつ大胆なリベンジ政争劇。
「私を神輿にするのなら、覚悟してくださいませ。……その行き先は、貴方の破滅ですわ」
(※カクヨムにも掲載中です。)

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか
まさかの
恋愛
皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。
己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。
カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。
誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。
ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。
シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。
そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。
嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。
カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。
小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

とある令嬢の優雅な別れ方 〜婚約破棄されたので、笑顔で地獄へお送りいたします〜
入多麗夜
恋愛
【完結まで執筆済!】
社交界を賑わせた婚約披露の茶会。
令嬢セリーヌ・リュミエールは、婚約者から突きつけられる。
「真実の愛を見つけたんだ」
それは、信じた誠実も、築いてきた未来も踏みにじる裏切りだった。だが、彼女は微笑んだ。
愛よりも冷たく、そして美しく。
笑顔で地獄へお送りいたします――

10年間の結婚生活を忘れました ~ドーラとレクス~
緑谷めい
恋愛
ドーラは金で買われたも同然の妻だった――
レクスとの結婚が決まった際「ドーラ、すまない。本当にすまない。不甲斐ない父を許せとは言わん。だが、我が家を助けると思ってゼーマン伯爵家に嫁いでくれ。頼む。この通りだ」と自分に頭を下げた実父の姿を見て、ドーラは自分の人生を諦めた。齢17歳にしてだ。
※ 全10話完結予定

婚約破棄されましたが、私はもう必要ありませんので
ふわふわ
恋愛
「婚約破棄?
……そうですか。では、私の役目は終わりですね」
王太子ロイド・ヴァルシュタインの婚約者として、
国と王宮を“滞りなく回す存在”であり続けてきた令嬢
マルグリット・フォン・ルーヴェン。
感情を表に出さず、
功績を誇らず、
ただ淡々と、最善だけを積み重ねてきた彼女に突きつけられたのは――
偽りの奇跡を振りかざす“聖女”による、突然の婚約破棄だった。
だが、マルグリットは嘆かない。
怒りもしない。
復讐すら、望まない。
彼女が選んだのは、
すべてを「仕組み」と「基準」に引き渡し、静かに前線から降りること。
彼女がいなくなっても、領地は回る。
判断は滞らず、人々は困らない。
それこそが、彼女が築いた“完成形”だった。
一方で、
彼女を切り捨てた王太子と偽聖女は、
「彼女がいない世界」で初めて、自分たちの無力さと向き合うことになる。
――必要とされない価値。
――前に出ない強さ。
――名前を呼ばれない完成。
これは、
騒がず、縋らず、静かに去った令嬢が、
最後にすべてを置き去りにして手に入れる“自由”の物語。
ざまぁは静かに、
恋は後半に、
そして物語は、凛と終わる。
アルファポリス女子読者向け
「大人の婚約破棄ざまぁ恋愛」、ここに完結。

【完結】断頭台で処刑された悪役王妃の生き直し
有栖多于佳
恋愛
近代ヨーロッパの、ようなある大陸のある帝国王女の物語。
30才で断頭台にかけられた王妃が、次の瞬間3才の自分に戻った。
1度目の世界では盲目的に母を立派な女帝だと思っていたが、よくよく思い起こせば、兄妹間で格差をつけて、お気に入りの子だけ依怙贔屓する毒親だと気づいた。
だいたい帝国は男子継承と決まっていたのをねじ曲げて強欲にも女帝になり、初恋の父との恋も成就させた結果、継承戦争起こし帝国は二つに割ってしまう。王配になった父は人の良いだけで頼りなく、全く人を見る目のないので軍の幹部に登用した者は役に立たない。
そんな両親と早い段階で決別し今度こそ幸せな人生を過ごすのだと、決意を胸に生き直すマリアンナ。
史実に良く似た出来事もあるかもしれませんが、この物語はフィクションです。
世界史の人物と同名が出てきますが、別人です。
全くのフィクションですので、歴史考察はありません。
*あくまでも異世界ヒューマンドラマであり、恋愛あり、残業ありの娯楽小説です。

【完】出来損ない令嬢は、双子の娘を持つ公爵様と契約結婚する~いつの間にか公爵様と7歳のかわいい双子たちに、めいっぱい溺愛されていました~
夏芽空
恋愛
子爵令嬢のエレナは、常に優秀な妹と比較され家族からひどい扱いを受けてきた。
しかし彼女は7歳の双子の娘を持つ公爵――ジオルトと契約結婚したことで、最低な家族の元を離れることができた。
しかも、条件は最高。公の場で妻を演じる以外は自由に過ごしていい上に、さらには給料までも出してくてれるという。
夢のような生活を手に入れた――と、思ったのもつかの間。
いきなり事件が発生してしまう。
結婚したその翌日に、双子の姉が令嬢教育の教育係をやめさせてしまった。
しかもジオルトは仕事で出かけていて、帰ってくるのはなんと一週間後だ。
(こうなったら、私がなんとかするしかないわ!)
腹をくくったエレナは、おもいきった行動を起こす。
それがきっかけとなり、ちょっと癖のある美少女双子義娘と、彼女たちよりもさらに癖の強いジオルトとの距離が縮まっていくのだった――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















