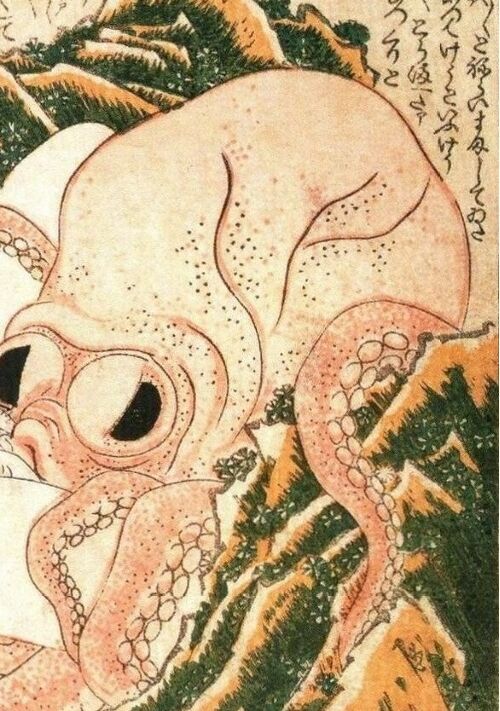4 / 7
『果実娘』R指定
しおりを挟む(…この人なら…、大丈夫だと、思ったのに…)
私がこの高校に転校してきたのは、前の学校で“ある事”がバレて酷い目にあったから…。
小さい頃から何度も同じような事があって、その度に嫌な思いをしてきた。
だから、この事は誰にも知られないようにずっと秘密にして生きてきたのだけれど…。
「あれ、なんか甘い匂いしない?」
「うん、するする!」
「いい匂い~!!」
「どこからしてくるのかな?」
「あ、ごめんなさい。私ちょっとトイレ…」
「うん、いってらっしゃ~い。本当、いい匂いだね」
(危なかった~…。さっきお昼ご飯食べている時に、舌噛んだの忘れてた…)
私が隠している“ある事”は二つある。
一つは、生まれた時から私の身体に流れている血液から甘い匂いがするという事。
少しでも血が出ると、その場所からは果物が熟した時に放つ甘い香りに近い匂いが辺りに広まり、それに気付いた人たちによって面白がられ、傷を付けられるなんてことがよくあった。
前の学校でも、私の不注意で怪我をしてからというものこの事に気付いたクラスメートから半分は気味悪がられ、半分は面白がられてかなり危険な状態にまでなってしまったのだ。
(なんでこんな体質なんだろう…)
「はぁ~…」
「ん?なんか今、すごく甘い匂いしなかったか?」
「ああ、したした!!」
「どこからしてくるんだろ?」
(もう、嫌…)
急いでトイレへと駆け込む。
鏡を見つめ、血が出ている箇所を探した。
(ここかぁ…)
なんとか止血することは出来たようだ。
「相変わらず甘いなぁ…」
この甘い香りがする血のもう一つのの特徴。
それは、甘い香りと同じ様な甘さがある。
この事を知ったのは小学校高学年の時だった。
図工の授業でカッターを使っていた時、勢いよく引きすぎて指をスッパリと切り、大量の血が溢れ出た。
その時にはすでに香りのことは分かっていたからなんとか匂いをさせないようにと頑張って止血していたのだけれど、あまりの勢いに一滴だけ零れて机に滴り落ちてしまった。
近くにいた男子が甘い匂いを放つその血に気付いて周りに言いふらし、挙げ句の果てには、面白半分にそれを指で掬って舐めてしまったのだ。
その男子は甘い甘いと騒ぎ始め、近くにいた子たちも気持ち悪がりながらも舐めていき、しまいには先生までもが舐め始めた。
私はとても恥ずかしいと感じながらもなんとか保健室へ駆け込み、手当てを終えて図工室へ戻った。
ドアを開けると、何故かみんなが私をじっと見つめてヒソヒソと小声で話していて、一番始めに私の血を舐めた男子はふざけているのか本気なのか分からないような目で私を見ると、「もっと血を舐めさせて」と言ってきた。
それからは私に対する周りの態度も悪化する一方で、先生ですらもう一度血を舐めさせてくれと頼んでくるようになっていた。
断ってもしつこく頼み込んできて、私は学校へは行けなくなった。
私の異変に気付いた両親に何があったのかと聞かれ始めは答えられずにいたけれど、本当に心配してくれていることに気付いて相談することに。
両親は甘い香りのことは知っていて、赤ちゃんの頃に調べて貰ったらしいのだが異変は見つからず、大きくなれば自然に治ると言われたらしい。
血の事について私も言わなかったから、てっきり治ったのだと思っていたと話してくれた。
その後もさまざまな病院に行って診てもらったけれど原因は分からず、結局私はその町を引っ越して違う小学校へ通うことになった。
小学校を卒業し、中学に入ってからも匂いや味は無くならず、むしろ酷くなっていく一方だった。
大きくなるにつれて怪我をしなければバレることもないと考えるようになり、かなり慎重な性格になっていた。
だけど、そんな調子だから同性の友達は出来ても異性の友達は出来ず、小学生の頃に体験した怖さもあって年頃になっても異性とお付き合いなど遠い夢のようだった。
そんな私がこの学校へ来て、生まれて初めて好きになった男子。
同じクラスであまり愛想は良くないけど、とても優しい人。
転校初日に、道に迷っていた私を助けてくれた人。
友達に相談したらその人のことを教えてくれて、ますます好きになっていった。
少しずつ距離を縮めてよく話すようになり、私は思いきって告白した。
返事は「いいよ」と一言だったけど、その日私は嬉しさで舞い上がったほど。
(この事、彼にはちゃんと話すべきだよね…)
彼と付き合い始めてそろそろ3ヶ月になる。
この学校に来てから大きな怪我は一度もしていない。
小さな怪我なら隠すことが出来ると思っているから、今回みたいに舌を噛んだり針を刺したりは日常茶飯事だけど…。
(知ったらやっぱり、気味悪がられるかな…。その勢いで別れ話になったりして!)
実際、彼といる時は怪我をしたこと事態隠している時もある。
バレるのが怖いということもあるが、意外と心配性な所もあるから…。
数日前、教室で男子たちが騒ぎ回って私にぶつかり、そのことで彼が騒いでいた男子たちを睨み付けたことがあったのだ。
怖がった男子たちは私に謝ってくれたけど…。
(あの時はちょっと怖かったかも…。普段、怒らない人が怒ると結構怖いもんな~…)
そんな事もあり、未だに血のことは言えないでいる。
(でも、隠し事は…)
キーンコーンカーンコーン
休み時間が終わる合図に考えるのを止め、私は教室に戻ることにした。
幸い、舌からの出血は傷口が浅かったからか完全に止まり、香りも一切無くなっていた。
「えっと、次の授業は…っと、うわっ!!」
ガシッ
「ご、ごめんなさ…て、え?」
「どうした?」
「う、ううん…。ちょっと驚いただけ…」
次の授業について考えていて、彼とぶつかってしまった。
突然のことに驚いたけれど、なんとか平静を装う。
さっきまで彼に血の事を話そうかどうか迷っていたから、なんとなく気まずかった。
「ご、ごめんね…」
「いや…。大丈夫か?」
「な、なにが?」
「突然トイレに向かったから、どこか調子が悪いのかと思って…」
「あ~、ううん、大丈夫だよ!ちょっと舌切ったから、どれくらい切れたのか見てただけ…」
「…舌、切ったのか…?」
「え…?」
なんだか彼の空気が変わったような気がした。
「あ、そろそろ授業の用意しないと先生来ちゃう…きゃっ!!」
「…口を開けろ」
「え…?」
なんとか話をそらして教室へ戻ろうと言った瞬間、私の腕を掴んだ彼はもう片方の手で私の顎を掴んだ。
状況が読めず固まる私に構わず、顔を近付けた彼はそのまま唇を押し付けて舌をねじ込んできた。
チャイムが鳴ったからと言って廊下にいる人の数が減った訳ではないのに、そんなことお構いなしに彼は私の舌を自分の舌で絡めていく。
ようやく解放されたのは2度目のチャイムが鳴る少し前。
突然私から離れた彼は掴んだままの私の腕を引いて、空き教室へと連れ込んだ。
ドアを閉めると同時に2度目のチャイムが鳴り、授業開始を知らせる。
教室に入るなり彼は私を押し倒し、両手で私の顔を挟むと見つめ合う状態のまま固定した。
色々と起こりすぎて頭が回らず、これから何をされるのかも分からず私はただ黙って彼を見つめた。
「………俺に舐めさせろ…」
「え…」
「…お前のあの血を、もっと舐めさせろ…」
「なっ!?なに言って…っ!!」
彼の目は、昔見たあの男子と同じ目をしていた。
そして、今までぼんやりとしか思い出せなかったあの男子の顔をはっきりと思い出した時、私の身体は彼を押し退けようと必死に腕を伸ばした。
だけどそんな私の腕を押さえ付け、彼は胸ポケットから取り出した折り畳み式のナイフで私の頬をそっと切りつけた。
「ようやく、味わえる…。ずっと忘れられなかったあの味を…、今度は手放さないからな」
彼の舌が私の頬をゆっくりと這っていく感覚と、傷口へと染み込む彼の唾液の感覚、鼻につく甘い香りが私の中で恐怖に変わっていく。
抵抗出来ず恐怖に支配されていく私の身体は小さく震え始め、そのことに気を良くした彼は、今度は首筋にナイフを当てた。
「そうだ、この味だ!!でも、あの頃より甘味が増してる」
「痛っ…、や、めて…」
「ん~?ここは香りが少し違うな…。もしかして…そうか」
私の首筋の血を舐め取りながら小さく呟いた彼は、もう一度頬の傷痕を舐めて嬉しそうに頷いた。
同時に、一旦私から離れるとベルトを外して私の両腕を頭の上で縛り、スカートを捲り上げて下着を下ろしてしまった。
恥ずかしさから、なんとか露になった下半身を見られないようにと身体を捩ったが、彼は私の足を持ち上げてガバッと開いた。
「きゃあああああっっ!!?」
「安心しろ、中には出さない。俺は、お前の血を味わいたいんだ…、全てな」
言いながら、彼は自身の勃ち始めたモノを自分で更に硬くさせ、私の大事な部分へ宛がうとゆっくりとナカへ侵入させてきた。
ナカが広がる感覚と痛みに息が詰まり、目を見開いた。
痛みから逃れようと足をバタつかせたが意味はなく、腰を引いたが足をがっしりと掴まれていて上手くいかなかった。
その間もモノは私のナカに侵入を続けていたが、ある部分まで来ると、腰に手を回した彼は一気に私を貫いた。
「いやぁああああっっ!!」
「ふっ…、…出てきたな」
私の奥まで差し込んだモノをゆっくりと抜きながら、何かを確認するように繋がった部分を見つめていた彼は嬉しそうに呟くと、ズルリと音がしそうな勢いでモノを抜き取った。
初めてだった私は大事な部分に感じた異物感が無くなったことや、いまだナカが痛み続けることに涙が溢れ、身体に力が入らなくなっていた。
辺りには甘ったるい香りが漂っていて、私の頭は働かなかった。
「やっぱり、初めてだったんだな…」
「………」
「しかもこの血は、香りが更に強い…。と言うことは」
「えっ!?や、止めてーっ!!」
彼は私の制止を聞き流して、自身のモノを差し込んだ部分に顔を埋めた。
自分の大事な部分に顔を埋められていることに対する羞恥と、彼に対する嫌悪感で気が狂いそうになりながらも、私は彼の頭を必死に押し退けた。
力の差は歴然だった。
ただでさえ普段からそんなに力が無いのに身体から力が抜けてる私が、好物を前にした男子相手に敵う訳がなかった。
そうしている内に、彼は舌を伸ばして私の大事な部分を舐め始めた。
ねっとりとじっくり味わうように…。
自分で触ることすらない部分を這う舌の感覚に身体が自然と仰け反り、鳥肌が立った。
瞬間、彼の舌はモノを差し込まれたナカへと侵入し、内壁を舐め始めたのだ。
そんなことをされ続ける内に私の身体は何故だか火照り始め、少しずつ声もくぐもっていった。
「やぁ…ん、もう、や、めて…」
「あと少しで、舐め終わるから…」
言い終えると彼は舌を抜き取り、最後に入り口を吸い上げた。
強い刺激に私の身体は仰け反り、頭が真っ白になっていった。
気を失っていた私は、息苦しさで目が覚めた。
頭が働かない中、ゆっくりと状況を確認すると私の口には彼のモノが押し込められていて、すでに硬くなっていたそれは私の意識がはっきりとした途端、大量の粘液を口の中に放った。
ほんのりと感じた甘味の後に続く苦味と独特の臭いにむせ返り、とにかく身体をバタつかせる。
私が意識を戻したことに気付いた彼はモノを口の中から抜き取り、私の顔をじっと見つめてにこっと笑った。
初めて見た彼の笑顔にドキッとして呆けていると、彼は血の付いたナイフを私の目の前に持ってきて一言だけ発した。
その日から私は彼と別れられなくなり、今もまだ私の身体に1つずつ傷が増えていく。
別に脅されている訳でも、彼が怖い訳でもない。
ただ、きっと彼以上に私を愛してくれる人はいないだろうと思えて、私が別れられないのだ。
「ちょっと、また傷が増えてるよ!?」
「本当にドジなんだから…」
「学校じゃしっかりしてるのにね…」
「また、彼に心配されるわよ?」
「大丈夫だよ。学校でした怪我じゃないから…」
「え、どういうこと?」
「もう、鈍いわね~」
「それだけ、いつも彼と一緒に居るってことでしょ」
友達の言葉に顔に熱が集まるのを感じて、思わず俯いた。
そう、学校以外で付いた傷のことを彼は全て知っている。
どうして付いたかも、どのように付いたのかも…。
付けたのは他の誰でもなく、彼自身だから…。
「噂をすれば…」
「あんまり見せつけないでよね~」
「それじゃあ私、行くね…」
「またね!!」
他の教室の掃除から戻ると、友達がふざけたように茶化しながらある所を指差し、そちらへ顔を向けた私の目には教室の入り口で待つ彼の姿が映った。
友達に別れを告げて教室で帰り支度を済ませ、彼の元へ急ぐ。
「ごめんね、遅くなって…」
「いや…、帰るか」
「うん」
「………」
私をじっと見つめて変わりがないことを確認すると、手を握って歩き出す彼。
相変わらず無愛想な彼に、少し苦笑がもれる。
少し照れながらも、私は彼の手を握り返した。
「今日はどこの味を確かめようか?」
「…どこでもいいよ」
「あまり、味わえない所にしよう。そうすれば、俺とお前の秘密がまた増える」
彼の言葉にふと、彼の正体を知ったあの日に言われた言葉を思い出して頬が緩む。
(…甘かったなぁ…)
私の変化に気付いた彼は、少しだけ足を早めたのだった。
「この血、甘いだろ?この甘さは、お前と俺しか知ることの出来ない特別な甘さなんだよ」
終わり
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
0
1 / 4
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる