あなたにおすすめの小説
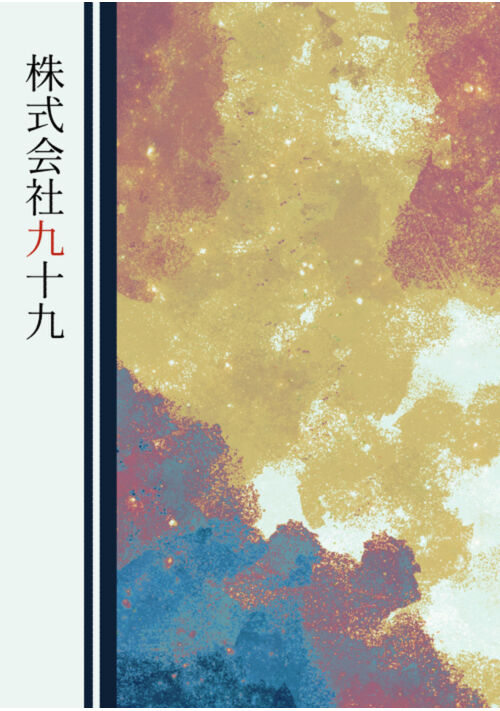
株式会社九十九
煤原
キャラ文芸
呪いに怯える人々が持ち込んだ品々を呪物と呼んで、依頼人から買い取ったり預かったりするのが、この会社の主な仕事内容だ。実際に持ち込まれる物はただの骨董品や古いだけのガラクタであることがほとんどだけれど、会社の倉庫にはそれらの呪物がずらりと並んでいる。本当に呪われているかどうかなんて、依頼人には関係がない。彼らはただ不安なのだ。その不安を手放したいのだ。
これは、人の不安を預かって安心させる仕事だった。
◇ ◆ ◇
ホラー要素と、痛々しい描写を含みます。人面瘡や異食、カニバリズム等が苦手な方はご注意ください。
◇ ◆ ◇
漫画の短編集(https://www.alphapolis.co.jp/manga/173302362/376868016)に4ページほどの小ネタを掲載しています。


怪奇蒐集帳(短編集)
naomikoryo
ホラー
この世には、知ってはいけない話がある。
怪談、都市伝説、語り継がれる呪い——
どれもがただの作り話かもしれない。
だが、それでも時々、**「本物」**が紛れ込むことがある。
本書は、そんな“見つけてしまった”怪異を集めた一冊である。
最後のページを閉じるとき、あなたは“何か”に気づくことになるだろう——。

彼の巨大な体に覆われ、満たされ、貪られた——一晩中
桜井ベアトリクス
恋愛
妹を救出するため、一ヶ月かけて死の山脈を越え、影の沼地を泳ぎ、マンティコアとポーカー勝負までした私、ローズ。
やっと辿り着いた先で見たのは——フェイ王の膝の上で甘える妹の姿。
「助けなんていらないわよ?」
は?
しかも運命の光が私と巨漢戦士マキシマスの間で光って、「お前は俺のものだ」宣言。
「片手だけなら……」そう妥協したのに、ワイン一杯で理性が飛んだ。
彼の心臓の音を聞いた瞬間、私から飛びついて、その夜、彼のベッドで戦士のものになった。

視える僕らのシェアハウス
橘しづき
ホラー
安藤花音は、ごく普通のOLだった。だが25歳の誕生日を境に、急におかしなものが見え始める。
電車に飛び込んでバラバラになる男性、やせ細った子供の姿、どれもこの世のものではない者たち。家の中にまで入ってくるそれらに、花音は仕事にも行けず追い詰められていた。
ある日、駅のホームで電車を待っていると、霊に引き込まれそうになってしまう。そこを、見知らぬ男性が間一髪で救ってくれる。彼は花音の話を聞いて名刺を一枚手渡す。
『月乃庭 管理人 竜崎奏多』
不思議なルームシェアが、始まる。

【完結】大量焼死体遺棄事件まとめサイト/裏サイド
まみ夜
ホラー
ここは、2008年2月09日朝に報道された、全国十ケ所総数六十体以上の「大量焼死体遺棄事件」のまとめサイトです。
事件の上澄みでしかない、ニュース報道とネット情報が序章であり終章。
一年以上も前に、偶然「写本」のネット検索から、オカルトな事件に巻き込まれた女性のブログ。
その家族が、彼女を探すことで、日常を踏み越える恐怖を、誰かに相談したかったブログまでが第一章。
そして、事件の、悪意の裏側が第二章です。
ホラーもミステリーと同じで、ラストがないと評価しづらいため、短編集でない長編はweb掲載には向かないジャンルです。
そのため、第一章にて、表向きのラストを用意しました。
第二章では、その裏側が明らかになり、予想を裏切れれば、とも思いますので、お付き合いください。
表紙イラストは、lllust ACより、乾大和様の「お嬢さん」を使用させていただいております。

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















