4 / 28
4
しおりを挟む
サーシャの王都グルメツアーは、とどまるところを知らなかった。
高級レストランから市場の屋台まで、彼女の食への探求は日に日に熱を帯びていく。
そして今日、彼女が新たな目的地として白羽の矢を立てたのは、騎士団の詰め所の近くにあるという一軒の大衆食堂だった。
その名も『満腹亭』。
いかにもな名前のその店は、安くて美味くて、とにかく量が多いと評判で、屈強な騎士や傭兵たちの胃袋をがっちりと掴んでいるという。
「お嬢様、本当にこのようなお店に入られるのですか…? ご覧くださいまし、屈強な殿方ばかりですわ…」
店の前で、侍女のアンナが不安そうに眉をひそめる。
確かに、がらりと開け放たれた扉の向こうからは、男たちの野太い笑い声や、ジョッキをぶつけ合う音が響いてきていた。
普通の貴族令嬢であれば、一歩踏み入るのも躊躇するだろう。
しかし、サーシャは違う。
「だからこそ、ですわアンナ!」
彼女は期待に胸を膨らませ、きらきらと瞳を輝かせた。
「屈強な殿方が集う店…それはつまり、量と味に一切の妥協がないという証拠! これは期待できますわよ!」
サーシャはアンナの細い腕をぐいと引き、迷うことなく店の中に足を踏み入れた。
瞬間、騒がしかった店内が水を打ったように静まり返る。
汗と油の匂いが染みついた空間に、場違いなほど上質な服を着た美しい令嬢が二人。
食事をしていた男たちの視線が、一斉に彼女たちに突き刺さった。
しかし、サーシャはそんな視線など全く意に介さない。
彼女は空いていたテーブルにどっかりと腰を下ろすと、壁に貼られたメニューを真剣な眼差しで吟味し始めた。
「ふむふむ…日替わりランチに、生姜焼き定食…どれも魅力的ですけれど…やはり、ここは名物と名高いアレをいただくしかありませんわね!」
「お、お客さん、ご注文は…?」
恐る恐る近づいてきた店主の女性に、サーシャはにこやかに告げた。
「ここの名物、『デカ盛りカツレツ定食』を一つ、お願いできるかしら?」
「…へい、毎度!」
その注文を聞いた瞬間、店内の空気がふっと和らいだ。
男たちは、ただの冷やかしではないと悟り、ニヤニヤしながら、あの華奢な令嬢が巨大なカツレツにどう立ち向かうのか、興味津々で見守り始めた。
やがて、湯気を立てながら運ばれてきた一皿を見て、サーシャは思わず「まあ!」と歓声を上げた。
大人の手のひらよりも大きなカツレツが、皿からはみ出さんばかりに鎮座している。
山盛りの白飯と、たっぷりの千切りキャベツ、そして具沢山の味噌汁。完璧な布陣だ。
(素晴らしい…! この衣の、剣のように鋭い立ち具合! そしてソースの芳醇な香り…!)
サーシャは恭しくナイフとフォークを手に取ると、カツレツにさくりと刃を入れた。
心地よい音とともに、分厚い豚肉の断面から、きらきらと輝く肉汁が溢れ出す。
一切れをソースにたっぷりと絡め、大きな口を開けて、ぱくりと頬張る。
(美味しいですわ…!)
サクサクの衣、驚くほど柔らかくジューシーな豚肉、そして果物の甘みとスパイスが絶妙に調和した特製ソース。
それらが口の中で渾然一体となり、至福の味が広がる。
すかさず白飯をかきこめば、もう何も言うことはない。
サーシャは、周囲の視線も忘れ、一心不乱にカツレツと向き合い始めた。
その食べっぷりは、もはや芸術的ですらあった。
夢中で半分ほど食べたところで、店がにわかに混み合ってきた。
「お客さん、すまねぇな! ちょっと、相席でも構わねぇかい?」
店主の声に、サーシャは口をもぐもぐさせながら顔を上げた。
「ええ、構いませんわよ。どうぞ」
サーシャがそう答えると、彼女の向かいの席に、一人の大男がどっかりと腰を下ろした。
日に焼けた肌に、無造作な黒髪。飾り気のない無骨な服を着ているが、その下にある鍛え上げられた体躯は隠しようもない。
厳しい眼差しは、戦場をいくつも越えてきた猛禽類を思わせる。
男は、サーシャの皿を一瞥すると、店主にぶっきらぼうに言った。
「俺も同じものを」
男――北の辺境を守るリアム・アシュフォード辺境伯は、目の前で夢中になってカツレツを頬張る女を、興味深く観察していた。
(なんだこの女は…。身なりからして貴族の令嬢だろうが、凄まじい食いっぷりだ。行儀が悪いというより、むしろ見ていて清々しい)
リアムも王都の社交界には疎いが、シュヴァルツ公爵家の悪名高い令嬢の噂くらいは耳にしていた。
しかし、目の前で幸せそうにご飯を食べるこの女が、その悪役令嬢だとは夢にも思わなかった。
一方のサーシャも、目の前の男が堅物で知られるアシュフォード辺境伯であることなど、知る由もない。
(体格の良い、騎士の方かしら。このお店の常連さんなのね)
くらいにしか思っていなかった。
沈黙の中、サクサク、もぐもぐ、という音だけが響く。
やがて、我慢できなくなったかのように、リアムが口を開いた。
「……美味そうに食うな」
それは、彼にしては珍しい、純粋な感嘆の声だった。
サーシャは、ぱちりと目を瞬かせ、こくんとカツレツを飲み込んでから答えた。
「ええ、とっても美味しいですわ! あなたもこれを召し上がるの?」
「ああ。ここのカツレツは王都で一番だと思っている」
「まあ! やはりそうですのね! わたくし、このソースの隠し味に使われている果物が何か、ずっと気になっていたのですけれど…林檎かしら? それとも少し桃も入っているような…」
サーシャがそう言うと、リアムは初めて少し驚いたような顔をした。
「…よく分かったな。ここの親父に聞いたことがある。林檎と、隠し味に桃のジャムを少し入れているそうだ」
「まあ、やっぱり! あのまろやかな甘みはそれでしたのね!」
それをきっかけに、二人の間に奇妙な会話が生まれた。
「この豚肉も、ただの豚ではありませんわ。一度、低温の油で火を通してから、注文が入るたびに高温で二度揚げしていますわね? だから、こんなに分厚いのに中まで柔らかい」
「ほう…付け合わせのキャベツはどうだ?」
「もちろん、手切りですわ。機械で切ったものとは、瑞々しさが違いますもの。水にさらす時間も絶妙ね」
マニアックすぎる食談義に、隣の席で聞いていた騎士たちが、あんぐりと口を開けている。
アンナは、もはや胃のあたりを押さえてうつむいていた。
やがて、巨大なカツレツ定食を綺麗に平らげたサーシャは、満足のため息をついて席を立った。
「ああ、美味しかった! では、わたくしはこれで」
「待て」
リアムが、彼女を呼び止めた。
「あんたの分も、俺が払っておこう。美味い飯を食いながら、実に楽しい話が聞けた礼だ」
「まあ、よろしいのですか?」
サーシャは少し驚いたが、素直に頷いた。
「では、お言葉に甘えさせていただきますわ。ごちそうさまでした、騎士様」
「…騎士じゃない」
リアムはそれだけ言うと、ふいと顔をそむけた。
「またどこかで会うかもしれんな」
そう言い残し、リアムはサーシャよりも先に会計を済ませ、店を出て行った。
「親切な方もいらっしゃるのね」
上機嫌なサーシャとは対照的に、店の外へ出たリアムは、一人、ぽつりと呟いていた。
「……面白い女だった。名前、聞いておけばよかったな」
北の守護神と呼ばれる男の胸に、今まで感じたことのない、温かく、そして少しだけむずがゆい感情が、確かに芽生え始めていた。
高級レストランから市場の屋台まで、彼女の食への探求は日に日に熱を帯びていく。
そして今日、彼女が新たな目的地として白羽の矢を立てたのは、騎士団の詰め所の近くにあるという一軒の大衆食堂だった。
その名も『満腹亭』。
いかにもな名前のその店は、安くて美味くて、とにかく量が多いと評判で、屈強な騎士や傭兵たちの胃袋をがっちりと掴んでいるという。
「お嬢様、本当にこのようなお店に入られるのですか…? ご覧くださいまし、屈強な殿方ばかりですわ…」
店の前で、侍女のアンナが不安そうに眉をひそめる。
確かに、がらりと開け放たれた扉の向こうからは、男たちの野太い笑い声や、ジョッキをぶつけ合う音が響いてきていた。
普通の貴族令嬢であれば、一歩踏み入るのも躊躇するだろう。
しかし、サーシャは違う。
「だからこそ、ですわアンナ!」
彼女は期待に胸を膨らませ、きらきらと瞳を輝かせた。
「屈強な殿方が集う店…それはつまり、量と味に一切の妥協がないという証拠! これは期待できますわよ!」
サーシャはアンナの細い腕をぐいと引き、迷うことなく店の中に足を踏み入れた。
瞬間、騒がしかった店内が水を打ったように静まり返る。
汗と油の匂いが染みついた空間に、場違いなほど上質な服を着た美しい令嬢が二人。
食事をしていた男たちの視線が、一斉に彼女たちに突き刺さった。
しかし、サーシャはそんな視線など全く意に介さない。
彼女は空いていたテーブルにどっかりと腰を下ろすと、壁に貼られたメニューを真剣な眼差しで吟味し始めた。
「ふむふむ…日替わりランチに、生姜焼き定食…どれも魅力的ですけれど…やはり、ここは名物と名高いアレをいただくしかありませんわね!」
「お、お客さん、ご注文は…?」
恐る恐る近づいてきた店主の女性に、サーシャはにこやかに告げた。
「ここの名物、『デカ盛りカツレツ定食』を一つ、お願いできるかしら?」
「…へい、毎度!」
その注文を聞いた瞬間、店内の空気がふっと和らいだ。
男たちは、ただの冷やかしではないと悟り、ニヤニヤしながら、あの華奢な令嬢が巨大なカツレツにどう立ち向かうのか、興味津々で見守り始めた。
やがて、湯気を立てながら運ばれてきた一皿を見て、サーシャは思わず「まあ!」と歓声を上げた。
大人の手のひらよりも大きなカツレツが、皿からはみ出さんばかりに鎮座している。
山盛りの白飯と、たっぷりの千切りキャベツ、そして具沢山の味噌汁。完璧な布陣だ。
(素晴らしい…! この衣の、剣のように鋭い立ち具合! そしてソースの芳醇な香り…!)
サーシャは恭しくナイフとフォークを手に取ると、カツレツにさくりと刃を入れた。
心地よい音とともに、分厚い豚肉の断面から、きらきらと輝く肉汁が溢れ出す。
一切れをソースにたっぷりと絡め、大きな口を開けて、ぱくりと頬張る。
(美味しいですわ…!)
サクサクの衣、驚くほど柔らかくジューシーな豚肉、そして果物の甘みとスパイスが絶妙に調和した特製ソース。
それらが口の中で渾然一体となり、至福の味が広がる。
すかさず白飯をかきこめば、もう何も言うことはない。
サーシャは、周囲の視線も忘れ、一心不乱にカツレツと向き合い始めた。
その食べっぷりは、もはや芸術的ですらあった。
夢中で半分ほど食べたところで、店がにわかに混み合ってきた。
「お客さん、すまねぇな! ちょっと、相席でも構わねぇかい?」
店主の声に、サーシャは口をもぐもぐさせながら顔を上げた。
「ええ、構いませんわよ。どうぞ」
サーシャがそう答えると、彼女の向かいの席に、一人の大男がどっかりと腰を下ろした。
日に焼けた肌に、無造作な黒髪。飾り気のない無骨な服を着ているが、その下にある鍛え上げられた体躯は隠しようもない。
厳しい眼差しは、戦場をいくつも越えてきた猛禽類を思わせる。
男は、サーシャの皿を一瞥すると、店主にぶっきらぼうに言った。
「俺も同じものを」
男――北の辺境を守るリアム・アシュフォード辺境伯は、目の前で夢中になってカツレツを頬張る女を、興味深く観察していた。
(なんだこの女は…。身なりからして貴族の令嬢だろうが、凄まじい食いっぷりだ。行儀が悪いというより、むしろ見ていて清々しい)
リアムも王都の社交界には疎いが、シュヴァルツ公爵家の悪名高い令嬢の噂くらいは耳にしていた。
しかし、目の前で幸せそうにご飯を食べるこの女が、その悪役令嬢だとは夢にも思わなかった。
一方のサーシャも、目の前の男が堅物で知られるアシュフォード辺境伯であることなど、知る由もない。
(体格の良い、騎士の方かしら。このお店の常連さんなのね)
くらいにしか思っていなかった。
沈黙の中、サクサク、もぐもぐ、という音だけが響く。
やがて、我慢できなくなったかのように、リアムが口を開いた。
「……美味そうに食うな」
それは、彼にしては珍しい、純粋な感嘆の声だった。
サーシャは、ぱちりと目を瞬かせ、こくんとカツレツを飲み込んでから答えた。
「ええ、とっても美味しいですわ! あなたもこれを召し上がるの?」
「ああ。ここのカツレツは王都で一番だと思っている」
「まあ! やはりそうですのね! わたくし、このソースの隠し味に使われている果物が何か、ずっと気になっていたのですけれど…林檎かしら? それとも少し桃も入っているような…」
サーシャがそう言うと、リアムは初めて少し驚いたような顔をした。
「…よく分かったな。ここの親父に聞いたことがある。林檎と、隠し味に桃のジャムを少し入れているそうだ」
「まあ、やっぱり! あのまろやかな甘みはそれでしたのね!」
それをきっかけに、二人の間に奇妙な会話が生まれた。
「この豚肉も、ただの豚ではありませんわ。一度、低温の油で火を通してから、注文が入るたびに高温で二度揚げしていますわね? だから、こんなに分厚いのに中まで柔らかい」
「ほう…付け合わせのキャベツはどうだ?」
「もちろん、手切りですわ。機械で切ったものとは、瑞々しさが違いますもの。水にさらす時間も絶妙ね」
マニアックすぎる食談義に、隣の席で聞いていた騎士たちが、あんぐりと口を開けている。
アンナは、もはや胃のあたりを押さえてうつむいていた。
やがて、巨大なカツレツ定食を綺麗に平らげたサーシャは、満足のため息をついて席を立った。
「ああ、美味しかった! では、わたくしはこれで」
「待て」
リアムが、彼女を呼び止めた。
「あんたの分も、俺が払っておこう。美味い飯を食いながら、実に楽しい話が聞けた礼だ」
「まあ、よろしいのですか?」
サーシャは少し驚いたが、素直に頷いた。
「では、お言葉に甘えさせていただきますわ。ごちそうさまでした、騎士様」
「…騎士じゃない」
リアムはそれだけ言うと、ふいと顔をそむけた。
「またどこかで会うかもしれんな」
そう言い残し、リアムはサーシャよりも先に会計を済ませ、店を出て行った。
「親切な方もいらっしゃるのね」
上機嫌なサーシャとは対照的に、店の外へ出たリアムは、一人、ぽつりと呟いていた。
「……面白い女だった。名前、聞いておけばよかったな」
北の守護神と呼ばれる男の胸に、今まで感じたことのない、温かく、そして少しだけむずがゆい感情が、確かに芽生え始めていた。
877
あなたにおすすめの小説

政略結婚の指南書
編端みどり
恋愛
【完結しました。ありがとうございました】
貴族なのだから、政略結婚は当たり前。両親のように愛がなくても仕方ないと諦めて結婚式に臨んだマリア。母が持たせてくれたのは、政略結婚の指南書。夫に愛されなかった母は、指南書を頼りに自分の役目を果たし、マリア達を立派に育ててくれた。
母の背中を見て育ったマリアは、愛されなくても自分の役目を果たそうと覚悟を決めて嫁いだ。お相手は、女嫌いで有名な辺境伯。
愛されなくても良いと思っていたのに、マリアは結婚式で初めて会った夫に一目惚れしてしまう。
屈強な見た目で女性に怖がられる辺境伯も、小動物のようなマリアに一目惚れ。
惹かれ合うふたりを引き裂くように、結婚式直後に辺境伯は出陣する事になってしまう。
戻ってきた辺境伯は、上手く妻と距離を縮められない。みかねた使用人達の手配で、ふたりは視察という名のデートに赴く事に。そこで、事件に巻き込まれてしまい……
※R15は保険です
※別サイトにも掲載しています

【完結】姉に婚約者を奪われ、役立たずと言われ家からも追放されたので、隣国で幸せに生きます
よどら文鳥
恋愛
「リリーナ、俺はお前の姉と結婚することにした。だからお前との婚約は取り消しにさせろ」
婚約者だったザグローム様は婚約破棄が当然のように言ってきました。
「ようやくお前でも家のために役立つ日がきたかと思ったが、所詮は役立たずだったか……」
「リリーナは伯爵家にとって必要ない子なの」
両親からもゴミのように扱われています。そして役に立たないと、家から追放されることが決まりました。
お姉様からは用が済んだからと捨てられます。
「あなたの手柄は全部私が貰ってきたから、今回の婚約も私のもの。当然の流れよね。だから謝罪するつもりはないわよ」
「平民になっても公爵婦人になる私からは何の援助もしないけど、立派に生きて頂戴ね」
ですが、これでようやく理不尽な家からも解放されて自由になれました。
唯一の味方になってくれた執事の助言と支援によって、隣国の公爵家へ向かうことになりました。
ここから私の人生が大きく変わっていきます。

妹のために愛の無い結婚をすることになりました
バンブー竹田
恋愛
「エミリー、君との婚約は破棄することに決まった」
愛するラルフからの唐突な通告に私は言葉を失ってしまった。
婚約が破棄されたことはもちろんショックだけど、それだけじゃない。
私とラルフの結婚は妹のシエルの命がかかったものでもあったから・・・。
落ちこむ私のもとに『アレン』という大金持ちの平民からの縁談が舞い込んできた。
思い悩んだ末、私は会ったこともない殿方と結婚することに決めた。
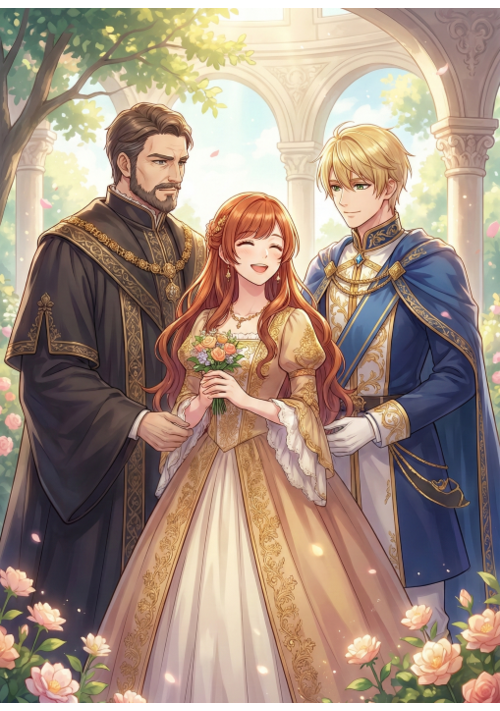
処刑された悪役令嬢、二周目は「ぼっち」を卒業して最強チームを作ります!
みかぼう。
恋愛
地方を救おうとして『反逆者』に仕立て上げられ、断頭台で散ったエリアナ・ヴァルドレイン。
彼女の失敗は、有能すぎるがゆえに「独りで背負いすぎたこと」だった。
ループから始まった二周目。
彼女はこれまで周囲との間に引いていた「線」を、踏み越えることを決意した。
「お父様、私に『線を引け』と教えた貴方に、処刑台から見た真実をお話しします」
「殿下、私が貴方の『目』となります。王国に張り巡らされた謀略の糸を、共に断ち切りましょう」
淑女の仮面を脱ぎ捨て、父と王太子を「共闘者」へと変貌させる政争の道。
未来知識という『目』を使い、一歩ずつ確実に、破滅への先手を取っていく。
これは、独りで戦い、独りで死んだ令嬢が、信頼と連帯によって王国の未来を塗り替える――緻密かつ大胆なリベンジ政争劇。
「私を神輿にするのなら、覚悟してくださいませ。……その行き先は、貴方の破滅ですわ」
(※カクヨムにも掲載中です。)

婚約者と王の座を捨てて、真実の愛を選んだ僕の結果
もふっとしたクリームパン
恋愛
タイトル通り、婚約者と王位を捨てた元第一王子様が過去と今を語る話です。ざまぁされる側のお話なので、明るい話ではありません。*書きたいとこだけ書いた小説なので、世界観などの設定はふんわりしてます。*文章の追加や修正を適時行います。*カクヨム様にも投稿しています。*本編十四話(幕間四話)+登場人物紹介+オマケ(四話:ざまぁする側の話)、で完結。

偽王を演じた侯爵令嬢は、名もなき人生を選ぶ」
鷹 綾
恋愛
内容紹介
王太子オレンに婚約破棄された侯爵令嬢ライアー・ユースティティア。
だが、それは彼女にとって「不幸の始まり」ではなかった。
国政を放棄し、重税と私欲に溺れる暴君ロネ国王。
その無責任さを補っていた宰相リシュリュー公爵が投獄されたことで、
国は静かに、しかし確実に崩壊へ向かい始める。
そんな中、変身魔法を使えるライアーは、
国王の身代わり――偽王として玉座に座ることを強要されてしまう。
「王太子妃には向いていなかったけれど……
どうやら、国王にも向いていなかったみたいですわね」
有能な宰相とともに国を立て直し、
理不尽な税を廃し、民の暮らしを取り戻した彼女は、
やがて本物の国王と王太子を“偽者”として流刑に処す。
そして最後に選んだのは、
王として君臨し続けることではなく――
偽王のまま退位し、名もなき人生を生きることだった。
これは、
婚約破棄から始まり、
偽王としてざまぁを成し遂げ、
それでも「王にならなかった」令嬢の物語。
玉座よりも遠く、
裁きよりも静かな場所で、
彼女はようやく“自分の人生”を歩き始める。

婚約破棄されましたが、私はもう必要ありませんので
ふわふわ
恋愛
「婚約破棄?
……そうですか。では、私の役目は終わりですね」
王太子ロイド・ヴァルシュタインの婚約者として、
国と王宮を“滞りなく回す存在”であり続けてきた令嬢
マルグリット・フォン・ルーヴェン。
感情を表に出さず、
功績を誇らず、
ただ淡々と、最善だけを積み重ねてきた彼女に突きつけられたのは――
偽りの奇跡を振りかざす“聖女”による、突然の婚約破棄だった。
だが、マルグリットは嘆かない。
怒りもしない。
復讐すら、望まない。
彼女が選んだのは、
すべてを「仕組み」と「基準」に引き渡し、静かに前線から降りること。
彼女がいなくなっても、領地は回る。
判断は滞らず、人々は困らない。
それこそが、彼女が築いた“完成形”だった。
一方で、
彼女を切り捨てた王太子と偽聖女は、
「彼女がいない世界」で初めて、自分たちの無力さと向き合うことになる。
――必要とされない価値。
――前に出ない強さ。
――名前を呼ばれない完成。
これは、
騒がず、縋らず、静かに去った令嬢が、
最後にすべてを置き去りにして手に入れる“自由”の物語。
ざまぁは静かに、
恋は後半に、
そして物語は、凛と終わる。
アルファポリス女子読者向け
「大人の婚約破棄ざまぁ恋愛」、ここに完結。

悪役令嬢が行方不明!?
mimiaizu
恋愛
乙女ゲームの設定では悪役令嬢だった公爵令嬢サエナリア・ヴァン・ソノーザ。そんな彼女が行方不明になるというゲームになかった事件(イベント)が起こる。彼女を見つけ出そうと捜索が始まる。そして、次々と明かされることになる真実に、妹が両親が、婚約者の王太子が、ヒロインの男爵令嬢が、皆が驚愕することになる。全てのカギを握るのは、一体誰なのだろう。
※初めての悪役令嬢物です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















