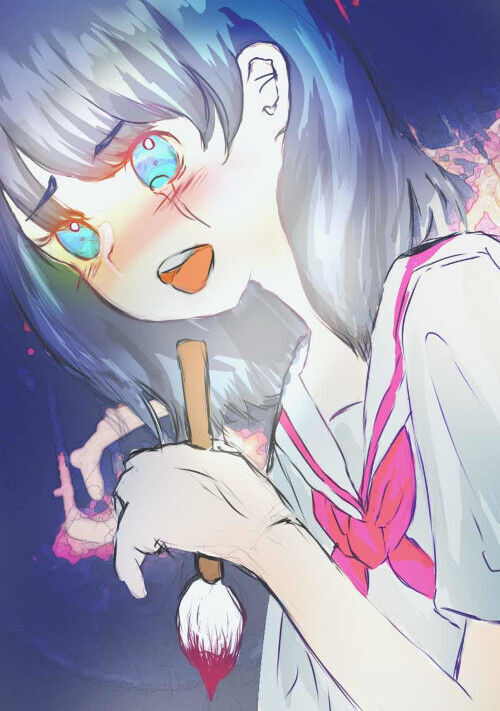10 / 13
九歩目.きみの隣にいたいんだ。
しおりを挟む
俺の話をした日から、俺はずっと落ち着かない。
なぜなら、もう待ちきれないと思った俺は、ついに俺から告白する決心をしたのだ。
でも、それがこんなにも難しいものだとは思わなかった。
もうその翌朝から目も合わせられないし、ふいに手が触れた時には、ものすごい勢いで距離をとってしまった。
柊哉もそんな俺を不安そうな顔で見ていた。
一応、いつものように視聴覚室に迎えに来てもらい、そのままマンションに送ってもらっているけど、会話もぎこちない。
正直、自分がこんなヘタレだとは思わなかったし、柊哉に何で早く告白してくれないんだろう、とか思っててごめんって気持ちでいっぱいだ。
そんな日が一週間続いたけど、今週末も泊まりに来てくれる予定だから、その時に言おう。
でも、なんて言ったらいいのかな……。
シンプルに『好きだ』とか、それとも『恋人になってください』とか。
そんなことを考えていて、ゲームにも全く集中できない。
大抵の悩みはゲームをやってれば忘れられたのに、こんなことは初めてで、思わず俺は大きなため息をつく。
「さっきからボーっとしてますけど、どうかしたんですか?」
eスポーツ部の後輩、緒方が不思議そうな目で俺の顔を覗き込んでいた。
でも、こんな相談、後輩にできるはずもない。
「いや、何でもない……」
そう答えると、緒方は怪訝そうな顔をした。
「僕、このやりとりお昼もしましたよ」
「へぇ、クラスのやつと?」
「はい、高槻と」
俺はその名前にドキッとした。そうだ、緒方は柊哉と同じクラスだった。
昼も一緒に食べているって柊哉からも聞いたことがある。
「何、高槻なんか悩んでんの」
「らしいですよ。気になる人が最近余所余所しいって」
「えっそ、そうなんだ。ってか、それ人にしゃべっていいの?」
「瀬良先輩ならいいでしょ?」
そう言って、にっこり緒方は笑った。やっぱり何か察している気がする……。
実は緒方とは結構長い付き合いになる。
俺が高等部に入ってからeスポーツ部――当時は人数が足らなくて同好会だったけど――を作ったことをどこかで知った緒方は、まだ中等部だったのにも関わらず、当時俺しかいなかった部室にやってきて、“参加させてほしい”と直談判してきた。
だから、緒方はこの部活の中では一番付き合いが長い。
eスポーツ部を作ったのは、この学校に一年生は部活動所属必須というルールがあったからで、友達もいない俺は、誰かと一緒に活動できるなんて思っていなかった。
だから、緒方が部室に来てくれた時、すごく驚いたけど、嬉しかったことを覚えている。
それから、緒方のおかげで部員も徐々に増えて、正式な“部活”として名乗れるようになった。
今ではこの部活も俺にとってかけがえのない居場所だ。
それを作ってくれた緒方には本当に感謝している。
ってつい過去を懐かしんでしまったけど、とにかく昔から緒方は恐ろしいほどに空気が読める。
きっと、これまで柊哉の話と俺の話を両方聞いていて、ピンと来ちゃったんだろう。
「で、先輩はどうして高槻の気になる人は急に余所余所しくなったんだと思いますか?」
どうやら、緒方はこの話を終わりにするつもりはないらしく、笑顔の中に変な圧を感じる。
「さぁ……」
「さぁ、ですか。うーん、僕ね、高槻のこと結構好きなんですよ。いいやつだし」
緒方の言った“好き”という言葉にドキッとして、つい真顔になってしまった。
その表情を見て、緒方はフフっと笑った。
「瀬良先輩のことも好きですよ。僕は、好きな人には幸せになって欲しいんです。だから、ハッピーエンドを期待してますよ」
やっぱり、緒方は俺の気持ちも、柊哉の気持ちも察してこの話をしている。
これまでも何かにつけて緒方には助けてもらっているけど、まさか恋愛方面までもサポートしてもらうことになるとは思わなかった。
「うん……。俺、緒方にはずっと勝てない気がするわ……」
「あはは、ゲームでは負けっぱなしですけどね」
緒方のおかげで、くよくよとしていた気持ちもすっきりとして、週末に告白する覚悟もできた。
そう思っていたのに、簡単にうまくいかないのが世の常なのかもしれない。
いつものように八時過ぎには他の部員は帰宅して、俺一人でゲームをしていると、視聴覚室のドアが開いた音に気が付いた。
時計は九時少し前。この時間に尋ねてくるのは柊哉しかいない。
まだ対戦が終わっていなかったから、モニターに顔を向けたまま、振り向かずに声だけかけた。
「ごめん、柊哉。もうちょっとだけ待ってて」
「……柊哉って高槻のこと?」
後ろからした声は、柊哉じゃなかった。
俺は聞き覚えのあるその声に驚いて振り向くと、そこにいたのは相原だった。
「浩平……なに、何の用」
画面から目を離した瞬間、俺が操作していたキャラクターは一気に追い込まれ、画面には俺が負けたことを知らせる文字が浮かぶ。
その文字を背に、俺は相原を睨みつけた。
「いつの間に名前で呼ぶくらい高槻と仲良くなったんだよ」
「お前には関係ないだろ」
俺はモニターに向き直し、もう一度ゲームを始める。
もう少しすれば柊哉もここに来るし、それまで無視していれば相原も諦めて帰るだろう。
「火月、話聞けって」
そう言って相原は俺の腕を掴んで、持っていたコントローラーを奪った。
俺は驚いて腕を思いっきり振り払う。
なんでこいつはいつもいきなり俺の腕を掴むんだろうか。
「なんなんだよ!」
「そんなに怒るなよ。だから、話がしたいだけだって言ってるだろ」
腕を掴まれてついカッとしてしまったけど、少し前に自分も悪いところがあったと気が付いたことを思い出す。
少しだけ話を聞いてそれで終わりにしよう。
そう思ったのが間違いだった。
「はぁ……なに?」
俺が拒絶しなかったことに相原はあからさまにホッとした顔をした。
「あれからずっと気になってたんだ。家からも出て行っちゃうし、連絡もつかなくなったから……俺があんなこと言ったせいかなって」
確かに、相原に告白されてからすぐに実家を出て一人暮らしを始めた。
告白をされたせいで相原の家に行けなくなったことは、一人暮らしを始めるきっかけの一つくらいにはなってるかもしれない。
でも、家を出たことと告白をされたことは全く関係ない。
「家を出たのはあそこにいるのが限界だったからだ。お前とは関係ない」
「そっか……今は一人暮らしなんだろ? ちゃんと飯とか食べてる?」
「普通にしてるよ。ってか今更なんなの?」
そんなこと相原に心配される筋合いはないし、何なら柊哉のおかげで最近はすごく健康的な生活をしてる。
まぁ言わないけど。
それよりも、今更になってなぜ俺と話をしようと思ったんだろうか。
同じ学校に通ってるんだから、これまでだって話すチャンスなんていくらでもあったはずなのに。
「そう冷たくされるとへこむな……高槻とは楽しそうにしてるのに」
どうしてそこで柊哉の話が出てくるのか。
俺はすごく嫌な顔をして見せる。
でもこれでわかった。相原は俺と柊哉の関係を確認しに来たんだ。
「高槻と付き合ってるのか?」
やっぱりそうだった。俺はわざと大きくため息をついて、相原を睨んだ。
「お前には関係ない」
「関係ある……。お前は男をそういう対象として見られないんだと思ったから諦めてたんだ。なのになんで……! なんで俺じゃダメなんだ!」
相原は俺の両腕を掴んで壁に押さえつけた。
俺は振り払おうとするが、力が強くてびくともしない。
「は、離せ……!」
「俺はまだお前が好きなんだ!」
相原はそのまま俺の唇にキスをした。
嫌だ……!
俺は、俺の口を塞ぐ相原の唇を噛み、ひるんだすきに相原を思いっきり突き飛ばした。
「こういう、俺の気持ちを考えないところが嫌なんだよ!」
俺に突き飛ばされて尻もちをついた相原は、呆然とした顔をしている。
その唇には血が滲んでいた。
「……昔、お前が俺を部屋に入れてくれたことで俺は救われてた。それについては本当に感謝してる。でも、お前の気持ちには答えられない。俺は、こういうことを無理やりするやつを好きにはならない、絶対に」
俺は、ここですべてを終わらせるという思いで、はっきりと相原に言い放った。
「わかった、ごめん」
二年前からくすぶったままだった俺と相原の関係は、これでようやく終わることができた。
相原が部屋を出てから、俺はさっき無理やり抑え込まれたことの恐怖が後から襲ってきて、その場に座り込んでしまった。
柊哉に会いたい。
少しして落ち着きを取り戻すと時計は九時半を回っていた。
柊哉はまだ来ていなかった。
スマホを確認するけど、特に連絡もない。
でも、窓の外に見える体育館はすでに明かりが消えていた。
俺はさっき相原が出て行った部室のドアを見る。
もしかして、相原と一緒にいるところを見られた…?
柊哉に慌てて電話を掛けたけど、出ない。
メッセージも何度か送ったけど、結局その日、柊哉は部室に現れることもなく、折り返しもメッセージの返信どころか、既読にすらならなかった。
俺は本当に久しぶりに、一人で、歩いてマンションに帰った。
翌朝、スマホを確認すると柊哉からメッセージが届いていた。
『電話、出られなくてすみませんでした。昨日は急用ができて、先に帰りました』
当たり障りのないメッセージ。
やっぱり昨日、相原といたところを見て、それで何か勘違いをしたのかもしれない。
こんなことで、柊哉との関係を壊されたくない。今日会わないと……。
でも今はもう部活のはずだから、とりあえず『今日来れる?』とだけメッセージを入れた。
メッセージが既読になることなく、気が付けば夜の八時前。
電話をかけてもいいものか、俺はスマホを握り締めて、悩んでいた。
でも、会いたい。
今日こそ言うんだ。
好きだって。俺の隣にいてほしいって。
俺は、ぐっと腹に力を入れて、震える手でスマホを握り通話ボダンを押そうとした瞬間、スマホがメッセージを受信したことを知らせた。
慌てて開くと、それは柊哉からだった。
『今、学校出ました。もうご飯食べましたか?』
俺は急いで返信を打つ。心臓がバクバクして体から飛び出してきてしまいそうだ。
『まだ。今から来る?』
そうメッセージを送ると、すぐに既読になった。
『行ってもいいですか?』
『うん、いいよ』
またすぐに“既読”になった。よかった、来てくれる……。
俺はそわそわしながら、柊哉の到着を待った。
「お疲れ、柊哉」
「あっはい。遅くなってすいません」
「全然、大丈夫だよ」
今週はずっとそわそわしてしまって、まともに顔も見られなかった。
でも、今はちゃんと柊哉と向き合うって決めたから、真っ直ぐと柊哉を見つめる。
変わらない優しい視線に、今週これをずっと見逃していたのかと後悔した。
汗だくだという柊哉は先にシャワーを浴び、交代して俺がシャワーを浴びている最中にチャーハンを作ってくれた。
すっかり当たり前のように作ってくれるようになったご飯は、いつもおいしくて、俺のことを考えてくれているメニューばかり。
大切にされている、そう感じた。
二人とも食べ終えて、俺が後片付けをしている間に柊哉はソファでうとうととしていた。
今日は練習試合だったと言っていたし、きっと疲れたんだろう。
いつか、柊哉が試合をしているところも見てみたいな、なんて思いながらそのきれいな寝顔を見下ろす。
ふいに触れたくなって、俺はソファの背に手をついて片膝だけソファに乗せ、額にキスをした。
唇を離し、目を開くと、顔のすぐ真下にあった長い睫毛が動き、切れ長の目の中に俺が映る。
俺は驚いて後ろに下がると、その勢いでローテーブルにぶつかって転びそうになったと思ったら腕をひかれ、気が付いた時には柊哉の上に倒れ込んでいた。
「大丈夫ですか」
「う、うん、ごめん」
俺は慌てて柊哉から離れようとしたけど、柊哉は腕を掴んだままだ。
もう、恥ずかしくて爆発しそうだ。
「柊哉、離して」
何とか声を振り絞ると、それまで俺を強くつかんでいた手が少しだけ緩められた。
でも、放してはくれない。
柊哉に捕まれている腕がじんわりと熱い。
俺は、腕を掴まれるのが苦手だ。
腕を掴まれると、怒鳴られる。そんなトラウマがすり込まれているせいだと思う。
昨日、相原に腕を掴まれたときも、背筋が凍るかと思うほど嫌悪感でいっぱいだった。
でも、柊哉はイヤじゃない。それどころか、離してほしくない、もっと触ってほしいと思う。
同じ動作でも、柊哉はいつも優しくて、温かい。
好きな人って言うのはこんなにも特別なものなんだ。
柊哉の方をちらっと見ると、視線が合った。
あぁ好きだなぁと思ってその顔を眺めていると、柊哉は俺の頬に手を伸ばし、そのままそっと額にキスをした。
「お返しです」
いたずらっこのような顔でそう言うから、俺は恥ずかしさのあまり柊哉の腕を振り払ってソファに置かれていたクッションを顔めがけて投げつけた。
「お、お返しって、そもそも先にしたのは柊哉だろ! この間だって……!」
いや、違う。それよりも前に俺もしてる。もう混乱しすぎて、よくわかない。
「あれ、バレてましたか。じゃー最近余所余所しかったのはやっぱりそのせい?」
柊哉は俺が投げたクッションを抱え、少し恥ずかしそうな顔をした。
よかった、俺が初めてキスした時は本当に寝てたんだ。
それならわざわざ言う必要はないし、今話さないといけないのはそっちじゃない。
「ち、違う。それはもっと前から気づいてたし……」
「えっ……」
柊哉が俺を寝室に運んでから、額にキスをするようになったのは、部屋に泊まるようになってから何度目かのことだった。
初めはもちろん驚いたけど、嫌なんかじゃなかったし、むしろもっと、それ以上のことをしてくれないかな、なんて思ってた。
だから、我慢できなくなって、一人でシてなんとか発散してた。
「寝たふりしてたんですか。ひどい」
「し、してない! っていうか、なんで俺が責められる流れなんだよ! 寝込み襲ったのは柊哉だろ!」
「襲ってません。チューしただけです。それにさっき瀬良さんだって……」
「わーーー! もういい、もういいから!!」
俺の恥ずかしさは頂点に達して、もう限界まで来ている。
少しでも意識を落ち着けようと、両手で耳を塞ぎ、そのままソファの上で体を丸める。
自分でも何してるんだって思うけど、もう本当に爆発しそうなんだ。
しばらく縮こまっていると、柊哉は優しく髪を撫でてくれた。
いつも優しいこの手が俺は大好きだ。
「瀬良さん、顔上げてください」
髪に触れる手の温もりで、だんだんと気持ちも落ち着いていく。
俺は丸くなったまま目線だけを上げて柊哉を見た。
すると、すぐに柊哉は俺の手を引いて体を起こし、そのまま抱き寄せられた。
急に抱きしめられ、はじめは硬直していたけど、柊哉の腕の中で優しい匂いと温かさに包まれて、ほっと力が抜けていく。
それもつかの間、柊哉の腕にぐっと力が入り俺の耳元に吐息がかかる。
「瀬良さん。俺、瀬良さんのことが好きです」
それはずっと欲しかった言葉だった。
涙があふれて来る。
それを見た柊哉はそっと俺の瞼にキスした。
「瀬良さんは? 俺のこと好き?」
気持ちがあふれて、なかなか言葉が出てこない。
でも、答えたい。
好きだって、大好きだって。
「好きだよ、俺も柊哉のことが好きだ」
柊哉がもう一度ぎゅっと抱きしめてくれたから、俺も背中に手をまわしてそれに応える。
俺は泣きすぎて鼻グズグズだし、結局告白もできなかった。
後だしだけど、俺からも伝えたい。
自分の気持ちを伝えるってことがどれだけ難しいことなのか、俺も知ってるから。
少しでも、俺から何か返せるように。
「ねぇ柊哉……、俺を柊哉の恋人にしてくれる?」
柊哉は少し驚いた顔をした後、またいつもの優しい笑顔になってぎゅって抱きしめてくれた。
「もちろんです」
きみが踏み出してくれた一歩で、ついに隣に立つことができた。
なぜなら、もう待ちきれないと思った俺は、ついに俺から告白する決心をしたのだ。
でも、それがこんなにも難しいものだとは思わなかった。
もうその翌朝から目も合わせられないし、ふいに手が触れた時には、ものすごい勢いで距離をとってしまった。
柊哉もそんな俺を不安そうな顔で見ていた。
一応、いつものように視聴覚室に迎えに来てもらい、そのままマンションに送ってもらっているけど、会話もぎこちない。
正直、自分がこんなヘタレだとは思わなかったし、柊哉に何で早く告白してくれないんだろう、とか思っててごめんって気持ちでいっぱいだ。
そんな日が一週間続いたけど、今週末も泊まりに来てくれる予定だから、その時に言おう。
でも、なんて言ったらいいのかな……。
シンプルに『好きだ』とか、それとも『恋人になってください』とか。
そんなことを考えていて、ゲームにも全く集中できない。
大抵の悩みはゲームをやってれば忘れられたのに、こんなことは初めてで、思わず俺は大きなため息をつく。
「さっきからボーっとしてますけど、どうかしたんですか?」
eスポーツ部の後輩、緒方が不思議そうな目で俺の顔を覗き込んでいた。
でも、こんな相談、後輩にできるはずもない。
「いや、何でもない……」
そう答えると、緒方は怪訝そうな顔をした。
「僕、このやりとりお昼もしましたよ」
「へぇ、クラスのやつと?」
「はい、高槻と」
俺はその名前にドキッとした。そうだ、緒方は柊哉と同じクラスだった。
昼も一緒に食べているって柊哉からも聞いたことがある。
「何、高槻なんか悩んでんの」
「らしいですよ。気になる人が最近余所余所しいって」
「えっそ、そうなんだ。ってか、それ人にしゃべっていいの?」
「瀬良先輩ならいいでしょ?」
そう言って、にっこり緒方は笑った。やっぱり何か察している気がする……。
実は緒方とは結構長い付き合いになる。
俺が高等部に入ってからeスポーツ部――当時は人数が足らなくて同好会だったけど――を作ったことをどこかで知った緒方は、まだ中等部だったのにも関わらず、当時俺しかいなかった部室にやってきて、“参加させてほしい”と直談判してきた。
だから、緒方はこの部活の中では一番付き合いが長い。
eスポーツ部を作ったのは、この学校に一年生は部活動所属必須というルールがあったからで、友達もいない俺は、誰かと一緒に活動できるなんて思っていなかった。
だから、緒方が部室に来てくれた時、すごく驚いたけど、嬉しかったことを覚えている。
それから、緒方のおかげで部員も徐々に増えて、正式な“部活”として名乗れるようになった。
今ではこの部活も俺にとってかけがえのない居場所だ。
それを作ってくれた緒方には本当に感謝している。
ってつい過去を懐かしんでしまったけど、とにかく昔から緒方は恐ろしいほどに空気が読める。
きっと、これまで柊哉の話と俺の話を両方聞いていて、ピンと来ちゃったんだろう。
「で、先輩はどうして高槻の気になる人は急に余所余所しくなったんだと思いますか?」
どうやら、緒方はこの話を終わりにするつもりはないらしく、笑顔の中に変な圧を感じる。
「さぁ……」
「さぁ、ですか。うーん、僕ね、高槻のこと結構好きなんですよ。いいやつだし」
緒方の言った“好き”という言葉にドキッとして、つい真顔になってしまった。
その表情を見て、緒方はフフっと笑った。
「瀬良先輩のことも好きですよ。僕は、好きな人には幸せになって欲しいんです。だから、ハッピーエンドを期待してますよ」
やっぱり、緒方は俺の気持ちも、柊哉の気持ちも察してこの話をしている。
これまでも何かにつけて緒方には助けてもらっているけど、まさか恋愛方面までもサポートしてもらうことになるとは思わなかった。
「うん……。俺、緒方にはずっと勝てない気がするわ……」
「あはは、ゲームでは負けっぱなしですけどね」
緒方のおかげで、くよくよとしていた気持ちもすっきりとして、週末に告白する覚悟もできた。
そう思っていたのに、簡単にうまくいかないのが世の常なのかもしれない。
いつものように八時過ぎには他の部員は帰宅して、俺一人でゲームをしていると、視聴覚室のドアが開いた音に気が付いた。
時計は九時少し前。この時間に尋ねてくるのは柊哉しかいない。
まだ対戦が終わっていなかったから、モニターに顔を向けたまま、振り向かずに声だけかけた。
「ごめん、柊哉。もうちょっとだけ待ってて」
「……柊哉って高槻のこと?」
後ろからした声は、柊哉じゃなかった。
俺は聞き覚えのあるその声に驚いて振り向くと、そこにいたのは相原だった。
「浩平……なに、何の用」
画面から目を離した瞬間、俺が操作していたキャラクターは一気に追い込まれ、画面には俺が負けたことを知らせる文字が浮かぶ。
その文字を背に、俺は相原を睨みつけた。
「いつの間に名前で呼ぶくらい高槻と仲良くなったんだよ」
「お前には関係ないだろ」
俺はモニターに向き直し、もう一度ゲームを始める。
もう少しすれば柊哉もここに来るし、それまで無視していれば相原も諦めて帰るだろう。
「火月、話聞けって」
そう言って相原は俺の腕を掴んで、持っていたコントローラーを奪った。
俺は驚いて腕を思いっきり振り払う。
なんでこいつはいつもいきなり俺の腕を掴むんだろうか。
「なんなんだよ!」
「そんなに怒るなよ。だから、話がしたいだけだって言ってるだろ」
腕を掴まれてついカッとしてしまったけど、少し前に自分も悪いところがあったと気が付いたことを思い出す。
少しだけ話を聞いてそれで終わりにしよう。
そう思ったのが間違いだった。
「はぁ……なに?」
俺が拒絶しなかったことに相原はあからさまにホッとした顔をした。
「あれからずっと気になってたんだ。家からも出て行っちゃうし、連絡もつかなくなったから……俺があんなこと言ったせいかなって」
確かに、相原に告白されてからすぐに実家を出て一人暮らしを始めた。
告白をされたせいで相原の家に行けなくなったことは、一人暮らしを始めるきっかけの一つくらいにはなってるかもしれない。
でも、家を出たことと告白をされたことは全く関係ない。
「家を出たのはあそこにいるのが限界だったからだ。お前とは関係ない」
「そっか……今は一人暮らしなんだろ? ちゃんと飯とか食べてる?」
「普通にしてるよ。ってか今更なんなの?」
そんなこと相原に心配される筋合いはないし、何なら柊哉のおかげで最近はすごく健康的な生活をしてる。
まぁ言わないけど。
それよりも、今更になってなぜ俺と話をしようと思ったんだろうか。
同じ学校に通ってるんだから、これまでだって話すチャンスなんていくらでもあったはずなのに。
「そう冷たくされるとへこむな……高槻とは楽しそうにしてるのに」
どうしてそこで柊哉の話が出てくるのか。
俺はすごく嫌な顔をして見せる。
でもこれでわかった。相原は俺と柊哉の関係を確認しに来たんだ。
「高槻と付き合ってるのか?」
やっぱりそうだった。俺はわざと大きくため息をついて、相原を睨んだ。
「お前には関係ない」
「関係ある……。お前は男をそういう対象として見られないんだと思ったから諦めてたんだ。なのになんで……! なんで俺じゃダメなんだ!」
相原は俺の両腕を掴んで壁に押さえつけた。
俺は振り払おうとするが、力が強くてびくともしない。
「は、離せ……!」
「俺はまだお前が好きなんだ!」
相原はそのまま俺の唇にキスをした。
嫌だ……!
俺は、俺の口を塞ぐ相原の唇を噛み、ひるんだすきに相原を思いっきり突き飛ばした。
「こういう、俺の気持ちを考えないところが嫌なんだよ!」
俺に突き飛ばされて尻もちをついた相原は、呆然とした顔をしている。
その唇には血が滲んでいた。
「……昔、お前が俺を部屋に入れてくれたことで俺は救われてた。それについては本当に感謝してる。でも、お前の気持ちには答えられない。俺は、こういうことを無理やりするやつを好きにはならない、絶対に」
俺は、ここですべてを終わらせるという思いで、はっきりと相原に言い放った。
「わかった、ごめん」
二年前からくすぶったままだった俺と相原の関係は、これでようやく終わることができた。
相原が部屋を出てから、俺はさっき無理やり抑え込まれたことの恐怖が後から襲ってきて、その場に座り込んでしまった。
柊哉に会いたい。
少しして落ち着きを取り戻すと時計は九時半を回っていた。
柊哉はまだ来ていなかった。
スマホを確認するけど、特に連絡もない。
でも、窓の外に見える体育館はすでに明かりが消えていた。
俺はさっき相原が出て行った部室のドアを見る。
もしかして、相原と一緒にいるところを見られた…?
柊哉に慌てて電話を掛けたけど、出ない。
メッセージも何度か送ったけど、結局その日、柊哉は部室に現れることもなく、折り返しもメッセージの返信どころか、既読にすらならなかった。
俺は本当に久しぶりに、一人で、歩いてマンションに帰った。
翌朝、スマホを確認すると柊哉からメッセージが届いていた。
『電話、出られなくてすみませんでした。昨日は急用ができて、先に帰りました』
当たり障りのないメッセージ。
やっぱり昨日、相原といたところを見て、それで何か勘違いをしたのかもしれない。
こんなことで、柊哉との関係を壊されたくない。今日会わないと……。
でも今はもう部活のはずだから、とりあえず『今日来れる?』とだけメッセージを入れた。
メッセージが既読になることなく、気が付けば夜の八時前。
電話をかけてもいいものか、俺はスマホを握り締めて、悩んでいた。
でも、会いたい。
今日こそ言うんだ。
好きだって。俺の隣にいてほしいって。
俺は、ぐっと腹に力を入れて、震える手でスマホを握り通話ボダンを押そうとした瞬間、スマホがメッセージを受信したことを知らせた。
慌てて開くと、それは柊哉からだった。
『今、学校出ました。もうご飯食べましたか?』
俺は急いで返信を打つ。心臓がバクバクして体から飛び出してきてしまいそうだ。
『まだ。今から来る?』
そうメッセージを送ると、すぐに既読になった。
『行ってもいいですか?』
『うん、いいよ』
またすぐに“既読”になった。よかった、来てくれる……。
俺はそわそわしながら、柊哉の到着を待った。
「お疲れ、柊哉」
「あっはい。遅くなってすいません」
「全然、大丈夫だよ」
今週はずっとそわそわしてしまって、まともに顔も見られなかった。
でも、今はちゃんと柊哉と向き合うって決めたから、真っ直ぐと柊哉を見つめる。
変わらない優しい視線に、今週これをずっと見逃していたのかと後悔した。
汗だくだという柊哉は先にシャワーを浴び、交代して俺がシャワーを浴びている最中にチャーハンを作ってくれた。
すっかり当たり前のように作ってくれるようになったご飯は、いつもおいしくて、俺のことを考えてくれているメニューばかり。
大切にされている、そう感じた。
二人とも食べ終えて、俺が後片付けをしている間に柊哉はソファでうとうととしていた。
今日は練習試合だったと言っていたし、きっと疲れたんだろう。
いつか、柊哉が試合をしているところも見てみたいな、なんて思いながらそのきれいな寝顔を見下ろす。
ふいに触れたくなって、俺はソファの背に手をついて片膝だけソファに乗せ、額にキスをした。
唇を離し、目を開くと、顔のすぐ真下にあった長い睫毛が動き、切れ長の目の中に俺が映る。
俺は驚いて後ろに下がると、その勢いでローテーブルにぶつかって転びそうになったと思ったら腕をひかれ、気が付いた時には柊哉の上に倒れ込んでいた。
「大丈夫ですか」
「う、うん、ごめん」
俺は慌てて柊哉から離れようとしたけど、柊哉は腕を掴んだままだ。
もう、恥ずかしくて爆発しそうだ。
「柊哉、離して」
何とか声を振り絞ると、それまで俺を強くつかんでいた手が少しだけ緩められた。
でも、放してはくれない。
柊哉に捕まれている腕がじんわりと熱い。
俺は、腕を掴まれるのが苦手だ。
腕を掴まれると、怒鳴られる。そんなトラウマがすり込まれているせいだと思う。
昨日、相原に腕を掴まれたときも、背筋が凍るかと思うほど嫌悪感でいっぱいだった。
でも、柊哉はイヤじゃない。それどころか、離してほしくない、もっと触ってほしいと思う。
同じ動作でも、柊哉はいつも優しくて、温かい。
好きな人って言うのはこんなにも特別なものなんだ。
柊哉の方をちらっと見ると、視線が合った。
あぁ好きだなぁと思ってその顔を眺めていると、柊哉は俺の頬に手を伸ばし、そのままそっと額にキスをした。
「お返しです」
いたずらっこのような顔でそう言うから、俺は恥ずかしさのあまり柊哉の腕を振り払ってソファに置かれていたクッションを顔めがけて投げつけた。
「お、お返しって、そもそも先にしたのは柊哉だろ! この間だって……!」
いや、違う。それよりも前に俺もしてる。もう混乱しすぎて、よくわかない。
「あれ、バレてましたか。じゃー最近余所余所しかったのはやっぱりそのせい?」
柊哉は俺が投げたクッションを抱え、少し恥ずかしそうな顔をした。
よかった、俺が初めてキスした時は本当に寝てたんだ。
それならわざわざ言う必要はないし、今話さないといけないのはそっちじゃない。
「ち、違う。それはもっと前から気づいてたし……」
「えっ……」
柊哉が俺を寝室に運んでから、額にキスをするようになったのは、部屋に泊まるようになってから何度目かのことだった。
初めはもちろん驚いたけど、嫌なんかじゃなかったし、むしろもっと、それ以上のことをしてくれないかな、なんて思ってた。
だから、我慢できなくなって、一人でシてなんとか発散してた。
「寝たふりしてたんですか。ひどい」
「し、してない! っていうか、なんで俺が責められる流れなんだよ! 寝込み襲ったのは柊哉だろ!」
「襲ってません。チューしただけです。それにさっき瀬良さんだって……」
「わーーー! もういい、もういいから!!」
俺の恥ずかしさは頂点に達して、もう限界まで来ている。
少しでも意識を落ち着けようと、両手で耳を塞ぎ、そのままソファの上で体を丸める。
自分でも何してるんだって思うけど、もう本当に爆発しそうなんだ。
しばらく縮こまっていると、柊哉は優しく髪を撫でてくれた。
いつも優しいこの手が俺は大好きだ。
「瀬良さん、顔上げてください」
髪に触れる手の温もりで、だんだんと気持ちも落ち着いていく。
俺は丸くなったまま目線だけを上げて柊哉を見た。
すると、すぐに柊哉は俺の手を引いて体を起こし、そのまま抱き寄せられた。
急に抱きしめられ、はじめは硬直していたけど、柊哉の腕の中で優しい匂いと温かさに包まれて、ほっと力が抜けていく。
それもつかの間、柊哉の腕にぐっと力が入り俺の耳元に吐息がかかる。
「瀬良さん。俺、瀬良さんのことが好きです」
それはずっと欲しかった言葉だった。
涙があふれて来る。
それを見た柊哉はそっと俺の瞼にキスした。
「瀬良さんは? 俺のこと好き?」
気持ちがあふれて、なかなか言葉が出てこない。
でも、答えたい。
好きだって、大好きだって。
「好きだよ、俺も柊哉のことが好きだ」
柊哉がもう一度ぎゅっと抱きしめてくれたから、俺も背中に手をまわしてそれに応える。
俺は泣きすぎて鼻グズグズだし、結局告白もできなかった。
後だしだけど、俺からも伝えたい。
自分の気持ちを伝えるってことがどれだけ難しいことなのか、俺も知ってるから。
少しでも、俺から何か返せるように。
「ねぇ柊哉……、俺を柊哉の恋人にしてくれる?」
柊哉は少し驚いた顔をした後、またいつもの優しい笑顔になってぎゅって抱きしめてくれた。
「もちろんです」
きみが踏み出してくれた一歩で、ついに隣に立つことができた。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
21
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる