1 / 12
第1章 初夜の宣言は「君を愛さない!」
しおりを挟む
わたし、セレナ・アルヴェールは、人生最大の晴れ舞台に立っていました。
きらびやかな王都の大聖堂。
ステンドグラスから差し込む光が、わたしが身につけた純白のドレスと、淡い金の髪をきらきらと照らします。
祭壇の前に立つのは、今日からわたしのお夫さまとなる、レオンハルト・グランツさま。
漆黒の髪と灰銀の瞳を持つ、寡黙な印象の青年です。
わたしは、政略結婚という名の使命のために、この場にいます。
伯爵家の次女として生まれたわたしに、いつか来るだろうと覚悟していた日でした。
相手は王都でも有数の名家、グランツ伯爵家の次男。
若くして独立し、子爵家の当主となった優秀な青年だという話です。
もちろん、お互いに顔を合わせるのは今日が初めてではありません。
顔合わせの席や、数度の社交の場ではご一緒しました。
ただ、そのすべてにおいて、レオンハルトさまは必要最小限の言葉しか口にしない、驚くほど無口で奥手な方でした。
そのため、わたしは彼のことを勝手に「氷の貴公子」などとあだ名をつけて、心の中でからかっていたものです。
まさか、その氷の貴公子さまが、わたしの夫になるとは。
わたしは、そんな状況も面白がってしまうような能天気な性格です。
父からは「くれぐれも失礼のないように」と厳しく言われていましたが、無理ですね。
王族でもなければ、わたしはただのアルヴェール伯爵家の次女。
夫との間に愛がなくとも、互いの利益のために協力する。
それでいいと割り切っていましたから。
結婚式を終え、馬車に乗り込んだわたしたちは、新居となるグランツ子爵家の離宮へと向かっていました。
馬車の中は、それはもう、気まずいほどの沈黙に包まれていました。
わたしが「あの、レオンハルトさま……」と口を開こうとすれば、彼は「セレナでいいだろ」とぶっきらぼうに言って、窓の外を見つめてしまいます。
ああ、そうですか。
名前を呼び合うことすら、こんなにぎこちないのですね。
わたしは、思わず笑いそうになりました。
この人が、こんなにも不器用で、しかも緊張しているなんて。
彼の耳が、ほんのり赤くなっているのをわたしは見逃しませんでしたよ。
「レオンハルトさま。もしかして、緊張されています?」
わたしがそう尋ねると、彼はびくりと肩を震わせ、そして勢いよくわたしの方を向きました。
「き、緊張などしていない!」
……どう見ても、緊張していますよね。
わたしはにこやかに微笑むと、彼の頬にそっと手を伸ばしました。
「大丈夫ですよ。わたしは、あなたのことを嫌いじゃありませんから」
彼の頬に触れると、ひどく熱を持った彼の肌がわたしの指先に伝わってきました。
わたしがそう言った途端、彼の顔は一気に真っ赤になります。
「は、離せ!」
そう言って、彼はわたしの手を振り払うと、まるで火傷でもしたかのように、自分の頬を触れていました。
わたしは、くすくすと笑いながら、窓の外の景色を眺めました。
ようやく馬車が止まり、新居に到着しました。
門をくぐり、庭を通り、屋敷の中へ。
屋敷の扉が開くと、そこには温かい光が灯されていました。
レオンハルトさまは、わたしの前に立ち、深々と頭を下げます。
「ようこそ、セレナ。ここが君の家だ」
彼の言葉に、わたしは思わず胸をときめかせました。
わたしがこの日を心待ちにしていたのは、政略結婚という使命のためだけではありません。
わたしは、ただの「妻」として、誰かと普通に笑い合える家庭を築くことを夢見ていましたから。
レオンハルトさまの不器用な優しさに、わたしは期待してしまいました。
しかし、その期待は、あっけなく打ち砕かれてしまいます。
「レオンハルトさま、どうぞこちらへ」
女中頭に案内され、たどり着いたのは寝室でした。
広々とした部屋には、暖炉の火が温かく燃えていて、大きな天蓋付きのベッドが中央に置かれています。
女中頭が部屋を出ていくと、レオンハルトさまは再び沈黙してしまいました。
わたしは、どうしたものかと悩んでいると、彼はゆっくりと、わたしの方を振り向きました。
「セレナ」
「はい、レオンハルトさま」
彼の声は、緊張からか、ほんの少し震えていました。
わたしは、彼の言葉を待っていました。
そして、彼は震える声で、わたしに告げたのです。
「聞いてくれ、セレナ。俺は……君を、愛することはない!」
その言葉を聞いた瞬間、わたしは、思わず目を見開いてしまいました。
まさか、初夜にそんなことを言われるなんて。
わたしは、彼の言葉の意味を理解しようと、頭の中をフル回転させました。
「愛することはない」
──それは、彼がわたしを嫌っているということでしょうか?
それとも、政略結婚だから、愛情は持てないということでしょうか?
どちらにしても、わたしは、彼がわたしのことを好きではないことを改めて突きつけられたのです。
わたしは、彼の言葉にどう答えればいいのか分からず、ただ、彼の顔を見つめることしかできませんでした。
しかし、わたしがそんな風に沈黙していると、彼は焦ったように言葉を続けます。
「これは、あくまで政略結婚だ! だから、お互いに干渉することなく、この結婚を全うすればいい! ……だ、だから、その、愛を求めてくるな! 絶対にだ!」
彼の必死な顔を見て、わたしは、ようやく理解しました。
ああ、なるほど。
彼は、緊張のあまり、こんな暴言を吐いてしまったのですね。
それに、彼は恋愛経験が皆無で、女性にどう接すればいいのか分からないのでしょう。
だから、こんな風に、突っ走ってしまったのですね。
わたしは、思わず笑いそうになるのを我慢し、にこやかに微笑んでみせました。
「それ、いいですね!」
「なっ!?」
わたしの予想外の返事に、レオンハルトさまはさらに目を丸くします。
「ええ、とてもいい考えですわ。レオンハルトさま。わたしたちは、お互い干渉しない“契約夫婦”として、気楽にいきましょうよ」
わたしがそう言うと、レオンハルトさまは、なぜか拍子抜けしたような顔をしていました。
「だ、だが、君は、その……悲しくないのか?」
「なぜです?」
「なぜって、その、愛を誓えないと言われたんだぞ?」
「ええ、そうですね。でも、これは政略結婚ですし。わたしもあなたに愛を求めてはいませんもの。お互い様です」
わたしがそう言うと、彼は「むぅ……」と唸りながら、何か考え込んでいました。
わたしは、そんな彼の姿を微笑ましく見つめます。
「では、レオンハルトさま。ひとつ、約束しませんか?」
「やくそく?」
「ええ。この契約夫婦生活が、わたしたちにとって、幸せなものになるように。そして、わたしたちが互いの秘密を守るために」
わたしがそう言うと、彼は、じっとわたしの目を見つめました。
「……秘密?」
「ええ。誰にだってそれぞれ触れてほしくない秘密なんて、一つや二つあるものでしょう? 夫婦だからって、すべてをさらけ出すのは止めましょう。互いに自由は尊重すべきよ。わたし、仕事も辞めるつもりもないし。あなたは騎士団の文官で、私は王女殿下の侍女ですものね」
わたしは、にこりと微笑んでみせました。
レオンハルトさまは、何も言いませんでしたが、彼の顔には「この女、まさか裏があるのか……!?」という驚愕の表情が浮かんでいました。
わたしは、そんな彼が面白くて仕方ありません。
「さあ、レオンハルトさま。わたくし、疲れてしまいました。もう休みましょう?」
わたしがそう言うと、彼は、ぎこちなく頷きました。
そして、彼はわたしに背を向け、ベッドへと向かいます。
わたしは、その背中を愛おしく思い、ゆっくりと彼に近づきました。
「レオンハルトさま」
「な、なんだ?」
わたしは、彼の背中にそっと手を回すと、彼の背中に顔をうずめます。
「おやすみなさいませ、レオンハルトさま。明日から、わたしたちの新しい生活が始まりますわね」
わたしの言葉に、彼の体がびくりと震えました。
彼は、わたしの手を振り払うことなく、ただ、じっとしていました。
わたしは、そんな彼に、くすくすと笑いながら、彼の背中から離れました。
「おやすみ、セレナ」
彼の声は、先ほどよりもずっと柔らかくなっていました。
わたしは、その声に、思わず胸が熱くなりました。
ああ、そうですか。
わたしも、あなたを嫌いじゃありませんよ、レオンハルトさま。
わたしたちの、不思議な契約夫婦生活が、今、始まったのですから。
きらびやかな王都の大聖堂。
ステンドグラスから差し込む光が、わたしが身につけた純白のドレスと、淡い金の髪をきらきらと照らします。
祭壇の前に立つのは、今日からわたしのお夫さまとなる、レオンハルト・グランツさま。
漆黒の髪と灰銀の瞳を持つ、寡黙な印象の青年です。
わたしは、政略結婚という名の使命のために、この場にいます。
伯爵家の次女として生まれたわたしに、いつか来るだろうと覚悟していた日でした。
相手は王都でも有数の名家、グランツ伯爵家の次男。
若くして独立し、子爵家の当主となった優秀な青年だという話です。
もちろん、お互いに顔を合わせるのは今日が初めてではありません。
顔合わせの席や、数度の社交の場ではご一緒しました。
ただ、そのすべてにおいて、レオンハルトさまは必要最小限の言葉しか口にしない、驚くほど無口で奥手な方でした。
そのため、わたしは彼のことを勝手に「氷の貴公子」などとあだ名をつけて、心の中でからかっていたものです。
まさか、その氷の貴公子さまが、わたしの夫になるとは。
わたしは、そんな状況も面白がってしまうような能天気な性格です。
父からは「くれぐれも失礼のないように」と厳しく言われていましたが、無理ですね。
王族でもなければ、わたしはただのアルヴェール伯爵家の次女。
夫との間に愛がなくとも、互いの利益のために協力する。
それでいいと割り切っていましたから。
結婚式を終え、馬車に乗り込んだわたしたちは、新居となるグランツ子爵家の離宮へと向かっていました。
馬車の中は、それはもう、気まずいほどの沈黙に包まれていました。
わたしが「あの、レオンハルトさま……」と口を開こうとすれば、彼は「セレナでいいだろ」とぶっきらぼうに言って、窓の外を見つめてしまいます。
ああ、そうですか。
名前を呼び合うことすら、こんなにぎこちないのですね。
わたしは、思わず笑いそうになりました。
この人が、こんなにも不器用で、しかも緊張しているなんて。
彼の耳が、ほんのり赤くなっているのをわたしは見逃しませんでしたよ。
「レオンハルトさま。もしかして、緊張されています?」
わたしがそう尋ねると、彼はびくりと肩を震わせ、そして勢いよくわたしの方を向きました。
「き、緊張などしていない!」
……どう見ても、緊張していますよね。
わたしはにこやかに微笑むと、彼の頬にそっと手を伸ばしました。
「大丈夫ですよ。わたしは、あなたのことを嫌いじゃありませんから」
彼の頬に触れると、ひどく熱を持った彼の肌がわたしの指先に伝わってきました。
わたしがそう言った途端、彼の顔は一気に真っ赤になります。
「は、離せ!」
そう言って、彼はわたしの手を振り払うと、まるで火傷でもしたかのように、自分の頬を触れていました。
わたしは、くすくすと笑いながら、窓の外の景色を眺めました。
ようやく馬車が止まり、新居に到着しました。
門をくぐり、庭を通り、屋敷の中へ。
屋敷の扉が開くと、そこには温かい光が灯されていました。
レオンハルトさまは、わたしの前に立ち、深々と頭を下げます。
「ようこそ、セレナ。ここが君の家だ」
彼の言葉に、わたしは思わず胸をときめかせました。
わたしがこの日を心待ちにしていたのは、政略結婚という使命のためだけではありません。
わたしは、ただの「妻」として、誰かと普通に笑い合える家庭を築くことを夢見ていましたから。
レオンハルトさまの不器用な優しさに、わたしは期待してしまいました。
しかし、その期待は、あっけなく打ち砕かれてしまいます。
「レオンハルトさま、どうぞこちらへ」
女中頭に案内され、たどり着いたのは寝室でした。
広々とした部屋には、暖炉の火が温かく燃えていて、大きな天蓋付きのベッドが中央に置かれています。
女中頭が部屋を出ていくと、レオンハルトさまは再び沈黙してしまいました。
わたしは、どうしたものかと悩んでいると、彼はゆっくりと、わたしの方を振り向きました。
「セレナ」
「はい、レオンハルトさま」
彼の声は、緊張からか、ほんの少し震えていました。
わたしは、彼の言葉を待っていました。
そして、彼は震える声で、わたしに告げたのです。
「聞いてくれ、セレナ。俺は……君を、愛することはない!」
その言葉を聞いた瞬間、わたしは、思わず目を見開いてしまいました。
まさか、初夜にそんなことを言われるなんて。
わたしは、彼の言葉の意味を理解しようと、頭の中をフル回転させました。
「愛することはない」
──それは、彼がわたしを嫌っているということでしょうか?
それとも、政略結婚だから、愛情は持てないということでしょうか?
どちらにしても、わたしは、彼がわたしのことを好きではないことを改めて突きつけられたのです。
わたしは、彼の言葉にどう答えればいいのか分からず、ただ、彼の顔を見つめることしかできませんでした。
しかし、わたしがそんな風に沈黙していると、彼は焦ったように言葉を続けます。
「これは、あくまで政略結婚だ! だから、お互いに干渉することなく、この結婚を全うすればいい! ……だ、だから、その、愛を求めてくるな! 絶対にだ!」
彼の必死な顔を見て、わたしは、ようやく理解しました。
ああ、なるほど。
彼は、緊張のあまり、こんな暴言を吐いてしまったのですね。
それに、彼は恋愛経験が皆無で、女性にどう接すればいいのか分からないのでしょう。
だから、こんな風に、突っ走ってしまったのですね。
わたしは、思わず笑いそうになるのを我慢し、にこやかに微笑んでみせました。
「それ、いいですね!」
「なっ!?」
わたしの予想外の返事に、レオンハルトさまはさらに目を丸くします。
「ええ、とてもいい考えですわ。レオンハルトさま。わたしたちは、お互い干渉しない“契約夫婦”として、気楽にいきましょうよ」
わたしがそう言うと、レオンハルトさまは、なぜか拍子抜けしたような顔をしていました。
「だ、だが、君は、その……悲しくないのか?」
「なぜです?」
「なぜって、その、愛を誓えないと言われたんだぞ?」
「ええ、そうですね。でも、これは政略結婚ですし。わたしもあなたに愛を求めてはいませんもの。お互い様です」
わたしがそう言うと、彼は「むぅ……」と唸りながら、何か考え込んでいました。
わたしは、そんな彼の姿を微笑ましく見つめます。
「では、レオンハルトさま。ひとつ、約束しませんか?」
「やくそく?」
「ええ。この契約夫婦生活が、わたしたちにとって、幸せなものになるように。そして、わたしたちが互いの秘密を守るために」
わたしがそう言うと、彼は、じっとわたしの目を見つめました。
「……秘密?」
「ええ。誰にだってそれぞれ触れてほしくない秘密なんて、一つや二つあるものでしょう? 夫婦だからって、すべてをさらけ出すのは止めましょう。互いに自由は尊重すべきよ。わたし、仕事も辞めるつもりもないし。あなたは騎士団の文官で、私は王女殿下の侍女ですものね」
わたしは、にこりと微笑んでみせました。
レオンハルトさまは、何も言いませんでしたが、彼の顔には「この女、まさか裏があるのか……!?」という驚愕の表情が浮かんでいました。
わたしは、そんな彼が面白くて仕方ありません。
「さあ、レオンハルトさま。わたくし、疲れてしまいました。もう休みましょう?」
わたしがそう言うと、彼は、ぎこちなく頷きました。
そして、彼はわたしに背を向け、ベッドへと向かいます。
わたしは、その背中を愛おしく思い、ゆっくりと彼に近づきました。
「レオンハルトさま」
「な、なんだ?」
わたしは、彼の背中にそっと手を回すと、彼の背中に顔をうずめます。
「おやすみなさいませ、レオンハルトさま。明日から、わたしたちの新しい生活が始まりますわね」
わたしの言葉に、彼の体がびくりと震えました。
彼は、わたしの手を振り払うことなく、ただ、じっとしていました。
わたしは、そんな彼に、くすくすと笑いながら、彼の背中から離れました。
「おやすみ、セレナ」
彼の声は、先ほどよりもずっと柔らかくなっていました。
わたしは、その声に、思わず胸が熱くなりました。
ああ、そうですか。
わたしも、あなたを嫌いじゃありませんよ、レオンハルトさま。
わたしたちの、不思議な契約夫婦生活が、今、始まったのですから。
0
あなたにおすすめの小説

結婚初夜、「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と夫に言われました
ましゅぺちーの
恋愛
侯爵令嬢のアリサは婚約者だった王太子テオドールと結婚した。
ちょうどその半年前、アリサの腹違いの妹のシアは不慮の事故で帰らぬ人となっていた。
王太子が婚約者の妹のシアを愛していたのは周知の事実だった。
そんな彼は、結婚初夜、アリサに冷たく言い放った。
「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と。

【完】出来損ない令嬢は、双子の娘を持つ公爵様と契約結婚する~いつの間にか公爵様と7歳のかわいい双子たちに、めいっぱい溺愛されていました~
夏芽空
恋愛
子爵令嬢のエレナは、常に優秀な妹と比較され家族からひどい扱いを受けてきた。
しかし彼女は7歳の双子の娘を持つ公爵――ジオルトと契約結婚したことで、最低な家族の元を離れることができた。
しかも、条件は最高。公の場で妻を演じる以外は自由に過ごしていい上に、さらには給料までも出してくてれるという。
夢のような生活を手に入れた――と、思ったのもつかの間。
いきなり事件が発生してしまう。
結婚したその翌日に、双子の姉が令嬢教育の教育係をやめさせてしまった。
しかもジオルトは仕事で出かけていて、帰ってくるのはなんと一週間後だ。
(こうなったら、私がなんとかするしかないわ!)
腹をくくったエレナは、おもいきった行動を起こす。
それがきっかけとなり、ちょっと癖のある美少女双子義娘と、彼女たちよりもさらに癖の強いジオルトとの距離が縮まっていくのだった――。


「出て行け!」と言われたのですから、本当に出て行ってあげます!
睡蓮
恋愛
アレス第一王子はイザベラとの婚約関係の中で、彼女の事を激しく束縛していた。それに対してイザベラが言葉を返したところ、アレスは「気に入らないなら出て行ってくれて構わない」と口にしてしまう。イザベラがそんな大それた行動をとることはないだろうと踏んでアレスはその言葉をかけたわけであったが、その日の夜にイザベラは本当に姿を消してしまう…。自分の行いを必死に隠しにかかるアレスであったが、それから間もなくこの一件は国王の耳にまで入ることとなり…。

『婚約者を大好きな自分』を演じてきた侯爵令嬢、自立しろと言われたので、好き勝手に生きていくことにしました
皇 翼
恋愛
「リーシャ、君も俺にかまってばかりいないで、自分の趣味でも見つけて自立したらどうだ?正直、こうやって話しかけられるのはその――やめて欲しいんだ……周りの目もあるし、君なら分かるだろう?」
頭を急に鈍器で殴られたような感覚に陥る一言だった。
彼がチラリと見るのは周囲。2学年上の彼の教室の前であったというのが間違いだったのかもしれない。
この一言で彼女の人生は一変した――。
******
※タイトル少し変えました。
・暫く書いていなかったらかなり文体が変わってしまったので、書き直ししています。
・トラブル回避のため、完結まで感想欄は開きません。

精霊姫の追放
あんど もあ
ファンタジー
栄華を極める国の国王が亡くなり、国王が溺愛していた幼い少女の姿の精霊姫を離宮から追放する事に。だが、その精霊姫の正体は……。
「優しい世界」と「ざまあ」の2バージョン。

悪役令嬢は婚約破棄されてからが本番です~次期宰相殿下の溺愛が重すぎて困っています~
usako
恋愛
侯爵令嬢リリアナは、王太子から公衆の面前で婚約破棄を告げられる。
「あなたのような冷酷な女と結婚できない!」
そう断罪された瞬間――リリアナの人生は終わりを迎えるはずだった。
だが彼女は知っている。この展開が“破滅フラグ”だと。
生まれ変わりの記憶を持つ彼女は、今度こそ幸せを掴むと誓う。
ところが、彼女を拾ったのは冷徹と名高い次期宰相殿下シオン。
「君は俺の庇護下に入る。もう誰にも傷つけさせない」
傲慢な王太子にざまぁされ、愛しすぎる殿下から逃げられない――
運命に抗う令嬢と、彼女を手放せない男の甘く激しい恋の再生譚。
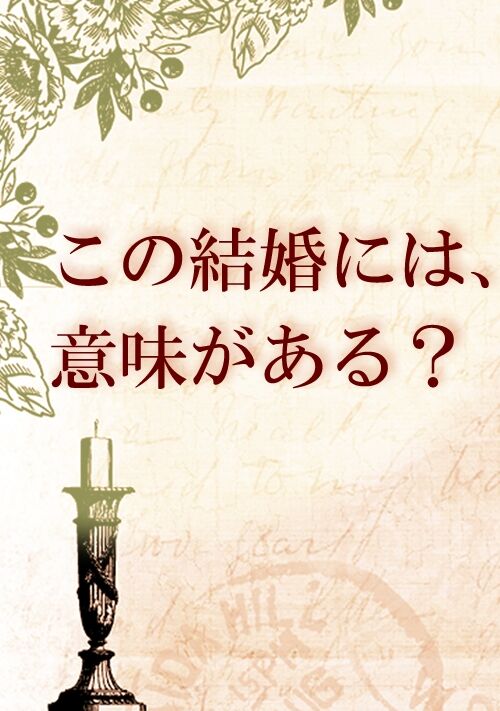
この結婚には、意味がある?
みこと。
恋愛
公爵家に降嫁した王女アリアは、初夜に夫から「オープンマリッジ」を提案される。
婚姻関係を維持しながら、他の異性との遊戯を認めろ、という要求を、アリアはどう解釈するのか?
王宮で冷遇されていた王女アリアの、密かな目的とは。
この結婚は、アリアにとってどんな意味がある?
※他のサイトにも掲載しています。
※他タイトル『沈黙の聖女は、ある日すべてを暴露する』も収録。←まったく別のお話です
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















