2 / 12
第2章 秘密を抱えた夫婦
しおりを挟む
「おはようございます、レオンハルトさま」
「……おはよう、セレナ」
あれから数週間が経ち、わたしたちの朝はすっかりこの挨拶で始まるようになりました。
朝食のテーブルは、慣れない空気が少しずつ溶けて、ほんの少しだけ温かいものに変わりつつあります。
わたしが淹れたハーブティーを一口飲むたびに、レオンハルトさまがわずかに口角を上げるのを、わたしは密かに楽しみにしているのです。
政略結婚から始まった夫婦生活は、想像していたよりもずっと穏やかで、しかし予測不能なものでした。
レオンハルトさまは、初夜の宣言通り、わたしに干渉しようとしません。
わたしもまた仕事として、王女付き侍女という表の顔と、宰相直属の情報員という裏の顔を持つ身として、彼に立ち入るつもりはありませんでした。
ところが、どうしてでしょうか。
先日、朝食の準備をしていた時のこと。
わたしの手から、滑りやすいガラスのジャム瓶がするりと落ちそうになったのです。
「あ!」
反射的に声を上げると、レオンハルトさまはすさまじい速さで手を伸ばし、わたしの手と瓶の間にすっと指を差し込みました。
「……危ない」
彼の大きな手が、わたしの手と瓶を優しく包み込むように支えています。
彼の指先がわたしの手の甲を撫でるように触れ、その熱がじんわりと伝わってきました。
「……ありがとうございます」
わたしは、心臓の音がうるさくて、うつむいてしまいました。
彼はすぐに手を離しましたが、わたしにはなぜかその温もりがしばらく残っているような気がして、妙に意識してしまうのでした。
互いに干渉しないはずなのに、気づけば互いのことばかり考えている。
それが、わたしたちの「秘密の夫婦生活」の始まりでした。
***
王城での勤務は、わたしの生活から切っても切り離せないものです。
表向きは、王女殿下の身の回りのお世話をする侍女。
ですが、裏では王宮内の噂話や、貴族間の小さな衝突、外国からの使者の動向まで、ありとあらゆる情報を収集しています。
「セレナ、この書類を宰相閣下に届けてくれるかしら」
わたしは、王女殿下から手渡された一通の封筒を受け取り、宰相の執務室へと向かいました。
廊下を歩いていると、すれ違う王宮勤めの文官や騎士たちが、わたしににこやかに挨拶をします。
わたしは、そんな彼ら一人ひとりに、笑顔で丁寧に頭を下げます。
そこに夫のレオンハルトさまもいました。
(……あ、彼、騎士団の文官だもの。最近、帝国との国境付近で不穏な動きがあるって話だから、何か情報を持っていないかしら)
わたしの頭の中は、常に情報収集モードです。
宰相の執務室の扉をノックし中へ入ると、宰相はわたしを温かく迎え入れてくれました。
「ご苦労だったね、セレナ」
「はい。王女殿下からのご伝言です」
わたしは、そう言って封筒を手渡すと、宰相は満足そうに頷きました。
「君には、本当に助けられているよ。まさか、結婚してからも続けてくれるとは」
「ええ。わたしも、この仕事が好きですから」
わたしは、にこやかに答えます。
この仕事は、わたしにとって誇りでした。
しかし、その誇りは、夫であるレオンハルトさまには言えない秘密なのです。
その日の夜、わたしは王城での任務を終え、へとへとに疲れ果てて馬車に揺られていました。
(ああ、早くお家に着いて、温かいミルクティーを飲みたい……)
そう思いながら屋敷の門をくぐると、玄関の明かりが灯っています。
レオンハルトさまが、わたしを待っていてくださったのでしょうか。
「……レオンハルトさま?」
わたしが声をかけると、彼は椅子から立ち上がり、わたしの元へと歩み寄ってきました。
「遅かったな。何かあったのか?」
「いいえ、ただ少し、仕事が長引いてしまって。レオンハルトさまこそ、お疲れではないですか?」
わたしがそう尋ねると、彼は一瞬、目を伏せました。
彼の右手の甲に、小さな擦り傷があるのをわたしは見逃しませんでした。
「レオンハルトさま、そのお怪我は……?」
わたしがそう言って、彼の手にそっと触れると、彼は慌てたように手を引っ込めました。
「たいしたことない。仕事中に書類に引っかかってな」
「書類でこんな傷はつきませんよね……」
わたしがそう言うと、彼は「むぅ……」と唸り、それ以上何も言いませんでした。
(おかしい。この傷は、書類でついたものではないわ。まるで、何か硬いものを握りしめたような……)
わたしは、彼の秘密に、少しだけ触れたような気がしました。
それからというもの、わたしたちは互いの秘密を探り合うようになりました。
夜遅く帰宅したわたしを、彼は何も言わずに待っていてくれる。
そのたびに、彼の服の裾に、見慣れない土が付いていたり、彼の髪の毛に枯葉が絡まっていたりするのです。
「レオンハルトさま、お庭のお手入れをされたのですか?」
「……いや、違う」
彼はそう言って、慌てて髪の毛を整えようとしますが、わたしは彼の不器用な姿に、心の中で微笑んでしまいます。
一方で、わたしも彼に怪しまれないよう、注意を払っていました。
「セレナ、そのスカートの裾、少し汚れているが……」
彼がそう言って、わたしのスカートの裾に触れようとした時、わたしは慌ててそれを隠しました。
「まあ! わたくしったら、お転婆でしたわ。でもご心配なく、明日の朝には綺麗にしておきますから」
わたしがそう言うと、彼は何も言いませんでしたが、彼の灰銀の瞳は、わたしをじっと見つめていました。
そんなある日の夜、わたしは書斎で宰相からの緊急の伝言を受け取っていました。
「──明日、帝国から新たな使節団が王都へ到着する。王家主催の舞踏会で、彼らの動向を探れ」
わたしは、小さく頷きました。
(舞踏会か……。わたしは、メイドに化けて潜入しましょうか)
離宮の書斎で、わたしがそう思案していると、背後から気配がしました。
「……夜更けまで、何を読んでいるんだ」
振り返ると、そこにはレオンハルトさまが立っていました。
わたしは、慌てて手元の書類を隠します。
「まあ、レオンハルトさま。こんな時間にどうなさいました?」
「いや、少し喉が渇いてな」
彼は、そう言って、わたしに近づいてきます。
わたしは、彼の背後から、見慣れない剣の鞘がチラリと見えたのを見逃しませんでした。
(おかしいわ。騎士団の文官が、なぜこんな時間に剣を持っているの?)
「セレナ、もしかして……」
彼は、わたしの手元をじっと見つめています。
わたしは、彼がわたしの秘密に気づいたのではないかと、思わず息を飲みました。
「……また、指先が冷えているんだろ?」
彼の言葉に、わたしは拍子抜けしてしまいました。
彼はそう言うと、わたしの手を取り、自分の手のひらで温め始めました。
「任務、ですか?」
わたしは、からかうように尋ねました。
「……そうだ。これは、俺の任務だ」
彼は、そう言って、少しだけはにかむように微笑みました。
わたしは、そんな彼が愛おしくて仕方ありませんでした。
(この人は、本当に不器用ね)
わたしたちは秘密を抱えたまま、互いの手を握りしめ、静かに夜を過ごしました。
「……おはよう、セレナ」
あれから数週間が経ち、わたしたちの朝はすっかりこの挨拶で始まるようになりました。
朝食のテーブルは、慣れない空気が少しずつ溶けて、ほんの少しだけ温かいものに変わりつつあります。
わたしが淹れたハーブティーを一口飲むたびに、レオンハルトさまがわずかに口角を上げるのを、わたしは密かに楽しみにしているのです。
政略結婚から始まった夫婦生活は、想像していたよりもずっと穏やかで、しかし予測不能なものでした。
レオンハルトさまは、初夜の宣言通り、わたしに干渉しようとしません。
わたしもまた仕事として、王女付き侍女という表の顔と、宰相直属の情報員という裏の顔を持つ身として、彼に立ち入るつもりはありませんでした。
ところが、どうしてでしょうか。
先日、朝食の準備をしていた時のこと。
わたしの手から、滑りやすいガラスのジャム瓶がするりと落ちそうになったのです。
「あ!」
反射的に声を上げると、レオンハルトさまはすさまじい速さで手を伸ばし、わたしの手と瓶の間にすっと指を差し込みました。
「……危ない」
彼の大きな手が、わたしの手と瓶を優しく包み込むように支えています。
彼の指先がわたしの手の甲を撫でるように触れ、その熱がじんわりと伝わってきました。
「……ありがとうございます」
わたしは、心臓の音がうるさくて、うつむいてしまいました。
彼はすぐに手を離しましたが、わたしにはなぜかその温もりがしばらく残っているような気がして、妙に意識してしまうのでした。
互いに干渉しないはずなのに、気づけば互いのことばかり考えている。
それが、わたしたちの「秘密の夫婦生活」の始まりでした。
***
王城での勤務は、わたしの生活から切っても切り離せないものです。
表向きは、王女殿下の身の回りのお世話をする侍女。
ですが、裏では王宮内の噂話や、貴族間の小さな衝突、外国からの使者の動向まで、ありとあらゆる情報を収集しています。
「セレナ、この書類を宰相閣下に届けてくれるかしら」
わたしは、王女殿下から手渡された一通の封筒を受け取り、宰相の執務室へと向かいました。
廊下を歩いていると、すれ違う王宮勤めの文官や騎士たちが、わたしににこやかに挨拶をします。
わたしは、そんな彼ら一人ひとりに、笑顔で丁寧に頭を下げます。
そこに夫のレオンハルトさまもいました。
(……あ、彼、騎士団の文官だもの。最近、帝国との国境付近で不穏な動きがあるって話だから、何か情報を持っていないかしら)
わたしの頭の中は、常に情報収集モードです。
宰相の執務室の扉をノックし中へ入ると、宰相はわたしを温かく迎え入れてくれました。
「ご苦労だったね、セレナ」
「はい。王女殿下からのご伝言です」
わたしは、そう言って封筒を手渡すと、宰相は満足そうに頷きました。
「君には、本当に助けられているよ。まさか、結婚してからも続けてくれるとは」
「ええ。わたしも、この仕事が好きですから」
わたしは、にこやかに答えます。
この仕事は、わたしにとって誇りでした。
しかし、その誇りは、夫であるレオンハルトさまには言えない秘密なのです。
その日の夜、わたしは王城での任務を終え、へとへとに疲れ果てて馬車に揺られていました。
(ああ、早くお家に着いて、温かいミルクティーを飲みたい……)
そう思いながら屋敷の門をくぐると、玄関の明かりが灯っています。
レオンハルトさまが、わたしを待っていてくださったのでしょうか。
「……レオンハルトさま?」
わたしが声をかけると、彼は椅子から立ち上がり、わたしの元へと歩み寄ってきました。
「遅かったな。何かあったのか?」
「いいえ、ただ少し、仕事が長引いてしまって。レオンハルトさまこそ、お疲れではないですか?」
わたしがそう尋ねると、彼は一瞬、目を伏せました。
彼の右手の甲に、小さな擦り傷があるのをわたしは見逃しませんでした。
「レオンハルトさま、そのお怪我は……?」
わたしがそう言って、彼の手にそっと触れると、彼は慌てたように手を引っ込めました。
「たいしたことない。仕事中に書類に引っかかってな」
「書類でこんな傷はつきませんよね……」
わたしがそう言うと、彼は「むぅ……」と唸り、それ以上何も言いませんでした。
(おかしい。この傷は、書類でついたものではないわ。まるで、何か硬いものを握りしめたような……)
わたしは、彼の秘密に、少しだけ触れたような気がしました。
それからというもの、わたしたちは互いの秘密を探り合うようになりました。
夜遅く帰宅したわたしを、彼は何も言わずに待っていてくれる。
そのたびに、彼の服の裾に、見慣れない土が付いていたり、彼の髪の毛に枯葉が絡まっていたりするのです。
「レオンハルトさま、お庭のお手入れをされたのですか?」
「……いや、違う」
彼はそう言って、慌てて髪の毛を整えようとしますが、わたしは彼の不器用な姿に、心の中で微笑んでしまいます。
一方で、わたしも彼に怪しまれないよう、注意を払っていました。
「セレナ、そのスカートの裾、少し汚れているが……」
彼がそう言って、わたしのスカートの裾に触れようとした時、わたしは慌ててそれを隠しました。
「まあ! わたくしったら、お転婆でしたわ。でもご心配なく、明日の朝には綺麗にしておきますから」
わたしがそう言うと、彼は何も言いませんでしたが、彼の灰銀の瞳は、わたしをじっと見つめていました。
そんなある日の夜、わたしは書斎で宰相からの緊急の伝言を受け取っていました。
「──明日、帝国から新たな使節団が王都へ到着する。王家主催の舞踏会で、彼らの動向を探れ」
わたしは、小さく頷きました。
(舞踏会か……。わたしは、メイドに化けて潜入しましょうか)
離宮の書斎で、わたしがそう思案していると、背後から気配がしました。
「……夜更けまで、何を読んでいるんだ」
振り返ると、そこにはレオンハルトさまが立っていました。
わたしは、慌てて手元の書類を隠します。
「まあ、レオンハルトさま。こんな時間にどうなさいました?」
「いや、少し喉が渇いてな」
彼は、そう言って、わたしに近づいてきます。
わたしは、彼の背後から、見慣れない剣の鞘がチラリと見えたのを見逃しませんでした。
(おかしいわ。騎士団の文官が、なぜこんな時間に剣を持っているの?)
「セレナ、もしかして……」
彼は、わたしの手元をじっと見つめています。
わたしは、彼がわたしの秘密に気づいたのではないかと、思わず息を飲みました。
「……また、指先が冷えているんだろ?」
彼の言葉に、わたしは拍子抜けしてしまいました。
彼はそう言うと、わたしの手を取り、自分の手のひらで温め始めました。
「任務、ですか?」
わたしは、からかうように尋ねました。
「……そうだ。これは、俺の任務だ」
彼は、そう言って、少しだけはにかむように微笑みました。
わたしは、そんな彼が愛おしくて仕方ありませんでした。
(この人は、本当に不器用ね)
わたしたちは秘密を抱えたまま、互いの手を握りしめ、静かに夜を過ごしました。
0
あなたにおすすめの小説

結婚初夜、「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と夫に言われました
ましゅぺちーの
恋愛
侯爵令嬢のアリサは婚約者だった王太子テオドールと結婚した。
ちょうどその半年前、アリサの腹違いの妹のシアは不慮の事故で帰らぬ人となっていた。
王太子が婚約者の妹のシアを愛していたのは周知の事実だった。
そんな彼は、結婚初夜、アリサに冷たく言い放った。
「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と。

【完】出来損ない令嬢は、双子の娘を持つ公爵様と契約結婚する~いつの間にか公爵様と7歳のかわいい双子たちに、めいっぱい溺愛されていました~
夏芽空
恋愛
子爵令嬢のエレナは、常に優秀な妹と比較され家族からひどい扱いを受けてきた。
しかし彼女は7歳の双子の娘を持つ公爵――ジオルトと契約結婚したことで、最低な家族の元を離れることができた。
しかも、条件は最高。公の場で妻を演じる以外は自由に過ごしていい上に、さらには給料までも出してくてれるという。
夢のような生活を手に入れた――と、思ったのもつかの間。
いきなり事件が発生してしまう。
結婚したその翌日に、双子の姉が令嬢教育の教育係をやめさせてしまった。
しかもジオルトは仕事で出かけていて、帰ってくるのはなんと一週間後だ。
(こうなったら、私がなんとかするしかないわ!)
腹をくくったエレナは、おもいきった行動を起こす。
それがきっかけとなり、ちょっと癖のある美少女双子義娘と、彼女たちよりもさらに癖の強いジオルトとの距離が縮まっていくのだった――。


「出て行け!」と言われたのですから、本当に出て行ってあげます!
睡蓮
恋愛
アレス第一王子はイザベラとの婚約関係の中で、彼女の事を激しく束縛していた。それに対してイザベラが言葉を返したところ、アレスは「気に入らないなら出て行ってくれて構わない」と口にしてしまう。イザベラがそんな大それた行動をとることはないだろうと踏んでアレスはその言葉をかけたわけであったが、その日の夜にイザベラは本当に姿を消してしまう…。自分の行いを必死に隠しにかかるアレスであったが、それから間もなくこの一件は国王の耳にまで入ることとなり…。

『婚約者を大好きな自分』を演じてきた侯爵令嬢、自立しろと言われたので、好き勝手に生きていくことにしました
皇 翼
恋愛
「リーシャ、君も俺にかまってばかりいないで、自分の趣味でも見つけて自立したらどうだ?正直、こうやって話しかけられるのはその――やめて欲しいんだ……周りの目もあるし、君なら分かるだろう?」
頭を急に鈍器で殴られたような感覚に陥る一言だった。
彼がチラリと見るのは周囲。2学年上の彼の教室の前であったというのが間違いだったのかもしれない。
この一言で彼女の人生は一変した――。
******
※タイトル少し変えました。
・暫く書いていなかったらかなり文体が変わってしまったので、書き直ししています。
・トラブル回避のため、完結まで感想欄は開きません。

精霊姫の追放
あんど もあ
ファンタジー
栄華を極める国の国王が亡くなり、国王が溺愛していた幼い少女の姿の精霊姫を離宮から追放する事に。だが、その精霊姫の正体は……。
「優しい世界」と「ざまあ」の2バージョン。

悪役令嬢は婚約破棄されてからが本番です~次期宰相殿下の溺愛が重すぎて困っています~
usako
恋愛
侯爵令嬢リリアナは、王太子から公衆の面前で婚約破棄を告げられる。
「あなたのような冷酷な女と結婚できない!」
そう断罪された瞬間――リリアナの人生は終わりを迎えるはずだった。
だが彼女は知っている。この展開が“破滅フラグ”だと。
生まれ変わりの記憶を持つ彼女は、今度こそ幸せを掴むと誓う。
ところが、彼女を拾ったのは冷徹と名高い次期宰相殿下シオン。
「君は俺の庇護下に入る。もう誰にも傷つけさせない」
傲慢な王太子にざまぁされ、愛しすぎる殿下から逃げられない――
運命に抗う令嬢と、彼女を手放せない男の甘く激しい恋の再生譚。
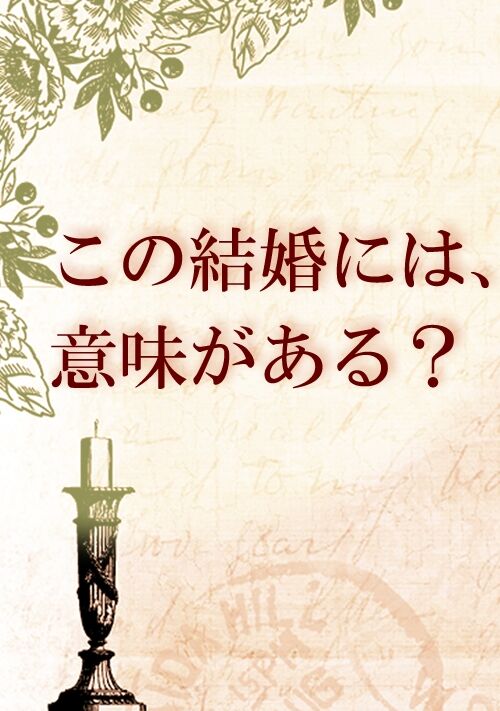
この結婚には、意味がある?
みこと。
恋愛
公爵家に降嫁した王女アリアは、初夜に夫から「オープンマリッジ」を提案される。
婚姻関係を維持しながら、他の異性との遊戯を認めろ、という要求を、アリアはどう解釈するのか?
王宮で冷遇されていた王女アリアの、密かな目的とは。
この結婚は、アリアにとってどんな意味がある?
※他のサイトにも掲載しています。
※他タイトル『沈黙の聖女は、ある日すべてを暴露する』も収録。←まったく別のお話です
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















