31 / 68
2章
19話 メメントモリ①
しおりを挟む
二十分ほどの短いバスツアーを終え、着いたのは六本木にある国立新美術館だった。
協会に保護されて、はや一か月。漣にとっては初めて許された外出だったが、空は生憎の雨模様でうんざりさせられる。六月も終盤に差しかかり、ここ一週間は梅雨らしいじめついた天気が続いている。
別に、雨に降られるのは構わない。むしろ雨そのものは好きだ。濡れた路面に映り込む街。滲む夜の光。通りに咲く色とりどりの傘と、帰り路を急ぐ人々の足取りは、どこか懐かしい気分にさせてくれる――が、問題はこの湿気だ。のべつ幕なしに身体を包むじめじめとした空気のせいで、肌どころか骨さえ腐り落ちそうだ。
「……痒っ」
首元を掻きながら、溜息まじりに漣はぼやく。ただでさえ湿気で鬱陶しい上、つけ慣れないチョーカーが不快感をいやましにする。
エントランス前に横付けされたバスを降り、正面エントランスから建物内に入る。この美術館にも漣は何度か足を運んだことがある。建築家の黒川紀章が設計した総ガラス張りの外観は、人工的でありながらも周囲の緑と優しく調和している。見上げるほどの天井を擁する吹き抜けのロビーには、これが晴天時ならたっぷりと日差しが降り注いでいただろう。
ただ、ひんやりと乾いた館内の空気は、それだけでも漣にひとときの安らぎを与えた。
「出発時にご説明したとおり、館内での行動は自由です! ただし、建物の外に出ることはできません! 万が一、外に出るにしても、行動は半径三百メートル以内に留めてください!」
ロビーに集合した三十名ほどの一行に、そう声を張り上げるのは非ギフテッドの事務員だ。協会では非ギフテッドの職員が、主に事務職や施設の管理要員として働いている。皆、非正規ではなく国家公務員として正規に雇われた人々だ。これも、機密を守るためのコスト、ということだろう。
まるで小学校の遠足だな、と、職員の注意を聞きながら漣は思う。引率される人間のほとんどは、いい歳をした大人たちで、社会における自分達の立ち位置を理解する人間がほとんどだろう。そうした人々が安易に逃走を図るとは思わない。あるいは……ここにも彼らと漣との間に意識のギャップがあるのかもしれない。漣は、半ば刑務所に収監されたつもりで施設にいるが、彼らにしてみればどこまでも理不尽な措置なのだ。
気を取り直し、ロビーを飾る巨大な垂れ幕を見上げる。ゴッホの『星月夜』をメインビジュアルに用いた垂れ幕には、白抜きの文字で『大印象派展』と堂々記されている。
明日からこの美術館では、印象派をテーマに大型の展覧会が開催される。
そうした展覧会の前には、必ず、ギフテッド向けの内覧会が組まれるのだそうだ。施設内の住人から希望者を募り、貸し切りで特別に鑑賞できるのだ。この日も、美術館は休館日という体を取っているが、これがギフテッドのための特別な計らいであることを、関係者なら誰もが知っている。
この日のために、漣は施設の図書室にあるだけの関連書籍を読み漁ってきた。
印象派の誕生は、社会制度の変革や、科学技術の進歩と分けて語ることはできない。それまでの貴族社会では、主に貴族がパトロンとなり、主題も彼らが求めるものに限られていた。が、市民革命により社会の主役は名もなき庶民へとバトンタッチする。そうした変化の中で、アーティスト達の画題も庶民の暮らしに寄り添ったものへとシフトしていった。さらにチューブ式絵具の発明により、屋外での自由なドローイングが可能となったことで、自然光を表現するための試行錯誤が始まる。もちろん、写真の登場で必ずしも写実に囚われる必要がなくなったせいもあるが、嶋野が以前語ったとおり、それは、あくまでも要因の一つにすぎない。
展示は、漣の想像以上に充実していた。
ただ絵を並べるだけでなく、印象派が生まれた経緯や時代背景、後世のアートに残した影響なども俯瞰的に紹介している。揺籃となったバルビゾン派の紹介から、東洋文化、とりわけ浮世絵との邂逅が与えた影響。それは当時の帝国主義とは不可分の現象で――といった注釈が会場のあちこちに掲示され、一巡するだけで概要を把握できる流れになっている。
そうしてアートへの理解を深めた上で、改めて絵に目を戻すと、やはり、解像度が上がっているなと感じる。技巧に込められた表現の意図、だけではない。アーティストが鑑賞者と共有したかったもの――おそらくは、そう、願い。
これが審美眼と呼ばれる力の正体なら、今この瞬間、確かに審美眼は鍛えられつつあるのだろう。それは同時に、キュレーターになる、という目標に一歩前進したことを意味している。
――ううん駄目! 絶対に駄目だからねそんなの!
結局……あれから瑠香とは、一度も顔を合わせていない。
以前は、会うつもりはなくても廊下や倉庫でちょくちょく顔を合わせた。それが今は気配すら感じられない。多分、瑠香の方で漣を避けているのだろう。何度か部屋を訪れたこともあるが、瑠香が顔を出してくれたことは一度もない。居留守を使われたのか、本当に留守だったのかは今でもわからない。
「おい、海江田漣」
「えっ?」
振り返ると、漣のすぐ背後で若い女性がじっと漣を睨みつけている。Tシャツにジーンズというラフな格好と、派手なピンクの髪には見覚えがある。カミツキガメを思わせる剣呑な表情にも。
彼女の名前は三原桜子。審美眼レベルは3で、専攻は彫刻。瑠香の友人で、一応、彼女の紹介で面識こそあるものの、漣が個人的に彼女と接点を持ったことはない。というのも、なぜか漣に対しては終始喧嘩腰で接してくるからだ。
瑠香は照れ隠しだというが、おそらく彼女の敵意は本物だ。今回のツアーに彼女が参加していると知った時は、正直うんざりした。とはいえ、触らぬ神に祟りなし。こちらから接触しなければ、まぁ問題はないだろうと高を括っていた……いたのだが。
「お前、キュレーターになりたいんだってな」
協会に保護されて、はや一か月。漣にとっては初めて許された外出だったが、空は生憎の雨模様でうんざりさせられる。六月も終盤に差しかかり、ここ一週間は梅雨らしいじめついた天気が続いている。
別に、雨に降られるのは構わない。むしろ雨そのものは好きだ。濡れた路面に映り込む街。滲む夜の光。通りに咲く色とりどりの傘と、帰り路を急ぐ人々の足取りは、どこか懐かしい気分にさせてくれる――が、問題はこの湿気だ。のべつ幕なしに身体を包むじめじめとした空気のせいで、肌どころか骨さえ腐り落ちそうだ。
「……痒っ」
首元を掻きながら、溜息まじりに漣はぼやく。ただでさえ湿気で鬱陶しい上、つけ慣れないチョーカーが不快感をいやましにする。
エントランス前に横付けされたバスを降り、正面エントランスから建物内に入る。この美術館にも漣は何度か足を運んだことがある。建築家の黒川紀章が設計した総ガラス張りの外観は、人工的でありながらも周囲の緑と優しく調和している。見上げるほどの天井を擁する吹き抜けのロビーには、これが晴天時ならたっぷりと日差しが降り注いでいただろう。
ただ、ひんやりと乾いた館内の空気は、それだけでも漣にひとときの安らぎを与えた。
「出発時にご説明したとおり、館内での行動は自由です! ただし、建物の外に出ることはできません! 万が一、外に出るにしても、行動は半径三百メートル以内に留めてください!」
ロビーに集合した三十名ほどの一行に、そう声を張り上げるのは非ギフテッドの事務員だ。協会では非ギフテッドの職員が、主に事務職や施設の管理要員として働いている。皆、非正規ではなく国家公務員として正規に雇われた人々だ。これも、機密を守るためのコスト、ということだろう。
まるで小学校の遠足だな、と、職員の注意を聞きながら漣は思う。引率される人間のほとんどは、いい歳をした大人たちで、社会における自分達の立ち位置を理解する人間がほとんどだろう。そうした人々が安易に逃走を図るとは思わない。あるいは……ここにも彼らと漣との間に意識のギャップがあるのかもしれない。漣は、半ば刑務所に収監されたつもりで施設にいるが、彼らにしてみればどこまでも理不尽な措置なのだ。
気を取り直し、ロビーを飾る巨大な垂れ幕を見上げる。ゴッホの『星月夜』をメインビジュアルに用いた垂れ幕には、白抜きの文字で『大印象派展』と堂々記されている。
明日からこの美術館では、印象派をテーマに大型の展覧会が開催される。
そうした展覧会の前には、必ず、ギフテッド向けの内覧会が組まれるのだそうだ。施設内の住人から希望者を募り、貸し切りで特別に鑑賞できるのだ。この日も、美術館は休館日という体を取っているが、これがギフテッドのための特別な計らいであることを、関係者なら誰もが知っている。
この日のために、漣は施設の図書室にあるだけの関連書籍を読み漁ってきた。
印象派の誕生は、社会制度の変革や、科学技術の進歩と分けて語ることはできない。それまでの貴族社会では、主に貴族がパトロンとなり、主題も彼らが求めるものに限られていた。が、市民革命により社会の主役は名もなき庶民へとバトンタッチする。そうした変化の中で、アーティスト達の画題も庶民の暮らしに寄り添ったものへとシフトしていった。さらにチューブ式絵具の発明により、屋外での自由なドローイングが可能となったことで、自然光を表現するための試行錯誤が始まる。もちろん、写真の登場で必ずしも写実に囚われる必要がなくなったせいもあるが、嶋野が以前語ったとおり、それは、あくまでも要因の一つにすぎない。
展示は、漣の想像以上に充実していた。
ただ絵を並べるだけでなく、印象派が生まれた経緯や時代背景、後世のアートに残した影響なども俯瞰的に紹介している。揺籃となったバルビゾン派の紹介から、東洋文化、とりわけ浮世絵との邂逅が与えた影響。それは当時の帝国主義とは不可分の現象で――といった注釈が会場のあちこちに掲示され、一巡するだけで概要を把握できる流れになっている。
そうしてアートへの理解を深めた上で、改めて絵に目を戻すと、やはり、解像度が上がっているなと感じる。技巧に込められた表現の意図、だけではない。アーティストが鑑賞者と共有したかったもの――おそらくは、そう、願い。
これが審美眼と呼ばれる力の正体なら、今この瞬間、確かに審美眼は鍛えられつつあるのだろう。それは同時に、キュレーターになる、という目標に一歩前進したことを意味している。
――ううん駄目! 絶対に駄目だからねそんなの!
結局……あれから瑠香とは、一度も顔を合わせていない。
以前は、会うつもりはなくても廊下や倉庫でちょくちょく顔を合わせた。それが今は気配すら感じられない。多分、瑠香の方で漣を避けているのだろう。何度か部屋を訪れたこともあるが、瑠香が顔を出してくれたことは一度もない。居留守を使われたのか、本当に留守だったのかは今でもわからない。
「おい、海江田漣」
「えっ?」
振り返ると、漣のすぐ背後で若い女性がじっと漣を睨みつけている。Tシャツにジーンズというラフな格好と、派手なピンクの髪には見覚えがある。カミツキガメを思わせる剣呑な表情にも。
彼女の名前は三原桜子。審美眼レベルは3で、専攻は彫刻。瑠香の友人で、一応、彼女の紹介で面識こそあるものの、漣が個人的に彼女と接点を持ったことはない。というのも、なぜか漣に対しては終始喧嘩腰で接してくるからだ。
瑠香は照れ隠しだというが、おそらく彼女の敵意は本物だ。今回のツアーに彼女が参加していると知った時は、正直うんざりした。とはいえ、触らぬ神に祟りなし。こちらから接触しなければ、まぁ問題はないだろうと高を括っていた……いたのだが。
「お前、キュレーターになりたいんだってな」
0
あなたにおすすめの小説

中1でEカップって巨乳だから熱く甘く生きたいと思う真理(マリー)と小説家を目指す男子、光(みつ)のラブな日常物語
jun( ̄▽ ̄)ノ
大衆娯楽
中1でバスト92cmのブラはEカップというマリーと小説家を目指す男子、光の日常ラブ
★作品はマリーの語り、一人称で進行します。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

十二輝の忍神 ーシノビガミ― 第一部
陵月夜白(りょうづきやしろ)
歴史・時代
天明三年――浅間山が火を噴いた。
神の怒りに触れたかのように、黒い灰は空を塞ぎ、郷も田畑も人の営みも、容赦なく呑み込んでいく。噴火と飢饉が藩を蝕み、救いを求める声の裏で、名もなき影が蠢いた。灰の夜を踏むのは、血も温もりも失った“黒屍人”。誰が、何のために――。
その災厄に呼応するように、忍びの郷に封じられていた「十二輝の干支の珠」が、ひとつ、またひとつと眠りから解かれる。
珠は器を選び、器は力に喰われ、力は人を裏返す。
伊賀と甲賀の長い因縁、奪われる珠、引き裂かれる同胞。
そして、灰の国で拾い集められていく十二の輝きが揃う時、世界の秩序そのものが――動き出す。

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。
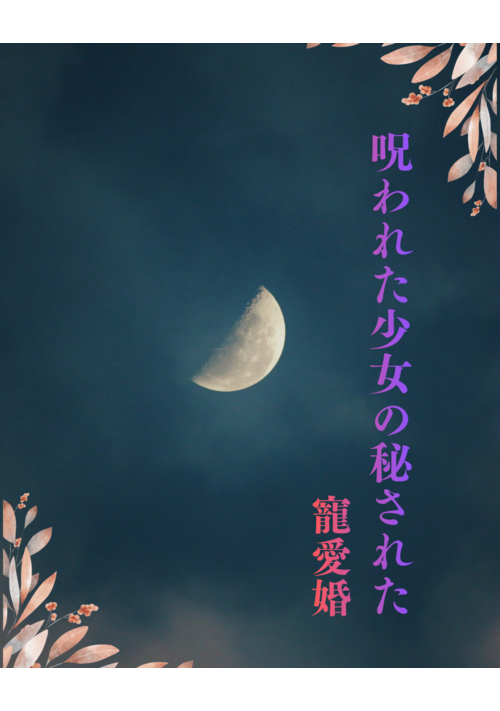
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

煙草屋さんと小説家
男鹿七海
キャラ文芸
※プラトニックな関係のBL要素を含む日常ものです。
商店街の片隅にある小さな煙草屋を営む霧弥。日々の暮らしは静かで穏やかだが、幼馴染であり売れっ子作家の龍二が店を訪れるたびに、心の奥はざわめく。幼馴染としてでも、客としてでもない――その存在は、言葉にできないほど特別だ。
ある日、龍二の周囲に仕事仲間の女性が現れ、霧弥は初めて嫉妬を自覚する。自分の感情を否定しようとしても、触れた手の温もりや視線の距離が、心を正直にさせる。日常の中で少しずつ近づく二人の距離は、言葉ではなく、ささやかな仕草や沈黙に宿る。
そして夜――霧弥の小さな煙草屋で、龍二は初めて自分の想いを口にし、霧弥は返事として告白する。互いの手の温もりと目の奥の真剣さが、これまで言葉にできなかった気持ちを伝える瞬間。静かな日常の向こうに、確かな愛が芽吹く。
小さな煙草屋に灯る、柔らかく温かな恋の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















