6 / 22
第6話 無名の護り手
しおりを挟む
三人は高台から慎重に下り、夕焼けの尾根道へと身を細くして消えていく。背を押す谷風はさっきより柔らかく、フェルンホルムの森は、ほんの少し近かった。
三人が進んだ森の先、祠の奥、岩棚に沿って半円に並ぶ青銅の群像があった。
中央はマントを翻した先頭の剣士。左右に盾持ち、弓手、槍兵、衛生兵……いずれも名は記されず、足元には小さな紋や傷跡だけが刻まれている。台座にはただ一語——《無名》。
風鈴の糸のように細い谷風が、像の間を渡っていった。
「これです。名もなき群像です。戦後、師匠が毎年、磨きに通って……」
テオは誇らしげに胸を張る。
先頭の青銅は、若き騎士の姿をとどめていた。翻るマント。欠けた鼻。肩の緑青。
ルカは見上げ、はっと息を呑む。
「これ、中央……爺ちゃん?」
クレインは何も答えず、群像へ歩み寄った。指先で一体の顔の汚れを払う。ふと、その目元が和らいだように見える。
「“無名の護り手”って、群像のことだったのか……」
ルカは小声でこぼす。
テオが修復道具を広げる横で、クレインはそっと手甲を外し、手拭いを取り出した。
「剣と同じじゃ。像に触れる前に、息を合わせい。“いち”で入れて、“に”“さん”で拭く」
彼は自分の像には手を伸ばさない。隣の盾持ちへ向き直り、古い友に触れるように布を当てる。
「ラガルド……また盾の縁で、ワシの脛を打つなよ」
次に弓手の頬を軽く磨く。
「ベルナ。あの丘の逆風、よう射抜いた。……顎をひけ。視界が広がる」
槍兵の手元——指のささくれを撫でるみたいに。
「ヨズ。槍は“押す”でなく“通す”ぞ。……そう、その拍じゃ」
衛生兵の小瓶には薄く蝋をのせる。
「ハンネス。おぬしの罵声は薬より効いたわ。よう怒鳴ってくれた」
偵察の娘の髪飾り。欠けを確かめ、そっと息を吹き掛ける。
「ミラ。歌は小さく、と言うても聞かなんだのう……」
ルカは見入った。テオはいつしかタガネを置き、自然と頭を垂れている。
クレインは一体ごとに拍を刻み、間を置いてから次へ移った。教場での型と寸分違わぬ間合いだった。
(“古い剣術”は、力じゃない……記憶を通すための設計だ)
ルカは胸の内で静かに言葉を組み立てる。
名を刻まれぬ名が、布の下で息を吹き返す。
最後に中央——若き日のクレイン像の前へ。だが手は伸ばさない。剣拭いを畳み、胸に当てる。
「真ん中は、磨かないんですか?」
思わず問うテオに、クレインは穏やかに笑った。
「風雨に任せる。ワシは、まだ道の途中じゃからな」
群像へ向き直り、声を低く落とす。
「待たせたな。もう少しでそっちに行く。その前に、ワシ——やっと冒険に出るんじゃ。……土産話を、もう少し溜めてからのう」
麓の小屋に戻るころには、山の影がすっかり谷底へ落ちきっていた。戸口の前で靴底の泥を払うと、土間の焚き火がぱちりと迎える。薬缶が低くうなり、外では水車のきしむ音がときおり風に乗った。
戸がきしみ、オルソが入ってくる。肩に麻袋、指先に金属の匂い。
「テオ、遅くなった。材料の追加を——」
目の端でクレインを捉えると、ふっと目礼。呼吸を一拍おいて、何も知らぬ体で踏み込んだ。
「遠路ご苦労様です。……茶でも」
湯呑が配られる。焚き火の光が梁に揺れ、湯気が三筋、静かに立つ。
クレインは一口すすって、視線を窓の外へ流した。
「……この辺りも、立派に復興したのう」
「ええ。橋も畑も戻りました」
オルソは火の高さを指で測りながら言う。
「戦の爪痕は、土と人で埋めるもんです」
ルカが湯呑を両手で包み、遠慮がちに口を開く。
「像の“無名”って、どういう——」
オルソは炎を見つめた。
「戦は表向き“和平”で終わったが、実のところは……ほとんど降伏だった。敵国は“英雄”を嫌う。火種になるからな。
だが撤退戦の先頭に立った剣士がいた。兵を置いて逃げず、最後尾で道を開いた男だ」
一拍。オルソはまっすぐクレインを見る。焚き火が小さく爆ぜた。
「——英雄に命を救われた兵士が、職人になって銅を打つ。名を刻めぬなら、山に立てばいい。見上げた者だけが知ればいい」
ルカは湯面の波を見つめ、短く息を吐く。
「……じいちゃん。撤退戦の話、ほんとうだったんだね。疑って、ごめん」
クレインは穏やかに笑った。
「気にするな。話は半分で聞くくらいが丁度よい。ただ、自分の目で確かめたら、その半分を埋めればええ」
膝の上で剣拭いをそっと撫でる。
「……長いあいだ、あやつらを磨いてくれておるな。名の代わりに“拍”を銅に刻み続けてくれて、礼を言うぞ、オルソ」
オルソはかすかに笑い、湯呑の縁を指で一度、ことりと叩いた——一拍。
「こちらこそ、隊長殿。あの夜、殿に立ってくれなきゃ、俺は土の下でした。生かされた身でやるべき仕事が、これです。……ありがとうございます」
「腕は鈍っておらんようじゃの、オルソ」
「師の“拍”は、手が、魂が覚えてます」
テオは意味を測りかねて目を瞬かせ、ルカは息をのみ、黙って湯呑を持ち直した。
外の風は山から里の匂いに変わり、水車の軋みが遠のいていく。真剣なほど可笑しい静けさの中、三つの湯気はゆっくり混じり、麓の夜はやわらかく沈んでいった。
翌朝。麓の小屋の戸がきしみ、冷えた土間に朝の匂いが流れ込んだ。
外では水車が湿った風に一度だけ軋み、オルソが簡素な握り飯を包んで差し出す。テオは荷の紐を締め直し、会釈した。
「王都に戻った後は、隊長殿?」
「グレイマーチ高原に向かおうと思う」
「そうですか……戦友たちに私の分もよろしくとお伝えください」
「任せい。——行くぞ、ルカ」
街道に出る。露の粒が麦の切り株に並び、三百歩ごとに光り方が変わる。
その三百歩目で、クレインは路傍の石に腰を下ろし、木剣を膝へ渡した。ルカは手帳を閉じて、筆を耳に挟み直す。
「ねぇ、じいちゃん」
「なんじゃ」
「なんで徒歩なの? 馬車の方が早いし、じいちゃんは三百メートルしか歩けないのに」
クレインは笑って顎で道端を示した。
「歩くとの。景色が三百歩ごとに一枚ずつ、手に入るんじゃ。……ほれ、見い。この春告草、美しいと思わんか」
白い小花がひと束、石の割れ目から顔を出している。薄い花弁が朝の光を透かした。
「それ、春になったらどこにでも生えるよ」
ルカは肩をすくめる。「図鑑だと“繁茂注意”の雑草マーク」
「図鑑は季節で書く。儂は今日で覚える」
クレインはそっと花茎の向きを風に合わせる。
「……次の春が来れば——じゃな」
ルカの手が、手帳の上で止まった。
「……じいちゃん?」
答えの代わりに、風に一度だけうなずく。
クレインは木剣を立て、膝に軽く力を集めた。
「さて、もう一枚、取りに行くか」
「うん。じゃ、三百歩の一枚ね」
二人は歩き出す。
ルカは耳の筆を外して、手帳の片隅にさらさらと書きつける。
——三番は、歯に砂、靴底に泥。
それでも歩け、拍を刻め。
「何を書いた」
「行軍歌の“非公式三番”。今日の色で、ね」
「ほう」
膝がぱきん、と小さく鳴る。ルカが片眉を上げる。
「膝で返事しないでよ」
「老骨の仕様じゃ」
二人の笑いが柳の葉擦れに溶けた。
三百歩の拍を数え終えるごとに、道はわずかずつ前へ伸びる。歩みは遅い。けれど確かに——一枚ずつ、重なっていった。
「——残寿:9ヶ月・往復2ヶ月の冒険」
三人が進んだ森の先、祠の奥、岩棚に沿って半円に並ぶ青銅の群像があった。
中央はマントを翻した先頭の剣士。左右に盾持ち、弓手、槍兵、衛生兵……いずれも名は記されず、足元には小さな紋や傷跡だけが刻まれている。台座にはただ一語——《無名》。
風鈴の糸のように細い谷風が、像の間を渡っていった。
「これです。名もなき群像です。戦後、師匠が毎年、磨きに通って……」
テオは誇らしげに胸を張る。
先頭の青銅は、若き騎士の姿をとどめていた。翻るマント。欠けた鼻。肩の緑青。
ルカは見上げ、はっと息を呑む。
「これ、中央……爺ちゃん?」
クレインは何も答えず、群像へ歩み寄った。指先で一体の顔の汚れを払う。ふと、その目元が和らいだように見える。
「“無名の護り手”って、群像のことだったのか……」
ルカは小声でこぼす。
テオが修復道具を広げる横で、クレインはそっと手甲を外し、手拭いを取り出した。
「剣と同じじゃ。像に触れる前に、息を合わせい。“いち”で入れて、“に”“さん”で拭く」
彼は自分の像には手を伸ばさない。隣の盾持ちへ向き直り、古い友に触れるように布を当てる。
「ラガルド……また盾の縁で、ワシの脛を打つなよ」
次に弓手の頬を軽く磨く。
「ベルナ。あの丘の逆風、よう射抜いた。……顎をひけ。視界が広がる」
槍兵の手元——指のささくれを撫でるみたいに。
「ヨズ。槍は“押す”でなく“通す”ぞ。……そう、その拍じゃ」
衛生兵の小瓶には薄く蝋をのせる。
「ハンネス。おぬしの罵声は薬より効いたわ。よう怒鳴ってくれた」
偵察の娘の髪飾り。欠けを確かめ、そっと息を吹き掛ける。
「ミラ。歌は小さく、と言うても聞かなんだのう……」
ルカは見入った。テオはいつしかタガネを置き、自然と頭を垂れている。
クレインは一体ごとに拍を刻み、間を置いてから次へ移った。教場での型と寸分違わぬ間合いだった。
(“古い剣術”は、力じゃない……記憶を通すための設計だ)
ルカは胸の内で静かに言葉を組み立てる。
名を刻まれぬ名が、布の下で息を吹き返す。
最後に中央——若き日のクレイン像の前へ。だが手は伸ばさない。剣拭いを畳み、胸に当てる。
「真ん中は、磨かないんですか?」
思わず問うテオに、クレインは穏やかに笑った。
「風雨に任せる。ワシは、まだ道の途中じゃからな」
群像へ向き直り、声を低く落とす。
「待たせたな。もう少しでそっちに行く。その前に、ワシ——やっと冒険に出るんじゃ。……土産話を、もう少し溜めてからのう」
麓の小屋に戻るころには、山の影がすっかり谷底へ落ちきっていた。戸口の前で靴底の泥を払うと、土間の焚き火がぱちりと迎える。薬缶が低くうなり、外では水車のきしむ音がときおり風に乗った。
戸がきしみ、オルソが入ってくる。肩に麻袋、指先に金属の匂い。
「テオ、遅くなった。材料の追加を——」
目の端でクレインを捉えると、ふっと目礼。呼吸を一拍おいて、何も知らぬ体で踏み込んだ。
「遠路ご苦労様です。……茶でも」
湯呑が配られる。焚き火の光が梁に揺れ、湯気が三筋、静かに立つ。
クレインは一口すすって、視線を窓の外へ流した。
「……この辺りも、立派に復興したのう」
「ええ。橋も畑も戻りました」
オルソは火の高さを指で測りながら言う。
「戦の爪痕は、土と人で埋めるもんです」
ルカが湯呑を両手で包み、遠慮がちに口を開く。
「像の“無名”って、どういう——」
オルソは炎を見つめた。
「戦は表向き“和平”で終わったが、実のところは……ほとんど降伏だった。敵国は“英雄”を嫌う。火種になるからな。
だが撤退戦の先頭に立った剣士がいた。兵を置いて逃げず、最後尾で道を開いた男だ」
一拍。オルソはまっすぐクレインを見る。焚き火が小さく爆ぜた。
「——英雄に命を救われた兵士が、職人になって銅を打つ。名を刻めぬなら、山に立てばいい。見上げた者だけが知ればいい」
ルカは湯面の波を見つめ、短く息を吐く。
「……じいちゃん。撤退戦の話、ほんとうだったんだね。疑って、ごめん」
クレインは穏やかに笑った。
「気にするな。話は半分で聞くくらいが丁度よい。ただ、自分の目で確かめたら、その半分を埋めればええ」
膝の上で剣拭いをそっと撫でる。
「……長いあいだ、あやつらを磨いてくれておるな。名の代わりに“拍”を銅に刻み続けてくれて、礼を言うぞ、オルソ」
オルソはかすかに笑い、湯呑の縁を指で一度、ことりと叩いた——一拍。
「こちらこそ、隊長殿。あの夜、殿に立ってくれなきゃ、俺は土の下でした。生かされた身でやるべき仕事が、これです。……ありがとうございます」
「腕は鈍っておらんようじゃの、オルソ」
「師の“拍”は、手が、魂が覚えてます」
テオは意味を測りかねて目を瞬かせ、ルカは息をのみ、黙って湯呑を持ち直した。
外の風は山から里の匂いに変わり、水車の軋みが遠のいていく。真剣なほど可笑しい静けさの中、三つの湯気はゆっくり混じり、麓の夜はやわらかく沈んでいった。
翌朝。麓の小屋の戸がきしみ、冷えた土間に朝の匂いが流れ込んだ。
外では水車が湿った風に一度だけ軋み、オルソが簡素な握り飯を包んで差し出す。テオは荷の紐を締め直し、会釈した。
「王都に戻った後は、隊長殿?」
「グレイマーチ高原に向かおうと思う」
「そうですか……戦友たちに私の分もよろしくとお伝えください」
「任せい。——行くぞ、ルカ」
街道に出る。露の粒が麦の切り株に並び、三百歩ごとに光り方が変わる。
その三百歩目で、クレインは路傍の石に腰を下ろし、木剣を膝へ渡した。ルカは手帳を閉じて、筆を耳に挟み直す。
「ねぇ、じいちゃん」
「なんじゃ」
「なんで徒歩なの? 馬車の方が早いし、じいちゃんは三百メートルしか歩けないのに」
クレインは笑って顎で道端を示した。
「歩くとの。景色が三百歩ごとに一枚ずつ、手に入るんじゃ。……ほれ、見い。この春告草、美しいと思わんか」
白い小花がひと束、石の割れ目から顔を出している。薄い花弁が朝の光を透かした。
「それ、春になったらどこにでも生えるよ」
ルカは肩をすくめる。「図鑑だと“繁茂注意”の雑草マーク」
「図鑑は季節で書く。儂は今日で覚える」
クレインはそっと花茎の向きを風に合わせる。
「……次の春が来れば——じゃな」
ルカの手が、手帳の上で止まった。
「……じいちゃん?」
答えの代わりに、風に一度だけうなずく。
クレインは木剣を立て、膝に軽く力を集めた。
「さて、もう一枚、取りに行くか」
「うん。じゃ、三百歩の一枚ね」
二人は歩き出す。
ルカは耳の筆を外して、手帳の片隅にさらさらと書きつける。
——三番は、歯に砂、靴底に泥。
それでも歩け、拍を刻め。
「何を書いた」
「行軍歌の“非公式三番”。今日の色で、ね」
「ほう」
膝がぱきん、と小さく鳴る。ルカが片眉を上げる。
「膝で返事しないでよ」
「老骨の仕様じゃ」
二人の笑いが柳の葉擦れに溶けた。
三百歩の拍を数え終えるごとに、道はわずかずつ前へ伸びる。歩みは遅い。けれど確かに——一枚ずつ、重なっていった。
「——残寿:9ヶ月・往復2ヶ月の冒険」
0
あなたにおすすめの小説
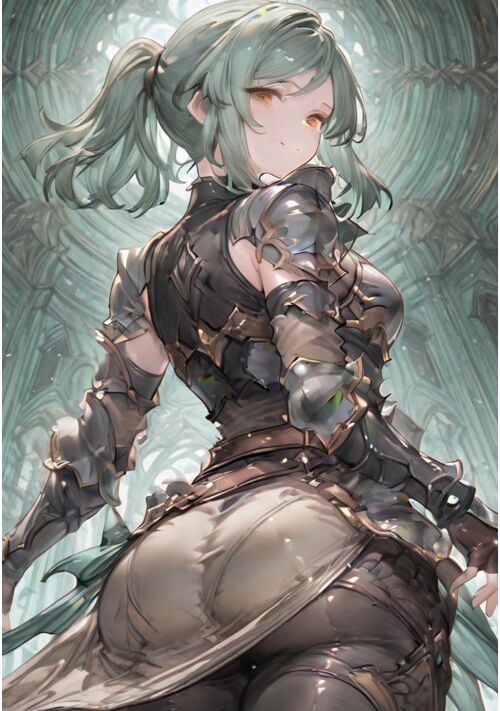
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

出来損ない貴族の三男は、謎スキル【サブスク】で世界最強へと成り上がる〜今日も僕は、無能を演じながら能力を徴収する〜
シマセイ
ファンタジー
実力至上主義の貴族家に転生したものの、何の才能も持たない三男のルキウスは、「出来損ない」として優秀な兄たちから虐げられる日々を送っていた。
起死回生を願った五歳の「スキルの儀」で彼が授かったのは、【サブスクリプション】という誰も聞いたことのない謎のスキル。
その結果、彼の立場はさらに悪化。完全な「クズ」の烙印を押され、家族から存在しない者として扱われるようになってしまう。
絶望の淵で彼に寄り添うのは、心優しき専属メイドただ一人。
役立たずと蔑まれたこの謎のスキルが、やがて少年の運命を、そして世界を静かに揺るがしていくことを、まだ誰も知らない。

『辺境伯一家の領地繁栄記』スキル育成記~最強双子、成長中~
鈴白理人
ファンタジー
ラザナキア王国の国民は【スキルツリー】という女神の加護を持つ。
そんな国の北に住むアクアオッジ辺境伯一家も例外ではなく、父は【掴みスキル】母は【育成スキル】の持ち主。
母のスキルのせいか、一家の子供たちは生まれたころから、派生スキルがポコポコ枝分かれし、スキルレベルもぐんぐん上がっていった。
双子で生まれた末っ子、兄のウィルフレッドの【精霊スキル】、妹のメリルの【魔法スキル】も例外なくレベルアップし、十五歳となった今、学園入学の秒読み段階を迎えていた──
前作→『辺境伯一家の領地繁栄記』序章:【動物スキル?】を持った辺境伯長男の場合

『白い結婚だったので、勝手に離婚しました。何か問題あります?』
夢窓(ゆめまど)
恋愛
「――離婚届、受理されました。お疲れさまでした」
教会の事務官がそう言ったとき、私は心の底からこう思った。
ああ、これでようやく三年分の無視に終止符を打てるわ。
王命による“形式結婚”。
夫の顔も知らず、手紙もなし、戦地から帰ってきたという噂すらない。
だから、はい、離婚。勝手に。
白い結婚だったので、勝手に離婚しました。
何か問題あります?

ラストアタック!〜御者のオッサン、棚ぼたで最強になる〜
KeyBow
ファンタジー
第18回ファンタジー小説大賞奨励賞受賞
ディノッゾ、36歳。職業、馬車の御者。
諸国を旅するのを生き甲斐としながらも、その実態は、酒と女が好きで、いつかは楽して暮らしたいと願う、どこにでもいる平凡なオッサンだ。
そんな男が、ある日、傲慢なSランクパーティーが挑むドラゴンの討伐に、くじ引きによって理不尽な捨て駒として巻き込まれる。
捨て駒として先行させられたディノッゾの馬車。竜との遭遇地点として聞かされていた場所より、遥か手前でそれは起こった。天を覆う巨大な影―――ドラゴンの襲撃。馬車は木っ端微塵に砕け散り、ディノッゾは、同乗していたメイドの少女リリアと共に、死の淵へと叩き落された―――はずだった。
腕には、守るべきメイドの少女。
眼下には、Sランクパーティーさえも圧倒する、伝説のドラゴン。
―――それは、ただの不運な落下のはずだった。
崩れ落ちる崖から転落する際、杖代わりにしていただけの槍が、本当に、ただ偶然にも、ドラゴンのたった一つの弱点である『逆鱗』を貫いた。
その、あまりにも幸運な事故こそが、竜の命を絶つ『最後の一撃(ラストアタック)』となったことを、彼はまだ知らない。
死の淵から生還した彼が手に入れたのは、神の如き規格外の力と、彼を「師」と慕う、新たな仲間たちだった。
だが、その力の代償は、あまりにも大きい。
彼が何よりも愛していた“酒と女と気楽な旅”――
つまり平和で自堕落な生活そのものだった。
これは、英雄になるつもりのなかった「ただのオッサン」が、
守るべき者たちのため、そして亡き友との誓いのために、
いつしか、世界を救う伝説へと祭り上げられていく物語。
―――その勘違いと優しさが、やがて世界を揺るがす。

アルフレッドは平穏に過ごしたい 〜追放されたけど謎のスキル【合成】で生き抜く〜
芍薬甘草湯
ファンタジー
アルフレッドは貴族の令息であったが天から与えられたスキルと家風の違いで追放される。平民となり冒険者となったが、生活するために竜騎士隊でアルバイトをすることに。
ふとした事でスキルが発動。
使えないスキルではない事に気付いたアルフレッドは様々なものを合成しながら密かに活躍していく。
⭐︎注意⭐︎
女性が多く出てくるため、ハーレム要素がほんの少しあります。特に苦手な方はご遠慮ください。

タダ働きなので待遇改善を求めて抗議したら、精霊達から『破壊神』と怖れられています。
渡里あずま
ファンタジー
出来損ないの聖女・アガタ。
しかし、精霊の加護を持つ新たな聖女が現れて、王子から婚約破棄された時――彼女は、前世(現代)の記憶を取り戻した。
「それなら、今までの報酬を払って貰えますか?」
※※※
虐げられていた子が、モフモフしながらやりたいことを探す旅に出る話です。
※重複投稿作品※
表紙の使用画像は、AdobeStockのものです。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















