16 / 22
第16話 秘伝の戦準備
しおりを挟む
宿の食堂。肉の煮込みと黒パン、薄い酒。卓の上で湯気が揺れる。
「王都への帰りは平坦な道にしよう。迂回してでも」
「何を言っとる。山道をまっすぐで構わん!昔は山三つを一日で行軍したものよ」
「今は三百歩で休憩してるからね!」
そこへ、恰幅のいい亭主がにょきりと現れる。
「話の途中で悪いね。じいさんに手紙だよ」
「誰からじゃ?」
ルカが封を確かめ、目を丸くする。
「差出人は……アシュレイ・ロウ!?」
文は簡潔だった。〈明日夕刻、町外れの丘にて“決闘”を乞う〉
「じいちゃん、ダメだよ!決闘なんて——」
「ふむ、安心せい。闘気は使わん」クレインは杯を置き、指で鍔の拍をコツリと刻む。「これは“決闘”じゃのうて“講義”みたいなものじゃ」
「へ?」
「まあ見とれ。わしが“絶対に勝ってしまう”からのう」
ルカは額を押さえ、半分は呆れ、半分は胸の奥で音を鳴るのを聞いた。
明日の丘で、何が起きる?拍を三つ、心の中でゆっくり数える。
酒の薄さが、少しだけ濃くなった気がした。
翌朝の宿の一室。薄い陽が格子から差し、卓の上には買い込んだ瓶と小袋がずらり——回復薬、止血薬、香油、絵の具、チョーク、皮袋。旅支度というより、理科実験の台だ。
「じいちゃん、朝から回復やら色々買ってきたけど、何に使うの?」
「ヴァルドナ流“秘伝の戦準備”じゃ」
クレインは真顔で答え、羊皮の袋を三重、四重と入れ子にしていく。
チョークの粉と絵の具を落とし、回復薬が鈍い赤へ沈む。「……良し」ことり、と拍。
口は蝋で封じ、麻紐で結び、指で“ことり”と拍を確かめる。ひと袋ごとに光へ透かし、角度を変え、「……良し」。また一拍、「良し」。
「それ、何入れるの?」
「“秘伝”じゃ」
即答。説明になっていない。何やら準備する動作は滑稽なほど厳粛だ。
ルカは額を押さえた。
「……嫌な予感しかしないよ」
「心配いらん。使うのは“講義”の終盤じゃ」
「講義(=決闘)だよね?」
「そうじゃ」
老剣士は最後の一つを握り、掌で重さを量ると、満足げに頷いた。袋はただの袋、に見える。だがその中には、水でも薬でもない、ヴァルドナ流の“秘伝”が、静かに詰められていた。
夕焼けが町はずれの丘をゆっくり舐めていた。赤く磨かれた草刈りの跡、風が一度通れば色が少しだけ薄くなる。
アシュレイはそこで待っていた。肩をすくめる身震いは寒さのせいでも気後れでもない。
あの不可思議な剣——不可思議な老剣士の流れ——を、もう一度この身で確かめたい。その渇きだけが、薄暗む丘を暖めていた。
「待っていたぞ」
背後からの足音は三つ。リズムが揃っている。クレインは夕焼けを背負って現れ、余計な挨拶もなく顎をわずかに引いた。
「うむ。さっさと始めるかのう。わしらのような人種は、剣を重ねた方が分かることが多い」
アシュレイは静かに剣を抜く。刃が赤を吸って細い線になる。対してクレインは鞘に手をやらず、腰の袋の具合を一つ確かめると、手に取ったのは木剣だった。軽く鍔を鳴らし、拍を一つ。
「……っ。馬鹿にしているのか?私の剣は、それほど弱いのか」
声に棘はあるが、足は崩れない。クレインは首を横に振った。
「いいや。速度——まったく敵わん。体力——これも敵わん。技術——これは同等か、ちとお主が上」
そこで一拍、わずかに口角が上がる。
「じゃが“決闘”と言ったかの?この実践の舞台なら、わしが勝ってしまうんじゃ」
夕風が草の穂先を逆立てる。アシュレイの瞳孔が細くなり、やがて元へ戻る。
「……くっ。わかった。飲む」
クレインは満足げに頷き、木剣を腰の高さに置く。鞘の刀は静かに眠ったまま、視線だけが相手の肩と踵を往復する。
「じゃが、闘気はなしで頼む。あれは老骨にはこたえるでのう」
「承知した」
短い取り決め。形式ばった儀礼はない。アシュレイは半身、刃先は揺れずに一点。クレインはため足で土を撫で、木剣の面をわずかに開いて風の通り道を作る。
「——さあ、始めよう」
「王都への帰りは平坦な道にしよう。迂回してでも」
「何を言っとる。山道をまっすぐで構わん!昔は山三つを一日で行軍したものよ」
「今は三百歩で休憩してるからね!」
そこへ、恰幅のいい亭主がにょきりと現れる。
「話の途中で悪いね。じいさんに手紙だよ」
「誰からじゃ?」
ルカが封を確かめ、目を丸くする。
「差出人は……アシュレイ・ロウ!?」
文は簡潔だった。〈明日夕刻、町外れの丘にて“決闘”を乞う〉
「じいちゃん、ダメだよ!決闘なんて——」
「ふむ、安心せい。闘気は使わん」クレインは杯を置き、指で鍔の拍をコツリと刻む。「これは“決闘”じゃのうて“講義”みたいなものじゃ」
「へ?」
「まあ見とれ。わしが“絶対に勝ってしまう”からのう」
ルカは額を押さえ、半分は呆れ、半分は胸の奥で音を鳴るのを聞いた。
明日の丘で、何が起きる?拍を三つ、心の中でゆっくり数える。
酒の薄さが、少しだけ濃くなった気がした。
翌朝の宿の一室。薄い陽が格子から差し、卓の上には買い込んだ瓶と小袋がずらり——回復薬、止血薬、香油、絵の具、チョーク、皮袋。旅支度というより、理科実験の台だ。
「じいちゃん、朝から回復やら色々買ってきたけど、何に使うの?」
「ヴァルドナ流“秘伝の戦準備”じゃ」
クレインは真顔で答え、羊皮の袋を三重、四重と入れ子にしていく。
チョークの粉と絵の具を落とし、回復薬が鈍い赤へ沈む。「……良し」ことり、と拍。
口は蝋で封じ、麻紐で結び、指で“ことり”と拍を確かめる。ひと袋ごとに光へ透かし、角度を変え、「……良し」。また一拍、「良し」。
「それ、何入れるの?」
「“秘伝”じゃ」
即答。説明になっていない。何やら準備する動作は滑稽なほど厳粛だ。
ルカは額を押さえた。
「……嫌な予感しかしないよ」
「心配いらん。使うのは“講義”の終盤じゃ」
「講義(=決闘)だよね?」
「そうじゃ」
老剣士は最後の一つを握り、掌で重さを量ると、満足げに頷いた。袋はただの袋、に見える。だがその中には、水でも薬でもない、ヴァルドナ流の“秘伝”が、静かに詰められていた。
夕焼けが町はずれの丘をゆっくり舐めていた。赤く磨かれた草刈りの跡、風が一度通れば色が少しだけ薄くなる。
アシュレイはそこで待っていた。肩をすくめる身震いは寒さのせいでも気後れでもない。
あの不可思議な剣——不可思議な老剣士の流れ——を、もう一度この身で確かめたい。その渇きだけが、薄暗む丘を暖めていた。
「待っていたぞ」
背後からの足音は三つ。リズムが揃っている。クレインは夕焼けを背負って現れ、余計な挨拶もなく顎をわずかに引いた。
「うむ。さっさと始めるかのう。わしらのような人種は、剣を重ねた方が分かることが多い」
アシュレイは静かに剣を抜く。刃が赤を吸って細い線になる。対してクレインは鞘に手をやらず、腰の袋の具合を一つ確かめると、手に取ったのは木剣だった。軽く鍔を鳴らし、拍を一つ。
「……っ。馬鹿にしているのか?私の剣は、それほど弱いのか」
声に棘はあるが、足は崩れない。クレインは首を横に振った。
「いいや。速度——まったく敵わん。体力——これも敵わん。技術——これは同等か、ちとお主が上」
そこで一拍、わずかに口角が上がる。
「じゃが“決闘”と言ったかの?この実践の舞台なら、わしが勝ってしまうんじゃ」
夕風が草の穂先を逆立てる。アシュレイの瞳孔が細くなり、やがて元へ戻る。
「……くっ。わかった。飲む」
クレインは満足げに頷き、木剣を腰の高さに置く。鞘の刀は静かに眠ったまま、視線だけが相手の肩と踵を往復する。
「じゃが、闘気はなしで頼む。あれは老骨にはこたえるでのう」
「承知した」
短い取り決め。形式ばった儀礼はない。アシュレイは半身、刃先は揺れずに一点。クレインはため足で土を撫で、木剣の面をわずかに開いて風の通り道を作る。
「——さあ、始めよう」
0
あなたにおすすめの小説
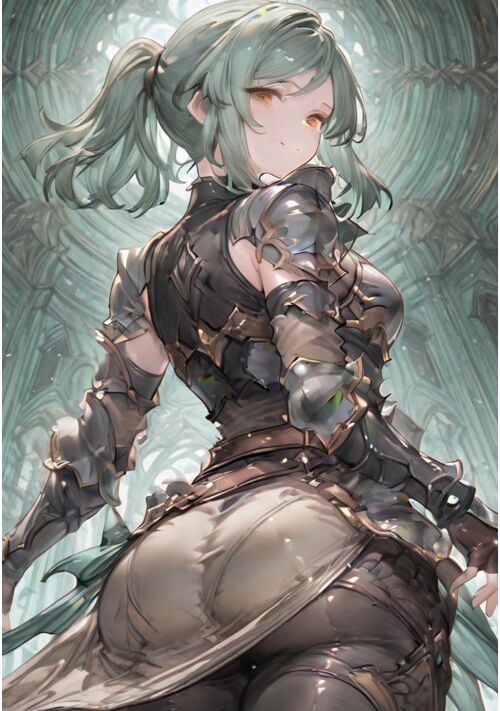
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

出来損ない貴族の三男は、謎スキル【サブスク】で世界最強へと成り上がる〜今日も僕は、無能を演じながら能力を徴収する〜
シマセイ
ファンタジー
実力至上主義の貴族家に転生したものの、何の才能も持たない三男のルキウスは、「出来損ない」として優秀な兄たちから虐げられる日々を送っていた。
起死回生を願った五歳の「スキルの儀」で彼が授かったのは、【サブスクリプション】という誰も聞いたことのない謎のスキル。
その結果、彼の立場はさらに悪化。完全な「クズ」の烙印を押され、家族から存在しない者として扱われるようになってしまう。
絶望の淵で彼に寄り添うのは、心優しき専属メイドただ一人。
役立たずと蔑まれたこの謎のスキルが、やがて少年の運命を、そして世界を静かに揺るがしていくことを、まだ誰も知らない。

『辺境伯一家の領地繁栄記』スキル育成記~最強双子、成長中~
鈴白理人
ファンタジー
ラザナキア王国の国民は【スキルツリー】という女神の加護を持つ。
そんな国の北に住むアクアオッジ辺境伯一家も例外ではなく、父は【掴みスキル】母は【育成スキル】の持ち主。
母のスキルのせいか、一家の子供たちは生まれたころから、派生スキルがポコポコ枝分かれし、スキルレベルもぐんぐん上がっていった。
双子で生まれた末っ子、兄のウィルフレッドの【精霊スキル】、妹のメリルの【魔法スキル】も例外なくレベルアップし、十五歳となった今、学園入学の秒読み段階を迎えていた──
前作→『辺境伯一家の領地繁栄記』序章:【動物スキル?】を持った辺境伯長男の場合

『白い結婚だったので、勝手に離婚しました。何か問題あります?』
夢窓(ゆめまど)
恋愛
「――離婚届、受理されました。お疲れさまでした」
教会の事務官がそう言ったとき、私は心の底からこう思った。
ああ、これでようやく三年分の無視に終止符を打てるわ。
王命による“形式結婚”。
夫の顔も知らず、手紙もなし、戦地から帰ってきたという噂すらない。
だから、はい、離婚。勝手に。
白い結婚だったので、勝手に離婚しました。
何か問題あります?

アルフレッドは平穏に過ごしたい 〜追放されたけど謎のスキル【合成】で生き抜く〜
芍薬甘草湯
ファンタジー
アルフレッドは貴族の令息であったが天から与えられたスキルと家風の違いで追放される。平民となり冒険者となったが、生活するために竜騎士隊でアルバイトをすることに。
ふとした事でスキルが発動。
使えないスキルではない事に気付いたアルフレッドは様々なものを合成しながら密かに活躍していく。
⭐︎注意⭐︎
女性が多く出てくるため、ハーレム要素がほんの少しあります。特に苦手な方はご遠慮ください。

ラストアタック!〜御者のオッサン、棚ぼたで最強になる〜
KeyBow
ファンタジー
第18回ファンタジー小説大賞奨励賞受賞
ディノッゾ、36歳。職業、馬車の御者。
諸国を旅するのを生き甲斐としながらも、その実態は、酒と女が好きで、いつかは楽して暮らしたいと願う、どこにでもいる平凡なオッサンだ。
そんな男が、ある日、傲慢なSランクパーティーが挑むドラゴンの討伐に、くじ引きによって理不尽な捨て駒として巻き込まれる。
捨て駒として先行させられたディノッゾの馬車。竜との遭遇地点として聞かされていた場所より、遥か手前でそれは起こった。天を覆う巨大な影―――ドラゴンの襲撃。馬車は木っ端微塵に砕け散り、ディノッゾは、同乗していたメイドの少女リリアと共に、死の淵へと叩き落された―――はずだった。
腕には、守るべきメイドの少女。
眼下には、Sランクパーティーさえも圧倒する、伝説のドラゴン。
―――それは、ただの不運な落下のはずだった。
崩れ落ちる崖から転落する際、杖代わりにしていただけの槍が、本当に、ただ偶然にも、ドラゴンのたった一つの弱点である『逆鱗』を貫いた。
その、あまりにも幸運な事故こそが、竜の命を絶つ『最後の一撃(ラストアタック)』となったことを、彼はまだ知らない。
死の淵から生還した彼が手に入れたのは、神の如き規格外の力と、彼を「師」と慕う、新たな仲間たちだった。
だが、その力の代償は、あまりにも大きい。
彼が何よりも愛していた“酒と女と気楽な旅”――
つまり平和で自堕落な生活そのものだった。
これは、英雄になるつもりのなかった「ただのオッサン」が、
守るべき者たちのため、そして亡き友との誓いのために、
いつしか、世界を救う伝説へと祭り上げられていく物語。
―――その勘違いと優しさが、やがて世界を揺るがす。

タダ働きなので待遇改善を求めて抗議したら、精霊達から『破壊神』と怖れられています。
渡里あずま
ファンタジー
出来損ないの聖女・アガタ。
しかし、精霊の加護を持つ新たな聖女が現れて、王子から婚約破棄された時――彼女は、前世(現代)の記憶を取り戻した。
「それなら、今までの報酬を払って貰えますか?」
※※※
虐げられていた子が、モフモフしながらやりたいことを探す旅に出る話です。
※重複投稿作品※
表紙の使用画像は、AdobeStockのものです。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















