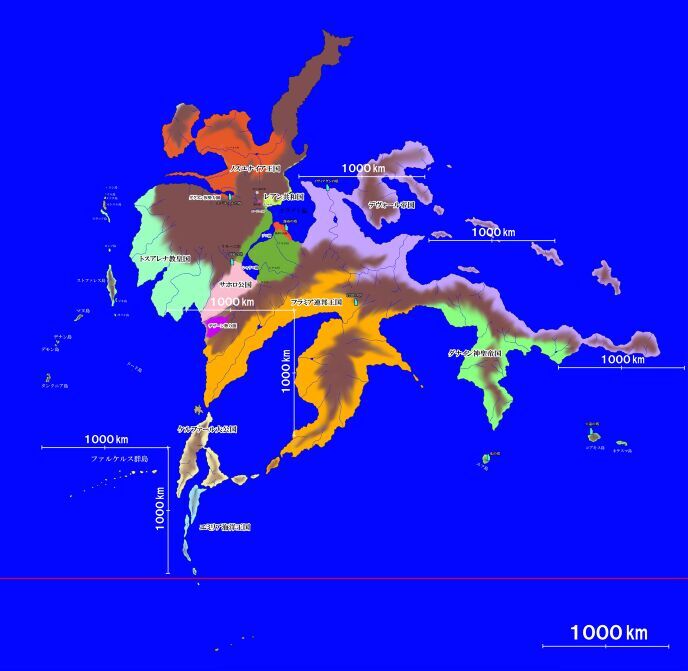2 / 49
第1章 第1話
しおりを挟む◆◆未研刀(みけんとう)◆◆
鋼鉄の風を切る音。
吐き出される荒い息遣い。
金属が擦れ、弾ける音
交(か)わされる殺気に満ちた激しい視線。
刀身がキラ、キラッと輝きを放ち、打ち合わされる毎に独特の音を奏でる。それは禍々しい音楽のようにも、心を惹きつけてやまない歌姫の声のようにも聞こえる。
相手が少しでも動けばそれに敏感に、あるいは過剰なまでに反応し、瞬時に上下左右どこへでも動けるように身構える。
自分の目は相手の目を決して視界から、・・・視線の先からはずさない。
視線の行き着く先には生死の狭間が見えるようだった。
脱兎のごとき跳躍。
回転する体。
思いがけないところから繰り出される刃。
その軌跡を追いかけるように光が反射し、しゅうんと風を切る音と共に美しい弧を描く。
受け止められると同時に散る火花。
それがまるで発火点ののように爆発する力の解放。
後ろでまとめた長い髪の毛がなびくと同時。
体制を崩されたまま、剣もろともに後ろへと吹き飛ばされる。
食いしばった歯が軋むほどに力を篭めて衝撃に耐え、鼻から息を吸う。
喉の奥から声を伴わない空気を短く吐き出す。
後方に一回転して着地。その刹那の時にも決して相手から視線をはずさない。
剣の柄はまだ手にあるということを確かめるように握りなおす。
眼前にいるのは屈強な大男。
腹立たしいほどにその佇まいには余裕があった。
自分が女だから?。
彼女は一瞬そう思ったがそれを否定するように小さく首を振った。
相手に余裕があると感じるのは自分の心の中に怖れがあるからだ。
彼女はそう考え直すとすっと立ち上がり、改めて両手で剣の柄を握る。
足を開き、腰を落とす。
怖れるな。
私は強い。
大きく息を吸い込み、相手に対してこれから行くぞといわんばかりに、気を溜め込んだ。
相手の身構えるのが見えた瞬間に走り出す。
斬りかかると見せかけてフェイント。
読まれる。
読み返す。
小さく繰り出す斬撃が、キン キン と、硬質で魅惑的な音を奏でる。
その音楽のテンポが徐々に速くなり、リズムが自分のものとなってくることを実感する。
すると大男の上半身がぶれて、ついに・・・。
揺らいだ。
いける。
最後の一撃を繰り出す。
男のわき腹から少し下あたりが明るくなっているように見えた。
これが
隙
・・・と言うものなのだろうか。
1億分の1秒の時間の中に相手の倒れる姿が描き出された。
「ごっ!・・・あ」
茶色い土ぼこりが舞った。
「余計なことを考えたな。エデリカ」
突如横腹を襲った衝撃と直後に訪れた激痛にエデリカの頭の中が真っ白になる。
「ごは!・・・・げへぇっ!」
自分が地面に這いつくばっていることに気がついた。何が起こったのか一瞬理解できなかった。
土煙が教えてくれたのは、自分が吹き飛ばされて転がったこと。
「だがそれまでは良かった。私も足を使ったのは久しぶりだ」
どよめきと歓声が二人の周りに立ち上がる。
そこにいた誰もが驚きと喜びを混在させたような表情をし、あるものは腕を振り上げて奇声を上げ、あるものは大きな声でエデリカの名を叫んでいた。
創世歴3733年3月下旬の出来事。
◆◆モルド大佐◆◆
肩で息をしながら目の前の大男を睨み付けるエデリカ。
大男は修練用の格闘着を着ていましたがその着衣の下に強靭な肉体があることはひと目でわかります。しかしその強靭な肉体よりもその上に乗っている首に張り付いている厳しい表情のほうにこそ、何事にも屈しない強靭な精神力があることを思わせます。
息ひとつ乱していない大男を睨みつけるエデリカのその目にはいまだに殺気が揺らめいていました。
「まだ・・・まだ・・・
「剣術の腕前はたいしたものだと言っておこう。認めてやる。短い期間でここまで鍛錬したことは称賛に値する。お前ほどの剣術使いはそうはいないだろう。だがまだ早い。入隊は17歳でなければ許可できん」
その言葉を聴いたエデリカが飛び上がるように立ち上がる。
「まだまだぁ!まだやれる・・・ぐ・・・」
エデリカは横腹に鈍痛を感じて顔をしかめます。それを振り切るように叫びました。
「称賛なんていらない!私がほしいのは近衛隊入隊許可よ!」
「お前はまだ16歳だ。許可は、できない」
エデリカは口元を震わせました。
「た・・・たったの一年じゃない!どうして?!」
大男は鼻息をふんと吐き出します。
「軍規は絶対だ。お前だけを特別扱いは出来ん」
そのひと言に二人を囲んでいた十数人の兵士たちから不満の声が漏れ、徐々に大きくなって行き、やがてエデリカの名前のシュプレヒコールと交じり合っていきます。
大男はその体躯がひと際大きくなるように背筋を伸ばして鋭い視線を右へ左へと覇気と共に投げかけます。すると怒号を浴びせかけられたかのごとくに歓声はざわめきへと収縮してしまいました。
それを見届けるように大男はエデリカに視線を返します。
「ここまでにしよう。お前の修行の成果、しかとこの胸に焼き付けた。だがお前はまだ若い。あわてるな。お前の言うとおり、17歳になる一年後に正式な入隊試験を行う。それまで更に腕を磨いておけ」
そう言って大男が背を向けかけると。
「モルド大佐!」
呼ばれた大男は噛み付くような視線のエデリカを肩越しに冷徹な瞳で見降ろし、同じ言葉をもう一度繰り返します。
「今日はここまでだ」
エデリカは口惜しさに自分の腕が、そして足が小刻みに震えているのを感じました。
この震えが緊張から解放されたからなのか、それとも己の若さに対するいらだちからなのか、エデリカにはわかりませんでした。
一年前。
自分は完膚なきまでにこの男に叩きのめされた。
10回も剣を交わさない内に自分の弱さを思い知らされた。
女だからといって遠慮してこなかった。
大佐と私の父が友人だからと言って手加減なんてしてくれなかった。
自分の中に甘えがあったと、今は認めるしかない。
だけど修行をした私は1年前とは違う。
修行の成果を認めたのに・・・。
称賛なんて何の役にも立たない。
私の力を認めたのなら規律なんて!
◆◆霊牙力(れいがりょく)◆◆
エデリカの突き刺すような視線を背中に感じながらも、モルド大佐は表情を変えませんでした。
「特例があっても良いのではないですか?」
大佐に随伴して歩いていたショートヘアの女が前を見たまま言います。
「特例?特例などない」
モルド大佐の返事に女がやっぱりねと言う風に吐息します。
「特例が続けば対象年齢が下がり続けるかも知れない。そうしたら我々は入隊試験のたびに稚児を相手にしなければならないかも知れんな」
「そんな大げさな」
「大げさなものか。入隊できないという点においては9歳だろうが16歳だろうが変わらん・・・・規則は守ってこそ規則だ。曲げたり破ったりすれば規律が乱れる。規律の乱れは隙を生み、混乱を招き入れ、死を呼び寄せる。近衛隊に必要なのは英雄ではない。規律を乱すことのない分別ある大人が必要なのだ」
彼女は右手に持っていた杖を左手に持ち替えました。そのときにその杖と自分の手首とをつなぐ鎖がチャラチャラと音を立てます。 その女は、髪が短いせいもあってか顔立ちの整った青年にも見えます。端整で中性的な表情から湧き出す妖しげな微笑がぞくりとするほどでした。
「私のような女のハーフセノンを入隊させてくださったあなたにしては苦しい言い訳ですね。モルド大佐」
モルドは小さく息を吐き「言い訳などではない」視線を少し上げます。
「カレラ。入隊時お前は既に17歳以上だったと私は信じている。そしてお前の実力は私を、そして国王陛下を満足させた。だがエデリカはまだ16歳になったばかりだ。私は男であろうと女であろうと種族が何でろうと遠慮も差別もしない。
鋭い刃は使い方を誤れば自身のみならず味方をも傷つけてしまうのとおなじで、扱いには充分な注意と用心が必要だ。若さというのは抜き身の剣と同じだ。エデリカの才能は認めるが、入隊許可年齢に達していないのであれば仕方のないことだ。それを私は残念とは思わない。ローデンもわかってくれるだろう」
カレラはふっと目を伏せるようにこちらを見続けているエデリカを肩越しに見、モルドに視線を戻して呟きます。
「ああ・・・かわいそうなエデリカ。好きな人に捧げる気持ちが強すぎて、きっとこんな方法しか思いつかなかったんでしょうに・・・そんな純粋な思いを打ち砕かれてしまうなんて」
そう言い終えて横目でモルドをチラリと盗み見るカレラ。その言葉の調子には彼を非難する色が含まれているように聞こえましたが。
「肉体の成長は早い。一年などあっという間だ。しかし精神はそうはいかんのだ」
「いいんですか?恨んでますよ?大佐のことを。きっと・・・ふふ」
カレラは少しだけ肩をすくめて楽しそうに微笑みます。
「ふん」
モルドは握った拳の痺れと僅かに残るわき腹の違和感を感じながら考えていました。「恨んでくれて結構だ。恨まれるぐらいで責務を全うできないくらいなら近衛の総隊長などとっくに辞めている」たいした霊牙力だ。未研刀でなければ倒れていたのはどちらだっただろうか、と。
「それはそうと大佐」
「ん?」
「先月のグナス=タイア討伐結果においてのガーラリエル少将の勲功授与についてですが」
「国王陛下が正式に決めたそうだな。何か問題でも?」
「少将はいまだに受けるかどうかの返事もしていないそうですよ。国王陛下も困惑しておられるご様子で・・・」
「・・・」
「大佐から何か言って差し上げたらいかがです?」
一瞬間を置いてからモルドは答えました。
「少将閣下は子供ではない。自分で考え結論を出すだろう。私の出る幕は無い」
「そうですか?」
「・・・何が言いたい。ドルシェ中尉」
モルドは時折改まった感じで階級付きで人を呼ぶことがありますが、それはハッキリとした会話を求めるときでした。
今回はカレラがもってまわった言葉で核心をぼかすのにうんざりしたようです。カレラはそれでも毅然とした感じで話をつづけました。
「ガーラリエル少将は私の前任者であり、あなたの副官だった人です。お忘れではないですよね?」
「忘れてなどいない」
「それを聞いて安心しました。・・・で、これまであったグナス討伐においてあれだけの戦果を上げたのは15年ぶりだそうですよ?嬉しいと思わないのですか?」
「喜ばしい限りだ」
「だったら・・・」
モルドはカレラの言葉を断ち切るように言いました。
「嬉しいと思うのはあくまでも同国人としてだ。武門の誉れ高き事もこの上なし。・・・しかし勲功を受けるか否かは本人が判断することで私が口をさしはさむことではない」
「あの人を軍へ送り出したのはあなたじゃありませんか」
「それとこれとは別の話だ」
「そんな・・・」
唖然とするカレラ。
「もうよせ。なぜそんなにムキになる」
「だって冷たすぎです。彼女はあなたの言葉を待っているんです」
「私の言葉を?それは違う」
「違いませんっ」
カレラは一歩も引きません。モルドも半ば観念したように鼻息を吐いて言いました。
「カレラ。もしも私が少将閣下とともに従軍し、共に戦地でグナス勢相手に戦ったのであれば、私にも勲功を受けるか否かの言葉をかける資格があっただろう。だがそうでは無い以上、私がロマに・・・」モルドは咳払いして言い直します「ガーラリエル閣下に言えるのは祝いの言葉ぐらいのものだ」
「それなら祝辞を贈りに行けばいいじゃないですか。第八師団の兵舎まで歩いても10分とかかりませんよ?」
「祝辞は勲功を授与した後に贈るものだ」
石頭。どうしてもっと簡単に考えられないの?カレラは目の前のわからず屋と言う名前の上官に苛立ちを募らせるばかりでした。
「もういい。その話は終わりだ。来月行われる国王陛下のマルデリワ視察の警備計画を立てねばならん。王下院メンバーでの連携もある。明日から士官を集めて計画会議を行うから周知しておけ」
「・・・はい」
苦虫を咬むような表情で返事だけはしましたが、カレラはどうにも気持ちが収まりませんでした。通路を歩いてゆくモルドの後姿を見ながら憮然とした表情を露にします。
”どうして女の気持ちがわからないのかしら・・・それともわかった上で言っているのかしら。いずれにしたってこのままではガーラリエル様がかわいそう過ぎる。彼女の元上官として少しは今回の勲功、いや大勲功と言ってもいい手柄を誉めても罰は当たらないだろうに・・・。”
カレラはひと月ほど前にあった獣人とノスユナイア軍との戦いに思いをはせました。
◆◆獣人とマクリエル=キンゼー=ガーラリエル◆◆
創世歴3733年2月
ここはノスユナイア王国南部にあるマルデリア湾の南岸地帯。整然と並ぶ軍隊のテントの向こうにエバキィルの塔がかすんで見えています。
ひときわ大きいテントでは、これから行われる戦闘の作戦確認が行われています。テーブルを挟んで立っている二人の人物はこの軍隊の司令官たちでした。
「ガーラリエル少将。本気かね?」
「何か問題でも?ボーラ元帥」
ボーラはガーラリエル少将に向かって何かを言いかけましたが、60前後であろう年齢を象徴する深いシワの刻まれた額を手のひらでゴシゴシと擦って目を閉じました。
「相手は怪物です。しかももう80年も我が国に・・・」
「改めて言われなくともわかっているよ。ロマ」
ロマ。ガーラリエル少将を親しみをこめてそう呼んだボーラは物憂げにひとつため息をついて、年齢はまだ30に届かないであろう女将軍の目を見据えました。
ロマは茶色の髪を短く切っていましたが一箇所だけ長くしてそれを細いみつ編みにしています。そんなやり方で自分が女である事をささやかに主張する、それが彼女の人となりを表しています。
太めの濃い眉毛にきりっとした眼差しが何事にも折れない強い精神の持ち主であることを物語っていました。
テーブルを挟んで彼女の前に座っていたボーラはロマの父親といっても差し支えない感じで、ロマを見る目は年齢から来る疲労感や柔和より軍人の厳しさを併せた光が強く宿っています。
ボーラは鼻から息を吐くとロマを暫く見つめ、そしてゆっくりとした口調でこういいました。
「貴公の父上が亡くなってどれぐらい経つかね?」
「?」
いきなりされた質問に怪訝そうにするロマを見ながら
「彼とも作戦会議ではよく衝突したものだよ。君の話しかたはそっくりだな。キンゼー=ガーラリエルに。もっとも、当時噛み付いていたのは私のほうだったが・・・」ボーラは若い頃の自分を思い出し、恥じ入るように微笑みました。
「ボーラ元帥」
ボーラは作戦の話し合いの最中に別の話をし始めたことに不服そうな表情をしたロマに「12年前・・・」手を上げて制するようにして言いました。
「・・・12年前、キンゼーは我々がこれから戦おうとしているグナス=タイアと闘い、そして死んだ」
ロマの表情に少し翳りが見えました。
「惜しい男を亡くしたと、あの時は心底から悲嘆に暮れたよ。唯一無二の戦友を私から奪った、この過酷な戦闘訓練に名を借りた戦争を恨みさえした・・・」
ロマは黙ってボーラを見ています。
「だが・・・その戦友の忘れ形見が、今こうして私の目の前にいる。時の流れは神の業(わざ)を見るようだとはよく言ったものだ。言葉もない・・・」 感慨深げにそう言ったボーラは落としていた視線をゆっくりとロマへと上げると、過去を懐かしんでいた初老の表情を一変させ、目つきを鋭くして言いました。
「貴公にひとつ言っておきたい」
「なんでしょう?」
「これから始めようとしている戦いは仇討ちではない」
「わかっています」
毅然とした表情のロマ。即答した声も揺らぐことのないまっすぐな調子で硬質でした。
「本当かね?ではなぜ12年前と・・・キンゼー=ガーラリエルと同じ作戦を?」
ロマは目を大きくして驚きました。不自然な間の後に口を開きます。
「父上が私と同じ戦術を?」
「・・・まさか、知らなかったのかね?わたしはてっきり・・・」
驚いているロマを見て同じようにボーラが驚き、そしてすぐに嬉しそうに笑い出したのです。
「蛙の子は蛙か。はっはっは」
「そんな・・・」
ボーラは考えてみれば無理からぬ事と思いながら言いました。
「キンゼーが死んだあのとき。私は会戦の記録をしなかったのだよ。あの敗戦は記録するにはあまりにも酷すぎた」
「・・・」
「師団は事実上崩壊し、兵の8割を失うという被害を受けた。・・・私はキンゼーの近くに在りながら彼を助けることさえ出来なかった。キンゼーは鎧を引き剥がされ奴の爪に・・・・」
ボーラは痛みに耐えるように目を閉じ、そして思い直すように首を振りながら顔を上げました。
「いや・・・それはいい・・・」
ロマはボーラの痛みを理解するかのように沈痛な表情のままボーラを見続けました。
「とにかくあの時は無様すぎた。あまりの恥辱に作戦内容を封印したのは私なのだ。私はてっきりキンゼーが出撃前に君に話していたのかと思ったが・・・」
「しかし封印なんて・・・よく陛下がお許しに・・・」
「敬愛するキンゼー=ガーラリエルの名誉を傷つけたくなかった・・・というのは言い逃れだな。だが本音だ。わたしはそれ以上に友を失った事に落胆して・・・そうすべきだと頑なに考えたのだよ。記録しようがしまいが無様な敗戦に変わりはない。記録しなかったことは誰からも言い咎められることもなかった。誰もがわかってくれていたのだと思う」
ロマは何も言わずにボーラの低いトーンのいくらかしわがれた声にジッと耳を澄ましました。
「作戦の内容を知るものは全て私と同じ考えだった。・・・とはいえ、生き残った当時の参謀は私を含めてたったの二人だったがね・・・。その生き残った友人も1年前に他界してしまった。だからこの作戦内容を知っているのは、もうわたし以外誰もいない」
軍人といっても人の子です。親友が目の前で殺され、敗走した恥辱はおそらくなにものにも変えられぬほどの思いだったに違いない。ロマはそのことについて理解は出来ました。
「閣下。なぜ今その話を?」
ボーラはジッとロマを見て言いました。
「お前はキンゼーの子。血は争えんものよな。モルドの奴もたいした目をしているよ。あの男には恐れ入る」
ボーラはそう言って頭を左右にふりましたが、「だが」すぐに表情を厳しくして言いました。
「キンゼーは戦術の天才と国王陛下からもお褒めの言葉を頂くほどの男だったことは、私が保証する。いや、私の保証など必要ないぐらいにそれは事実だった。だがその天才が死んだ。・・・しかも君が今提案したのと同じ戦術で」
ロマは不服を表すように口を引き結びますが、ボーラの言葉は同じでした。
「ダメだ。その作戦遂行に賛成するわけにはいかん。獣人共もこの戦術は覚えておるだろうから失敗する可能性が高い。キンゼーの二の舞だ。戦友の娘に同じ轍は踏ませられん」
ロマは暫く考えてから顔を上げます。
「では元帥閣下。キンゼー=ガーラリエル将軍の率いた第六師団と今目の前にいる第八師団は同じに見えますか?」
「違うと言いたいのかね」
ボーラ元帥はそう言ってすぐに。
「確かに違っているが、どう違うかは私には言えない。戦力の差を言うのであれば遜色はないと思えるが?」
「私は一個師団を任されてこの5年間、師団長と言う地位に胡坐をかいていたわけではありません。確かに師団長に任命されたのは青天の霹靂でしたし戸惑いもしましたが、第八師団の兵士たちを自分なりに見つめて評価分析し、その上で、今回の戦術は私の部下に一番ふさわしいものだと考えたのです」
フウッと息を吐くボーラ。
「しかしなロマ・・・いやガーラリエル少将。君は第六師団を見たことぐらいしかないだろう?なぜ自分の師団なら上手くいくといえる?」
ロマは反論しようとするボーラを抑えて言いました。
「私も当時、父が稀代の戦術家であったことは幼いながらも理解していましたし、噂も評判も誰よりも身近で感じていました。ですからもしもわたしの考えた今回の戦術が父の考えた物と同じだと言うなら、この作戦は最上の作戦であったのだと信じます。もしも敗因を求めるのであれば、それは父のが稀代の戦術家であったことこそが問題だったとわたしは考えます」
「手厳しいな。貴公は実の父の戦術家たるゆえんを問題だというのかね?」
「そうです」
「なぜだ」
「閣下。兵士が有能な上官についていきたがるのは、何より生存率が高いからと言うのが根底にあるからだと思われませんか?」
「うむ、まあそれも一事だろうな。だがそれだけではなかろう?」
「はい。しかし戦うのなら犬死はしたくないというのは本音でしょう」
「うむ・・・」
「さらにそれに加えて、自分の能力をより有効に活用してもらえるという期待感も大きいと私は思います」
「ふむ。それで?」
「戦術の天才とまで評された父の元には、自分の能力を有効に使って、勝利を手にするであろう。そう期待する兵士が大勢いたと思います。そしてそれは事実グナス戦に連戦連勝した事で証明されてきたことでした」
ボーラはジッと聞いています。
「父が学生だった私にこう言った事を覚えています」
”兵士を他の司令官たちと取り合うというみっともない事はしたくない”
「父はそういう性格だったので、新兵を一から育てる事にも情熱を注いでいました。教わる側の兵士も父に認められようと努力したでしょう。しかし兵士の能力は思えば手に入るというモノではないという事は今も同じです」
「手厳しいな」
「閣下は実際に父の師団で旅団長を務められましたが、心当たりはありませんか?」
ロマの言い方は断定的で確信的でもありました。しかし。
「人は平等ではないからな。だが補い合うことが出来るのもまた人間だよ」
「ではその補い合う事を念頭に置いた作戦立案は成されたことがおありですか?」
ボーラはハッとしました。
言われてみれば作戦立案にそんな要素を取り入れた事も、取り入れた作戦も見た事がないと。作戦に人を合わせる事が当たり前で、そんなことを正否で考えた事もなかったのです。
ロマはすっと視線を落として言いました。
「ガーラリエル将軍は自分の育てた兵士を信じていた。そして兵士もその信頼に応えようと思った。だけど・・・」
結果は敗戦。ボーラはロマに問います。
「では兵士の出来が悪かったのが敗因とでも言いたいのかね。それは承服しかねる」
当事者であるボーラにとってそれは受け止め難い事でした。
「違います。私が言いたいのは稀代の天才の立案した戦術だから、その通りに動けば誰にでも勝てるというのは間違いだという事を言いたいのです」
「何が言いたい?」
「もちろん戦術は優劣もありましょうが、私が第一に考えたいのは優劣より相性です」
「相性?」
「そうです。稀代の戦術家が良いと言ったところで、その戦術との相性が良くない兵士は相性の良い兵士より先に死にます。ならば相性の良い戦術を複数考えてそれに一番寄り添える者を割り当てていく方が損害も最小限で最大の効果を期待できます」
ボーラはウームと唸って返答に詰まりました。
作戦と兵士の相性などと言う司令官を見た事がなかったのです。
「先ほども言いましたが、私は1個師団を任されてこの5年間胡坐をかいていたわけでなく、今日この日のように、いつかは自分の部下たちを戦場に送らなければならなくなった時に、どうすれば一番兵士たちを勇気づけられるか、そして死の恐怖を乗り越えて戦える戦士にしてやれるかを毎日考えていました」
ボーラは瞬きもせずロマの言葉に耳を傾けます。
「その為に、過去の戦記や歴史上の事実などを紐解き、いくつもの戦術を立案しては考え直しという作業を幾度となく繰り返しました。その間に大隊単位での兵士の異動も何十回にもなります」
突撃狂と言われてしまうナバ=コーレルという大隊長があることをボーラは思い出して、あれはロマの思考の産物かと微(かす)かに笑みました。
「ひとつには兵士と作戦の齟齬、そしてもう一つは」
ロマは少し言葉を切ってから続けます。
「ふたつめは・・・12年前はまだラティ・・・、失礼。ラットリア=ツェーデル魔法院長は三賢者ではなく、父の作戦に参加もしていませんでした」
「ふむ・・・ツェーデル殿か・・・」
ヴィッツ=ボーラ元帥はそのひと言に並々ならない大きな意味を感じ取りました。確かに三賢者のひとりであるラットリア=ツェーデルの存在は大きい、と。
此度の戦闘は獣人による隊商襲撃によるアスミュウム強奪が原因です。時を置いてしまうと売り払われてしまう可能性もあり、準備が整っている師団がボーラの第10師団とロマの第8師団が急遽エバキィルの塔の西側に派遣されたのです。
この魔法院長ラットリア=ツェーデルの軍に対する助力で一番大きなものはすべての兵士の軍装に施されている魔印による防御です。
魔印防御は外部からの物理魔法両方の衝撃を緩和する効果を与えるものですが、その効果は衝撃相殺なので、いつかは効果が消えてしまいます。ところがツェーデルの魔印の効果の持続性能はこれまでの誰より抜群だったのです。
そしてロマの率いる第8師団はその防御の魔印の恩恵を受けた者たちでした。
「幼馴染の気遣いか」
「閣下」
「いいではないか。友情は大切だ。誰も特別扱いとは思わんよ」
ロマはフッと笑ってからまた話を続けました。
「万が一のため、といつも気づかいをしてくれたことを感謝しています」
ボーラはロマの言わんとするところを悟ったように言いました。
「もしも今貴公の手にしている力が、12年前のキンゼーにあったら・・・」
ロマは強く頷きました。
「父ならば必ず勝っていたはずです」
ボーラは暫く押し黙っていましたが、ポツリと呟きました。
「雪辱か・・・」
「いえ、ボーラ元帥。今回の討伐に仇討ちなどと言う感情はありません。今回私が考えた作戦が父と同じ作戦であったことには驚きましたが、私も軍人の端くれ。私情はさし挟みません。ですがそうであれば尚の事、軍人として思うのです。父、キンゼー=ガーラリエル元帥の立案した戦術が条件さえ整えば、獣人を討つには最上の戦術であったと」
「ううむ・・・」
ロマはボーラの表情を見ながら更に言います。
「屈辱を雪ぐのは、同じ相手、同じ場所、そして同じ作戦であればこの上はないと私は考えます」
ボーラ元帥は自信を見せるロマを見ながら、2年前の大敗を思い出していました。
第1師団、第2師団、そして第9師団の3個師団、25000兵をもって獣人討伐に赴いたものの、結果は敗退だったのです。
敗因は兵種を重装甲歩兵に極端に割り振ったため、慣れない重装甲を装備した兵士たちが思ったように戦えなかったことと、兵士の動きを獣人に読まれてしまったことでした。
なんにしても負けが続けば獣人の勢いが増し、マルデリワの港も危険に晒されてしまいます。
ボーラは自分だったらどんな作戦を立てて獣人からアスミュウムを奪還するだろうかと考えました。思い起こしてみればキンゼーの部下であった自分が、キンゼーに似通った作戦を立てたりそれを見習ったりして生きた事を思い出します。
偶然とはいえ、ロマの父であり、そして稀代の戦術家と謳われたキンゼー=ガーラリエルと同じ戦術を考案し、しかも時の利、人脈を味方につけた戦友の娘であるロマに対し、期待にも似た感情が湧き上がって来るのをボーラは禁じ得ませんでした。
ユリアス=ロマ=ガーラリエル。稀代の戦術家キンゼーの子。この娘なら・・・。
ボーラは決心しました。
「よかろう。ガーラリエル少将。貴公の御手並み、徳と拝見しよう」
「ありがとうございます」
「だがいいかね。私の判断で絶対防御を展開しても恨まんでくれよ」
「はい・・・閣下の判断に異論は申し上げません」
二人はほほ笑みあいます。
「では今晩の大隊長以上の指揮官全員で本作戦の打ち合わせを行う。良いな?」
「はい。・・・あの・・・ボーラ元帥」
「ん?なにかね?」
ロマは少しためらいがちにあけた口を一度結んでから言いました。
「・・・今回の作戦、父と同じと言いましたが、少し手を加えたいと思っているのです」
「ほう」
「それについて閣下にお願いが」
そのときの自信にあふれたロマの表情をボーラは生涯忘れませんでした。
◆◆過酷とその代価◆◆
現在ロマとボーラの指揮する軍隊が駐屯している場所は太古の遺跡であるエバキィルの塔からそれほど遠くないノスユナイア南部の海岸地帯。ノスユナイア王国が最前線と位置づけている場所です。
大山岳地帯の鬱蒼とした深い森に覆われたこの辺り一帯をグナス=タイアを頭目とする獣人の一団が住み着き始めたのは今からおよそ80年前。この獣人たちはもともとフスラン王国の西側地帯を活動拠点にしていましたが、フスラン王国の軍隊に追いやられ、大山岳地帯を越えてノスユナイア王国側に移住してきたのです。怪物の総数は3万とも5万とも言われていましたが、はっきりとした実数はわかっていません。
移住当時、獣人たちはタイア王国の名乗りを上げ、そのあたりにあったいくつかの村を襲って被害をもたらし、それを端緒に始まったノスユナイア王国による獣人討伐は既に50回以上になりますが、ノスユナイアの軍隊が明確に勝った事は一度としてありませんでした。しかし先代のノスユナイアの王は勝つことに意義を見出すのではなく、怪物たちを封じ込める為に常に圧力をかけ続けることを目的としたのです。
国王の真意は軍隊の弱体化を防ぐ目的があったと言われています。つまり平和になって戦うことがなくなってしまった軍隊では有事の際に使い物にならないと考えたのです。そこで移住してきた怪物を封じ込めることで国土への被害を抑え、なおかつ軍隊の鍛錬にも役立てようと考えたのでした。
実際、初期の頃の戦いは国王軍に散々の結果をもたらしました。同盟国であるレアン共和国の軍事的協力があってもなお、怪物の撃退に数万の犠牲を強いられてしまったのです。
先代のノスユナイア国王はこれを重く見て軍の再編成を行い強兵に努めます。その甲斐あってか、怪物を封じ込めると言う当初の目的を達成することが出来たものの、その実現には実に10年もかかってしまいました。その間の被害は計り知れなかったのですが、苦渋を舐めて築き上げた軍事力はいまやノスユナイア王国にとって必要不可欠なものへと成長を遂げました。そしてレアン共和国との協力体制が二国間のつながりをより強固にそして親密にし、数多くの勇敢な武人を生み出すという結果をももたらしたのです。その武人の中にはロマの父キンゼーの名前があり、ボーラの名前があります。
こういった経緯から、グナス=タイア率いる獣人族との実戦が過酷であっても、戦闘力維持の為には無くてはならない軍事訓練のひとつであると広く認識され、現在に至っているのでした。
第1章 第2話へ続く
情報◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■未研刀(みけんとう)
※研いでおらず刃のついていない刀のこと。試闘、試合に使用される殺傷能力の低い刀
ただし、剣術の心得のない者に剣術の心得がある者が使用すればその限りでなくなることもある
■霊牙力(れいがりょく)
魔法使いは魔法力を持っているが、魔法を使えない戦士は霊牙力という自分の力を何倍にも増加させる能力を持っている。この霊牙力が強い者が戦士(兵士)に向いている。
しかし魔法力に限界があるように霊牙力にも限界がある。尽きてしまえば通常の戦闘力だけとなる。
この力は体の各部に集中させることでその部位のみに力を増幅させることもできる。
0
あなたにおすすめの小説

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話
登夢
恋愛
春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。



百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~
桂
ファンタジー
探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。
そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。
そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる