3 / 20
第1章 破滅のミルコ
2
しおりを挟む
「下がれ!ミルコ!」
爆発音がして、石畳の床に叩きつけられた。
術師の声がかき消えた。
口の中が切れている。
「くそ…なぜだ…この階層で会う敵じゃないぞ」
震える声がする。
ミルコを巻き込むことを厭わず爆発魔法を連発したのは、石蝿を近寄らせないようにするためだった。
「ミルコ噛まれるな!石になるぞ!」
魔術師が魔法晶石を握りしめた。
違う、と言いたかった。ストーンフライを追うのに爆裂の魔法は違う。
だがもう声は出そうにない。喉が裂けている。
恐怖で震える。声が出なければ魔法は使えない。
違う、違うの…と言いたくて、ミルコは喉を絞った。
違う!今は!
「気がつきましたか」
薄目を開ける。
「夢…」
「ずいぶんうなされてましたね」
硬いベッド、白いシーツ、体が温かく感じるのは、治療魔法が効いているからだと思われる。
(生きてる…)
ほっとした。
涙が溢れる。
(また、生き残ってしまった)
「あの」ミルコは声をあげる。まだ声が掠れている。
「他の、人たちは」
綺麗な白を着た治療士は、濡れタオルをミルコの額に当てる。
(また、私だけ)
「状況から見て、ストーンフライの群れに襲われたと想像されます」
治療士は痛ましそうに言った。
「ミルコさんはうずくまって丸まったまま石化していたので、蘇生は容易でした…でも他の人は」
「私、ダメですね…また…」
治療士は首を振った。
「運が悪かったとしか」
濡れタオルが涙を隠すように目の下に当てられた。
「低階層では絶対に出ないストーンフライに遭遇したんですから」
違う。私たちは倒せた。私がためらわなければ。魔術師に最良の選択をさせることができていれば。私は彼らの正体を知っていた。
そう心の中で言いながら、もう一つの声が心で響いた。
私のせいではない。私はパーティーのリーダーではなかった。パーティーリーダーの戦士は真っ先に石にされてしまった。重心を崩して倒れ、粉々になった戦士を見てパニックになった術師が魔法の選択をミスした。それがなければ…。
「いや」
小さな否定を精一杯の声で出して、ミルコは布団に潜り込む。
もういい。やめよう。
私はハンターをやめよう。
体が動くようになってすぐ、ギルドに呼び出された。
能面のような顔の事務官に、ここで待つように、と言われた部屋は、大きな机の置かれた会議室だった。
ぼんやりと待っていると、よく通る声で
「待たせてすまない」
という声とともに、背の高い男が入ってきた。
あまりに見慣れたその顔を見て、思わず立ち上がり、少しよろめいた。
ミルコと同じように眼鏡をかけ、短い髪を撫でつけている。よれよれの皺だらけの長衣は、とてもその地位にある者が身につけるのにはおよそ似つかわしくない。
「ああ、そのまま、そのまま」
「ギルドマスター!すいません…」
攻略省の出先機関でもあるギルドの最高責任者。本当の名前は誰も知らない。ただこう呼ばれている。
バッシュ・ザ・ギルドマスター。
「すまないね、回復がまだだろう」
「申し訳ありません、また」
「三回目だったか」バッシュはまるで、茶に砂糖を三つ入れるのか、というような感じで言った。「全滅を経験するのは」
「申し訳あ…」
「いやいや、責めているわけではないよ」バッシュは慌てて言った。「君に落ち度がないことは回収班の証言からも明らかだ。君はエラーに巻き込まれた。三度も特異点に遭遇した」
ミルコは首を振った。私が悪いのだ、と言いたかった。
だがバッシュは構わず続けた。
「君が遭遇した、低階層では起こり得ない強敵や難易度の高い罠の存在、それを我々は特異点と呼んでいる」
バッシュは顎髭を撫でた。
「その特異点に三度も遭遇して生き延びた者などいない。君以外はね」
ミルコは首を振った。「たまたまです」
「謙遜は口当たりの良い毒である」
「…はい」
「タウリスの言葉だよ。聞いたことはないかね」
「タウリス…って誰ですか」
「大切なことはタウリスが2000年前にだいたい言っているからね」
だからタウリスって誰なんだろう、という問いが宙ぶらりんになって、ミルコは首を傾げたままだ。
「君は特異点の全てで生き延びた。その才能には謙遜は似合わない。だからこそ、君に新しい任務を与えたい。これはギルドの意志として受け取ってくれたまえ」
「それは」穏やかな物言いの中にある意図を感じ取ってミルコは顔を上げる。
「命令ですね」
「そう、君に拒否権はない」
バッシュは嬉しそうにポン、と手を叩いた。「いいね。知性あるものとの会話は時を稼ぐ」
「それもタウリスですか」
バッシュはいかにも愉快そうに吹き出した。
「今のは私の言葉だよ」
「ギルドマスターはこう言いました。迷宮に関しては素人だと」
のびた酔漢を片付けたウェイターがお礼に持ってきた肉料理をつまみながら、ミルコは言った。
「まあ、そうだな」ハックは認めた。
「戦場が長かったからな」
「3年だ」スラッシュが訂正した。「大して長いわけじゃない」
「戦場で3年生き延びるのは、長いですよ」
ミルコは言った。「大概そこまでもたないです。お二人の若さなら、尚更」
ハックは意外そうにミルコを見て、再び吹き出した。
「そんなふうに言われたことはないな」
「確かに」スラッシュも微笑んだ。
「あんたも大概若いぜ」
「確かに」ミルコは認めた。「そんなには変わらないかもですね」
新米のハンターを二人、君に面倒を見てもらいたいんだ、とバッシュは言った。
全然新米ではない。私には荷が重い。
ミルコは心の中でため息をつく。
「とりあえずお二人に前衛に回っていただくとして」ミルコは言った。
「マカリスターの法則をご存知ですか」
ハックはスラッシュを見た。
スラッシュは首を振る。
「なんだそれは」
そこからか。
「タリスマンの迷宮は、一から九十九階層まであります。深くなればなるほど晶石濃度が増えます。つまり、晶石の影響を受けた魔物も強大化し、危険度が増します」
ミルコはこぼれたエールでテーブルに丸を六つ描いた。
「迷宮の危険度が増し、死亡率が上がるのは十三階層です。そこを越えるのであれば、六人のパーティー編成が最も効率的だと言われています。これがマカリスター・セオリーです」
「必ず六人必要?」ハックが尋ねた。
「そういうわけではないのですが、いろいろな試行錯誤の結果、これが最もしっくりくる編成だと言われています」
タリスマンの迷宮に挑んだ初期のハンターの一人、マカリスターは、引退するまでにギルドの編成担当として、多くのハンターに助言を行ってきた。
マカリスターは最初の王属でないハンターとして、まだギルドが誕生したばかりの時に雇われて迷宮に侵入した。当時のマカリスターの経歴は不明である(野盗の類だったとも言われている)。当時の迷宮探索の編成は、騎士団メンバーが中心で、騎士四人に魔術師が一人という編成が多かったらしい。
しかし、この編成は迷宮の深部に到達してから、ことごとく失敗した。
迷宮の通路の広さは騎士三人が並んで戦うのに精一杯の広さである。よってマカリスターは最初、騎士三人魔術師一人の編成が妥当だと考えた。しかし、自分がその編成についていくことで、中距離射撃の武器で後方支援をし、生存率が上がるのではないかと考えた。
この後マカリスターは治療士の資格を持つ聖騎士を連れて六人で侵入し、成果を挙げた。この、前衛三人に魔術師、治療士、後方支援の六名で侵入するスタイルを、いつの頃からかマカリスターセオリーと呼ぶようになった、というわけだ。
「ですから今、深いところを目指すハンターは、皆この形式をとっています」
「つまり」ハックは言った。「あれか、あと三人は仲間を入れろ、ってことかい」
「そうなりますね」
「分け前は減るけどな」銀髪をかきあげてハックは思案した。「それが安全だというわけか」
「死ねば分け前もないですからね」ミルコは言った。「三人では不意打ちなどに対応できないですし、無茶だと思います」
「どう思う」ハックはスラッシュを振り返った。
「誰かを誘うにしても、実績がいるだろう」スラッシュは言った。
「まずは手っ取り早く名を売らなければ、一緒に行ってくれる奴の腕前も期待できない」
「確かにそうですね」
ミルコは暗い表情で言った。
「まあ、私の場合、逆の名声が立っちゃってますけどね…」
「あんたはどうなんだ」急にハックが黙って肉を齧っていたエヴァリスに声をかけた。
「ふゃい」口の中にいっぱいに肉を頬張ったエヴァリスが目を白黒させた。
「エヴァリスは聖騎士団ですから」ミルコは慌てて止めた。
「私たちと同行するのは、騎士団からの命令がある時だけです」
エヴァリスが深く頷いた。肉を飲み込んだらしい。
「先輩を私たちのパーティーに入れることはできます。先輩は教徒ですから」
「なるほどな」ハックはつぶやいた。「面倒臭いな、あんた」
「失礼ですね」エヴァリスが憤慨した。「信心深いだけですわ」
「となると、やはり実績が必要だ」スラッシュが言った。
「そうですね…でも最初から六人である必要は、必ずしもないんですよ」
ミルコは説明した。
「低階層、チュートリアルレーン、と言われる第一階層は、一人でも侵入可能です」
「三人ならどこまでいける」
「さあ…何もなければ、三階が限度かと」
「なるほど」ハックが言った。
「では、まず潜ることだな。案内してくれ」
爆発音がして、石畳の床に叩きつけられた。
術師の声がかき消えた。
口の中が切れている。
「くそ…なぜだ…この階層で会う敵じゃないぞ」
震える声がする。
ミルコを巻き込むことを厭わず爆発魔法を連発したのは、石蝿を近寄らせないようにするためだった。
「ミルコ噛まれるな!石になるぞ!」
魔術師が魔法晶石を握りしめた。
違う、と言いたかった。ストーンフライを追うのに爆裂の魔法は違う。
だがもう声は出そうにない。喉が裂けている。
恐怖で震える。声が出なければ魔法は使えない。
違う、違うの…と言いたくて、ミルコは喉を絞った。
違う!今は!
「気がつきましたか」
薄目を開ける。
「夢…」
「ずいぶんうなされてましたね」
硬いベッド、白いシーツ、体が温かく感じるのは、治療魔法が効いているからだと思われる。
(生きてる…)
ほっとした。
涙が溢れる。
(また、生き残ってしまった)
「あの」ミルコは声をあげる。まだ声が掠れている。
「他の、人たちは」
綺麗な白を着た治療士は、濡れタオルをミルコの額に当てる。
(また、私だけ)
「状況から見て、ストーンフライの群れに襲われたと想像されます」
治療士は痛ましそうに言った。
「ミルコさんはうずくまって丸まったまま石化していたので、蘇生は容易でした…でも他の人は」
「私、ダメですね…また…」
治療士は首を振った。
「運が悪かったとしか」
濡れタオルが涙を隠すように目の下に当てられた。
「低階層では絶対に出ないストーンフライに遭遇したんですから」
違う。私たちは倒せた。私がためらわなければ。魔術師に最良の選択をさせることができていれば。私は彼らの正体を知っていた。
そう心の中で言いながら、もう一つの声が心で響いた。
私のせいではない。私はパーティーのリーダーではなかった。パーティーリーダーの戦士は真っ先に石にされてしまった。重心を崩して倒れ、粉々になった戦士を見てパニックになった術師が魔法の選択をミスした。それがなければ…。
「いや」
小さな否定を精一杯の声で出して、ミルコは布団に潜り込む。
もういい。やめよう。
私はハンターをやめよう。
体が動くようになってすぐ、ギルドに呼び出された。
能面のような顔の事務官に、ここで待つように、と言われた部屋は、大きな机の置かれた会議室だった。
ぼんやりと待っていると、よく通る声で
「待たせてすまない」
という声とともに、背の高い男が入ってきた。
あまりに見慣れたその顔を見て、思わず立ち上がり、少しよろめいた。
ミルコと同じように眼鏡をかけ、短い髪を撫でつけている。よれよれの皺だらけの長衣は、とてもその地位にある者が身につけるのにはおよそ似つかわしくない。
「ああ、そのまま、そのまま」
「ギルドマスター!すいません…」
攻略省の出先機関でもあるギルドの最高責任者。本当の名前は誰も知らない。ただこう呼ばれている。
バッシュ・ザ・ギルドマスター。
「すまないね、回復がまだだろう」
「申し訳ありません、また」
「三回目だったか」バッシュはまるで、茶に砂糖を三つ入れるのか、というような感じで言った。「全滅を経験するのは」
「申し訳あ…」
「いやいや、責めているわけではないよ」バッシュは慌てて言った。「君に落ち度がないことは回収班の証言からも明らかだ。君はエラーに巻き込まれた。三度も特異点に遭遇した」
ミルコは首を振った。私が悪いのだ、と言いたかった。
だがバッシュは構わず続けた。
「君が遭遇した、低階層では起こり得ない強敵や難易度の高い罠の存在、それを我々は特異点と呼んでいる」
バッシュは顎髭を撫でた。
「その特異点に三度も遭遇して生き延びた者などいない。君以外はね」
ミルコは首を振った。「たまたまです」
「謙遜は口当たりの良い毒である」
「…はい」
「タウリスの言葉だよ。聞いたことはないかね」
「タウリス…って誰ですか」
「大切なことはタウリスが2000年前にだいたい言っているからね」
だからタウリスって誰なんだろう、という問いが宙ぶらりんになって、ミルコは首を傾げたままだ。
「君は特異点の全てで生き延びた。その才能には謙遜は似合わない。だからこそ、君に新しい任務を与えたい。これはギルドの意志として受け取ってくれたまえ」
「それは」穏やかな物言いの中にある意図を感じ取ってミルコは顔を上げる。
「命令ですね」
「そう、君に拒否権はない」
バッシュは嬉しそうにポン、と手を叩いた。「いいね。知性あるものとの会話は時を稼ぐ」
「それもタウリスですか」
バッシュはいかにも愉快そうに吹き出した。
「今のは私の言葉だよ」
「ギルドマスターはこう言いました。迷宮に関しては素人だと」
のびた酔漢を片付けたウェイターがお礼に持ってきた肉料理をつまみながら、ミルコは言った。
「まあ、そうだな」ハックは認めた。
「戦場が長かったからな」
「3年だ」スラッシュが訂正した。「大して長いわけじゃない」
「戦場で3年生き延びるのは、長いですよ」
ミルコは言った。「大概そこまでもたないです。お二人の若さなら、尚更」
ハックは意外そうにミルコを見て、再び吹き出した。
「そんなふうに言われたことはないな」
「確かに」スラッシュも微笑んだ。
「あんたも大概若いぜ」
「確かに」ミルコは認めた。「そんなには変わらないかもですね」
新米のハンターを二人、君に面倒を見てもらいたいんだ、とバッシュは言った。
全然新米ではない。私には荷が重い。
ミルコは心の中でため息をつく。
「とりあえずお二人に前衛に回っていただくとして」ミルコは言った。
「マカリスターの法則をご存知ですか」
ハックはスラッシュを見た。
スラッシュは首を振る。
「なんだそれは」
そこからか。
「タリスマンの迷宮は、一から九十九階層まであります。深くなればなるほど晶石濃度が増えます。つまり、晶石の影響を受けた魔物も強大化し、危険度が増します」
ミルコはこぼれたエールでテーブルに丸を六つ描いた。
「迷宮の危険度が増し、死亡率が上がるのは十三階層です。そこを越えるのであれば、六人のパーティー編成が最も効率的だと言われています。これがマカリスター・セオリーです」
「必ず六人必要?」ハックが尋ねた。
「そういうわけではないのですが、いろいろな試行錯誤の結果、これが最もしっくりくる編成だと言われています」
タリスマンの迷宮に挑んだ初期のハンターの一人、マカリスターは、引退するまでにギルドの編成担当として、多くのハンターに助言を行ってきた。
マカリスターは最初の王属でないハンターとして、まだギルドが誕生したばかりの時に雇われて迷宮に侵入した。当時のマカリスターの経歴は不明である(野盗の類だったとも言われている)。当時の迷宮探索の編成は、騎士団メンバーが中心で、騎士四人に魔術師が一人という編成が多かったらしい。
しかし、この編成は迷宮の深部に到達してから、ことごとく失敗した。
迷宮の通路の広さは騎士三人が並んで戦うのに精一杯の広さである。よってマカリスターは最初、騎士三人魔術師一人の編成が妥当だと考えた。しかし、自分がその編成についていくことで、中距離射撃の武器で後方支援をし、生存率が上がるのではないかと考えた。
この後マカリスターは治療士の資格を持つ聖騎士を連れて六人で侵入し、成果を挙げた。この、前衛三人に魔術師、治療士、後方支援の六名で侵入するスタイルを、いつの頃からかマカリスターセオリーと呼ぶようになった、というわけだ。
「ですから今、深いところを目指すハンターは、皆この形式をとっています」
「つまり」ハックは言った。「あれか、あと三人は仲間を入れろ、ってことかい」
「そうなりますね」
「分け前は減るけどな」銀髪をかきあげてハックは思案した。「それが安全だというわけか」
「死ねば分け前もないですからね」ミルコは言った。「三人では不意打ちなどに対応できないですし、無茶だと思います」
「どう思う」ハックはスラッシュを振り返った。
「誰かを誘うにしても、実績がいるだろう」スラッシュは言った。
「まずは手っ取り早く名を売らなければ、一緒に行ってくれる奴の腕前も期待できない」
「確かにそうですね」
ミルコは暗い表情で言った。
「まあ、私の場合、逆の名声が立っちゃってますけどね…」
「あんたはどうなんだ」急にハックが黙って肉を齧っていたエヴァリスに声をかけた。
「ふゃい」口の中にいっぱいに肉を頬張ったエヴァリスが目を白黒させた。
「エヴァリスは聖騎士団ですから」ミルコは慌てて止めた。
「私たちと同行するのは、騎士団からの命令がある時だけです」
エヴァリスが深く頷いた。肉を飲み込んだらしい。
「先輩を私たちのパーティーに入れることはできます。先輩は教徒ですから」
「なるほどな」ハックはつぶやいた。「面倒臭いな、あんた」
「失礼ですね」エヴァリスが憤慨した。「信心深いだけですわ」
「となると、やはり実績が必要だ」スラッシュが言った。
「そうですね…でも最初から六人である必要は、必ずしもないんですよ」
ミルコは説明した。
「低階層、チュートリアルレーン、と言われる第一階層は、一人でも侵入可能です」
「三人ならどこまでいける」
「さあ…何もなければ、三階が限度かと」
「なるほど」ハックが言った。
「では、まず潜ることだな。案内してくれ」
0
あなたにおすすめの小説

最愛の番に殺された獣王妃
望月 或
恋愛
目の前には、最愛の人の憎しみと怒りに満ちた黄金色の瞳。
彼のすぐ後ろには、私の姿をした聖女が怯えた表情で口元に両手を当てこちらを見ている。
手で隠しているけれど、その唇が堪え切れず嘲笑っている事を私は知っている。
聖女の姿となった私の左胸を貫いた彼の愛剣が、ゆっくりと引き抜かれる。
哀しみと失意と諦めの中、私の身体は床に崩れ落ちて――
突然彼から放たれた、狂気と絶望が入り混じった慟哭を聞きながら、私の思考は止まり、意識は閉ざされ永遠の眠りについた――はずだったのだけれど……?
「憐れなアンタに“選択”を与える。このままあの世に逝くか、別の“誰か”になって新たな人生を歩むか」
謎の人物の言葉に、私が選択したのは――

私はもう必要ないらしいので、国を護る秘術を解くことにした〜気づいた頃には、もう遅いですよ?〜
AK
ファンタジー
ランドロール公爵家は、数百年前に王国を大地震の脅威から護った『要の巫女』の子孫として王国に名を残している。
そして15歳になったリシア・ランドロールも一族の慣しに従って『要の巫女』の座を受け継ぐこととなる。
さらに王太子がリシアを婚約者に選んだことで二人は婚約を結ぶことが決定した。
しかし本物の巫女としての力を持っていたのは初代のみで、それ以降はただ形式上の祈りを捧げる名ばかりの巫女ばかりであった。
それ故に時代とともにランドロール公爵家を敬う者は減っていき、遂に王太子アストラはリシアとの婚約破棄を宣言すると共にランドロール家の爵位を剥奪する事を決定してしまう。
だが彼らは知らなかった。リシアこそが初代『要の巫女』の生まれ変わりであり、これから王国で発生する大地震を予兆し鎮めていたと言う事実を。
そして「もう私は必要ないんですよね?」と、そっと術を解き、リシアは国を後にする決意をするのだった。
※小説家になろう・カクヨムにも同タイトルで投稿しています。

寵愛の花嫁は毒を愛でる~いじわる義母の陰謀を華麗にスルーして、最愛の公爵様と幸せになります~
紅葉山参
恋愛
アエナは貧しい子爵家から、国の英雄と名高いルーカス公爵の元へと嫁いだ。彼との政略結婚は、彼の底なしの優しさと、情熱的な寵愛によって、アエナにとってかけがえのない幸福となった。しかし、その幸福を妬み、毎日のように粘着質ないじめを繰り返す者が一人、それは夫の継母であるユーカ夫人である。
「たかが子爵の娘が、公爵家の奥様面など」 ユーカ様はそう言って、私に次から次へと理不尽な嫌がらせを仕掛けてくる。大切な食器を隠したり、ルーカス様に嘘の告げ口をしたり、社交界で恥をかかせようとしたり。
だが、私は決して挫けない。愛する公爵様との穏やかな日々を守るため、そして何より、彼が大切な家族と信じているユーカ様を悲しませないためにも、私はこの毒を静かに受け流すことに決めたのだ。
誰も気づかないほど巧妙に、いじめを優雅にスルーするアエナ。公爵であるあなたに心配をかけまいと、彼女は今日も微笑みを絶やさない。しかし、毒は徐々に、確実に、その濃度を増していく。ついに義母は、アエナの命に関わるような、取り返しのつかない大罪に手を染めてしまう。
愛と策略、そして運命の結末。この溺愛系ヒロインが、華麗なるスルー術で、最愛の公爵様との未来を掴み取る、痛快でロマンティックな物語の幕開けです。
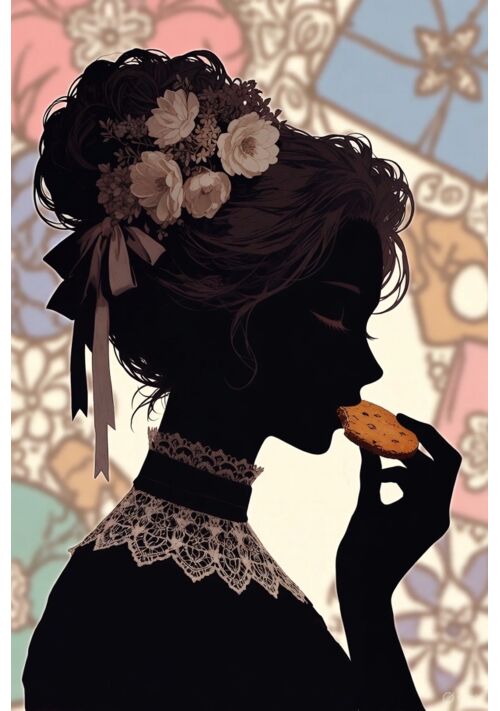
誰からも食べられずに捨てられたおからクッキーは異世界転生して肥満令嬢を幸福へ導く!
ariya
ファンタジー
誰にも食べられずゴミ箱に捨てられた「おからクッキー」は、異世界で150kgの絶望令嬢・ロザリンドと出会う。
転生チートを武器に、88kgの減量を導く!
婚約破棄され「豚令嬢」と罵られたロザリンドは、
クッキーの叱咤と分裂で空腹を乗り越え、
薔薇のように美しく咲き変わる。
舞踏会での王太子へのスカッとする一撃、
父との涙の再会、
そして最後の別れ――
「僕を食べてくれて、ありがとう」
捨てられた一枚が紡いだ、奇跡のダイエット革命!
※カクヨム・小説家になろうでも同時掲載中
※表紙イラストはAIに作成していただきました。

【完結】ひとつだけ、ご褒美いただけますか?――没落令嬢、氷の王子にお願いしたら溺愛されました。
猫屋敷 むぎ
恋愛
没落伯爵家の娘の私、ノエル・カスティーユにとっては少し眩しすぎる学院の舞踏会で――
私の願いは一瞬にして踏みにじられました。
母が苦労して買ってくれた唯一の白いドレスは赤ワインに染められ、
婚約者ジルベールは私を見下ろしてこう言ったのです。
「君は、僕に恥をかかせたいのかい?」
まさか――あの優しい彼が?
そんなはずはない。そう信じていた私に、現実は冷たく突きつけられました。
子爵令嬢カトリーヌの冷笑と取り巻きの嘲笑。
でも、私には、味方など誰もいませんでした。
ただ一人、“氷の王子”カスパル殿下だけが。
白いハンカチを差し出し――その瞬間、止まっていた時間が静かに動き出したのです。
「……ひとつだけ、ご褒美いただけますか?」
やがて、勇気を振り絞って願った、小さな言葉。
それは、水底に沈んでいた私の人生をすくい上げ、
冷たい王子の心をそっと溶かしていく――最初の奇跡でした。
没落令嬢ノエルと、孤独な氷の王子カスパル。
これは、そんなじれじれなふたりが“本当の幸せを掴むまで”のお話です。
※全10話+番外編・約2.5万字の短編。一気読みもどうぞ
※わんこが繋ぐ恋物語です
※因果応報ざまぁ。最後は甘く、後味スッキリ

【完結】もう…我慢しなくても良いですよね?
アノマロカリス
ファンタジー
マーテルリア・フローレンス公爵令嬢は、幼い頃から自国の第一王子との婚約が決まっていて幼少の頃から厳しい教育を施されていた。
泣き言は許されず、笑みを浮かべる事も許されず、お茶会にすら参加させて貰えずに常に完璧な淑女を求められて教育をされて来た。
16歳の成人の義を過ぎてから王子との婚約発表の場で、事あろうことか王子は聖女に選ばれたという男爵令嬢を連れて来て私との婚約を破棄して、男爵令嬢と婚約する事を選んだ。
マーテルリアの幼少からの血の滲むような努力は、一瞬で崩壊してしまった。
あぁ、今迄の苦労は一体なんの為に…
もう…我慢しなくても良いですよね?
この物語は、「虐げられる生活を曽祖母の秘術でざまぁして差し上げますわ!」の続編です。
前作の登場人物達も多数登場する予定です。
マーテルリアのイラストを変更致しました。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

『白い結婚だったので、勝手に離婚しました。何か問題あります?』
夢窓(ゆめまど)
恋愛
「――離婚届、受理されました。お疲れさまでした」
教会の事務官がそう言ったとき、私は心の底からこう思った。
ああ、これでようやく三年分の無視に終止符を打てるわ。
王命による“形式結婚”。
夫の顔も知らず、手紙もなし、戦地から帰ってきたという噂すらない。
だから、はい、離婚。勝手に。
白い結婚だったので、勝手に離婚しました。
何か問題あります?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















