5 / 9
本編
君と一緒がいい
しおりを挟む
高校1年生の冬の日、私は陽光君と賭けをして負けた。
その結果魂を半分彼に奪われてしまった。それからどうなるのだろうと戦々恐々としていた。
いいように弄ばれ、今までの恨みを晴らされるのかと不安にもなった。
意外にも、それからは特に怖い事は無かった。
もちろん陽光君は毎日そばにいる。だから変なことは言えないし、プライベートの時間は無いに等しい。
だけど彼はとても優しかった。
私の事を好きと言っていたが、実際に彼の私の対する接し方は恋人に近いものだった。
友達というには近すぎる距離と、熱のこもった視線に、呼びかける時の声は甘い。
話が合うので一緒にお喋りしていたりするのが楽しい。お互いの空気感が合うおかげか彼と一緒にいるのは居心地がいいとすら思い始めていたのだ。
「これで合っている?」
今日は部屋で陽光君と勉強会だった。私は解いた問題が合っているかどうか陽光君に確認してもらう。
陽光君は私のノートを真剣な表情で見る。
「そう。正解だよ。前は解けなかったのに今日はちゃんと解けたね。えらいよ、ほのか」
魂を半分奪われてから陽光君は私のことを信濃さんではなく、ほのかと呼ぶようになった。まさかの名前呼びに最初はくすぐったい気分だったけど今ではすっかり慣れてしまった。
彼は僅かに微笑んで赤ペンで丁寧に丸をつける。
霊となった彼は物が持てないから念力みたいな力で赤いペンはふわふわと浮いている。ちょっと不思議な光景だけど私は既に見慣れてしまった。
幽霊で肉体を持たないが故、物に触れない陽光君はポルターガイストの応用みたいな感じで物を触らずに動かす。彼が唯一触れられるのは魂を奪った私だけだ。
実は陽光君は勉強はかなりできる方だった。本人曰く生前はクラスで常に3番以内だったらしいし、学年でも常に上位10位以内の成績だったそうだ。
私の学校は成績が張り出されず個人にしか順位が伝えられない方式をとっている。
だから陽光君の具体的な成績は知らなかった。普段の様子から勉強はできるんだろうなとは思っていた。
この情報は私が聞いたら本人が教えてくれた事だ。
「僕の成績って中途半端であんまり自慢にならないから言わないようにしていたんだ。学年1位とかだったら格好いいだろうけどね」
陽光君は恥ずかしそうにポツリと言った。私からしたら十分に成績優秀ですごいと思う。
ちなみに総合的な私の成績は中の中で平均そのものだ。文系科目はそこそこ上位の成績なのだが、数学と化学が足を引っ張り最終的に平均に落ち着いていた。
数学と化学を含めた理科系科目が苦手な私のために陽光君はたまにこうやって勉強を見てくれる。
今日も2週間後の期末考査に向けて勉強を見てもらっていた。こうして彼に勉強を見てもらう日が来るなんて想像がつかなかった。
そもそも幽霊で勉強をする必要のない彼の方が勉強できるっていう事に私は恥を覚えなければならないのだろう。だけど陽光君が優秀すぎるのだから仕方がない。
意外と彼は家庭教師の才能があると思う。彼はちょっとした事で褒めてモチベーションを上げてくれるし、わからないところを馬鹿にする事なく根気よく説明してくれる。
教えるのも上手で彼の説明はするすると頭に入ってくる。
私のノートに書かれた陽光君の読みやすく整った字がすごく好きだった。
陽光君は私が間違えたりわからない問題があったらどうして間違えたのかとか、問題を解く際の注意するポイントを丁寧に教えてノートに書いてくれるのだ。
綺麗な字とたまに描かれるどこかで見たことのあるキャラクターをデフォルメ化した絵がとても好きだった。
何よりも勉強を教えてくれる時の彼の声は落ち着いていてとても優しい。またその時の真剣な顔がとても格好よく見えたのだ。
「良かった。ここ苦手だから自信なかったんだ」
「大丈夫だよ。合っているよ。他にわからないところとかある?」
「うーん。一通り問題解いてからでいい?自分がどこまでできるか試したいから」
「わかったよ。じゃあ僕は適当に何かしているから終わったら呼んで」
私は再びに机に向かって問題を解き始める。
しばらくすると問題が解き終わったので陽光君を呼ぶ。
「終わったんだね。お疲れ様。せっかくだから休憩にしない?紅茶とお菓子持って来たよ」
「ありがとう」
「どういたしまして」
机の片隅には湯気がたった温かい紅茶と味を調節するためのコーヒー用のシュガーとおやつであるチョコレートが置いてあった。
紅茶に砂糖を入れて口をつける。紅茶の濃さと熱さはちょうど良くて私好みだ。これも陽光君の気遣いなんだと思う。
彼がいれた紅茶は最初は少し濃かったり薄かったりした。それに紅茶の熱さだって火傷しそうなほどに熱かったり逆にぬるかったりしていた。
しかしいつの間にか私好みの濃さの紅茶がいれられるようになっていた。逆に言えば好みが把握できるほど私たちは一緒の時間を過ごしたという事だ。
そして休憩が終わると再び勉強会が始まった。
こうして穏やかで優しい振る舞いを見ると、笑って人を殺し、傷つけ、時には恐怖で意のままに人を従わせようとする苛烈で残酷な人物とは思えなかった。
そもそも生前の振る舞いを考えるとこれが本来の彼の姿なのだろう。
そして私は陽光君と楽しい時間を過ごしていた。
夏祭りでは打ち上げ花火を一緒に見て、それからこっそり川辺で2人で線香花火をした。
またある時は電車に乗って大きい町の博物館の展示を見に行った。そして冬は雪祭りにも参加した。
見た目は独りぼっちで遊びに出かける痛々しい女だけど隣に陽光君がいるだけで楽しかったのだ。
陽光君が楽しそうにしているのを見るのが好きだった。
そんな時間を過ごしているうちに彼とだったら一緒にいてもいい。ううん、この言い方はおこがましいので言い方を変えよう。
陽光君と一緒にいたいと思ってしまうようになった。それだけ彼と過ごす時間は幸せだったのだ。
***
そして私は高校3年生になった7月の事だった。
妹のあずさに誘われて映画を観に行くことになった。
あずさがチョイスした映画は意外にもホラーもので少し驚いた。
彼女の選んだものはキッズ向けのホラーだけどホラー全般は苦手だったはずだ。家にいる時も家族でホラー映画のビデオを見るとあずさは自分の部屋に籠もってしまう。
「あずさどうしたの?ホラーとかダメだったじゃない」
「そうなんだけどさ。クラスのみんな、この映画の話ばっかであずさついてけなくてつまんない。友達はもうみんな見てるしあずさ1人で見るのも怖いんだもん」
「そっか。だからお姉ちゃん誘ったんだね」
「うん」
あずさらしい理由だ。ホラーが怖いくせに話についていけず疎外感を感じたくないから映画を観ようとなったらしい。
そして友達には怖がる姿が恥ずかしいから見られたく無いという理由で私を誘ったそうだ。
映画館でチケットとポップコーンと飲み物を買う。
当然陽光君も着いてきた。だけど陽光君はこの映画に興味がないみたい。
だって別の映画のポスターを眺めている。彼が眺めていたポスターはアクションものの映画でちょっと意外だった。
ミステリーとかノンフィクションとかそういったシリアスなものが好きな印象だったからだ。
「ほのか、僕は外で待ってるからね」
人が大勢いるところで陽光君と会話していると1人で喋っているちょっと危険な人なので目線だけでわかったと伝える。
いつもだったらどんな駄作の映画でも絶対についてきて一緒に見ているが今回に限っては着いてこなかった。
同じ幽霊だから何か思うところがあるのだろうか。陽光君は1度たりとも上映室には入ってこなかった。そして上映が終わった後、陽光君は珍しく黙ったままどこかへ消えてしまった。
「なんか切なかったね。でも幽霊のお姉ちゃんは最後は成仏できてよかったね。やっぱり死んでから幽霊になると辛いんだね。好きな人が新しい恋人を作って幸せなのを見てるだけって辛いよ」
映画の上映が終わってから家に戻るとあずさがポツリと感想を漏らした。
「そうね」
あの映画は子供向けと言う割には大人でも響く映画だったと思う。
アニメ映画で可愛らしい絵とは裏腹に残された人間の想いや未練を残した女性の幽霊に焦点が当てられて大人向けだったと思う。
女性の幽霊は最初は好きな人を待っているだけの無害な霊だったのに、この世に渦巻く人間の悪意や欲望に影響されて変質しまい好きだった男性を連れて行こうとしていた。
そしてその男性は新たな恋人を作っていてなおややこしい状況となるのだ。
それを知った幽霊の妹である小学生の主人公とその友人が幽霊になった姉を成仏させようとするストーリーだ。
その成仏させる過程でアクションあり冒険ありなので小学生には飽きない内容だろう。
最終的には女性は無事に未練や執着から解放されて成仏する。そして晴れやかな感じで終わった。
だけどこの終わりは私にはスッキリしなかったのだ。死んだ人間は何がなんでも成仏しなくてはいけないのかと私は思ってしまった。
一緒に遊びに行って楽しそうにする陽光君を見ると幽霊だってこの世を楽しんでもいいのではないかと思ってしまうのだ。
何よりも私は陽光君に消えて欲しくないと思ってしまった。
確かに陽光君が霊となって私の前に現れた時はとても怖かった。
正直今でも怖い時はある。それに魂を奪われて彼によって呪縛を受けている状態だ。
それでも彼は普段は優しく愛情深い人だ。ただ誰よりも不安になりやすく、失う事を恐れているのだ。
あの映画の結末を見ると彼を私という未練から解き放たなくてはいけないのかと思う。
陽光君にいて欲しいという気持ちと成仏した方が救われるのではという2つの想いがせめぎ合っている。
私は陽光君とどうなりたいんだろう。情けないけど自分でもよくわかっていない。
***
そんな曖昧な想いを抱えた私に転機が訪れる。それはお盆の日だった。
「じゃあ僕は実家にいるね。父さんも母さんも僕の事は見えないけどせめてこの日はそばにいようと思うんだ。気をつけてね、君は悪い人に目をつけられやすいからね」
そして陽光君は煙のように消えてしまった。本当になんでもありだ。
お盆は陽光君と離れる数少ない期間だ。
迎え盆から送り盆にかけての3日間だけ彼は私の前から姿を消す。8月13日から15日までは彼は家族の元に戻っている
これは私が提案した事だった。
彼の家庭関係は良好だったらしく彼のご両親は大層陽光君に愛情を注いでいたそうだ。だから私はお盆くらいは実家で過ごすことを提案した。
最初は私の側を離れるのを嫌がったが家族に情はあったのか最終的にはわかったと言って納得してくれた。
私の部屋は彼が姿を消した事でいつもと違って見えた。いつもここには彼の姿があったから陽光君の姿が見えないだけで全く違う風景に見える。
でも少しだけほっとしていた。この間だけは陽光君からの視線から逃れられる。いくら仲のいい相手でもずっと視線を向けられると疲れるのだ。
そしてあの赤い瞳に見つめられると魅入られそうになる。
彼は過保護だ。私の事をすぐに狙われるお姫様か何かと勘違いしている。だから私が出かけるたびに心配そうに見守っていた。
お盆の日、私の家も家族揃ってお墓参りに行くことになった。と言ってもお墓があるのは近所の墓地なのでたいして遠出する事はない。さっさと家族でお墓参りを済ませた。
その後は好きに過ごしていいと言われたので自転車に乗って近所の本屋へ出かけた。
新作の小説が発売されるのだ。ずっと好きだった作家の新作だったのでずっと楽しみにしていたのだ。
陽光君も読みたいと言っていたものだ。
自転車を停めて本屋に入ろうとした時だ。
「貴方。一体何をしたの?どうやったらそんな霊に憑かれるの?」
見知らぬ女の子が声をかけてくる。紺色の和服を着た楚々な雰囲気の女の子だ。黒髪のロングヘアーが似合う美少女だった。
だけど突然声をかけられた上に意味のわからないことを言われて戸惑ってしまう。
「??」
「ごめんなさい。貴女からあまりにもすごい霊の執着を感じ取ったものだから……実は私霊能者の家系に生まれてお祓いみたいな事をしているの。ねえ貴方は霊を信じる?もしそうだったら話を聞いて欲しいの」
信じるも何も本物の幽霊が私には取り憑いている。だけど彼女が本当に霊が見えるかどうかはわからない。
「……幽霊自体は信じてるよ。でも私には貴女が本当に霊能者かどうかはわからない。貴女が霊能者みたいな存在だったらどんな霊が憑いているのか教えてもらってもいい?」
「わかった。はっきり言うわ。赤い糸が貴女の薬指に巻きついていて、どこかに繋がっているように見える。まるで赤い糸でできた指輪みたい。それだけじゃないわ。その糸は貴女の全身を雁字搦めにする様に巻きついている。そして多分貴女に憑いている霊は男の子かしら?わかるのは貴女に強い想いを持って取り憑いている事くらい」
強い想いを持って私に取り憑いている男の子の存在を当てられたら信じるしかなかった。
身体中に赤い糸が巻きついたようになっているのは知らなかった。けれどロマンチストな陽光君だったらそういったことをしてもおかしくはない。
私は陽光君に魂まで囚われた時のことを事細かに話した。霊能者である彼女だったらこの話を信じてくれるだろうと思ったのだ。
最悪、信じてもらえなくてもそれでいい。現実離れしたこの話は私の作り話として処理されるだけなのだ。
彼女にこの話をしたのは陽光君をこの世から解き放つべきかどうかの意見を聞きたかったからなのだろう。
「そうだったの。信じるわ。それにしてもすごい話ね。話長くなりそうだし私の家でお話ししない」
「いいの? でも大丈夫?」
「大丈夫よ。この時期になると家族みんな除霊とかで呼ばれて家にいるのまだ半人前の私だけなの」
「じゃあお邪魔させてもらいます」
そして私は彼女の家に案内された。
1年半前に私が陽光君の除霊を頼んだ霊能者の家だった。彼女はおそらく彼の家族か親戚か何かだろう。
この家は悪い意味で印象的な場所だった。
ここに私が除霊を頼んだのが陽光君と拗れに拗れた原因だからだ。
それにここの一人前の霊能者が陽光君はどうにもできないと匙を投げたのだ。半人前を自称する彼女にどうに何できるとは思わなかったのだ。
霊能者の家だからかわからないけれどお線香のような香りが家に漂っている。
私は彼女の部屋へ案内される。
「ここは私の実家なの。普段は実家から離れた大学に通っているからここに帰ってくるのはお盆と正月くらいね」
「そうなの。やっぱり私帰らせてもらってもいい?」
私は帰り支度をする。
せっかく家に招待してもらったがあまりいい思い出がないので帰りたい。
何よりも陽光君は勘が鋭い。私に隠し事や後ろめたい事がある時は「何か隠してるの? ほのか」と必ずと言っていいほど聞いてくるのだ。
そして私は彼の追求を1度たりとも逃れた事がない。
下手な事をして陽光君の怒りは買いたくない。彼は怒ると非常に怖いのだ。私にとっては鬼すら可愛く見えてくるのだ。
「待って。話を聞いて。信濃さんはこのまま赤城君が苦しんだままでもいいの?」
思わず振り返ってしまう。陽光君が苦しんでいるとはいったいどういう事なのだろうか。
「待って⁉︎ どういうことなの? 陽光君が苦しんでいるってどういうこと?!お願い教えて!!」
「辛い事実だけど聞いてほしいの。貴女が赤城君をここに縛りつけているの!」
「私が…?」
「そう。厳しい事を言うけれど信濃さん、本当は赤城君に成仏して欲しくないって思っているのじゃないかしら」
「……思ってないって言ったら嘘になる。だけどどうすればいいか私にはわからない。それに陽光君が望んでいるのは死んでからも私といる事。本当に成仏する事が陽光君の幸せかわからない」
「聞いてくれる?これはあくまでも私の考えよ。私が見てきた霊は大体、ううん全てが何かしらの未練を持っていたの。それで霊になった人間はその未練が強く出るの。そしてその一面が強調されて他の一面はあまり表に出なくなるの。例えば何かの復讐心に囚われた人間が霊になった場合はその復讐を果たすと言う面が強く出る。そしてそれ以外の事はあまり気にかけなくなるの。その目的を達成するためなら手段を選ばなくなるわ」
「何が言いたいの?」
「だから赤城君の場合は貴女の恋心が未練になっている。だから彼はそれが未練になったから生前よりも貴女に強い想いを持っている。本来の恋心が歪んでしまったの。生前の彼はそこまで貴女に狂っていた?」
「そんな事はなかった。普通の優しい男の子だった。……聞きたい事があるの?」
「何かしら」
「霊になると目的を達成するために人間としての優しさや常識を失って赤の他人を平気で傷つけるようにもなる?」
「……そういった霊もいると思う。ううん、むしろ多いくらいよ」
「そう……」
彼女が説明したケースは陽光君にも大いに当て嵌まった。
彼は今でこそ冷酷で他人を傷つけて、時には命を奪うのに躊躇しない悪魔のような存在だ。
だけど彼の生前は普通の優しい男の子だった。
あずさのかっこいいという言葉に嬉しいと照れ臭そうに反応したり、知らない人に道を聞かれたら丁寧に答える普通の男の子だった。
少なくとも普通の人間としての道徳はあった。亡くなる前とその後だと性格の振れ幅が違いすぎる。
「信濃さんはこのままでいいの?赤城君が現世に留まっているって事は執着が断ち切れていないの。このままだと赤城君はどんどん未練に支配されておかしくなるわ!貴女への過度な執着だって未練に支配された結果だと思う。祓ってあげるのが1番彼にとって幸せよ!」
「……」
自分可愛さに負けて1度だけ陽光君の除霊を頼んだ時のことを思い出す。
依頼した男性の霊能者には陽光君が強すぎて祓えませんと申し訳なさそうに断られた。そして除霊をしようとした事がバレた時の陽光君は鬼よりも怖かった。あれだけ怒った彼を見たのはあの事件の時だけだ。
「信濃さん、貴女のわがままで彼を現世に縛り付けるつもりなの?」
「うっ。でも私は彼に居なくなってほしく無い。それに陽光くんが成仏を望んでいるとは思えない」
霊となった彼は生前よりもよく笑うようになった。そして感情豊かになった。
成仏を望んでいるようにはとても思えなかったのだ。
「貴女は彼に自分を好きなままこの世に留まってろっていうの?!それこそ酷い話じゃない!それに赤城君、おそらく人間に危害を加えているわね。はっきり言って怨霊の類よ。このままだと人を殺しかねないわ。信濃さん、自分のわがままで貴女人を殺すつもりなの?」
「……」
厳しい口調で彼女は私に問いかける。
彼女の言葉に黙り込んでしまう。最近は陽光君は優しいからその事をすっかり忘れていた。
彼への自分の邪魔になると思えば眉を動かさずに他人を傷つけて命を奪う。最初の頃は容赦無く周りを祟り、ある時は廃人にするほど精神的に追い込んだ。
実際に人を殺してもいるのだ。
「それでも私は……」
「ほのか、こんなところで何をしているの?」
突然聞こえる男の子の声。
そして途端に果物が熟れたような甘く重い香りが漂い始める。それと同時に部屋の空気がどこか禍々しいものに変わった。
私と彼女が振り向くとすぐ後ろには陽光君がいた。
陽光君はいつもの半袖開襟シャツと黒のスラックス姿ではなく、真っ白い着物を纏っていた。襟が左前になっている。おそらく彼が着ているのは死装束だ。
今の彼は美しい容姿と非日常的な格好と相まって人間とは思えなかった。妖しい美しさで人間を誑かす妖といってもおかしくはないだろう。
どうしてここにいるんだろう。彼は実家で家族と過ごしていたはずだ。
「陽光君。どうしてここに?!」
「質問をしているのは僕だよ。でもその質問に答えてあげる。嫌な予感がしたから君を探しに気配を追ったんだ。そしてここに来たんだ。わかった? 僕も答えたからほのかもも答えてね。もう1度訊くよ。こんなところで何をしているの?」
陽光君はあくまでも静かに問いかけてくる。彼はどんなに怒っても声を荒らげる事はない。だけど声には明らかな怒りの感情が含まれている。
「貴方が……すごい執着。間違いなく悪霊の部類に入るわね。悪いけどこのままだと人を殺しかねないから祓わせてもらうわ」
彼女は懐からお札みたいなのを取り出して陽光君に向かって投げる。しかし彼女が投げたお札は陽光君に触れた途端にチリになって消えた。
彼女の顔色が蝋燭のように血の気のない真っ青に変わる。
陽光君は不快そうな眉を顰める。
「こんなおもちゃ痛くも痒くもないよ。初対面で悪霊ってひどいなあ」
「嘘…お札が効かないなんて。だってこのお札は……」
陽光君は彼女を睨みつける。美形の怒った顔はすごく怖い。それに元々彼は目力のある人だからそういった表情が尚更怖く見える。
「君の持っていたお札がどれだけすごいものかはわからないけど僕には効果がないみたいだね。喧嘩を売る相手はちゃんと考えないと駄目だよ。それよりもほのか、僕は君とお話がしたいな」
陽光君は私の方へ振り向く。
間違いなく怒っている。顔はいつもと変わらず無表情だけど目や声色から怒りが伝わってくる。
「ねえほのか、正直に言ってね。彼女と何を話していたの? 嘘ついたら承知しないからね」
「……陽光君の話していた。陽光君がこの世に留まっているのはよくないって。成仏した方が幸せなんじゃないかって……それに陽光君が私にここまで執着するのは霊になった副作用みたいなもので生きていたらこうはならなかった……だからこのままだともっと歪んじゃうから成仏したほうがいいって話をしてたの……」
「なにそれ……僕の在り方を君たちが勝手に決めるなよ!僕の在り方は僕が決める‼︎ ふざけるな!」
陽光君が叫ぶと壁にかけられた時計は時針、分針、秒針の全てが出鱈目に動き始めた。部屋に置いてあるは全てカタカタと揺れ始めたり浮かび上がったりする。
空気もピリピリとした重たく鋭いものに変わる。陽光君は今までにみたことがないほどの怒気を放っている。
陽光君の放った邪気にあてられて霊能者の女の子は泡を噴いて倒れてしまった。
「偉そうな事を言ってたのに泡吹いちゃったんだ。こんな弱いのに僕を除霊するとか言ってたの。本当に愚かで笑っちゃう」
「まさか死んだの?」
「さあ? 知ったこっちゃ無いよ。今の僕には彼女はどうでもいいんだ」
彼は彼女に目もくれずに私の元へとゆっくりと歩みよってくる。
ゆっくりとした優雅な足取りは彼の整いすぎた容姿と相まって美しい。
「ねえほのか、どうすれば僕の気持ちは君に伝わるの? 行動で愛を示しても怖がる。ううん、それならまだいいんだ。だけど許せないことがあるんだ。幾度となく言葉で伝えたよね。愛してる、君しかいない、世界で1番大好きだって。それなのに君は僕の言葉じゃなくて出会ってすぐのどこの誰かもわからない人間の言葉の方を信じるんだね。っははははは。ほんとうに酷いね」
陽光君は高笑いをする。だけど心底苦しそうに笑っている。こんな苦しそうに笑う彼を初めて見た。
「死後の未来を奪ったくらいで安心していた僕が愚かだった。変な奴らの言葉に惑わされないように耳を塞いでしまおうか。それとも君が誰も見れなくなるように目を潰してしまえばいいのかな?……だけどほのかが喋れなくなってしまうのも、ほのかの綺麗な目を潰すのも惜しいなあ」
私の耳に触れて、次に瞼に触れる。彼の白くて冷たい手に体温を奪われていく。そして彼の声は私の頭の中で染み込むように響いている。
言葉自体はゆっくりと落ち着いている様に紡いでいるけど一言一言がいつも以上に感情が込められている。
体の自由は完全に陽光君に奪われていて指一本動かせないどころか瞬きすらできない。ずっと突っ立って陽光君を見つめているしかない。
不思議な魔力を秘めた真っ赤な瞳から目を逸らしたいのに目を逸せない。
「僕と同じ幽霊になる?そして一緒にいよう。……ううん君を幽霊にするのはいつだってできる。……君の夢の中でずーっと2人きりで過ごそう。僕と君だけの世界。それだったら君は僕以外と関わる事もないからどこの馬の骨ともわからない人間も言葉にだって惑わされる事はないね。僕の気がすんだら意識を戻してあげる」
「……」
「ふふ。鳥肌が立ってるね。そんなに怖い?顔にでているよ。だけどここまで僕を悲しませて怒らせたのは君だよ。今から金縛り解いてあげる。思いつく限りの言葉で言い訳してみてよ。言い訳が思いつかないなら精一杯僕に媚びてみたら?君の態度次第では許してあげる。それができないならどうしようかな?」
彼の言葉と同時に金縛りがとける。
「ごめんなさい。今まで陽光君が私に執着してると思ってた。だけど本当は私が貴方をここに縛り付けているんじゃないかって……貴方がこの世に留まり続けている方が辛いんじゃないかって……成仏した方が幸せになれるんじゃないかって思ったの。」
「あはははは。はっははははは! もしかしてあずさちゃんと見た映画に影響された? 僕は成仏したいと思ったことなんて一度たりとも無いよ」
私は彼の哄笑を黙って眺めているだけだった。
「言いたいことはそれだけ? 聞いていれば随分と自分勝手だね。勝手に人の幸せを決めつけないでよ。君が僕を縛りつけている? 自惚れちゃってかーわいい。どう見たって僕が君を縛り付けているのにそう思っちゃうんだ。成仏したほうが幸せ?ふざけるな。何が何でも君が僕から離れるというのなら代わりにあずさちゃんを貰おうかな。僕も独りだと寂しいからね」
「あずさ!?」
「顔が変わったね。そう君の大事なあずさちゃん。彼女、成長したらほのかに似るだろうし、僕のことすごく気に入ってくれてるみたいだしね」
「お願い!!それだけは許して!お願い!!あずさだけは。あずさだけは」
「必死で僕にお願いするほのかは可愛いね。そんなにあずさちゃんが大事? そうだとますます貰いたくなるなあ。想像してみて。あずさちゃんの心臓がゆっくりと動きを止めるところを。呼吸ができなくて胸の痛みで苦悶に満ちたあずさちゃんの顔はきっととても素敵だと思うよ」
陽光君は舌舐めずりをする。その行動は恐ろしいほどの色気を放ってまるで妖と対峙しているみたいだった。目が本気だ。このままだと彼は本気であずさを自分の所に連れて行ってしまう。あずさを失う恐怖で涙が出てくる。
私がとれる行動はこれしかなかった。
床に手をついて頭を下げる。こうするしか私にできることが思いつかなかった。陽光君に土下座をする。
「お願い、なんでもするから許して」
「プライドってものがないんだね。土下座なんてしちゃうの。僕が味わった苦しさを君も味わえばいい。君への想いで身が燃える僕の苦しみを君も味わえばいいんだ。それよりもこの女だ。僕のいない所でほのかを唆すなんて許せない」
陽光君が彼女を睨みつけると、苦しそうに彼女が呻き出す。
顔色も真っ青でみているだけで辛そうだ。
「ごめんなさい。私ができる範囲で、耐えられる範囲で何でもするから、あずさの命を助けて。あと彼女も助けてあげて。お願いします」
「……今回はほのかの土下座姿がすっごく可愛かったからそれで許してあげるね。僕って本当ほのかに甘いな」
陽光君がそう言うと彼女の悲鳴は止んだ。気絶しているのか眠っているのかはわからないけれど彼女は目を閉じて倒れたままだ。
「ありがとうございます」
「そんなかしこまった言葉遣いしないでいいよ。ねえ君はどうしていつもこうなの?」
「いつも??何を指しているの?」
「本当自覚ないんだね。君はいつだって誰かの言葉に惑わされる。今回だって大方あの子が君に何か吹き込んだんでしょう」
陽光君は倒れている彼女に視線をやる。その視線は氷のように冷たいけれど、怒りで燃え上がっているようにも見える。
彼の言葉に黙り込んでしまう。確かに私と陽光君の歪な関係を危険だと彼女は指摘した。彼女の言葉は間違っていない。
実際に私もだんだんおかしくなっていった。陽光君が他人を平気で害する様子を昔ほど気にしなくなった。
最低な私は陽光君が傷つけた他人よりも、陽光くんといる居心地の良さを選んでいた。
陽光君は本来の陽光君としての人格を失って私を求める怪物に変化し続けているz
彼女はこのままだとお互いに幸せになれないと語った。そして私と陽光君の間にあるのは愛じゃなくて依存だと指摘した。
「沈黙は肯定と受け取るよ。ねえ、お話しようか。ちゃんと君の言葉でどう思っているかを聞きたい。そして僕の想いを伝えたいんだ。君には何千回何万回言わないとわかってもらえないからね。そしたら彼女邪魔だね」
陽光君が指を鳴らすとあの子は操り人形のような不自然な動きをして部屋から出て行く。あの子が部屋を出た途端にガチャリと音が鳴ってドアの鍵、窓の鍵全てが閉まった。
「これで2人きりだね。これで誰も入って来られない」
「陽光君……」
「ほのか、僕は君に好かれているんじゃないかって少し浮かれていたんだ。去年の誕生日は僕が頼んだら僕をモデルにして絵を描いてくれた。家族旅行のお土産では僕が字を書くのが好きって知ってるからガラスペンとインクをくれたね。何回かデートみたいな事もしたよね。夏は花火大会に行って花火を見て、博物館に遊びに行って、冬は雪祭りで氷像を眺めたりしたね。今度は新しくオープンする水族館に行こうって約束したよね。はっきり言うと僕は生きていた時よりも今の方が楽しい。ほのかは違ったの?僕といるのは本当は嫌だった?」
陽光君は寂しげに喋る。表情だって少し切なそうだ。赤い瞳が僅かに揺らいでいる。普段から冷静沈着で余裕のある態度を崩さない彼らしくなかった。
陽光君と過ごす日々は最初は確かに怖くて仕方がなかった。悪魔のように笑いながら私の大切なものを1つ1つ奪い、時にはあずさの命を盾に私を縛ろうとした。実際に魂を半分奪っていった。
だけど一緒に過ごすに連れて陽光君への恐怖はだんだんと薄れていった。
少なくとも彼に絵を書いたり、旅先でお土産を買ってくるくらいには情があった。
それどころか好きなものが合うおかげか、一緒にお出かけするのは楽しいとすら思えた。
2人で勉強するのも好きだった。勉強を教えてくれる時の陽光君の落ち着いた喋りとノートに書かれる綺麗な字が好きだった。
彼がいないと寂しいなと思うくらいには情が湧いていた。それに彼に惹かれつつあったのも事実だ。
だけど彼は亡霊だ。ここにいていい人間ではきっとないのだと思う。彼女の言葉を信じるなら私が心の中で彼を求めたから、一緒にいたいと願ったから現世に縛り付けてしまった。そして苦しめてしまっているのだ。
「楽しかった。だって陽光君ほど話しの合う人はいなかった。それに貴方は些細なことで喜んでくれてた。私の下手くそな絵を嬉しそうに受け取ってくれたときは本当に嬉しかった一緒に博物館を歩いた時はとても楽しかったわ。だけどこんなのおかしいじゃない!私の想いで貴方を縛り付けてる。貴方だったら私なんかに執着しなくても幸せになれたはず。生まれ変わった方が絶対幸せなはずなのに」
「生まれ変わりか。ごめんね、僕そういうのは一切信じてないんだ。もし来世があったとして、輪廻の輪に乗って生まれ変わってしまえばそれはもう僕じゃない。そして君が生まれ変わっても同じだ。君は信濃ほのかではなくなる。僕は今世の信濃ほのかを愛してるんだ。だから来世なんてどうでもいいんだ。だって来世は僕たちは別人だもの。さっきも言ったけどそういうの一切信じていないから。君が何を言っても僕は君からは離れてあげない。だって愛しい人とずっと一緒にいられる今が僕にとっては幸せなんだ。僕は幽霊になれてよかったよ。君と一緒なら地獄だって天国だよ」
陽光君はうっとりしたように私に語りかける。生前の彼からは考えられないほどの情熱的な言葉だ。
「陽光君それは愛じゃなくて執着だよ。霊になってからの貴方は生前とは別人よ!生きていた時の貴方はこんな酷い事を笑ってできる人じゃなかった!だからやっぱり霊になってから変わっちゃったんだよ!」
やってしまった。きっとまた陽光君の怒りを買ってしまった。気持ちのままに思ったことをそのまま言ってしまうのは私の悪い癖だ。だけど言わずにはいられなかったのだ。
恐る恐る陽光君の様子を確認する。陽光君の表情は変わらない。怒りで冷たい氷のような表情をしていると思ったがそういった表情ではない。怒っていないのかな。
「愛してるから執着するんだ。死んでからは別人みたい。当たり前でしょ。人間なんて変わるものだよ。僕は生前の鈍感で臆病で行動できない自分が大嫌いだったんだ。でも今は違う。君を守る力がある。それにずっと一緒にいる事ができる手段だってある。僕は変われて良かったと思っている。それに生前の僕だって君が思っているような優しい人間じゃないよ。君以外の人間には興味が無かったし、女の子たちに囲まれた時はほのかに近づけなかったから正直邪魔だって思っていたよ。それどころかいきなり囲まれるようになって戸惑っていたくらいだよ。生前から僕は君さえいれば他に何も要らないって思っていたんだ」
「嘘……そんなに私がいいの?だって私なんか臆病でわがままでなんの取り柄もない人間だよ。それでも私のことが好きなの?」
「私なんかって言わないでよ。確かに君は臆病だしすぐ人に流されるし、僕を心配させたりするよ。それでも最初に僕に手を差し伸べてくれたのは君だ。僕は君が君、ただそれだけで君を愛しているんだ。やっぱりこうやって口に出すのは少し恥ずかしいな。だけど言わないと伝わらないから言い続けるよ」
「陽光君、いっつも情熱的なことを言うくせに恥ずかしいって思ってたの?」
「当たり前でしょ。生前だったら絶対に言えなかった。でも何も言えないで後悔するのは嫌だからこれからも言い続けるよ。こんな姿になってまで君と一緒にいたいと思ったんだ。君といるためなら僕は悪魔にでもなって見せるよ」
「……」
「お願い、僕を受け入れて。君も一緒に奈落の底に落ちて。断ったって逃しはしないよ。でも僕は君の口から僕を受け入れると言って欲しい。ねえ、お願い」
陽光君は私をきつく抱きしめる。1年半前に魂を奪っておいて雁字搦めにしておきながら受け入れて欲しいとか矛盾もいいところだ。
最初から拒否権なんてない。だけどきっと彼は私からの言葉が欲しいのだ。私から一緒にいると言う言葉が欲しいのだ。もし言葉に出してしまえば言質として取られて事あるごとに彼に引き合いに出されるだろう。
だけど私に懇願する声は切なそうで、泣きそうな声だった。いつもどこか余裕そうな彼らしくない姿だ。そんな彼だからこう懇願されるとつい首を縦に振ってしまいそうになる。
陽光君がいなくなるのは寂しい。確かに怒ると怖いし他人を平気で傷つける残酷さも持ち合わせているし、酷いこともいっぱいされた。
だけどそれ以上に一緒にいるのは心地よかった。話も合うし、陽光君のことは嫌いじゃない。それに一緒に過ごしていくうちに段々と彼に惹かれていった。
彼とだったらずっと一緒にいてもいいかなって思えるくらいには好意は持っていた。だけどこれは恋愛感情ではないと思う。だって彼とは恋人がするような事がしたいとは全く思わない。だからきっと友人として、一緒に過ごす人間として惹かれていたのだ。そして彼はいつの間にか私の日常を構成する必要不可欠なピースになっていたのだ。
「陽光君はずるい人だね。だって何を言ったって離してくれないくせに。私から自分を受け入れさせて逃げ道を奪っていくんだもの。陽光君の事受け入れるよ。一緒に奈落に落ちてあげる。陽光君なら奈落の底でもなんとかしてくれそうだもの」
「僕がずるいのは今に始まったことじゃないよ。安心して僕がいる限りは君には傷一つつけさせやしないよ。嬉しい。君から受け入れてくれて本当に嬉しい」
陽光君が優しく微笑んだ。どんな時でも絶対に涙を流さなかった彼なのに一筋の涙が伝っていた。卑怯な人だ。さっきまで笑って恐ろしい目に遭わせていたのに今はとても嬉しそうで優しい顔をしている。何があってもこの人は絶対に私を離してくれないのだ。
本当に私の事が好きなんだなとわかってしまた。
私は陽光君を抱きしめた。貴方のことを受け入れたという私なりのアピールだった。陽光君の身体は相変わらず氷のように冷たい。だけど今はその冷たさが心地よかった。
陽光君も私のことをギュッと抱きしめ返す。その時に彼の着物の袖から彼の腕に火傷みたいな傷があるのが見えた。
「陽光君、腕が火傷みたく赤くなっている」
「あっ!」
「見せて!」
陽光君の着物の袖を捲ると彼の左腕は火傷したかのように赤くなっていた。
「これどうしたの?話して!私ばっかりに話させて自分は黙ってるのどうかと思う!」
「わかったよ。……この家、僕みたいな霊を避けるための結界みたいなの張られてて、それを無理やり破った時に怪我したんだ……大丈夫だよ。1日もしたら治ると思う」
「私の心配するくせに自分は結構無茶するよね。今日着物姿だったのだって普段の半袖シャツにスラックス姿だとこの怪我ばれるからでしょ。まさか着物姿になれるとは思わなかったけど」
「うん。ほのかの言う通りだよ。あんまりかっこ悪いというか余裕がない姿は見られたくなかったな」
「そういう問題じゃないよ。本当びっくりしたし心配した」
「嬉しい。僕のことそれくらいは好きでいてくれるんだね」
「そう思うくらいには陽光君に私も絆されちゃったの。そりゃあ怖い時もいっぱいあるけど……」
そして私は陽光君の頭をポンって叩く。
「それは君が僕を怒らせるような事ばかりするからでしょ。確認だけど本当に僕の事受け入れてくれるんだね」
「うん。受け入れるわ。それにそもそも私たちとっくに一蓮托生じゃない」
私はついに自分から陽光君と共に生きていく覚悟を決めた。自分勝手でも何でもいい。それでも2人がいいのだ
***
高校を卒業した後の私の進路は就職だった。小さい会社に就職が決まって、今日私は生まれ育った街を去っていく。
不思議と不安はない。陽光君が一緒にいるからだろうか。彼となら大体の事はどうにかなると思ってしまう。そんな不思議な安心感を陽光君はくれた。
駅のホームまではお母さんとお父さん、そしてあずさが見送りに来てくれた。私が新しく住む町はローカル電車で2時間ほどだ。特急を使えばもっと速く着く。会おうと思えばいつだって会える距離だ。それなのに家族全員で見送りに来てくれた事には感謝しかない。
「お姉ちゃん、遠い街でお仕事頑張ってね。あずさ夏休みや冬休みに遊びにいくからね」
「ありがとう、あずさ。お姉ちゃん頑張るね。電車きたからもういくね」
「わかった。バイバイ」
私は電車に乗り込む。車両はガラガラを通り越して誰もいなかった。空いている席に適当に座る。隣の席には陽光君が座った。
窓を見るとまだ家族が手を振っていた。
「まさか君が就職して家を出るとは思わなかったよ。頭がいいから大学に進学って道もあったのに」
「そうだね。勉強したいわけでもなかったし、だったら仕事して自立したいって思ったの」
「そうか。僕は君の選択を尊重するよ。でも嬉しいな。僕と君が一緒に暮らすなんて実質同棲だよね」
「同棲ってなんか恋人みたい言い方だね」
「死んでからも離れられないんだから恋人よりもずっと深い関係でしょう」
「そうだね。でも離れられないじゃなくて離さないの間違いじゃない」
「うん。絶対に離してあげない」
普段だったらこうやって公共の場で陽光君とはお喋りはしない。陽光君の姿は誰にも見えないので私がおかしい人だと思われるからだ。だけど今電車にいるのは2人だけだ。お喋りしたって許されるだろう。
車窓から変わりゆく景色を見つめながら陽光君と会話をする。見慣れた町の景色が少しずつ変わっていくのは新鮮な気分だった。普段電車に乗らないのでなおそう思うのだろう。
景色が変わっていくように私の未来も変化していくのだろう。
「そうだったんだね。僕はどんな道を選んでもほのかを応援するよ。例え周り全てが敵になっても僕だけはずーっと君の味方でいてあげる」
「大袈裟な物言いだね。でも陽光君がそう言ってくれるなら心強いかな」
「全部本気だよ。愛してるよ。2人で幸せになろうね。君に降りかかる火の粉は全部僕が払ってあげる。君の事は僕が守ってあげるね」
「うん、ありがとう」
それから人が乗ってくるまで私と陽光君は取り留めない話をした。最近読んだ小説や興味のあるテレビ番組、本当にどうでもいいことだ。
次の駅ですぐに人が乗ってきたからお喋りは短い時間だけだった。陽光君は残念と笑って、私に寄りかかる。
私と陽光君の在り方は世間では間違っているのだろう。だけど私たちはこれでいいのだ。だって陽光君は私を求めているし、私だって陽光君を求めている。
私たちのあり方が歪んだ形なのは知っている。
この美しい人は世界が滅んだって私を離してくれない。最初魂を奪われたときにわかっていた筈だった。だけど本当はわかっていなかったのだ。彼の荒れ狂う想いの正体は私は勝手に幽霊になっておかしくなったが故の結果だと思っていた。でも違った。彼はおかしくなるほど荒れ狂う想いを持っていたから幽霊になってしまったのだ。
だけどこれでいいのだ。だって私も陽光君も幸せなのだから。陽光君とだったら奈落の底でも大丈夫。
その結果魂を半分彼に奪われてしまった。それからどうなるのだろうと戦々恐々としていた。
いいように弄ばれ、今までの恨みを晴らされるのかと不安にもなった。
意外にも、それからは特に怖い事は無かった。
もちろん陽光君は毎日そばにいる。だから変なことは言えないし、プライベートの時間は無いに等しい。
だけど彼はとても優しかった。
私の事を好きと言っていたが、実際に彼の私の対する接し方は恋人に近いものだった。
友達というには近すぎる距離と、熱のこもった視線に、呼びかける時の声は甘い。
話が合うので一緒にお喋りしていたりするのが楽しい。お互いの空気感が合うおかげか彼と一緒にいるのは居心地がいいとすら思い始めていたのだ。
「これで合っている?」
今日は部屋で陽光君と勉強会だった。私は解いた問題が合っているかどうか陽光君に確認してもらう。
陽光君は私のノートを真剣な表情で見る。
「そう。正解だよ。前は解けなかったのに今日はちゃんと解けたね。えらいよ、ほのか」
魂を半分奪われてから陽光君は私のことを信濃さんではなく、ほのかと呼ぶようになった。まさかの名前呼びに最初はくすぐったい気分だったけど今ではすっかり慣れてしまった。
彼は僅かに微笑んで赤ペンで丁寧に丸をつける。
霊となった彼は物が持てないから念力みたいな力で赤いペンはふわふわと浮いている。ちょっと不思議な光景だけど私は既に見慣れてしまった。
幽霊で肉体を持たないが故、物に触れない陽光君はポルターガイストの応用みたいな感じで物を触らずに動かす。彼が唯一触れられるのは魂を奪った私だけだ。
実は陽光君は勉強はかなりできる方だった。本人曰く生前はクラスで常に3番以内だったらしいし、学年でも常に上位10位以内の成績だったそうだ。
私の学校は成績が張り出されず個人にしか順位が伝えられない方式をとっている。
だから陽光君の具体的な成績は知らなかった。普段の様子から勉強はできるんだろうなとは思っていた。
この情報は私が聞いたら本人が教えてくれた事だ。
「僕の成績って中途半端であんまり自慢にならないから言わないようにしていたんだ。学年1位とかだったら格好いいだろうけどね」
陽光君は恥ずかしそうにポツリと言った。私からしたら十分に成績優秀ですごいと思う。
ちなみに総合的な私の成績は中の中で平均そのものだ。文系科目はそこそこ上位の成績なのだが、数学と化学が足を引っ張り最終的に平均に落ち着いていた。
数学と化学を含めた理科系科目が苦手な私のために陽光君はたまにこうやって勉強を見てくれる。
今日も2週間後の期末考査に向けて勉強を見てもらっていた。こうして彼に勉強を見てもらう日が来るなんて想像がつかなかった。
そもそも幽霊で勉強をする必要のない彼の方が勉強できるっていう事に私は恥を覚えなければならないのだろう。だけど陽光君が優秀すぎるのだから仕方がない。
意外と彼は家庭教師の才能があると思う。彼はちょっとした事で褒めてモチベーションを上げてくれるし、わからないところを馬鹿にする事なく根気よく説明してくれる。
教えるのも上手で彼の説明はするすると頭に入ってくる。
私のノートに書かれた陽光君の読みやすく整った字がすごく好きだった。
陽光君は私が間違えたりわからない問題があったらどうして間違えたのかとか、問題を解く際の注意するポイントを丁寧に教えてノートに書いてくれるのだ。
綺麗な字とたまに描かれるどこかで見たことのあるキャラクターをデフォルメ化した絵がとても好きだった。
何よりも勉強を教えてくれる時の彼の声は落ち着いていてとても優しい。またその時の真剣な顔がとても格好よく見えたのだ。
「良かった。ここ苦手だから自信なかったんだ」
「大丈夫だよ。合っているよ。他にわからないところとかある?」
「うーん。一通り問題解いてからでいい?自分がどこまでできるか試したいから」
「わかったよ。じゃあ僕は適当に何かしているから終わったら呼んで」
私は再びに机に向かって問題を解き始める。
しばらくすると問題が解き終わったので陽光君を呼ぶ。
「終わったんだね。お疲れ様。せっかくだから休憩にしない?紅茶とお菓子持って来たよ」
「ありがとう」
「どういたしまして」
机の片隅には湯気がたった温かい紅茶と味を調節するためのコーヒー用のシュガーとおやつであるチョコレートが置いてあった。
紅茶に砂糖を入れて口をつける。紅茶の濃さと熱さはちょうど良くて私好みだ。これも陽光君の気遣いなんだと思う。
彼がいれた紅茶は最初は少し濃かったり薄かったりした。それに紅茶の熱さだって火傷しそうなほどに熱かったり逆にぬるかったりしていた。
しかしいつの間にか私好みの濃さの紅茶がいれられるようになっていた。逆に言えば好みが把握できるほど私たちは一緒の時間を過ごしたという事だ。
そして休憩が終わると再び勉強会が始まった。
こうして穏やかで優しい振る舞いを見ると、笑って人を殺し、傷つけ、時には恐怖で意のままに人を従わせようとする苛烈で残酷な人物とは思えなかった。
そもそも生前の振る舞いを考えるとこれが本来の彼の姿なのだろう。
そして私は陽光君と楽しい時間を過ごしていた。
夏祭りでは打ち上げ花火を一緒に見て、それからこっそり川辺で2人で線香花火をした。
またある時は電車に乗って大きい町の博物館の展示を見に行った。そして冬は雪祭りにも参加した。
見た目は独りぼっちで遊びに出かける痛々しい女だけど隣に陽光君がいるだけで楽しかったのだ。
陽光君が楽しそうにしているのを見るのが好きだった。
そんな時間を過ごしているうちに彼とだったら一緒にいてもいい。ううん、この言い方はおこがましいので言い方を変えよう。
陽光君と一緒にいたいと思ってしまうようになった。それだけ彼と過ごす時間は幸せだったのだ。
***
そして私は高校3年生になった7月の事だった。
妹のあずさに誘われて映画を観に行くことになった。
あずさがチョイスした映画は意外にもホラーもので少し驚いた。
彼女の選んだものはキッズ向けのホラーだけどホラー全般は苦手だったはずだ。家にいる時も家族でホラー映画のビデオを見るとあずさは自分の部屋に籠もってしまう。
「あずさどうしたの?ホラーとかダメだったじゃない」
「そうなんだけどさ。クラスのみんな、この映画の話ばっかであずさついてけなくてつまんない。友達はもうみんな見てるしあずさ1人で見るのも怖いんだもん」
「そっか。だからお姉ちゃん誘ったんだね」
「うん」
あずさらしい理由だ。ホラーが怖いくせに話についていけず疎外感を感じたくないから映画を観ようとなったらしい。
そして友達には怖がる姿が恥ずかしいから見られたく無いという理由で私を誘ったそうだ。
映画館でチケットとポップコーンと飲み物を買う。
当然陽光君も着いてきた。だけど陽光君はこの映画に興味がないみたい。
だって別の映画のポスターを眺めている。彼が眺めていたポスターはアクションものの映画でちょっと意外だった。
ミステリーとかノンフィクションとかそういったシリアスなものが好きな印象だったからだ。
「ほのか、僕は外で待ってるからね」
人が大勢いるところで陽光君と会話していると1人で喋っているちょっと危険な人なので目線だけでわかったと伝える。
いつもだったらどんな駄作の映画でも絶対についてきて一緒に見ているが今回に限っては着いてこなかった。
同じ幽霊だから何か思うところがあるのだろうか。陽光君は1度たりとも上映室には入ってこなかった。そして上映が終わった後、陽光君は珍しく黙ったままどこかへ消えてしまった。
「なんか切なかったね。でも幽霊のお姉ちゃんは最後は成仏できてよかったね。やっぱり死んでから幽霊になると辛いんだね。好きな人が新しい恋人を作って幸せなのを見てるだけって辛いよ」
映画の上映が終わってから家に戻るとあずさがポツリと感想を漏らした。
「そうね」
あの映画は子供向けと言う割には大人でも響く映画だったと思う。
アニメ映画で可愛らしい絵とは裏腹に残された人間の想いや未練を残した女性の幽霊に焦点が当てられて大人向けだったと思う。
女性の幽霊は最初は好きな人を待っているだけの無害な霊だったのに、この世に渦巻く人間の悪意や欲望に影響されて変質しまい好きだった男性を連れて行こうとしていた。
そしてその男性は新たな恋人を作っていてなおややこしい状況となるのだ。
それを知った幽霊の妹である小学生の主人公とその友人が幽霊になった姉を成仏させようとするストーリーだ。
その成仏させる過程でアクションあり冒険ありなので小学生には飽きない内容だろう。
最終的には女性は無事に未練や執着から解放されて成仏する。そして晴れやかな感じで終わった。
だけどこの終わりは私にはスッキリしなかったのだ。死んだ人間は何がなんでも成仏しなくてはいけないのかと私は思ってしまった。
一緒に遊びに行って楽しそうにする陽光君を見ると幽霊だってこの世を楽しんでもいいのではないかと思ってしまうのだ。
何よりも私は陽光君に消えて欲しくないと思ってしまった。
確かに陽光君が霊となって私の前に現れた時はとても怖かった。
正直今でも怖い時はある。それに魂を奪われて彼によって呪縛を受けている状態だ。
それでも彼は普段は優しく愛情深い人だ。ただ誰よりも不安になりやすく、失う事を恐れているのだ。
あの映画の結末を見ると彼を私という未練から解き放たなくてはいけないのかと思う。
陽光君にいて欲しいという気持ちと成仏した方が救われるのではという2つの想いがせめぎ合っている。
私は陽光君とどうなりたいんだろう。情けないけど自分でもよくわかっていない。
***
そんな曖昧な想いを抱えた私に転機が訪れる。それはお盆の日だった。
「じゃあ僕は実家にいるね。父さんも母さんも僕の事は見えないけどせめてこの日はそばにいようと思うんだ。気をつけてね、君は悪い人に目をつけられやすいからね」
そして陽光君は煙のように消えてしまった。本当になんでもありだ。
お盆は陽光君と離れる数少ない期間だ。
迎え盆から送り盆にかけての3日間だけ彼は私の前から姿を消す。8月13日から15日までは彼は家族の元に戻っている
これは私が提案した事だった。
彼の家庭関係は良好だったらしく彼のご両親は大層陽光君に愛情を注いでいたそうだ。だから私はお盆くらいは実家で過ごすことを提案した。
最初は私の側を離れるのを嫌がったが家族に情はあったのか最終的にはわかったと言って納得してくれた。
私の部屋は彼が姿を消した事でいつもと違って見えた。いつもここには彼の姿があったから陽光君の姿が見えないだけで全く違う風景に見える。
でも少しだけほっとしていた。この間だけは陽光君からの視線から逃れられる。いくら仲のいい相手でもずっと視線を向けられると疲れるのだ。
そしてあの赤い瞳に見つめられると魅入られそうになる。
彼は過保護だ。私の事をすぐに狙われるお姫様か何かと勘違いしている。だから私が出かけるたびに心配そうに見守っていた。
お盆の日、私の家も家族揃ってお墓参りに行くことになった。と言ってもお墓があるのは近所の墓地なのでたいして遠出する事はない。さっさと家族でお墓参りを済ませた。
その後は好きに過ごしていいと言われたので自転車に乗って近所の本屋へ出かけた。
新作の小説が発売されるのだ。ずっと好きだった作家の新作だったのでずっと楽しみにしていたのだ。
陽光君も読みたいと言っていたものだ。
自転車を停めて本屋に入ろうとした時だ。
「貴方。一体何をしたの?どうやったらそんな霊に憑かれるの?」
見知らぬ女の子が声をかけてくる。紺色の和服を着た楚々な雰囲気の女の子だ。黒髪のロングヘアーが似合う美少女だった。
だけど突然声をかけられた上に意味のわからないことを言われて戸惑ってしまう。
「??」
「ごめんなさい。貴女からあまりにもすごい霊の執着を感じ取ったものだから……実は私霊能者の家系に生まれてお祓いみたいな事をしているの。ねえ貴方は霊を信じる?もしそうだったら話を聞いて欲しいの」
信じるも何も本物の幽霊が私には取り憑いている。だけど彼女が本当に霊が見えるかどうかはわからない。
「……幽霊自体は信じてるよ。でも私には貴女が本当に霊能者かどうかはわからない。貴女が霊能者みたいな存在だったらどんな霊が憑いているのか教えてもらってもいい?」
「わかった。はっきり言うわ。赤い糸が貴女の薬指に巻きついていて、どこかに繋がっているように見える。まるで赤い糸でできた指輪みたい。それだけじゃないわ。その糸は貴女の全身を雁字搦めにする様に巻きついている。そして多分貴女に憑いている霊は男の子かしら?わかるのは貴女に強い想いを持って取り憑いている事くらい」
強い想いを持って私に取り憑いている男の子の存在を当てられたら信じるしかなかった。
身体中に赤い糸が巻きついたようになっているのは知らなかった。けれどロマンチストな陽光君だったらそういったことをしてもおかしくはない。
私は陽光君に魂まで囚われた時のことを事細かに話した。霊能者である彼女だったらこの話を信じてくれるだろうと思ったのだ。
最悪、信じてもらえなくてもそれでいい。現実離れしたこの話は私の作り話として処理されるだけなのだ。
彼女にこの話をしたのは陽光君をこの世から解き放つべきかどうかの意見を聞きたかったからなのだろう。
「そうだったの。信じるわ。それにしてもすごい話ね。話長くなりそうだし私の家でお話ししない」
「いいの? でも大丈夫?」
「大丈夫よ。この時期になると家族みんな除霊とかで呼ばれて家にいるのまだ半人前の私だけなの」
「じゃあお邪魔させてもらいます」
そして私は彼女の家に案内された。
1年半前に私が陽光君の除霊を頼んだ霊能者の家だった。彼女はおそらく彼の家族か親戚か何かだろう。
この家は悪い意味で印象的な場所だった。
ここに私が除霊を頼んだのが陽光君と拗れに拗れた原因だからだ。
それにここの一人前の霊能者が陽光君はどうにもできないと匙を投げたのだ。半人前を自称する彼女にどうに何できるとは思わなかったのだ。
霊能者の家だからかわからないけれどお線香のような香りが家に漂っている。
私は彼女の部屋へ案内される。
「ここは私の実家なの。普段は実家から離れた大学に通っているからここに帰ってくるのはお盆と正月くらいね」
「そうなの。やっぱり私帰らせてもらってもいい?」
私は帰り支度をする。
せっかく家に招待してもらったがあまりいい思い出がないので帰りたい。
何よりも陽光君は勘が鋭い。私に隠し事や後ろめたい事がある時は「何か隠してるの? ほのか」と必ずと言っていいほど聞いてくるのだ。
そして私は彼の追求を1度たりとも逃れた事がない。
下手な事をして陽光君の怒りは買いたくない。彼は怒ると非常に怖いのだ。私にとっては鬼すら可愛く見えてくるのだ。
「待って。話を聞いて。信濃さんはこのまま赤城君が苦しんだままでもいいの?」
思わず振り返ってしまう。陽光君が苦しんでいるとはいったいどういう事なのだろうか。
「待って⁉︎ どういうことなの? 陽光君が苦しんでいるってどういうこと?!お願い教えて!!」
「辛い事実だけど聞いてほしいの。貴女が赤城君をここに縛りつけているの!」
「私が…?」
「そう。厳しい事を言うけれど信濃さん、本当は赤城君に成仏して欲しくないって思っているのじゃないかしら」
「……思ってないって言ったら嘘になる。だけどどうすればいいか私にはわからない。それに陽光君が望んでいるのは死んでからも私といる事。本当に成仏する事が陽光君の幸せかわからない」
「聞いてくれる?これはあくまでも私の考えよ。私が見てきた霊は大体、ううん全てが何かしらの未練を持っていたの。それで霊になった人間はその未練が強く出るの。そしてその一面が強調されて他の一面はあまり表に出なくなるの。例えば何かの復讐心に囚われた人間が霊になった場合はその復讐を果たすと言う面が強く出る。そしてそれ以外の事はあまり気にかけなくなるの。その目的を達成するためなら手段を選ばなくなるわ」
「何が言いたいの?」
「だから赤城君の場合は貴女の恋心が未練になっている。だから彼はそれが未練になったから生前よりも貴女に強い想いを持っている。本来の恋心が歪んでしまったの。生前の彼はそこまで貴女に狂っていた?」
「そんな事はなかった。普通の優しい男の子だった。……聞きたい事があるの?」
「何かしら」
「霊になると目的を達成するために人間としての優しさや常識を失って赤の他人を平気で傷つけるようにもなる?」
「……そういった霊もいると思う。ううん、むしろ多いくらいよ」
「そう……」
彼女が説明したケースは陽光君にも大いに当て嵌まった。
彼は今でこそ冷酷で他人を傷つけて、時には命を奪うのに躊躇しない悪魔のような存在だ。
だけど彼の生前は普通の優しい男の子だった。
あずさのかっこいいという言葉に嬉しいと照れ臭そうに反応したり、知らない人に道を聞かれたら丁寧に答える普通の男の子だった。
少なくとも普通の人間としての道徳はあった。亡くなる前とその後だと性格の振れ幅が違いすぎる。
「信濃さんはこのままでいいの?赤城君が現世に留まっているって事は執着が断ち切れていないの。このままだと赤城君はどんどん未練に支配されておかしくなるわ!貴女への過度な執着だって未練に支配された結果だと思う。祓ってあげるのが1番彼にとって幸せよ!」
「……」
自分可愛さに負けて1度だけ陽光君の除霊を頼んだ時のことを思い出す。
依頼した男性の霊能者には陽光君が強すぎて祓えませんと申し訳なさそうに断られた。そして除霊をしようとした事がバレた時の陽光君は鬼よりも怖かった。あれだけ怒った彼を見たのはあの事件の時だけだ。
「信濃さん、貴女のわがままで彼を現世に縛り付けるつもりなの?」
「うっ。でも私は彼に居なくなってほしく無い。それに陽光くんが成仏を望んでいるとは思えない」
霊となった彼は生前よりもよく笑うようになった。そして感情豊かになった。
成仏を望んでいるようにはとても思えなかったのだ。
「貴女は彼に自分を好きなままこの世に留まってろっていうの?!それこそ酷い話じゃない!それに赤城君、おそらく人間に危害を加えているわね。はっきり言って怨霊の類よ。このままだと人を殺しかねないわ。信濃さん、自分のわがままで貴女人を殺すつもりなの?」
「……」
厳しい口調で彼女は私に問いかける。
彼女の言葉に黙り込んでしまう。最近は陽光君は優しいからその事をすっかり忘れていた。
彼への自分の邪魔になると思えば眉を動かさずに他人を傷つけて命を奪う。最初の頃は容赦無く周りを祟り、ある時は廃人にするほど精神的に追い込んだ。
実際に人を殺してもいるのだ。
「それでも私は……」
「ほのか、こんなところで何をしているの?」
突然聞こえる男の子の声。
そして途端に果物が熟れたような甘く重い香りが漂い始める。それと同時に部屋の空気がどこか禍々しいものに変わった。
私と彼女が振り向くとすぐ後ろには陽光君がいた。
陽光君はいつもの半袖開襟シャツと黒のスラックス姿ではなく、真っ白い着物を纏っていた。襟が左前になっている。おそらく彼が着ているのは死装束だ。
今の彼は美しい容姿と非日常的な格好と相まって人間とは思えなかった。妖しい美しさで人間を誑かす妖といってもおかしくはないだろう。
どうしてここにいるんだろう。彼は実家で家族と過ごしていたはずだ。
「陽光君。どうしてここに?!」
「質問をしているのは僕だよ。でもその質問に答えてあげる。嫌な予感がしたから君を探しに気配を追ったんだ。そしてここに来たんだ。わかった? 僕も答えたからほのかもも答えてね。もう1度訊くよ。こんなところで何をしているの?」
陽光君はあくまでも静かに問いかけてくる。彼はどんなに怒っても声を荒らげる事はない。だけど声には明らかな怒りの感情が含まれている。
「貴方が……すごい執着。間違いなく悪霊の部類に入るわね。悪いけどこのままだと人を殺しかねないから祓わせてもらうわ」
彼女は懐からお札みたいなのを取り出して陽光君に向かって投げる。しかし彼女が投げたお札は陽光君に触れた途端にチリになって消えた。
彼女の顔色が蝋燭のように血の気のない真っ青に変わる。
陽光君は不快そうな眉を顰める。
「こんなおもちゃ痛くも痒くもないよ。初対面で悪霊ってひどいなあ」
「嘘…お札が効かないなんて。だってこのお札は……」
陽光君は彼女を睨みつける。美形の怒った顔はすごく怖い。それに元々彼は目力のある人だからそういった表情が尚更怖く見える。
「君の持っていたお札がどれだけすごいものかはわからないけど僕には効果がないみたいだね。喧嘩を売る相手はちゃんと考えないと駄目だよ。それよりもほのか、僕は君とお話がしたいな」
陽光君は私の方へ振り向く。
間違いなく怒っている。顔はいつもと変わらず無表情だけど目や声色から怒りが伝わってくる。
「ねえほのか、正直に言ってね。彼女と何を話していたの? 嘘ついたら承知しないからね」
「……陽光君の話していた。陽光君がこの世に留まっているのはよくないって。成仏した方が幸せなんじゃないかって……それに陽光君が私にここまで執着するのは霊になった副作用みたいなもので生きていたらこうはならなかった……だからこのままだともっと歪んじゃうから成仏したほうがいいって話をしてたの……」
「なにそれ……僕の在り方を君たちが勝手に決めるなよ!僕の在り方は僕が決める‼︎ ふざけるな!」
陽光君が叫ぶと壁にかけられた時計は時針、分針、秒針の全てが出鱈目に動き始めた。部屋に置いてあるは全てカタカタと揺れ始めたり浮かび上がったりする。
空気もピリピリとした重たく鋭いものに変わる。陽光君は今までにみたことがないほどの怒気を放っている。
陽光君の放った邪気にあてられて霊能者の女の子は泡を噴いて倒れてしまった。
「偉そうな事を言ってたのに泡吹いちゃったんだ。こんな弱いのに僕を除霊するとか言ってたの。本当に愚かで笑っちゃう」
「まさか死んだの?」
「さあ? 知ったこっちゃ無いよ。今の僕には彼女はどうでもいいんだ」
彼は彼女に目もくれずに私の元へとゆっくりと歩みよってくる。
ゆっくりとした優雅な足取りは彼の整いすぎた容姿と相まって美しい。
「ねえほのか、どうすれば僕の気持ちは君に伝わるの? 行動で愛を示しても怖がる。ううん、それならまだいいんだ。だけど許せないことがあるんだ。幾度となく言葉で伝えたよね。愛してる、君しかいない、世界で1番大好きだって。それなのに君は僕の言葉じゃなくて出会ってすぐのどこの誰かもわからない人間の言葉の方を信じるんだね。っははははは。ほんとうに酷いね」
陽光君は高笑いをする。だけど心底苦しそうに笑っている。こんな苦しそうに笑う彼を初めて見た。
「死後の未来を奪ったくらいで安心していた僕が愚かだった。変な奴らの言葉に惑わされないように耳を塞いでしまおうか。それとも君が誰も見れなくなるように目を潰してしまえばいいのかな?……だけどほのかが喋れなくなってしまうのも、ほのかの綺麗な目を潰すのも惜しいなあ」
私の耳に触れて、次に瞼に触れる。彼の白くて冷たい手に体温を奪われていく。そして彼の声は私の頭の中で染み込むように響いている。
言葉自体はゆっくりと落ち着いている様に紡いでいるけど一言一言がいつも以上に感情が込められている。
体の自由は完全に陽光君に奪われていて指一本動かせないどころか瞬きすらできない。ずっと突っ立って陽光君を見つめているしかない。
不思議な魔力を秘めた真っ赤な瞳から目を逸らしたいのに目を逸せない。
「僕と同じ幽霊になる?そして一緒にいよう。……ううん君を幽霊にするのはいつだってできる。……君の夢の中でずーっと2人きりで過ごそう。僕と君だけの世界。それだったら君は僕以外と関わる事もないからどこの馬の骨ともわからない人間も言葉にだって惑わされる事はないね。僕の気がすんだら意識を戻してあげる」
「……」
「ふふ。鳥肌が立ってるね。そんなに怖い?顔にでているよ。だけどここまで僕を悲しませて怒らせたのは君だよ。今から金縛り解いてあげる。思いつく限りの言葉で言い訳してみてよ。言い訳が思いつかないなら精一杯僕に媚びてみたら?君の態度次第では許してあげる。それができないならどうしようかな?」
彼の言葉と同時に金縛りがとける。
「ごめんなさい。今まで陽光君が私に執着してると思ってた。だけど本当は私が貴方をここに縛り付けているんじゃないかって……貴方がこの世に留まり続けている方が辛いんじゃないかって……成仏した方が幸せになれるんじゃないかって思ったの。」
「あはははは。はっははははは! もしかしてあずさちゃんと見た映画に影響された? 僕は成仏したいと思ったことなんて一度たりとも無いよ」
私は彼の哄笑を黙って眺めているだけだった。
「言いたいことはそれだけ? 聞いていれば随分と自分勝手だね。勝手に人の幸せを決めつけないでよ。君が僕を縛りつけている? 自惚れちゃってかーわいい。どう見たって僕が君を縛り付けているのにそう思っちゃうんだ。成仏したほうが幸せ?ふざけるな。何が何でも君が僕から離れるというのなら代わりにあずさちゃんを貰おうかな。僕も独りだと寂しいからね」
「あずさ!?」
「顔が変わったね。そう君の大事なあずさちゃん。彼女、成長したらほのかに似るだろうし、僕のことすごく気に入ってくれてるみたいだしね」
「お願い!!それだけは許して!お願い!!あずさだけは。あずさだけは」
「必死で僕にお願いするほのかは可愛いね。そんなにあずさちゃんが大事? そうだとますます貰いたくなるなあ。想像してみて。あずさちゃんの心臓がゆっくりと動きを止めるところを。呼吸ができなくて胸の痛みで苦悶に満ちたあずさちゃんの顔はきっととても素敵だと思うよ」
陽光君は舌舐めずりをする。その行動は恐ろしいほどの色気を放ってまるで妖と対峙しているみたいだった。目が本気だ。このままだと彼は本気であずさを自分の所に連れて行ってしまう。あずさを失う恐怖で涙が出てくる。
私がとれる行動はこれしかなかった。
床に手をついて頭を下げる。こうするしか私にできることが思いつかなかった。陽光君に土下座をする。
「お願い、なんでもするから許して」
「プライドってものがないんだね。土下座なんてしちゃうの。僕が味わった苦しさを君も味わえばいい。君への想いで身が燃える僕の苦しみを君も味わえばいいんだ。それよりもこの女だ。僕のいない所でほのかを唆すなんて許せない」
陽光君が彼女を睨みつけると、苦しそうに彼女が呻き出す。
顔色も真っ青でみているだけで辛そうだ。
「ごめんなさい。私ができる範囲で、耐えられる範囲で何でもするから、あずさの命を助けて。あと彼女も助けてあげて。お願いします」
「……今回はほのかの土下座姿がすっごく可愛かったからそれで許してあげるね。僕って本当ほのかに甘いな」
陽光君がそう言うと彼女の悲鳴は止んだ。気絶しているのか眠っているのかはわからないけれど彼女は目を閉じて倒れたままだ。
「ありがとうございます」
「そんなかしこまった言葉遣いしないでいいよ。ねえ君はどうしていつもこうなの?」
「いつも??何を指しているの?」
「本当自覚ないんだね。君はいつだって誰かの言葉に惑わされる。今回だって大方あの子が君に何か吹き込んだんでしょう」
陽光君は倒れている彼女に視線をやる。その視線は氷のように冷たいけれど、怒りで燃え上がっているようにも見える。
彼の言葉に黙り込んでしまう。確かに私と陽光君の歪な関係を危険だと彼女は指摘した。彼女の言葉は間違っていない。
実際に私もだんだんおかしくなっていった。陽光君が他人を平気で害する様子を昔ほど気にしなくなった。
最低な私は陽光君が傷つけた他人よりも、陽光くんといる居心地の良さを選んでいた。
陽光君は本来の陽光君としての人格を失って私を求める怪物に変化し続けているz
彼女はこのままだとお互いに幸せになれないと語った。そして私と陽光君の間にあるのは愛じゃなくて依存だと指摘した。
「沈黙は肯定と受け取るよ。ねえ、お話しようか。ちゃんと君の言葉でどう思っているかを聞きたい。そして僕の想いを伝えたいんだ。君には何千回何万回言わないとわかってもらえないからね。そしたら彼女邪魔だね」
陽光君が指を鳴らすとあの子は操り人形のような不自然な動きをして部屋から出て行く。あの子が部屋を出た途端にガチャリと音が鳴ってドアの鍵、窓の鍵全てが閉まった。
「これで2人きりだね。これで誰も入って来られない」
「陽光君……」
「ほのか、僕は君に好かれているんじゃないかって少し浮かれていたんだ。去年の誕生日は僕が頼んだら僕をモデルにして絵を描いてくれた。家族旅行のお土産では僕が字を書くのが好きって知ってるからガラスペンとインクをくれたね。何回かデートみたいな事もしたよね。夏は花火大会に行って花火を見て、博物館に遊びに行って、冬は雪祭りで氷像を眺めたりしたね。今度は新しくオープンする水族館に行こうって約束したよね。はっきり言うと僕は生きていた時よりも今の方が楽しい。ほのかは違ったの?僕といるのは本当は嫌だった?」
陽光君は寂しげに喋る。表情だって少し切なそうだ。赤い瞳が僅かに揺らいでいる。普段から冷静沈着で余裕のある態度を崩さない彼らしくなかった。
陽光君と過ごす日々は最初は確かに怖くて仕方がなかった。悪魔のように笑いながら私の大切なものを1つ1つ奪い、時にはあずさの命を盾に私を縛ろうとした。実際に魂を半分奪っていった。
だけど一緒に過ごすに連れて陽光君への恐怖はだんだんと薄れていった。
少なくとも彼に絵を書いたり、旅先でお土産を買ってくるくらいには情があった。
それどころか好きなものが合うおかげか、一緒にお出かけするのは楽しいとすら思えた。
2人で勉強するのも好きだった。勉強を教えてくれる時の陽光君の落ち着いた喋りとノートに書かれる綺麗な字が好きだった。
彼がいないと寂しいなと思うくらいには情が湧いていた。それに彼に惹かれつつあったのも事実だ。
だけど彼は亡霊だ。ここにいていい人間ではきっとないのだと思う。彼女の言葉を信じるなら私が心の中で彼を求めたから、一緒にいたいと願ったから現世に縛り付けてしまった。そして苦しめてしまっているのだ。
「楽しかった。だって陽光君ほど話しの合う人はいなかった。それに貴方は些細なことで喜んでくれてた。私の下手くそな絵を嬉しそうに受け取ってくれたときは本当に嬉しかった一緒に博物館を歩いた時はとても楽しかったわ。だけどこんなのおかしいじゃない!私の想いで貴方を縛り付けてる。貴方だったら私なんかに執着しなくても幸せになれたはず。生まれ変わった方が絶対幸せなはずなのに」
「生まれ変わりか。ごめんね、僕そういうのは一切信じてないんだ。もし来世があったとして、輪廻の輪に乗って生まれ変わってしまえばそれはもう僕じゃない。そして君が生まれ変わっても同じだ。君は信濃ほのかではなくなる。僕は今世の信濃ほのかを愛してるんだ。だから来世なんてどうでもいいんだ。だって来世は僕たちは別人だもの。さっきも言ったけどそういうの一切信じていないから。君が何を言っても僕は君からは離れてあげない。だって愛しい人とずっと一緒にいられる今が僕にとっては幸せなんだ。僕は幽霊になれてよかったよ。君と一緒なら地獄だって天国だよ」
陽光君はうっとりしたように私に語りかける。生前の彼からは考えられないほどの情熱的な言葉だ。
「陽光君それは愛じゃなくて執着だよ。霊になってからの貴方は生前とは別人よ!生きていた時の貴方はこんな酷い事を笑ってできる人じゃなかった!だからやっぱり霊になってから変わっちゃったんだよ!」
やってしまった。きっとまた陽光君の怒りを買ってしまった。気持ちのままに思ったことをそのまま言ってしまうのは私の悪い癖だ。だけど言わずにはいられなかったのだ。
恐る恐る陽光君の様子を確認する。陽光君の表情は変わらない。怒りで冷たい氷のような表情をしていると思ったがそういった表情ではない。怒っていないのかな。
「愛してるから執着するんだ。死んでからは別人みたい。当たり前でしょ。人間なんて変わるものだよ。僕は生前の鈍感で臆病で行動できない自分が大嫌いだったんだ。でも今は違う。君を守る力がある。それにずっと一緒にいる事ができる手段だってある。僕は変われて良かったと思っている。それに生前の僕だって君が思っているような優しい人間じゃないよ。君以外の人間には興味が無かったし、女の子たちに囲まれた時はほのかに近づけなかったから正直邪魔だって思っていたよ。それどころかいきなり囲まれるようになって戸惑っていたくらいだよ。生前から僕は君さえいれば他に何も要らないって思っていたんだ」
「嘘……そんなに私がいいの?だって私なんか臆病でわがままでなんの取り柄もない人間だよ。それでも私のことが好きなの?」
「私なんかって言わないでよ。確かに君は臆病だしすぐ人に流されるし、僕を心配させたりするよ。それでも最初に僕に手を差し伸べてくれたのは君だ。僕は君が君、ただそれだけで君を愛しているんだ。やっぱりこうやって口に出すのは少し恥ずかしいな。だけど言わないと伝わらないから言い続けるよ」
「陽光君、いっつも情熱的なことを言うくせに恥ずかしいって思ってたの?」
「当たり前でしょ。生前だったら絶対に言えなかった。でも何も言えないで後悔するのは嫌だからこれからも言い続けるよ。こんな姿になってまで君と一緒にいたいと思ったんだ。君といるためなら僕は悪魔にでもなって見せるよ」
「……」
「お願い、僕を受け入れて。君も一緒に奈落の底に落ちて。断ったって逃しはしないよ。でも僕は君の口から僕を受け入れると言って欲しい。ねえ、お願い」
陽光君は私をきつく抱きしめる。1年半前に魂を奪っておいて雁字搦めにしておきながら受け入れて欲しいとか矛盾もいいところだ。
最初から拒否権なんてない。だけどきっと彼は私からの言葉が欲しいのだ。私から一緒にいると言う言葉が欲しいのだ。もし言葉に出してしまえば言質として取られて事あるごとに彼に引き合いに出されるだろう。
だけど私に懇願する声は切なそうで、泣きそうな声だった。いつもどこか余裕そうな彼らしくない姿だ。そんな彼だからこう懇願されるとつい首を縦に振ってしまいそうになる。
陽光君がいなくなるのは寂しい。確かに怒ると怖いし他人を平気で傷つける残酷さも持ち合わせているし、酷いこともいっぱいされた。
だけどそれ以上に一緒にいるのは心地よかった。話も合うし、陽光君のことは嫌いじゃない。それに一緒に過ごしていくうちに段々と彼に惹かれていった。
彼とだったらずっと一緒にいてもいいかなって思えるくらいには好意は持っていた。だけどこれは恋愛感情ではないと思う。だって彼とは恋人がするような事がしたいとは全く思わない。だからきっと友人として、一緒に過ごす人間として惹かれていたのだ。そして彼はいつの間にか私の日常を構成する必要不可欠なピースになっていたのだ。
「陽光君はずるい人だね。だって何を言ったって離してくれないくせに。私から自分を受け入れさせて逃げ道を奪っていくんだもの。陽光君の事受け入れるよ。一緒に奈落に落ちてあげる。陽光君なら奈落の底でもなんとかしてくれそうだもの」
「僕がずるいのは今に始まったことじゃないよ。安心して僕がいる限りは君には傷一つつけさせやしないよ。嬉しい。君から受け入れてくれて本当に嬉しい」
陽光君が優しく微笑んだ。どんな時でも絶対に涙を流さなかった彼なのに一筋の涙が伝っていた。卑怯な人だ。さっきまで笑って恐ろしい目に遭わせていたのに今はとても嬉しそうで優しい顔をしている。何があってもこの人は絶対に私を離してくれないのだ。
本当に私の事が好きなんだなとわかってしまた。
私は陽光君を抱きしめた。貴方のことを受け入れたという私なりのアピールだった。陽光君の身体は相変わらず氷のように冷たい。だけど今はその冷たさが心地よかった。
陽光君も私のことをギュッと抱きしめ返す。その時に彼の着物の袖から彼の腕に火傷みたいな傷があるのが見えた。
「陽光君、腕が火傷みたく赤くなっている」
「あっ!」
「見せて!」
陽光君の着物の袖を捲ると彼の左腕は火傷したかのように赤くなっていた。
「これどうしたの?話して!私ばっかりに話させて自分は黙ってるのどうかと思う!」
「わかったよ。……この家、僕みたいな霊を避けるための結界みたいなの張られてて、それを無理やり破った時に怪我したんだ……大丈夫だよ。1日もしたら治ると思う」
「私の心配するくせに自分は結構無茶するよね。今日着物姿だったのだって普段の半袖シャツにスラックス姿だとこの怪我ばれるからでしょ。まさか着物姿になれるとは思わなかったけど」
「うん。ほのかの言う通りだよ。あんまりかっこ悪いというか余裕がない姿は見られたくなかったな」
「そういう問題じゃないよ。本当びっくりしたし心配した」
「嬉しい。僕のことそれくらいは好きでいてくれるんだね」
「そう思うくらいには陽光君に私も絆されちゃったの。そりゃあ怖い時もいっぱいあるけど……」
そして私は陽光君の頭をポンって叩く。
「それは君が僕を怒らせるような事ばかりするからでしょ。確認だけど本当に僕の事受け入れてくれるんだね」
「うん。受け入れるわ。それにそもそも私たちとっくに一蓮托生じゃない」
私はついに自分から陽光君と共に生きていく覚悟を決めた。自分勝手でも何でもいい。それでも2人がいいのだ
***
高校を卒業した後の私の進路は就職だった。小さい会社に就職が決まって、今日私は生まれ育った街を去っていく。
不思議と不安はない。陽光君が一緒にいるからだろうか。彼となら大体の事はどうにかなると思ってしまう。そんな不思議な安心感を陽光君はくれた。
駅のホームまではお母さんとお父さん、そしてあずさが見送りに来てくれた。私が新しく住む町はローカル電車で2時間ほどだ。特急を使えばもっと速く着く。会おうと思えばいつだって会える距離だ。それなのに家族全員で見送りに来てくれた事には感謝しかない。
「お姉ちゃん、遠い街でお仕事頑張ってね。あずさ夏休みや冬休みに遊びにいくからね」
「ありがとう、あずさ。お姉ちゃん頑張るね。電車きたからもういくね」
「わかった。バイバイ」
私は電車に乗り込む。車両はガラガラを通り越して誰もいなかった。空いている席に適当に座る。隣の席には陽光君が座った。
窓を見るとまだ家族が手を振っていた。
「まさか君が就職して家を出るとは思わなかったよ。頭がいいから大学に進学って道もあったのに」
「そうだね。勉強したいわけでもなかったし、だったら仕事して自立したいって思ったの」
「そうか。僕は君の選択を尊重するよ。でも嬉しいな。僕と君が一緒に暮らすなんて実質同棲だよね」
「同棲ってなんか恋人みたい言い方だね」
「死んでからも離れられないんだから恋人よりもずっと深い関係でしょう」
「そうだね。でも離れられないじゃなくて離さないの間違いじゃない」
「うん。絶対に離してあげない」
普段だったらこうやって公共の場で陽光君とはお喋りはしない。陽光君の姿は誰にも見えないので私がおかしい人だと思われるからだ。だけど今電車にいるのは2人だけだ。お喋りしたって許されるだろう。
車窓から変わりゆく景色を見つめながら陽光君と会話をする。見慣れた町の景色が少しずつ変わっていくのは新鮮な気分だった。普段電車に乗らないのでなおそう思うのだろう。
景色が変わっていくように私の未来も変化していくのだろう。
「そうだったんだね。僕はどんな道を選んでもほのかを応援するよ。例え周り全てが敵になっても僕だけはずーっと君の味方でいてあげる」
「大袈裟な物言いだね。でも陽光君がそう言ってくれるなら心強いかな」
「全部本気だよ。愛してるよ。2人で幸せになろうね。君に降りかかる火の粉は全部僕が払ってあげる。君の事は僕が守ってあげるね」
「うん、ありがとう」
それから人が乗ってくるまで私と陽光君は取り留めない話をした。最近読んだ小説や興味のあるテレビ番組、本当にどうでもいいことだ。
次の駅ですぐに人が乗ってきたからお喋りは短い時間だけだった。陽光君は残念と笑って、私に寄りかかる。
私と陽光君の在り方は世間では間違っているのだろう。だけど私たちはこれでいいのだ。だって陽光君は私を求めているし、私だって陽光君を求めている。
私たちのあり方が歪んだ形なのは知っている。
この美しい人は世界が滅んだって私を離してくれない。最初魂を奪われたときにわかっていた筈だった。だけど本当はわかっていなかったのだ。彼の荒れ狂う想いの正体は私は勝手に幽霊になっておかしくなったが故の結果だと思っていた。でも違った。彼はおかしくなるほど荒れ狂う想いを持っていたから幽霊になってしまったのだ。
だけどこれでいいのだ。だって私も陽光君も幸せなのだから。陽光君とだったら奈落の底でも大丈夫。
0
あなたにおすすめの小説

ヤンデレ男子の告白を断ってから毎日家の前で待ち伏せされるようになった話
チハヤ
恋愛
「告白の返事を撤回してくれるまで帰らない」と付きまとわれても迷惑なので今日こそ跳ねのけようと思います――。
ヤンデレ男子×他に好きな人がいるヒロインのとある冬の日の出来事。
メリバです。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?

【ヤンデレ蛇神様に溺愛された貴方は そのまま囲われてしまいました】
一ノ瀬 瞬
恋愛
貴方が小さな頃から毎日通う神社の社には
陽の光に照らされて綺麗に輝く美しい鱗と髪を持つ
それはそれはとても美しい神様がおりました
これはそんな神様と
貴方のお話ー…
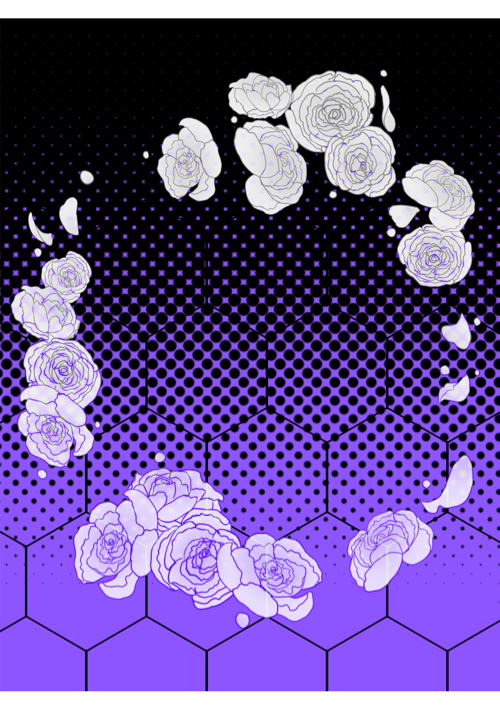



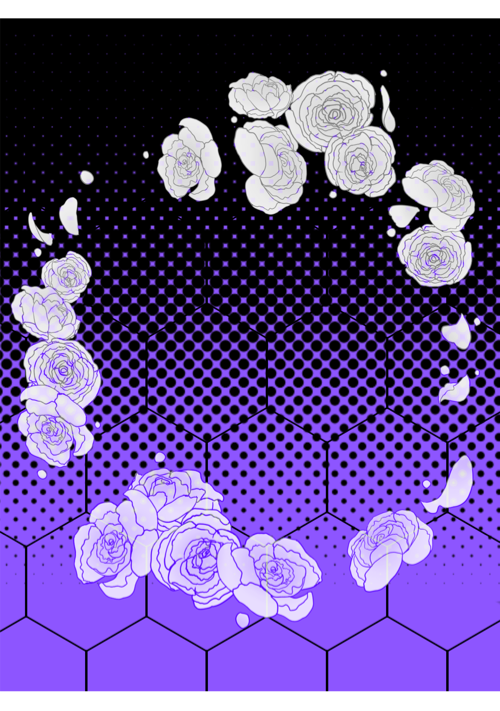
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















