8 / 30
熾火
しおりを挟む
私の見た限りでは、彼は決して劇に出てくるような陽気な荒くれ者ではなかった。ロゲルトはむしろ寡黙で、いつも何かを考えているように思えた。それは彼自身の過去のことでもあっただろうし、これから先の日々のことでもある。彼は自分の生き方について考えあぐねていたのかもしれなかった。私は蛮族に従いたくはなかった。例え実際に滅ぼしたのが彼でないにしてもだ。しかし幼い私には荒廃と死に囲まれてじっとしているだけの勇気もなく、かといって一人で生きていく術もなかった。今もそうだろうか。幼い私が心の暗闇で、誰にも見つからずに震えているかもしれない。私は彼と一緒でなければいずれ飢え死にしてしまうだろう。ロゲルトは狩りに出ると言っただけで、私にその戦果を分けるという約束はしていない。だが、火を起こす他にすることも見つからない。結局私は彼に従うしかなかった。彼は木の実を集めて回り、一角兎の首をへし折って腰にぶら下げている。その中には私の取り分も含まれていただろう。
「食え。働けない奴に用はない」
その日の夜、彼は焦げた肉を薄く切り分けて持ってきた。哀れに思ってではなく、明日も明後日も働かせ続けるためだが。彼もまた同じように、自分一人ではどうしようもない現実に抗うための手段を探していた。
私は火を起こす。幸い薪には困らなかった。冬の乾いた風が木壁と屋根を縮こまらせ、果てしない冬が村から熱を奪っていった。火種はロゲルトが作っていった。彼は農具の錆びた鉄に拾ってきた石を擦る。私もそれを真似たが、腕に鈍く痛み続ける傷を作っただけだった。私は村中の家々に足を踏み入れては、ありあわせの木材で簡単な松明を作ろうとした。それらの炎は煙を吐き出して夜を照らし、我々はようやくほんの僅かな暖かさを得た。私が火と石の時代を身近に感じるのはそのせいだ。私が火の元を立ち去っても、彼は特に何も言わなかっただろう。村の中で私たちは家の裏手にある丘から枯れ枝を集め、暖炉の前に積み上げて乾いた葉に火をつけた。
「お前は何者なんだ?」
一度だけ、彼に尋ねたことがある。彼は答えた。
「ロゲルト・オッリ。意味のない名だ」
彼がそれ以上語ろうとしなかったので、私はそれ以上の追及を諦めた。
最初は小さな炎だったが、やがて轟々と燃える赤々としたものになる。ロゲルトは満足げにそれを眺めていたが、私は違った。あの日瓦礫に射した光がなければ、この炎を孤独の中のささやかな慰めと考えたかもしれない。あの村は今でも私の中で燃えていた。狂った小さな太陽の中で、人々の朱い山が燻っていた。実体が失われてもなお、私の中には彼らがいる。
私が眠っている間に、炎は熾火に変わるだろう。記憶が白い灰の中に埋もれてゆく。私は生きるために生きていて、それ以外のことを考えることはできない。日差しが以前の亀裂や荒廃ぶりだけでなく、エファイマの蛮族が無残にも破壊した家々を白日の下に晒し出すだろう。やがてロゲルトは目を覚まして斧の手入れを始めるだろう。私はぼんやりとその光景を思い描くことができる。彼は丁寧に時間をかけて刃を研ぎ、斧の先端に刻まれた幻獣の印は日の光を受けてきらりと輝くだろう。そして彼はまた斧を手に取って、私の作った不格好な松明の残骸をなぎ倒し、狩りに出かけるだろう。冬は深く、厳しくなっていく。彼も私もそのことに気付いていた。石積みは崩れ、材木も雪がもたらす湿気のせいで徐々に腐っていくだろう。雨風に耐えている狭苦しい家は、やがて打ち捨てられ他と変わらない瓦礫に変わるだろう。そうなったとしても、私たちは暫らくの間生き残るだろう。この村を包む雪を耐えるためには、新しい家が必要だった。誰も住んでいない家はやけに早く崩れ落ちる。風に屋根が吹き飛ばされた家や、柱が折れた家が蘇ることはないだろう。私が自分の家があった場所に戻ったところで跡形もなく消えているだろう。私の心には小さな穴が開いていた。その穴は螺旋を描いて、心臓の奥まった場所に捻じれた膨らみを広げているだろう。私たちが眠る間に、廃墟となった村が朝日に照らされて目覚める。時折、軋んだ骨組みが音を立てた。痛い、痛い、殺してくれ。耳鳴りのような声が聞こえ続ける。村人の魂は戻る場所を間違え、今や古い家々に宿っているのだ、と私は夢想した。
何度目かの夕暮れ時から、太陽はこの地に飽き始めた。ロゲルトが私に話しかけるようになってから幾日か経っている。私は黙ってそれを聞いていた。それは天気のことだったり、今日の食事のことだったりする。会話は長く続かない。彼が船を作りたいのは分かったが、説得は遅々として進まなかった。いつも黙って彼の話を聞いているだけだ。彼は時々苛立った様子を見せた。彼は船を作ってエファイマの離れ小島まで帰り着くことしか考えておらず、そのためには仮の住まいが早急に必要だった。もしもこの瞬間にそれを成し遂げていたら、彼はすぐさま私を殺しただろう。何度目かの夕暮れ時に、彼は私に尋ねた。もし家を作らないなら、お前はどうして俺に従ったのか?
私はそれに答えられなかった。彼は私の沈黙を肯定の意味に捉えたらしく、私の肩に手を置いた。私はその手を払い除ける。その瞬間、彼は驚いたように目を見開いた。私は彼に背を向けたままじっとしていた。彼は少しの間その場を離れ、古びた斧を持ってくる。
「お前は死にたがっているのか?」
振り返ると、彼は斧の刃を私の首筋に押し当てていた。その問いに対する答えは持っていなかったが、私は虚勢を張って頷いた。自分がどうしたいのか分からなくなっていた。彼は斧の柄を握りしめ、私を品定めするようにじっと見つめた。そうか、とロゲルトは呟いた。なら、死ぬがいい。
次の瞬間、彼の斧は私の脇腹目掛けて振り下ろされた。私にはそれがゆっくりと見えて、出会いの時のようにこの斧は止まらないだろう、という予感がした。何ができたわけでもない。体に強い衝撃が走って、私は地面に叩きつけられる。少し遅れて地鳴りのような痛みと吐き気がやってきた。私は顔を上げることすらできずにいた。すっぱりと断たれたような痛みではない。彼はあの時、斧の背の部分を使っていたから。しかし、それでも息はできなかった。
死にたくない。今になって全身がそう騒ぎ立てていた。
「まだ、死にたいか」
彼は私の目の前にしゃがみこみ、私の顔を覗き込んだ。彼の瞳に映る私はまるで死者のようだった。彼は硬い表情でこう告げた。
「では、立って歩け。結局のところ、お前は死にたくないのだ」
私は言われるがままに必死で立ち上がる。傷口は濃い痣になるだろう。私は震えながら一歩ずつ足を踏み出した。足元で小枝が割れ、乾いた音が響く。私は歯を食いしばった。ロゲルトは私が歩き出すのを確認して家の方へ戻っていったが、その際こう告げるのを忘れなかった。
「明日から船を作ろう。だが無理強いはすまい。次にお前が死にたいと思った時には、俺も刃の方を振り下ろしてやる」
私は悔しくなって、黙って小屋への道を歩いていった。打たれた箇所が熾火のような熱を持って、じりじりと痛み続けていた。
「食え。働けない奴に用はない」
その日の夜、彼は焦げた肉を薄く切り分けて持ってきた。哀れに思ってではなく、明日も明後日も働かせ続けるためだが。彼もまた同じように、自分一人ではどうしようもない現実に抗うための手段を探していた。
私は火を起こす。幸い薪には困らなかった。冬の乾いた風が木壁と屋根を縮こまらせ、果てしない冬が村から熱を奪っていった。火種はロゲルトが作っていった。彼は農具の錆びた鉄に拾ってきた石を擦る。私もそれを真似たが、腕に鈍く痛み続ける傷を作っただけだった。私は村中の家々に足を踏み入れては、ありあわせの木材で簡単な松明を作ろうとした。それらの炎は煙を吐き出して夜を照らし、我々はようやくほんの僅かな暖かさを得た。私が火と石の時代を身近に感じるのはそのせいだ。私が火の元を立ち去っても、彼は特に何も言わなかっただろう。村の中で私たちは家の裏手にある丘から枯れ枝を集め、暖炉の前に積み上げて乾いた葉に火をつけた。
「お前は何者なんだ?」
一度だけ、彼に尋ねたことがある。彼は答えた。
「ロゲルト・オッリ。意味のない名だ」
彼がそれ以上語ろうとしなかったので、私はそれ以上の追及を諦めた。
最初は小さな炎だったが、やがて轟々と燃える赤々としたものになる。ロゲルトは満足げにそれを眺めていたが、私は違った。あの日瓦礫に射した光がなければ、この炎を孤独の中のささやかな慰めと考えたかもしれない。あの村は今でも私の中で燃えていた。狂った小さな太陽の中で、人々の朱い山が燻っていた。実体が失われてもなお、私の中には彼らがいる。
私が眠っている間に、炎は熾火に変わるだろう。記憶が白い灰の中に埋もれてゆく。私は生きるために生きていて、それ以外のことを考えることはできない。日差しが以前の亀裂や荒廃ぶりだけでなく、エファイマの蛮族が無残にも破壊した家々を白日の下に晒し出すだろう。やがてロゲルトは目を覚まして斧の手入れを始めるだろう。私はぼんやりとその光景を思い描くことができる。彼は丁寧に時間をかけて刃を研ぎ、斧の先端に刻まれた幻獣の印は日の光を受けてきらりと輝くだろう。そして彼はまた斧を手に取って、私の作った不格好な松明の残骸をなぎ倒し、狩りに出かけるだろう。冬は深く、厳しくなっていく。彼も私もそのことに気付いていた。石積みは崩れ、材木も雪がもたらす湿気のせいで徐々に腐っていくだろう。雨風に耐えている狭苦しい家は、やがて打ち捨てられ他と変わらない瓦礫に変わるだろう。そうなったとしても、私たちは暫らくの間生き残るだろう。この村を包む雪を耐えるためには、新しい家が必要だった。誰も住んでいない家はやけに早く崩れ落ちる。風に屋根が吹き飛ばされた家や、柱が折れた家が蘇ることはないだろう。私が自分の家があった場所に戻ったところで跡形もなく消えているだろう。私の心には小さな穴が開いていた。その穴は螺旋を描いて、心臓の奥まった場所に捻じれた膨らみを広げているだろう。私たちが眠る間に、廃墟となった村が朝日に照らされて目覚める。時折、軋んだ骨組みが音を立てた。痛い、痛い、殺してくれ。耳鳴りのような声が聞こえ続ける。村人の魂は戻る場所を間違え、今や古い家々に宿っているのだ、と私は夢想した。
何度目かの夕暮れ時から、太陽はこの地に飽き始めた。ロゲルトが私に話しかけるようになってから幾日か経っている。私は黙ってそれを聞いていた。それは天気のことだったり、今日の食事のことだったりする。会話は長く続かない。彼が船を作りたいのは分かったが、説得は遅々として進まなかった。いつも黙って彼の話を聞いているだけだ。彼は時々苛立った様子を見せた。彼は船を作ってエファイマの離れ小島まで帰り着くことしか考えておらず、そのためには仮の住まいが早急に必要だった。もしもこの瞬間にそれを成し遂げていたら、彼はすぐさま私を殺しただろう。何度目かの夕暮れ時に、彼は私に尋ねた。もし家を作らないなら、お前はどうして俺に従ったのか?
私はそれに答えられなかった。彼は私の沈黙を肯定の意味に捉えたらしく、私の肩に手を置いた。私はその手を払い除ける。その瞬間、彼は驚いたように目を見開いた。私は彼に背を向けたままじっとしていた。彼は少しの間その場を離れ、古びた斧を持ってくる。
「お前は死にたがっているのか?」
振り返ると、彼は斧の刃を私の首筋に押し当てていた。その問いに対する答えは持っていなかったが、私は虚勢を張って頷いた。自分がどうしたいのか分からなくなっていた。彼は斧の柄を握りしめ、私を品定めするようにじっと見つめた。そうか、とロゲルトは呟いた。なら、死ぬがいい。
次の瞬間、彼の斧は私の脇腹目掛けて振り下ろされた。私にはそれがゆっくりと見えて、出会いの時のようにこの斧は止まらないだろう、という予感がした。何ができたわけでもない。体に強い衝撃が走って、私は地面に叩きつけられる。少し遅れて地鳴りのような痛みと吐き気がやってきた。私は顔を上げることすらできずにいた。すっぱりと断たれたような痛みではない。彼はあの時、斧の背の部分を使っていたから。しかし、それでも息はできなかった。
死にたくない。今になって全身がそう騒ぎ立てていた。
「まだ、死にたいか」
彼は私の目の前にしゃがみこみ、私の顔を覗き込んだ。彼の瞳に映る私はまるで死者のようだった。彼は硬い表情でこう告げた。
「では、立って歩け。結局のところ、お前は死にたくないのだ」
私は言われるがままに必死で立ち上がる。傷口は濃い痣になるだろう。私は震えながら一歩ずつ足を踏み出した。足元で小枝が割れ、乾いた音が響く。私は歯を食いしばった。ロゲルトは私が歩き出すのを確認して家の方へ戻っていったが、その際こう告げるのを忘れなかった。
「明日から船を作ろう。だが無理強いはすまい。次にお前が死にたいと思った時には、俺も刃の方を振り下ろしてやる」
私は悔しくなって、黙って小屋への道を歩いていった。打たれた箇所が熾火のような熱を持って、じりじりと痛み続けていた。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

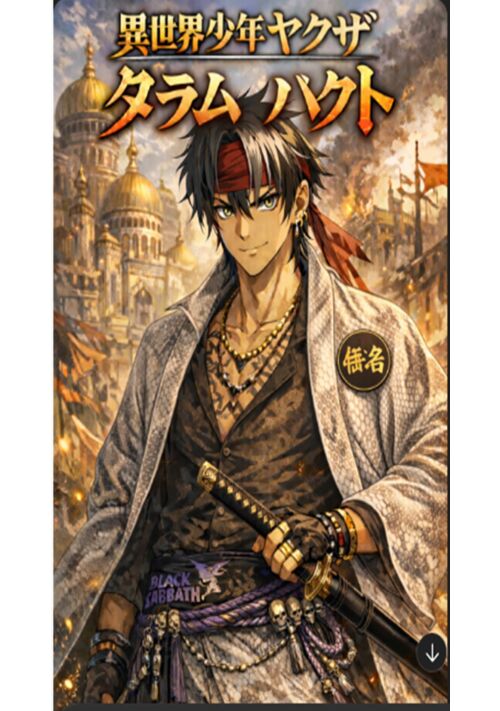
異世界子供ヤクザ【ダラムルバクト】
忍絵 奉公
ファンタジー
孤児院からスラムで育ったバクト。異空間収納と鑑定眼のダブルギフト持ちだった。王都西地区20番街では8割を縄張りとする先代のじいさんに拾われる。しかしその爺さんが死んだときに幹部同士のいざこざが起こり、組は解散。どさくさにまぎれてバクトが5・6番街の守役となった。物語はそこから始まる。7・8番街を収めるダモンとの争い。また後ろ盾になろうと搾取しようとする侯爵ポンポチーコ。バクトは彼らを越えて、どんどん規格外に大きくなっていく。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

盾の間違った使い方
KeyBow
ファンタジー
その日は快晴で、DIY日和だった。
まさかあんな形で日常が終わるだなんて、誰に想像できただろうか。
マンションの屋上から落ちてきた女子高生と、運が悪く――いや、悪すぎることに激突して、俺は死んだはずだった。
しかし、当たった次の瞬間。
気がつけば、今にも動き出しそうなドラゴンの骨の前にいた。
周囲は白骨死体だらけ。
慌てて武器になりそうなものを探すが、剣はすべて折れ曲がり、鎧は胸に大穴が空いたりひしゃげたりしている。
仏様から脱がすのは、物理的にも気持ち的にも無理だった。
ここは――
多分、ボス部屋。
しかもこの部屋には入り口しかなく、本来ドラゴンを倒すために進んできた道を、逆進行するしかなかった。
与えられた能力は、現代日本の商品を異世界に取り寄せる
【異世界ショッピング】。
一見チートだが、完成された日用品も、人が口にできる食べ物も飲料水もない。買えるのは素材と道具、作業関連品、農作業関連の品や種、苗等だ。
魔物を倒して魔石をポイントに換えなければ、
水一滴すら買えない。
ダンジョン最奥スタートの、ハード・・・どころか鬼モードだった。
そんな中、盾だけが違った。
傷はあっても、バンドの残った盾はいくつも使えた。
両手に円盾、背中に大盾、そして両肩に装着したL字型とスパイク付きのそれは、俺をリアルザクに仕立てた。
盾で殴り
盾で守り
腹が減れば・・・盾で焼く。
フライパン代わりにし、竈の一部にし、用途は盛大に間違っているが、生きるためには、それが正解だった。
ボス部屋手前のセーフエリアを拠点に、俺はひとりダンジョンを生き延びていく。
――そんなある日。
聞こえるはずのない女性の悲鳴が、ボス部屋から響いた。
盾のまちがった使い方から始まる異世界サバイバル、ここに開幕。
【AIの使用について】
本作は執筆補助ツールとして生成AIを使用しています。
主な用途は「誤字脱字のチェック」「表現の推敲」「壁打ち(アイデア出しの補助)」です。
ストーリー構成および本文の執筆は作者自身が行っております。


旧校舎の地下室
守 秀斗
恋愛
高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















