13 / 42
第十三章
出発
しおりを挟む
「リィフェルト卿がお着きです」
執事の命令で侍童が呼びにきた。予定よりだいぶ早い。さあ! と女達がいきり立つ。
「急にご旅行なんてびっくりしましたが、いざ準備が整うとドキドキしますね」
「若いお二人の……ああ、目の辺りにすると素敵ですかも」
ポリーヌとカチャが勝手に盛り上がっている。叔母も満更ではなさそうだ。この家族同然の彼女らがこんなに乙女とは思わなかった。
「全く……」
騎士様に同行してもらってアルトバインに行くだけだと言うのに。あちらもアルトバインに用があるみたいだし、ナディもどうしても行きたい目的があるのだ。具体的には言えないが。叔母だけにしか知らせていないが。
「ああ、もうジェルマと初めて会った頃を思い出すわあ」
その知っているはずの叔母まで盛り上がっているのはなんなんだろう。
ナディはその三人に押し込められる様にして広間に移動した。そこに主も客人も待っている。
「おお、ナディ」
大袈裟に迎えてくれたのは男爵家当主の叔父だった。席から立ち上がり、不安げだった顔がまず姪の乗馬服姿に驚く。
「立派になって、おおぉぉぉ、凛々しい。爽やかだ。まるでアルベリクの様な」
誉めてくれている様だがそれは王都歌劇団の人気美男俳優の名だ。喜んでいいのか悪いのか。いや、失礼じゃないのだろうか。
「お早うございます。ナディー……ナディ殿」
向こうの席に座っていた客人も立ち上がって一礼した。旅装だろうか、昨日とは出で立ちが違う。革系の上下で手元には帽子と脱いだマントに二本の剣が見える。中性的なその声も幾分硬い。
「まああ、カーリャ様」
まず喜んだのは叔母だった。
「なんて凛々しい逞しいお姿。さすが騎士様ですわ」
そうかあ? とナディは思う。凛々しくは見えるが、やはりナディより小柄だ。無駄のない意匠の服装は逆に身体の華奢さを見せている。やっぱりこの人、女よね。
「恐縮です」
「これなら姪をお任せ出来ますわあ」
叔母が恐らくわざと騒ぎ立て、控えているはずのメイド二人が何故か赤い頬で騎士様とナディをちらちら見ている。叔父の席の後ろに直立不動の執事は厳かな顔を小揺るぎもさせなかった。
「なのにまだ何のおもてなしも――モルガン。ご用意をして」
「いえ、お構い無く。そろそろ時刻ですので」
叔母の申し出を騎士様は即断った。モルガンも無言で一礼する。おもてなしなど彼ほどの執事が気づかぬはずがない。ナディらがこの部屋に入る前に用意しようとして既に断られているのだ。
「あら、もうそうかしら」
「リィフェルト卿」
まだも何か言う叔母を珍しく叔父の声が遮った。
「アルトバイン迄との事だが、姪を宜しく頼むよ」
「お任せあれ。男爵閣下。不肖、カーリャ・リィフェルト。騎士の名誉にかけても」
不安げなお願いに凛々しく宣言する。ナディの目にも戦場に向かう騎士の誓いのようだった。
つまり、メイドらが期待している甘さや甘酸っぱさが欠片もない。
「では参りましょう」
そしてナディへ声をかける。まるで命令の様にきびきびと。うん、この方は勘違いしていないわとナディはちょっとだけ安心した。
これからは単に女司書と姫騎士様がアルトバインへ旅するだけのお話なんですから。
すぐにも一同は玄関前に移動する。性格なのだろうか。この騎士様が本気で主導権を持つと何でもきびきびと速いのをナディはたっぷり知らされる事になる。
「な……ナディ殿は乗馬は大丈夫ですね」
見送りの皆が見守る中、まずそう訪ねてきた騎士様にナディは答えず、その前に不思議そうに相手の格好を見ていた。知っている騎士や貴族とは些か趣が異なっていたのだ。
旅装はともかく剣を二本装備していた。一本の柄が左肩から見える。背負っているのか。もう一本は左腰だが、そこに締めた剣帯に前から後ろに挿している。通常、剣は腰に横か、右肩から左腰に巻いた剣帯に吊るすものだが。騎士に限らず、兵でも貴族の護身用でもそれが普通だ。
小柄だから上から吊るすと鐺が地に着くとかかしら? とナディは些か失礼な事を考えた。そう言えば剣も緩く湾曲している。あれは本にあった『獅子の尾』と呼ばれる片刃なのかも。
「ナディ殿?」
再度、名を呼ばれてナディは我に帰る。うわ、愛称で呼ばれたと、ちょっとどきりとした。
「あ、はい。なんですか?」
「乗馬でよろしいですか?」
騎士様が再度丁寧に問う。声に出さない失礼な事を思われているのに実に優しい。
「はい。えっと、乗った事はありますが」
我ながら自信の無い声である。本当にここ数年は移動はずっと馬車だった。だって淑女なんだからそうしなさいと皆が――
「ではこちらのウイッカをお使い下さい」
そう言ってカーリャが示す。その先のちょっと離れた所に昨日も見た二頭の馬がおり、ロドがついていた。客人の馬の世話役だろう。乗馬は貸してくれるらしい。
「よろしく」
あらかじめ言っておいたのか、それだけでロドが手綱を引いて白い方の馬を連れてきた。中くらいの大きさの牝馬だ。
「これは大人しく賢い牝馬です。ナディさ……殿にはよろしいかと」
騎士様の言う通りに大人しそうな馬だった。葦毛の毛並みも綺麗でよく手入れされているのがわかる。目も大きくて優しそうだ。
「こ、この子ですか?」
そう見るとナディの心がむくむくと沸き上がってきた。室内派の癖に基本的にお調子者なのである。最初の怯えも消えて、すごい久しぶりのはずなのに乗ってみたくなっていた。
「噛みついたりしませんか?」
「大丈夫です」
「蹴っ飛ばされたりとかは?」
「……多分」
素人そのもののナディの質問に真面目に答える騎士様である。なんか和やかだと見ている数人は思っただろう。
「ただ舐めるのが好きですけど」
「はあ」
騎士様がロドから手綱を受け取る。馬に慣れた青年は何故か頬を赤くしていた。騎士様の美貌にあらぬ勘違いをしているのかも知れない。
「どうぞ」
そして手綱をしっかり握り、馬を安定させてからナディに勧める。ナディは恐る恐る近づいた。近くで見ると中々大きい。でも白い毛並みが本当に綺麗。大きめの鞍が乗せられ、そこには下から――
「猫ちゃん?」
「あ、ラージャ」
あの太め大きめの猫が鎮座していた。影にいたのか、音もなく飛び乗ったのだ。ナディと目が合う。
お前かい
確かにそう言われた気がした。
「ラージャ。そこはナディ殿が乗られるのだ」
やや慌てた騎士様が手を伸ばしてラージャを抱えようとする。だが、やだ! とばかりにラージャは鞍にしがみついた。
「ラージャ!」
「あ、あの。わたしは構いませんよ」
見かねてナディが言った。別に嫌ではない。鞍は十分に大きくて、前にちょこんとくらいに乗せられそうだ。それにそのもふもふにも触ってみたい。
「しかし」
「猫ちゃ……ラージャが嫌でなければ」
「……はあ」
そう言われてちょっと困った顔になった騎士様だが、それ以上は言わなかった。確かにラージャはこの旅行中、鞍先に乗ったり、荷物やカーリャの懐にもぐり込んだりしているのだ。利口な奴だから、このお嬢様の番も出来るかもと思ったのだ。
「では」
手綱を握ったまま再度、勧める。ナディは鞍の前に立って、え~~とと固まる。確か、鞍の前にある握り部を掴んで身体を引き上げて――
「え、えっと」
左手で掴んだ。右手を鞍の後部にかける。身体を引き上げて……上がらない。
「ナディ殿。ちょっと離れて」
すぐにも騎士様が動いた。ナディを制止し、目の前で片膝をつく。次に手の指を組み合わせ、籠のように膝の高さに差し出した。
「どうぞ」
ここに左足を乗せろと言うのだ。そう言う作法はナディも知っている。あくまで本の図で見ただけで、こんなに近くで、さらに足で他人の、それも殿方の掌を踏むと言うのに思わず躊躇してしまう。
「さあ」
だが騎士様は容赦ない。これが自分の責務かの様に真面目に言う。ナディの感じた乙女らしい遠慮や羞じらいは無視するのか、わからないのか。
「ナディ殿」
「は、はい」
再度言われて抗えなかった。そっと半長靴の足を乗せる。痛いかもと案じた瞬間、ぐい! と身体が浮いた。すごい力で馬の上までいく。短い悲鳴を上げてナディは鞍の上にすとんと落ちた。
「お見事」
決して本気ではない声で騎士様が言った。その証拠に馬が動かない様に鞍ごとナディの身体を支える。踏んづけた次には抱かれる形になってナディはもっと大きな悲鳴を上げた。鞍の前のラージャが急いで飛び退いたが、それに気付きもしない。
「お静かに。大丈夫です」
騎士様は落ち着いていた。子供に苦い薬を無理矢理飲ます医師の様に淡々とナディを支え、手綱を引く。鞍上の小騒ぎに愛馬は微動だにしない。さすが調教が出来ている。
「大丈夫ですね」
馬からしばし遅れてナディが落ち着いたのを確認してから騎士様は身体を離した。今更ながらにナディの胸がドキドキ動揺している。落ち着けわたし。ちゃんと騎乗出来たんだから。急に抱き抱えられてちょっと驚いただけなんだから。
「なんて見事な牝馬捌き」
叔母が向こうで何か言っている。ナディには意味がわからない。
「ナディ様にはこれで行っていただくとして。ウイッカが慣れる迄はわたしが轡を取りましょう」
要するに騎士様は馬の横について制御をしてくれると言っているのだ。助かったとナディは思う。騎乗出来たとは言え、今でも鞍にしがみつきたい余裕の無さだ。さすがにそれは恥ずかしい。道行く他人から指さして笑われるだろう。慣れる迄なんて言わずにアルトバイン迄そうして欲しい。
「ナディ殿のお荷物は?」
騎士様が声をかけるとポリーヌとカチャがそれぞれ鞄と包みを両手に抱えてえっちらおっちら持ってきた。初めての泊旅行と言う事で張り切って詰めていたから、重いのだろう。
「お預かりします」
騎士様はそれを受け取ると片手で重さを確かめる。え? そんな軽そうに? とメイド達が驚く前で革紐で二つをつなぎ合わせ、そのままひょいと馬の背――鞍の後ろに上げた。振り分けで乗せる。手慣れたものだった。
「アンティオ!」
騎士様はもう一頭を呼ぶ。大柄な黒馬はそれだけでゆっくりと歩んできた。蹄鉄が玄関前に敷き詰められた煉瓦を鳴らす。
「あっ」
その音にそっと振り返ったナディはラージャが黒馬の鞍に座っているのを見つけた。いつの間に。
そして黒馬は既にかなりの荷物を負っていた。鞍の前後の左右に振り分けとお尻の手前に大きな山が見える。棒状のものもあり、これがカーリャの旅支度なのだろうか。
「よしよし」
騎士様はその荷物の中から革紐を取り出すと黒馬の手綱をナディの乗っている白馬の鞍の後ろとでつなげた。これで移動するのか。慣れている様で馬達は平気でいる。
「では男爵閣下。ご夫人」
「あ、ああ」
手綱を持ち、皆に向いて恭しく片膝をついた騎士様に急に呼ばれて、叔父がようやく声を出す。あまりの手際の良さにぽかんと見とれていたのだ。下手くそと大きな荷物をちゃんと馬に乗せ、出発の準備を整える作業を誰の手も借りずにさっさとやってしまった。なかなかに有能である。モルガンやロドですら感心していた。
「あなた。あれを」
「あ、そうだった」
叔母に短く注意されて叔父は思い出した。並んで見ていた執事に掌を数度振る。こちらは忘れずに待ち構えていたので、執事は指示通りに用意されていた小さめの革袋をいそいそとカーリャに差し出した。
「姪が世話になる。リィフェルト卿。大した額でもないが足しにしてくれ」
えへんと叔父が言う。路銀だろう。一瞬、騎士様はどうしようかと言う顔になったが、男爵が出したものを断るのも悪いと思った様で、恭しく受け取った。その際に執事が小声で「銀貨を多めで」と付け加える。執事なりの配慮だった。意味がわかった騎士様も小さくうなずく。
「ナディ殿のことはお任せを。行って参ります」
最後に見送りの皆に帽子をとって深々と一礼する。実に見事な態度だった。その隣では手綱を取られた白馬の上でナディがあわあわと身体を揺らしていた。動き出したので怖い。馬の首に抱きつきそうである。
「こら、ナディ。あなたも何か言いなさい」
「は、はいぃぃ」
怖いのだ。馬の上って結構高い。まだゆっくりなのに馬の脚が動く度にぐらぐらする。鐔広の帽子が夏の扇子の様に大揺れだ。
「ナディ」
叔母の声が呆れていた。ああ、と他の皆からも溜め息が漏れる。大丈夫? ナディ様。アルトバインまで持つ?
「い、行ってきまぁすぅっ」
それでも何とかそう叫んで、でも顔も向けることすらも出来ずにナディは出発したのだった。
「大丈夫でしょうか」
お嬢様と騎士が玄関から立ち、門を抜けて王都の街並みにゆっくり紛れて行くのを男爵と夫人と執事は並んで最後まで見届けていた。
「わたしは今でも心配です。確かにしっかりとした若者でしたが」
モルガンが溜め息をつくように言う。立場上、断固として反対出来なかった。旦那様らに逆らいはしないが、でもなんと言ってもナディ様である。知識豊富な世間知らずはどうしても安心出来ない。
「大丈夫なんじゃない? 何とかなるわよ」
エロイーズの言い様は忠実な執事にも無責任に聞こえた。いや、この方の賢明さは知ってはいるが。
「いやまあその。ナディもあの」
実は全く優柔不断だったのはジェルマである。何せ昨日はいい気分で酔っぱらって眠りこけてしまい、早朝に起こされてようやく今の事態をエロイーズに聞いたのだ。
自分もリンツ卿も昨日に納得した決定事項として。
「あの子は賢いから大丈夫です。それにあの綺麗なカーリャ様ですもの。お似合いの二人ですわ」
「そ、そうかな」
旦那様と奥様の会話を横で聞いているモルガンは言いたい。昨日は絶対にそんな話ではなかった。覗いていたカチャの報告ではナディは初対面でふっていたし、その後の昼食会でもそんな話にはならなかった。
「憧れの殿方と二人きりでの時間を過ごす。ああ、なんて浪漫な。まるで本物の歌劇でも見ているよう」
いや、奥様? とモルガンは口の端がぴくぴく動く。なんの流れかで騎士がアルトバインに行く話になり、それに奥様がけしかけたナディ様が何故か同行に納得したのだ。この縁談には無礼なくらいに意固地だったはずなのに。今でもその理由がさっぱりわからない。
「ま、まあそうだが。でも嫁入り前の娘がだがなあ」
そうです。不謹慎です。慎みがありません。そこの処はもっと強く言って下さい。旦那様。
「あら、いいじゃないですか」
いいわけない。これでリィフェルト卿との縁談が成就しないと、うちのナディ様が良くない噂を立てられてしまう。既にうちの使用人達にも『婚前旅行』とか言う、実にはしたないお話として流れているのだ。
「わたしだってあなたと初めてお会いした時には、一緒に何処か遠くへ連れて行って欲しかったですわ」
「エロイーズ……」
ああ、駄目だとモルガンは嘆息する。こうなったら旦那様は終わりだ。その方向には弱い。この奥様が先の家で離婚するまで独身で待っていたくらいだからなあ。ほら、もう完全に奥様の掌の上だ。感動の余りにすぐにも身体が動いている。
「あなた。まだ、ほら。皆が見ているし」
「愛しているよ。エロイーズ」
主のある意味幸せな光景から遠慮して目を逸らしながら、モルガンはお嬢様と騎士の行く末に加護あれと心から神に祈ったのだった。
執事の命令で侍童が呼びにきた。予定よりだいぶ早い。さあ! と女達がいきり立つ。
「急にご旅行なんてびっくりしましたが、いざ準備が整うとドキドキしますね」
「若いお二人の……ああ、目の辺りにすると素敵ですかも」
ポリーヌとカチャが勝手に盛り上がっている。叔母も満更ではなさそうだ。この家族同然の彼女らがこんなに乙女とは思わなかった。
「全く……」
騎士様に同行してもらってアルトバインに行くだけだと言うのに。あちらもアルトバインに用があるみたいだし、ナディもどうしても行きたい目的があるのだ。具体的には言えないが。叔母だけにしか知らせていないが。
「ああ、もうジェルマと初めて会った頃を思い出すわあ」
その知っているはずの叔母まで盛り上がっているのはなんなんだろう。
ナディはその三人に押し込められる様にして広間に移動した。そこに主も客人も待っている。
「おお、ナディ」
大袈裟に迎えてくれたのは男爵家当主の叔父だった。席から立ち上がり、不安げだった顔がまず姪の乗馬服姿に驚く。
「立派になって、おおぉぉぉ、凛々しい。爽やかだ。まるでアルベリクの様な」
誉めてくれている様だがそれは王都歌劇団の人気美男俳優の名だ。喜んでいいのか悪いのか。いや、失礼じゃないのだろうか。
「お早うございます。ナディー……ナディ殿」
向こうの席に座っていた客人も立ち上がって一礼した。旅装だろうか、昨日とは出で立ちが違う。革系の上下で手元には帽子と脱いだマントに二本の剣が見える。中性的なその声も幾分硬い。
「まああ、カーリャ様」
まず喜んだのは叔母だった。
「なんて凛々しい逞しいお姿。さすが騎士様ですわ」
そうかあ? とナディは思う。凛々しくは見えるが、やはりナディより小柄だ。無駄のない意匠の服装は逆に身体の華奢さを見せている。やっぱりこの人、女よね。
「恐縮です」
「これなら姪をお任せ出来ますわあ」
叔母が恐らくわざと騒ぎ立て、控えているはずのメイド二人が何故か赤い頬で騎士様とナディをちらちら見ている。叔父の席の後ろに直立不動の執事は厳かな顔を小揺るぎもさせなかった。
「なのにまだ何のおもてなしも――モルガン。ご用意をして」
「いえ、お構い無く。そろそろ時刻ですので」
叔母の申し出を騎士様は即断った。モルガンも無言で一礼する。おもてなしなど彼ほどの執事が気づかぬはずがない。ナディらがこの部屋に入る前に用意しようとして既に断られているのだ。
「あら、もうそうかしら」
「リィフェルト卿」
まだも何か言う叔母を珍しく叔父の声が遮った。
「アルトバイン迄との事だが、姪を宜しく頼むよ」
「お任せあれ。男爵閣下。不肖、カーリャ・リィフェルト。騎士の名誉にかけても」
不安げなお願いに凛々しく宣言する。ナディの目にも戦場に向かう騎士の誓いのようだった。
つまり、メイドらが期待している甘さや甘酸っぱさが欠片もない。
「では参りましょう」
そしてナディへ声をかける。まるで命令の様にきびきびと。うん、この方は勘違いしていないわとナディはちょっとだけ安心した。
これからは単に女司書と姫騎士様がアルトバインへ旅するだけのお話なんですから。
すぐにも一同は玄関前に移動する。性格なのだろうか。この騎士様が本気で主導権を持つと何でもきびきびと速いのをナディはたっぷり知らされる事になる。
「な……ナディ殿は乗馬は大丈夫ですね」
見送りの皆が見守る中、まずそう訪ねてきた騎士様にナディは答えず、その前に不思議そうに相手の格好を見ていた。知っている騎士や貴族とは些か趣が異なっていたのだ。
旅装はともかく剣を二本装備していた。一本の柄が左肩から見える。背負っているのか。もう一本は左腰だが、そこに締めた剣帯に前から後ろに挿している。通常、剣は腰に横か、右肩から左腰に巻いた剣帯に吊るすものだが。騎士に限らず、兵でも貴族の護身用でもそれが普通だ。
小柄だから上から吊るすと鐺が地に着くとかかしら? とナディは些か失礼な事を考えた。そう言えば剣も緩く湾曲している。あれは本にあった『獅子の尾』と呼ばれる片刃なのかも。
「ナディ殿?」
再度、名を呼ばれてナディは我に帰る。うわ、愛称で呼ばれたと、ちょっとどきりとした。
「あ、はい。なんですか?」
「乗馬でよろしいですか?」
騎士様が再度丁寧に問う。声に出さない失礼な事を思われているのに実に優しい。
「はい。えっと、乗った事はありますが」
我ながら自信の無い声である。本当にここ数年は移動はずっと馬車だった。だって淑女なんだからそうしなさいと皆が――
「ではこちらのウイッカをお使い下さい」
そう言ってカーリャが示す。その先のちょっと離れた所に昨日も見た二頭の馬がおり、ロドがついていた。客人の馬の世話役だろう。乗馬は貸してくれるらしい。
「よろしく」
あらかじめ言っておいたのか、それだけでロドが手綱を引いて白い方の馬を連れてきた。中くらいの大きさの牝馬だ。
「これは大人しく賢い牝馬です。ナディさ……殿にはよろしいかと」
騎士様の言う通りに大人しそうな馬だった。葦毛の毛並みも綺麗でよく手入れされているのがわかる。目も大きくて優しそうだ。
「こ、この子ですか?」
そう見るとナディの心がむくむくと沸き上がってきた。室内派の癖に基本的にお調子者なのである。最初の怯えも消えて、すごい久しぶりのはずなのに乗ってみたくなっていた。
「噛みついたりしませんか?」
「大丈夫です」
「蹴っ飛ばされたりとかは?」
「……多分」
素人そのもののナディの質問に真面目に答える騎士様である。なんか和やかだと見ている数人は思っただろう。
「ただ舐めるのが好きですけど」
「はあ」
騎士様がロドから手綱を受け取る。馬に慣れた青年は何故か頬を赤くしていた。騎士様の美貌にあらぬ勘違いをしているのかも知れない。
「どうぞ」
そして手綱をしっかり握り、馬を安定させてからナディに勧める。ナディは恐る恐る近づいた。近くで見ると中々大きい。でも白い毛並みが本当に綺麗。大きめの鞍が乗せられ、そこには下から――
「猫ちゃん?」
「あ、ラージャ」
あの太め大きめの猫が鎮座していた。影にいたのか、音もなく飛び乗ったのだ。ナディと目が合う。
お前かい
確かにそう言われた気がした。
「ラージャ。そこはナディ殿が乗られるのだ」
やや慌てた騎士様が手を伸ばしてラージャを抱えようとする。だが、やだ! とばかりにラージャは鞍にしがみついた。
「ラージャ!」
「あ、あの。わたしは構いませんよ」
見かねてナディが言った。別に嫌ではない。鞍は十分に大きくて、前にちょこんとくらいに乗せられそうだ。それにそのもふもふにも触ってみたい。
「しかし」
「猫ちゃ……ラージャが嫌でなければ」
「……はあ」
そう言われてちょっと困った顔になった騎士様だが、それ以上は言わなかった。確かにラージャはこの旅行中、鞍先に乗ったり、荷物やカーリャの懐にもぐり込んだりしているのだ。利口な奴だから、このお嬢様の番も出来るかもと思ったのだ。
「では」
手綱を握ったまま再度、勧める。ナディは鞍の前に立って、え~~とと固まる。確か、鞍の前にある握り部を掴んで身体を引き上げて――
「え、えっと」
左手で掴んだ。右手を鞍の後部にかける。身体を引き上げて……上がらない。
「ナディ殿。ちょっと離れて」
すぐにも騎士様が動いた。ナディを制止し、目の前で片膝をつく。次に手の指を組み合わせ、籠のように膝の高さに差し出した。
「どうぞ」
ここに左足を乗せろと言うのだ。そう言う作法はナディも知っている。あくまで本の図で見ただけで、こんなに近くで、さらに足で他人の、それも殿方の掌を踏むと言うのに思わず躊躇してしまう。
「さあ」
だが騎士様は容赦ない。これが自分の責務かの様に真面目に言う。ナディの感じた乙女らしい遠慮や羞じらいは無視するのか、わからないのか。
「ナディ殿」
「は、はい」
再度言われて抗えなかった。そっと半長靴の足を乗せる。痛いかもと案じた瞬間、ぐい! と身体が浮いた。すごい力で馬の上までいく。短い悲鳴を上げてナディは鞍の上にすとんと落ちた。
「お見事」
決して本気ではない声で騎士様が言った。その証拠に馬が動かない様に鞍ごとナディの身体を支える。踏んづけた次には抱かれる形になってナディはもっと大きな悲鳴を上げた。鞍の前のラージャが急いで飛び退いたが、それに気付きもしない。
「お静かに。大丈夫です」
騎士様は落ち着いていた。子供に苦い薬を無理矢理飲ます医師の様に淡々とナディを支え、手綱を引く。鞍上の小騒ぎに愛馬は微動だにしない。さすが調教が出来ている。
「大丈夫ですね」
馬からしばし遅れてナディが落ち着いたのを確認してから騎士様は身体を離した。今更ながらにナディの胸がドキドキ動揺している。落ち着けわたし。ちゃんと騎乗出来たんだから。急に抱き抱えられてちょっと驚いただけなんだから。
「なんて見事な牝馬捌き」
叔母が向こうで何か言っている。ナディには意味がわからない。
「ナディ様にはこれで行っていただくとして。ウイッカが慣れる迄はわたしが轡を取りましょう」
要するに騎士様は馬の横について制御をしてくれると言っているのだ。助かったとナディは思う。騎乗出来たとは言え、今でも鞍にしがみつきたい余裕の無さだ。さすがにそれは恥ずかしい。道行く他人から指さして笑われるだろう。慣れる迄なんて言わずにアルトバイン迄そうして欲しい。
「ナディ殿のお荷物は?」
騎士様が声をかけるとポリーヌとカチャがそれぞれ鞄と包みを両手に抱えてえっちらおっちら持ってきた。初めての泊旅行と言う事で張り切って詰めていたから、重いのだろう。
「お預かりします」
騎士様はそれを受け取ると片手で重さを確かめる。え? そんな軽そうに? とメイド達が驚く前で革紐で二つをつなぎ合わせ、そのままひょいと馬の背――鞍の後ろに上げた。振り分けで乗せる。手慣れたものだった。
「アンティオ!」
騎士様はもう一頭を呼ぶ。大柄な黒馬はそれだけでゆっくりと歩んできた。蹄鉄が玄関前に敷き詰められた煉瓦を鳴らす。
「あっ」
その音にそっと振り返ったナディはラージャが黒馬の鞍に座っているのを見つけた。いつの間に。
そして黒馬は既にかなりの荷物を負っていた。鞍の前後の左右に振り分けとお尻の手前に大きな山が見える。棒状のものもあり、これがカーリャの旅支度なのだろうか。
「よしよし」
騎士様はその荷物の中から革紐を取り出すと黒馬の手綱をナディの乗っている白馬の鞍の後ろとでつなげた。これで移動するのか。慣れている様で馬達は平気でいる。
「では男爵閣下。ご夫人」
「あ、ああ」
手綱を持ち、皆に向いて恭しく片膝をついた騎士様に急に呼ばれて、叔父がようやく声を出す。あまりの手際の良さにぽかんと見とれていたのだ。下手くそと大きな荷物をちゃんと馬に乗せ、出発の準備を整える作業を誰の手も借りずにさっさとやってしまった。なかなかに有能である。モルガンやロドですら感心していた。
「あなた。あれを」
「あ、そうだった」
叔母に短く注意されて叔父は思い出した。並んで見ていた執事に掌を数度振る。こちらは忘れずに待ち構えていたので、執事は指示通りに用意されていた小さめの革袋をいそいそとカーリャに差し出した。
「姪が世話になる。リィフェルト卿。大した額でもないが足しにしてくれ」
えへんと叔父が言う。路銀だろう。一瞬、騎士様はどうしようかと言う顔になったが、男爵が出したものを断るのも悪いと思った様で、恭しく受け取った。その際に執事が小声で「銀貨を多めで」と付け加える。執事なりの配慮だった。意味がわかった騎士様も小さくうなずく。
「ナディ殿のことはお任せを。行って参ります」
最後に見送りの皆に帽子をとって深々と一礼する。実に見事な態度だった。その隣では手綱を取られた白馬の上でナディがあわあわと身体を揺らしていた。動き出したので怖い。馬の首に抱きつきそうである。
「こら、ナディ。あなたも何か言いなさい」
「は、はいぃぃ」
怖いのだ。馬の上って結構高い。まだゆっくりなのに馬の脚が動く度にぐらぐらする。鐔広の帽子が夏の扇子の様に大揺れだ。
「ナディ」
叔母の声が呆れていた。ああ、と他の皆からも溜め息が漏れる。大丈夫? ナディ様。アルトバインまで持つ?
「い、行ってきまぁすぅっ」
それでも何とかそう叫んで、でも顔も向けることすらも出来ずにナディは出発したのだった。
「大丈夫でしょうか」
お嬢様と騎士が玄関から立ち、門を抜けて王都の街並みにゆっくり紛れて行くのを男爵と夫人と執事は並んで最後まで見届けていた。
「わたしは今でも心配です。確かにしっかりとした若者でしたが」
モルガンが溜め息をつくように言う。立場上、断固として反対出来なかった。旦那様らに逆らいはしないが、でもなんと言ってもナディ様である。知識豊富な世間知らずはどうしても安心出来ない。
「大丈夫なんじゃない? 何とかなるわよ」
エロイーズの言い様は忠実な執事にも無責任に聞こえた。いや、この方の賢明さは知ってはいるが。
「いやまあその。ナディもあの」
実は全く優柔不断だったのはジェルマである。何せ昨日はいい気分で酔っぱらって眠りこけてしまい、早朝に起こされてようやく今の事態をエロイーズに聞いたのだ。
自分もリンツ卿も昨日に納得した決定事項として。
「あの子は賢いから大丈夫です。それにあの綺麗なカーリャ様ですもの。お似合いの二人ですわ」
「そ、そうかな」
旦那様と奥様の会話を横で聞いているモルガンは言いたい。昨日は絶対にそんな話ではなかった。覗いていたカチャの報告ではナディは初対面でふっていたし、その後の昼食会でもそんな話にはならなかった。
「憧れの殿方と二人きりでの時間を過ごす。ああ、なんて浪漫な。まるで本物の歌劇でも見ているよう」
いや、奥様? とモルガンは口の端がぴくぴく動く。なんの流れかで騎士がアルトバインに行く話になり、それに奥様がけしかけたナディ様が何故か同行に納得したのだ。この縁談には無礼なくらいに意固地だったはずなのに。今でもその理由がさっぱりわからない。
「ま、まあそうだが。でも嫁入り前の娘がだがなあ」
そうです。不謹慎です。慎みがありません。そこの処はもっと強く言って下さい。旦那様。
「あら、いいじゃないですか」
いいわけない。これでリィフェルト卿との縁談が成就しないと、うちのナディ様が良くない噂を立てられてしまう。既にうちの使用人達にも『婚前旅行』とか言う、実にはしたないお話として流れているのだ。
「わたしだってあなたと初めてお会いした時には、一緒に何処か遠くへ連れて行って欲しかったですわ」
「エロイーズ……」
ああ、駄目だとモルガンは嘆息する。こうなったら旦那様は終わりだ。その方向には弱い。この奥様が先の家で離婚するまで独身で待っていたくらいだからなあ。ほら、もう完全に奥様の掌の上だ。感動の余りにすぐにも身体が動いている。
「あなた。まだ、ほら。皆が見ているし」
「愛しているよ。エロイーズ」
主のある意味幸せな光景から遠慮して目を逸らしながら、モルガンはお嬢様と騎士の行く末に加護あれと心から神に祈ったのだった。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

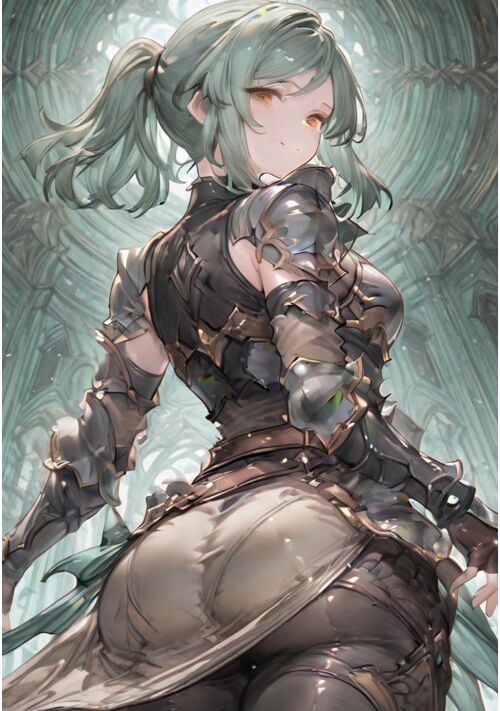
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?

相続した畑で拾ったエルフがいつの間にか嫁になっていた件 ~魔法で快適!田舎で農業スローライフ~
ちくでん
ファンタジー
山科啓介28歳。祖父の畑を相続した彼は、脱サラして農業者になるためにとある田舎町にやってきた。
休耕地を畑に戻そうとして草刈りをしていたところで発見したのは、倒れた美少女エルフ。
啓介はそのエルフを家に連れ帰ったのだった。
異世界からこちらの世界に迷い込んだエルフの魔法使いと初心者農業者の主人公は、畑をおこして田舎に馴染んでいく。
これは生活を共にする二人が、やがて好き合うことになり、付き合ったり結婚したり作物を育てたり、日々を生活していくお話です。

おばさんは、ひっそり暮らしたい
波間柏
恋愛
30歳村山直子は、いわゆる勝手に落ちてきた異世界人だった。
たまに物が落ちてくるが人は珍しいものの、牢屋行きにもならず基礎知識を教えてもらい居場所が分かるように、また定期的に国に報告する以外は自由と言われた。
さて、生きるには働かなければならない。
「仕方がない、ご飯屋にするか」
栄養士にはなったものの向いてないと思いながら働いていた私は、また生活のために今日もご飯を作る。
「地味にそこそこ人が入ればいいのに困るなぁ」
意欲が低い直子は、今日もまたテンション低く呟いた。
騎士サイド追加しました。2023/05/23
番外編を不定期ですが始めました。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















