1 / 1
偶然で必然
しおりを挟む
ある冬の静かな雨の夜。行きつけの喫茶店で、いつもの席でいつものコーヒーを飲みながらお気に入り本を読んでいた。カランコロンとレトロな音とともに開いたドアの後ろには、少し濡れた長い黒髪を風で揺らした、とても綺麗な女性がいた。そそくさと店に入り僕の一つ隣のカウンター席に座った。
「私もあれください。」
そう言って人差し指でさしたのは僕のもっているコーヒーカップだった。一瞬だけ目が合うと胸が締め付けられるという久しぶりな感じを味わった。
彼女と笑顔を交わして、一気にコーヒーを飲みほす。
「今日はいつにも増して寒いですね。」
彼女は出てきたコーヒーカップで両手の指先を温めるような仕草をしながらそう言った。ふと、自分に言っていると気づき読んでいた本を置いて、とっさに返事を返した。
「いっそのこと雪とか降って会社が休みになってくれればいんですけどね…。」
小さく笑いながら小学生のような弱音を吐いた。彼女も微笑みながら「そうですね。」と答えた。
「えっと…、お仕事は何をされているんですか?」
「あー、僕は普通のサラリーマンですよ。…あなたは?」
「私は…売れない小説家です。」
苦笑いをしながら彼女は言った。
「本は出版されているですか?」
「まぁ、一応何冊か出させていただいています。」
「へー、ちなみに名前は?」
「桐島 葉月です。」
どっかで聞いたことのある名前だなと、考えながらさっきまで読んでいた本に視線を落とした時、表紙に書いてあった名前が頭の中で一致した。
「えっ!?この本、書いた人って…?」
「はい、私ですよ。自分の書いた本を読んでいらっしゃったので、つい、舞い上がって声をかけてしまいました。」
ふふっと笑う彼女の顔はとても無邪気でかわいかった。
その後、何度か会うようになり、会う度に色んなことを話すようになっていった。
街はいつの間にかクリスマス色に囲まれていつもより少しだけ騒がしい(相変わらずうるさいのは変わらないが)。
人と人の隙間を縫って歩き、小さな道に入る。一気に静かになり、ちょっと歩くとあのいつもの喫茶店がある。また、彼女に会える。と、ワクワクしながら扉を開ける。
───カランコロン
中に入ってキョロキョロ見回すと奥の方に彼女はいた。こちらに気づいたらしく、小さく手を振ってくれる。今日はいつもより話したいことがたくさんあった。彼女いるテーブル席の向かい側に座り、まず一つ目の話題を振った。
「そういえば、新作出てましたね!買っちゃいました!!」
「…ありがとうございます。読んでくれましたか?」
なぜか、彼女は少しおどおどしたような表情でそう言った。
「? さっき買ったので、まだ読んでませんけど…帰りの電車で読もうかな…と思ってます。」
「そうですか…。楽しんでもらえたらいいのですが…。」
「いえいえ!毎回桐島さんの作品には楽しませてもらっていますよ!だから、今回もすごく楽しみなんです。」
不安そうな彼女の顔はあまり変わらなかったが、それでも小さく笑いながらたくさんの話をした。ふと腕時計に目を向けると針は22時過ぎを指していた。目を疑いながらみた窓の外は月明かりが建物の影を作っていた。
「あっ!もうこんな時間!つい、あなたと喋っていると時間を忘れてしまいますね。今日はありがとうございました。」
彼女はそう言いながら帰る準備をし始めた。僕はスマホをのロック画面を開いてから、今日の1番大事な目的を忘れていたことに気づく。
「あ、あの!えっと…その……メアド交換しませんか?せっかくなんで…。」
やっと言えた。毎回、会うたびに言おうとするのに、話に夢中になって言えなくなるから、今日こそっと思って、スマホのロック画面に『メアド』と書いたメモが見えるようにしておいて正解だった。
「いいですよ。あっ、でも、もし良ければLINEの交換もしませんか?そっちの方がいろいろ便利ですし。どう…ですか…?」
「もちろんです!むしろ、嬉しいです!!」
2人でスマホを出して交換した。追加ボタンを押した。彼女のほうからスタンプでよろしくと来たので僕もスタンプでよろしくと返す。顔を見合わせながら笑って、「ありがとうございます」と言う彼女の笑顔は、さっきまでの不安そうな顔をかき消すくらい眩しく、可愛かった。
カフェの最寄り駅まで一緒に話しながら歩く。距離がないから、話す内容も少なくる。ホームは違うから改札を出てすぐに分かれることになる。彼女はペコっと頭を下げ、「本当にありがとうございました」と言って、階段のあるほうへ行った。僕も階段を上って前のホームを見ると笑顔でこっちを見る彼女がいた。先に僕のほうの電車が来たので、乗り込んでから、彼女に手を振ってから、椅子に座り今日買った新作を出して読み始める。この電車の終点に近いところで降りるため、約3、40分はかかる。このくらいあれば文庫本は読み終えてしまう。しかも、これは短編集なので長編より早く読むことができる。
新作の題名は『本当の恋』
─────主人公の女性は一目惚れという恋はありえない。そう思っていた。女性自身の思う恋とは性格も知ったうえで好きになることで、一目惚れとは、外見だけの判断にすぎない。だから、一目惚れはルックス重視の遊びのための恋だと思っていた。 そんなある日、突然の雨で傘を忘れた女性は近くにあった、喫茶店に足を踏み入れた。そこは趣味に合っていてとても好みな店だった。近くのカウンターに座り隣の隣にいる男性が飲んでいるコーヒーを指差し、カウンターの奥にいるマスターらしき人に注文する。男性は本を読んでいた。男性が読んでいる本の表紙を見たとき、なぜか急に胸が苦しくなって「わたし、その本好きなんです!」と言葉が不意に出てきた。そのまま、本の話で意気投合した。その後、喫茶店に行くのが楽しみになった。最後、後悔するとも知らないで。
と、一番最初の物語が終わった。すごい不思議で中途半端な終わり方だと感じた。そして、どこか僕の彼女との出会いに似ているようなそんな気がした。
残り5本ほどの短編を読み終えると、ちょうど、家の最寄り駅に着いた。
LINEを使って彼女に感想を書き、送信をする。
『新作面白かったです!特に三本目のミステリーっぽいところとか!楽しく読ませていただきました!!』
早い段階で既読がついた。
『そうですか!よかったです(ホッとしている絵文字)』
『それと、一本目の物語も自分の出会いに少し似ていました!でも、終わり方がすごくモヤモヤする感じだったんですけど…?』
1番言いたかったことを書いて送信する。
『それなら、まだ終わってないんです…』
すぐに返ってきたその返信を見て不思議に思う。
『それは、どういう意味ですか?』
恐る恐る打ち送信。
『今度話します。次、喫茶店で会った時にでも。』
次に会うときはきっとすぐだろうと思っていたのもつかの間。そのメールをした翌日に課長から大きな仕事を任されてしまい、あの喫茶店へ行くことがなくなってしまった。
あのメールから、一ヶ月。ようやく仕事が落ち着いてきたから、あの喫茶店へ行くことにした。出来るだけ早く切り上げて、扉の前に着いたのが丁度20時。
カランコロン…。懐かしい響きを耳にしながら奥へ進むと、彼女の後ろ姿が見えた。彼女は僕たちがいつも話していた席で僕のお気に入りのコーヒーを飲みながら、大学ノートになにかを書いていた。マスターにコーヒーを頼み、彼女の前の椅子を引いて静かに座った。
数分してマスターがコーヒーを運んでテーブルに置いた。彼女は初めて顔を上げて僕の顔を見た。これまで、集中して気づかれていなかったみたいだった。
「こんにちは。新しい作品ですか?」
少しぎこちない感じで彼女に話しかける。彼女は驚きながら、ペンを置いてコーヒーを一気に飲んだ。
「こ、こんにちは、気付かないですみません。これは、ただの設定ですよ。小説のネタみたいなものです。」
見せたくなかったのか、ノートを閉めた。
「そういえば、最近なかなか会えませんでしたね。すれ違ってたのでしょうか。」
彼女は首を傾げた。
「いや、仕事の方が忙しくて一ヶ月ほどここに来てなかったんです。」
「そうだったんですか。」
「それが、その仕事がとても大きなもので!先週の金曜日に、プレゼンがありまして!…」
僕は、彼女に今回あった仕事の話をした。大きな仕事とは大手企業との重大な取引があり、その取引のプレゼンの資料作成、司会を務めることになった。これは、今後の給料とかにも関わる仕事だから、適当にやってられない。熱心にこれまであったことを話していると、彼女は時々相槌を打ったり、笑ってくれたりしてくれた。それから話が弾み、会っていなかった間、どんな事があったのか2人で話していた。ふと我に帰り時計をみる。やはり、時間が経つのが早い。針は22時を指していた。僕の行動に気づき、時計を見た彼女は
「もうこんな時間!また、話しすぎちゃいました。」
そう言って彼女は笑う。机に置いたままだったノートとペンをカバンにしまい、席を立とうとしたのをみて僕はとっさに彼女の腕をつかんだ。
「あ、すみません!つい…。」
パッと手を離し頭を下げる。
「えっと、今日は、この前のメールの話がしたくて…。話が随分曲がっちゃいましたけど…。」
そう言いながら頭をあげると、彼女は目をそらして顔を下げた。2人でゆっくり席に座り、数秒間沈黙が続く。
「…あの!」
「…あの!」
重なった言葉で少し場の空気が軽くなった気がした。今まで何度かこのようなことがあった時、彼女は絶対に最初に喋ろうとしない。つまり、僕が話し出さなければいけなくなった。
「メールの件で、その…。あの物語の終わりって…?」
きっと彼女も同じことを考えているのだろう。今日、この場所に来た一番の目的。彼女が真剣表情をする理由はまるでわからない。ただ、さっきまでの和んだ空気はもうどこにもない。
「そうでしたね。私、話すって言いましたしね。」
「…はい。」
彼女は深く息をはき、吸ったのと同時に話し出した。
「実は、あの作品私の実体験なんです。ある程度、変えてる部分もありますけど。だから、まだ、終わってないんです。いや、終わらせちゃダメなんです。私が、あの物語のラストを言わなきゃいけないんです。」
彼女は必死に言葉を探しながら僕に伝える。だけど、理解できず、尋ねる。
「言わなきゃ、いけない?」
「はい。あなたに、言わなきゃいけない事があるんです。」
一瞬の沈黙は今までで一番静かで重い。
「私、好きです。その…恋愛的な意味で。」
下に向けた顔は見えなかったが、耳はとても赤かった。
そして、僕は動揺し、すごく焦っている。
「えっと、その…。僕の事が…ですよね?」
こんなこと聞くのは流石に酷いとは思ったけど、一応、念のため、その言葉に確信を持ちたかった。
「はい。好きです。会った時からずっと。」
やはり、僕の聞き間違えではなかった。彼女のその言葉には真剣に答えなきゃいけない。あたりまえだ。
「僕も好きです。ただ、恋愛…とは違う意味で。それに、言いづらいんですが…」
続けて言おうとすると彼女は僕と目を合わせて話し始めた。
「知ってましたよ。あなたに、大切な家族がいること。初めて会った日、覚えてますか?」
「はい、雨がすごい降ってた日ですよね。」
「恥ずかしながら、あの日、初恋というものをしたんです。生まれてこの方、『恋』というものに無縁で、小説の中の空想上のものと思っていました。それに、一目惚れなんてもってのほか、まるで意味がわからないものだと自分から『恋』を遠ざけていました。ですが、そんな時、あなたと出会ったんです。無縁だと思っていた『一目惚れ』という言葉が素直に当てはまるそんな感情が芽生えたのです。でも、あなたと喋っていると、時々恋人らしき人の話をしたり、クリスマスイブの日には可愛くラッピングされたプレゼントをいくつも持っていたりして、きっと、結婚している女性がいて、子供も数人いるのだろう。と思ったのです。ただ、自分の気持ちをあやふやにしておくのが嫌だったので、ご迷惑を承知で素直に伝えることにしました。この気持ちにきっぱり縁を切るように。」
彼女は話し終えると、コーヒーを少し口に含んだ。これが、彼女が書きたかったあの物語のラストなんだ。僕は何も言えずただ、彼女の頬をつたう光を見ていた。彼女は僕と目を合わせないようにして、再び話し始めた。
「これが、私の思っていたこと全てです。時間を割いていただき、ありがとうございました。」
そう言って彼女は席を立ち、出口へ向かった。僕は言葉を探し、とっさに立ち上がり彼女に言った。
「えっと、まだ、最後じゃないと思います。きっと、次があります。その時また、ここに来てそういう話をしましょう!」
彼女は振り向かずに返す
「ありがとうございます。もっと早くにあなたに会っていたかったです。」
そのままドアを押し、帰って行ってしまった。喫茶店は少しだけいつもと違うような気がした。
それ以来、彼女の書く本は今までよりカラフルで深い作品になった。
僕たちは今日も、いつもと同じように、あの席であのコーヒーを飲みながら話すだろう。そして、時間を忘れていろんな話をするだろう。
「私もあれください。」
そう言って人差し指でさしたのは僕のもっているコーヒーカップだった。一瞬だけ目が合うと胸が締め付けられるという久しぶりな感じを味わった。
彼女と笑顔を交わして、一気にコーヒーを飲みほす。
「今日はいつにも増して寒いですね。」
彼女は出てきたコーヒーカップで両手の指先を温めるような仕草をしながらそう言った。ふと、自分に言っていると気づき読んでいた本を置いて、とっさに返事を返した。
「いっそのこと雪とか降って会社が休みになってくれればいんですけどね…。」
小さく笑いながら小学生のような弱音を吐いた。彼女も微笑みながら「そうですね。」と答えた。
「えっと…、お仕事は何をされているんですか?」
「あー、僕は普通のサラリーマンですよ。…あなたは?」
「私は…売れない小説家です。」
苦笑いをしながら彼女は言った。
「本は出版されているですか?」
「まぁ、一応何冊か出させていただいています。」
「へー、ちなみに名前は?」
「桐島 葉月です。」
どっかで聞いたことのある名前だなと、考えながらさっきまで読んでいた本に視線を落とした時、表紙に書いてあった名前が頭の中で一致した。
「えっ!?この本、書いた人って…?」
「はい、私ですよ。自分の書いた本を読んでいらっしゃったので、つい、舞い上がって声をかけてしまいました。」
ふふっと笑う彼女の顔はとても無邪気でかわいかった。
その後、何度か会うようになり、会う度に色んなことを話すようになっていった。
街はいつの間にかクリスマス色に囲まれていつもより少しだけ騒がしい(相変わらずうるさいのは変わらないが)。
人と人の隙間を縫って歩き、小さな道に入る。一気に静かになり、ちょっと歩くとあのいつもの喫茶店がある。また、彼女に会える。と、ワクワクしながら扉を開ける。
───カランコロン
中に入ってキョロキョロ見回すと奥の方に彼女はいた。こちらに気づいたらしく、小さく手を振ってくれる。今日はいつもより話したいことがたくさんあった。彼女いるテーブル席の向かい側に座り、まず一つ目の話題を振った。
「そういえば、新作出てましたね!買っちゃいました!!」
「…ありがとうございます。読んでくれましたか?」
なぜか、彼女は少しおどおどしたような表情でそう言った。
「? さっき買ったので、まだ読んでませんけど…帰りの電車で読もうかな…と思ってます。」
「そうですか…。楽しんでもらえたらいいのですが…。」
「いえいえ!毎回桐島さんの作品には楽しませてもらっていますよ!だから、今回もすごく楽しみなんです。」
不安そうな彼女の顔はあまり変わらなかったが、それでも小さく笑いながらたくさんの話をした。ふと腕時計に目を向けると針は22時過ぎを指していた。目を疑いながらみた窓の外は月明かりが建物の影を作っていた。
「あっ!もうこんな時間!つい、あなたと喋っていると時間を忘れてしまいますね。今日はありがとうございました。」
彼女はそう言いながら帰る準備をし始めた。僕はスマホをのロック画面を開いてから、今日の1番大事な目的を忘れていたことに気づく。
「あ、あの!えっと…その……メアド交換しませんか?せっかくなんで…。」
やっと言えた。毎回、会うたびに言おうとするのに、話に夢中になって言えなくなるから、今日こそっと思って、スマホのロック画面に『メアド』と書いたメモが見えるようにしておいて正解だった。
「いいですよ。あっ、でも、もし良ければLINEの交換もしませんか?そっちの方がいろいろ便利ですし。どう…ですか…?」
「もちろんです!むしろ、嬉しいです!!」
2人でスマホを出して交換した。追加ボタンを押した。彼女のほうからスタンプでよろしくと来たので僕もスタンプでよろしくと返す。顔を見合わせながら笑って、「ありがとうございます」と言う彼女の笑顔は、さっきまでの不安そうな顔をかき消すくらい眩しく、可愛かった。
カフェの最寄り駅まで一緒に話しながら歩く。距離がないから、話す内容も少なくる。ホームは違うから改札を出てすぐに分かれることになる。彼女はペコっと頭を下げ、「本当にありがとうございました」と言って、階段のあるほうへ行った。僕も階段を上って前のホームを見ると笑顔でこっちを見る彼女がいた。先に僕のほうの電車が来たので、乗り込んでから、彼女に手を振ってから、椅子に座り今日買った新作を出して読み始める。この電車の終点に近いところで降りるため、約3、40分はかかる。このくらいあれば文庫本は読み終えてしまう。しかも、これは短編集なので長編より早く読むことができる。
新作の題名は『本当の恋』
─────主人公の女性は一目惚れという恋はありえない。そう思っていた。女性自身の思う恋とは性格も知ったうえで好きになることで、一目惚れとは、外見だけの判断にすぎない。だから、一目惚れはルックス重視の遊びのための恋だと思っていた。 そんなある日、突然の雨で傘を忘れた女性は近くにあった、喫茶店に足を踏み入れた。そこは趣味に合っていてとても好みな店だった。近くのカウンターに座り隣の隣にいる男性が飲んでいるコーヒーを指差し、カウンターの奥にいるマスターらしき人に注文する。男性は本を読んでいた。男性が読んでいる本の表紙を見たとき、なぜか急に胸が苦しくなって「わたし、その本好きなんです!」と言葉が不意に出てきた。そのまま、本の話で意気投合した。その後、喫茶店に行くのが楽しみになった。最後、後悔するとも知らないで。
と、一番最初の物語が終わった。すごい不思議で中途半端な終わり方だと感じた。そして、どこか僕の彼女との出会いに似ているようなそんな気がした。
残り5本ほどの短編を読み終えると、ちょうど、家の最寄り駅に着いた。
LINEを使って彼女に感想を書き、送信をする。
『新作面白かったです!特に三本目のミステリーっぽいところとか!楽しく読ませていただきました!!』
早い段階で既読がついた。
『そうですか!よかったです(ホッとしている絵文字)』
『それと、一本目の物語も自分の出会いに少し似ていました!でも、終わり方がすごくモヤモヤする感じだったんですけど…?』
1番言いたかったことを書いて送信する。
『それなら、まだ終わってないんです…』
すぐに返ってきたその返信を見て不思議に思う。
『それは、どういう意味ですか?』
恐る恐る打ち送信。
『今度話します。次、喫茶店で会った時にでも。』
次に会うときはきっとすぐだろうと思っていたのもつかの間。そのメールをした翌日に課長から大きな仕事を任されてしまい、あの喫茶店へ行くことがなくなってしまった。
あのメールから、一ヶ月。ようやく仕事が落ち着いてきたから、あの喫茶店へ行くことにした。出来るだけ早く切り上げて、扉の前に着いたのが丁度20時。
カランコロン…。懐かしい響きを耳にしながら奥へ進むと、彼女の後ろ姿が見えた。彼女は僕たちがいつも話していた席で僕のお気に入りのコーヒーを飲みながら、大学ノートになにかを書いていた。マスターにコーヒーを頼み、彼女の前の椅子を引いて静かに座った。
数分してマスターがコーヒーを運んでテーブルに置いた。彼女は初めて顔を上げて僕の顔を見た。これまで、集中して気づかれていなかったみたいだった。
「こんにちは。新しい作品ですか?」
少しぎこちない感じで彼女に話しかける。彼女は驚きながら、ペンを置いてコーヒーを一気に飲んだ。
「こ、こんにちは、気付かないですみません。これは、ただの設定ですよ。小説のネタみたいなものです。」
見せたくなかったのか、ノートを閉めた。
「そういえば、最近なかなか会えませんでしたね。すれ違ってたのでしょうか。」
彼女は首を傾げた。
「いや、仕事の方が忙しくて一ヶ月ほどここに来てなかったんです。」
「そうだったんですか。」
「それが、その仕事がとても大きなもので!先週の金曜日に、プレゼンがありまして!…」
僕は、彼女に今回あった仕事の話をした。大きな仕事とは大手企業との重大な取引があり、その取引のプレゼンの資料作成、司会を務めることになった。これは、今後の給料とかにも関わる仕事だから、適当にやってられない。熱心にこれまであったことを話していると、彼女は時々相槌を打ったり、笑ってくれたりしてくれた。それから話が弾み、会っていなかった間、どんな事があったのか2人で話していた。ふと我に帰り時計をみる。やはり、時間が経つのが早い。針は22時を指していた。僕の行動に気づき、時計を見た彼女は
「もうこんな時間!また、話しすぎちゃいました。」
そう言って彼女は笑う。机に置いたままだったノートとペンをカバンにしまい、席を立とうとしたのをみて僕はとっさに彼女の腕をつかんだ。
「あ、すみません!つい…。」
パッと手を離し頭を下げる。
「えっと、今日は、この前のメールの話がしたくて…。話が随分曲がっちゃいましたけど…。」
そう言いながら頭をあげると、彼女は目をそらして顔を下げた。2人でゆっくり席に座り、数秒間沈黙が続く。
「…あの!」
「…あの!」
重なった言葉で少し場の空気が軽くなった気がした。今まで何度かこのようなことがあった時、彼女は絶対に最初に喋ろうとしない。つまり、僕が話し出さなければいけなくなった。
「メールの件で、その…。あの物語の終わりって…?」
きっと彼女も同じことを考えているのだろう。今日、この場所に来た一番の目的。彼女が真剣表情をする理由はまるでわからない。ただ、さっきまでの和んだ空気はもうどこにもない。
「そうでしたね。私、話すって言いましたしね。」
「…はい。」
彼女は深く息をはき、吸ったのと同時に話し出した。
「実は、あの作品私の実体験なんです。ある程度、変えてる部分もありますけど。だから、まだ、終わってないんです。いや、終わらせちゃダメなんです。私が、あの物語のラストを言わなきゃいけないんです。」
彼女は必死に言葉を探しながら僕に伝える。だけど、理解できず、尋ねる。
「言わなきゃ、いけない?」
「はい。あなたに、言わなきゃいけない事があるんです。」
一瞬の沈黙は今までで一番静かで重い。
「私、好きです。その…恋愛的な意味で。」
下に向けた顔は見えなかったが、耳はとても赤かった。
そして、僕は動揺し、すごく焦っている。
「えっと、その…。僕の事が…ですよね?」
こんなこと聞くのは流石に酷いとは思ったけど、一応、念のため、その言葉に確信を持ちたかった。
「はい。好きです。会った時からずっと。」
やはり、僕の聞き間違えではなかった。彼女のその言葉には真剣に答えなきゃいけない。あたりまえだ。
「僕も好きです。ただ、恋愛…とは違う意味で。それに、言いづらいんですが…」
続けて言おうとすると彼女は僕と目を合わせて話し始めた。
「知ってましたよ。あなたに、大切な家族がいること。初めて会った日、覚えてますか?」
「はい、雨がすごい降ってた日ですよね。」
「恥ずかしながら、あの日、初恋というものをしたんです。生まれてこの方、『恋』というものに無縁で、小説の中の空想上のものと思っていました。それに、一目惚れなんてもってのほか、まるで意味がわからないものだと自分から『恋』を遠ざけていました。ですが、そんな時、あなたと出会ったんです。無縁だと思っていた『一目惚れ』という言葉が素直に当てはまるそんな感情が芽生えたのです。でも、あなたと喋っていると、時々恋人らしき人の話をしたり、クリスマスイブの日には可愛くラッピングされたプレゼントをいくつも持っていたりして、きっと、結婚している女性がいて、子供も数人いるのだろう。と思ったのです。ただ、自分の気持ちをあやふやにしておくのが嫌だったので、ご迷惑を承知で素直に伝えることにしました。この気持ちにきっぱり縁を切るように。」
彼女は話し終えると、コーヒーを少し口に含んだ。これが、彼女が書きたかったあの物語のラストなんだ。僕は何も言えずただ、彼女の頬をつたう光を見ていた。彼女は僕と目を合わせないようにして、再び話し始めた。
「これが、私の思っていたこと全てです。時間を割いていただき、ありがとうございました。」
そう言って彼女は席を立ち、出口へ向かった。僕は言葉を探し、とっさに立ち上がり彼女に言った。
「えっと、まだ、最後じゃないと思います。きっと、次があります。その時また、ここに来てそういう話をしましょう!」
彼女は振り向かずに返す
「ありがとうございます。もっと早くにあなたに会っていたかったです。」
そのままドアを押し、帰って行ってしまった。喫茶店は少しだけいつもと違うような気がした。
それ以来、彼女の書く本は今までよりカラフルで深い作品になった。
僕たちは今日も、いつもと同じように、あの席であのコーヒーを飲みながら話すだろう。そして、時間を忘れていろんな話をするだろう。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

【完結】20年後の真実
ゴールデンフィッシュメダル
恋愛
公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。
マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。
それから20年。
マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。
そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。
おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。
全4話書き上げ済み。

【完結】仲の良かったはずの婚約者に一年無視され続け、婚約解消を決意しましたが
ゆらゆらぎ
恋愛
エルヴィラ・ランヴァルドは第二王子アランの幼い頃からの婚約者である。仲睦まじいと評判だったふたりは、今では社交界でも有名な冷えきった仲となっていた。
定例であるはずの茶会もなく、婚約者の義務であるはずのファーストダンスも踊らない
そんな日々が一年と続いたエルヴィラは遂に解消を決意するが──
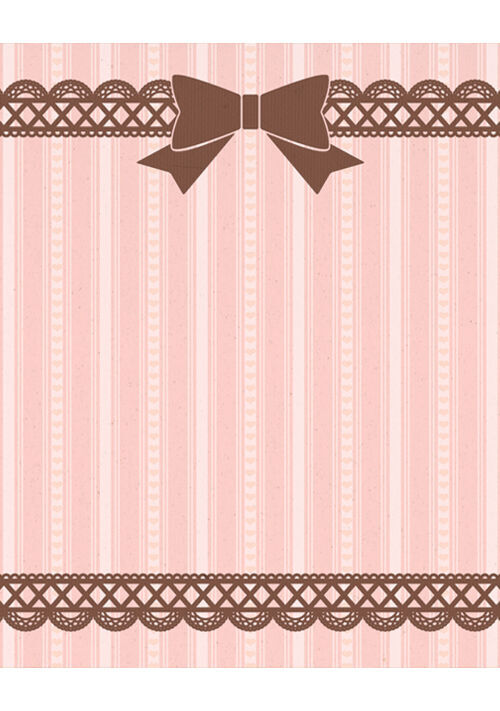
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」

つまらない妃と呼ばれた日
柴田はつみ
恋愛
公爵令嬢リーシャは政略結婚で王妃に迎えられる。だが国王レオニスの隣には、幼馴染のセレスが“当然”のように立っていた。祝宴の夜、リーシャは国王が「つまらない妃だ」と語る声を聞いてしまい、心を閉ざす。
舞踏会で差し出された手を取らず、王弟アドリアンの助けで踊ったことで、噂は一気に燃え上がる――「王妃は王弟と」「国王の本命は幼馴染」と。
さらに宰相は儀礼と世論を操り、王妃を孤立させる策略を進める。監視の影、届かない贈り物、すり替えられた言葉、そして“白薔薇の香”が事件現場に残る冤罪の罠。
リーシャは微笑を鎧に「今日から、王の隣に立たない」と決めるが、距離を取るほど誤解は確定し、王宮は二人を引き裂いていく。
――つまらない妃とは、いったい誰が作ったのか。真実が露わになった時、失われた“隣”は戻るのか。

蝋燭
悠十
恋愛
教会の鐘が鳴る。
それは、祝福の鐘だ。
今日、世界を救った勇者と、この国の姫が結婚したのだ。
カレンは幸せそうな二人を見て、悲し気に目を伏せた。
彼女は勇者の恋人だった。
あの日、勇者が記憶を失うまでは……

失った真実の愛を息子にバカにされて口車に乗せられた
しゃーりん
恋愛
20数年前、婚約者ではない令嬢を愛し、結婚した現国王。
すぐに産まれた王太子は2年前に結婚したが、まだ子供がいなかった。
早く後継者を望まれる王族として、王太子に側妃を娶る案が出る。
この案に王太子の返事は?
王太子である息子が国王である父を口車に乗せて側妃を娶らせるお話です。

悪役令嬢は手加減無しに復讐する
田舎の沼
恋愛
公爵令嬢イザベラ・フォックストーンは、王太子アレクサンドルの婚約者として完璧な人生を送っていたはずだった。しかし、華やかな誕生日パーティーで突然の婚約破棄を宣告される。
理由は、聖女の力を持つ男爵令嬢エマ・リンドンへの愛。イザベラは「嫉妬深く陰険な悪役令嬢」として糾弾され、名誉を失う。
婚約破棄をされたことで彼女の心の中で何かが弾けた。彼女の心に燃え上がるのは、容赦のない復讐の炎。フォックストーン家の膨大なネットワークと経済力を武器に、裏切り者たちを次々と追い詰めていく。アレクサンドルとエマの秘密を暴き、貴族社会を揺るがす陰謀を巡らせ、手加減なしの報復を繰り広げる。

~春の国~片足の不自由な王妃様
クラゲ散歩
恋愛
春の暖かい陽気の中。色鮮やかな花が咲き乱れ。蝶が二人を祝福してるように。
春の国の王太子ジーク=スノーフレーク=スプリング(22)と侯爵令嬢ローズマリー=ローバー(18)が、丘の上にある小さな教会で愛を誓い。女神の祝福を受け夫婦になった。
街中を馬車で移動中。二人はずっと笑顔だった。
それを見た者は、相思相愛だと思っただろう。
しかし〜ここまでくるまでに、王太子が裏で動いていたのを知っているのはごくわずか。
花嫁は〜その笑顔の下でなにを思っているのだろうか??
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















