6 / 33
無粋プロポーズ1
しおりを挟む
とがった耳をピクリピクリと震わせる愛らしい娘――それがルシア・カントールだった。
最初は生後数日といったところだが、今はなんと5ヶ月ほどの姿に成長している。
なんと言っても、成長スピードが異様にはやいのだ。
むちむちとした手足をばたつかせ、あーうーと声をあげる。
「ん? どうした、ルシア」
ミルクの用意をしながら、声をかけるルイトの姿もまた様になりつつあった。
人は順応というか、慣れる生き物らしい。
最初はおっかなびっくりで慌てふためいていた育児も、いくつもの力を借りてこなせるようになってきた。
とはいえ、驚くべきはこの子どもの成長スピードと発達。あと、育てやすさだ。
「コノ子、つくづく親孝行ヨ」
そう言いながら、換えのオムツをもって現れた大柄な身体。
「おはよう、ロロ」
「そろそろ出かける時間デショ? ほら、荷物はそろえといたネ」
「いつもすまないな」
オムツを替える手つきすら、すっかり父親だ。
人間、やればなんとかなるとルイトは感慨深く思っていた。
(こうしてみると可愛いんだよなァ)
自分に似た色の瞳をぱちくりさせて、むにゃむにゃと何事か語りかけているような口元。
ぷにぷにとしてやわらかい曲線を描く頬を、そっと指先でなでる。
「あぅぅ、ぅ? 」
「そうだぞ。パパ、今日もお仕事だ」
「うぁぁぅ……」
「すねるなよ。危ないから、今日はセトのとこに行こうな?」
まるで会話しているかのようだ。
まだ言語も理解していないだろう赤ん坊だが、ルシアはこちらの言葉を分かったように聞く。
ルイトもまた、彼女の声や表情から少しずつ感情を読み取れるようになっていた。
あれから二週間とは思えない、脅威の変化である。
「すっかりパパ、よネ」
「よせやい」
ロロに冷やかされ、視線をそらす。
自分でも戸惑うくらいに、娘に対して得体の知れない質量の愛情が湧いてくる。それが日増しに大きく強くなるのだから、なおのこと不思議だった。
最初は壊れそうで怖かったこの小さな存在も、それが愛しいに変わるのだから面白い。
とはいえ夜泣きもそこそこするもので、寝不足で泣けてくることも無くはない。でもそれを差し引いてもオツリが来るくらい、この幼子は可愛いかった。
「悪いネ、ほんとならワタシが――」
「いやいや。いつもありがとう、ロロ」
ルイトは片手をあげて微笑んだ。
自分に隠し子が、と打ち明けたとき。彼女は一瞬だけ目を見開いた。
『#$Δζζ♩м……』
異国の言葉で、それが彼女の生まれ故郷のものだという事をルイトは知らない。
ただ予想に反して、彼女が彼の育児の手助けを率先して手伝い始めたことが驚きだった。
ミルクやらオムツ、服をそろえるだけでなく。冒険者の仕事に復帰した彼のために、託児も買ってでたのだ。
今では、ロロか。彼女の都合が悪ければ、酒場の主人セトと店員女の子たちが交代で面倒みてくれる。
文字通り、多くの人の手でこの子は育てられている。
皆は、ルイトの子だということを驚きつつも受け入れてくれたからだ。
(まぁぶちのめされないだけ、よかった)
「じゃ、そろそろ行ってくるよ」
背中におんぶ紐を使い、ルシアを背負う。
「行ってらっシャイ。η♩ζ$$м」
厳つい顔だが優しい目で異国の言葉をつぶやく彼女の眼差しに、ルイトは小さくうなずいた。
(ロロも、ああ見えて子供好きなんだな)
などと思いながら。
※※※
「さて、と」
背中に負っていた大剣は、しまい込んだ。
今は腰につけた太刀をふるうのが、彼のスタイルとなっている。
そうでないとこのおんぶ紐も付けられないし。万が一、ルシアにケガでもさせたら大変だから。
思考がすでに母親だ、なんてセトからは揶揄われたが鼻で笑っておく。
「とりあえず即日でこなせる依頼をくれ」
スマートにカクテルを注文するのも面倒で、カウンターの向こうの女性に声をかけた。
「かしこまりました。少しお待ちを」
彼女はわずかに眉をよせたが、すぐに手元の羊皮紙の束に視線を落とす。
相変わらず無機質かつ、人形めいた表情にむしろ安堵すらした。
その時――。
「よォ、久しぶりじゃん。ルイトちゃん」
「また君か。その呼び方やめろって、いつも言ってるだろ」
「アハハ。まぁまぁ、そう怖い顔すんなよ。べっぴんさんが台無しだぜェ?」
「っ、さわんな」
馴れ馴れしく隣に座り、肩に腕を回してくる男。
ランス・ロンドは拒まれても、くすんだ赤髪をかきあげてニヤついている。
またそれがカンに触った。
「ほんと、ジャジャ馬だよなァ。でも、そーゆートコも愛してるよン♡」
「笑えもしないどころか、虫唾が走る冗談だな」
身体を密着させんとグイグイ寄ってくる男に、殺意のかたまりのような視線を投げて寄越す。
だがいっこうに効果はないらしい。
「なぁなぁなぁなぁ」
「……しゃべるな、バカ」
「ひっどぉい! ってか。ルイトってば、みずくさいんじゃねーの」
「ハァ?」
いまだクエストが提示されないのにイライラしつつ、ため息をつく。
はやいところ、仕事を決めてこの場を去りたい。しかし何かを手間取っているのか、受付嬢は黙って羊皮紙をめくっている。
「女の子だってね、ルイトちゃんの隠し子」
「隠してない。それに君には関係ないだろ」
「もー、またそんなツレナイことを」
そんな素っ気ない返事も一笑し、ランスは言葉を続けた。
「相手は誰?」
「それこそ君には関係ない」
「ふーん。ま、いいけどねェ」
そこで、突然彼は表情を変える。
「ねぇルイト」
真剣な顔。
そして、やにわに掴まれた肩にルイトは顔をしかめた。
「は、離せよ」
「ルイト」
「だから離せって!」
「……コブ付きでも、オレなら幸せに出来るから」
(は?)
何を言い出すかと思えば。
あまりの言葉に意味を理解しかねて絶句する。
そんな彼に、今度は耳元でささやく。
「お前の子なら、きっと美人に育つだろうな。オレと一緒に、子育てしよう? 絶対に幸せにするからさァ」
「な……な……な……」
「他のヤツに渡したくねぇんだよ」
(まさかコイツ!?)
ルイトの頭に、衝撃的 (または見当違い)な考えがよぎった。
(うちの娘をモノにするつもりかーッ!!!)
一気に血が上る。
よりにもよって、大事な娘を頂こうとする不届き者に怒りのボルテージが爆上がりしたのだ。
「こんのっ、ロリコン野郎がァァァッ!!!」
「ブヘッ!?」
無防備な腹部に、渾身の一撃が肘鉄となって炸裂。
くぐもった呻き声と共に、ランスはイスごと後ろに転げ落ちる。
「ろ、ロリコンって……」
「ぺド野郎と言い直してやろうか。この変態」
忌々しげに舌打ちして、あ然とした顔で見上げる男に吐き捨てた。
「うちの娘を、貴様になんてやらんっ!」
「そ、そういう意味じゃ――」
ちょうどタイミングよく。差し出された依頼書をひったくるように手にして、ルイトは足早にギルドを後にする。
後ろで響く。
『ルイトぉぉぉぉっ、結婚してくれぇぇぇッ!!!』
という悲痛な叫びのような告白も、耳に入らない。
夢にも思わないだろう。
シングルファーザーとなった自分に、同業者でライバル。しかも、日頃からいけ好かないヤツが突然プロポーズしてくるなんて。
(僕が、娘を守らないと)
またひとつ。ルイト・カントールの、愛娘に対する愛を深めただけであった。
最初は生後数日といったところだが、今はなんと5ヶ月ほどの姿に成長している。
なんと言っても、成長スピードが異様にはやいのだ。
むちむちとした手足をばたつかせ、あーうーと声をあげる。
「ん? どうした、ルシア」
ミルクの用意をしながら、声をかけるルイトの姿もまた様になりつつあった。
人は順応というか、慣れる生き物らしい。
最初はおっかなびっくりで慌てふためいていた育児も、いくつもの力を借りてこなせるようになってきた。
とはいえ、驚くべきはこの子どもの成長スピードと発達。あと、育てやすさだ。
「コノ子、つくづく親孝行ヨ」
そう言いながら、換えのオムツをもって現れた大柄な身体。
「おはよう、ロロ」
「そろそろ出かける時間デショ? ほら、荷物はそろえといたネ」
「いつもすまないな」
オムツを替える手つきすら、すっかり父親だ。
人間、やればなんとかなるとルイトは感慨深く思っていた。
(こうしてみると可愛いんだよなァ)
自分に似た色の瞳をぱちくりさせて、むにゃむにゃと何事か語りかけているような口元。
ぷにぷにとしてやわらかい曲線を描く頬を、そっと指先でなでる。
「あぅぅ、ぅ? 」
「そうだぞ。パパ、今日もお仕事だ」
「うぁぁぅ……」
「すねるなよ。危ないから、今日はセトのとこに行こうな?」
まるで会話しているかのようだ。
まだ言語も理解していないだろう赤ん坊だが、ルシアはこちらの言葉を分かったように聞く。
ルイトもまた、彼女の声や表情から少しずつ感情を読み取れるようになっていた。
あれから二週間とは思えない、脅威の変化である。
「すっかりパパ、よネ」
「よせやい」
ロロに冷やかされ、視線をそらす。
自分でも戸惑うくらいに、娘に対して得体の知れない質量の愛情が湧いてくる。それが日増しに大きく強くなるのだから、なおのこと不思議だった。
最初は壊れそうで怖かったこの小さな存在も、それが愛しいに変わるのだから面白い。
とはいえ夜泣きもそこそこするもので、寝不足で泣けてくることも無くはない。でもそれを差し引いてもオツリが来るくらい、この幼子は可愛いかった。
「悪いネ、ほんとならワタシが――」
「いやいや。いつもありがとう、ロロ」
ルイトは片手をあげて微笑んだ。
自分に隠し子が、と打ち明けたとき。彼女は一瞬だけ目を見開いた。
『#$Δζζ♩м……』
異国の言葉で、それが彼女の生まれ故郷のものだという事をルイトは知らない。
ただ予想に反して、彼女が彼の育児の手助けを率先して手伝い始めたことが驚きだった。
ミルクやらオムツ、服をそろえるだけでなく。冒険者の仕事に復帰した彼のために、託児も買ってでたのだ。
今では、ロロか。彼女の都合が悪ければ、酒場の主人セトと店員女の子たちが交代で面倒みてくれる。
文字通り、多くの人の手でこの子は育てられている。
皆は、ルイトの子だということを驚きつつも受け入れてくれたからだ。
(まぁぶちのめされないだけ、よかった)
「じゃ、そろそろ行ってくるよ」
背中におんぶ紐を使い、ルシアを背負う。
「行ってらっシャイ。η♩ζ$$м」
厳つい顔だが優しい目で異国の言葉をつぶやく彼女の眼差しに、ルイトは小さくうなずいた。
(ロロも、ああ見えて子供好きなんだな)
などと思いながら。
※※※
「さて、と」
背中に負っていた大剣は、しまい込んだ。
今は腰につけた太刀をふるうのが、彼のスタイルとなっている。
そうでないとこのおんぶ紐も付けられないし。万が一、ルシアにケガでもさせたら大変だから。
思考がすでに母親だ、なんてセトからは揶揄われたが鼻で笑っておく。
「とりあえず即日でこなせる依頼をくれ」
スマートにカクテルを注文するのも面倒で、カウンターの向こうの女性に声をかけた。
「かしこまりました。少しお待ちを」
彼女はわずかに眉をよせたが、すぐに手元の羊皮紙の束に視線を落とす。
相変わらず無機質かつ、人形めいた表情にむしろ安堵すらした。
その時――。
「よォ、久しぶりじゃん。ルイトちゃん」
「また君か。その呼び方やめろって、いつも言ってるだろ」
「アハハ。まぁまぁ、そう怖い顔すんなよ。べっぴんさんが台無しだぜェ?」
「っ、さわんな」
馴れ馴れしく隣に座り、肩に腕を回してくる男。
ランス・ロンドは拒まれても、くすんだ赤髪をかきあげてニヤついている。
またそれがカンに触った。
「ほんと、ジャジャ馬だよなァ。でも、そーゆートコも愛してるよン♡」
「笑えもしないどころか、虫唾が走る冗談だな」
身体を密着させんとグイグイ寄ってくる男に、殺意のかたまりのような視線を投げて寄越す。
だがいっこうに効果はないらしい。
「なぁなぁなぁなぁ」
「……しゃべるな、バカ」
「ひっどぉい! ってか。ルイトってば、みずくさいんじゃねーの」
「ハァ?」
いまだクエストが提示されないのにイライラしつつ、ため息をつく。
はやいところ、仕事を決めてこの場を去りたい。しかし何かを手間取っているのか、受付嬢は黙って羊皮紙をめくっている。
「女の子だってね、ルイトちゃんの隠し子」
「隠してない。それに君には関係ないだろ」
「もー、またそんなツレナイことを」
そんな素っ気ない返事も一笑し、ランスは言葉を続けた。
「相手は誰?」
「それこそ君には関係ない」
「ふーん。ま、いいけどねェ」
そこで、突然彼は表情を変える。
「ねぇルイト」
真剣な顔。
そして、やにわに掴まれた肩にルイトは顔をしかめた。
「は、離せよ」
「ルイト」
「だから離せって!」
「……コブ付きでも、オレなら幸せに出来るから」
(は?)
何を言い出すかと思えば。
あまりの言葉に意味を理解しかねて絶句する。
そんな彼に、今度は耳元でささやく。
「お前の子なら、きっと美人に育つだろうな。オレと一緒に、子育てしよう? 絶対に幸せにするからさァ」
「な……な……な……」
「他のヤツに渡したくねぇんだよ」
(まさかコイツ!?)
ルイトの頭に、衝撃的 (または見当違い)な考えがよぎった。
(うちの娘をモノにするつもりかーッ!!!)
一気に血が上る。
よりにもよって、大事な娘を頂こうとする不届き者に怒りのボルテージが爆上がりしたのだ。
「こんのっ、ロリコン野郎がァァァッ!!!」
「ブヘッ!?」
無防備な腹部に、渾身の一撃が肘鉄となって炸裂。
くぐもった呻き声と共に、ランスはイスごと後ろに転げ落ちる。
「ろ、ロリコンって……」
「ぺド野郎と言い直してやろうか。この変態」
忌々しげに舌打ちして、あ然とした顔で見上げる男に吐き捨てた。
「うちの娘を、貴様になんてやらんっ!」
「そ、そういう意味じゃ――」
ちょうどタイミングよく。差し出された依頼書をひったくるように手にして、ルイトは足早にギルドを後にする。
後ろで響く。
『ルイトぉぉぉぉっ、結婚してくれぇぇぇッ!!!』
という悲痛な叫びのような告白も、耳に入らない。
夢にも思わないだろう。
シングルファーザーとなった自分に、同業者でライバル。しかも、日頃からいけ好かないヤツが突然プロポーズしてくるなんて。
(僕が、娘を守らないと)
またひとつ。ルイト・カントールの、愛娘に対する愛を深めただけであった。
10
あなたにおすすめの小説

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

出戻り王子が幸せになるまで
あきたいぬ大好き(深凪雪花)
BL
初恋の相手と政略結婚した主人公セフィラだが、相手には愛人ながら本命がいたことを知る。追及した結果、離縁されることになり、母国に出戻ることに。けれど、バツイチになったせいか父王に厄介払いされ、後宮から追い出されてしまう。王都の下町で暮らし始めるが、ふと訪れた先の母校で幼馴染であるフレンシスと再会。事情を話すと、突然求婚される。
一途な幼馴染×強がり出戻り王子のお話です。
※他サイトにも掲載しております。

過労死転生した公務員、魔力がないだけで辺境に追放されたので、忠犬騎士と知識チートでざまぁしながら領地経営はじめます
水凪しおん
BL
過労死した元公務員の俺が転生したのは、魔法と剣が存在する異世界の、どうしようもない貧乏貴族の三男だった。
家族からは能無しと蔑まれ、与えられたのは「ゴミ捨て場」と揶揄される荒れ果てた辺境の領地。これは、事実上の追放だ。
絶望的な状況の中、俺に付き従ったのは、無口で無骨だが、その瞳に確かな忠誠を宿す一人の護衛騎士だけだった。
「大丈夫だ。俺がいる」
彼の言葉を胸に、俺は決意する。公務員として培った知識と経験、そして持ち前のしぶとさで、この最悪な領地を最高の楽園に変えてみせると。
これは、不遇な貴族と忠実な騎士が織りなす、絶望の淵から始まる領地改革ファンタジー。そして、固い絆で結ばれた二人が、やがて王国を揺るがす運命に立ち向かう物語。
無能と罵った家族に、見て見ぬふりをした者たちに、最高の「ざまぁ」をお見舞いしてやろうじゃないか!
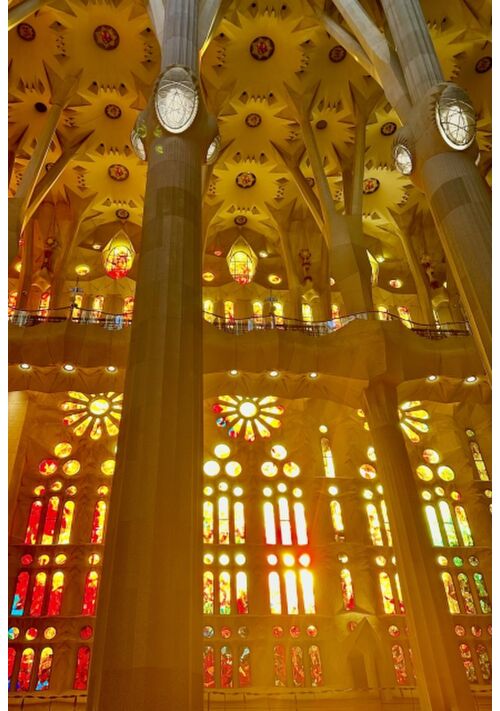
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。


【8話完結】帰ってきた勇者様が褒美に私を所望している件について。
キノア9g
BL
異世界召喚されたのは、
ブラック企業で心身ボロボロになった陰キャ勇者。
国王が用意した褒美は、金、地位、そして姫との結婚――
だが、彼が望んだのは「何の能力もない第三王子」だった。
顔だけ王子と蔑まれ、周囲から期待されなかったリュシアン。
過労で倒れた勇者に、ただ優しく手を伸ばしただけの彼は、
気づかぬうちに勇者の心を奪っていた。
「それでも俺は、あなたがいいんです」
だけど――勇者は彼を「姫」だと誤解していた。
切なさとすれ違い、
それでも惹かれ合う二人の、
優しくて不器用な恋の物語。
全8話。

【第二章開始】死に戻りに疲れた美貌の傾国王子、生存ルートを模索する
とうこ
BL
その美しさで知られた母に似て美貌の第三王子ツェーレンは、王弟に嫁いだ隣国で不貞を疑われ哀れ極刑に……と思ったら逆行!? しかもまだ夫選びの前。訳が分からないが、同じ道は絶対に御免だ。
「隣国以外でお願いします!」
死を回避する為に選んだ先々でもバラエティ豊かにkillされ続け、巻き戻り続けるツェーレン。これが最後と十二回目の夫となったのは、有名特殊な一族の三男、天才魔術師アレスター。
彼は婚姻を拒絶するが、ツェーレンが呪いを受けていると言い解呪を約束する。
いじられ体質の情けない末っ子天才魔術師×素直前向きな呪われ美形王子。
転移日本人を祖に持つグレイシア三兄弟、三男アレスターの物語。
小説家になろう様にも掲載しております。
※本編完結。ぼちぼち番外編を投稿していきます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















