23 / 33
瘴気の森
しおりを挟む
獣道を歩き、倒れた木々を分け入って。
鳥の声一つ聞こえぬ静寂の森。不気味さと共に強い緊張が広がる。
「……チッ。くせぇな」
ボソリと呟かれた言葉に、他の3人は足を止める。
言ったのはトマスだ。
「どうしたの?」
「シモン、お前にゃ分からんかもしれんが。ここは、かなりヤバいぞ」
キョトンとするシモンをよそに、ルイトとイゼベルは小さくうなずく。
彼が指しているのは、言ってみれば魔法の痕跡。
魔法は、発動させればその痕跡が残る。それは強大なものになればなるほど、強く濃く感じる事が出来るのだ。
それは魔力を持つものだけが感じることのできるもので、その感知の仕方は個人差がある。
特にトマスは、嗅覚 (臭い)によっても感じることができるようで。
「ひどい臭いがする。これは相当タチの悪い黒魔法だ」
なんて顔をしかめている。
「確かに、この辺りから空気が灰色ですね」
「肌がチクチクするな……」
イザベルとルイトもまた、それぞれ色彩と肌感覚で感知しているらしい。分からぬのは、根っから魔力を持たない剣士のシモンのみだ。
首をかしげながら、鼻をくんくんさせたり目を凝らしたり。腕の装備を外してみたり。不思議そうである。
「やはりキメラ獣を創った奴らが、この辺りにいるんだろうか」
「そうかもしれませんね、これほどの瘴気に満ちているのですから」
「ああ、臭いは向こうの方からだ」
今度は三人が、うんうんとうなずいている時だった。
「なんかボクだけ仲間外れみたい……」
完全にすねてしまったシモンが、しゃがみこむ。
しかしこればかりは、生まれ持った体質なので仕方がない。ただ、確かに面白くはなかろうとルイトは彼の肩を軽く叩く。
「気にすんなよ、僕がちゃんと君をアシストしてやるさ」
「ルイトさんっ♡ じゃあボク頑張りますね!」
「お、おう……」
「よーしっ、がんばるぞぉぉっ!!」
一変して元気になった彼の様子に、ややひき気味だが。
まぁ、そんなこんなで。四人は邪悪な気配の漂う森を突き進んでいくことになった。
(なんかおかしい)
ルイトの頭の中に違和感と疑問が広がるのに、そう時間はかからなかった。
そう広くはない森のはずであったのに、やけに鬱蒼と。そして広大な森。
そして聞こえてくる奇妙な声は、鳥だろうか。
「イゼベル、トマス」
「ええ」
「わかるぜ」
そう感じていたのは、二人も同じだったようで。
「ここは、あの森でしょうか」
ぽつりと言葉を投げかけたのは、イゼベル。胸のロザリオをにぎりしめ、不安げな顔だ。
「どういう意味だ?」
わたし達……空間を超えてしまったのかもしれません」
空間をこえる――。
首を傾げた彼に、彼女は言葉を慎重に選ぶように口をひらいた。
「空間、というと少し違うかもしれませんが。少なくても、わたしたちが先程までいた森ではなさそうです」
どうも曖昧な表現だが、実際イゼベルも状況を判断しかねているようだ。
しかしその時。
「うっ……」
「おい、大丈夫か」
見ればシモンの顔が青ざめている。今にも膝から崩れ落ちそうな様子で、ガタガタと震えていた。
「シモン!」
「な、なんか……すごく……っ、寒くて……」
とっさに手を差し伸べれば、あっけなくその場に倒れ込む。その身体は、触れるだけで分かるほどに冷たく。まるで氷のようで。
「どうしたんだ。おい、シモン!!」
「ルイト……さん……ボク……」
みるみるうちに色を無くす唇。浅い呼吸を繰り返す胸も弱々しく、今にも止まってしまいそうだ。
「おいっ、一体なにがどうしたっていうんだ!?」
なにか特殊な呪術。つまり魔法攻撃を受けたのか。
今さっきまで元気にしていたのに。どんどん冷えていく身体に、焦りがつのる。
「ルイトさんっ、離れてください!」
イザベルが鋭く呪文を唱える。
まばゆい光が辺りに弾け、彼を包み込んだ。しかし。
「っ、ダメです……これは……っ」
どんどん弱まる光。
彼女の放った回復魔法は効かないどころか、逆にその魔力を吸い取られているという。
そして見れば。シモンの身体から黒い影のような塊が湧き出て、光を包みこまんとして――。
「危ねぇッ!」
トマスがイゼベルを突き飛ばす。
「きゃっ!?」
勢いよく転げた彼女がさっきまでいた場所に、黒い火炎が激しく立ち上った。
あと一瞬遅かったら。たちまち火だるまになり、骨すら残らなかったかもしれない。それだけ邪悪で危険な闇の劫火であった。
「トマス。ありがとう……」
「そんなことより、これはマズイぜ」
見ればもう、シモンの身体はだらりと弛緩している。わずかに開いた瞼からは、血走った白目が覗いていた。
誰が見ても尋常ではない。
「なあ二人とも」
ルイトは森の奥を見すえた。
「もしこれが呪術のたぐいであるんなら、どこかに術者がいるんだろうな」
あくまで魔法というのは、掛けるものと掛けられるもの。それが明確になっていることが多い。
つまり。彼をこんな風にした者がこの森のどこかから、彼らを監視しているのだ。
「君たちは、とにかく彼をなんとか持ちこたえさせてくれないか。そして出来れば、この場から退却しろ」
「ルイトさんは?」
「僕は、少し探索をしてからだ」
「!」
剣をにぎりしめる。
「そんなっ、危険です!」
「そうだぞ! ここは一旦、退避して立て直さねぇと」
二人の言葉に首をよこにふる。
「いいや。それじゃあ事態は治まらないだろう」
よしんばここから逃げおおせたとて、彼にかかった死の呪いは解けないだろう。それは執念深い蛇のように、どこまでも追ってくる黒魔法。
その恐ろしさはもう今は昔。国に多くを禁じられているのだ。
しかし書物や伝聞の中で、その恐ろしささは知られている。
「大丈夫、僕には武器がある。そして、これもだ」
服の下のポケットをそっとたたく。
そこには幼い娘が気に入って着ていた服の端切れ。長いこと着ていたが、最近小さくなって着れなくなったそれは。宿屋の女主人であるロロがプレゼントしてくれたものだった。
「ルシアの手がかりがあるかもしれない」
ほんの針の先に灯る光より小さな希望。だとしても、必死につかみ取りたい。
ルイトの決意に、二人は唇を噛んでうなずいた。
「……ごめんなさい」
「何を謝ることがあるんだ。シモンを頼んだぞ。そして――」
若き冒険者たち。恩人でもあり、もはや戦友でもあった彼らに微笑む。
「死ぬな。生きて、会おう」
これが冒険者というものだ。
生きるためとはいえ。村を出てたった一人、身を置いた場所。
そこで彼は伝説としか知らぬ強大で邪悪とされる存在と、対峙することになる。
鳥の声一つ聞こえぬ静寂の森。不気味さと共に強い緊張が広がる。
「……チッ。くせぇな」
ボソリと呟かれた言葉に、他の3人は足を止める。
言ったのはトマスだ。
「どうしたの?」
「シモン、お前にゃ分からんかもしれんが。ここは、かなりヤバいぞ」
キョトンとするシモンをよそに、ルイトとイゼベルは小さくうなずく。
彼が指しているのは、言ってみれば魔法の痕跡。
魔法は、発動させればその痕跡が残る。それは強大なものになればなるほど、強く濃く感じる事が出来るのだ。
それは魔力を持つものだけが感じることのできるもので、その感知の仕方は個人差がある。
特にトマスは、嗅覚 (臭い)によっても感じることができるようで。
「ひどい臭いがする。これは相当タチの悪い黒魔法だ」
なんて顔をしかめている。
「確かに、この辺りから空気が灰色ですね」
「肌がチクチクするな……」
イザベルとルイトもまた、それぞれ色彩と肌感覚で感知しているらしい。分からぬのは、根っから魔力を持たない剣士のシモンのみだ。
首をかしげながら、鼻をくんくんさせたり目を凝らしたり。腕の装備を外してみたり。不思議そうである。
「やはりキメラ獣を創った奴らが、この辺りにいるんだろうか」
「そうかもしれませんね、これほどの瘴気に満ちているのですから」
「ああ、臭いは向こうの方からだ」
今度は三人が、うんうんとうなずいている時だった。
「なんかボクだけ仲間外れみたい……」
完全にすねてしまったシモンが、しゃがみこむ。
しかしこればかりは、生まれ持った体質なので仕方がない。ただ、確かに面白くはなかろうとルイトは彼の肩を軽く叩く。
「気にすんなよ、僕がちゃんと君をアシストしてやるさ」
「ルイトさんっ♡ じゃあボク頑張りますね!」
「お、おう……」
「よーしっ、がんばるぞぉぉっ!!」
一変して元気になった彼の様子に、ややひき気味だが。
まぁ、そんなこんなで。四人は邪悪な気配の漂う森を突き進んでいくことになった。
(なんかおかしい)
ルイトの頭の中に違和感と疑問が広がるのに、そう時間はかからなかった。
そう広くはない森のはずであったのに、やけに鬱蒼と。そして広大な森。
そして聞こえてくる奇妙な声は、鳥だろうか。
「イゼベル、トマス」
「ええ」
「わかるぜ」
そう感じていたのは、二人も同じだったようで。
「ここは、あの森でしょうか」
ぽつりと言葉を投げかけたのは、イゼベル。胸のロザリオをにぎりしめ、不安げな顔だ。
「どういう意味だ?」
わたし達……空間を超えてしまったのかもしれません」
空間をこえる――。
首を傾げた彼に、彼女は言葉を慎重に選ぶように口をひらいた。
「空間、というと少し違うかもしれませんが。少なくても、わたしたちが先程までいた森ではなさそうです」
どうも曖昧な表現だが、実際イゼベルも状況を判断しかねているようだ。
しかしその時。
「うっ……」
「おい、大丈夫か」
見ればシモンの顔が青ざめている。今にも膝から崩れ落ちそうな様子で、ガタガタと震えていた。
「シモン!」
「な、なんか……すごく……っ、寒くて……」
とっさに手を差し伸べれば、あっけなくその場に倒れ込む。その身体は、触れるだけで分かるほどに冷たく。まるで氷のようで。
「どうしたんだ。おい、シモン!!」
「ルイト……さん……ボク……」
みるみるうちに色を無くす唇。浅い呼吸を繰り返す胸も弱々しく、今にも止まってしまいそうだ。
「おいっ、一体なにがどうしたっていうんだ!?」
なにか特殊な呪術。つまり魔法攻撃を受けたのか。
今さっきまで元気にしていたのに。どんどん冷えていく身体に、焦りがつのる。
「ルイトさんっ、離れてください!」
イザベルが鋭く呪文を唱える。
まばゆい光が辺りに弾け、彼を包み込んだ。しかし。
「っ、ダメです……これは……っ」
どんどん弱まる光。
彼女の放った回復魔法は効かないどころか、逆にその魔力を吸い取られているという。
そして見れば。シモンの身体から黒い影のような塊が湧き出て、光を包みこまんとして――。
「危ねぇッ!」
トマスがイゼベルを突き飛ばす。
「きゃっ!?」
勢いよく転げた彼女がさっきまでいた場所に、黒い火炎が激しく立ち上った。
あと一瞬遅かったら。たちまち火だるまになり、骨すら残らなかったかもしれない。それだけ邪悪で危険な闇の劫火であった。
「トマス。ありがとう……」
「そんなことより、これはマズイぜ」
見ればもう、シモンの身体はだらりと弛緩している。わずかに開いた瞼からは、血走った白目が覗いていた。
誰が見ても尋常ではない。
「なあ二人とも」
ルイトは森の奥を見すえた。
「もしこれが呪術のたぐいであるんなら、どこかに術者がいるんだろうな」
あくまで魔法というのは、掛けるものと掛けられるもの。それが明確になっていることが多い。
つまり。彼をこんな風にした者がこの森のどこかから、彼らを監視しているのだ。
「君たちは、とにかく彼をなんとか持ちこたえさせてくれないか。そして出来れば、この場から退却しろ」
「ルイトさんは?」
「僕は、少し探索をしてからだ」
「!」
剣をにぎりしめる。
「そんなっ、危険です!」
「そうだぞ! ここは一旦、退避して立て直さねぇと」
二人の言葉に首をよこにふる。
「いいや。それじゃあ事態は治まらないだろう」
よしんばここから逃げおおせたとて、彼にかかった死の呪いは解けないだろう。それは執念深い蛇のように、どこまでも追ってくる黒魔法。
その恐ろしさはもう今は昔。国に多くを禁じられているのだ。
しかし書物や伝聞の中で、その恐ろしささは知られている。
「大丈夫、僕には武器がある。そして、これもだ」
服の下のポケットをそっとたたく。
そこには幼い娘が気に入って着ていた服の端切れ。長いこと着ていたが、最近小さくなって着れなくなったそれは。宿屋の女主人であるロロがプレゼントしてくれたものだった。
「ルシアの手がかりがあるかもしれない」
ほんの針の先に灯る光より小さな希望。だとしても、必死につかみ取りたい。
ルイトの決意に、二人は唇を噛んでうなずいた。
「……ごめんなさい」
「何を謝ることがあるんだ。シモンを頼んだぞ。そして――」
若き冒険者たち。恩人でもあり、もはや戦友でもあった彼らに微笑む。
「死ぬな。生きて、会おう」
これが冒険者というものだ。
生きるためとはいえ。村を出てたった一人、身を置いた場所。
そこで彼は伝説としか知らぬ強大で邪悪とされる存在と、対峙することになる。
0
あなたにおすすめの小説

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

出戻り王子が幸せになるまで
あきたいぬ大好き(深凪雪花)
BL
初恋の相手と政略結婚した主人公セフィラだが、相手には愛人ながら本命がいたことを知る。追及した結果、離縁されることになり、母国に出戻ることに。けれど、バツイチになったせいか父王に厄介払いされ、後宮から追い出されてしまう。王都の下町で暮らし始めるが、ふと訪れた先の母校で幼馴染であるフレンシスと再会。事情を話すと、突然求婚される。
一途な幼馴染×強がり出戻り王子のお話です。
※他サイトにも掲載しております。

過労死転生した公務員、魔力がないだけで辺境に追放されたので、忠犬騎士と知識チートでざまぁしながら領地経営はじめます
水凪しおん
BL
過労死した元公務員の俺が転生したのは、魔法と剣が存在する異世界の、どうしようもない貧乏貴族の三男だった。
家族からは能無しと蔑まれ、与えられたのは「ゴミ捨て場」と揶揄される荒れ果てた辺境の領地。これは、事実上の追放だ。
絶望的な状況の中、俺に付き従ったのは、無口で無骨だが、その瞳に確かな忠誠を宿す一人の護衛騎士だけだった。
「大丈夫だ。俺がいる」
彼の言葉を胸に、俺は決意する。公務員として培った知識と経験、そして持ち前のしぶとさで、この最悪な領地を最高の楽園に変えてみせると。
これは、不遇な貴族と忠実な騎士が織りなす、絶望の淵から始まる領地改革ファンタジー。そして、固い絆で結ばれた二人が、やがて王国を揺るがす運命に立ち向かう物語。
無能と罵った家族に、見て見ぬふりをした者たちに、最高の「ざまぁ」をお見舞いしてやろうじゃないか!

虐げられた令息の第二の人生はスローライフ
りまり
BL
僕の生まれたこの世界は魔法があり魔物が出没する。
僕は由緒正しい公爵家に生まれながらも魔法の才能はなく剣術も全くダメで頭も下から数えたほうがいい方だと思う。
だから僕は家族にも公爵家の使用人にも馬鹿にされ食事もまともにもらえない。
救いだったのは僕を不憫に思った王妃様が僕を殿下の従者に指名してくれたことで、少しはまともな食事ができるようになった事だ。
お家に帰る事なくお城にいていいと言うので僕は頑張ってみたいです。
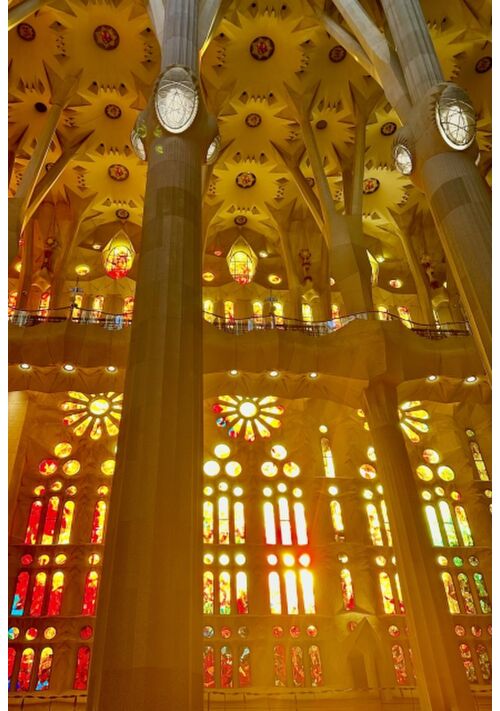
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。


【8話完結】帰ってきた勇者様が褒美に私を所望している件について。
キノア9g
BL
異世界召喚されたのは、
ブラック企業で心身ボロボロになった陰キャ勇者。
国王が用意した褒美は、金、地位、そして姫との結婚――
だが、彼が望んだのは「何の能力もない第三王子」だった。
顔だけ王子と蔑まれ、周囲から期待されなかったリュシアン。
過労で倒れた勇者に、ただ優しく手を伸ばしただけの彼は、
気づかぬうちに勇者の心を奪っていた。
「それでも俺は、あなたがいいんです」
だけど――勇者は彼を「姫」だと誤解していた。
切なさとすれ違い、
それでも惹かれ合う二人の、
優しくて不器用な恋の物語。
全8話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















