28 / 33
瘴気の森の小屋2
しおりを挟む
……ハンスとマルガレーテ。
彼ら兄妹はそう名乗った。
柄はまったく見えないが、ふんわりとしたエプロンドレス (だと思われる)をひるがえす少女の豊かな髪はゆれる。
「ようこそ、カワイイお客さま!」
小さな淑女のようなお辞儀に、思わず会釈を返す。
顔は見えないが。おおよそ7、8歳くらいだろうか。
その動きのシルエットから、なかなか明るくてチャーミングな性格が見て取れる。
「お茶をいれるわね。ハンス兄さん」
「ぼくはお菓子をお皿に飾るよ。マルガレーテ」
対して、ハンスという少年はいささか内気らしい。ぺこりとこちらに頭を下げて、小走りで立ち去ってしまった。
「もう兄さんったら! うふふ。あんまりにアナタがカワイイから、真っ赤になってしまったわ」
あの通りの顔だから、赤くなったいようと青くなっていようと分からないが。そう言うのならそうなのだろう。
ルイトはかろうじて愛想笑いを浮かべた。
男にカワイイなんて。しかもこんな子どもに言われるのは、あまり嬉しくはない。
だが、それも今はどうでも良いことで。
「ルシアはどこだ」
彼にとって最優先事項だった。
しかしマルガレーテは小首をかしげて数秒。そして鈴のような声をあげて、笑いだす。
「あははっ、せっかちさんなのね。でも大丈夫、すべてはうまくいくのよ。そういうことになっているんだから」
くるくると巻き毛を指先でもてあそびながら、まるで唄うように言う。
「それに今はお茶の時間。かわいいベイビーに会うのは、それからでもいいででしょう?」
「だが……」
「今はぐーっすり眠っているわ。かわいいかわいい、あなたのベイビーちゃん。赤毛が、魅力的な素敵な子ね」
ウィンクでもしたのだろうか。くるくると踊るような足取りで近付いてきて、椅子を引いた。
「良い香りのお茶をめしあがれ!」
「大丈夫だ。彼女たちは信用できる。俺が保証するぜ」
リュウガがそう言って、肩に手を置く。まるで強引に、席につかせるような。思わず彼の顔を見上げるが、その表情を読むことができない。
視線が交差する。
「まったく、ハンス兄さんったら! なにグズグズしてるのかしら」
焦れたような少女は、またステップを踏みながら窓辺に駆け寄った。
さながら歌演劇だ。
限りなく芝居がかった仕草や言動に、不安と不信がつのる。
「少し、様子をみてくるわ――ねぇリュウガ」
相変わらず引かれた椅子の前で立ち尽くすルイトに、ピッタリくっつくように寄り添う男。
彼女は、そんな彼らを振り返った。
やはりポッカリとした闇の広がる顔面には、表情らしい表情はわからない。
そして落ち着きのない、小刻みに揺れる身体と妙に明るい声と。不気味としか言いようのない存在に、戸惑いが隠せなかった。
「お客様のおもてなしは、あなたに任せていいかしら?」
そう言われて、リュウガは大きくうなずく。
「ああ、まかせておけ」
シルエットの少女は嬉しそうな声をあげると、無邪気に外に飛び出していく。
差し込んだ明るい陽の光と、歓声と。
「……」
「……」
お菓子の家に取り残された二人は、顔を見合わせる。
暖かな空気は、淹れたての香ばしいハーブティーの香りに満たされていた。
甘く。少し濃厚な果実のようなそれは、おおよそ嗅いだことのない匂いだ。
ルイトは反射的に口と鼻を手で押さえる。
「どうした」
「い、いや」
(この香り、どこかで)
記憶の底にある。思い出したくない、感覚。
「緊張しているのか?」
彼の大きくて無骨に見える手が、そっと彼の手の甲に触れた。
恐ろしく冷えている。
「大丈夫だ、彼らは信用できる」
先程からリュウガもマルガレーテも、その言葉ばかりだ。言い聞かされているような気分になるくらい、繰り返される『大丈夫』という言葉。
「あの二人は確かに魔族だが、こうやってここでヒッソリと暮らしている善良なヤツらでな」
「か、顔がない……」
「ははは、そんなことか」
さわやかに歯を見せて笑う。それがらしくなくて、思わず二度見した。
ここは、いや。彼らはどこがおかしい。
「本当にルシアはここにいるのか……?」
疑問が口の端からこぼれる。しかし、言うべきではなかったかもしれない。
彼が綺麗な顔を歪める笑みを浮かべたから。
「俺がお前をだましたことなんてないだろう」
「りゅ、リュウガ。本当に君は――」
本物なのか。
さっきから気になってはいたのだ。彼の瞳の色は、何色だった?
(くそ。まだ頭がぼんやりする)
焦燥と不安が胸に渦巻くのがわかった。なにが現実で何が幻覚なのか。
実はまだ娘の死体を抱き抱えながら、空虚で絶望と希望の入り交じった悪夢をみているのかもしれない。
だとすれば。
「……」
引かれた椅子に、ふるえながらも腰を下ろした。
そうでなければ耐えられない。
(ひとりぼっちはもう嫌だ)
蔑まれて虐げられるより、その存在を殺されるような孤独。抱けば応えてくれる熱がない、それが彼を確実に壊しにかかっていた。
気が狂うより恐ろしいのは、そこから正気にかえることなのだ。
それならば、この狂気と瘴気の森に沈むのも仕方ない。
「ルイト、大丈夫だ」
後ろから椅子ごと抱きしめる男の腕。確かに力強く、逞しい。ひんやりとしたそれに頬を寄せる。
「俺は、お前を愛している」
「リュウガ……僕は……」
鼓膜を震わせる低音。これが自分の幸福であれば、甘んじて受け入れるべきなのだろうか。
今まで恋を渡り歩いてきたこの身にとっては、戸惑いも覚えるが。
(ちがう)
心の奥底で鳴らされる警報も、この腕には抗えまい。
「そろそろ思い出してくれないか」
「え……」
吹き込まれた言葉に、背中が粟立つ。
「あの男でなく、オレを」
「っ、!?」
鷹揚な低い声でなく、ねっとりとしたあの――。
「ま、さか」
「オレは何度でも、お前を迎えにいくぜぇ」
ハッとして辺りを見渡す。
華やかで愛らしいお菓子の家。
チョコレートとマシュマロで出来た壁が、ドロリと溶ける。
「ら、ランス……バカな……君は……」
「言っただろゔ、オレは、お前゙を゙、愛してる゙ぅ゙ぅ、ってぇ゙」
「っ、うわぁぁぁッ!!!」
顔を剥ぎとられ、氷の魔法をかけられ死んだはずの男が目の前に。
自分を抱きすくめていた腕の肉が、糸をひいて落ちた。
熟れて腐りきった果実のように。甘いような酸っぱいような、そんな刺激臭を放っている。
必死で逃げ出そうと暴れても、ピクリとも動かない身体に恐怖はつのった。
「いやだッ、離せ!!!」
これが悪夢か。
バットエンドの夢の果て。救いのない、最低のエンディング。恐怖と絶望の、中を這いずり回るしかないのか。
「はや゙ぐ、堕ちて、ごい゙よォ」
腐肉にて撫で回される身体。虫唾が走るどころではない。
歯をガチガチと震わせる彼に、忌々しい男の呪詛が響く。
「あんな゙、エセ王子より……我が……正当なる゙……後継者゙……の゙……王゙ォォ……」
「ひっ!?」
レロォ、と長く赤い舌が頬を舐める。
(このまま殺してくれ)
悪夢の中であっていい。すべてを終わらせてくれるのならば。
そう願った時。
『――てめぇいい加減にしろよ』
憤怒の声色と共に、鮮烈な光が爆ぜて辺りを真っ白に染めた。
それは一瞬。
まばたきすら、するヒマがなかった。
(あっ)
「おい。大丈夫か」
「!」
小さく揺すられていたらしい。
大写しになった美男子は、見慣れた顔で。
「りゅ……リュウガ……」
「ずいぶん魘されてたぜ。そんなに俺の背中は寝心地わるいか?」
(どういうことだ)
どうやら彼に背負われている間に、眠ってしまったらしい。
そしてあんな悪夢をみたと。
「どうした」
「いや……」
(あのお菓子の家も、影絵のような少年少女も。全部、夢?)
ひどく強烈でリアルなものだった。本当に脳が見せた錯覚なんだろうかと疑う程に。
(じゃあ、彼は)
「お、おい」
彼が慌てたような声をあげる。
「お前、なに泣いてんだ」
「……」
リュウガが戸惑うのも無理はない。
なぜなら、その紫水晶のような瞳からとめどなく大粒の雫が零れていたから。
(怖かった)
まるで幼子のように。
あふれ落ちる涙をぬぐうこともせず、ルイトは泣き始めた。
「ルイト」
そこへおずおずと、遠慮げに差し出された腕。
そっと触れれば高い体温に安堵した。
――ここは瘴気の森。
人に悪夢をみせる、狂気の森。
彼ら兄妹はそう名乗った。
柄はまったく見えないが、ふんわりとしたエプロンドレス (だと思われる)をひるがえす少女の豊かな髪はゆれる。
「ようこそ、カワイイお客さま!」
小さな淑女のようなお辞儀に、思わず会釈を返す。
顔は見えないが。おおよそ7、8歳くらいだろうか。
その動きのシルエットから、なかなか明るくてチャーミングな性格が見て取れる。
「お茶をいれるわね。ハンス兄さん」
「ぼくはお菓子をお皿に飾るよ。マルガレーテ」
対して、ハンスという少年はいささか内気らしい。ぺこりとこちらに頭を下げて、小走りで立ち去ってしまった。
「もう兄さんったら! うふふ。あんまりにアナタがカワイイから、真っ赤になってしまったわ」
あの通りの顔だから、赤くなったいようと青くなっていようと分からないが。そう言うのならそうなのだろう。
ルイトはかろうじて愛想笑いを浮かべた。
男にカワイイなんて。しかもこんな子どもに言われるのは、あまり嬉しくはない。
だが、それも今はどうでも良いことで。
「ルシアはどこだ」
彼にとって最優先事項だった。
しかしマルガレーテは小首をかしげて数秒。そして鈴のような声をあげて、笑いだす。
「あははっ、せっかちさんなのね。でも大丈夫、すべてはうまくいくのよ。そういうことになっているんだから」
くるくると巻き毛を指先でもてあそびながら、まるで唄うように言う。
「それに今はお茶の時間。かわいいベイビーに会うのは、それからでもいいででしょう?」
「だが……」
「今はぐーっすり眠っているわ。かわいいかわいい、あなたのベイビーちゃん。赤毛が、魅力的な素敵な子ね」
ウィンクでもしたのだろうか。くるくると踊るような足取りで近付いてきて、椅子を引いた。
「良い香りのお茶をめしあがれ!」
「大丈夫だ。彼女たちは信用できる。俺が保証するぜ」
リュウガがそう言って、肩に手を置く。まるで強引に、席につかせるような。思わず彼の顔を見上げるが、その表情を読むことができない。
視線が交差する。
「まったく、ハンス兄さんったら! なにグズグズしてるのかしら」
焦れたような少女は、またステップを踏みながら窓辺に駆け寄った。
さながら歌演劇だ。
限りなく芝居がかった仕草や言動に、不安と不信がつのる。
「少し、様子をみてくるわ――ねぇリュウガ」
相変わらず引かれた椅子の前で立ち尽くすルイトに、ピッタリくっつくように寄り添う男。
彼女は、そんな彼らを振り返った。
やはりポッカリとした闇の広がる顔面には、表情らしい表情はわからない。
そして落ち着きのない、小刻みに揺れる身体と妙に明るい声と。不気味としか言いようのない存在に、戸惑いが隠せなかった。
「お客様のおもてなしは、あなたに任せていいかしら?」
そう言われて、リュウガは大きくうなずく。
「ああ、まかせておけ」
シルエットの少女は嬉しそうな声をあげると、無邪気に外に飛び出していく。
差し込んだ明るい陽の光と、歓声と。
「……」
「……」
お菓子の家に取り残された二人は、顔を見合わせる。
暖かな空気は、淹れたての香ばしいハーブティーの香りに満たされていた。
甘く。少し濃厚な果実のようなそれは、おおよそ嗅いだことのない匂いだ。
ルイトは反射的に口と鼻を手で押さえる。
「どうした」
「い、いや」
(この香り、どこかで)
記憶の底にある。思い出したくない、感覚。
「緊張しているのか?」
彼の大きくて無骨に見える手が、そっと彼の手の甲に触れた。
恐ろしく冷えている。
「大丈夫だ、彼らは信用できる」
先程からリュウガもマルガレーテも、その言葉ばかりだ。言い聞かされているような気分になるくらい、繰り返される『大丈夫』という言葉。
「あの二人は確かに魔族だが、こうやってここでヒッソリと暮らしている善良なヤツらでな」
「か、顔がない……」
「ははは、そんなことか」
さわやかに歯を見せて笑う。それがらしくなくて、思わず二度見した。
ここは、いや。彼らはどこがおかしい。
「本当にルシアはここにいるのか……?」
疑問が口の端からこぼれる。しかし、言うべきではなかったかもしれない。
彼が綺麗な顔を歪める笑みを浮かべたから。
「俺がお前をだましたことなんてないだろう」
「りゅ、リュウガ。本当に君は――」
本物なのか。
さっきから気になってはいたのだ。彼の瞳の色は、何色だった?
(くそ。まだ頭がぼんやりする)
焦燥と不安が胸に渦巻くのがわかった。なにが現実で何が幻覚なのか。
実はまだ娘の死体を抱き抱えながら、空虚で絶望と希望の入り交じった悪夢をみているのかもしれない。
だとすれば。
「……」
引かれた椅子に、ふるえながらも腰を下ろした。
そうでなければ耐えられない。
(ひとりぼっちはもう嫌だ)
蔑まれて虐げられるより、その存在を殺されるような孤独。抱けば応えてくれる熱がない、それが彼を確実に壊しにかかっていた。
気が狂うより恐ろしいのは、そこから正気にかえることなのだ。
それならば、この狂気と瘴気の森に沈むのも仕方ない。
「ルイト、大丈夫だ」
後ろから椅子ごと抱きしめる男の腕。確かに力強く、逞しい。ひんやりとしたそれに頬を寄せる。
「俺は、お前を愛している」
「リュウガ……僕は……」
鼓膜を震わせる低音。これが自分の幸福であれば、甘んじて受け入れるべきなのだろうか。
今まで恋を渡り歩いてきたこの身にとっては、戸惑いも覚えるが。
(ちがう)
心の奥底で鳴らされる警報も、この腕には抗えまい。
「そろそろ思い出してくれないか」
「え……」
吹き込まれた言葉に、背中が粟立つ。
「あの男でなく、オレを」
「っ、!?」
鷹揚な低い声でなく、ねっとりとしたあの――。
「ま、さか」
「オレは何度でも、お前を迎えにいくぜぇ」
ハッとして辺りを見渡す。
華やかで愛らしいお菓子の家。
チョコレートとマシュマロで出来た壁が、ドロリと溶ける。
「ら、ランス……バカな……君は……」
「言っただろゔ、オレは、お前゙を゙、愛してる゙ぅ゙ぅ、ってぇ゙」
「っ、うわぁぁぁッ!!!」
顔を剥ぎとられ、氷の魔法をかけられ死んだはずの男が目の前に。
自分を抱きすくめていた腕の肉が、糸をひいて落ちた。
熟れて腐りきった果実のように。甘いような酸っぱいような、そんな刺激臭を放っている。
必死で逃げ出そうと暴れても、ピクリとも動かない身体に恐怖はつのった。
「いやだッ、離せ!!!」
これが悪夢か。
バットエンドの夢の果て。救いのない、最低のエンディング。恐怖と絶望の、中を這いずり回るしかないのか。
「はや゙ぐ、堕ちて、ごい゙よォ」
腐肉にて撫で回される身体。虫唾が走るどころではない。
歯をガチガチと震わせる彼に、忌々しい男の呪詛が響く。
「あんな゙、エセ王子より……我が……正当なる゙……後継者゙……の゙……王゙ォォ……」
「ひっ!?」
レロォ、と長く赤い舌が頬を舐める。
(このまま殺してくれ)
悪夢の中であっていい。すべてを終わらせてくれるのならば。
そう願った時。
『――てめぇいい加減にしろよ』
憤怒の声色と共に、鮮烈な光が爆ぜて辺りを真っ白に染めた。
それは一瞬。
まばたきすら、するヒマがなかった。
(あっ)
「おい。大丈夫か」
「!」
小さく揺すられていたらしい。
大写しになった美男子は、見慣れた顔で。
「りゅ……リュウガ……」
「ずいぶん魘されてたぜ。そんなに俺の背中は寝心地わるいか?」
(どういうことだ)
どうやら彼に背負われている間に、眠ってしまったらしい。
そしてあんな悪夢をみたと。
「どうした」
「いや……」
(あのお菓子の家も、影絵のような少年少女も。全部、夢?)
ひどく強烈でリアルなものだった。本当に脳が見せた錯覚なんだろうかと疑う程に。
(じゃあ、彼は)
「お、おい」
彼が慌てたような声をあげる。
「お前、なに泣いてんだ」
「……」
リュウガが戸惑うのも無理はない。
なぜなら、その紫水晶のような瞳からとめどなく大粒の雫が零れていたから。
(怖かった)
まるで幼子のように。
あふれ落ちる涙をぬぐうこともせず、ルイトは泣き始めた。
「ルイト」
そこへおずおずと、遠慮げに差し出された腕。
そっと触れれば高い体温に安堵した。
――ここは瘴気の森。
人に悪夢をみせる、狂気の森。
0
あなたにおすすめの小説

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

出戻り王子が幸せになるまで
あきたいぬ大好き(深凪雪花)
BL
初恋の相手と政略結婚した主人公セフィラだが、相手には愛人ながら本命がいたことを知る。追及した結果、離縁されることになり、母国に出戻ることに。けれど、バツイチになったせいか父王に厄介払いされ、後宮から追い出されてしまう。王都の下町で暮らし始めるが、ふと訪れた先の母校で幼馴染であるフレンシスと再会。事情を話すと、突然求婚される。
一途な幼馴染×強がり出戻り王子のお話です。
※他サイトにも掲載しております。

過労死転生した公務員、魔力がないだけで辺境に追放されたので、忠犬騎士と知識チートでざまぁしながら領地経営はじめます
水凪しおん
BL
過労死した元公務員の俺が転生したのは、魔法と剣が存在する異世界の、どうしようもない貧乏貴族の三男だった。
家族からは能無しと蔑まれ、与えられたのは「ゴミ捨て場」と揶揄される荒れ果てた辺境の領地。これは、事実上の追放だ。
絶望的な状況の中、俺に付き従ったのは、無口で無骨だが、その瞳に確かな忠誠を宿す一人の護衛騎士だけだった。
「大丈夫だ。俺がいる」
彼の言葉を胸に、俺は決意する。公務員として培った知識と経験、そして持ち前のしぶとさで、この最悪な領地を最高の楽園に変えてみせると。
これは、不遇な貴族と忠実な騎士が織りなす、絶望の淵から始まる領地改革ファンタジー。そして、固い絆で結ばれた二人が、やがて王国を揺るがす運命に立ち向かう物語。
無能と罵った家族に、見て見ぬふりをした者たちに、最高の「ざまぁ」をお見舞いしてやろうじゃないか!

虐げられた令息の第二の人生はスローライフ
りまり
BL
僕の生まれたこの世界は魔法があり魔物が出没する。
僕は由緒正しい公爵家に生まれながらも魔法の才能はなく剣術も全くダメで頭も下から数えたほうがいい方だと思う。
だから僕は家族にも公爵家の使用人にも馬鹿にされ食事もまともにもらえない。
救いだったのは僕を不憫に思った王妃様が僕を殿下の従者に指名してくれたことで、少しはまともな食事ができるようになった事だ。
お家に帰る事なくお城にいていいと言うので僕は頑張ってみたいです。
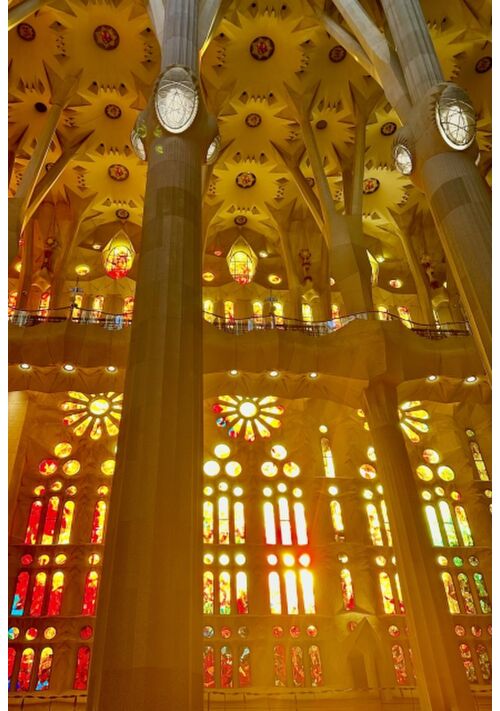
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。


【8話完結】帰ってきた勇者様が褒美に私を所望している件について。
キノア9g
BL
異世界召喚されたのは、
ブラック企業で心身ボロボロになった陰キャ勇者。
国王が用意した褒美は、金、地位、そして姫との結婚――
だが、彼が望んだのは「何の能力もない第三王子」だった。
顔だけ王子と蔑まれ、周囲から期待されなかったリュシアン。
過労で倒れた勇者に、ただ優しく手を伸ばしただけの彼は、
気づかぬうちに勇者の心を奪っていた。
「それでも俺は、あなたがいいんです」
だけど――勇者は彼を「姫」だと誤解していた。
切なさとすれ違い、
それでも惹かれ合う二人の、
優しくて不器用な恋の物語。
全8話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















