33 / 33
豪炎の悪夢
しおりを挟む
それからの手腕は鮮やかの一言。
片手を失っているとは思えぬほどの身のこなしで、猛然と突っ込んでくる魔物をかわす。
「だから言ったろ」
爆音とともに砕け散った床を、数センチの差で身をひるがえしながら口を開く。
「僕をなめるな、ってさ」
叩き込む一撃。
素早く背後に回り込み、大きく切りつけた。
肉が爆ぜ、骨が砕ける手応えに思わず口角が上がる。
まさに興奮と恍惚のないまぜとなった瞬間。魔物を狩る冒険者としての本能ともいえよう。
『っ、ギャ゙ァ゙ァァ゙ァァァッ!!!』
それからはただひたすら舞った。
刃をつきたてて、絶望の幻想を消し去るように。断続的に響く断末魔すら、耳に心地良くて。
そうこれだ、これなのだ。冒険者である自分が飢えていた、狩りの本能。獲物を追い詰め、絶対的な強さを見せつけていく。
そして切り開く、己の未来を。
「殺してやる、全部……悪夢なんてすべて……っ」
知らず知らずのうちにつぶやいていた。忌々しい、この荒廃した世界を壊したくてたまらない。
そうして早く会いたかった。
愛する娘に。そして、すべてが元に戻るはず。
そう疑わなかったのだ。その時の彼は。
「っ、さっさと、くたばれ。この化け物ッ!」
『亡霊を追うのは楽しい、かしら』
「なっ、なにッ!?」
鋭い痛みと衝撃に思考停止する。
囁きは不快な機械音に似ていて、ほとばしる血潮は――。
「あ゙ッ、あ゙、な、なん、で」
おびただしい赤の中で呻いているのは、なぜか自分。切りつけていたはずの悪魔は、冷たい宝石のような瞳を歪に煌めかせ嗤う。
思わず手にしていた剣を投げ捨てて床に膝をついたルイトを、巨大な影が見下ろした。
『言ったでしょう。ここは夢の中。そしてアタシは』
悪夢の毒を撒き散らす影――、優雅に発音する異形の口。
『悪夢を受け入れる準備はできて? 子猫ちゃん』
ブルル、と馬のようにいなないた。
「くっ」
やはり自分の夢の中とはいえ、それを操る夢魔には勝てないのか。
夢とは思えぬ痛みの中、ルイトは奥歯を食いしばる。そうでもしていないと、今にも倒れてしまいそうなのだ。
その証拠に、どんどん目がかすんでいく。古ぼけた廃屋の部屋も、打ち捨てられている火の気を感じさせないランプや散らばるガラスの破片も色を失っていた。
「ぁ……っ、ち、ちがう、これは現実、じゃない」
『そうね。アナタの夢の中。そしてアタシの養分となる』
「ほざくなッ!」
なにかが違う、そう思った。
眠りから目覚めて、先程まで見ていた夢を忘れていた時のような違和感。実際は逆でここが幻想の世界であるのに関わらず、だ。
「大人しくやられると思うなよ」
『でもねぇ、すでにその心は悪夢に蝕まれているのよね』
欠損した左腕。足もずたずたで、立っているのがやっとの状態。しかし。
「そうかもしれないな」
そう言いつつ壁きわに手を伸ばす。
すると、木のささくれが左の人差し指を傷つけた。
微かな痛み。この感覚だけが最悪な状況への一筋の光となるのだ。
確かにそこに左腕が存在という、確証。
「だとしてもこのまま、一人勝ちにはさせないぜ」
『ふふ、いまさらなにを――っ、がッ!?』
転がっている剣、ではなくガラスの破片を投げつけた。その異形の影に向かって。
「すべては嘘だった」
これみよがしに現れた剣、この部屋の光景に大きな仕掛けがあったのだ。夢に寄生し、その精神すら乗っ取ろうとする夢魔の罠。
『ア゙……ガッ……ィ゙ぎ、な゙、ナニ゙、ヲ……ッ』
ぐにゃりと歪む巨体、揺らめく蜃気楼のように。一瞬、極彩色に彩られた空間にルイトは自らの計算が正しかったと知る。
「夢というのは人の精神世界らしいな。だとすれば、そこに介入するお前には何らかの小道具が必要なはずだ」
本来なら、完全なる他者が存在し得ない空間に出現するには悪魔といえど様々な魔法と舞台装置がいるのだろう。
ぐにゃぐにゃと形を粘土のように変化させながら苦しみ喘ぐ悪魔を前に、ルイトは立った。
その左手には古びたランプ。
「この部屋に元々あったものでこそ、意味があったんだな」
やはりあの影の一部が彼女の弱点であるのは間違いないらしい。しかし、それを攻撃するのは最初からここにあったモノでないと意味は無い。
あの剣は、夢魔の用意したルイトの精神を揺さぶり深層部へ食い込むための幻想に過ぎなかったのだ。
夢の中というのは本人の思い通りになるとはいうものの、そんな簡単なことでは無い。
無意識、無自覚といった言わば自らも知らぬ欲求において変化するのだ。
簡単に双剣が彼の手に出現するのは、ハナから不自然な話であった。
そこまで思い入れのある物ではなかったのだ。
「このランプ、とても懐かしい」
怪我ひとつない指で、錆びたそれを撫でる。
「あの街に来た時、売りつけられたんだ。魔具ランプだって。田舎者の僕はそんな馬鹿みたいな嘘にひっかかって」
大都会の街に出ていきなり悪徳商人に騙されて、有り金のうち数割をはたいた微妙にイヤな記憶だ。
「あのガラス片だって。僕がこの街で最初に付き合った彼女が別れる前、目の前で叩きつけられたグラスでね」
あれは自分が悪かった。
まだスマートな遊び方を知らず、変に本気にさせてしまった。それからすったもんだしたが、隣町にて踊り子をしていると風の噂で聞いている。数年前とはいえ、若気の至りだろう。
「いつまでも砕けているのは多分、 僕にも未練があるからなのかなぁ」
そんなことを言いながら歩み寄るルイトは、右手の指をぱちんと鳴らし呪文を唱えた。
「【点火】!」
爆ぜたのはほんの小さな種火。
しかし古びたランプに灯りをともすのには充分である。
『ナ゙……なニ゙、を゙……』
「これで丸焼きにしてやるよ」
にやりと微笑むと彼は、火のついたランプを躊躇なく床に叩きつけた。夢魔の、揺らめく影に向かって。
『ギャァ゙ァァァ゙ァァッ!!!』
一気に立つ火柱。肉が焦げ、体毛が焼ける嫌な匂いが辺りに立ち込める。絶叫し、激しくのたうつ悪魔の身体もまた炎に包まれていた。
「弱点を焼かれれば相応に苦しいんだな」
『ア゙、ヅ、ィ゙ィィッ、ヤめろ゙ぉォォッ!!!』
腐肉が焦げたような悪臭に顔をしかめながら、ルイトは心の底から念じる。
――この手に武器を、と。
「えっ……」
手の中にはナイフ。小さくて、まるでこの醜く巨大な悪魔を引き裂けるとは思えぬものだった。
しかし、選んではいられない。
「信じるしかないのか」
これが己の精神世界において、真実の武器。なぜか慣れ親しんだ大剣や双剣でなく。
まるで貴族の娘が護身用に持つような。
「!」
その時、ルイトの胸が小さく痛む。わずかな棘が刺さったような、うっかりすると逃してしまう感覚。しかし違和感だけが、いつまでも不快な。
「な、なんだ」
なにか大切な事を忘れている。そんな気がした。
『キャハハハハッ! バカめ、愚かな人間風情がッ!!!』
「!?」
轟々と燃える炎の中、夢魔が嗤い叫んだ。
『夢を燃やす者はっ、その精神ごと灰に返レェェェェッ!!!』
「どういう――うわぁぁぁっ!!!」
すぐにその意味が理解出来た。身体を猛烈な熱が襲ったのだ。
「あ゙ッ、ぐっ」
思わずその場に崩れ落ちるほどの苦痛。目の前の黒い塊がしゃがれ声で嘲笑する姿すら、目がかすんで見えなくなるほどに。
「し、しまっ、た」
ここは彼の夢の中。今までも、部屋の外が燃えたことがあってもこの部屋そのものが破壊されたことはなかった。それは、ここがルイトの精神の核となる聖域の一つであったから。
主に記憶をの末端をつかさどる場所。
元来、夢というのはその人の記憶を整理するための感覚。
だからこそ古く朽ちた姿をしていても、記憶の中の物が詰め込まれていたのだ。
きっとこの部屋自体も、彼にとって何らかの思い出のひとつなのだろう。
そこを破壊するということは。
『こうなったらすべて食らってやる。タダではすまさない。すべて、壊して、食らって、潰してやる、殺して、やる、死ね、死ね死ね死ね死ね死ねッ、あははははははっ、愚かなヤツめーッ!!』
紅く大きな裂け目のような口が、目の前に開かれる。そこにのぞいた鋭利な歯が、鈍く光る。
もはやここまでか、と額に汗をにじませた時だった。
「!」
ぴちゃん――と水の音が響く。
激痛に悶える狂気と絶望の中でそれはたしかに、そして凛として。
その刹那、水面に大きな波紋が広がるようなイメージが脳内に広がった。
「あ……」
一人の男の姿が、脳裏に蘇る。
深いエメラルドグリーンの瞳が印象的なで、はっとするほど美しい男。
いつだったか。優しく、しかしどこか哀しみのような影を背負った表情が忘れられない。
何度手をのばそうと思っただろう。大きく無骨な指に触れたい、触れて欲しいと願ったこともある。
ふっくらとした唇を奪ってしまえたらと――。
「っ、僕はなにを」
こんな状況で何を考えているのだ。苛立ちより焦燥と羞恥で頭を抱えそうになる。しかしそんな思考とは裏腹に、呟いた名前。
「リュウ、ガ」
会いたい、そう願った。ルイトは気づいてしまったのだ。
「ルシア……リュウガ……」
どうして彼らがここにいないのだろう。
愛しい娘と、あの男がそばにいない。孤独感に叫び出したくなる。
偽りであってもいい、それでもいいから会いたい。
切実は願いに心が引き裂かれそう。胸が痛み、苦しげに吐息を漏らす。
すると。
ふと遠くで、子どもの声を聞いた。
「――やっと俺たちの名を呼んでくれた」
ふわり優しく背中を覆った体温。熱い囁きに目を見開く。
「リュウ、ガ……?」
「ああ。ようやく会えた」
温もりに涙があふれる。夢であれば今度こそ覚めないで欲しい、そう願った。
「ルイト。お前の忌々しい悪夢ごと、覚ましてやろう」
心を見透かしたかのような言葉とともに男の声は笑い、そして。
『あ゙ア゙ァァァ゙ァァァ゙ッ!!!』
目の前の悪魔は断末魔とともに、突如として上がった黒炎の業火に包まれた。
それは一瞬。あとの煤さえ残さず、霧散したのだ。
「……」
「帰ろう、現実に」
唖然とするルイトに、懐かしい男の声。しかし振り返ることさえできない。
その代わり、抱き寄せられた腕にそっと自らの指を祈るような重ねた。
片手を失っているとは思えぬほどの身のこなしで、猛然と突っ込んでくる魔物をかわす。
「だから言ったろ」
爆音とともに砕け散った床を、数センチの差で身をひるがえしながら口を開く。
「僕をなめるな、ってさ」
叩き込む一撃。
素早く背後に回り込み、大きく切りつけた。
肉が爆ぜ、骨が砕ける手応えに思わず口角が上がる。
まさに興奮と恍惚のないまぜとなった瞬間。魔物を狩る冒険者としての本能ともいえよう。
『っ、ギャ゙ァ゙ァァ゙ァァァッ!!!』
それからはただひたすら舞った。
刃をつきたてて、絶望の幻想を消し去るように。断続的に響く断末魔すら、耳に心地良くて。
そうこれだ、これなのだ。冒険者である自分が飢えていた、狩りの本能。獲物を追い詰め、絶対的な強さを見せつけていく。
そして切り開く、己の未来を。
「殺してやる、全部……悪夢なんてすべて……っ」
知らず知らずのうちにつぶやいていた。忌々しい、この荒廃した世界を壊したくてたまらない。
そうして早く会いたかった。
愛する娘に。そして、すべてが元に戻るはず。
そう疑わなかったのだ。その時の彼は。
「っ、さっさと、くたばれ。この化け物ッ!」
『亡霊を追うのは楽しい、かしら』
「なっ、なにッ!?」
鋭い痛みと衝撃に思考停止する。
囁きは不快な機械音に似ていて、ほとばしる血潮は――。
「あ゙ッ、あ゙、な、なん、で」
おびただしい赤の中で呻いているのは、なぜか自分。切りつけていたはずの悪魔は、冷たい宝石のような瞳を歪に煌めかせ嗤う。
思わず手にしていた剣を投げ捨てて床に膝をついたルイトを、巨大な影が見下ろした。
『言ったでしょう。ここは夢の中。そしてアタシは』
悪夢の毒を撒き散らす影――、優雅に発音する異形の口。
『悪夢を受け入れる準備はできて? 子猫ちゃん』
ブルル、と馬のようにいなないた。
「くっ」
やはり自分の夢の中とはいえ、それを操る夢魔には勝てないのか。
夢とは思えぬ痛みの中、ルイトは奥歯を食いしばる。そうでもしていないと、今にも倒れてしまいそうなのだ。
その証拠に、どんどん目がかすんでいく。古ぼけた廃屋の部屋も、打ち捨てられている火の気を感じさせないランプや散らばるガラスの破片も色を失っていた。
「ぁ……っ、ち、ちがう、これは現実、じゃない」
『そうね。アナタの夢の中。そしてアタシの養分となる』
「ほざくなッ!」
なにかが違う、そう思った。
眠りから目覚めて、先程まで見ていた夢を忘れていた時のような違和感。実際は逆でここが幻想の世界であるのに関わらず、だ。
「大人しくやられると思うなよ」
『でもねぇ、すでにその心は悪夢に蝕まれているのよね』
欠損した左腕。足もずたずたで、立っているのがやっとの状態。しかし。
「そうかもしれないな」
そう言いつつ壁きわに手を伸ばす。
すると、木のささくれが左の人差し指を傷つけた。
微かな痛み。この感覚だけが最悪な状況への一筋の光となるのだ。
確かにそこに左腕が存在という、確証。
「だとしてもこのまま、一人勝ちにはさせないぜ」
『ふふ、いまさらなにを――っ、がッ!?』
転がっている剣、ではなくガラスの破片を投げつけた。その異形の影に向かって。
「すべては嘘だった」
これみよがしに現れた剣、この部屋の光景に大きな仕掛けがあったのだ。夢に寄生し、その精神すら乗っ取ろうとする夢魔の罠。
『ア゙……ガッ……ィ゙ぎ、な゙、ナニ゙、ヲ……ッ』
ぐにゃりと歪む巨体、揺らめく蜃気楼のように。一瞬、極彩色に彩られた空間にルイトは自らの計算が正しかったと知る。
「夢というのは人の精神世界らしいな。だとすれば、そこに介入するお前には何らかの小道具が必要なはずだ」
本来なら、完全なる他者が存在し得ない空間に出現するには悪魔といえど様々な魔法と舞台装置がいるのだろう。
ぐにゃぐにゃと形を粘土のように変化させながら苦しみ喘ぐ悪魔を前に、ルイトは立った。
その左手には古びたランプ。
「この部屋に元々あったものでこそ、意味があったんだな」
やはりあの影の一部が彼女の弱点であるのは間違いないらしい。しかし、それを攻撃するのは最初からここにあったモノでないと意味は無い。
あの剣は、夢魔の用意したルイトの精神を揺さぶり深層部へ食い込むための幻想に過ぎなかったのだ。
夢の中というのは本人の思い通りになるとはいうものの、そんな簡単なことでは無い。
無意識、無自覚といった言わば自らも知らぬ欲求において変化するのだ。
簡単に双剣が彼の手に出現するのは、ハナから不自然な話であった。
そこまで思い入れのある物ではなかったのだ。
「このランプ、とても懐かしい」
怪我ひとつない指で、錆びたそれを撫でる。
「あの街に来た時、売りつけられたんだ。魔具ランプだって。田舎者の僕はそんな馬鹿みたいな嘘にひっかかって」
大都会の街に出ていきなり悪徳商人に騙されて、有り金のうち数割をはたいた微妙にイヤな記憶だ。
「あのガラス片だって。僕がこの街で最初に付き合った彼女が別れる前、目の前で叩きつけられたグラスでね」
あれは自分が悪かった。
まだスマートな遊び方を知らず、変に本気にさせてしまった。それからすったもんだしたが、隣町にて踊り子をしていると風の噂で聞いている。数年前とはいえ、若気の至りだろう。
「いつまでも砕けているのは多分、 僕にも未練があるからなのかなぁ」
そんなことを言いながら歩み寄るルイトは、右手の指をぱちんと鳴らし呪文を唱えた。
「【点火】!」
爆ぜたのはほんの小さな種火。
しかし古びたランプに灯りをともすのには充分である。
『ナ゙……なニ゙、を゙……』
「これで丸焼きにしてやるよ」
にやりと微笑むと彼は、火のついたランプを躊躇なく床に叩きつけた。夢魔の、揺らめく影に向かって。
『ギャァ゙ァァァ゙ァァッ!!!』
一気に立つ火柱。肉が焦げ、体毛が焼ける嫌な匂いが辺りに立ち込める。絶叫し、激しくのたうつ悪魔の身体もまた炎に包まれていた。
「弱点を焼かれれば相応に苦しいんだな」
『ア゙、ヅ、ィ゙ィィッ、ヤめろ゙ぉォォッ!!!』
腐肉が焦げたような悪臭に顔をしかめながら、ルイトは心の底から念じる。
――この手に武器を、と。
「えっ……」
手の中にはナイフ。小さくて、まるでこの醜く巨大な悪魔を引き裂けるとは思えぬものだった。
しかし、選んではいられない。
「信じるしかないのか」
これが己の精神世界において、真実の武器。なぜか慣れ親しんだ大剣や双剣でなく。
まるで貴族の娘が護身用に持つような。
「!」
その時、ルイトの胸が小さく痛む。わずかな棘が刺さったような、うっかりすると逃してしまう感覚。しかし違和感だけが、いつまでも不快な。
「な、なんだ」
なにか大切な事を忘れている。そんな気がした。
『キャハハハハッ! バカめ、愚かな人間風情がッ!!!』
「!?」
轟々と燃える炎の中、夢魔が嗤い叫んだ。
『夢を燃やす者はっ、その精神ごと灰に返レェェェェッ!!!』
「どういう――うわぁぁぁっ!!!」
すぐにその意味が理解出来た。身体を猛烈な熱が襲ったのだ。
「あ゙ッ、ぐっ」
思わずその場に崩れ落ちるほどの苦痛。目の前の黒い塊がしゃがれ声で嘲笑する姿すら、目がかすんで見えなくなるほどに。
「し、しまっ、た」
ここは彼の夢の中。今までも、部屋の外が燃えたことがあってもこの部屋そのものが破壊されたことはなかった。それは、ここがルイトの精神の核となる聖域の一つであったから。
主に記憶をの末端をつかさどる場所。
元来、夢というのはその人の記憶を整理するための感覚。
だからこそ古く朽ちた姿をしていても、記憶の中の物が詰め込まれていたのだ。
きっとこの部屋自体も、彼にとって何らかの思い出のひとつなのだろう。
そこを破壊するということは。
『こうなったらすべて食らってやる。タダではすまさない。すべて、壊して、食らって、潰してやる、殺して、やる、死ね、死ね死ね死ね死ね死ねッ、あははははははっ、愚かなヤツめーッ!!』
紅く大きな裂け目のような口が、目の前に開かれる。そこにのぞいた鋭利な歯が、鈍く光る。
もはやここまでか、と額に汗をにじませた時だった。
「!」
ぴちゃん――と水の音が響く。
激痛に悶える狂気と絶望の中でそれはたしかに、そして凛として。
その刹那、水面に大きな波紋が広がるようなイメージが脳内に広がった。
「あ……」
一人の男の姿が、脳裏に蘇る。
深いエメラルドグリーンの瞳が印象的なで、はっとするほど美しい男。
いつだったか。優しく、しかしどこか哀しみのような影を背負った表情が忘れられない。
何度手をのばそうと思っただろう。大きく無骨な指に触れたい、触れて欲しいと願ったこともある。
ふっくらとした唇を奪ってしまえたらと――。
「っ、僕はなにを」
こんな状況で何を考えているのだ。苛立ちより焦燥と羞恥で頭を抱えそうになる。しかしそんな思考とは裏腹に、呟いた名前。
「リュウ、ガ」
会いたい、そう願った。ルイトは気づいてしまったのだ。
「ルシア……リュウガ……」
どうして彼らがここにいないのだろう。
愛しい娘と、あの男がそばにいない。孤独感に叫び出したくなる。
偽りであってもいい、それでもいいから会いたい。
切実は願いに心が引き裂かれそう。胸が痛み、苦しげに吐息を漏らす。
すると。
ふと遠くで、子どもの声を聞いた。
「――やっと俺たちの名を呼んでくれた」
ふわり優しく背中を覆った体温。熱い囁きに目を見開く。
「リュウ、ガ……?」
「ああ。ようやく会えた」
温もりに涙があふれる。夢であれば今度こそ覚めないで欲しい、そう願った。
「ルイト。お前の忌々しい悪夢ごと、覚ましてやろう」
心を見透かしたかのような言葉とともに男の声は笑い、そして。
『あ゙ア゙ァァァ゙ァァァ゙ッ!!!』
目の前の悪魔は断末魔とともに、突如として上がった黒炎の業火に包まれた。
それは一瞬。あとの煤さえ残さず、霧散したのだ。
「……」
「帰ろう、現実に」
唖然とするルイトに、懐かしい男の声。しかし振り返ることさえできない。
その代わり、抱き寄せられた腕にそっと自らの指を祈るような重ねた。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

俺の居場所を探して
夜野
BL
小林響也は炎天下の中辿り着き、自宅のドアを開けた瞬間眩しい光に包まれお約束的に異世界にたどり着いてしまう。
そこには怪しい人達と自分と犬猿の仲の弟の姿があった。
そこで弟は聖女、自分は弟の付き人と決められ、、、
このお話しは響也と弟が対立し、こじれて決別してそれぞれお互い的に幸せを探す話しです。
シリアスで暗めなので読み手を選ぶかもしれません。
遅筆なので不定期に投稿します。
初投稿です。

出戻り王子が幸せになるまで
あきたいぬ大好き(深凪雪花)
BL
初恋の相手と政略結婚した主人公セフィラだが、相手には愛人ながら本命がいたことを知る。追及した結果、離縁されることになり、母国に出戻ることに。けれど、バツイチになったせいか父王に厄介払いされ、後宮から追い出されてしまう。王都の下町で暮らし始めるが、ふと訪れた先の母校で幼馴染であるフレンシスと再会。事情を話すと、突然求婚される。
一途な幼馴染×強がり出戻り王子のお話です。
※他サイトにも掲載しております。

過労死転生した公務員、魔力がないだけで辺境に追放されたので、忠犬騎士と知識チートでざまぁしながら領地経営はじめます
水凪しおん
BL
過労死した元公務員の俺が転生したのは、魔法と剣が存在する異世界の、どうしようもない貧乏貴族の三男だった。
家族からは能無しと蔑まれ、与えられたのは「ゴミ捨て場」と揶揄される荒れ果てた辺境の領地。これは、事実上の追放だ。
絶望的な状況の中、俺に付き従ったのは、無口で無骨だが、その瞳に確かな忠誠を宿す一人の護衛騎士だけだった。
「大丈夫だ。俺がいる」
彼の言葉を胸に、俺は決意する。公務員として培った知識と経験、そして持ち前のしぶとさで、この最悪な領地を最高の楽園に変えてみせると。
これは、不遇な貴族と忠実な騎士が織りなす、絶望の淵から始まる領地改革ファンタジー。そして、固い絆で結ばれた二人が、やがて王国を揺るがす運命に立ち向かう物語。
無能と罵った家族に、見て見ぬふりをした者たちに、最高の「ざまぁ」をお見舞いしてやろうじゃないか!

虐げられた令息の第二の人生はスローライフ
りまり
BL
僕の生まれたこの世界は魔法があり魔物が出没する。
僕は由緒正しい公爵家に生まれながらも魔法の才能はなく剣術も全くダメで頭も下から数えたほうがいい方だと思う。
だから僕は家族にも公爵家の使用人にも馬鹿にされ食事もまともにもらえない。
救いだったのは僕を不憫に思った王妃様が僕を殿下の従者に指名してくれたことで、少しはまともな食事ができるようになった事だ。
お家に帰る事なくお城にいていいと言うので僕は頑張ってみたいです。
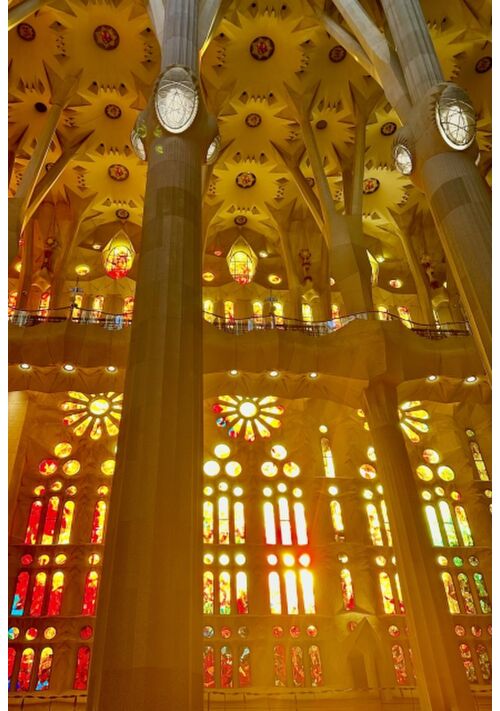
優秀な婚約者が去った後の世界
月樹《つき》
BL
公爵令嬢パトリシアは婚約者である王太子ラファエル様に会った瞬間、前世の記憶を思い出した。そして、ここが前世の自分が読んでいた小説『光溢れる国であなたと…』の世界で、自分は光の聖女と王太子ラファエルの恋を邪魔する悪役令嬢パトリシアだと…。
パトリシアは前世の知識もフル活用し、幼い頃からいつでも逃げ出せるよう腕を磨き、そして準備が整ったところでこちらから婚約破棄を告げ、母国を捨てた…。
このお話は捨てられた後の王太子ラファエルのお話です。


【8話完結】帰ってきた勇者様が褒美に私を所望している件について。
キノア9g
BL
異世界召喚されたのは、
ブラック企業で心身ボロボロになった陰キャ勇者。
国王が用意した褒美は、金、地位、そして姫との結婚――
だが、彼が望んだのは「何の能力もない第三王子」だった。
顔だけ王子と蔑まれ、周囲から期待されなかったリュシアン。
過労で倒れた勇者に、ただ優しく手を伸ばしただけの彼は、
気づかぬうちに勇者の心を奪っていた。
「それでも俺は、あなたがいいんです」
だけど――勇者は彼を「姫」だと誤解していた。
切なさとすれ違い、
それでも惹かれ合う二人の、
優しくて不器用な恋の物語。
全8話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















