46 / 109
やっと出会えた二人
46.思い出は味がする
しおりを挟む
眠れぬ夜を過ごした翌日。
目の下にくまを作った真紘と重盛を見兼ねたノエルは今日の予定を全て中止にした。
ルーミは真紘と遊ぶと言って聞かなかったが、ジョエルに抱えられ街へと散歩に出て行った。
森に行くので汚れても良い格好で、と言いつけられた真紘と重盛は動きやすい格好に着替えて玄関に集まった。
ノエルは淡々と今日の行程を言い渡す。そして最後にこう付け加えた。
「いいですか、本日中に色々と決着をつけてください。やることが終わったら裏山にある大木の下でピクニックなんていかがでしょうか」
「……決着ってなんのことかさっぱりわかんねぇ」
しらばっくれる重盛に構わず、ノエルは続けた。
「ささ、いってらっしゃいませ。あっ、薬草もついでに摘んできてくださいね。回復魔法では治せない腰痛や肩こりに効くやつですよ。では!」
有無を言わさぬ圧が重盛と真紘にのしかかる。二人はコクコクと頷き、裏山を目指した。
その途中に騎士団の訓練場があり、ノエルから預けられた魔石を担当者に受け渡した。
屋敷のすぐ横にあるのは剣などの道具を扱う訓練場で、こちらは魔法の訓練場だ。
そのさらに奥には山が広がっていて、薄っすらと紅葉した木々も見える。
タルハネイリッカは林業が盛んで、住居区よりも森林部が圧倒的に多い。
行けども行けども坂道だ。
「重盛、体調悪いんじゃない? まだ虫も完全にいなくなったわけじゃないし、薬草採取は僕一人でも大丈夫だよ」
後ろを歩く真紘は先をずんずんと進む重盛に声を掛けた。
「んや、ちょっと寝不足なだけ。それより真紘ちゃんの方がいつも以上に真っ白じゃん。先帰って休んでてもいいよ」
「いや、僕もちょっと寝不足なだけだから……」
「……そっか。珍しいな」
三言二言で会話が終わる。
こんなことは初めてであった。
どうしよう。
重盛は海外にもいたというし、距離感が人よりも近いだけでそこに感情がなかったとしたら、こちらからの下心は不快だったのかもしれない。
はっきりしない自分の態度に呆れられたのかもしれない。
考えはどんどんマイナスな方向へと沈んでいく。
遠のいていく重盛の背中に手を伸ばしてみても、真紘は何も掴めなかった。
悶々としている間に、ノエルが言っていた大きな木の下に到着した。
重盛はレジャーシートをせっせと広げていく。
真紘はこういう時に率先して動かなければと反対側のシートの端を丁寧に整え、風に飛ばされぬよう四隅に石を乗せた。
「この石何?」
「漬物石だよ。杭を打ち込むよりも簡単でいいかなと思って」
「さっすが、助かる~! てか、ポンと魔法で出せるってことは地球でも漬物作ってたの?」
「祖父母がね。遊びに行った時によく手伝ってたから。料理はできないけど、ずっと観察していたから調理器具を出すのは得意かも。祖父母は手際が良くて、魔法みたいに美味しいご飯をいつも作ってくれたんだ」
「いいな、それ。やっぱ飯の記憶は残るもんだよなぁ」
シートに寝そべった重盛は青い空を見上げて呟いた。
亡くなった母の味を思い出しているのだろうか。
志水家の味といえば、仕事で忙しい両親に代わって姉が作った甘い卵焼きと、馴染みの弁当屋の揚げ物だ。
二人分のスペースを開けて、真紘も横になった。
そよそよと吹く秋の風は心地よく、心が洗われるようであった。
木漏れ日がチカチカと目元を照らし、真紘は眩しさに眉間に皺を寄せた。
どうやらあのまま寝てしまったようだ。
遠くにあった楕円形の雲はとっくの昔に形を変え、どこかに消え去っていた。
「ん……。ごめん。また寝ちゃった。もうお昼の時間かな」
腕時計を見ると時刻は十一時だった。
薄いミント色のノーカラーシャツにいつものチェックのショールを羽織ってきたが、上半身を起こすとそれは腹からずるりと落ちた。
足元には重盛が着ていた桃色のシャツが掛かっている。
「寒くないとはいえ、腹出して寝る季節は終わったんじゃね?」
「お、お見苦しいところを……ありがとう、上着返すね」
「いーえ、どういたしまして。よっし、昼飯作るか」
頭をわしゃわしゃと撫でられ、真紘は驚きの声をあげた。
雑なようでいて、起こさぬようそっと自分の上着をかけてくれるような優しさの塩梅が心地よく、すぐに離れていく手が寂しくもあった。
立候補制の役割分担はすぐに決まった。
重盛は昼食の準備、真紘は薬草採取だ。
別れる直前、重盛はまっぽけに収納している時の神からもらった調味料を使っても良いかと聞いてきた。
元より重盛のために頼んだ物なので、真紘は勿論と返した。
真紘は一時間ほど森を駆け回り、薬草をひたすら集めた。
気分が晴れない日は一人で何かに打ち込むに限る。読書や睡眠もその手段の一つだ。
初めこそ似たような雑草と薬草を見分けるのに苦労したが、今となれば板に付いたものだ。
地球にいた頃も、自宅にあった植物の書物は好きで何度も読み込んでいたし、母のガーデニングを休日に手伝うこともあったが、あくまで趣味の範囲だったので、大学は文学部を志望していた。
志望動機は文字を読むのが好きという漠然とした理由と、父親と同じ道に進むかは決めかねていたが、教職の資格を取ろうと考えていたからだ。
ふと、農学部や薬学部も良かったかもしれないと、もしもの世界を想う。
あのまま地球で暮らしていたら、きっと重盛とここまで仲良くなることはなかっただろう。元々交わることのない運命だったのなら、彼のために今離れるべきか。
この半年間で生きる術は教わった。お互いがいないと生きていけないわけではない。
自分の身勝手な独占欲で彼を縛り付けておくのは勿体ない気がした。
「このまま離れた方がいいのかな……。適切な友人との距離ってどれくらいなんだろう」
人付き合いを避けてきた真紘に取って、それは大変難しい問題であった。
今日も朝から重盛に避けられている気がした。
普段はのんびり歩くこちらのペースに合わせてくれていたのだと、先を歩く彼の背中を見て知った。
このままエルフらしく、森でひっそり動植物の研究をしながら一人で暮らした方が良いのではないか、と殻に閉じこもっていた頃の自分が囁く。
懐に入れていた便利屋の名刺を触ると、指に痛みが走った。
紙で右手の人差し指の先端を切ったようだ。
ぷっくりと赤い粒が膨らむ。
重盛は何度か寝る前に鼻血を出していたので、赤いことは知っていたが、エルフも血液は赤いらしい。
鏡に映る肌はいつも真っ白で、自分の血はもしかしたら緑色かもしれない、なんて少し思っていた。
同じ人間なのに、どこか人と違うと思い込んでいた自分がいたことに気付く。
案外、今回の悩みもそんな思い込みなのかもしれない。
しかし、自分は人の感情に対して疎いところがあると理解している。それで痛い思いをしたのだから、人の何倍も考えて行動しなくてはならない。
異世界に来てからというもの、人との縁に恵まれているから、結果的に丸く収まっているだけだと常々感じていた。
自分なりに努力してきたつもりだが、いつまで経っても中途半端から抜け出せない。
もう少し、自分に自信が持てれば何が変わるのだろうか。
「うー、だめだめ! ポジティブに、前向きに、良い魔法は良い気から! 先ずは、視覚から明るくいこう!」
真紘は沈んだ気持ちを吹き飛ばすため、オーケストラの指揮者のように杖を振るい、空に光のシャワーを降らせた。
大木の下に戻ると、懐かしい匂いがした。
「ただいま」
「おっかえり~。森ん中で魔法ぶっ放して遊んでたっしょ。真紘ちゃんがどこにいるか分かって、こっちの準備も楽だったわ。じゃーん、本日のお昼はこちらです!」
「遊んでたわけじゃないよ、えっ、これが昼食――」
キャンプ用の簡易テーブルに並べられたおかずは意外にも下町の定食屋のようなメニューだった。
王都での二人暮らしでは専ら洋食が多く、どれも美味しいものだったが、この醤油や味噌の香ばしさが恋しかった。
つやつやと輝く白米、きつね色のコロッケ二つ、かつお節の乗ったおひたし、細切りにした人参の酢の和え物、そしてわかめの味噌汁。
日本人ならば一度は食べたことのあるメニューだが、実に半年ぶりの和食に真紘のテンションは今までにないほど上がっていた。
調味料一式の中に、基本の【さしすせそ】が入っていたのは知っていたが、料理酒、油、乾燥わかめやかつお節といった出汁が取れるものまで入っていたらしい。
姉の姿をした時の神を思い出し、真紘は改めて感謝した。
「どうよ、懐かしいっしょ? 漬物は流石に時間的に無理だったから、酢の和え物にしてみた。胡瓜とかこの世界にもあんのかなぁ。俺、漬物だと大根と柚子のが一番好きなんだよねぇ」
メニューの説明を聞きながら、真紘は少し泣きそうになった。
「わあ~! やったあ、嬉しい! わしょくだぁっ!」
「うおっ! わはっ、はっはッ! そんな喜んでくれると思わなかった~! もっと早く作れば良かった、ごめんな。温かいうちに食おうぜ」
低いテーブルに合わせ、正座するといよいよ日本の食事風景だ。
「うう、正座もできて嬉しい」
「喜ぶポイントそこかよ! んじゃ、せーので」
「いただきます」「いただきまーす」
真紘はうきうきと箸を持った。
早速、味噌汁のお椀を持ち上げ鼻に近づけると、こちらを伺う重盛と目が合った。
口の端を上げ、そのままゆっくりと啜る。
嗚呼、これだ。
目を閉じて故郷の味を噛み締める。鼻から味噌の優しい風味が抜け、じわっと心臓が芯から温まったような感覚に肩の力が抜けた。
次いで副菜の酢の物、おひたしを口に運ぶ。
素材の味を生かしつつ、ひと手間加えられた野菜は、どれも体が求めていたもので満足感と幸福感でいっぱいになった。
味噌汁と野菜だけでこんなに幸せになれる男子高校生は世界でただ二人だけだろう。緩む頬と目尻がそのまま蕩け落ちてしまいそうなほどだ。
そして、メインのコロッケを半分に箸で半分に割る。
中はごろっとしたジャガイモにひき肉といったシンプルなもの。
ソースはあえて付けず、そのまま食べた。
「ヒロちゃんってば、本当にコロッケ好きだよね。たまにはロースカツとか、ヒレカツにしたらいいのに」
妹の真織と、いつもの弁当屋に立ち寄る度に購入していたコロッケは、何も付けずとも下味がしっかりついているもので、一向に飽きが来ない至極の一品だった。
「だって美味しいんだから仕方ないよ。僕は一途だからいいの」
「うわーヒロちゃん、大人になっても実家から出ないでここに通うつもりでしょ」
姉そっくりな率直な物言いに真紘は笑い声を上げた。
「いいんだよ。もし実家から追い出されたらここに永久就職させてもらおうかな」
「だってさ、お姉さん。ヒロちゃんのことお婿にもらってくれる?」
ピンクのエプロンを着た女性は豪快に笑って、コロッケをもう一個サービスしてくれた。
そして誰かにそっくりな顔で彼女は言った。
「いいわよ。ヒロちゃんが大きくなったら、松永に永久就職しちゃいな」
「――ひろちゃん、真紘ちゃんッ!」
何度目かの呼びかけで心がリアースに帰ってきた。
コロッケを食べた友人がいきなり目の前でフリーズしては料理に何かあったのかと不安にさせてしまったかもしれない。真紘はハッとして正直に味の感想を伝える。
「どれもとっても美味しいよ。特にコロッケがあまりにも懐かしい味がしてさ。これが九条院家の味なんだね」
真紘の言葉に重盛は困ったように笑った。
既視感に懐かしい味。
中学の頃に突如閉店した弁当屋。
重盛の母は他界しているという事実。
ザァッと突風が草木を揺らし、辺りが騒めく。
違う、僕はこの味を昔から知っている。
「九条院じゃない。君は……」
二人の出会いは十年前に遡る。
目の下にくまを作った真紘と重盛を見兼ねたノエルは今日の予定を全て中止にした。
ルーミは真紘と遊ぶと言って聞かなかったが、ジョエルに抱えられ街へと散歩に出て行った。
森に行くので汚れても良い格好で、と言いつけられた真紘と重盛は動きやすい格好に着替えて玄関に集まった。
ノエルは淡々と今日の行程を言い渡す。そして最後にこう付け加えた。
「いいですか、本日中に色々と決着をつけてください。やることが終わったら裏山にある大木の下でピクニックなんていかがでしょうか」
「……決着ってなんのことかさっぱりわかんねぇ」
しらばっくれる重盛に構わず、ノエルは続けた。
「ささ、いってらっしゃいませ。あっ、薬草もついでに摘んできてくださいね。回復魔法では治せない腰痛や肩こりに効くやつですよ。では!」
有無を言わさぬ圧が重盛と真紘にのしかかる。二人はコクコクと頷き、裏山を目指した。
その途中に騎士団の訓練場があり、ノエルから預けられた魔石を担当者に受け渡した。
屋敷のすぐ横にあるのは剣などの道具を扱う訓練場で、こちらは魔法の訓練場だ。
そのさらに奥には山が広がっていて、薄っすらと紅葉した木々も見える。
タルハネイリッカは林業が盛んで、住居区よりも森林部が圧倒的に多い。
行けども行けども坂道だ。
「重盛、体調悪いんじゃない? まだ虫も完全にいなくなったわけじゃないし、薬草採取は僕一人でも大丈夫だよ」
後ろを歩く真紘は先をずんずんと進む重盛に声を掛けた。
「んや、ちょっと寝不足なだけ。それより真紘ちゃんの方がいつも以上に真っ白じゃん。先帰って休んでてもいいよ」
「いや、僕もちょっと寝不足なだけだから……」
「……そっか。珍しいな」
三言二言で会話が終わる。
こんなことは初めてであった。
どうしよう。
重盛は海外にもいたというし、距離感が人よりも近いだけでそこに感情がなかったとしたら、こちらからの下心は不快だったのかもしれない。
はっきりしない自分の態度に呆れられたのかもしれない。
考えはどんどんマイナスな方向へと沈んでいく。
遠のいていく重盛の背中に手を伸ばしてみても、真紘は何も掴めなかった。
悶々としている間に、ノエルが言っていた大きな木の下に到着した。
重盛はレジャーシートをせっせと広げていく。
真紘はこういう時に率先して動かなければと反対側のシートの端を丁寧に整え、風に飛ばされぬよう四隅に石を乗せた。
「この石何?」
「漬物石だよ。杭を打ち込むよりも簡単でいいかなと思って」
「さっすが、助かる~! てか、ポンと魔法で出せるってことは地球でも漬物作ってたの?」
「祖父母がね。遊びに行った時によく手伝ってたから。料理はできないけど、ずっと観察していたから調理器具を出すのは得意かも。祖父母は手際が良くて、魔法みたいに美味しいご飯をいつも作ってくれたんだ」
「いいな、それ。やっぱ飯の記憶は残るもんだよなぁ」
シートに寝そべった重盛は青い空を見上げて呟いた。
亡くなった母の味を思い出しているのだろうか。
志水家の味といえば、仕事で忙しい両親に代わって姉が作った甘い卵焼きと、馴染みの弁当屋の揚げ物だ。
二人分のスペースを開けて、真紘も横になった。
そよそよと吹く秋の風は心地よく、心が洗われるようであった。
木漏れ日がチカチカと目元を照らし、真紘は眩しさに眉間に皺を寄せた。
どうやらあのまま寝てしまったようだ。
遠くにあった楕円形の雲はとっくの昔に形を変え、どこかに消え去っていた。
「ん……。ごめん。また寝ちゃった。もうお昼の時間かな」
腕時計を見ると時刻は十一時だった。
薄いミント色のノーカラーシャツにいつものチェックのショールを羽織ってきたが、上半身を起こすとそれは腹からずるりと落ちた。
足元には重盛が着ていた桃色のシャツが掛かっている。
「寒くないとはいえ、腹出して寝る季節は終わったんじゃね?」
「お、お見苦しいところを……ありがとう、上着返すね」
「いーえ、どういたしまして。よっし、昼飯作るか」
頭をわしゃわしゃと撫でられ、真紘は驚きの声をあげた。
雑なようでいて、起こさぬようそっと自分の上着をかけてくれるような優しさの塩梅が心地よく、すぐに離れていく手が寂しくもあった。
立候補制の役割分担はすぐに決まった。
重盛は昼食の準備、真紘は薬草採取だ。
別れる直前、重盛はまっぽけに収納している時の神からもらった調味料を使っても良いかと聞いてきた。
元より重盛のために頼んだ物なので、真紘は勿論と返した。
真紘は一時間ほど森を駆け回り、薬草をひたすら集めた。
気分が晴れない日は一人で何かに打ち込むに限る。読書や睡眠もその手段の一つだ。
初めこそ似たような雑草と薬草を見分けるのに苦労したが、今となれば板に付いたものだ。
地球にいた頃も、自宅にあった植物の書物は好きで何度も読み込んでいたし、母のガーデニングを休日に手伝うこともあったが、あくまで趣味の範囲だったので、大学は文学部を志望していた。
志望動機は文字を読むのが好きという漠然とした理由と、父親と同じ道に進むかは決めかねていたが、教職の資格を取ろうと考えていたからだ。
ふと、農学部や薬学部も良かったかもしれないと、もしもの世界を想う。
あのまま地球で暮らしていたら、きっと重盛とここまで仲良くなることはなかっただろう。元々交わることのない運命だったのなら、彼のために今離れるべきか。
この半年間で生きる術は教わった。お互いがいないと生きていけないわけではない。
自分の身勝手な独占欲で彼を縛り付けておくのは勿体ない気がした。
「このまま離れた方がいいのかな……。適切な友人との距離ってどれくらいなんだろう」
人付き合いを避けてきた真紘に取って、それは大変難しい問題であった。
今日も朝から重盛に避けられている気がした。
普段はのんびり歩くこちらのペースに合わせてくれていたのだと、先を歩く彼の背中を見て知った。
このままエルフらしく、森でひっそり動植物の研究をしながら一人で暮らした方が良いのではないか、と殻に閉じこもっていた頃の自分が囁く。
懐に入れていた便利屋の名刺を触ると、指に痛みが走った。
紙で右手の人差し指の先端を切ったようだ。
ぷっくりと赤い粒が膨らむ。
重盛は何度か寝る前に鼻血を出していたので、赤いことは知っていたが、エルフも血液は赤いらしい。
鏡に映る肌はいつも真っ白で、自分の血はもしかしたら緑色かもしれない、なんて少し思っていた。
同じ人間なのに、どこか人と違うと思い込んでいた自分がいたことに気付く。
案外、今回の悩みもそんな思い込みなのかもしれない。
しかし、自分は人の感情に対して疎いところがあると理解している。それで痛い思いをしたのだから、人の何倍も考えて行動しなくてはならない。
異世界に来てからというもの、人との縁に恵まれているから、結果的に丸く収まっているだけだと常々感じていた。
自分なりに努力してきたつもりだが、いつまで経っても中途半端から抜け出せない。
もう少し、自分に自信が持てれば何が変わるのだろうか。
「うー、だめだめ! ポジティブに、前向きに、良い魔法は良い気から! 先ずは、視覚から明るくいこう!」
真紘は沈んだ気持ちを吹き飛ばすため、オーケストラの指揮者のように杖を振るい、空に光のシャワーを降らせた。
大木の下に戻ると、懐かしい匂いがした。
「ただいま」
「おっかえり~。森ん中で魔法ぶっ放して遊んでたっしょ。真紘ちゃんがどこにいるか分かって、こっちの準備も楽だったわ。じゃーん、本日のお昼はこちらです!」
「遊んでたわけじゃないよ、えっ、これが昼食――」
キャンプ用の簡易テーブルに並べられたおかずは意外にも下町の定食屋のようなメニューだった。
王都での二人暮らしでは専ら洋食が多く、どれも美味しいものだったが、この醤油や味噌の香ばしさが恋しかった。
つやつやと輝く白米、きつね色のコロッケ二つ、かつお節の乗ったおひたし、細切りにした人参の酢の和え物、そしてわかめの味噌汁。
日本人ならば一度は食べたことのあるメニューだが、実に半年ぶりの和食に真紘のテンションは今までにないほど上がっていた。
調味料一式の中に、基本の【さしすせそ】が入っていたのは知っていたが、料理酒、油、乾燥わかめやかつお節といった出汁が取れるものまで入っていたらしい。
姉の姿をした時の神を思い出し、真紘は改めて感謝した。
「どうよ、懐かしいっしょ? 漬物は流石に時間的に無理だったから、酢の和え物にしてみた。胡瓜とかこの世界にもあんのかなぁ。俺、漬物だと大根と柚子のが一番好きなんだよねぇ」
メニューの説明を聞きながら、真紘は少し泣きそうになった。
「わあ~! やったあ、嬉しい! わしょくだぁっ!」
「うおっ! わはっ、はっはッ! そんな喜んでくれると思わなかった~! もっと早く作れば良かった、ごめんな。温かいうちに食おうぜ」
低いテーブルに合わせ、正座するといよいよ日本の食事風景だ。
「うう、正座もできて嬉しい」
「喜ぶポイントそこかよ! んじゃ、せーので」
「いただきます」「いただきまーす」
真紘はうきうきと箸を持った。
早速、味噌汁のお椀を持ち上げ鼻に近づけると、こちらを伺う重盛と目が合った。
口の端を上げ、そのままゆっくりと啜る。
嗚呼、これだ。
目を閉じて故郷の味を噛み締める。鼻から味噌の優しい風味が抜け、じわっと心臓が芯から温まったような感覚に肩の力が抜けた。
次いで副菜の酢の物、おひたしを口に運ぶ。
素材の味を生かしつつ、ひと手間加えられた野菜は、どれも体が求めていたもので満足感と幸福感でいっぱいになった。
味噌汁と野菜だけでこんなに幸せになれる男子高校生は世界でただ二人だけだろう。緩む頬と目尻がそのまま蕩け落ちてしまいそうなほどだ。
そして、メインのコロッケを半分に箸で半分に割る。
中はごろっとしたジャガイモにひき肉といったシンプルなもの。
ソースはあえて付けず、そのまま食べた。
「ヒロちゃんってば、本当にコロッケ好きだよね。たまにはロースカツとか、ヒレカツにしたらいいのに」
妹の真織と、いつもの弁当屋に立ち寄る度に購入していたコロッケは、何も付けずとも下味がしっかりついているもので、一向に飽きが来ない至極の一品だった。
「だって美味しいんだから仕方ないよ。僕は一途だからいいの」
「うわーヒロちゃん、大人になっても実家から出ないでここに通うつもりでしょ」
姉そっくりな率直な物言いに真紘は笑い声を上げた。
「いいんだよ。もし実家から追い出されたらここに永久就職させてもらおうかな」
「だってさ、お姉さん。ヒロちゃんのことお婿にもらってくれる?」
ピンクのエプロンを着た女性は豪快に笑って、コロッケをもう一個サービスしてくれた。
そして誰かにそっくりな顔で彼女は言った。
「いいわよ。ヒロちゃんが大きくなったら、松永に永久就職しちゃいな」
「――ひろちゃん、真紘ちゃんッ!」
何度目かの呼びかけで心がリアースに帰ってきた。
コロッケを食べた友人がいきなり目の前でフリーズしては料理に何かあったのかと不安にさせてしまったかもしれない。真紘はハッとして正直に味の感想を伝える。
「どれもとっても美味しいよ。特にコロッケがあまりにも懐かしい味がしてさ。これが九条院家の味なんだね」
真紘の言葉に重盛は困ったように笑った。
既視感に懐かしい味。
中学の頃に突如閉店した弁当屋。
重盛の母は他界しているという事実。
ザァッと突風が草木を揺らし、辺りが騒めく。
違う、僕はこの味を昔から知っている。
「九条院じゃない。君は……」
二人の出会いは十年前に遡る。
25
あなたにおすすめの小説

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします
み馬下諒
BL
志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。
わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?
これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。
おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。
※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。
★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★
★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★


裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。
みーやん
BL
何日の時をこのソファーと過ごしただろう。
愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。
「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。
あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。
最後のエンドロールまで見た後に
「裏乙女ゲームを開始しますか?」
という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。
あ。俺3日寝てなかったんだ…
そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。
次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。
「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」
何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。
え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?
これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される
水凪しおん
BL
勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。
絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。
帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?
「私の至宝に、指一本触れるな」
荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。
裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。
ありま氷炎
BL
高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。
異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。
二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。
しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。
再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。
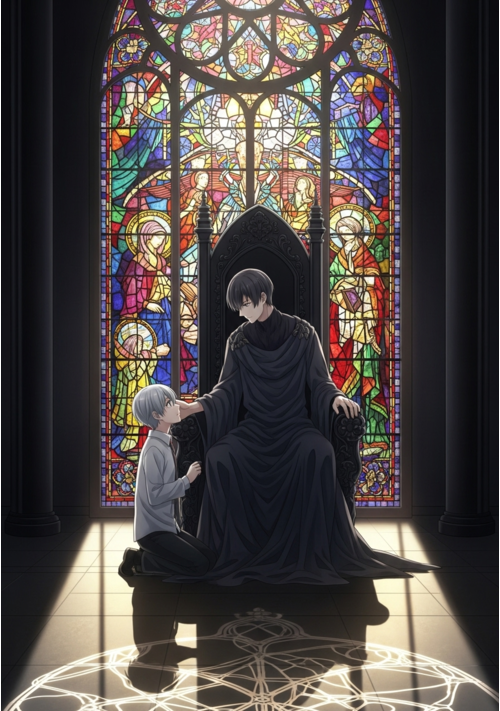
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

無能と追放された宮廷神官、実は動物を癒やすだけのスキル【聖癒】で、呪われた騎士団長を浄化し、もふもふ達と辺境で幸せな第二の人生を始めます
水凪しおん
BL
「君はもう、必要ない」
宮廷神官のルカは、動物を癒やすだけの地味なスキル【聖癒】を「無能」と蔑まれ、一方的に追放されてしまう。
前世で獣医だった彼にとって、祈りと権力争いに明け暮れる宮廷は息苦しい場所でしかなく、むしろ解放された気分で当てもない旅に出る。
やがてたどり着いたのは、"黒銀の鬼"が守るという辺境の森。そこでルカは、瘴気に苦しむ一匹の魔狼を癒やす。
その出会いが、彼の運命を大きく変えることになった。
魔狼を救ったルカの前に現れたのは、噂に聞く"黒銀の鬼"、騎士団長のギルベルトその人だった。呪いの鎧をその身に纏い、常に死の瘴気を放つ彼は、しかしルカの力を目の当たりにすると、意外な依頼を持ちかける。
「この者たちを、救ってやってはくれまいか」
彼に案内された砦の奥には、彼の放つ瘴気に当てられ、弱りきった動物たちが保護されていた。
"黒銀の鬼"の仮面の下に隠された、深い優しさ。
ルカの温かい【聖癒】は、動物たちだけでなく、ギルベルトの永い孤独と呪いさえも癒やし始める。
追放された癒し手と、呪われた騎士。もふもふ達に囲まれて、二つの孤独な魂がゆっくりと惹かれ合っていく――。
心温まる、もふもふ癒やしファンタジー!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















