51 / 109
旅の記録
51.シーグラス
しおりを挟む
王都の自宅の契約は二年更新のため、既に家賃は一括して払ってあるが、借りているからには部屋の状態維持も自分たちの役割。
クリスマスというイベントは歴代の救世主によってリアースに持ち込まれていたようで、十二月には王都でクリスマスマーケットが開催されるため、それに合わせて自宅の換気をするため王都に戻る予定だ。
リアースでは時の神の一神教で、クリスマスは祭りとしての意味合いが強い。
王都の書庫で救世主が描いたと思われるクリスマスの絵本の原本を見つけたので、一つの物語として親しまれているのかもしれない。ちょっと贅沢な食事をして一年の終わりを家族で語り合う。凡その日本人が考えるクリスマスそのものだ。
さらに十一月の末には重盛の二十歳の誕生日もある。
真紘の誕生日は六月で、リアースに来て早々に十九歳になっていた。地球とリアースで暦が半年ほどずれているため、日数でいえば重盛も誕生日を迎えるには些か早いのだが、逆算して考えるのは面倒なので、彼の誕生日からはこの世界基準で祝うことにした。
記念すべき二十歳の誕生日は見知らぬどこかの山道ではなく、二人がこれから過ごす王都の自宅で迎えたいというのは本人たっての希望だ。
来た時とは違う街を巡り、王都を目指す。
二人は旅人らしく、フードのついたそろいの茶色いローブのようなものを羽織っている。
体温調節が簡単にできる優れもので、職人が魔石を粉にしたものを糸に練り込み、快適な状態を保てるように魔法を付与しているのだという。
この逸品を仕立て上げるのに大変な労力が費やされているということは想像に難くない。
恋人を着飾ることに金の糸目をつけない重盛に小言を並べることの方が圧倒的に多いのだが、この買い物ばかりは真紘も素直に称賛せざるを得なかった。
二日間、ひたすら歩いていくと雲が街を覆うような高い場所にあったタルハネイリッカとは、自生している植物の種類も変わって来た。
タイニーハウスを導入した甲斐もあり、時間や天候に左右されることなく自由気ままに進んでいる。
肌寒くなり夜に飛び回る虫も減ってきた。重盛は天体観測をして新しい星を見つけようなんてご機嫌だ。
ロマンティック全開の彼に、夜空に浮かぶ星座はどれも見たことのない形をしているし、太陽や月すら地球と同じものではないかもしれないと真紘が言うと、こういうのは恋人と星を見るというシチュエーションが大事なのだと指南を受けた。
「おっ、潮風。もうすぐ海だ」
口の端を片方だけ器用に上げた重盛は目を輝かせて言った。
スンスンと意識して鼻から息を吸っても真紘には潮風を感じられない。だが、彼が言うのならばそうなのだろう。
「久しぶりの海だなぁ」
「地球では行ってなかった?」
「そうだね、姉と妹は日焼けしたくないお年頃らしくって、小学校三年生の潮干狩りが最後の海かな」
「ああ、真紘ちゃんって日焼けしたら赤み引くのも時間かかりそうだもんな。姉ちゃんも妹ちゃんも同じか」
「そうなんだよね。一家そろって暑さに弱くて、夏休みはひたすら家にいるか、避暑地にある祖父母宅に避難してたよ」
「だから夏休みに弁当屋に来ない日が続いてたんだな」
「冷静に分析しないで、なんか恥ずかしい……」
『キャーッ! 誰か助けて!』
重盛は誰と海に行っていたのかという言葉は、長閑な一本道を切り裂くような女性の悲鳴にかき消された。
断末魔といった方が近い悲鳴に、ただ事ではないと察した重盛は声がした方へと走る。真紘も彼の背中を追いかけて坂を急いで駆け下りた。
森を抜けると急激に視界が開け、坂の下には小さな街、そのさらに先には海が広がっていた。
街へと続く道の途中にモデルハウスのような三角屋根の一軒家がポツンと佇んでいる。
カーテンは閉め切られていて、人の気配は感じられないが、周辺には他の民家がないため、先ほどの悲鳴はこのクリーム色の家からで間違いなかった。
真紘は神経を集中させ、家に人がいるか探った。
「家の中には五人。四人は大人で、一人は魔力量的にも多分子供かな」
「ピンポンしてみる?」と言う重盛の言葉に頷き、思い切ってその家を訪ねてみることにした。
家は真紘の背丈ほどの鉄格子のような柵にぐるりと取り囲まれている。
開きっぱなしになっていた門をくぐると、足元には白いタイルを埋めるように青や緑といったシーグラスが敷き詰められている。庭の一角には小さな砂場があり、如雨露やスコップが転がっていた。
表札は青いガラス板のようなものに見たことのない書体で“ティアード”と彫られており、家主のこだわりが見て取れた。
扉をノックしても反応がない。
むしろ息を殺してやり過ごそうとしているような気配がする。
「すいませーん! 旅の者なんですけどぉ、腹壊してピンチなのでトイレ貸してくださーい」
ガチャガチャと遠慮なくドアを引く重盛に内緒話をするように囁く。
「これで何もなかったら僕達ただの不審者だね」
「わはっ、そうだな。まあ何もなけりゃそれでいいっしょ」
「君のそういうところ、す――」
「す?」
「好き、だな。えへっ」
玄関の持ち手がメキッと音を立てたのと同時に、扉が勢いよく開いた。
中から現れたのは二十代半ばくらいの男女。
男はブロンドの髪を一つに束ねており、黒い作業着のようなものを着ていた。
女も同じ髪色のショートカット。モスグリーンのミリタリージャンパーのようなものを羽織っている。海辺で仕事をしているのか、日焼けで鼻のてっぺんが少し赤く擦りむけていた。
女は愛想よく口角を上げた。
「ごめんなさい、今から夫と出かけるところなの」
「そりゃすいません。てか、さっき悲鳴が聞こえたけど何かあったんすか?」
「お願い、助けて!」
ガタリと玄関の奥から音がして、ルーミくらいの小さな子供が飛び出してきた。
黒髪のショートカット、白い肌は父親譲りなのか、少々顔色が悪い。こんな小さな子供を一人残して出かけるのは不自然だが、半袖短パンはこの季節に出かける格好には到底思えず、ちぐはぐな子供の姿に重盛は首を傾げた。
そして子供の登場に夫婦の顔色も変わった。
「や、やだ、外まで聞こえたのね。虫が出たのよ。男の子なのに虫が怖いなんて恥ずかしいったらありゃしない」
「お前は留守番だと言っただろう。奥の部屋で寝てないと、どうなるか、分かるよな?」
男の言葉に肩を震わせた子供は、その場に座り込み声をあげて泣き出した。
その様子を見兼ねた真紘は口を挟んだ。
「年齢や性別関係なく、苦手なものは人それぞれですから。ね? 重盛?」
「ぐっ、そうだな。こんなでっかくなっても俺も虫がめっちゃ苦手。叫ぶ気持ちも分かるぜ……。だから気にすんな!」
悲壮感たっぷりに同意する重盛を見て女は鼻で笑った。
「とにかく急いでるので、他の家をあたってくださる?」
「ええ、分かりました。お忙しいところすみません」
「じゃあ――」
男が玄関を閉めようと扉に手を伸ばすタイミングで、真紘は玄関の左手にある一枚の絵画を指さした。
「最後に一つだけ。この絵画はどなたが描いたものですか?」
全員の視線が絵に集まる。
畳一枚分ほどの長方形の大きなキャンバスには、立体感と艶のある青と緑と白の波に、今にも動き出しそうなヨットが描かれていて、右下には小さくTomとサインが入っている。
角度によってチカチカと反射するのは絵具に何か宝石のようなものが混ざっているせいだろう。
室内にいながら潮風を感じられる、そんな躍動感のある絵画に真紘は心惹かれた。
「は、はあ……」
男は訳の分からない質問に若干引きつった笑みを浮かべた。
「何? 真紘ちゃん絵画とか興味あったっけ?」
「いや、ただとても素敵な絵だなと思って。息子さんが描いたんですか?」
口をポカンと開けた男は嘲笑するように言った。
「そんなわけないだろう。あんた、この子がいくつに見えてるんだ? 市場で買ったものなので作者はわかりませんよ」
「ふふっ、冗談ですよ」
余所行き用の笑みを浮かべる真紘を見て察したのか、重盛はすまし顔で一歩後ろに下がった。
奥で泣きじゃくっていた子供もすっかり落ち着き、むすっとした表情で両手をズボンのポケットに入れている。
女はため息をつくと「もういいわね」と言って玄関を閉めた。
追い出された真紘と重盛は家の裏手に回ってみることにした。
「やっぱ虫がでたんじゃね? 虫が嫌いな人間にとって、家の中に現れるって死活問題なわけよ。あの坊ちゃんの気持ちも分かるぜ」
「ええー……」
「何よ?」
冷ややかな視線を浴びた重盛は眉間に皺を寄せた。
障害物がほとんどないため、海からの風がダイレクトに木々を揺らす。砂場の隣にあった小さな花壇で咲いているコスモスのほのかな甘い香りが真紘の鼻を掠めた。
「重盛風に言えば、あの子は坊ちゃんじゃなくて嬢ちゃんだよ」
「は? 女の子だったの!?」
「見れば分かる、と思ったけど、君は僕のことも女の子だと思ってたんだった」
「ちょっ、それは怒ってないんじゃなかったのぉ……」
「怒ってないよ。それで、気付いたことはない?」
「それについてはマジごめんってば! でもあの夫婦だって――いや、自分の子供の性別を間違うか?」
「自分達の子供の性別を間違う親なんていないよね。奥にいた残りの大人二人が本当のご両親なのかも。あの子よりも大きいお子さんがいるのかなと思ったけどそうではなさそう」
「やっぱり偽親の髪はブロンドだったし、子供だけ黒髪なのも変だよな?」
「そうだね。両親のどちらかが髪を染めている場合もあるし、海の仕事をしていると自然と髪が明るくなる人も多いって聞いたことがあるから断言はできないけど……。でも、男と女の耳の形がそっくりだったから、あの二人は夫婦じゃなくて兄妹か姉弟なんじゃないかなって」
「じゃあやっぱりトラブってんじゃないの? 強盗か? やばいじゃん、今すぐ乗り込むしかなくね!?」
「それでも確証がなかったんだよ! 出てきた二人はこの家の人の親戚とか、知り合いなのかなとか、色々考えてたら玄関が閉まっちゃった……。でも追い出されて確信した、彼らは絶対に悪い人達だ」
二人は家の裏側に着いた。
一階の窓はどこも閉まっているが、屋根に近い場所にある窓から星柄のカーテンがはみ出ていた。
「悪い人達だって根拠は? 良くも悪くも血や火薬の臭いはしなかったけど」
重盛が玄関先でも普通に呼吸していたので、それは真紘にも分かっていた。
それは――。
真紘が口を開くより前に、まっぽけから取り出していた魔石が淡く光った。
コンコンと叩くと、家の中の会話が聞こえてくる。
『本当に厄介なやつらだった。あのエルフを売り払った方が余程金になっただろうに』
先ほどの男の声に、重盛は眉間に皺を寄せてこめかみに青筋を立てた。
「まあまあ」
「あの男、絶対に許さねぇ……ぶっ潰してやる」
「わぁ……」
物騒な言葉を吐きながら重盛は真紘の首筋に顔を埋めて、思いっきり抱きしめた。
『はあ……。あのね、横には護衛か何か知らないけど獣人もいたのよ? 勝てるわけがないじゃない。それで、この家の金庫はどこにあんの』
『金庫に金はありません、全て銀行に預けてあります。金ならいくらでも引き出してきます。ですからお願いです、娘だけでも先に解放してやってくださいッ!』
『パパ……。ママ、起きて……おねがい、ままぁ……』
おそらく本当の父親の声と女の子の声が聞こえた。
状況から察するに母親は意識がないらしい。
「最悪っ、悪人確定じゃん! あのカーテンがはみ出してる子供部屋の窓は鍵かかってないっぽいね。あそこから家に入ろう」
「うん。行ける?」
「誰に言ってんの? ホイっと」
重盛は地面を蹴って軽く飛び上ると、易々と二階の窓を開けて中に飛び込んで行った。真紘もふわりと浮くとそのまま窓枠に足を掛ける。
「やべ、靴だけ綺麗にしてくんない?」
「君が飛んだ時点でもう綺麗にしたよ」
「流石じゃん」
「誰に言ってんのさ?」
「うおっ、惚れ直すわぁ」
重盛ほど器用に足音を立てないで歩く自信がない真紘は、彼の腕に掴まり浮いたまま移動する。
廊下に出ると、リビングから二階の廊下までは吹き抜けになっており一階の様子が見て取れた。真紘は魔石に向かって囁く。
「助けに来ました。悪い人はナイフを持った二人だけですね」
「うん」
女の子のか細い声を合図に真紘と重盛は二階から飛び降り、男と女を拘束した。
重盛が蹴り飛ばした男は完全に伸びてしまっている。若干の私怨感は否めない。
真紘は女の手足を魔法で縛りあげた。
野木を拘束した時よりも格段に魔法の使い方が上達し、無駄に大きなクリスタルを出現させることはもうない。これもルノとの魔法の訓練のおかげであった。
女が金切り声をあげて暴れるので、魔法で作ったガムテープを飛ばし口元を封じる。
突然の出来事に小さく悲鳴を上げて腰を抜かした父親に女の子はしっかり抱えられていた。
真紘は気を失って倒れている母親に近づき、回復魔法をかけると彼女は小さな呻き声をあげて目を覚ました。
父親は慌てて自分の妻に駆け寄る。
すると女の子は真紘の元にやってきた。
真紘はしゃがんで優しく彼女を労う。
「遅くなってごめんなさい。中の様子を教えてくれてありがとうございます」
「お兄ちゃん、こちらこそありがとう! みんながヨットの絵を見てる時にこの石を投げられてびっくりしたけど、花壇の如雨露にセットされた魔石に魔力を流していつもお手伝いしてたから使い方はわかったよ」
魔石を両手できゅっと握りしめながら女の子は言った。
「それは素晴らしい、しっかり者のお姉さんですね。もう悪い人は退治したので大丈夫ですよ。僕は真紘、あちらのお兄さんは重盛です。君は何さんですか?」
「わたしはラナ」
「ラナさん。僕の故郷の星では、玄関にあった絵画と同じで美しく穏やかな水面という意味の言葉なんです。素敵なお名前ですね」
真紘がにこりと微笑みかけると、ラナは顔を赤く染めた。
強盗二人を回収し、彼らを両脇に抱えた重盛は不満を爆発させた。
「こらこら、強盗退治して初恋泥棒になるんじゃないよ! そっちの方がよっぽど立ち悪いぞ!」
「そんなつもりじゃないのに、ねぇ?」
ラナの顔を覗き込むようにして問いかけると彼女はコクコクと首を縦に振った。
街のギルドに連絡して強盗の身柄を引き渡すと、彼らは港町を渡り歩いていた指名手配犯だと判明した。
ティアード夫妻には真紘と重盛の存在は伏せて欲しいと頼んでいたので、指名手配犯を捕まえた懸賞金はティアード家に支払われることになった。
「本当に良かったのでしょうか、助けてもらった上に、懸賞金まで……」
「ええ、ある意味僕のせいで玄関のドアの取手が壊れたかもしれないので、その修理代に……。それから、ラナさんが勇気を出して知らせてくれたおかげで僕達も異変に気付くことができました。是非、彼女にご褒美を。よろしければ皆さんで美味しい物でも食べに行ってください」
「俺がうっかりときめいたせいでドアを壊しました、ごめんなさい」
付き合いたてで浮かれていたんです、なんて言えるわけもなく、二人は深々と頭を下げた。
強盗退治とは無関係の器物破損だったが、ティアード家にとっては知り得ないことのため、お気になさらずと父親は笑って許してくれた。
「それでも貰い過ぎなくらいです。他に何かお礼ができれば良いのですが……」
「では、トムさん、いやトーマスさんかな。僕達の新居に飾る絵をお願いしてもよろしいでしょうか?」
「トム? 真紘ちゃんてば、なんで父ちゃんの名前知ってんの?」
ラナの父親は目を見開く。同じ黒髪に灰色の瞳は娘とそっくりだ。
「私のことをご存じで……?」
「失礼ながら知ったのは先ほどです。表札のTieredのTと、玄関先にあった絵のサイン、TomのTが、同じように見えたので、家主は玄関の絵を描いた人物なのだと思いました」
「でもそれだけじゃ、ここの家主がその絵の作者のファンで、表札も依頼しただけかもしれないよな?」
重盛の言葉に真紘は同意した。
「そうだね。でも庭のシーグラスはどうだろう。敷き詰められていたのは玄関の絵とかなり近い色をしたシーグラスだけだったよ。庭から玄関の中まで統一感を出すなんて難しいよ。表札ならともかく、庭のプロデュースまで画家に依頼しないんじゃないかな?」
真紘の推測通り、トーマスは手を叩いて正解だと笑った。
「炭鉱で働いていたが、どうしても故郷の海に戻りたくて家族でこの街に引っ越して来たんです。表札も絵も僕が手掛けていて――と言ってもまだまだ駆け出しの自称画家。庭のシーグラスは家族で海に行って拾ってきたもので、節約も兼ねてそれをさらに細かく砕き、樹脂のような特殊な絵具と混ぜているから、絵がキラキラして見えるんですよ」
「へぇ、俺、絵のことはあんま詳しくないけど、玄関の絵は見ていてワクワクしたな」
「僕も。家族で集めたシーグラスが絵に……。とても素敵ですね」
トーマスの描く絵の魅力は砕いたシーグラスによる人工的な輝きだけではないように思えた。美しい水面が、希望や愛といった明るい未来を彷彿とさせ、見る者の心まで輝かせる。
たまにしか帰らない自宅だが、彼の描いた絵があれば雰囲気も一瞬で明るくなる気がしたのだ。
「ありがとうございます。嬉しい限りです。精一杯心を込めて描かせていただきます。お代は結構ですよ、それでも貰い過ぎなくらいです」
父親の隣で嬉しそうに微笑むラナも頷いた。
「パパの絵を素敵だって言ってくれてありがとう。わたしもシーグラス頑張って集めるから楽しみにしててね」
「ふふっ、それは楽しみが増えました。心待ちにしています」
王都の自宅の住所を告げ、真紘と重盛はまた旅へと戻った。
坂を下りきると、ようやく真紘にもはっきりと潮風が感じられた。
「ねえ、記念にシーグラスを拾って行こうか」
「賛成! 波打ち際で追いかけっこもしたい」
「相変わらずベタだなぁ。じゃあ第一ラウンド、今から海まで競争しよう。三十秒数えたら追いかけてきてね」
「はーい」
銀色の髪を靡かせながら港町へと駆ける背中と、その背中を猛追する金色の尻尾を丘の上から画家は眺めていた。
百年もしない内に、トーマス・ティアードの絵画は世界中から高い評価を受け、様々な国の美術館に展示されることになる。
彼が描いた絵の中で、『銀の船』と『金の船』という作品だけ所在不明のまま。この二つは恩人に贈呈したものだという。
王都にあるエレベーターもないアパートの五階で、二枚の絵は長い時を共に過ごし、輝き続けるのであった。
クリスマスというイベントは歴代の救世主によってリアースに持ち込まれていたようで、十二月には王都でクリスマスマーケットが開催されるため、それに合わせて自宅の換気をするため王都に戻る予定だ。
リアースでは時の神の一神教で、クリスマスは祭りとしての意味合いが強い。
王都の書庫で救世主が描いたと思われるクリスマスの絵本の原本を見つけたので、一つの物語として親しまれているのかもしれない。ちょっと贅沢な食事をして一年の終わりを家族で語り合う。凡その日本人が考えるクリスマスそのものだ。
さらに十一月の末には重盛の二十歳の誕生日もある。
真紘の誕生日は六月で、リアースに来て早々に十九歳になっていた。地球とリアースで暦が半年ほどずれているため、日数でいえば重盛も誕生日を迎えるには些か早いのだが、逆算して考えるのは面倒なので、彼の誕生日からはこの世界基準で祝うことにした。
記念すべき二十歳の誕生日は見知らぬどこかの山道ではなく、二人がこれから過ごす王都の自宅で迎えたいというのは本人たっての希望だ。
来た時とは違う街を巡り、王都を目指す。
二人は旅人らしく、フードのついたそろいの茶色いローブのようなものを羽織っている。
体温調節が簡単にできる優れもので、職人が魔石を粉にしたものを糸に練り込み、快適な状態を保てるように魔法を付与しているのだという。
この逸品を仕立て上げるのに大変な労力が費やされているということは想像に難くない。
恋人を着飾ることに金の糸目をつけない重盛に小言を並べることの方が圧倒的に多いのだが、この買い物ばかりは真紘も素直に称賛せざるを得なかった。
二日間、ひたすら歩いていくと雲が街を覆うような高い場所にあったタルハネイリッカとは、自生している植物の種類も変わって来た。
タイニーハウスを導入した甲斐もあり、時間や天候に左右されることなく自由気ままに進んでいる。
肌寒くなり夜に飛び回る虫も減ってきた。重盛は天体観測をして新しい星を見つけようなんてご機嫌だ。
ロマンティック全開の彼に、夜空に浮かぶ星座はどれも見たことのない形をしているし、太陽や月すら地球と同じものではないかもしれないと真紘が言うと、こういうのは恋人と星を見るというシチュエーションが大事なのだと指南を受けた。
「おっ、潮風。もうすぐ海だ」
口の端を片方だけ器用に上げた重盛は目を輝かせて言った。
スンスンと意識して鼻から息を吸っても真紘には潮風を感じられない。だが、彼が言うのならばそうなのだろう。
「久しぶりの海だなぁ」
「地球では行ってなかった?」
「そうだね、姉と妹は日焼けしたくないお年頃らしくって、小学校三年生の潮干狩りが最後の海かな」
「ああ、真紘ちゃんって日焼けしたら赤み引くのも時間かかりそうだもんな。姉ちゃんも妹ちゃんも同じか」
「そうなんだよね。一家そろって暑さに弱くて、夏休みはひたすら家にいるか、避暑地にある祖父母宅に避難してたよ」
「だから夏休みに弁当屋に来ない日が続いてたんだな」
「冷静に分析しないで、なんか恥ずかしい……」
『キャーッ! 誰か助けて!』
重盛は誰と海に行っていたのかという言葉は、長閑な一本道を切り裂くような女性の悲鳴にかき消された。
断末魔といった方が近い悲鳴に、ただ事ではないと察した重盛は声がした方へと走る。真紘も彼の背中を追いかけて坂を急いで駆け下りた。
森を抜けると急激に視界が開け、坂の下には小さな街、そのさらに先には海が広がっていた。
街へと続く道の途中にモデルハウスのような三角屋根の一軒家がポツンと佇んでいる。
カーテンは閉め切られていて、人の気配は感じられないが、周辺には他の民家がないため、先ほどの悲鳴はこのクリーム色の家からで間違いなかった。
真紘は神経を集中させ、家に人がいるか探った。
「家の中には五人。四人は大人で、一人は魔力量的にも多分子供かな」
「ピンポンしてみる?」と言う重盛の言葉に頷き、思い切ってその家を訪ねてみることにした。
家は真紘の背丈ほどの鉄格子のような柵にぐるりと取り囲まれている。
開きっぱなしになっていた門をくぐると、足元には白いタイルを埋めるように青や緑といったシーグラスが敷き詰められている。庭の一角には小さな砂場があり、如雨露やスコップが転がっていた。
表札は青いガラス板のようなものに見たことのない書体で“ティアード”と彫られており、家主のこだわりが見て取れた。
扉をノックしても反応がない。
むしろ息を殺してやり過ごそうとしているような気配がする。
「すいませーん! 旅の者なんですけどぉ、腹壊してピンチなのでトイレ貸してくださーい」
ガチャガチャと遠慮なくドアを引く重盛に内緒話をするように囁く。
「これで何もなかったら僕達ただの不審者だね」
「わはっ、そうだな。まあ何もなけりゃそれでいいっしょ」
「君のそういうところ、す――」
「す?」
「好き、だな。えへっ」
玄関の持ち手がメキッと音を立てたのと同時に、扉が勢いよく開いた。
中から現れたのは二十代半ばくらいの男女。
男はブロンドの髪を一つに束ねており、黒い作業着のようなものを着ていた。
女も同じ髪色のショートカット。モスグリーンのミリタリージャンパーのようなものを羽織っている。海辺で仕事をしているのか、日焼けで鼻のてっぺんが少し赤く擦りむけていた。
女は愛想よく口角を上げた。
「ごめんなさい、今から夫と出かけるところなの」
「そりゃすいません。てか、さっき悲鳴が聞こえたけど何かあったんすか?」
「お願い、助けて!」
ガタリと玄関の奥から音がして、ルーミくらいの小さな子供が飛び出してきた。
黒髪のショートカット、白い肌は父親譲りなのか、少々顔色が悪い。こんな小さな子供を一人残して出かけるのは不自然だが、半袖短パンはこの季節に出かける格好には到底思えず、ちぐはぐな子供の姿に重盛は首を傾げた。
そして子供の登場に夫婦の顔色も変わった。
「や、やだ、外まで聞こえたのね。虫が出たのよ。男の子なのに虫が怖いなんて恥ずかしいったらありゃしない」
「お前は留守番だと言っただろう。奥の部屋で寝てないと、どうなるか、分かるよな?」
男の言葉に肩を震わせた子供は、その場に座り込み声をあげて泣き出した。
その様子を見兼ねた真紘は口を挟んだ。
「年齢や性別関係なく、苦手なものは人それぞれですから。ね? 重盛?」
「ぐっ、そうだな。こんなでっかくなっても俺も虫がめっちゃ苦手。叫ぶ気持ちも分かるぜ……。だから気にすんな!」
悲壮感たっぷりに同意する重盛を見て女は鼻で笑った。
「とにかく急いでるので、他の家をあたってくださる?」
「ええ、分かりました。お忙しいところすみません」
「じゃあ――」
男が玄関を閉めようと扉に手を伸ばすタイミングで、真紘は玄関の左手にある一枚の絵画を指さした。
「最後に一つだけ。この絵画はどなたが描いたものですか?」
全員の視線が絵に集まる。
畳一枚分ほどの長方形の大きなキャンバスには、立体感と艶のある青と緑と白の波に、今にも動き出しそうなヨットが描かれていて、右下には小さくTomとサインが入っている。
角度によってチカチカと反射するのは絵具に何か宝石のようなものが混ざっているせいだろう。
室内にいながら潮風を感じられる、そんな躍動感のある絵画に真紘は心惹かれた。
「は、はあ……」
男は訳の分からない質問に若干引きつった笑みを浮かべた。
「何? 真紘ちゃん絵画とか興味あったっけ?」
「いや、ただとても素敵な絵だなと思って。息子さんが描いたんですか?」
口をポカンと開けた男は嘲笑するように言った。
「そんなわけないだろう。あんた、この子がいくつに見えてるんだ? 市場で買ったものなので作者はわかりませんよ」
「ふふっ、冗談ですよ」
余所行き用の笑みを浮かべる真紘を見て察したのか、重盛はすまし顔で一歩後ろに下がった。
奥で泣きじゃくっていた子供もすっかり落ち着き、むすっとした表情で両手をズボンのポケットに入れている。
女はため息をつくと「もういいわね」と言って玄関を閉めた。
追い出された真紘と重盛は家の裏手に回ってみることにした。
「やっぱ虫がでたんじゃね? 虫が嫌いな人間にとって、家の中に現れるって死活問題なわけよ。あの坊ちゃんの気持ちも分かるぜ」
「ええー……」
「何よ?」
冷ややかな視線を浴びた重盛は眉間に皺を寄せた。
障害物がほとんどないため、海からの風がダイレクトに木々を揺らす。砂場の隣にあった小さな花壇で咲いているコスモスのほのかな甘い香りが真紘の鼻を掠めた。
「重盛風に言えば、あの子は坊ちゃんじゃなくて嬢ちゃんだよ」
「は? 女の子だったの!?」
「見れば分かる、と思ったけど、君は僕のことも女の子だと思ってたんだった」
「ちょっ、それは怒ってないんじゃなかったのぉ……」
「怒ってないよ。それで、気付いたことはない?」
「それについてはマジごめんってば! でもあの夫婦だって――いや、自分の子供の性別を間違うか?」
「自分達の子供の性別を間違う親なんていないよね。奥にいた残りの大人二人が本当のご両親なのかも。あの子よりも大きいお子さんがいるのかなと思ったけどそうではなさそう」
「やっぱり偽親の髪はブロンドだったし、子供だけ黒髪なのも変だよな?」
「そうだね。両親のどちらかが髪を染めている場合もあるし、海の仕事をしていると自然と髪が明るくなる人も多いって聞いたことがあるから断言はできないけど……。でも、男と女の耳の形がそっくりだったから、あの二人は夫婦じゃなくて兄妹か姉弟なんじゃないかなって」
「じゃあやっぱりトラブってんじゃないの? 強盗か? やばいじゃん、今すぐ乗り込むしかなくね!?」
「それでも確証がなかったんだよ! 出てきた二人はこの家の人の親戚とか、知り合いなのかなとか、色々考えてたら玄関が閉まっちゃった……。でも追い出されて確信した、彼らは絶対に悪い人達だ」
二人は家の裏側に着いた。
一階の窓はどこも閉まっているが、屋根に近い場所にある窓から星柄のカーテンがはみ出ていた。
「悪い人達だって根拠は? 良くも悪くも血や火薬の臭いはしなかったけど」
重盛が玄関先でも普通に呼吸していたので、それは真紘にも分かっていた。
それは――。
真紘が口を開くより前に、まっぽけから取り出していた魔石が淡く光った。
コンコンと叩くと、家の中の会話が聞こえてくる。
『本当に厄介なやつらだった。あのエルフを売り払った方が余程金になっただろうに』
先ほどの男の声に、重盛は眉間に皺を寄せてこめかみに青筋を立てた。
「まあまあ」
「あの男、絶対に許さねぇ……ぶっ潰してやる」
「わぁ……」
物騒な言葉を吐きながら重盛は真紘の首筋に顔を埋めて、思いっきり抱きしめた。
『はあ……。あのね、横には護衛か何か知らないけど獣人もいたのよ? 勝てるわけがないじゃない。それで、この家の金庫はどこにあんの』
『金庫に金はありません、全て銀行に預けてあります。金ならいくらでも引き出してきます。ですからお願いです、娘だけでも先に解放してやってくださいッ!』
『パパ……。ママ、起きて……おねがい、ままぁ……』
おそらく本当の父親の声と女の子の声が聞こえた。
状況から察するに母親は意識がないらしい。
「最悪っ、悪人確定じゃん! あのカーテンがはみ出してる子供部屋の窓は鍵かかってないっぽいね。あそこから家に入ろう」
「うん。行ける?」
「誰に言ってんの? ホイっと」
重盛は地面を蹴って軽く飛び上ると、易々と二階の窓を開けて中に飛び込んで行った。真紘もふわりと浮くとそのまま窓枠に足を掛ける。
「やべ、靴だけ綺麗にしてくんない?」
「君が飛んだ時点でもう綺麗にしたよ」
「流石じゃん」
「誰に言ってんのさ?」
「うおっ、惚れ直すわぁ」
重盛ほど器用に足音を立てないで歩く自信がない真紘は、彼の腕に掴まり浮いたまま移動する。
廊下に出ると、リビングから二階の廊下までは吹き抜けになっており一階の様子が見て取れた。真紘は魔石に向かって囁く。
「助けに来ました。悪い人はナイフを持った二人だけですね」
「うん」
女の子のか細い声を合図に真紘と重盛は二階から飛び降り、男と女を拘束した。
重盛が蹴り飛ばした男は完全に伸びてしまっている。若干の私怨感は否めない。
真紘は女の手足を魔法で縛りあげた。
野木を拘束した時よりも格段に魔法の使い方が上達し、無駄に大きなクリスタルを出現させることはもうない。これもルノとの魔法の訓練のおかげであった。
女が金切り声をあげて暴れるので、魔法で作ったガムテープを飛ばし口元を封じる。
突然の出来事に小さく悲鳴を上げて腰を抜かした父親に女の子はしっかり抱えられていた。
真紘は気を失って倒れている母親に近づき、回復魔法をかけると彼女は小さな呻き声をあげて目を覚ました。
父親は慌てて自分の妻に駆け寄る。
すると女の子は真紘の元にやってきた。
真紘はしゃがんで優しく彼女を労う。
「遅くなってごめんなさい。中の様子を教えてくれてありがとうございます」
「お兄ちゃん、こちらこそありがとう! みんながヨットの絵を見てる時にこの石を投げられてびっくりしたけど、花壇の如雨露にセットされた魔石に魔力を流していつもお手伝いしてたから使い方はわかったよ」
魔石を両手できゅっと握りしめながら女の子は言った。
「それは素晴らしい、しっかり者のお姉さんですね。もう悪い人は退治したので大丈夫ですよ。僕は真紘、あちらのお兄さんは重盛です。君は何さんですか?」
「わたしはラナ」
「ラナさん。僕の故郷の星では、玄関にあった絵画と同じで美しく穏やかな水面という意味の言葉なんです。素敵なお名前ですね」
真紘がにこりと微笑みかけると、ラナは顔を赤く染めた。
強盗二人を回収し、彼らを両脇に抱えた重盛は不満を爆発させた。
「こらこら、強盗退治して初恋泥棒になるんじゃないよ! そっちの方がよっぽど立ち悪いぞ!」
「そんなつもりじゃないのに、ねぇ?」
ラナの顔を覗き込むようにして問いかけると彼女はコクコクと首を縦に振った。
街のギルドに連絡して強盗の身柄を引き渡すと、彼らは港町を渡り歩いていた指名手配犯だと判明した。
ティアード夫妻には真紘と重盛の存在は伏せて欲しいと頼んでいたので、指名手配犯を捕まえた懸賞金はティアード家に支払われることになった。
「本当に良かったのでしょうか、助けてもらった上に、懸賞金まで……」
「ええ、ある意味僕のせいで玄関のドアの取手が壊れたかもしれないので、その修理代に……。それから、ラナさんが勇気を出して知らせてくれたおかげで僕達も異変に気付くことができました。是非、彼女にご褒美を。よろしければ皆さんで美味しい物でも食べに行ってください」
「俺がうっかりときめいたせいでドアを壊しました、ごめんなさい」
付き合いたてで浮かれていたんです、なんて言えるわけもなく、二人は深々と頭を下げた。
強盗退治とは無関係の器物破損だったが、ティアード家にとっては知り得ないことのため、お気になさらずと父親は笑って許してくれた。
「それでも貰い過ぎなくらいです。他に何かお礼ができれば良いのですが……」
「では、トムさん、いやトーマスさんかな。僕達の新居に飾る絵をお願いしてもよろしいでしょうか?」
「トム? 真紘ちゃんてば、なんで父ちゃんの名前知ってんの?」
ラナの父親は目を見開く。同じ黒髪に灰色の瞳は娘とそっくりだ。
「私のことをご存じで……?」
「失礼ながら知ったのは先ほどです。表札のTieredのTと、玄関先にあった絵のサイン、TomのTが、同じように見えたので、家主は玄関の絵を描いた人物なのだと思いました」
「でもそれだけじゃ、ここの家主がその絵の作者のファンで、表札も依頼しただけかもしれないよな?」
重盛の言葉に真紘は同意した。
「そうだね。でも庭のシーグラスはどうだろう。敷き詰められていたのは玄関の絵とかなり近い色をしたシーグラスだけだったよ。庭から玄関の中まで統一感を出すなんて難しいよ。表札ならともかく、庭のプロデュースまで画家に依頼しないんじゃないかな?」
真紘の推測通り、トーマスは手を叩いて正解だと笑った。
「炭鉱で働いていたが、どうしても故郷の海に戻りたくて家族でこの街に引っ越して来たんです。表札も絵も僕が手掛けていて――と言ってもまだまだ駆け出しの自称画家。庭のシーグラスは家族で海に行って拾ってきたもので、節約も兼ねてそれをさらに細かく砕き、樹脂のような特殊な絵具と混ぜているから、絵がキラキラして見えるんですよ」
「へぇ、俺、絵のことはあんま詳しくないけど、玄関の絵は見ていてワクワクしたな」
「僕も。家族で集めたシーグラスが絵に……。とても素敵ですね」
トーマスの描く絵の魅力は砕いたシーグラスによる人工的な輝きだけではないように思えた。美しい水面が、希望や愛といった明るい未来を彷彿とさせ、見る者の心まで輝かせる。
たまにしか帰らない自宅だが、彼の描いた絵があれば雰囲気も一瞬で明るくなる気がしたのだ。
「ありがとうございます。嬉しい限りです。精一杯心を込めて描かせていただきます。お代は結構ですよ、それでも貰い過ぎなくらいです」
父親の隣で嬉しそうに微笑むラナも頷いた。
「パパの絵を素敵だって言ってくれてありがとう。わたしもシーグラス頑張って集めるから楽しみにしててね」
「ふふっ、それは楽しみが増えました。心待ちにしています」
王都の自宅の住所を告げ、真紘と重盛はまた旅へと戻った。
坂を下りきると、ようやく真紘にもはっきりと潮風が感じられた。
「ねえ、記念にシーグラスを拾って行こうか」
「賛成! 波打ち際で追いかけっこもしたい」
「相変わらずベタだなぁ。じゃあ第一ラウンド、今から海まで競争しよう。三十秒数えたら追いかけてきてね」
「はーい」
銀色の髪を靡かせながら港町へと駆ける背中と、その背中を猛追する金色の尻尾を丘の上から画家は眺めていた。
百年もしない内に、トーマス・ティアードの絵画は世界中から高い評価を受け、様々な国の美術館に展示されることになる。
彼が描いた絵の中で、『銀の船』と『金の船』という作品だけ所在不明のまま。この二つは恩人に贈呈したものだという。
王都にあるエレベーターもないアパートの五階で、二枚の絵は長い時を共に過ごし、輝き続けるのであった。
26
あなたにおすすめの小説

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします
み馬下諒
BL
志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。
わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?
これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。
おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。
※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。
★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★
★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される
水凪しおん
BL
勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。
絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。
帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?
「私の至宝に、指一本触れるな」
荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。
裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。


裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。
みーやん
BL
何日の時をこのソファーと過ごしただろう。
愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。
「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。
あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。
最後のエンドロールまで見た後に
「裏乙女ゲームを開始しますか?」
という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。
あ。俺3日寝てなかったんだ…
そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。
次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。
「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」
何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。
え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?
これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。
ありま氷炎
BL
高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。
異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。
二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。
しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。
再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。
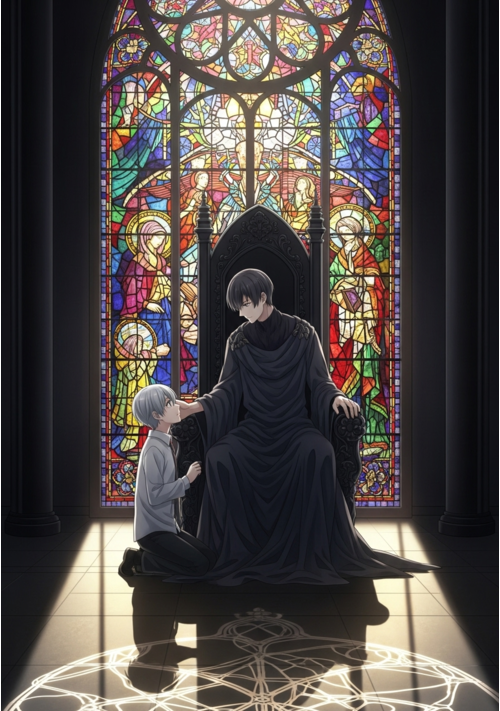
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

【完結】テルの異世界転換紀?!転がり落ちたら世界が変わっていた。
カヨワイさつき
BL
小学生の頃両親が蒸発、その後親戚中をたらいまわしにされ住むところも失った田辺輝(たなべ てる)は毎日切り詰めた生活をしていた。複数のバイトしていたある日、コスプレ?した男と出会った。
異世界ファンタジー、そしてちょっぴりすれ違いの恋愛。
ドワーフ族に助けられ家族として過ごす"テル"。本当の両親は……。
そして、コスプレと思っていた男性は……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















