61 / 109
新しい年
61.五分の四の集い
しおりを挟む
待ち合わせの十分前。
変身を解いた真紘は広場にある噴水の縁に座って皆を待った。
自分で髪を結ってもどこか歪になってしまうため、重盛のいない日は降ろしている。リボンで髪を結うというのは意外と難しい。拘束魔法を上手いこと使えば束ねることは簡単そうだが、重盛が頭を撫でて微笑む姿が拝めなくなる方が嫌なので、これからもできないフリをするのだ。
ジャバジャバと音を立てる噴水を背に、下腹部あたりまで伸びる銀の糸をぼんやり見つめる。
足元でチッチと囀る小鳥達に、もうすぐ日が暮れるのにいいのかい、と声を掛けると皆一斉に飛び立っていった。
「お待たせ、俺のプリンセス」
「時間通りだよ」
片膝を立て、真紘の手の甲に口付けを落す重盛は濃紺のロングコートのせいか、中々様になっていた。
黒いPコートを身に纏った野木が従者のように見守っている。
「仰々しいな……。プリンセスでもないよ」
「水辺のほとりで小っちゃい動物と戯れる様子は流石にプリンセスっすよ」
太ももの上に重盛の顔がちょこんと乗ったので、真紘はやわやわとその頭を撫でる。そして顔を上げて野木に挨拶をした。
「こんばんは、野木くん。もしかして二人でいてもずっとこの調子なの?」
「真紘君、こんばんはっす。いや~俺と二人の時はもっとかっけぇ感じだけど、話題の半分は惚気かも。真紘君も想像の三倍くらいアニキに甘いっすね……。麻耶さんは?」
「なんかごめんね。麻耶さんはまだだよ。もう少しで来るんじゃないかな?」
「そっか。会うの久しぶりでちょっと緊張するな……」
「緊張?」
「やっぱさ、最初に傷付けた事実は変わらないし、俺の事怖いんじゃないかと思って。積極的には会いたくないだろうから――」
「だから気にすることないってば!」
澄んだ声がする方へ三人は顔を向けると、にかっと昼間の太陽みたいな笑みを浮かべた麻耶が立っていた。
蛍光オレンジのようなブルゾンに黒いパンツ、冒険者の履くような編み上げブーツ。ショートカットだった水色の髪は伸びていて外はねのボブになっていた。
「次に気を遣ったら今日のご飯、勇也くんのおごりだからね」
「うっ、はい」
「うんうん、よろしい。というか、三人ともフォーマルな感じ……。一番年上なのに私が一番子供っぽい格好してない⁉」
「こんばんは、麻耶さん。お久しぶりです。どんなお店か聞くのを忘れていたので、一応かっちりした服を……。逆に浮きますかね?」
「真紘君も重盛君も直接会うのは久しぶりね。こちらこそ伝えてなくてごめんなさい。今日は来年のクルーズトレインでメインの料理を担当する人がいるレストランなの。個人経営のお店だから貸し切り。私は何度か会っているから普段着で来ちゃた。でもみんなフォーマルな洋服でバッチリだよ、若いのにしっかりしてるわ」
「それは良かった。お店のご予約もありがとうございます」
「いえいえ。四人で集まるのは初めてじゃない? 記念すべき同窓会ならぬ同星会なんだもん、はりきっちゃった。ほら、重盛君も真紘君にいつまでも引っ付いてないで行くよ!」
この世界に来た頃よりも豪胆な雰囲気になった麻耶は手をパンパンと叩てから歩き出した。ぞろぞろと自分より大きな男達を引率する様子は勇者一行の勇者のようであった。
本物の勇者は最後尾でぐうぐうと腹を鳴らしている。
「野木の腹、爆音すぎじゃね?」
「こっちの世界に来てから食う量が増えて、めちゃくちゃ腹が減るんすよ~」
私も、僕も、と全員が同意する。腹の音で合唱ができそうな頃、一軒の洋館の前で麻耶は立ち止まった。
オリーブ色の急勾配な三角帽子の屋根が複数連なっている洋館は、立面に木材が露出しており、白い壁とのコントラストが際立っている。
レンガで飾り立てられた入口もさることながら、室内は淡いクリーム色に小さな花の模様の壁、淡いランプがテーブルや椅子を照らしていて、地球で暮らしていた時に行った伝統ある三つ星レストランを彷彿とさせた。
この店の主であるシェフは来年からクルーズトレインの運営の大元であるタブルビー社の社員になる。
クルーズトレインには製紙会社の社長から招待されていて、麻耶経由で真紘と重盛も製紙会社の招待で参加する。
最近になってダブルビー社からも救世主全員がオープンランに招かれたようだが、三人は既に招待されている旨を伝え、野木は王城での仕事を理由に不参加を表明した。この場にいないもう一人の救世主であるフミは保護者であるリーベ神官から断りの連絡があったそうだ。
全員でシェフのレミーに挨拶をすると、麻耶は彼に尋ねた。
レミーは一般的なシェフが着ているようなシェフコートではなく、家庭用の黒いエプロンを身に着けている。四十になる男性だと聞いていたが、柔和な顔立ちな上、額が出るほど短く切り揃えられた前髪のせいか、若々しくとてもそうは見えない。
「せっかくのオープンランなのに、誰もダブルビー社の招待を受けなかったのよね。怒っていないかしら?」
レミーは苦笑いを浮かべ、手を振って否定した。
「怒ってはいないさ。私もクルーズトレインのメインシェフにと打診を受けたのが一年前。店を経営しているのだから、それでも遅いくらいだ。それからもキッチンスタッフを集めたりパティシエを探したりと難航していたようでね。スケジュール管理が下手なのは先方の責任。ウィルトン製紙の社長もダブルビー社との打ち合わせの度にげんなりしていただろう?」
「ええ。納期ギリギリにデザインの変更や発注ミスが多発して呆然としてたわ。その度に飲みに付き合わされていたのだけど」
「そうなのかい? 呆然とするよりも大激怒すると思っていたけれど……。あの社長、今は会長かな。お元気で?」
「会長はお元気よ。秋にご隠居されて、来春の正式なオープン初日からクルーズトレインで奥様と旅に出ると張り切っているわ。今はお孫さんが社長に就任されて、年明けに同行するのはその方」
「ああ、あの坊主が……。まあ、仲良くやりなさいな」
「……はい」
一瞬だけ渋い顔をした麻耶は邪念を振り払うかのように頭を振って、真紘達に好きなところへ座ってと声をかけた。
レミーは厨房前のスイングドアの前に移動し、皆に声をかける。
「つまらない話ばかりで申し訳ないね、今日はゆっくりしていってください。クルーズトレインの準備もあるから昨日でこの店は閉店したんだ。年明けに改装して、来春から弟子がこの場所を引き継ぐことになるのでどうぞ御贔屓に。今日は私のおごりです」
「それは悪いわ。私が無理を言ってお願いしたんだから、ちゃんと支払わせてください!」
レミーは、代わりにクルーズトレインで出すコース料理の試食をお願いしたいと申し出た。自分のペースで料理を食べることができないが良いかと問う。
勿論、こちらに得でしかない提案だが頷くほかない。四人が了承するとレミーは鼻歌混じりに厨房へと入っていった。
重盛は腰を浮かせてレミーが消えたスイングドアの向こう側を覗き込む。
「ねえ、気になるんでしょ。料理してるところ見せてもらえないか聞いてみたら?」と真紘が重盛の耳元で囁くと、彼は母親に背中を押された子供のようにおずおずと厨房へと向かって行った。
その様子に麻耶は目を三日月にしてニンマリ笑う。
「あの、麻耶さんにはご報告が遅れましたが、重盛とお付き合いをすることになりました。特段何が変わるわけでもないのですが、お世話になっている方にはきちんと自ら報告しようと――」
「あはは、硬い硬い! でもご丁寧にご報告ありがとうございます。そしておめでとう。勇也君はもう知ってるの?」
「そうっすね。俺は二人が付き合う前からアニキの相談っていうか、惚気に付き合ってたので」
「確かに重盛君からは矢印出まくってたもんねー。三人で魔石の魔力補充の内職してる時も私お邪魔かな~なんて思ったりして。さらに気付いてないのは真紘君だけっていうオチ」
「麻耶さんもそんなに前から気づいてらっしゃったんですか!?」
改めて突きつけられる自身の鈍感さに眩暈がする。真紘が顔を真っ赤にしていると、重盛が厨房から戻ってきた。
「えっ、何なに⁉ どうした?」
「全然、何にも問題ないよ、どうもしないよ!」
「レミーさんがエプロン貸してくれたからもう少し見てていいかなって聞きに来たんだけど行かない方がいい?」
「ううん、気にしないで行っておいで……」
弱々しく真紘が首を振ると、重盛は「その顔、あんまり人前ですんなよ」と言い残して厨房へと戻っていった。
その一言に真紘は撃沈し、両手で顔を覆う。見ているこちらが照れると麻耶と野木も頬を染めて顔を手で仰いだ。
互いの近況報告をしている間に料理が運ばれてきた。
レミーと共に皿を並べる重盛は、プロからマンツーマンで話を聞くという貴重な経験ができて満足したようで、ふりふりと控えめに尻尾を振っていた。
「お酒を飲まない方にもご満足いただけるとは思うけど、皆さんのようなお若い方にはどうだろうか。食べ終わったら感想を聞かせて欲しい。今回のコースは旅の思い出に残るような味、時間旅行がテーマなんだ。フォーマルなコースで八品。先ずは突き出し(アミューズ)から――」
説明が続く中、誰かの腹の音が鳴った。
「つい仕事モードになってしまった。ごめんね、食べながら説明しよう」とレミーは両手を上げた。
テーブルに並ぶ数枚のメニュー表はオープンランを記念したものと通常営業時のものだ。
寝台列車ということもあり、コースメニューを出せる日は主要都市で食材の補充が出来た時に限るため、謂わばコース自体が限定メニューなのである。
十号車あるうちの両端は展望室で、従業員の休憩室にもなっている。さらに中央の二両が魔石の保管室と食堂車、ラウンジ。スペースは限られている。
東に一万二千キロ、西に一万キロも伸びている線路は次の駅に到達するまでに二日ほどかかる場合もあり、走行距離でいえば日本を一周するよりも長い。
さらにクルーズトレインの路線と並走するように敷かれたレールが何本かある。先行して主要都市に停まる移動用の特急列車が既に運行しているので、途中で乗り換えることも可能だ。
クルーズトレインは観光目的の列車のため、絶景ポイントでは停車したり鈍行になったりもする。そんな条件の中で食材を確保するのは料理を作る以上に頭を悩ませるポイントであることは間違いない。
実際、レミーの最大の懸念は食材の確保にあるようで、予定していた食材が入手できなかった場合に備え、臨機応変に対応できるようにレストランで出している何倍もの品数を用意しているらしい。
最後のデザート(デセール)、コーヒーと菓子(カフェ・ブティフール)はパティシエが担当するので、そこだけは気が楽なんだと笑っていた。
コーヒーと焼き菓子を堪能しながら、真紘は麻耶から受け取った冊子に目を通す。
今回は不参加の野木の分までは用意できなかったようで、麻耶は彼に謝っていた。
「野木君もいつか行ってみようかなと思う時が来るかもしれないから、参考程度に聞いておいてね」
「はいっす!」
「真紘君と重盛君に渡したのは行程表と、持ち物リスト。出発は一月の三週目の月曜日。決起会みたいなパーティーも年明けてすぐにあるの。これは強制参加じゃないけど、行っておいた方が顔見知りも増えて何かと良いかも」
「麻耶姉さんありがとー……って、これ全部手書きじゃん、大変だったんじゃね?」
「わあ、本当だ。停車する駅の特徴や東側の列車に同乗する人の一覧まで……。沢山調べてくださったんですね。本当にありがとうございます!」
旅行代理店のパンフレット程の厚みがある冊子をパラパラ捲ると、準備段階から乗車後のことまで詳細に綴られていた。地図やイラストも入っていて分かりやすい。印刷会社で働いていたことのある麻耶ならではの旅のしおりだ。
「いやあ~私も東行に同行できたらいいんだけどごめんね。せめて事前準備くらいはサポートしないと、と思って。まあ、二人のほうがしっかりしているから問題ないかしら」
「僕は寝台列車も初めてで少し不安だったので、この冊子をいただけて良かった。とても心強いです!」
「麻耶姉さんマジで感謝! それに今回は婚前旅行だから二人でいーのよ」
真面目な顔でピースを掲げる重盛に麻耶はため息交じりにピースを返した。
「惚気だ~。次に王都で再会した時に俺達入籍しましたって左手に光るリングを見せられても驚かないわ。結婚式は呼んでね」
「俺も呼んでください! 友人代表でスピーチするっす」と野木も目を輝かせる。
「うははっ、ばあちゃん達と同じ事言うじゃん! やっぱ王都でも式しないとダメか?」
「あのさ、重盛は結婚式の話をよくするけど本気なの? 僕、ちゃんとしたプロポーズもしてないんだけど……」
真紘の発言に三人はぴたりと口を開けたまま停止した。
わなわなと肩を震わせて先陣を切ったのは年長者の麻耶だ。
「口約束ってこと!? 駄目じゃない大事なことはちゃんとしなきゃ! 重盛君なんて三百六十五日を記念日にしたい人でしょ!?」
「そう、うす。はい。その通り」
「この世界もちゃんと役所で婚姻届けを出して、入籍して法的に認められて家族になれるのよ。私達は身元保証人がメフシィ家とタルハネイリッカ家だから婚姻届けも保証人欄は空欄で良いみたいだけど、本当はちゃんとしないと身分証も作れないんだからね⁉ というかこの世界にお役所があるのもご存じ?」
怒涛の勢いに圧倒される青年三人は瞬きすら許されない。本来関係のない野木も縮こまっていて気の毒である。
「麻耶さん、なんだかお詳しいですね?」
「……それはこの世界に来てから生きていくために色々と必要を強いられたので調べたのよ。とにかく私のことはいいの。その辺もちゃんと調べておかないと、地方に行けば行くほど、その土地特有のルールに翻弄されることになるわ。ほら、渡した冊子の十八ページをご参照ください。これ見て、ここ。特に東側の方は異性同性関係なく、家族以外の者同士の同室を禁ずるなんてところもあるんだから。重盛君耐えられるの⁉」
「はー何それ! 由々しき問題すぎる! もっとちゃんと調べておくんだった。ヤダヤダ、真紘ちゃんと一晩でも離れたら俺、寂しくて死んじゃう」
「大丈夫だよ、重盛はできるよ。二、三日くらい頑張ろう」
「はあ~⁉ 離れる日数勝手に伸ばすなし!」
「それより入籍できるってことは、僕が思っていたより役所は地球と同じように機能しているのかもしれないな。なんで国が運営するギルドの雇用形態はあんなに杜撰なんだ……?」
真紘は国のお膝元にあるはずのギルドの粗雑な仕組みを目の当たりにして、戸籍や住民票といった日本では当たり前に存在していた制度もないのだろうとすっかり思い込んでいた。
異世界から来た自分達が単に免除されていただけで、この世界で生まれた者たちにとっては当たり前の規則というものが存在しているのだと、今になって知る。
ではなぜギルドだけぼんやりとした組織形態なのか。
この星の魔力量が減退し始めた原因は戦争。魔暴走が起きるようになったのもそれ以降のはずだ。その対策として立ち上がった機関だと聞いていたが、大戦中から名もなき機関として存在しており、領土によって規則が違っていたためにありとあらゆる面で決まり事が曖昧になっているのではないだろうか。
戦争による負の遺産は現代まで引き継がれている。
一秒も離れたくないと騒ぎ立てる重盛に抱き着かれながら真紘は黙り込む。
エルフの里があるように、希少種だけが暮らす地域、獣人が多い地域、人間のみが居住できる国家――。
王都の書庫で知り得た限りの情報だけでも、戦争の名残りは田舎に行けば行くほど色濃く、今も土地に根付いているのだ。
各地に存在するギルドの組織化は考えていたものよりも何倍も、何十倍も困難な事なのかもしれないと真紘は青ざめた。
麻耶の言う通り、口約束だけではなく書類上の関係も結んでおくべきなのだろう。
告白は予定していなかった展開になってしまったため、せめてプロポーズは記憶に残るものにしたい。付き合って数ヶ月で考える事ではないのかもしれないが、真紘は重盛以外と人生を歩つもりはないため、そこには早いか遅いかの違いしか存在しないのだ。
「もっと勉強しないと駄目ですね……」
「二人とも十分にやっているわ。特に真紘君はしっかりしているから、つい何でも知っている気になっていたけど、三人とも大学生くらいなのよね……。何も急いで入籍しなさいってことじゃなくて、そういうことが分からない時は聞いてねってこと。地球では学生だったんだし、役所みたいな面倒な手続きには不慣れなはずでしょ? 私だって社会人うん年目なのに去年まで確定申告に苦戦してたし、指導してくれる人も不在で一気に覚えようなんて無理なのよ」
「ありがとうございます。ノエルさんから色々教えていただいてはいたのですが、役所関係は確かに丸投げしてしまっていたので、とても勉強になりました」
プロポーズから役所手続きの話題になり、いつの間にか野木が一人暮らしをする際の物件探しへと議題は移り変わっていった。
空の魔石と王城での鍛錬のおかげで魔力が暴走するようなこともなくなった野木も、王城付近で一人暮らしを考えているらしい。
皆リアースでの人生を着実に歩み始めている。
クルーズトレインから帰ってきた後のことも改めて重盛と話し合う必要があるのだが、先ほどから百面相している彼を見る限りプロポーズのことで頭がいっぱいといったところだろう。
向かい側に座る麻耶と野木には見えない位置で重盛の手を握ると、彼は肩をびくっとさせてこちらを見た。
「頑張ろうね」
「何を?」
「人生を?」
「壮大じゃん」
皿を洗い終えて厨房から戻ってきたレミーは、真紘と重盛の会話を聞いて困惑していた。
ご馳走になった礼に困り事があればいつでも駆けつけると、レミーに便利屋の名刺を渡して別れた翌朝。
空は灰色の雲に覆われており、今にも雨が降り出しそうである。
真紘はベッドを揺らさぬようそっと太い腕の中から抜け出す。すやすやと寝ている重盛の頬にそっと唇を寄せてからリビングへと移動した。
寝る前に彼はうんうんと唸っていたので恐らくまだ起きてこない。
いつも通り寝落ちした真紘は早い。
プロポーズの前に、先ずは誕生日の準備に取り掛からねばと姿見の前で気合を入れる。きっと遠くばかり見ていては足が縺れて転んでしまう。一つ、ひとつの記念日を大事にいこう。
パジャマを脱ぎ、糊の利いたシャツを手に取ると仕事用の魔石に反応した。名刺の紙に通話用の魔石を砕いたものを練り込んでいるので、五分程度であれば連絡できる。
依頼の内容を聞いて、時には待ち合わせする必要もあるため、真紘はシャツを羽織りボタンも留めぬまま慌てて魔石に触れた。
「はい。こちら便利屋M&Sでございます」
「真紘さんですか? シェフのレミーです。こんなに早くから申し訳ないが、依頼できませんか。今私は王都の南部にあるリドレー男爵の自宅にいるのですが、少々困ったことになりまして……」
「ああ、レミーさん。おはようございます。昨日はごちそうさまでした。お気になさらないでください、早速ですが、どのようなご依頼でしょうか?」
リドレー男爵といえば美食家で有名で、王都では主に食材の流通に関わっている人物だ。王城の倉庫が燃焼した際にも熱心に尽力してくれたらしい。
悪い噂を聞いた事はないが、人に恨まれるような人物なのだろうかと真紘は首をかしげた。
「ああ、感謝します。昨晩遅くにお得意様だったリドレー男爵の屋敷に窃盗の予告状が届いたんです。それで相談を受けまして……。どうかお力添えいただけないでしょうか」
「窃盗ですか。何が狙われているんですか? 貴族の屋敷となると、宝石や美術館でしょうか?」
「いえ、それが分からなくて。恐らくこれだろうというものはあるようですが……」
「分からない?」
そして言いよどむレミーはなぞなぞのような事を口にした。
「予告状にはこう書いてあったそうです」
【屋敷の中で一番美しいものを明晩、頂戴しに参ります。怪盗アンノーン】
変身を解いた真紘は広場にある噴水の縁に座って皆を待った。
自分で髪を結ってもどこか歪になってしまうため、重盛のいない日は降ろしている。リボンで髪を結うというのは意外と難しい。拘束魔法を上手いこと使えば束ねることは簡単そうだが、重盛が頭を撫でて微笑む姿が拝めなくなる方が嫌なので、これからもできないフリをするのだ。
ジャバジャバと音を立てる噴水を背に、下腹部あたりまで伸びる銀の糸をぼんやり見つめる。
足元でチッチと囀る小鳥達に、もうすぐ日が暮れるのにいいのかい、と声を掛けると皆一斉に飛び立っていった。
「お待たせ、俺のプリンセス」
「時間通りだよ」
片膝を立て、真紘の手の甲に口付けを落す重盛は濃紺のロングコートのせいか、中々様になっていた。
黒いPコートを身に纏った野木が従者のように見守っている。
「仰々しいな……。プリンセスでもないよ」
「水辺のほとりで小っちゃい動物と戯れる様子は流石にプリンセスっすよ」
太ももの上に重盛の顔がちょこんと乗ったので、真紘はやわやわとその頭を撫でる。そして顔を上げて野木に挨拶をした。
「こんばんは、野木くん。もしかして二人でいてもずっとこの調子なの?」
「真紘君、こんばんはっす。いや~俺と二人の時はもっとかっけぇ感じだけど、話題の半分は惚気かも。真紘君も想像の三倍くらいアニキに甘いっすね……。麻耶さんは?」
「なんかごめんね。麻耶さんはまだだよ。もう少しで来るんじゃないかな?」
「そっか。会うの久しぶりでちょっと緊張するな……」
「緊張?」
「やっぱさ、最初に傷付けた事実は変わらないし、俺の事怖いんじゃないかと思って。積極的には会いたくないだろうから――」
「だから気にすることないってば!」
澄んだ声がする方へ三人は顔を向けると、にかっと昼間の太陽みたいな笑みを浮かべた麻耶が立っていた。
蛍光オレンジのようなブルゾンに黒いパンツ、冒険者の履くような編み上げブーツ。ショートカットだった水色の髪は伸びていて外はねのボブになっていた。
「次に気を遣ったら今日のご飯、勇也くんのおごりだからね」
「うっ、はい」
「うんうん、よろしい。というか、三人ともフォーマルな感じ……。一番年上なのに私が一番子供っぽい格好してない⁉」
「こんばんは、麻耶さん。お久しぶりです。どんなお店か聞くのを忘れていたので、一応かっちりした服を……。逆に浮きますかね?」
「真紘君も重盛君も直接会うのは久しぶりね。こちらこそ伝えてなくてごめんなさい。今日は来年のクルーズトレインでメインの料理を担当する人がいるレストランなの。個人経営のお店だから貸し切り。私は何度か会っているから普段着で来ちゃた。でもみんなフォーマルな洋服でバッチリだよ、若いのにしっかりしてるわ」
「それは良かった。お店のご予約もありがとうございます」
「いえいえ。四人で集まるのは初めてじゃない? 記念すべき同窓会ならぬ同星会なんだもん、はりきっちゃった。ほら、重盛君も真紘君にいつまでも引っ付いてないで行くよ!」
この世界に来た頃よりも豪胆な雰囲気になった麻耶は手をパンパンと叩てから歩き出した。ぞろぞろと自分より大きな男達を引率する様子は勇者一行の勇者のようであった。
本物の勇者は最後尾でぐうぐうと腹を鳴らしている。
「野木の腹、爆音すぎじゃね?」
「こっちの世界に来てから食う量が増えて、めちゃくちゃ腹が減るんすよ~」
私も、僕も、と全員が同意する。腹の音で合唱ができそうな頃、一軒の洋館の前で麻耶は立ち止まった。
オリーブ色の急勾配な三角帽子の屋根が複数連なっている洋館は、立面に木材が露出しており、白い壁とのコントラストが際立っている。
レンガで飾り立てられた入口もさることながら、室内は淡いクリーム色に小さな花の模様の壁、淡いランプがテーブルや椅子を照らしていて、地球で暮らしていた時に行った伝統ある三つ星レストランを彷彿とさせた。
この店の主であるシェフは来年からクルーズトレインの運営の大元であるタブルビー社の社員になる。
クルーズトレインには製紙会社の社長から招待されていて、麻耶経由で真紘と重盛も製紙会社の招待で参加する。
最近になってダブルビー社からも救世主全員がオープンランに招かれたようだが、三人は既に招待されている旨を伝え、野木は王城での仕事を理由に不参加を表明した。この場にいないもう一人の救世主であるフミは保護者であるリーベ神官から断りの連絡があったそうだ。
全員でシェフのレミーに挨拶をすると、麻耶は彼に尋ねた。
レミーは一般的なシェフが着ているようなシェフコートではなく、家庭用の黒いエプロンを身に着けている。四十になる男性だと聞いていたが、柔和な顔立ちな上、額が出るほど短く切り揃えられた前髪のせいか、若々しくとてもそうは見えない。
「せっかくのオープンランなのに、誰もダブルビー社の招待を受けなかったのよね。怒っていないかしら?」
レミーは苦笑いを浮かべ、手を振って否定した。
「怒ってはいないさ。私もクルーズトレインのメインシェフにと打診を受けたのが一年前。店を経営しているのだから、それでも遅いくらいだ。それからもキッチンスタッフを集めたりパティシエを探したりと難航していたようでね。スケジュール管理が下手なのは先方の責任。ウィルトン製紙の社長もダブルビー社との打ち合わせの度にげんなりしていただろう?」
「ええ。納期ギリギリにデザインの変更や発注ミスが多発して呆然としてたわ。その度に飲みに付き合わされていたのだけど」
「そうなのかい? 呆然とするよりも大激怒すると思っていたけれど……。あの社長、今は会長かな。お元気で?」
「会長はお元気よ。秋にご隠居されて、来春の正式なオープン初日からクルーズトレインで奥様と旅に出ると張り切っているわ。今はお孫さんが社長に就任されて、年明けに同行するのはその方」
「ああ、あの坊主が……。まあ、仲良くやりなさいな」
「……はい」
一瞬だけ渋い顔をした麻耶は邪念を振り払うかのように頭を振って、真紘達に好きなところへ座ってと声をかけた。
レミーは厨房前のスイングドアの前に移動し、皆に声をかける。
「つまらない話ばかりで申し訳ないね、今日はゆっくりしていってください。クルーズトレインの準備もあるから昨日でこの店は閉店したんだ。年明けに改装して、来春から弟子がこの場所を引き継ぐことになるのでどうぞ御贔屓に。今日は私のおごりです」
「それは悪いわ。私が無理を言ってお願いしたんだから、ちゃんと支払わせてください!」
レミーは、代わりにクルーズトレインで出すコース料理の試食をお願いしたいと申し出た。自分のペースで料理を食べることができないが良いかと問う。
勿論、こちらに得でしかない提案だが頷くほかない。四人が了承するとレミーは鼻歌混じりに厨房へと入っていった。
重盛は腰を浮かせてレミーが消えたスイングドアの向こう側を覗き込む。
「ねえ、気になるんでしょ。料理してるところ見せてもらえないか聞いてみたら?」と真紘が重盛の耳元で囁くと、彼は母親に背中を押された子供のようにおずおずと厨房へと向かって行った。
その様子に麻耶は目を三日月にしてニンマリ笑う。
「あの、麻耶さんにはご報告が遅れましたが、重盛とお付き合いをすることになりました。特段何が変わるわけでもないのですが、お世話になっている方にはきちんと自ら報告しようと――」
「あはは、硬い硬い! でもご丁寧にご報告ありがとうございます。そしておめでとう。勇也君はもう知ってるの?」
「そうっすね。俺は二人が付き合う前からアニキの相談っていうか、惚気に付き合ってたので」
「確かに重盛君からは矢印出まくってたもんねー。三人で魔石の魔力補充の内職してる時も私お邪魔かな~なんて思ったりして。さらに気付いてないのは真紘君だけっていうオチ」
「麻耶さんもそんなに前から気づいてらっしゃったんですか!?」
改めて突きつけられる自身の鈍感さに眩暈がする。真紘が顔を真っ赤にしていると、重盛が厨房から戻ってきた。
「えっ、何なに⁉ どうした?」
「全然、何にも問題ないよ、どうもしないよ!」
「レミーさんがエプロン貸してくれたからもう少し見てていいかなって聞きに来たんだけど行かない方がいい?」
「ううん、気にしないで行っておいで……」
弱々しく真紘が首を振ると、重盛は「その顔、あんまり人前ですんなよ」と言い残して厨房へと戻っていった。
その一言に真紘は撃沈し、両手で顔を覆う。見ているこちらが照れると麻耶と野木も頬を染めて顔を手で仰いだ。
互いの近況報告をしている間に料理が運ばれてきた。
レミーと共に皿を並べる重盛は、プロからマンツーマンで話を聞くという貴重な経験ができて満足したようで、ふりふりと控えめに尻尾を振っていた。
「お酒を飲まない方にもご満足いただけるとは思うけど、皆さんのようなお若い方にはどうだろうか。食べ終わったら感想を聞かせて欲しい。今回のコースは旅の思い出に残るような味、時間旅行がテーマなんだ。フォーマルなコースで八品。先ずは突き出し(アミューズ)から――」
説明が続く中、誰かの腹の音が鳴った。
「つい仕事モードになってしまった。ごめんね、食べながら説明しよう」とレミーは両手を上げた。
テーブルに並ぶ数枚のメニュー表はオープンランを記念したものと通常営業時のものだ。
寝台列車ということもあり、コースメニューを出せる日は主要都市で食材の補充が出来た時に限るため、謂わばコース自体が限定メニューなのである。
十号車あるうちの両端は展望室で、従業員の休憩室にもなっている。さらに中央の二両が魔石の保管室と食堂車、ラウンジ。スペースは限られている。
東に一万二千キロ、西に一万キロも伸びている線路は次の駅に到達するまでに二日ほどかかる場合もあり、走行距離でいえば日本を一周するよりも長い。
さらにクルーズトレインの路線と並走するように敷かれたレールが何本かある。先行して主要都市に停まる移動用の特急列車が既に運行しているので、途中で乗り換えることも可能だ。
クルーズトレインは観光目的の列車のため、絶景ポイントでは停車したり鈍行になったりもする。そんな条件の中で食材を確保するのは料理を作る以上に頭を悩ませるポイントであることは間違いない。
実際、レミーの最大の懸念は食材の確保にあるようで、予定していた食材が入手できなかった場合に備え、臨機応変に対応できるようにレストランで出している何倍もの品数を用意しているらしい。
最後のデザート(デセール)、コーヒーと菓子(カフェ・ブティフール)はパティシエが担当するので、そこだけは気が楽なんだと笑っていた。
コーヒーと焼き菓子を堪能しながら、真紘は麻耶から受け取った冊子に目を通す。
今回は不参加の野木の分までは用意できなかったようで、麻耶は彼に謝っていた。
「野木君もいつか行ってみようかなと思う時が来るかもしれないから、参考程度に聞いておいてね」
「はいっす!」
「真紘君と重盛君に渡したのは行程表と、持ち物リスト。出発は一月の三週目の月曜日。決起会みたいなパーティーも年明けてすぐにあるの。これは強制参加じゃないけど、行っておいた方が顔見知りも増えて何かと良いかも」
「麻耶姉さんありがとー……って、これ全部手書きじゃん、大変だったんじゃね?」
「わあ、本当だ。停車する駅の特徴や東側の列車に同乗する人の一覧まで……。沢山調べてくださったんですね。本当にありがとうございます!」
旅行代理店のパンフレット程の厚みがある冊子をパラパラ捲ると、準備段階から乗車後のことまで詳細に綴られていた。地図やイラストも入っていて分かりやすい。印刷会社で働いていたことのある麻耶ならではの旅のしおりだ。
「いやあ~私も東行に同行できたらいいんだけどごめんね。せめて事前準備くらいはサポートしないと、と思って。まあ、二人のほうがしっかりしているから問題ないかしら」
「僕は寝台列車も初めてで少し不安だったので、この冊子をいただけて良かった。とても心強いです!」
「麻耶姉さんマジで感謝! それに今回は婚前旅行だから二人でいーのよ」
真面目な顔でピースを掲げる重盛に麻耶はため息交じりにピースを返した。
「惚気だ~。次に王都で再会した時に俺達入籍しましたって左手に光るリングを見せられても驚かないわ。結婚式は呼んでね」
「俺も呼んでください! 友人代表でスピーチするっす」と野木も目を輝かせる。
「うははっ、ばあちゃん達と同じ事言うじゃん! やっぱ王都でも式しないとダメか?」
「あのさ、重盛は結婚式の話をよくするけど本気なの? 僕、ちゃんとしたプロポーズもしてないんだけど……」
真紘の発言に三人はぴたりと口を開けたまま停止した。
わなわなと肩を震わせて先陣を切ったのは年長者の麻耶だ。
「口約束ってこと!? 駄目じゃない大事なことはちゃんとしなきゃ! 重盛君なんて三百六十五日を記念日にしたい人でしょ!?」
「そう、うす。はい。その通り」
「この世界もちゃんと役所で婚姻届けを出して、入籍して法的に認められて家族になれるのよ。私達は身元保証人がメフシィ家とタルハネイリッカ家だから婚姻届けも保証人欄は空欄で良いみたいだけど、本当はちゃんとしないと身分証も作れないんだからね⁉ というかこの世界にお役所があるのもご存じ?」
怒涛の勢いに圧倒される青年三人は瞬きすら許されない。本来関係のない野木も縮こまっていて気の毒である。
「麻耶さん、なんだかお詳しいですね?」
「……それはこの世界に来てから生きていくために色々と必要を強いられたので調べたのよ。とにかく私のことはいいの。その辺もちゃんと調べておかないと、地方に行けば行くほど、その土地特有のルールに翻弄されることになるわ。ほら、渡した冊子の十八ページをご参照ください。これ見て、ここ。特に東側の方は異性同性関係なく、家族以外の者同士の同室を禁ずるなんてところもあるんだから。重盛君耐えられるの⁉」
「はー何それ! 由々しき問題すぎる! もっとちゃんと調べておくんだった。ヤダヤダ、真紘ちゃんと一晩でも離れたら俺、寂しくて死んじゃう」
「大丈夫だよ、重盛はできるよ。二、三日くらい頑張ろう」
「はあ~⁉ 離れる日数勝手に伸ばすなし!」
「それより入籍できるってことは、僕が思っていたより役所は地球と同じように機能しているのかもしれないな。なんで国が運営するギルドの雇用形態はあんなに杜撰なんだ……?」
真紘は国のお膝元にあるはずのギルドの粗雑な仕組みを目の当たりにして、戸籍や住民票といった日本では当たり前に存在していた制度もないのだろうとすっかり思い込んでいた。
異世界から来た自分達が単に免除されていただけで、この世界で生まれた者たちにとっては当たり前の規則というものが存在しているのだと、今になって知る。
ではなぜギルドだけぼんやりとした組織形態なのか。
この星の魔力量が減退し始めた原因は戦争。魔暴走が起きるようになったのもそれ以降のはずだ。その対策として立ち上がった機関だと聞いていたが、大戦中から名もなき機関として存在しており、領土によって規則が違っていたためにありとあらゆる面で決まり事が曖昧になっているのではないだろうか。
戦争による負の遺産は現代まで引き継がれている。
一秒も離れたくないと騒ぎ立てる重盛に抱き着かれながら真紘は黙り込む。
エルフの里があるように、希少種だけが暮らす地域、獣人が多い地域、人間のみが居住できる国家――。
王都の書庫で知り得た限りの情報だけでも、戦争の名残りは田舎に行けば行くほど色濃く、今も土地に根付いているのだ。
各地に存在するギルドの組織化は考えていたものよりも何倍も、何十倍も困難な事なのかもしれないと真紘は青ざめた。
麻耶の言う通り、口約束だけではなく書類上の関係も結んでおくべきなのだろう。
告白は予定していなかった展開になってしまったため、せめてプロポーズは記憶に残るものにしたい。付き合って数ヶ月で考える事ではないのかもしれないが、真紘は重盛以外と人生を歩つもりはないため、そこには早いか遅いかの違いしか存在しないのだ。
「もっと勉強しないと駄目ですね……」
「二人とも十分にやっているわ。特に真紘君はしっかりしているから、つい何でも知っている気になっていたけど、三人とも大学生くらいなのよね……。何も急いで入籍しなさいってことじゃなくて、そういうことが分からない時は聞いてねってこと。地球では学生だったんだし、役所みたいな面倒な手続きには不慣れなはずでしょ? 私だって社会人うん年目なのに去年まで確定申告に苦戦してたし、指導してくれる人も不在で一気に覚えようなんて無理なのよ」
「ありがとうございます。ノエルさんから色々教えていただいてはいたのですが、役所関係は確かに丸投げしてしまっていたので、とても勉強になりました」
プロポーズから役所手続きの話題になり、いつの間にか野木が一人暮らしをする際の物件探しへと議題は移り変わっていった。
空の魔石と王城での鍛錬のおかげで魔力が暴走するようなこともなくなった野木も、王城付近で一人暮らしを考えているらしい。
皆リアースでの人生を着実に歩み始めている。
クルーズトレインから帰ってきた後のことも改めて重盛と話し合う必要があるのだが、先ほどから百面相している彼を見る限りプロポーズのことで頭がいっぱいといったところだろう。
向かい側に座る麻耶と野木には見えない位置で重盛の手を握ると、彼は肩をびくっとさせてこちらを見た。
「頑張ろうね」
「何を?」
「人生を?」
「壮大じゃん」
皿を洗い終えて厨房から戻ってきたレミーは、真紘と重盛の会話を聞いて困惑していた。
ご馳走になった礼に困り事があればいつでも駆けつけると、レミーに便利屋の名刺を渡して別れた翌朝。
空は灰色の雲に覆われており、今にも雨が降り出しそうである。
真紘はベッドを揺らさぬようそっと太い腕の中から抜け出す。すやすやと寝ている重盛の頬にそっと唇を寄せてからリビングへと移動した。
寝る前に彼はうんうんと唸っていたので恐らくまだ起きてこない。
いつも通り寝落ちした真紘は早い。
プロポーズの前に、先ずは誕生日の準備に取り掛からねばと姿見の前で気合を入れる。きっと遠くばかり見ていては足が縺れて転んでしまう。一つ、ひとつの記念日を大事にいこう。
パジャマを脱ぎ、糊の利いたシャツを手に取ると仕事用の魔石に反応した。名刺の紙に通話用の魔石を砕いたものを練り込んでいるので、五分程度であれば連絡できる。
依頼の内容を聞いて、時には待ち合わせする必要もあるため、真紘はシャツを羽織りボタンも留めぬまま慌てて魔石に触れた。
「はい。こちら便利屋M&Sでございます」
「真紘さんですか? シェフのレミーです。こんなに早くから申し訳ないが、依頼できませんか。今私は王都の南部にあるリドレー男爵の自宅にいるのですが、少々困ったことになりまして……」
「ああ、レミーさん。おはようございます。昨日はごちそうさまでした。お気になさらないでください、早速ですが、どのようなご依頼でしょうか?」
リドレー男爵といえば美食家で有名で、王都では主に食材の流通に関わっている人物だ。王城の倉庫が燃焼した際にも熱心に尽力してくれたらしい。
悪い噂を聞いた事はないが、人に恨まれるような人物なのだろうかと真紘は首をかしげた。
「ああ、感謝します。昨晩遅くにお得意様だったリドレー男爵の屋敷に窃盗の予告状が届いたんです。それで相談を受けまして……。どうかお力添えいただけないでしょうか」
「窃盗ですか。何が狙われているんですか? 貴族の屋敷となると、宝石や美術館でしょうか?」
「いえ、それが分からなくて。恐らくこれだろうというものはあるようですが……」
「分からない?」
そして言いよどむレミーはなぞなぞのような事を口にした。
「予告状にはこう書いてあったそうです」
【屋敷の中で一番美しいものを明晩、頂戴しに参ります。怪盗アンノーン】
26
あなたにおすすめの小説

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします
み馬下諒
BL
志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。
わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?
これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。
おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。
※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。
★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★
★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★


裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。
みーやん
BL
何日の時をこのソファーと過ごしただろう。
愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。
「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。
あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。
最後のエンドロールまで見た後に
「裏乙女ゲームを開始しますか?」
という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。
あ。俺3日寝てなかったんだ…
そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。
次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。
「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」
何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。
え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?
これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される
水凪しおん
BL
勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。
絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。
帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?
「私の至宝に、指一本触れるな」
荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。
裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。
ありま氷炎
BL
高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。
異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。
二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。
しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。
再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。
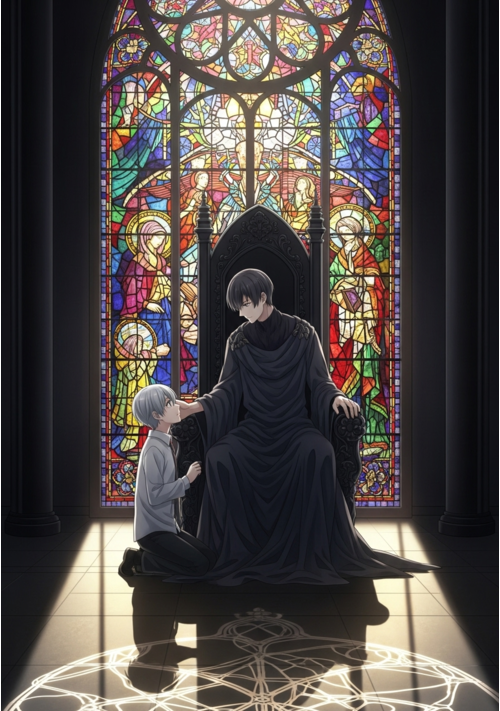
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

無能と追放された宮廷神官、実は動物を癒やすだけのスキル【聖癒】で、呪われた騎士団長を浄化し、もふもふ達と辺境で幸せな第二の人生を始めます
水凪しおん
BL
「君はもう、必要ない」
宮廷神官のルカは、動物を癒やすだけの地味なスキル【聖癒】を「無能」と蔑まれ、一方的に追放されてしまう。
前世で獣医だった彼にとって、祈りと権力争いに明け暮れる宮廷は息苦しい場所でしかなく、むしろ解放された気分で当てもない旅に出る。
やがてたどり着いたのは、"黒銀の鬼"が守るという辺境の森。そこでルカは、瘴気に苦しむ一匹の魔狼を癒やす。
その出会いが、彼の運命を大きく変えることになった。
魔狼を救ったルカの前に現れたのは、噂に聞く"黒銀の鬼"、騎士団長のギルベルトその人だった。呪いの鎧をその身に纏い、常に死の瘴気を放つ彼は、しかしルカの力を目の当たりにすると、意外な依頼を持ちかける。
「この者たちを、救ってやってはくれまいか」
彼に案内された砦の奥には、彼の放つ瘴気に当てられ、弱りきった動物たちが保護されていた。
"黒銀の鬼"の仮面の下に隠された、深い優しさ。
ルカの温かい【聖癒】は、動物たちだけでなく、ギルベルトの永い孤独と呪いさえも癒やし始める。
追放された癒し手と、呪われた騎士。もふもふ達に囲まれて、二つの孤独な魂がゆっくりと惹かれ合っていく――。
心温まる、もふもふ癒やしファンタジー!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















