62 / 109
新しい年
62.美しいものⅠ
しおりを挟む
重盛が眠い目を擦りながら起きてきたのはレミーとの通話を終えたすぐ後だった。
リビングには白いシャツを羽織っただけの着替え途中の真紘。桃色のスラックスと茶色のベルトはソファーに投げ捨てられていて、白い足は惜しみなく晒されていた。
寝ぐせによって四方八方に散らばる重盛の髪先がさらにぶわりと広がる。
「おはよう、重盛」
「じ、事後みたいな格好すんなって!」
「はあ? 朝から何言ってるんだか……。それよりついさっきレミーさんから依頼があったんだ。寄りたいところもあるから朝食を食べたらすぐに出かけるよ。顔洗っておいで」
キス以上のことはまだ先にと約束をしてから煽らないようにと懇願されていたが、予告なく肌を晒すだけでも駄目らしい。
今まで宿屋であったりタイニーハウスであったり、人の目があるかもしれないという心配で気が抜けなかった反動か、真紘も自宅の中ではかなり気が抜けている自覚はあった。そのせいなのか今ではパジャマのボタンも一番上まで閉めろという指令付きだ。
しかし、言いつけもきちんと守っているのだから着替えのタイミングくらい好きにさせて欲しい。
キスもしているし毎日一緒に寝てもいるのにと抗議すれば、その顔も止めろと重盛はしゃがみ込む。
観念してさっとスラックスを履くと、重盛は少し残念そうな顔をしていた。
「僕は煽ってるつもりは一切ないんだけど……。君の基準が全然わからない」
「それはこちらが判断することなのであります」
「んふっ、照れるとたまに変なキャラになるよね。それ笑っちゃうから止めてよ」
「なんだよその余裕~襲われても文句言うなよ!」
「襲って後悔するのは重盛の方でしょうに」
「だあッ! 朝から俺の純情弄ぶなぁ!」
ごめんごめんと言いながら真紘は仕上げのリボンを重盛に手渡した。
ソファーに座ると長い髪を右側にまとめて白い首を晒す。
「うなじはもう見飽きたでしょ、セーフだよね?」
「ううっ……泣くぞホントに……」
見たくないのに見たい、複雑なお年頃はまだ続くようだ。
怪盗アンノーン――。
彼、又は彼女は、王都や大きな都市に出没する有名な怪盗で、年齢、種族、性別、全てにおいて不明。
知られているのは、珍しい石ばかりを狙う石専門の怪盗ということだけだ。希少価値が高ければ宝石の他にも魔石なども含まれる。
アンノーンは犯行時に必ず予告状を出すわけではない。
貴族の屋敷のみ何度か予告状を出している。そういう場合は大抵盗みに入られた貴族の不正が後に暴かれるオマケ付きだ。
平民の自宅や店などには相場以上の金貨を置いて無言で立ち去るらしい。
王城の書庫や新聞で調べることができたのはここまでだ。
リドレー男爵については、王城で働く者達から話しを聞けた。特に王城で働く騎士は貴族の次男や三男が多く、男爵と交流のある者が多かった。
リドレー家は二代で大農家から貴族へと成り上がった。
野菜の品質も良く、商売の手腕も良く、それでいて男爵本人の温和な性格は身分関係なく評判も高い。
既に王都の食を支えている三大貴族に食い込む勢いで、四代貴族の一角と呼ばれる日も近い。爵位も上がると専らの噂だ。
しかし、なぜ宝石や美術品、絵画などを生業としている貴族ではなく、農業を主としている男爵が狙われているのか――。
彼も怪盗アンノーンに目を付けられるような不正を行っているのだろうか。
とにかく直接会ってみなければ何も始まらない。
約束の時間より早いが、真紘と重盛はリドレー男爵の屋敷へと向かうことにした。
背後には屋敷、目の前には広大な畑。
王都の最南端に位置する草原を開拓した広大な敷地には、触らずとも分かる瑞々しい白と黄緑のグラデーションが地面いっぱいに広がっていた。
王都の市場ではキャベツと白菜の間のような形の野菜が主流のようで、重盛もパスタやスープによく使用している。
「一面の白菜じゃん。真紘ちゃんが貰った調味料もまだあるし、明日は鍋にするか」
「いいね。野菜いっぱい食べたいな。豚肉を挟んでミルフィーユ鍋にしようよ」
「天才、採用!」
冬らしい薄い灰色の空。
最後に家族と囲んだ鍋もミルフィーユ鍋だったな、と思い出して日本の冬が恋しくなった。
カタカタという音が次第に大きくなり、十メートル程先にある屋敷の入口で一台の馬車が停まった。
降りてきたのは豪華なフリルのドレスを着た長身の美しい女性。桃色の長い髪はふわふわと風に揺れている。
「ここはうちの土地ですが」
棘のある声はこちらを警戒している。
犯行予告が届いているのだから無理もないだろう、と真紘は思ったが、重盛はすぐさま鼻を押さえて空いた方の手で真紘の腰をぐっと引き寄せた。
風に乗って、畑道に不釣り合いな人工的な甘い香りが鼻先を掠めた。
自分でこれならば重盛は相当辛いだろうと丸まった背中を擦る。
「勝手に敷地に立ち入って申し訳ございません。レミーさんからご紹介いただきました便利屋の志水と松永です」
「……あら、女性かと思ったら殿方でしたの。ふーん、レミーの紹介って聞いたからてっきりおじさんが来るのかっと思ってた。まあ、いいわ。丁度屋敷に戻るところなの。ここは従業員用の宿舎で、屋敷はもう少し先。見たところ身なりも良いし特別に載せてあげる。そこの御者、案内して」
「かしこまりました」
七十近い白髪の紳士は御者席から降りてこちらに近づいて来た。
苛烈な主人に振り回されているのか、素早い身のこなしに対し、かなりやつれている。
「ごめんなさい。香りに敏感なので、歩いて向かってもよろしいでしょうか? 約束の時間までには必ず参りますので……」
真紘が丁重に断ると、御者は穏やかに微笑み「それがいいと思います」と鼻の下の髭を撫でながら頷き、ゆっくりと馬車へと戻っていった。
「大丈夫? 香水、苦しかったね……」
「うげえ、外だったから油断してた~。あの馬車に乗ってたら確実に死んでたわ。助かった、サンキューね」
「どういたしまして」
「てか御者のじーさん、俺達が同乗拒否ったの伝えて超怒鳴られてたな……。後で謝んなきゃ」
口直しをするように、重盛は真紘の首筋から耳の裏にかけてスンスンと鼻を鳴らす。
御者が戻っていった直後に女の怒鳴り声が周囲に響き渡っていた。御者が何と言われたのかも彼に聞こえていたのだろう。
初めて会った人の心配をして落ち込む重盛を押しのけることはできない。暫く好きにさせていると、彼は漸く顔を上げた。
「てか、香水も性格もきついって、なんか聞いてた話と違くね? 温和な人って話じゃなかった?」
「それはお父様の方で、今のは娘さんじゃない? もうすぐどこかの子爵に嫁ぐって聞いたよ。馬車の家紋もリドレー男爵家のものとは違っていたし、丁度お相手のところから帰って来たんじゃないかな?」
「あー娘ね。あれ? 俺は今年成人したから婿を探しているって聞いたけど?」
「うーん、正反対な噂だね。とにかく回復したならお屋敷までゆっくり歩いて向かおうか。行けそう?」
重盛は首を横に振った。
そして「元気でない。んっ」と瞳を閉じて唇をにゅっと突き出す。
「もう、仕方ないなぁ」
真紘がそっと頬を包み踵を浮かせると、重盛はふにゃりと笑った。
リドレー男爵の屋敷に着くと、二人は二階の応接間へ通された。
大きな長方形の長テーブルを挟んで、リドレー男爵、先ほど会った長女のローザ、次女のマリー、その後ろに従業員のポール。
レミーはクルーズトレインの打ち合わせがあるため、真紘と重盛と入れ違いで出て行った。打ち合わせが上手くいけば戻って来ると言っていたが、ダブルビー社と揉めている最中らしいので難しいだろうと男爵は言う。
そんなリドレー男爵は噂通りの人物で、真紘と重盛を温かく歓迎してくれた。
マリーが作ったというほかほかと湯気の上がるポタージュを啜りながら男爵の話に相槌を打つ。
スープは温かくて美味しいが、なんだか緊張感に欠ける。
困惑が顔に出ていたのか、男爵は笑いながら無くなって困るほど高価な宝が自宅にはないのだと胸を叩いた。
ギルドや騎士に相談すべきだとレミーから進言されたが、長女の婚約が決まっている今、大きな騒ぎは起こしたくないというのが本音らしい。王家の紋章入りの馬車が自宅まで来たとなると、階級が上がったのか、事件なのか、と嫌でも注目を浴びる事態に陥ることは想像に難くない。
だから便利屋の自分達にお鉢が回ってきたということかと真紘は納得した。
「予告状には【美しいもの】を頂戴すると書かれていますね。怪盗アンノーンは珍しい石の収集家と聞いていますが、高価ではなくとも宝石や魔石は所有しているのではないですか?」
「宝石は亡くなった妻が残した物と、娘達の物だけで特別珍しい物はありません。不甲斐ないことですが、そこまで高価な物でもありません。私は宝石や美術品に疎くて……。宝と言えば娘達と従業員、広大な農地くらいです」
リドレー男爵はドワーフ族のようなずんぐりとした体型で、頬が零れそうなほどぽっこりしている。
長女は亡くなった母親似のようですらっとしており、階級が上の貴族からも求婚されるほどの美人だ。
次女は頬がぷっくりしていて誰が見ても父親似と答えるほど瓜二つ。垂れた目尻と上った口角は陽だまりのようで、どこかほっとする。
全員似ている志水家とは違い、真逆の印象を与える姉妹であった。
「そうですか。失礼ながら、お屋敷の警備などが少々手薄なようにお見受けします。変装が得意な怪盗アンノーンが変装して忍び込まないようにあえて人員を減らしているのでしょうか?」
「いいえ、これが普通なのです。警備も馴染みの者ばかりで、何かあれば宿舎にいる従業員達も飛んできます。夜以外は大体誰かが畑に出ているため、不審な人物がいれば目立ちます。慣れない者が畑に入ろうものならば、害獣対策の罠に嵌って一晩中動けなくなっていると思いますよ」
「なるほど。郊外にあるからこそ不審な人物がいれば目立つ。人の目が防犯対策になっているということですね」
「そうなります」
狙われている物を特定できない以上、屋敷全体の警備を強化するしかない。しかし今回は目立ちたくはないというオーダー付きだ。
一晩くらいならば王城のように屋敷を囲む結界を張れば済む話なのだが、狙われている物が長女の所有する宝石だった場合、嫁ぎ先で盗まれる可能性もある。
今夜の犯行を防いだとしても、また狙われるかもしれないという恐怖と付き合っていくのは耐え難いだろう。犯人を捕まえなくては根本的な解決とは言えない。
頭を悩ませていると、使用人のポールがあの、と手を挙げた。
「なんだい、ポール。良い案でも浮かんだかい?」
「いえ、そういう事ではないのですが、畑に大きな石のようなものがあります。美しいものはそれではないかと思いまして――」
「はあ? あんなのが美しいだなんてどうかしてる。ただ邪魔くさいだけじゃないの」
畑作業をしないにも関わらずローザはポールの意見を払い除けた。彼女は石自体よりもリドレー家に関する物全てが気に入らないのだ。それは御者や従業員に対する接し方からも見て取れる。
ポールは金髪にブラウンの瞳、精悍な顔立ちで、重盛の弟と言われても納得できるほどの体格だ。そんな屈強な彼だが、立場上ローザに言い返すことはできない。
「そんなことないよ。あの石、割れた断面が茄子みたいに黒々としていて綺麗だもの! 私も好きだよ」
ずっとにこにこと微笑んでいた次女のマリーはポールの手を取った。
ローザは興味を失ったように「あんたには聞いてない」と呟き、そっぽを向いた。
ギスギスとした雰囲気を変えるために真紘は手を一度叩いてポールに話しかけた。
「ポールさん、畑にある石というのはどのようなものですか?」
「腰かけ石といって畑の中央にある大きな黒い石なのですが、自然と割れた面がキラキラと輝いていて! 確かに野ざらしになっているただの石なのですが、座っていると不思議と力が湧いてくると言いますか……」
「それは興味深いですね。誰かが置いたんですか?」
「いえ、元からあるもので、畑を作る際にもその石が重すぎて除けることができなかったそうです。今はみんなの休憩用の腰かけになっています」
「なるほど。男爵様、後で見に行かせていただいてもよろしいでしょうか?」
「勿論でございます。自慢の畑も是非」
大きく頷いた男爵に続きマリーが手を挙げる。
「私がご案内致します。腰かけ石も、皆が手塩に掛けた野菜たちも見てもらわないと!」
はんっとローザは馬鹿にしたように鼻で笑う。
「お父様の真似事ばかりで土にまみれてばかり。そんなんだから婿候補も一人だけなの。しかも家畜貴族。笑っちゃうわね。私が子爵家に嫁いでもこんな家、絶対に援助なんてしないから」
「ローザ様!」
「いいの、ポール。私は畑仕事が好きだし、お姉さまのように綺麗ではないのは本当のことだから……」
憤るポールを諫めるマリーの瞳は大きく揺れていた。
「ローザ。トランシルヴァ伯爵は立派なお方だ。爵位の問題ではなく、礼儀として弁えなければならないよ。頼むから失礼のないように。彼の育てる牛や豚はどれも素晴らしく、我が家の廃棄野菜を引き取ってくださる大事な取引先でもあるのだから――」
「はあーあ。またその話? 聞き飽きたわ。疲れたから部屋に戻る」
実父の話をも遮り、ローザは自室へと戻っていった。
リビングには白いシャツを羽織っただけの着替え途中の真紘。桃色のスラックスと茶色のベルトはソファーに投げ捨てられていて、白い足は惜しみなく晒されていた。
寝ぐせによって四方八方に散らばる重盛の髪先がさらにぶわりと広がる。
「おはよう、重盛」
「じ、事後みたいな格好すんなって!」
「はあ? 朝から何言ってるんだか……。それよりついさっきレミーさんから依頼があったんだ。寄りたいところもあるから朝食を食べたらすぐに出かけるよ。顔洗っておいで」
キス以上のことはまだ先にと約束をしてから煽らないようにと懇願されていたが、予告なく肌を晒すだけでも駄目らしい。
今まで宿屋であったりタイニーハウスであったり、人の目があるかもしれないという心配で気が抜けなかった反動か、真紘も自宅の中ではかなり気が抜けている自覚はあった。そのせいなのか今ではパジャマのボタンも一番上まで閉めろという指令付きだ。
しかし、言いつけもきちんと守っているのだから着替えのタイミングくらい好きにさせて欲しい。
キスもしているし毎日一緒に寝てもいるのにと抗議すれば、その顔も止めろと重盛はしゃがみ込む。
観念してさっとスラックスを履くと、重盛は少し残念そうな顔をしていた。
「僕は煽ってるつもりは一切ないんだけど……。君の基準が全然わからない」
「それはこちらが判断することなのであります」
「んふっ、照れるとたまに変なキャラになるよね。それ笑っちゃうから止めてよ」
「なんだよその余裕~襲われても文句言うなよ!」
「襲って後悔するのは重盛の方でしょうに」
「だあッ! 朝から俺の純情弄ぶなぁ!」
ごめんごめんと言いながら真紘は仕上げのリボンを重盛に手渡した。
ソファーに座ると長い髪を右側にまとめて白い首を晒す。
「うなじはもう見飽きたでしょ、セーフだよね?」
「ううっ……泣くぞホントに……」
見たくないのに見たい、複雑なお年頃はまだ続くようだ。
怪盗アンノーン――。
彼、又は彼女は、王都や大きな都市に出没する有名な怪盗で、年齢、種族、性別、全てにおいて不明。
知られているのは、珍しい石ばかりを狙う石専門の怪盗ということだけだ。希少価値が高ければ宝石の他にも魔石なども含まれる。
アンノーンは犯行時に必ず予告状を出すわけではない。
貴族の屋敷のみ何度か予告状を出している。そういう場合は大抵盗みに入られた貴族の不正が後に暴かれるオマケ付きだ。
平民の自宅や店などには相場以上の金貨を置いて無言で立ち去るらしい。
王城の書庫や新聞で調べることができたのはここまでだ。
リドレー男爵については、王城で働く者達から話しを聞けた。特に王城で働く騎士は貴族の次男や三男が多く、男爵と交流のある者が多かった。
リドレー家は二代で大農家から貴族へと成り上がった。
野菜の品質も良く、商売の手腕も良く、それでいて男爵本人の温和な性格は身分関係なく評判も高い。
既に王都の食を支えている三大貴族に食い込む勢いで、四代貴族の一角と呼ばれる日も近い。爵位も上がると専らの噂だ。
しかし、なぜ宝石や美術品、絵画などを生業としている貴族ではなく、農業を主としている男爵が狙われているのか――。
彼も怪盗アンノーンに目を付けられるような不正を行っているのだろうか。
とにかく直接会ってみなければ何も始まらない。
約束の時間より早いが、真紘と重盛はリドレー男爵の屋敷へと向かうことにした。
背後には屋敷、目の前には広大な畑。
王都の最南端に位置する草原を開拓した広大な敷地には、触らずとも分かる瑞々しい白と黄緑のグラデーションが地面いっぱいに広がっていた。
王都の市場ではキャベツと白菜の間のような形の野菜が主流のようで、重盛もパスタやスープによく使用している。
「一面の白菜じゃん。真紘ちゃんが貰った調味料もまだあるし、明日は鍋にするか」
「いいね。野菜いっぱい食べたいな。豚肉を挟んでミルフィーユ鍋にしようよ」
「天才、採用!」
冬らしい薄い灰色の空。
最後に家族と囲んだ鍋もミルフィーユ鍋だったな、と思い出して日本の冬が恋しくなった。
カタカタという音が次第に大きくなり、十メートル程先にある屋敷の入口で一台の馬車が停まった。
降りてきたのは豪華なフリルのドレスを着た長身の美しい女性。桃色の長い髪はふわふわと風に揺れている。
「ここはうちの土地ですが」
棘のある声はこちらを警戒している。
犯行予告が届いているのだから無理もないだろう、と真紘は思ったが、重盛はすぐさま鼻を押さえて空いた方の手で真紘の腰をぐっと引き寄せた。
風に乗って、畑道に不釣り合いな人工的な甘い香りが鼻先を掠めた。
自分でこれならば重盛は相当辛いだろうと丸まった背中を擦る。
「勝手に敷地に立ち入って申し訳ございません。レミーさんからご紹介いただきました便利屋の志水と松永です」
「……あら、女性かと思ったら殿方でしたの。ふーん、レミーの紹介って聞いたからてっきりおじさんが来るのかっと思ってた。まあ、いいわ。丁度屋敷に戻るところなの。ここは従業員用の宿舎で、屋敷はもう少し先。見たところ身なりも良いし特別に載せてあげる。そこの御者、案内して」
「かしこまりました」
七十近い白髪の紳士は御者席から降りてこちらに近づいて来た。
苛烈な主人に振り回されているのか、素早い身のこなしに対し、かなりやつれている。
「ごめんなさい。香りに敏感なので、歩いて向かってもよろしいでしょうか? 約束の時間までには必ず参りますので……」
真紘が丁重に断ると、御者は穏やかに微笑み「それがいいと思います」と鼻の下の髭を撫でながら頷き、ゆっくりと馬車へと戻っていった。
「大丈夫? 香水、苦しかったね……」
「うげえ、外だったから油断してた~。あの馬車に乗ってたら確実に死んでたわ。助かった、サンキューね」
「どういたしまして」
「てか御者のじーさん、俺達が同乗拒否ったの伝えて超怒鳴られてたな……。後で謝んなきゃ」
口直しをするように、重盛は真紘の首筋から耳の裏にかけてスンスンと鼻を鳴らす。
御者が戻っていった直後に女の怒鳴り声が周囲に響き渡っていた。御者が何と言われたのかも彼に聞こえていたのだろう。
初めて会った人の心配をして落ち込む重盛を押しのけることはできない。暫く好きにさせていると、彼は漸く顔を上げた。
「てか、香水も性格もきついって、なんか聞いてた話と違くね? 温和な人って話じゃなかった?」
「それはお父様の方で、今のは娘さんじゃない? もうすぐどこかの子爵に嫁ぐって聞いたよ。馬車の家紋もリドレー男爵家のものとは違っていたし、丁度お相手のところから帰って来たんじゃないかな?」
「あー娘ね。あれ? 俺は今年成人したから婿を探しているって聞いたけど?」
「うーん、正反対な噂だね。とにかく回復したならお屋敷までゆっくり歩いて向かおうか。行けそう?」
重盛は首を横に振った。
そして「元気でない。んっ」と瞳を閉じて唇をにゅっと突き出す。
「もう、仕方ないなぁ」
真紘がそっと頬を包み踵を浮かせると、重盛はふにゃりと笑った。
リドレー男爵の屋敷に着くと、二人は二階の応接間へ通された。
大きな長方形の長テーブルを挟んで、リドレー男爵、先ほど会った長女のローザ、次女のマリー、その後ろに従業員のポール。
レミーはクルーズトレインの打ち合わせがあるため、真紘と重盛と入れ違いで出て行った。打ち合わせが上手くいけば戻って来ると言っていたが、ダブルビー社と揉めている最中らしいので難しいだろうと男爵は言う。
そんなリドレー男爵は噂通りの人物で、真紘と重盛を温かく歓迎してくれた。
マリーが作ったというほかほかと湯気の上がるポタージュを啜りながら男爵の話に相槌を打つ。
スープは温かくて美味しいが、なんだか緊張感に欠ける。
困惑が顔に出ていたのか、男爵は笑いながら無くなって困るほど高価な宝が自宅にはないのだと胸を叩いた。
ギルドや騎士に相談すべきだとレミーから進言されたが、長女の婚約が決まっている今、大きな騒ぎは起こしたくないというのが本音らしい。王家の紋章入りの馬車が自宅まで来たとなると、階級が上がったのか、事件なのか、と嫌でも注目を浴びる事態に陥ることは想像に難くない。
だから便利屋の自分達にお鉢が回ってきたということかと真紘は納得した。
「予告状には【美しいもの】を頂戴すると書かれていますね。怪盗アンノーンは珍しい石の収集家と聞いていますが、高価ではなくとも宝石や魔石は所有しているのではないですか?」
「宝石は亡くなった妻が残した物と、娘達の物だけで特別珍しい物はありません。不甲斐ないことですが、そこまで高価な物でもありません。私は宝石や美術品に疎くて……。宝と言えば娘達と従業員、広大な農地くらいです」
リドレー男爵はドワーフ族のようなずんぐりとした体型で、頬が零れそうなほどぽっこりしている。
長女は亡くなった母親似のようですらっとしており、階級が上の貴族からも求婚されるほどの美人だ。
次女は頬がぷっくりしていて誰が見ても父親似と答えるほど瓜二つ。垂れた目尻と上った口角は陽だまりのようで、どこかほっとする。
全員似ている志水家とは違い、真逆の印象を与える姉妹であった。
「そうですか。失礼ながら、お屋敷の警備などが少々手薄なようにお見受けします。変装が得意な怪盗アンノーンが変装して忍び込まないようにあえて人員を減らしているのでしょうか?」
「いいえ、これが普通なのです。警備も馴染みの者ばかりで、何かあれば宿舎にいる従業員達も飛んできます。夜以外は大体誰かが畑に出ているため、不審な人物がいれば目立ちます。慣れない者が畑に入ろうものならば、害獣対策の罠に嵌って一晩中動けなくなっていると思いますよ」
「なるほど。郊外にあるからこそ不審な人物がいれば目立つ。人の目が防犯対策になっているということですね」
「そうなります」
狙われている物を特定できない以上、屋敷全体の警備を強化するしかない。しかし今回は目立ちたくはないというオーダー付きだ。
一晩くらいならば王城のように屋敷を囲む結界を張れば済む話なのだが、狙われている物が長女の所有する宝石だった場合、嫁ぎ先で盗まれる可能性もある。
今夜の犯行を防いだとしても、また狙われるかもしれないという恐怖と付き合っていくのは耐え難いだろう。犯人を捕まえなくては根本的な解決とは言えない。
頭を悩ませていると、使用人のポールがあの、と手を挙げた。
「なんだい、ポール。良い案でも浮かんだかい?」
「いえ、そういう事ではないのですが、畑に大きな石のようなものがあります。美しいものはそれではないかと思いまして――」
「はあ? あんなのが美しいだなんてどうかしてる。ただ邪魔くさいだけじゃないの」
畑作業をしないにも関わらずローザはポールの意見を払い除けた。彼女は石自体よりもリドレー家に関する物全てが気に入らないのだ。それは御者や従業員に対する接し方からも見て取れる。
ポールは金髪にブラウンの瞳、精悍な顔立ちで、重盛の弟と言われても納得できるほどの体格だ。そんな屈強な彼だが、立場上ローザに言い返すことはできない。
「そんなことないよ。あの石、割れた断面が茄子みたいに黒々としていて綺麗だもの! 私も好きだよ」
ずっとにこにこと微笑んでいた次女のマリーはポールの手を取った。
ローザは興味を失ったように「あんたには聞いてない」と呟き、そっぽを向いた。
ギスギスとした雰囲気を変えるために真紘は手を一度叩いてポールに話しかけた。
「ポールさん、畑にある石というのはどのようなものですか?」
「腰かけ石といって畑の中央にある大きな黒い石なのですが、自然と割れた面がキラキラと輝いていて! 確かに野ざらしになっているただの石なのですが、座っていると不思議と力が湧いてくると言いますか……」
「それは興味深いですね。誰かが置いたんですか?」
「いえ、元からあるもので、畑を作る際にもその石が重すぎて除けることができなかったそうです。今はみんなの休憩用の腰かけになっています」
「なるほど。男爵様、後で見に行かせていただいてもよろしいでしょうか?」
「勿論でございます。自慢の畑も是非」
大きく頷いた男爵に続きマリーが手を挙げる。
「私がご案内致します。腰かけ石も、皆が手塩に掛けた野菜たちも見てもらわないと!」
はんっとローザは馬鹿にしたように鼻で笑う。
「お父様の真似事ばかりで土にまみれてばかり。そんなんだから婿候補も一人だけなの。しかも家畜貴族。笑っちゃうわね。私が子爵家に嫁いでもこんな家、絶対に援助なんてしないから」
「ローザ様!」
「いいの、ポール。私は畑仕事が好きだし、お姉さまのように綺麗ではないのは本当のことだから……」
憤るポールを諫めるマリーの瞳は大きく揺れていた。
「ローザ。トランシルヴァ伯爵は立派なお方だ。爵位の問題ではなく、礼儀として弁えなければならないよ。頼むから失礼のないように。彼の育てる牛や豚はどれも素晴らしく、我が家の廃棄野菜を引き取ってくださる大事な取引先でもあるのだから――」
「はあーあ。またその話? 聞き飽きたわ。疲れたから部屋に戻る」
実父の話をも遮り、ローザは自室へと戻っていった。
24
あなたにおすすめの小説

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします
み馬下諒
BL
志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。
わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?
これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。
おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。
※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。
★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★
★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★

裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。
みーやん
BL
何日の時をこのソファーと過ごしただろう。
愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。
「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。
あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。
最後のエンドロールまで見た後に
「裏乙女ゲームを開始しますか?」
という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。
あ。俺3日寝てなかったんだ…
そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。
次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。
「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」
何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。
え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?
これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)
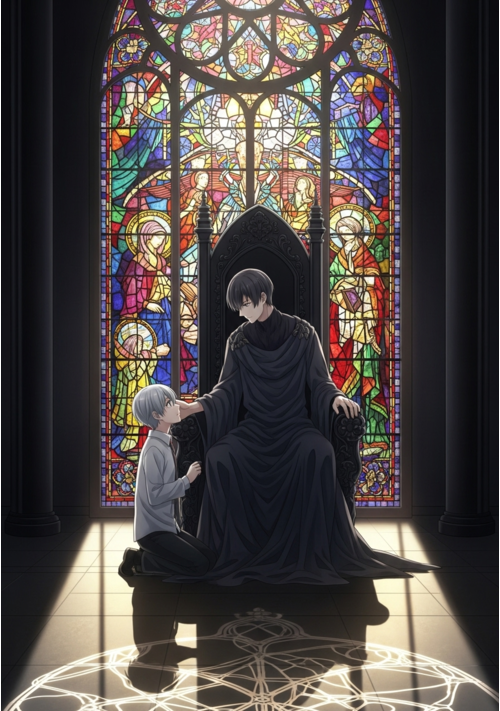
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。
ありま氷炎
BL
高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。
異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。
二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。
しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。
再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される
水凪しおん
BL
勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。
絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。
帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?
「私の至宝に、指一本触れるな」
荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。
裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。


男子高校生だった俺は異世界で幼児になり 訳あり筋肉ムキムキ集団に保護されました。
カヨワイさつき
ファンタジー
高校3年生の神野千明(かみの ちあき)。
今年のメインイベントは受験、
あとはたのしみにしている北海道への修学旅行。
だがそんな彼は飛行機が苦手だった。
電車バスはもちろん、ひどい乗り物酔いをするのだった。今回も飛行機で乗り物酔いをおこしトイレにこもっていたら、いつのまにか気を失った?そして、ちがう場所にいた?!
あれ?身の危険?!でも、夢の中だよな?
急死に一生?と思ったら、筋肉ムキムキのワイルドなイケメンに拾われたチアキ。
さらに、何かがおかしいと思ったら3歳児になっていた?!
変なレアスキルや神具、
八百万(やおよろず)の神の加護。
レアチート盛りだくさん?!
半ばあたりシリアス
後半ざまぁ。
訳あり幼児と訳あり集団たちとの物語。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
北海道、アイヌ語、かっこ良さげな名前
お腹がすいた時に食べたい食べ物など
思いついた名前とかをもじり、
なんとか、名前決めてます。
***
お名前使用してもいいよ💕っていう
心優しい方、教えて下さい🥺
悪役には使わないようにします、たぶん。
ちょっとオネェだったり、
アレ…だったりする程度です😁
すでに、使用オッケーしてくださった心優しい
皆様ありがとうございます😘
読んでくださる方や応援してくださる全てに
めっちゃ感謝を込めて💕
ありがとうございます💞
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















