3 / 112
3話~加護の授与~
しおりを挟む
~加護の授与~
「アンセートル・ベネトラクト・アコーデ」
「アンセートル・ベネトラクト・アコーデ……」
樹液の入った小瓶を手にした大司教たちの唱和が再び始まる。
さっきまでリシャール殿下やナタン、アルチュールのデピスタージュを傍から見ていただけだったから分からなかったが、体験してみると先ずは手に、そこから脳に、そして脊髄から足の先まで隙間なく力が漲るような感覚に圧倒された。
これが魔力の流れ――。この世界の言葉では、『サリトゥ』と呼ぶ。
まるで体中のあちこちに仕掛けられていた見えないリミッターが一つ残らず消失し、重力からも解放されたたかのようだ。いや、持っていた能力が底上げされたと言った方がいいのか? 兎に角、全身が軽い。
しばらくすると、俺の両掌に、ローリエの木を伴った見事な『ベネン』が浮かび上がった。外枠の細い円は、銀灰色で縁取られ、鈍い輝きを放っている。
なるほど、美しい。確かに、これは誰かに見せたくなるな。
ついさっき、アルチュールが上機嫌で自分のベネンを見せて来た顔を思い出す。濡れた宝石のような瞳が印象的な、原作ではお目にかかったことのないレアな推しショットだった。脳の記憶メモリーの最前列に保管しておこう。
一連の義が終わると、俺を取り囲んでいた幻影の柱が強風に攫われる浜辺の砂城のように崩れ、跡形もなく消えた。
中々、感慨深い。
ほんの一瞬、余韻に浸ったあと、直ぐ横で未だ尻もちをついていた少女漫画風の修道士に手を差し伸べる。
「ありがとうございます。ロード・コルベール」
修道士は遠慮がちに俺の手を取り、左足に体重をかけようとして眉根を寄せ、かばうようにして立ち上がった。
「痛めたのか?」
俺は腰を下ろし、床に片膝を付いてしゃがむと修道士の左足首に手を添えた。確実にベネンの働きだろう、サリトゥの流れに乱れがあることがありありと分かる――。というか、見える。それは実際に視認しているわけではないが、脳内にイメージとして浮かび上がって来る感覚。
「だ、大丈夫です」
「いや、大丈夫じゃないだろ」
回復魔法の呪文なら知っている。もしも魔法に関する事象が改変されず原作通りだとしたら、この世界で使われている呪文、全てを俺は覚えている。ファンサイトのホームページまで作って新刊が出る度にこつこつと用語集をまとめ上げたんだから。
先ずは、自らの左手首に右手を当て、微量の魔力を流してみた。いきなり他人で試すわけにはいかない。
「トゥレイト……」
温かい波動が伝わって来る。よし、これなら何も問題はなさそうだ。
「もしも違和感や不具合があれば直ぐに教えてくれ」そう言ってから、俺は再び修道士の足首に手を置いて治癒の呪文を唱えた。「トゥレイト」
修道士の膝から踝までのサリトゥの歪みが瞬く間に修正されていく。
あとは――「アレンテドゥラ」。 これで痛みも消えるはず……。
顔を上げると、口をぽかんと開けて硬直する修道士と目が合った。
「まだ痛いか?」
「い、いえ、全く! 痛みが嘘のように消えています!」
「それは良かった」
「ありがとうございます、『銀の君』、あっ、ロード・コルベール」
修道士の頬は微かに紅潮し、はにかんだような少し読み取りにくい笑みを唇に浮かべていた。
「凄いな、セレスは。もう回復魔法が使えるのか……?」
いつからそこにいたのか、背後に立つアルチュールが膝に両手を置いて腰をかがめながら俺の手元をのぞき込んでそう言った。
ぐるりと周囲を見渡すと、この場に居る全員の視線が俺に注がれている。
浄化系魔法は相手側に注ぎ込む自身のサリトゥの調整が難しく、ただ呪文を知っているだけでは的確に、尚且つ思う通りに扱えるわけではない。
それを例え傷を負った相手の状態が重症ではなく打ち身や捻挫であれ、加護の魔法陣が掌に付与された直後にやってしまった。
怪我をした相手を癒したいと思った気持ちが一番大きかったことは嘘偽りのない本心だが……、魔法への好奇心がそこに無かったかと聞かれれば――、
否定はできない。
「口伝や、いくらかの文献では、『リュミエール』は、それだけで能力を発するが、他の持っている能力を安定、増幅、躍進もさせるといわれている」
声がした方向を向いて立ち上がると、若い夏の香りがしそうな爽やかな笑みを浮かべたリシャール殿下がこちらに向かって歩いて来るところだった。ナタンも居る。
「殿下」
「リシャールと呼べ、セレス。でないと私もお前を『麗しき銀の君』とか、『憧れのロード・コルベール』と呼ぶぞ」
「やめて下さい!」
即座の俺の拒否反応に、いたずらっぽく片眉を上げて殿下がくすりと笑った。やんごとなき相手、しかも推しから恭しく扱われるだなんて、尻がこそばゆいにもほどがある。
ってゆーか、『麗しき』とか『憧れの』って何なんだよ?? それ、『金の君』こと、あなた様を表現する形容詞だろう!?
「『リュミエール』に属す者になんて、先ず、今まで会ったことがないどころか、我が王国に伝わる数多き文献にも記述は少なく、色々と分からない部分が多過ぎる。今後は常にセレスの側に居て観察させてもらおうかな」
いや、殿下にそんなことをする時間があるのなら、俺なんかほっといてアルチュールと行動を共にしててくれ、頼むから。間近でそれが見たいんだよ、お願いします。
「いいえ、側に居るのはこの私です。今までも、これからも。現在、侍従としては休職中ですが、なんといってもセレスさま……、セレスは私の主ですから」
口元を弓形にゆるませてナタンが言った。
「前々から思っていたが、セレスに友達が少ないのはナタン、お前のせいじゃないか? サロンでもセレスが私だけではなく他の誰かと話していると直ぐに間に入って来るし、「お時間ですセレスさま」とか言って、早々と帰宅を促すし」
「そうですか? でも殿下の場合は仕方がないと思いますよ。異国から来られた要人が目の前に居ても、ほったらかしにしてセレスさ……、セレスと二人で話し込もうとするからです」
「殿下じゃない。ここではリシャールと呼べと、……いや、お前だけ私のことをリシャールと呼び捨てにするのを許さん」
「なんでですか、リシャール、リシャール、リシャール!!」
何か……この二人、仲良いな……、と思って眺めていたら――、
「あの二人、仲良いな」
隣でアルチュールが同じ事を考えていた。
「うん。原作にはこんなシーンは無かったから、新鮮だわ……」
「……原作?」
「あ、いや、その……」
やばい。
どう誤魔化そうかと一瞬、頭を捻っていると、
「なあ、セレスは友達が少ないのか?」
どうやらアルチュールは俺が口を滑らせた『原作』という言葉に関して何も関心を持たなかったようだ。寧ろ、先ほど殿下が話した内容に興味を示している。
「まあ……、友達は多くはないかな」
「そんな風には見えないけど」
「そうか?」
「俺は……、セレスが初めての友達だと勝手に思っている」
えっ!?
俺が弾かれたかのように隣に視線を向けると、居心地が悪そうな子供のような顔をしたアルチュールがそこに居た。微かに耳が赤い。
彼がどうやって辺境のシルエット領で育ったか――勿論、俺はそれも知っている。
文武共に優秀な父と兄に憧れ、ずっとその背中を追い続け、物心ついたころには友達と遊ぶよりも数人の護衛とオオカミ犬を伴い、近年は護衛を伴わず、日々、人と魔族との境界地に現れる小物とはいえ魔物の退治をしながら鍛錬を続けて来た。
友達を作ろうにも、アルチュールと対等に『遊ぶ』ことが出来るような子供は家臣の家にも居なかった。領民の子なら猶更だ。ただでさえ普通の子供には魔力がない。駆けっこ、剣術ごっこ――大人顔負けの相手と遊ぶだなんて、負け続けるのは退屈な上に面白くない。下手したら怪我をすることになる。
「迷惑……、だよな? 俺、口が悪いし、なんといっても礼儀を知らないし」
不安を誤魔化すためか、頭を傾げてちらりとこちらを見たアルチュールに、それだけで胸が締め付けられるように痛くなった。
うーん、アルチュールは、女性がよく言う『守ってあげたくなるような男』……、というキャラではなかったはずなんだけどな。まあ、俺が萌えるから良いか。
「迷惑なわけないだろう」
たたみかけるように俺は言った。
推しから友達認定されるだなんて、嬉しすぎてプルプル震えるじゃないか。今、俺、チワワだぞ。
「本当に迷惑ではないのか?」
「迷惑なわけない! 殿下が言うように俺は友達が少ないんだ。アルチュールが友達になってくれたら嬉しいに決まってる!」
「じゃあ、俺もセレスの側に居れるってことだよな?」
「当たり前だ!」
と即答してから直ぐに我に返る。
殿下もアルチュールも、ついでにナタンも俺の側に居たら、どうやって俺は、アル×リシャの推しが二人っきりで人目をはばかりながら愛をはぐくんで行く行程をこっそりと観察すればいいんだ??
いや、マジこれどうすべきなんだよ!?
༺ ༒ ༻
一旦、食堂に戻り、全員のデピスタージュが終了するのをそこで待つ。
本来なら入寮発表が行われるまでの退屈で仕方がない長い待ち時間に、衛生管理の行き届いた軽食と飲み物がビュッフェスタイルで自由に好きなだけ摂取出来たのは、どの生徒たちにとっても大変有難かった。辺境の貴族子息や留学生たちが、何となく周囲に馴染みつつあるのもこの心遣いと雰囲気のおかげだろう。見ず知らずの者同士が同じ釜の飯を食べながら次第に打ち解けていく――そういう光景が、今まさに広がっている。
異世界とはいえ原作によると、時代設定の参考は一八〇〇年代のフランス。
しかし、これはコルベール家でも感じたことだが、公衆衛生や食事の品質、電気はないが必要最低限のインフラの質は現代の日本とさほど変わらない。
水属性の魔法陣と浄化魔法を使って整備された上下水道は、この王都では貴族以外の家にまで行き届いているし、街中には火属性の魔法陣が描かれた街灯が立ち並び、夜も明るい。
さしずめ、無くて残念なのはスマホやインターネット、ゲームぐらいのものかもしれないな。
――と、転生前の世界のことをぼんやりと思い出していると、やや低めの落ち着いた声が食堂に響いた。
「諸君、この度は入学おめでとう。そして、お待ちかねの入寮発表の時間だ」
全員の注目を一身に浴びながら、壇上に置かれたコフルの上で喋り出したのは、一羽のコルネイユだった。
艶やかな漆黒の翼をゆるやかに畳み、眼に暗い琥珀のような光を湛えて、その胸を誇らしげに張りながら、「尚、我が名はゾンブル。ゾンブル閣下である」と彼は名乗った。
よし、先ずは原作通りに進んでいる。
留学生たちの間に微かなざわめきが巻き起こる。しかし王国の者は使い魔や言葉を操る動物を見慣れているせいで、特に驚いた様子はない。
「いよいよですね、セレスさ……、セレス。同じ寮になることを心より願っています」
隣に座るナタンが、興奮を隠しきれない様子で小声で話しかけて来た。頬はほころび、目はきらきらと輝いている。
余談にはなるが、この世界における『寮』とは、日本の学校制度で言うところの『クラス』に近しい役割を担っている。
一度割り当てられた寮が変更されることは、三年間の在学期間を通してほぼない。たとえ他寮への移動を願い出たとしても、それが認められるのは極めて明確かつ正当な理由がある場合に限られる。
寮塔は本校舎の東側、聖堂や食堂とともに、外廊下の回廊によって結ばれている。建物は四棟。いずれも長方形で、その配置はひし形を描くように設計されていた。
一棟は職員寮だが、残る三棟が学生たちの住まい──第一寮『サヴォワール寮』、第二寮『レスポワール寮』、第三寮『ソルスティス寮』。それらの建物に囲まれた中庭には、回復薬ポーションの素材となる薬草が整然と植えられ、中央には白いドーム型のガゼボが静かに佇んでいる。
この学び舎において、生徒は入学と同時にいずれかの寮へと振り分けられ、そこで暮らし、学び、友情や軋轢のすべてを経験することとなる。
「なあナタン、セレスって呼びにくいなら、もう好きに呼んでもいいぞ。あと、お前とは別の寮がいいと俺は思っている」
「な、なんでですか、セレスさま!?」
お前が側に居ると、推し活がはかどらないからだよ――とは口が裂けても言えない。
壇上では、ゾンブル閣下がくるりと翼を広げて向きを変えた。いよいよ結果が発表される。食堂の空気がぴんと張り詰めた。
「アペリオ、コフル!! オゥヴァ・ヴォランティス!」
ゾンブル閣下の声が高らかに天井を打ったと同時に、箱の表面に刻まれた文様が光り出し、重厚そうな蓋がひとりでに、そして静かに、しかし確かな気配をもって開き始める。まるで意志を持っているかのように。そして次に、ぼんやりとした光を纏った何通もの小さな封筒が中から一斉に飛び出して生徒全員の目の前に落ちて行く。
圧巻の光景。このシーン、滅茶苦茶好きだったんだよ。体験出来るだなんて、感動もひとしおだ!
しばらくの静寂のあと、あちらこちらから紙がテーブルに落ちる小さな音と共に、感嘆の息が漏れ聞こえてきた。
俺の前にも一通、月光を思わせる柔らかな手すき紙に、深紅の封蝋が凛として咲く一輪の薔薇のようにあしらわれた封筒が着地する。そこには、王家の紋章とゼコールリッツ学院のシンボル、二つの印が並んでいた。
指先で慎重に封を解く。すると、中から一枚の薄紙が静かに滑り出し、その紙面には名前と共に、これからの日々を過ごすことになる寮の名が凛とした筆致で刻まれていた。
| セレスタン・ギレヌ・コルベール
| 所属寮:第一寮・サヴォワール寮(310号室)
| 寮監:ヴィクター・デュボア
ナタンが身を乗り出して自分の封筒を開封する様子を横目で見つつ、俺は、改めて記された文字に視線を落とした。
「サヴォワール……」
原作本編のセレスタン・ギレヌ・コルベールが所属していたのは、第三寮の『ソルスティス寮』だ。
そして、アルチュール・ド・シルエットとリシャール・ドメーヌ・ル・ワンジェ王太子殿下が所属していたのが第一寮の『サヴォワール寮』――。
ここでまた原作とは異なる展開が現れてしまった。
そう思いながらふと顔を上げると……、
「セレスもサヴォワール寮なのか!?」
嬉しそうに声を上げたアルチュールが、ナタンの背後から俺の視界に飛び込んで来た。「セレスも」ということは、彼自身がすでにサヴォワール寮だということは間違いない。
「俺は、309号室だ。セレスは?」
おいおい、推しの隣かよ。
「310号室だ」
「よしっ!」
何故かガッツポーズを取るアルチュールの横で、リシャール殿下が封筒の中に入っていた紙をこちらに向け、ひらひらと揺らしながら満面の笑みを浮かべている。
「私もサヴォワール、311号室だ」
なんてこった。推しカプに挟まれてしまった……。
ちなみに今の座席の配置は、俺の右隣にナタン、さらにその隣にアルチュール、そしてリシャール。何故か食堂に戻った直後、俺以外の三人がジャンケンで決めていた。意味が分からない。
「はいはい、リシャールもサヴォワールですか」
思わず肩をすくめて呟くと、殿下は「当然だ」と言わんばかりに胸を張って見せた。その仕草がいちいち様になっている。
流石『金の君』。マジで眩しい。
ナタンも封を開け終えたらしく、「やった!」と小さく声を上げた。
「私もサヴォワールです! 320号室」
微妙に遠いな。
しかし、これで『アル×リシャ』を近接距離でこっそりと一人、隠れて見守りつつ萌えを補給するという俺の推し活環境は崩壊したと言っても過言ではない。自分の存在を一切主張することなく、ただ影になり、ある時は路傍の草となり、静かに音を立てず傍で見つめる。耳を澄まし、目を凝らし、二人が紡ぐ何気ない瞬間に心を満たす――。
それが、こんな「俺たち仲良し四人組~」みたいになってしまったら、叶わねぇじゃねぇか!
ああ、このままだと腐脳が渇いて干からびそうだ。
この寮分け、魔力特性の相性か、学院側の戦略的配慮か何かだろうな。想定外すぎるセレスタンのチート能力に関しては、この際、無視しても、基本的な魔力量の多いこの四人で『風火水土』全部揃ってるし……。
食堂内では、生徒たちの喜びや戸惑いが錯綜していた。封筒を開けて友人同士で握手する者、相性の悪い誰かと一緒になってしまったのか予想外の結果にぼう然とする者――。
そんな中、壇上のゾンブル閣下が再び声を張る。
「では諸君、君たちの荷物は既に寮監の指示のもと、二年生が部屋に運び込んでくれている。自分が入居する寮と部屋番号を確認の上、自室で夕食の知らせがあるまで待機のこと。では、解散!」
ゾンブル閣下の号令が響き渡ると、それまでの緊張感が嘘のように一気にほどけ、生徒たちの間に活気が溢れ出した。皆、それぞれの封筒を大事そうに握りしめながら、歓声を上げたり談笑したりと、三々五々、にわかに賑やかになった食堂をあとにして行く。その人波に、俺たちも紛れ込んだ。
「セレスと同じ寮になるなんて、ホッとした。これからが楽しみだ」
席を立つとすぐに俺の右隣に滑り込むようにしてやって来たアルチュールが、柔らかい笑みを浮かべながら声を弾ませた。まるで遠足に胸を躍らせる子供のようだ。気のせいではなく、その言葉の端々には、俺との距離が縮まることへの明らかな喜びが感じ取れる。
――余程、初めて出来た友達の存在が嬉しいのか……?
「しかも、お隣さんだな。今日から宜しくアルチュール」
原作では、鋭利な視線の奥に決して揺るがぬ芯を秘めた騎士――それが、アルチュール・ド・シルエットという男だったはず。
けれど今の彼は、無防備な笑みを浮かべながら、尻尾でも振りそうな勢いで上機嫌な大型犬のように俺の隣を歩いている。再び頭の上にぴょこんと立った犬の耳が、空想じゃなく本当に見えた気がして俺は思わず笑いそうになった。
「私もセレスの隣人だぞ」
「あー、はいはい。そうでしたね、リシャール」
にこやかに微笑みながら、殿下も当然のように俺の左隣をキープした。まるで誰にも譲るつもりはないといった風情で。
夕陽をそのまま閉じ込めたような金髪が眩しすぎて目を細める。王族の血筋というだけでは説明のつかない、何か特別な存在感を放っていた。
尊い――。
思わず、お手々の皴と皴を合わせて「皴合わせ」と拝みたくなる。尚、お手々の節と節を合わせると「節合わせ」になってしまうからやめたほうが良い。よく、妹のアヤちゃんが、深夜にバイト先の嫌な先輩を呪う儀式の最中にやっていたなぁ……、
と、そんなことを思い出しながら、ちらりと二人の顔を見比べる。
右隣のアルチュールは、まだ屈託のない笑顔を浮かべているが、その視線は時折、リシャール殿下のほうへ向かい、一瞬だけ警戒の色を帯びる。
一方の殿下は、余裕の笑みを崩さない。
もう、原作のはかなげで嫋やかなリシャール・ドメーヌ・ル・ワンジェ王太子殿下は何処に行ったんだ!? 戻ってこいよ! こんなの、確実に俺が考える『攻めキャラ』だろうが!? 胸板、厚すぎ! 他人のこと、『雑〇』とか言い出しそうじゃねぇか?!
推しカプ二人に挟まれるのは本望だが、一体、これはどういうことなんだ。
――いや、ここから先は考えたくない。
セレスタンだって、立ち位置は向かって左! 『攻め』キャラのはず……。いや、『はず』ではない。攻めキャラなんだよ。原作本編の美少年リシャール殿下に一方的な恋心を抱く『攻め』の"当て馬"だったんだよ。
……なんで、殿下の胸板があんなに厚いんだ??
「――そこのお二人、さっきからセレスさまとの距離が近すぎませんか?」
唐突に低く、そしてぼやくような声が背後から聞こえた。俺の真後ろ――いつもの“定位置”からだ。
振り返るまでもなく、そこに居たのはナタンだった。彼は俺の幼馴染であり、屋敷では専属の侍従。何も言わずとも常に一歩引いた場所で控え、だが決して俺から目を離さない。今も、眉間にうっすら皺を寄せながら、リシャール殿下とアルチュールを交互に睨んでいる。特にアルチュールを。
「必要以上に距離が近いかと思います。それと、リシャールのセレスさまに対する視線に不必要な圧を感じます」
「お前だけは私のことを『殿下』と呼べ、ナタン。これが王族というものの存在感だよ」
「リっシャール、リシャール、リシャ~~ル!!」
ほんと、この二人、仲良いな……。
よく見ると、殿下の口角がほんのりと持ち上がっていた。その目元も和らいで見える。さっきまでの威風堂々たる王子の仮面に、ほんの僅かに少年らしい素の表情が覗いた気がした。
楽しんでるな、この人。ちょっと貴重な瞬間かもしれない。この微笑も脳の記憶メモリー最前列に保管しておこう。
幼い頃から常に『王子』として扱われ、彼に近づく者の大半は、同年代でも利権や損得勘定で動く者ばかりだった。友人らしい友人は、セレスタンを含め、数少ない。
王族という肩書きに縛られた彼が、ほんの一瞬でもこの学院で『ただの学生』になれるような時間を作れたらいいな――と心から思う。
食堂を出ると、新入生たちのざわめきが更に熱を帯びて広がり、抑えきれない興奮が石畳の回廊に反響する。俺たち四人は自然と肩を並べ、その流れに乗って寮へと足を進めた。
外廊下には午後の風がやわらかく吹き抜け、傾きかけた陽が淡い金色の光となって石畳を照らしていた。
みんな一緒に歩くこの瞬間が、新しい日々の始まりを告げているようで、胸が少しだけ高鳴った。
寮塔は原作の設定よりもやや簡素だったが、古びた印象はまるでなかった。時計塔を備えた正面玄関の壁も床も丁寧に磨き上げられ、隅々まで清潔感が行き届いている。長年使い込まれてきた建物特有の落ち着きは感じられるが、決して、くたびれたという言葉は当てはまらない。
装飾は必要最低限で、絢爛さや豪奢な趣きはない。しかし、その簡素さがかえって居住空間としての品格を引き立てていて、全体としては質実剛健という言葉がしっくりくる造りだった。
「ここは、落ち着く」
隣に立つアルチュールが俺の耳に顔を寄せて小声で話しかけて来た。その率直な感想に、思わず笑みがこぼれた。貴族なのに珍しい感性――と一瞬考えかけて、そういえば彼の生まれ育った城は辺境にあるため、魔物との戦闘を考慮した要塞城だったのを思い出す。
「うん。同じくそう思う。ちゃんと人の手が入ってるって感じで、質素だがホッとするよな」
俺の場合、現代社会で庶民の暮らしをしていたので、むしろコルベール邸よりもこっちのほうが肌に合う。というか、しっくりくるというか、自然体でいられる。
アルチュールが、「だよな」と短く応じると、俺たちはしばし無言で歩みを進めた。
༺ ༒ ༻
第一寮のホールに到着すると、新入生――つまり俺たち一年生――を迎える“グラン・フレール”たちが、整然と並んで待っていた。セレスタンの記憶によれば、大半はサロンで顔を合わせたことのある面々だ。纏っている制服はきちんと整えられ、それぞれに責任ある者の風格が漂っている。
尚、この世界でのフレール制度とは――、
寮生活を支える柱のひとつであり、上級生であるグラン・フレールが、新入生であるプティ・フレール一人一人に割り当てられる仕組みだ。
具体的には、一年生には原則として二年生がグラン・フレールとなる。三年生は卒業に向けた高度な学問や専門的な鍛錬に集中する時期に入るため、この制度には組み込まれていない。
グラン・フレールは、困ったときや知りたいことがあれば、生活面から学業、校内の暗黙のルールに至るまで、幅広く教え、支え、導いてくれる。
原則として、彼らの役割は、あくまで見守りと助言にとどまり、過度に干渉することは禁じられている。しかし、必要とあれば、私的な悩み相談にも応じてくれる上、その際、話した内容が第三者に口外されることは決してなく、プティ・フレールの信頼を損なうような行為は違反とされる。これは学園が正式に定めた“守秘義務”でもあり、制度の根幹を支える重要な約束事でもある。
だからこそ、グラン・フレールは単なる案内役に留まらない。
基本的には同じ建物の上下階に住む者同士でペアが組まれるため、階段を下りればすぐに会える安心感もあり、新しい環境に戸惑う新入生にとって、グラン・フレールの存在は、まさに最初の“拠り所”となるものだ。
第一寮のホールへと足を踏み入れると、待機していたグラン・フレールたちが静かに一列に並び直した。そのきびきびとした動きに、新入生一同が思わず背筋を伸ばす。緊張感が戻ってきた――というより、空気に飲まれた、というのが正しいかもしれない。
直後、整列した二年生の前に一歩進み出たのは、『サヴォワール寮』の寮監ヴィクター・デュボアだった。
年齢は、三十代半ば。背が高く、膂力あふれるがっしりした体格に、無精ひげをたくわえた口元。髪は真っ黒で、短髪がごわつきながら無造作に立っている。派手さはないものの、彫りの深い骨格と、端正な鼻筋が顔全体に凛とした印象を与え、目鼻立ちははっきりしており野性味のある顔立ちだ。眉は濃く、鋭い輪郭の中にも、目元だけは不思議と優しさを残していた。その柔らかな眼差しとは裏腹、軍人のように背筋を伸ばして立つ姿には、ただそこにいるだけで場の空気を引き締めるような不思議な重みがあった。威圧的というよりは、底知れぬ存在感のある人物だ。
今のところ、名前も見た目も、原作通り――。
この世界の基となる『ドメーヌ・ル・ワンジェ王国の薔薇 金の君と黒の騎士』を読んでいた時の俺の『デュボア先生』に対する印象は、無骨でデリカシーに欠けるところがある一方、人当たりは悪くなく、誠実な人物。
よく通る声で話し、笑うときは実に気持ちがいい。しかも、一緒にいると周囲も自然と笑顔になる。飾らない人柄と率直な物言いが場を和ませ、妙に人の懐に入り込む、人たらしの気質が彼にはあった。原作では、そんなデュボアの在り様が、高齢者や子供、動物、使い魔に懐かれる描写を通して表現されていた。
「――ようこそ、サヴォワール寮へ。俺は、寮監のヴィクター・デュボアだ。これからの学園生活、不安も多いだろうが、遠慮はいらん。困ったことがあれば、直属のグラン・フレールでも俺でもいい。遠慮なく頼れ!」デュボアはホール全体に響くようなよく通る低い声で語りかけたあと、口元をほころばせると腹の底から響くような大きな笑い声を上げた。「はははっ、まあ、もう肩の力を抜け。ここはお前たちの家だ」
その一言で、場の空気がほんの少し和らいだ気がした。
どうやら内面も原作通りのようだ。
寮監ヴィクター・デュボアの言葉に、一年生たちの表情が徐々に緩んでいく。張り詰めていた空気がふっと和らぎ、緊張の糸がほぐれたのが目に見えて分かる。
「ゾンブル閣下からも話があったと思うが、夕食までは各自、自室で待機すること。部屋までは君たちのグラン・フレールが案内する」
低く落ち着いた声でそう付け加えると、デュボアは軽く頷き、ゆっくりと半歩下がった。それと同時に、背後で控えていた二年生たちが、まるで呼吸を合わせたかのように足並みも乱さず音もなく前へ進み出る。ぴたりと横一列に並んだ彼らには微塵の歪みもない。その見事な整列に、新入生たちは思わず息を呑んだ。
場に静けさが満ちたそのとき、グラン・フレールたちは、今度はそれぞれのプティ・フレールの前へと一人一人、無駄のない動きで歩み出た。足取りは軽やかでありながら、どこか儀式めいた厳かさがある。
「セレスタン・ギレヌ・コルベール殿」
目の前に立ち止まった相手から落ち着いた声で名を呼ばれた。彼の顔には、セレスタンの記憶の中で見覚えがある。
「……レオ・ド・ヴィルヌーヴ殿」
ヴィルヌーヴ伯爵家の次男。
王城での他国要人歓迎晩餐会、各家の子弟が集う舞踏会やサロン――そのどれかしらの場で彼の姿は視界の端に映っていた。正装姿で談笑する様子、微笑みを絶やさず貴婦人と踊るときの流れるような優雅な身のこなし。礼儀と品位を綺麗に身に纏った好青年としての姿が記憶に残っている。
だが、実際にセレスタンと言葉を交わしたことは、数える程度。挨拶や形式的な短いやりとりだけだ。
今、俺の目の前に立つレオは、あの記憶の中の『よそ行き』の彼とは、どこか雰囲気が違っていた。
真っ直ぐな黒髪は軽く前に流され、目元をかすかに隠している。手入れされた髪だが、どこかラフな印象も与えていた。鋭くも涼やかな深い紫色の瞳がこちらを見つめているが、決して敵意や威圧感はない。むしろ、探るような、少しだけ面白がっているような光が宿っている気がした。
整った顔立ちには貴族らしい品があるが、それ以上に目を引くのは、その内に潜む『何か』だった。整然とした場でも浮かないだけの礼儀を身に着けつつ、いざとなれば、安全を保障する柵を軽々と越えてしまいそうな自由さと奔放さ、そして独特の貫禄を持つ――。それは、まるで鷹揚な猛禽が羽根をたたんで人に化けているのではないかと思える、そんな印象だった。
そもそも原作には、この場面は存在しない。セレスタンは、この第一寮『サヴォワール』所属ではなく、第三寮の『ソルスティス』所属、そして、本来のグラン・フレールは、別の伯爵家の子息で至極真面目な青年だったからだ。
この予定外の配役変更に、思わず息を飲む。
今後の展開が全くもって分からない。知っているはずの物語が、形を変えていく。次に何が起こるのか――?
「本日よりあなたのグラン・フレールを務めることになった、レオ・ド・ヴィルヌーヴです。どうぞよろしく――ロード・コルベール」
折目高い立ち居振る舞いで軽く頭を下げたレオの声は落ち着いていて丁重な印象だったが、その奥底には、どこか掴みどころのない色気と、不意に弾けそうな荒々しさが潜んでいた。まるで、きちんと整えた髪の下で、バラガキがひそかに火花を散らしているような――そんな気配がほんのわずかに漂っている。
なんでだろう……。出るキャラ出るキャラの背後に、片っ端から悉く攻めのオーラが見える気がする。こいつも胸板が厚い。
「荷物はすでに俺が部屋に運んだ。案内いたしますよ、ロード・コルベール」
そう言ったレオに俺は軽く片眉を上げて見せた。丁寧過ぎる呼び方は、やはり違和感がある。
「ただの新入生として接してくれませんか。肩書きは、学院では抜きにして欲しい」
言い切る俺に、彼はほんの僅かに驚いた顔をして間を置いてから口角を持ち上げ、軽く含みのある笑みを浮かべた。
「分かった。君がそう望むなら、そうしよう」
レオと並んで歩き出すと、俺の周囲でも他の新入生たちが、それぞれのグラン・フレールとペアになって動き始めていた。
緊張で顔をこわばらせていた一年生たちが、少しずつ表情を解いている。
話しかけるグラン・フレールの語り口が柔らかいのか、肩をすくめながらも小さく笑う者、頷きながら歩調を合わせる者――反応はそれぞれだったが、いずれもこの瞬間から始まる『寮生活』に心を揺らしているのが分かった。
俺の隣を歩くレオは、そんなことをよそに悠然としていた。背筋はまっすぐ、歩幅も無理がなく、要所で俺に気を配る。まるで他人に見せるための所作を体に叩き込まれたような歩き方だった。
だが、そんな空気の中でも、背後から――というより、少し離れた数方向から妙な熱の籠った視線が突き刺さってくるのを、俺はしっかりと感じていた。
刺すような鋭さを帯びた目線。振り返らなくても分かる。これはアルチュールだ。どうやら彼も、グラン・フレールと共に寮室へ向かっている最中のようだったが、その足をほんの一瞬だけ止め、こちらを見ていた気配がした。
続いて、ずっしりと重たい視線。堂々としていながら、妙に棘を含んでいる。これは殿下――リシャール王太子。王族特有の気配に気付かないふりをしてやるのも、正直、ちょっと疲れる。目を合わせなくても伝わってくる不機嫌さに、俺はこっそり溜息を吐きたくなった。
極めつけは、じんわり胸に残るような、感情の混ざった視線。ナタン。彼もまた、自分のグラン・フレールと一緒にいるはずだが、ふとした瞬間にこちらを見たのだろう。目が合ったわけでもないのに、それはやけに刺さる。
俺は顔を向けることなく、気配だけで三人の居場所を探りながら、表情には一切出さないよう努めた。周囲の新入生たちは、そんなこと気付きもしないまま、自分のグラン・フレールとの会話に一生懸命だ。
レオがふと、こちらに目を向ける。
「どうかしたか?」
「いや……、何でもありません」
軽く首を振り、そのまま歩を進める。視線なんかに気を取られていられない。――俺の部屋は、もうすぐそこだ。
階段をのぼりきると、静かな気配に包まれた長い廊下が目の前に現れた。
新入生の個室は三階、二年生であるグラン・フレールたちの部屋はその真下の二階、三年生の部屋はさらにその下、一階にある。
この階には、301号室から320号室までの扉が整然と並び、まるでどれもが同じ重みを持って未来を待っているようだった。
中庭に面した各々の窓からは、傾きかけた夕陽が斜めに差し込み床に影を落とす。空気は澄んでいて、風に乗って微かな薬草の香りが漂って来る。
その時、ふと「君にはチュテレールが三人も居るんだな」と、レオが不意に口を開いた。
俺は思わず真横を歩くレオの顔を盗み見た。彼はさっきの、殿下とアルチュール、ナタンたち三人の視線に気付いていたようだ。
「チュテレールではなく、友人です」
っていうか、チュテレールってなんだよ。俺、成人した社会人だぞ? おとぎ話に出て来るか弱き姫じゃないって!
俺の返答に、「ふうん」と応えたあと、レオは立ち止まらず、ゆっくりと歩きながらちらりとこちらに視線を投げた。その目元には、言葉にしない微かな笑みが浮かんでいる。まるで、何か面白い遊びを見つけた子供のような、いや、それよりももう少し大人びた余裕と好奇心が入り混じっていた。
「『金の君』と『銀の君』が入学すると聞いて、学院内は昨年の末ごろから少し浮足立っていたんだ。どの寮に来るか、誰がグラン・フレールに選ばれるか? 小さな賭けをしていた者もいたくらいだ」
廊下を三分の一ほど進んだところで、レオは立ち止まり、扉を指さした。
310と刻まれた真鍮のプレートが、夕陽に照らされてやわらかく光っている。
「担当するプティ・フレールが誰なのか、俺たちに正式に知らされたのは今日。君たちが入学式に出ていたころだ」
そう言いながら、レオはジャケットのポケットから鍵と封筒を取り出し、中の紙を俺に見せた。
| レオ・ド・ヴィルヌーヴ
| プティ・フレール:セレスタン・ギレヌ・コルベール
| 所属寮:第一寮・サヴォワール寮(310号室)
「担当になれて光栄だ。ようこそ、『サヴォワール』へ。310号室、今日からここが君の部屋だ。鍵をどうぞ、セレスタン君」
「呼び捨てでいいです。セレスタンか、セレスで」
レオは少し目を見開いたあと、ふっと笑って首を傾げた。
「じゃあ、俺のこともレオでいい……。ああ、もう堅苦しいのは嫌いだ。普段通りにしていいか?」
「……今までのイメージと違いますね」
「それは俺の台詞。君のことはもっと杓子定規な優等生で、礼儀作法に厳しい堅物だと思っていたんだけどな」
中身、異世界から来たチャランポランな別人です……、とは言えない。
「セレス……、でいいんだよな。ところで入学前に事故にあったと聞いている。無理に張り切ったりしないように」
レオの声は静かだったが、気遣いの色が滲んでいた。形式的なものではなく、個として向き合おうとしているところに好感が持てる。
「……ありがとう。気をつけます」
「時計塔の鐘が六度響けば、食堂に向かう時間だ。それまで部屋でゆっくりしていてくれ。何かあったら真下の210号室をノックすればいい。床ドンでもいいぞ」
彼は冗談めかした口調でそう言い、「じゃあ、また食堂で」と、俺に鍵を渡してから軽く片手を上げ、踵を返して廊下を戻っていった。
その背中が遠ざかるのと入れ替わるように、アルチュールが彼のグラン・フレールと並んでこちらへと向かって歩いて来る。淡い褐色の肌をした長身のグラン・フレールは、肩まで届く銀灰の髪を後ろで束ね、整った顔立ちと落ち着いた物腰を備えた人物で、アルチュールと並ぶ姿は、まるで一枚の絵画のように華やかだっだ。
原作でも未見、セレスタンの記憶の中にも存在していない。完全な新キャラだ。十中八九、留学生だろう。
一瞬、アルチュールはすれ違いざまにレオを一瞥し、それから俺に目を向けると小さく微笑み、声に出さずに唇の動きだけで「あとで行く」と告げてきた。
いや、来なくていいし。出来れば、リシャール殿下の部屋でも訪ねたらどだろうか? ――と、腐男子は思う。
レオの背中が角を曲がって見えなくなるのを見届けてから、俺は扉に鍵を差し込んだ。
カチリ、と小気味よい音を立てて鍵が回る。扉を押し開けると、ふわりとやさしい香りが鼻先をかすめた。主張しすぎない、軽やかな花の香り?
埃っぽさは一切なく、空気は清々しく、部屋は綺麗に整えられている。
目を向けると、重厚なデスクの上に小さなサシェが置かれていた。飾り気のない薄い布袋に詰められた乾いた花。ほのかな魔力の気配――、
レオだな。このサリトゥの残余から彼の攻めオーラと同じ波動を感じる。
サシェの下には、丁寧な筆跡で短いメモが添えられていた。
――頭を打ったと聞いていたから、少しでもリラックスできればと思って。中庭の薬草を使い、昼休みの時間に急遽作ってみた。要らなかったら捨ててくれ。
思わず胸がきゅっとなった。
……クッソ、イケメンかよ。
ちょい悪系で見た目がいいだけじゃねぇのかよ。さりげない気配りに、距離の詰め方も自然。これで無自覚なんだったら、天性のタラシだ。
いやもう、俺が女だったら完全に落ちてたわ。
なんか、今ちょっとときめいてしまった自分が悔しい。
レオ・ド・ヴィルヌーヴ、恐るべし。
「アンセートル・ベネトラクト・アコーデ」
「アンセートル・ベネトラクト・アコーデ……」
樹液の入った小瓶を手にした大司教たちの唱和が再び始まる。
さっきまでリシャール殿下やナタン、アルチュールのデピスタージュを傍から見ていただけだったから分からなかったが、体験してみると先ずは手に、そこから脳に、そして脊髄から足の先まで隙間なく力が漲るような感覚に圧倒された。
これが魔力の流れ――。この世界の言葉では、『サリトゥ』と呼ぶ。
まるで体中のあちこちに仕掛けられていた見えないリミッターが一つ残らず消失し、重力からも解放されたたかのようだ。いや、持っていた能力が底上げされたと言った方がいいのか? 兎に角、全身が軽い。
しばらくすると、俺の両掌に、ローリエの木を伴った見事な『ベネン』が浮かび上がった。外枠の細い円は、銀灰色で縁取られ、鈍い輝きを放っている。
なるほど、美しい。確かに、これは誰かに見せたくなるな。
ついさっき、アルチュールが上機嫌で自分のベネンを見せて来た顔を思い出す。濡れた宝石のような瞳が印象的な、原作ではお目にかかったことのないレアな推しショットだった。脳の記憶メモリーの最前列に保管しておこう。
一連の義が終わると、俺を取り囲んでいた幻影の柱が強風に攫われる浜辺の砂城のように崩れ、跡形もなく消えた。
中々、感慨深い。
ほんの一瞬、余韻に浸ったあと、直ぐ横で未だ尻もちをついていた少女漫画風の修道士に手を差し伸べる。
「ありがとうございます。ロード・コルベール」
修道士は遠慮がちに俺の手を取り、左足に体重をかけようとして眉根を寄せ、かばうようにして立ち上がった。
「痛めたのか?」
俺は腰を下ろし、床に片膝を付いてしゃがむと修道士の左足首に手を添えた。確実にベネンの働きだろう、サリトゥの流れに乱れがあることがありありと分かる――。というか、見える。それは実際に視認しているわけではないが、脳内にイメージとして浮かび上がって来る感覚。
「だ、大丈夫です」
「いや、大丈夫じゃないだろ」
回復魔法の呪文なら知っている。もしも魔法に関する事象が改変されず原作通りだとしたら、この世界で使われている呪文、全てを俺は覚えている。ファンサイトのホームページまで作って新刊が出る度にこつこつと用語集をまとめ上げたんだから。
先ずは、自らの左手首に右手を当て、微量の魔力を流してみた。いきなり他人で試すわけにはいかない。
「トゥレイト……」
温かい波動が伝わって来る。よし、これなら何も問題はなさそうだ。
「もしも違和感や不具合があれば直ぐに教えてくれ」そう言ってから、俺は再び修道士の足首に手を置いて治癒の呪文を唱えた。「トゥレイト」
修道士の膝から踝までのサリトゥの歪みが瞬く間に修正されていく。
あとは――「アレンテドゥラ」。 これで痛みも消えるはず……。
顔を上げると、口をぽかんと開けて硬直する修道士と目が合った。
「まだ痛いか?」
「い、いえ、全く! 痛みが嘘のように消えています!」
「それは良かった」
「ありがとうございます、『銀の君』、あっ、ロード・コルベール」
修道士の頬は微かに紅潮し、はにかんだような少し読み取りにくい笑みを唇に浮かべていた。
「凄いな、セレスは。もう回復魔法が使えるのか……?」
いつからそこにいたのか、背後に立つアルチュールが膝に両手を置いて腰をかがめながら俺の手元をのぞき込んでそう言った。
ぐるりと周囲を見渡すと、この場に居る全員の視線が俺に注がれている。
浄化系魔法は相手側に注ぎ込む自身のサリトゥの調整が難しく、ただ呪文を知っているだけでは的確に、尚且つ思う通りに扱えるわけではない。
それを例え傷を負った相手の状態が重症ではなく打ち身や捻挫であれ、加護の魔法陣が掌に付与された直後にやってしまった。
怪我をした相手を癒したいと思った気持ちが一番大きかったことは嘘偽りのない本心だが……、魔法への好奇心がそこに無かったかと聞かれれば――、
否定はできない。
「口伝や、いくらかの文献では、『リュミエール』は、それだけで能力を発するが、他の持っている能力を安定、増幅、躍進もさせるといわれている」
声がした方向を向いて立ち上がると、若い夏の香りがしそうな爽やかな笑みを浮かべたリシャール殿下がこちらに向かって歩いて来るところだった。ナタンも居る。
「殿下」
「リシャールと呼べ、セレス。でないと私もお前を『麗しき銀の君』とか、『憧れのロード・コルベール』と呼ぶぞ」
「やめて下さい!」
即座の俺の拒否反応に、いたずらっぽく片眉を上げて殿下がくすりと笑った。やんごとなき相手、しかも推しから恭しく扱われるだなんて、尻がこそばゆいにもほどがある。
ってゆーか、『麗しき』とか『憧れの』って何なんだよ?? それ、『金の君』こと、あなた様を表現する形容詞だろう!?
「『リュミエール』に属す者になんて、先ず、今まで会ったことがないどころか、我が王国に伝わる数多き文献にも記述は少なく、色々と分からない部分が多過ぎる。今後は常にセレスの側に居て観察させてもらおうかな」
いや、殿下にそんなことをする時間があるのなら、俺なんかほっといてアルチュールと行動を共にしててくれ、頼むから。間近でそれが見たいんだよ、お願いします。
「いいえ、側に居るのはこの私です。今までも、これからも。現在、侍従としては休職中ですが、なんといってもセレスさま……、セレスは私の主ですから」
口元を弓形にゆるませてナタンが言った。
「前々から思っていたが、セレスに友達が少ないのはナタン、お前のせいじゃないか? サロンでもセレスが私だけではなく他の誰かと話していると直ぐに間に入って来るし、「お時間ですセレスさま」とか言って、早々と帰宅を促すし」
「そうですか? でも殿下の場合は仕方がないと思いますよ。異国から来られた要人が目の前に居ても、ほったらかしにしてセレスさ……、セレスと二人で話し込もうとするからです」
「殿下じゃない。ここではリシャールと呼べと、……いや、お前だけ私のことをリシャールと呼び捨てにするのを許さん」
「なんでですか、リシャール、リシャール、リシャール!!」
何か……この二人、仲良いな……、と思って眺めていたら――、
「あの二人、仲良いな」
隣でアルチュールが同じ事を考えていた。
「うん。原作にはこんなシーンは無かったから、新鮮だわ……」
「……原作?」
「あ、いや、その……」
やばい。
どう誤魔化そうかと一瞬、頭を捻っていると、
「なあ、セレスは友達が少ないのか?」
どうやらアルチュールは俺が口を滑らせた『原作』という言葉に関して何も関心を持たなかったようだ。寧ろ、先ほど殿下が話した内容に興味を示している。
「まあ……、友達は多くはないかな」
「そんな風には見えないけど」
「そうか?」
「俺は……、セレスが初めての友達だと勝手に思っている」
えっ!?
俺が弾かれたかのように隣に視線を向けると、居心地が悪そうな子供のような顔をしたアルチュールがそこに居た。微かに耳が赤い。
彼がどうやって辺境のシルエット領で育ったか――勿論、俺はそれも知っている。
文武共に優秀な父と兄に憧れ、ずっとその背中を追い続け、物心ついたころには友達と遊ぶよりも数人の護衛とオオカミ犬を伴い、近年は護衛を伴わず、日々、人と魔族との境界地に現れる小物とはいえ魔物の退治をしながら鍛錬を続けて来た。
友達を作ろうにも、アルチュールと対等に『遊ぶ』ことが出来るような子供は家臣の家にも居なかった。領民の子なら猶更だ。ただでさえ普通の子供には魔力がない。駆けっこ、剣術ごっこ――大人顔負けの相手と遊ぶだなんて、負け続けるのは退屈な上に面白くない。下手したら怪我をすることになる。
「迷惑……、だよな? 俺、口が悪いし、なんといっても礼儀を知らないし」
不安を誤魔化すためか、頭を傾げてちらりとこちらを見たアルチュールに、それだけで胸が締め付けられるように痛くなった。
うーん、アルチュールは、女性がよく言う『守ってあげたくなるような男』……、というキャラではなかったはずなんだけどな。まあ、俺が萌えるから良いか。
「迷惑なわけないだろう」
たたみかけるように俺は言った。
推しから友達認定されるだなんて、嬉しすぎてプルプル震えるじゃないか。今、俺、チワワだぞ。
「本当に迷惑ではないのか?」
「迷惑なわけない! 殿下が言うように俺は友達が少ないんだ。アルチュールが友達になってくれたら嬉しいに決まってる!」
「じゃあ、俺もセレスの側に居れるってことだよな?」
「当たり前だ!」
と即答してから直ぐに我に返る。
殿下もアルチュールも、ついでにナタンも俺の側に居たら、どうやって俺は、アル×リシャの推しが二人っきりで人目をはばかりながら愛をはぐくんで行く行程をこっそりと観察すればいいんだ??
いや、マジこれどうすべきなんだよ!?
༺ ༒ ༻
一旦、食堂に戻り、全員のデピスタージュが終了するのをそこで待つ。
本来なら入寮発表が行われるまでの退屈で仕方がない長い待ち時間に、衛生管理の行き届いた軽食と飲み物がビュッフェスタイルで自由に好きなだけ摂取出来たのは、どの生徒たちにとっても大変有難かった。辺境の貴族子息や留学生たちが、何となく周囲に馴染みつつあるのもこの心遣いと雰囲気のおかげだろう。見ず知らずの者同士が同じ釜の飯を食べながら次第に打ち解けていく――そういう光景が、今まさに広がっている。
異世界とはいえ原作によると、時代設定の参考は一八〇〇年代のフランス。
しかし、これはコルベール家でも感じたことだが、公衆衛生や食事の品質、電気はないが必要最低限のインフラの質は現代の日本とさほど変わらない。
水属性の魔法陣と浄化魔法を使って整備された上下水道は、この王都では貴族以外の家にまで行き届いているし、街中には火属性の魔法陣が描かれた街灯が立ち並び、夜も明るい。
さしずめ、無くて残念なのはスマホやインターネット、ゲームぐらいのものかもしれないな。
――と、転生前の世界のことをぼんやりと思い出していると、やや低めの落ち着いた声が食堂に響いた。
「諸君、この度は入学おめでとう。そして、お待ちかねの入寮発表の時間だ」
全員の注目を一身に浴びながら、壇上に置かれたコフルの上で喋り出したのは、一羽のコルネイユだった。
艶やかな漆黒の翼をゆるやかに畳み、眼に暗い琥珀のような光を湛えて、その胸を誇らしげに張りながら、「尚、我が名はゾンブル。ゾンブル閣下である」と彼は名乗った。
よし、先ずは原作通りに進んでいる。
留学生たちの間に微かなざわめきが巻き起こる。しかし王国の者は使い魔や言葉を操る動物を見慣れているせいで、特に驚いた様子はない。
「いよいよですね、セレスさ……、セレス。同じ寮になることを心より願っています」
隣に座るナタンが、興奮を隠しきれない様子で小声で話しかけて来た。頬はほころび、目はきらきらと輝いている。
余談にはなるが、この世界における『寮』とは、日本の学校制度で言うところの『クラス』に近しい役割を担っている。
一度割り当てられた寮が変更されることは、三年間の在学期間を通してほぼない。たとえ他寮への移動を願い出たとしても、それが認められるのは極めて明確かつ正当な理由がある場合に限られる。
寮塔は本校舎の東側、聖堂や食堂とともに、外廊下の回廊によって結ばれている。建物は四棟。いずれも長方形で、その配置はひし形を描くように設計されていた。
一棟は職員寮だが、残る三棟が学生たちの住まい──第一寮『サヴォワール寮』、第二寮『レスポワール寮』、第三寮『ソルスティス寮』。それらの建物に囲まれた中庭には、回復薬ポーションの素材となる薬草が整然と植えられ、中央には白いドーム型のガゼボが静かに佇んでいる。
この学び舎において、生徒は入学と同時にいずれかの寮へと振り分けられ、そこで暮らし、学び、友情や軋轢のすべてを経験することとなる。
「なあナタン、セレスって呼びにくいなら、もう好きに呼んでもいいぞ。あと、お前とは別の寮がいいと俺は思っている」
「な、なんでですか、セレスさま!?」
お前が側に居ると、推し活がはかどらないからだよ――とは口が裂けても言えない。
壇上では、ゾンブル閣下がくるりと翼を広げて向きを変えた。いよいよ結果が発表される。食堂の空気がぴんと張り詰めた。
「アペリオ、コフル!! オゥヴァ・ヴォランティス!」
ゾンブル閣下の声が高らかに天井を打ったと同時に、箱の表面に刻まれた文様が光り出し、重厚そうな蓋がひとりでに、そして静かに、しかし確かな気配をもって開き始める。まるで意志を持っているかのように。そして次に、ぼんやりとした光を纏った何通もの小さな封筒が中から一斉に飛び出して生徒全員の目の前に落ちて行く。
圧巻の光景。このシーン、滅茶苦茶好きだったんだよ。体験出来るだなんて、感動もひとしおだ!
しばらくの静寂のあと、あちらこちらから紙がテーブルに落ちる小さな音と共に、感嘆の息が漏れ聞こえてきた。
俺の前にも一通、月光を思わせる柔らかな手すき紙に、深紅の封蝋が凛として咲く一輪の薔薇のようにあしらわれた封筒が着地する。そこには、王家の紋章とゼコールリッツ学院のシンボル、二つの印が並んでいた。
指先で慎重に封を解く。すると、中から一枚の薄紙が静かに滑り出し、その紙面には名前と共に、これからの日々を過ごすことになる寮の名が凛とした筆致で刻まれていた。
| セレスタン・ギレヌ・コルベール
| 所属寮:第一寮・サヴォワール寮(310号室)
| 寮監:ヴィクター・デュボア
ナタンが身を乗り出して自分の封筒を開封する様子を横目で見つつ、俺は、改めて記された文字に視線を落とした。
「サヴォワール……」
原作本編のセレスタン・ギレヌ・コルベールが所属していたのは、第三寮の『ソルスティス寮』だ。
そして、アルチュール・ド・シルエットとリシャール・ドメーヌ・ル・ワンジェ王太子殿下が所属していたのが第一寮の『サヴォワール寮』――。
ここでまた原作とは異なる展開が現れてしまった。
そう思いながらふと顔を上げると……、
「セレスもサヴォワール寮なのか!?」
嬉しそうに声を上げたアルチュールが、ナタンの背後から俺の視界に飛び込んで来た。「セレスも」ということは、彼自身がすでにサヴォワール寮だということは間違いない。
「俺は、309号室だ。セレスは?」
おいおい、推しの隣かよ。
「310号室だ」
「よしっ!」
何故かガッツポーズを取るアルチュールの横で、リシャール殿下が封筒の中に入っていた紙をこちらに向け、ひらひらと揺らしながら満面の笑みを浮かべている。
「私もサヴォワール、311号室だ」
なんてこった。推しカプに挟まれてしまった……。
ちなみに今の座席の配置は、俺の右隣にナタン、さらにその隣にアルチュール、そしてリシャール。何故か食堂に戻った直後、俺以外の三人がジャンケンで決めていた。意味が分からない。
「はいはい、リシャールもサヴォワールですか」
思わず肩をすくめて呟くと、殿下は「当然だ」と言わんばかりに胸を張って見せた。その仕草がいちいち様になっている。
流石『金の君』。マジで眩しい。
ナタンも封を開け終えたらしく、「やった!」と小さく声を上げた。
「私もサヴォワールです! 320号室」
微妙に遠いな。
しかし、これで『アル×リシャ』を近接距離でこっそりと一人、隠れて見守りつつ萌えを補給するという俺の推し活環境は崩壊したと言っても過言ではない。自分の存在を一切主張することなく、ただ影になり、ある時は路傍の草となり、静かに音を立てず傍で見つめる。耳を澄まし、目を凝らし、二人が紡ぐ何気ない瞬間に心を満たす――。
それが、こんな「俺たち仲良し四人組~」みたいになってしまったら、叶わねぇじゃねぇか!
ああ、このままだと腐脳が渇いて干からびそうだ。
この寮分け、魔力特性の相性か、学院側の戦略的配慮か何かだろうな。想定外すぎるセレスタンのチート能力に関しては、この際、無視しても、基本的な魔力量の多いこの四人で『風火水土』全部揃ってるし……。
食堂内では、生徒たちの喜びや戸惑いが錯綜していた。封筒を開けて友人同士で握手する者、相性の悪い誰かと一緒になってしまったのか予想外の結果にぼう然とする者――。
そんな中、壇上のゾンブル閣下が再び声を張る。
「では諸君、君たちの荷物は既に寮監の指示のもと、二年生が部屋に運び込んでくれている。自分が入居する寮と部屋番号を確認の上、自室で夕食の知らせがあるまで待機のこと。では、解散!」
ゾンブル閣下の号令が響き渡ると、それまでの緊張感が嘘のように一気にほどけ、生徒たちの間に活気が溢れ出した。皆、それぞれの封筒を大事そうに握りしめながら、歓声を上げたり談笑したりと、三々五々、にわかに賑やかになった食堂をあとにして行く。その人波に、俺たちも紛れ込んだ。
「セレスと同じ寮になるなんて、ホッとした。これからが楽しみだ」
席を立つとすぐに俺の右隣に滑り込むようにしてやって来たアルチュールが、柔らかい笑みを浮かべながら声を弾ませた。まるで遠足に胸を躍らせる子供のようだ。気のせいではなく、その言葉の端々には、俺との距離が縮まることへの明らかな喜びが感じ取れる。
――余程、初めて出来た友達の存在が嬉しいのか……?
「しかも、お隣さんだな。今日から宜しくアルチュール」
原作では、鋭利な視線の奥に決して揺るがぬ芯を秘めた騎士――それが、アルチュール・ド・シルエットという男だったはず。
けれど今の彼は、無防備な笑みを浮かべながら、尻尾でも振りそうな勢いで上機嫌な大型犬のように俺の隣を歩いている。再び頭の上にぴょこんと立った犬の耳が、空想じゃなく本当に見えた気がして俺は思わず笑いそうになった。
「私もセレスの隣人だぞ」
「あー、はいはい。そうでしたね、リシャール」
にこやかに微笑みながら、殿下も当然のように俺の左隣をキープした。まるで誰にも譲るつもりはないといった風情で。
夕陽をそのまま閉じ込めたような金髪が眩しすぎて目を細める。王族の血筋というだけでは説明のつかない、何か特別な存在感を放っていた。
尊い――。
思わず、お手々の皴と皴を合わせて「皴合わせ」と拝みたくなる。尚、お手々の節と節を合わせると「節合わせ」になってしまうからやめたほうが良い。よく、妹のアヤちゃんが、深夜にバイト先の嫌な先輩を呪う儀式の最中にやっていたなぁ……、
と、そんなことを思い出しながら、ちらりと二人の顔を見比べる。
右隣のアルチュールは、まだ屈託のない笑顔を浮かべているが、その視線は時折、リシャール殿下のほうへ向かい、一瞬だけ警戒の色を帯びる。
一方の殿下は、余裕の笑みを崩さない。
もう、原作のはかなげで嫋やかなリシャール・ドメーヌ・ル・ワンジェ王太子殿下は何処に行ったんだ!? 戻ってこいよ! こんなの、確実に俺が考える『攻めキャラ』だろうが!? 胸板、厚すぎ! 他人のこと、『雑〇』とか言い出しそうじゃねぇか?!
推しカプ二人に挟まれるのは本望だが、一体、これはどういうことなんだ。
――いや、ここから先は考えたくない。
セレスタンだって、立ち位置は向かって左! 『攻め』キャラのはず……。いや、『はず』ではない。攻めキャラなんだよ。原作本編の美少年リシャール殿下に一方的な恋心を抱く『攻め』の"当て馬"だったんだよ。
……なんで、殿下の胸板があんなに厚いんだ??
「――そこのお二人、さっきからセレスさまとの距離が近すぎませんか?」
唐突に低く、そしてぼやくような声が背後から聞こえた。俺の真後ろ――いつもの“定位置”からだ。
振り返るまでもなく、そこに居たのはナタンだった。彼は俺の幼馴染であり、屋敷では専属の侍従。何も言わずとも常に一歩引いた場所で控え、だが決して俺から目を離さない。今も、眉間にうっすら皺を寄せながら、リシャール殿下とアルチュールを交互に睨んでいる。特にアルチュールを。
「必要以上に距離が近いかと思います。それと、リシャールのセレスさまに対する視線に不必要な圧を感じます」
「お前だけは私のことを『殿下』と呼べ、ナタン。これが王族というものの存在感だよ」
「リっシャール、リシャール、リシャ~~ル!!」
ほんと、この二人、仲良いな……。
よく見ると、殿下の口角がほんのりと持ち上がっていた。その目元も和らいで見える。さっきまでの威風堂々たる王子の仮面に、ほんの僅かに少年らしい素の表情が覗いた気がした。
楽しんでるな、この人。ちょっと貴重な瞬間かもしれない。この微笑も脳の記憶メモリー最前列に保管しておこう。
幼い頃から常に『王子』として扱われ、彼に近づく者の大半は、同年代でも利権や損得勘定で動く者ばかりだった。友人らしい友人は、セレスタンを含め、数少ない。
王族という肩書きに縛られた彼が、ほんの一瞬でもこの学院で『ただの学生』になれるような時間を作れたらいいな――と心から思う。
食堂を出ると、新入生たちのざわめきが更に熱を帯びて広がり、抑えきれない興奮が石畳の回廊に反響する。俺たち四人は自然と肩を並べ、その流れに乗って寮へと足を進めた。
外廊下には午後の風がやわらかく吹き抜け、傾きかけた陽が淡い金色の光となって石畳を照らしていた。
みんな一緒に歩くこの瞬間が、新しい日々の始まりを告げているようで、胸が少しだけ高鳴った。
寮塔は原作の設定よりもやや簡素だったが、古びた印象はまるでなかった。時計塔を備えた正面玄関の壁も床も丁寧に磨き上げられ、隅々まで清潔感が行き届いている。長年使い込まれてきた建物特有の落ち着きは感じられるが、決して、くたびれたという言葉は当てはまらない。
装飾は必要最低限で、絢爛さや豪奢な趣きはない。しかし、その簡素さがかえって居住空間としての品格を引き立てていて、全体としては質実剛健という言葉がしっくりくる造りだった。
「ここは、落ち着く」
隣に立つアルチュールが俺の耳に顔を寄せて小声で話しかけて来た。その率直な感想に、思わず笑みがこぼれた。貴族なのに珍しい感性――と一瞬考えかけて、そういえば彼の生まれ育った城は辺境にあるため、魔物との戦闘を考慮した要塞城だったのを思い出す。
「うん。同じくそう思う。ちゃんと人の手が入ってるって感じで、質素だがホッとするよな」
俺の場合、現代社会で庶民の暮らしをしていたので、むしろコルベール邸よりもこっちのほうが肌に合う。というか、しっくりくるというか、自然体でいられる。
アルチュールが、「だよな」と短く応じると、俺たちはしばし無言で歩みを進めた。
༺ ༒ ༻
第一寮のホールに到着すると、新入生――つまり俺たち一年生――を迎える“グラン・フレール”たちが、整然と並んで待っていた。セレスタンの記憶によれば、大半はサロンで顔を合わせたことのある面々だ。纏っている制服はきちんと整えられ、それぞれに責任ある者の風格が漂っている。
尚、この世界でのフレール制度とは――、
寮生活を支える柱のひとつであり、上級生であるグラン・フレールが、新入生であるプティ・フレール一人一人に割り当てられる仕組みだ。
具体的には、一年生には原則として二年生がグラン・フレールとなる。三年生は卒業に向けた高度な学問や専門的な鍛錬に集中する時期に入るため、この制度には組み込まれていない。
グラン・フレールは、困ったときや知りたいことがあれば、生活面から学業、校内の暗黙のルールに至るまで、幅広く教え、支え、導いてくれる。
原則として、彼らの役割は、あくまで見守りと助言にとどまり、過度に干渉することは禁じられている。しかし、必要とあれば、私的な悩み相談にも応じてくれる上、その際、話した内容が第三者に口外されることは決してなく、プティ・フレールの信頼を損なうような行為は違反とされる。これは学園が正式に定めた“守秘義務”でもあり、制度の根幹を支える重要な約束事でもある。
だからこそ、グラン・フレールは単なる案内役に留まらない。
基本的には同じ建物の上下階に住む者同士でペアが組まれるため、階段を下りればすぐに会える安心感もあり、新しい環境に戸惑う新入生にとって、グラン・フレールの存在は、まさに最初の“拠り所”となるものだ。
第一寮のホールへと足を踏み入れると、待機していたグラン・フレールたちが静かに一列に並び直した。そのきびきびとした動きに、新入生一同が思わず背筋を伸ばす。緊張感が戻ってきた――というより、空気に飲まれた、というのが正しいかもしれない。
直後、整列した二年生の前に一歩進み出たのは、『サヴォワール寮』の寮監ヴィクター・デュボアだった。
年齢は、三十代半ば。背が高く、膂力あふれるがっしりした体格に、無精ひげをたくわえた口元。髪は真っ黒で、短髪がごわつきながら無造作に立っている。派手さはないものの、彫りの深い骨格と、端正な鼻筋が顔全体に凛とした印象を与え、目鼻立ちははっきりしており野性味のある顔立ちだ。眉は濃く、鋭い輪郭の中にも、目元だけは不思議と優しさを残していた。その柔らかな眼差しとは裏腹、軍人のように背筋を伸ばして立つ姿には、ただそこにいるだけで場の空気を引き締めるような不思議な重みがあった。威圧的というよりは、底知れぬ存在感のある人物だ。
今のところ、名前も見た目も、原作通り――。
この世界の基となる『ドメーヌ・ル・ワンジェ王国の薔薇 金の君と黒の騎士』を読んでいた時の俺の『デュボア先生』に対する印象は、無骨でデリカシーに欠けるところがある一方、人当たりは悪くなく、誠実な人物。
よく通る声で話し、笑うときは実に気持ちがいい。しかも、一緒にいると周囲も自然と笑顔になる。飾らない人柄と率直な物言いが場を和ませ、妙に人の懐に入り込む、人たらしの気質が彼にはあった。原作では、そんなデュボアの在り様が、高齢者や子供、動物、使い魔に懐かれる描写を通して表現されていた。
「――ようこそ、サヴォワール寮へ。俺は、寮監のヴィクター・デュボアだ。これからの学園生活、不安も多いだろうが、遠慮はいらん。困ったことがあれば、直属のグラン・フレールでも俺でもいい。遠慮なく頼れ!」デュボアはホール全体に響くようなよく通る低い声で語りかけたあと、口元をほころばせると腹の底から響くような大きな笑い声を上げた。「はははっ、まあ、もう肩の力を抜け。ここはお前たちの家だ」
その一言で、場の空気がほんの少し和らいだ気がした。
どうやら内面も原作通りのようだ。
寮監ヴィクター・デュボアの言葉に、一年生たちの表情が徐々に緩んでいく。張り詰めていた空気がふっと和らぎ、緊張の糸がほぐれたのが目に見えて分かる。
「ゾンブル閣下からも話があったと思うが、夕食までは各自、自室で待機すること。部屋までは君たちのグラン・フレールが案内する」
低く落ち着いた声でそう付け加えると、デュボアは軽く頷き、ゆっくりと半歩下がった。それと同時に、背後で控えていた二年生たちが、まるで呼吸を合わせたかのように足並みも乱さず音もなく前へ進み出る。ぴたりと横一列に並んだ彼らには微塵の歪みもない。その見事な整列に、新入生たちは思わず息を呑んだ。
場に静けさが満ちたそのとき、グラン・フレールたちは、今度はそれぞれのプティ・フレールの前へと一人一人、無駄のない動きで歩み出た。足取りは軽やかでありながら、どこか儀式めいた厳かさがある。
「セレスタン・ギレヌ・コルベール殿」
目の前に立ち止まった相手から落ち着いた声で名を呼ばれた。彼の顔には、セレスタンの記憶の中で見覚えがある。
「……レオ・ド・ヴィルヌーヴ殿」
ヴィルヌーヴ伯爵家の次男。
王城での他国要人歓迎晩餐会、各家の子弟が集う舞踏会やサロン――そのどれかしらの場で彼の姿は視界の端に映っていた。正装姿で談笑する様子、微笑みを絶やさず貴婦人と踊るときの流れるような優雅な身のこなし。礼儀と品位を綺麗に身に纏った好青年としての姿が記憶に残っている。
だが、実際にセレスタンと言葉を交わしたことは、数える程度。挨拶や形式的な短いやりとりだけだ。
今、俺の目の前に立つレオは、あの記憶の中の『よそ行き』の彼とは、どこか雰囲気が違っていた。
真っ直ぐな黒髪は軽く前に流され、目元をかすかに隠している。手入れされた髪だが、どこかラフな印象も与えていた。鋭くも涼やかな深い紫色の瞳がこちらを見つめているが、決して敵意や威圧感はない。むしろ、探るような、少しだけ面白がっているような光が宿っている気がした。
整った顔立ちには貴族らしい品があるが、それ以上に目を引くのは、その内に潜む『何か』だった。整然とした場でも浮かないだけの礼儀を身に着けつつ、いざとなれば、安全を保障する柵を軽々と越えてしまいそうな自由さと奔放さ、そして独特の貫禄を持つ――。それは、まるで鷹揚な猛禽が羽根をたたんで人に化けているのではないかと思える、そんな印象だった。
そもそも原作には、この場面は存在しない。セレスタンは、この第一寮『サヴォワール』所属ではなく、第三寮の『ソルスティス』所属、そして、本来のグラン・フレールは、別の伯爵家の子息で至極真面目な青年だったからだ。
この予定外の配役変更に、思わず息を飲む。
今後の展開が全くもって分からない。知っているはずの物語が、形を変えていく。次に何が起こるのか――?
「本日よりあなたのグラン・フレールを務めることになった、レオ・ド・ヴィルヌーヴです。どうぞよろしく――ロード・コルベール」
折目高い立ち居振る舞いで軽く頭を下げたレオの声は落ち着いていて丁重な印象だったが、その奥底には、どこか掴みどころのない色気と、不意に弾けそうな荒々しさが潜んでいた。まるで、きちんと整えた髪の下で、バラガキがひそかに火花を散らしているような――そんな気配がほんのわずかに漂っている。
なんでだろう……。出るキャラ出るキャラの背後に、片っ端から悉く攻めのオーラが見える気がする。こいつも胸板が厚い。
「荷物はすでに俺が部屋に運んだ。案内いたしますよ、ロード・コルベール」
そう言ったレオに俺は軽く片眉を上げて見せた。丁寧過ぎる呼び方は、やはり違和感がある。
「ただの新入生として接してくれませんか。肩書きは、学院では抜きにして欲しい」
言い切る俺に、彼はほんの僅かに驚いた顔をして間を置いてから口角を持ち上げ、軽く含みのある笑みを浮かべた。
「分かった。君がそう望むなら、そうしよう」
レオと並んで歩き出すと、俺の周囲でも他の新入生たちが、それぞれのグラン・フレールとペアになって動き始めていた。
緊張で顔をこわばらせていた一年生たちが、少しずつ表情を解いている。
話しかけるグラン・フレールの語り口が柔らかいのか、肩をすくめながらも小さく笑う者、頷きながら歩調を合わせる者――反応はそれぞれだったが、いずれもこの瞬間から始まる『寮生活』に心を揺らしているのが分かった。
俺の隣を歩くレオは、そんなことをよそに悠然としていた。背筋はまっすぐ、歩幅も無理がなく、要所で俺に気を配る。まるで他人に見せるための所作を体に叩き込まれたような歩き方だった。
だが、そんな空気の中でも、背後から――というより、少し離れた数方向から妙な熱の籠った視線が突き刺さってくるのを、俺はしっかりと感じていた。
刺すような鋭さを帯びた目線。振り返らなくても分かる。これはアルチュールだ。どうやら彼も、グラン・フレールと共に寮室へ向かっている最中のようだったが、その足をほんの一瞬だけ止め、こちらを見ていた気配がした。
続いて、ずっしりと重たい視線。堂々としていながら、妙に棘を含んでいる。これは殿下――リシャール王太子。王族特有の気配に気付かないふりをしてやるのも、正直、ちょっと疲れる。目を合わせなくても伝わってくる不機嫌さに、俺はこっそり溜息を吐きたくなった。
極めつけは、じんわり胸に残るような、感情の混ざった視線。ナタン。彼もまた、自分のグラン・フレールと一緒にいるはずだが、ふとした瞬間にこちらを見たのだろう。目が合ったわけでもないのに、それはやけに刺さる。
俺は顔を向けることなく、気配だけで三人の居場所を探りながら、表情には一切出さないよう努めた。周囲の新入生たちは、そんなこと気付きもしないまま、自分のグラン・フレールとの会話に一生懸命だ。
レオがふと、こちらに目を向ける。
「どうかしたか?」
「いや……、何でもありません」
軽く首を振り、そのまま歩を進める。視線なんかに気を取られていられない。――俺の部屋は、もうすぐそこだ。
階段をのぼりきると、静かな気配に包まれた長い廊下が目の前に現れた。
新入生の個室は三階、二年生であるグラン・フレールたちの部屋はその真下の二階、三年生の部屋はさらにその下、一階にある。
この階には、301号室から320号室までの扉が整然と並び、まるでどれもが同じ重みを持って未来を待っているようだった。
中庭に面した各々の窓からは、傾きかけた夕陽が斜めに差し込み床に影を落とす。空気は澄んでいて、風に乗って微かな薬草の香りが漂って来る。
その時、ふと「君にはチュテレールが三人も居るんだな」と、レオが不意に口を開いた。
俺は思わず真横を歩くレオの顔を盗み見た。彼はさっきの、殿下とアルチュール、ナタンたち三人の視線に気付いていたようだ。
「チュテレールではなく、友人です」
っていうか、チュテレールってなんだよ。俺、成人した社会人だぞ? おとぎ話に出て来るか弱き姫じゃないって!
俺の返答に、「ふうん」と応えたあと、レオは立ち止まらず、ゆっくりと歩きながらちらりとこちらに視線を投げた。その目元には、言葉にしない微かな笑みが浮かんでいる。まるで、何か面白い遊びを見つけた子供のような、いや、それよりももう少し大人びた余裕と好奇心が入り混じっていた。
「『金の君』と『銀の君』が入学すると聞いて、学院内は昨年の末ごろから少し浮足立っていたんだ。どの寮に来るか、誰がグラン・フレールに選ばれるか? 小さな賭けをしていた者もいたくらいだ」
廊下を三分の一ほど進んだところで、レオは立ち止まり、扉を指さした。
310と刻まれた真鍮のプレートが、夕陽に照らされてやわらかく光っている。
「担当するプティ・フレールが誰なのか、俺たちに正式に知らされたのは今日。君たちが入学式に出ていたころだ」
そう言いながら、レオはジャケットのポケットから鍵と封筒を取り出し、中の紙を俺に見せた。
| レオ・ド・ヴィルヌーヴ
| プティ・フレール:セレスタン・ギレヌ・コルベール
| 所属寮:第一寮・サヴォワール寮(310号室)
「担当になれて光栄だ。ようこそ、『サヴォワール』へ。310号室、今日からここが君の部屋だ。鍵をどうぞ、セレスタン君」
「呼び捨てでいいです。セレスタンか、セレスで」
レオは少し目を見開いたあと、ふっと笑って首を傾げた。
「じゃあ、俺のこともレオでいい……。ああ、もう堅苦しいのは嫌いだ。普段通りにしていいか?」
「……今までのイメージと違いますね」
「それは俺の台詞。君のことはもっと杓子定規な優等生で、礼儀作法に厳しい堅物だと思っていたんだけどな」
中身、異世界から来たチャランポランな別人です……、とは言えない。
「セレス……、でいいんだよな。ところで入学前に事故にあったと聞いている。無理に張り切ったりしないように」
レオの声は静かだったが、気遣いの色が滲んでいた。形式的なものではなく、個として向き合おうとしているところに好感が持てる。
「……ありがとう。気をつけます」
「時計塔の鐘が六度響けば、食堂に向かう時間だ。それまで部屋でゆっくりしていてくれ。何かあったら真下の210号室をノックすればいい。床ドンでもいいぞ」
彼は冗談めかした口調でそう言い、「じゃあ、また食堂で」と、俺に鍵を渡してから軽く片手を上げ、踵を返して廊下を戻っていった。
その背中が遠ざかるのと入れ替わるように、アルチュールが彼のグラン・フレールと並んでこちらへと向かって歩いて来る。淡い褐色の肌をした長身のグラン・フレールは、肩まで届く銀灰の髪を後ろで束ね、整った顔立ちと落ち着いた物腰を備えた人物で、アルチュールと並ぶ姿は、まるで一枚の絵画のように華やかだっだ。
原作でも未見、セレスタンの記憶の中にも存在していない。完全な新キャラだ。十中八九、留学生だろう。
一瞬、アルチュールはすれ違いざまにレオを一瞥し、それから俺に目を向けると小さく微笑み、声に出さずに唇の動きだけで「あとで行く」と告げてきた。
いや、来なくていいし。出来れば、リシャール殿下の部屋でも訪ねたらどだろうか? ――と、腐男子は思う。
レオの背中が角を曲がって見えなくなるのを見届けてから、俺は扉に鍵を差し込んだ。
カチリ、と小気味よい音を立てて鍵が回る。扉を押し開けると、ふわりとやさしい香りが鼻先をかすめた。主張しすぎない、軽やかな花の香り?
埃っぽさは一切なく、空気は清々しく、部屋は綺麗に整えられている。
目を向けると、重厚なデスクの上に小さなサシェが置かれていた。飾り気のない薄い布袋に詰められた乾いた花。ほのかな魔力の気配――、
レオだな。このサリトゥの残余から彼の攻めオーラと同じ波動を感じる。
サシェの下には、丁寧な筆跡で短いメモが添えられていた。
――頭を打ったと聞いていたから、少しでもリラックスできればと思って。中庭の薬草を使い、昼休みの時間に急遽作ってみた。要らなかったら捨ててくれ。
思わず胸がきゅっとなった。
……クッソ、イケメンかよ。
ちょい悪系で見た目がいいだけじゃねぇのかよ。さりげない気配りに、距離の詰め方も自然。これで無自覚なんだったら、天性のタラシだ。
いやもう、俺が女だったら完全に落ちてたわ。
なんか、今ちょっとときめいてしまった自分が悔しい。
レオ・ド・ヴィルヌーヴ、恐るべし。
203
あなたにおすすめの小説

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新

悪役令嬢の兄に転生!破滅フラグ回避でスローライフを目指すはずが、氷の騎士に溺愛されてます
水凪しおん
BL
三十代半ばの平凡な会社員だった俺は、ある日、乙女ゲーム『君と紡ぐ光の協奏曲』の世界に転生した。
しかも、最推しの悪役令嬢リリアナの兄、アシェルとして。
このままでは妹は断罪され、一家は没落、俺は処刑される運命だ。
そんな未来は絶対に回避しなくてはならない。
俺の夢は、穏やかなスローライフを送ること。ゲームの知識を駆使して妹を心優しい少女に育て上げ、次々と破滅フラグをへし折っていく。
順調に進むスローライフ計画だったが、関わると面倒な攻略対象、「氷の騎士」サイラスになぜか興味を持たれてしまった。
家庭菜園にまで現れる彼に困惑する俺。
だがそれはやがて、国を揺るがす陰謀と、甘く激しい恋の始まりを告げる序曲に過ぎなかった――。

悪役キャラに転生したので破滅ルートを死ぬ気で回避しようと思っていたのに、何故か勇者に攻略されそうです
菫城 珪
BL
サッカーの練習試合中、雷に打たれて目が覚めたら人気ゲームに出て来る破滅確約悪役ノアの子供時代になっていた…!
苦労して生きてきた勇者に散々嫌がらせをし、魔王軍の手先となって家族を手に掛け、最後は醜い怪物に変えられ退治されるという最悪の未来だけは絶対回避したい。
付き纏う不安と闘い、いずれ魔王と対峙する為に研鑽に励みつつも同級生である勇者アーサーとは距離を置いてをなるべく避ける日々……だった筈なのになんかどんどん距離が近くなってきてない!?
そんな感じのいずれ勇者となる少年と悪役になる筈だった少年によるBLです。
のんびり連載していきますのでよろしくお願いします!
※小説家になろう、アルファポリス、カクヨムエブリスタ各サイトに掲載中です。
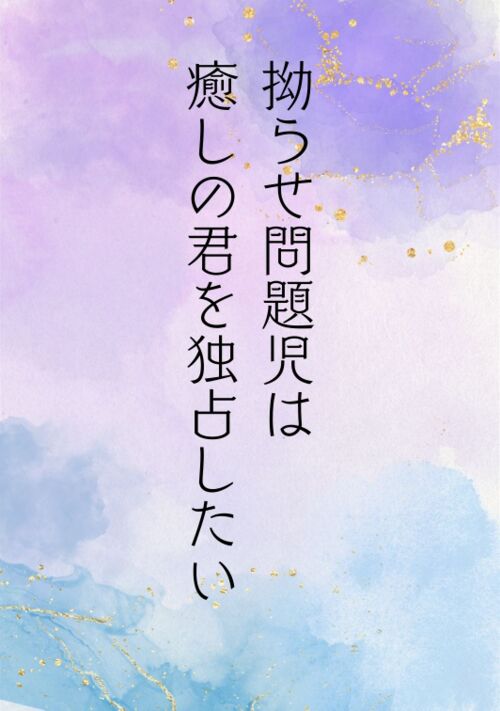
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

今日もBL営業カフェで働いています!?
卵丸
BL
ブラック企業の会社に嫌気がさして、退職した沢良宜 篤は給料が高い、男だけのカフェに面接を受けるが「腐男子ですか?」と聞かれて「腐男子ではない」と答えてしまい。改めて、説明文の「BLカフェ」と見てなかったので不採用と思っていたが次の日に採用通知が届き疑心暗鬼で初日バイトに向かうと、店長とBL営業をして腐女子のお客様を喜ばせて!?ノンケBL初心者のバイトと同性愛者の店長のノンケから始まるBLコメディ
※ 不定期更新です。

悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

異世界で孵化したので全力で推しを守ります
のぶしげ
BL
ある日、聞いていたシチュエーションCDの世界に転生してしまった主人公。推しの幼少期に出会い、魔王化へのルートを回避して健やかな成長をサポートしよう!と奮闘していく異世界転生BL 執着最強×人外美人BL

魔王の息子を育てることになった俺の話
お鮫
BL
俺が18歳の時森で少年を拾った。その子が将来魔王になることを知りながら俺は今日も息子としてこの子を育てる。そう決意してはや数年。
「今なんつった?よっぽど死にたいんだね。そんなに俺と離れたい?」
現在俺はかわいい息子に殺害予告を受けている。あれ、魔王は?旅に出なくていいの?とりあえず放してくれません?
魔王になる予定の男と育て親のヤンデレBL
BLは初めて書きます。見ずらい点多々あるかと思いますが、もしありましたら指摘くださるとありがたいです。
BL大賞エントリー中です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















