8 / 114
8話~模擬戦~
しおりを挟む
~模擬戦~
回廊に出るとすでに陽は沈み、空には薄暮の青が広がっていた。吹き抜ける風が、柱に絡みつく蔦をゆらゆらと揺らしている。
俺たちは魔道具の照明がぽつぽつと灯る中庭を横切り、足を速めた。花壇の薬草がかすかに香り、芝の上に落ちた柔らかな光が足元をぼんやりと照らしている。
やがて、寮のホールが見えてきた。
リシャールがデュボアから預かっていた鍵を取り出し、鍵穴に差し込んで低く呪文を唱える。
「アペリオ・セザム」
すると、小さな金属音が響いたあと、扉がごく自然に音もなく内側へと開かれた。
当然のことながらホール内には誰もいない。昼の活動がひと段落した時間帯、校舎の方からは、講義や実習を終えた生徒たちが寮へと戻ってくる気配がかすかに聞こえてくる。
外のざわめきとは対照的に、ここはまるで音を吸い込むような静けさに包まれていた。
アルチュールとナタンはそれぞれ一本ずつ、魔法布に丁寧に包まれたエクラ・ダシエを抱えていた。
人の気配を感知して照明魔法の光が高天井の燭台に淡く灯る。
ホールの片隅に着くと、まずアルチュールがその場に膝をつき、剣を包んでいた布を手早く広げる。ナタンも同じようにして、自分の持っていた剣の布を横に敷いた。二人は互いに頷き合いながら、その上に慎重にエクラ・ダシエを並べる。
魔道具特有の淡い反応がわずかに揺らぎ、室内の空気に静かな緊張感がにじんだ。
それを確認したあと、ナタンがまっすぐ天井の方を見上げる。
「少し、明るくしておきましょう」ナタンはそう呟くと、掌を燭台に向けて静かに呪文を唱えた。「アリューム・ルクス」
光がひときわ強まり、天井から降りそそぐようにホール全体を満たした。床の模様や壁の装飾がくっきりと浮かび上がる。
その後、俺たちは手分けして簡易的な障壁をホールの四隅に張っていく。魔力を込めた紋章が床に広がり、光の筋がゆるやかに結ばれて、ぱん、と軽い音とともに結界が閉じ薄膜のような魔力の気配が漂った。
これで外部への音漏れを防ぐと同時に、訓練による衝撃からホールの内装や構造を保護する準備が整ったことになる。必要最低限の安全措置としては十分だろう。
「……準備は万端だな」
リシャールが中央に立ち、淡く微笑みながら言った。ナタンと俺が左右に立ち、アルチュールは軽く肩を回しながら、床に置いていたエクラ・ダシエの剣を一本持って鞘から抜き、前へと進み出た。
「なら、始めよう」アルチュールが振り返る。その目には、戦う前の特有な光が宿っていた。「対戦相手は、どうする?」
「俺がやる」
自然と口がそう動いた。考えるより先に身体が応じていた。
一瞬の沈黙のあと、ナタンがわずかに息を呑む音がした。目を見開き、俺を見返す。リシャールもまた、眉をわずかに上げてこちらを見た。
アルチュールの目が僅かに細められる。
「いいのか?」
「ああ、勿論」
俺は残りのエクラ・ダシエの剣を持ち、鞘から抜いて戻り、軽く"無構え"で応じる。
そのとき、リシャールが念のためといった調子で言葉を添えた。
「魔法の使用は禁止。加えて、剣は切れない模造刀で刃が身体に触れた瞬間に霧散する魔道具だが、首から上への攻撃も全面的に禁ずる。いいな?」
「了解」
「問題ない」
アルチュールはわずかに顎を引き、真剣な眼差しで俺を見据えた。
少し離れた場所で、ナタンが声を上げた。
「セ、セレスさま、本気で!?」
その声には、驚きだけではなく、焦りの色も混じっていた。
アルチュールの面構えが鋭くなったその一瞬で、ナタンは察したのだ。彼の動きに宿る揺るぎのない自信と、辺境で魔物相手に幾多の実戦をくぐり抜けた者だけが持つ研ぎ澄まされた集中が宿っていること、剣の腕前が並の生徒とは明らかに一線を画していることを。
それは、学内の剣術稽古では見せていなかった、戦場の眼だった。
それだけに、セレスタンが魔法を封じた上で、正面から立ち合うというのが信じられなかったのだろう。
だが、返事はしない。
目の前のアルチュールの気配が変わった。彼もまた、剣を構え体を低く沈める。
「セレスでも手加減はしないぞ」
「上等」
「いいのか?」
「アルチュール――俺を舐めんな」
二人同時に口角を持ち上げ、息を整えて足の裏に力を込める。
――転生前、かつての俺は剣道をたしなんでいた。
道場では、何度も打ち込み、走り込み、受け、避け、跳んだ。黙々と汗を流しながら、技を繰り返し体に刻み込む日々だった。
はじめは、親に言われていやいや通いはじめたのだ。
子供の頃の俺はというと、忘れ物は日常茶飯事で片付けや掃除もろくにできず、生活全般がずさんだった。何をするにもどこかちゃらんぽらんで、真剣味に欠けていたと思う。親としては少しでも姿勢を改めさせたかったのだろう。厳しい礼儀作法と規律のある世界に、そんな俺を放り込んだ。
けれど、不思議なことに、竹刀を握って立ち合うのが、やけに楽しかった。
打ち合うたび、体の奥が熱くなるような感覚があった。型を覚え、足さばきが自然に身につき、初めて一本を取ったときのあの感触は、今でも覚えている。
黙って鍛錬に打ち込むうちに、少しずつだらしない癖も抜けていった。忘れ物も前ほどはしなくなったし、整理整頓もそこそこできるようになった。
まあ、それでも最後まで「完璧」とは言いがたかったが、自分なりにましになったのは確かだ。
床を蹴る音とともに、アルチュールが飛び込んできた。
一瞬の初撃――速い。だが、見える。
その刃を、紙一重の角度で受け流す。
カン、と澄んだ音が響いた。
手応えに戸惑ったのか、アルチュールが目を見開いた。確かに捉えたはずだ、そう言いたげな顔だった。
剣筋の流れを読むことも、足の運びも、呼吸の合わせ方も――大丈夫だ、すべてを覚えている。動ける。
高校生のとき、体育の教師から言われた。
「お前、フィジカルおばけだな」
今なら、信じられる。あれは正しかった。
この身体も、なかなかのポテンシャルだ。
反応の鋭さ、筋力、柔軟性――全て、凡人の域を優に超えている。筋繊維の質も、バネの利いた動きも、生まれつきのものではない。かなり鍛えたのだろう。
おそらくセレスタンに足りなかったのは、あと少しの経験ぐらいだ。ならば、それは俺が補ってやる。
周囲からは「脳筋」だの「フィジモン」だのと呼ばれ、卓上の授業はそこそこに、毎日のように部活や道場に通い詰め、夜はヲタ活に全フリしながら県内外の大会を回っていた俺が、補ってやる。
この身体でも前世と同じくらい――いや、それ以上に戦えるようになる。
床を蹴る音が響いた。距離を取ったアルチュールが再び真正面から突っ込んでくる。少し遅れて俺も踏み出す。空気が裂ける音。剣と剣がぶつかり合う甲高い金属音が弾け、お互いの剣先が空を切りわずかに逸れる。
アルチュールの剣筋は鋭い。重く、無駄がなく正確。こいつは天才だ。だが、俺に受けられる前提で戦い方が組み立てられていない。その分、俺に利がある。直撃するはずの一撃を、俺は一瞬、重心をずらして受け流す。床を滑るように移動し、片手を地面につけ高く飛んでバク転を一回。
視線を切らさず、着地と同時に斜めから袈裟懸けに切り返す。それを受けられるとすぐに、俺の剣の腹でアルチュールの剣を撥ねた。アルチュールの体の軸が大きく乱れる。その隙に、一歩。さらに一歩。脇から刃を差し込み、下から打ち込む。
――読み切った。
もう一歩、踏み込む。
ただの練習試合のはずが、アルチュールの表情が変わっていった。歯を食いしばる気配が伝わる。最初の余裕が完全に消え、額に汗がにじんでいる。
剣を上段から振り下ろすアルチュール。その動きに熱が混じってきた。冷静さをわずかに欠いたその刹那、見えた一撃を真横に回転しながら避け、俺は壁を駆け上がるように蹴って角度を変えて宙で反転しながら背後を取る。
直後、アルチュールの首元すれすれに、俺の剣が止まっていた。
静寂。
その場の空気が凍るような沈黙。勝敗は、火を見るより明らかだった。
ナタンが呆然としたように呟く。
「……セレスさまって、こんなに強かったでしたっけ……?」
リシャールは小さく頷きながら、「これは……想定外だな……」とぽつりとこぼした。
アルチュールは、荒くなった呼吸を整えようとしながら一歩前に移動する。額には大粒の汗。
俺も、さすがに肩で息をしながら、無言のまま剣を下ろした。
――今回、俺には、勝たなければならない理由があった。
アルチュールは、強い。人並外れて強い。そしてその強さゆえに誰にも頼らず、一人で背負い込み、独りで突っ走る。それは、彼の美点であり、同時に――危うさでもある。
小説本編では、この先、彼は陸軍近衛師団に入る。そして、魔物相手に常に自らの力だけで解決しようとした。その結果、彼はスタンピードで大けがを負い、生死の境をさまようことになる。
誰かが彼の無謀な行動を止め、背中を預けて共に戦うということを教えなければ……、彼はまた、あの結末へ向かってしまう。
だから、俺は負けるわけにはいかなかった。真正面から彼を制してみせる必要があった。その役目は誰でもよかったのだが、まあ、たまたま俺だったというだけだ。
この稽古は、ただの実力試しではない。
アルチュールに「共闘する」ということを、肌で理解させる機会だった。
仲間は、お前の足手まといにはならない。
一緒に戦うことは、弱さの証ではない。
そのことを、伝えるために――俺は、絶対に勝たなければならなかったのだ。
剣先を床に向けたまま、アルチュールが口を引き結び、じっと俺を見つめている。
鋭い視線。でも、その奥に宿るものは――屈辱……、ではない?
まるで何かに触れてしまったような、あるいは、まだ名もなき感情に立ちすくんでいるような……。
……これは、嫌われたかもしれないな……。推しに嫌われるのはつらいが、これもいたし方ない。
リシャールが微笑みながら近づいてくる。
「今の剣の動き、まるで無駄がなかった。貴族の護身術の域を超えているな」
ナタンが、首を傾げたまま視線だけで俺とアルチュールを見比べていた。
「そうなんです……。セレスさま、魔法を使わず壁を走って空中で回転し、背後を取るとか……、いつ人間をやめたんですか?」
「やめてねぇわ!」
「……今日は、セレスさまの、私が知らなかった一面を拝見できて感動しています」
「……うん、ちょっと気持ち悪いな、それ」
「尊敬です。畏怖と尊敬が混ざった……新しい感情です」
「いらない新感情、今すぐ封印しておいてくれ」
ナタンが「それはちょっと無理ですね……」と真顔で返してくるのに、またしても言葉を失う。リシャールがくすりと笑った。
アルチュールはといえば、さっきからずっと黙っていた。その視線はまだ俺に向けられている。先ほどまでの激しさは鳴りを潜め、そのまなざしはどこか戸惑いすら帯びていたが――何か言いかけて、しかし彼は唇を閉じた。
「――このことを知れば、騎士団の教官も顔を青くするな」リシャールは笑みを深め、続けた。「セレス、では――次は私だ」
冗談めかした声音とは裏腹に、リシャールの眼差しは鋭かった。
彼もまた、王太子としての資質を問われ続けて育ってきた男だ。模擬戦といえど、手を抜くつもりはないらしい。
だが、何度でも言うが、原作では彼は、『はかなげで麗しきリシャール・ドメーヌ・ル・ワンジェ王太子殿下』だったはずなんだ。嫋やかで慈愛に満ちた微笑みを浮かべ、いつも周囲を和ませる癒し系ポジション。剣ではなく弓を得意とし、戦いの最前線に立つよりも後方で支援することに長けていた。
……それが、どうして今、この攻め感あふれる仁王立ちなのか。
俺を射抜くように見据え、いつの間にかアルチュールの持っていたエクラ・ダシエの剣を手に、まるで「次は仕留めるぞ」と言わんばかりの気迫を放っている。
肘を張った構えは軍人のそれ。王太子の気品もどこへやら、その姿は歴戦の将校と見まがうばかりだ。
……誰だよ、お前。俺の可愛いもう一人の推し、どこ行った? なんか、怖えーわ。
内心で突っ込みながらも、こちらも気を抜くわけにはいかない。
興味を持ったこと、好奇心をくすぐられることがあると、殿下は言い出したら聞かない。
俺は小さく溜息をつき、もう一度剣を構え直した。
すでにアルチュールとの一戦で体力はかなり削られている。だが――逃げるわけにはいかない。
リシャールは、はかなげで麗しき『受け殿下』のときでも、こういう場面では本性を隠そうとしなかった。全力で来る気だ。
「……はあ……、では、仕方ないですね」そう呟いて、俺はゆっくりと体制を整える。「この一戦で、今日はおしまいにしましょう。デュボア寮監との約束がありますので」
「いいだろう」
リシャールが剣を構える。剣先が静かにこちらを指し、呼吸のリズムが変わった瞬間――地を蹴ってきた。速い。しかも、アルチュールとは違う“精度”の速さだ。
正確で、理詰めで、王太子としての矜持すら乗せたような洗練された一撃。
突きを身を翻して避けながら、続く踏み込みはすぐさま逆足でかわし、返す刀で斜めに振り下ろす――が、受け止められた。
金属の打ち合う音が再び響く。会話のように、剣と剣が応酬し合い、こちらの癖を読み取る動きが洗練されていく。
「……少しは疲れてくれ、セレス」
「殿下こそ、試すみたいな攻撃はやめてください」
互いの目を見据えたまま、静かに笑い合う。だが彼の剣は容赦なく、鋭さを増す。
リシャールの戦い方は、一言で言えば“王道”だ。変則的な技は使わない。だからこそ恐ろしい。
地力の差だけで圧倒してくる、貴族の中でも限られた者だけが持つ“威圧”。
だが――それでも、引けない。
ここで俺が負けてしまえば、リシャールが、俺や俺に敗れたアルチュールよりも強いことになってしまう。これ以上、アルチュールの誇りが傷つくのは避けたい。
俺は跳ねるように前へ出て、低い姿勢から刃を突き上げた。リシャールが即座に受けたが、それは、あまりにもアカデミック過ぎる。右へと回り込む動きを読んで、俺は、すぐさま一旦、後ろに飛んでから踏み込んだ。
リシャールは――剣を振り上げたまま、固まっていた。
俺は、明確に空白を晒す彼の胴に、横なぎに払った剣の刃を当てていた。
息を切らしながら、リシャールが苦笑する。
「……まいったな。完全にこちらの手の内を読まれていた」
「殿下、先ほどの試合で俺が疲れているのを見越して、長期戦に持ち込むつもりでしたね?」
「王太子ともなれば、勝てる手はすべて使って然るべきだろう? というか、リシャールと呼べ」
いや、なんで王太子がそんなずる賢い作戦立ててんだよ。正々堂々でいてくれよ……。
俺もリッシャーるるるるるって呼ぶぞ!
心の中でそっと突っ込みながら、俺は床に置かれていた鞘を手に取り剣を収め、布の上に置いて言った。
「リシャール、そろそろ片付けましょう」
デュボア寮監の顔が脳裏にちらつく。今日は初日だ。もしも使用時間を少しでも過ぎてしまえば、借りた側としての信頼が損なわれかねない。この空間を、また自由に使わせてもらうためにも、守るべきところは守らないといけない。
「ナタン、今日は見学だけで悪かったな」
「いいえ、セレスさま。今日は本当にいいものを見れました」ナタンが小さく拍手をしていた手のひらを軽くこすり合わせるようにして、満足げに微笑んだ。「しっかりと、ナタン・トレモイユ著『~セレスタン・ギレヌ・コルベール様の日々~日記』に書きます」
「すぐ燃やせ」
「きっと後世に残すべき記録になります」
「残すな。俺の知らないところで完結して燃やしてくれ」
「……出版の際は、一部献本を頼む」
ふと挟まったリシャールの声に、俺は即座に振り向いた。
なんなんだろう、この二人……。もう突っ込むのもしんどい。
回廊に出るとすでに陽は沈み、空には薄暮の青が広がっていた。吹き抜ける風が、柱に絡みつく蔦をゆらゆらと揺らしている。
俺たちは魔道具の照明がぽつぽつと灯る中庭を横切り、足を速めた。花壇の薬草がかすかに香り、芝の上に落ちた柔らかな光が足元をぼんやりと照らしている。
やがて、寮のホールが見えてきた。
リシャールがデュボアから預かっていた鍵を取り出し、鍵穴に差し込んで低く呪文を唱える。
「アペリオ・セザム」
すると、小さな金属音が響いたあと、扉がごく自然に音もなく内側へと開かれた。
当然のことながらホール内には誰もいない。昼の活動がひと段落した時間帯、校舎の方からは、講義や実習を終えた生徒たちが寮へと戻ってくる気配がかすかに聞こえてくる。
外のざわめきとは対照的に、ここはまるで音を吸い込むような静けさに包まれていた。
アルチュールとナタンはそれぞれ一本ずつ、魔法布に丁寧に包まれたエクラ・ダシエを抱えていた。
人の気配を感知して照明魔法の光が高天井の燭台に淡く灯る。
ホールの片隅に着くと、まずアルチュールがその場に膝をつき、剣を包んでいた布を手早く広げる。ナタンも同じようにして、自分の持っていた剣の布を横に敷いた。二人は互いに頷き合いながら、その上に慎重にエクラ・ダシエを並べる。
魔道具特有の淡い反応がわずかに揺らぎ、室内の空気に静かな緊張感がにじんだ。
それを確認したあと、ナタンがまっすぐ天井の方を見上げる。
「少し、明るくしておきましょう」ナタンはそう呟くと、掌を燭台に向けて静かに呪文を唱えた。「アリューム・ルクス」
光がひときわ強まり、天井から降りそそぐようにホール全体を満たした。床の模様や壁の装飾がくっきりと浮かび上がる。
その後、俺たちは手分けして簡易的な障壁をホールの四隅に張っていく。魔力を込めた紋章が床に広がり、光の筋がゆるやかに結ばれて、ぱん、と軽い音とともに結界が閉じ薄膜のような魔力の気配が漂った。
これで外部への音漏れを防ぐと同時に、訓練による衝撃からホールの内装や構造を保護する準備が整ったことになる。必要最低限の安全措置としては十分だろう。
「……準備は万端だな」
リシャールが中央に立ち、淡く微笑みながら言った。ナタンと俺が左右に立ち、アルチュールは軽く肩を回しながら、床に置いていたエクラ・ダシエの剣を一本持って鞘から抜き、前へと進み出た。
「なら、始めよう」アルチュールが振り返る。その目には、戦う前の特有な光が宿っていた。「対戦相手は、どうする?」
「俺がやる」
自然と口がそう動いた。考えるより先に身体が応じていた。
一瞬の沈黙のあと、ナタンがわずかに息を呑む音がした。目を見開き、俺を見返す。リシャールもまた、眉をわずかに上げてこちらを見た。
アルチュールの目が僅かに細められる。
「いいのか?」
「ああ、勿論」
俺は残りのエクラ・ダシエの剣を持ち、鞘から抜いて戻り、軽く"無構え"で応じる。
そのとき、リシャールが念のためといった調子で言葉を添えた。
「魔法の使用は禁止。加えて、剣は切れない模造刀で刃が身体に触れた瞬間に霧散する魔道具だが、首から上への攻撃も全面的に禁ずる。いいな?」
「了解」
「問題ない」
アルチュールはわずかに顎を引き、真剣な眼差しで俺を見据えた。
少し離れた場所で、ナタンが声を上げた。
「セ、セレスさま、本気で!?」
その声には、驚きだけではなく、焦りの色も混じっていた。
アルチュールの面構えが鋭くなったその一瞬で、ナタンは察したのだ。彼の動きに宿る揺るぎのない自信と、辺境で魔物相手に幾多の実戦をくぐり抜けた者だけが持つ研ぎ澄まされた集中が宿っていること、剣の腕前が並の生徒とは明らかに一線を画していることを。
それは、学内の剣術稽古では見せていなかった、戦場の眼だった。
それだけに、セレスタンが魔法を封じた上で、正面から立ち合うというのが信じられなかったのだろう。
だが、返事はしない。
目の前のアルチュールの気配が変わった。彼もまた、剣を構え体を低く沈める。
「セレスでも手加減はしないぞ」
「上等」
「いいのか?」
「アルチュール――俺を舐めんな」
二人同時に口角を持ち上げ、息を整えて足の裏に力を込める。
――転生前、かつての俺は剣道をたしなんでいた。
道場では、何度も打ち込み、走り込み、受け、避け、跳んだ。黙々と汗を流しながら、技を繰り返し体に刻み込む日々だった。
はじめは、親に言われていやいや通いはじめたのだ。
子供の頃の俺はというと、忘れ物は日常茶飯事で片付けや掃除もろくにできず、生活全般がずさんだった。何をするにもどこかちゃらんぽらんで、真剣味に欠けていたと思う。親としては少しでも姿勢を改めさせたかったのだろう。厳しい礼儀作法と規律のある世界に、そんな俺を放り込んだ。
けれど、不思議なことに、竹刀を握って立ち合うのが、やけに楽しかった。
打ち合うたび、体の奥が熱くなるような感覚があった。型を覚え、足さばきが自然に身につき、初めて一本を取ったときのあの感触は、今でも覚えている。
黙って鍛錬に打ち込むうちに、少しずつだらしない癖も抜けていった。忘れ物も前ほどはしなくなったし、整理整頓もそこそこできるようになった。
まあ、それでも最後まで「完璧」とは言いがたかったが、自分なりにましになったのは確かだ。
床を蹴る音とともに、アルチュールが飛び込んできた。
一瞬の初撃――速い。だが、見える。
その刃を、紙一重の角度で受け流す。
カン、と澄んだ音が響いた。
手応えに戸惑ったのか、アルチュールが目を見開いた。確かに捉えたはずだ、そう言いたげな顔だった。
剣筋の流れを読むことも、足の運びも、呼吸の合わせ方も――大丈夫だ、すべてを覚えている。動ける。
高校生のとき、体育の教師から言われた。
「お前、フィジカルおばけだな」
今なら、信じられる。あれは正しかった。
この身体も、なかなかのポテンシャルだ。
反応の鋭さ、筋力、柔軟性――全て、凡人の域を優に超えている。筋繊維の質も、バネの利いた動きも、生まれつきのものではない。かなり鍛えたのだろう。
おそらくセレスタンに足りなかったのは、あと少しの経験ぐらいだ。ならば、それは俺が補ってやる。
周囲からは「脳筋」だの「フィジモン」だのと呼ばれ、卓上の授業はそこそこに、毎日のように部活や道場に通い詰め、夜はヲタ活に全フリしながら県内外の大会を回っていた俺が、補ってやる。
この身体でも前世と同じくらい――いや、それ以上に戦えるようになる。
床を蹴る音が響いた。距離を取ったアルチュールが再び真正面から突っ込んでくる。少し遅れて俺も踏み出す。空気が裂ける音。剣と剣がぶつかり合う甲高い金属音が弾け、お互いの剣先が空を切りわずかに逸れる。
アルチュールの剣筋は鋭い。重く、無駄がなく正確。こいつは天才だ。だが、俺に受けられる前提で戦い方が組み立てられていない。その分、俺に利がある。直撃するはずの一撃を、俺は一瞬、重心をずらして受け流す。床を滑るように移動し、片手を地面につけ高く飛んでバク転を一回。
視線を切らさず、着地と同時に斜めから袈裟懸けに切り返す。それを受けられるとすぐに、俺の剣の腹でアルチュールの剣を撥ねた。アルチュールの体の軸が大きく乱れる。その隙に、一歩。さらに一歩。脇から刃を差し込み、下から打ち込む。
――読み切った。
もう一歩、踏み込む。
ただの練習試合のはずが、アルチュールの表情が変わっていった。歯を食いしばる気配が伝わる。最初の余裕が完全に消え、額に汗がにじんでいる。
剣を上段から振り下ろすアルチュール。その動きに熱が混じってきた。冷静さをわずかに欠いたその刹那、見えた一撃を真横に回転しながら避け、俺は壁を駆け上がるように蹴って角度を変えて宙で反転しながら背後を取る。
直後、アルチュールの首元すれすれに、俺の剣が止まっていた。
静寂。
その場の空気が凍るような沈黙。勝敗は、火を見るより明らかだった。
ナタンが呆然としたように呟く。
「……セレスさまって、こんなに強かったでしたっけ……?」
リシャールは小さく頷きながら、「これは……想定外だな……」とぽつりとこぼした。
アルチュールは、荒くなった呼吸を整えようとしながら一歩前に移動する。額には大粒の汗。
俺も、さすがに肩で息をしながら、無言のまま剣を下ろした。
――今回、俺には、勝たなければならない理由があった。
アルチュールは、強い。人並外れて強い。そしてその強さゆえに誰にも頼らず、一人で背負い込み、独りで突っ走る。それは、彼の美点であり、同時に――危うさでもある。
小説本編では、この先、彼は陸軍近衛師団に入る。そして、魔物相手に常に自らの力だけで解決しようとした。その結果、彼はスタンピードで大けがを負い、生死の境をさまようことになる。
誰かが彼の無謀な行動を止め、背中を預けて共に戦うということを教えなければ……、彼はまた、あの結末へ向かってしまう。
だから、俺は負けるわけにはいかなかった。真正面から彼を制してみせる必要があった。その役目は誰でもよかったのだが、まあ、たまたま俺だったというだけだ。
この稽古は、ただの実力試しではない。
アルチュールに「共闘する」ということを、肌で理解させる機会だった。
仲間は、お前の足手まといにはならない。
一緒に戦うことは、弱さの証ではない。
そのことを、伝えるために――俺は、絶対に勝たなければならなかったのだ。
剣先を床に向けたまま、アルチュールが口を引き結び、じっと俺を見つめている。
鋭い視線。でも、その奥に宿るものは――屈辱……、ではない?
まるで何かに触れてしまったような、あるいは、まだ名もなき感情に立ちすくんでいるような……。
……これは、嫌われたかもしれないな……。推しに嫌われるのはつらいが、これもいたし方ない。
リシャールが微笑みながら近づいてくる。
「今の剣の動き、まるで無駄がなかった。貴族の護身術の域を超えているな」
ナタンが、首を傾げたまま視線だけで俺とアルチュールを見比べていた。
「そうなんです……。セレスさま、魔法を使わず壁を走って空中で回転し、背後を取るとか……、いつ人間をやめたんですか?」
「やめてねぇわ!」
「……今日は、セレスさまの、私が知らなかった一面を拝見できて感動しています」
「……うん、ちょっと気持ち悪いな、それ」
「尊敬です。畏怖と尊敬が混ざった……新しい感情です」
「いらない新感情、今すぐ封印しておいてくれ」
ナタンが「それはちょっと無理ですね……」と真顔で返してくるのに、またしても言葉を失う。リシャールがくすりと笑った。
アルチュールはといえば、さっきからずっと黙っていた。その視線はまだ俺に向けられている。先ほどまでの激しさは鳴りを潜め、そのまなざしはどこか戸惑いすら帯びていたが――何か言いかけて、しかし彼は唇を閉じた。
「――このことを知れば、騎士団の教官も顔を青くするな」リシャールは笑みを深め、続けた。「セレス、では――次は私だ」
冗談めかした声音とは裏腹に、リシャールの眼差しは鋭かった。
彼もまた、王太子としての資質を問われ続けて育ってきた男だ。模擬戦といえど、手を抜くつもりはないらしい。
だが、何度でも言うが、原作では彼は、『はかなげで麗しきリシャール・ドメーヌ・ル・ワンジェ王太子殿下』だったはずなんだ。嫋やかで慈愛に満ちた微笑みを浮かべ、いつも周囲を和ませる癒し系ポジション。剣ではなく弓を得意とし、戦いの最前線に立つよりも後方で支援することに長けていた。
……それが、どうして今、この攻め感あふれる仁王立ちなのか。
俺を射抜くように見据え、いつの間にかアルチュールの持っていたエクラ・ダシエの剣を手に、まるで「次は仕留めるぞ」と言わんばかりの気迫を放っている。
肘を張った構えは軍人のそれ。王太子の気品もどこへやら、その姿は歴戦の将校と見まがうばかりだ。
……誰だよ、お前。俺の可愛いもう一人の推し、どこ行った? なんか、怖えーわ。
内心で突っ込みながらも、こちらも気を抜くわけにはいかない。
興味を持ったこと、好奇心をくすぐられることがあると、殿下は言い出したら聞かない。
俺は小さく溜息をつき、もう一度剣を構え直した。
すでにアルチュールとの一戦で体力はかなり削られている。だが――逃げるわけにはいかない。
リシャールは、はかなげで麗しき『受け殿下』のときでも、こういう場面では本性を隠そうとしなかった。全力で来る気だ。
「……はあ……、では、仕方ないですね」そう呟いて、俺はゆっくりと体制を整える。「この一戦で、今日はおしまいにしましょう。デュボア寮監との約束がありますので」
「いいだろう」
リシャールが剣を構える。剣先が静かにこちらを指し、呼吸のリズムが変わった瞬間――地を蹴ってきた。速い。しかも、アルチュールとは違う“精度”の速さだ。
正確で、理詰めで、王太子としての矜持すら乗せたような洗練された一撃。
突きを身を翻して避けながら、続く踏み込みはすぐさま逆足でかわし、返す刀で斜めに振り下ろす――が、受け止められた。
金属の打ち合う音が再び響く。会話のように、剣と剣が応酬し合い、こちらの癖を読み取る動きが洗練されていく。
「……少しは疲れてくれ、セレス」
「殿下こそ、試すみたいな攻撃はやめてください」
互いの目を見据えたまま、静かに笑い合う。だが彼の剣は容赦なく、鋭さを増す。
リシャールの戦い方は、一言で言えば“王道”だ。変則的な技は使わない。だからこそ恐ろしい。
地力の差だけで圧倒してくる、貴族の中でも限られた者だけが持つ“威圧”。
だが――それでも、引けない。
ここで俺が負けてしまえば、リシャールが、俺や俺に敗れたアルチュールよりも強いことになってしまう。これ以上、アルチュールの誇りが傷つくのは避けたい。
俺は跳ねるように前へ出て、低い姿勢から刃を突き上げた。リシャールが即座に受けたが、それは、あまりにもアカデミック過ぎる。右へと回り込む動きを読んで、俺は、すぐさま一旦、後ろに飛んでから踏み込んだ。
リシャールは――剣を振り上げたまま、固まっていた。
俺は、明確に空白を晒す彼の胴に、横なぎに払った剣の刃を当てていた。
息を切らしながら、リシャールが苦笑する。
「……まいったな。完全にこちらの手の内を読まれていた」
「殿下、先ほどの試合で俺が疲れているのを見越して、長期戦に持ち込むつもりでしたね?」
「王太子ともなれば、勝てる手はすべて使って然るべきだろう? というか、リシャールと呼べ」
いや、なんで王太子がそんなずる賢い作戦立ててんだよ。正々堂々でいてくれよ……。
俺もリッシャーるるるるるって呼ぶぞ!
心の中でそっと突っ込みながら、俺は床に置かれていた鞘を手に取り剣を収め、布の上に置いて言った。
「リシャール、そろそろ片付けましょう」
デュボア寮監の顔が脳裏にちらつく。今日は初日だ。もしも使用時間を少しでも過ぎてしまえば、借りた側としての信頼が損なわれかねない。この空間を、また自由に使わせてもらうためにも、守るべきところは守らないといけない。
「ナタン、今日は見学だけで悪かったな」
「いいえ、セレスさま。今日は本当にいいものを見れました」ナタンが小さく拍手をしていた手のひらを軽くこすり合わせるようにして、満足げに微笑んだ。「しっかりと、ナタン・トレモイユ著『~セレスタン・ギレヌ・コルベール様の日々~日記』に書きます」
「すぐ燃やせ」
「きっと後世に残すべき記録になります」
「残すな。俺の知らないところで完結して燃やしてくれ」
「……出版の際は、一部献本を頼む」
ふと挟まったリシャールの声に、俺は即座に振り向いた。
なんなんだろう、この二人……。もう突っ込むのもしんどい。
130
あなたにおすすめの小説

【完結】『ルカ』
瀬川香夜子
BL
―――目が覚めた時、自分の中は空っぽだった。
倒れていたところを一人の老人に拾われ、目覚めた時には記憶を無くしていた。
クロと名付けられ、親切な老人―ソニーの家に置いて貰うことに。しかし、記憶は一向に戻る気配を見せない。
そんなある日、クロを知る青年が現れ……?
貴族の青年×記憶喪失の青年です。
※自サイトでも掲載しています。
2021年6月28日 本編完結
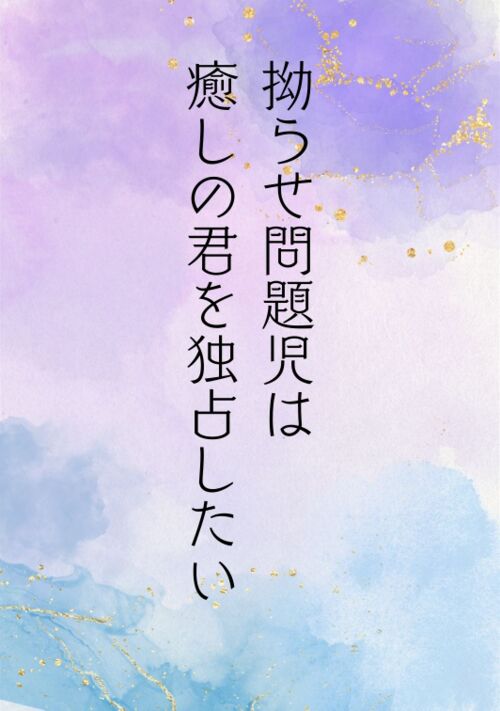
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

腹違いの妹にすべてを奪われた薄幸の令嬢が、義理の母に殴られた瞬間、前世のインテリヤクザなおっさんがぶちギレた場合。
灯乃
ファンタジー
十二歳のときに母が病で亡くなった途端、父は後妻と一歳年下の妹を新たな『家族』として迎え入れた。
彼らの築く『家族』の輪から弾き出されたアニエスは、ある日義母の私室に呼び出され――。
タイトル通りのおっさんコメディーです。

売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

彼はやっぱり気づかない!
水場奨
BL
さんざんな1日を終え目を覚ますと、そこは漫画に似た世界だった。
え?もしかして俺、敵側の端役として早々に死ぬやつじゃね?
死亡フラグを回避して普通に暮らしたい主人公が気づかないうちに主人公パートを歩み始めて、周りをかき回しながら生き抜きます。

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新

猫を追いかけて異世界に来たら、拾ってくれたのは優しい貴族様でした
水無瀬 蒼
BL
清石拓也はある日飼い猫の黒猫・ルナを追って古びた神社に紛れ込んだ。
そこで、御神木の根に足をひっかけて転んでしまう。
倒れる瞬間、大きな光に飲み込まれる。
そして目を覚ましたのは、遺跡の中だった。
体調の悪い拓也を助けてくれたのは貴族のレオニス・アーゼンハイツだった。
2026.1.5〜

美形×平凡の子供の話
めちゅう
BL
美形公爵アーノルドとその妻で平凡顔のエーリンの間に生まれた双子はエリック、エラと名付けられた。エリックはアーノルドに似た美形、エラはエーリンに似た平凡顔。平凡なエラに幸せはあるのか?
──────────────────
お読みくださりありがとうございます。
お楽しみいただけましたら幸いです。
お話を追加いたしました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















