15 / 112
15話~ガーゴイル ~
しおりを挟む
~ガーゴイル~
「怪我はありませんか」
カナードは静かに歩み寄り、デュボアの顔に視線を向けた。
「ああ、大丈夫だ」
応じる声は低く、落ち着いている。鋭い輪郭と精悍な眼差しが、その答えに説得力を添えていた。
「相変わらず、頑丈ですね」
「まあ、それぐらいしか取り柄がないからな」
短く答えて胸を張るデュボアの姿には、荒々しさよりも凛とした美しさがあった。カナードが軽く微笑む。
「ご謙遜を。頑丈さに加えて、冷静さと勇気も先生の取り柄でしょう。子供たちを守ってくれて、ありがとうございます」
そして、傍らに控えるガーロンへカナードの視線が流れる。
「……あなたもよく耐えてくれました。カリュストから逐一、報告を受けています。ご主人を支え、子供たちを守ってくれた。立派な働きです」
ガーロンは低く喉を鳴らし、ほんのわずかに鼻先を上げて誇らしげに応えた。
次にカナードの目がオベールに向けられる。
「……その足のことは、既に私からカリュスト、そこからボンシャン先生の伝書使オレリアンへ、そしてご本人に伝わっています」
デュボアもにっこりと笑い、オベールに向かって言った。
「俺もノクスに頼んで、オレリアンへ伝言を届けてもらった。急いで戻って来るらしい」
オベールはかすかに肩をすくめ、あっけらかんと答えた。
「医者に直させればいい。別にあいつに直してもらう必要はないからな」
それを聞いたカナードは、わずかに目を細め、息を吐く。
オベールは無言で笑みを浮かべた。まるで忌々しい足を失って清々しいとでも言いたげな――いや、そもそも最初からどうでもいいと言わんばかりの、冷めきった笑みだった。
「直す医師などいないでしょう。あの先生の作品を誰が触りますか?」わずかに間を置き、言葉を継ぐ。「しかも、アルケ・ビスクですよ? フラフラで何日か仕事に支障が出ます。私にはできません。また、ご存知の通り、ボンシャン先生は自分の作ったものに他人の手が触れることを、好みませんし。特に、あなたに関しては」
カナードは言いながら、静かにオベールの目を見据える。
――オベールから直接、義足と義手の話を聞いたときに、アルケ・ビスクの名が出てきた。あとで気になって、俺は調べたのだが、術そのものの難易度はさほど高くはなかった。
難しいのは、人体と一部融合させ、意のままに動くよう仕立てる過程。特に接着の段階では莫大な魔力を要し、足りなければ急性魔力虚脱に陥る。
オベールなら義足を「作る」こと自体は朝飯前だろう。問題は、その後。身体とどう折り合わせるか、ということなのだ。ふと考える。他の医師が作ったとしたら、オベールが見せたような素早い動きを果たして実現できるのだろうか。単なる技術だけでは到底及ばない、才と魔力の桁の違いがそこにあるように思えてならない。
ボンシャンの膨大な魔力量があって初めて成り立つ仕組みを真似るのは難しい。
努力と研鑽を重ねてなお、オベールやカナードのような優秀な魔術師ですら決して追いつけない領域――それは理不尽なほどに、生まれ持った才の差を思わせる。
「くそっ。こんなもん、その辺の木切れでもくくり付けておけば充分だ」
吐き捨てるような言葉が、あまりに整った顔立ちと不釣り合いで、場に微かな違和感を落とした。
「任務に支障が出ます」
「俺の足一本で支障? 笑わせるな」
オベールは肩をすくめ、投げやりに言い放つ。その無頓着さが、かえって頑なさを際立たせていた。
「……お二人のことは、お二人のことです」表情を消したまま、カナードは淡々と続ける。「ですが、その確執が私たちに影を及ぼすことだけは、どうかご容赦願いたい」
その声音は冷ややかに平坦で、諫めとも牽制ともつかない――だが確かに、重さをもって場に沈んだ。
「ロイク・アランティゴス・モロー!」オベールが隣の隊長に向けて、ぞんざいに言い放つ。「お前、ジャンの数少ない友達で、しかも、元同じ寮で同級だろう。殴れ」
「えー、嫌っスよー」
モローは即答した。肩を貸したまま、呆れ顔でため息をつく。
長身細身の体躯に短く刈った栗色の髪。どこか人懐っこい目元が印象的で、飾らない雰囲気を纏い、気難しい相手のそばでも平然とマイペースでいられる――そんなタイプの男だ。上も下もつい甘やかしてしまうような愛嬌もあり、カッコいいというより、可愛い印象を与える。
「自分で殴って下さい」
「俺が、可愛い後輩を殴れるか」
「その可愛い後輩を、今、俺に殴れって言いましたよね?」
皮肉っぽくモローが笑うと、オベールは、ふんっとふてくされたように鼻で返した。
「ロイク……、その人を早く救護室へ連れて行ってください」カナードは声のトーンを落とし、地を這うように低く、ぼそっと付け加えた。「……人の友人関係をどうこう言えるほど、あなたも交遊が広いわけではないでしょう」
一瞬の静寂とともに誰もが息を呑み、口を挟めずにいる中、モローだけが肩を震わせ、はははと軽快に声を出して笑って見せた。自然な仕草に重苦しい空気が少しだけ和らぐ。
「了ー解ー」
モローは頷き、反対側で顔を引きつらせながら支えているデュラン副警備官と視線を交わす。
彼は、役職と見た目から考えるとデュボアと同年代くらいだろうか。短髪の黒髪に上品な顔立ち。転生前の俺の母がよく言っていた「シュッとしてはる」タイプそのもの。物静かな雰囲気は、どこか日本の平安貴族を彷彿とさせる。
真面目そうな中間管理職の男――。
気の毒に……。
二人はオベールの体をしっかりと支え直すと、ゆっくりと歩を進め、その場を離れた。
「ジャン、また今夜なー」
去り際に、モローは何気ない調子で振り返り、カナードへそう声をかけた。そのカナードも小さく片手を上げ、頷いている。
本当に友達だったんだ……。いや、彼に友達がいたこと自体にじゃない。正反対なタイプの二人が友達だなんて、と思っただけで――、
驚きのあまり顔に出ていたのだろうか。カナードが俺を見ている。いや、見据えている。視線が痛い。
そして、モローは俺とアルチュールの方を向き、最後に軽く手を挙げて一言。
「お二人さん、凄かったねー。危なげなく決めてくれて助かったよ。ジャン、あまり叱らないでやってくれよー」
モローの声は明るく、軽やかだった。その調子のまま、彼はデュランと共にオベールを支えて歩み去っていく。
三人の背中が、ゆっくりと遠ざかり、静けさが戻った。
目の前には、ほほ笑むカナード。
……えっ、笑ってる?
唇が笑みの形をしているのに目は全く笑っていなかった。その違和感が、余計にぞっとさせる。
カナードは、冷ややかな美貌を持つ男――『ドメーヌ・ル・ワンジェ王国の薔薇 金の君と黒の騎士』を読んでいた時、俺の中では、同じく人を寄せつけぬ輝きを纏うセレスタンと同じ円に分類されていた。
撫でつけられた薄茶色の髪は、あえて魅力を抑えるかのような偽りの装い。微かに色の入った伊達眼鏡は、限りなく銀に近い藍白色の瞳を少しでも隠すためのもの。人を惹きつけずにはいられない、その稀な色彩を誤魔化すように薄い硝子を瞳にまとわせている。
学院時代、その聡明さと美貌ゆえに、彼は近寄りがたい美少年として知られ、影で『月下美人』と呼ばれていた。今もなお、眼鏡を外し髪を下ろせば、誰もが息を呑むほどの美しさを隠し持っている。
転生前の世界で、俺はよく彼を題材にした二次創作をコミケで見かけた。
夜更けに課題を提出に来たレスポワール寮の生徒が、拡張ポストにレポートを入れようとしたところ、偶然内側から扉が開き、シャワー上がりで髪を下ろし、眼鏡を外したカナードと鉢合わせしてしまう。そこで心臓を射抜かれ、夢中になる年下生徒攻めと年上インテリ教師受けの物語――あれはなかなか良かった。
もっとも、この世界の彼は、今のところフィクションの甘い幻想など寄せつけぬ、ひたすら真面目でストイックな人物――といったところか。
その冷たく整った姿と視線のひとつひとつが今、無言の威圧となってこちらに迫ってくるのだからたまったものではない。
背筋に冷たいものが走る。怖い。
そうだよな。俺とアルチュールがしたことは、誰がどう見ても無茶だ。
結果が良ければ全てが良し――そんな甘い話ではない。たとえ成功したとしても、そこに至るまでの危うさや軽率さは、責められるべき。
弁解の余地はなく、叱責は免れまい。
周囲には、地下から出てきた生徒たちが群れ、遠巻きに俺たちを窺っていた。ひそひそと囁き交わす声が揺れる。
昔からほぼ全員と顔見知りではあるが――もちろん、それはセレスタンの過去の交友関係であって、俺が築いたものではない――、中でもそこそこ親交のある生徒の顔が確認でき、最近、水属性の授業で頻繁に話すようになった者たちと一緒になって「セレス!」や「銀の君!」と声をかけ手を振って来た。ほんと、やめて欲しい。
俺じゃない。アルチュール・ド・シルエットを絶賛しろ。
目の前では、数名の騎士が瓦礫を踏み分け、再び石に戻ったガーゴイルの残骸を調べている。
戦闘の爪痕を刻んだまま砕けた外殻は、ところどころ肉体の痕跡を帯びたまま固まり、異様な断面を見せていた。散乱した欠片を袋に詰め、騎士たちが砕片の軌跡を慎重に追う。
旧礼拝堂にも人が続々と入っていく。交代に中から出てくる者の表情は硬い。何が起きたのかを理解したのだろう。
そのとき、デュボアとカナードが同時に振り返り、集まってきた生徒たちの方へ視線を向けた。
「おいお前達、一旦、寮室に戻れ。一年は現在、主の居ない伝書使を含め、ちゃんと保護しろ」
「全員、部屋に戻っていなさい。あとで連絡します。気分が悪い者がいれば、誰かが付き添って医務室へ行くように。尚、エドマンド・アショーカが運び込まれています。医務室、救護室近辺ではくれぐれも静かに行動を!」
二人が声を張り上げると、生徒たちはびくりと肩を震わせ、蜘蛛の子を散らすように群れを解いた。
騒ぎが収まると、デュボアは重く息を吐き、胸元から奇石を取り出した。
「フェルマ・ヴォカ」
直ぐにノクスからの返答があった。
《なんだ、ヴィクター》
「二、三年の伝書使たちは、ゾンブル閣下の指揮下に入り、時計塔の小屋で待機と伝えてくれ。まだ通達は来てないが、今からこの上空は、騎士が連れてきた何羽か知らないが、彼らの伝書使の領域となり、鑑識が行われるだろう」
《了解》
「セレ」
通信を終えると、デュボアはゆっくりとこちらに向き直り、表情を整えた。
「さて――お前達に話がある」
その低い声は、ひどく嫌な前触れのように響いた。
カナードは表情を変えぬままうなずき、俺とアルチュールをまっすぐに見据える。
「無断で戦いの場に出てきた件、詳しく伺います。……移動しましょう」
叱られることに覚悟はできている。だが、もしも処罰を受けることになったら――今更ながら、巻き込んでしまったアルチュールに申し訳なく思う。
横を歩く彼に、思わず小声でつぶやいた。
「……ごめんな。俺が「行こう」なんて言ってしまって」
アルチュールは首を振り、かすかな声で答える。
「違う。俺は、自分一人でも来ていた。……エドマンドのことがあるから」
ああ……、この男はそうだったな。手の届く範囲のものなら、必死なって守ろうとする――さすが、俺の最推しだ。
歩きながら、彼の手にそっと触れた。アルチュールはわずかに目を見開き、驚いたようにこちらを見たが、すぐにぎこちなくも力強く握り返してきた。
自然と視線が合い、短い沈黙のあいだに互いの心の動きを確かめ合う。やがて、どちらからともなく手を離した。
「アショーカ先輩は、きっと大丈夫だ……」
俺は、囁くように伝えた。
ここは王立寄宿制男子校ゼコールリッツ学院。実質、士官学校で、最精鋭部隊養成所最高峰。
つまり教える側に、
「魔術師も治療師も医師も揃っている」
歩き出して少しすると、頭上をひときわ鋭い羽音がかすめ、振り仰ぐと一羽の伝書使が旋回し、勢いよく舞い降りてきた。
「……ヤン!」
デュボアが名を呼ぶと、コルネイユは小さく鳴き、彼のもとへ一直線に向かった。デュボアは肘を曲げ、ためらいなく腕を高く掲げる。荒っぽい仕草にもかかわらず、差し出された手にヤンが羽ばたきを収めてとまった。
「主、リュドヴィック・シルヴァン・オベール警備官からの伝言だ」
ヤンのくぐもった声が響く。
俺とアルチュールは、思わず顔を見合わせた。この伝書使は、オベールの従者だ。
「――君たち、俺の剣に何をした? 後で話を聞く。そっちが終わったら、その腰の剣をぶら下げたまま管理室に来い」
告げ終えるとヤンは一瞬、にやりと笑い、再び翼を広げ飛び去っていった。
その場には、デュボアとカナード、そして俺とアルチュールだけが取り残される。
しん、とした沈黙の中で、誰より先に口を開いたのはデュボアだった。
「……二重に叱ることになりそうだな」
༺ ༒ ༻
その後、俺たちはデュボアの自室に連れていかれ、こっぴどく叱られた。
途中で一人の騎士に引率されたリシャールとナタンも参加し、四人揃って注意を受けることになった。勝手に戦場へ飛び出し、オベールの剣を弄り、倉庫から弓を持ち出したこと――全てが問題視される。口調は厳しいが、どこか冷静で、必要以上の叱責ではなかった。
課題として、後日レポート提出と訓練での追加演習が課せられることになったが、停学や重い処罰ではなく、戒めとしては正直、軽いと俺は感じた。多分、この処置には学院側の配慮があったのだろう。なにせ王太子殿下が、俺たちと一緒になって倉庫から弓を無断で持ち出していたのだから。
デュボアとカナードからの指導が一区切りつき、部屋を出ると、廊下の向こうからレオがやって来た。彼もまた、今回の一件で叱責を受ける対象である。
「レオ! アショーカ先輩は?」
「エドマンドは?」
思わず駆け寄って訊ねる俺とアルチュールに、レオは深く息を吐く。
「命は取りとめた。命だけは――」
その言葉に、俺もアルチュールも胸を撫で下ろす。特にアルチュールは、肩の力を抜き、ほっとした表情を浮かべた。
しかし、レオの顔がすぐに陰った。
「怪我はありませんか」
カナードは静かに歩み寄り、デュボアの顔に視線を向けた。
「ああ、大丈夫だ」
応じる声は低く、落ち着いている。鋭い輪郭と精悍な眼差しが、その答えに説得力を添えていた。
「相変わらず、頑丈ですね」
「まあ、それぐらいしか取り柄がないからな」
短く答えて胸を張るデュボアの姿には、荒々しさよりも凛とした美しさがあった。カナードが軽く微笑む。
「ご謙遜を。頑丈さに加えて、冷静さと勇気も先生の取り柄でしょう。子供たちを守ってくれて、ありがとうございます」
そして、傍らに控えるガーロンへカナードの視線が流れる。
「……あなたもよく耐えてくれました。カリュストから逐一、報告を受けています。ご主人を支え、子供たちを守ってくれた。立派な働きです」
ガーロンは低く喉を鳴らし、ほんのわずかに鼻先を上げて誇らしげに応えた。
次にカナードの目がオベールに向けられる。
「……その足のことは、既に私からカリュスト、そこからボンシャン先生の伝書使オレリアンへ、そしてご本人に伝わっています」
デュボアもにっこりと笑い、オベールに向かって言った。
「俺もノクスに頼んで、オレリアンへ伝言を届けてもらった。急いで戻って来るらしい」
オベールはかすかに肩をすくめ、あっけらかんと答えた。
「医者に直させればいい。別にあいつに直してもらう必要はないからな」
それを聞いたカナードは、わずかに目を細め、息を吐く。
オベールは無言で笑みを浮かべた。まるで忌々しい足を失って清々しいとでも言いたげな――いや、そもそも最初からどうでもいいと言わんばかりの、冷めきった笑みだった。
「直す医師などいないでしょう。あの先生の作品を誰が触りますか?」わずかに間を置き、言葉を継ぐ。「しかも、アルケ・ビスクですよ? フラフラで何日か仕事に支障が出ます。私にはできません。また、ご存知の通り、ボンシャン先生は自分の作ったものに他人の手が触れることを、好みませんし。特に、あなたに関しては」
カナードは言いながら、静かにオベールの目を見据える。
――オベールから直接、義足と義手の話を聞いたときに、アルケ・ビスクの名が出てきた。あとで気になって、俺は調べたのだが、術そのものの難易度はさほど高くはなかった。
難しいのは、人体と一部融合させ、意のままに動くよう仕立てる過程。特に接着の段階では莫大な魔力を要し、足りなければ急性魔力虚脱に陥る。
オベールなら義足を「作る」こと自体は朝飯前だろう。問題は、その後。身体とどう折り合わせるか、ということなのだ。ふと考える。他の医師が作ったとしたら、オベールが見せたような素早い動きを果たして実現できるのだろうか。単なる技術だけでは到底及ばない、才と魔力の桁の違いがそこにあるように思えてならない。
ボンシャンの膨大な魔力量があって初めて成り立つ仕組みを真似るのは難しい。
努力と研鑽を重ねてなお、オベールやカナードのような優秀な魔術師ですら決して追いつけない領域――それは理不尽なほどに、生まれ持った才の差を思わせる。
「くそっ。こんなもん、その辺の木切れでもくくり付けておけば充分だ」
吐き捨てるような言葉が、あまりに整った顔立ちと不釣り合いで、場に微かな違和感を落とした。
「任務に支障が出ます」
「俺の足一本で支障? 笑わせるな」
オベールは肩をすくめ、投げやりに言い放つ。その無頓着さが、かえって頑なさを際立たせていた。
「……お二人のことは、お二人のことです」表情を消したまま、カナードは淡々と続ける。「ですが、その確執が私たちに影を及ぼすことだけは、どうかご容赦願いたい」
その声音は冷ややかに平坦で、諫めとも牽制ともつかない――だが確かに、重さをもって場に沈んだ。
「ロイク・アランティゴス・モロー!」オベールが隣の隊長に向けて、ぞんざいに言い放つ。「お前、ジャンの数少ない友達で、しかも、元同じ寮で同級だろう。殴れ」
「えー、嫌っスよー」
モローは即答した。肩を貸したまま、呆れ顔でため息をつく。
長身細身の体躯に短く刈った栗色の髪。どこか人懐っこい目元が印象的で、飾らない雰囲気を纏い、気難しい相手のそばでも平然とマイペースでいられる――そんなタイプの男だ。上も下もつい甘やかしてしまうような愛嬌もあり、カッコいいというより、可愛い印象を与える。
「自分で殴って下さい」
「俺が、可愛い後輩を殴れるか」
「その可愛い後輩を、今、俺に殴れって言いましたよね?」
皮肉っぽくモローが笑うと、オベールは、ふんっとふてくされたように鼻で返した。
「ロイク……、その人を早く救護室へ連れて行ってください」カナードは声のトーンを落とし、地を這うように低く、ぼそっと付け加えた。「……人の友人関係をどうこう言えるほど、あなたも交遊が広いわけではないでしょう」
一瞬の静寂とともに誰もが息を呑み、口を挟めずにいる中、モローだけが肩を震わせ、はははと軽快に声を出して笑って見せた。自然な仕草に重苦しい空気が少しだけ和らぐ。
「了ー解ー」
モローは頷き、反対側で顔を引きつらせながら支えているデュラン副警備官と視線を交わす。
彼は、役職と見た目から考えるとデュボアと同年代くらいだろうか。短髪の黒髪に上品な顔立ち。転生前の俺の母がよく言っていた「シュッとしてはる」タイプそのもの。物静かな雰囲気は、どこか日本の平安貴族を彷彿とさせる。
真面目そうな中間管理職の男――。
気の毒に……。
二人はオベールの体をしっかりと支え直すと、ゆっくりと歩を進め、その場を離れた。
「ジャン、また今夜なー」
去り際に、モローは何気ない調子で振り返り、カナードへそう声をかけた。そのカナードも小さく片手を上げ、頷いている。
本当に友達だったんだ……。いや、彼に友達がいたこと自体にじゃない。正反対なタイプの二人が友達だなんて、と思っただけで――、
驚きのあまり顔に出ていたのだろうか。カナードが俺を見ている。いや、見据えている。視線が痛い。
そして、モローは俺とアルチュールの方を向き、最後に軽く手を挙げて一言。
「お二人さん、凄かったねー。危なげなく決めてくれて助かったよ。ジャン、あまり叱らないでやってくれよー」
モローの声は明るく、軽やかだった。その調子のまま、彼はデュランと共にオベールを支えて歩み去っていく。
三人の背中が、ゆっくりと遠ざかり、静けさが戻った。
目の前には、ほほ笑むカナード。
……えっ、笑ってる?
唇が笑みの形をしているのに目は全く笑っていなかった。その違和感が、余計にぞっとさせる。
カナードは、冷ややかな美貌を持つ男――『ドメーヌ・ル・ワンジェ王国の薔薇 金の君と黒の騎士』を読んでいた時、俺の中では、同じく人を寄せつけぬ輝きを纏うセレスタンと同じ円に分類されていた。
撫でつけられた薄茶色の髪は、あえて魅力を抑えるかのような偽りの装い。微かに色の入った伊達眼鏡は、限りなく銀に近い藍白色の瞳を少しでも隠すためのもの。人を惹きつけずにはいられない、その稀な色彩を誤魔化すように薄い硝子を瞳にまとわせている。
学院時代、その聡明さと美貌ゆえに、彼は近寄りがたい美少年として知られ、影で『月下美人』と呼ばれていた。今もなお、眼鏡を外し髪を下ろせば、誰もが息を呑むほどの美しさを隠し持っている。
転生前の世界で、俺はよく彼を題材にした二次創作をコミケで見かけた。
夜更けに課題を提出に来たレスポワール寮の生徒が、拡張ポストにレポートを入れようとしたところ、偶然内側から扉が開き、シャワー上がりで髪を下ろし、眼鏡を外したカナードと鉢合わせしてしまう。そこで心臓を射抜かれ、夢中になる年下生徒攻めと年上インテリ教師受けの物語――あれはなかなか良かった。
もっとも、この世界の彼は、今のところフィクションの甘い幻想など寄せつけぬ、ひたすら真面目でストイックな人物――といったところか。
その冷たく整った姿と視線のひとつひとつが今、無言の威圧となってこちらに迫ってくるのだからたまったものではない。
背筋に冷たいものが走る。怖い。
そうだよな。俺とアルチュールがしたことは、誰がどう見ても無茶だ。
結果が良ければ全てが良し――そんな甘い話ではない。たとえ成功したとしても、そこに至るまでの危うさや軽率さは、責められるべき。
弁解の余地はなく、叱責は免れまい。
周囲には、地下から出てきた生徒たちが群れ、遠巻きに俺たちを窺っていた。ひそひそと囁き交わす声が揺れる。
昔からほぼ全員と顔見知りではあるが――もちろん、それはセレスタンの過去の交友関係であって、俺が築いたものではない――、中でもそこそこ親交のある生徒の顔が確認でき、最近、水属性の授業で頻繁に話すようになった者たちと一緒になって「セレス!」や「銀の君!」と声をかけ手を振って来た。ほんと、やめて欲しい。
俺じゃない。アルチュール・ド・シルエットを絶賛しろ。
目の前では、数名の騎士が瓦礫を踏み分け、再び石に戻ったガーゴイルの残骸を調べている。
戦闘の爪痕を刻んだまま砕けた外殻は、ところどころ肉体の痕跡を帯びたまま固まり、異様な断面を見せていた。散乱した欠片を袋に詰め、騎士たちが砕片の軌跡を慎重に追う。
旧礼拝堂にも人が続々と入っていく。交代に中から出てくる者の表情は硬い。何が起きたのかを理解したのだろう。
そのとき、デュボアとカナードが同時に振り返り、集まってきた生徒たちの方へ視線を向けた。
「おいお前達、一旦、寮室に戻れ。一年は現在、主の居ない伝書使を含め、ちゃんと保護しろ」
「全員、部屋に戻っていなさい。あとで連絡します。気分が悪い者がいれば、誰かが付き添って医務室へ行くように。尚、エドマンド・アショーカが運び込まれています。医務室、救護室近辺ではくれぐれも静かに行動を!」
二人が声を張り上げると、生徒たちはびくりと肩を震わせ、蜘蛛の子を散らすように群れを解いた。
騒ぎが収まると、デュボアは重く息を吐き、胸元から奇石を取り出した。
「フェルマ・ヴォカ」
直ぐにノクスからの返答があった。
《なんだ、ヴィクター》
「二、三年の伝書使たちは、ゾンブル閣下の指揮下に入り、時計塔の小屋で待機と伝えてくれ。まだ通達は来てないが、今からこの上空は、騎士が連れてきた何羽か知らないが、彼らの伝書使の領域となり、鑑識が行われるだろう」
《了解》
「セレ」
通信を終えると、デュボアはゆっくりとこちらに向き直り、表情を整えた。
「さて――お前達に話がある」
その低い声は、ひどく嫌な前触れのように響いた。
カナードは表情を変えぬままうなずき、俺とアルチュールをまっすぐに見据える。
「無断で戦いの場に出てきた件、詳しく伺います。……移動しましょう」
叱られることに覚悟はできている。だが、もしも処罰を受けることになったら――今更ながら、巻き込んでしまったアルチュールに申し訳なく思う。
横を歩く彼に、思わず小声でつぶやいた。
「……ごめんな。俺が「行こう」なんて言ってしまって」
アルチュールは首を振り、かすかな声で答える。
「違う。俺は、自分一人でも来ていた。……エドマンドのことがあるから」
ああ……、この男はそうだったな。手の届く範囲のものなら、必死なって守ろうとする――さすが、俺の最推しだ。
歩きながら、彼の手にそっと触れた。アルチュールはわずかに目を見開き、驚いたようにこちらを見たが、すぐにぎこちなくも力強く握り返してきた。
自然と視線が合い、短い沈黙のあいだに互いの心の動きを確かめ合う。やがて、どちらからともなく手を離した。
「アショーカ先輩は、きっと大丈夫だ……」
俺は、囁くように伝えた。
ここは王立寄宿制男子校ゼコールリッツ学院。実質、士官学校で、最精鋭部隊養成所最高峰。
つまり教える側に、
「魔術師も治療師も医師も揃っている」
歩き出して少しすると、頭上をひときわ鋭い羽音がかすめ、振り仰ぐと一羽の伝書使が旋回し、勢いよく舞い降りてきた。
「……ヤン!」
デュボアが名を呼ぶと、コルネイユは小さく鳴き、彼のもとへ一直線に向かった。デュボアは肘を曲げ、ためらいなく腕を高く掲げる。荒っぽい仕草にもかかわらず、差し出された手にヤンが羽ばたきを収めてとまった。
「主、リュドヴィック・シルヴァン・オベール警備官からの伝言だ」
ヤンのくぐもった声が響く。
俺とアルチュールは、思わず顔を見合わせた。この伝書使は、オベールの従者だ。
「――君たち、俺の剣に何をした? 後で話を聞く。そっちが終わったら、その腰の剣をぶら下げたまま管理室に来い」
告げ終えるとヤンは一瞬、にやりと笑い、再び翼を広げ飛び去っていった。
その場には、デュボアとカナード、そして俺とアルチュールだけが取り残される。
しん、とした沈黙の中で、誰より先に口を開いたのはデュボアだった。
「……二重に叱ることになりそうだな」
༺ ༒ ༻
その後、俺たちはデュボアの自室に連れていかれ、こっぴどく叱られた。
途中で一人の騎士に引率されたリシャールとナタンも参加し、四人揃って注意を受けることになった。勝手に戦場へ飛び出し、オベールの剣を弄り、倉庫から弓を持ち出したこと――全てが問題視される。口調は厳しいが、どこか冷静で、必要以上の叱責ではなかった。
課題として、後日レポート提出と訓練での追加演習が課せられることになったが、停学や重い処罰ではなく、戒めとしては正直、軽いと俺は感じた。多分、この処置には学院側の配慮があったのだろう。なにせ王太子殿下が、俺たちと一緒になって倉庫から弓を無断で持ち出していたのだから。
デュボアとカナードからの指導が一区切りつき、部屋を出ると、廊下の向こうからレオがやって来た。彼もまた、今回の一件で叱責を受ける対象である。
「レオ! アショーカ先輩は?」
「エドマンドは?」
思わず駆け寄って訊ねる俺とアルチュールに、レオは深く息を吐く。
「命は取りとめた。命だけは――」
その言葉に、俺もアルチュールも胸を撫で下ろす。特にアルチュールは、肩の力を抜き、ほっとした表情を浮かべた。
しかし、レオの顔がすぐに陰った。
100
あなたにおすすめの小説

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新

悪役令嬢の兄に転生!破滅フラグ回避でスローライフを目指すはずが、氷の騎士に溺愛されてます
水凪しおん
BL
三十代半ばの平凡な会社員だった俺は、ある日、乙女ゲーム『君と紡ぐ光の協奏曲』の世界に転生した。
しかも、最推しの悪役令嬢リリアナの兄、アシェルとして。
このままでは妹は断罪され、一家は没落、俺は処刑される運命だ。
そんな未来は絶対に回避しなくてはならない。
俺の夢は、穏やかなスローライフを送ること。ゲームの知識を駆使して妹を心優しい少女に育て上げ、次々と破滅フラグをへし折っていく。
順調に進むスローライフ計画だったが、関わると面倒な攻略対象、「氷の騎士」サイラスになぜか興味を持たれてしまった。
家庭菜園にまで現れる彼に困惑する俺。
だがそれはやがて、国を揺るがす陰謀と、甘く激しい恋の始まりを告げる序曲に過ぎなかった――。

悪役キャラに転生したので破滅ルートを死ぬ気で回避しようと思っていたのに、何故か勇者に攻略されそうです
菫城 珪
BL
サッカーの練習試合中、雷に打たれて目が覚めたら人気ゲームに出て来る破滅確約悪役ノアの子供時代になっていた…!
苦労して生きてきた勇者に散々嫌がらせをし、魔王軍の手先となって家族を手に掛け、最後は醜い怪物に変えられ退治されるという最悪の未来だけは絶対回避したい。
付き纏う不安と闘い、いずれ魔王と対峙する為に研鑽に励みつつも同級生である勇者アーサーとは距離を置いてをなるべく避ける日々……だった筈なのになんかどんどん距離が近くなってきてない!?
そんな感じのいずれ勇者となる少年と悪役になる筈だった少年によるBLです。
のんびり連載していきますのでよろしくお願いします!
※小説家になろう、アルファポリス、カクヨムエブリスタ各サイトに掲載中です。
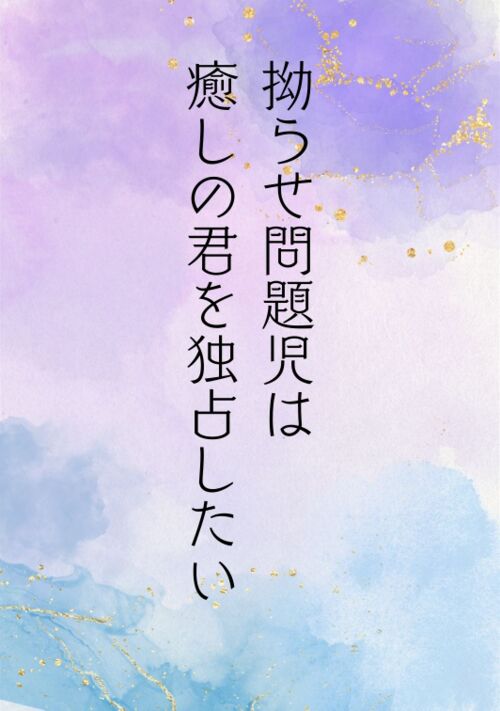
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

異世界で孵化したので全力で推しを守ります
のぶしげ
BL
ある日、聞いていたシチュエーションCDの世界に転生してしまった主人公。推しの幼少期に出会い、魔王化へのルートを回避して健やかな成長をサポートしよう!と奮闘していく異世界転生BL 執着最強×人外美人BL

魔王の息子を育てることになった俺の話
お鮫
BL
俺が18歳の時森で少年を拾った。その子が将来魔王になることを知りながら俺は今日も息子としてこの子を育てる。そう決意してはや数年。
「今なんつった?よっぽど死にたいんだね。そんなに俺と離れたい?」
現在俺はかわいい息子に殺害予告を受けている。あれ、魔王は?旅に出なくていいの?とりあえず放してくれません?
魔王になる予定の男と育て親のヤンデレBL
BLは初めて書きます。見ずらい点多々あるかと思いますが、もしありましたら指摘くださるとありがたいです。
BL大賞エントリー中です。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















