6 / 74
File.01 闇色の秘密
赤い闇の世界で
しおりを挟む
彼に触れた指先から、赤い闇が溢れた。それは刹那に全てを覆い尽くし、私の世界を塗り潰した。
血の霧が漂うように、重たく濁った大気が辺りを満たしている。腐食した鉄と、生臭い肉の匂いが鼻を突く。赤黒い闇の中で光はねじれ、遠くの輪郭は滲み、溶け崩れていた。
正常な世界から隔絶されたような異空間で立ちくらんでいると、先ほどまで何もなかった部屋が——突如、確かな形を取り戻したように存在を顕示した。
——信じられない、夢のようだ。
男の声が聞こえて、私は室内を改めた。
広く無人だった部屋には二人の人間が立っていた。若い男女が、恋人のような距離感で見つめ合っている。眼鏡を掛けた男の指がそっと女の髪に触れると、彼女は受け入れるように瞳を閉じた。男の顔が応えるように近寄って、くちづけを——。
甘い恋人の睦み合い。経験のない私は、恋愛ドラマでも同じシーンを目にしたら頬を染めて恥じらうところだが、今ばかりは身の毛のよだつ思いで息を詰めていた。
甘やかな行為と相反して、男の足許には灰白色の人影たちが呪うように纏わっていた。
——こわい、いたい、たすけて。
人影の境界は溶けている。しかし、注視すると四人いた。一人は顔がねじれ、一人は両手がもげ……個々の影は歪み崩れているが、たしかに四つの影があった。女の足下から生えたかのように、それらは床に這いつくばった姿で男の脚に縋り、金属の擦れるような細い声をあげている。
男はまるで察していないのか、目の前の女に夢中だった。壊れ物に触れるよう慎重に女の肌を撫で、感触を味わい、男は顔に歓喜の笑みを広げた。その顔は狂気が滲んでいて、笑みというよりも何かに取り憑かれたような歪さがあった。男が笑うたび頬の筋肉が不自然に痙攣し、見ているだけで背筋が凍る。
男の狂った笑みの裏には、常識や理性などとうに捨て去った、正気の通じぬ世界が広がっていた。
——きみは、僕の理想どおり、完璧な女性だ。愛しているよ。
男の口が、偏執的な想いを零した。
向かい合う女は微笑みを崩さない。男の狂気じみた笑い顔にも、人形のように完成された淡い笑みを返していた。女は微笑みを微動だにせず、腕を広げて甘えるみたいに男の首裏へと手を回し、
ゴギッ、と。
耳に嫌な音が鳴った。
音に身を竦ませた私の目の先で、男の首に女の細い指先が食い込んでいた。恍惚としていた男の顔は一変し、目を剝いた悪魔の形相で、断末魔をあげることなく息絶えていた。命を終えた身体が、手を離した女の目前を崩れ落ちていく。
——こわい、いたい、たすけて、かえして。
足許の人影たちが、さざめきながら男の肉体に絡まっていく。耳の奥を這う細声に、女の声が重なった。
——ゆるさナイ。ゼッタイに赦さなイイイイィ。
壊れた、オルゴール人形のようだった。
女の声は金属を擦るような悲鳴となって私の鼓膜を引き裂き、赤黒い闇の隅々まで突き刺さった。つたない言葉を乗せた金切り声の余韻が消えないうちに、女は固まった笑顔で私を振り返る。ドクンっと跳ねた心臓に、私は逃げようとしたが——足が、動かない。
男の肉体に絡まっていたはずの人影たちは、いつのまにか離れて私の足に擦り寄っていた。
——たすけて、たすけて、たすけて。
触れようとするたび、見えない膜に阻まれるように弾かれ、呻きながら揺らめいている。
私の足は動こうと思えば動けるはずだ。でも、彼女らを足蹴にして逃げ出すことができない。
彼女らは、私に訴えていた。
——たすけて、たすけて、たすけて。
懸命な囁き声は、段々と軋むように変質していく。
——たすけて、たすけて、ゆるさない、ゆるさナイ。
悲痛なさざめきの声は、いつしか奥に不気味な怨念の渦が生まれ、私の意思に染み込んでいく。
——赦さない。
ハッとしたときには遅く。
気づけば視界のすべてが、女の顔に埋め尽くされていた。
それは笑顔の形をした何かだった。頬はひずみ、唇の端は不自然に吊り上がり、目は空洞のように感情を宿していない。
生きものの顔ではない。
——お姉ちゃん。
女の肩から垂れた長い髪に、妹の面影が重なってしまう。
震える足は、もう、逃げられない。
微笑んだまま近づく女の手を、私は目を閉じて覚悟し——
誰かが、私の肩を強く掴んだ。
呼び声もあった。遠くの漠然とした声が誰のものか考えていると、さまよう意識を水底から引き上げられるように、突如として私は目を醒ました。
私の視界には、金と黒の色違いの虹彩があった。
「あ……捜査官さん……?」
掴まれた私の肩は廊下側に引かれ、背の高い彼が横から私の顔を覗き込んでいた。焦りの見える彼の瞳を、夢が醒めたような心地で見返す。
私は部屋の境目に立っていた。微笑みの女は跡形もなく、足許の人影や辺りの赤い闇さえも消え失せていた。
「私、いま……」
恐ろしい白昼夢を、見たような。
冷えきっていた手足に満ちる現実感を確かめるように、私は胸の前で両の拳を握りしめる。体に異変はない。いま見たものは、なんだったのか。不可解な現象を消化できず、茫然として彼の瞳を見つめていた。
向かいの双眸は、緊張を解いて私に尋ねた。
「お前、俺に同調した?」
「……どうちょう?」
「あ~、なんつぅの? シンクロ、共振、共鳴……あ、俺に重なった?」
「重なる……?」
私が首をかしげると、彼も眉間を狭めて首をかしげた。他人の家の廊下で、よく知らぬ相手と鏡合わせに頭を傾ける姿は滑稽な気がする。
彼も似たようなことを思ったらしく、肩をすくめて吐息を鳴らした。
「ま、いっか。答えは分かった。戻ろ」
くるっと回る彼の身体に、手錠の鎖が引かれる。(私はいつまで繋がれていないといけないのだ)不満を抱きかけて、自分が一緒にいることを願ったのだと思い出した。
「あのっ……警視庁に行くなら、手錠はもう外してもらっても……!」
繋がった状態で階段を下りるのは危ない。しかし、申し入れは例のごとく届いていなかったので、階段を足早に下りていく彼のスピードに合わせられず、私は段差を踏み外した。
「わっ」
前のめりになった私の身体は、振り向きざまの彼にあっさりと片手で受け止められた。背中にも目があるみたいな反応速度だった。
私が転びかけたことなんて大したことではないらしく、彼は事もなげに「警視庁は行かねぇけど?」数秒遅れで会話を成立させる。私は彼の腕にしがみついてしまっていた身を起こした。
「えっ……あ、もしかして検察のほうですか?」
「検察~? お前、俺の自己紹介、ちゃんと聞いてなかったな?」
いや、聞いてた。捜査官であると、きちんと聞いていたから警視庁と検察を挙げたのだ。
階段の差で近くに並んだ金の眼に、私は疑問の目を投げかける。ならば、どこへ行くのか。無言の問いを受けた彼は、唇を自嘲じみた薄い笑みの形にした。
「特異事件捜査室」
トクイジケンソウサシツ。絡みつく声が呪文を奏でる。脳裏で復唱する私は意味を拾いきれず、曲がる唇をきょとりと見つめた。
頭上の窓から降りそそぐ陽光が、赤銅色の髪を明るく染める。
笑う唇とは裏腹に、金の眼は冷ややかに輝いていた。
血の霧が漂うように、重たく濁った大気が辺りを満たしている。腐食した鉄と、生臭い肉の匂いが鼻を突く。赤黒い闇の中で光はねじれ、遠くの輪郭は滲み、溶け崩れていた。
正常な世界から隔絶されたような異空間で立ちくらんでいると、先ほどまで何もなかった部屋が——突如、確かな形を取り戻したように存在を顕示した。
——信じられない、夢のようだ。
男の声が聞こえて、私は室内を改めた。
広く無人だった部屋には二人の人間が立っていた。若い男女が、恋人のような距離感で見つめ合っている。眼鏡を掛けた男の指がそっと女の髪に触れると、彼女は受け入れるように瞳を閉じた。男の顔が応えるように近寄って、くちづけを——。
甘い恋人の睦み合い。経験のない私は、恋愛ドラマでも同じシーンを目にしたら頬を染めて恥じらうところだが、今ばかりは身の毛のよだつ思いで息を詰めていた。
甘やかな行為と相反して、男の足許には灰白色の人影たちが呪うように纏わっていた。
——こわい、いたい、たすけて。
人影の境界は溶けている。しかし、注視すると四人いた。一人は顔がねじれ、一人は両手がもげ……個々の影は歪み崩れているが、たしかに四つの影があった。女の足下から生えたかのように、それらは床に這いつくばった姿で男の脚に縋り、金属の擦れるような細い声をあげている。
男はまるで察していないのか、目の前の女に夢中だった。壊れ物に触れるよう慎重に女の肌を撫で、感触を味わい、男は顔に歓喜の笑みを広げた。その顔は狂気が滲んでいて、笑みというよりも何かに取り憑かれたような歪さがあった。男が笑うたび頬の筋肉が不自然に痙攣し、見ているだけで背筋が凍る。
男の狂った笑みの裏には、常識や理性などとうに捨て去った、正気の通じぬ世界が広がっていた。
——きみは、僕の理想どおり、完璧な女性だ。愛しているよ。
男の口が、偏執的な想いを零した。
向かい合う女は微笑みを崩さない。男の狂気じみた笑い顔にも、人形のように完成された淡い笑みを返していた。女は微笑みを微動だにせず、腕を広げて甘えるみたいに男の首裏へと手を回し、
ゴギッ、と。
耳に嫌な音が鳴った。
音に身を竦ませた私の目の先で、男の首に女の細い指先が食い込んでいた。恍惚としていた男の顔は一変し、目を剝いた悪魔の形相で、断末魔をあげることなく息絶えていた。命を終えた身体が、手を離した女の目前を崩れ落ちていく。
——こわい、いたい、たすけて、かえして。
足許の人影たちが、さざめきながら男の肉体に絡まっていく。耳の奥を這う細声に、女の声が重なった。
——ゆるさナイ。ゼッタイに赦さなイイイイィ。
壊れた、オルゴール人形のようだった。
女の声は金属を擦るような悲鳴となって私の鼓膜を引き裂き、赤黒い闇の隅々まで突き刺さった。つたない言葉を乗せた金切り声の余韻が消えないうちに、女は固まった笑顔で私を振り返る。ドクンっと跳ねた心臓に、私は逃げようとしたが——足が、動かない。
男の肉体に絡まっていたはずの人影たちは、いつのまにか離れて私の足に擦り寄っていた。
——たすけて、たすけて、たすけて。
触れようとするたび、見えない膜に阻まれるように弾かれ、呻きながら揺らめいている。
私の足は動こうと思えば動けるはずだ。でも、彼女らを足蹴にして逃げ出すことができない。
彼女らは、私に訴えていた。
——たすけて、たすけて、たすけて。
懸命な囁き声は、段々と軋むように変質していく。
——たすけて、たすけて、ゆるさない、ゆるさナイ。
悲痛なさざめきの声は、いつしか奥に不気味な怨念の渦が生まれ、私の意思に染み込んでいく。
——赦さない。
ハッとしたときには遅く。
気づけば視界のすべてが、女の顔に埋め尽くされていた。
それは笑顔の形をした何かだった。頬はひずみ、唇の端は不自然に吊り上がり、目は空洞のように感情を宿していない。
生きものの顔ではない。
——お姉ちゃん。
女の肩から垂れた長い髪に、妹の面影が重なってしまう。
震える足は、もう、逃げられない。
微笑んだまま近づく女の手を、私は目を閉じて覚悟し——
誰かが、私の肩を強く掴んだ。
呼び声もあった。遠くの漠然とした声が誰のものか考えていると、さまよう意識を水底から引き上げられるように、突如として私は目を醒ました。
私の視界には、金と黒の色違いの虹彩があった。
「あ……捜査官さん……?」
掴まれた私の肩は廊下側に引かれ、背の高い彼が横から私の顔を覗き込んでいた。焦りの見える彼の瞳を、夢が醒めたような心地で見返す。
私は部屋の境目に立っていた。微笑みの女は跡形もなく、足許の人影や辺りの赤い闇さえも消え失せていた。
「私、いま……」
恐ろしい白昼夢を、見たような。
冷えきっていた手足に満ちる現実感を確かめるように、私は胸の前で両の拳を握りしめる。体に異変はない。いま見たものは、なんだったのか。不可解な現象を消化できず、茫然として彼の瞳を見つめていた。
向かいの双眸は、緊張を解いて私に尋ねた。
「お前、俺に同調した?」
「……どうちょう?」
「あ~、なんつぅの? シンクロ、共振、共鳴……あ、俺に重なった?」
「重なる……?」
私が首をかしげると、彼も眉間を狭めて首をかしげた。他人の家の廊下で、よく知らぬ相手と鏡合わせに頭を傾ける姿は滑稽な気がする。
彼も似たようなことを思ったらしく、肩をすくめて吐息を鳴らした。
「ま、いっか。答えは分かった。戻ろ」
くるっと回る彼の身体に、手錠の鎖が引かれる。(私はいつまで繋がれていないといけないのだ)不満を抱きかけて、自分が一緒にいることを願ったのだと思い出した。
「あのっ……警視庁に行くなら、手錠はもう外してもらっても……!」
繋がった状態で階段を下りるのは危ない。しかし、申し入れは例のごとく届いていなかったので、階段を足早に下りていく彼のスピードに合わせられず、私は段差を踏み外した。
「わっ」
前のめりになった私の身体は、振り向きざまの彼にあっさりと片手で受け止められた。背中にも目があるみたいな反応速度だった。
私が転びかけたことなんて大したことではないらしく、彼は事もなげに「警視庁は行かねぇけど?」数秒遅れで会話を成立させる。私は彼の腕にしがみついてしまっていた身を起こした。
「えっ……あ、もしかして検察のほうですか?」
「検察~? お前、俺の自己紹介、ちゃんと聞いてなかったな?」
いや、聞いてた。捜査官であると、きちんと聞いていたから警視庁と検察を挙げたのだ。
階段の差で近くに並んだ金の眼に、私は疑問の目を投げかける。ならば、どこへ行くのか。無言の問いを受けた彼は、唇を自嘲じみた薄い笑みの形にした。
「特異事件捜査室」
トクイジケンソウサシツ。絡みつく声が呪文を奏でる。脳裏で復唱する私は意味を拾いきれず、曲がる唇をきょとりと見つめた。
頭上の窓から降りそそぐ陽光が、赤銅色の髪を明るく染める。
笑う唇とは裏腹に、金の眼は冷ややかに輝いていた。
71
あなたにおすすめの小説

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。
沼野 花
恋愛
夫と子供たちに、選ばれなかったイネス。
すべてを愛人に奪われ、彼女は限界を迎え、屋敷を去る。
だが、その先に待っていたのは、救いではなかった。
イネスを襲った、取り返しのつかない出来事。
変わり果てた現実を前に、
夫はようやく、自分が何を失ったのかを思い知る。
深い後悔と悲しみに苛まれながら、
失ったイネスの心を取り戻そうとする夫。
しかし、彼女の心はすでに、外の世界へと向かっていた。
贖罪を背負いながらもイネスを求め続ける夫。
そして、母の心を知っていく子供たち。
イネスが求める愛とは、
そして、幸せとは――。
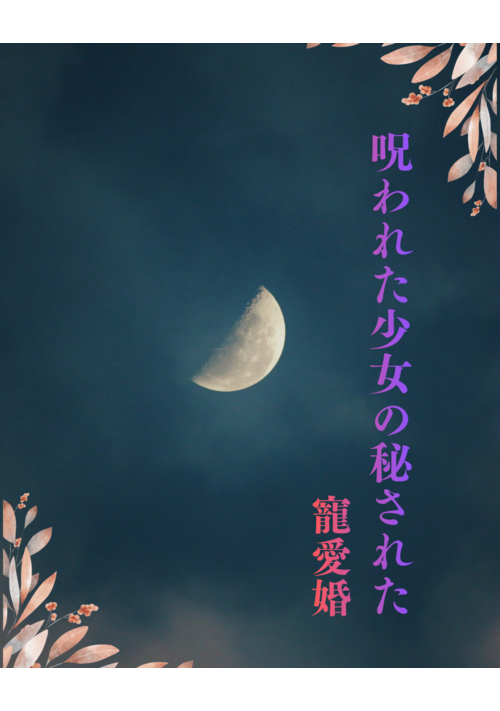
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

烏の王と宵の花嫁
水川サキ
キャラ文芸
吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。
唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。
その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。
ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。
死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。
※初出2024年7月

身代わりで呪いの公爵に嫁ぎましたが、聖女の力で浄化したら離縁どころか国一番の溺愛妻になりました〜実家が泣きついてももう遅い〜
しょくぱん
恋愛
「お前のような無能は、死神の生贄にでもなっていろ」
魔力なしの無能と蔑まれ、家族に虐げられてきた伯爵令嬢レティシア。 彼女に命じられたのは、近づく者すべてを病ませるという『呪いの公爵』アレクシスへの身代わり結婚だった。
鉄格子の馬車で運ばれ、たどり着いたのは瘴気に満ちた死の城。 恐ろしい怪物のような男に殺される――。 そう覚悟していたレティシアだったが、目の前の光景に絶望よりも先に別の感情が湧き上がる。
(な、何これ……汚すぎるわ! 雑巾とブラシはどこ!?)
実は、彼女が「無能」と言われていたのは、その力が『洗浄』と『浄化』に特化した特殊な聖女の魔力だったから。
レティシアが掃除をすれば、呪いの瘴気は消え去り、枯れた大地には花が咲き、不気味だった公爵城はまたたく間にピカピカの聖域に塗り替えられていく。 さらには、呪いで苦しんでいたアレクシスの素顔は、見惚れるほどの美青年で――。
「レティシア、君は一体何者なんだ……? 体が、こんなに軽いのは初めてだ」
冷酷だったはずの公爵様から、まさかの執着と溺愛。 さらには、呪いが解けたことで領地は国一番の豊かさを取り戻していく。
一方で、レティシアを捨てた実家は、彼女の『浄化』を失ったことで災厄に見舞われ、今さら「戻ってきてくれ」と泣きついてくるが……。
「私は今、お城の掃除と旦那様のお世話で忙しいんです。お引き取りくださいませ」
これは、掃除を愛する薄幸令嬢が、その愛と魔力で死神公爵を救い、最高に幸せな居場所を手に入れるまでのお話。

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

ママはヤンママ女子高生! ラン&ジュリー!!
オズ研究所《横須賀ストーリー紅白へ》
キャラ文芸
神崎ランの父親の再婚相手は幼馴染みで女子高生の高原ジュリーだった。
ジュリーは金髪美少女だが、地元では『ワイルドビーナス』の異名を取る有名なヤンキーだった。
学校ではジュリーは、ランを使いっ走りにしていた。
当然のようにアゴで使われたが、ジュリーは十八歳になったら結婚する事を告白した。
同級生のジュリーが結婚するなんて信じられない。
ランは密かにジュリーの事を憧れていたので、失恋した気分だ。
そう言えば、昨夜、ランの父親も再婚すると言っていた。
まさかとは思ったが、ランはジュリーに結婚相手を聞くと、ランの父親だと判明した。
その夜、改めて父親とジュリーのふたりは結婚すると報告された。
こうしてジュリーとの同居が決まった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















