10 / 77
第二章:花嫁の数奇な事情
10:餡パンと香水
しおりを挟む
可畏の肩に荷物のように抱えあげられ、賑わう通りまで戻ると馬車が用意されていた。担ぎ上げられたまま葛葉が乗りこむと、馭者台から男が振りかえる。
「可畏様、こちらが頼まれていたものです」
「いきなり呼びつけたのに、すまないな」
馭者が差し出した風呂敷を受けとると、可畏は座席でぐったりとしている葛葉の膝の上におく。
「葛葉。とりあえずそれを食え」
可畏が風呂敷をとくと、餡パンが山のように積み重なっている。酒種と餡のあまい香りを克明にかぎわけて、葛葉は反射的に身を乗りだす。
「これは! 人気のお店の餡パン!」
ふたたび腹の虫が大合唱をはじめそうだったが、可畏の視線を感じて、勢いよく手を伸ばすことを思いとどまる。
「あの、本当にいただいても?」
「おまえ、よだれがすごいことになっているぞ。その飢餓感は夜叉のせいだ。今さら遠慮をするな」
風呂敷から餡パンをひとつ掴むと、可畏が有無を言わせず葛葉の口に突っ込んだ。ふわりと広がった生地の香りとうっとりするような餡のあまさが、一瞬で葛葉の恥じらいやためらいを吹きとばす。
口に突っ込まれた餡パンをあっというまに平らげて、葛葉は素直に感謝した。
「御門様、ありがとうございます!」
「おまえに餓鬼が憑いたのは、私のせいだ。存分に食っておけ」
「はい!」
いともたやすく乙女心を放りだして、葛葉は餡パンを両手で鷲掴みにする。我を忘れてかぶりついた。
「すごく美味しいです!」
「それで復活できそうだな」
可畏が馭者へ「出してくれ」とうながすと、男が葛葉と可畏を交互に見てから、すこし戸惑った顔をした。
「どうした?」
「いえ、可畏様の使役する式鬼が届いた時に、じつは陛下からも勅使の式鬼が参られまして」
「帝から?」
「はい。陛下から可畏様へ、花嫁を伴って至急御所へ参内されるようにと」
「至急? まさか、このまま参れと?」
「おそらく」
葛葉はさらなる急展開に、頬張っていた餡パンは吹きだしそうになる。可畏がちらりと冷ややかな視線をこちらによこした。
「葛葉、今の話を聞いていたか?」
「あの、まさかとは思いますが、花嫁って……」
「おまえ以外に誰がいる」
「む、無理です! わたしが天子様の御前に参るなど!」
「これは帝の命令だ」
「御門様は皇に連なる公爵様ですよね? きっと昨夜の騒動が天子様のお耳に入ったのでは? わたしなんかを花嫁だと紹介したことについて、一門からお咎めがあるのではありませんか?」
「それはない」
「わたしはあると思います! ここは当初の予定通り紅葉様をお連れになった方が良いのでは?」
このまま身寄りもあやしい自分が、帝の前に参内していいはずがない。
葛葉が必死に言い募ると、可畏が笑いとばす。
「帝は稀にみる千里眼だぞ。きっと全てお見通しだ」
「絶対に罰を受けます!」
「何の罰だ。おまえはいちいち悲観的だな」
「だって御門様もご覧になればわかるでしょう! わたしは天子様に拝謁が叶うような支度もできておりません!」
「いきなり呼びつけたのは帝の方だ。そのくらい理解されるだろう」
「いえ、ですが……」
「まぁ、たしかにもっと垢抜けた状態にしてから参内したかったが、勅使があったのなら仕方がない」
可畏が馭者に目配せする。
「このまま御所へ向かってくれ」
「かしこまりました」
うなずいてから馭者が手綱をさばく。ゆっくりと馬車がすすみはじめた。
葛葉が慌てて身を乗りだす。
「待ってください! わたしなどが参内しては、神聖な御所で何が起きるかわかりません。鬼が憑いておりますし、さっきだって俥夫が……」
葛葉は左腕の数珠を撫でながら不安を訴えるが、可畏は平然と笑っている。
「心配するな。夜叉は悪い妖ではない。おまえにとっては飢餓感をもたらす迷惑者だろうが」
「良いとか悪いとかの問題ではなく、私なんかが参内しては不吉です」
「問題ない。私がついている」
「ですが」
「何度も言わせるな、おまえの状況は理解している。おそらく帝も」
「天子様が!?」
可畏は葛葉に視線をよこして頷いた。
「私はこの急な呼び出しで少しわかった気がしている。おまえの存在はずっと隠されていた。この私にもだ。倉橋侯爵の力だけで、そんなことは不可能だ。きっと帝が噛んでいるに違いない」
馬車ががたがたと揺れる。食堂や牛鍋屋の暖簾が、葛葉の視界の端をながれていく。通りは着流しの男性や、着物の女性が徒歩で行き交い賑わっていた。
可畏と葛葉の乗った馬車を、決められた路線にそって走る鉄道馬車が追い越していく。葛葉は昨日までの日常が、どこかへ置き去りにされているような気がした。
寄宿舎で寝起きして、特務科で学ぶだけだった平穏な日々。
可畏と出会ってから、葛葉の触れる世界が明らかに変わりはじめている。
「でも、わたしは天子様とお会いしたことはありませんが」
「帝はおまえのことを把握していたはずだ。おまえは羅刹の花嫁だからな」
「あの、その羅刹の花嫁って、いったい何でしょうか?」
特別な存在のように語られているが、葛葉には本当にそれが自分のことなのかわからない。
可畏はふっと自嘲的な吐息をついた。
「すぐにわかる」
彼はそのまま座席の背面に身をあずけて目を閉じた。それ以上は語ってくれそうもない。葛葉も黙って、最後の餡パンをかじる。
馬車の進路が変更される気配はなかった。
どうやら御所への参内は避けられないようだ。
葛葉がなるようになると開きおなった気持ちで往来の喧騒に耳を傾けていると、風向きにのってふんわりと爽やかな香りが舞った。
(あ、この香り……)
焚きしめる香とは違う、とても瑞々しく広がる心地の良い匂い。
(もしかして、異国の香水?)
葛葉の脳裏に、彼の懐に身を寄せていた一瞬がよみがえる。あの時は意識する余裕がなかったが、思い出すと何とも言えない恥じらいが込みあげてきた。
香りに紐付いてしまった記憶。
葛葉は恥ずかしさをふり払うように、勢いよく餡パンを頬張った。
「可畏様、こちらが頼まれていたものです」
「いきなり呼びつけたのに、すまないな」
馭者が差し出した風呂敷を受けとると、可畏は座席でぐったりとしている葛葉の膝の上におく。
「葛葉。とりあえずそれを食え」
可畏が風呂敷をとくと、餡パンが山のように積み重なっている。酒種と餡のあまい香りを克明にかぎわけて、葛葉は反射的に身を乗りだす。
「これは! 人気のお店の餡パン!」
ふたたび腹の虫が大合唱をはじめそうだったが、可畏の視線を感じて、勢いよく手を伸ばすことを思いとどまる。
「あの、本当にいただいても?」
「おまえ、よだれがすごいことになっているぞ。その飢餓感は夜叉のせいだ。今さら遠慮をするな」
風呂敷から餡パンをひとつ掴むと、可畏が有無を言わせず葛葉の口に突っ込んだ。ふわりと広がった生地の香りとうっとりするような餡のあまさが、一瞬で葛葉の恥じらいやためらいを吹きとばす。
口に突っ込まれた餡パンをあっというまに平らげて、葛葉は素直に感謝した。
「御門様、ありがとうございます!」
「おまえに餓鬼が憑いたのは、私のせいだ。存分に食っておけ」
「はい!」
いともたやすく乙女心を放りだして、葛葉は餡パンを両手で鷲掴みにする。我を忘れてかぶりついた。
「すごく美味しいです!」
「それで復活できそうだな」
可畏が馭者へ「出してくれ」とうながすと、男が葛葉と可畏を交互に見てから、すこし戸惑った顔をした。
「どうした?」
「いえ、可畏様の使役する式鬼が届いた時に、じつは陛下からも勅使の式鬼が参られまして」
「帝から?」
「はい。陛下から可畏様へ、花嫁を伴って至急御所へ参内されるようにと」
「至急? まさか、このまま参れと?」
「おそらく」
葛葉はさらなる急展開に、頬張っていた餡パンは吹きだしそうになる。可畏がちらりと冷ややかな視線をこちらによこした。
「葛葉、今の話を聞いていたか?」
「あの、まさかとは思いますが、花嫁って……」
「おまえ以外に誰がいる」
「む、無理です! わたしが天子様の御前に参るなど!」
「これは帝の命令だ」
「御門様は皇に連なる公爵様ですよね? きっと昨夜の騒動が天子様のお耳に入ったのでは? わたしなんかを花嫁だと紹介したことについて、一門からお咎めがあるのではありませんか?」
「それはない」
「わたしはあると思います! ここは当初の予定通り紅葉様をお連れになった方が良いのでは?」
このまま身寄りもあやしい自分が、帝の前に参内していいはずがない。
葛葉が必死に言い募ると、可畏が笑いとばす。
「帝は稀にみる千里眼だぞ。きっと全てお見通しだ」
「絶対に罰を受けます!」
「何の罰だ。おまえはいちいち悲観的だな」
「だって御門様もご覧になればわかるでしょう! わたしは天子様に拝謁が叶うような支度もできておりません!」
「いきなり呼びつけたのは帝の方だ。そのくらい理解されるだろう」
「いえ、ですが……」
「まぁ、たしかにもっと垢抜けた状態にしてから参内したかったが、勅使があったのなら仕方がない」
可畏が馭者に目配せする。
「このまま御所へ向かってくれ」
「かしこまりました」
うなずいてから馭者が手綱をさばく。ゆっくりと馬車がすすみはじめた。
葛葉が慌てて身を乗りだす。
「待ってください! わたしなどが参内しては、神聖な御所で何が起きるかわかりません。鬼が憑いておりますし、さっきだって俥夫が……」
葛葉は左腕の数珠を撫でながら不安を訴えるが、可畏は平然と笑っている。
「心配するな。夜叉は悪い妖ではない。おまえにとっては飢餓感をもたらす迷惑者だろうが」
「良いとか悪いとかの問題ではなく、私なんかが参内しては不吉です」
「問題ない。私がついている」
「ですが」
「何度も言わせるな、おまえの状況は理解している。おそらく帝も」
「天子様が!?」
可畏は葛葉に視線をよこして頷いた。
「私はこの急な呼び出しで少しわかった気がしている。おまえの存在はずっと隠されていた。この私にもだ。倉橋侯爵の力だけで、そんなことは不可能だ。きっと帝が噛んでいるに違いない」
馬車ががたがたと揺れる。食堂や牛鍋屋の暖簾が、葛葉の視界の端をながれていく。通りは着流しの男性や、着物の女性が徒歩で行き交い賑わっていた。
可畏と葛葉の乗った馬車を、決められた路線にそって走る鉄道馬車が追い越していく。葛葉は昨日までの日常が、どこかへ置き去りにされているような気がした。
寄宿舎で寝起きして、特務科で学ぶだけだった平穏な日々。
可畏と出会ってから、葛葉の触れる世界が明らかに変わりはじめている。
「でも、わたしは天子様とお会いしたことはありませんが」
「帝はおまえのことを把握していたはずだ。おまえは羅刹の花嫁だからな」
「あの、その羅刹の花嫁って、いったい何でしょうか?」
特別な存在のように語られているが、葛葉には本当にそれが自分のことなのかわからない。
可畏はふっと自嘲的な吐息をついた。
「すぐにわかる」
彼はそのまま座席の背面に身をあずけて目を閉じた。それ以上は語ってくれそうもない。葛葉も黙って、最後の餡パンをかじる。
馬車の進路が変更される気配はなかった。
どうやら御所への参内は避けられないようだ。
葛葉がなるようになると開きおなった気持ちで往来の喧騒に耳を傾けていると、風向きにのってふんわりと爽やかな香りが舞った。
(あ、この香り……)
焚きしめる香とは違う、とても瑞々しく広がる心地の良い匂い。
(もしかして、異国の香水?)
葛葉の脳裏に、彼の懐に身を寄せていた一瞬がよみがえる。あの時は意識する余裕がなかったが、思い出すと何とも言えない恥じらいが込みあげてきた。
香りに紐付いてしまった記憶。
葛葉は恥ずかしさをふり払うように、勢いよく餡パンを頬張った。
3
あなたにおすすめの小説

復讐のための五つの方法
炭田おと
恋愛
皇后として皇帝カエキリウスのもとに嫁いだイネスは、カエキリウスに愛人ルジェナがいることを知った。皇宮ではルジェナが権威を誇示していて、イネスは肩身が狭い思いをすることになる。
それでも耐えていたイネスだったが、父親に反逆の罪を着せられ、家族も、彼女自身も、処断されることが決まった。
グレゴリウス卿の手を借りて、一人生き残ったイネスは復讐を誓う。
72話で完結です。

皇太后(おかあ)様におまかせ!〜皇帝陛下の純愛探し〜
菰野るり
キャラ文芸
皇帝陛下はお年頃。
まわりは縁談を持ってくるが、どんな美人にもなびかない。
なんでも、3年前に一度だけ出逢った忘れられない女性がいるのだとか。手がかりはなし。そんな中、皇太后は自ら街に出て息子の嫁探しをすることに!
この物語の皇太后の名は雲泪(ユンレイ)、皇帝の名は堯舜(ヤオシュン)です。つまり【後宮物語〜身代わり宮女は皇帝陛下に溺愛されます⁉︎〜】の続編です。しかし、こちらから読んでも楽しめます‼︎どちらから読んでも違う感覚で楽しめる⁉︎こちらはポジティブなラブコメです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

後宮の偽花妃 国を追われた巫女見習いは宦官になる
gari@七柚カリン
キャラ文芸
旧題:国を追われた巫女見習いは、隣国の後宮で二重に花開く
☆4月上旬に書籍発売です。たくさんの応援をありがとうございました!☆ 植物を慈しむ巫女見習いの凛月には、二つの秘密がある。それは、『植物の心がわかること』『見目が変化すること』。
そんな凛月は、次期巫女を侮辱した罪を着せられ国外追放されてしまう。
心機一転、紹介状を手に向かったのは隣国の都。そこで偶然知り合ったのは、高官の峰風だった。
峰風の取次ぎで紹介先の人物との対面を果たすが、提案されたのは後宮内での二つの仕事。ある時は引きこもり後宮妃(欣怡)として巫女の務めを果たし、またある時は、少年宦官(子墨)として庭園管理の仕事をする、忙しくも楽しい二重生活が始まった。
仕事中に秘密の能力を活かし活躍したことで、子墨は女嫌いの峰風の助手に抜擢される。女であること・巫女であることを隠しつつ助手の仕事に邁進するが、これがきっかけとなり、宮廷内の様々な騒動に巻き込まれていく。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮なりきり夫婦録
石田空
キャラ文芸
「月鈴、ちょっと嫁に来るか?」
「はあ……?」
雲仙国では、皇帝が三代続いて謎の昏睡状態に陥る事態が続いていた。
あまりにも不可解なために、新しい皇帝を立てる訳にもいかない国は、急遽皇帝の「影武者」として跡継ぎ騒動を防ぐために寺院に入れられていた皇子の空燕を呼び戻すことに決める。
空燕の国の声に応える条件は、同じく寺院で方士修行をしていた方士の月鈴を妃として後宮に入れること。
かくしてふたりは片や皇帝の影武者として、片や皇帝の偽りの愛妃として、後宮と言う名の魔窟に潜入捜査をすることとなった。
影武者夫婦は、後宮内で起こる事件の謎を解けるのか。そしてふたりの想いの行方はいったい。
サイトより転載になります。
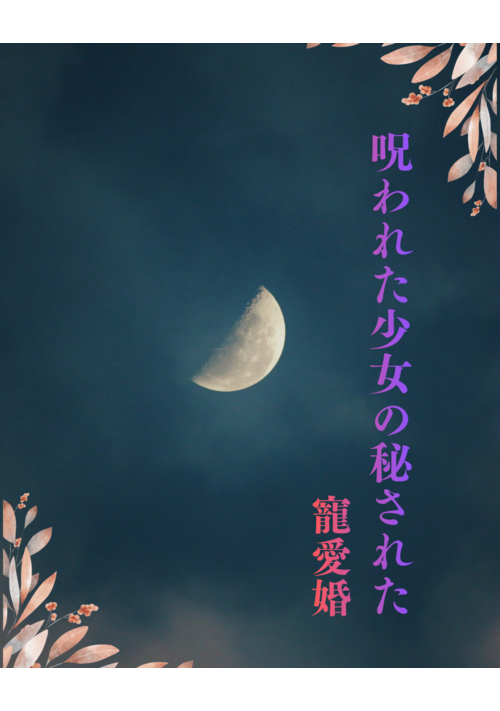
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

今さらやり直しは出来ません
mock
恋愛
3年付き合った斉藤翔平からプロポーズを受けれるかもと心弾ませた小泉彩だったが、当日仕事でどうしても行けないと断りのメールが入り意気消沈してしまう。
落胆しつつ帰る道中、送り主である彼が見知らぬ女性と歩く姿を目撃し、いてもたってもいられず後を追うと二人はさっきまで自身が待っていたホテルへと入っていく。
そんなある日、夢に出てきた高木健人との再会を果たした彩の運命は少しずつ変わっていき……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















