15 / 77
第三章:帝と妖
15:九尾の妖狐
しおりを挟む
二人は御座所の隣に設けられた麒麟の間へと案内された。まるで山頂に築かれた御殿のように、麒麟の間からは雲海がみえる。どういうカラクリになっているのかは可畏にもわからない。
帝はあまたの妖を使役できる稀有な能力者である。千里眼も帝が夢見を行うわけではなく、彼が使役した九尾の妖狐――玉藻を介して視ているのだ。
「とりあえず、無事に可畏との出会いを果たした彼女に、羅刹の花嫁について説明すべきだな」
麒麟の間へ入ると、帝は徽章がならぶ上着を脱いで、くつろいだ様子をみせる。
帝の結界内にあり、真の御座所をもつ豊礼殿も和洋折衷な殿舎で、外見は和風建築のようだが内装は洋風を模している。外界から遮断された結界内には、帝と玉藻、可畏と葛葉、そして夜叉の五人しかいない。夜叉いがいの四人が、ルネサンス様式の美しい椅子をひき、長い卓につくと、帝の式鬼が接待のために茶器を用意した。
葛葉もはじめのような極度の緊張からは開放されたようだ。進められるがまま珈琲をすすっている。彼女の背後から上体だけ見せている夜叉が、皿に盛られた茶菓子を見て目を輝かせていた。
可畏は帝の式鬼に、夜叉が望むだけの茶菓子を出すようにうながす。嬉々として茶菓子をほおばる夜叉をみて、葛葉が「鬼なのに」とおかしそうに笑った。
「では、葛葉」
帝に呼ばれて、葛葉がびくりと背筋をのばす。
「はい」
「まず君に説明しよう。羅刹の花嫁とは、ここにいる玉藻が夢見――いわゆる千里眼で示した存在だ」
「あの、天子様。玉藻様はいったいどういうお方なのでしょうか?」
「彼女は私が使役している妖だ」
帝が玉藻の正体を明かすと、葛葉がたじろいだのがわかる。彼女の顔を隠す長い前髪が邪魔だが、それでも表情が伝わってきた。
葛葉も特務科で学んでいるなら、異能と異形、そして妖についての知識はそなえている。
世間では妖と異形がわけて考えられることは少ないが、異能者の立場から見ると両者には決定的な違いがあった。妖は古来から人に紛れて生きてきた妖怪や魑魅魍魎の類である。中には人に害をなす者もあり、そういった妖は討伐の対象になるが、よほどの大妖でない限り調伏するのはたやすい。仮に玉藻のような大妖であっても、帝のような強力な能力者があれば人に仇なす存在となることはない。
妖と人には共存の希望がみえる。
一方で、異形は調伏できない。人を屠るだけの化け物である。遭遇したら異能の炎で焼くしか倒す術がないのだ。
結果として、妖は屍を残さないが異形は遺体が残る。
妖にも人の想念や怨念を糧として誕生する者があるが、数多くの異形を討伐してきた可畏には、異形という存在の不自然さがぬぐえない。
古来より存在する妖とは異なる、もっと人為的な作為をもった発生源があるのではないかと感じはじめていた。
「異形への脅威は高まる一方で、今のところ特務部の討伐以外の打開策がない。これには政府も頭を抱えている。我が国は開国をして海外諸国との関係を築いているが、このままでは国際問題に発展するだろう。遠くない将来に、この島国は異形のはびこる危険な地域として封鎖される。望まぬ鎖国の時代に逆戻りだ」
帝の説明を聞いて、葛葉は想像以上に事態が逼迫していることに気づいたようだ。緊張した声が問いかえす。
「そのような情勢と、千里眼で示された羅刹の花嫁にどのような関係があるのですか?」
「際限なく発生する異形には、羅刹という鬼が関わっている」
「羅刹?」
「そう、羅刹は妖というよりは神に近く異能者の手にも負えない強大な鬼神だ」
葛葉がぶるっと身ぶるいする。
「まさか、わたしがその鬼神の生贄になるとか、そういうお話でしょうか?」
「葛葉、それは違う」
彼女の怯える心が手にとるようにわかってしまい、可畏は咄嗟に否定していた。帝の隣にかけている玉藻がくすりと笑みをもらす。
「ここからは妾が説明しよう。妾が視たのは、折れた羅刹の角じゃ」
「角ですか?」
「そうじゃ。鬼の角が人の手に渡ったとなると厄介きわまりない」
「でも鬼神の角を折るなんて、不可能なのでは?」
玉藻はうなずいた。
「問題はそこじゃ。それを可能にした者がある。鬼神を堕したとなると、敵は相当な力の持ち主であろう」
「羅刹の角を折ったのは、人間なのですか?」
「陛下と可畏は、特務華族の中に紛れていると考えておる」
「特務華族の中に? ではもしかして軍にも?」
こちらを見る葛葉に、可畏は首肯した。
「可能性は否定できない」
「そんな……、あ、でも、それでわたしがどのように役立つのでしょうか?」
「「羅刹の花嫁」というのは、そなたの異能の名じゃ。可畏の異能が「羅刹の業火」と言われていることと同じ」
「わたしの異能? でも、わたしは大した力もありませんが」
「まだ知らぬだけじゃ。いや、そなたはもう感じておっただろう。自分が他のものとは異なると言うことを」
「それは」
葛葉の指先が、目元をかくす長い前髪にふれた。幼い頃からの数奇な体験の意味。
彼女には痛いほど自覚があるだろう。人と目を合わせることが禁忌なのだと思いこむほどに、幼い彼女の世界は特殊な体験で完成されていたのだ。
玉藻が赤い唇で囁くように告げる。
「可畏の炎は解放の攻撃だが、そなたの力は封印の守り。そなたの異能はいずれ羅刹の封印を叶える。強い鬼ほどそなたには抗えまい。鬼も一途な妖であるからな」
玉藻が葛葉から可畏へと目を向ける。まるで憐れむような眼差しだった。
九尾の妖狐がもつ千里眼。可畏には彼女が何を視ているのかわからない。だが、わからない方が良いのだろう。どんな助言を受けても、自分の役目が覆ることはないのだ。
「葛葉。羅刹の花嫁がどういうものであるか、理解したか?」
可畏が問うと、彼女は困惑気味に頷いた。
「意味は理解したと思います。でも、わたしがどのように御門様のお役に立てるのかわかりません」
「「羅刹の花嫁」は切り札のようなものだが、その能力の利用価値ははかりしれない」
「あ……」
「おまえが羅刹を堕した者の手に奪われると、異形による被害はさらに甚大なものになるだろう。だから、おまえは私の傍にあるだけで価値がある」
「もしかして、御門様との婚約は、わたしを敵から守るための政略結婚ですか?」
「……まぁ、そうだな」
曖昧に頷くと、葛葉は目に見えてがっかりと肩を落とした。
「それでは御門様にとって、わたしはただの足手まといですね」
「自分を卑下するのはやめろ。おまえは重要な切り札だ。羅刹の消息にたどり着いた時には働いてもらう。角を折られた荒ぶる鬼神が相手だぞ。羅刹の封印はおまえにしかできない。自分が特別な人間だと言う自覚をもて」
「は、はい!」
焚き付けると、葛葉は立ち上がりそうな勢いで返事をする。
可畏はにやにやとこちらを見ている帝に向き直った。
「陛下が花嫁を隠していた理由は、なんとなく察しがつきました。隠していても、彼女には幼い頃から災難が降りかかった。相当な存在感なのでしょうね。そして、やはり帝の知るところで、彼女をめぐって怪しい動きがあったのですか?」
可畏にも心当たりがあるが、まだ口にするのは憚られた。
帝の千里眼をもってしても正体に辿り着けないのだ。甘くみるべき相手ではない。
「そうだな。敵を欺くには味方からだと言うだろう。花嫁は絶対に守らねばならなかったからね。倉橋侯爵は全面的に協力してくれた。彼らにきつく当たらないでくれよ、可畏」
「わかりました」
可畏は茶菓子を平らげておかわりを要求している夜叉と、それを宥めている葛葉を見た。彼女に聞かれないように、声を落としてさりげなく玉藻にたしかめる。
「幼い葛葉を守っていた彼女の祖母は、もしかして……」
おそらく葛葉を守るための妖だろう。可畏の予想を裏付けるように、玉藻が低くささやく。
「そう、妾の同胞の尾崎じゃ。火災から行方が掴めぬ」
正体はどうであれ、祖母を見つけ出すという葛葉の目的が失われることはないようだ。できれば再会を果たしてほしいが、敵は羅刹を手中におさめるほどの相手である。
ながく花嫁を守っていた妖狐の安否にも暗雲が立ちこめている。
(葛葉が悲しむようなことにならなければいいが……)
帝はあまたの妖を使役できる稀有な能力者である。千里眼も帝が夢見を行うわけではなく、彼が使役した九尾の妖狐――玉藻を介して視ているのだ。
「とりあえず、無事に可畏との出会いを果たした彼女に、羅刹の花嫁について説明すべきだな」
麒麟の間へ入ると、帝は徽章がならぶ上着を脱いで、くつろいだ様子をみせる。
帝の結界内にあり、真の御座所をもつ豊礼殿も和洋折衷な殿舎で、外見は和風建築のようだが内装は洋風を模している。外界から遮断された結界内には、帝と玉藻、可畏と葛葉、そして夜叉の五人しかいない。夜叉いがいの四人が、ルネサンス様式の美しい椅子をひき、長い卓につくと、帝の式鬼が接待のために茶器を用意した。
葛葉もはじめのような極度の緊張からは開放されたようだ。進められるがまま珈琲をすすっている。彼女の背後から上体だけ見せている夜叉が、皿に盛られた茶菓子を見て目を輝かせていた。
可畏は帝の式鬼に、夜叉が望むだけの茶菓子を出すようにうながす。嬉々として茶菓子をほおばる夜叉をみて、葛葉が「鬼なのに」とおかしそうに笑った。
「では、葛葉」
帝に呼ばれて、葛葉がびくりと背筋をのばす。
「はい」
「まず君に説明しよう。羅刹の花嫁とは、ここにいる玉藻が夢見――いわゆる千里眼で示した存在だ」
「あの、天子様。玉藻様はいったいどういうお方なのでしょうか?」
「彼女は私が使役している妖だ」
帝が玉藻の正体を明かすと、葛葉がたじろいだのがわかる。彼女の顔を隠す長い前髪が邪魔だが、それでも表情が伝わってきた。
葛葉も特務科で学んでいるなら、異能と異形、そして妖についての知識はそなえている。
世間では妖と異形がわけて考えられることは少ないが、異能者の立場から見ると両者には決定的な違いがあった。妖は古来から人に紛れて生きてきた妖怪や魑魅魍魎の類である。中には人に害をなす者もあり、そういった妖は討伐の対象になるが、よほどの大妖でない限り調伏するのはたやすい。仮に玉藻のような大妖であっても、帝のような強力な能力者があれば人に仇なす存在となることはない。
妖と人には共存の希望がみえる。
一方で、異形は調伏できない。人を屠るだけの化け物である。遭遇したら異能の炎で焼くしか倒す術がないのだ。
結果として、妖は屍を残さないが異形は遺体が残る。
妖にも人の想念や怨念を糧として誕生する者があるが、数多くの異形を討伐してきた可畏には、異形という存在の不自然さがぬぐえない。
古来より存在する妖とは異なる、もっと人為的な作為をもった発生源があるのではないかと感じはじめていた。
「異形への脅威は高まる一方で、今のところ特務部の討伐以外の打開策がない。これには政府も頭を抱えている。我が国は開国をして海外諸国との関係を築いているが、このままでは国際問題に発展するだろう。遠くない将来に、この島国は異形のはびこる危険な地域として封鎖される。望まぬ鎖国の時代に逆戻りだ」
帝の説明を聞いて、葛葉は想像以上に事態が逼迫していることに気づいたようだ。緊張した声が問いかえす。
「そのような情勢と、千里眼で示された羅刹の花嫁にどのような関係があるのですか?」
「際限なく発生する異形には、羅刹という鬼が関わっている」
「羅刹?」
「そう、羅刹は妖というよりは神に近く異能者の手にも負えない強大な鬼神だ」
葛葉がぶるっと身ぶるいする。
「まさか、わたしがその鬼神の生贄になるとか、そういうお話でしょうか?」
「葛葉、それは違う」
彼女の怯える心が手にとるようにわかってしまい、可畏は咄嗟に否定していた。帝の隣にかけている玉藻がくすりと笑みをもらす。
「ここからは妾が説明しよう。妾が視たのは、折れた羅刹の角じゃ」
「角ですか?」
「そうじゃ。鬼の角が人の手に渡ったとなると厄介きわまりない」
「でも鬼神の角を折るなんて、不可能なのでは?」
玉藻はうなずいた。
「問題はそこじゃ。それを可能にした者がある。鬼神を堕したとなると、敵は相当な力の持ち主であろう」
「羅刹の角を折ったのは、人間なのですか?」
「陛下と可畏は、特務華族の中に紛れていると考えておる」
「特務華族の中に? ではもしかして軍にも?」
こちらを見る葛葉に、可畏は首肯した。
「可能性は否定できない」
「そんな……、あ、でも、それでわたしがどのように役立つのでしょうか?」
「「羅刹の花嫁」というのは、そなたの異能の名じゃ。可畏の異能が「羅刹の業火」と言われていることと同じ」
「わたしの異能? でも、わたしは大した力もありませんが」
「まだ知らぬだけじゃ。いや、そなたはもう感じておっただろう。自分が他のものとは異なると言うことを」
「それは」
葛葉の指先が、目元をかくす長い前髪にふれた。幼い頃からの数奇な体験の意味。
彼女には痛いほど自覚があるだろう。人と目を合わせることが禁忌なのだと思いこむほどに、幼い彼女の世界は特殊な体験で完成されていたのだ。
玉藻が赤い唇で囁くように告げる。
「可畏の炎は解放の攻撃だが、そなたの力は封印の守り。そなたの異能はいずれ羅刹の封印を叶える。強い鬼ほどそなたには抗えまい。鬼も一途な妖であるからな」
玉藻が葛葉から可畏へと目を向ける。まるで憐れむような眼差しだった。
九尾の妖狐がもつ千里眼。可畏には彼女が何を視ているのかわからない。だが、わからない方が良いのだろう。どんな助言を受けても、自分の役目が覆ることはないのだ。
「葛葉。羅刹の花嫁がどういうものであるか、理解したか?」
可畏が問うと、彼女は困惑気味に頷いた。
「意味は理解したと思います。でも、わたしがどのように御門様のお役に立てるのかわかりません」
「「羅刹の花嫁」は切り札のようなものだが、その能力の利用価値ははかりしれない」
「あ……」
「おまえが羅刹を堕した者の手に奪われると、異形による被害はさらに甚大なものになるだろう。だから、おまえは私の傍にあるだけで価値がある」
「もしかして、御門様との婚約は、わたしを敵から守るための政略結婚ですか?」
「……まぁ、そうだな」
曖昧に頷くと、葛葉は目に見えてがっかりと肩を落とした。
「それでは御門様にとって、わたしはただの足手まといですね」
「自分を卑下するのはやめろ。おまえは重要な切り札だ。羅刹の消息にたどり着いた時には働いてもらう。角を折られた荒ぶる鬼神が相手だぞ。羅刹の封印はおまえにしかできない。自分が特別な人間だと言う自覚をもて」
「は、はい!」
焚き付けると、葛葉は立ち上がりそうな勢いで返事をする。
可畏はにやにやとこちらを見ている帝に向き直った。
「陛下が花嫁を隠していた理由は、なんとなく察しがつきました。隠していても、彼女には幼い頃から災難が降りかかった。相当な存在感なのでしょうね。そして、やはり帝の知るところで、彼女をめぐって怪しい動きがあったのですか?」
可畏にも心当たりがあるが、まだ口にするのは憚られた。
帝の千里眼をもってしても正体に辿り着けないのだ。甘くみるべき相手ではない。
「そうだな。敵を欺くには味方からだと言うだろう。花嫁は絶対に守らねばならなかったからね。倉橋侯爵は全面的に協力してくれた。彼らにきつく当たらないでくれよ、可畏」
「わかりました」
可畏は茶菓子を平らげておかわりを要求している夜叉と、それを宥めている葛葉を見た。彼女に聞かれないように、声を落としてさりげなく玉藻にたしかめる。
「幼い葛葉を守っていた彼女の祖母は、もしかして……」
おそらく葛葉を守るための妖だろう。可畏の予想を裏付けるように、玉藻が低くささやく。
「そう、妾の同胞の尾崎じゃ。火災から行方が掴めぬ」
正体はどうであれ、祖母を見つけ出すという葛葉の目的が失われることはないようだ。できれば再会を果たしてほしいが、敵は羅刹を手中におさめるほどの相手である。
ながく花嫁を守っていた妖狐の安否にも暗雲が立ちこめている。
(葛葉が悲しむようなことにならなければいいが……)
3
あなたにおすすめの小説

復讐のための五つの方法
炭田おと
恋愛
皇后として皇帝カエキリウスのもとに嫁いだイネスは、カエキリウスに愛人ルジェナがいることを知った。皇宮ではルジェナが権威を誇示していて、イネスは肩身が狭い思いをすることになる。
それでも耐えていたイネスだったが、父親に反逆の罪を着せられ、家族も、彼女自身も、処断されることが決まった。
グレゴリウス卿の手を借りて、一人生き残ったイネスは復讐を誓う。
72話で完結です。

皇太后(おかあ)様におまかせ!〜皇帝陛下の純愛探し〜
菰野るり
キャラ文芸
皇帝陛下はお年頃。
まわりは縁談を持ってくるが、どんな美人にもなびかない。
なんでも、3年前に一度だけ出逢った忘れられない女性がいるのだとか。手がかりはなし。そんな中、皇太后は自ら街に出て息子の嫁探しをすることに!
この物語の皇太后の名は雲泪(ユンレイ)、皇帝の名は堯舜(ヤオシュン)です。つまり【後宮物語〜身代わり宮女は皇帝陛下に溺愛されます⁉︎〜】の続編です。しかし、こちらから読んでも楽しめます‼︎どちらから読んでも違う感覚で楽しめる⁉︎こちらはポジティブなラブコメです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

後宮の偽花妃 国を追われた巫女見習いは宦官になる
gari@七柚カリン
キャラ文芸
旧題:国を追われた巫女見習いは、隣国の後宮で二重に花開く
☆4月上旬に書籍発売です。たくさんの応援をありがとうございました!☆ 植物を慈しむ巫女見習いの凛月には、二つの秘密がある。それは、『植物の心がわかること』『見目が変化すること』。
そんな凛月は、次期巫女を侮辱した罪を着せられ国外追放されてしまう。
心機一転、紹介状を手に向かったのは隣国の都。そこで偶然知り合ったのは、高官の峰風だった。
峰風の取次ぎで紹介先の人物との対面を果たすが、提案されたのは後宮内での二つの仕事。ある時は引きこもり後宮妃(欣怡)として巫女の務めを果たし、またある時は、少年宦官(子墨)として庭園管理の仕事をする、忙しくも楽しい二重生活が始まった。
仕事中に秘密の能力を活かし活躍したことで、子墨は女嫌いの峰風の助手に抜擢される。女であること・巫女であることを隠しつつ助手の仕事に邁進するが、これがきっかけとなり、宮廷内の様々な騒動に巻き込まれていく。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮なりきり夫婦録
石田空
キャラ文芸
「月鈴、ちょっと嫁に来るか?」
「はあ……?」
雲仙国では、皇帝が三代続いて謎の昏睡状態に陥る事態が続いていた。
あまりにも不可解なために、新しい皇帝を立てる訳にもいかない国は、急遽皇帝の「影武者」として跡継ぎ騒動を防ぐために寺院に入れられていた皇子の空燕を呼び戻すことに決める。
空燕の国の声に応える条件は、同じく寺院で方士修行をしていた方士の月鈴を妃として後宮に入れること。
かくしてふたりは片や皇帝の影武者として、片や皇帝の偽りの愛妃として、後宮と言う名の魔窟に潜入捜査をすることとなった。
影武者夫婦は、後宮内で起こる事件の謎を解けるのか。そしてふたりの想いの行方はいったい。
サイトより転載になります。
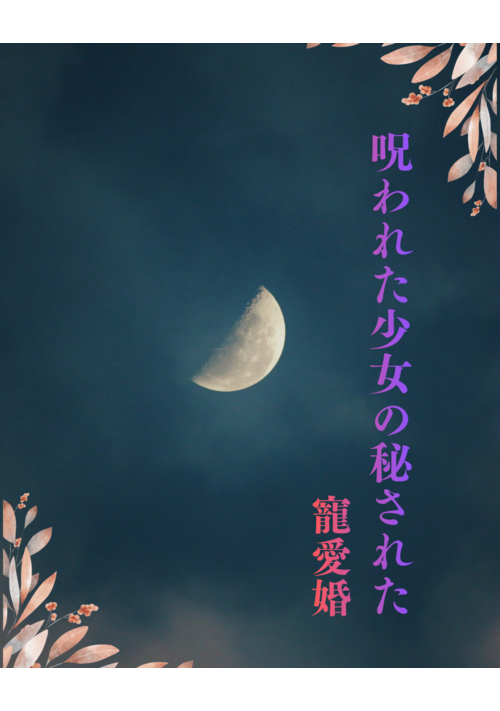
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

今さらやり直しは出来ません
mock
恋愛
3年付き合った斉藤翔平からプロポーズを受けれるかもと心弾ませた小泉彩だったが、当日仕事でどうしても行けないと断りのメールが入り意気消沈してしまう。
落胆しつつ帰る道中、送り主である彼が見知らぬ女性と歩く姿を目撃し、いてもたってもいられず後を追うと二人はさっきまで自身が待っていたホテルへと入っていく。
そんなある日、夢に出てきた高木健人との再会を果たした彩の運命は少しずつ変わっていき……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















