18 / 77
第四章:心がまえ
18:断ち切るための儀式
しおりを挟む
前髪を編みこむように結いあげられて、葛葉はそわそわとおちつかない。
「とてもお似合いです。今まで前髪でお顔が隠れていたなんてもったいない」
鏡にうつる自分のすっきりとした顔に、和歌はかるく紅をさす。葛葉は見慣れない自分の顔が、ひたすら面映い。だくだくと変な汗が吹きだしてくる。
「葛葉様。着物のご用意も整っておりますので、こちらも試してみられては?」
「け、結構です」
和歌はうきうきと生地をみせてくるが、葛葉は自分には場ちがいだと固辞する。
「わたしは特務科の制服が動きやすくて好きなんです」
学校に通うようになってからは、寝むとき以外は制服で過ごしている。小袖と袴のうえに、洋装の上着をはおるスタイルの制服で、とても動きやすいのだ。
いずれ袖を通す特務部の隊服も和洋折衷で、似かよった趣があった。
「あの、和歌さん。もう充分です。ありがとうございます」
これ以上彼女といると、着せ替え人形にされそうである。葛葉はそそくさと立ちあがったが、可畏のいる居間へ戻るのかと考えると、足が前にでない。
(いきなり御門様にこの顔を見せるって、すごく恥ずかしい)
視界が開けて世界がより明るくなったように感じる。けれど、自分ですらまったく見慣れていない顔である。顔面がすぅすぅするし、とんでもなく心許ない。
「葛葉様。不安なのですか?」
和歌が背後からがしっと葛葉の肩をつかむ。
「ほら、わたしと目があっても何も起きません。大丈夫ですよ」
顔を覗きこむようにして、彼女は心配ないとほほえむ。そんなことはまったく懸念していなかったが、和歌には葛葉の戸惑いがそう映ったのだろう。
「可愛くできましたよ。居間へもどって、可畏様にもご覧になっていただきましょう」
葛葉のとまどいを蹴散らすかのごとく、和歌はぐいぐいと背中をおす。まるで二人羽織のような状態で廊下に押しだされ、居間へとすすんでしまう。
「さぁ、いかがでしょうか? 可畏様」
部屋に戻ったとたん、和歌のはつらつとした声がひびく。この細腕のどこにそんな力があるのか、葛葉はあっさりと彼の前に押しだされてしまう。
(ひぇ!)
可畏と目があう前に、葛葉はとっさに自分の顔を両手でおおった。
「おい、なぜ隠すんだ? さっきも言ったが、おまえの目には何の力も宿っていないぞ」
「は、はい。それは理解しましたが……、やはり慣れなくて」
「大丈夫ですよ、葛葉さん」
ぐぐぐっと和歌の怪力が葛葉の手を顔から引きはがす。途端に座卓についたままこちらを仰いでいる可畏と目があった。
「あ、あの」
葛葉は即座に自分の顔がじゅっと沸騰するのをかんじた。
「み、見苦しいモノをお見せして申し訳ございません」
こちらを見たまま、明らかに言葉を失っている可畏の様子を察して、葛葉はさらにあわてる。
「やっぱりおかしいでしょうか? 前髪で顔を隠しておいた方が……」
逃げだす勢いで退散しようとすると、可畏が葛葉の袖をつかんだ。
「待て。そうじゃない」
「わ!?」
咄嗟に袖をひかれた勢いで重心がくるう。袴の裾にも足をとられて、葛葉は可畏の前に身を投げだすようにボテっと転倒していた。
「大丈夫か?」
身をうちつけた痛みと恥ずかしさで、葛葉は倒れこんだまま、涙目になってあやまる。
「見苦しくて、申し訳ございません」
「どこかぶつけたのか?」
「大したことはありません」
むくりと起きあがって、葛葉はその場に正座した。無様すぎて顔をあげられない。
「下を向くな」
「でも、御門様は私の顔を見て絶句しておられましたよね」
「違う。あれは……」
可畏がふっと息をのんだ。葛葉がおそるおそる顔色をうかがうと、彼は居たたまれない様子で口元をおさえた。
「おまえがあまりに照れるから、私まで恥ずかしくなっただけだ」
「御門様が?」
たしかに彼の白皙の頬にすこし朱がさしている。
(え?)
葛葉は彼の意外な一面に意識がもっていかれる。まじまじと目前の美しい顔面をみつめた。舐め回すように眺めてしまう。
「おまえ、飢えた獣のような目でこっちを見るな」
「あ、申し訳ありません」
可畏の声は吐き捨てるように冷たかったが、葛葉は好奇心にあらがえない。にやにやしたくなるような、くすぐったくなるような、複雑な感情がこみあげてくる。
彼は呆れたように、はぁっと大きくため息をついた。
「とにかく、前髪おばけの状態よりは今の方がよっぽどいい」
「あ、これは……」
葛葉ははっと自分の前髪事情を思いだして、再び頬に熱がこもる。ふたたびうつむき加減になると、可畏が長い指でパチンと葛葉の額をはじいた。
「いたっ!」
声をあげて額を押さえると、可畏の低い声がまっすぐに戸惑う気持ちをみちびく。
「葛葉。もう二度と自分を卑下して目をそらすな」
(あ……)
妖のような赤眼に、真摯な光があった。葛葉は無意識に背筋を伸ばしていた。
彼が本当に伝えたかったこと。
「今日をもって、人を不幸にするという後ろ向きな考えは捨てろ。そんな思いこみは必要ない。これからは人を救うために働いてもらう。おまえにはその力がある」
葛葉はしっかりと可畏の赤い瞳をみつめた。
もう前髪の隙間から、かろうじて世界を覗くような卑小な自分とは決別しなければならない。
可畏はやはり特務部を率いる大将なのだ。脆弱な部下をそのままにはしておかないのだろう。
「はい、御門様。お役に立てるように努めます」
これは、葛葉の弱さを断ちきるための儀式。
(もう目をそらさない。前向きにかんがえる)
そう決意を新たにした葛葉の目前を、ひらりと小さな影がよぎる。はたはたとひらめくのは鴉アゲハだった。
可畏が掬いあげるように指さきを差しだす。漆黒のアゲハは迷うことなく彼の指にとまった。
葛葉はすぐにそれが偶然の来訪者ではないのだと、気持ちをひきしめる。
鴉アゲハは特務部の伝令をとどける使いなのだ。可畏の作りだした式鬼であるという噂は、葛葉の耳にも入っていた。
「どうやら休んでばかりもいられないようだ」
伝令を受けとり、可畏が素早く立ちあがる。
「任務ですか?」
葛葉も同行するつもりですぐに腰をあげるが、可畏が束の間逡巡しているのがわかる。
「わたしも連れていってください」
可畏に呼びだしがかかるということは、容易な現場ではないだろう。実務も実戦も経験をしていない自分は、足手まといになるだけかもしれない。
頭ではわかっていたが、葛葉は黙って見おくれない。
特務部の一員となって己の力で身をたてる。それは目標であり夢だった。
可畏の婚約者となっても、葛葉が後ろ盾になるような実家を持たない孤児であることは変わらない。
自分に特別な力があると言われても、まるで実感がないのだ。
役立たずだと見放されれば、すぐに路頭に迷うだろう。
「本当にわたしに特別な異能があるのなら、一刻も早くお役に立てるようになりたいです!」
「……たしかに、そうだな」
可畏は迷っていたが、何かをふっきるように指先から漆黒のアゲハをはなつ。
「おまえが深窓の令嬢ではなくて良かった」
「え?」
「そのやる気は評価できる」
「ありがとうございます!」
素直な喜びが声を弾ませる。可畏は苦笑していたが、すぐに厳しさを取り戻して葛葉をみちびいた。
「おまえは羅刹封印のために、失うことのできない切り札だ」
「はい。心得ております」
頻出する異形には、折られた鬼神の角が関わっている。それが帝と玉藻の説明だった。
際限のない異形の発生を止めるために、特務部は討伐を行いながら、角の在処と羅刹の所在を追っている。
そして。
葛葉のもつ「羅刹の花嫁」という異能は、鬼神を制する力。
にわかには信じられないが、今は受け入れるしかない。
「おまえの身は必ず守るし、守らねばならない。だが、その異能で具体的に何ができるのかは手探りだ。羅刹と対峙するまでに、力の使い方を理解する必要がある」
「はい」
葛葉自身も力についてはよくわかっていない。帝の千里眼が示した、いずれ羅刹の封印を叶えるということだけが手がかりの、心もとない状態だった。
「力を理解するためには、実践しかない」
「望むところです」
勢いよく訴えると、可畏が困ったように笑った。
「これから向かう現場はすこし曰くのある場所だ。異形との戦闘になるような激しさはないが、だからこそ警戒が必要になる。私がおまえの傍を離れることはないが、絶対に無理はするな」
「はい」
「気になることがあれば、すぐに私に報告か相談をしろ」
葛葉はうなずいて、挙手の敬礼をする。
「了解しました」
「とてもお似合いです。今まで前髪でお顔が隠れていたなんてもったいない」
鏡にうつる自分のすっきりとした顔に、和歌はかるく紅をさす。葛葉は見慣れない自分の顔が、ひたすら面映い。だくだくと変な汗が吹きだしてくる。
「葛葉様。着物のご用意も整っておりますので、こちらも試してみられては?」
「け、結構です」
和歌はうきうきと生地をみせてくるが、葛葉は自分には場ちがいだと固辞する。
「わたしは特務科の制服が動きやすくて好きなんです」
学校に通うようになってからは、寝むとき以外は制服で過ごしている。小袖と袴のうえに、洋装の上着をはおるスタイルの制服で、とても動きやすいのだ。
いずれ袖を通す特務部の隊服も和洋折衷で、似かよった趣があった。
「あの、和歌さん。もう充分です。ありがとうございます」
これ以上彼女といると、着せ替え人形にされそうである。葛葉はそそくさと立ちあがったが、可畏のいる居間へ戻るのかと考えると、足が前にでない。
(いきなり御門様にこの顔を見せるって、すごく恥ずかしい)
視界が開けて世界がより明るくなったように感じる。けれど、自分ですらまったく見慣れていない顔である。顔面がすぅすぅするし、とんでもなく心許ない。
「葛葉様。不安なのですか?」
和歌が背後からがしっと葛葉の肩をつかむ。
「ほら、わたしと目があっても何も起きません。大丈夫ですよ」
顔を覗きこむようにして、彼女は心配ないとほほえむ。そんなことはまったく懸念していなかったが、和歌には葛葉の戸惑いがそう映ったのだろう。
「可愛くできましたよ。居間へもどって、可畏様にもご覧になっていただきましょう」
葛葉のとまどいを蹴散らすかのごとく、和歌はぐいぐいと背中をおす。まるで二人羽織のような状態で廊下に押しだされ、居間へとすすんでしまう。
「さぁ、いかがでしょうか? 可畏様」
部屋に戻ったとたん、和歌のはつらつとした声がひびく。この細腕のどこにそんな力があるのか、葛葉はあっさりと彼の前に押しだされてしまう。
(ひぇ!)
可畏と目があう前に、葛葉はとっさに自分の顔を両手でおおった。
「おい、なぜ隠すんだ? さっきも言ったが、おまえの目には何の力も宿っていないぞ」
「は、はい。それは理解しましたが……、やはり慣れなくて」
「大丈夫ですよ、葛葉さん」
ぐぐぐっと和歌の怪力が葛葉の手を顔から引きはがす。途端に座卓についたままこちらを仰いでいる可畏と目があった。
「あ、あの」
葛葉は即座に自分の顔がじゅっと沸騰するのをかんじた。
「み、見苦しいモノをお見せして申し訳ございません」
こちらを見たまま、明らかに言葉を失っている可畏の様子を察して、葛葉はさらにあわてる。
「やっぱりおかしいでしょうか? 前髪で顔を隠しておいた方が……」
逃げだす勢いで退散しようとすると、可畏が葛葉の袖をつかんだ。
「待て。そうじゃない」
「わ!?」
咄嗟に袖をひかれた勢いで重心がくるう。袴の裾にも足をとられて、葛葉は可畏の前に身を投げだすようにボテっと転倒していた。
「大丈夫か?」
身をうちつけた痛みと恥ずかしさで、葛葉は倒れこんだまま、涙目になってあやまる。
「見苦しくて、申し訳ございません」
「どこかぶつけたのか?」
「大したことはありません」
むくりと起きあがって、葛葉はその場に正座した。無様すぎて顔をあげられない。
「下を向くな」
「でも、御門様は私の顔を見て絶句しておられましたよね」
「違う。あれは……」
可畏がふっと息をのんだ。葛葉がおそるおそる顔色をうかがうと、彼は居たたまれない様子で口元をおさえた。
「おまえがあまりに照れるから、私まで恥ずかしくなっただけだ」
「御門様が?」
たしかに彼の白皙の頬にすこし朱がさしている。
(え?)
葛葉は彼の意外な一面に意識がもっていかれる。まじまじと目前の美しい顔面をみつめた。舐め回すように眺めてしまう。
「おまえ、飢えた獣のような目でこっちを見るな」
「あ、申し訳ありません」
可畏の声は吐き捨てるように冷たかったが、葛葉は好奇心にあらがえない。にやにやしたくなるような、くすぐったくなるような、複雑な感情がこみあげてくる。
彼は呆れたように、はぁっと大きくため息をついた。
「とにかく、前髪おばけの状態よりは今の方がよっぽどいい」
「あ、これは……」
葛葉ははっと自分の前髪事情を思いだして、再び頬に熱がこもる。ふたたびうつむき加減になると、可畏が長い指でパチンと葛葉の額をはじいた。
「いたっ!」
声をあげて額を押さえると、可畏の低い声がまっすぐに戸惑う気持ちをみちびく。
「葛葉。もう二度と自分を卑下して目をそらすな」
(あ……)
妖のような赤眼に、真摯な光があった。葛葉は無意識に背筋を伸ばしていた。
彼が本当に伝えたかったこと。
「今日をもって、人を不幸にするという後ろ向きな考えは捨てろ。そんな思いこみは必要ない。これからは人を救うために働いてもらう。おまえにはその力がある」
葛葉はしっかりと可畏の赤い瞳をみつめた。
もう前髪の隙間から、かろうじて世界を覗くような卑小な自分とは決別しなければならない。
可畏はやはり特務部を率いる大将なのだ。脆弱な部下をそのままにはしておかないのだろう。
「はい、御門様。お役に立てるように努めます」
これは、葛葉の弱さを断ちきるための儀式。
(もう目をそらさない。前向きにかんがえる)
そう決意を新たにした葛葉の目前を、ひらりと小さな影がよぎる。はたはたとひらめくのは鴉アゲハだった。
可畏が掬いあげるように指さきを差しだす。漆黒のアゲハは迷うことなく彼の指にとまった。
葛葉はすぐにそれが偶然の来訪者ではないのだと、気持ちをひきしめる。
鴉アゲハは特務部の伝令をとどける使いなのだ。可畏の作りだした式鬼であるという噂は、葛葉の耳にも入っていた。
「どうやら休んでばかりもいられないようだ」
伝令を受けとり、可畏が素早く立ちあがる。
「任務ですか?」
葛葉も同行するつもりですぐに腰をあげるが、可畏が束の間逡巡しているのがわかる。
「わたしも連れていってください」
可畏に呼びだしがかかるということは、容易な現場ではないだろう。実務も実戦も経験をしていない自分は、足手まといになるだけかもしれない。
頭ではわかっていたが、葛葉は黙って見おくれない。
特務部の一員となって己の力で身をたてる。それは目標であり夢だった。
可畏の婚約者となっても、葛葉が後ろ盾になるような実家を持たない孤児であることは変わらない。
自分に特別な力があると言われても、まるで実感がないのだ。
役立たずだと見放されれば、すぐに路頭に迷うだろう。
「本当にわたしに特別な異能があるのなら、一刻も早くお役に立てるようになりたいです!」
「……たしかに、そうだな」
可畏は迷っていたが、何かをふっきるように指先から漆黒のアゲハをはなつ。
「おまえが深窓の令嬢ではなくて良かった」
「え?」
「そのやる気は評価できる」
「ありがとうございます!」
素直な喜びが声を弾ませる。可畏は苦笑していたが、すぐに厳しさを取り戻して葛葉をみちびいた。
「おまえは羅刹封印のために、失うことのできない切り札だ」
「はい。心得ております」
頻出する異形には、折られた鬼神の角が関わっている。それが帝と玉藻の説明だった。
際限のない異形の発生を止めるために、特務部は討伐を行いながら、角の在処と羅刹の所在を追っている。
そして。
葛葉のもつ「羅刹の花嫁」という異能は、鬼神を制する力。
にわかには信じられないが、今は受け入れるしかない。
「おまえの身は必ず守るし、守らねばならない。だが、その異能で具体的に何ができるのかは手探りだ。羅刹と対峙するまでに、力の使い方を理解する必要がある」
「はい」
葛葉自身も力についてはよくわかっていない。帝の千里眼が示した、いずれ羅刹の封印を叶えるということだけが手がかりの、心もとない状態だった。
「力を理解するためには、実践しかない」
「望むところです」
勢いよく訴えると、可畏が困ったように笑った。
「これから向かう現場はすこし曰くのある場所だ。異形との戦闘になるような激しさはないが、だからこそ警戒が必要になる。私がおまえの傍を離れることはないが、絶対に無理はするな」
「はい」
「気になることがあれば、すぐに私に報告か相談をしろ」
葛葉はうなずいて、挙手の敬礼をする。
「了解しました」
12
あなたにおすすめの小説

復讐のための五つの方法
炭田おと
恋愛
皇后として皇帝カエキリウスのもとに嫁いだイネスは、カエキリウスに愛人ルジェナがいることを知った。皇宮ではルジェナが権威を誇示していて、イネスは肩身が狭い思いをすることになる。
それでも耐えていたイネスだったが、父親に反逆の罪を着せられ、家族も、彼女自身も、処断されることが決まった。
グレゴリウス卿の手を借りて、一人生き残ったイネスは復讐を誓う。
72話で完結です。

皇太后(おかあ)様におまかせ!〜皇帝陛下の純愛探し〜
菰野るり
キャラ文芸
皇帝陛下はお年頃。
まわりは縁談を持ってくるが、どんな美人にもなびかない。
なんでも、3年前に一度だけ出逢った忘れられない女性がいるのだとか。手がかりはなし。そんな中、皇太后は自ら街に出て息子の嫁探しをすることに!
この物語の皇太后の名は雲泪(ユンレイ)、皇帝の名は堯舜(ヤオシュン)です。つまり【後宮物語〜身代わり宮女は皇帝陛下に溺愛されます⁉︎〜】の続編です。しかし、こちらから読んでも楽しめます‼︎どちらから読んでも違う感覚で楽しめる⁉︎こちらはポジティブなラブコメです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

後宮の偽花妃 国を追われた巫女見習いは宦官になる
gari@七柚カリン
キャラ文芸
旧題:国を追われた巫女見習いは、隣国の後宮で二重に花開く
☆4月上旬に書籍発売です。たくさんの応援をありがとうございました!☆ 植物を慈しむ巫女見習いの凛月には、二つの秘密がある。それは、『植物の心がわかること』『見目が変化すること』。
そんな凛月は、次期巫女を侮辱した罪を着せられ国外追放されてしまう。
心機一転、紹介状を手に向かったのは隣国の都。そこで偶然知り合ったのは、高官の峰風だった。
峰風の取次ぎで紹介先の人物との対面を果たすが、提案されたのは後宮内での二つの仕事。ある時は引きこもり後宮妃(欣怡)として巫女の務めを果たし、またある時は、少年宦官(子墨)として庭園管理の仕事をする、忙しくも楽しい二重生活が始まった。
仕事中に秘密の能力を活かし活躍したことで、子墨は女嫌いの峰風の助手に抜擢される。女であること・巫女であることを隠しつつ助手の仕事に邁進するが、これがきっかけとなり、宮廷内の様々な騒動に巻き込まれていく。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮なりきり夫婦録
石田空
キャラ文芸
「月鈴、ちょっと嫁に来るか?」
「はあ……?」
雲仙国では、皇帝が三代続いて謎の昏睡状態に陥る事態が続いていた。
あまりにも不可解なために、新しい皇帝を立てる訳にもいかない国は、急遽皇帝の「影武者」として跡継ぎ騒動を防ぐために寺院に入れられていた皇子の空燕を呼び戻すことに決める。
空燕の国の声に応える条件は、同じく寺院で方士修行をしていた方士の月鈴を妃として後宮に入れること。
かくしてふたりは片や皇帝の影武者として、片や皇帝の偽りの愛妃として、後宮と言う名の魔窟に潜入捜査をすることとなった。
影武者夫婦は、後宮内で起こる事件の謎を解けるのか。そしてふたりの想いの行方はいったい。
サイトより転載になります。
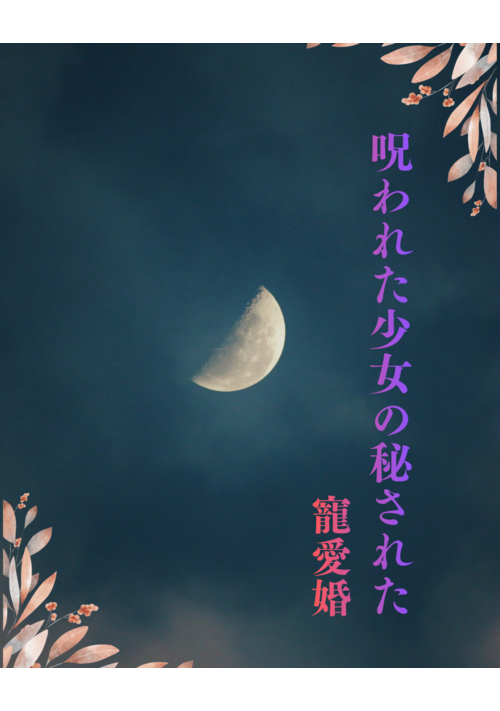
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

今さらやり直しは出来ません
mock
恋愛
3年付き合った斉藤翔平からプロポーズを受けれるかもと心弾ませた小泉彩だったが、当日仕事でどうしても行けないと断りのメールが入り意気消沈してしまう。
落胆しつつ帰る道中、送り主である彼が見知らぬ女性と歩く姿を目撃し、いてもたってもいられず後を追うと二人はさっきまで自身が待っていたホテルへと入っていく。
そんなある日、夢に出てきた高木健人との再会を果たした彩の運命は少しずつ変わっていき……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















