20 / 77
第四章:心がまえ
20:子守唄のかわりに
しおりを挟む
本陣跡の屋敷で寝床について散々もめていたが、結局は藩主や要人などが使用していた上段の間に、そのまま二組の寝具が用意された。
可畏は葛葉と横並びに寝むはめになる。
板の間で雑魚寝をするのは自分だと、葛葉が一歩もひかなかったのだ。
埒があかないと渋面をつくる可畏に配慮したのか、四方が玄関にあった衝立障子をもってきて、二組の蒲団のあいだをさえぎる。
「こうすれば良いのではありませんか?」
「ありがとうございます! 四方少将!」
葛葉は律儀に彼に会釈した。可畏には四方が面白がっているのがわかる。
問題が解決したと言いたげに、葛葉の表情がぱっとあかるくなった。
「おまえはこれで平気なのか?」
「もちろんです」
一片の迷いもない返答である。
複雑な気持ちになったが、可畏はなぜ葛葉の勢いに押し切られているのか、自分がよくわからない。
(まさか、これも花嫁の力か?)
変な女だと強くおもう反面、彼女の様子をみていると調子がくるう。
萎縮しながらも、自分を曲げない威勢の良さがあった。けれど、強情かと思えば素直で、何事にも懸命なのだ。多少のおかしさも愛嬌だと受けとめたくなる。
特務部の第五隊には女子だけの隊があるが、特務華族の子女に見られるような自尊心や傲慢さが、葛葉には感じられない。
孤児であるという貧しい生い立ちのせいかもしれないが、可畏には新鮮にうつった。
(いや、どう考えても変な女だ)
四方が退室して二人きりなると、可畏は衝立障子の向こう側で、ごそごそと落ち着きなく身動きする気配をかんじた。
やはり自分と二人では落ちつかないのだろう。可畏は吐息をついてから声をかける。
「葛葉」
「は、はい!」
「こんな宵前から寝めと言われても、どうせ眠れないだろ」
「……はい」
「ここで起きていることについて話してやる。横になったまま聞いていろ」
「はい!」
あきらかに彼女の意気込みが跳ねあがった。横にならずに正座している気配をかんじる。
やる気だけは人一倍のようだ。
「まず横になれ。私の話を子守唄にして眠れるならそれもいい。仮眠も特務部には重要な任務だ。休むべき時に休めないのは褒められたことじゃない」
「はい」
即座にばさりと蒲団をかぶって横になる気配があった。やはりどこまでも素直である。
「この旧街道周辺には、鬼火がでるという噂がある」
鬼火の伝承や目撃情報は各地にある。人を土葬によって弔ったばあい、屍の腐敗と気候条件によって発光現象がおきる。
墓地で火の玉をみた、鬼火がでたという話は自然現象なのだ。
けれど、可畏のいう鬼火はそれらとは一線を画す。
特務部が追うべき妖の証であり、鬼の痕跡や所在をしめすものだった。
「では、周辺に鬼がいるということですか?」
葛葉からすぐに問いかけがあった。彼女も特務部のさす鬼火の意味は理解している。可畏は子守唄がわりに一方的に語るつもりだったが、やる気をみなぎらせている葛葉が黙って聞いているはずもない。
仮眠をとらせることは諦めたほうがよいのかもしれないと、なかば諦めながら答える。
「潜伏していると踏んで、第三隊が周辺を調査しているが、なかなか手がかりがつかめない」
「御門様が呼ばれるということは、その鬼は今朝うかがった羅刹につながるのでしょうか」
「残念ながら、まだわからない」
「でも、第三隊には少将もいらっしゃいますし、餓鬼のような調伏がたやすい鬼ではないのでは?」
「この件でやっかいなのは、関わっている鬼がどの程度なのかもつかめないところだ。鬼火も噂だけが独り歩きをしていて、実際には誰も見たことがない。だが、その噂の延長に事件が起きている節がある」
「事件?」
「そうだ。鬼火を見たという者が、数日以内に亡くなっている。はじめは作り話かただの偶然だと思われていたようだが、頻繁に犠牲者が出て特務部も看過できなくなった。今日も三人が亡くなったようだ」
伝令で可畏の元に届いたのは、その報せだった。
「三人もですか? でも、それが鬼火と関係があるという確証はどこで? 遺体に何か特徴が?」
葛葉の問いは的を得ていた。どうやら可畏が思っていたより根は聡明なようだ。
鬼や妖が直接人に手をくだすことは稀である。もし犠牲がでる場合、鬼や妖に憑かれた人間の憎悪による殺人か、憑かれた本人の自殺という形で現れる。
死因はすぐに特定されるが、そこに妖の影があるかどうかはわかりにくい。
「この一連の事件がさらに複雑なのは、異形の気配があることだ」
「え?」
「遺体の損壊は人為的なものとは思えない。野犬や害獣の線も当たっているが、どうやら違うらしい。人を食い散らかす何かが在る」
「でも鬼火は妖を示すものですし、異形には人や妖のような知能はないと習いました」
「私のこれまでの経験でもそうだった」
「本当に異形を見た人はいないのですか?」
「そういう報告になっている」
しんと室内に沈黙が満ちる。
「恐ろしいか?」
「いいえ! ただ、もしそれが事実なら、人の目をしのぶ異形がいるということになります」
「そうだな。討伐が困難になる」
にわか隊員の彼女には難易度のたかい任務だが、彼女の能力をより顕現させるには本番あるのみなのだ。異能の発現とともに完全に力が開花するものは多いが、ときおり身の危険によってつよく発現する者があった。葛葉の場合はおろらく後者なのだろう。
「異形は昼夜を問わないが、妖は夜に動くものが多い。私たちは鬼火を追うために、夜にでる。だから、今は仮眠が重要だが……」
「そんなお話を聞いては、余計に眠れません」
素直な反応だった。
「とにかく、いまは子守唄でも唱えて休め」
日没からすでに半刻はすぎている。うとうとした頃には、鬼火を求めて動かねばならない。
可畏は葛葉と横並びに寝むはめになる。
板の間で雑魚寝をするのは自分だと、葛葉が一歩もひかなかったのだ。
埒があかないと渋面をつくる可畏に配慮したのか、四方が玄関にあった衝立障子をもってきて、二組の蒲団のあいだをさえぎる。
「こうすれば良いのではありませんか?」
「ありがとうございます! 四方少将!」
葛葉は律儀に彼に会釈した。可畏には四方が面白がっているのがわかる。
問題が解決したと言いたげに、葛葉の表情がぱっとあかるくなった。
「おまえはこれで平気なのか?」
「もちろんです」
一片の迷いもない返答である。
複雑な気持ちになったが、可畏はなぜ葛葉の勢いに押し切られているのか、自分がよくわからない。
(まさか、これも花嫁の力か?)
変な女だと強くおもう反面、彼女の様子をみていると調子がくるう。
萎縮しながらも、自分を曲げない威勢の良さがあった。けれど、強情かと思えば素直で、何事にも懸命なのだ。多少のおかしさも愛嬌だと受けとめたくなる。
特務部の第五隊には女子だけの隊があるが、特務華族の子女に見られるような自尊心や傲慢さが、葛葉には感じられない。
孤児であるという貧しい生い立ちのせいかもしれないが、可畏には新鮮にうつった。
(いや、どう考えても変な女だ)
四方が退室して二人きりなると、可畏は衝立障子の向こう側で、ごそごそと落ち着きなく身動きする気配をかんじた。
やはり自分と二人では落ちつかないのだろう。可畏は吐息をついてから声をかける。
「葛葉」
「は、はい!」
「こんな宵前から寝めと言われても、どうせ眠れないだろ」
「……はい」
「ここで起きていることについて話してやる。横になったまま聞いていろ」
「はい!」
あきらかに彼女の意気込みが跳ねあがった。横にならずに正座している気配をかんじる。
やる気だけは人一倍のようだ。
「まず横になれ。私の話を子守唄にして眠れるならそれもいい。仮眠も特務部には重要な任務だ。休むべき時に休めないのは褒められたことじゃない」
「はい」
即座にばさりと蒲団をかぶって横になる気配があった。やはりどこまでも素直である。
「この旧街道周辺には、鬼火がでるという噂がある」
鬼火の伝承や目撃情報は各地にある。人を土葬によって弔ったばあい、屍の腐敗と気候条件によって発光現象がおきる。
墓地で火の玉をみた、鬼火がでたという話は自然現象なのだ。
けれど、可畏のいう鬼火はそれらとは一線を画す。
特務部が追うべき妖の証であり、鬼の痕跡や所在をしめすものだった。
「では、周辺に鬼がいるということですか?」
葛葉からすぐに問いかけがあった。彼女も特務部のさす鬼火の意味は理解している。可畏は子守唄がわりに一方的に語るつもりだったが、やる気をみなぎらせている葛葉が黙って聞いているはずもない。
仮眠をとらせることは諦めたほうがよいのかもしれないと、なかば諦めながら答える。
「潜伏していると踏んで、第三隊が周辺を調査しているが、なかなか手がかりがつかめない」
「御門様が呼ばれるということは、その鬼は今朝うかがった羅刹につながるのでしょうか」
「残念ながら、まだわからない」
「でも、第三隊には少将もいらっしゃいますし、餓鬼のような調伏がたやすい鬼ではないのでは?」
「この件でやっかいなのは、関わっている鬼がどの程度なのかもつかめないところだ。鬼火も噂だけが独り歩きをしていて、実際には誰も見たことがない。だが、その噂の延長に事件が起きている節がある」
「事件?」
「そうだ。鬼火を見たという者が、数日以内に亡くなっている。はじめは作り話かただの偶然だと思われていたようだが、頻繁に犠牲者が出て特務部も看過できなくなった。今日も三人が亡くなったようだ」
伝令で可畏の元に届いたのは、その報せだった。
「三人もですか? でも、それが鬼火と関係があるという確証はどこで? 遺体に何か特徴が?」
葛葉の問いは的を得ていた。どうやら可畏が思っていたより根は聡明なようだ。
鬼や妖が直接人に手をくだすことは稀である。もし犠牲がでる場合、鬼や妖に憑かれた人間の憎悪による殺人か、憑かれた本人の自殺という形で現れる。
死因はすぐに特定されるが、そこに妖の影があるかどうかはわかりにくい。
「この一連の事件がさらに複雑なのは、異形の気配があることだ」
「え?」
「遺体の損壊は人為的なものとは思えない。野犬や害獣の線も当たっているが、どうやら違うらしい。人を食い散らかす何かが在る」
「でも鬼火は妖を示すものですし、異形には人や妖のような知能はないと習いました」
「私のこれまでの経験でもそうだった」
「本当に異形を見た人はいないのですか?」
「そういう報告になっている」
しんと室内に沈黙が満ちる。
「恐ろしいか?」
「いいえ! ただ、もしそれが事実なら、人の目をしのぶ異形がいるということになります」
「そうだな。討伐が困難になる」
にわか隊員の彼女には難易度のたかい任務だが、彼女の能力をより顕現させるには本番あるのみなのだ。異能の発現とともに完全に力が開花するものは多いが、ときおり身の危険によってつよく発現する者があった。葛葉の場合はおろらく後者なのだろう。
「異形は昼夜を問わないが、妖は夜に動くものが多い。私たちは鬼火を追うために、夜にでる。だから、今は仮眠が重要だが……」
「そんなお話を聞いては、余計に眠れません」
素直な反応だった。
「とにかく、いまは子守唄でも唱えて休め」
日没からすでに半刻はすぎている。うとうとした頃には、鬼火を求めて動かねばならない。
12
あなたにおすすめの小説

復讐のための五つの方法
炭田おと
恋愛
皇后として皇帝カエキリウスのもとに嫁いだイネスは、カエキリウスに愛人ルジェナがいることを知った。皇宮ではルジェナが権威を誇示していて、イネスは肩身が狭い思いをすることになる。
それでも耐えていたイネスだったが、父親に反逆の罪を着せられ、家族も、彼女自身も、処断されることが決まった。
グレゴリウス卿の手を借りて、一人生き残ったイネスは復讐を誓う。
72話で完結です。

皇太后(おかあ)様におまかせ!〜皇帝陛下の純愛探し〜
菰野るり
キャラ文芸
皇帝陛下はお年頃。
まわりは縁談を持ってくるが、どんな美人にもなびかない。
なんでも、3年前に一度だけ出逢った忘れられない女性がいるのだとか。手がかりはなし。そんな中、皇太后は自ら街に出て息子の嫁探しをすることに!
この物語の皇太后の名は雲泪(ユンレイ)、皇帝の名は堯舜(ヤオシュン)です。つまり【後宮物語〜身代わり宮女は皇帝陛下に溺愛されます⁉︎〜】の続編です。しかし、こちらから読んでも楽しめます‼︎どちらから読んでも違う感覚で楽しめる⁉︎こちらはポジティブなラブコメです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

後宮の偽花妃 国を追われた巫女見習いは宦官になる
gari@七柚カリン
キャラ文芸
旧題:国を追われた巫女見習いは、隣国の後宮で二重に花開く
☆4月上旬に書籍発売です。たくさんの応援をありがとうございました!☆ 植物を慈しむ巫女見習いの凛月には、二つの秘密がある。それは、『植物の心がわかること』『見目が変化すること』。
そんな凛月は、次期巫女を侮辱した罪を着せられ国外追放されてしまう。
心機一転、紹介状を手に向かったのは隣国の都。そこで偶然知り合ったのは、高官の峰風だった。
峰風の取次ぎで紹介先の人物との対面を果たすが、提案されたのは後宮内での二つの仕事。ある時は引きこもり後宮妃(欣怡)として巫女の務めを果たし、またある時は、少年宦官(子墨)として庭園管理の仕事をする、忙しくも楽しい二重生活が始まった。
仕事中に秘密の能力を活かし活躍したことで、子墨は女嫌いの峰風の助手に抜擢される。女であること・巫女であることを隠しつつ助手の仕事に邁進するが、これがきっかけとなり、宮廷内の様々な騒動に巻き込まれていく。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮なりきり夫婦録
石田空
キャラ文芸
「月鈴、ちょっと嫁に来るか?」
「はあ……?」
雲仙国では、皇帝が三代続いて謎の昏睡状態に陥る事態が続いていた。
あまりにも不可解なために、新しい皇帝を立てる訳にもいかない国は、急遽皇帝の「影武者」として跡継ぎ騒動を防ぐために寺院に入れられていた皇子の空燕を呼び戻すことに決める。
空燕の国の声に応える条件は、同じく寺院で方士修行をしていた方士の月鈴を妃として後宮に入れること。
かくしてふたりは片や皇帝の影武者として、片や皇帝の偽りの愛妃として、後宮と言う名の魔窟に潜入捜査をすることとなった。
影武者夫婦は、後宮内で起こる事件の謎を解けるのか。そしてふたりの想いの行方はいったい。
サイトより転載になります。
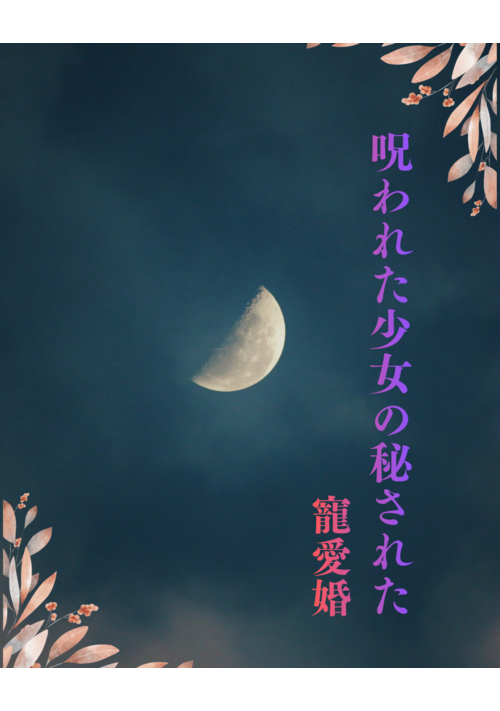
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

今さらやり直しは出来ません
mock
恋愛
3年付き合った斉藤翔平からプロポーズを受けれるかもと心弾ませた小泉彩だったが、当日仕事でどうしても行けないと断りのメールが入り意気消沈してしまう。
落胆しつつ帰る道中、送り主である彼が見知らぬ女性と歩く姿を目撃し、いてもたってもいられず後を追うと二人はさっきまで自身が待っていたホテルへと入っていく。
そんなある日、夢に出てきた高木健人との再会を果たした彩の運命は少しずつ変わっていき……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















