27 / 77
第六章:鬼火と異形
27:暴かれた墓
しおりを挟む
黄昏が近づいている。華やかな大通りも店じまいをはじめ、日中の賑わいが嘘のように辺りが閑散としはじめた。
風が冷たくなり、昨日屋敷に到着した頃のように、ひっそりとした風情が漂う。
「逢う魔が時だな」
可畏が空の果てをながめるように、目を眇めている。
西の空に大きな夕日が赤く燃えている。半刻もしないうちに、空の端が染まり、見事な夕焼けに染まる。
葛葉は長く伸びた自分の影を視線で追った。すぐに立ち並ぶ家屋の大きな影にのまれて沈んでしまう。足元から黄昏の空に目をむけた。
「夕日が綺麗ですが、魑魅魍魎の出そうな迫力があります」
真っ赤に焼ける空。美しいのに禍々しい。地獄の灼熱に続いているかのような、深い夕焼け。
(こっちにおいでー)
そんな空耳が聞こえてきそうだった。ススキ野原の夢を見たからだろうか。
「夕日の怪しさに誘われて、鬼火でも出ればいいが」
可畏が諦めたように吐息をついた。日中の巡回は、何事もなく終わろうとしている。
「ひとまず屋敷に戻ろう」
「はい」
答える葛葉の前を、ひらりと黒い影がよぎった。優雅に羽ばたくのは鴉アゲハの伝令だった。可畏が表情を動かすのをみて、葛葉は何かがあったのだと察する。
「御門様? 何か事件が?」
「寺院の墓が荒らされていたらしい」
葛葉はぞっとしたが、すぐに気持ちを立てなおす。
「でも御門様と寺院を巡回してからは、まだ一刻もたっていません。その後も隊員の方が巡回していたはずですし」
「だが、暴かれているのは間違いない」
「いったい、誰が……」
葛葉は可畏とともに、即座に寺院へ駆けつけた。
境内には数人の隊員と住職の姿があった。暴かれていたのは、無縁仏の埋葬されている塚の一部で、土を掘り返したあとがある。
隊員の話によると、巡回してからいくらも刻がたっていないようだ。
住職も境内に庭火を灯すために僧房からでていた。寺院の敷地内に不審な人影はなく、本堂から山門にかけて、隊員以外に誰かが出入りする様子はなかったという。
「各隊員にも一報をいれる」
可畏が両手を広げると、どこから現れたのか、無数の影がいっせいに放たれる。ひらひらと優雅に羽ばたく様子で、その小さな影が漆黒のアゲハなのだとわかった。
夕闇に呑まれつつある茜の空を、蝶の一群が舞っていく。
伝令をはなつと、可畏は境内に残っている隊員と異形の仕業であるか検証をはじめた。
葛葉も彼らのかたわらで話を聞くが、ふいに肌をなでるような湿った風をかんじる。背筋を指先でなぞられるような、ぞっとした悪寒がせりあがった。
(この感じ、覚えがある)
どこでだったのかは、思い出せない。
思い出せないのに、よくないことの前兆なのだとわかる。
(こころぼそいのかー)
黄昏に輝くススキ野原の光景が脳裏をよぎった。でも、野原の果てから呼ぶ彼らではない。彼らには、こんな恐れは感じなかった。
(もっと、ちがう何か)
じっと見つめてくる誰か。
(わたしを見る眼……)
形にならない印象だけがあった。忘却の彼方にある記憶を引きずりだせない。
ふたたび、ざわりとしめった風が肌をなでる。
(うしろに何かいたら、どうしよう)
手に冷や汗がにじんだ。葛葉はゆっくりと振りかえる。
夕闇の影の中。
見えるはずがないのに、はっきりと視線を感じた。
山門の影に何かがいる。
一気に血の気が引いて、思わず叫ぶ。
「御門様!」
彼の上着の裾を思い切りつかんでいた。
「山門に何かいます!」
金切声がさらに裏返るが、葛葉にはそんなことを気にする余裕がない。
自分を見つめてくる眼。よくないことが起きる前兆。
固く目をとじて競り上がった戦慄に耐えていると、まぶたごしにも感じるほどの光がほとばしる。
風が炎を巻き込むような、ごおっという音が響いた。
ふたたび葛葉が目をあけると、可畏の手からひときわ激しい炎が一閃する。
清浄な蒼い炎。
山門をめがけて飛びだした豪速の火球は、すぐに火柱になった。
「こども?」
可畏が山門の影を見わける。青い炎が陽光のように激しく辺りを照らした。次の瞬間、うわーんとこどもの泣き声がする。
蒼い炎の中から、泣きながら駆け寄ってくる影。ぎこちない足取りで、こちらに走ってくる。
可畏の異能に焼かれることのない、小さな人影。
「……あ」
異能の炎が、人を焼くことはない。
「この子は」
葛葉にも正体がわかった。
ふたつにわけて結った髪。じっとこちらを見てくる黒目がちの瞳。
日中に訪れた長屋で、妙と一緒にいた子どもだった。
突然の火に驚いたのか、しゃくりあげながら葛葉を仰ぐ。
そして、嗚咽しながら訴えた。
「……お姉ちゃんが、いないの」
「お姉ちゃんって、妙さんのこと?」
葛葉が泣きじゃくる童女に寄りそうと、彼女はこくりと深くうなずく。
可畏が異能の炎をおさめた。ふたたび辺りが夕闇に沈むと、雑木林から、ばさばさと何かがとびたつ音がする。
夕闇に呑まれた空で暗くうねるものがあった。漆黒の大群が上空で旋回している。その群れに合流するかのように、木々から飛び立つ影があった。
「鴉の葬式か?」
可畏の言うとおり、朝にもみた鴉の群れだった。
さっきまで視界をいろどっていた夕焼けは、すでに夜に飲みこまれている。とおくの山の端にすこしだけ、名残の色があるだけだった。
鴉たちは、黒い砂あらしのように夜空でうごめいている。その行方をたしかめる暇もなく、どこからかひらりと黒い影が可畏のもとへ集まってきた。
漆黒の蝶がひらひらと舞っている。伝令が届いているのだ。
「どうやら異形がでたらしい」
葛葉はぎくりとしたが、可畏は動じる様子もない。
空で群れる鴉の行方をみながら、彼はその場にいた隊員へ指示をあたえた。ひきつづき寺院にのこる者と、この場から移る者。分かれた隊員が、すばやく動いている。
「葛葉」
「はい」
可畏が不安そうにおびえる童女と葛葉の前に立った。
「私たちはいったんその娘を連れて屋敷へ戻るぞ」
「御門様は、現場に急行しなくても良いのですか?」
「状況は把握している。手に負えないような相手ではない。それよりも、こちらの話も気になる」
「はい」
葛葉は童女の手をひいて歩きながら、寺院の山門をでる。
(さっきの感じは、なんだったんだろう)
山門をふりかえりるが、ひっそりと夜の闇が漂っているだけだった。
まとわりつくような嫌なかんじも、視線もかんじない。
(雰囲気にのまれていたのかな)
暴かれた墓への恐れが、なんでもない童女の気配を錯覚させた。
(もっと、しっかりしないと)
一人前になるには程遠い。自分を叱咤しながら、葛葉は屋敷へもどった。
風が冷たくなり、昨日屋敷に到着した頃のように、ひっそりとした風情が漂う。
「逢う魔が時だな」
可畏が空の果てをながめるように、目を眇めている。
西の空に大きな夕日が赤く燃えている。半刻もしないうちに、空の端が染まり、見事な夕焼けに染まる。
葛葉は長く伸びた自分の影を視線で追った。すぐに立ち並ぶ家屋の大きな影にのまれて沈んでしまう。足元から黄昏の空に目をむけた。
「夕日が綺麗ですが、魑魅魍魎の出そうな迫力があります」
真っ赤に焼ける空。美しいのに禍々しい。地獄の灼熱に続いているかのような、深い夕焼け。
(こっちにおいでー)
そんな空耳が聞こえてきそうだった。ススキ野原の夢を見たからだろうか。
「夕日の怪しさに誘われて、鬼火でも出ればいいが」
可畏が諦めたように吐息をついた。日中の巡回は、何事もなく終わろうとしている。
「ひとまず屋敷に戻ろう」
「はい」
答える葛葉の前を、ひらりと黒い影がよぎった。優雅に羽ばたくのは鴉アゲハの伝令だった。可畏が表情を動かすのをみて、葛葉は何かがあったのだと察する。
「御門様? 何か事件が?」
「寺院の墓が荒らされていたらしい」
葛葉はぞっとしたが、すぐに気持ちを立てなおす。
「でも御門様と寺院を巡回してからは、まだ一刻もたっていません。その後も隊員の方が巡回していたはずですし」
「だが、暴かれているのは間違いない」
「いったい、誰が……」
葛葉は可畏とともに、即座に寺院へ駆けつけた。
境内には数人の隊員と住職の姿があった。暴かれていたのは、無縁仏の埋葬されている塚の一部で、土を掘り返したあとがある。
隊員の話によると、巡回してからいくらも刻がたっていないようだ。
住職も境内に庭火を灯すために僧房からでていた。寺院の敷地内に不審な人影はなく、本堂から山門にかけて、隊員以外に誰かが出入りする様子はなかったという。
「各隊員にも一報をいれる」
可畏が両手を広げると、どこから現れたのか、無数の影がいっせいに放たれる。ひらひらと優雅に羽ばたく様子で、その小さな影が漆黒のアゲハなのだとわかった。
夕闇に呑まれつつある茜の空を、蝶の一群が舞っていく。
伝令をはなつと、可畏は境内に残っている隊員と異形の仕業であるか検証をはじめた。
葛葉も彼らのかたわらで話を聞くが、ふいに肌をなでるような湿った風をかんじる。背筋を指先でなぞられるような、ぞっとした悪寒がせりあがった。
(この感じ、覚えがある)
どこでだったのかは、思い出せない。
思い出せないのに、よくないことの前兆なのだとわかる。
(こころぼそいのかー)
黄昏に輝くススキ野原の光景が脳裏をよぎった。でも、野原の果てから呼ぶ彼らではない。彼らには、こんな恐れは感じなかった。
(もっと、ちがう何か)
じっと見つめてくる誰か。
(わたしを見る眼……)
形にならない印象だけがあった。忘却の彼方にある記憶を引きずりだせない。
ふたたび、ざわりとしめった風が肌をなでる。
(うしろに何かいたら、どうしよう)
手に冷や汗がにじんだ。葛葉はゆっくりと振りかえる。
夕闇の影の中。
見えるはずがないのに、はっきりと視線を感じた。
山門の影に何かがいる。
一気に血の気が引いて、思わず叫ぶ。
「御門様!」
彼の上着の裾を思い切りつかんでいた。
「山門に何かいます!」
金切声がさらに裏返るが、葛葉にはそんなことを気にする余裕がない。
自分を見つめてくる眼。よくないことが起きる前兆。
固く目をとじて競り上がった戦慄に耐えていると、まぶたごしにも感じるほどの光がほとばしる。
風が炎を巻き込むような、ごおっという音が響いた。
ふたたび葛葉が目をあけると、可畏の手からひときわ激しい炎が一閃する。
清浄な蒼い炎。
山門をめがけて飛びだした豪速の火球は、すぐに火柱になった。
「こども?」
可畏が山門の影を見わける。青い炎が陽光のように激しく辺りを照らした。次の瞬間、うわーんとこどもの泣き声がする。
蒼い炎の中から、泣きながら駆け寄ってくる影。ぎこちない足取りで、こちらに走ってくる。
可畏の異能に焼かれることのない、小さな人影。
「……あ」
異能の炎が、人を焼くことはない。
「この子は」
葛葉にも正体がわかった。
ふたつにわけて結った髪。じっとこちらを見てくる黒目がちの瞳。
日中に訪れた長屋で、妙と一緒にいた子どもだった。
突然の火に驚いたのか、しゃくりあげながら葛葉を仰ぐ。
そして、嗚咽しながら訴えた。
「……お姉ちゃんが、いないの」
「お姉ちゃんって、妙さんのこと?」
葛葉が泣きじゃくる童女に寄りそうと、彼女はこくりと深くうなずく。
可畏が異能の炎をおさめた。ふたたび辺りが夕闇に沈むと、雑木林から、ばさばさと何かがとびたつ音がする。
夕闇に呑まれた空で暗くうねるものがあった。漆黒の大群が上空で旋回している。その群れに合流するかのように、木々から飛び立つ影があった。
「鴉の葬式か?」
可畏の言うとおり、朝にもみた鴉の群れだった。
さっきまで視界をいろどっていた夕焼けは、すでに夜に飲みこまれている。とおくの山の端にすこしだけ、名残の色があるだけだった。
鴉たちは、黒い砂あらしのように夜空でうごめいている。その行方をたしかめる暇もなく、どこからかひらりと黒い影が可畏のもとへ集まってきた。
漆黒の蝶がひらひらと舞っている。伝令が届いているのだ。
「どうやら異形がでたらしい」
葛葉はぎくりとしたが、可畏は動じる様子もない。
空で群れる鴉の行方をみながら、彼はその場にいた隊員へ指示をあたえた。ひきつづき寺院にのこる者と、この場から移る者。分かれた隊員が、すばやく動いている。
「葛葉」
「はい」
可畏が不安そうにおびえる童女と葛葉の前に立った。
「私たちはいったんその娘を連れて屋敷へ戻るぞ」
「御門様は、現場に急行しなくても良いのですか?」
「状況は把握している。手に負えないような相手ではない。それよりも、こちらの話も気になる」
「はい」
葛葉は童女の手をひいて歩きながら、寺院の山門をでる。
(さっきの感じは、なんだったんだろう)
山門をふりかえりるが、ひっそりと夜の闇が漂っているだけだった。
まとわりつくような嫌なかんじも、視線もかんじない。
(雰囲気にのまれていたのかな)
暴かれた墓への恐れが、なんでもない童女の気配を錯覚させた。
(もっと、しっかりしないと)
一人前になるには程遠い。自分を叱咤しながら、葛葉は屋敷へもどった。
12
あなたにおすすめの小説

復讐のための五つの方法
炭田おと
恋愛
皇后として皇帝カエキリウスのもとに嫁いだイネスは、カエキリウスに愛人ルジェナがいることを知った。皇宮ではルジェナが権威を誇示していて、イネスは肩身が狭い思いをすることになる。
それでも耐えていたイネスだったが、父親に反逆の罪を着せられ、家族も、彼女自身も、処断されることが決まった。
グレゴリウス卿の手を借りて、一人生き残ったイネスは復讐を誓う。
72話で完結です。

皇太后(おかあ)様におまかせ!〜皇帝陛下の純愛探し〜
菰野るり
キャラ文芸
皇帝陛下はお年頃。
まわりは縁談を持ってくるが、どんな美人にもなびかない。
なんでも、3年前に一度だけ出逢った忘れられない女性がいるのだとか。手がかりはなし。そんな中、皇太后は自ら街に出て息子の嫁探しをすることに!
この物語の皇太后の名は雲泪(ユンレイ)、皇帝の名は堯舜(ヤオシュン)です。つまり【後宮物語〜身代わり宮女は皇帝陛下に溺愛されます⁉︎〜】の続編です。しかし、こちらから読んでも楽しめます‼︎どちらから読んでも違う感覚で楽しめる⁉︎こちらはポジティブなラブコメです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

後宮の偽花妃 国を追われた巫女見習いは宦官になる
gari@七柚カリン
キャラ文芸
旧題:国を追われた巫女見習いは、隣国の後宮で二重に花開く
☆4月上旬に書籍発売です。たくさんの応援をありがとうございました!☆ 植物を慈しむ巫女見習いの凛月には、二つの秘密がある。それは、『植物の心がわかること』『見目が変化すること』。
そんな凛月は、次期巫女を侮辱した罪を着せられ国外追放されてしまう。
心機一転、紹介状を手に向かったのは隣国の都。そこで偶然知り合ったのは、高官の峰風だった。
峰風の取次ぎで紹介先の人物との対面を果たすが、提案されたのは後宮内での二つの仕事。ある時は引きこもり後宮妃(欣怡)として巫女の務めを果たし、またある時は、少年宦官(子墨)として庭園管理の仕事をする、忙しくも楽しい二重生活が始まった。
仕事中に秘密の能力を活かし活躍したことで、子墨は女嫌いの峰風の助手に抜擢される。女であること・巫女であることを隠しつつ助手の仕事に邁進するが、これがきっかけとなり、宮廷内の様々な騒動に巻き込まれていく。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮なりきり夫婦録
石田空
キャラ文芸
「月鈴、ちょっと嫁に来るか?」
「はあ……?」
雲仙国では、皇帝が三代続いて謎の昏睡状態に陥る事態が続いていた。
あまりにも不可解なために、新しい皇帝を立てる訳にもいかない国は、急遽皇帝の「影武者」として跡継ぎ騒動を防ぐために寺院に入れられていた皇子の空燕を呼び戻すことに決める。
空燕の国の声に応える条件は、同じく寺院で方士修行をしていた方士の月鈴を妃として後宮に入れること。
かくしてふたりは片や皇帝の影武者として、片や皇帝の偽りの愛妃として、後宮と言う名の魔窟に潜入捜査をすることとなった。
影武者夫婦は、後宮内で起こる事件の謎を解けるのか。そしてふたりの想いの行方はいったい。
サイトより転載になります。
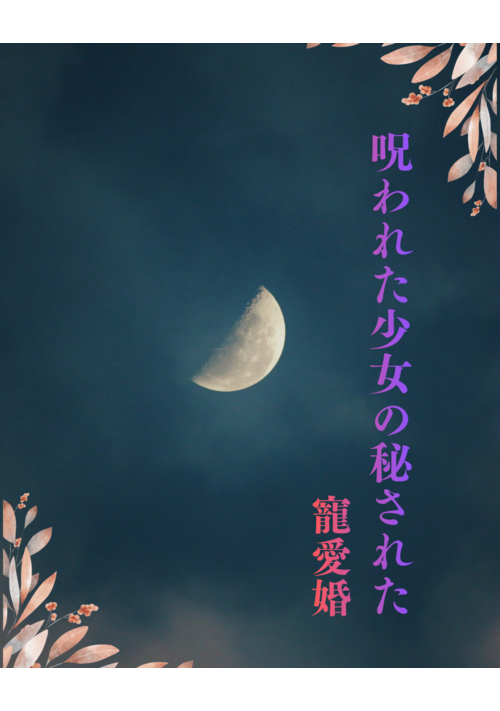
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

今さらやり直しは出来ません
mock
恋愛
3年付き合った斉藤翔平からプロポーズを受けれるかもと心弾ませた小泉彩だったが、当日仕事でどうしても行けないと断りのメールが入り意気消沈してしまう。
落胆しつつ帰る道中、送り主である彼が見知らぬ女性と歩く姿を目撃し、いてもたってもいられず後を追うと二人はさっきまで自身が待っていたホテルへと入っていく。
そんなある日、夢に出てきた高木健人との再会を果たした彩の運命は少しずつ変わっていき……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















