46 / 53
希望の兆し
しおりを挟む
(これが『闇の糸』……ローズの私への想いなのだな……)
フェルナンド皇帝は、ローズ皇妃が放った『闇の糸』に全身を覆いつくされ、自分がどこにいるのかも分からなかった。
ただ耳を切り裂く阿鼻叫喚と身を切る激しい痛み、焼き尽くすかの如く灼熱が押し寄せ、『闇の糸』の中でフェルナンドは死を覚悟していた。
「ああっ、陛下の姿が見えませんわ! あの気味の悪い靄は何ですの? なぜ『大地の精霊リュー』の力を使われないのかしら」
固唾を呑んでその場を見守っていたアリーヌは、我慢できず叫んだ。
「それは……強大な『大地の精霊リュー』の力を使えば、ローズ様に大変な傷を負わせてしまうわ」
「それじゃあ陛下は……」
「それに『大地の精霊リュー』の力では、『闇の精霊エゴヌ』の封印はできないの」
「オレリーお姉様、『闇の精霊エゴヌ』って……?」
「……古に存在した精霊の力。人々の憎悪を強い呪いに変えてしまう恐ろしい力よ」
「そんな精霊が存在するだなんて……」
アリーヌは信じられないという表情を浮かべ言葉を失った。
オレリーは、フェルナンドの命もこのままでは消えてしまうのではと不安が頭をよぎった。
(でも、陛下がローズ様の心を掬い上げるしか『闇の糸』を止める方法はないわ。ローズ様の命の灯も少ないはず……)
「陛下! ローズ様は取り繕った言葉も見せかけの関係も望まれていませんわ! 本当に望まれているのは、純粋な心の交流ではありませんか?」
オレリーは隠れていたことを忘れ、思わず声を上げた。
「オレリー嬢……しかし私はローズの心に応えることは出来ないのだ。私の心を渡せないのに、どうやってローズの心を救うというのだ」
「たとえ男女の愛を育めなかったとしても、人としての信頼や絆は育めたはずですわ」
「やめて! やめなさい! なんて目障りな娘……お前にわたくしの孤独や苦しみが分かるというの!」
ローズは燃え盛る怒りの炎をその琥珀色の瞳に映し、今度はオレリーに『闇の糸』のオーラで襲いかかった。
「オレリーお姉様!」
アリーヌの隣でオレリーが黒い靄にたちまち飲み込まれた。
オレリーは目を開けると、『闇の糸』に襲われたとは思えないほど静かな闇の中にいた。
ただ寂しく震えているような、沈んだ琥珀色のローズの魂が目の前を漂っていた。
「ああ、もう私は消えるだけなのね。最後に陛下とカトリーヌ様の命を呪いで奪って……私には何が残ったのかしら」
ローズの魂の叫びがオレリーの耳に悲しい音色となって届いた。
オレリーは同じように『闇の糸』に飲み込まれたフェルナンドの姿を探した。
(セリュネア様……どうか私に力をお貸し下さい)
そう祈ったオレリーの体から、まるで闇を覆うように柔らかで温かな光が放たれた。
「陛下……」
放心状態で虚空を見つめているフェルナンドを見つけ、オレリーは駆け寄った。
「ああ、オレリー嬢よ……もうローズは逝ってしまったのか?」
「いいえ、陛下」
「ローズは私の大切な者たちを傷付けた。憎いのだ……憎い。しかしローズが憐れで……もっと近付きたいという心もあったのだ」
「陛下、人の心は割り切れないものですわ。初めから憎しみ合っていたわけではありませんから」
「憎しみ合いながらも……互いに絆を取り戻したいと心のどこかで願っていたのかもしれぬな」
そう言うとフェルナンドは、そっとローズの魂を胸に抱いた。
「寂しい思いをさせて……すまなかった」
ローズの魂が応えるように美しい琥珀色に変わり、覆われていた闇が完全に消え失せた。
「陛下! オレリーお姉様!」
アリーヌは突然闇が消えたかと思うと、フェルナンドの腕に抱かれたローズの姿を見つけた。
その傍らにはオレリーがいた。
「わたくしの命は……もう尽きるでしょう。『闇の糸』で人々を苦しめた対価を払うのは当然ですから」
「ローズ……」
ローズの命が尽きようとした時、ジェレミーが勢いよく部屋に入って来た。
「お母様!」
ローズは閉じかけた瞼を再び開いた。
「ジェレミー……わたくしの愛する息子。皇太子の座も権力もその手に掴ませてやれなかった……何も残してあげられなくて、ごめんなさい」
「お母様! 僕は……そんなもの一度も望んでいません! お母様に愛されていたから……僕は自分で人生を切り開く覚悟はできていたのですよ!」
ローズは小さく息を吐き、ジェレミーの方へ手を差し伸べた。
ジェレミーはその手をしっかりと握り、涙を流しながらもローズに優しく微笑んだ。
「お母様、僕の笑顔を覚えていて下さい……」
「……ええ、ありがとう、ジェレミー。陛下、ごめんなさい。それにカトリーヌ様とアレクシス殿下にも」
「必ず伝えよう」
ローズはオレリーの方を向いた。
「アレクサンドル公爵にご両親の事を……お詫びして許されることではないけれど。ごめんなさい」
「お母様の罪は僕も背負い償います。『精霊の闇エゴヌ』に心を囚われないためにも」
「私も同じように背負って償おう」
フェルナンドはジェレミーの手に手を重ねた。
「ローズ様、ロシュー……ロシュディ様には必ずお伝えしますわ」
そして強い眼差しでオレリーはローズを見た。
「ローズ様、今、リアンはどこへ?」
「ベルタ……いえベルタの姿をしたエリカ嬢の手の中にいるわ。わたくしが消えるせいで……『闇の精霊エゴヌ』はベルタ姫に力を授けたわ」
「私は娘を必ず救います。この命に代えても……ですから、どうか安らかに」
ローズの瞳から一筋の涙が流れた。
そして、オレリーの言葉を聞いたローズは静かに逝った。
「オレリーお姉様……一体何が起こったのか……私には……」
アリーヌは目の前で起こった事が現実のものとは思えなかった。
「オレリー嬢、早くリアン嬢とアレクサンドル公爵の元へ行って下さい!」
「ロシューがどうして……」
「エリカ嬢……それにベルタ姫との因縁はアレクサンドル公爵しか終わらせられないでしょう」
「私の娘はどこにいるのですか!」
「きっと謁見室だと思う……兄上が糸を引いているなら」
オレリーは心のざわめきを感じながら、ロシュディとリアンの元へ急いだ。
フェルナンド皇帝は、ローズ皇妃が放った『闇の糸』に全身を覆いつくされ、自分がどこにいるのかも分からなかった。
ただ耳を切り裂く阿鼻叫喚と身を切る激しい痛み、焼き尽くすかの如く灼熱が押し寄せ、『闇の糸』の中でフェルナンドは死を覚悟していた。
「ああっ、陛下の姿が見えませんわ! あの気味の悪い靄は何ですの? なぜ『大地の精霊リュー』の力を使われないのかしら」
固唾を呑んでその場を見守っていたアリーヌは、我慢できず叫んだ。
「それは……強大な『大地の精霊リュー』の力を使えば、ローズ様に大変な傷を負わせてしまうわ」
「それじゃあ陛下は……」
「それに『大地の精霊リュー』の力では、『闇の精霊エゴヌ』の封印はできないの」
「オレリーお姉様、『闇の精霊エゴヌ』って……?」
「……古に存在した精霊の力。人々の憎悪を強い呪いに変えてしまう恐ろしい力よ」
「そんな精霊が存在するだなんて……」
アリーヌは信じられないという表情を浮かべ言葉を失った。
オレリーは、フェルナンドの命もこのままでは消えてしまうのではと不安が頭をよぎった。
(でも、陛下がローズ様の心を掬い上げるしか『闇の糸』を止める方法はないわ。ローズ様の命の灯も少ないはず……)
「陛下! ローズ様は取り繕った言葉も見せかけの関係も望まれていませんわ! 本当に望まれているのは、純粋な心の交流ではありませんか?」
オレリーは隠れていたことを忘れ、思わず声を上げた。
「オレリー嬢……しかし私はローズの心に応えることは出来ないのだ。私の心を渡せないのに、どうやってローズの心を救うというのだ」
「たとえ男女の愛を育めなかったとしても、人としての信頼や絆は育めたはずですわ」
「やめて! やめなさい! なんて目障りな娘……お前にわたくしの孤独や苦しみが分かるというの!」
ローズは燃え盛る怒りの炎をその琥珀色の瞳に映し、今度はオレリーに『闇の糸』のオーラで襲いかかった。
「オレリーお姉様!」
アリーヌの隣でオレリーが黒い靄にたちまち飲み込まれた。
オレリーは目を開けると、『闇の糸』に襲われたとは思えないほど静かな闇の中にいた。
ただ寂しく震えているような、沈んだ琥珀色のローズの魂が目の前を漂っていた。
「ああ、もう私は消えるだけなのね。最後に陛下とカトリーヌ様の命を呪いで奪って……私には何が残ったのかしら」
ローズの魂の叫びがオレリーの耳に悲しい音色となって届いた。
オレリーは同じように『闇の糸』に飲み込まれたフェルナンドの姿を探した。
(セリュネア様……どうか私に力をお貸し下さい)
そう祈ったオレリーの体から、まるで闇を覆うように柔らかで温かな光が放たれた。
「陛下……」
放心状態で虚空を見つめているフェルナンドを見つけ、オレリーは駆け寄った。
「ああ、オレリー嬢よ……もうローズは逝ってしまったのか?」
「いいえ、陛下」
「ローズは私の大切な者たちを傷付けた。憎いのだ……憎い。しかしローズが憐れで……もっと近付きたいという心もあったのだ」
「陛下、人の心は割り切れないものですわ。初めから憎しみ合っていたわけではありませんから」
「憎しみ合いながらも……互いに絆を取り戻したいと心のどこかで願っていたのかもしれぬな」
そう言うとフェルナンドは、そっとローズの魂を胸に抱いた。
「寂しい思いをさせて……すまなかった」
ローズの魂が応えるように美しい琥珀色に変わり、覆われていた闇が完全に消え失せた。
「陛下! オレリーお姉様!」
アリーヌは突然闇が消えたかと思うと、フェルナンドの腕に抱かれたローズの姿を見つけた。
その傍らにはオレリーがいた。
「わたくしの命は……もう尽きるでしょう。『闇の糸』で人々を苦しめた対価を払うのは当然ですから」
「ローズ……」
ローズの命が尽きようとした時、ジェレミーが勢いよく部屋に入って来た。
「お母様!」
ローズは閉じかけた瞼を再び開いた。
「ジェレミー……わたくしの愛する息子。皇太子の座も権力もその手に掴ませてやれなかった……何も残してあげられなくて、ごめんなさい」
「お母様! 僕は……そんなもの一度も望んでいません! お母様に愛されていたから……僕は自分で人生を切り開く覚悟はできていたのですよ!」
ローズは小さく息を吐き、ジェレミーの方へ手を差し伸べた。
ジェレミーはその手をしっかりと握り、涙を流しながらもローズに優しく微笑んだ。
「お母様、僕の笑顔を覚えていて下さい……」
「……ええ、ありがとう、ジェレミー。陛下、ごめんなさい。それにカトリーヌ様とアレクシス殿下にも」
「必ず伝えよう」
ローズはオレリーの方を向いた。
「アレクサンドル公爵にご両親の事を……お詫びして許されることではないけれど。ごめんなさい」
「お母様の罪は僕も背負い償います。『精霊の闇エゴヌ』に心を囚われないためにも」
「私も同じように背負って償おう」
フェルナンドはジェレミーの手に手を重ねた。
「ローズ様、ロシュー……ロシュディ様には必ずお伝えしますわ」
そして強い眼差しでオレリーはローズを見た。
「ローズ様、今、リアンはどこへ?」
「ベルタ……いえベルタの姿をしたエリカ嬢の手の中にいるわ。わたくしが消えるせいで……『闇の精霊エゴヌ』はベルタ姫に力を授けたわ」
「私は娘を必ず救います。この命に代えても……ですから、どうか安らかに」
ローズの瞳から一筋の涙が流れた。
そして、オレリーの言葉を聞いたローズは静かに逝った。
「オレリーお姉様……一体何が起こったのか……私には……」
アリーヌは目の前で起こった事が現実のものとは思えなかった。
「オレリー嬢、早くリアン嬢とアレクサンドル公爵の元へ行って下さい!」
「ロシューがどうして……」
「エリカ嬢……それにベルタ姫との因縁はアレクサンドル公爵しか終わらせられないでしょう」
「私の娘はどこにいるのですか!」
「きっと謁見室だと思う……兄上が糸を引いているなら」
オレリーは心のざわめきを感じながら、ロシュディとリアンの元へ急いだ。
1
あなたにおすすめの小説
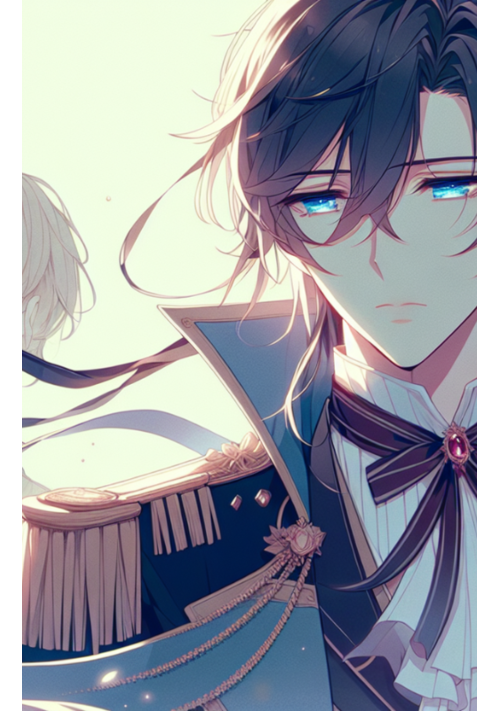
私たちの離婚幸福論
桔梗
ファンタジー
ヴェルディア帝国の皇后として、順風満帆な人生を歩んでいたルシェル。
しかし、彼女の平穏な日々は、ノアの突然の記憶喪失によって崩れ去る。
彼はルシェルとの記憶だけを失い、代わりに”愛する女性”としてイザベルを迎え入れたのだった。
信じていた愛が消え、冷たく突き放されるルシェル。
だがそこに、隣国アンダルシア王国の皇太子ゼノンが現れ、驚くべき提案を持ちかける。
それは救済か、あるいは——
真実を覆う闇の中、ルシェルの新たな運命が幕を開ける。

離婚した彼女は死ぬことにした
はるかわ 美穂
恋愛
事故で命を落とす瞬間、政略結婚で結ばれた夫のアルバートを愛していたことに気づいたエレノア。
もう一度彼との結婚生活をやり直したいと願うと、四年前に巻き戻っていた。
今度こそ彼に相応しい妻になりたいと、これまでの臆病な自分を脱ぎ捨て奮闘するエレノア。しかし、
「前にも言ったけど、君は妻としての役目を果たさなくていいんだよ」
返ってくるのは拒絶を含んだ鉄壁の笑みと、表面的で義務的な優しさ。
それでも夫に想いを捧げ続けていたある日のこと、アルバートの大事にしている弟妹が原因不明の体調不良に襲われた。
神官から、二人の体調不良はエレノアの体内に宿る瘴気が原因だと告げられる。
大切な人を守るために離婚して彼らから離れることをエレノアは決意するが──。

壊れていく音を聞きながら
夢窓(ゆめまど)
恋愛
結婚してまだ一か月。
妻の留守中、夫婦の家に突然やってきた母と姉と姪
何気ない日常のひと幕が、
思いもよらない“ひび”を生んでいく。
母と嫁、そしてその狭間で揺れる息子。
誰も気づきがないまま、
家族のかたちが静かに崩れていく――。
壊れていく音を聞きながら、
それでも誰かを思うことはできるのか。

婚姻契約には愛情は含まれていません。 旦那様には愛人がいるのですから十分でしょう?
すもも
恋愛
伯爵令嬢エーファの最も嫌いなものは善人……そう思っていた。
人を救う事に生き甲斐を感じていた両親が、陥った罠によって借金まみれとなった我が家。
これでは領民が冬を越せない!!
善良で善人で、人に尽くすのが好きな両親は何の迷いもなくこう言った。
『エーファ、君の結婚が決まったんだよ!! 君が嫁ぐなら、お金をくれるそうだ!! 領民のために尽くすのは領主として当然の事。 多くの命が救えるなんて最高の幸福だろう。 それに公爵家に嫁げばお前も幸福になるに違いない。 これは全員が幸福になれる機会なんだ、当然嫁いでくれるよな?』
と……。
そして、夫となる男の屋敷にいたのは……三人の愛人だった。

寵愛の花嫁は毒を愛でる~いじわる義母の陰謀を華麗にスルーして、最愛の公爵様と幸せになります~
紅葉山参
恋愛
アエナは貧しい子爵家から、国の英雄と名高いルーカス公爵の元へと嫁いだ。彼との政略結婚は、彼の底なしの優しさと、情熱的な寵愛によって、アエナにとってかけがえのない幸福となった。しかし、その幸福を妬み、毎日のように粘着質ないじめを繰り返す者が一人、それは夫の継母であるユーカ夫人である。
「たかが子爵の娘が、公爵家の奥様面など」 ユーカ様はそう言って、私に次から次へと理不尽な嫌がらせを仕掛けてくる。大切な食器を隠したり、ルーカス様に嘘の告げ口をしたり、社交界で恥をかかせようとしたり。
だが、私は決して挫けない。愛する公爵様との穏やかな日々を守るため、そして何より、彼が大切な家族と信じているユーカ様を悲しませないためにも、私はこの毒を静かに受け流すことに決めたのだ。
誰も気づかないほど巧妙に、いじめを優雅にスルーするアエナ。公爵であるあなたに心配をかけまいと、彼女は今日も微笑みを絶やさない。しかし、毒は徐々に、確実に、その濃度を増していく。ついに義母は、アエナの命に関わるような、取り返しのつかない大罪に手を染めてしまう。
愛と策略、そして運命の結末。この溺愛系ヒロインが、華麗なるスルー術で、最愛の公爵様との未来を掴み取る、痛快でロマンティックな物語の幕開けです。


旦那様、そんなに彼女が大切なら私は邸を出ていきます
おてんば松尾
恋愛
彼女は二十歳という若さで、領主の妻として領地と領民を守ってきた。二年後戦地から夫が戻ると、そこには見知らぬ女性の姿があった。連れ帰った親友の恋人とその子供の面倒を見続ける旦那様に、妻のソフィアはとうとう離婚届を突き付ける。
if 主人公の性格が変わります(元サヤ編になります)
※こちらの作品カクヨムにも掲載します

悪役令嬢、記憶をなくして辺境でカフェを開きます〜お忍びで通ってくる元婚約者の王子様、私はあなたのことなど知りません〜
咲月ねむと
恋愛
王子の婚約者だった公爵令嬢セレスティーナは、断罪イベントの最中、興奮のあまり階段から転げ落ち、頭を打ってしまう。目覚めた彼女は、なんと「悪役令嬢として生きてきた数年間」の記憶をすっぽりと失い、動物を愛する心優しくおっとりした本来の性格に戻っていた。
もはや王宮に居場所はないと、自ら婚約破棄を申し出て辺境の領地へ。そこで動物たちに異常に好かれる体質を活かし、もふもふの聖獣たちが集まるカフェを開店し、穏やかな日々を送り始める。
一方、セレスティーナの豹変ぶりが気になって仕方ない元婚約者の王子・アルフレッドは、身分を隠してお忍びでカフェを訪れる。別人になったかのような彼女に戸惑いながらも、次第に本当の彼女に惹かれていくが、セレスティーナは彼のことを全く覚えておらず…?
※これはかなり人を選ぶ作品です。
感想欄にもある通り、私自身も再度読み返してみて、皆様のおっしゃる通りもう少しプロットをしっかりしてればと。
それでも大丈夫って方は、ぜひ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















