1 / 1
猫の島
しおりを挟む
1. 休息の旅へ
「……というわけで、アイリさん。今日は約束どおり《猫の島》いえ、沖島へ行きますよ!」
神崎イサナは、やけに嬉しそうに胸を張った。
彼と黒野アイリが訪れているのは、滋賀県・琵琶湖。
先日、県内の別の場所で起きた異変の調査を終えたばかりだった。
ひと仕事終えた後の少しの余暇——それを利用して、神崎がずっと気になっていた場所へ向かうことになったのだ。
「沖島って知ってます? 日本で唯一、人が住んでいる《湖に浮かぶ有人島》なんですよ。そして昔は……猫がいっぱいいて、《猫の島》って呼ばれてたんです」
「……昔は、か」
アイリはわずかに眉を動かす。
「最近は猫が減っちゃったらしいんですけどね。それでも、島の暮らしとか、猫の名残とか、見てみたいなぁって」
神崎は、スマホの画面を見せながら続ける。映っているのは、少し前の、猫の多かった頃の写真だ。
「……それで先日からやたら騒いでいたのか」
アイリは呆れたようにため息をつく。
確かに、ここ数日、神崎はしきりにスマホを見ながら「癒される……」とか「これは行くしかない」とか、何やら浮かれた様子だった。
「まあ、仕事は終わりましたし、少しくらい観光してもいいでしょう?」
「……私はどこでも構わないが」
アイリは淡々と答えた。
(……それにしても)
彼女はちらりと神崎を見やる。
彼は、どこか安心したような顔をしていた。
神崎イサナ。
金髪碧眼の華やかな顔立ちをした男。
普段は軽薄そうに見えるが、その奥には鋭い観察眼を持ち、場の空気を読むのに長けている。
今日は黒のパーカーにカジュアルなデニム姿。
軽やかな服装だが、その仕草にはどこか気品を感じさせる。
(事件続きの冥府庁の仕事では、どうしても《死》と向き合うことが多い)
(……だからこそ、今くらいは)
アイリは、静かに視線を戻した。
「……行くぞ、船が出る」
「はい!」
神崎は満面の笑みで頷くと、勢いよく桟橋へ向かった。
2. 湖の船旅
船に乗り込むと、思ったよりも風が強かった。
琵琶湖は波が穏やかとはいえ、広い湖上では風が吹き抜ける。
アイリは、一瞬だけ神崎を見やる。
(……こいつ、本当に大丈夫なのか?)
彼は過去に「船が苦手」と言っていたことがある。
だが、今のところ、特に酔っている様子はない。
「いやぁ、船は苦手なんですけどね」
神崎はどこか楽しげに言った。
「でも、琵琶湖なら波も穏やかで酔いにくいらしいんですよ! これは素晴らしい」
「……本当に船が苦手なら、もっと別の場所を選べばいいだろう」
「いやいや、《猫の島》のためなら俺は多少の波くらい耐えます」
神崎は腕を組み、どこか誇らしげに言った。
アイリは、かすかに眉を寄せる。
「……風が強い。気分が悪くなったら言え」
「アイリさん、意外と優しいですね?」
「別に。お前に吐かれたら面倒だからだ」
「はいはい、ちゃんと耐えますよ」
そう言いながらも、神崎の表情は明るいままだった。
湖の青が広がる。
島が少しずつ近づいてくると、桟橋に座る猫の姿が見えた。
「……あ、いましたよ!」
神崎が指差した先。
そこには、のんびりと桟橋の端に座る一匹の猫がいた。
「……一匹だけか」
アイリがぽつりと呟く。
「ええ。でも、ちゃんといるじゃないですか」
神崎は、もう心を奪われたような顔をしていた。
3. 猫の楽園と島の暮らし
沖島に足を踏み入れると、すぐに島独特の静けさを感じた。
車がほとんどないこの島では、鳥の声や風の音、波の音がよく通る。
その合間に——。
「にゃあ」
小さな鳴き声が迎えてくれる。
「おおっ……!」
神崎は思わず立ち止まった。
路地の先で、二匹の猫がゆるやかに歩いていた。写真集で見た「猫だらけ」の風景とは違うが、それでもこの島が猫と共にあった時間を思わせる光景だった。
「神崎……お前、そんなに猫が好きだったのか」
アイリが冷静に問いかける。
「ええ、もう大好きですよ!」
神崎は満面の笑みで答える。
島には漁港があり、網の上で昼寝をしている猫もいる——と言っても、その姿はまばらだ。漁師たちが黙々と網を直す横で、一匹の猫がのんびりと毛繕いをしている。そのささやかな存在が、逆に目を引いた。
「……いいですね。ここに住んでいる人たちは、ずっと猫と一緒に暮らしてきたんですね」
「この島は、漁師の町だ」
アイリがぽつりと言う。
「……漁港の魚が猫の食料になり、猫はネズミを捕る。昔から人と共存してきたんだろう」
「なるほど……素敵な関係ですね」
神崎は、しばらく猫を撫でたあと、ふと周囲を見渡した。
「……アイリさん、お腹空きません?」
「まあ、少しくらいなら」
「じゃあ、小さな食堂があるらしいので、行きましょう!」
4. 小さな食堂での昼食
島の細い路地を抜けると、小さな食堂があった。
暖簾をくぐると、優しい煮炊きの香りが漂う。昔ながらの日本家屋そのままのどこか懐かしい感じの内装だ。
店主のおばあさんが、穏やかな笑顔で迎えてくれた。
「おや、旅のお客さんかい?」
「はい。《猫の島》って聞いて、来てみました」
神崎がにこやかに答えると、おばあさんは少し懐かしそうに目を細めた。
「昔はねぇ、本当にそこらじゅう猫だらけでね。今はだいぶ減っちゃったけど……まだ何匹かは、島の子みたいな顔して歩いてるよ」
そう言って笑う足元には、小さな三毛猫が座っていた。
「……こちらのおすすめは?」
アイリが尋ねると、おばあさんはメニューを指差す。
「ここは元々漁業で有名な島だからね。琵琶湖の恵みを味わって欲しいね。鮒寿司や小鮎の天ぷらや佃煮が人気だよ」
「いいですね、それください!」
神崎は迷わず注文し、アイリもそれに倣った。
カラリと揚がった小鮎の天ぷらを頬張る神崎。
「……これは美味しい」
アイリも静かに佃煮を口に運ぶ。
(……湖の恵みを、こうして受けて生きている人たちがいる)
事件の調査では、非日常ばかりを目にする。
だが、こうして普通の暮らしに触れると、どこかほっとするものがあった。
「猫も、だいぶ年をとっちゃってねぇ。島の人も減ったし……」
おばあさんは、窓の外を見やりながらぽつりと言った。
「それでも、こうやって猫目当てでもたまにそとから来てくれる人がいると、何だか嬉しいよ」
静かな島の食堂で、猫と人と、ささやかな食事。
それもまた、彼らにとって必要な時間だった。
——束の間の休息が、穏やかに流れていく。
冥府庁の旅は、まだ続く。
5. 猫と島の午後
小さな食堂を後にし、二人は島の細い路地を歩いていた。
島の家々はどこもこぢんまりとしており、玄関先には鉢植えや干した網が並ぶ。
かつては猫がずらりと並んでいたという軒先も、今はぽつりぽつりと、日向で丸くなる姿があるだけだ。
「……思っていたより静かですね」
神崎はそう言いながら、見かけた猫のところへしゃがみ込んで撫でる。
「ここに住む人たちにとって、猫は特別な存在なんだろうな」
アイリは、ゆったりとした町並みを眺めながら静かに言った。
「そうですね。数は減っても、ちゃんと“ここにいる”って感じがします」
神崎は猫と目線を合わせるように屈み、穏やかに微笑んだ。
(……あいつ、ずっと楽しそうだな)
アイリは神崎を観察しながら、ふとそんなことを思った。
彼の金髪は湖からの風に揺れ、碧い瞳は猫を映している。
普段は軽薄そうな表情を見せることもあるが、今はただ純粋にこの時間を楽しんでいるように見えた。
(こういう時間も、悪くないな)
そんなことを考えながら細い路地を歩いていると、小高い丘の上に差し掛かった。
階段を登っていくと、そこは小さな神社の境内だった。
鳥居の下で、二、三匹の猫が丸くなっている。
「……ここにもいますね」
神崎はふわりと笑った。
「猫にとっても、神社って落ち着く場所なんでしょうか」
「……かもしれないな」
アイリは鳥居を見上げた。
小さな祠があり、誰かがお供えをした形跡がある。辺りは静かな空気に満ちていた。
「ここにいる猫は、みんな穏やかですね」
神崎は境内のベンチに腰掛け、ゆっくりと息を吐いた。
「こういう場所で暮らすっていうのも、いいなぁ」
「お前がここに住んだら、船の移動で毎回酔いそうだが」
「それは……確かに」
神崎は苦笑した。
「でも、慣れれば大丈夫かもしれませんよ?」
「……そうか?」
アイリは、湖を眺めながら呟いた。
(……本当に、静かだ)
目の前の景色は、いつもの仕事とはまるで違う。
ここでは、死も、怪異も、遠いもののように感じられた。
「神崎」
アイリはふと、彼を呼んだ。
「ん?」
「お前は……こういう穏やかな場所でずっと過ごしたいと思うか?」
神崎は少し考え、それから笑った。
「うーん……たまにはいいですけど、ずっとは無理かもしれません」
「……なぜだ?」
「俺自身は、結局のところ騒がしい場所が好きなんですよね」
神崎は猫を撫でながら言う。
「たくさんの人がいて、忙しないくらい誰かの会話が聞こえて、動きがある場所の方が落ち着くというか……。でも、たまにこういう場所に来るのはいいですね」
「……そうか」
アイリは、ふっと目を細めた。
彼は“静けさ”に身を置くことを望んでいない。
常に動き続けることを選び、その中で生きているのだ。
(……それもまた、神崎らしい)
アイリは、静かにそう思った。
6. 夕暮れの漁港
島の路地を歩きながら、二人は漁港へ向かった。
港には、小さな漁船が並び、漁師たちが網の手入れをしていた。
その足元では、数匹の猫たちがのんびりと寝そべっている。
「……のどかですねぇ」
神崎は、漁師たちの働く様子を見ながら呟いた。
「俺たちが普段いる世界とは、まるで違いますね」
「そうだな」
アイリも同意する。
漁師の一人が、神崎たちに気づき、声をかけてきた。
「観光かい? 今日はいい天気だったろう」
「はい、とてもいい時間を過ごせました」
神崎は微笑みながら答えた。
「“猫の島”って聞いて来たんですけど、今は猫も少ないんですね」
「おう、昔はもっといたんだけどなぁ。人も猫も歳をとるし、いつまでも同じってわけにはいかんさ」
漁師は笑いながら、足元の猫の頭を軽く撫でる。
「それでも、こうやって港に座ってりゃ、ちゃんと見張りはしてくれる。魚を分けてやると、恩返しみたいにネズミを捕ってくれるんだよ」
「いい関係ですね」
神崎はその言葉に頷く。
夕暮れの港には、ゆるやかな風が吹き、波の音が心地よく響いていた。
7. 帰りの船
「さて……そろそろ戻りますか」
神崎は、桟橋へ向かいながらそう言った。
「また船か……」
「はい。でも、猫にも会えましたし、島の空気も味わえました。満足です!」
神崎は満面の笑みで答えた。
船が出港すると、湖の上には夕焼けが広がっていた。
「……湖の夕陽も、いいものですね」
神崎がぽつりと言う。
アイリは、静かにそれを見つめた。
「……お前にしては、今日は随分穏やかだったな」
「え?」
「普段は、もう少しふざけているだろう」
神崎は少し考え、それから笑った。
「まぁ……たまにはね」
「……そうか」
アイリは、微かに頷いた。
船の揺れは、穏やかだった。
神崎は、波の音を聞きながら、静かに目を閉じた。
「……また来たいですね。猫がもっと少なくなっても」
「……そうだな」
アイリもまた、そう答えた。
湖の水面が夕陽に染まり、船はゆるやかに進む。
穏やかな時間は、ゆっくりと過ぎていった——。
エンドロール:島に残るもの
沖島の猫たちは、今も少しずつ年をとりながら、のんびりと暮らしている。
漁港の端で、神社の境内で、軒先で。
昔ほどの賑やかさはなくとも、そこにいる一匹一匹が、この島の時間を確かに刻んでいる。
かつて《猫の島》と呼ばれた世界に、少しだけ神崎とアイリが足を踏み入れた。
そして、また静かに島を後にする。
今日触れ合った猫たちの中で、次に来たときにはもう会えない子もいるかもしれない。
それでも、どこか別の場所で、あるいはこの島のどこかで——
猫たちは猫たちの気まぐれな時間を生きていくのだろう。
——次の仕事までの、束の間の休息。
変わっていく世界の中で、冥府庁の旅は、まだ続く。
「……というわけで、アイリさん。今日は約束どおり《猫の島》いえ、沖島へ行きますよ!」
神崎イサナは、やけに嬉しそうに胸を張った。
彼と黒野アイリが訪れているのは、滋賀県・琵琶湖。
先日、県内の別の場所で起きた異変の調査を終えたばかりだった。
ひと仕事終えた後の少しの余暇——それを利用して、神崎がずっと気になっていた場所へ向かうことになったのだ。
「沖島って知ってます? 日本で唯一、人が住んでいる《湖に浮かぶ有人島》なんですよ。そして昔は……猫がいっぱいいて、《猫の島》って呼ばれてたんです」
「……昔は、か」
アイリはわずかに眉を動かす。
「最近は猫が減っちゃったらしいんですけどね。それでも、島の暮らしとか、猫の名残とか、見てみたいなぁって」
神崎は、スマホの画面を見せながら続ける。映っているのは、少し前の、猫の多かった頃の写真だ。
「……それで先日からやたら騒いでいたのか」
アイリは呆れたようにため息をつく。
確かに、ここ数日、神崎はしきりにスマホを見ながら「癒される……」とか「これは行くしかない」とか、何やら浮かれた様子だった。
「まあ、仕事は終わりましたし、少しくらい観光してもいいでしょう?」
「……私はどこでも構わないが」
アイリは淡々と答えた。
(……それにしても)
彼女はちらりと神崎を見やる。
彼は、どこか安心したような顔をしていた。
神崎イサナ。
金髪碧眼の華やかな顔立ちをした男。
普段は軽薄そうに見えるが、その奥には鋭い観察眼を持ち、場の空気を読むのに長けている。
今日は黒のパーカーにカジュアルなデニム姿。
軽やかな服装だが、その仕草にはどこか気品を感じさせる。
(事件続きの冥府庁の仕事では、どうしても《死》と向き合うことが多い)
(……だからこそ、今くらいは)
アイリは、静かに視線を戻した。
「……行くぞ、船が出る」
「はい!」
神崎は満面の笑みで頷くと、勢いよく桟橋へ向かった。
2. 湖の船旅
船に乗り込むと、思ったよりも風が強かった。
琵琶湖は波が穏やかとはいえ、広い湖上では風が吹き抜ける。
アイリは、一瞬だけ神崎を見やる。
(……こいつ、本当に大丈夫なのか?)
彼は過去に「船が苦手」と言っていたことがある。
だが、今のところ、特に酔っている様子はない。
「いやぁ、船は苦手なんですけどね」
神崎はどこか楽しげに言った。
「でも、琵琶湖なら波も穏やかで酔いにくいらしいんですよ! これは素晴らしい」
「……本当に船が苦手なら、もっと別の場所を選べばいいだろう」
「いやいや、《猫の島》のためなら俺は多少の波くらい耐えます」
神崎は腕を組み、どこか誇らしげに言った。
アイリは、かすかに眉を寄せる。
「……風が強い。気分が悪くなったら言え」
「アイリさん、意外と優しいですね?」
「別に。お前に吐かれたら面倒だからだ」
「はいはい、ちゃんと耐えますよ」
そう言いながらも、神崎の表情は明るいままだった。
湖の青が広がる。
島が少しずつ近づいてくると、桟橋に座る猫の姿が見えた。
「……あ、いましたよ!」
神崎が指差した先。
そこには、のんびりと桟橋の端に座る一匹の猫がいた。
「……一匹だけか」
アイリがぽつりと呟く。
「ええ。でも、ちゃんといるじゃないですか」
神崎は、もう心を奪われたような顔をしていた。
3. 猫の楽園と島の暮らし
沖島に足を踏み入れると、すぐに島独特の静けさを感じた。
車がほとんどないこの島では、鳥の声や風の音、波の音がよく通る。
その合間に——。
「にゃあ」
小さな鳴き声が迎えてくれる。
「おおっ……!」
神崎は思わず立ち止まった。
路地の先で、二匹の猫がゆるやかに歩いていた。写真集で見た「猫だらけ」の風景とは違うが、それでもこの島が猫と共にあった時間を思わせる光景だった。
「神崎……お前、そんなに猫が好きだったのか」
アイリが冷静に問いかける。
「ええ、もう大好きですよ!」
神崎は満面の笑みで答える。
島には漁港があり、網の上で昼寝をしている猫もいる——と言っても、その姿はまばらだ。漁師たちが黙々と網を直す横で、一匹の猫がのんびりと毛繕いをしている。そのささやかな存在が、逆に目を引いた。
「……いいですね。ここに住んでいる人たちは、ずっと猫と一緒に暮らしてきたんですね」
「この島は、漁師の町だ」
アイリがぽつりと言う。
「……漁港の魚が猫の食料になり、猫はネズミを捕る。昔から人と共存してきたんだろう」
「なるほど……素敵な関係ですね」
神崎は、しばらく猫を撫でたあと、ふと周囲を見渡した。
「……アイリさん、お腹空きません?」
「まあ、少しくらいなら」
「じゃあ、小さな食堂があるらしいので、行きましょう!」
4. 小さな食堂での昼食
島の細い路地を抜けると、小さな食堂があった。
暖簾をくぐると、優しい煮炊きの香りが漂う。昔ながらの日本家屋そのままのどこか懐かしい感じの内装だ。
店主のおばあさんが、穏やかな笑顔で迎えてくれた。
「おや、旅のお客さんかい?」
「はい。《猫の島》って聞いて、来てみました」
神崎がにこやかに答えると、おばあさんは少し懐かしそうに目を細めた。
「昔はねぇ、本当にそこらじゅう猫だらけでね。今はだいぶ減っちゃったけど……まだ何匹かは、島の子みたいな顔して歩いてるよ」
そう言って笑う足元には、小さな三毛猫が座っていた。
「……こちらのおすすめは?」
アイリが尋ねると、おばあさんはメニューを指差す。
「ここは元々漁業で有名な島だからね。琵琶湖の恵みを味わって欲しいね。鮒寿司や小鮎の天ぷらや佃煮が人気だよ」
「いいですね、それください!」
神崎は迷わず注文し、アイリもそれに倣った。
カラリと揚がった小鮎の天ぷらを頬張る神崎。
「……これは美味しい」
アイリも静かに佃煮を口に運ぶ。
(……湖の恵みを、こうして受けて生きている人たちがいる)
事件の調査では、非日常ばかりを目にする。
だが、こうして普通の暮らしに触れると、どこかほっとするものがあった。
「猫も、だいぶ年をとっちゃってねぇ。島の人も減ったし……」
おばあさんは、窓の外を見やりながらぽつりと言った。
「それでも、こうやって猫目当てでもたまにそとから来てくれる人がいると、何だか嬉しいよ」
静かな島の食堂で、猫と人と、ささやかな食事。
それもまた、彼らにとって必要な時間だった。
——束の間の休息が、穏やかに流れていく。
冥府庁の旅は、まだ続く。
5. 猫と島の午後
小さな食堂を後にし、二人は島の細い路地を歩いていた。
島の家々はどこもこぢんまりとしており、玄関先には鉢植えや干した網が並ぶ。
かつては猫がずらりと並んでいたという軒先も、今はぽつりぽつりと、日向で丸くなる姿があるだけだ。
「……思っていたより静かですね」
神崎はそう言いながら、見かけた猫のところへしゃがみ込んで撫でる。
「ここに住む人たちにとって、猫は特別な存在なんだろうな」
アイリは、ゆったりとした町並みを眺めながら静かに言った。
「そうですね。数は減っても、ちゃんと“ここにいる”って感じがします」
神崎は猫と目線を合わせるように屈み、穏やかに微笑んだ。
(……あいつ、ずっと楽しそうだな)
アイリは神崎を観察しながら、ふとそんなことを思った。
彼の金髪は湖からの風に揺れ、碧い瞳は猫を映している。
普段は軽薄そうな表情を見せることもあるが、今はただ純粋にこの時間を楽しんでいるように見えた。
(こういう時間も、悪くないな)
そんなことを考えながら細い路地を歩いていると、小高い丘の上に差し掛かった。
階段を登っていくと、そこは小さな神社の境内だった。
鳥居の下で、二、三匹の猫が丸くなっている。
「……ここにもいますね」
神崎はふわりと笑った。
「猫にとっても、神社って落ち着く場所なんでしょうか」
「……かもしれないな」
アイリは鳥居を見上げた。
小さな祠があり、誰かがお供えをした形跡がある。辺りは静かな空気に満ちていた。
「ここにいる猫は、みんな穏やかですね」
神崎は境内のベンチに腰掛け、ゆっくりと息を吐いた。
「こういう場所で暮らすっていうのも、いいなぁ」
「お前がここに住んだら、船の移動で毎回酔いそうだが」
「それは……確かに」
神崎は苦笑した。
「でも、慣れれば大丈夫かもしれませんよ?」
「……そうか?」
アイリは、湖を眺めながら呟いた。
(……本当に、静かだ)
目の前の景色は、いつもの仕事とはまるで違う。
ここでは、死も、怪異も、遠いもののように感じられた。
「神崎」
アイリはふと、彼を呼んだ。
「ん?」
「お前は……こういう穏やかな場所でずっと過ごしたいと思うか?」
神崎は少し考え、それから笑った。
「うーん……たまにはいいですけど、ずっとは無理かもしれません」
「……なぜだ?」
「俺自身は、結局のところ騒がしい場所が好きなんですよね」
神崎は猫を撫でながら言う。
「たくさんの人がいて、忙しないくらい誰かの会話が聞こえて、動きがある場所の方が落ち着くというか……。でも、たまにこういう場所に来るのはいいですね」
「……そうか」
アイリは、ふっと目を細めた。
彼は“静けさ”に身を置くことを望んでいない。
常に動き続けることを選び、その中で生きているのだ。
(……それもまた、神崎らしい)
アイリは、静かにそう思った。
6. 夕暮れの漁港
島の路地を歩きながら、二人は漁港へ向かった。
港には、小さな漁船が並び、漁師たちが網の手入れをしていた。
その足元では、数匹の猫たちがのんびりと寝そべっている。
「……のどかですねぇ」
神崎は、漁師たちの働く様子を見ながら呟いた。
「俺たちが普段いる世界とは、まるで違いますね」
「そうだな」
アイリも同意する。
漁師の一人が、神崎たちに気づき、声をかけてきた。
「観光かい? 今日はいい天気だったろう」
「はい、とてもいい時間を過ごせました」
神崎は微笑みながら答えた。
「“猫の島”って聞いて来たんですけど、今は猫も少ないんですね」
「おう、昔はもっといたんだけどなぁ。人も猫も歳をとるし、いつまでも同じってわけにはいかんさ」
漁師は笑いながら、足元の猫の頭を軽く撫でる。
「それでも、こうやって港に座ってりゃ、ちゃんと見張りはしてくれる。魚を分けてやると、恩返しみたいにネズミを捕ってくれるんだよ」
「いい関係ですね」
神崎はその言葉に頷く。
夕暮れの港には、ゆるやかな風が吹き、波の音が心地よく響いていた。
7. 帰りの船
「さて……そろそろ戻りますか」
神崎は、桟橋へ向かいながらそう言った。
「また船か……」
「はい。でも、猫にも会えましたし、島の空気も味わえました。満足です!」
神崎は満面の笑みで答えた。
船が出港すると、湖の上には夕焼けが広がっていた。
「……湖の夕陽も、いいものですね」
神崎がぽつりと言う。
アイリは、静かにそれを見つめた。
「……お前にしては、今日は随分穏やかだったな」
「え?」
「普段は、もう少しふざけているだろう」
神崎は少し考え、それから笑った。
「まぁ……たまにはね」
「……そうか」
アイリは、微かに頷いた。
船の揺れは、穏やかだった。
神崎は、波の音を聞きながら、静かに目を閉じた。
「……また来たいですね。猫がもっと少なくなっても」
「……そうだな」
アイリもまた、そう答えた。
湖の水面が夕陽に染まり、船はゆるやかに進む。
穏やかな時間は、ゆっくりと過ぎていった——。
エンドロール:島に残るもの
沖島の猫たちは、今も少しずつ年をとりながら、のんびりと暮らしている。
漁港の端で、神社の境内で、軒先で。
昔ほどの賑やかさはなくとも、そこにいる一匹一匹が、この島の時間を確かに刻んでいる。
かつて《猫の島》と呼ばれた世界に、少しだけ神崎とアイリが足を踏み入れた。
そして、また静かに島を後にする。
今日触れ合った猫たちの中で、次に来たときにはもう会えない子もいるかもしれない。
それでも、どこか別の場所で、あるいはこの島のどこかで——
猫たちは猫たちの気まぐれな時間を生きていくのだろう。
——次の仕事までの、束の間の休息。
変わっていく世界の中で、冥府庁の旅は、まだ続く。
11
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

いい子ちゃんなんて嫌いだわ
F.conoe
ファンタジー
異世界召喚され、聖女として厚遇されたが
聖女じゃなかったと手のひら返しをされた。
おまけだと思われていたあの子が聖女だという。いい子で優しい聖女さま。
どうしてあなたは、もっと早く名乗らなかったの。
それが優しさだと思ったの?


【1話完結】あなたの恋人は毎夜わたしのベッドで寝てますよ。
ariya
ファンタジー
ソフィア・ラテットは、婚約者アレックスから疎まれていた。
彼の傍らには、いつも愛らしい恋人リリアンヌ。
婚約者の立場として注意しても、アレックスは聞く耳を持たない。
そして迎えた学園卒業パーティー。
ソフィアは公衆の面前で婚約破棄を言い渡される。
ガッツポーズを決めるリリアンヌ。
そのままアレックスに飛び込むかと思いきや――
彼女が抱きついた先は、ソフィアだった。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。
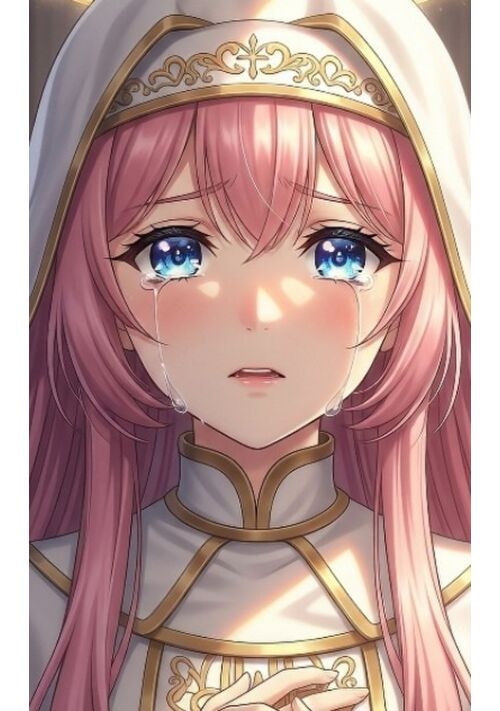
聖女は聞いてしまった
夕景あき
ファンタジー
「道具に心は不要だ」
父である国王に、そう言われて育った聖女。
彼女の周囲には、彼女を心を持つ人間として扱う人は、ほとんどいなくなっていた。
聖女自身も、自分の心の動きを無視して、聖女という治癒道具になりきり何も考えず、言われた事をただやり、ただ生きているだけの日々を過ごしていた。
そんな日々が10年過ぎた後、勇者と賢者と魔法使いと共に聖女は魔王討伐の旅に出ることになる。
旅の中で心をとり戻し、勇者に恋をする聖女。
しかし、勇者の本音を聞いてしまった聖女は絶望するのだった·····。
ネガティブ思考系聖女の恋愛ストーリー!
※ハッピーエンドなので、安心してお読みください!



三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















