2 / 13
2 思いやり、援け合う
しおりを挟む
翌日の、日曜日。
朝、回って来た回覧板を隣家に回しに行ったついでに、祐子は宏に昨日有智から聞いた菜々美の緑茶の事を話した。
すると宏は、お恥ずかしい、と口ごもって。
「ちいさい頃に私がやっていたのを見よう見真似で覚えて淹れてくれるようになったんですが、蒸らす時間とか判らずにやっていたからいつも渋くて」
苦笑いしながらそう言った。
「まだ幼くて、折角自分でやりたいと言ってくれたのにやる気を削ぐのも可哀想だと思ってつい好きなようにさせていたんですが」
その気持ちは祐子にもよく解る。
「あのままじゃやはりまずいですよね、私がきちんと教えないと」
宏が言いかけたのを、いえあの、と引き取って。
「もし良かったら、私がななちゃんに教えましょうか?」
「え、いや、でも」
「今日午後からお料理を教える約束をしていますから、ついでにでも」
「……でしたら、甘えさせて頂いていいですか」
いつも申し訳ない、と頭を下げる宏に、いえいえ、と首を振って
「実は私も興味があって。うちのユーチがあそこまで褒めるなんてどんな味なんだろう、って」
くすくす笑いながら言うと、頭を上げた宏も
「有智君にそんなに褒められたんじゃ、ななも喜ぶだろうな」
ちいさく笑った。
「いつも有智君には何だかんだと怒られてばっかりだって言ってますから」
「あらやだ!もうあの子ったら!」
小学校の高学年になったあたりから、有智は学校であった事を殆ど話してくれなくなった。だから菜々美にそんな態度を取っているという事も初耳で。
ひどく慌てながら、ごめんなさい、と謝る祐子に
「いやいいんですよ。ななも色々おっちょこちょいな所とかわがままな所とかあるし、良くない所は良くないとちゃんと怒ってくれる友達がいるのは有難いと思っていますから」
宏は柔らかい笑みを浮かべて、そう言った。
「ちいさい頃から仲がいい有智君の言う事なら、間違いないでしょうし」
「そんな風に仰って頂けると有難いです、けど……」
恐縮しつつ
「あんまりななちゃんいじめたら承知しないって、ユーチにびしっと言っておきますね」
と言って、祐子は隣家を辞した。
『有智君』
宏が有智をそう呼ぶようになったのは、何時頃からだっただろうか。
祐子が菜々美を『ななちゃん』と愛称で呼ぶのと同様、以前は『ユーチ君』と言っていた。だが今は一貫して名前で呼んでいる。本人に対しても、祐子との会話の中でも。
もしかしたら、と。
何となく思い当たることが、祐子にはあった。
亡き夫が息子を愛称で呼んでいた事に対しての配慮だろうか、と。
息子の中にある、幼い頃からずっと『ユーチ』と呼んでくれた父親の思い出を、慮っての。
宏本人からそのことについて何か聞いた訳ではないが、多分そうなんだろうと祐子は推察していた。
あの、思いやり深い穏やかな隣人ならば、さもあろうと。
父亡き後、それより前の天真爛漫な面が影を潜め口数もめっきり減り落ち着いた性格になってしまった息子も、『隣の宏おじさん』の気さくで温厚な人柄を慕っていて、祐子には話さない学校での出来事を時折宏に話す事もあるらしい。
『ゆこは絶対、ユーチって呼ばないんだな』
随分前に、夫に言われた。
有智が『とーた』『かぁか』と、片言で父母を呼ぶようになった頃。
息子に『有智』と命名したのは、夫の有希だった。
『有』は自分の名前から。『智』は当時テレビで放映していた、里見八犬伝に題材を取った人形劇に登場する八犬士のひとり、美貌の智将犬坂毛野が持つ玉の字から取ったものだった。
夫なりに父親の願いを込めてつけた良い名だと、祐子も特に異存はなかったのだが。
何故か命名した当の本人が、家では専ら『ユーチ』と音読みで息子を呼んでいた。
そんな彼に、ある日そう指摘されて。
『だって!ふたりでそう呼んだら、この子絶対自分の名前はユーチだって覚えちゃうでしょ?』
すぐ横でちいさな寝息を立てている有智のあどけない寝顔を見ながら
『ユーキが『ありとも』って呼ばない限り、私は絶対ユーチって呼ばないから!』
口を尖らせて、祐子は返した。
『それにユーキとユーチじゃ音が一緒でどっち呼んでるんだか混乱しそうだし?』
『これで俺がゆこの事『ユーコ』って呼んだらもう大混乱だな』
『ユーキにユーコにユーチ?ややこしい一家よね』
顔を見合わせて、ぷぷっと噴き出しかけて。
『しぃっ!有智が起きちゃう!』
口に人差し指を当てて祐子が制止するのに、有希が掌で口を塞いで。
目と目を見交わして、黙ったまま互いに顔だけを綻ばせた。
夫婦ふたりでも。
親子三人でも。
いつでも笑いが絶えなかった、幸せな日々。
有希が他界した後。
何時の間にか何となく、息子を『ユーチ』と呼ぶようになった。
有希が呼んでいたように。
『ユーキとユーチじゃ音が一緒でどっち呼んでるんだか混乱しそうだし?』
もう、その心配はないから。
『ユーキ』と。
夫の名を呼ぶことはもう二度とない、から――。
午後になって、約束通り菜々美が訪ねて来た。
いつものようにふたりで台所に並んで楽しくお喋りしながら肉巻きを作り、それぞれの家の夕食の分を取り分けて、残った僅かな分を試食した後
「そうそう、昨日ユーチがななちゃんのお茶が美味しいって言ってたんだけど、おばさんにも飲ませてくれないかな?」
さり気なくねだると、菜々美はえ、と困惑の表情を見せた。
「昨日……って言うとそれって学校に持って行ってるの、ですよね。あれ冷たいのだから……今ウチの方にも作り置きなくて」
「ううん、あったかいのでいいから、ここで淹れてくれる?」
そう言って、祐子は茶葉と急須を出した。
「お茶っ葉は普通のお茶用でいいのね?」
「普通のお茶?」
きょとんとする菜々美に、玉露とか番茶とか、と言うと
「ぎょくろ?ばんちゃ?」
ますます不思議そうな顔をして首を傾げた。どうやらそのあたりは知らないようだ。
「お茶の種類。じゃあそれは後で教えるから、お茶、ななちゃんのやり方で淹れてみて」
「あ、じゃあお湯、沸かさせて下さい」
沸かした湯を程々に冷まして茶葉を入れた急須に注ぎ、普通よりもやや時間を置いた後菜々美が茶碗に注いだ茶は、濃い暗緑色で。
一見して渋そうだと思いつつ、頂きます、と言って祐子は茶碗を口許に運んだ。
何とも言えない渋味が、口の中に拡がる。
けれどそれは嫌な感じではない。むしろさっぱりとした味わいで。
「美味しい!」
思わず祐子は、そう口にしていた。
「ユーチが凄く美味しかったって褒めてたの、解る、うん!」
正に息子が言った通りの味わいだった。
「おばさん、ユーチが褒めてたって、ホントに?」
「ホントホント!なぁに?ユーチ、ななちゃんには何も言わなかったの?」
「美味い、って言ってはくれたんだけど……」
菜々美がどこか懐疑的な口調で
「ユーチに褒められる事なんて滅多にないから、本気にしていいのかなぁって」
首を傾げるのに
「ううんホントに美味しいし!ユーチも間違いなく本気だから!昨日学校から帰って来て大絶賛してたのよ?」
声に力を込めて祐子がそう言うと
「そっかぁ」
菜々美はやっと嬉しそうに笑った。
「あ、そうそうおばさん、さっきの『ぎょくろ』とか『ばんちゃ』って、何ですか?」
「ああそれはね」
菜々美の方から水を向けて来たのを幸いと、祐子は菜々美に茶の種類とそれぞれに応じた淹れ方を実演しながら教えた。
良い茶葉程、ぬるめのお湯で時間をかけてじっくりと淹れること、来客に出す場合は茶を注ぐ前に茶碗を湯で温めること、等。
祐子に教えられた通りに自身でもそれぞれの茶を淹れて、飲んでみて美味しさを納得した菜々美が
「有難うごさいます、おばさん」
丁寧に頭を下げた後
「私ずっと自己流でやってたから。今度から今教えてもらったやり方で淹れます!」
きっぱり言うのに、祐子は慌てた。
ううん!と手を振って。
「ななちゃんがさっき淹れてくれたお茶、本当に美味しいから、やり方変えちゃ駄目!」
「え、でもあれって完全に淹れ方間違ってますよね?色濃過ぎるし渋過ぎるし」
「そんな事ないよ?確かに渋いけれど渋味が凄くいい感じに口に残って美味しかったもの。あれ、ななちゃん自分で色々工夫して淹れてるんでしょ?お湯の温度とか時間とか」
菜々美が最初に茶を淹れた時、一旦沸騰させた湯をある程度冷ましてから使っていた事や、急須に湯を注いでから時計を気にしていた事に、祐子は気づいていた。
「おばさん、ななちゃんのお茶凄く美味しくて気に入っちゃったから。今おばさんが教えた事はお客さんが来た時とか外でお茶を淹れて欲しいって頼まれた時のやり方だから、覚えておいて自分のやり方と上手く使い分けてね?」
常識は押さえておいて欲しい。けれど、自分なりに編み出したやり方のオリジナリティーもまた大切にして欲しい、と。
祐子が話して聞かせると、それでも菜々美は気になるようで
「でも、いいのかなホントにあれで……」
ぼそぼそと呟いた。
「いいのあれはあれで!絶対変えないで!でないとおばさんがユーチに怒られちゃうから!ななちゃんに余計な事教えたからお茶が普通の味になっちゃったって!」
「やだおばさんってば!普通の味になったら怒られるって何それ!」
「あら?そうね、正しい淹れ方して怒られるって変な話よね?」
声を立てて菜々美と笑い合いながら。
祐子は、心の底から感心していた。
幼い頃に父親の『茶の淹れ方』を見よう見真似で覚えたのならば、最初のそれはおそらく『急須に茶葉を入れて湯を注いで少したったら茶碗に注ぐ』というだけの事だったはずだ。
それをこの探求心旺盛な子は、誰かに何かを教えられた訳でもないのに自分なりに色々と考えて試行錯誤した末に、ちょうど良い渋味になるように湯の温度や茶葉を蒸らす時間を調整する事を覚えたのだろう。
その途中経過を多分見ていたであろう宏が、最適と言われる湯の温度や時間を敢えて教えなかった気持ちが、解る気がした。
初めて会った頃は、ひどく内気で。
クラスでいじめられてよく泣いていた、と
『ななちゃんこの頃泣かなくなったんだよ。いじわるな事言うやつにも自分で言い返せるようになったんだ』
大分後になって息子が嬉しそうに報告してくれたことから、判った。
うつむいてもじもじしていた女の子は、何時の間にか顔を上げて晴れやかに笑う娘になった。
頑張り屋さんで、明るくて、素直で、優しくて。
菜々美を見ていると、父の宏が一人娘をどれだけ大切に愛し育んできたかが、よく解る。
妻に死別して、まだ物心つかない程に幼かった娘を男手ひとつでここまで育て上げるのは、どれ程大変だっただろう、と。
これまで、漠然と捉えていただけの。
隣家の主の十数年来の苦労に、祐子は初めて深く思いを致した。
朝、回って来た回覧板を隣家に回しに行ったついでに、祐子は宏に昨日有智から聞いた菜々美の緑茶の事を話した。
すると宏は、お恥ずかしい、と口ごもって。
「ちいさい頃に私がやっていたのを見よう見真似で覚えて淹れてくれるようになったんですが、蒸らす時間とか判らずにやっていたからいつも渋くて」
苦笑いしながらそう言った。
「まだ幼くて、折角自分でやりたいと言ってくれたのにやる気を削ぐのも可哀想だと思ってつい好きなようにさせていたんですが」
その気持ちは祐子にもよく解る。
「あのままじゃやはりまずいですよね、私がきちんと教えないと」
宏が言いかけたのを、いえあの、と引き取って。
「もし良かったら、私がななちゃんに教えましょうか?」
「え、いや、でも」
「今日午後からお料理を教える約束をしていますから、ついでにでも」
「……でしたら、甘えさせて頂いていいですか」
いつも申し訳ない、と頭を下げる宏に、いえいえ、と首を振って
「実は私も興味があって。うちのユーチがあそこまで褒めるなんてどんな味なんだろう、って」
くすくす笑いながら言うと、頭を上げた宏も
「有智君にそんなに褒められたんじゃ、ななも喜ぶだろうな」
ちいさく笑った。
「いつも有智君には何だかんだと怒られてばっかりだって言ってますから」
「あらやだ!もうあの子ったら!」
小学校の高学年になったあたりから、有智は学校であった事を殆ど話してくれなくなった。だから菜々美にそんな態度を取っているという事も初耳で。
ひどく慌てながら、ごめんなさい、と謝る祐子に
「いやいいんですよ。ななも色々おっちょこちょいな所とかわがままな所とかあるし、良くない所は良くないとちゃんと怒ってくれる友達がいるのは有難いと思っていますから」
宏は柔らかい笑みを浮かべて、そう言った。
「ちいさい頃から仲がいい有智君の言う事なら、間違いないでしょうし」
「そんな風に仰って頂けると有難いです、けど……」
恐縮しつつ
「あんまりななちゃんいじめたら承知しないって、ユーチにびしっと言っておきますね」
と言って、祐子は隣家を辞した。
『有智君』
宏が有智をそう呼ぶようになったのは、何時頃からだっただろうか。
祐子が菜々美を『ななちゃん』と愛称で呼ぶのと同様、以前は『ユーチ君』と言っていた。だが今は一貫して名前で呼んでいる。本人に対しても、祐子との会話の中でも。
もしかしたら、と。
何となく思い当たることが、祐子にはあった。
亡き夫が息子を愛称で呼んでいた事に対しての配慮だろうか、と。
息子の中にある、幼い頃からずっと『ユーチ』と呼んでくれた父親の思い出を、慮っての。
宏本人からそのことについて何か聞いた訳ではないが、多分そうなんだろうと祐子は推察していた。
あの、思いやり深い穏やかな隣人ならば、さもあろうと。
父亡き後、それより前の天真爛漫な面が影を潜め口数もめっきり減り落ち着いた性格になってしまった息子も、『隣の宏おじさん』の気さくで温厚な人柄を慕っていて、祐子には話さない学校での出来事を時折宏に話す事もあるらしい。
『ゆこは絶対、ユーチって呼ばないんだな』
随分前に、夫に言われた。
有智が『とーた』『かぁか』と、片言で父母を呼ぶようになった頃。
息子に『有智』と命名したのは、夫の有希だった。
『有』は自分の名前から。『智』は当時テレビで放映していた、里見八犬伝に題材を取った人形劇に登場する八犬士のひとり、美貌の智将犬坂毛野が持つ玉の字から取ったものだった。
夫なりに父親の願いを込めてつけた良い名だと、祐子も特に異存はなかったのだが。
何故か命名した当の本人が、家では専ら『ユーチ』と音読みで息子を呼んでいた。
そんな彼に、ある日そう指摘されて。
『だって!ふたりでそう呼んだら、この子絶対自分の名前はユーチだって覚えちゃうでしょ?』
すぐ横でちいさな寝息を立てている有智のあどけない寝顔を見ながら
『ユーキが『ありとも』って呼ばない限り、私は絶対ユーチって呼ばないから!』
口を尖らせて、祐子は返した。
『それにユーキとユーチじゃ音が一緒でどっち呼んでるんだか混乱しそうだし?』
『これで俺がゆこの事『ユーコ』って呼んだらもう大混乱だな』
『ユーキにユーコにユーチ?ややこしい一家よね』
顔を見合わせて、ぷぷっと噴き出しかけて。
『しぃっ!有智が起きちゃう!』
口に人差し指を当てて祐子が制止するのに、有希が掌で口を塞いで。
目と目を見交わして、黙ったまま互いに顔だけを綻ばせた。
夫婦ふたりでも。
親子三人でも。
いつでも笑いが絶えなかった、幸せな日々。
有希が他界した後。
何時の間にか何となく、息子を『ユーチ』と呼ぶようになった。
有希が呼んでいたように。
『ユーキとユーチじゃ音が一緒でどっち呼んでるんだか混乱しそうだし?』
もう、その心配はないから。
『ユーキ』と。
夫の名を呼ぶことはもう二度とない、から――。
午後になって、約束通り菜々美が訪ねて来た。
いつものようにふたりで台所に並んで楽しくお喋りしながら肉巻きを作り、それぞれの家の夕食の分を取り分けて、残った僅かな分を試食した後
「そうそう、昨日ユーチがななちゃんのお茶が美味しいって言ってたんだけど、おばさんにも飲ませてくれないかな?」
さり気なくねだると、菜々美はえ、と困惑の表情を見せた。
「昨日……って言うとそれって学校に持って行ってるの、ですよね。あれ冷たいのだから……今ウチの方にも作り置きなくて」
「ううん、あったかいのでいいから、ここで淹れてくれる?」
そう言って、祐子は茶葉と急須を出した。
「お茶っ葉は普通のお茶用でいいのね?」
「普通のお茶?」
きょとんとする菜々美に、玉露とか番茶とか、と言うと
「ぎょくろ?ばんちゃ?」
ますます不思議そうな顔をして首を傾げた。どうやらそのあたりは知らないようだ。
「お茶の種類。じゃあそれは後で教えるから、お茶、ななちゃんのやり方で淹れてみて」
「あ、じゃあお湯、沸かさせて下さい」
沸かした湯を程々に冷まして茶葉を入れた急須に注ぎ、普通よりもやや時間を置いた後菜々美が茶碗に注いだ茶は、濃い暗緑色で。
一見して渋そうだと思いつつ、頂きます、と言って祐子は茶碗を口許に運んだ。
何とも言えない渋味が、口の中に拡がる。
けれどそれは嫌な感じではない。むしろさっぱりとした味わいで。
「美味しい!」
思わず祐子は、そう口にしていた。
「ユーチが凄く美味しかったって褒めてたの、解る、うん!」
正に息子が言った通りの味わいだった。
「おばさん、ユーチが褒めてたって、ホントに?」
「ホントホント!なぁに?ユーチ、ななちゃんには何も言わなかったの?」
「美味い、って言ってはくれたんだけど……」
菜々美がどこか懐疑的な口調で
「ユーチに褒められる事なんて滅多にないから、本気にしていいのかなぁって」
首を傾げるのに
「ううんホントに美味しいし!ユーチも間違いなく本気だから!昨日学校から帰って来て大絶賛してたのよ?」
声に力を込めて祐子がそう言うと
「そっかぁ」
菜々美はやっと嬉しそうに笑った。
「あ、そうそうおばさん、さっきの『ぎょくろ』とか『ばんちゃ』って、何ですか?」
「ああそれはね」
菜々美の方から水を向けて来たのを幸いと、祐子は菜々美に茶の種類とそれぞれに応じた淹れ方を実演しながら教えた。
良い茶葉程、ぬるめのお湯で時間をかけてじっくりと淹れること、来客に出す場合は茶を注ぐ前に茶碗を湯で温めること、等。
祐子に教えられた通りに自身でもそれぞれの茶を淹れて、飲んでみて美味しさを納得した菜々美が
「有難うごさいます、おばさん」
丁寧に頭を下げた後
「私ずっと自己流でやってたから。今度から今教えてもらったやり方で淹れます!」
きっぱり言うのに、祐子は慌てた。
ううん!と手を振って。
「ななちゃんがさっき淹れてくれたお茶、本当に美味しいから、やり方変えちゃ駄目!」
「え、でもあれって完全に淹れ方間違ってますよね?色濃過ぎるし渋過ぎるし」
「そんな事ないよ?確かに渋いけれど渋味が凄くいい感じに口に残って美味しかったもの。あれ、ななちゃん自分で色々工夫して淹れてるんでしょ?お湯の温度とか時間とか」
菜々美が最初に茶を淹れた時、一旦沸騰させた湯をある程度冷ましてから使っていた事や、急須に湯を注いでから時計を気にしていた事に、祐子は気づいていた。
「おばさん、ななちゃんのお茶凄く美味しくて気に入っちゃったから。今おばさんが教えた事はお客さんが来た時とか外でお茶を淹れて欲しいって頼まれた時のやり方だから、覚えておいて自分のやり方と上手く使い分けてね?」
常識は押さえておいて欲しい。けれど、自分なりに編み出したやり方のオリジナリティーもまた大切にして欲しい、と。
祐子が話して聞かせると、それでも菜々美は気になるようで
「でも、いいのかなホントにあれで……」
ぼそぼそと呟いた。
「いいのあれはあれで!絶対変えないで!でないとおばさんがユーチに怒られちゃうから!ななちゃんに余計な事教えたからお茶が普通の味になっちゃったって!」
「やだおばさんってば!普通の味になったら怒られるって何それ!」
「あら?そうね、正しい淹れ方して怒られるって変な話よね?」
声を立てて菜々美と笑い合いながら。
祐子は、心の底から感心していた。
幼い頃に父親の『茶の淹れ方』を見よう見真似で覚えたのならば、最初のそれはおそらく『急須に茶葉を入れて湯を注いで少したったら茶碗に注ぐ』というだけの事だったはずだ。
それをこの探求心旺盛な子は、誰かに何かを教えられた訳でもないのに自分なりに色々と考えて試行錯誤した末に、ちょうど良い渋味になるように湯の温度や茶葉を蒸らす時間を調整する事を覚えたのだろう。
その途中経過を多分見ていたであろう宏が、最適と言われる湯の温度や時間を敢えて教えなかった気持ちが、解る気がした。
初めて会った頃は、ひどく内気で。
クラスでいじめられてよく泣いていた、と
『ななちゃんこの頃泣かなくなったんだよ。いじわるな事言うやつにも自分で言い返せるようになったんだ』
大分後になって息子が嬉しそうに報告してくれたことから、判った。
うつむいてもじもじしていた女の子は、何時の間にか顔を上げて晴れやかに笑う娘になった。
頑張り屋さんで、明るくて、素直で、優しくて。
菜々美を見ていると、父の宏が一人娘をどれだけ大切に愛し育んできたかが、よく解る。
妻に死別して、まだ物心つかない程に幼かった娘を男手ひとつでここまで育て上げるのは、どれ程大変だっただろう、と。
これまで、漠然と捉えていただけの。
隣家の主の十数年来の苦労に、祐子は初めて深く思いを致した。
0
あなたにおすすめの小説


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


『愛が揺れるお嬢さん妻』- かわいいひと - 〇
設楽理沙
ライト文芸
♡~好きになった人はクールビューティーなお医者様~♡
やさしくなくて、そっけなくて。なのに時々やさしくて♡
――――― まただ、胸が締め付けられるような・・
そうか、この気持ちは恋しいってことなんだ ―――――
ヤブ医者で不愛想なアイッは年下のクールビューティー。
絶対仲良くなんてなれないって思っていたのに、
遠く遠く、限りなく遠い人だったのに、
わたしにだけ意地悪で・・なのに、
気がつけば、一番近くにいたYO。
幸せあふれる瞬間・・いつもそばで感じていたい
◇ ◇ ◇ ◇
💛画像はAI生成画像 自作

罪悪と愛情
暦海
恋愛
地元の家電メーカー・天の香具山に勤務する20代後半の男性・古城真織は幼い頃に両親を亡くし、それ以降は父方の祖父母に預けられ日々を過ごしてきた。
だけど、祖父母は両親の残した遺産を目当てに真織を引き取ったに過ぎず、真織のことは最低限の衣食を与えるだけでそれ以外は基本的に放置。祖父母が自身を疎ましく思っていることを知っていた真織は、高校卒業と共に就職し祖父母の元を離れる。業務上などの必要なやり取り以外では基本的に人と関わらないので友人のような存在もいない真織だったが、どうしてかそんな彼に積極的に接する後輩が一人。その後輩とは、頗る優秀かつ息を呑むほどの美少女である降宮蒔乃で――


友達婚~5年もあいつに片想い~
日下奈緒
恋愛
求人サイトの作成の仕事をしている梨衣は
同僚の大樹に5年も片想いしている
5年前にした
「お互い30歳になっても独身だったら結婚するか」
梨衣は今30歳
その約束を大樹は覚えているのか
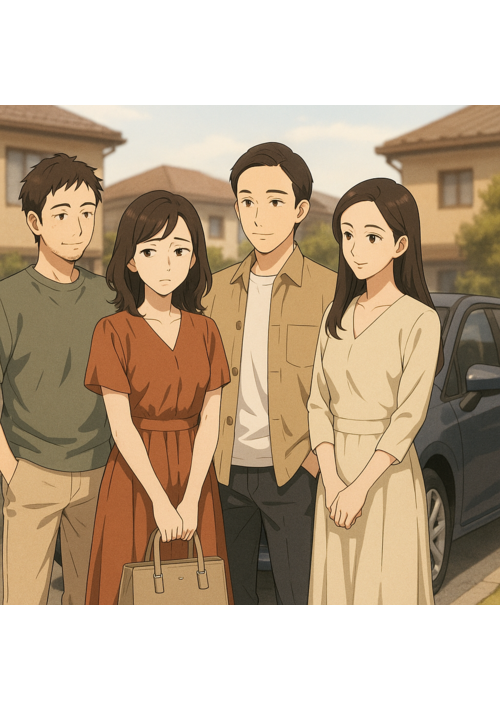
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















