あなたにおすすめの小説


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


罪悪と愛情
暦海
恋愛
地元の家電メーカー・天の香具山に勤務する20代後半の男性・古城真織は幼い頃に両親を亡くし、それ以降は父方の祖父母に預けられ日々を過ごしてきた。
だけど、祖父母は両親の残した遺産を目当てに真織を引き取ったに過ぎず、真織のことは最低限の衣食を与えるだけでそれ以外は基本的に放置。祖父母が自身を疎ましく思っていることを知っていた真織は、高校卒業と共に就職し祖父母の元を離れる。業務上などの必要なやり取り以外では基本的に人と関わらないので友人のような存在もいない真織だったが、どうしてかそんな彼に積極的に接する後輩が一人。その後輩とは、頗る優秀かつ息を呑むほどの美少女である降宮蒔乃で――

『愛が揺れるお嬢さん妻』- かわいいひと - 〇
設楽理沙
ライト文芸
♡~好きになった人はクールビューティーなお医者様~♡
やさしくなくて、そっけなくて。なのに時々やさしくて♡
――――― まただ、胸が締め付けられるような・・
そうか、この気持ちは恋しいってことなんだ ―――――
ヤブ医者で不愛想なアイッは年下のクールビューティー。
絶対仲良くなんてなれないって思っていたのに、
遠く遠く、限りなく遠い人だったのに、
わたしにだけ意地悪で・・なのに、
気がつけば、一番近くにいたYO。
幸せあふれる瞬間・・いつもそばで感じていたい
◇ ◇ ◇ ◇
💛画像はAI生成画像 自作

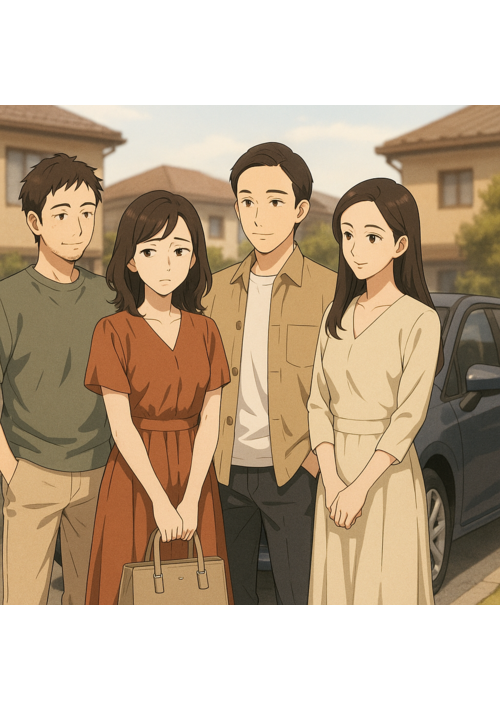

Husband's secret (夫の秘密)
設楽理沙
ライト文芸
果たして・・
秘密などあったのだろうか!
むちゃくちゃ、1回投稿文が短いです。(^^ゞ💦アセアセ
10秒~30秒?
何気ない隠し事が、とんでもないことに繋がっていくこともあるんですね。
❦ イラストはAI生成画像 自作
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















