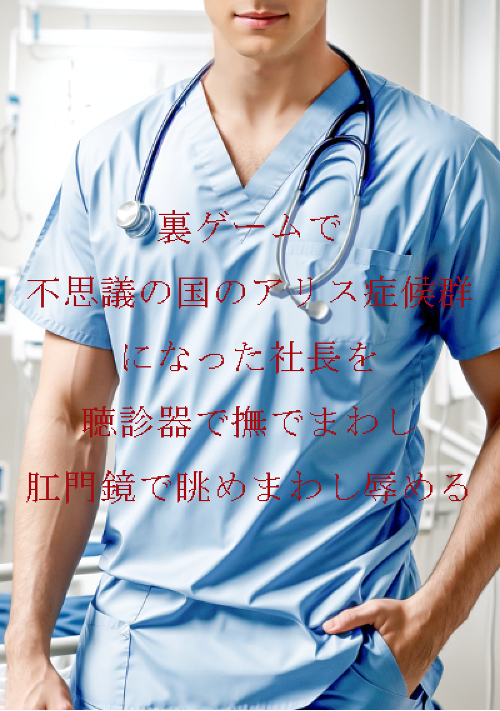7 / 24
怪人ヤッラーの禁断の恋
⑦
しおりを挟む二度目はアウトだろう。
ということで、気が進まなかったけど、本来のピンクレンジャーの彼女とアカルイオサムに打ち明けて、相談しようとした。
その矢先に、アカルイオサムのほうからスマホに電話がかかってきた。
用件は別だろうとはいえ、ついでにレンジャーのことを相談しようと思い、電話に出たところ「しばらく、脚本家の家に泊まり込んでカンヅメするから」とだけ言って切られた。
まあ、そもそも、声が出ない俺に電話をしてきた時点で、おかしかったわけだが。
アカルイオサムにして、鬱っぽい本家のように暗く沈んだ調子で声も掠れていたから、冗談ではなく追い詰められているのだろう。
これまでも脚本が中々、仕上がらずに、その手伝いをさせられて脚本家の家に泊まり込んだことはあった。
ただ、今回の場合、今日も劇団にきていないライオンの絶不調のせいで、大幅な脚本の手直しをしているものと思われる。
いつもの泊まり込みでも、連絡がつきにくいというのに、公演が近く、いつも以上に追い詰められているアカルイオサムなら、この電話を最後にスマホの電源を落とすかもしれない。
たとえ、連絡がついたとしても、心身を疲弊しきっているアカルイオサムに、さらに負担をかけるようなことはしたくなかった。
これはもう、彼女に直接、連絡を取るしかないかと腹をくくって「すみません。ご相談があるのですが」とラインを送ったら、すこしして既読がついて直後に「どちらさまでしょうか」と返ってきた。
へ?と当惑する間もなく「俺は彼女と一緒に住んでいる者です」と新たなメッセージが表示された。
会社員の彼氏かと、こちらも察しがついて「あの、なにかあったんですか?」とやや緊張しつつ打てば「すみません、あなたは」と問い返される。
「こちらこそ、すみません。俺はピンクレンジャーの代役をやっている者で」と我ながら怪しさ満点な自己紹介をしたものの、彼女からバイトや代役について聞いていたのだろう。
「そうでしたか」とすんなり返ってきて「ご存知かと思いますが、彼女は今、大きな舞台に向けて稽古中で」にはじまり、長い文章がつづいた。
「はじめての大きな舞台、しかも大役なんでストレスとプレッシャーがすごいらしいんです。
それで、彼女、ノイローゼ気味でして。
仕事仲間と僕以外とは口を利きたくないと、外に出るときはスマホを持ち歩かないし、家にいるときは、僕に取り次いでほしいというんですよ」
アカルイオサムだけでなく、彼女も精神的に不安定で、まともにやり取りできる状態にないらしい。
いくら、話を取り次いでくれるといっても、内容が内容なだけに、彼氏に伝えることはできない。
諦めるしかないと、すぐに判断して、相手に不審に思われないためにも「そんな大変なときに申し訳ありません」と返事もすぐにした。
「代役をしているピンクレンジャーのことで相談があったのですが、急ぐことではないので。
俺から連絡があったことだけお伝えしていただけますか?」
既読がつきつつ、返信はこないで、微妙な間が空いてから「そう言ってもらえると助かります。彼女にはきちんと伝えておくので」と相手は応じてくれた。
「ではお大事に」と打って「ありがとうございます」と返ってきたなら、やや間を置いてラインのアプリを閉じた。
アカルイオサムが言うには、彼女の彼氏は仕事にあまり理解がない人らしいので、胡散臭く思ったのかもしれないけど、表面上は礼儀正しく、俺のことを浮気相手だと勘ぐったり騒ぐようなことはなかった。
厄介ごとが避けられたのにほっとしたとはいえ、アカルイオサムにも彼女にも助けを求められない状況となり、安堵だけでないため息を吐かざるをえない。
彼女のノイローゼは、舞台の公演が終わるまでつづくだろうから、当てにはできない。
アカルイオサムは、そこまで長引かないかもしれないけど、舞台の要のライオンが絶不調であり、稽古のたびに揉めるとなれば、脚本家と共に頭を抱えつづけることになる。
そんなときに「怪人ヤッラーにキスをされるんだ」と相談をして、その頭を余計に悩ませるのは、気が引けるというもの。
いや、二人に相談しないでも、対処法は分かっているのだ。
二度と変な気を起こさせないよう、完膚なきまで拒絶をすること。
俺はあくまで代役。
三か月を過ぎたら、彼女がピンクレンジャーに復帰するけど、他の演者やスタッフは中身が変わったことに気づきはしない。
大柄の怪人ヤッラーも気づかないだろうから、俺が今のうちに拒絶をしておかないと、バトンタッチした彼女にまで迫ってくるかもしれないのだ。
といって、素性がばれるから声は出せないし、俺は声を出したくても出せない状態にある。
だったら、態度で示す。
ピンクレンジャーの格好をしているなら、拳や蹴りで語るしかない。
容赦なく股間を蹴り上げるとか。
ただ、大柄の怪人ヤッラーの場合は、股間を蹴り上げられて怯むどころか、照れ隠しと捉えたり「嫌よ嫌よも好きのうち」と解釈して、もっと情熱的で過激な行為に及んで、歯止めがかからなくなる可能性が高い。
ショーのアクションをするときも、その傾向が見られるのだから。
乱暴で遠慮のないアクションに、誰も相手をしたがらないところ、俺だけが対応してやっているとなれば、俺をマゾかなにかと、勘違いしていそうだし。
暴力で拒むのは、逆に俺のほうが危険だ。
となると、他に思いつくのは、手紙くらいだった。
手紙でも、あの大柄の怪人ヤッラーなら、真っ二つに引き裂きそうだったけど、破られても破られても手紙を渡せば、諦めてくれるかもしれないと考えた。
力で抵抗されて興奮するようなタイプだとしたら、しおらしい手紙攻撃には、調子が狂うはずだ。
おそらく俺のことを女性だと思っているだろうから、劇団の親しい女優に代筆をしてもらった。
「役の練習をしたいから」と頼めば、女優は怪訝そうな顔をしたものの、細かいことは聞かないで、ピンクの便箋に、俺の言う通りの文字を綴ってくれた。
「ありがとう」と画面を見せて、お茶のペットボトルを渡し、引き換えのように渡された便箋をピンクの封筒に入れようとしたら着信音が鳴った。
脇に挟んでいたから驚いて、とりあえず便箋と封筒をテーブルに置き、画面を見れば「アカルイオサム」の名前と、太宰治の真似をした写真が表示されていた。
もしかして、脚本のほうが落ち着いたのか。
だったら、怪人ヤッラーのことと手紙のことを教えるのにちょうどいいと思い、電話に出たら「おっす、ピンクレンジャー!」とけたたましい声が耳を打った。
昨日、脚本家の家に泊まり込むと報告したときとは一転、陽気なもので、酔っているようだ。が、アカルイオサムは酒が飲めないはず。
どこかに頭でも打ったのか。
追い詰められるあまり精神が破綻したのか。
と心配する俺をよそに「明日、お前、ショーに出るんだろお?」と言って「ぐっふ、ふ、ふ、ふふ・・・」と笑いだした。
心配するより薄気味悪く思いだしたところで「ぱっぱぱーん!」とファンファーレのような声を上げ「なんと、実はあ」ともったいぶって言ったことには。
「俺も明日、魔人ダンダーラになって、お前と一緒にステージに立ちます!」
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
15
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる