11 / 44
山芒編
11復路
しおりを挟む
燕太傅が賢妃宮に訪れる日は戊陽は普段より落ち着きがなくなる。玲馨は一見落ち着いているように見えて、心の中では浮かれていた。
「燕老師! お待ちしておりました!」
戊陽は燕太傅の姿が見えるなり駆け寄っていく。燕太傅の前でぴたりと止まって拱手をするが慌てたせいで所作がいい加減だ。すると燕太傅がたちまち厳しい顔をするので、戊陽は拱手の姿勢を改めた。戊陽がきちんと拱手をしたのを見て、燕太傅も恭しく拱手を返すのである。
年の功だと言ってしまえばそれまでだが、燕太傅は泰然自若とした人で、誰しもが自然と敬うような徳の高い人だ。
燕太傅はその名を燕宋文という。御年七十を迎えるが、背筋はピンと伸び、足を引き摺って歩くような事もなく矍鑠としている。
沈の官服が円領の袍に定められてからも、よほどの場合でなければ交領の襦と裙の上から半臂を羽織って腰帯で締めた格好を好んでしている事が多い。曰く、自分は官僚とはいえ名誉職でしかないので他の者たちとは分けるべきである、だそうだ。彼が政から遠退いて久しい。
「今日は何をお話して下さるのです? 私としては遊歴をされていた頃の続きなどが良いかと思いますが」
提案というよりこれは戊陽の単なる願望だ。小難しい政治や思想の話より詩作を教わりたいし、詩作よりもさながら冒険譚のような遊歴の話が楽しみなのだ。
とは言え燕太傅に教わる事が出来るなら何でも構わないとも思っている。教え方が上手く、訊いた事に対して曖昧にせず必ず答えが返ってくるので意欲を持って勉学に励もうという気になるのだ。
「そうだろう、玲馨?」
戊陽より数歩下がった所で拱手していた玲馨がパッと顔を上げる。同意するかと思いきや「燕太傅のお話を聞けるだけでも貴重な事です」と答えた。戊陽よりも燕太傅の顔を立てたいらしい。それからまた玲馨は頭を下げる。
燕太傅はなかなか拱手を解かない玲馨の両腕を持って楽にさせてやると、用意しておいた椅子に腰を下ろし、一冊の本を取り出した。
「今日はひとつ東の民族についてお話し致しましょう」
*
結局あの日、燕太傅は遊歴の話をする事はなかった。持参した本は東の民族、つまり練族の習慣や生活様式を記したもので、あの当時で百年ほど前に編纂されたものだった。元は巻子だったものを燕太傅自ら写本し綴じた物だったので、やたらと達筆だった事を覚えている。
「練族はやがてまた山芒を襲ってくるでしょう。七十年の間、山芒軍は都度追い返す事しか出来なかった。しかしここで一矢報いねばならぬのです」
向の屋敷の母屋には戊陽と李将軍、そして向青倫と山芒軍の節度使が揃っていた。
節度使とは元々は刺史の役割も兼任した官職だったが、やがて行政と軍事で別れ刺史が行政を、節度使が軍事の監察官となった。
当然のように節度使も地方組織と癒着しており、こちらは最早皇帝直轄とは到底言えなくなっている。地方軍の頂点に王を置き、節度使はその参謀といったところだ。節度使の任命も三代も前、つまり戊陽の祖父が任命したのを最後に、以降は兵部が代わりに任命している。
節度使の事はさておき、向青倫の言っている事を噛み砕くと「戦を仕掛けましょう陛下」となる。それを尤もらしく聞こえの良い言い回しに変えているだけだ。
向青倫と戊陽が座る卓には山芒を中心にした大きな地図が広げてあり、練族が暮らす東の高原には新しく墨で書き足されている。薄い墨で塗られたそれは、どうやら高原地帯で発生してあるあわいのようだ。
「それを私が二つ返事で了承すると思ったか、向青倫」
「お聞き下さい陛下。高原を調査した所、現在練族は全体で四千に満たないようなのです。そのうち戦える者は千を割ります」
先日戊陽は山芒を救うために必要ならば千の兵を貸し出すという話をした。そこで向青倫は考えたのだろう。この機に戊陽をせっついてもう少し多く兵を出させ、東一帯を山芒で治めてしまおうと。
練族が降れば高原が沈の統治下という事になるが、内実は山芒の配下になる。練族は馬を駆るのに長け女でも戦うというので山芒の軍事力を拡大させる算段なのだ。
そうと分かっていて是を出せるほど、これは簡単な事ではない。
「高原と山芒までを繋ぐ行路は二箇所しかなく、どちらか一方を寡兵で抑え、もう一方から大軍を練族が暮らす天幕に向かわせるだけで勝てるのです。血は多くは流れませぬ」
「今、多くはと言ったか?」
「は……。曲がりなりにも戦と言うからには、無血とはいきませぬ、陛下」
「お前は自身の失態で山芒兵から百以上も死傷者を出しておきながら、まだ兵士たちに死ねと申すのか」
雄弁だった向青倫の勢いが、水の流れを堰き止めたかのように留まった。兵士百余名が死傷したその果てに皇帝が二日昏倒した事を考えたのだろう。そして何よりそこには自身の息子が勘定に含まれている。
向青倫の行いがいかに横暴であったか、まずそこを正さなくては戦をしても兵がついてこない。
「陛下──」
「木王様、よろしいですか」
侍従の男がやってくると向青倫は一瞬忌々しげに目を眇めたが「申せ」と許しを出す。それから何事かを耳打ちされると、顔色が変わった。
「陛下、申し訳ございませぬ。少し席を外す時間を頂きたい」
「構わぬが、何があった?」
「息子が、向峻が目を覚ましました」
「……そうか。早く行ってやると良い」
元々大柄で動きのひとつひとつが大きい向青倫が、細々と動くように素早く出ていく背中を見て、戊陽は胸を撫でおろした。
向青倫の次男向峻は戊陽が最後に救った兵士だと思われた青年で、目に見えるものも見えないものも戊陽が治癒を施した。しかしそれから一度も目を覚まさず、今漸く意識回復の報せが入ったのだった。
叩頭する向青倫の姿を見た戊陽としてはこの場で息子のところへ行かせない選択肢は無い。戊陽としても肩の力が抜けるような思いだ。
「陛下、よう御座いましたな」
「ああ」
この場から山芒側の人間は一時的に消えている。少し気を緩めると伸ばしていた背中が勝手に丸まった。
「今朝方、寺院の方もほとんどの兵士が自宅へと戻ったと聞いておりますし、ここは我が軍の兵士だけ残して一度紫沈へ戻られるのがよろしいかと」
李将軍に言われた言葉を頭の中で噛み砕く。彼なりに助け舟を出したつもりだろう。向青倫がした話を一旦持ち帰って検討した方が良いという李将軍の意見でもある。この後向青倫が戻るのに合わせて李将軍に今のことを発言させ、尻馬に乗れば多少なりと楽に話が展開しそうだが。
──それで良いのか?
何かが引っ掛かって、李将軍に同意を返せない。
もしここで戊陽が練族の話を先送りにして紫沈に戻ったとしたら、向青倫はどう動くだろうか。
まず、山芒軍の力だけで練族を圧倒してしまう事は、恐らく難しいだろう。
山芒に到着してからすぐに、戊陽も密偵というほどではないが玲馨とは別に、山芒軍について四郎に調べさせていてる。
四郎によれば山芒軍はその総数を四千としているが実際にはもっと少ない。今回の事故の事を踏まえれば更に減って三千から三千五百を推移する。
対して練族は千を割ると向青倫は言ったが、遊牧の民とは普段から一所に定住しないので数の正確性は怪しむべきだろう。想定よりも五百ほど増えるだけで戦況は一気に泥沼化するのではないか。
その上こちらは山間部という都合上、騎馬兵力が極端に低い。相手は遊牧民と言うが馬を駆るのだから騎馬民族とも言える。機動力の差が元から大きい事を考えたら、禁軍の援護なく山芒軍だけで戦を展開するのは愚策と言わざるを得なかった。
向青倫の事を戊陽はよく知らないが、彼は約二十年に渡ってこの山芒を治めてきた男だ。戊陽が生まれた頃から王を務めてきた男がこんな所で過つはずがない。
では、向青倫は高原に向けて出兵はせず、引き続き守備に努めるか?
この問いに対して戊陽は、そうだ、と確信が持てないでいた。
「戊陽陛下」
声がして顔を上げると、四郎が部屋の入り口に立っていた。彼には回廊で待つよう伝えてあったので、何かあったようだ。
「入れ」
許しを得た四郎が音もなく入ってくる。この男が私というものを見せた事は一度も無いので戊陽は四郎がどんな人間かを知らない。
二十年来、滅私を貫く四郎は戊陽の傍まで来ると声を落として報告した。
「玲馨が来ています」
四郎には向青倫の姿が見えたら報告するよう伝えて部屋のすぐ外に立たせた。
玲馨が入れ違いで中へと入ってくる。彼の後ろには辛新と梅がついてきていた。
「陛下、お伝えしたき儀が御座います」
「申せ」
「はい。北玄海刺史、及び山芒の刺史の両名が現在捕らえられております」
「北玄海の刺史だと? なぜ北の刺史がこんな所へ」
「逃げてきたものと」
「逃げる?」
北玄海の刺史が山芒へ逃げてきたと聞かされても、その二点だけでは上手く繋がらない。玲馨に続けて報告させる。
「両名は主に監察報告の義務を怠っておりましたが、その中にあわいの消失とそれに伴う領土の拡大、引いては兵力増強の件が含まれます」
玲馨の言葉の中に聞き捨てならない台詞があった。兵力増強とは、つまり北玄海軍の事を指しているのか。
「北の岳川下流付近のあわいの減少は上流の影響によるものと推測されます。両刺史を通して密に連絡を取り合い、山芒と北玄海は水面下で手を組んでいる可能性が高いかと」
わざわざ向青倫の屋敷まで来て、恐らくは一度外を見張る兵士に止められたろう。それでも尚強引に玲馨が報告へ来た理由が分かった。
おかげで、先の「引っ掛かり」の原因も分かった。向青倫は中央からの援軍などなくとも高原へ戦を仕掛けるつもりだ。
そもそも戊陽が事故の件で禁軍を動かすかどうかは半ば賭けだった。にも関わらず向青倫は既に高原地帯の調査を終えており、練族の戦力を概ね把握していた。
何より本来なら互いに警戒しあうはずの北玄海に対して秘密裏に援護するような行為、つまり川の上流で行った工事とやらがそれに当たるとして、それらを実行したなら北玄海からも山芒に対して何らかの見返りがあるものと考えなくてはならない。
見返りとは何か。山芒が欲しているもるのは何か。そう、軍事力だ。
「よく報告してくれた玲馨」
「いえ。陛下の御為ならば」
玲馨の顔付きはさほど良くない。褒められて手放しで喜ぶ性格でもないが、それにしては暗いというか苛立ちのようなものが見え隠れしている。
何故かと考えた時、北玄海の事を思い出す。玲馨は一ヶ月ばかり北の調査に赴いていたが、成果はいまひとつ得られなかった。どうやら北玄海の水王にしてやられたと気付いたのだろう。それが玲馨は悔しいのだ。
昔はもう少し素直で可愛い奴だと思っていたが、いつからこんなに強気な人間になったのだか。
「陛下?」
玲馨に首を傾げられ、つい笑ってしまった事に気が付いた。
この場に留まらせれば向青倫に余計な詮索をされるので帰した方が良いだろう。それに梅がもう退屈でたまらないようだ。
三人に下がるよう言うと、去り際に辛新が大声で「失礼致します!」と半ば叫ぶようにして去っていった。李将軍が謝る横で、辛新の声を聞いてはてと戊陽は考え込む。今の声、どこかで聞いた覚えがあったような。
「……ん? いかがなさいました陛下」
一度、斜め後ろに立ちっぱなしの李将軍を振り返ってから、戊陽はたちまち頭を抱えたくなった。
辛新の声はあの夜、向家の屋敷の西側、向の公主の部屋からしていた声にそっくりだった。
*
「声がでけぇなー辛新」
「肺活量には自信があります!」
相変わらず辛新には嫌味が通じないので、肩透かしを食らった梅はつまらなさそうだ。嫌味など通用する必要はないが、あの場で戊陽が三人を下がらせた意味くらいは気付くべきだろうなと思うので複雑である。辛新に出世は期待出来なさそうだ。
山芒の玄関口である藍心と領都株景は片道徒歩で二時辰がかかる。せっかくなら領都まで出向いたついでにこちらで調べられる事はないかと考えていたが、ふと頭に過ぎったのは向家屋敷で見た山芒の地図だった。辛新が実家から借りてきてくれた地図より広域で且つ詳細なあれを見るに、地図一つで震えていた辛新を思い出した。
地図は重要な情報の一つだ。地理、地形、方位、その他諸々が分かるのと分からないとでは、「統治」の精度が違う。更にそれは戦にも応用出来る訳だが。
「地図が欲しいな」
「地図なら持ってるじゃねぇか。借りモンなのにあんたが色々書き込んだお手製のがよ」
「そうではない。あわいの地図が欲しいんだ」
「あわいだぁ?」
「それなら今回の行軍の行路を決めた武官の方に訊いてみては?」
確かにそれなら地図を持っていなくてはおかしい。今頃山芒軍の救助活動中だろうが、行ってみるべきか。だが軍の邪魔はしたくない。これには人命が関わっている。
「向のお屋敷に、戻ってみます……?」
出来る限り断ってくれと願っているような顔と声で言われても、元からそのつもりはない。
考えてみたら何故辛新は屋敷の中までついてきたのだろう。向青倫には辛新と公主の関係は既に知られているはずだが。恋敵の顔を間近で拝んでおきたかったのだろうか。
「屋敷にあった地図よりもっと広域の、沈全体、いえ周辺国までが記されたようなものがあるとより良いのですが」
「そんなに広い地図ですか? それはさすがに山芒には無いかと……」
そうだろう。地図には測量という技術が必要で、誰にでも簡単に描けるものではない。特にあわい発生後は国内を自由に歩く事が出来なくなり、少なくとも七十年の間は測量しておらず、現在の各領地はそれぞれの都市が領有する範囲を自己申告したものに従って描いただけで、より正確性は失われているだろう。
玲馨が地図を初めて見たのは燕太傅が見せてくれたものだった。あわい発生より前の古い地図で、沈全体が描かれていた。
あれは、燕太傅個人の物ではなかったはずだ。
「で、どうするよ?」
訊かれるまでもなく、玲馨の心は決まっていた。
「紫沈に戻る」
皇帝付きの宦官というが、このところは名ばかりだなと思う。北玄海へ発つ前は戊陽の身の回りの世話を何から何までやっていた。食事、着替え、朝議では必ず傍に控えていたし、四郎では話し相手が一切務まらないので何気ない雑談から政治的な独り言──要は愚痴──にまで付き合っていた。
午後からは皇弟の小杰の宮へ行くのだが、小杰へは勉強を教えるだけなので共に過ごす時間は戊陽の方が長かった。
夜は黄麟宮に向かわず宦官の宿舎へ帰る。四郎は黄麟宮に部屋を与えられているので緊急時は四郎が対応するのだが、これにも戊陽は難色を示していた。四郎が嫌なのではなく玲馨が良いのだそうだ。まるで子供のようだが、即位し皇帝と呼ばれるようになってからも彼の根の素直な所が変わらずほっとしている。
確かに、彼の素直さは美徳だとは思うのだが……。
「玲馨さん馬に乗れたんですね!」
「嘘つきじゃん。嘘つきー!」
梅は一人だけ歩かされているのでその文句は甘んじて受けようと思う。いや、実際にはもう一人四郎が徒歩だがふとすると彼の存在は意識から消えていってしまう。
嘘を吐いた事に深い理由はなく、強いて言うなら癖だ。
宦官にしては玲馨は過分な待遇を受けてきた。そこで得た知識や教養、あるいは技芸のようなものをひけらかすと、大抵は良い顔をされないので出来る事、知っている事も相手を選んで話すようにしていた。
さてそんな玲馨が何の嘘をついていたかというと。
玲馨は現在、皇帝が乗るために育てられた黒馬「驥驥」に跨り手綱を引いている。その背中に皇帝本人を掴まらせて。
これでも説得は試みたのだ。体調が思わしくないならもう一日二日休んで、李将軍他数名の兵士と共に安全に帰還してくれと。しかしどうあっても戊陽は聞く耳を持たず、結局玲馨たち三人に皇帝と李将軍を加えた五人であわいの街道を紫沈へ向かって帰途に着く事になった。
戊陽は二日で病床からは復帰してきたものの、結局体調は万全とはいかなかった。向青倫との話を一旦纏めるとその足で玲馨たちを追い掛けて、どうせ紫沈に帰るつもりだろうと見事に玲馨の考えを看破してみせ一緒に帰りたいとごねだした。
「陛下は随分とその宦官の事を信頼しておるのだな」
驥驥と並走していた李将軍が言うと、あらゆる意味を含んだ複雑な視線が辛新と梅から李将軍へ向かって飛んでいく。確かに李将軍はあまり人の噂には詳しくなさそうだ。玲馨が言えた義理ではないが。
辛新はさておき、梅は李将軍にまで軽口を叩きかねないので「やめておけよ」と釘を刺しておく。
戊陽に刺史の事を報告し、その後は再びあわいを進む準備をしたのであれから一日が経過しているのだが、背中に感じる体温はあまり温かくはなく仮病という事はないのだろう。これから数日はその状態で野宿が続く事になる。
「全員止まれ。ここで一度馬に餌を与えておくぞ」
李将軍の合図で全員が止まる。
あわいを馬で行こうとすると馬の餌を馬に引かせるか、出発地近くと到着地近くで餌を与えて数日餌無しで進む方法を選ばなくてはならない。今回は少人数のため山芒の芒守門で餌を与え、水はあわいが浅い川沿いで補給する道を行く事になる。
人間は水筒と携帯食に餅という小麦を練って丸めて焼いた物を各自で持っていく。行きは最初の数日だけからし菜の漬物があったので、既にあの塩気が恋しい。
「陛下、ご自分で降りられますか?」
腹に巻き付いている手に手を添えそっと剥がしつつ問うと、一瞬だけしがみつく力が強まった。かと思えばすぐに腕は離れて戊陽は軽々と馬を降りる。
──やはり仮病だったか?
「驥驥、たくさん食べておくのだぞ」
馬を降りた戊陽が驥驥の顔を撫でると、驥驥は返事をするようにブルルと鼻喇叭を鳴らす。戊陽が半元服を迎える十二歳の時に産まれた馬なので、今年で九歳だ。大人になり、落ち着きや余裕が出た頃なので過酷な旅でも戊陽を安心して任せられる。
「この後はお一人で乗られて下さい」
「何故だ? お前も驥驥に乗った方が楽だろう」
「驥驥を大切に思われるなら私は歩きがよろしいでしょう」
むう、と指を下唇の下に当てて押し上げる仕草は考えているフリをして実は不満がある時だ。しかし自分のわがままで馬を使い潰すほど傲慢にはなれないようで渋々了承した。
芒守門付近には主に行商のために飼料を保存する貯蔵庫が設けてある。古くは軍馬のための厩舎と水路も確保されていたが、管理が厳しくなってから厩舎は崩れ、水路は枯れてしまった。これは辛新からの受け売りである。
面々は三々五々に木陰や貯蔵庫の近くに腰を下ろし、馬が食事を終えるのを待った。
玲馨は驥驥に飼料を与えると、自分も少しだけ水を飲む。そのまま驥驥の傍で何気なく食事を見ていると戊陽が寄ってきた。
「枯れた土地はこんなにも寂寞としているが、北ではあわいが消えたと言っていたな」
思いの外真面目な話題だ。
「あわいは消せると思うか?」
分からない。そんな事は誰にも分からない。これが答えだ。
「あわいが消え、国土が回復すれば、民の暮らしは今より安定するでしょう。しかし」
「しかし消せなければやがて──」
言葉の続きを戊陽は言わなかった。他でもない皇帝がそれを口にしてはならないと理性が働いたのだろう。
「俺は今のうちに、お前と過ごす時間を堪能せねばならんのだな」
「お戯れを──」
てっきりそこにはにやついた表情があると思っていたのに、隣には全くもって真剣な顔をした戊陽が居た。何かを惜しむような表情に、玲馨の胸が嫌な跳ね方をした。
悲観しているのだろうか、未来を。
昔から玲馨は、こういう時に掛ける言葉を持たなかった。よくよく玲馨を知る人物は、そんな玲馨をそのままで良いと受け入れてくれた。
今ではもうそんな人は、戊陽だけになってしまったが。
「私は、ずっとあなたの傍におります。陛下が私をお引き立て下さった時から、そう決めています」
戊陽の眉尻が下がり何だか顔付きが情けなくなる。何かまずい事を言ったかと焦ったが、戊陽が深く息を吐き出して顔を覆うと「そういうのはもっと時と場所を選んで言うもんだ」と耳を真っ赤にして言うので、玲馨はそっと戊陽から視線を外した。お互い様だろうという文句は心の中に仕舞っておく。
それからは諸々落ち着くまで、驥驥がもしゃもしゃと餌を食べるのを凝視していた。
山芒からの復路は、往路とは比較にならないほど順調に進んだ。少人数だとあわいの浅い道を選べるのが大きく、夜は妖魔避けの薬と焚き火の炎だけで妖魔は寄ってこなくなった。また、単純に往路は荷車を引いていた関係で遠回りだった事も一因だ。
行きは六日かかった旅程を、帰りはさほど急がずとも四日で終える事になった。
朝靄が晴れると紫沈を囲う高い城壁が目前に迫っていた。
「帰ってきましたね」
辛新が言う。誰も答えないかと思いきや、強が代わりに鼻喇叭を鳴らす。
およそ半月に及んだ山芒の旅が、間もなく終わろうとしている。
「燕老師! お待ちしておりました!」
戊陽は燕太傅の姿が見えるなり駆け寄っていく。燕太傅の前でぴたりと止まって拱手をするが慌てたせいで所作がいい加減だ。すると燕太傅がたちまち厳しい顔をするので、戊陽は拱手の姿勢を改めた。戊陽がきちんと拱手をしたのを見て、燕太傅も恭しく拱手を返すのである。
年の功だと言ってしまえばそれまでだが、燕太傅は泰然自若とした人で、誰しもが自然と敬うような徳の高い人だ。
燕太傅はその名を燕宋文という。御年七十を迎えるが、背筋はピンと伸び、足を引き摺って歩くような事もなく矍鑠としている。
沈の官服が円領の袍に定められてからも、よほどの場合でなければ交領の襦と裙の上から半臂を羽織って腰帯で締めた格好を好んでしている事が多い。曰く、自分は官僚とはいえ名誉職でしかないので他の者たちとは分けるべきである、だそうだ。彼が政から遠退いて久しい。
「今日は何をお話して下さるのです? 私としては遊歴をされていた頃の続きなどが良いかと思いますが」
提案というよりこれは戊陽の単なる願望だ。小難しい政治や思想の話より詩作を教わりたいし、詩作よりもさながら冒険譚のような遊歴の話が楽しみなのだ。
とは言え燕太傅に教わる事が出来るなら何でも構わないとも思っている。教え方が上手く、訊いた事に対して曖昧にせず必ず答えが返ってくるので意欲を持って勉学に励もうという気になるのだ。
「そうだろう、玲馨?」
戊陽より数歩下がった所で拱手していた玲馨がパッと顔を上げる。同意するかと思いきや「燕太傅のお話を聞けるだけでも貴重な事です」と答えた。戊陽よりも燕太傅の顔を立てたいらしい。それからまた玲馨は頭を下げる。
燕太傅はなかなか拱手を解かない玲馨の両腕を持って楽にさせてやると、用意しておいた椅子に腰を下ろし、一冊の本を取り出した。
「今日はひとつ東の民族についてお話し致しましょう」
*
結局あの日、燕太傅は遊歴の話をする事はなかった。持参した本は東の民族、つまり練族の習慣や生活様式を記したもので、あの当時で百年ほど前に編纂されたものだった。元は巻子だったものを燕太傅自ら写本し綴じた物だったので、やたらと達筆だった事を覚えている。
「練族はやがてまた山芒を襲ってくるでしょう。七十年の間、山芒軍は都度追い返す事しか出来なかった。しかしここで一矢報いねばならぬのです」
向の屋敷の母屋には戊陽と李将軍、そして向青倫と山芒軍の節度使が揃っていた。
節度使とは元々は刺史の役割も兼任した官職だったが、やがて行政と軍事で別れ刺史が行政を、節度使が軍事の監察官となった。
当然のように節度使も地方組織と癒着しており、こちらは最早皇帝直轄とは到底言えなくなっている。地方軍の頂点に王を置き、節度使はその参謀といったところだ。節度使の任命も三代も前、つまり戊陽の祖父が任命したのを最後に、以降は兵部が代わりに任命している。
節度使の事はさておき、向青倫の言っている事を噛み砕くと「戦を仕掛けましょう陛下」となる。それを尤もらしく聞こえの良い言い回しに変えているだけだ。
向青倫と戊陽が座る卓には山芒を中心にした大きな地図が広げてあり、練族が暮らす東の高原には新しく墨で書き足されている。薄い墨で塗られたそれは、どうやら高原地帯で発生してあるあわいのようだ。
「それを私が二つ返事で了承すると思ったか、向青倫」
「お聞き下さい陛下。高原を調査した所、現在練族は全体で四千に満たないようなのです。そのうち戦える者は千を割ります」
先日戊陽は山芒を救うために必要ならば千の兵を貸し出すという話をした。そこで向青倫は考えたのだろう。この機に戊陽をせっついてもう少し多く兵を出させ、東一帯を山芒で治めてしまおうと。
練族が降れば高原が沈の統治下という事になるが、内実は山芒の配下になる。練族は馬を駆るのに長け女でも戦うというので山芒の軍事力を拡大させる算段なのだ。
そうと分かっていて是を出せるほど、これは簡単な事ではない。
「高原と山芒までを繋ぐ行路は二箇所しかなく、どちらか一方を寡兵で抑え、もう一方から大軍を練族が暮らす天幕に向かわせるだけで勝てるのです。血は多くは流れませぬ」
「今、多くはと言ったか?」
「は……。曲がりなりにも戦と言うからには、無血とはいきませぬ、陛下」
「お前は自身の失態で山芒兵から百以上も死傷者を出しておきながら、まだ兵士たちに死ねと申すのか」
雄弁だった向青倫の勢いが、水の流れを堰き止めたかのように留まった。兵士百余名が死傷したその果てに皇帝が二日昏倒した事を考えたのだろう。そして何よりそこには自身の息子が勘定に含まれている。
向青倫の行いがいかに横暴であったか、まずそこを正さなくては戦をしても兵がついてこない。
「陛下──」
「木王様、よろしいですか」
侍従の男がやってくると向青倫は一瞬忌々しげに目を眇めたが「申せ」と許しを出す。それから何事かを耳打ちされると、顔色が変わった。
「陛下、申し訳ございませぬ。少し席を外す時間を頂きたい」
「構わぬが、何があった?」
「息子が、向峻が目を覚ましました」
「……そうか。早く行ってやると良い」
元々大柄で動きのひとつひとつが大きい向青倫が、細々と動くように素早く出ていく背中を見て、戊陽は胸を撫でおろした。
向青倫の次男向峻は戊陽が最後に救った兵士だと思われた青年で、目に見えるものも見えないものも戊陽が治癒を施した。しかしそれから一度も目を覚まさず、今漸く意識回復の報せが入ったのだった。
叩頭する向青倫の姿を見た戊陽としてはこの場で息子のところへ行かせない選択肢は無い。戊陽としても肩の力が抜けるような思いだ。
「陛下、よう御座いましたな」
「ああ」
この場から山芒側の人間は一時的に消えている。少し気を緩めると伸ばしていた背中が勝手に丸まった。
「今朝方、寺院の方もほとんどの兵士が自宅へと戻ったと聞いておりますし、ここは我が軍の兵士だけ残して一度紫沈へ戻られるのがよろしいかと」
李将軍に言われた言葉を頭の中で噛み砕く。彼なりに助け舟を出したつもりだろう。向青倫がした話を一旦持ち帰って検討した方が良いという李将軍の意見でもある。この後向青倫が戻るのに合わせて李将軍に今のことを発言させ、尻馬に乗れば多少なりと楽に話が展開しそうだが。
──それで良いのか?
何かが引っ掛かって、李将軍に同意を返せない。
もしここで戊陽が練族の話を先送りにして紫沈に戻ったとしたら、向青倫はどう動くだろうか。
まず、山芒軍の力だけで練族を圧倒してしまう事は、恐らく難しいだろう。
山芒に到着してからすぐに、戊陽も密偵というほどではないが玲馨とは別に、山芒軍について四郎に調べさせていてる。
四郎によれば山芒軍はその総数を四千としているが実際にはもっと少ない。今回の事故の事を踏まえれば更に減って三千から三千五百を推移する。
対して練族は千を割ると向青倫は言ったが、遊牧の民とは普段から一所に定住しないので数の正確性は怪しむべきだろう。想定よりも五百ほど増えるだけで戦況は一気に泥沼化するのではないか。
その上こちらは山間部という都合上、騎馬兵力が極端に低い。相手は遊牧民と言うが馬を駆るのだから騎馬民族とも言える。機動力の差が元から大きい事を考えたら、禁軍の援護なく山芒軍だけで戦を展開するのは愚策と言わざるを得なかった。
向青倫の事を戊陽はよく知らないが、彼は約二十年に渡ってこの山芒を治めてきた男だ。戊陽が生まれた頃から王を務めてきた男がこんな所で過つはずがない。
では、向青倫は高原に向けて出兵はせず、引き続き守備に努めるか?
この問いに対して戊陽は、そうだ、と確信が持てないでいた。
「戊陽陛下」
声がして顔を上げると、四郎が部屋の入り口に立っていた。彼には回廊で待つよう伝えてあったので、何かあったようだ。
「入れ」
許しを得た四郎が音もなく入ってくる。この男が私というものを見せた事は一度も無いので戊陽は四郎がどんな人間かを知らない。
二十年来、滅私を貫く四郎は戊陽の傍まで来ると声を落として報告した。
「玲馨が来ています」
四郎には向青倫の姿が見えたら報告するよう伝えて部屋のすぐ外に立たせた。
玲馨が入れ違いで中へと入ってくる。彼の後ろには辛新と梅がついてきていた。
「陛下、お伝えしたき儀が御座います」
「申せ」
「はい。北玄海刺史、及び山芒の刺史の両名が現在捕らえられております」
「北玄海の刺史だと? なぜ北の刺史がこんな所へ」
「逃げてきたものと」
「逃げる?」
北玄海の刺史が山芒へ逃げてきたと聞かされても、その二点だけでは上手く繋がらない。玲馨に続けて報告させる。
「両名は主に監察報告の義務を怠っておりましたが、その中にあわいの消失とそれに伴う領土の拡大、引いては兵力増強の件が含まれます」
玲馨の言葉の中に聞き捨てならない台詞があった。兵力増強とは、つまり北玄海軍の事を指しているのか。
「北の岳川下流付近のあわいの減少は上流の影響によるものと推測されます。両刺史を通して密に連絡を取り合い、山芒と北玄海は水面下で手を組んでいる可能性が高いかと」
わざわざ向青倫の屋敷まで来て、恐らくは一度外を見張る兵士に止められたろう。それでも尚強引に玲馨が報告へ来た理由が分かった。
おかげで、先の「引っ掛かり」の原因も分かった。向青倫は中央からの援軍などなくとも高原へ戦を仕掛けるつもりだ。
そもそも戊陽が事故の件で禁軍を動かすかどうかは半ば賭けだった。にも関わらず向青倫は既に高原地帯の調査を終えており、練族の戦力を概ね把握していた。
何より本来なら互いに警戒しあうはずの北玄海に対して秘密裏に援護するような行為、つまり川の上流で行った工事とやらがそれに当たるとして、それらを実行したなら北玄海からも山芒に対して何らかの見返りがあるものと考えなくてはならない。
見返りとは何か。山芒が欲しているもるのは何か。そう、軍事力だ。
「よく報告してくれた玲馨」
「いえ。陛下の御為ならば」
玲馨の顔付きはさほど良くない。褒められて手放しで喜ぶ性格でもないが、それにしては暗いというか苛立ちのようなものが見え隠れしている。
何故かと考えた時、北玄海の事を思い出す。玲馨は一ヶ月ばかり北の調査に赴いていたが、成果はいまひとつ得られなかった。どうやら北玄海の水王にしてやられたと気付いたのだろう。それが玲馨は悔しいのだ。
昔はもう少し素直で可愛い奴だと思っていたが、いつからこんなに強気な人間になったのだか。
「陛下?」
玲馨に首を傾げられ、つい笑ってしまった事に気が付いた。
この場に留まらせれば向青倫に余計な詮索をされるので帰した方が良いだろう。それに梅がもう退屈でたまらないようだ。
三人に下がるよう言うと、去り際に辛新が大声で「失礼致します!」と半ば叫ぶようにして去っていった。李将軍が謝る横で、辛新の声を聞いてはてと戊陽は考え込む。今の声、どこかで聞いた覚えがあったような。
「……ん? いかがなさいました陛下」
一度、斜め後ろに立ちっぱなしの李将軍を振り返ってから、戊陽はたちまち頭を抱えたくなった。
辛新の声はあの夜、向家の屋敷の西側、向の公主の部屋からしていた声にそっくりだった。
*
「声がでけぇなー辛新」
「肺活量には自信があります!」
相変わらず辛新には嫌味が通じないので、肩透かしを食らった梅はつまらなさそうだ。嫌味など通用する必要はないが、あの場で戊陽が三人を下がらせた意味くらいは気付くべきだろうなと思うので複雑である。辛新に出世は期待出来なさそうだ。
山芒の玄関口である藍心と領都株景は片道徒歩で二時辰がかかる。せっかくなら領都まで出向いたついでにこちらで調べられる事はないかと考えていたが、ふと頭に過ぎったのは向家屋敷で見た山芒の地図だった。辛新が実家から借りてきてくれた地図より広域で且つ詳細なあれを見るに、地図一つで震えていた辛新を思い出した。
地図は重要な情報の一つだ。地理、地形、方位、その他諸々が分かるのと分からないとでは、「統治」の精度が違う。更にそれは戦にも応用出来る訳だが。
「地図が欲しいな」
「地図なら持ってるじゃねぇか。借りモンなのにあんたが色々書き込んだお手製のがよ」
「そうではない。あわいの地図が欲しいんだ」
「あわいだぁ?」
「それなら今回の行軍の行路を決めた武官の方に訊いてみては?」
確かにそれなら地図を持っていなくてはおかしい。今頃山芒軍の救助活動中だろうが、行ってみるべきか。だが軍の邪魔はしたくない。これには人命が関わっている。
「向のお屋敷に、戻ってみます……?」
出来る限り断ってくれと願っているような顔と声で言われても、元からそのつもりはない。
考えてみたら何故辛新は屋敷の中までついてきたのだろう。向青倫には辛新と公主の関係は既に知られているはずだが。恋敵の顔を間近で拝んでおきたかったのだろうか。
「屋敷にあった地図よりもっと広域の、沈全体、いえ周辺国までが記されたようなものがあるとより良いのですが」
「そんなに広い地図ですか? それはさすがに山芒には無いかと……」
そうだろう。地図には測量という技術が必要で、誰にでも簡単に描けるものではない。特にあわい発生後は国内を自由に歩く事が出来なくなり、少なくとも七十年の間は測量しておらず、現在の各領地はそれぞれの都市が領有する範囲を自己申告したものに従って描いただけで、より正確性は失われているだろう。
玲馨が地図を初めて見たのは燕太傅が見せてくれたものだった。あわい発生より前の古い地図で、沈全体が描かれていた。
あれは、燕太傅個人の物ではなかったはずだ。
「で、どうするよ?」
訊かれるまでもなく、玲馨の心は決まっていた。
「紫沈に戻る」
皇帝付きの宦官というが、このところは名ばかりだなと思う。北玄海へ発つ前は戊陽の身の回りの世話を何から何までやっていた。食事、着替え、朝議では必ず傍に控えていたし、四郎では話し相手が一切務まらないので何気ない雑談から政治的な独り言──要は愚痴──にまで付き合っていた。
午後からは皇弟の小杰の宮へ行くのだが、小杰へは勉強を教えるだけなので共に過ごす時間は戊陽の方が長かった。
夜は黄麟宮に向かわず宦官の宿舎へ帰る。四郎は黄麟宮に部屋を与えられているので緊急時は四郎が対応するのだが、これにも戊陽は難色を示していた。四郎が嫌なのではなく玲馨が良いのだそうだ。まるで子供のようだが、即位し皇帝と呼ばれるようになってからも彼の根の素直な所が変わらずほっとしている。
確かに、彼の素直さは美徳だとは思うのだが……。
「玲馨さん馬に乗れたんですね!」
「嘘つきじゃん。嘘つきー!」
梅は一人だけ歩かされているのでその文句は甘んじて受けようと思う。いや、実際にはもう一人四郎が徒歩だがふとすると彼の存在は意識から消えていってしまう。
嘘を吐いた事に深い理由はなく、強いて言うなら癖だ。
宦官にしては玲馨は過分な待遇を受けてきた。そこで得た知識や教養、あるいは技芸のようなものをひけらかすと、大抵は良い顔をされないので出来る事、知っている事も相手を選んで話すようにしていた。
さてそんな玲馨が何の嘘をついていたかというと。
玲馨は現在、皇帝が乗るために育てられた黒馬「驥驥」に跨り手綱を引いている。その背中に皇帝本人を掴まらせて。
これでも説得は試みたのだ。体調が思わしくないならもう一日二日休んで、李将軍他数名の兵士と共に安全に帰還してくれと。しかしどうあっても戊陽は聞く耳を持たず、結局玲馨たち三人に皇帝と李将軍を加えた五人であわいの街道を紫沈へ向かって帰途に着く事になった。
戊陽は二日で病床からは復帰してきたものの、結局体調は万全とはいかなかった。向青倫との話を一旦纏めるとその足で玲馨たちを追い掛けて、どうせ紫沈に帰るつもりだろうと見事に玲馨の考えを看破してみせ一緒に帰りたいとごねだした。
「陛下は随分とその宦官の事を信頼しておるのだな」
驥驥と並走していた李将軍が言うと、あらゆる意味を含んだ複雑な視線が辛新と梅から李将軍へ向かって飛んでいく。確かに李将軍はあまり人の噂には詳しくなさそうだ。玲馨が言えた義理ではないが。
辛新はさておき、梅は李将軍にまで軽口を叩きかねないので「やめておけよ」と釘を刺しておく。
戊陽に刺史の事を報告し、その後は再びあわいを進む準備をしたのであれから一日が経過しているのだが、背中に感じる体温はあまり温かくはなく仮病という事はないのだろう。これから数日はその状態で野宿が続く事になる。
「全員止まれ。ここで一度馬に餌を与えておくぞ」
李将軍の合図で全員が止まる。
あわいを馬で行こうとすると馬の餌を馬に引かせるか、出発地近くと到着地近くで餌を与えて数日餌無しで進む方法を選ばなくてはならない。今回は少人数のため山芒の芒守門で餌を与え、水はあわいが浅い川沿いで補給する道を行く事になる。
人間は水筒と携帯食に餅という小麦を練って丸めて焼いた物を各自で持っていく。行きは最初の数日だけからし菜の漬物があったので、既にあの塩気が恋しい。
「陛下、ご自分で降りられますか?」
腹に巻き付いている手に手を添えそっと剥がしつつ問うと、一瞬だけしがみつく力が強まった。かと思えばすぐに腕は離れて戊陽は軽々と馬を降りる。
──やはり仮病だったか?
「驥驥、たくさん食べておくのだぞ」
馬を降りた戊陽が驥驥の顔を撫でると、驥驥は返事をするようにブルルと鼻喇叭を鳴らす。戊陽が半元服を迎える十二歳の時に産まれた馬なので、今年で九歳だ。大人になり、落ち着きや余裕が出た頃なので過酷な旅でも戊陽を安心して任せられる。
「この後はお一人で乗られて下さい」
「何故だ? お前も驥驥に乗った方が楽だろう」
「驥驥を大切に思われるなら私は歩きがよろしいでしょう」
むう、と指を下唇の下に当てて押し上げる仕草は考えているフリをして実は不満がある時だ。しかし自分のわがままで馬を使い潰すほど傲慢にはなれないようで渋々了承した。
芒守門付近には主に行商のために飼料を保存する貯蔵庫が設けてある。古くは軍馬のための厩舎と水路も確保されていたが、管理が厳しくなってから厩舎は崩れ、水路は枯れてしまった。これは辛新からの受け売りである。
面々は三々五々に木陰や貯蔵庫の近くに腰を下ろし、馬が食事を終えるのを待った。
玲馨は驥驥に飼料を与えると、自分も少しだけ水を飲む。そのまま驥驥の傍で何気なく食事を見ていると戊陽が寄ってきた。
「枯れた土地はこんなにも寂寞としているが、北ではあわいが消えたと言っていたな」
思いの外真面目な話題だ。
「あわいは消せると思うか?」
分からない。そんな事は誰にも分からない。これが答えだ。
「あわいが消え、国土が回復すれば、民の暮らしは今より安定するでしょう。しかし」
「しかし消せなければやがて──」
言葉の続きを戊陽は言わなかった。他でもない皇帝がそれを口にしてはならないと理性が働いたのだろう。
「俺は今のうちに、お前と過ごす時間を堪能せねばならんのだな」
「お戯れを──」
てっきりそこにはにやついた表情があると思っていたのに、隣には全くもって真剣な顔をした戊陽が居た。何かを惜しむような表情に、玲馨の胸が嫌な跳ね方をした。
悲観しているのだろうか、未来を。
昔から玲馨は、こういう時に掛ける言葉を持たなかった。よくよく玲馨を知る人物は、そんな玲馨をそのままで良いと受け入れてくれた。
今ではもうそんな人は、戊陽だけになってしまったが。
「私は、ずっとあなたの傍におります。陛下が私をお引き立て下さった時から、そう決めています」
戊陽の眉尻が下がり何だか顔付きが情けなくなる。何かまずい事を言ったかと焦ったが、戊陽が深く息を吐き出して顔を覆うと「そういうのはもっと時と場所を選んで言うもんだ」と耳を真っ赤にして言うので、玲馨はそっと戊陽から視線を外した。お互い様だろうという文句は心の中に仕舞っておく。
それからは諸々落ち着くまで、驥驥がもしゃもしゃと餌を食べるのを凝視していた。
山芒からの復路は、往路とは比較にならないほど順調に進んだ。少人数だとあわいの浅い道を選べるのが大きく、夜は妖魔避けの薬と焚き火の炎だけで妖魔は寄ってこなくなった。また、単純に往路は荷車を引いていた関係で遠回りだった事も一因だ。
行きは六日かかった旅程を、帰りはさほど急がずとも四日で終える事になった。
朝靄が晴れると紫沈を囲う高い城壁が目前に迫っていた。
「帰ってきましたね」
辛新が言う。誰も答えないかと思いきや、強が代わりに鼻喇叭を鳴らす。
およそ半月に及んだ山芒の旅が、間もなく終わろうとしている。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
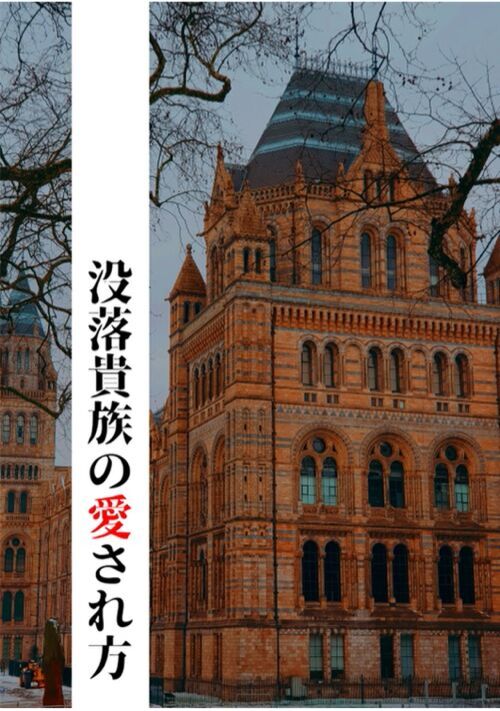
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















