13 / 44
宮廷編
13一日千秋
しおりを挟む
「あったぞ、昔の地図だ」
戊陽の声で懐かしくて初々しい思い出から意識が戻ってくる。「これを見ろ」という声に呼ばれて棚の向こう、戊陽の居る方へと回り込む。
戊陽が出してきた地図は三尺四方の軍議で使うような大きな地図だった。四つの都市と中央の紫沈とが紙ではなく麻の布に墨で書かれており所々滲んでしまっている。古い物のようで全体的に黄ばんでいて、長らく折りたたまれていたせいで折り目がくっきりとついてしまっていた。
禁書室から出てきたその地図は一般に見る地図とは様子が異なっている。
「この朱墨はあわい……?」
「恐らくな。今俺たちが使う地図と発生域が少し違っているような気がするが、小規模な地脈の変動が起きているのかも知れない」
禁書室には机がないので床に広げた地図を二人で見下ろす。
朱墨と思われる赤い墨は水で薄く溶いているようで、まるで染みのように沈全体のあちこちに滲んでいる。濃淡もまばらなら、濃い赤い線で円状に囲ってある所も見受けられる。
もしこの濃淡が意図して分けられているのだとしたら、濃い所が地脈の濃い所で、薄い所はその逆という事だろうか。または濃い所はあわいが濃い所かもしれない。
凱寧はあわいの発生の前年に卜師を徹底して排除したので、この地図は実地で川や植物や妖魔の出没状況を調査して地図に記していったはず。それを裏付けるのは南に連なる険峻な山脈だ。
山芒から南部に伸びている山脈は人の足で踏み入れないほど険しい。川によって大きく削られた渓谷など危険な場所が多く、天候の変わりやすさがそれに拍車をかける。山々を越えた先には他の国が築かれていると言われているが、沈の長い歴史の中で南から他国が侵略してきたり、或いは雲朱より南から来た人間というものが現れた事は一度もない。つまりただでさえ人を寄せ付けない山だったのが、あわいによってついに完全な人跡未踏となった訳だ。
その山脈付近は地図上では朱墨が一切塗られておらず真っ白になっている。山に人が立ち入れないからだ。しかし実際には春を迎えても遠目に山肌が茶色く枯れたままなので、現代では南の山脈にもあわいが発生しているとされる。
事前に持ってきておいた現代の地図を隣に並べると、あわいの区域は格段に広がっているのが分かる。後年になるにつれて調査が進んでいったのだろう。
恐らくはあわいが発生して間もない頃に描かれただろう古い地図を見ていると、玲馨はある事が気になった。
「主要な河川は、当時から無事だったのですね」
「そうだな」
地脈変動で沈が多くの犠牲を出しても国としての体裁が保たれたのは、川があわいに飲み込まれなかった事が最たる要因だ。
岳川他、一部の河川はあわいを流れているが、生活用水に使われる各都市の主要河川は、濁らず今も人に恵みを与え続けている。
「偶然、なんでしょうか……」
「どういう意味だ?」
「何故あわいは町そのものを飲み込む事はなかったのかと思ったのです」
「町そのもの……」
沈の国は京師紫沈、水王領北玄海、木王領山芒、金王領東江、火王領雲朱の五つの領地からなり、各領地間に他に町や村どころか小さな集落すらない。あわいは各領地の周辺を脅かしたものの、例えば汀彩城を丸ごと飲み込んでしまうような事はなかったおかげで、どこかの領地が地図から消えてしまうなんて事は起きなかった。
「陛下、私は教練房で学んでいた頃こんな風に教わりました。地脈豊かな土地はあわいを寄せ付けず、民の暮らしを守ったと」
「俺とて同じだ。それは七十年間、沈人にとって常識だ」
「では岳川は? 岳川中流から下流にかけては地脈豊かな土地ではないのですか? 上流はあわいの被害が無かったのに」
戊陽は言葉が出てこないようで、地図を見つめたまま口を閉ざした。
于雨は言わなかっただろうか。地脈が「溢れている」と。それは地面が陥没する事故に繋がった、地下水の事を言っていたのではないだろうか。山芒から休まず急げば丸二日で紫沈に来る事が可能で、戊陽のもとに急使が来た頃にはまだ地下水は川へ向かって流れ出していた可能性がある。
于雨が感じた「溢れる」という感覚は、地表に溢れ出した地下水が原因だったとしたら──。
地下水が川に流れ出た事で、北のあわいが薄れた可能性が高いのではないだろうか。そしてそれらが北と東によって計画された事なのだとしたら、今後も東は川を増水させるために動き続けるだろうし、北の領地は拡大し続ける事になる。
地脈を含んだ水で大地にはびこるあわいを浄化出来るというその事実を、どうにかこちらでも検証する必要があるだろう。とくれば。
「ひとつ、私から進言させて頂けますか」
「聞こう」
「卜師を」
戊陽の顔付きが変わる。それはたった今まで忘れていたものを思い出したような、はっと閃いた表情だった。
「卜師を探しましょう。そして脈読をさせるのです」
蔵書楼を出る頃には日が随分傾いており、戊陽とまたしても馬車へ相乗りする事になった。
黄麟宮へ着く頃には空のほとんどが濃紺に覆われて、急いで宿舎へ戻ろうとしたが戊陽がそれを引き止めた。
後ろ手に掴まれた手にはさほど力は入っていない。少しの力でふり解けそうだ。弱いながらも戊陽の主張が混じったそれは玲馨に選べと言っているようで、玲馨は戊陽から視線を逸らした。
『今夜、黄麟宮に来い』
戊陽がああ言ったのは紛れもなく玲馨が焚き付けたからだ。
自分で自分の言葉を覆したくはない。約束ほど固いものではなく、引っ張れば解けてしまう蝶結びのように浅く交わした言葉ではあったが、だからこそその内実は決して適当に扱って良いものではないと玲馨も心得ている。
だけど、と玲馨は狡い事を考える。戊陽はこうも言っていた。待てる間は待つと。
ならば今は目先の事を優先したい。懸案事項を抱えたまま、黄麟宮で夜を過ごしたくなかった。
「陛下」
どう言葉を組み立てたところで全部言い訳にしかならないと思うとその先が続かない。迷っていると、戊陽の方から手を放してくれた。
「爺になるまでは待てない」
拗ねたような口調に、玲馨の頬が緩んでいく。知らずと入っていた肩の力も抜けて、玲馨は改めて戊陽を振り返ると、丁寧に拱手した。
「私は陛下の宦官です。必ずあなたのもとへ、帰ってきます」
これは忠誠? 親愛?
戊陽と出会ったあの日に生まれ、すくすく育ってきた自分の中にあるものに、玲馨は名前をつけられないでいる。そのせいか戊陽から向けられるものの正体も確かな事は分からない。ただとにかく、戊陽という人間を脅かすものから彼を守るだけだ。
黄麟宮で帆のついた手燭を借りて急ぎ宦官の宿舎に戻る。
予感というほど強くはないが、昼間に于雨の姿が見えなかった事が後になってどうしても気になり始めていた。
軽く汗を額に滲ませながらひっそりと静まる宿舎へ入る。時刻は亥の刻には少し早いくらいだ。この時間まで仕事をしている事はまずないので、戻ってきていなければ疑わなくてはならない。
些か乱暴な手付きで扉を開けるが灯りがついていない。于雨は大抵この時間まで起きて机に向かっている。そのうちの半分は机に伏せて眠ってしまっている事も多いが、その場合は灯りが点いたままなのだ。
衝立の向こうの于雨の寝台も確かめたが、案の定空っぽだった。
焦りが募る。嫌な感覚が玲馨の足元からじわじわと這い上がってくる。
既に休んでいる者も居るため、玲馨は自身の立てる音に注意を払いつつもまだ起きて活動している人を探した。
二人部屋が並んだ廊下を行くと一部屋だけまだ灯りが消されていないのを見つけて一瞬喜びかけた玲馨だったが、その部屋の主を思い出してすぐさま足を止めた。
玲馨は顔にも態度にも出さなくなったが、宦官の中に未だに恐れている男がいる。ここはその男の部屋だ。そして、玲馨より先に于雨と二人部屋で生活するはずだった男でもある。
或いは彼なら于雨の行方を知っているかも知れない。彼は現在、少年宦官たちの浄身について医者と連携して日程を組む立場にある。思えば玲馨の浄身が決まった頃には既に彼はそちらに対して顔が利くようだった。その後数年すると正式にその仕事を別の宦官から引き継いでいた。
声を掛けようとして、喉の奥が途端に詰まった。ひゅっと空気を変な風に吸い込んで勢い余って噎せてしまう。しまったと思うより早く扉は中から開いて、彼が出てきた。
「……お前か、玲馨」
永参は、酷く忌々しいものを見る目で玲馨を見上げた。
この目だ。この粘土で捏ねたみたいに光を通さない黒目がちな目が、玲馨から時間の流れを奪って少年だったあの頃に戻してしまう。
「お手間は取らせません。少々訊きたい事があって参りました」
この段になって用事が無いフリをするのはまずかった。永参は非常に疑り深い性格で且つ歪んだ執着心を持っている。そんな永参から玲馨は于雨を半ば奪うようにして部屋を変えさせたという経緯があった。永参は玲馨が手を回して于雨の部屋替えを行った事を知らないはずだが、古株の永参は宦官の中でもそれなりの力を持っているのでどこかで真相を知った可能性は非常に高い。
ここで引き返せば玲馨に後ろめたい事があると永参は勘繰るだろう。それは避けたい。于雨を取り戻されるのも困る。
逃げられないとくれば、後はこの男と向き合う他に余地はなかった。
「ここ半月ほどの間に浄身を行った者を教えて頂けませんか」
凹凸が少なくのっぺりとした顔に訝る色が浮かび上がる。
「……何を探っている?」
「何も。同室者が戻らないので心配しておりました」
「教える義理がないな」
「っ……」
永参は確かに色々と歪な人間だ。だが一度手放した少年にはさほど執着する事はなく、手放す頃には次に慰み者にするのに丁度よい少年へと目星をつけている。だが玲馨だけは違った。永参は玲馨の事だけは今もすれ違うたびに憎くてたまらないような目をする。
玲馨は自分でも本来の年齢が分からない。だが公にしている年齢より下という事はないだろう。それが災いしたのが、永参に玲馨の精通を知られた事だった。
手篭めにした少年が大人になっていく。永参にとって、それはきっと酷い裏切りなのだ。
子供の頃からずっと憎まれ続けてきて、いっときは賢妃の宮で過ごしたおかげで彼を忘れていられたが、小杰付きになり黄麟宮で過ごす訳にはいかなくなると、またこの男の呪い殺さんばかりの視線を浴びせられる日々に戻った。
それでも昔ほど頻繁に顔を合わせる訳ではない。すれ違うのは大抵日の高い日中で、他にも人が居る事がほとんどだ。だから平気なフリをしていられたが、日の落ちた夜半、人気のない薄暗い廊下は、永参の部屋で過ごした二年半ばかりの景色を否が応にも連想させられた。
「……男の物を噛み千切るようなじゃじゃ馬を、いっときでも僕の部屋に置いていたかと思うと寒気がする」
永参は玲馨が何も言わなくなったので捨て台詞を残して部屋へ戻っていく。静かな音を立てて目の前の扉が閉まるまで、玲馨は身動ぐ事も出来なかった。
永参が一体何の事を話していたのか分からなかったが、やがて約十年前に自分が武官に襲われた事を思い出した。
瞬間、怖じ気と共に怒りが湧いた。筋骨隆々とした兵士に口淫させられたそもそもの原因は、戊陽が玲馨を癒やし床に臥した事を何故か兵士が知っていた事だった。先の永参の言葉を思うに、情報を流したのは十中八九彼だ。ともすれば猿猿の手紙を届ける事を口実に姿を見せた事さえ計算で、兵士に玲馨を陵辱させたかったのかも知れない。
今更気付かされた事実に怒りのまま叫びたい衝動に駆られたが、拳を握りしめて堪えた。
寝付けないという理由で疲労を押して黄麟宮から蔵書楼へと行き、夜になって宿舎に戻っても于雨の事が気がかりで──或いは恐怖のせいで──結局まんじりともせず夜明けを迎えた。外が白み始めるより早く起き出して、手早く支度を済ませる。
朝は黄麟宮へは行かずに直接外廷へと足を運び、それから朝議の間中は戊陽の傍に控えていなくてはならない。その後は東妃宮へと向かわなくてはならないので、どこで于雨の様子を見に行くべきかを決めあぐねる。
于雨はほとんと間違いなく浄身のために宿舎から出ているのだろう。という事はあの病室へ行けば会えるはずだが。
他の宦官に訊きたくとも、玲馨は外廷に向かう事情から他の宦官たちより基本的に動き出しが早く、宿舎から出るまで誰とも出会わなかった。日によっては一人二人、厠に起きてきたりするのだが、こういう時に限って誰とも会わないものである。
「顔色が優れぬな」
玲馨より少し遅れて玉座までやってきた戊陽が眉を顰めた。
「申し訳御座いません陛下」
戊陽は責めたつもりはないし、それを玲馨も理解しているがここが外廷である以上人目があるのでこう答えるしかない。言い換えたとしても「お見苦しいものを失礼致しました」となるだけだ。
「その顔は解決しておらぬ顔だな」
「陛下のお心を煩わせるほどの事では御座いません」
玲馨が他人行儀ならぬ宦官行儀過ぎる態度を取ると戊陽は決まって退屈そうな顔をする。恐らく本人にその自覚はない。玉座の斜め後ろに控えているので横顔が辛うじて見える程度だが、瞼が半分閉じたのが分かった。
「……四郎を呼べ」
「はい……?」
「今日は下がると良い」
「……陛下のご厚情に感謝致します」
恐らく戊陽は休めと言っているのだろうが、玲馨は四郎と入れ替わりに出ていくと、その足で病棟へと向かった。
つかつかと足音を鳴らし早歩きに移動しながら玲馨はそう言えばと四郎の事が気になった。昨日、戊陽と共に蔵書楼へ行った時には四郎の姿が見当たらなかった。常日頃、戊陽の影のように侍る彼にしては珍しい事だ。
恬淡とした彼の事なのでどうも私用とは思えないが、かと言って四郎という人を知らなさ過ぎて何が理由か全く見当がつかない。今日見たところ不調といった様子でもなかったのでたまたまか、或いは山芒から戻ってすぐだからと戊陽が無理矢理にでも休養を取らせたか。
あれこれと四郎について思考を巡らせているうちに、相も変わらず古ぼけて薄汚れた浄身のためだけの病棟が見えてきて、玲馨は辟易とした気分になった。
玲馨がここで生死を彷徨ったのも衛生面の管理不足が原因だった。それを改善すべく戊陽が皇帝となってから建て替えの話が出たはずだが予算で揉めて放り出されたままになっている。
今や宦官は後宮にとっては不可欠で、宦官がなくなれば後宮はあっという間に立ち行かなくなるだろう。戊陽の妃たちを入宮させるとなれば尚更だ。だがそんな宦官の命を気に留める官吏は少ない。貴族には宦官が必要ないからだ。
かと思えば東妃と小杰を少しでも早く後宮から追い出そうと躍起になっている。
蔑ろにされる宦官と、同じく蔑ろにされる東妃たちは矛盾すると玲馨は思う。つまり皇帝に阿ろうとすれば東妃たちを追い出そうと画策し、逆に皇帝が邪魔だと思えば皇帝の力となる宦官を排除したがる事になる。
宮廷は沈という国の性質上もともと四つに勢力が別れているが、今は大きく二つに纏まろうとしているのではないだろうか。皇帝に取り入ろうとする勢力と、皇帝を追い出そうとする勢力と。それは、大きな政争へと発展する凶兆だ。
恐ろしい想像をしてしまって、玲馨の背中を薄ら寒いものが駆け上がっていった。
今考えても仕方ない事を頭から追い出して、医者の格好をした男に于雨の部屋を訊ねて奥へ進む。宦官なら誰しもここに良い思い出はないだろうが死にかけた玲馨は一入だ。
病棟に入った瞬間から感じていた独特の臭気が病室に入ると一気に増す。採光用の窓がない薄暗い室内に寝かされた于雨を見つけ、玲馨はそっと傍に寄った。
採光用の窓がないのはここが嘗て罪人の宮刑のためだけに作られたものだったからだ。自宮という言葉が生まれるまで、ここは刑場だった。
「……っ?」
于雨は人の気配に敏く、玲馨が近付くと目を覚ましてしまった。申し訳ない事をしたと思いつつ、額に浮いていた汗を手巾で拭ってやる。
「よく頑張ったな于雨」
辛そうな顔付きではあるが、額や頬、首の辺りに触っても自分の時のように発熱はない。ただ痛みはまだまだ引かないようで、体を動かそうとして于雨が声も無く悲鳴を上げた。
「無理をするな。まさか拱手しようとしたのか?」
こ、く、と首がゆっくり縦に振られて、その健気さに身につまされる。
大人の言い付けを愚直に守る于雨を見て、昔の玲馨もこんな風に見えていたのだろうかと何とも言えない気分になる。
「于雨、自分を大切にしろ。今お前は大怪我をしたのと同じ状態だ。そんな時に無理をしてはいけない」
またゆっくりと于雨が頷くが、本当に分かっているのか不安になる。しかし今の于雨に対して懇々と言って聞かせるのはかえって彼に無理をさせるだろう。とにかく無事を確認出来たので戻ろうと踵を返すと于雨が掠れた声で「先輩」と玲馨を呼んだ。
「どうした?」
「知らない宦官が、来ました」
「宦官? ここにか?」
「はい」
知らない、という事は黄麟宮か東妃宮付きの宦官か、または下級宦官だろう。しかし一体誰が、どんな目的で于雨の所へ?
「訊かれました」
「何と」
「お前は卜師か、と」
雷に打たれたような衝撃が走る。
「……それで、お前は何と答えたんだ?」
辛うじて言葉を継いだ。
「知りませんと」
「そうか……」
一言一言喋るごとに于雨が辛そうに顔を歪める。見ていてこちらまで苦しくなる表情だが、あとひとつどうしても訊いておかねばならない事があった。
「それはどんな宦官だった? 顔や身長や、歳でもいい」
今于雨に無理をさせれば命に関わるが、于雨に脈読の力があると知られても結果は同じなのだ。どちらも防がなくてはならない。
「年上の、顔が変わらない……後、石を、持っていました」
「石……?」
于雨はそれだけ伝えるとぐったりと目を閉じてしまう。目の下や瞼が血色の悪い色をしているので、浄身してからあまり眠れていないのだろう。無理もない。
「よく教えてくれた。ゆっくり休みなさい」
一ヶ月経てば玲馨が同室者として于雨を看病してやれる。つきっきりとはいかないのでもちろん他の宦官と協力してだが、夜は専ら玲馨が面倒を見る事になる。それが于雨のためになるとまで自惚れてはいないが、誰が寝ていたかも分からない薄気味悪い病室よりは宿舎の方が于雨も気が休まるというもの。
玲馨は于雨を訪ねてきたという宦官の事を考えながら部屋を出ていく。
年上というのはきっと玲馨よりも上に見えたという事だろう。
顔が変わらないと言われた時永参が頭を過ぎってゾッとした。于雨は永参に手を出される前に玲馨が引き取ったので、于雨への未練があっても不思議ではない。だが永参は浄身してしまった少年には悉く愛想を尽かすようで、于雨も例にもれず途端に冷たく接するようになった。中には永参に懐いていた少年も居たので浄身後の永参の態度に戸惑う子を見た事がある。第一、于雨は永参のことを知っている。
永参ではない。だとすると、今のところ他に思い付く候補はなかった。
石とは何のことか。それが分かれば、何か見えてくるような気がするのだが。
*
玲馨が于雨を見舞っていた頃、朝議の場はいつになく張り詰めていた。戊陽は自分が紫沈を離れていた間に何かあったのかと思ったが、官吏たちの視線がある勢力に集中している事に気付き戊陽が山芒に発ったからこその空気だと察する。向青倫が皇帝を味方に引き込んだのではないかと皆戊陽と向側の出方をうかがっているのだ。
上奏を聞きながらそのほとんどを良きに計らえと流していく中に後宮の話が混ざってこない。戊陽が止めたところで手を変え品を変え後宮の話を持ち出すのだろうと思っていただけに、案に相違して肩透かしを食らった気分だ。
やがて話は当然、先日の山芒での事故に発展していく。これについては李将軍が諸侯に向けて報告した。
現場の事故の規模、怪我人たちの救出状況や、国境の警備。最後、警備については禁軍から派兵しなくてはならない事を述べて李将軍の話は終わる。
各省各部から長官のみならず次官までもががん首を揃えているというのに、しん、と耳に痛いほどの静寂が下りる。次に誰が発言するか互いに見計らっている時の独特の空気が流れていた。
戊陽は小さく嘆息すると、笏を持ち換えた。右手で笏を官吏たちに向けて指す。
「李将軍の申した事が、今日のそなたらの本命であろう。そうして他人の顔色ばかり見ておらずにはっきりと口にせよ」
気まずそうに顔を下げる者、近くの者と目を合わせる者、何を探っているのか左見右見して落ち着きがなくなる者など様々だったが、口を開く者は一人たりとて出てこない。
「ならば私が話そう。──後宮に妃を迎える」
とうとう痺れを切らした戊陽が自ら事の次第を告げると、官吏たちの探るようだった気配が一斉に膨れ上がって戊陽へと圧し掛かってくる。
「無論、小杰が宮を移した後だ」
相手は一体どこの公主なのか。
全員の興味がある一点に集中した時、一人の男が「失礼ながら」と粛々と声を出した。男が話そうとすると、更に隣の男が手で制して代わりに話し始める。彼らが一目に主従の関係である事が分かった。
そして彼らの正体とは──。
「生家より文が届いております。入宮が決まった妃とは、我が妹の向峰公主の事で御座いますね、陛下」
「そうだ」
戊陽が男の言葉を肯定するとあちこちから様々な思惑の籠った息が漏れた。
ざわめきの中、戊陽は男の姿を見つめてそうきたかと思う。
彼は向家長男の向亗だ。最初に断りを入れたのは向家の親戚筋の者。従者の生家は凱寧の時代より紫沈に屋敷を構えており、当時、凱寧の従姉妹が降嫁されたため戊陽の遠戚でもある。
そんな立場の男たちから向公主の名が出てくれば、自ずと官吏たちはこう思う訳だ。「後見は向家に決めたのか」と。その内実はさておき、傍から見れば向家と皇帝が手を組んだように見えてもおかしくない。
向公主を妃にすると決めた以上こうなる事は想定済みだったが、想像していた以上に官吏からの視線が突き刺さる。目に見えて以前までより皇帝に対する警戒が強くなった。
妃が一人、入宮する。この事で今後、他の三王たちがどういう行動に出るか、戊陽はこれまで以上に皇帝として官吏たちを見張っていかなくてはならない。可能なら内実共に向と協調出来れば心強いが、恐らく向青倫と戊陽の見据える沈という国の形には隔たりがある。話はそう簡単には進んでくれないだろう。
「妃の話はまだ当分先の事だ。これよりは、諸侯らに対し糺さねばならない事がある。北玄海と山芒の刺史についてな」
どこか色めくようでもあった空気は一瞬で萎み、一部の者たちが顔から血の気を引かせていくのが見えた。
即位してからのこの二年、右も左も分からないままただ座らされてきた玉座から見える景色が、じわりじわりと変わっていく。見えなかったものが明るみになり、意味や形がはっきりとしていく。きっかけを作ったのは北玄海と山芒に違いないが、それを暴いたのは間違いなく玲馨だ。玲馨のおかげで向青倫の思惑のままに動く傀儡にならずに済んでいる。
そんなつもりで傍に置いた訳ではなかったのに、今頃玲馨が居なければ自分の治世はどうなっていたか分からないと思うと空恐ろしくなる。不慮の玉座に振り回された二年間でとっくに心折れて投げ出していたかもしれない。
玲馨──。
初めは、ただ会話が出来れば良かった。友が欲しかった。そのうちその気持ちは少しずつ変化したものの、ただ傍に居て欲しいという気持ちだけは今の今になっても変わらなかった。
しかし玲馨はそれでは満足出来ないのだと気付いた時、戊陽は玲馨を少しだけ手放す事に決めた。玲馨の望む物が何かは知らない。だけどそれを掴むまでは待っていようと決めた。
戊陽は玉座から見える官吏たちの顔をひとつひとつつぶさに観察し、全員の名前が頭の中に浮かんでくる事を確かめる。議題ごとに誰がどんな表情をしているか、議事録には記録されない戊陽の目で見て得た情報を心に留めていく。
戊陽の声で懐かしくて初々しい思い出から意識が戻ってくる。「これを見ろ」という声に呼ばれて棚の向こう、戊陽の居る方へと回り込む。
戊陽が出してきた地図は三尺四方の軍議で使うような大きな地図だった。四つの都市と中央の紫沈とが紙ではなく麻の布に墨で書かれており所々滲んでしまっている。古い物のようで全体的に黄ばんでいて、長らく折りたたまれていたせいで折り目がくっきりとついてしまっていた。
禁書室から出てきたその地図は一般に見る地図とは様子が異なっている。
「この朱墨はあわい……?」
「恐らくな。今俺たちが使う地図と発生域が少し違っているような気がするが、小規模な地脈の変動が起きているのかも知れない」
禁書室には机がないので床に広げた地図を二人で見下ろす。
朱墨と思われる赤い墨は水で薄く溶いているようで、まるで染みのように沈全体のあちこちに滲んでいる。濃淡もまばらなら、濃い赤い線で円状に囲ってある所も見受けられる。
もしこの濃淡が意図して分けられているのだとしたら、濃い所が地脈の濃い所で、薄い所はその逆という事だろうか。または濃い所はあわいが濃い所かもしれない。
凱寧はあわいの発生の前年に卜師を徹底して排除したので、この地図は実地で川や植物や妖魔の出没状況を調査して地図に記していったはず。それを裏付けるのは南に連なる険峻な山脈だ。
山芒から南部に伸びている山脈は人の足で踏み入れないほど険しい。川によって大きく削られた渓谷など危険な場所が多く、天候の変わりやすさがそれに拍車をかける。山々を越えた先には他の国が築かれていると言われているが、沈の長い歴史の中で南から他国が侵略してきたり、或いは雲朱より南から来た人間というものが現れた事は一度もない。つまりただでさえ人を寄せ付けない山だったのが、あわいによってついに完全な人跡未踏となった訳だ。
その山脈付近は地図上では朱墨が一切塗られておらず真っ白になっている。山に人が立ち入れないからだ。しかし実際には春を迎えても遠目に山肌が茶色く枯れたままなので、現代では南の山脈にもあわいが発生しているとされる。
事前に持ってきておいた現代の地図を隣に並べると、あわいの区域は格段に広がっているのが分かる。後年になるにつれて調査が進んでいったのだろう。
恐らくはあわいが発生して間もない頃に描かれただろう古い地図を見ていると、玲馨はある事が気になった。
「主要な河川は、当時から無事だったのですね」
「そうだな」
地脈変動で沈が多くの犠牲を出しても国としての体裁が保たれたのは、川があわいに飲み込まれなかった事が最たる要因だ。
岳川他、一部の河川はあわいを流れているが、生活用水に使われる各都市の主要河川は、濁らず今も人に恵みを与え続けている。
「偶然、なんでしょうか……」
「どういう意味だ?」
「何故あわいは町そのものを飲み込む事はなかったのかと思ったのです」
「町そのもの……」
沈の国は京師紫沈、水王領北玄海、木王領山芒、金王領東江、火王領雲朱の五つの領地からなり、各領地間に他に町や村どころか小さな集落すらない。あわいは各領地の周辺を脅かしたものの、例えば汀彩城を丸ごと飲み込んでしまうような事はなかったおかげで、どこかの領地が地図から消えてしまうなんて事は起きなかった。
「陛下、私は教練房で学んでいた頃こんな風に教わりました。地脈豊かな土地はあわいを寄せ付けず、民の暮らしを守ったと」
「俺とて同じだ。それは七十年間、沈人にとって常識だ」
「では岳川は? 岳川中流から下流にかけては地脈豊かな土地ではないのですか? 上流はあわいの被害が無かったのに」
戊陽は言葉が出てこないようで、地図を見つめたまま口を閉ざした。
于雨は言わなかっただろうか。地脈が「溢れている」と。それは地面が陥没する事故に繋がった、地下水の事を言っていたのではないだろうか。山芒から休まず急げば丸二日で紫沈に来る事が可能で、戊陽のもとに急使が来た頃にはまだ地下水は川へ向かって流れ出していた可能性がある。
于雨が感じた「溢れる」という感覚は、地表に溢れ出した地下水が原因だったとしたら──。
地下水が川に流れ出た事で、北のあわいが薄れた可能性が高いのではないだろうか。そしてそれらが北と東によって計画された事なのだとしたら、今後も東は川を増水させるために動き続けるだろうし、北の領地は拡大し続ける事になる。
地脈を含んだ水で大地にはびこるあわいを浄化出来るというその事実を、どうにかこちらでも検証する必要があるだろう。とくれば。
「ひとつ、私から進言させて頂けますか」
「聞こう」
「卜師を」
戊陽の顔付きが変わる。それはたった今まで忘れていたものを思い出したような、はっと閃いた表情だった。
「卜師を探しましょう。そして脈読をさせるのです」
蔵書楼を出る頃には日が随分傾いており、戊陽とまたしても馬車へ相乗りする事になった。
黄麟宮へ着く頃には空のほとんどが濃紺に覆われて、急いで宿舎へ戻ろうとしたが戊陽がそれを引き止めた。
後ろ手に掴まれた手にはさほど力は入っていない。少しの力でふり解けそうだ。弱いながらも戊陽の主張が混じったそれは玲馨に選べと言っているようで、玲馨は戊陽から視線を逸らした。
『今夜、黄麟宮に来い』
戊陽がああ言ったのは紛れもなく玲馨が焚き付けたからだ。
自分で自分の言葉を覆したくはない。約束ほど固いものではなく、引っ張れば解けてしまう蝶結びのように浅く交わした言葉ではあったが、だからこそその内実は決して適当に扱って良いものではないと玲馨も心得ている。
だけど、と玲馨は狡い事を考える。戊陽はこうも言っていた。待てる間は待つと。
ならば今は目先の事を優先したい。懸案事項を抱えたまま、黄麟宮で夜を過ごしたくなかった。
「陛下」
どう言葉を組み立てたところで全部言い訳にしかならないと思うとその先が続かない。迷っていると、戊陽の方から手を放してくれた。
「爺になるまでは待てない」
拗ねたような口調に、玲馨の頬が緩んでいく。知らずと入っていた肩の力も抜けて、玲馨は改めて戊陽を振り返ると、丁寧に拱手した。
「私は陛下の宦官です。必ずあなたのもとへ、帰ってきます」
これは忠誠? 親愛?
戊陽と出会ったあの日に生まれ、すくすく育ってきた自分の中にあるものに、玲馨は名前をつけられないでいる。そのせいか戊陽から向けられるものの正体も確かな事は分からない。ただとにかく、戊陽という人間を脅かすものから彼を守るだけだ。
黄麟宮で帆のついた手燭を借りて急ぎ宦官の宿舎に戻る。
予感というほど強くはないが、昼間に于雨の姿が見えなかった事が後になってどうしても気になり始めていた。
軽く汗を額に滲ませながらひっそりと静まる宿舎へ入る。時刻は亥の刻には少し早いくらいだ。この時間まで仕事をしている事はまずないので、戻ってきていなければ疑わなくてはならない。
些か乱暴な手付きで扉を開けるが灯りがついていない。于雨は大抵この時間まで起きて机に向かっている。そのうちの半分は机に伏せて眠ってしまっている事も多いが、その場合は灯りが点いたままなのだ。
衝立の向こうの于雨の寝台も確かめたが、案の定空っぽだった。
焦りが募る。嫌な感覚が玲馨の足元からじわじわと這い上がってくる。
既に休んでいる者も居るため、玲馨は自身の立てる音に注意を払いつつもまだ起きて活動している人を探した。
二人部屋が並んだ廊下を行くと一部屋だけまだ灯りが消されていないのを見つけて一瞬喜びかけた玲馨だったが、その部屋の主を思い出してすぐさま足を止めた。
玲馨は顔にも態度にも出さなくなったが、宦官の中に未だに恐れている男がいる。ここはその男の部屋だ。そして、玲馨より先に于雨と二人部屋で生活するはずだった男でもある。
或いは彼なら于雨の行方を知っているかも知れない。彼は現在、少年宦官たちの浄身について医者と連携して日程を組む立場にある。思えば玲馨の浄身が決まった頃には既に彼はそちらに対して顔が利くようだった。その後数年すると正式にその仕事を別の宦官から引き継いでいた。
声を掛けようとして、喉の奥が途端に詰まった。ひゅっと空気を変な風に吸い込んで勢い余って噎せてしまう。しまったと思うより早く扉は中から開いて、彼が出てきた。
「……お前か、玲馨」
永参は、酷く忌々しいものを見る目で玲馨を見上げた。
この目だ。この粘土で捏ねたみたいに光を通さない黒目がちな目が、玲馨から時間の流れを奪って少年だったあの頃に戻してしまう。
「お手間は取らせません。少々訊きたい事があって参りました」
この段になって用事が無いフリをするのはまずかった。永参は非常に疑り深い性格で且つ歪んだ執着心を持っている。そんな永参から玲馨は于雨を半ば奪うようにして部屋を変えさせたという経緯があった。永参は玲馨が手を回して于雨の部屋替えを行った事を知らないはずだが、古株の永参は宦官の中でもそれなりの力を持っているのでどこかで真相を知った可能性は非常に高い。
ここで引き返せば玲馨に後ろめたい事があると永参は勘繰るだろう。それは避けたい。于雨を取り戻されるのも困る。
逃げられないとくれば、後はこの男と向き合う他に余地はなかった。
「ここ半月ほどの間に浄身を行った者を教えて頂けませんか」
凹凸が少なくのっぺりとした顔に訝る色が浮かび上がる。
「……何を探っている?」
「何も。同室者が戻らないので心配しておりました」
「教える義理がないな」
「っ……」
永参は確かに色々と歪な人間だ。だが一度手放した少年にはさほど執着する事はなく、手放す頃には次に慰み者にするのに丁度よい少年へと目星をつけている。だが玲馨だけは違った。永参は玲馨の事だけは今もすれ違うたびに憎くてたまらないような目をする。
玲馨は自分でも本来の年齢が分からない。だが公にしている年齢より下という事はないだろう。それが災いしたのが、永参に玲馨の精通を知られた事だった。
手篭めにした少年が大人になっていく。永参にとって、それはきっと酷い裏切りなのだ。
子供の頃からずっと憎まれ続けてきて、いっときは賢妃の宮で過ごしたおかげで彼を忘れていられたが、小杰付きになり黄麟宮で過ごす訳にはいかなくなると、またこの男の呪い殺さんばかりの視線を浴びせられる日々に戻った。
それでも昔ほど頻繁に顔を合わせる訳ではない。すれ違うのは大抵日の高い日中で、他にも人が居る事がほとんどだ。だから平気なフリをしていられたが、日の落ちた夜半、人気のない薄暗い廊下は、永参の部屋で過ごした二年半ばかりの景色を否が応にも連想させられた。
「……男の物を噛み千切るようなじゃじゃ馬を、いっときでも僕の部屋に置いていたかと思うと寒気がする」
永参は玲馨が何も言わなくなったので捨て台詞を残して部屋へ戻っていく。静かな音を立てて目の前の扉が閉まるまで、玲馨は身動ぐ事も出来なかった。
永参が一体何の事を話していたのか分からなかったが、やがて約十年前に自分が武官に襲われた事を思い出した。
瞬間、怖じ気と共に怒りが湧いた。筋骨隆々とした兵士に口淫させられたそもそもの原因は、戊陽が玲馨を癒やし床に臥した事を何故か兵士が知っていた事だった。先の永参の言葉を思うに、情報を流したのは十中八九彼だ。ともすれば猿猿の手紙を届ける事を口実に姿を見せた事さえ計算で、兵士に玲馨を陵辱させたかったのかも知れない。
今更気付かされた事実に怒りのまま叫びたい衝動に駆られたが、拳を握りしめて堪えた。
寝付けないという理由で疲労を押して黄麟宮から蔵書楼へと行き、夜になって宿舎に戻っても于雨の事が気がかりで──或いは恐怖のせいで──結局まんじりともせず夜明けを迎えた。外が白み始めるより早く起き出して、手早く支度を済ませる。
朝は黄麟宮へは行かずに直接外廷へと足を運び、それから朝議の間中は戊陽の傍に控えていなくてはならない。その後は東妃宮へと向かわなくてはならないので、どこで于雨の様子を見に行くべきかを決めあぐねる。
于雨はほとんと間違いなく浄身のために宿舎から出ているのだろう。という事はあの病室へ行けば会えるはずだが。
他の宦官に訊きたくとも、玲馨は外廷に向かう事情から他の宦官たちより基本的に動き出しが早く、宿舎から出るまで誰とも出会わなかった。日によっては一人二人、厠に起きてきたりするのだが、こういう時に限って誰とも会わないものである。
「顔色が優れぬな」
玲馨より少し遅れて玉座までやってきた戊陽が眉を顰めた。
「申し訳御座いません陛下」
戊陽は責めたつもりはないし、それを玲馨も理解しているがここが外廷である以上人目があるのでこう答えるしかない。言い換えたとしても「お見苦しいものを失礼致しました」となるだけだ。
「その顔は解決しておらぬ顔だな」
「陛下のお心を煩わせるほどの事では御座いません」
玲馨が他人行儀ならぬ宦官行儀過ぎる態度を取ると戊陽は決まって退屈そうな顔をする。恐らく本人にその自覚はない。玉座の斜め後ろに控えているので横顔が辛うじて見える程度だが、瞼が半分閉じたのが分かった。
「……四郎を呼べ」
「はい……?」
「今日は下がると良い」
「……陛下のご厚情に感謝致します」
恐らく戊陽は休めと言っているのだろうが、玲馨は四郎と入れ替わりに出ていくと、その足で病棟へと向かった。
つかつかと足音を鳴らし早歩きに移動しながら玲馨はそう言えばと四郎の事が気になった。昨日、戊陽と共に蔵書楼へ行った時には四郎の姿が見当たらなかった。常日頃、戊陽の影のように侍る彼にしては珍しい事だ。
恬淡とした彼の事なのでどうも私用とは思えないが、かと言って四郎という人を知らなさ過ぎて何が理由か全く見当がつかない。今日見たところ不調といった様子でもなかったのでたまたまか、或いは山芒から戻ってすぐだからと戊陽が無理矢理にでも休養を取らせたか。
あれこれと四郎について思考を巡らせているうちに、相も変わらず古ぼけて薄汚れた浄身のためだけの病棟が見えてきて、玲馨は辟易とした気分になった。
玲馨がここで生死を彷徨ったのも衛生面の管理不足が原因だった。それを改善すべく戊陽が皇帝となってから建て替えの話が出たはずだが予算で揉めて放り出されたままになっている。
今や宦官は後宮にとっては不可欠で、宦官がなくなれば後宮はあっという間に立ち行かなくなるだろう。戊陽の妃たちを入宮させるとなれば尚更だ。だがそんな宦官の命を気に留める官吏は少ない。貴族には宦官が必要ないからだ。
かと思えば東妃と小杰を少しでも早く後宮から追い出そうと躍起になっている。
蔑ろにされる宦官と、同じく蔑ろにされる東妃たちは矛盾すると玲馨は思う。つまり皇帝に阿ろうとすれば東妃たちを追い出そうと画策し、逆に皇帝が邪魔だと思えば皇帝の力となる宦官を排除したがる事になる。
宮廷は沈という国の性質上もともと四つに勢力が別れているが、今は大きく二つに纏まろうとしているのではないだろうか。皇帝に取り入ろうとする勢力と、皇帝を追い出そうとする勢力と。それは、大きな政争へと発展する凶兆だ。
恐ろしい想像をしてしまって、玲馨の背中を薄ら寒いものが駆け上がっていった。
今考えても仕方ない事を頭から追い出して、医者の格好をした男に于雨の部屋を訊ねて奥へ進む。宦官なら誰しもここに良い思い出はないだろうが死にかけた玲馨は一入だ。
病棟に入った瞬間から感じていた独特の臭気が病室に入ると一気に増す。採光用の窓がない薄暗い室内に寝かされた于雨を見つけ、玲馨はそっと傍に寄った。
採光用の窓がないのはここが嘗て罪人の宮刑のためだけに作られたものだったからだ。自宮という言葉が生まれるまで、ここは刑場だった。
「……っ?」
于雨は人の気配に敏く、玲馨が近付くと目を覚ましてしまった。申し訳ない事をしたと思いつつ、額に浮いていた汗を手巾で拭ってやる。
「よく頑張ったな于雨」
辛そうな顔付きではあるが、額や頬、首の辺りに触っても自分の時のように発熱はない。ただ痛みはまだまだ引かないようで、体を動かそうとして于雨が声も無く悲鳴を上げた。
「無理をするな。まさか拱手しようとしたのか?」
こ、く、と首がゆっくり縦に振られて、その健気さに身につまされる。
大人の言い付けを愚直に守る于雨を見て、昔の玲馨もこんな風に見えていたのだろうかと何とも言えない気分になる。
「于雨、自分を大切にしろ。今お前は大怪我をしたのと同じ状態だ。そんな時に無理をしてはいけない」
またゆっくりと于雨が頷くが、本当に分かっているのか不安になる。しかし今の于雨に対して懇々と言って聞かせるのはかえって彼に無理をさせるだろう。とにかく無事を確認出来たので戻ろうと踵を返すと于雨が掠れた声で「先輩」と玲馨を呼んだ。
「どうした?」
「知らない宦官が、来ました」
「宦官? ここにか?」
「はい」
知らない、という事は黄麟宮か東妃宮付きの宦官か、または下級宦官だろう。しかし一体誰が、どんな目的で于雨の所へ?
「訊かれました」
「何と」
「お前は卜師か、と」
雷に打たれたような衝撃が走る。
「……それで、お前は何と答えたんだ?」
辛うじて言葉を継いだ。
「知りませんと」
「そうか……」
一言一言喋るごとに于雨が辛そうに顔を歪める。見ていてこちらまで苦しくなる表情だが、あとひとつどうしても訊いておかねばならない事があった。
「それはどんな宦官だった? 顔や身長や、歳でもいい」
今于雨に無理をさせれば命に関わるが、于雨に脈読の力があると知られても結果は同じなのだ。どちらも防がなくてはならない。
「年上の、顔が変わらない……後、石を、持っていました」
「石……?」
于雨はそれだけ伝えるとぐったりと目を閉じてしまう。目の下や瞼が血色の悪い色をしているので、浄身してからあまり眠れていないのだろう。無理もない。
「よく教えてくれた。ゆっくり休みなさい」
一ヶ月経てば玲馨が同室者として于雨を看病してやれる。つきっきりとはいかないのでもちろん他の宦官と協力してだが、夜は専ら玲馨が面倒を見る事になる。それが于雨のためになるとまで自惚れてはいないが、誰が寝ていたかも分からない薄気味悪い病室よりは宿舎の方が于雨も気が休まるというもの。
玲馨は于雨を訪ねてきたという宦官の事を考えながら部屋を出ていく。
年上というのはきっと玲馨よりも上に見えたという事だろう。
顔が変わらないと言われた時永参が頭を過ぎってゾッとした。于雨は永参に手を出される前に玲馨が引き取ったので、于雨への未練があっても不思議ではない。だが永参は浄身してしまった少年には悉く愛想を尽かすようで、于雨も例にもれず途端に冷たく接するようになった。中には永参に懐いていた少年も居たので浄身後の永参の態度に戸惑う子を見た事がある。第一、于雨は永参のことを知っている。
永参ではない。だとすると、今のところ他に思い付く候補はなかった。
石とは何のことか。それが分かれば、何か見えてくるような気がするのだが。
*
玲馨が于雨を見舞っていた頃、朝議の場はいつになく張り詰めていた。戊陽は自分が紫沈を離れていた間に何かあったのかと思ったが、官吏たちの視線がある勢力に集中している事に気付き戊陽が山芒に発ったからこその空気だと察する。向青倫が皇帝を味方に引き込んだのではないかと皆戊陽と向側の出方をうかがっているのだ。
上奏を聞きながらそのほとんどを良きに計らえと流していく中に後宮の話が混ざってこない。戊陽が止めたところで手を変え品を変え後宮の話を持ち出すのだろうと思っていただけに、案に相違して肩透かしを食らった気分だ。
やがて話は当然、先日の山芒での事故に発展していく。これについては李将軍が諸侯に向けて報告した。
現場の事故の規模、怪我人たちの救出状況や、国境の警備。最後、警備については禁軍から派兵しなくてはならない事を述べて李将軍の話は終わる。
各省各部から長官のみならず次官までもががん首を揃えているというのに、しん、と耳に痛いほどの静寂が下りる。次に誰が発言するか互いに見計らっている時の独特の空気が流れていた。
戊陽は小さく嘆息すると、笏を持ち換えた。右手で笏を官吏たちに向けて指す。
「李将軍の申した事が、今日のそなたらの本命であろう。そうして他人の顔色ばかり見ておらずにはっきりと口にせよ」
気まずそうに顔を下げる者、近くの者と目を合わせる者、何を探っているのか左見右見して落ち着きがなくなる者など様々だったが、口を開く者は一人たりとて出てこない。
「ならば私が話そう。──後宮に妃を迎える」
とうとう痺れを切らした戊陽が自ら事の次第を告げると、官吏たちの探るようだった気配が一斉に膨れ上がって戊陽へと圧し掛かってくる。
「無論、小杰が宮を移した後だ」
相手は一体どこの公主なのか。
全員の興味がある一点に集中した時、一人の男が「失礼ながら」と粛々と声を出した。男が話そうとすると、更に隣の男が手で制して代わりに話し始める。彼らが一目に主従の関係である事が分かった。
そして彼らの正体とは──。
「生家より文が届いております。入宮が決まった妃とは、我が妹の向峰公主の事で御座いますね、陛下」
「そうだ」
戊陽が男の言葉を肯定するとあちこちから様々な思惑の籠った息が漏れた。
ざわめきの中、戊陽は男の姿を見つめてそうきたかと思う。
彼は向家長男の向亗だ。最初に断りを入れたのは向家の親戚筋の者。従者の生家は凱寧の時代より紫沈に屋敷を構えており、当時、凱寧の従姉妹が降嫁されたため戊陽の遠戚でもある。
そんな立場の男たちから向公主の名が出てくれば、自ずと官吏たちはこう思う訳だ。「後見は向家に決めたのか」と。その内実はさておき、傍から見れば向家と皇帝が手を組んだように見えてもおかしくない。
向公主を妃にすると決めた以上こうなる事は想定済みだったが、想像していた以上に官吏からの視線が突き刺さる。目に見えて以前までより皇帝に対する警戒が強くなった。
妃が一人、入宮する。この事で今後、他の三王たちがどういう行動に出るか、戊陽はこれまで以上に皇帝として官吏たちを見張っていかなくてはならない。可能なら内実共に向と協調出来れば心強いが、恐らく向青倫と戊陽の見据える沈という国の形には隔たりがある。話はそう簡単には進んでくれないだろう。
「妃の話はまだ当分先の事だ。これよりは、諸侯らに対し糺さねばならない事がある。北玄海と山芒の刺史についてな」
どこか色めくようでもあった空気は一瞬で萎み、一部の者たちが顔から血の気を引かせていくのが見えた。
即位してからのこの二年、右も左も分からないままただ座らされてきた玉座から見える景色が、じわりじわりと変わっていく。見えなかったものが明るみになり、意味や形がはっきりとしていく。きっかけを作ったのは北玄海と山芒に違いないが、それを暴いたのは間違いなく玲馨だ。玲馨のおかげで向青倫の思惑のままに動く傀儡にならずに済んでいる。
そんなつもりで傍に置いた訳ではなかったのに、今頃玲馨が居なければ自分の治世はどうなっていたか分からないと思うと空恐ろしくなる。不慮の玉座に振り回された二年間でとっくに心折れて投げ出していたかもしれない。
玲馨──。
初めは、ただ会話が出来れば良かった。友が欲しかった。そのうちその気持ちは少しずつ変化したものの、ただ傍に居て欲しいという気持ちだけは今の今になっても変わらなかった。
しかし玲馨はそれでは満足出来ないのだと気付いた時、戊陽は玲馨を少しだけ手放す事に決めた。玲馨の望む物が何かは知らない。だけどそれを掴むまでは待っていようと決めた。
戊陽は玉座から見える官吏たちの顔をひとつひとつつぶさに観察し、全員の名前が頭の中に浮かんでくる事を確かめる。議題ごとに誰がどんな表情をしているか、議事録には記録されない戊陽の目で見て得た情報を心に留めていく。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
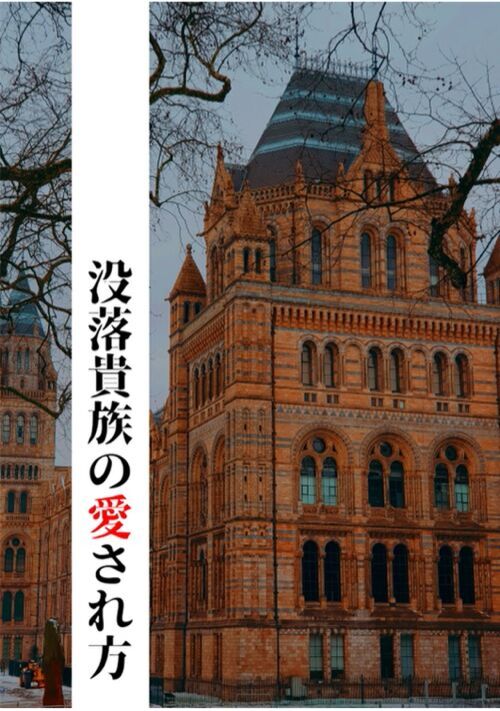
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















