21 / 44
雲朱編
21花一匁
しおりを挟む
室内には沈鬱な空気が流れていた。戊陽は寝台で横たわる枯れ木のような手を握りしめ、もうずっと目を閉じて祈り続けている。
黄雷皇帝の崩御から一ヶ月も経たないうちに、今度は燕太傅が病床に臥した。玲馨は黄昌の名代として見舞った戊陽の供をして、暗く沈んだ部屋の端に四郎と二人で控えている。
燕太傅は何か重篤な病を患った訳ではない。だが今日明日にも峠を迎えるだろうと医者は診断した。
出来れば燕太傅の顔をもう一度間近に見ておきたい。欲を言うなら声を聞きたい。だが宦官程度にそんなわがままが許されるはずもなく、ただ、小さく丸まった主人の背中を遠くに見つめる事しか出来ない。
ちらと横に立つ四郎の顔を見上げるも、彼は普段の様子と何ら変わりない。玲馨は彼が慌てたり取り乱したりする姿を見た事がなかった。それどころか泣きも笑いもしないので、心をどこかに落っことしてきたのだと思っている。そうでなければ、この悲痛な空気の中で眉一つ動かさずに平然と立っている事など出来ないだろう。
外は間もなく正午を過ぎる頃だ。燕太傅の屋敷は汀彩城から少し離れた所にあるので、馬車に乗るとはいえ日のあるうちに城に戻ろうと思うならそろそろ帰途に着かなくてはならない時間帯だ。だが玲馨はとてもではないが今の戊陽に帰ろうなどとは声を掛けられなかった。
戊陽には癒やしの力がある。傷も病もたちまち治してしまう奇跡のような力だが、決して万能ではなかった。
戊陽は燕太傅の屋敷を訪れると真っ先に病を消そうと力を使ったが、彼の父の時と同様に燕太傅の命を延ばしてはくれなかった。致死の傷や不治の病、そして老いていく肉体に対して癒やしの力は無力だった。燕太傅の体は、もはや老いによって今にも活動を終えようとしているのだ。
自分には何も出来る事がないと分かると、戊陽は祈り始めた。それから何時辰が過ぎただろうか。まるで時が止まってしまったかのように、玲馨の目に映る景色に変化は起きない。
燕太傅は生涯妻を娶らず独り身だった。屋敷に数人の侍女を雇い、慎ましやかな生活を送り、彼の不調を報せたのも侍女の書いた書簡だった。半月ほど前に風邪を引き拗らせてしまっていたのだが、まだ意識のあった燕太傅は黄雷の訃報を聞いて葬儀に参列出来なかった事を侘びつつ、侍女には決して燕太傅の状況については報せるなと言い含めてあったそうだ。師の気遣いのおかげで戊陽たち兄弟は父との別れをきちんと済ませる事が出来たのだ。その代わり、玲馨たちは燕太傅の意識があるうちに再会は叶わなくなってしまった。
ふと気が付くと、戊陽と燕太傅を照らしていた窓の明かりが半分ほど影になっていた。本来なら戊陽も父の喪に服して城を出てはならない時期で、帰りが遅くなると良くない噂を招くだろう。ましてこの屋敷で夜を明かす事などあってはならない。
四郎が微動だにしないので玲馨が戊陽に声を掛けようと足を踏み出すと、その肩を掴んで四郎が引き止めた。理由を問おうと振り返ると四郎は玲馨を見ておらず、その目は部屋の奥で横たわる燕太傅に付き添う戊陽を捉えていた。
「燕老師……!」
戊陽が握っていた燕太傅の手が動き、戊陽の後頭部に回るのが玲馨にも見えた。玲馨を引き留めていた四郎の手が離れていく。
「老師、見舞うのが遅くなってしまって、すまなかった」
燕太傅の手は少しの間、子供をあやすように戊陽の頭を撫でてていたがすぐに力を失い下へと下ろされる。戊陽はその手を再び取って、そっと布団の中へと戻した。
それから戊陽は燕太傅の口元に耳を寄せる。玲馨には何かを話している声だけが届きその内容までは聞き取れなかった。だが、最後に一言でも彼らが言葉を交わしあえたおかげか、重たく凝っていた空気は僅かに払拭されていた。
「玲馨」
戊陽が肩越しに振り返った。目の縁が赤い。
こちらへ来いという声に従い寝台の傍に寄ると、目が窪み窶れた姿の燕太傅が目だけで玲馨を見上げた。その細く頼りなげな姿は嘗てのかくしゃくとした老師の見る影もなく、一瞬だけ呆然とした。すぐに手を組み頭を下げると、燕太傅は腕を伸ばし玲馨の組んだ手にそっと手を重ねた。
「殿下、玲馨と二人で話すお時間を頂けますか」
声量こそ落ちているものの、今日明日が山だというのが嘘のようにはっきりとした口調だった。戊陽はすぐに椅子から立ち上がり、入れ替わりに玲馨を椅子へと座らせてから去っていく。
どうして良いか分からずに、玲馨はただとにかく辛うじて熱を宿した燕太傅の手を戊陽がしていたように握りしめる。
「玲馨」と燕太傅が名を呼ぶまでに時間がかかった。
「私はね、殿下にお会い出来た事と同じくらい、お前に私の知識と知恵を教えられた事を誇りに思っているよ」
ツン、と鼻の奥に痛みを感じた。目の縁からじわじわと迫ってくる気配を必死で押し留める。
「心残りがあるとすれば、小杰殿下の師事をお断りした事だ」
「何故断られたのですか?」
「愚拙の歳を考えれば、必然であった。代わりにな、お前の事を話しておいた」
「私の……?」
ぐ、と燕太傅の手に力が籠もり握り返される。それが今出せる全ての力だと思うとあまりに弱々しくて胸の奥を抓られるような痛みが走る。
「西は……。私の若い頃から東江の蘇家は、西方の大国昆と国境を隔て、新しいものを運んできた。よく、見ておきなさい。西方には常に新奇の風が吹く」
すー……、と空気が抜けていくようにして、燕太傅の手から力が消えていく。
「太傅……? 燕太傅!」
玲馨の声を聞きつけた戊陽が駆け寄ってくると、遅れて医者も中へ入ってくる。「眠られたようです」という医者の声をどこか遠くに聞きながら、玲馨は燕太傅の言葉の意味を考えていた。
明朝、燕太傅は眠ったまま息を引き取った。御年七十三の大往生だった。
これは今からおよそ六年ほど前の、玲馨にとって忘れがたい過去の一つだ。
*
「玲馨! これを見ろ!」
場所は東妃宮。間もなく自身を主役にした半元服の儀が迫っているせいかこのところ小杰はすこぶるご機嫌だ。
小杰は玲馨の手を引き跳ねるようにして卓のところまで連れていくと、玲馨を椅子に座らせる。卓には玲馨も昔夢中になった盤上遊戯の棋盤が置いてあった。
「象棋ですね。久しぶりに見ました」
いつ頃だったか、後宮で象棋が大流行した事がある。戊陽が蔵書楼から棋譜を見つけてきたのがきっかけではなかったか。二人で指南書を探し出して駒の動き方から学び、燕太傅にも勉強の息抜きによく教えてもらった。
「今母様に教わっているのだ」
「東妃様が?」
玲馨はちらと奥の部屋へと目を向ける。
「東妃様はどちらへ?」
姿が見えないのでごく自然に出た疑問だったのだが、どうやら踏んではいけないものだったようでせっかくのご機嫌がみるみる下降していく。ふう、と溜息をついた後、いかにも不満ですと言わんばかりに頬杖をついて象棋の駒を指で軽く弾く。
「……東江から新居にとたくさんの衣や装飾品が届いたのだ。お召し替えに夢中になっておられる」
言い終えるとむっと唇を引き結び、駒を棋盤の上に並べ始める。
なるほど道理でと玲馨は納得する。小杰は母に構ってもらえず拗ねていた。
玲馨は駒が入っていたもう一つの箱を手に取り、玲馨側の盤にも円盤型の小さな駒を並べていく。
「やはり玲馨は象棋が打てるのだな」
迷う事なく駒を規定の位置に並べていたので察したらしい。
「東妃様からお聞きになられませんでしたか? 小杰殿下がまだお小さかった頃、後宮で象棋が流行した事があったのです」
「聞いた事ないな。でも玲馨は負け知らずなのだろう?」
「まさか。燕太傅には終ぞ和局にさえさせてもらえませんでした」
「玲馨でも敵わぬのか!」
小杰のそれは買い被りだ。玲馨は苦笑して首を振る。
「私は、せいぜい数年嗜んだ程度でしたから。燕太傅はそれこそお若い頃より代々の皇帝陛下のお相手をなさっていたそうです」
「戊陽兄上も玲馨もよく燕太傅の名を出す。私も一度会ってみたかったな」
「はい……」
駒を並べ終えた段階になって、今更違和感に気付く。昔象棋が流行った頃に使っていた駒の文字の色は、紅と黒ではなかっただろうか。
「こちらの駒も東妃様のご実家からですか?」
「文字の色が違うと思ったのでしょう? それは昆からの舶来品ですよ」
声が聞こえた瞬間玲馨は椅子から立ち上がり、奥の部屋から現れた東妃へと恭しく手を組んだ。
いつになくきらびやかな衣はまさに東妃好みといった意匠で、真っ赤な深衣に彼女の髪とよく似た色合いの金糸の刺繍が目を引いた。
「大変お似合いで御座います、東妃様」
「玲馨、顔をお上げ。どうでしょう、これで一局私の相手をするというのは?」
これと言って東妃は本来なら黒であるはずの青文字の駒を持ち、小杰が並べ間違えていた駒を置き直した。
東妃が玲馨を象棋に誘うその真意は分からない。ほんの戯れか、象棋は口実で何か他にあるのか。いずれにせよ、北玄海から山芒へ続き、その後宮廷のごたごたで小杰付きとしての役目が疎かになってしまっていた以上、玲馨は断れる立場ではない。
東妃が小杰と椅子を替わり正面に座ると、彼女の醸す冷たく尖った空気がいっそう研ぎ澄まされるのが分かった。
玲馨が持つのは本来は紅である茶文字の駒だ。玲馨たちが夢中になった象棋では紅が先手だったが、東妃が初手を指す様子が無いので、玲馨が先に駒を動かしてみる。東妃は何も言わなかったので、玲馨が知っている規則に従って良いらしい。
パチ、パチ、と響く駒の音は耳に心地よく、懐かしいような気分になる。玲馨は戊陽の相手をよくしていたが、初めは絶対に勝ってはいけないと考えてわざと負けていた。しかしそのうち玲馨が手を抜いている事に気付くと戊陽はこう言った。「負けた時の言い訳のためにわざと手加減するんだろう?」それを聞いて尚負けてやれるほど玲馨は大人ではなかったし、本来はとても負けず嫌いなので以降は本気を出して戊陽と対局した。戦績は総合すると戊陽が少しだけ勝り、故意に負けていた対局を数えないと玲馨が勝る。わざと負けたのはほんの数戦なので実力は五分だった。
懐かしい思い出に浸りながら淀みなく打っていた玲馨だったが、不意に手を止め棋盤を見下ろす。突然次の手が頭に浮かんでこなくなったのだ。
「私を侮っていましたね?」
東妃に図星を突かれて言葉に詰まる。始めから程よく負けようと考えていただけに尚更だった。
「申し訳」
「謝罪はいいわ。あなたから聞きたいのはもっと別の言葉ですから」
玲馨の口から聞きたい言葉とは何だろうか。状況を考えたら投了が相応しく思えるが。
「本気でやりなさい、玲馨」
「……はい」
どうも戊陽や玲馨のように負けず嫌いなどが理由ではなさそうだ。闘志と言えば良いか、必死さのようなものが東妃からは感じられない。もっと圧倒的な高みから片手間に駒を動かすような、或いは児戯を片手であしらうような余裕がある。
東妃は強かった。その後も一度はどこかで見た事があるような展開が続くのだが、一手打つ度にどんどん道を潰されていくような感覚が強くなっていく。
打たされている、と気付いたのは対局が終盤に差し掛かった頃だった。途中まで目をキラキラ輝かせて夢中で二人の対局を見ていた小杰が、とっくに飽いて居眠りをしてしまっている。気を利かせた宮女が寝ぼけ眼の小杰を連れて寝台の方へ連れていった。
外でアー、と烏が一声鳴いた時、盤の上は勝敗が決していた。
「……私は、もしや東妃様に勝ちを譲って頂いたのでしょうか?」
沈みゆく夕日に玲馨の腑に落ちない声が滲んでいく。
残局際になって東妃の手はそれまでの猛攻が嘘のように緩んだ。まるで見えていた道が幻だったかのように迷い、手損が増えて、本気を出せと言われたからには玲馨は勝たざるを得なかった。
「私は象棋が嫌いでした。お忙しい父上は、いつも残局まで打たずに『また今度』と言われるのです。それなのに少し時間が出来ると子供と象棋をやりたがった」
「棋譜を残されなかったのですか?」
東妃は緩く首を左右に振る。
「遊びや息抜きのつもりだったのでしょう」
続けて東妃は言う。一度も父に勝てなかったが、一度も負けなかった、と。
「だから私は残局の布局を一つも知りません。指し方が分からないのです」
つまり彼女は父の打った手の模倣だけで象棋をしていたというのだ。途中までのゆっくりとこちらの首を締めていくような圧力の掛け方も実際の打ち手は東妃ではなく彼女の父だったという訳だ。
少し気になった。東妃の父がどんな人だったか。蘇家の公主の父、つまり先代金王は既に亡くなっている。
「父が象棋を好んだのは、象棋には人柄が出るからだそうです。私は父としか打たなかったからその言葉の意味がよく分からなかったけれど、玲馨、あなたと打って少しだけ理解した気がします」
人柄と言われて玲馨はよく対局した戊陽と燕太傅の事を思い浮かべる。
戊陽はこちらのやりたい事を捉えるのが上手かった。それをいなして自分の流れに持っていく事が下手だったが、それは単純に経験が不足しているせいで、玲馨はいずれ戊陽に勝てなくなる日が来るだろうと思っていた。
燕太傅は開局、中局、残局と常に指導するような指し方であらゆる布局を玲馨に学ばせてくれた。師の人柄なるものが現れるほど、玲馨の腕前は燕太傅には及ばなかった。
では東妃はどうだったろうか。
「あなたは、見た目には分からないけれど、とても真っ直ぐな象棋を打つのですね」
東妃は父の受け売りだが、それが彼女の手に残り馴染んだというなら、東妃の気質を構成する一つくらいにはなっているのかも知れない。相手の希望を摘み取るような恐ろしい指し方は、実力差がなければ成立しない気がするので、誰にでもこうとはいかないだろうが。
「私は、捻くれているように見えるということでしょうか?」
つい思った事をそのまま口にしてしまい、玲馨は遅れて自分自身に驚いた。東妃相手にこんなに素直な言葉を返してしまったのは初めてだ。慌てて頭を下げようとするも東妃の密やかな笑い声が聞こえてきて、玲馨の動きが止まる。
「もう少し策略家だと思った、という事よ。それを捻くれていると言うならそうなのかも知れません」
東妃が笑顔を浮かべる事は決して珍しい訳ではない。小杰にはよく笑い掛けているし、若い宮女たちと他愛ない話に花を咲かせては柔和な表情を見せる事もある。
それでもどうしてか貴重なものだと感じるのは、玲馨が自分に向けられた東妃の笑みをほとんど見た事が無かったからだと気付く。
ずっと、東妃と玲馨の間には言葉にし難い緊張感があった。それは宮女にも伝播し、東妃宮付きの宦官たちとも微妙な距離感が出来る原因になっていた。それらが今、期せずして僅かばかり解けていったような気がする。
「玲馨、私は決めました」
東妃はどこか憑き物が落ちたように言う。
「あなたを白蓮宮付きの宦官に出来ないか、陛下に相談します」
もしかして彼女はこの事でずっと悩んでいたのかも知れない。宣言した後の東妃はとても清々しい表情で、象棋を片付け始める。
玲馨は今度こそ「何て勝手な事を」などと言えるはずもなく、どこか浮かれたような東妃を前に、ただ途方に暮れるしかなかった。
*
戊陽にとって果物といえば幼少期から桃で、他には乾燥させた林檎や梨、干し柿などに馴染みがあるが、山芒の果実はどれも見慣れぬ物が多い。そして赤い実のものが多いようで酒に漬かっている物も干して砂糖をまぶした物もどれも赤い実が目についた。名前も分からないそのうちの一つを指で摘んで口の中に入れながら、向青倫が広間に戻ってくるのを待っている。
時は再び戊陽たちが山芒を訪れた頃まで遡る。向青倫の次男で跡取りである向峻が事故の怪我によって数日昏睡していたが、戊陽と練族について話し合っている時に漸く目を覚ましたのがつい今し方の事だ。
玲馨たちを屋敷から去らせた後、戊陽は向青倫との話を早く終わらせ玲馨たちを追いかけようと考えていた。玲馨はしきりに地図を気にしていたので、汀彩城にある沈全域を記した地図を欲しがって紫沈へ帰還すると予想していた。結果、その予想は的中し、この後戊陽は玲馨と共に紫沈への帰還が叶うわけだが。
戊陽がどう理由をつけて向家の屋敷を出ようかと算段していると、戻ってきた向青倫が思わぬ事を言ってきた。
「どうか次男にお会いして頂けませんか、陛下」
命を助けたその礼を言いたいのだと言われると無下には出来ず、戊陽は向青倫に伴われて屋敷の母屋を進む。
客堂で寝泊まりしていた頃はあまり意識していなかったが、改めて屋敷の内装や調度品を見ていると向青倫が古風な物を好むらしい事が分かる。どれも戊陽の目利きでは年代までは判然とせず、とにかく古いという事だけ分かる物ばかりだ。しかし一目に価値のつけられない貴重な物である事は分かる意匠で、それらが品よく飾られている。狸爺という印象に、趣のある男、という印象が足された。
「こちらで御座います」
家主自ら扉を開け中へ誘われると、そこでは寝台から降りて拱手の姿勢で待つ向峻の姿があった。
「よせ。まだ病み上がりであろう。せめて寝台に腰掛けると良い」
「いいえ陛下。此度の事は感謝してもしきれませぬ」
「せっかく拾った命なのだ。無理は許さぬ」
「は……」
向峻が顔を上げると似ていると思った。面差しもだが目付きが似ている。頑固そうな中に狡猾さがうかがえる、一筋縄ではいかせないという雰囲気が目によく表れている。長男の向亗と比較すると、次男が長男を差し置いて跡取りになったと聞かされて納得するだけのものがあった。
向峻が寝台に腰を下ろすと、ついてきていた李将軍がどこからか椅子を引っ張って来たので戊陽も座る。
「私は、意識を失う寸前、もはや今生と別れるしかないのだと諦めておりました」
向峻は膝を手でぎゅっと掴んでいる。その爪が奇形のまま傷が塞がってしまっているのを見つけてしまい、戊陽は瞼を僅かに伏せた。向峻の歪んだ爪は彼が生きたいと必死だった事の証だ。
「目を覚ました時はこの世ではないのだと俄かに現実を信じられなかった私に、侍女が私が助けられた事を話してくれました」
戊陽には一生をかけても返しきれない大恩が出来た。しかし自分は山芒を導く立場にあるため紫沈に行く事は叶わない。
そこまでを訥々と語った向峻は気持ちを改めるようにして顔を上げ、意を決したように続けた。
「陛下、どうぞ私の代わりに妹を後宮に入れて陛下に仕えさせて下さいませんか」
「っ、向峻!!」
一瞬頭の中で言葉の意味を理解する間を挟み、怒号が向青倫から上がる。その顔に、カッと怒りの表情が灯っていた。
戊陽としても向の公主である向峰の事は父親の口から聞かされるだろうと予測していただけに疑問が過る。
「この事を妹御は知っているのか?」
「はい」
「お前たちは、勝手に……」
向青倫から生気のようなものが抜けていく。彼が示すその反応は諦念のように見えた。反対するでもなくだんまりとして向峻が何を話すつもりかうかがっているようだ。
おかしい、とやはり戊陽の中の疑問は消えていかない。向峰は辛新と関係を持っているはずだ。しかし向峰が入宮に関して承知しているとなると、何かの企みがある事を疑わなくてはならなくなる。
どう答えるが良いかしばし黙考した末、戊陽は重い口を開く。
「向峰が承知だと言うなら私に断る理由はない。近く向峰を妃として迎えよう。──それで良いか、向青倫」
戊陽の決断を受けて、向青倫は辛うじて溜息をこぼさないよう堪えるので精一杯という風にやおら目線を下げた。
「……もちろんで御座います。娘も戊陽陛下の妃に迎えて頂けるのなら女としてこれほど幸福な事はありますまい」
「ありがとう御座います陛下!」
感極まったように声を上ずらせる向峻の一方で、父親である向青倫が返すのは切口上。親子の温度差はいかんともしがたいもののようだった。
向の屋敷を出て李将軍と共に玲馨を追いかけていると、李将軍が控えめに「陛下」と声をかけてくる。
「あの場で即決なさってよろしかったので?」
「私が私の妃を選ぶのに、何故他の者の意見を聞かねばならぬ」
「いや、しかしですなぁ。この李孟義、戊陽陛下は、その……妃を迎えるのがお嫌なのだとばかり」
「そうだ。当たっているぞ李孟義」
「では一体何故」
何故も何も政治的に考えれば集権的で向家以外の力を失いつつある貴族の娘を妃にするよりも、山芒において絶対的な支配力を持つ向の娘を妃にして向家を、引いては向青倫とその跡取りである向峻の機嫌を取ったほうが良いに決まっている。
しかし戊陽の目的はそれだけではない。
「向青倫は娘を溺愛しておるのだろうな」
「は。そのようでした」
「だが皇帝と懇意にするため、或いは宮廷を我が物とすべく愛娘を後宮に入れると決めた。練族との戦を見据えながらな」
「……! 陛下、よもや……。いや、ここは皇帝らしくなられたと喜ぶべき場面なのか……?」
言葉を濁した李将軍の困惑を残した独り言は戊陽の耳にも聞こえている。わさわさとした顎髭を撫でる李将軍の表情が険しくなるのも、その心情はよく理解出来た。
戊陽は向峰を手元においてその企みを暴くと共に、向家を抑制する駒に使うつもりだ。人質と言っても良いのかも知れない。これで向青倫は独断でも、或いは北玄海と協力したとしても高原攻めを安易に行えなくなった事になる。向峻の口から妹の名が出た時の向青倫の激昂には焦りも混ざっていたようだった。
戊陽は鬼になるつもりはない。皇帝としてただ沈を安寧に導きたいだけだ。だが回ってきた玉座はその時点で張りぼてで、沈は砂上の楼閣へと零落してゆく最中にあった。多少強引にでも手を施さなくてはやがて反乱を招くだろう。唯々諾々と椅子に座るだけでは、張りぼてと共に最後の沈の皇帝として滅んでいくに違いない。
そうならないためにまず一手、向青倫の娘を妃として迎え山芒に対しての抑止力とした。しかしそれだけではもちろん不足する。高原攻めを終えてから向峰を入宮させれば良いだけの話だ。故にもう一手戊陽は向青倫に対して布石を打たねばならない。
*
時は現在へ戻り、朝議を終えた後、戊陽は黄麟宮へは戻らず離宮である紅桃宮へと向かった。密談を交わすとなるとどうしてもここになってしまう。
戊陽は四郎を軍部へと遣いに出して、彼が目的の人物を連れてくるのを待っていた。
紅桃宮には戊陽が幼少期を過ごした賢妃宮にあった桃の木が全て植え替えられてある。今でも毎年春に多くの花をつけ、夏にはみずみずしい桃の実が生った。
桃の木には戊陽の母である賢妃の様々な思いが込められている。
最初は桃をとても好んだ賢妃のためにと桃の木のある庭へと作り変えられて、花を楽しむためだけのものだった。しかし、桃には子宝に恵まれるための運気をあげてくれる力があると分かると、賢妃は桃を結実させるために躍起になった。
賢妃は黄雷よりも歳が上で、二十歳を優に越えてからの入宮だった。妃となったは良いもののしばらくの間子宝に恵まれず、彼女への風当たりはきつくなっていった。四妃である賢妃は後宮内でも立場が強くなく、更に薹が立った女だったので二妃や三妃に仕えていた宮女たちからは影で笑われていた。
しかしやがて皇帝の次男となる戊陽を出産すると、徐々に賢妃の立場は回復していったという。母は戊陽が産まれる以前の苦悩を戊陽に聞かせる時、必ず桃の何かを傍に置きながら語った。ある時は桃の花弁を茶に浮かべ、ある時は桃の皮を剥きながら、ある時は桃のお香を調香しながら。
桃の香りにはいつも賢妃の記憶が合わさり戊陽の思い出を刺激する。十二を迎える頃にはそこに玲馨の姿が加わった。
「陛下、連れて参りました」
遣いに行かせていた四郎が戻ってくると、その後ろで武官にしては少々小柄な好青年風の若い男が、緊張と警戒の面持ちで抱拳礼をした。
「この辛新、陛下のご用命と聞き参りました」
名を辛新という。山芒で調査する玲馨に付けていた元案内役の武官の青年だ。見た目に随分若いが戊陽と同い年だという。
玲馨に彼を付けさせたのは戊陽の指示だった。
禁軍というのはその兵たちのほとんどが紫沈で生まれ育った貴族の子息たちで構成されている。数少ない地方出身者は紫沈に婿入りでやってきた下級貴族ばかりだ。その中で貴族とはいえ婿に来た訳でもない山芒出身である辛新が軍の中で目立つのは必然だったと言えよう。
辛新の存在はやがて李将軍の耳にも届く事になる。辛新の事情を概ね知っている兵士が禁軍に居た事で李将軍が疑いを強めていたところ、山芒での事故の話から玲馨に話題が及び、玲馨なら辛新の正体も暴けるだろうと踏んで玲馨の案内役を任せる案を思い付いた。結果、玲馨は辛新の事にどれだけ気付いたかは報告がないので分からないが、今となってはこれについて玲馨に問おうとは考えていない。
辛新は向公主、つまり戊陽の後宮に入る事が決まっている向峰と密通した事で、山芒を追い出された不義の男だ。と、戊陽は推測している。そう考える理由は向峰の部屋で深夜に辛新の声を聞いたからというだけなのだが、辛新と向峰が懇ろな仲を隠し通していたなら何も辛新が禁軍の兵士になる必要はなかったろう。
さて、と戊陽は気持ちを改めるようにして、指の先まで固まっていそうな辛新に向き直る。
「辛新、お前は何故武官になった? 禁軍の兵士なら誰しもが出世を望むだろうがお前はまだ若い。苦労して武科挙を受けてまで早く武官になった理由は何故だ?」
こんな事を聞かれるとは予想だにしなかったのだろう、辛新はしどろもどろになりながら「出世のためです」と答えた。
「お前の望む地位はどこだ? 尉官か? 左官? それとも、将軍か?」
将軍と言った時、辛新は弾かれたように顔を上げて小刻みに顔を左右に振った。
「とんでもありません! 私に将軍などとても……」
「ふむ。では今の地位で満足か」
「……いえ」
「望む地位につけるなら、お前はどんな努力も厭わぬか」
辛新の視線が考え込むようにして下を向いたのは一瞬の事で、すぐに力を持った目で戊陽を見返した。
「はい」
戊陽は辛新とはそう多く顔を合わせていない。最初は李将軍が紹介のために連れてきた時で、次は向家の屋敷で玲馨が彼を伴っていた時。直接言葉を交わしたのは今回が初めてだ。
到底辛新の人となりを見抜けるほどの交流は持てていないがこれだけは分かる。この男は馬鹿ではないと。
「辛新、ついて参れ。四郎はここへ残り待つように」
「はい」という二つの返事を聞いて、戊陽は歩きだす。向かうのは四阿だ。
桃の花が全て散ったのでもはや香りが風に乗ってくる事はなくなった。春が終わりに向かうと、紅桃宮は青々と茂る木々に囲まれるだけになり、他に咲く花はない。
戊陽は四阿の椅子に座り、辛新を正面に座らせる。
漏窓から抜けていく風はまだ夏を感じるには早い爽やかな温度を運んでくる。対象的に、辛新が戊陽へと向ける視線は決して穏やかとは言い難い。緊張から固くなった表情に浮かぶ畏怖。更に敢えて言葉にするなら敵愾心のようなものが混じっていた。
「これより先は他言無用である。心しろ」
「はっ……」
辛新は顔に出やすい男だ。若いと一言に言ってしまってもよいが、根が単純なのだろう。だからこそ戊陽は辛新に賭けてみても良いかもしれないと考えた。もし裏切れば、辛新は必ず襤褸を出すと予想したのだ。
「辛新、お前を山芒の刺史に任命したいと考えている」
「は……はい……?」
「お前は卓刺史を捕らえたのだったな」
「はっ、私は玲馨さんに言われて動いていただけですが」
「手柄がどこにあるかの話は本題ではない。山芒の刺史が捕らえられたという事は、山芒の刺史を新たに任命せねばならない。しかし、適当な人材というものはそう簡単に見つかるものではないのだ」
刺史とは令外官といって本来なら皇帝の一任で選べる職位だが、捕まった卓浩の選定に戊陽はおろか黄昌の意思は介在していない。そうでなければ北玄海の刺史と山芒の刺史が従兄弟関係という事態は起きなかったろう。
故にここで戊陽は改めて信の置ける文官を刺史として遣わしたいところなのだが、文官たちの顔を改めて眺めた時、それに値する者が居ない事に気付いた。どこに林勢力の残党が潜んでいるかも分からなければ、或いは桂昭の手の者とも限らない。今となっては後者の方がよっぽど悪い。
概ねどちらにも属さないだろう者を絞れたところで十割の信頼を置ける者など宮廷の文官には見当たらなかった。となると、その外から連れてくる他ないのである。
四郎や玲馨といった幼少から戊陽に仕えていた中でも政治に知見のある宦官をつかせる事も一度は考えたが、沈では宦官の立場があまりに低すぎるのが問題だった。刺史として山芒に赴任しても地方官吏が言う事を聞かないのでは意味がない。
宦官が無理なら最後はもう門外漢である武官から引っ張ってくるしかなかった。だが刺史に適切な人材といってもしばらくは戊陽の頭には誰の顔も浮かぶ事はなかった。
「ですが、私は一介の武官でしかありません。刺史というと文官なのでは……?」
「そも昔は地方軍を束ねる節度使という武官の職位はなかった。刺史が兼ねておったのだ」
「つ、つまり……刺史となって節度使からその役割を奪ってこいと仰っている訳では」
「その通りだ。やはりお前はそれなりに頭の回る者のようだな」
ややもすると李将軍よりも政治的な事への考え方が出来ているのではないだろうか。
しかし分かったところで実行するとなると話は別だ。現状、節度使には恐らく向青倫の息がかかっており、軍を指揮し編成する権限を奪おうとしたら全力で妨害してくる可能性が高い。北玄海まで巻き込んで高原を制覇したいと考える野心的な男が、娘を後宮に取られたくらいでそれを諦めるとは思えないのだ。
「辛新は玲馨に付き添いいくらか山芒の、向青倫の思惑を傍で見てきたはずだな?」
「はい」
「それを牽制し、出来うる限り遅らせろ。そうすれば──向峰の入宮を遅らせる事になるだろうからな」
戊陽が向峰の名を出した途端、辛新は一瞬にして色を失った。己の不義が戊陽にも知られていると考えたのだろう。些か素直過ぎる反応だ。
腹芸が出来ないのでは向青倫に太刀打ちするなど到底不可能だが、丸め込む相手は何も向青倫である必要はない。山芒軍で実際に指揮を執っているのは次男の向峻のはずだからだ。
「私はな、妃を娶ると表向きには言ったが、まだそのつもりはないのだ」
蒼白な顔をしながらも辛新はどうにか戊陽の言葉に耳を傾けている。
辛うじて焦点を戊陽に定めている辛新の目を見つめて、戊陽はこれまでより一段、声色を和らげた。
「もし向峰に心寄せる者が他にいるのなら、その者に降嫁しても良いと考えている」
つまりそれはどういう事なのか。それを汲み取れない辛新ではなかったようで、みるみると目に力が戻っていく。
やはりそうだ。この男は紛れもなく向峰のためだけに動いている。禁軍での出世も、どうにか皇帝に近づく力を得ようと考えた時に出た結論がそれだったのだろう。辛新のその考え方は、全くのはずれではなかったという事だ。
「辛新に今一度訊く。刺史を任されてくれるか?」
力が戻った辛新は、一端の男の顔をしてしかと頷いた。
「陛下の仰せのままに、この辛新、刺史としてのお役目を立派に務めて参ります」
*
半ば茫然自失として東妃宮を出た玲馨は、去り際に目を覚ました小杰の駄々を上手く躱す事も出来ずになおざりにして出てきてしまった。
上手く働かない頭で、それでも自分の置かれた状況を確認するために思考を重ねてゆく。
東妃が望むのは今までのように皇帝と皇弟の双方に仕える宦官ではなく、小杰専任になれというものだ。そうなった時、玲馨の立場はどう変わるのか。
まず戊陽に付いて朝議の場に控える事がなくなり、宮廷の動きが分からなくなる。そして基本的に皇帝であっても玲馨の主である小杰の頭を越えて玲馨に命令を出す事は出来ないので、戊陽の思うように玲馨を使えなくなる。
後者で困るのは戊陽だが、前者は玲馨にとっても捨て置けない。宮廷の動きが分からなければ戊陽を支えていく事が出来なくなるからだ。
だがしかし、と足を動かしたおかげで血の巡りがよくなり始めた頭で、玲馨は更に思考を深める。
小杰に付けば東妃からの信頼は今よりも格段に得やすくなるだろう。西の動きも東妃を通して見えてくるかも知れない。このところ身の回りで起こった出来事の悉くが西方に繋がる事を思えば、今東妃や小杰たちから離れてしまうのは得策とは言い難い。いかに小杰専任になるからといって戊陽と全く連絡を取り合えなくなる訳ではないのだから、戊陽付きから外れてしまう事は損失ばかりではないともいえた。
しかし。
──私が戊陽付きの宦官ではなくなる……?
しかし、どれだけ理路整然と考えを纏めても、理屈ではないところで拒絶する気持ちが胸に溢れてくる。
戊陽の傍で過ごし始めて今年で九年になる。来年で十年の大台に乗ると思うと、人生の半分近くを戊陽と共にしてきたのだ。離れがたくなっても何ら不思議はない。
「あ! 玲馨さんじゃないですか!」
見覚えのある姿を夕日の中に見つけて玲馨は刹那の夢から覚めたような心地になる。おーいと手を振る辛新がにこやかに駆け寄ってくると、胸を占めていた底冷えのするような冷たさは幾分紛れていった。
「昨日の朝に別れたばかりなのにこんな所でお会いするとは!」
辛新の言うこんな所とは汀彩城内の東に位置する東沈と呼ばれる区域だ。こちらには主に文官に関連した建物が集中しており、武官である辛新の方こそ「こんな所」に何故現れたのか疑問である。
「辛新殿は東沈に何か用があったのですか?」
「それがですね、突然陛下に呼ばれまして」
「陛下に……?」
歩いてきた方角から、辛新は恐らく離宮である紅桃宮に呼ばれていたのだろう。
辛新は声を潜めたかと思うと、左見右見して周囲に人気がないのを確かめてから、僅かに玲馨へと顔を寄せた。
「あの、先日の件を改めて謝罪したいと……」
辛新から玲馨へ謝する事があるとしたらあの件しかない。玲馨を盾に戊陽を脅そうとした事だ。
「大変申し訳ありませんでした。私の早合点が招いた結果です」
「早合点?」
殊勝に謝ってきたかと思えば、辛新はまたちらりと左右を確認してから「玲馨さんは陛下付きの宦官でしたよね?」とどこか含みのある物言いで問うてくる。
「ええ、陛下にお仕えしていますが……」
「では既にお聞きになられていると思いますが、近く陛下は向公主をお迎えなさるそうですね」
「は……」
咄嗟に言葉が出なかった。知らされていなかったという衝撃もあるが、その一方で戊陽はそう決めたのかという納得が、辛うじて玲馨を冷静にさせてくれる。
それにしても辛新がやけにこの事を冷静に報告してくる事が気になった。つい今しがた謝罪したのはその向公主が原因ではなかったか。
「辛新殿は納得がいかないのでは?」
「……納得も何も、私はそもそも公主様とは格の違う人間ですから」
そうだろうか。下級とはいえ辛新も貴族は貴族だ。もしも向家にもう一人娘が生まれていれば、或いは辛新との結婚が認められていてもそう不思議はない。
そんな風に玲馨が考えるからだろうか、辛新の態度は本音や反省というよりも、謙遜の意味合いが強いように見えた。今いっとき我慢すれば、やがて向峰が自分のものになるような、そんな余裕が垣間見える。
「陛下に呼ばれた件ですが、私、この度刺史のお役目を陛下より仰せつかりました」
「刺史に、辛新殿が……?」
辛新の口から聞かされる話題が知らない事ばかりでそろそろ目を回しそうだ。まさか空いた刺史という席に辛新をあてがうとは考えもしなかった。
彼は武官なので役者が不足する以前の問題だが、戊陽は一体何を考えての采配なのだろうか。
「近々、正式に刺史についての詔勅を出されるそうです。正直私などで務まるとも思えないのですが……それでも! 私は出来る限り刺史としての役目を果たしたいと思います!」
自分の胸をドンと叩いて背筋を伸ばす辛新はやけにやる気に満ちた表情をしており、自分が畑の違う役職を任されている事などひとつも気にしていないようだ。これまで剣を振るってきた努力は捨てる事になると思うのだが。
「それでは玲馨さん、またどこかでお会い出来る日を楽しみにしています!」
宣言するだけして満足したのか、辛新は足取り軽く去っていく。刺史になる事にやたらとやる気を感じているようだ。勇み足にならなければ良いが。誰も彼も皆、玲馨に言うだけ言って勝手にすっきりするのは何なのか。受け止める方の身にもなってほしい。
まるで嵐のようだった辛新が去っていくと、玲馨はおもむろに歩みを再開させる。完全に日が暮れてしまう前に宿舎に戻らなくては。
それからしばらく無心で歩いていたつもりだったが、ふと同じ事ばかりを繰り返し考えていることに気付く。
『近く陛下は向公主をお迎えなさるそうですね』
玲馨は官吏たちからの声が大きくなるほどに、入宮させる妃は慎重に選べと口を酸っぱくして戊陽を諫めてきた。つい最近もそんな会話をしたと思う。だから勝手に戊陽はまだ後宮については何も考えていないと思い込んでいた。いや、確かにあの時までは具体的な構想などなく、官吏たちの声を強引に封殺していたのだ。
山芒で向青倫と公主について話をする機会があったのだろう。そして向公主を妃に決めてしまった。戊陽の初めての妃が決まってしまった。玲馨の知らないところで。
皇帝である限り絶対に逃げられないものだと頭で理解していたが、東妃の事も相俟って、再び胸の奥が冷えていく。
「私に相談するまでもなく、決めてしまったか……」
ひとりごちる玲馨の言葉を、宿舎前で懸命に枝葉を伸ばす桃の木だけが聞いていた。
*
「いいんですかねぇー、俺がこんな所でこんな事してて」
「もともと宦官は後宮で皇帝や妃に仕えるのが仕事だ」
「いやいや。宦官なら他に腐るほどいるでしょう」
「梅、少し反省しろ。泣きつかれたのだ、内侍監にな。仕事はしないわ喧嘩ばかりして風紀を乱すわで手に負えないと」
「喧嘩ねぇ……」
文句を垂れながらも本を整理していく手際は悪くない。お喋りな口を閉じれば能率はもっと上がるのだから、基本的に優秀な男なのだ。
戊陽が梅と知り合ったのは数年前、まだ兄の黄昌が存命だった頃に兄の名代で慰問に市井へと降りた時だ。その頃の梅はまだ羅清と名乗っていた頃で、町の自警組織に所属する兵士だった。
「何だ、言い分があるなら聞くぞ」
「えー、聞くんです? 気分悪くなっても責任取れませんけど」
「内侍監が匙を投げたなら、私が宦官たちの調停を図るしかあるまい」
そりゃあご苦労な事ですねと他人事のように言う。
「いえね? 女を犯して人生転落した奴が今度は皇帝陛下の尻を追っかけて出世するのかって言われたら、どんなに懐の深い梅梅さんでも怒りますって話ですよ」
聞くんじゃなかったと早々に後悔しつつも、聞いておいて良かったとも思う。上級宦官たちも立身出世のための蹴落とし合いは常態化してしまっているが、下級宦官のそれはもっと露骨で暴力が付き纏う。どうにか環境を改善してやりたいところだが、そのためには早いところ妃を増やして仕事を与えるくらいしか今のところ他に手段が無い。
梅がやっかまれるのもこうして戊陽が梅を使うのが原因だが、その程度でへこたれるような男ではないので重宝していた。
梅は本を整理し終えると、戊陽の手元を遠慮なく覗き込んでくる。
「こんなに地図ばっかり持ち出してきて、何をなさるんで?」
「あわいの変化を調べている」
「へぇ」
聞くだけ聞いてあっという間に興味をなくし、梅は適当な椅子を引き寄せて腰を下ろす。
ここは紅桃宮の戊陽の執務室だ。いくら気心が知れているといっても皇帝を前にこれだけ寛げる人間を他に知らない。
「梅。休んでも構わないが、これをまとめ終えたら太常寺まで遣いに出てもらうぞ」
「へいへい承知。で、太常寺って何ですかい?」
「祭祀を担当している官署だな。卜占を禁じる法を全て撤廃し、卜師の職位を太常寺に置く。そのための地均しを太常寺の官吏に担当してほしいのだ」
何の話だかさっぱり、という顔で「へーい」と気怠げな返事が返ってくる。つくづく出世欲の無い男だ。まぁ、元は市井で暮らしてきた平民である事を思えば、卜占や卜師への関心はこれが普通だろう。
「ところで、あの仏頂面はどうしたんです? 山芒じゃあの宦官がずっと陛下について回ってたんでしょう?」
「四郎の事か? 四郎なら玲馨の所だ。玲馨が調べ物をしたいと言うので、その手伝いを任せた」
「何でまたわざわざ仏頂面に。手伝いくらいならもっと下っ端の宦官を寄越せば」
「俺がここに駆り出されずに済んだのに、か?」
図星だったようで梅は誤魔化すようにへらりと笑う。
「お前は人の話を聞かぬな。梅をここに呼んだのは内侍監に泣きつかれたからだと言ったろう。四郎が居ようが居まいがお前には罰として私の手伝いをさせていた」
「そんなご無体な」
「何が無体か。自業自得だ」
玲馨と四郎が居るのは蔵書楼の禁書室だ。おいそれと誰にでも入る許可を与えられる場所ではない。何故わざわざ四郎をという問いへの答えは、四郎以外に禁書室へ立ち入らせられる者が居なかったという事になる。つくづく自分には信用の置ける者が少なすぎると、人知れず戊陽は落胆する。
「そう言えば、梅の妹は西に嫁いだのだったな」
「地方官吏のおっさんに惚れられて……ってそんな話したことありましたっけ?」
「離宮の執務室にまで立ち入らせる宦官の身辺調査を怠るほど、私は平和ボケしていないぞ」
答えながらあわいについて調べたものと合わせていかに卜占が必要かを認めた書簡を梅に握らせる。
敢えて西の話題を出したおかげか、梅は遅れて何かに勘付いたらしい。苦いものでも噛んだような顔でじとっと怪訝な目で戊陽を見る。そんな梅に対し、戊陽は爽やかに微笑む。
「西は昆との交易で随分栄えていると聞く」
「俺ぁ行きませんよ」
「これを逃せば妹には生涯会えぬままかもしれんな。本来宮刑とはそういうものだ」
梅はぎくっとして、頬を引きつらせた。妹の存在は梅にとっての泣き所のようだ。
「はぁー……やだやだ。好青年風の顔から出てくる脅し文句は性質が悪いですよ陛下」
顔よりも戊陽が国の最高位である事の方が問題のはずだが、とことん梅は身分というものに鈍感である。
「寧ろ恩情であろう。身内に会わせてやろうというのだ」
「全く、物は言いようですねぇ」
梅はやれやれと大袈裟に肩を竦めてみせてから、受け取った書簡を懐に仕舞う。
「西に発ったが最後、戻ってこなくても知りませんよ」
「それは、寂しいな」
本心だ。梅と話している間は何一つ気負わずに済むおかげで会話がよく弾む。そんな関係性でいられる人間は戊陽にとって二人と居ない。
梅は小さく嘆息して「やっぱり平和ボケしてますよ」と呟き去っていった。
戊陽は梅の言う通りかも知れないと思う。後宮の中で行われる水面下の権力抗争は、幼い戊陽に親しい身内というものを作らせてはくれなかった。寂しい思いをしてきたおかげで、梅や玲馨のように歳の近い者との交流を大人になった今でも欲しているという自覚がある。
幼少期、他の妃からはあまり好かれていないと幼心に気付きながらも、弟たちが暮らす宮に足繁く通ったりしていた。兄とは母同士のいざこざもなく良好な関係を築けていたが、弟たちの母は皆賢妃と何かしらの憚りがあった。その中でも東妃との関係が特に思わしくなく、それは現在まで続いている。
例え血は繋がらなくとも血を分けた弟の生母ならば身内であると戊陽は考えているが、母同士の家格はそれを許さない。そして母同士、妃同士、女同士の矜持があるようで、生家の事を抜きにしても賢妃と東妃の仲は冷えきっていた。
梅が去った後、ほとんど入れ違うようにして四郎が執務室へとやってきた。「陛下」と呼ぶ抑揚のないいつもの声に振り向くと、四郎はその手に書簡を携えていた。
「誰からだ?」
「東妃様からです。離宮の前で東妃宮付きの宦官と鉢合わせましたところ、この書簡を届けたいと申していたので、代わりに私が」
東妃からの書簡だと言われて内容が良いものだとは一つも思えない。書簡を読みたいような読みたくないような思いで開き、さっと目を通していく。
「これは……」
二つ返事では承諾しがたい内容に、戊陽の眉がひそめられる。
書簡は、玲馨を小杰付きにさせたいと望む内容だった。権威ある燕太傅の推薦だったとはいえ、戊陽の宦官である玲馨を小杰の教育係につけた事でさえも当時意外に思うほどだったというのに。
あれから数年、一体玲馨の何を気に入ったのだろうか。或いは別の思惑から玲馨を欲しているのか。
「返事をお書きになるなら、私が届けて参りますが」
「いや……良い。返事はまた後日出す」
四郎は寸分の狂いもない拱手をしてから退室していく。玲馨の調べものについて聞こうと考えていたのだが、そんな気も削がれてしまった。
東妃の行動は、西の蘇家の動きと考えるべきだろう。だとしたら、蘇家は玲馨を一体どうするつもりなのか。
「梅には是が非でも西に行ってもらわなくてはならなくなったな……」
戊陽は書簡を二つの意味で握りつぶしたい衝動を堪え、ふぅ、と疲れた溜め息を吐き出した。
黄雷皇帝の崩御から一ヶ月も経たないうちに、今度は燕太傅が病床に臥した。玲馨は黄昌の名代として見舞った戊陽の供をして、暗く沈んだ部屋の端に四郎と二人で控えている。
燕太傅は何か重篤な病を患った訳ではない。だが今日明日にも峠を迎えるだろうと医者は診断した。
出来れば燕太傅の顔をもう一度間近に見ておきたい。欲を言うなら声を聞きたい。だが宦官程度にそんなわがままが許されるはずもなく、ただ、小さく丸まった主人の背中を遠くに見つめる事しか出来ない。
ちらと横に立つ四郎の顔を見上げるも、彼は普段の様子と何ら変わりない。玲馨は彼が慌てたり取り乱したりする姿を見た事がなかった。それどころか泣きも笑いもしないので、心をどこかに落っことしてきたのだと思っている。そうでなければ、この悲痛な空気の中で眉一つ動かさずに平然と立っている事など出来ないだろう。
外は間もなく正午を過ぎる頃だ。燕太傅の屋敷は汀彩城から少し離れた所にあるので、馬車に乗るとはいえ日のあるうちに城に戻ろうと思うならそろそろ帰途に着かなくてはならない時間帯だ。だが玲馨はとてもではないが今の戊陽に帰ろうなどとは声を掛けられなかった。
戊陽には癒やしの力がある。傷も病もたちまち治してしまう奇跡のような力だが、決して万能ではなかった。
戊陽は燕太傅の屋敷を訪れると真っ先に病を消そうと力を使ったが、彼の父の時と同様に燕太傅の命を延ばしてはくれなかった。致死の傷や不治の病、そして老いていく肉体に対して癒やしの力は無力だった。燕太傅の体は、もはや老いによって今にも活動を終えようとしているのだ。
自分には何も出来る事がないと分かると、戊陽は祈り始めた。それから何時辰が過ぎただろうか。まるで時が止まってしまったかのように、玲馨の目に映る景色に変化は起きない。
燕太傅は生涯妻を娶らず独り身だった。屋敷に数人の侍女を雇い、慎ましやかな生活を送り、彼の不調を報せたのも侍女の書いた書簡だった。半月ほど前に風邪を引き拗らせてしまっていたのだが、まだ意識のあった燕太傅は黄雷の訃報を聞いて葬儀に参列出来なかった事を侘びつつ、侍女には決して燕太傅の状況については報せるなと言い含めてあったそうだ。師の気遣いのおかげで戊陽たち兄弟は父との別れをきちんと済ませる事が出来たのだ。その代わり、玲馨たちは燕太傅の意識があるうちに再会は叶わなくなってしまった。
ふと気が付くと、戊陽と燕太傅を照らしていた窓の明かりが半分ほど影になっていた。本来なら戊陽も父の喪に服して城を出てはならない時期で、帰りが遅くなると良くない噂を招くだろう。ましてこの屋敷で夜を明かす事などあってはならない。
四郎が微動だにしないので玲馨が戊陽に声を掛けようと足を踏み出すと、その肩を掴んで四郎が引き止めた。理由を問おうと振り返ると四郎は玲馨を見ておらず、その目は部屋の奥で横たわる燕太傅に付き添う戊陽を捉えていた。
「燕老師……!」
戊陽が握っていた燕太傅の手が動き、戊陽の後頭部に回るのが玲馨にも見えた。玲馨を引き留めていた四郎の手が離れていく。
「老師、見舞うのが遅くなってしまって、すまなかった」
燕太傅の手は少しの間、子供をあやすように戊陽の頭を撫でてていたがすぐに力を失い下へと下ろされる。戊陽はその手を再び取って、そっと布団の中へと戻した。
それから戊陽は燕太傅の口元に耳を寄せる。玲馨には何かを話している声だけが届きその内容までは聞き取れなかった。だが、最後に一言でも彼らが言葉を交わしあえたおかげか、重たく凝っていた空気は僅かに払拭されていた。
「玲馨」
戊陽が肩越しに振り返った。目の縁が赤い。
こちらへ来いという声に従い寝台の傍に寄ると、目が窪み窶れた姿の燕太傅が目だけで玲馨を見上げた。その細く頼りなげな姿は嘗てのかくしゃくとした老師の見る影もなく、一瞬だけ呆然とした。すぐに手を組み頭を下げると、燕太傅は腕を伸ばし玲馨の組んだ手にそっと手を重ねた。
「殿下、玲馨と二人で話すお時間を頂けますか」
声量こそ落ちているものの、今日明日が山だというのが嘘のようにはっきりとした口調だった。戊陽はすぐに椅子から立ち上がり、入れ替わりに玲馨を椅子へと座らせてから去っていく。
どうして良いか分からずに、玲馨はただとにかく辛うじて熱を宿した燕太傅の手を戊陽がしていたように握りしめる。
「玲馨」と燕太傅が名を呼ぶまでに時間がかかった。
「私はね、殿下にお会い出来た事と同じくらい、お前に私の知識と知恵を教えられた事を誇りに思っているよ」
ツン、と鼻の奥に痛みを感じた。目の縁からじわじわと迫ってくる気配を必死で押し留める。
「心残りがあるとすれば、小杰殿下の師事をお断りした事だ」
「何故断られたのですか?」
「愚拙の歳を考えれば、必然であった。代わりにな、お前の事を話しておいた」
「私の……?」
ぐ、と燕太傅の手に力が籠もり握り返される。それが今出せる全ての力だと思うとあまりに弱々しくて胸の奥を抓られるような痛みが走る。
「西は……。私の若い頃から東江の蘇家は、西方の大国昆と国境を隔て、新しいものを運んできた。よく、見ておきなさい。西方には常に新奇の風が吹く」
すー……、と空気が抜けていくようにして、燕太傅の手から力が消えていく。
「太傅……? 燕太傅!」
玲馨の声を聞きつけた戊陽が駆け寄ってくると、遅れて医者も中へ入ってくる。「眠られたようです」という医者の声をどこか遠くに聞きながら、玲馨は燕太傅の言葉の意味を考えていた。
明朝、燕太傅は眠ったまま息を引き取った。御年七十三の大往生だった。
これは今からおよそ六年ほど前の、玲馨にとって忘れがたい過去の一つだ。
*
「玲馨! これを見ろ!」
場所は東妃宮。間もなく自身を主役にした半元服の儀が迫っているせいかこのところ小杰はすこぶるご機嫌だ。
小杰は玲馨の手を引き跳ねるようにして卓のところまで連れていくと、玲馨を椅子に座らせる。卓には玲馨も昔夢中になった盤上遊戯の棋盤が置いてあった。
「象棋ですね。久しぶりに見ました」
いつ頃だったか、後宮で象棋が大流行した事がある。戊陽が蔵書楼から棋譜を見つけてきたのがきっかけではなかったか。二人で指南書を探し出して駒の動き方から学び、燕太傅にも勉強の息抜きによく教えてもらった。
「今母様に教わっているのだ」
「東妃様が?」
玲馨はちらと奥の部屋へと目を向ける。
「東妃様はどちらへ?」
姿が見えないのでごく自然に出た疑問だったのだが、どうやら踏んではいけないものだったようでせっかくのご機嫌がみるみる下降していく。ふう、と溜息をついた後、いかにも不満ですと言わんばかりに頬杖をついて象棋の駒を指で軽く弾く。
「……東江から新居にとたくさんの衣や装飾品が届いたのだ。お召し替えに夢中になっておられる」
言い終えるとむっと唇を引き結び、駒を棋盤の上に並べ始める。
なるほど道理でと玲馨は納得する。小杰は母に構ってもらえず拗ねていた。
玲馨は駒が入っていたもう一つの箱を手に取り、玲馨側の盤にも円盤型の小さな駒を並べていく。
「やはり玲馨は象棋が打てるのだな」
迷う事なく駒を規定の位置に並べていたので察したらしい。
「東妃様からお聞きになられませんでしたか? 小杰殿下がまだお小さかった頃、後宮で象棋が流行した事があったのです」
「聞いた事ないな。でも玲馨は負け知らずなのだろう?」
「まさか。燕太傅には終ぞ和局にさえさせてもらえませんでした」
「玲馨でも敵わぬのか!」
小杰のそれは買い被りだ。玲馨は苦笑して首を振る。
「私は、せいぜい数年嗜んだ程度でしたから。燕太傅はそれこそお若い頃より代々の皇帝陛下のお相手をなさっていたそうです」
「戊陽兄上も玲馨もよく燕太傅の名を出す。私も一度会ってみたかったな」
「はい……」
駒を並べ終えた段階になって、今更違和感に気付く。昔象棋が流行った頃に使っていた駒の文字の色は、紅と黒ではなかっただろうか。
「こちらの駒も東妃様のご実家からですか?」
「文字の色が違うと思ったのでしょう? それは昆からの舶来品ですよ」
声が聞こえた瞬間玲馨は椅子から立ち上がり、奥の部屋から現れた東妃へと恭しく手を組んだ。
いつになくきらびやかな衣はまさに東妃好みといった意匠で、真っ赤な深衣に彼女の髪とよく似た色合いの金糸の刺繍が目を引いた。
「大変お似合いで御座います、東妃様」
「玲馨、顔をお上げ。どうでしょう、これで一局私の相手をするというのは?」
これと言って東妃は本来なら黒であるはずの青文字の駒を持ち、小杰が並べ間違えていた駒を置き直した。
東妃が玲馨を象棋に誘うその真意は分からない。ほんの戯れか、象棋は口実で何か他にあるのか。いずれにせよ、北玄海から山芒へ続き、その後宮廷のごたごたで小杰付きとしての役目が疎かになってしまっていた以上、玲馨は断れる立場ではない。
東妃が小杰と椅子を替わり正面に座ると、彼女の醸す冷たく尖った空気がいっそう研ぎ澄まされるのが分かった。
玲馨が持つのは本来は紅である茶文字の駒だ。玲馨たちが夢中になった象棋では紅が先手だったが、東妃が初手を指す様子が無いので、玲馨が先に駒を動かしてみる。東妃は何も言わなかったので、玲馨が知っている規則に従って良いらしい。
パチ、パチ、と響く駒の音は耳に心地よく、懐かしいような気分になる。玲馨は戊陽の相手をよくしていたが、初めは絶対に勝ってはいけないと考えてわざと負けていた。しかしそのうち玲馨が手を抜いている事に気付くと戊陽はこう言った。「負けた時の言い訳のためにわざと手加減するんだろう?」それを聞いて尚負けてやれるほど玲馨は大人ではなかったし、本来はとても負けず嫌いなので以降は本気を出して戊陽と対局した。戦績は総合すると戊陽が少しだけ勝り、故意に負けていた対局を数えないと玲馨が勝る。わざと負けたのはほんの数戦なので実力は五分だった。
懐かしい思い出に浸りながら淀みなく打っていた玲馨だったが、不意に手を止め棋盤を見下ろす。突然次の手が頭に浮かんでこなくなったのだ。
「私を侮っていましたね?」
東妃に図星を突かれて言葉に詰まる。始めから程よく負けようと考えていただけに尚更だった。
「申し訳」
「謝罪はいいわ。あなたから聞きたいのはもっと別の言葉ですから」
玲馨の口から聞きたい言葉とは何だろうか。状況を考えたら投了が相応しく思えるが。
「本気でやりなさい、玲馨」
「……はい」
どうも戊陽や玲馨のように負けず嫌いなどが理由ではなさそうだ。闘志と言えば良いか、必死さのようなものが東妃からは感じられない。もっと圧倒的な高みから片手間に駒を動かすような、或いは児戯を片手であしらうような余裕がある。
東妃は強かった。その後も一度はどこかで見た事があるような展開が続くのだが、一手打つ度にどんどん道を潰されていくような感覚が強くなっていく。
打たされている、と気付いたのは対局が終盤に差し掛かった頃だった。途中まで目をキラキラ輝かせて夢中で二人の対局を見ていた小杰が、とっくに飽いて居眠りをしてしまっている。気を利かせた宮女が寝ぼけ眼の小杰を連れて寝台の方へ連れていった。
外でアー、と烏が一声鳴いた時、盤の上は勝敗が決していた。
「……私は、もしや東妃様に勝ちを譲って頂いたのでしょうか?」
沈みゆく夕日に玲馨の腑に落ちない声が滲んでいく。
残局際になって東妃の手はそれまでの猛攻が嘘のように緩んだ。まるで見えていた道が幻だったかのように迷い、手損が増えて、本気を出せと言われたからには玲馨は勝たざるを得なかった。
「私は象棋が嫌いでした。お忙しい父上は、いつも残局まで打たずに『また今度』と言われるのです。それなのに少し時間が出来ると子供と象棋をやりたがった」
「棋譜を残されなかったのですか?」
東妃は緩く首を左右に振る。
「遊びや息抜きのつもりだったのでしょう」
続けて東妃は言う。一度も父に勝てなかったが、一度も負けなかった、と。
「だから私は残局の布局を一つも知りません。指し方が分からないのです」
つまり彼女は父の打った手の模倣だけで象棋をしていたというのだ。途中までのゆっくりとこちらの首を締めていくような圧力の掛け方も実際の打ち手は東妃ではなく彼女の父だったという訳だ。
少し気になった。東妃の父がどんな人だったか。蘇家の公主の父、つまり先代金王は既に亡くなっている。
「父が象棋を好んだのは、象棋には人柄が出るからだそうです。私は父としか打たなかったからその言葉の意味がよく分からなかったけれど、玲馨、あなたと打って少しだけ理解した気がします」
人柄と言われて玲馨はよく対局した戊陽と燕太傅の事を思い浮かべる。
戊陽はこちらのやりたい事を捉えるのが上手かった。それをいなして自分の流れに持っていく事が下手だったが、それは単純に経験が不足しているせいで、玲馨はいずれ戊陽に勝てなくなる日が来るだろうと思っていた。
燕太傅は開局、中局、残局と常に指導するような指し方であらゆる布局を玲馨に学ばせてくれた。師の人柄なるものが現れるほど、玲馨の腕前は燕太傅には及ばなかった。
では東妃はどうだったろうか。
「あなたは、見た目には分からないけれど、とても真っ直ぐな象棋を打つのですね」
東妃は父の受け売りだが、それが彼女の手に残り馴染んだというなら、東妃の気質を構成する一つくらいにはなっているのかも知れない。相手の希望を摘み取るような恐ろしい指し方は、実力差がなければ成立しない気がするので、誰にでもこうとはいかないだろうが。
「私は、捻くれているように見えるということでしょうか?」
つい思った事をそのまま口にしてしまい、玲馨は遅れて自分自身に驚いた。東妃相手にこんなに素直な言葉を返してしまったのは初めてだ。慌てて頭を下げようとするも東妃の密やかな笑い声が聞こえてきて、玲馨の動きが止まる。
「もう少し策略家だと思った、という事よ。それを捻くれていると言うならそうなのかも知れません」
東妃が笑顔を浮かべる事は決して珍しい訳ではない。小杰にはよく笑い掛けているし、若い宮女たちと他愛ない話に花を咲かせては柔和な表情を見せる事もある。
それでもどうしてか貴重なものだと感じるのは、玲馨が自分に向けられた東妃の笑みをほとんど見た事が無かったからだと気付く。
ずっと、東妃と玲馨の間には言葉にし難い緊張感があった。それは宮女にも伝播し、東妃宮付きの宦官たちとも微妙な距離感が出来る原因になっていた。それらが今、期せずして僅かばかり解けていったような気がする。
「玲馨、私は決めました」
東妃はどこか憑き物が落ちたように言う。
「あなたを白蓮宮付きの宦官に出来ないか、陛下に相談します」
もしかして彼女はこの事でずっと悩んでいたのかも知れない。宣言した後の東妃はとても清々しい表情で、象棋を片付け始める。
玲馨は今度こそ「何て勝手な事を」などと言えるはずもなく、どこか浮かれたような東妃を前に、ただ途方に暮れるしかなかった。
*
戊陽にとって果物といえば幼少期から桃で、他には乾燥させた林檎や梨、干し柿などに馴染みがあるが、山芒の果実はどれも見慣れぬ物が多い。そして赤い実のものが多いようで酒に漬かっている物も干して砂糖をまぶした物もどれも赤い実が目についた。名前も分からないそのうちの一つを指で摘んで口の中に入れながら、向青倫が広間に戻ってくるのを待っている。
時は再び戊陽たちが山芒を訪れた頃まで遡る。向青倫の次男で跡取りである向峻が事故の怪我によって数日昏睡していたが、戊陽と練族について話し合っている時に漸く目を覚ましたのがつい今し方の事だ。
玲馨たちを屋敷から去らせた後、戊陽は向青倫との話を早く終わらせ玲馨たちを追いかけようと考えていた。玲馨はしきりに地図を気にしていたので、汀彩城にある沈全域を記した地図を欲しがって紫沈へ帰還すると予想していた。結果、その予想は的中し、この後戊陽は玲馨と共に紫沈への帰還が叶うわけだが。
戊陽がどう理由をつけて向家の屋敷を出ようかと算段していると、戻ってきた向青倫が思わぬ事を言ってきた。
「どうか次男にお会いして頂けませんか、陛下」
命を助けたその礼を言いたいのだと言われると無下には出来ず、戊陽は向青倫に伴われて屋敷の母屋を進む。
客堂で寝泊まりしていた頃はあまり意識していなかったが、改めて屋敷の内装や調度品を見ていると向青倫が古風な物を好むらしい事が分かる。どれも戊陽の目利きでは年代までは判然とせず、とにかく古いという事だけ分かる物ばかりだ。しかし一目に価値のつけられない貴重な物である事は分かる意匠で、それらが品よく飾られている。狸爺という印象に、趣のある男、という印象が足された。
「こちらで御座います」
家主自ら扉を開け中へ誘われると、そこでは寝台から降りて拱手の姿勢で待つ向峻の姿があった。
「よせ。まだ病み上がりであろう。せめて寝台に腰掛けると良い」
「いいえ陛下。此度の事は感謝してもしきれませぬ」
「せっかく拾った命なのだ。無理は許さぬ」
「は……」
向峻が顔を上げると似ていると思った。面差しもだが目付きが似ている。頑固そうな中に狡猾さがうかがえる、一筋縄ではいかせないという雰囲気が目によく表れている。長男の向亗と比較すると、次男が長男を差し置いて跡取りになったと聞かされて納得するだけのものがあった。
向峻が寝台に腰を下ろすと、ついてきていた李将軍がどこからか椅子を引っ張って来たので戊陽も座る。
「私は、意識を失う寸前、もはや今生と別れるしかないのだと諦めておりました」
向峻は膝を手でぎゅっと掴んでいる。その爪が奇形のまま傷が塞がってしまっているのを見つけてしまい、戊陽は瞼を僅かに伏せた。向峻の歪んだ爪は彼が生きたいと必死だった事の証だ。
「目を覚ました時はこの世ではないのだと俄かに現実を信じられなかった私に、侍女が私が助けられた事を話してくれました」
戊陽には一生をかけても返しきれない大恩が出来た。しかし自分は山芒を導く立場にあるため紫沈に行く事は叶わない。
そこまでを訥々と語った向峻は気持ちを改めるようにして顔を上げ、意を決したように続けた。
「陛下、どうぞ私の代わりに妹を後宮に入れて陛下に仕えさせて下さいませんか」
「っ、向峻!!」
一瞬頭の中で言葉の意味を理解する間を挟み、怒号が向青倫から上がる。その顔に、カッと怒りの表情が灯っていた。
戊陽としても向の公主である向峰の事は父親の口から聞かされるだろうと予測していただけに疑問が過る。
「この事を妹御は知っているのか?」
「はい」
「お前たちは、勝手に……」
向青倫から生気のようなものが抜けていく。彼が示すその反応は諦念のように見えた。反対するでもなくだんまりとして向峻が何を話すつもりかうかがっているようだ。
おかしい、とやはり戊陽の中の疑問は消えていかない。向峰は辛新と関係を持っているはずだ。しかし向峰が入宮に関して承知しているとなると、何かの企みがある事を疑わなくてはならなくなる。
どう答えるが良いかしばし黙考した末、戊陽は重い口を開く。
「向峰が承知だと言うなら私に断る理由はない。近く向峰を妃として迎えよう。──それで良いか、向青倫」
戊陽の決断を受けて、向青倫は辛うじて溜息をこぼさないよう堪えるので精一杯という風にやおら目線を下げた。
「……もちろんで御座います。娘も戊陽陛下の妃に迎えて頂けるのなら女としてこれほど幸福な事はありますまい」
「ありがとう御座います陛下!」
感極まったように声を上ずらせる向峻の一方で、父親である向青倫が返すのは切口上。親子の温度差はいかんともしがたいもののようだった。
向の屋敷を出て李将軍と共に玲馨を追いかけていると、李将軍が控えめに「陛下」と声をかけてくる。
「あの場で即決なさってよろしかったので?」
「私が私の妃を選ぶのに、何故他の者の意見を聞かねばならぬ」
「いや、しかしですなぁ。この李孟義、戊陽陛下は、その……妃を迎えるのがお嫌なのだとばかり」
「そうだ。当たっているぞ李孟義」
「では一体何故」
何故も何も政治的に考えれば集権的で向家以外の力を失いつつある貴族の娘を妃にするよりも、山芒において絶対的な支配力を持つ向の娘を妃にして向家を、引いては向青倫とその跡取りである向峻の機嫌を取ったほうが良いに決まっている。
しかし戊陽の目的はそれだけではない。
「向青倫は娘を溺愛しておるのだろうな」
「は。そのようでした」
「だが皇帝と懇意にするため、或いは宮廷を我が物とすべく愛娘を後宮に入れると決めた。練族との戦を見据えながらな」
「……! 陛下、よもや……。いや、ここは皇帝らしくなられたと喜ぶべき場面なのか……?」
言葉を濁した李将軍の困惑を残した独り言は戊陽の耳にも聞こえている。わさわさとした顎髭を撫でる李将軍の表情が険しくなるのも、その心情はよく理解出来た。
戊陽は向峰を手元においてその企みを暴くと共に、向家を抑制する駒に使うつもりだ。人質と言っても良いのかも知れない。これで向青倫は独断でも、或いは北玄海と協力したとしても高原攻めを安易に行えなくなった事になる。向峻の口から妹の名が出た時の向青倫の激昂には焦りも混ざっていたようだった。
戊陽は鬼になるつもりはない。皇帝としてただ沈を安寧に導きたいだけだ。だが回ってきた玉座はその時点で張りぼてで、沈は砂上の楼閣へと零落してゆく最中にあった。多少強引にでも手を施さなくてはやがて反乱を招くだろう。唯々諾々と椅子に座るだけでは、張りぼてと共に最後の沈の皇帝として滅んでいくに違いない。
そうならないためにまず一手、向青倫の娘を妃として迎え山芒に対しての抑止力とした。しかしそれだけではもちろん不足する。高原攻めを終えてから向峰を入宮させれば良いだけの話だ。故にもう一手戊陽は向青倫に対して布石を打たねばならない。
*
時は現在へ戻り、朝議を終えた後、戊陽は黄麟宮へは戻らず離宮である紅桃宮へと向かった。密談を交わすとなるとどうしてもここになってしまう。
戊陽は四郎を軍部へと遣いに出して、彼が目的の人物を連れてくるのを待っていた。
紅桃宮には戊陽が幼少期を過ごした賢妃宮にあった桃の木が全て植え替えられてある。今でも毎年春に多くの花をつけ、夏にはみずみずしい桃の実が生った。
桃の木には戊陽の母である賢妃の様々な思いが込められている。
最初は桃をとても好んだ賢妃のためにと桃の木のある庭へと作り変えられて、花を楽しむためだけのものだった。しかし、桃には子宝に恵まれるための運気をあげてくれる力があると分かると、賢妃は桃を結実させるために躍起になった。
賢妃は黄雷よりも歳が上で、二十歳を優に越えてからの入宮だった。妃となったは良いもののしばらくの間子宝に恵まれず、彼女への風当たりはきつくなっていった。四妃である賢妃は後宮内でも立場が強くなく、更に薹が立った女だったので二妃や三妃に仕えていた宮女たちからは影で笑われていた。
しかしやがて皇帝の次男となる戊陽を出産すると、徐々に賢妃の立場は回復していったという。母は戊陽が産まれる以前の苦悩を戊陽に聞かせる時、必ず桃の何かを傍に置きながら語った。ある時は桃の花弁を茶に浮かべ、ある時は桃の皮を剥きながら、ある時は桃のお香を調香しながら。
桃の香りにはいつも賢妃の記憶が合わさり戊陽の思い出を刺激する。十二を迎える頃にはそこに玲馨の姿が加わった。
「陛下、連れて参りました」
遣いに行かせていた四郎が戻ってくると、その後ろで武官にしては少々小柄な好青年風の若い男が、緊張と警戒の面持ちで抱拳礼をした。
「この辛新、陛下のご用命と聞き参りました」
名を辛新という。山芒で調査する玲馨に付けていた元案内役の武官の青年だ。見た目に随分若いが戊陽と同い年だという。
玲馨に彼を付けさせたのは戊陽の指示だった。
禁軍というのはその兵たちのほとんどが紫沈で生まれ育った貴族の子息たちで構成されている。数少ない地方出身者は紫沈に婿入りでやってきた下級貴族ばかりだ。その中で貴族とはいえ婿に来た訳でもない山芒出身である辛新が軍の中で目立つのは必然だったと言えよう。
辛新の存在はやがて李将軍の耳にも届く事になる。辛新の事情を概ね知っている兵士が禁軍に居た事で李将軍が疑いを強めていたところ、山芒での事故の話から玲馨に話題が及び、玲馨なら辛新の正体も暴けるだろうと踏んで玲馨の案内役を任せる案を思い付いた。結果、玲馨は辛新の事にどれだけ気付いたかは報告がないので分からないが、今となってはこれについて玲馨に問おうとは考えていない。
辛新は向公主、つまり戊陽の後宮に入る事が決まっている向峰と密通した事で、山芒を追い出された不義の男だ。と、戊陽は推測している。そう考える理由は向峰の部屋で深夜に辛新の声を聞いたからというだけなのだが、辛新と向峰が懇ろな仲を隠し通していたなら何も辛新が禁軍の兵士になる必要はなかったろう。
さて、と戊陽は気持ちを改めるようにして、指の先まで固まっていそうな辛新に向き直る。
「辛新、お前は何故武官になった? 禁軍の兵士なら誰しもが出世を望むだろうがお前はまだ若い。苦労して武科挙を受けてまで早く武官になった理由は何故だ?」
こんな事を聞かれるとは予想だにしなかったのだろう、辛新はしどろもどろになりながら「出世のためです」と答えた。
「お前の望む地位はどこだ? 尉官か? 左官? それとも、将軍か?」
将軍と言った時、辛新は弾かれたように顔を上げて小刻みに顔を左右に振った。
「とんでもありません! 私に将軍などとても……」
「ふむ。では今の地位で満足か」
「……いえ」
「望む地位につけるなら、お前はどんな努力も厭わぬか」
辛新の視線が考え込むようにして下を向いたのは一瞬の事で、すぐに力を持った目で戊陽を見返した。
「はい」
戊陽は辛新とはそう多く顔を合わせていない。最初は李将軍が紹介のために連れてきた時で、次は向家の屋敷で玲馨が彼を伴っていた時。直接言葉を交わしたのは今回が初めてだ。
到底辛新の人となりを見抜けるほどの交流は持てていないがこれだけは分かる。この男は馬鹿ではないと。
「辛新、ついて参れ。四郎はここへ残り待つように」
「はい」という二つの返事を聞いて、戊陽は歩きだす。向かうのは四阿だ。
桃の花が全て散ったのでもはや香りが風に乗ってくる事はなくなった。春が終わりに向かうと、紅桃宮は青々と茂る木々に囲まれるだけになり、他に咲く花はない。
戊陽は四阿の椅子に座り、辛新を正面に座らせる。
漏窓から抜けていく風はまだ夏を感じるには早い爽やかな温度を運んでくる。対象的に、辛新が戊陽へと向ける視線は決して穏やかとは言い難い。緊張から固くなった表情に浮かぶ畏怖。更に敢えて言葉にするなら敵愾心のようなものが混じっていた。
「これより先は他言無用である。心しろ」
「はっ……」
辛新は顔に出やすい男だ。若いと一言に言ってしまってもよいが、根が単純なのだろう。だからこそ戊陽は辛新に賭けてみても良いかもしれないと考えた。もし裏切れば、辛新は必ず襤褸を出すと予想したのだ。
「辛新、お前を山芒の刺史に任命したいと考えている」
「は……はい……?」
「お前は卓刺史を捕らえたのだったな」
「はっ、私は玲馨さんに言われて動いていただけですが」
「手柄がどこにあるかの話は本題ではない。山芒の刺史が捕らえられたという事は、山芒の刺史を新たに任命せねばならない。しかし、適当な人材というものはそう簡単に見つかるものではないのだ」
刺史とは令外官といって本来なら皇帝の一任で選べる職位だが、捕まった卓浩の選定に戊陽はおろか黄昌の意思は介在していない。そうでなければ北玄海の刺史と山芒の刺史が従兄弟関係という事態は起きなかったろう。
故にここで戊陽は改めて信の置ける文官を刺史として遣わしたいところなのだが、文官たちの顔を改めて眺めた時、それに値する者が居ない事に気付いた。どこに林勢力の残党が潜んでいるかも分からなければ、或いは桂昭の手の者とも限らない。今となっては後者の方がよっぽど悪い。
概ねどちらにも属さないだろう者を絞れたところで十割の信頼を置ける者など宮廷の文官には見当たらなかった。となると、その外から連れてくる他ないのである。
四郎や玲馨といった幼少から戊陽に仕えていた中でも政治に知見のある宦官をつかせる事も一度は考えたが、沈では宦官の立場があまりに低すぎるのが問題だった。刺史として山芒に赴任しても地方官吏が言う事を聞かないのでは意味がない。
宦官が無理なら最後はもう門外漢である武官から引っ張ってくるしかなかった。だが刺史に適切な人材といってもしばらくは戊陽の頭には誰の顔も浮かぶ事はなかった。
「ですが、私は一介の武官でしかありません。刺史というと文官なのでは……?」
「そも昔は地方軍を束ねる節度使という武官の職位はなかった。刺史が兼ねておったのだ」
「つ、つまり……刺史となって節度使からその役割を奪ってこいと仰っている訳では」
「その通りだ。やはりお前はそれなりに頭の回る者のようだな」
ややもすると李将軍よりも政治的な事への考え方が出来ているのではないだろうか。
しかし分かったところで実行するとなると話は別だ。現状、節度使には恐らく向青倫の息がかかっており、軍を指揮し編成する権限を奪おうとしたら全力で妨害してくる可能性が高い。北玄海まで巻き込んで高原を制覇したいと考える野心的な男が、娘を後宮に取られたくらいでそれを諦めるとは思えないのだ。
「辛新は玲馨に付き添いいくらか山芒の、向青倫の思惑を傍で見てきたはずだな?」
「はい」
「それを牽制し、出来うる限り遅らせろ。そうすれば──向峰の入宮を遅らせる事になるだろうからな」
戊陽が向峰の名を出した途端、辛新は一瞬にして色を失った。己の不義が戊陽にも知られていると考えたのだろう。些か素直過ぎる反応だ。
腹芸が出来ないのでは向青倫に太刀打ちするなど到底不可能だが、丸め込む相手は何も向青倫である必要はない。山芒軍で実際に指揮を執っているのは次男の向峻のはずだからだ。
「私はな、妃を娶ると表向きには言ったが、まだそのつもりはないのだ」
蒼白な顔をしながらも辛新はどうにか戊陽の言葉に耳を傾けている。
辛うじて焦点を戊陽に定めている辛新の目を見つめて、戊陽はこれまでより一段、声色を和らげた。
「もし向峰に心寄せる者が他にいるのなら、その者に降嫁しても良いと考えている」
つまりそれはどういう事なのか。それを汲み取れない辛新ではなかったようで、みるみると目に力が戻っていく。
やはりそうだ。この男は紛れもなく向峰のためだけに動いている。禁軍での出世も、どうにか皇帝に近づく力を得ようと考えた時に出た結論がそれだったのだろう。辛新のその考え方は、全くのはずれではなかったという事だ。
「辛新に今一度訊く。刺史を任されてくれるか?」
力が戻った辛新は、一端の男の顔をしてしかと頷いた。
「陛下の仰せのままに、この辛新、刺史としてのお役目を立派に務めて参ります」
*
半ば茫然自失として東妃宮を出た玲馨は、去り際に目を覚ました小杰の駄々を上手く躱す事も出来ずになおざりにして出てきてしまった。
上手く働かない頭で、それでも自分の置かれた状況を確認するために思考を重ねてゆく。
東妃が望むのは今までのように皇帝と皇弟の双方に仕える宦官ではなく、小杰専任になれというものだ。そうなった時、玲馨の立場はどう変わるのか。
まず戊陽に付いて朝議の場に控える事がなくなり、宮廷の動きが分からなくなる。そして基本的に皇帝であっても玲馨の主である小杰の頭を越えて玲馨に命令を出す事は出来ないので、戊陽の思うように玲馨を使えなくなる。
後者で困るのは戊陽だが、前者は玲馨にとっても捨て置けない。宮廷の動きが分からなければ戊陽を支えていく事が出来なくなるからだ。
だがしかし、と足を動かしたおかげで血の巡りがよくなり始めた頭で、玲馨は更に思考を深める。
小杰に付けば東妃からの信頼は今よりも格段に得やすくなるだろう。西の動きも東妃を通して見えてくるかも知れない。このところ身の回りで起こった出来事の悉くが西方に繋がる事を思えば、今東妃や小杰たちから離れてしまうのは得策とは言い難い。いかに小杰専任になるからといって戊陽と全く連絡を取り合えなくなる訳ではないのだから、戊陽付きから外れてしまう事は損失ばかりではないともいえた。
しかし。
──私が戊陽付きの宦官ではなくなる……?
しかし、どれだけ理路整然と考えを纏めても、理屈ではないところで拒絶する気持ちが胸に溢れてくる。
戊陽の傍で過ごし始めて今年で九年になる。来年で十年の大台に乗ると思うと、人生の半分近くを戊陽と共にしてきたのだ。離れがたくなっても何ら不思議はない。
「あ! 玲馨さんじゃないですか!」
見覚えのある姿を夕日の中に見つけて玲馨は刹那の夢から覚めたような心地になる。おーいと手を振る辛新がにこやかに駆け寄ってくると、胸を占めていた底冷えのするような冷たさは幾分紛れていった。
「昨日の朝に別れたばかりなのにこんな所でお会いするとは!」
辛新の言うこんな所とは汀彩城内の東に位置する東沈と呼ばれる区域だ。こちらには主に文官に関連した建物が集中しており、武官である辛新の方こそ「こんな所」に何故現れたのか疑問である。
「辛新殿は東沈に何か用があったのですか?」
「それがですね、突然陛下に呼ばれまして」
「陛下に……?」
歩いてきた方角から、辛新は恐らく離宮である紅桃宮に呼ばれていたのだろう。
辛新は声を潜めたかと思うと、左見右見して周囲に人気がないのを確かめてから、僅かに玲馨へと顔を寄せた。
「あの、先日の件を改めて謝罪したいと……」
辛新から玲馨へ謝する事があるとしたらあの件しかない。玲馨を盾に戊陽を脅そうとした事だ。
「大変申し訳ありませんでした。私の早合点が招いた結果です」
「早合点?」
殊勝に謝ってきたかと思えば、辛新はまたちらりと左右を確認してから「玲馨さんは陛下付きの宦官でしたよね?」とどこか含みのある物言いで問うてくる。
「ええ、陛下にお仕えしていますが……」
「では既にお聞きになられていると思いますが、近く陛下は向公主をお迎えなさるそうですね」
「は……」
咄嗟に言葉が出なかった。知らされていなかったという衝撃もあるが、その一方で戊陽はそう決めたのかという納得が、辛うじて玲馨を冷静にさせてくれる。
それにしても辛新がやけにこの事を冷静に報告してくる事が気になった。つい今しがた謝罪したのはその向公主が原因ではなかったか。
「辛新殿は納得がいかないのでは?」
「……納得も何も、私はそもそも公主様とは格の違う人間ですから」
そうだろうか。下級とはいえ辛新も貴族は貴族だ。もしも向家にもう一人娘が生まれていれば、或いは辛新との結婚が認められていてもそう不思議はない。
そんな風に玲馨が考えるからだろうか、辛新の態度は本音や反省というよりも、謙遜の意味合いが強いように見えた。今いっとき我慢すれば、やがて向峰が自分のものになるような、そんな余裕が垣間見える。
「陛下に呼ばれた件ですが、私、この度刺史のお役目を陛下より仰せつかりました」
「刺史に、辛新殿が……?」
辛新の口から聞かされる話題が知らない事ばかりでそろそろ目を回しそうだ。まさか空いた刺史という席に辛新をあてがうとは考えもしなかった。
彼は武官なので役者が不足する以前の問題だが、戊陽は一体何を考えての采配なのだろうか。
「近々、正式に刺史についての詔勅を出されるそうです。正直私などで務まるとも思えないのですが……それでも! 私は出来る限り刺史としての役目を果たしたいと思います!」
自分の胸をドンと叩いて背筋を伸ばす辛新はやけにやる気に満ちた表情をしており、自分が畑の違う役職を任されている事などひとつも気にしていないようだ。これまで剣を振るってきた努力は捨てる事になると思うのだが。
「それでは玲馨さん、またどこかでお会い出来る日を楽しみにしています!」
宣言するだけして満足したのか、辛新は足取り軽く去っていく。刺史になる事にやたらとやる気を感じているようだ。勇み足にならなければ良いが。誰も彼も皆、玲馨に言うだけ言って勝手にすっきりするのは何なのか。受け止める方の身にもなってほしい。
まるで嵐のようだった辛新が去っていくと、玲馨はおもむろに歩みを再開させる。完全に日が暮れてしまう前に宿舎に戻らなくては。
それからしばらく無心で歩いていたつもりだったが、ふと同じ事ばかりを繰り返し考えていることに気付く。
『近く陛下は向公主をお迎えなさるそうですね』
玲馨は官吏たちからの声が大きくなるほどに、入宮させる妃は慎重に選べと口を酸っぱくして戊陽を諫めてきた。つい最近もそんな会話をしたと思う。だから勝手に戊陽はまだ後宮については何も考えていないと思い込んでいた。いや、確かにあの時までは具体的な構想などなく、官吏たちの声を強引に封殺していたのだ。
山芒で向青倫と公主について話をする機会があったのだろう。そして向公主を妃に決めてしまった。戊陽の初めての妃が決まってしまった。玲馨の知らないところで。
皇帝である限り絶対に逃げられないものだと頭で理解していたが、東妃の事も相俟って、再び胸の奥が冷えていく。
「私に相談するまでもなく、決めてしまったか……」
ひとりごちる玲馨の言葉を、宿舎前で懸命に枝葉を伸ばす桃の木だけが聞いていた。
*
「いいんですかねぇー、俺がこんな所でこんな事してて」
「もともと宦官は後宮で皇帝や妃に仕えるのが仕事だ」
「いやいや。宦官なら他に腐るほどいるでしょう」
「梅、少し反省しろ。泣きつかれたのだ、内侍監にな。仕事はしないわ喧嘩ばかりして風紀を乱すわで手に負えないと」
「喧嘩ねぇ……」
文句を垂れながらも本を整理していく手際は悪くない。お喋りな口を閉じれば能率はもっと上がるのだから、基本的に優秀な男なのだ。
戊陽が梅と知り合ったのは数年前、まだ兄の黄昌が存命だった頃に兄の名代で慰問に市井へと降りた時だ。その頃の梅はまだ羅清と名乗っていた頃で、町の自警組織に所属する兵士だった。
「何だ、言い分があるなら聞くぞ」
「えー、聞くんです? 気分悪くなっても責任取れませんけど」
「内侍監が匙を投げたなら、私が宦官たちの調停を図るしかあるまい」
そりゃあご苦労な事ですねと他人事のように言う。
「いえね? 女を犯して人生転落した奴が今度は皇帝陛下の尻を追っかけて出世するのかって言われたら、どんなに懐の深い梅梅さんでも怒りますって話ですよ」
聞くんじゃなかったと早々に後悔しつつも、聞いておいて良かったとも思う。上級宦官たちも立身出世のための蹴落とし合いは常態化してしまっているが、下級宦官のそれはもっと露骨で暴力が付き纏う。どうにか環境を改善してやりたいところだが、そのためには早いところ妃を増やして仕事を与えるくらいしか今のところ他に手段が無い。
梅がやっかまれるのもこうして戊陽が梅を使うのが原因だが、その程度でへこたれるような男ではないので重宝していた。
梅は本を整理し終えると、戊陽の手元を遠慮なく覗き込んでくる。
「こんなに地図ばっかり持ち出してきて、何をなさるんで?」
「あわいの変化を調べている」
「へぇ」
聞くだけ聞いてあっという間に興味をなくし、梅は適当な椅子を引き寄せて腰を下ろす。
ここは紅桃宮の戊陽の執務室だ。いくら気心が知れているといっても皇帝を前にこれだけ寛げる人間を他に知らない。
「梅。休んでも構わないが、これをまとめ終えたら太常寺まで遣いに出てもらうぞ」
「へいへい承知。で、太常寺って何ですかい?」
「祭祀を担当している官署だな。卜占を禁じる法を全て撤廃し、卜師の職位を太常寺に置く。そのための地均しを太常寺の官吏に担当してほしいのだ」
何の話だかさっぱり、という顔で「へーい」と気怠げな返事が返ってくる。つくづく出世欲の無い男だ。まぁ、元は市井で暮らしてきた平民である事を思えば、卜占や卜師への関心はこれが普通だろう。
「ところで、あの仏頂面はどうしたんです? 山芒じゃあの宦官がずっと陛下について回ってたんでしょう?」
「四郎の事か? 四郎なら玲馨の所だ。玲馨が調べ物をしたいと言うので、その手伝いを任せた」
「何でまたわざわざ仏頂面に。手伝いくらいならもっと下っ端の宦官を寄越せば」
「俺がここに駆り出されずに済んだのに、か?」
図星だったようで梅は誤魔化すようにへらりと笑う。
「お前は人の話を聞かぬな。梅をここに呼んだのは内侍監に泣きつかれたからだと言ったろう。四郎が居ようが居まいがお前には罰として私の手伝いをさせていた」
「そんなご無体な」
「何が無体か。自業自得だ」
玲馨と四郎が居るのは蔵書楼の禁書室だ。おいそれと誰にでも入る許可を与えられる場所ではない。何故わざわざ四郎をという問いへの答えは、四郎以外に禁書室へ立ち入らせられる者が居なかったという事になる。つくづく自分には信用の置ける者が少なすぎると、人知れず戊陽は落胆する。
「そう言えば、梅の妹は西に嫁いだのだったな」
「地方官吏のおっさんに惚れられて……ってそんな話したことありましたっけ?」
「離宮の執務室にまで立ち入らせる宦官の身辺調査を怠るほど、私は平和ボケしていないぞ」
答えながらあわいについて調べたものと合わせていかに卜占が必要かを認めた書簡を梅に握らせる。
敢えて西の話題を出したおかげか、梅は遅れて何かに勘付いたらしい。苦いものでも噛んだような顔でじとっと怪訝な目で戊陽を見る。そんな梅に対し、戊陽は爽やかに微笑む。
「西は昆との交易で随分栄えていると聞く」
「俺ぁ行きませんよ」
「これを逃せば妹には生涯会えぬままかもしれんな。本来宮刑とはそういうものだ」
梅はぎくっとして、頬を引きつらせた。妹の存在は梅にとっての泣き所のようだ。
「はぁー……やだやだ。好青年風の顔から出てくる脅し文句は性質が悪いですよ陛下」
顔よりも戊陽が国の最高位である事の方が問題のはずだが、とことん梅は身分というものに鈍感である。
「寧ろ恩情であろう。身内に会わせてやろうというのだ」
「全く、物は言いようですねぇ」
梅はやれやれと大袈裟に肩を竦めてみせてから、受け取った書簡を懐に仕舞う。
「西に発ったが最後、戻ってこなくても知りませんよ」
「それは、寂しいな」
本心だ。梅と話している間は何一つ気負わずに済むおかげで会話がよく弾む。そんな関係性でいられる人間は戊陽にとって二人と居ない。
梅は小さく嘆息して「やっぱり平和ボケしてますよ」と呟き去っていった。
戊陽は梅の言う通りかも知れないと思う。後宮の中で行われる水面下の権力抗争は、幼い戊陽に親しい身内というものを作らせてはくれなかった。寂しい思いをしてきたおかげで、梅や玲馨のように歳の近い者との交流を大人になった今でも欲しているという自覚がある。
幼少期、他の妃からはあまり好かれていないと幼心に気付きながらも、弟たちが暮らす宮に足繁く通ったりしていた。兄とは母同士のいざこざもなく良好な関係を築けていたが、弟たちの母は皆賢妃と何かしらの憚りがあった。その中でも東妃との関係が特に思わしくなく、それは現在まで続いている。
例え血は繋がらなくとも血を分けた弟の生母ならば身内であると戊陽は考えているが、母同士の家格はそれを許さない。そして母同士、妃同士、女同士の矜持があるようで、生家の事を抜きにしても賢妃と東妃の仲は冷えきっていた。
梅が去った後、ほとんど入れ違うようにして四郎が執務室へとやってきた。「陛下」と呼ぶ抑揚のないいつもの声に振り向くと、四郎はその手に書簡を携えていた。
「誰からだ?」
「東妃様からです。離宮の前で東妃宮付きの宦官と鉢合わせましたところ、この書簡を届けたいと申していたので、代わりに私が」
東妃からの書簡だと言われて内容が良いものだとは一つも思えない。書簡を読みたいような読みたくないような思いで開き、さっと目を通していく。
「これは……」
二つ返事では承諾しがたい内容に、戊陽の眉がひそめられる。
書簡は、玲馨を小杰付きにさせたいと望む内容だった。権威ある燕太傅の推薦だったとはいえ、戊陽の宦官である玲馨を小杰の教育係につけた事でさえも当時意外に思うほどだったというのに。
あれから数年、一体玲馨の何を気に入ったのだろうか。或いは別の思惑から玲馨を欲しているのか。
「返事をお書きになるなら、私が届けて参りますが」
「いや……良い。返事はまた後日出す」
四郎は寸分の狂いもない拱手をしてから退室していく。玲馨の調べものについて聞こうと考えていたのだが、そんな気も削がれてしまった。
東妃の行動は、西の蘇家の動きと考えるべきだろう。だとしたら、蘇家は玲馨を一体どうするつもりなのか。
「梅には是が非でも西に行ってもらわなくてはならなくなったな……」
戊陽は書簡を二つの意味で握りつぶしたい衝動を堪え、ふぅ、と疲れた溜め息を吐き出した。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
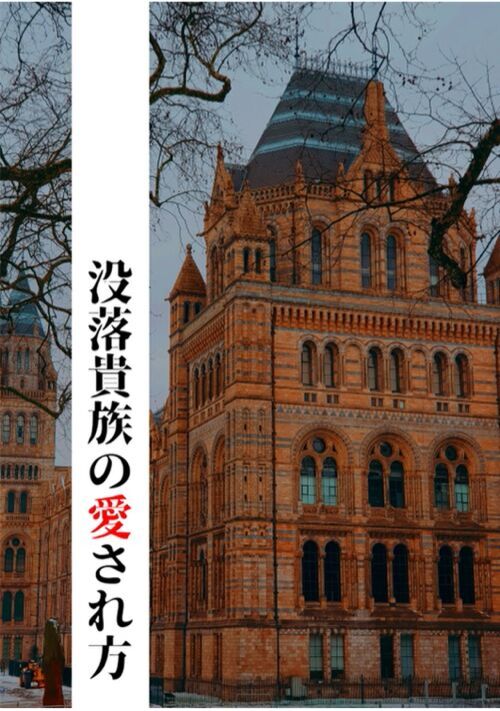
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















