35 / 44
完結編
35帰結
しおりを挟む
時は星昴が死ぬよりも遡り、汪軍が紫沈に攻め入るよりも更に前。紫沈のある一画を二人の男が歩いていた。
紫沈は基本的に「門」に近付くほど栄えている。まずは午門から北に位置する東沈と西沈を含む汀彩城だ。皇帝の居所である黄麟宮を始めとした宮殿と、妃や皇子、公主が暮らす後宮は、建材から職人に至るまで一切費用を惜しまず造り上げた贅の庭である。他には政の中心となる外廷や禁軍の詰めている兵舎など、紫沈の半分以上を汀彩城が占めている。
次に東西南の三方に構える門の周辺には座商行商問わず商人たちが商いをする地区で、更に地方との行き交いも多く賑やかな場所だ。
そして商人たちの地区より内側に入ると東西南の地方出身の貴族たちの屋敷が軒を連ねており、北の貴族は紫沈のほぼ中央に屋敷を構えている。沈の長い歴史の中では皇族から臣籍降下された所謂生まれも育ちも紫沈の貴族というものが存在したが、現在は言わずもがなだ。名誉貴族などは特に決まった場所に屋敷を構えていない。
汀彩城を除く城下のうち、旅人と行商で溢れかえる各門と貴族が住まう屋敷周辺の他は平民たちが暮らしているが、紫沈の中で最も人が過密になっているのは貧民街だ。
貧民街の中でもより重度の貧困者が暮らす辺りは自警団の目も届かないほど荒れており、中には死体と隣り合って暮らす者が居たりと病の発生源と呼ばれる地区になってしまっている。
あわい発生以後、貧民を救うのはよりいっそう困難になり半ば無法地帯となったここはしかし、ある一定の人間たちにとってはなくてはならないものとなっていた。
一体どこから調達してきたのか見事な短褐穿結を与えられ、旅装束から着替えた梅は紫沈にまで戻ってきていた。
雲朱で捕らわれたすぐ後の事である。梅は玲馨のように牢に繋がれる事はなかった。事情を説明されてすぐさま紫沈へ蜻蛉帰りさせられたのである。
紫沈の城壁を抜けるのには西門を利用したのだが、門衛は梅の隣に立つ男の顔を見ただけで旅券の確認も何者かを問われるような事もなく素通り出来てしまう。
「よっぽど念入りに鼻薬を嗅がせてるって? 西のお偉方はやる事が賢いねぇ」
嫌味たっぷりに言ってやったが少し先を歩く男からの反応はない。梅は短く舌打ちをして、男を見失わないよう歩調を早める。とは言え、その体格のおかげで目立つ大男を見失うような間抜けはそうそう居ないだろうが。
雲朱で自分の正体を玲馨だと偽った梅だったが拷問を受けるでも牢に入れられるでもなくこの銅像のような大男、関虎に連れられ東江の領主だという男の前に引っ立てられた。そこですぐに自分の正体が知られているのだと分かって恥じを掻いたのだが、領主の話を聞いているうちにそんなものはどうでもよくなっていた。
「おいあんた。あんたみたいなでけぇ男がこんなとこうろついてたんじゃ目立って仕方なかったろ。けど、俺ぁ城下で暮らしてた時あんたの噂なんざこれっぽっちも聞いた事なかったぜ?」
「俺は紫沈へ来るのは初めてだ」
「はぁ!? 初めて来るのに道案内しようってのか!?」
「雲朱でお前たちを捕らえた時も、初めて雲朱の市井に出た時だった」
「は……。そりゃすげぇ。頭ん中に沈の都市全部の地図が入ってるんじゃねぇか?」
「その通りだ」
もう言葉も出なかったので、後は黙って関虎の後ろをついていく。
関虎はとにかく愛想の悪いやつだった。玲馨と共に皇帝の宦官として付いている四郎を思わせる。
話す事は必要最低限。聞かれた事には答えるが雑談には付き合わずたちまち黙ってしまう四角四面ぶり。二人の違うところは、四郎は何を考えているか分からない底知れない雰囲気があるのに対して、こちらは命令にごく忠実な蘇智望の番犬である事。主に死ねと言われたら顔色一つ変えず即座に腹に剣を突き刺しそうだ。一言で言って、梅との相性は最悪だった。
西門の辺りは紫沈の中でも比較的閑静な雰囲気がある。南門ほど商店や露店はなく宿も無い。貴族の屋敷と平民の家とが近いためか、心なしか平民でさえも気位が高くてお淑やかな印象だ。仮にここで関虎と大立ち回りを演じても、観客は群がってこないだろうと思わせる澄ました空気を感じる。
梅は自警団に居た頃は古くは沈の元皇族たちが住んでいたとされる地区を担当していた。あちらは高貴な人間が住んでいたとは思えないほど下町風情のあるごちゃごちゃとした場所だ。紫沈の中だけでもこれだけ雰囲気が違うものかと城から出られない身になってから回る紫沈は妙に趣深く感じる。
関虎からすっかり興味が失せていた梅は、大男が足を止めたのにも気付かなかった。関虎の逞しい背中に鼻をぶつけそうになって慌てて足を止める。
「ここがそうなのか?」
「そうだ」
関虎は古びた倉庫のような小屋の前で立ち止まっていた。壊れたところに後から後から板を継ぎ足したような色がまだらな壁に禿げた瓦屋根は、城暮らしに馴染んだ梅の目には悲惨に映る。
もっともこの辺り一帯はどこも同じように古くて襤褸の掘っ立て小屋のような家屋がひしめきあう貧民街なので、目の前の小屋が特別そうという訳ではない。
「……ここに」
──ここに、常義が居る。
腰帯に提げた剣に勝手に手が伸びる。
騙され、罠に嵌められ、梅を罪人に仕立て上げた極悪人。妹はきっと一生残る傷を心に負った。あの時市井で起こっていた強盗や殺人にも常義が関わっていただろう。
「外で待っているか?」
ここに来て初めて関虎から質問というものをされ、梅の顔が歪む。
「やっとあんたから口を聞いたかと思えば、愚問じゃねぇか」
「お前は〈羊〉の頭領と面識があるんだろう。〈羊〉は郷間──間諜──の組織だ。必ず戦闘になる」
「この小屋の中で刃傷沙汰を起こしても構わねぇってんなら、答えは決まってる」
「そうか。官吏は切るな。奴らは〈羊〉ではない」
つまり官吏を殺す以外は好きにしろという意味だと受け取って、剣を鞘から抜き戸を開けても中からは見えない位置に立った。
小屋の壁は板を継ぎ接ぎしただけの粗末なもので、ところどころ隙間が空いている。そのうちの一つから中を覗く。
一方関虎は堂々と戸を開け中へ入っていく。断りも無く突然現れた闖入者に当然、男の誰何する声が飛んでくる。
「おいおい、人様のおうちに無言で入ってくるとはどんな了見だ?」
「いや待て。まさかお前は……」
「関虎だ。俺がここへ来た理由の説明が必要か?」
正直に名乗った事に一瞬驚いたが、この石部金吉が何かを偽るような姿を想像する方がよほど難しいかと思い直す。
「……なるほどな。蘇智望がジャンをかけたか」
その声を聞いた瞬間、梅の頭にカッと血が上る。
壁の隙間の向こうには襤褸の卓があり、それを複数の男たちが囲んでいる。常義は卓の最も奥に座っているようだった。舶来の品だろう、細長い筒のようなものを口に当ててそれを吸っているように見える。
「理解しているなら今すぐ果てろ。それが怖いというなら俺が手伝ってやろう」
主のために死ねと言われたところで、納得して首を差し出す忠誠心のある者などこの場には居なかったようだ。各々武器を構えじりじりと移動しながら関虎を囲んでいく。
「やはり胡安の言う事は嘘だったか。それとも、あの男もお前の飼い主に騙されていたのか?」
常義の挑発に、関虎は反応を示さなかった。
どこか関虎を蔑むようだった常義の目付きが変わる。
梅は手の中の剣を強く握りしめた。
「──死ね、関虎」
常義が低く呟いた瞬間、武器を構えていた男たちが一斉に関虎へと襲い掛かる。
一方、小屋の中には武芸に覚えのない者も居るようで護身用の短剣を持ちはしているものの端に寄って怯えていた。全部で三人、恐らくは官吏だろう男たちは関虎の隙を窺ってそろりと小屋から逃げ出そうとしていた。
「小屋の外で死なれちゃ、死体が目立っちまうな。お前は官吏か?」
「ち、違う! 俺は官吏なんかじゃない!」
「そうかよ」
梅は一番最初に逃げ出そうとしていた臆病者を躊躇なく切り伏せる。すると残りの二人は悲鳴を上げて尻もちをつき、足を縺れさせながら尻を引きずって再び小屋の奥へと下がっていった。
二人を追って梅も中へ突入すると、悠々と一番奥に座っていた常義が梅に気付く。
「……『宦官』は、帝の所有物じゃなかったか? 部屋の貸主を斬り殺して、今度は皇帝を裏切るのか。大した傑物だな羅清」
関虎が一瞬だけ梅を振り返る。その一瞬に特別何かの表情は浮かんでおらず、ただ淡々と主命に従い〈羊〉の男たちを斬っていく。その徹底した仕事ぶりに、悔しい事に上っていた血が下りていくのが分かった。
「常義、お前は禁軍を辞めて自警団に入って、一体何がしたかったんだ。何のために犯罪なんてやりやがった。……妹を、傷つけた。死ぬ前に、話せ。全部だ」
常義を殺してもきっと、心がすっきりと晴れる事はないだろう。だがこの降って湧いたような機会をみすみす逃して、不殺の偽善を掲げる気も毛頭なかった。
関虎によって小屋の中に居た〈羊〉の掃討は終わっていた。転がされた死体から、噎せ返るような血の匂いが小屋に充満している。常義の居る奥に向かって歩くと、靴の底が血溜まりを踏みつけべちゃりと音が鳴った。
「常義」
「一族の復興だ。そのために自警団を牛耳れと胡安に言われた。目的を果たせば常家の家格を元に戻すよう陛下に進言する。その頃には東江が沈の政の中心にいると、奴は豪語していた」
梅は知らないが胡安は沈の高官の名だ。〈羊〉を取りまとめて動かしていたのは常義だが、その陰には常義よりも上の立場の人間が居た。
常義は胡安に命じられるまま自警団の団長となるために、当時自警団の中で次期隊長として、そしてゆくゆくは団を率いていく統率者として人望と期待を集めていた梅をどうにか自警団から追い出す必要があった。そのために常義は、とある官吏の起こした強盗や殺人を庇わせ梅を犯人に仕立て上げるという筋書きを描いた。
それはまんまと常義の思い通りになり、彼は現在自警団の団長という肩書を得ている。
「お前そのものに特別な恨みはなかったよ。同門のよしみとして振る舞ってはいたが、そんなもの口から出まかせだ。まぁ、計画のために身に覚えのない罪で引っ立てられるお前は気の毒だったかな」
殺せ──と梅の感情が騒ぎ立てる。
「ああ、でも、良かったなぁ。お前の妹は〈羊〉の男が懸想していたんで、そいつに助けられて逃げていったよ。本当は俺たちで輪姦してやるつもりだったんだがなぁ。ハハ……ハハハッ」
常義は何が可笑しいのか突然気が狂ったように笑い出す。得意の槍を構えようともせず、椅子に座ったまま天を仰いで大声で笑っている。
梅の右腕が勝手に剣を持ち上げていた。もはや梅の方を見ていないその男を殺すのは、とても簡単な事だった。
*
梅が常義と対峙していた時から間もなく汪軍の先頭が西門に到着するかという頃まで時は進む。
場所は蔵書楼の露台、地図と実際の外の景色とをじっくり比較させながら、四郎は于雨に力を使わせようとしていた。狙いは汪軍の紫沈侵入の阻止だったが、分断でも出来れば上々のはずだった。
しかし──。
「す、すみませんっ」
于雨はじわりと額に汗を浮かべて地図と外を交互に見比べている。于雨はその身に宿っているはずの操脈の力を全く使いこなせなかった。
地脈の流れはしっかりと読み取れているようなのだが、その流れを自分自身で制御するという事が上手く想像出来ないようだ。
脈読した地脈の流れを地図に再現する技術は才能であり訓練して身につけるものではないと、四郎は教わって来た。門外不出の教本にもそのように書いてあった事を記憶している。
于雨は卜師ではない。だから卜師と同じ技を扱えなくとも問題無いと考えていたが、于雨にとっては操脈するために地図上で地脈の流れを可視化させた方が良いのかも知れない。
しかし今はそれをさせてやるための時が無かった。是が非でも彼はその力で汪軍を断たなくては、この先の于雨の未来を汪に支配されるのは必定なのだ。
「あの……、す、少し、休ませてあげて下さい」
か細くて弱々しい声が四郎に怯えながらもはっきりとその意思を伝えた。子珠だ。びっしりと額に汗を掻いて、並ぶ瑠璃瓦の先を見つめる于雨の手を握り子珠は必死に訴える。
「浄身した傷もまだ、癒えてなくて、于雨が、た、倒れて、しまいます……!」
子珠に言われずとも、地脈を読める四郎には今于雨の身にどれだけ負担がかかっているのかを、おおよそ読む事が出来る。続けさせるのは確かに危険だろう。
この国の大地、大気、それから人や獣や植物に至るまで全てに流れる地脈をちっぽけな人の体で感じ読み取るのが脈読だ。より精緻に読もうとすれば、膨大な地脈の流れが自分の意識を浚って流されてしまいそうな感覚に陥る事もある。地脈を読む、というだけでも大変な事だ。
そして于雨にやらせようとしている操脈は、うねるようでもあり真っ直ぐなようでもある縦横無尽な地脈を正確に把握した上で、その大きな流れの一部を機を織るようにして己の手で作り変えるようなものだ。簡単ではない事は四郎も重々承知していた。
「于雨」
水の入った皮革の袋を于雨に渡し、于雨には地図を見るよう言いつける。頭の中に沈の国が思い描けない事には、自分が感じている地脈の流れが一体どこのものかなど分かろうはずもない。
四郎は于雨たちを露台に残し、自分は禁書室の中へと入っていく。事ここに至って皇帝だけが継ぐ操脈の力について記した文献などが出てくるとは考えていない。玲馨と共に調べた時に見つけた物については全て彼が持っていった。今頃は黄麟宮の皇帝の寝所にでも積まれている事だろう。それでも見つけそこねた文献が出てこないとも限らない。
于雨が力を正しく使うためには何か手順などを知る必要があるのかも知れない。少しでも手掛かりが見つかればと考えて、于雨を休ませる間四郎は禁書室の中を探して回った。
汪軍が現れてから二時辰ほど過ぎただろうか。外から聞こえてくる喧騒が近くなっている。露台から見える範囲で官吏が荷物を抱えて逃げてゆく姿に混じり、後方支援の兵士が忙しなく走り回っている。
ひょっとすると西門が破られたのかも知れない。あの付近は西に縁のある貴族が住んでいる。四郎のように事前に襲撃を知らされていたなら開門のために協力するだろう。自警団が金軍に味方する事もない。あれは今ではすっかり東江の手勢のようなものに成り下がった。
「これが、兄の見たかったものなのだろうか……」
四郎がふと溢した言葉は、誰に聞かれる事もなく喧騒に紛れて消えていく。
四郎は汪軍と合流しない事を選択をした。それは四郎にとって生家と対立する立場を決めた事になる。
今頃汪の当主、汪宵白は四郎が姿を現さないので焦れ始めている頃だろう。〈羊〉の手の者に探させているかも知れない。
禁書室には鍵がある。先日入った時に細工をしておいたおかげで再び訪れるのは簡単だったが、その代わりに鍵を閉める事は出来なくなってしまった。見つかるのも時間の問題だろう。
このまま于雨が力を使えないままなら、逃げる先を考えなくてはならない。
黄麟宮は万が一汪軍が禁軍に競り勝ち宮廷に雪崩れ込んでくるような事があればそこで捕まってお仕舞いだ。紅桃宮も同様の理由で却下だ。
もちろん城の外や紫沈の外にまで出ていくのは得策ではない。非常時であるからこそ城の出入りは常より更に厳しくなっているだろう。禁軍に捕まっても汪軍に捕まってもやはり四郎たちの道は閉ざされる。
「残すは一つか」
幼い少年宦官の形をした兵器とも呼べる力を匿うなら、最後に勝利を掴むこの国の「未来」の元が最も相応しいのではないか。
于雨は「勝者の証」だ。汪軍の侵攻をきっかけに始まった戦いの最後に立っていた者にこそ、于雨を所持する権利があるだろう。
「于雨、子珠、移動するぞ」
少年と少女は顔を見合わせる。ぐったりと濃い疲労のおかげで于雨の表情は今ひとつ分かりにくいが、子珠の方ははっきりと不安が表れている。今の自分たちがどんな状況に置かれているのか分かっていないのだろう。しかし分からない事を不安に感じるのであれば、この少女は決して愚鈍ではないという事だ。
于雨はこの先、何者にも害されない確固とした人格を磨いていかなくてはならない。だが、所詮は人である以上、ある一定の負荷を与えられたら屈する外なくなる。ならばその時、彼の理解者が傍に居る事はきっと悪い事ではないはずだ。
子珠を連れてきてしまった事が今後どんな風に影響していくかは誰にも分からない。十年、二十年後に子珠のために于雨が馬鹿な選択をする日が来るかも知れない。
その時、果たして四郎は後悔するのだろうか。ほんの昨日までの自分なら、後悔は無いと確信出来ただろう。だが今となっては最早自分の事なのに少し先の自分の行動でさえ予測できなくなってしまった。今まさに生家である汪を裏切ろうとしている事と同じように。
*
太陽は厚い雲の向こうに隠れ、海面は白波が立っている。船体は時々大きく揺れて、船酔いに喘ぐ者が一人、二人。
往路はあんなにも清々しい青空だったのに、一日経った今日は晴天の海原など見る影もない。
「航海士の話では嵐にはならず夜には収まるみたいです」
出航の準備が出来たと報せに来た東江の兵士を下がらせた後、蘇智望は問う。
「これから紫沈へ向かう。そなたも着いてくるか? 玲馨」
紫沈は基本的に「門」に近付くほど栄えている。まずは午門から北に位置する東沈と西沈を含む汀彩城だ。皇帝の居所である黄麟宮を始めとした宮殿と、妃や皇子、公主が暮らす後宮は、建材から職人に至るまで一切費用を惜しまず造り上げた贅の庭である。他には政の中心となる外廷や禁軍の詰めている兵舎など、紫沈の半分以上を汀彩城が占めている。
次に東西南の三方に構える門の周辺には座商行商問わず商人たちが商いをする地区で、更に地方との行き交いも多く賑やかな場所だ。
そして商人たちの地区より内側に入ると東西南の地方出身の貴族たちの屋敷が軒を連ねており、北の貴族は紫沈のほぼ中央に屋敷を構えている。沈の長い歴史の中では皇族から臣籍降下された所謂生まれも育ちも紫沈の貴族というものが存在したが、現在は言わずもがなだ。名誉貴族などは特に決まった場所に屋敷を構えていない。
汀彩城を除く城下のうち、旅人と行商で溢れかえる各門と貴族が住まう屋敷周辺の他は平民たちが暮らしているが、紫沈の中で最も人が過密になっているのは貧民街だ。
貧民街の中でもより重度の貧困者が暮らす辺りは自警団の目も届かないほど荒れており、中には死体と隣り合って暮らす者が居たりと病の発生源と呼ばれる地区になってしまっている。
あわい発生以後、貧民を救うのはよりいっそう困難になり半ば無法地帯となったここはしかし、ある一定の人間たちにとってはなくてはならないものとなっていた。
一体どこから調達してきたのか見事な短褐穿結を与えられ、旅装束から着替えた梅は紫沈にまで戻ってきていた。
雲朱で捕らわれたすぐ後の事である。梅は玲馨のように牢に繋がれる事はなかった。事情を説明されてすぐさま紫沈へ蜻蛉帰りさせられたのである。
紫沈の城壁を抜けるのには西門を利用したのだが、門衛は梅の隣に立つ男の顔を見ただけで旅券の確認も何者かを問われるような事もなく素通り出来てしまう。
「よっぽど念入りに鼻薬を嗅がせてるって? 西のお偉方はやる事が賢いねぇ」
嫌味たっぷりに言ってやったが少し先を歩く男からの反応はない。梅は短く舌打ちをして、男を見失わないよう歩調を早める。とは言え、その体格のおかげで目立つ大男を見失うような間抜けはそうそう居ないだろうが。
雲朱で自分の正体を玲馨だと偽った梅だったが拷問を受けるでも牢に入れられるでもなくこの銅像のような大男、関虎に連れられ東江の領主だという男の前に引っ立てられた。そこですぐに自分の正体が知られているのだと分かって恥じを掻いたのだが、領主の話を聞いているうちにそんなものはどうでもよくなっていた。
「おいあんた。あんたみたいなでけぇ男がこんなとこうろついてたんじゃ目立って仕方なかったろ。けど、俺ぁ城下で暮らしてた時あんたの噂なんざこれっぽっちも聞いた事なかったぜ?」
「俺は紫沈へ来るのは初めてだ」
「はぁ!? 初めて来るのに道案内しようってのか!?」
「雲朱でお前たちを捕らえた時も、初めて雲朱の市井に出た時だった」
「は……。そりゃすげぇ。頭ん中に沈の都市全部の地図が入ってるんじゃねぇか?」
「その通りだ」
もう言葉も出なかったので、後は黙って関虎の後ろをついていく。
関虎はとにかく愛想の悪いやつだった。玲馨と共に皇帝の宦官として付いている四郎を思わせる。
話す事は必要最低限。聞かれた事には答えるが雑談には付き合わずたちまち黙ってしまう四角四面ぶり。二人の違うところは、四郎は何を考えているか分からない底知れない雰囲気があるのに対して、こちらは命令にごく忠実な蘇智望の番犬である事。主に死ねと言われたら顔色一つ変えず即座に腹に剣を突き刺しそうだ。一言で言って、梅との相性は最悪だった。
西門の辺りは紫沈の中でも比較的閑静な雰囲気がある。南門ほど商店や露店はなく宿も無い。貴族の屋敷と平民の家とが近いためか、心なしか平民でさえも気位が高くてお淑やかな印象だ。仮にここで関虎と大立ち回りを演じても、観客は群がってこないだろうと思わせる澄ました空気を感じる。
梅は自警団に居た頃は古くは沈の元皇族たちが住んでいたとされる地区を担当していた。あちらは高貴な人間が住んでいたとは思えないほど下町風情のあるごちゃごちゃとした場所だ。紫沈の中だけでもこれだけ雰囲気が違うものかと城から出られない身になってから回る紫沈は妙に趣深く感じる。
関虎からすっかり興味が失せていた梅は、大男が足を止めたのにも気付かなかった。関虎の逞しい背中に鼻をぶつけそうになって慌てて足を止める。
「ここがそうなのか?」
「そうだ」
関虎は古びた倉庫のような小屋の前で立ち止まっていた。壊れたところに後から後から板を継ぎ足したような色がまだらな壁に禿げた瓦屋根は、城暮らしに馴染んだ梅の目には悲惨に映る。
もっともこの辺り一帯はどこも同じように古くて襤褸の掘っ立て小屋のような家屋がひしめきあう貧民街なので、目の前の小屋が特別そうという訳ではない。
「……ここに」
──ここに、常義が居る。
腰帯に提げた剣に勝手に手が伸びる。
騙され、罠に嵌められ、梅を罪人に仕立て上げた極悪人。妹はきっと一生残る傷を心に負った。あの時市井で起こっていた強盗や殺人にも常義が関わっていただろう。
「外で待っているか?」
ここに来て初めて関虎から質問というものをされ、梅の顔が歪む。
「やっとあんたから口を聞いたかと思えば、愚問じゃねぇか」
「お前は〈羊〉の頭領と面識があるんだろう。〈羊〉は郷間──間諜──の組織だ。必ず戦闘になる」
「この小屋の中で刃傷沙汰を起こしても構わねぇってんなら、答えは決まってる」
「そうか。官吏は切るな。奴らは〈羊〉ではない」
つまり官吏を殺す以外は好きにしろという意味だと受け取って、剣を鞘から抜き戸を開けても中からは見えない位置に立った。
小屋の壁は板を継ぎ接ぎしただけの粗末なもので、ところどころ隙間が空いている。そのうちの一つから中を覗く。
一方関虎は堂々と戸を開け中へ入っていく。断りも無く突然現れた闖入者に当然、男の誰何する声が飛んでくる。
「おいおい、人様のおうちに無言で入ってくるとはどんな了見だ?」
「いや待て。まさかお前は……」
「関虎だ。俺がここへ来た理由の説明が必要か?」
正直に名乗った事に一瞬驚いたが、この石部金吉が何かを偽るような姿を想像する方がよほど難しいかと思い直す。
「……なるほどな。蘇智望がジャンをかけたか」
その声を聞いた瞬間、梅の頭にカッと血が上る。
壁の隙間の向こうには襤褸の卓があり、それを複数の男たちが囲んでいる。常義は卓の最も奥に座っているようだった。舶来の品だろう、細長い筒のようなものを口に当ててそれを吸っているように見える。
「理解しているなら今すぐ果てろ。それが怖いというなら俺が手伝ってやろう」
主のために死ねと言われたところで、納得して首を差し出す忠誠心のある者などこの場には居なかったようだ。各々武器を構えじりじりと移動しながら関虎を囲んでいく。
「やはり胡安の言う事は嘘だったか。それとも、あの男もお前の飼い主に騙されていたのか?」
常義の挑発に、関虎は反応を示さなかった。
どこか関虎を蔑むようだった常義の目付きが変わる。
梅は手の中の剣を強く握りしめた。
「──死ね、関虎」
常義が低く呟いた瞬間、武器を構えていた男たちが一斉に関虎へと襲い掛かる。
一方、小屋の中には武芸に覚えのない者も居るようで護身用の短剣を持ちはしているものの端に寄って怯えていた。全部で三人、恐らくは官吏だろう男たちは関虎の隙を窺ってそろりと小屋から逃げ出そうとしていた。
「小屋の外で死なれちゃ、死体が目立っちまうな。お前は官吏か?」
「ち、違う! 俺は官吏なんかじゃない!」
「そうかよ」
梅は一番最初に逃げ出そうとしていた臆病者を躊躇なく切り伏せる。すると残りの二人は悲鳴を上げて尻もちをつき、足を縺れさせながら尻を引きずって再び小屋の奥へと下がっていった。
二人を追って梅も中へ突入すると、悠々と一番奥に座っていた常義が梅に気付く。
「……『宦官』は、帝の所有物じゃなかったか? 部屋の貸主を斬り殺して、今度は皇帝を裏切るのか。大した傑物だな羅清」
関虎が一瞬だけ梅を振り返る。その一瞬に特別何かの表情は浮かんでおらず、ただ淡々と主命に従い〈羊〉の男たちを斬っていく。その徹底した仕事ぶりに、悔しい事に上っていた血が下りていくのが分かった。
「常義、お前は禁軍を辞めて自警団に入って、一体何がしたかったんだ。何のために犯罪なんてやりやがった。……妹を、傷つけた。死ぬ前に、話せ。全部だ」
常義を殺してもきっと、心がすっきりと晴れる事はないだろう。だがこの降って湧いたような機会をみすみす逃して、不殺の偽善を掲げる気も毛頭なかった。
関虎によって小屋の中に居た〈羊〉の掃討は終わっていた。転がされた死体から、噎せ返るような血の匂いが小屋に充満している。常義の居る奥に向かって歩くと、靴の底が血溜まりを踏みつけべちゃりと音が鳴った。
「常義」
「一族の復興だ。そのために自警団を牛耳れと胡安に言われた。目的を果たせば常家の家格を元に戻すよう陛下に進言する。その頃には東江が沈の政の中心にいると、奴は豪語していた」
梅は知らないが胡安は沈の高官の名だ。〈羊〉を取りまとめて動かしていたのは常義だが、その陰には常義よりも上の立場の人間が居た。
常義は胡安に命じられるまま自警団の団長となるために、当時自警団の中で次期隊長として、そしてゆくゆくは団を率いていく統率者として人望と期待を集めていた梅をどうにか自警団から追い出す必要があった。そのために常義は、とある官吏の起こした強盗や殺人を庇わせ梅を犯人に仕立て上げるという筋書きを描いた。
それはまんまと常義の思い通りになり、彼は現在自警団の団長という肩書を得ている。
「お前そのものに特別な恨みはなかったよ。同門のよしみとして振る舞ってはいたが、そんなもの口から出まかせだ。まぁ、計画のために身に覚えのない罪で引っ立てられるお前は気の毒だったかな」
殺せ──と梅の感情が騒ぎ立てる。
「ああ、でも、良かったなぁ。お前の妹は〈羊〉の男が懸想していたんで、そいつに助けられて逃げていったよ。本当は俺たちで輪姦してやるつもりだったんだがなぁ。ハハ……ハハハッ」
常義は何が可笑しいのか突然気が狂ったように笑い出す。得意の槍を構えようともせず、椅子に座ったまま天を仰いで大声で笑っている。
梅の右腕が勝手に剣を持ち上げていた。もはや梅の方を見ていないその男を殺すのは、とても簡単な事だった。
*
梅が常義と対峙していた時から間もなく汪軍の先頭が西門に到着するかという頃まで時は進む。
場所は蔵書楼の露台、地図と実際の外の景色とをじっくり比較させながら、四郎は于雨に力を使わせようとしていた。狙いは汪軍の紫沈侵入の阻止だったが、分断でも出来れば上々のはずだった。
しかし──。
「す、すみませんっ」
于雨はじわりと額に汗を浮かべて地図と外を交互に見比べている。于雨はその身に宿っているはずの操脈の力を全く使いこなせなかった。
地脈の流れはしっかりと読み取れているようなのだが、その流れを自分自身で制御するという事が上手く想像出来ないようだ。
脈読した地脈の流れを地図に再現する技術は才能であり訓練して身につけるものではないと、四郎は教わって来た。門外不出の教本にもそのように書いてあった事を記憶している。
于雨は卜師ではない。だから卜師と同じ技を扱えなくとも問題無いと考えていたが、于雨にとっては操脈するために地図上で地脈の流れを可視化させた方が良いのかも知れない。
しかし今はそれをさせてやるための時が無かった。是が非でも彼はその力で汪軍を断たなくては、この先の于雨の未来を汪に支配されるのは必定なのだ。
「あの……、す、少し、休ませてあげて下さい」
か細くて弱々しい声が四郎に怯えながらもはっきりとその意思を伝えた。子珠だ。びっしりと額に汗を掻いて、並ぶ瑠璃瓦の先を見つめる于雨の手を握り子珠は必死に訴える。
「浄身した傷もまだ、癒えてなくて、于雨が、た、倒れて、しまいます……!」
子珠に言われずとも、地脈を読める四郎には今于雨の身にどれだけ負担がかかっているのかを、おおよそ読む事が出来る。続けさせるのは確かに危険だろう。
この国の大地、大気、それから人や獣や植物に至るまで全てに流れる地脈をちっぽけな人の体で感じ読み取るのが脈読だ。より精緻に読もうとすれば、膨大な地脈の流れが自分の意識を浚って流されてしまいそうな感覚に陥る事もある。地脈を読む、というだけでも大変な事だ。
そして于雨にやらせようとしている操脈は、うねるようでもあり真っ直ぐなようでもある縦横無尽な地脈を正確に把握した上で、その大きな流れの一部を機を織るようにして己の手で作り変えるようなものだ。簡単ではない事は四郎も重々承知していた。
「于雨」
水の入った皮革の袋を于雨に渡し、于雨には地図を見るよう言いつける。頭の中に沈の国が思い描けない事には、自分が感じている地脈の流れが一体どこのものかなど分かろうはずもない。
四郎は于雨たちを露台に残し、自分は禁書室の中へと入っていく。事ここに至って皇帝だけが継ぐ操脈の力について記した文献などが出てくるとは考えていない。玲馨と共に調べた時に見つけた物については全て彼が持っていった。今頃は黄麟宮の皇帝の寝所にでも積まれている事だろう。それでも見つけそこねた文献が出てこないとも限らない。
于雨が力を正しく使うためには何か手順などを知る必要があるのかも知れない。少しでも手掛かりが見つかればと考えて、于雨を休ませる間四郎は禁書室の中を探して回った。
汪軍が現れてから二時辰ほど過ぎただろうか。外から聞こえてくる喧騒が近くなっている。露台から見える範囲で官吏が荷物を抱えて逃げてゆく姿に混じり、後方支援の兵士が忙しなく走り回っている。
ひょっとすると西門が破られたのかも知れない。あの付近は西に縁のある貴族が住んでいる。四郎のように事前に襲撃を知らされていたなら開門のために協力するだろう。自警団が金軍に味方する事もない。あれは今ではすっかり東江の手勢のようなものに成り下がった。
「これが、兄の見たかったものなのだろうか……」
四郎がふと溢した言葉は、誰に聞かれる事もなく喧騒に紛れて消えていく。
四郎は汪軍と合流しない事を選択をした。それは四郎にとって生家と対立する立場を決めた事になる。
今頃汪の当主、汪宵白は四郎が姿を現さないので焦れ始めている頃だろう。〈羊〉の手の者に探させているかも知れない。
禁書室には鍵がある。先日入った時に細工をしておいたおかげで再び訪れるのは簡単だったが、その代わりに鍵を閉める事は出来なくなってしまった。見つかるのも時間の問題だろう。
このまま于雨が力を使えないままなら、逃げる先を考えなくてはならない。
黄麟宮は万が一汪軍が禁軍に競り勝ち宮廷に雪崩れ込んでくるような事があればそこで捕まってお仕舞いだ。紅桃宮も同様の理由で却下だ。
もちろん城の外や紫沈の外にまで出ていくのは得策ではない。非常時であるからこそ城の出入りは常より更に厳しくなっているだろう。禁軍に捕まっても汪軍に捕まってもやはり四郎たちの道は閉ざされる。
「残すは一つか」
幼い少年宦官の形をした兵器とも呼べる力を匿うなら、最後に勝利を掴むこの国の「未来」の元が最も相応しいのではないか。
于雨は「勝者の証」だ。汪軍の侵攻をきっかけに始まった戦いの最後に立っていた者にこそ、于雨を所持する権利があるだろう。
「于雨、子珠、移動するぞ」
少年と少女は顔を見合わせる。ぐったりと濃い疲労のおかげで于雨の表情は今ひとつ分かりにくいが、子珠の方ははっきりと不安が表れている。今の自分たちがどんな状況に置かれているのか分かっていないのだろう。しかし分からない事を不安に感じるのであれば、この少女は決して愚鈍ではないという事だ。
于雨はこの先、何者にも害されない確固とした人格を磨いていかなくてはならない。だが、所詮は人である以上、ある一定の負荷を与えられたら屈する外なくなる。ならばその時、彼の理解者が傍に居る事はきっと悪い事ではないはずだ。
子珠を連れてきてしまった事が今後どんな風に影響していくかは誰にも分からない。十年、二十年後に子珠のために于雨が馬鹿な選択をする日が来るかも知れない。
その時、果たして四郎は後悔するのだろうか。ほんの昨日までの自分なら、後悔は無いと確信出来ただろう。だが今となっては最早自分の事なのに少し先の自分の行動でさえ予測できなくなってしまった。今まさに生家である汪を裏切ろうとしている事と同じように。
*
太陽は厚い雲の向こうに隠れ、海面は白波が立っている。船体は時々大きく揺れて、船酔いに喘ぐ者が一人、二人。
往路はあんなにも清々しい青空だったのに、一日経った今日は晴天の海原など見る影もない。
「航海士の話では嵐にはならず夜には収まるみたいです」
出航の準備が出来たと報せに来た東江の兵士を下がらせた後、蘇智望は問う。
「これから紫沈へ向かう。そなたも着いてくるか? 玲馨」
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
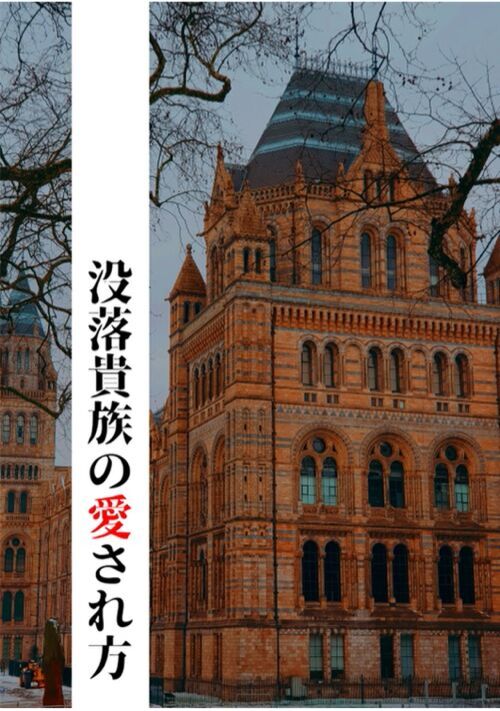
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















