39 / 44
完結編
39運命の鐘
しおりを挟む
カーン、カーン、とけたたましく鐘が鳴る。
始めは誰もが火事を疑った。数日前にも鳴った鐘は、沈の歴史でも百年余り例が無かった「敵兵」の出現を告げたのだ。今度こそ火事か、そうでなければ雨の影響で水路が溢れたかのどちらかだと思うのも無理はなかった。
宮廷に詰めていた官吏たちもやはり火事を心配した。小降りになった雨空の下に走り出てきて、手で庇を作りながら空を見上げる。
煙は立っていない。何分この雨で火事は起きても火がついた傍からたちまち消えていく事だろう。
ならば水害だろうか。城内に流れる堀は多少水位が増しているようだが、市井の方はもっと酷いのだろうか。
カーン、カーン、と鐘は鳴り止まない。
そのうち伝令兵が走っていくのが見えて官吏たちがざわつき始める。伝令は軍の兵舎がある方角へと走っていくではないか。
「まさか、また敵が現れたとでもいうのか……?」
誰かが疑心暗鬼に呟くと、一呼吸の間をあけてからドッと笑いが沸き起こった。
まさか、そんなはずがない、冗談はほどほどにしてくれ。
官吏たちは口々に言い合っては頬を引き攣らせたが、やがて伝令兵が彼らのもとにもやってくると血相を変えて蜘蛛の子を散らすように各々逃げ出した。
もう城には居られない。家に帰ろう。
いいや城の奥で隠れていよう。敵も見つけられないような所でやり過ごすのだ──。
思い思いの場所へ三々五々と散っていく官吏に、もはや城を、紫沈を、守らなくてはという大義は微塵もなくなっていた。
*
見張りの兵から兵舎に詰めていた亥壬たちの元に敵兵の出現が伝わると、状況を確かめるべく数名の兵が外へ出て行った。
「まさか汪軍への援軍か!?」
「落ち着いて下さい緑歳兄上。すぐに兵が──」
亥壬が言い終えるより早くに駆け込んできた兵士は血相を変えてこう報告する。「西方に白旗に虎を確認致しました」
「東江の軍だ。今度こそ正規軍という訳か。腕の見せ所だな亥壬!」
「興奮しないで下さい! 事は試合とは訳が違うのですよ!」
「そう言うお前の方が声がでかいがな」
「うるさいです!」
亥壬と緑歳は生まれた日がほとんど違わないので、亥壬はどうしても緑歳に対して遠慮というものをしなくなる。緑歳も特にそれを咎めようとはしないので、昔から二人の仲の良さは後宮では知らぬ人がないくらいだ。
亥壬は緑歳を無視して伝令に言う。「前線の李将軍にも報告を。恐らく東江の本隊です」
現在雨のせいで汪軍との戦いは一時中断されていたが、小降りになった事で両軍機を窺っているところだった。瓦解寸前の汪軍など最早敵ではなく、物量によって強引に押さえつけてしまえるというところまで来ていた。
そこへ援軍が到着してしまっては再び状況が拮抗するかも知れない。何としてでも分断したいところだが、そのためには西以外の門から部隊を外に出して大きく城外を回らせて本隊と汪軍の間に出るか、或いは本隊の横や背後をつかなくてはならない。しかし、この雨で視界の悪い中、物見が旗の色だけでなく「虎」を目視出来るほどの距離まで近付いて来ているとなると、もう間に合わないだろう。
そも汪軍を城の外から挟み撃ちにしなかったのも、本隊の援軍や別働隊が伏せられている可能性を考慮した結果だったのだ。
「内乱となると全方位を警戒しなくてはならない汀彩城は、攻めるに易く守るに難い城です。禁軍の数も全く足りていない。その上、戊陽兄上が東に遠征なさっていた隙をついてきたのですから、恐らく西は北と結託していたのでしょうね。本隊を出してくる事も概ね想定内ですよ」
援軍の出現によって兵舎は騒々しくなる中、亥壬は冷静だった。淡々と考えを語り、緑歳がうんうんとさも心得ているように頷く。
「皇居のある北はまた別格ですが、汀彩城も紫沈の街も、西からの侵略には一応の備えとして砦や門が丈夫に設計されています。他国と言えば遥か西方の昆しかありませんから。しかし既に汪と紫沈の貴族が手を結んで中から門を開けられてしまった以上、これからの作戦は失敗から開始する事になりますが……」
北門から戊陽が帰還した報せを受けた直後、北門も固く閉じられこれで西門以外の門は全てその門扉を閉ざした事になる。後はどうにか西門さえ閉じてしまえば──。
「──籠城が成る。例え本隊が合流したところで未だ数的には禁軍が圧倒的に有利なのです。城攻めには三倍の数の兵が必要だと書で読んだ事があります。加えて外には天然の要害である『あわい』だってあるんです。夜にはあわいの妖魔を相手にしながら、昼には城から矢を射掛けられながら攻め続けなければならない。僕たちは城に籠もっているだけで勝てるんです。勝てる戦いのはずなのです」
そうは言いながらも亥壬の表情は優れない。卓の上に広げられた地図をじっと見下ろしながら、ずっと何かを考え続けており、亥壬の指は摩擦熱で火傷を起こしである。
「亥壬、とにかく我らは汪軍を西門付近から追い出してしまう事が急務なのだな」
「そうです」
「では、俺に一個大隊とは言わないからいくらか兵を預けてくれ」
「緑歳兄上、まさか」
「俺は前線へ行くぞ」
緑歳は戦いとなると猪のような男で、力任せに相手をねじ伏せるのは得手だが、そこに罠が仕掛けられたら天晴れなほどに嵌る人である。汪軍を単純に城外まで押し返すという戦法を取るとなった時、緑歳はきっと強大な力を発揮してくれる事だろう。禁軍内でも評判の緑歳の姿が見えれば、兵の士気も上がるはずだ。
亥壬には緑歳の出陣を止めるだけの理屈が思いつかなかった。
「死なないで下さい」
「無論だ」
「死んだら、総指揮なんてやめて僕も後を追います」
「む、それは良くないぞ亥壬」
「冗談ですよ」
「俺は冗談じゃない。弟を悲しませるような兄にはならんぞ」
緑歳の左手が幼少の頃の癖で亥壬の頭を撫でようとしたが寸でで止まる。頭を撫でる代わりにその手は固く拳を握り込み、亥壬の胸に当てられた。
「必ず戻る」
難しい顔をしていた亥壬の表情が一瞬くしゃりと歪んだが、きつく唇を引き結んで亥壬は無言で頷いた。
緑歳が兵を率いて出て行く姿を見送って、籠城のために亥壬が手筈を整えようとした時だった。
カーン、カーンと鐘が鳴る。鐘は鳴ったが煙はどこにも見当たらない。まして水路が決壊した訳でもない。
「伝令ー! 南門より赤旗に朱雀の軍勢を捕捉!」
*
「互いに叶わぬ恋に盲いた者同士、本懐を遂げようではないか」
蘇智望の言葉に反論する気は一切起きなかった。彼の言葉に酷く納得して、玲馨は初めて自分の心にあったものを形容させた。
形にしてみれば案外何でもないもので、どこにでもあるし誰でも焦がれたり破れたり、或いは溺れたりするような普遍的なものだった。なにも自分の中にあるものが他と比べて特別なものだと思っていた訳ではないが、ずっと身分を理由に形を取ってはいけないものだと思い込んでいた。
これが初めての自覚だった訳ではない。例えば草むらから猫の耳だけが飛び出して見えているのを猫だと知りながら、草をかき分けてまで追いかけるのを野暮だというような、そんな感覚。自己満足に近いものだ。けれど、他人の手によって草が刈られたら、やはりそこに居たのは猫でしかなかった。それと同じようなもので「やっぱり」というある種安心に似た感情に包まれただけだった。
名前を付けず、形を認めなかったせいでふわふわと浮いていたものが、とうとう地に足をつけた。それだけだ。これが叶わぬもの、叶ってはいけないものであることも、玲馨はよく知っていた。
蘇智望との会話を終えた後、蘇智望は玲馨に監視をつけた。変わらず甲板に出るのは自由のままだが、玲馨の部屋の外には屈強な兵が見張りに立っている。
しかしもはや甲板どころか部屋の外にも出ようという気は起こりそうにないので、不要の人手になるかも知れない。
玲馨は与えられた部屋の中で蘇智望から聞かされた今の状況と今後の作戦を頭の中で整理していた。
まず、蘇智望が玲馨を伴い軍と共に急な出港となったのは、分家である汪家が勝手に紫沈へ続く森を突破したという情報が入ったからだ。
蘇智望はそれを止めるためにまず西から東江本隊に汪軍を追わせた。その指揮には何とあの風蘭がつけられているらしいが、実権は別の蘇智望の手の者が握っているのだろう。
しかし、西から紫沈へ向かうのが本隊だとすると現在五隻の船に乗っている兵士たちは一体何者だろうか。目算では一隻辺り千人近くが乗っているが、東江の兵数も記憶の通りならば山芒とそう変わらないはずだ。四千か多くとも五、六千のはずで、しかし船に乗る兵士たちの体付きは決して農民のそれではない。
これに対し蘇智望は自嘲するように笑って答えた。「いずれ分かるさ」
とにもかくにも数千の兵を乗せた船はこのまま雲朱を通り過ぎ、紫沈から見て南東に流れる岳川の支流に入る。そこから北上し、陸路で先行しているはずの雲朱軍と合流する形で、南方から紫沈を攻めるという。
この作戦を聞いた時、玲馨に思いの外絶望は無かった。話が大きすぎて、感情が追いついていなかったのだろう。
蘇智望によれば、上手くいけば北方からも軍が出る予定で、東を除く三方から紫沈を包囲するという。当然包囲網を完全な物にするために、多少遅れはするが東にも兵は回す。
その数、しめて五万。更に北、西、南の三方にはそれぞれ援軍を控えさせており、籠城作戦に出れられたとしても兵站を切らす事無く数ヶ月は攻め続けられる構えになっている。あわいの妖魔を退けるための薬も十分な数確保し、例え戦闘になっても物の数で押し切ってしまうつもりだ。これだけの物量を一体どこから確保したというのか玲馨には分からない。
蘇智望は、長い時をかけてこの日の作戦を練ってきた。北と南と交渉を続け、互いに示し合わせて紫沈を攻める。汪軍の裏切りはあったがせいぜい数百の兵が減ったところで作戦に支障はなく、寧ろ先遣隊として禁軍を疲弊させてくれる事に期待出来ると、蘇智望は冷たく笑っていた。
今起きているのはつまり内乱だ。東江の金王が中心となって水王と火王の三勢力が共謀し、戊陽皇帝を討つ内乱。蘇智望の狙いは戊陽の帝位追放である。
玲馨はこの壮大な作戦を聞きながら、今この手で蘇智望を討てば内乱は止まるのかと考えなかったと言えば嘘になる。だがきっと戦いは止められないだろうし、玲馨も東江の兵に殺され二人の命は無為に失われる事になる。
ならばいっそ、蘇智望の望みを叶えると共に、自分の望みも叶えるこれは好機なのだと、そう思う事にした。
考えるべき事がなくなってしまうと今更船の揺れが気になった。
海は紫沈に近付くにつれ荒れているらしく、外は雨が降り出していた。
或いは船は紫沈に辿り着かず暗い海で難破してしまうかも知れない。五隻の船は海の藻屑となって、東江軍の本隊は禁軍に敗れて潰走。
そうなれば今度こそ戊陽の御世は安泰となるのかも知れない。東江という大きな勢力が潰え、後継となる風蘭が育つのはずっと先の事だ。
だけど、それこそを玲馨は望まない。望まないのだ。船は難破してもらっては困るし、本隊は援軍の到着まで持ち堪えてもらわなくてはならない。
己の死は何故だがずっと先の事のような気がして全く現実感を伴わないのに、戊陽の世が安泰する未来は想像するだけで恐ろしくなる。
玉座は孤独な頂であると、誰が言ったのだったか。何故、孤独であらねばならないのか。あの人に孤独ほど似合わないものはないというのに──。
いつの間にか眠りに落ちていた。目が覚めると船の揺れが減っている事に気付く。雨が止んだのだろうか。
眠ったおかげで気分も落ち着いたので少し外の空気が吸いたくなった。扉の外の監視に頼み甲板に上がらせてもらうと、水平線の先が朝日に焼けるところだった。
一晩眠っていたらしい。ほんの短い間のつもりだったが、やはり疲れていたのだろう。
「あの、少しお話をしてもいいですか?」
「春梅さん」
梅の妹が甲板に居る玲馨に声を掛けてきた。
羅春梅はちらと監視の兵に視線を向ける。その視線をどう受け取ったのか、監視は二人に向かって気怠げに言った。
「女なら別に部屋に入れても構わないぞ」
「えっ? あの、いえ私は」
蘇智望は玲馨についてこの監視に何と話したのか、宦官である事を彼は知らないらしい。
「……春梅、ここは彼の言葉に甘えましょうか」
「ええ!?」
「あ、あのっ、私には夫が!!」
「落ち着いて下さい。私は宦官ですよ。お忘れですか?」
「あ……」
勘違いに気付いた春梅は顔を真っ赤にしながら謝罪した。兄とは本当に似ても似つかない可憐な人だ。
「監視の目を気にしていたようでしたので。余計な事だったでしょうか?」
宦官とはいえ玲馨も元は男だ。夫のある身で、しかも蘇智望の侍女が皇帝の宦官と部屋で二人きりになったなど噂になったら、確かに少々面倒かも知れない。船室に戻った今更になって後悔しそうになったが、羅春梅は緩く首を振り「いいえ、助かりました」と礼を口にする。
「あまり長居は出来ないので単刀直入にお話します。私、あなたについて行きたいんです」
「……それは、一体」
「ただの、私の勘なんです。でもあなたと一緒に居たら兄に会えるような気がして」
玲馨の一存でどうこう出来る問題ではないが、羅春梅の決意は固いようだ。
「本当は蘇蘭様に付いていくはずだったのですが、戦地に行かれるとの事で侍女から外されてしまって。船に乗ったものの身の置きどころがなくて困っていたんです。だから瑠璃に頼んで玲馨さんの侍女の仕事の手伝いを許してもらいました」
行動派なところも自堕落な雰囲気のある梅とはまるで違うようだが、もしかすると梅も宦官になる前はそういう人間だったのかも知れない。
「何やら私の知らない所で話が進んでいるのですね。私に確認を取る必要も無さそうですが……ところで、瑠璃というのは?」
「瑠璃は汪家の子です。玲馨さんについているあのちょっとぶっきらぼうな侍女ですよ」
ちょっと、かどうかの審議はさておいて、瑠璃とはあの四郎に似た蘇智望の侍女の名らしい。
名前に使われている字は何かの書で見覚えがあった。確か色の付いた玻璃の事をそう呼ぶ国があるのではなかったか。美しく透き通った青い玻璃だ。
「本当は蘇蘭様に瑠璃が、玲馨さんには私が付くはずでした。でも何故か瑠璃が嫌がっているようだったので交替したんです」
四郎と蘇蘭は発音は違うが音そのものがよく似ている。四郎と雰囲気が似ている事も相俟って彼女とは妙な縁を感じた。
「あの、それで玲馨さん。私、お世話を務めさせて頂いても大丈夫でしょうか?」
「風蘭……蘇蘭が戦地に行くという理由で侍女を外されたのでしたら、私も同様では?」
「玲馨さんが戦地に? いいえ、そんなはずは御座いません。玲馨さんは蘇智望様と後方にて待機なさると聞いています」
よくよく考えてみたら当然だった。つまり蘇智望は反乱軍の総大将で、そんな立場の人間が武器を片手に戦場へ向かうはずがない。その点戊陽は自分で行きたがる性質なので、すっかり戦う主というものが当たり前になってしまっていたようだ。
「そういう事なら、私から断る理由はありませんよ。ですが私は宦官です。誰かの世話をする事は得意ですが、された事は一度もありません。なのでどうかあまり畏まらないで、ただ私の話し相手になって頂けませんか?」
玲馨はこれから死ぬ日取りが決まっている人間だ。そんな相手にあれこれと世話を焼かせるのはあまりに忍びない。あわよくば玲馨の傍に控える事で情報を得ようとする彼女の協力が出来れば、それで十分だろう。
兄が冤罪で捕らえられ、以後兄の生存さえ不確かだったはずなのに、羅春梅の瞳に翳りは無い。兄との再会をずっと諦めずに生きてきたのだろう。そんな羅春梅が今の玲馨にはとても眩しく見えた。
やがて数日の後、船は河口から岳川の支流に入った。岳川支流は紫沈へと流れ込んで生活用水としても使われている主要な河川のひとつだ。上流に向かって進めばやがて紫沈へ辿り着くが、玲馨たちを乗せてきた軍用船は大きすぎるので途中から陸路を行く事になる。ただしそれは船に乗った兵士たちに限った話だ。
蘇智望を始めとした一部の人間は尚も船に残る事になる。ここが臨時の反乱軍拠点となるのだ。
蘇智望が海路を選んだ理由は、あわいだ。これから紫沈を陥落させるまでに長くとも一月以上はかかる想定だ。その間、人も武器も食料も、陸路を使うとなると常に妖魔の危険に晒される。一方海路は海の豊富な地脈のおかげで妖魔とは無縁。嵐さえ凌げれば、陸路よりずっと安全に且つ速く兵站を補給出来るという狙いがあった。
「とはいえ、きっとそう長く城には籠もらないだろうね」
「陛下がすぐに降伏なさると?」
「そなたや、内間から聞いた陛下の印象だ。彼は民間人を危険な目に遭わせる事はしないだろう。長く籠もって飢えさせるような事も良しとしないはずさ」
蘇智望は更にこう続ける。「汪家さえ先走らなければ、無血開城も成ったかも知れなかった」と。
数倍に及ぶ兵で城を完全に包囲されたら、戊陽はどういう判断を下すだろうか。まず対話を望むのは間違いないだろう。いきなり武力で解決しようとするのは彼らしくない。だがお互い譲れないと分かった時、戊陽は必ず自分の身を差し出す事で紫沈の民を救おうとするはず。
ああ、と玲馨は胸の奥にとうとう現実という重さを伴って居座り始めた「死」を思う。
皇帝の首一つで戦いは丸く収まり他には誰の血も流れないのなら、戊陽はその決断をしてしまう人だ。例え「黄」の字を与えられなかった偽りの太陽でも、皇族に生まれた皇子としてそれくらいの腹は決めて玉座に座っている。
それを、救うのが玲馨の今の使命だ。そのために、玲馨は蘇智望の望みを受け入れたのだから。
東江の甲冑に東江の象徴である虎の旗を掲げているが偽装兵だという軍勢が、船を下りて去っていく。その行進は禁軍の迫力に勝るとも劣らない。
これから紫沈を攻める彼らの背中を見送りながら、玲馨は蘇智望の願いを思い出していた。
「では、これは私からの頼み事だ。そなた、戊陽のために死んでくれるか」
そう言われても咄嗟に言葉が出なかった。当たり前だ。死ねと言われて即座にはいと答えられるほど、玲馨は蘇智望の事を知らない。同じ事を戊陽に言われたとて動揺するだろう。
「これは私の我儘だ。私は甥をこの手にかけたくはない。だが『皇帝』を断罪すると決めたからには生かしてはおけないだろう」
なるほどつまり影武者となって死ねという事らしい。
「何故、会った事もない外甥の命を惜しまれるのです? ましてや国家の罪を全て押し付けて殺そうという相手の、何を」
蘇智望は戊陽に対して直接的な恨みがある訳ではないだろう。ほんの二年で命を狙われるほどの悪政を敷いたはずもなければ、傍で彼の政務を見てきた限り戊陽は前例に倣い良くも悪くも大きな改革はしなかった。いや、これから改善されていくはずだったのを、どこかの誰かが台無しにしようとしているのだ。
やはり紛れもなく蘇智望は戊陽の敵だ。少なくとも戊陽は、彼なりに沈という国を良くしていこうと味方の少ない宮廷で邁進してきたはずだ。その努力は漸くこれから結実していこうとした矢先、それら全てを一息に奪ってしまおうという。
けれど、玲馨はそれでも蘇智望に否やを返せなかった。
玲馨こそが誰よりも望んでいたからだ。戊陽から玉座を奪ってしまう何かの存在を──。
「私の従姉は、とても優しい人だった」
蘇智望は卓に置いた器の縁を指先で撫でる。中身は酒だろうか。ほんの微かに酒精のツンとした香りが部屋の空気に溶けている気がする。
「初めは私の兄の妻になる筈だった。しかし兄を亡くして、彼女は後宮に連れて行かれた。望まぬ婚儀であったが、もちろん他の妃たちと比べて彼女が誰より不幸だったとは言わぬ」
過去に後宮に連れられ妃嬪となった女たちで、己が不幸を嘆かなかった女がどれほどいたろう。強く覚悟を決めて来た者でも泣いて故郷を思う日々を過ごす事になった者も少なくない。そして、過去の妃嬪たちの手記を読んでは自分を慰めるのだ。辛いのは自分だけではない、と。
だが黄雷の頃の妃嬪たちは比較的穏やかな日々を過ごせたのではないかと玲馨は思う。黄雷は誰か一人を特別寵愛するような事はなかった。常に平等に妃たちのもとへ通い、後宮暮らしに不都合が無いかをよく聞いてやっていた。
長男を生んだ事で貴妃が皇后となりはしたものの、妻と子を顧みる良い夫だった。それでも女同士の諍いは確かにあった。閉鎖的なおかげで醜悪に歪む女たちの感情を玲馨はすぐ傍で見て来た。
後宮には幸も不幸も同時に存在していた。だが、そんな事は蘇智望にとって問題ではなかった。
「素朴な方だったのだ。桃がお好きで桃園に通っては、侍従に呆れ顔をされながらも手や衣を汚して桃を穫ってよく私や姉に振る舞って下さった。贅沢をして着飾るよりも、桃の木の世話に精を出す事がお好きな方だった。それが……」
言葉を区切り、蘇智望は器の中身を煽る。ふわりと酒の香りが漂った。
「男児がお生まれになり、そのお披露目の儀であった。私は金王となる以前にも、紫沈に行った事があるのだよ。三年ぶりに見たお姿は、昔が嘘のように煌びやかな衣に包まれ、金の盃を片手にたくさんの種類の果物を召しあがっていた。そうして笑いかけておられたのだ、息子と、夫に。その笑顔は昔のまま、素朴で可憐なまま。気が狂いそうだった」
戊陽が生まれた頃だというなら今から二十年ほど前の話だ。当時の蘇智望はきっと十代半ばかそれよりも幼いくらいだったろう。
恋焦がれた女性が愛する人と子に恵まれた幸せな光景も、十代の蘇智望にとっては地獄の光景だった。着飾ったところのない素朴で可憐な女が後宮に染まり、自分以外の男の傍で笑っている。
蘇智望を見ていると、やがて妃嬪を迎え自分の子を作るだろう戊陽の傍に宦官として仕え続ける事の辛さがより具体的に想像出来るようだった。
堪えられるだろうか。妃と我が子に笑いかける戊陽を、誰よりも傍で見続ける事に。
「……必ず」
未来を想像した時、ぞ、と背筋に悪寒めいたものが駆け抜けて、思わず玲馨は口を開いていた。
「必ず生かして下さると、約束して頂けますか」
そうした嫌なものを払拭するかのように、玲馨は承諾する。
自分と戊陽の未来を引き換えにする事を。
始めは誰もが火事を疑った。数日前にも鳴った鐘は、沈の歴史でも百年余り例が無かった「敵兵」の出現を告げたのだ。今度こそ火事か、そうでなければ雨の影響で水路が溢れたかのどちらかだと思うのも無理はなかった。
宮廷に詰めていた官吏たちもやはり火事を心配した。小降りになった雨空の下に走り出てきて、手で庇を作りながら空を見上げる。
煙は立っていない。何分この雨で火事は起きても火がついた傍からたちまち消えていく事だろう。
ならば水害だろうか。城内に流れる堀は多少水位が増しているようだが、市井の方はもっと酷いのだろうか。
カーン、カーン、と鐘は鳴り止まない。
そのうち伝令兵が走っていくのが見えて官吏たちがざわつき始める。伝令は軍の兵舎がある方角へと走っていくではないか。
「まさか、また敵が現れたとでもいうのか……?」
誰かが疑心暗鬼に呟くと、一呼吸の間をあけてからドッと笑いが沸き起こった。
まさか、そんなはずがない、冗談はほどほどにしてくれ。
官吏たちは口々に言い合っては頬を引き攣らせたが、やがて伝令兵が彼らのもとにもやってくると血相を変えて蜘蛛の子を散らすように各々逃げ出した。
もう城には居られない。家に帰ろう。
いいや城の奥で隠れていよう。敵も見つけられないような所でやり過ごすのだ──。
思い思いの場所へ三々五々と散っていく官吏に、もはや城を、紫沈を、守らなくてはという大義は微塵もなくなっていた。
*
見張りの兵から兵舎に詰めていた亥壬たちの元に敵兵の出現が伝わると、状況を確かめるべく数名の兵が外へ出て行った。
「まさか汪軍への援軍か!?」
「落ち着いて下さい緑歳兄上。すぐに兵が──」
亥壬が言い終えるより早くに駆け込んできた兵士は血相を変えてこう報告する。「西方に白旗に虎を確認致しました」
「東江の軍だ。今度こそ正規軍という訳か。腕の見せ所だな亥壬!」
「興奮しないで下さい! 事は試合とは訳が違うのですよ!」
「そう言うお前の方が声がでかいがな」
「うるさいです!」
亥壬と緑歳は生まれた日がほとんど違わないので、亥壬はどうしても緑歳に対して遠慮というものをしなくなる。緑歳も特にそれを咎めようとはしないので、昔から二人の仲の良さは後宮では知らぬ人がないくらいだ。
亥壬は緑歳を無視して伝令に言う。「前線の李将軍にも報告を。恐らく東江の本隊です」
現在雨のせいで汪軍との戦いは一時中断されていたが、小降りになった事で両軍機を窺っているところだった。瓦解寸前の汪軍など最早敵ではなく、物量によって強引に押さえつけてしまえるというところまで来ていた。
そこへ援軍が到着してしまっては再び状況が拮抗するかも知れない。何としてでも分断したいところだが、そのためには西以外の門から部隊を外に出して大きく城外を回らせて本隊と汪軍の間に出るか、或いは本隊の横や背後をつかなくてはならない。しかし、この雨で視界の悪い中、物見が旗の色だけでなく「虎」を目視出来るほどの距離まで近付いて来ているとなると、もう間に合わないだろう。
そも汪軍を城の外から挟み撃ちにしなかったのも、本隊の援軍や別働隊が伏せられている可能性を考慮した結果だったのだ。
「内乱となると全方位を警戒しなくてはならない汀彩城は、攻めるに易く守るに難い城です。禁軍の数も全く足りていない。その上、戊陽兄上が東に遠征なさっていた隙をついてきたのですから、恐らく西は北と結託していたのでしょうね。本隊を出してくる事も概ね想定内ですよ」
援軍の出現によって兵舎は騒々しくなる中、亥壬は冷静だった。淡々と考えを語り、緑歳がうんうんとさも心得ているように頷く。
「皇居のある北はまた別格ですが、汀彩城も紫沈の街も、西からの侵略には一応の備えとして砦や門が丈夫に設計されています。他国と言えば遥か西方の昆しかありませんから。しかし既に汪と紫沈の貴族が手を結んで中から門を開けられてしまった以上、これからの作戦は失敗から開始する事になりますが……」
北門から戊陽が帰還した報せを受けた直後、北門も固く閉じられこれで西門以外の門は全てその門扉を閉ざした事になる。後はどうにか西門さえ閉じてしまえば──。
「──籠城が成る。例え本隊が合流したところで未だ数的には禁軍が圧倒的に有利なのです。城攻めには三倍の数の兵が必要だと書で読んだ事があります。加えて外には天然の要害である『あわい』だってあるんです。夜にはあわいの妖魔を相手にしながら、昼には城から矢を射掛けられながら攻め続けなければならない。僕たちは城に籠もっているだけで勝てるんです。勝てる戦いのはずなのです」
そうは言いながらも亥壬の表情は優れない。卓の上に広げられた地図をじっと見下ろしながら、ずっと何かを考え続けており、亥壬の指は摩擦熱で火傷を起こしである。
「亥壬、とにかく我らは汪軍を西門付近から追い出してしまう事が急務なのだな」
「そうです」
「では、俺に一個大隊とは言わないからいくらか兵を預けてくれ」
「緑歳兄上、まさか」
「俺は前線へ行くぞ」
緑歳は戦いとなると猪のような男で、力任せに相手をねじ伏せるのは得手だが、そこに罠が仕掛けられたら天晴れなほどに嵌る人である。汪軍を単純に城外まで押し返すという戦法を取るとなった時、緑歳はきっと強大な力を発揮してくれる事だろう。禁軍内でも評判の緑歳の姿が見えれば、兵の士気も上がるはずだ。
亥壬には緑歳の出陣を止めるだけの理屈が思いつかなかった。
「死なないで下さい」
「無論だ」
「死んだら、総指揮なんてやめて僕も後を追います」
「む、それは良くないぞ亥壬」
「冗談ですよ」
「俺は冗談じゃない。弟を悲しませるような兄にはならんぞ」
緑歳の左手が幼少の頃の癖で亥壬の頭を撫でようとしたが寸でで止まる。頭を撫でる代わりにその手は固く拳を握り込み、亥壬の胸に当てられた。
「必ず戻る」
難しい顔をしていた亥壬の表情が一瞬くしゃりと歪んだが、きつく唇を引き結んで亥壬は無言で頷いた。
緑歳が兵を率いて出て行く姿を見送って、籠城のために亥壬が手筈を整えようとした時だった。
カーン、カーンと鐘が鳴る。鐘は鳴ったが煙はどこにも見当たらない。まして水路が決壊した訳でもない。
「伝令ー! 南門より赤旗に朱雀の軍勢を捕捉!」
*
「互いに叶わぬ恋に盲いた者同士、本懐を遂げようではないか」
蘇智望の言葉に反論する気は一切起きなかった。彼の言葉に酷く納得して、玲馨は初めて自分の心にあったものを形容させた。
形にしてみれば案外何でもないもので、どこにでもあるし誰でも焦がれたり破れたり、或いは溺れたりするような普遍的なものだった。なにも自分の中にあるものが他と比べて特別なものだと思っていた訳ではないが、ずっと身分を理由に形を取ってはいけないものだと思い込んでいた。
これが初めての自覚だった訳ではない。例えば草むらから猫の耳だけが飛び出して見えているのを猫だと知りながら、草をかき分けてまで追いかけるのを野暮だというような、そんな感覚。自己満足に近いものだ。けれど、他人の手によって草が刈られたら、やはりそこに居たのは猫でしかなかった。それと同じようなもので「やっぱり」というある種安心に似た感情に包まれただけだった。
名前を付けず、形を認めなかったせいでふわふわと浮いていたものが、とうとう地に足をつけた。それだけだ。これが叶わぬもの、叶ってはいけないものであることも、玲馨はよく知っていた。
蘇智望との会話を終えた後、蘇智望は玲馨に監視をつけた。変わらず甲板に出るのは自由のままだが、玲馨の部屋の外には屈強な兵が見張りに立っている。
しかしもはや甲板どころか部屋の外にも出ようという気は起こりそうにないので、不要の人手になるかも知れない。
玲馨は与えられた部屋の中で蘇智望から聞かされた今の状況と今後の作戦を頭の中で整理していた。
まず、蘇智望が玲馨を伴い軍と共に急な出港となったのは、分家である汪家が勝手に紫沈へ続く森を突破したという情報が入ったからだ。
蘇智望はそれを止めるためにまず西から東江本隊に汪軍を追わせた。その指揮には何とあの風蘭がつけられているらしいが、実権は別の蘇智望の手の者が握っているのだろう。
しかし、西から紫沈へ向かうのが本隊だとすると現在五隻の船に乗っている兵士たちは一体何者だろうか。目算では一隻辺り千人近くが乗っているが、東江の兵数も記憶の通りならば山芒とそう変わらないはずだ。四千か多くとも五、六千のはずで、しかし船に乗る兵士たちの体付きは決して農民のそれではない。
これに対し蘇智望は自嘲するように笑って答えた。「いずれ分かるさ」
とにもかくにも数千の兵を乗せた船はこのまま雲朱を通り過ぎ、紫沈から見て南東に流れる岳川の支流に入る。そこから北上し、陸路で先行しているはずの雲朱軍と合流する形で、南方から紫沈を攻めるという。
この作戦を聞いた時、玲馨に思いの外絶望は無かった。話が大きすぎて、感情が追いついていなかったのだろう。
蘇智望によれば、上手くいけば北方からも軍が出る予定で、東を除く三方から紫沈を包囲するという。当然包囲網を完全な物にするために、多少遅れはするが東にも兵は回す。
その数、しめて五万。更に北、西、南の三方にはそれぞれ援軍を控えさせており、籠城作戦に出れられたとしても兵站を切らす事無く数ヶ月は攻め続けられる構えになっている。あわいの妖魔を退けるための薬も十分な数確保し、例え戦闘になっても物の数で押し切ってしまうつもりだ。これだけの物量を一体どこから確保したというのか玲馨には分からない。
蘇智望は、長い時をかけてこの日の作戦を練ってきた。北と南と交渉を続け、互いに示し合わせて紫沈を攻める。汪軍の裏切りはあったがせいぜい数百の兵が減ったところで作戦に支障はなく、寧ろ先遣隊として禁軍を疲弊させてくれる事に期待出来ると、蘇智望は冷たく笑っていた。
今起きているのはつまり内乱だ。東江の金王が中心となって水王と火王の三勢力が共謀し、戊陽皇帝を討つ内乱。蘇智望の狙いは戊陽の帝位追放である。
玲馨はこの壮大な作戦を聞きながら、今この手で蘇智望を討てば内乱は止まるのかと考えなかったと言えば嘘になる。だがきっと戦いは止められないだろうし、玲馨も東江の兵に殺され二人の命は無為に失われる事になる。
ならばいっそ、蘇智望の望みを叶えると共に、自分の望みも叶えるこれは好機なのだと、そう思う事にした。
考えるべき事がなくなってしまうと今更船の揺れが気になった。
海は紫沈に近付くにつれ荒れているらしく、外は雨が降り出していた。
或いは船は紫沈に辿り着かず暗い海で難破してしまうかも知れない。五隻の船は海の藻屑となって、東江軍の本隊は禁軍に敗れて潰走。
そうなれば今度こそ戊陽の御世は安泰となるのかも知れない。東江という大きな勢力が潰え、後継となる風蘭が育つのはずっと先の事だ。
だけど、それこそを玲馨は望まない。望まないのだ。船は難破してもらっては困るし、本隊は援軍の到着まで持ち堪えてもらわなくてはならない。
己の死は何故だがずっと先の事のような気がして全く現実感を伴わないのに、戊陽の世が安泰する未来は想像するだけで恐ろしくなる。
玉座は孤独な頂であると、誰が言ったのだったか。何故、孤独であらねばならないのか。あの人に孤独ほど似合わないものはないというのに──。
いつの間にか眠りに落ちていた。目が覚めると船の揺れが減っている事に気付く。雨が止んだのだろうか。
眠ったおかげで気分も落ち着いたので少し外の空気が吸いたくなった。扉の外の監視に頼み甲板に上がらせてもらうと、水平線の先が朝日に焼けるところだった。
一晩眠っていたらしい。ほんの短い間のつもりだったが、やはり疲れていたのだろう。
「あの、少しお話をしてもいいですか?」
「春梅さん」
梅の妹が甲板に居る玲馨に声を掛けてきた。
羅春梅はちらと監視の兵に視線を向ける。その視線をどう受け取ったのか、監視は二人に向かって気怠げに言った。
「女なら別に部屋に入れても構わないぞ」
「えっ? あの、いえ私は」
蘇智望は玲馨についてこの監視に何と話したのか、宦官である事を彼は知らないらしい。
「……春梅、ここは彼の言葉に甘えましょうか」
「ええ!?」
「あ、あのっ、私には夫が!!」
「落ち着いて下さい。私は宦官ですよ。お忘れですか?」
「あ……」
勘違いに気付いた春梅は顔を真っ赤にしながら謝罪した。兄とは本当に似ても似つかない可憐な人だ。
「監視の目を気にしていたようでしたので。余計な事だったでしょうか?」
宦官とはいえ玲馨も元は男だ。夫のある身で、しかも蘇智望の侍女が皇帝の宦官と部屋で二人きりになったなど噂になったら、確かに少々面倒かも知れない。船室に戻った今更になって後悔しそうになったが、羅春梅は緩く首を振り「いいえ、助かりました」と礼を口にする。
「あまり長居は出来ないので単刀直入にお話します。私、あなたについて行きたいんです」
「……それは、一体」
「ただの、私の勘なんです。でもあなたと一緒に居たら兄に会えるような気がして」
玲馨の一存でどうこう出来る問題ではないが、羅春梅の決意は固いようだ。
「本当は蘇蘭様に付いていくはずだったのですが、戦地に行かれるとの事で侍女から外されてしまって。船に乗ったものの身の置きどころがなくて困っていたんです。だから瑠璃に頼んで玲馨さんの侍女の仕事の手伝いを許してもらいました」
行動派なところも自堕落な雰囲気のある梅とはまるで違うようだが、もしかすると梅も宦官になる前はそういう人間だったのかも知れない。
「何やら私の知らない所で話が進んでいるのですね。私に確認を取る必要も無さそうですが……ところで、瑠璃というのは?」
「瑠璃は汪家の子です。玲馨さんについているあのちょっとぶっきらぼうな侍女ですよ」
ちょっと、かどうかの審議はさておいて、瑠璃とはあの四郎に似た蘇智望の侍女の名らしい。
名前に使われている字は何かの書で見覚えがあった。確か色の付いた玻璃の事をそう呼ぶ国があるのではなかったか。美しく透き通った青い玻璃だ。
「本当は蘇蘭様に瑠璃が、玲馨さんには私が付くはずでした。でも何故か瑠璃が嫌がっているようだったので交替したんです」
四郎と蘇蘭は発音は違うが音そのものがよく似ている。四郎と雰囲気が似ている事も相俟って彼女とは妙な縁を感じた。
「あの、それで玲馨さん。私、お世話を務めさせて頂いても大丈夫でしょうか?」
「風蘭……蘇蘭が戦地に行くという理由で侍女を外されたのでしたら、私も同様では?」
「玲馨さんが戦地に? いいえ、そんなはずは御座いません。玲馨さんは蘇智望様と後方にて待機なさると聞いています」
よくよく考えてみたら当然だった。つまり蘇智望は反乱軍の総大将で、そんな立場の人間が武器を片手に戦場へ向かうはずがない。その点戊陽は自分で行きたがる性質なので、すっかり戦う主というものが当たり前になってしまっていたようだ。
「そういう事なら、私から断る理由はありませんよ。ですが私は宦官です。誰かの世話をする事は得意ですが、された事は一度もありません。なのでどうかあまり畏まらないで、ただ私の話し相手になって頂けませんか?」
玲馨はこれから死ぬ日取りが決まっている人間だ。そんな相手にあれこれと世話を焼かせるのはあまりに忍びない。あわよくば玲馨の傍に控える事で情報を得ようとする彼女の協力が出来れば、それで十分だろう。
兄が冤罪で捕らえられ、以後兄の生存さえ不確かだったはずなのに、羅春梅の瞳に翳りは無い。兄との再会をずっと諦めずに生きてきたのだろう。そんな羅春梅が今の玲馨にはとても眩しく見えた。
やがて数日の後、船は河口から岳川の支流に入った。岳川支流は紫沈へと流れ込んで生活用水としても使われている主要な河川のひとつだ。上流に向かって進めばやがて紫沈へ辿り着くが、玲馨たちを乗せてきた軍用船は大きすぎるので途中から陸路を行く事になる。ただしそれは船に乗った兵士たちに限った話だ。
蘇智望を始めとした一部の人間は尚も船に残る事になる。ここが臨時の反乱軍拠点となるのだ。
蘇智望が海路を選んだ理由は、あわいだ。これから紫沈を陥落させるまでに長くとも一月以上はかかる想定だ。その間、人も武器も食料も、陸路を使うとなると常に妖魔の危険に晒される。一方海路は海の豊富な地脈のおかげで妖魔とは無縁。嵐さえ凌げれば、陸路よりずっと安全に且つ速く兵站を補給出来るという狙いがあった。
「とはいえ、きっとそう長く城には籠もらないだろうね」
「陛下がすぐに降伏なさると?」
「そなたや、内間から聞いた陛下の印象だ。彼は民間人を危険な目に遭わせる事はしないだろう。長く籠もって飢えさせるような事も良しとしないはずさ」
蘇智望は更にこう続ける。「汪家さえ先走らなければ、無血開城も成ったかも知れなかった」と。
数倍に及ぶ兵で城を完全に包囲されたら、戊陽はどういう判断を下すだろうか。まず対話を望むのは間違いないだろう。いきなり武力で解決しようとするのは彼らしくない。だがお互い譲れないと分かった時、戊陽は必ず自分の身を差し出す事で紫沈の民を救おうとするはず。
ああ、と玲馨は胸の奥にとうとう現実という重さを伴って居座り始めた「死」を思う。
皇帝の首一つで戦いは丸く収まり他には誰の血も流れないのなら、戊陽はその決断をしてしまう人だ。例え「黄」の字を与えられなかった偽りの太陽でも、皇族に生まれた皇子としてそれくらいの腹は決めて玉座に座っている。
それを、救うのが玲馨の今の使命だ。そのために、玲馨は蘇智望の望みを受け入れたのだから。
東江の甲冑に東江の象徴である虎の旗を掲げているが偽装兵だという軍勢が、船を下りて去っていく。その行進は禁軍の迫力に勝るとも劣らない。
これから紫沈を攻める彼らの背中を見送りながら、玲馨は蘇智望の願いを思い出していた。
「では、これは私からの頼み事だ。そなた、戊陽のために死んでくれるか」
そう言われても咄嗟に言葉が出なかった。当たり前だ。死ねと言われて即座にはいと答えられるほど、玲馨は蘇智望の事を知らない。同じ事を戊陽に言われたとて動揺するだろう。
「これは私の我儘だ。私は甥をこの手にかけたくはない。だが『皇帝』を断罪すると決めたからには生かしてはおけないだろう」
なるほどつまり影武者となって死ねという事らしい。
「何故、会った事もない外甥の命を惜しまれるのです? ましてや国家の罪を全て押し付けて殺そうという相手の、何を」
蘇智望は戊陽に対して直接的な恨みがある訳ではないだろう。ほんの二年で命を狙われるほどの悪政を敷いたはずもなければ、傍で彼の政務を見てきた限り戊陽は前例に倣い良くも悪くも大きな改革はしなかった。いや、これから改善されていくはずだったのを、どこかの誰かが台無しにしようとしているのだ。
やはり紛れもなく蘇智望は戊陽の敵だ。少なくとも戊陽は、彼なりに沈という国を良くしていこうと味方の少ない宮廷で邁進してきたはずだ。その努力は漸くこれから結実していこうとした矢先、それら全てを一息に奪ってしまおうという。
けれど、玲馨はそれでも蘇智望に否やを返せなかった。
玲馨こそが誰よりも望んでいたからだ。戊陽から玉座を奪ってしまう何かの存在を──。
「私の従姉は、とても優しい人だった」
蘇智望は卓に置いた器の縁を指先で撫でる。中身は酒だろうか。ほんの微かに酒精のツンとした香りが部屋の空気に溶けている気がする。
「初めは私の兄の妻になる筈だった。しかし兄を亡くして、彼女は後宮に連れて行かれた。望まぬ婚儀であったが、もちろん他の妃たちと比べて彼女が誰より不幸だったとは言わぬ」
過去に後宮に連れられ妃嬪となった女たちで、己が不幸を嘆かなかった女がどれほどいたろう。強く覚悟を決めて来た者でも泣いて故郷を思う日々を過ごす事になった者も少なくない。そして、過去の妃嬪たちの手記を読んでは自分を慰めるのだ。辛いのは自分だけではない、と。
だが黄雷の頃の妃嬪たちは比較的穏やかな日々を過ごせたのではないかと玲馨は思う。黄雷は誰か一人を特別寵愛するような事はなかった。常に平等に妃たちのもとへ通い、後宮暮らしに不都合が無いかをよく聞いてやっていた。
長男を生んだ事で貴妃が皇后となりはしたものの、妻と子を顧みる良い夫だった。それでも女同士の諍いは確かにあった。閉鎖的なおかげで醜悪に歪む女たちの感情を玲馨はすぐ傍で見て来た。
後宮には幸も不幸も同時に存在していた。だが、そんな事は蘇智望にとって問題ではなかった。
「素朴な方だったのだ。桃がお好きで桃園に通っては、侍従に呆れ顔をされながらも手や衣を汚して桃を穫ってよく私や姉に振る舞って下さった。贅沢をして着飾るよりも、桃の木の世話に精を出す事がお好きな方だった。それが……」
言葉を区切り、蘇智望は器の中身を煽る。ふわりと酒の香りが漂った。
「男児がお生まれになり、そのお披露目の儀であった。私は金王となる以前にも、紫沈に行った事があるのだよ。三年ぶりに見たお姿は、昔が嘘のように煌びやかな衣に包まれ、金の盃を片手にたくさんの種類の果物を召しあがっていた。そうして笑いかけておられたのだ、息子と、夫に。その笑顔は昔のまま、素朴で可憐なまま。気が狂いそうだった」
戊陽が生まれた頃だというなら今から二十年ほど前の話だ。当時の蘇智望はきっと十代半ばかそれよりも幼いくらいだったろう。
恋焦がれた女性が愛する人と子に恵まれた幸せな光景も、十代の蘇智望にとっては地獄の光景だった。着飾ったところのない素朴で可憐な女が後宮に染まり、自分以外の男の傍で笑っている。
蘇智望を見ていると、やがて妃嬪を迎え自分の子を作るだろう戊陽の傍に宦官として仕え続ける事の辛さがより具体的に想像出来るようだった。
堪えられるだろうか。妃と我が子に笑いかける戊陽を、誰よりも傍で見続ける事に。
「……必ず」
未来を想像した時、ぞ、と背筋に悪寒めいたものが駆け抜けて、思わず玲馨は口を開いていた。
「必ず生かして下さると、約束して頂けますか」
そうした嫌なものを払拭するかのように、玲馨は承諾する。
自分と戊陽の未来を引き換えにする事を。
0
あなたにおすすめの小説

愛玩人形
誠奈
BL
そろそろ季節も春を迎えようとしていたある夜、僕の前に突然天使が現れた。
父様はその子を僕の妹だと言った。
僕は妹を……智子をとても可愛がり、智子も僕に懐いてくれた。
僕は智子に「兄ちゃま」と呼ばれることが、むず痒くもあり、また嬉しくもあった。
智子は僕の宝物だった。
でも思春期を迎える頃、智子に対する僕の感情は変化を始め……
やがて智子の身体と、そして両親の秘密を知ることになる。
※この作品は、過去に他サイトにて公開したものを、加筆修正及び、作者名を変更して公開しております。
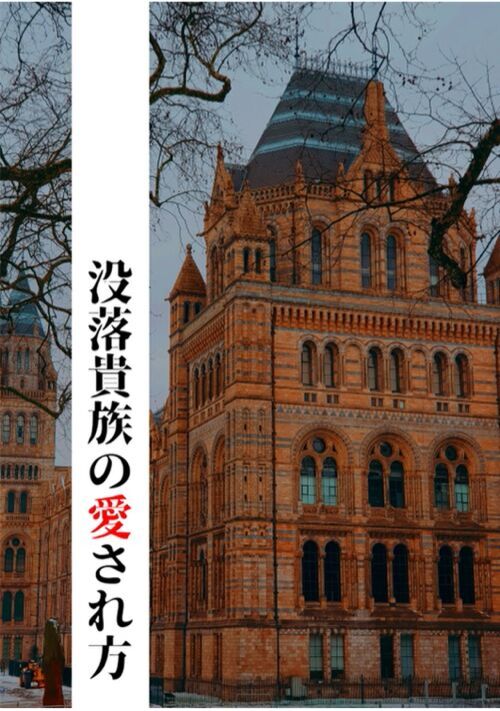
没落貴族の愛され方
シオ
BL
魔法が衰退し、科学技術が躍進を続ける現代に似た世界観です。没落貴族のセナが、勝ち組貴族のラーフに溺愛されつつも、それに気付かない物語です。
※攻めの女性との絡みが一話のみあります。苦手な方はご注意ください。


すべてはあなたを守るため
高菜あやめ
BL
【天然超絶美形な王太子×妾のフリした護衛】 Y国の次期国王セレスタン王太子殿下の妾になるため、はるばるX国からやってきたロキ。だが妾とは表向きの姿で、その正体はY国政府の依頼で派遣された『雇われ』護衛だ。戴冠式を一か月後に控え、殿下をあらゆる刺客から守りぬかなくてはならない。しかしこの任務、殿下に素性を知られないことが条件で、そのため武器も取り上げられ、丸腰で護衛をするとか無茶な注文をされる。ロキははたして殿下を守りぬけるのか……愛情深い王太子殿下とポンコツ護衛のほのぼの切ないラブコメディです

完結・オメガバース・虐げられオメガ側妃が敵国に売られたら激甘ボイスのイケメン王から溺愛されました
美咲アリス
BL
虐げられオメガ側妃のシャルルは敵国への貢ぎ物にされた。敵国のアルベルト王は『人間を食べる』という恐ろしい噂があるアルファだ。けれども実際に会ったアルベルト王はものすごいイケメン。しかも「今日からそなたは国宝だ」とシャルルに激甘ボイスで囁いてくる。「もしかして僕は国宝級の『食材』ということ?」シャルルは恐怖に怯えるが、もちろんそれは大きな勘違いで⋯⋯? 虐げられオメガと敵国のイケメン王、ふたりのキュン&ハッピーな異世界恋愛オメガバースです!


売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

血のつながらない弟に誘惑されてしまいました。【完結】
まつも☆きらら
BL
突然できたかわいい弟。素直でおとなしくてすぐに仲良くなったけれど、むじゃきなその弟には実は人には言えない秘密があった。ある夜、俺のベッドに潜り込んできた弟は信じられない告白をする。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















