1 / 4
1
しおりを挟む
私の名前は、リディア・アシュレイ。
アシュレイ伯爵家の長女で、今年で二十歳になる。
──けれど、そう名乗ったところで、「ああ、あの地味な令嬢」と返されるのがオチだ。
きらびやかなドレスや、香水の香り、舞踏会のざわめき。
社交界のあの空気が、どうにも苦手だった。
私はいつも、隅っこの椅子に座って、甘くないお茶をすする役。
口元に笑みを浮かべて、ただ静かに時が過ぎるのを待っていた。
「また、つまらなそうな顔してるな」
ふいに声をかけられて顔を上げると、目の前には、
いつものように気だるげな笑みを浮かべた、私の婚約者がいた。
ダミアン・フェリル。
侯爵家の三男で、金髪碧眼、背も高くて、顔立ちも整っている。
だけど──口を開けば、だいたい人を小馬鹿にしたようなことばかり言う。
「僕の隣にいるっていうのに、どうしてそんなに退屈そうなんだ?
可愛いドレスも着てるのに、笑いもしない。ほんと、つまらないよ、リディア」
「……そう。ごめんなさい、ダミアン様。つまらなくて」
私は少しだけ首を傾げて、そう答えた。
彼は、ふん、と鼻で笑ってワイングラスをくるくる回した。
私の顔を見ようともしないで、グラスの中の赤い液体ばかり見ていた。
私のことなんて、もともと見ていなかったのよね。
リディアという名の“お飾り”に、ほんの少しの興味もなかったくせに。
でもそれで、よかった。
彼の興味が私に向かなくなってから、もうずいぶん経つし。
私はただ、その日が来るのを待っていた。
──婚約破棄のその日を。
舞踏会の夜は、まるで絵に描いたように煌びやかだった。
真紅のドレスに身を包んだ私は、いつもよりもほんの少しだけ、背筋を伸ばしていた。
貴族たちが集う大広間で、音楽が鳴り響く中、
ダミアンは美しい金髪の少女と手を取り、軽やかにステップを踏んでいた。
その少女の名前は、セリーヌ・モルドレッド。
侯爵家の次女で、妖精のように愛らしく、誰よりも注目を浴びる存在。
──彼が私の元から離れる理由としては、申し分ない相手だった。
そして、音楽が止まった瞬間。
ダミアンは皆の前で、誇らしげに笑ってこう言った。
「本日をもって、僕はリディア・アシュレイとの婚約を破棄する。
理由は簡単。彼女はあまりにも“つまらない”からだ。
僕には、もっとふさわしい相手がいる。
そう──このセリーヌこそ、僕の理想の女性なんだ!」
空気が凍った。
セリーヌは頬を赤らめて、うっとりした顔でダミアンの腕に寄り添っていた。
周囲の貴族たちは、口元を手で隠してささやき合う。
「まあ……」「なんてことを……」「婚約破棄を、こんな場で……!」
だけど私は、静かにその場に立っていただけだった。
涙も出なかったし、怒りもなかった。
ただ、「ああ、ついに来たな」と思っただけ。
「そう……わかりました」
私はダミアンを見上げて、ゆっくりと微笑んだ。
会場中の視線が、私に集まっていた。
「これで……あなたの“退屈”も、少しは晴れるといいですね」
それだけ言って、私はくるりと背を向けた。
ドレスの裾を踏まないように気をつけながら、
扉の向こうへと、一歩ずつ、歩いていった。
彼が何かを言いかけていたけれど、もう聞こえなかった。
私の耳には、誰の声も届かない。
──さようなら、ダミアン様。
これから、私は自由にさせていただきます。
屋敷に戻ると、私はそっと書き置きを残して、
長年暮らした伯爵家を後にした。
「──お嬢様……どちらへ……!」
慌てて飛び出してきた侍女の声に、私はふと足を止める。
「少し、風に当たってくるわ」
そう言って、月明かりの下、馬車に乗り込んだ。
私の帰る場所は、ここではない。
ずっと封じていた“あの場所”へ──
魔塔。
それが、私の本当の居場所。
そして、私はもう誰にも遠慮しない。
誰にも蔑まれず、誰にも縛られず。
私の力を、私の生き方を、私のすべてを、自分で決める。
さようなら、令嬢リディア。
これからは、魔女リディアとして──
夜の風は、思っていたよりもずっと冷たかった。
私を乗せた馬車が、ゆっくりと街を抜けていく。
煌びやかで人の多い王都の中心から離れれば離れるほど、
街灯の数は減り、静寂が広がっていった。
「本当に……これでよかったの?」
小さな声で、自分に問いかけてみたけど、返事はなかった。
もちろん。返してくれる人なんて、最初からいなかった。
私はただ、前を向くしかなかった。
婚約破棄の場で、あれだけのことを言われたのに、
悔しくて泣くことも、声を荒げることもなかった。
というより……そんな価値もない相手だったって、
本当は、もうずっと前からわかってた。
でも、それでも。
「許嫁」という肩書きに、私は少しだけしがみついていたのかもしれない。
だってそれを失ったら、私は──何者でもなくなってしまう気がして、こわかったから。
「……ううん、違う。私は、最初から“誰かのもの”なんかじゃなかった」
小さく息を吸って、馬車の窓を開けた。
遠くに、月が見える。
冷たいくらいに白くて、鋭く光っていて──でも、不思議と安心した。
あの月が見ていた。
私が婚約を破棄される瞬間も、誰にも必要とされなかった日々も。
全部、見ていた。
「リディア様、まもなく魔塔が見えてまいります」
御者の声がして、私は目を細めた。
……そう。私の帰るべき場所。
それは、王都の華やかさでも、伯爵家の屋敷でもない。
──それは、誰も寄りつかない、封印された塔。
“魔塔(まとう)”。
人々が「災厄の塔」と恐れた場所。
でもそこは、私にとっては……一番落ち着く“家”だった。
「ただいま、帰ってきたわ」
誰に言うでもなく、私は小さくつぶやいた。
塔の扉を開けた瞬間、重たくきしむ音が響いた。
埃の匂いと、なつかしい薬草の香りが鼻をくすぐる。
「ふふ……やっぱり、ここの匂いが好き」
私はドレスの裾をたくしあげて、ゆっくりと階段をのぼる。
この螺旋階段、昔は何度も転びそうになったっけ。
だけど今は、目をつむっていても登れる。
「……来たか、リディア」
中層の書斎にたどり着くと、そこにいたのは、私の“師匠”だった。
マルグリット様。
元は宮廷魔導師団の最高顧問で、今は引退して魔塔に隠居している。
彼女がいなければ、私は魔法の力も、心の支えも持てなかった。
「おかえり。遅かったじゃないか」
「……ただいま、マルグリット様」
私はその場に膝をついて、頭を下げた。
だけど次の瞬間、マルグリット様は私の髪をくしゃくしゃと撫でて、
まるで子どもにするみたいに、ふわっと笑った。
「お前がここに戻ってくる日を、ずっと待っていたよ。
――“月影のリディア”が、世界に戻ってくる日をね」
私は目を見開いた。
……その名前は。
昔、魔塔で修行していた頃、仲間たちが私につけた異名。
夜の魔力を操る得意属性から、そう呼ばれていた。
だけど、伯爵家に戻ってからは、ずっと封じていたの。
“魔法のことは忘れなさい”って、父に言われて……
いい子の令嬢でいるために、ずっと……ずっと。
「マルグリット様、わたし……本当に、これでよかったのかな」
「後悔しているのか?」
「……いいえ。してません。
私は……ただ、魔法を“使ってはいけない”って思い込んでいただけ。
でも今は違う。今は……使いたいって思ってる」
胸に手を当てると、熱くなった。
冷たい塔の空気とはまるで反対の、あたたかい火が、胸の奥で灯っていた。
「もう、誰かに否定されるのは嫌なんです。
誰かのために、自分を小さくするのも……」
「よく言った。では、その魔力……見せてごらん」
マルグリット様の声に、私は深く息を吸って、
ずっと、ずっと封じていた力にそっと手を伸ばした。
「――月影よ、私に応えなさい」
その瞬間、部屋の中に冷たい風が吹いた。
月の光が窓から差し込み、私の髪がふわりと浮かぶ。
まるで世界が私を認めてくれるような、そんな感覚。
何もかもが静かに、でも確かに動き出した。
「ああ……帰ってきたんだ、私……」
私は、もう“ただの令嬢”じゃない。
私は、魔女として生きる。
――“月影の魔女”として。
アシュレイ伯爵家の長女で、今年で二十歳になる。
──けれど、そう名乗ったところで、「ああ、あの地味な令嬢」と返されるのがオチだ。
きらびやかなドレスや、香水の香り、舞踏会のざわめき。
社交界のあの空気が、どうにも苦手だった。
私はいつも、隅っこの椅子に座って、甘くないお茶をすする役。
口元に笑みを浮かべて、ただ静かに時が過ぎるのを待っていた。
「また、つまらなそうな顔してるな」
ふいに声をかけられて顔を上げると、目の前には、
いつものように気だるげな笑みを浮かべた、私の婚約者がいた。
ダミアン・フェリル。
侯爵家の三男で、金髪碧眼、背も高くて、顔立ちも整っている。
だけど──口を開けば、だいたい人を小馬鹿にしたようなことばかり言う。
「僕の隣にいるっていうのに、どうしてそんなに退屈そうなんだ?
可愛いドレスも着てるのに、笑いもしない。ほんと、つまらないよ、リディア」
「……そう。ごめんなさい、ダミアン様。つまらなくて」
私は少しだけ首を傾げて、そう答えた。
彼は、ふん、と鼻で笑ってワイングラスをくるくる回した。
私の顔を見ようともしないで、グラスの中の赤い液体ばかり見ていた。
私のことなんて、もともと見ていなかったのよね。
リディアという名の“お飾り”に、ほんの少しの興味もなかったくせに。
でもそれで、よかった。
彼の興味が私に向かなくなってから、もうずいぶん経つし。
私はただ、その日が来るのを待っていた。
──婚約破棄のその日を。
舞踏会の夜は、まるで絵に描いたように煌びやかだった。
真紅のドレスに身を包んだ私は、いつもよりもほんの少しだけ、背筋を伸ばしていた。
貴族たちが集う大広間で、音楽が鳴り響く中、
ダミアンは美しい金髪の少女と手を取り、軽やかにステップを踏んでいた。
その少女の名前は、セリーヌ・モルドレッド。
侯爵家の次女で、妖精のように愛らしく、誰よりも注目を浴びる存在。
──彼が私の元から離れる理由としては、申し分ない相手だった。
そして、音楽が止まった瞬間。
ダミアンは皆の前で、誇らしげに笑ってこう言った。
「本日をもって、僕はリディア・アシュレイとの婚約を破棄する。
理由は簡単。彼女はあまりにも“つまらない”からだ。
僕には、もっとふさわしい相手がいる。
そう──このセリーヌこそ、僕の理想の女性なんだ!」
空気が凍った。
セリーヌは頬を赤らめて、うっとりした顔でダミアンの腕に寄り添っていた。
周囲の貴族たちは、口元を手で隠してささやき合う。
「まあ……」「なんてことを……」「婚約破棄を、こんな場で……!」
だけど私は、静かにその場に立っていただけだった。
涙も出なかったし、怒りもなかった。
ただ、「ああ、ついに来たな」と思っただけ。
「そう……わかりました」
私はダミアンを見上げて、ゆっくりと微笑んだ。
会場中の視線が、私に集まっていた。
「これで……あなたの“退屈”も、少しは晴れるといいですね」
それだけ言って、私はくるりと背を向けた。
ドレスの裾を踏まないように気をつけながら、
扉の向こうへと、一歩ずつ、歩いていった。
彼が何かを言いかけていたけれど、もう聞こえなかった。
私の耳には、誰の声も届かない。
──さようなら、ダミアン様。
これから、私は自由にさせていただきます。
屋敷に戻ると、私はそっと書き置きを残して、
長年暮らした伯爵家を後にした。
「──お嬢様……どちらへ……!」
慌てて飛び出してきた侍女の声に、私はふと足を止める。
「少し、風に当たってくるわ」
そう言って、月明かりの下、馬車に乗り込んだ。
私の帰る場所は、ここではない。
ずっと封じていた“あの場所”へ──
魔塔。
それが、私の本当の居場所。
そして、私はもう誰にも遠慮しない。
誰にも蔑まれず、誰にも縛られず。
私の力を、私の生き方を、私のすべてを、自分で決める。
さようなら、令嬢リディア。
これからは、魔女リディアとして──
夜の風は、思っていたよりもずっと冷たかった。
私を乗せた馬車が、ゆっくりと街を抜けていく。
煌びやかで人の多い王都の中心から離れれば離れるほど、
街灯の数は減り、静寂が広がっていった。
「本当に……これでよかったの?」
小さな声で、自分に問いかけてみたけど、返事はなかった。
もちろん。返してくれる人なんて、最初からいなかった。
私はただ、前を向くしかなかった。
婚約破棄の場で、あれだけのことを言われたのに、
悔しくて泣くことも、声を荒げることもなかった。
というより……そんな価値もない相手だったって、
本当は、もうずっと前からわかってた。
でも、それでも。
「許嫁」という肩書きに、私は少しだけしがみついていたのかもしれない。
だってそれを失ったら、私は──何者でもなくなってしまう気がして、こわかったから。
「……ううん、違う。私は、最初から“誰かのもの”なんかじゃなかった」
小さく息を吸って、馬車の窓を開けた。
遠くに、月が見える。
冷たいくらいに白くて、鋭く光っていて──でも、不思議と安心した。
あの月が見ていた。
私が婚約を破棄される瞬間も、誰にも必要とされなかった日々も。
全部、見ていた。
「リディア様、まもなく魔塔が見えてまいります」
御者の声がして、私は目を細めた。
……そう。私の帰るべき場所。
それは、王都の華やかさでも、伯爵家の屋敷でもない。
──それは、誰も寄りつかない、封印された塔。
“魔塔(まとう)”。
人々が「災厄の塔」と恐れた場所。
でもそこは、私にとっては……一番落ち着く“家”だった。
「ただいま、帰ってきたわ」
誰に言うでもなく、私は小さくつぶやいた。
塔の扉を開けた瞬間、重たくきしむ音が響いた。
埃の匂いと、なつかしい薬草の香りが鼻をくすぐる。
「ふふ……やっぱり、ここの匂いが好き」
私はドレスの裾をたくしあげて、ゆっくりと階段をのぼる。
この螺旋階段、昔は何度も転びそうになったっけ。
だけど今は、目をつむっていても登れる。
「……来たか、リディア」
中層の書斎にたどり着くと、そこにいたのは、私の“師匠”だった。
マルグリット様。
元は宮廷魔導師団の最高顧問で、今は引退して魔塔に隠居している。
彼女がいなければ、私は魔法の力も、心の支えも持てなかった。
「おかえり。遅かったじゃないか」
「……ただいま、マルグリット様」
私はその場に膝をついて、頭を下げた。
だけど次の瞬間、マルグリット様は私の髪をくしゃくしゃと撫でて、
まるで子どもにするみたいに、ふわっと笑った。
「お前がここに戻ってくる日を、ずっと待っていたよ。
――“月影のリディア”が、世界に戻ってくる日をね」
私は目を見開いた。
……その名前は。
昔、魔塔で修行していた頃、仲間たちが私につけた異名。
夜の魔力を操る得意属性から、そう呼ばれていた。
だけど、伯爵家に戻ってからは、ずっと封じていたの。
“魔法のことは忘れなさい”って、父に言われて……
いい子の令嬢でいるために、ずっと……ずっと。
「マルグリット様、わたし……本当に、これでよかったのかな」
「後悔しているのか?」
「……いいえ。してません。
私は……ただ、魔法を“使ってはいけない”って思い込んでいただけ。
でも今は違う。今は……使いたいって思ってる」
胸に手を当てると、熱くなった。
冷たい塔の空気とはまるで反対の、あたたかい火が、胸の奥で灯っていた。
「もう、誰かに否定されるのは嫌なんです。
誰かのために、自分を小さくするのも……」
「よく言った。では、その魔力……見せてごらん」
マルグリット様の声に、私は深く息を吸って、
ずっと、ずっと封じていた力にそっと手を伸ばした。
「――月影よ、私に応えなさい」
その瞬間、部屋の中に冷たい風が吹いた。
月の光が窓から差し込み、私の髪がふわりと浮かぶ。
まるで世界が私を認めてくれるような、そんな感覚。
何もかもが静かに、でも確かに動き出した。
「ああ……帰ってきたんだ、私……」
私は、もう“ただの令嬢”じゃない。
私は、魔女として生きる。
――“月影の魔女”として。
24
あなたにおすすめの小説

「地味ブス」と捨てられた私、文化祭の大型スクリーンで王子様の裏の顔を全校生に配信します
スカッと文庫
恋愛
「お前みたいな地味女、引き立て役にもならないんだよ」
眼鏡にボサボサ頭の特待生・澪(みお)は、全校生徒が見守る中、恋人だった学園の王子・ハルトから冷酷に捨てられた。
隣には、可憐な微笑みを浮かべる転校生・エマ。
エマの自作自演により「いじめの犯人」という濡れ衣まで着せられ、学園中から蔑まれる澪。
しかし、彼女を嘲笑う者たちはまだ知らない。
彼女が眼鏡の奥に、誰もが平伏す「真実の美貌」と、学園さえも支配できる「最強の背景」を隠していることを――。
「……ねぇ、文化祭、最高のステージにしてあげる」
裏切りへのカウントダウンが今、始まる。
スクリーンの裏側を暴き、傲慢な王子と偽りのヒロインを奈落へ突き落とす、痛快・学園下剋上ファンタジー!

【完結】捨てられた令嬢は、国一の美女で精霊の姫でした。
丸顔ちゃん。
恋愛
「無能力で地味」
そう言われ、第二王子レオンハルトに婚約破棄された公爵令嬢エリシア。
だが彼女は知らなかった。
自分が“精霊王の血”を継ぐ、唯一の精霊姫であることを。
王城を去ろうとしたその時、寝たきりの第一王子アルベルトに呼び止められる。
彼は幼いころからエリシアを想い続けていた。
暴走する魔力に苦しむ彼の手を取った瞬間、精霊たちが光を放ち、
アルベルトの魔力は静まり、彼は初めて立ち上がる。
「……ずっと、君を迎えに行きたかった」
その奇跡は王国中に広まり、
アルベルトは王位継承権を取り戻す。
一方、エリシアを失った第二王子と男爵令嬢は、
公務は崩壊、魔道具は暴走、貴族社会からの信用も失い、
互いに責任を押し付け合いながら破滅していく。
これは、捨てられた令嬢が“国一の美女で精霊姫”として覚醒し、
真の王と共に歩むまでの逆転劇。
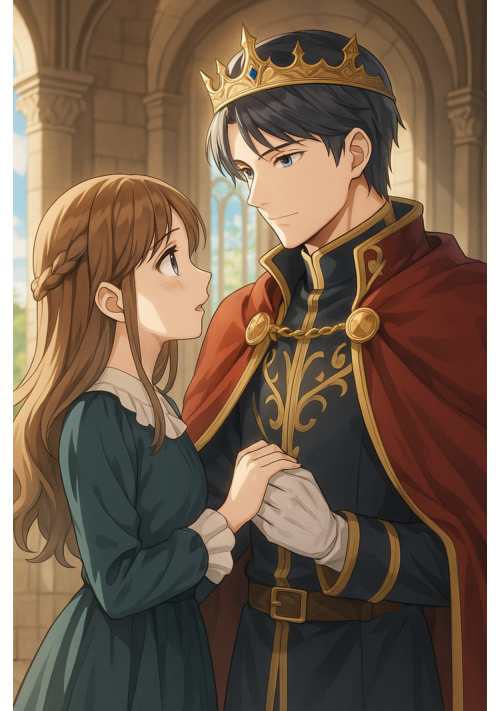
ご愁傷様です~「冴えない女」と捨てられた私が、王妃になりました~
有賀冬馬
恋愛
「地味な君とは釣り合わない」――私は、婚約者の騎士エルマーにそう告げられ、婚約破棄された。病弱で目立たない私は、美しい妹と比べられ、家族からも冷遇されてきた。
居場所を失い、ひっそり暮らしていたある日、市場で助けた老人が、なんとこの国の若き国王陛下で!?
彼と私は密かに逢瀬を重ねるように。
「愚かな男には一生かかっても分かるまい。私は、彼女のような女性を誇りに思う」妃選びの場で告げられた国王陛下の一言に、貴族社会は騒然。

「影が薄い」と 捨てられた地味令嬢は、王太子に見初められました ~元婚約者と妹は、どうぞご勝手に~
有賀冬馬
恋愛
「君は影が薄い」――そう言って、婚約者の騎士様は華やかな妹を選び、私を捨てた。
何もかもを諦めて静かに暮らそうと決めた私を待っていたのは、孤児院での心温まる出会いだった。
そこで素性を隠して旅をしていたのは、なんと隣国の王太子様。
「君こそ、僕の唯一の光だ」そう言って、私のありのままを受け入れてくれる彼。その彼の隣で、私は生まれ変わる。
数年後、王国間の会議で再会した元婚約者は、美しく気品あふれる私を見て絶句する……

物置部屋に追いやられた伯爵令嬢ですが、公爵様に見初められて人生逆転しました〜妹の引き立て役だったのに、今では社交界の花と呼ばれています〜
丸顔ちゃん。
恋愛
伯爵家の令嬢セレナは、実母の死後、継母と義妹に虐げられて育った。
与えられた部屋は使用人以下の物置、食事は残飯、服はボロ。
専属侍女も与えられず、家の運営や帳簿管理まで押し付けられ、
失敗すれば鞭打ち――それが彼女の日常だった。
そんなある日、世間体のためだけに同行させられた夜会で、
セレナは公爵家の跡取りレオンと出会う。
「あなたの瞳は、こんな場所に閉じ込めていいものではない」
彼はセレナの知性と静かな強さに一瞬で心を奪われ、
彼女の境遇を知ると激怒し、家族の前で堂々と求婚する。
嫁ぎ先の公爵家で、セレナは初めて“人として扱われ”、
広い部屋、美味しい食事、優しい侍女たちに囲まれ、
独学で身につけた知識を活かして家の運営でも大活躍。
栄養と愛情を取り戻したセレナは、
誰もが振り返るほどの美しさを開花させ、
社交界で注目される存在となる。
一方、セレナを失った伯爵家は、
彼女の能力なしでは立ち行かず、
ゆっくりと没落していくのだった――。
虐げられた令嬢が、公爵の愛と自分の才能で幸せを掴む逆転物語。

婚約破棄されましたが、隣国の大将軍に溺愛されて困ってます
有賀冬馬
恋愛
「君といると退屈だ」
幼い頃からの許嫁・エドワルドにそう言われ、婚約破棄された令嬢リーナ。
王都では“平凡で地味な娘”と陰口を叩かれてきたけれど、もう我慢しない。
わたしはこの国を離れて、隣国の親戚のもとへ――
……だったはずが、なぜか最強でイケメンな大将軍グレイ様に気に入られて、
まさかの「お前は俺の妻になる運命だ」と超スピード展開で屋敷に招かれることに!?
毎日「可愛い」「お前がいないと寂しい」と甘やかされて、気づけば心も体も恋に落ちて――
そして訪れた国際会議での再会。
わたしの姿に愕然とするエドワルドに、わたしは言う。
「わたし、今とっても幸せなの」

公爵家の家政を10年回した私が出ていったら、3ヶ月で領地が破綻しました
歩人
ファンタジー
エレナは公爵家に嫁いで10年、夫は愛人に入れ込み、義母には「家政婦代わり」と
罵られた。だが領地の財務も、商会との交渉も、使用人の管理も、全部エレナが
やっていた。ある日、義母から「あなたの代わりなんていくらでもいる」と言われ、
エレナは静かに離縁届を出した。「では、代わりの方にお任せください」
辺境の町で小さな商会を開いたエレナ。10年間の実務経験は伊達ではなかった。
商会はたちまち繁盛する。一方、エレナがいなくなった公爵家は3ヶ月で経営破綻。
元夫が「戻ってこい」と泣きつくが——
「お断りです。あと、10年分の未払い給金を請求いたしますね」

【本編完結】真実の愛を見つけた? では、婚約を破棄させていただきます
ハリネズミ
恋愛
「王妃は国の母です。私情に流されず、民を導かねばなりません」
「決して感情を表に出してはいけません。常に冷静で、威厳を保つのです」
シャーロット公爵家の令嬢カトリーヌは、 王太子アイクの婚約者として、幼少期から厳しい王妃教育を受けてきた。
全ては幸せな未来と、民の為―――そう自分に言い聞かせて、縛られた生活にも耐えてきた。
しかし、ある夜、アイクの突然の要求で全てが崩壊する。彼は、平民出身のメイドマーサであるを正妃にしたいと言い放った。王太子の身勝手な要求にカトリーヌは絶句する。
アイクも、マーサも、カトリーヌですらまだ知らない。この婚約の破談が、後に国を揺るがすことも、王太子がこれからどんな悲惨な運命なを辿るのかも―――
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















