1 / 1
序章
四つ辻
しおりを挟む
彼女は、よくいる女子高生だった。毎日学校に通い、勉強して友達と遊び、部活に通う。勉強はそこそこ。部活はそれなり。親とも友人とも関係が良かった。親は彼女をちゃんと育てていたし、人との接し方、話し方、表情の作り方、マナー、社会的な場での振る舞い、礼儀をわきまえておた。だから、社会生活で障害を持つことなどある訳がなかった。
だが、そんな彼女はある時、地上に向けて高速に落ちた。その最中、彼女はずっと自問していた。
─────どうして、こんなことにと。
彼女は、どこにでもいる少女だったのだ。親に愛され、友人らと親しみ、日々を楽しんで生きていた。なのに、何故こんなことに。
地面に顔の半分をめり込ませながら、まだかろうじて残る意識の中で、彼女は自問し続けた。
何故こんなことに、どうして────。
誰のせいで。
石畳に自ら流した血が広がっていくのを見つめながら、ただ問い続けた。
束川董也は夜の学校を一人で歩いていた。彼はこの長月第七高校の生徒会長で、他の生徒より早く来て、遅く帰ることが多かったが、それにしても今日は遅かった。窓の外はとっぷりと日が暮れて、水平線の向こうに僅かに赤い夕陽の残滓が残るのみで、殆ど夜。暗い中で廊下だけに灯りがともり、ぼんやりと浮き立つように光る様は何だか不気味だった。
だが、董也はその中を確かな足取りで歩いていた。彼は身長は平均程度だが姿勢が非常に良いので歩む様に妙に威厳がある。刈り込まれた黒髪、黒縁眼鏡の奥に、少し厚めの瞼に覆われたゆえに半眼に見えて些か目つきが悪く見えるが、それでも覗く黒い瞳に誠実さと平静さ湛えているから怖くは見えない。眉は平坦で面長の顔はのっぺりして、表情から一切の動揺は見えず、口は厳に引き結ばれて堅固な意志を感じる。
彼はある目的があって、もう人のいなくなった校舎に一人いるのだ。
「……」
ふいに、人の気配がした。ちょうど眼前にある曲がり角の先。彼の立ち位置からは見えないが、確かに人の足音がした。
「おいっ、誰かいるのか!?」
そう叫ぶと、足音が急に早く大きくなりだした。そこから駆け出したようだ。
「待てっ!!」
叫びつつ、董也も駆け出す。足音が二重になった。角を曲がると、校舎中央の階段を降りたらしい。三階のその場所から、董也も駆け降りる。決して運動神経が悪くない彼だが、眼前の人物はそれより数歩早く、踊り場に出る時にはもう階下にいて、姿を認めることが出来ない。軽い足取りでリズミカルに早く、階段を降りているようだ。────女の足か?と、董也は一階まで降りていた。すると今度は平面での追いかけっこが始まる。
「おいっ……、いい加減に……!」
苛立ちのまま足に力を込めて速度を上げる。距離が詰まるのを感じる。そして、中央の階段から真っ直ぐ伸びた廊下の終点、校庭と逆の樹木に覆われた校舎裏に面するそこは、夜の時間は真っ暗闇だ。そこに追い込む。董也は制服のポケットから携帯電話を取り出し、ライトを付けて暗闇で佇む人物を照らした。
その瞬間、黒縁の眼鏡の奥の吊り上がった目に映ったのは、真っ赤な毛並み。暗闇の中で一点に絞られた光の中で異様に輝いて見える赤色。
「……野茨か?」
董也が問う。すると赤毛に少女は少々気まずげに微笑んだ。その瞬間、廊下に灯りがつく。それに驚きつつも、眼前を見ると、そこにはやはり見知った少女が立っていた。クラスは違うが同級生。
二年生の野茨織麻。数多くいる生徒の中で、生徒会長とはいえ束川董也が彼女を知っていたのは、その少女が校内でもひどく目立つ存在だからだ。人目を引く真っ赤な髪。腰まで伸びたその髪は波打ち、少女の華奢な身体を覆うようだ。赤い穂波の中の顔は白く小さい。細い輪郭の中にくっきした眦の大きな目。その中央の虹彩は青く、やたらと白い肌といい筋の通った鼻といい、全体に彫りの深い顔立ちといい、一目で混血と分かる彼女は校内でも目立つ存在だ。二年生の中でも群を抜く美少女。それがこの長月第七高校の、野茨織麻に対する評価。
「……何やってんだ、こんな時間に」
普段から親しい間柄ではないが、それでも生徒会長の義務として、下校時間を過ぎて校舎にいる彼女の行動を咎める。単純に疑問でもあった。織麻は、校内では目立っても風紀を乱す存在ではない。成績も授業態度もまあ普通、友人関係、教師との関係も悪くない。ダンス部に所属する、極めて模範的な女子生徒である。
模範生、野茨織麻は気まずそうに微笑む。
「ええっと……。探検?」
おどけるような口調で返され、董也は瞬間的に眉間に皺を寄せた。
「お前か?最近夜に校舎うろついてるのは」
そう問われると、織麻は慌てたように手を振る。
「違う違う。夜来たのは今日が初めてで……」
「じゃあお前も妙な噂聞きつけて、肝試しでもしに来たのか。高校生にもなって、何やってる!」
怒鳴る生徒会長に織麻は肩をすくめる。
「……会長は、そういうのの取り締まり?」
「ああ、そうだよ。馬鹿な噂の真相と、それを間に受けて校内を嗅ぎ回る奴を見つけに来たんだ」
束川董也の目的はそれだった。この頃、長月第七高校には、妙な噂が立っていて、生徒らが浮き足立っていた。董也は生徒会長として、その収束のために動こうとしていた。
「高校生にもなって、噂を信じ込んで下校後に学校に居残ってたり、他校から進入者まで出た」
「ああ、知ってる。投稿サイトに上がってたね」
「すぐに消させたよ。はた迷惑な……」
ひどく忌々しげに周囲を見る。別段変わったところもない夜の学校。
「ああいう手合いを寄せ付けないために、根本を解決しないと」
「え?」
織麻が首を傾げる。束川は眉間の皺を更に深くした。
「噂の元になってる奴から聞き取りしたんだよ。そしたら、複数人から共通の目撃証言があった。それだけの証言があるなら、眉唾じゃない。何かしらある」
「……どう考えてるの?」
実に行動的な有能な生徒会長に問う。董也は黒縁の眼鏡の奥の目を険しくさせて答える。
「誰かの演出だろ。騒動起こして楽しんでんだ」
「なるほど」
「だから見回りしてたんだよ。人がいれば姿を現すかも」
「手伝うよ」
そう声を出したのは、織麻でも董也でもなかった。董也がぎょっとして、声の方を見る。すると、制服姿の男子学生が立っていた。先程電気つけたのは彼らしい。
「転校生……」
「上屋だ」
そう名乗った彼は、つい先頃この学校に来た転校生だった。そうだ、確か上屋清鈴といった。季節外れの転校生に関する情報を思い出す。
「……お前ら、二人で来てたのか?」
「あ、うん……」
織麻は頷く。学年は一緒でもクラスは違うこの二人に接点は見えないが、いつに間にそんなに親密になったのだろう。真っ赤な髪でいつも溌剌とした印象の明るい美少女と、黒髪を短く切り揃え、大きな瞳ではあるがいつも伏せ目がちであるゆえ切れ長に見えてやや冷淡な印象の、口を尖り気味に引き結びそこに細い顎の鋭角性も伴って、端正であるが親しみにくい顔つきの神経質そうな少年とは、どうにも合わない気がするのだが。
「別に変な仲じゃないよ」
「……今回の件に興味があって」
清鈴の発言に、董也は首を傾げる。
「心霊に興味でも?」
「そんなところ」
そんな印象は全くない同級生に、不可解な点を感じたが、しかし浮ついた感はない彼と、根は真面目と知っている織麻なら信用できると思った。
「そうだな。人が多い方が目立つし、釣りやすいかもしれない」
そう言って、改めて廊下を見据える。一階のちょうど端に来て、真っ直ぐ伸びる長い廊下が見渡せた。
「せっかくだ。ここから三階までしらみ潰しで行こう」
「おー」
「行こう」
そう言って、清鈴は壁に設置された電気のスイッチを全て押した。一階廊下が一気に明るくなって暗がりを照らし、闇夜との境界線がより目立って、その対比を際立たせた。
長月第七高校は、その名で設立されてからはまだ二年目である。しかし、校舎自体は十数年が経っており、それなりに年季が入っている。校名と校舎の歴史に食い違いがあることで分かるように、成り立ちがやや複雑であったが、基本的には平和な校風の中で近頃不穏な噂が流れていた。
曰く、夜な夜な女の霊が出て、通りがかった生徒の眼前で死んで見せると。
部活や自習で遅くまで居残っていた者が見たらしい。中校舎の屋上から制服姿の女性が飛び降りる様を。慌てて飛び降りた先に駆けつけると、そこには何の痕跡もない。一度なら見間違いで済むだろうが、そんなことが何度も起きた。女子生徒が飛び降りて、しかし地面には何もない。何人もがそれを見たと証言したから、こんな噂が立ったのだ。
昔自殺した女子生徒の霊が成仏できないまま彷徨い、何度も自身の“死”を繰り返しているのだと。
「馬鹿馬鹿しい」
束川董也は吐き捨てた。いかにも厳格な生徒会長の言いように、織麻は苦笑いした。
「言い切るな。人為的なもんだった確信してんのか」
心霊現象に全く感応がないらしい生徒会長に上屋清鈴が問う。黒縁眼鏡の奥から睨めつけながら、董也は答える。
「当たり前だ。自殺者の霊なんて、ある訳がない」
「根拠は?」
「今探してる」
廊下を進みながら教室を覗いて回る。トイレや用具入れまで確認した。だが、根拠は見つからない。
「異常なし……」
董也が険しい顔で溜め息をつく。その様を見て、清鈴は眉を寄せる。
「ずいぶん熱心だな」
生徒会長の職責としてもやたら力の入っている様子を訝しむ。董也は更に顔を険しくする。
「当たり前だろ。こんなタチの悪い悪戯、何度も……」
「何度も?」
董也の言葉に反応すると、織麻が苦笑いした。
「前にもちょっとあったんだよね、ネット関係で……。ほら、うちって成り立ちが複雑じゃない?元からネット社会の一部から注目されてて、それでまあ……変な情報ってか校内の動画が流出しちゃって、そこから一時期ひどかったのよ。イタズラ電話とか」
「まあすぐに収まったがな。ほんとにタチが悪い……」
憤慨する生徒会長に、清鈴は肩をすくめる。まあ何かしら前例があるなら、それを疑いたくなるのも分かる。しきりに周囲に目を光らす厳しい顔は、生真面目さと律儀さに満ちている。自身の考えが正しいと信じて、その行動が学校や生徒にためになると信じ、自らの役職に相応しい義務を果たそうとしている。今時珍しい真面目な高校生。だが、真面目な人間というのは裏を返せば頑固で偏狂でもあり、自分が見たものしか信じない。そこに以前の悪質な工作の事例もあって、今回のものもそれに倣うものと決め込んでいるようだ。
清鈴の視線を感じ取ったのか、董也はふいに振り向いた。いかにも現実主義的な理系の顔。眉間に皺が寄る。
「何だよ」
「別に」
更に歩を進める。人のいない校舎には、三人の足音だけが響いている。普段は喧騒に包まれる場に、いやに目立つ足音。廊下には影がくっきり見えるて、光の加減で二重三重にもなって、一つの影が別の影を追うようにも見えてぎょっと驚く。振り返っても誰もいない。だが、妙に不安が心にかかる。
野茨織麻が呟く。
「夜の学校って不気味……」
その言葉に、束川董也は眉をひそめる。
「別に必要以上に怖がることじゃない。時間と人数が違うだけで、いつもと同じ学校だ」
どこまでも冷静で現実的な物言い。やはり理性が強い。理屈抜きの本能的恐怖というものが少ないのだろうし、それを抱く他者に共感もしない。頼もしいとも言えるが、織麻はやや不満げである。
「会長ー。ホラー映画じゃそういうこと言う人からヤられちゃうんだから」
「やられるかよ。夜の学校でこそこそ生徒怖がらせてる愉快犯に負けるほど弱くない」
「……」
彼にとって、今回の件の真相はそれで決着がついているらしい。
その頑固さに呆れた視線を感じたか、生真面目な生徒会長はまた振り向いて、清鈴を睨む。
「だから何だ」
「現実的だなと思って」
「お前、幽霊とか信じてるクチか?」
超常現象として伝えられる今回の件をそうと捉えているのかと、堅そうな端正な顔に問うが、清鈴は無言のままだ。それを是と取り、董也は溜め息をつく。また背を向けて歩き出した彼に、清鈴が問う。
「逆にあんたは何で信じない?」
「見たことがない」
簡潔な答え。予想通りだ。
「あんたが見たことないからって無いとは限らない。あんたの視野が狭いだけかも」
「……見たことないもんを、どう信じろっていうんだ」
堂々巡りになりそうな言葉を吐き合う。清鈴は正論屋の理系を見つめる。
「それを言うなら、あんたが探す誰かだって、いるかどうか分からないだろ」
前例があるにしても、今回もそれとは限らない。探し求める先が見えないという点では、彼の意見もまた根拠がない。
董也の眼鏡の奥の、歳の割には光の据わった目が歪む。
「根拠はなくても、経験はあんだよ。伊達に生徒会長なんかやってない。」
そう言いながら、少し歩調を早める。それに合わせて、他の二人も早足になった。董也は真っ直ぐに階段を駆け上がり出した。脇目も振らない駆け足に、二人はやや戸惑うが、付いて行く。三階の更に上、生徒らの活動範囲を越え、階段しか無くなったその先に、小さなドア。董也は、その鍵穴に簡素なキーホルダーの付いた鍵を入れて回す。ひどく錆びついた音を立てて、ドアは開いた。
瞬間、湿った空気。六月も終わりの時期だった。本来は梅雨なのだろうが、昨今の気候事情ゆえか雨が少なく、それでも湿った空気は立ち込めていて、そこに早い夏の暑気が混じって、日中には耐え難い不快な空気に纏わりつかれることもあるが、今は夜半。しかも四階の高さの屋上は風も強い。湿り気と風と、ほんの僅かな冷気。まだらの空気の中で、野茨織麻は赤い髪を風の中で翻して、静かに言った。
「屋上に来たの初めてかも……」
「そうなのか?」
転校生の上屋清鈴が問うと、普段は立ち入り禁止だと董也が言い添える。
「だからこそ、鍵の複製なんか作られちゃ、やりたい放題なんだよな……」
この場への鍵は普段は職員室に保管されているが、そう厳重でもなく、持ち出そうと思えば出来るらしい。複製でも造られらたかも、というのが董也の意見らしい。
三人は周囲を見渡した。校舎全体の屋根の上にある広い広い空間。暗く寒く、今は三人しかない。
……ここが、件の“幽霊”が飛び降りるとされる場所なのだ。
三人、そこに歩む。ちょうど屋上の中央、胸元までの柵がある。
「ちょうど校舎の真ん中でもあるんだ」
手すりから視線を下ろし、織麻が呟く。ここは横に広がる校舎の中心でもある。そして、前面に校舎、後面にも校舎、縦に見ても真ん中だった。
長月第七高校の校舎は、90メートルほどの校舎が並行に三列並んでおり、その真ん中を渡り廊下が貫いている造りだ。南北に一棟ずつ。ここはその間。ちなみに南校舎の向こうには食堂や体育館、プールがあり、北校舎の裏はちょっとした林になっている。
「何か新鮮……。こんな角度から学校見ることなんてないし」
校舎を高い位置から真横に見る。確かに、滅多にあることではない。時折校舎の窓からぼんやり外を見やって、何となく対面の校舎を眺めているが、あくまで視界に入るのは一部だ。こんな高みから、校舎全体を俯瞰で見ることはない。三棟ある校舎の中で屋上があるのはこの中央棟だけなので、名実ともにここが校内で一番高い場所だ。
「おい、あんまり乗り出すな」
手すりの向こうの光景に魅入る織麻を、清鈴が制す。彼女はハッと気付いたように後ろに退く。
束川董也は、むしろ積極的に前のめりになって、柵の付近を確認している。
「……見た感じ、それらしい小細工はないな」
清鈴がどこか挑むように言う。董也は眉間を寄せた。
人を使って飛び降りを演出しているなら滑車、それ自体が映像ならプロジェクターでもあるかと思ったが、見当たらない。ただ錆びて古ぼけた暗褐色の柵があるだけだ。
「……他に隠してるかも」
まだ言う董也に、清鈴は肩をずり下ろす。
「まだ疑うのかよ。他の場所っていったって、さんざん探しただろ」
咎めるような言葉に、董也は鋭い視線を向ける。
「ここに来るまでの場所だけだろ。他の校舎も含めて、教室がいくつあると思ってんだ」
「……いくつあるの?」
織麻が聞く。
「普通教室で三十、特別教室が十五」
「……」
「そんなにあるの!?」
董也の言葉に驚く。自校だが、案外詳しい内容は知らない。改めて聞いてみれば、結構多い。
「うちは一学年5クラス。少子化時代にしちゃ多い方だが、昔はもっと多かった。その名残だよ」
「その計算じゃ、使われてない教室も多そうだな」
単純計算すれば、普通教室は半分余る。締め切られ、誰も足を踏み入れなくなった場所。
「誰かが隠れたり、何かを隠したりするには十分か」
「そういうことだ」
束川董也は踵を返して、扉に向かおうとする。その背に、上屋清鈴は声をかける。
「それが人外だっていう選択肢は?」
董也は胡乱げな目で振り向いた。その視線に構わず、清鈴は腰に手を置いて問い続ける。
「あんたの“経験”てのは、学校の間取りに詳しいことか?まあさすがは生徒会長だな」
一般の生徒より学校設備に詳しいのはさすがと言える。そこに何かがあるという確信には説得力がある。だが、その何かが何かまでは、彼の“経験”の中に根拠は見えない。
董也は眉間を寄せて、眼鏡の奥の眦を吊り上げた。我を譲らない男二人が見合う様を見て、野茨織麻はやや焦る。落ち着いてと言いかけたところに、束川董也はふいに表情を緩めて、小さく溜め息をつく。
その様子に、織麻も清鈴も目を丸くする。彼は言った。
「……確かにああいう場所には得体の知れないもんが湧くもんさ。……案外、人でないものもいるかもな」
「………」
先程までと真逆の言葉に、二人はますます目を丸くする。董也は俯いて深々と溜め息をつく。
「本当に、どうやって見つけるんだっていうぐらい、器用に人目を避けて湧く。………………校舎裏で煙草吸う不良」
「……」
「………」
「空き教室でイチャつくカップル、人通りの少ない階段の踊り場でゲーム、未使用倉庫で喧嘩、廃品置き場でひたすら寝てる奴………」
最後の方に怒気があった。恐らく日々彼を苛立たせている出来事なのだろう。……なるほど、これが“経験”か。
「場所を閉め切っても、また別の場所を見つけて、下手すりゃ忍び込んででも同じことをしやがる。……っその根性を他に向けろ、ていうか家でやれ!!」
「………」
「……学校でやるってのがいいんだろうね──」
董也の叫びに清鈴は眉を歪め、織麻は苦笑した。
少女の笑みに、董也は少し呼吸を整える。冷静な表情が戻って来る。
「何か一つ見つけたとしても、その時にはまた別の場所で別の何かが起こってて、その歯止めはない」
ましてや、と、董也は眉間を深く寄せる。
「それが机の下で操作されるスマホの中で起こってるんじゃ、そうそう見つけることも叶わねえよ」
「……」
忸怩たる響きがあった。董也はまた大きく溜め息をつく。
「調べたんだけどな。……確かに昔、校内で死んだ女子生徒はいた」
「え」
織麻、清鈴が目を見開く。
「結構前のことだが、今時ネット使えば昔の事件のことはいくらでも調べられる。……まあ、調査不足だが」
「原因は?」
「いじめを苦にした自殺」
「気の毒ね……」
織麻の呟きに董也は頷く。
「それを利用して騒動起こして、それをまたネットでの馬鹿騒ぎの燃料にしようとしてるなら許せない」
その声と表情には真摯な怒りがあった。
「もう話題が上がってるの?」
「ちらほらとな」
そう言いながら、董也は自分のスマートフォンを出して、SNSを開く。その中に、“長月第七高校”“幽霊”“女子生徒”“飛び降り”の文字がある。
「……これで動画でも上がろうもんなら大バズりだろうね」
織麻が引き攣った笑いを浮かべるが、董也は険しい表情のままだ。
「そんなことさせられるか。また学校の運営に影響が出たら困るし、……何より、遺族がどう思う」
その言葉に、織麻、清鈴は董也を見る。彼の顔はやはり険しく、真摯だ。
「昔って言っても、十数年前のことだ。まだ遺族は健在だろうし、身内の悲劇を面白おかしくネタにされたらたまったもんじゃない」
「そうだね……」
董也の言葉はどこまでも正しかった。学校のため、生徒のため、死んだ生徒、その家族。誰もが傷つかないように、今回の件を早急に解決しようとしている。
董也はスマホの画面を睨む。根拠のない推測や真贋の分からない情報が入り乱れている。それに反応して、また新たな推論が、情報が現れる。彼は忌々しげに言う。
「隠れてこそこそ悪さする連中の中で、こいつらが一番厄介だよ。つまみ出して怒鳴りつけることも出来ない」
「……だからこその悪さだろ」
清鈴が言うと、董也はまた小さく息を吐いて、スマホの画面を落とす。
この僅かな作業で断ち切れる世界は、しかしその簡潔さゆえに使用者に責任というものを感じさせない。簡単に開けて、簡単に言葉を入れて、その結果がどうなろうと、スイッチを切って画面を落としたらおしまい。その奥底でどんな暗雲が広がっているかなど気付きもしないし、気付いたところで責任を持つこともない。
「それでも始まりがここなら、ここで止めることは出来る。……向こう側に行かれる前に止めるぞ」
どれだけ向こう側が広く暗く深い世界でも、そこで広がっていくものが生まれるのはこちらだ。ならば止められる。
三人は屋上を歩み、校内の戻った。
最後、野茨織麻は振り向いて、柵の向こうの、開けた空を見上げた。日の暮れたそこは暗黒。高い位置から見ても、星も見えなかった。ただただ暗く広いそこには奇妙な引力があって、ひどく目と、心を奪われるようだった。
校舎の中をつぶさに見て回る。空き教室、滅多に開けない倉庫、校舎の隅の階段やトイレ。生徒数数百人を数えるこの長月第七高校でも、人通りの少ない場所は結構ある。
野茨織麻ははあと息を吐く。
「何か変な感じー。毎日通ってる学校なのに、知らない場所がこんなにある」
現在二年の六月。およそ一年半通った高校なのに、今日見るのは一度も立ち入ったことのない場所ばかりだ。
束川董也が二人を先導しながら言う。
「そりゃな。毎日通うって言っても、実際使う場所なんて限られてるだろ。自分のクラスの教室、部室、食堂や体育館、いくつかの特別教室。ほぼルーティン化してて、……お前、今すぐに一年一組の教室に行けって言われて行けるか?」
その問いに、織麻は目を丸くした後で少し考えて、首を振る。
「そんなもんさ。自分が関わらない限り、どこにどんな教室があるかも分からない」
学校と言っても、生活範囲はあくまでも学年内の授業範囲内。別学年、選択していない授業や活動の場は知らない。
「三年通っても、一度も足を踏み入れない場所もあるだろうな……」
校舎を見渡しながら、董也が呟く。その様を見つつ、上屋清鈴は小さく言う。
「まるで異界だな……」
彼は少し笑っていた。董也は目を見開き、織麻は静かに視線を寄せた。
「すぐ身近にあるのに、立ち入らない、触れない。線が引いてある訳じゃないのに、どうしてか行かない。そういう場所はあるもんだし、そういう場所がどうなってるのか人は知らないし、知ろうとしない」
無意識の向こうがわ。普段立ち入る場所がどこにあって何があるか常に意識に中にある。だがその隣にあったとしても、行かないなら、見ないならないも同然だ。完全に無意識の存在。
「壁一枚先は未知、一学年の差は無知、選択の外は無関心。知らないまま、意識しないままなら、ただそれだけだが、……時たま、何かのきっかけで無意識を意識した時に、人間は得体の知れない恐怖を抱くのかもな」
野茨織麻は笑う。
「まあ、考えれば学校の怪談って要はそういうことだもんね。昼間普段使いしてるものが、どうしてか突然怖いものになるんだもん」
日常が突然恐怖に。すぐ身近にあるものが、これは怖いものだと意識した途端に恐怖の対象になる。階段、ピアノ、トイレ、プール、貼り出されている絵。普通に見ていればそのままなのに、怖いように見れば怖い。恐怖とはそんなもの、と言うと、束川董也はまた生真面目な顔で溜め息をついた。
「そんなのただの無知とこじつけの賜物だろ。そりゃ立ち入ったことのない場所は怖いもんだし、日常のちょっとしたことを超常現象に結びつけようとすればいくらでも出来る」
いつも通りの平静そのものの声。二人は目を丸くする。
「階段がたまたま十三段になってることもあるし、音楽室の写真が傾いていることもあるさ。だからってその階段が処刑台への道だったり、音楽家の霊が夜な夜な飛び出してるなんて、さすがに飛躍しすぎだろ」
想像力には敬意を払うけど、とどこまでも生真面目に言う。
織麻は苦笑した。
「会長さ……。一応調査して、自殺者がいたことは知ったんだし、それが霊になってるって発想、一ミリも浮かばなかったの?」
何も前情報のない状態なら、霊など眉唾、と言い捨てることもあるだろうが、少しでもその根拠になる情報があれば、いくら現実主義者でも、僅かばかりの疑問は抱くものではないのか。
織麻のその言葉に、董也は少し考えた後、眉を歪めつつ首を捻った。
「……それ、前から思ってたが、理屈に合わないだろ」
「は?」
「何で自殺者が霊になる」
二人は眉を歪める。
「自殺ってのは、自分から進んで死んだんだから、この世に未練なんかないはずだろう。死ねて満足、さっさとあの世に行けばい」
「……」
「………」
何という簡潔かつ理性的な考え方だ。だがまあ確かに、理屈は合ってはいる。
自信ありげな生徒会長に、織麻は恐る恐る物申す。
「けど自殺する人って、この世の何かを、誰かを恨んだ結果死んだんでしょ。未練というか、悪意は残るんじゃない」
そう言うと、束川董也は心底複雑そうな表情を浮かべる。そして溜め息をつく。
「……確かにそうだろうよ。何かに苦しんで死んだ。……けど、本当にそれで死ぬほど苦しんでる人間ってのは、その苦悩を人にぶつけたりしないもんだ」
二人は目を見開いた。
「俺も立場上、そういう人間からよく相談を受けるよ。あれが辛い、これがしんどい、生きていたくない、死にたいってな。……けど」
そうやって死にたい死にたいという人間が、本当に死んだことはない、と束川董也は言い切る。
「苦しみを人にぶつけられる人間ってのはまだ余裕があるんだ。というか、口で言うほど苦しんでもいない。……まあそれはそれで良いんだ。何か悩みがあるのは確かなんだから。それを他人に話したり、誰かを恨んだりすることで解消出来てるなら、それはそれだ」
少し呆れたような口調になりつつも、苦悩者のそういう心情に一定の理解はあるらしい。だが生真面目な彼が本当に気がかりに思うのは、そうでない人種。
「本当に危ないのは、苦しいとも死にたいとも言わず、表情にも出さない奴。そういう人間は、本当に、ある時突然、まるで思いついたように死ぬ」
「……」
二人は静かに彼を見る。
「苦しみを他人にぶつけられない人間ってのはいるもんだ。そういう人間にとっては、苦しみを除く最大の手段が死ぬことなんだろう」
苦しみも悲しみも恨みも全て己の内に抱いて、誰にもぶつけず漏らさず、抱いたまま死んで、全ての苦悩を終わらせたのだ。その時点で、本当に全ては終わり。その先はない。何もかも消えたのだ。消えるために消したのだから。
「─────潔い」
董也は、視線を上向けて、そこにいる人間に敬服するように、言った。
「そんな風に全てを自己完結出来る人間が、死んでから誰かに恨みをぶつけたり、脅かしたりする浅ましい真似するもんかよ」
「……その苦しみを与えた当人にも危害は加えないと?この場合はいじめの加害者か」
怨霊の本懐は即ちそれだろうと、清鈴の言葉に、董也はまたも簡潔に言う。
「それをしたいと思うなら生前にやってるだろ。自分を殺す度胸があるなら、嫌いな奴を殴るなり刺すなり、いくらでも出来るだろ」
「……」
「………」
簡潔な上にやたら物騒な意見である。この生真面目な生徒会長、理性的なのか感情的なのか分からない。呆れ顔の生徒二人に、董也は言い募る。
「さっきも言ったが、人間、どれだけ辛い苦しいって言っても、いざ自分を殺す度胸はそう湧かないもんだ。自分で自分を殺せる奴っていうのは勇敢だよ」
その勇猛さがあれば、他人を攻撃することなど容易いと。織麻が可愛らしい顔を歪めた。
「……もしかして生徒会長、自殺に賛成するタイプ?立派な行為とでも?」
苦い問いに、董也は首を横に振る。
「そんな訳あるか。命を大事にしない奴なんてろくでもないさ。……ただ」
そこで少し言葉を切る。
「そんな行動が出来る度胸というか、思い切りの良さは認めるってことだ。そこに至るほどに苦しんだっていうことも」
厳粛な顔を少し緩める。
「自殺を賛美することは断じてしないが、苦しんだ末に死を選んだことを、恥だとは思わない」
「……」
自殺は逃避だと言う人間もいるが、束川董也はそうは思わない。本当の逃避者とは、現状の苦しみに対して自分にも他人にも何の行動も起こさず、口先だけで苦しみを垂れ流す人種だ。辛い苦しいと口を動かす元気はあるのに、その口で辛い苦しいと訴える人間の何とも滑稽なこと。それに比べれば、苦しみを終わらせるためにさっさと身体を動かす人間の潔いことだ。その行動が、生きて苦悩を取り除くためであれ、死んで苦悩から解放されるためであれ、董也は“行動”自体は称賛するかは置いておいて少なくとも認めるし、そういう人間が死んだ後になって人を害すような馬鹿げた真似はしないと確信している。
董也の理論は奇抜であったし、そう簡単に認めていいものではないだろう。だが、野茨織麻には、少しだけ同調できる部分があった。
「ま…確かに度胸はあるかもね。自分で自分を殺すって、思ってるよりずっと怖いよ」
そう言いながら、彼女は先程足を踏み入れた屋上を見つめた。今三人は例の屋上がちょうど見上げられる中央、北校舎の合間の屋外通路にいた。距離はあるが、高い位置にある屋上と、そこに並ぶ柵がはっきり見える。
それを見て、野茨織麻は静かに言う。
「飛び降りたってことは、あの柵を越えたんだよね」
その言葉に二人は目を丸くし、彼女に倣って、階上の屋上を見た。先程見た、風と静寂に満ちた場所。
「近寄って見てわかったけど、あの高さって本当に怖い。柵のこっち側にいても、下見たらぞくっとした。……それを、柵の向こうで見るってどんな気分なんだろうね」
「……」
建物として四階の高さ。10メートル弱とというところか。あの位置から見れば、地上では等身大のものたちが全て小さく、遠く見えた。その様を認めると、誰もが背筋に冷たいものを感じるだろう。ここからそこに行けばどうなるか、想像して身震いする。
あそこから飛び降りた人間は、その震撼を越えたのだ。
「それだけの絶望ってどんなものだろ」
青い目に暗くなった夜を写し、そこに茫洋と浮かぶ校舎、その最上階の規則的に並んだ金属の柵を見る。
あの柵も境界だろう、物理的な。柵のこちらがわとあちらがわを分ける。
意識とは違う、物理的な一線。あの柵の向こうもこちらも学校の一部だが、錆びた鉄柵一つで隔てられた向こう側はまさに異界だ。あちらは死、こちらは生。分ける世界はあまりに違う。
野茨織麻は束川董也を見る。
「人間って悩みが尽きないよね。会長にしんどい死にたいって言う人達も、その時には本気なんだと思うよ」
その言葉に、董也はぴくりと顔を揺らす。織麻は薄く笑った。
誰でも思い悩むものだし、時には死さえ望むこともあるだろう。その衝動のままふらふらと、あの屋上に彷徨い行くこともあるのかもしれない。だが、いざ飛ぼうとした時に、胸元に当たるあの柵が、一瞬歩みを止めるのだ。そしてふいに下を見て、瞬間、恐れに襲われる。その恐怖というのは生存本能。死から遠ざかるための感情。衝動的な行動を抑制し、冷静さをもたらす。そして、理性が衝動に勝てば、人はあの生死を隔てる柵から遠ざかる。死から遠ざかる。
……だが、その本能さえ打ち消して、柵を乗り越え向こう側に行く人間もいる。爪先で立って、片足を上げて柵に引っかける。乗せた手に体重を預けて、そのまま身を乗り出す。身長よりは低くても、それでも越えるには高い柵を越えて、それだけの動作を経て、敢えて、向こう側に行く。その間に一切の逡巡はなく、思い留まることもなく、柵の向こう側へ。それはもう衝動ではない。覚悟だ。阻むものなど何もないそこで、本当に一歩先に出れば全てが終わるそこで、その一歩を踏み出すことをもはや躊躇わなくなった覚悟と諦念、────絶望。
落ち行く瞬間は開放感に包まれているのかもしれない。そして地表に着いたその瞬間が、まさに全ての終わりの時。命と共に、全ての苦しみが終わる。
潔く終わらせた人間が、その後を望むだろうか。
「何か、行動と心理がちぐはぐって感じ。終わらせたいはずのことを何度も繰り返すって、それ……」
結果が不満か。……或いは、終わらせたくない。終わりというたった一つの結果しか望んでいないはずなのに。
霊現象そのものよりも、霊の心理状態に疑念を持ち出した二人に、上屋清鈴はやや焦燥を示す。
「お前ら、今はそういうことを言ってる場合じゃ……」
言いかけて、清鈴も視線を件の屋上に戻した。そして、視界の端にそれを見やる。
「現象の起源や理なんざ、どうだっていいだろ……。実際、起こってるんだ」
その呟きに、織麻、董也もまた屋上を見た。
「!!」
驚愕する。二人もまた、それを認めた。
暗闇の中で、相変わらず毅然と佇む校舎。その最上。暗闇に慣れだした目に、確かにそれが見えた。
遠目だが、確かに人間のシルエットだ。短いスカートは女子である証。肩まで伸びた髪も分かる。それらは風の中で揺らめいて、その揺らめきのまま、その女は体幹をぶれさせる。
「お、おい……」
さすがに董也が慌てる。
「……出た」
「ああ」
対して、織麻と清鈴は妙に冷静だった。静かに、高い屋上でゆらゆら揺れる少女を見つめる。その視線の先で、彼女は上半身を前にのめらせた。
「……っ!」
董也が駆け出す。
「ちょ……、待って」
織麻が制止するが、董也は聞かずに少女のいる校舎に向かって走る。ここでそうしても、もうどうしようもないが、それでも董也は走る。
「……偽物だと思ってるんじゃ?」
着いて来て並走する清鈴が皮肉っぽく言うが、董也は吐き捨てる。
「そう思ってるよ!けど、さすがに……」
どうやっているのかは分からないが、あれは明らかに危ない。屋上でゆらゆらと身体を揺らして、今にも落ちそうではないか。
「!!」
駆け寄る最中に、屋上の女子生徒は大きく上半身を前にのめらせた。そしてゆっくりと、頭から地上に落ちて行く。
「おいっ……」
焦燥を声に滲ませて、足を速める。今から屋上に駆け上がることは出来ない。彼女が落ちたと思われる校舎の足元に向かう。そこに行ったところでどうなるものでもなかったが、董也は人間の義務として駆けた。
そしてそこに辿り着く。目を剥いた。
「……え?」
少女が落ちたはずのそこ、悲惨な有り様が広がっていると思っていた場所には、何もなかった。思わず上を向く。屋上にも何もない。その途中にも。先程間違いなく目で見たはずの少女は、影も形もなかった。
「どうなって……?」
前後左右を見渡しながら戸惑う。見間違いか、それともやはり悪戯か。それにしても。あのゆらゆらと揺れる人影、転落のモーション、その動きに合わせて翻る髪にスカート。偽装には思えなかった。あまりに自然だった。
「……やっぱり幽霊かな?」
いつの間にか追いついて来ていた野茨織麻がどこか面白げに言った。
「いや、そんな訳……」
混乱したまままた上を向く。するとそこには、また彼女がいた。やはりゆらゆら揺れて、危うい足元で屋上に立っている。
「………っ!?」
「こりゃ、決まりだ」
清鈴が険しい顔で言う。
「そんな訳ない……」
「まだ言う?さすがに、私らのハズレだよ」
織麻が呆れ顔で言う。
「いやだから……」
言い合う内に屋上の少女はまた落ちた。真下にいる三人に向かって真っ逆様に落ちて来た。
「……おい!?」
慌てるが何も出来ない。立ち尽くしたまま、どんどん迫って来る少女を見つめた。猛スピードで落ちてくる。次第にその髪が、制服が、四肢がはっきり見えて来る。顔が見えそうになった。が、その瞬間に、彼女は消えた。三人の眼前まで迫って来て、地面にぶつかると思った瞬間、吸い込まれるように、消えた。
「……っ!?……!!」
董也は声を出せないまま、ただ彼女が消えた地面を見つめていた。
「……仕込みじゃないな」
清鈴が静かに言う。董也が彼を凝視する。今の光景を作り物と言えないことは、直に見た皆が分かった。
董也も、今のモノが見たことがないから無いと、宣言していたモノだと、そう認めざるを得ない。見てしまったのだ。もう否定出来ない。
幽霊。自殺者。死して生者の世界にいるモノ。自分が否定した存在が、今まさに眼前に現れた。その現実と、その事実に対する恐怖、混乱、そして同時に、董也はなおも納得はしきれていなかった。
「そんなはずは……」
なおも言い続ける董也に、清鈴は呆れた顔で溜め息をつく。
「いや、現実に見ただろうが」
「会長の調べた通りじゃない?自殺した女子生徒」
織麻も言う。だが董也は緩く首を振る。
「いやだから、そんなはずないんだって……。言っただろうが、調査不足だって」
清鈴と織麻、二人が目を見開く。
「自殺した女は首を吊ったんだ。飛び降りじゃない……っ」
「え」
男女が同時に言った。その、瞬間だった。三人の足元から、何かが出た。
「…………っ!?」
先程制服姿の女が吸い込まれた地面から。今度は何かが溢れ出て来た。それを視認することは出来ない。凄まじい圧で、何か煙のような、風のような、ガスのような何かが迫って来た。
「来たっ!」
「やっぱりじゃん」
「え」
清鈴は意気込み、織麻は面白がるようで、董也は戸惑った。
次の瞬間、溢れて来たそれを囲うように、今度は地面から蔓が伸びて来た。棘のついた太い蔓がたわんで、風圧をそのまま包み込んだ。
更に訳の分からない光景に、董也は目を剥く。
「やれそうか?」
「分かんない。結構強い」
混乱しきりの董也に対し、清鈴と織麻は妙に冷静である。そんな二人を驚愕の表情で見る。すると、球形になった蔓の一部が剥がれた。内から何かに押し出されているようだった。
「あら、思ったより強い」
「面倒だな……」
「おい…………」
なおも冷静な様子の二人に、董也はたまりかねて声をかける。二人はどこまでも平静な顔で、同級生を見てきた。
「あんた、ここを離れてろ」
「は」
「ごめんねー、会長」
織麻が笑いながら詫びた次の瞬間、董也の胴体に何かが絡んだ。見ると、彼の足元から生える蔓だった。棘もない細いそれは、見た目に似つかわしくない奇妙な力強さで董也を抱き込み、そして、浮かせた。
「お……」
何事も言えないまま、董也はその外力に従うまま身体を投げ出させた。瞬時に飛ばされ、その思いもよらぬ干渉を受け入れきれないまま、何とか残る冷静さで同級生二人を見た。だが、その姿は見えなかった。そこに至るまでの視界に、濁った幕が張られいたから。よく見るとそれは、水だった。噴水が湧き上がった瞬間に現れるものと似た水の壁がそこにあった。だが当然そこには噴水器も散水資材もない。完全に物理法則を無視した形で、水の壁が四方を囲み、二人と謎の現象を覆い隠していた。
「……」
束川董也は呆然として、眼前の非現実的な光景を見つめる。事実を咀嚼しきれないまま、慎重な彼にしては珍しく、無防備に自身の手を水の膜に伸ばした。触れた感触は確かに水。冷感と濡れた感触が指先から伝わる。しかし、妙に固い。本来ならすぐに通過できるはずの水面に奇妙な弾性があり、董也の指の圧力を拒む。今まで感じたことのない感触に驚き、思わず手を離す。
訳が分からなかった。今まさに目の前で起こっている全て。飛び降りて消える少女。地面から浮き上がる黒い何か。それにさほど驚きもしない同級生達。……董也は、あの二人のことを、少なくとも野茨織麻のことはよく知っているつもりだった。なのに、今見た二人の様相は彼の知見にはないものだった。何者だ、あの二人は。先程起きた現象と何か関係があるのか。伸びた蔓。眼前に聳える水の壁。
視線を上げると、ゆうに人三人分の高さある。越えられないし、くぐれないし、通ることも出来ない。この壁の中で、何が起こっているのか分からない。あの二人は、何をしようとしている。
不可解な出来事に、それに対して理解も解決も出来ない状況。混乱と共に、彼が本来持つ使命感や責任感から、無力感が湧き出す。何か尋常ならざることが起きているのに、自分は何も出来ない。そう思って拳を握ると、ふと、湿った感触があった。指先に、先程触れた水壁の雫があった。
「水……」
それはどう見ても感じても、ただの水だった。指先にはよくある濡れた冷たい感触。非日常な状況の中での、ひどく日常的な感覚。それが、束川董也にある種の冷静さを取り戻させた。
そうだ、理解不能な状況ではあるが、自身に緊急性の高い状況ではない。そして、この事態に対して、あの二人が何かしら対処しようとしていることは分かる。ならば。再び拳を握る。
長月第七高校の生徒らの長は、制服のポケットから携帯電話を取り出した。
水壁の中。
上屋清鈴と野茨織麻は、眼前の怪異に向き合っていた。地面から湧き上がり続ける禍々しい気流。二人には、それを構成する因子の一つ一つが見えていた。
「何か色々いるね────…」
「ああ。小妖魔どもの寄せ集めだ」
気流の中には色々いた。吊り上がった目で睨んでくるモノ、歯を剥いて笑うモノ、爪を剥き出しにして威嚇してくるモノ。どれも小さな異形の動物にようだ。
「どれも大した邪気もない小物だな。だが……」
「………大きいね」
目の前の怪異は、構成している一つ一つの要素は小さいが、それらが集まって、二人を見下ろすほどに大きい。家を逆立てた小動物のように、気を禍々しく燃え立たせている。
「………繋ぎはあれだな」
燃え立つ邪気の中に、一人の少女が認められた。地面に立ち尽くし、俯いている。先程屋上から飛び降りた少女だと分かる。制服姿の細い身体で、肩までの髪の毛。一見すると平凡な少女。だが、その身体のあちこちから禍々しい邪気の妖を生やしている。逆立つ邪気の根本を辿れば、彼女がいる。始まりは彼女。根源は彼女だ。
「小物どもを纏めちまったんだな。ここまでデカくなると厄介だぜ」
「……やっぱり自殺した娘なのかなぁ」
織麻が言うと、清鈴は首を捻る。
「会長殿の調査が正しければ、別口かもな。何にせよ、屋上から飛び降りて死んだ。……これだけの邪気を引くほどの悪心を抱いてな」
「……」
「マイナスはマイナスを引く」
膨れ上がった邪気を睨んで言う。
「しかも落ちた場所も悪い」
「え?」
「学校の中央から見た場合の、鬼門だ」
そう言われて織麻は目を丸くし、思わず周囲を見渡す。そして気付く。今怪異が現れる場所。恐らく彼女が飛び降りた場所は、三つ並んだ校舎の真ん中の棟で、極めて中央に近いがそのやや左寄り。そこから前にせり出して北、つまりは東と北の合間、北東、鬼門。────古来から、悪いモノが出入りする場所と言われる。
「おまけに“角”だ。校舎と廊下の交差する角地。……校舎の影になって陽も当たらず、人通りもなく目にもつかない。……ああいう場所は溜まる」
「……」
確かに、校舎の中央近くから真下に行けば、そこは三校舎の中央を貫く渡り廊下と、中央校舎が交わって出来る“角”。南側に高い校舎が建って陽を妨げ、常に影があるそこは、人通りもない。見られることもない。
校内に数多ある見える死角の一つだ。人々の意識の外の空間に彼女は居続け、邪を取り込み続けた。
「元から学校みたいな大勢の人間が集まる場所には色んな念が渦巻いてる。ここはその溜まり場でだ。こんな所で邪念を持って死んだら、この有り様だも納得だ」
「………ひどいね」
元はただの少女だったはずのモノの変貌ぶりを嘆く。
「ここまでになる邪念って何?」
「さあな。恨みや嘆きか……自殺者は恨んで化けないって、会長殿の推測は大外れかも」
「そうかなぁ……」
野茨織麻は、今もまだその推測には違和感があった。自ら死にに行く人間は潔い。そういう人間は、現世に恨みなど残さない、織麻はそんな生徒会長の推測に、不思議な納得を感じていたのだ。彼女は再び、変貌した少女を見る。すると、彼女と、目が合った。
「!!」
その場に、女の絶叫がこだました。俯いていた少女は弾かれたように首を振り上げ、凄まじい形相で、天に向かって咆哮を上げた。それと同時に、彼女から噴く邪気が一気に大きくなった。
「きゃっ……!」
邪気の塊が二人に向かって来る。それを二人は避けるが、避けた後の地面には、大きな邪気溜まり。それを見て清鈴は舌打ちする。
「弱い奴らも、寄り集まるとここまでかよ……っ」
呻きながら、更に向かって来る邪気に対して指を向ける。その指先に、水の球が生まれる。それは鋭い速さで飛び、邪気の塊にぶつかる。その瞬間、邪気が霧散した。
更に織麻も手を振る。それ合わせて地面から緑の芽が出て、一気に伸び、一本の蔓となって空を舞った。その一閃で、邪気は裂けた。
大きかった邪気は小さくなる。だが。
「なっ……」
それと同時に、また大きな咆哮が響いた。一段と大きく鋭い絶叫。それが発生する少女の口は限界まで開かれ、口角が引き裂けているようだった。その形相と身に纏っている平凡な制服がひどくちぐはぐで、その差異がかえって不気味だった。そしてその制服を纏った身体から、また異形のモノ達が湧き出て来る。
「………っ!?」
二人は目を剥く。
「まだあんなに……?」
一度縮んだ邪気がまた膨れ上がり、先程より大きくなった。それ合わせて異形の禍々しさも増し、妖魔の避けた口からは嘲笑うような笑い声が聞こえた。
「ありゃ、繋ぎというより、もう巣穴だな。どんだけ溜め込んでんだ……」
清鈴が呆れるように、恐れるように言う。織麻の目にもそう見えた。あの細身の少女から、どんどん異形の化け物が湧き出て、それが少女を中心にして纏まって、大きくなって脅威を増す。
「気持ち悪い……」
「だな。化け物どもが更に醜くなってる」
清鈴が嫌悪を込めて吐き捨てる。だが織麻は少し複雑な顔をした。
「そうだけど……。それだけじゃなく」
言い淀む織麻に、清鈴は怪訝な顔をするが、そこにまた邪気が襲う。圧力が先程より強い。
清鈴は水珠を出し、織麻も蔓を踊らせて、邪気を払うが、先程よりも効果が薄いのが分かる。まだ巨大な邪気の圧が、二人の迫る。
「面倒くせぇ……」
その攻撃を避けながら、清鈴が苛立たしげに舌打ちする。元は弱い妖魔らだというのに、寄り集まるとこうも厄介かと。清鈴は妖魔の発生源となっている少女を睨む。
「あれをどうにかしねえと。キリがない」
あの少女の亡霊が元凶だ。あれから湧き立ち、混ざって強くなっている。あれさえ無ければ、恐らく元の弱い小さい妖邪に戻る。それだけならばすぐに対処できる。
織麻も頷く。彼女も邪の中心となっている少女を見る。濃密な邪気の中にあって、その姿はもう朧げだが、間違いなく自分と同年代の少女だ。細い身体で、制服姿で、どこにでもいそうな女の子。そこに多くの弱く小さいモノが溜まって、奇怪な脅威となる。
「……」
織麻は、そうなったモノというより、そうなる事実がどうにも不気味に感じられた。
うろに溜まるような集団性。寄り集まって、個々の境目がわからなくなったような歪な密着。その上で肥大化する邪念。─────気持ちが悪い。
何だかそれは、彼女の本来の人間像とあまりにかけ離れているように感じた。やはり、どうも織麻には、董也の言葉が強く印象に残っていた。
“自殺者は恨まない”
苦悩も悲嘆も全て自身の身の内に抱いて、一人孤独に逝った少女の、行く末があれなのか。うじゃうじゃと集まった小物達。その中心にいる。
何かが、おかしい。しっくり来ないというか、噛み合わないような。ふと気付く。
「……ああ、あの子は違うんだ」
「は?」
次々来る攻撃を避けながら、ぽつりと言った織麻を清鈴が睨む。
「自殺した子じゃない」
「……」
清鈴は目を見開いた。彼も気付いたらしい。
そうだ、あの少女は話していた自殺者ではない。彼女は、恐らく誰も来ない場所で、一人首を吊った。徹頭徹尾、ひとりだったのだ。
あの娘は真ん中で────こんな人の行き交う大道で死んだ。
そして今も、多くに取り巻かれている。
あれは違う。
その瞬間、緊迫した状況のそぐわない間の抜けた電子音が聞こえた。
その正体をすぐに見抜いた織麻が、女子高生の習性としてポケットに手を入れ、自身のスマートフォンを取り出す。
おい、と清鈴は咎めるが、織麻は瞬時に画面を読み取って、少し目を見開く。
「………会長からだ」
清鈴も目を見開いた。
状況を半端ながら把握した束川董也は、とりあえず距離を取った。危険からは身を離すべしと、どんな状況であれ共通するだろう鉄則に従う。
渡り廊下の影に隠れ、状況を確認しつつスマホを取り出す。
不可解な状況。理解不能で対処不能。だが、そんな中でも自分にできることは。そう考えた末に辿り着いた答えが、“調査”。情報の収集と整理だった。
どうにも気になるのだ。あの屋上から飛び降りた女子生徒の幽霊───と、もう認めるしかないモノ。自殺した女生徒の霊と噂されていて、しかしそれには迎合できない。自身の事前調査によれば、自殺した生徒は首吊り自殺。あの飛び降りた女とは別物だろう。ならばあれは。別の自殺者か。……そうも思えない。どんな理由で命を絶ったにせよ、自ら死にに行く者が、ああも浅ましいだろうか。死を決意して飛んで、せっかく落ちて死んだのに、なのにまた戻って落ちることを繰り返す。その鬱陶しい反復行動には、“死”という結果が本当に欲しいのかと疑いたくなるいじましさがあった。
そもそもあの屋上でゆらゆらと揺れる、落ちるか落ちまいか躊躇うような、その逡巡を見せつけるような、わざとらしい、押し付けがましい、あのどっちつかずの動き。あれを見て一瞬抱いた苛立ち。覚えのあるあの感情。そうだあれは。よく抱く、辛い辛いと口では言いながら、現状を変える努力を一切しない、自身の前で突っ伏して、その隙間からちらちらこちらを覗いて来る相談者を前にした時のものと同じものだった。
束川董也は基本的には論理的な人間だが、この時だけは自身の直感を信じた。そして、その直感に根拠を添えようとした。恐らくはその結果が、あの亡霊の正体だ。
董也はポケットからスマートフォンを取り出す。そして登録してあった連絡先に電話をかける。
『────はい』
数コールで相手は出た。
「夜分にすみません。泰地先生」
礼儀としてまず詫びを入れる。
『いえいえ。どうしたの?』
相手は朗らかだ。泰地暁教諭。この長月第七高校の化学教師だ。まだ三十代前半の若手教師は穏やかで優しく、生徒らに親しまれている。こうして個人的に連絡先を交換するほどだ。
束川董也もこの話をしやすく、更に事情を把握してそうな彼ならばと連絡を取ったのだ。
「ちょっと聞きたいことが……。最近学校で流れてる噂なんですけど」
『ああ、幽霊が出るってやつでしょう。定期的に出るよねぇ、そういう噂』
教員としてそれなりに経験がある彼には、そういう眉唾の噂は慣れっこのようだ。
「……」
董也も何事も見なければ、ただの噂と吐き捨てた。或いは誰ぞの演出だと。だが、今はそうは言えない。
「………マジっぽいんですよ」
『え』
深刻な調子の董也の声に泰地教諭は一瞬静止したようだった。理性的な束川董也の口から出る言葉とは思えなかったのだろうが、だからこそ嘘ではないとすぐに確信したのだろう。
『……………本当?』
その疑問に董也は頷いた。電話越しに頷いても相手には分からないというのに、そんな反応をしてしまう程度には董也も冷静ではなかった。だが相手にしてみればただの沈黙でしかなかったその反応に、生徒をよく知る泰地教諭は真実を確信したようだった。
『見たの?』
「ええ……。けど変なんですよ。噂通り女子生徒なんですが、屋上から飛び降りたんです」
『……うん?』
董也の言葉に電話の向こうで相手が眉を寄せる気配がする。言葉の意味が分からないのだろう。
董也は相手に、自殺者の霊が出ると噂が出てから、自分なりに調べていたこと、過去に確かに自殺者はいたが、飛び降り自殺ではなかったことを語った。
『そうそう。確か、自分の家で首を吊ったんだ』
「知ってましたか……」
知っているだろう。事件があったのは彼が教職が就く前のはずだが、彼はこの校舎が長月第七高校となる前からここにいるのだ。
……そうだ。憐れな自殺者が逝ったのは、学校ですらなかった。だが実際にこの校舎の屋上には、執拗に死を繰り返す少女がいる。あれは、結局何なのだ。この教師なら知っているかもしれない。
「その自殺以外、何かなかったですか。生徒の誰かが屋上から転落した……自殺じゃないかも」
自身の直感と経験を信じて問うが、董也の緊迫感に反して、電話の向こうの若い教師は意外な答えを返してくる。
『ああ、あったよ』
「…………」
驚くほどあっさり返された。
「あったんですか!?」
勇んで問いただすと、うん、と相手はまたあっさり返してくる。
『逆に君の調査には引っ掛からなかった?』
「自殺者しか調べなかったので……」
『そう。その自殺に絡む話なんだけどね』
董也が眉を歪める。
『あんまり外聞の良い話じゃないから、事故ってことで記録には残したのかな』
「直近で自殺者出してる時点で、外聞も何も」
『まあそうなんだけど。その件は学校にとって、更なる恥の上塗りだったから。……それ以外の人間にとっては、案外愉快な話かもしれないけど』
「………何があったんです?」
人死にがえらく軽く扱われている気配に鼻白む。電話の向こうで溜め息が聞こえる。
『嘆いて沈めばいいのか、呆れて笑えばいいのか分からない話。……屋上から落ちて死んだ子は、自殺した子を殺した子」
董也の眦が吊り上がった。
『いじめの主犯格だった女子生徒だよ』
その事件は、言ってしまえばありきたりないじめ事件だった。あるクラスの女子生徒がクラスメイト数人から執拗な嫌がらせを受けた。揶揄われるとか仲間外れにされるとか、所持品を隠されるとか壊されるとか、段々エスカレートして密室に閉じ込められ、小突かれ、水をかけられ、挙げ句万引きを強要されそうになり。ひどい話だが、妙なことにそれらが明らかになったのは取り返しにつかない事態になってから。いじめられていた当人が自死し、自らが受けた所業をきっちり遺書に書き残して逝ってからだ。
これもまたありきたりな話で、悪質性の高い行為に死亡生徒の親も他の保護者も警察もマスコミも関係ない一般人も一気に騒ぎ出し、その追求に対し、当事者らも学校関係者も、そこまで深刻な事態だと認識していなかったと言い訳するのもまた、よくある話だった。よくあるその言い訳は、しかし事態をより悪化させ、騒ぎはどんどん大きくなった。
その騒音の矛先は、学校、教師、そして当然ながら、虐めの当事者達だった。集団になって一人の弱者を虐げていた少女達は、今度は虐げられる側に回った。死んだ生徒の親に、親族に、周りの生徒に、教師に、教育委員会に、マスコミに、全く関係ない第三者に責められ、無視され、笑われ、晒され、彼女らの家族も含めて生活は滅茶苦茶になった。それもよくある話だった。被害者や学校、関係者が与えた正当な罰以外にこそ痛めつけられる。当時は既にネット社会で、個人情報は容易に漏れ出た。もはや道を歩くことさえ困難になった彼女らはどんどん追い詰められ、その内の一人の母親が良心の呵責と世間からの非難に耐えられずに自殺未遂を起こすなど、もはや混乱の極みだった。
そうなるとどうなるかというと、内輪揉めが起こる。ついこの前まで徒党を組んで一人を虐げていた集団が、お互いに責任をなすりつけ合い、いがみ合った。いや正確に言うと、一部が纏まり、一部を離反した。要は、主犯格の一人を、それ以外で責めたのである。
だんだん話が見えてきた、と束川董也は眉を寄せた。
「いじめっ子がいじめられっ子に」
『まあ、よくあることだね』
呆れ笑いのような声が、電話の向こうで聞こえる。
『で、ある時ブチ切れた。授業中コソコソされて耐えられずに、奇声あげながら教室飛び出して、屋上に駆け上がったの』
電話の向こうの男性教師も、笑っているのか呆れているのか分からない声音である。実際、その後の彼女の行動はどう評価していいか分からない。屋上に行って、勢いのまま柵の向こうに渡り、追いかけて来た生徒、教師に向かって死んでやると叫んだ。そして、そのまま落ちて死んだのだ。
「…………自殺?」
『どうかな。その場にいた訳じゃないから。……ただねえ、君も分かるだろ。死にたい人間は騒がない」
「ですね」
そうだ。本当に死ぬ気のある人間は、死んでやると人前では言わない。奇声を上げて注目を引くようなことはしない。
「………“自殺未遂に失敗した”って奴ですか」
『正確に言うと、狂言自殺に失敗した、かな?………実態は今となっては分からないけど、まあ学校は事故ってことにしたんだろうね』
だから、董也の調査には引っ掛からなかった。彼は溜め息をついた。
「………そいつ、化けて出てるみたいなんですけど」
『おやおや』
電話の向こうの教師は笑っている。まあ分かる。生徒に死について笑うのは不謹慎だが、その点においてはもう笑うしかない。
自分の考えは間違っていなかったと董也は溜め息をつく。やはり自ら死にに行く人間は恨みを残して現世にしがみついたりしない。この世にしがみつくのは死にたくなかった奴。それなのに、死なされた奴だ。恨む理由は分かる。不慮の死は誰でも恨めしい。………だが今回に限っては、完全に逆恨みだ。
董也は教師に礼を言って電話を切る。そしてスマホ画面に文字を打ち込み始める。その文の送り先は野茨織麻。転校生の連絡先は知らない。
「……」
先程まで共にいた同級生らの顔を思い浮かべる。彼らの正体は知れないが、あの厄介な怪異に立ち向かおうとしているのは分かる。この行動が彼らの力になるかは分からないが、董也に出来るのはこれだけだ。
……これだけなのだが。
董也はふいに立ち上がって、相変わらず自分を締め出す水の膜を見やって、それを避けて校内に戻る。
その行動により何が出来るかは分からない。だが、何かやらずにはおれないのが彼だった。階段を駆け昇る。
彼女はずっと煩悶していた。あれ以来、周囲から訳の分からない悲鳴や嗚咽を聞かされて、その中心に自らがいる意味が掴めずにいた。
どうして自分はこうなっているのだろう。大勢の声に、視線に責められて、こんな辛い思いをしなければならないのだろうと。
ついこの前まで、彼女は本当に普通の少女だったのだ。親に愛され、友に恵まれ。どこにでもいる、ごく普通の。
普通でなかったのは、むしろあっちだったはずだ。教室内の華やぎにも騒々しさにも馴染まず、いつも一人で窓の外を見ていた女子生徒。彼女は他と違った。その違いが周囲に何か実害をもたらした訳ではなかったが、しかし、ただ何となく、気に障ったのだ。
最初は少し揶揄うだけ。だがそれに相手が何の反応も返して来ないと腹が立って、余計に揶揄ったり悪態をついたり、いつしか小突いたり椅子から引き摺り下ろすようなことをしても何も言わなかった。しかし、そうやって反応が返って来ないからこそ、ずぶずぶと入り込むように行動は激化した。だがそれにも何も返って来ない。行動は進む。その繰り返し。
そうなって来ると、その行為自体も特異でなくなる。まるで朝起きてから顔を洗うように、当然のように、あの娘を揶揄っていると、─────突然、結局何も言わず何もしないまま、あの娘は死んだ。その死に至る苦しみをわざわざ文書に書き残して。彼女達がしたあらゆる行為が苦しかったと。
その瞬間、世界の全てが敵になった。普通だったはずのは彼女は、途端に悪い子になった。
そのことに彼女は混乱した。何で。どうして。どうして皆責めてくるのだ。先生が怒る。あの娘の親には泣かれた。自分の親も泣いて、あの娘の親に詫びて、学校にも謝って、騒ぎ立てるメディアにも頭を下げて、挙げ句勤め先に迷惑がかかるからと辞めて、家に籠る生活を始めた。家の中では両親がお互いを罵り合って、娘がこんな人間に育ったのはお前のせいだとお互いに言い合っていた。
……─────こんな人間?自分は、親にとってどんな人間に育ったというのか。親の思う子供にはならなかったのか。でもずっと、親の言いつけは守って来た。遅くまで外にいちゃ駄目だとか、電気をつけっぱなしにしちゃ駄目だとか。そうやって教えられたことはやっていない。それなのに、親は我が子が良い子じゃないと言う。私の育て方が悪かった、死んでお詫びすると、勝手に死んだ。何とか命を取り留めた友達の母親は、長く入院することになって、どうしてこんなことになったのと、友達は泣きながら電話してきた。
…………………分からない。どうしてこんなことに。こんなことになるなんて、誰も教えてくれなかった。自分はただ、普通に過ごしていただけなのに。
何だか怒りが湧いて、何ヶ月かぶりに学校に行った。どこかやけくそで、投げやりだった。責めたければ責めろと、開き直りにも似たような心境で席に座って、しかし何も言ってこられなくて、ただ湿った視線が絡んで、囁く声だけだけが耳に届く。
鬱陶しい。どうしてこんな風に責められるのだ。何で今更。
今更。
彼らはずっと、この教室で行われていたことを、彼女らがしたことをずっと見ていたくせに、何も言わなかった。なのに今更になって。何故。
怒りが湧き、悲しみが湧いて、彼女は立ち上がって、叫びながら階段を駆け上がった。屋上の柵をまたいで、死んでやると叫んだ。私が死ねば満足なんだろう。なら死んでやると。何もかも私が悪いんだろうと。
ひとしきり叫んだ後で、漂ったのは、沈黙。
柵に乗りかかった彼女と、それを茫洋と見ているだけのクラスメイト達。
見ているだけの。
それを認めた瞬間、彼女の中の何かが冷えた。
高所での強い風吹き荒ぶ中で、彼女の足は震えた。不安定だった姿勢が、ぐらりと揺れた。
あ、と思ったのは一瞬で、その時初めて、観衆の口から声が漏れた。悲鳴、驚愕。本当に、誰も彼も、何かが起こってからじゃないと何も言わないししない。
…………どうして。彼女は地面い倒れ伏して、まだかろうじてある吐息の中で、地面に広がる血を見ながら自問し続けた。
何で、こんなことに。死にたくなったのに。死なせるつもりじゃなかったのに。誰も死ぬはずじゃなかったのに。何で、どうして、あの娘は、私は死ぬの。
どうして。
涙が伝って、地面に染みた。そこから、彼女の血と涙が染みた大地から何かが湧き上がってきた。小さな手、赤い舌、いやらしい触手。それらが彼女の身に入り込んで、彼女の混乱と悲しみと無念を食い荒らした。そしていつしかその魂を苗床にして、一つに大きな悪意になる。混乱と不安、嘆きと怒りは妖邪の好む人間の思念。暗い感情ほど、共感し合うものだ。………他者への攻撃性、蔑視、嫌悪。そして無関心も。彼女はいつも、そうした人間の中心にいた。そして、今もそうなのだ。
「………」
「……………」
野茨織麻、上屋清鈴の両名は、今しがた生徒会長から送られてきた情報と、眼前の事実を組み合わせて、状況を察した。
「……自殺じゃなかったね───」
どこか空寒い口調の織麻に、清鈴は深く溜め息をつく。
「自殺より馬鹿馬鹿しい……」
「……」
「……あの生徒会長殿の言葉は、結局いちいち正しかった訳だ」
束川董也の言葉を一つ一つ思い出す。
自殺者は恨まない。死んでこの世に残らない。自ら死んで、死を受け入れらえる者は愚かだが潔い。周囲を恨んでこの世に留まるのは、自分がそうされることに不満がある者だ。自分はあんな風に死ぬべき人間ではなかったと。どうして死んだのか、誰のせいで死んだのか、ぐずぐずと悩み恨み続けて、その負の感情で多くの邪を呼んだ。その内に、自らが邪になって、醜くおどろおどろしく、おぞましい姿になった。
「るつぼになって、くっついて膨れ上がって、他人を攻撃する。……まんまだね」
あの歪さ、気色悪さ、あれは恐らく、生前の彼女そのままだ。
清鈴が溜め息をつく。
「最後にはその報いが返って来るところもな」
黒い塊がまた迫って来る。二人はそれを避けて、高く跳び上がる。そして、その黒い邪妖を見下ろせる位置に上がる。
「……──────馬鹿は死んでも治らない」
冷たく言い捨てる。
織麻は憐れむように黒い塊を見ていた。
「元は普通の娘だったんでしょうに」
その呟きに、清鈴は織麻を凝視する。
織麻らが先程生徒会長から受け取った“彼女”の情報によれば、基本的には目立つ部分がない、家族関係、学校関係も問題なかった、ごく普通の女子生徒だった。
育ちにも問題なく、普通に両親に教育され、友人とも良い関係を築いてきた。
それが崩れたのはたった一つの過ち。それが致命的であったことと、何よりそれが致命的だと最後まで……というか、今に至っても分からなかったことだ。
自分の行動が、どんな風に人に影響を与え、どんな結果をもたらすか考えられない。
決して悪人でも、残酷な訳でもない。……ただ幼稚で、どうしようもなく馬鹿なのだ。
「一番タチ悪いだろ」
「だね……。今もなのかな」
また黒い塊を見る。
「まだ意識あるのかな。……今自分がどうなってて、何してるか分かってる?」
感情と衝動のまま邪気を膨らませて、暴れて他人を傷つけようとしている。自分の有り様を自覚しているか。
清鈴は舌打ちする。
「分かってないだろうし、分かったところで止めないし、止めようもない。……あそこまでになっちゃ」
苦い顔で視線を向ける。黒い塊りは更に大きくなった。そして高くにいる二人に迫って来る。より速く、より凶暴に。水と蔓で応戦するが、次々に湧いて出て来る。どれだけ凶暴化しても一撃一撃、対抗できないほど強くないのだが、とかく大きく再生が早いのできりがない。
それを見やって、織麻が言う。
「何にしてもやっぱり、あの娘をどうにかしないとね」
自主的に引かないなら、力ずくでも。織麻が清鈴に言う。
「“水牢”を作ってくれる?あの中に押し入んで」
清鈴が眉を寄せる。
「私、中に入るわ」
清鈴が更に顔を歪める。
「安全は保証できねえぞ」
「けどこのままじゃ埒があかないもの。ちょっと思い切った方向で行こう」
どこまでも穏やかな顔をしながら大胆なことを言う織麻に、清鈴は顔を顰めた後で、どこか諦めたように溜め息ついて、彼は両掌に水球を作り、それを細く引き延ばす。
それは、この現場を覆い、束川董也を拒んだものと同種だったが、それよりも更に小さく、その分幕がやや分厚い。それきれいな球体になって織麻の身体を覆う。
「内側の酸素がなくなるまでそう時間はないからな」
「分かった」
織麻は身構える。
「すぐ決めるよ」
そう宣言して、彼女はそこを飛び出した。文字通り、急速で場を離れ、黒く膨れ上がった邪気の中に突っ込んで行く。その瞬間、黒塊は霧散する。水に含まれた霊力が邪気を祓っているのだ。だが、祓われた先から邪気は膨れて、織麻を包む水球を巻き込んで行く。真っ黒な邪気に中に潜り込んで、徐々に姿を失って行く少女を見て、清鈴の胸中に焦燥が湧くが、しかしこういう土壇場で妙な力を発揮するのが彼女だ。
……そして、思い切りのいい行動に行こうとする彼女は、言い出したら聞かない。
「…………決めろよ」
信じながら、祈りながら、上屋清鈴は呟いた。
野茨織麻は、水の膜に包まれながら、黒い邪気の最中を突き進んでいた。邪気を押し広げるように進んでいたが、徐々に邪気が近くなっている。じわじわと、霊気を含んだ水膜を侵食している。
弾いても叩き付けても迫って来る。密度は大したことはないのに、この圧倒的な質量。数の力というのは恐ろしい。……これを発生させているのは、たった一人の少女だというのに。
じりじり脅威に取り巻かれているのを感じながら、織麻は前だけを見る。この肥大した悪意の足元。自身から黒い邪気を生やして、燃える最中に徐々に大きくなって、その先はもう自身で収めること叶わなくなった。非力な、ちっぽけ、ただの少女だ。
「………ねえっ!」
迫る最中、織麻は声を張り上げる。
「あなた、名前は?覚えてる?」
もはや意思や記憶があるかも分からない怨霊に声をかける。相手は答えない。織麻はそれでも語りかけ続ける。
「じゃあ、いじめた娘の名前は?どんな顔してた?」
答えない。
「……悲惨だね。名前も顔も覚えてない人間のために、こんなことになって」
少女は答えなかった。
「どうでもいい相手だってんでしょう。いじめたって言っても大した理由じゃない。ちょっと気に入らない程度?それで皆と一緒になって揶揄って、どれだけやってもそれぐらいのつもりだったんだよね。だから罪悪感もなくて、最悪の結果になっても自分が悪いと思えなかったのよね。そんなつもりでなければ、現実の行動がどうでもどこまでもそんなつもりじゃないもの」
少女が邪気の中で静かに漂っている。
「今更貴方に罪悪感持てなんて言わないよ。貴方は何も深く考えられない人だから、きっと今でも悪いことしたなんて思ってないんでしょ。……他人に対しては」
少女は何も言わない。ただ彼女から発生する邪気だけが、薄い水の膜を徐々に侵食して、織麻に迫っていた。
「自分のことは?……今の自分のことも分からない?」
織麻は畳みかける。
「馬鹿みたいだと思わないの?どうでもいい人間のために人生を壊して。……ろくな生き方もろくな死に方もせず、死んだ後もこの有り様」
水の膜が、極限まで薄くなっている。黒い塊が、赤い髪に絡み付こうとしていた。
「貴方の人生、何のためにあったの?何のために生きてた?何のために生まれて来たの?」
水の膜が弾けた。
だがなだれ込んでくると思っていた邪気は、その瞬間に霧散した。
大きく分厚く膨れ上がっていたが、散ればそれぞれはちっぽけな存在だ。織麻が瞬時に蔓を振り回すと、すぐに切り裂かれた。
「やったか?」
清鈴が寄って来た。大元を打てたかと問うが、織麻は答えないまま視線を彷徨わせた。
「……その前に自分でいなくなった」
「あ?」
清鈴が目を丸くする。邪妖らをつないでいた根本を叩いて、巨大化した低級邪物らを霧散させたのか思ったが、そうではないという。
あの少女は自ら引いた。
「かろうじて意識があったのかな」
自身の言葉に応えたのではないかと織麻は言うが、清鈴は渋面だ。
「だからって、急に改心でもしたって言うのか」
あそこまで拗らせておいて、と疑問を呈するが、それに対して織麻は悪戯っぽく笑って肩をすくめた。
「単にブチ切れちゃっただけかも……」
先程の織麻の発言を聞いていなかった清鈴は首を捻る。そして周囲を見渡す。そこここに、先程まであった巨塊の残滓が見える。小妖怪、低級霊。つなぎがなくなれば、本当にただの小物だ。清鈴は冷徹に水流で祓った。
「本丸は…いなくなった、てのは……」
「消えてはないよ。祓えてない。本当に、どこかに行った」
その言葉に、清鈴は顔を引き締める。
「どこだ。あれをちゃんとどうにかしないと。また繰り返すぞ」
「……」
焦る清鈴に対し、織麻は奇妙に平静だった。
彼女は静かに上を向く。
清鈴もそれに倣う。上向いた視線の先には、高々とある建造物、その頂点。暗い空を背景にした、鉄の柵の並び。
「あの娘の行くべき場所はあそこしかないよ。見てもらえるのは、あそこしかないもの」
確信があるようだった。清鈴も、不思議とそう思えた。
「ここは誰も来ない、誰も見ない行き止まりだもの。あの娘はこんなところにはいたくなかったはず。……だからこそ、何度もやり直してる」
ここに来る前の分かれ道。あの天頂こそが彼女にとっての選択の場だった。最後の最後に人生を賭けた。恐らく、一方的に。
彼女はまたそこにいた。風と無音だけがある、ぐらぐら揺れる足元と、その先にある遠い地面。そればかりの視界は、これで何度目だろう。もう思い出せない。
ぐらぐら、ゆらゆら。揺れるのは、身体か、頭の中か。記憶も意識も、何かも溢れ落ちそうだ。
どうして、こんなところにいるんだっけ。どうして、何度も、何度もここへ。
何もかも分からないまま揺らぎ続ける。この場所で一人。たった一人。誰もいない。誰も来ない。
─────ぎいい、と金属の軋む音がした。
彼女は、久しぶりに振り向いた。
「…────小林愛佳!」
束川董也が叫んだ。
屋上に駆け上がった彼は、ドアを開けた瞬間、行き合ったその怪異に対して、その名を叫んだ。先程教諭から授かった情報にあった死亡生徒の名。
小林愛佳、だったものは振り向いた。その姿は影のようで、表情は見えない。ただ、その陰影と髪の毛をゆらゆらと揺らしている。
その様を見て、董也は眉を寄せる。先程から見せるどっちつかず。行動の行き先を決め切れない、決めようとしない優柔不断。────苛立たしい。あれは、聞き飽きた、口だけの苦悩と同じ種類のものだ。
「────飛ばないのか?」
董也は低く言った。相手は、何も反応しない。反応しているのかもしれないが、見えない。こちらを向いたまま、しかし揺らぐのはやめてただ静止する。その様を見やって、董也は腕を組んだ。
「飛び降りないのかって。死にたいんだろうが。あと一歩前に行けば死ねるぞ」
挑発するように言っても、相手は微動だにしない。董也は溜め息をつく。
「うんざりなんだよなぁ……、お前みたいな奴。死にたい死にたい言いながらこっちをちらちら見て、死ぬな生きろって言われるのを待ってる奴。まあ立場上、言わなきゃしょうがないからそう言うが、……一度言ってみたかったんだ。お前には、言ってもいいだろ?」
死にたいならさっさと死ねと。そう言われた少女は、風の中ただ佇んでいる。
董也は鼻で笑った。
「こう言われたら死なねえんだろ。本当は死にたくなんかないんだもんな。お前は死ななきゃなんて思ってない。罪悪感も責任感も持っちゃないんだから。ただ周りに理不尽に責められて癇癪起こしてるだけ。恨みや嫌悪なんて上等なものじゃない。ただ拗ねて当たり散らしてるだけだ」
周囲の悪口雑言や白眼に耐えられずに、悲憤のあまりこの屋上に駆け上がったというが、彼女は本当に死ぬ気はなかった。ただ当てつけたかった。自分は周りのせいで死ぬほど苦しんでいると、だからこの死に対して責任を感じて、自分を止めろと、暗に訴えた。……結果は、沈黙。
やめろとも、生きろとも、死ねとさえ言われなかった。誰も何も言わず、ただ黙って佇んでいた。よく見ると、そこにいたのはクラスメイト全員でもなく、教師とかクラス委員、生徒会役員など、それが責務である人間だけだ。多くは、教室にいるまま。
「そんな有り様だってのに、何度もこの場面を繰り返してどうする。何度目かに、今度こそ誰かが止めてくれるとでも思ったのか?」
何度も繰り返せば、今度こそ。違う結果があるのではないかと。柵の内側に帰れるような、別の可能性。
「どこまでも人任せなんだな。他人の言動で自分の言動も決める。……いじめにしたって、周りの責任にしてるんだろ。誰かが止めてくれてればって。……確かにそうだ。皆知らん顔して、それが悪かった。けど、何でそうなったか分かるか?」
表情の見えない少女が、ほんの少し、反応したように見えた。
「どうでもよかったからだよ。お前もお前がやってることも。他の奴らには気にかける必要もないどうでもいい行為で、存在だった」
董也は、彼の人柄には珍しいほどの悪い笑みを浮かべて言う。挑発するように、嘲るように。
「お前はさ、悪いことしてるどころか、良いことしてる気分でもあっただろ。仲間内に娯楽を提供してやってる、クラスのはみ出し者を皆を代表して罰してやってるんだっていうくらいの気でいただろ。皆が喜んでくれてるって」
だからこそ、相手が死んで、全てが敵に回った状況が許せなかった。沈黙という同意のもと、彼女がクラスの厄介者を虐げる姿を密かに楽しんでいると、そう思っていた。だが、いざこれまで視線を向けていた少女がいなくなって、ゆっくり周囲を見渡してみると、……自分達を見ている者など、誰もいなかった。
「それが答えだ。お前が何をしようと、誰をいじめようと、死のうと、周りの奴は知ったこっちゃない。お前の行動もお前自身も、興味なんかない。自分達には関わりのない人間」
──────どうでもいい人間だったんだ。お前達は。
そう言い放つ。すると、目の前の影は、揺らめきでも翳りでもなく、明確に揺れた。そして、影になっていた顔がはっきり見える。
………どこにでもいる、普通の少女だった。彼女は、その顔を歪ませて、拗ねたような、いじけるような表情を浮かべて、唇を噛んで、顔を背けた。
そして、揺れることなく、真っ直ぐに、足を前に踏み出して、明確に、そちらがわに行った。自ら境界線を越えた。
そして、そのまま消えた。
束川董也は前に進んだ。彼女がいた位置に。
後に、野茨織麻と上屋清鈴もやって来た。三人、柵ににじり寄る。
下を覗くと、そこには何もなかった。小さく見える木や校舎だけがある。
織麻、清鈴は、そこに一切の怪異がないことを認めた。何度も落ちては鬼門を騒がせていた少女の怨霊は、完全に消えたようだった。
「……どうしたんだ」
先程までの荒れくれようを見ていた清鈴は不可解に呻いた。董也は溜め息をついた。
「終わったんだよ。……言ったろ、自殺者は恨まない」
そう言いながら、振り向いて柵から離れた。
「やっと自分で死んだんだ。自殺できたんだよ、あいつは」
静かに言って、彼は歩み去る。二人は、それに続いた。
織麻はまた、そこで振り向いた。そこにはやはり闇だけがあって、その暗さにはどうしてか引かれる。……あの娘も、そこに引き込まれたんだろうか。行き詰まった地べたではなく、広々した虚空に溶けることが出来たのか、やっと。
織麻は少しだけ笑った。そして虚空に背を向けて、風の中を去った。
校内の北東の日陰に、花と線香が供えられた。束川董也は、そこで手を合わせた。
「……そういう行動は、かえって霊を留めるぜ」
背後に、上屋清鈴、そして野茨織麻がいた。董也は彼らに向いた後で、また花の前で手を合わす。
「もう完全にいないんだろ」
「……ああ」
清鈴は周囲に視線を巡らせて答える。昨日はあれだけの騒乱があった場だが、今は静かなものだ。影らしく小さな邪妖が蠢いているが、無害なものだ。霊力を帯びる二人を見るとこそこそ逃げて行く。溜まれば威勢が良いくせにと呆れる。
「いないならいないで、無意味じゃない?」
織麻は語りかけるが、董也は涼しい顔だ。
「元からこんなのは自己満足だよ。死んでから花を見たって何にもならない」
小さな花束を足元に、そんなことを言う。
「誰かのために行動するなら生きている内にしないとな。……同情も労りも、死後に与えても何も救わない」
「……あの女の場合、生前であっても、何をしても無駄のように思えるけどな」
清鈴は侮蔑するように言う。あの女とは、今花を供えられている女。この場で怨霊となり、最後には空に散った愚かで憐れな女。
「最後まで理解不能だった。結局何がしたかったんだ」
「自分でも分かってなかったさ。ていうか、何もしたいことがないからこそ、ここでずっとグダ巻いてた」
そもそもいじめ自体、やることのない奴らの娯楽だと苦笑しつつ董也は言う。
「最後の最後まで、何がしたいか、何になれるか、何になりたいのか分からなかった。……あの女子、本当に普通の奴だったよ。成績も平均的なら、文化面、スポーツでも功績はない。家庭も普通。何の特異性もない。……個人を引き立てて証明するものが何もない奴だった」
普通の人間。裏を返せば、何も特徴のない平凡な人間だということだ。何者でもない。
「誰かを貶めて、無理矢理自分の立ち位置を上げて、大胆さや残虐さで集団の中で注目を集めても、結局は仮初だ。自分が何者でもないって現実は変わらない」
加虐というのは一種の承認行為だ。誰かに傷を与えることで相手に認識され、畏怖されることで自分が強くなったように錯覚できる。他人を下げることで自分を上げる行為はコンプレックスが強い人間がよくやることで、更にそれを集団でやることで団結と、そして集団内での力関係の指標にもなる。
「いじめでも何でも、悪さは集団で行われるもんだ。で、集団ってのは、大方似たような者同士で作られる。……この場合は同じ、取り柄のない、平凡な連中」
件の事件で加害者となった生徒らは、皆そんな評価だった。この一件以外、特に目立った悪点もない。外野から見れば、どうして彼女らがそんな大胆かつ悪質な事件を起こしたのか不思議にさえ思える。
董也には何となく掴めた。
「……つまんねえ奴らって、集団を保たせるのにも苦労すんだよ。共通の話題もないし、一緒になって打ち込むこともない。話す内容はすぐなくなって、同じ空間にいながら、各々でスマホの画面を覗き込んでいるような状況になる」
「そういう集団、結構見るけどね……」
最近多い気がする。同じ席で向かい合って座っているのに、視線はスマホ画面に向く。……何のために一緒にいるんだと聞きたくなるが、恐らく、他に行きようもないからそこにいるのだろう。
「だから無理矢理にでも皆で楽しめる内容を作るんだよ。ついでに、そこでの行為の過激さでもって、集団内の序列も決める」
行為をお互いに肯定し合った上で、より大胆で過激な行為をした者が集団の中でのイニシアティブを取るという認識が出来ると、上位を競って行動は更に加速し、時制の利かない段階まで進んでしまう。集団に属していないと自己を保てないのに、その集団の中で優位でありたいと願うのだから、人間の業は底知れない。
「救いようがねえな……」
「……何かおかしな話。他人を虐げるのに、その虐げる相手がいないと、立場や集団性を守れない訳?」
董也は肩をすくめた。
「だから、いじめの相手がいなくなったらすぐに瓦解したのさ。集団も周囲との関係も崩壊。そしてまざまざと思い知った。本来の自分の価値。集団内での地位も、弱者を虐げることで強制的に上げてた自分の価値も、全て幻だったってな」
本来の自分は、ただのつまらない人間だった。いじめという行為も含めて、丸ごと馬鹿にされていて、周囲には無価値な存在として捨て置かれていた。どうでもいい存在だと。
その現実に押し潰されつつある中で、あの屋上での狂言自殺はいわば最後の賭けだった。誰か一人でも自分を止めてくれたら、自分はまだ望まれている存在だと信じられた。だが止める者は誰もおらず、彼女は結局、自分が周りにとってどうでもいい存在なのだと自覚するしかなかった。自身を責めた社会を恨み、そしてその現実を受け入れたくないばかりに、何度もその絶望の場面を再現していた。
そして今、ようやく彼女は絶望を受け入れて、ちゃんと自殺したのだ。自身が生まれた価値はなかったのだと、その事実を刻みつけて。
上屋清鈴は溜め息をつく。
「馬鹿らしい……。そんなに自分の人生が嫌なら、他人を傷付ける前にさっさと死ねば良かったんだ」
「ここまで来ても、死んだ理由に相手が不在なのが凄いよね……。ていうか、その“絶望”って、相手の子も経験したことなのに、そこに共感することはないのかな」
「……そういう共感性や想像力があるなら、そもそも虐めはしてない」
理不尽に攻撃され、周囲に無視され、どうでもいいと見捨てられることは、そもそも最初に死んだ少女が経験したことだ。いじめっ子がいじめられっ子に逆転した現象は、まさにその経験の後追いだ。かつて自分が与えた痛みを自身で味わいながら、彼女は最後まで、相手に申し訳ないとは思わなかったのだ。
織麻の言葉には、董也も暗い顔をした。
「つっても、いわゆるサイコパスとかそういう上等なもんじゃない。……そこまで頭が働かないだけ。未熟なんだよ」
他人の心理や都合を慮る視野がない、自身の行動が他人にどんな影響をもたらすか想像する感性がない。行動には結果があり、結果には責任を取らねばならない。そんな当たり前のことさえ知らなかった。無知で愚かで、……幼い。どこまでも未熟で、子供なのだ。
「だからって行動が正当化される訳じゃない」
「それはそうだよ。どんな事情でもあいつのしたことは許されない。断罪されるべきだったし、今回のことは自業自得だ……」
そこは言い切る。だが、言葉尻はやや曖昧だった。彼は、足元の花を見る。その目元を窄めて、極めて複雑な、何とも言えない煩悶を浮かべた表情をする。
「………どうしてもな、憐れにも思っちまうよ。こいつなりに必死だったんだろうから」
「……」
確かに、必死ではあったんだろう。自分が何者であるか、何者になれるかを懸命に探し求めていた。それがどうしても分からなくて、とち狂った方法で何者かになろうとした。……そんな方法でしか自己を確認できず、そして何より、そのことに彼女自身が無自覚だったことが憐れというか、滑稽だった。彼女は自分が何かを欲していたことを 何かを成そうとしたかったことを、恐らく分かっていなかった。自身の行動や、その心理を自覚しないまま大きな責任が生じる事態を引き起こして、覚悟もないまま浴びせられた非難に耐えられず衝動で死んで、最後、ようやく自分の希求に気付いた時に、全てが取り返しがつかなくなっていた。
野茨織麻は複雑な笑みを浮かべた。
「何か、馬鹿とか幼いとかっていうより、そこが一番深刻かもね。……何にもなかった。からっぽだった」
その呟きに、董也も清鈴も小さく嘆息した。
あの大量の邪は、そこに入り込んだのかもしれない。彼女自身の邪念に引かれ、そのうろの中に巣食った。それであそこまで大きくなったのだから、その空虚の大きさは計り知れない。
「普通ってのが、一番怖いのかもね」
「……贅沢な話だよ」
織麻、そして董也が言い合う。その様を見て、清鈴は片眉を吊り上げる。
「凡庸であること自体は何の問題もないだろうが。……それに勝手に倦んで、かといって何もせず何も出来ず生み出さないまま、奪うばかりで、結局全て失ったのは自分の責任だ」
「ああ……」
清鈴の言葉に、董也は伏せていた目を上げる。
「何もかも自己責任だよ。何もかもこいつが悪い。……学ぶ機会はあったのに、最後まで何も学ばなかった」
そしてまた花を見る。
「けどさすがに今回は何かに気付いただろ。……もう、この先はないが」
─────もし今世の記憶を持って行けるなら、来世こそは、と。
そう言って、彼はその場を去ろうとした。
その背中を見ながら、織麻、そして清鈴は複雑な顔を見せる。
「………」
「ねえ、会長」
呼びかけられて、董也は振り返る。同級生二人が並んでいる。
「私らに何か聞きたいことないの?」
「……」
その言葉に、束川董也は目を丸くして、眉を寄せる。じっと、二人を見る。
いつもと変わらぬ制服姿で佇む、見慣れた、よく知っていると思っていた同級生。だが昨夜、彼女らは普段とはまるで違う姿を見せた。恐舞い飛ぶ水球と縦横無尽に踊る蔦は、恐らく彼らが発生させていた。そして怨霊と、得体の知れない何かに立ち向かっていた。それは普段の彼女らとも違っていたし、常人のそれでもなかった。
普通の人間ではない。その事実を、束川董也はその目で認めた。そこに恐怖や忌避はないのかと。一切そんな様子を見せず、常と変わらぬ会話をする董也を、織麻は不思議そうに見ていた。
彼は言う。
「ない」
「……豪胆だな」
清鈴は肩をすくめる。董也は彼を見据えて、挑むように言う。
「言っただろうが。俺は見たものしか信じない」
昨夜、彼らが常人でないことはよく分かった。この世には人外の怪異があり、彼らはそれに立ち向かい、そして打ち勝った。脅威の上を行く脅威。得体の知れない何かを越えた、得体の知れない何かだ。
と、同時に、彼らが自身には何の害ももたらさず、そして、校内の厄介ごとを解決してくれたということも、間違いない事実だった。
「今はそれでいい」
潔く言い切る。全く迷いもない。その姿に、清鈴は笑う。
「本当に腹がすわってる」
「そうでなけりゃ、長月第七で生徒会長なんて出来る訳ないだろ」
小さな溜め息混じりに言う。心労も見えるが、しかしその姿は、どこか誇らしげであり、楽しげだった。
「今更、変わり種が増えたところでどうも思わねえよ」
そう言い切る姿は実に潔い。本当に、心の底からそう思っているのだろう。この学府の全生徒の長である彼にとって、二人は自校に突如として現れた、しかしこれまでと変わらぬ見知った同級生であるらしい。
少なくとも今は。
彼はその意見を曲げる気はないらしい。結論の出た問題をいつまでも引きずる性格ではない。
……だが、そんな彼に、織麻は問うた。
「今はそうでも、その先は?」
董也、そして清鈴も彼女を見た。彼女は無表情で、しかし、その顔は相も変わらず可愛らしい。その柔さと、表情の硬さがひどくちぐはぐで、だがその乖離が妙に艶かしかった。
彼女は目元を真摯にしたまま、口元だけ笑ませて言う。
「これから私達が、貴方の脅威になるって思わないの?何か悪いことをするって」
今は良くても、これからはどうか。
董也は大きく目を見開いた後で、ひどく苦々しい目つきをした。
織麻の言葉が、全く響かない訳ではないのだ。今はそれでいい、と、彼自身が言った。……この先は、彼にとって未知だ。
それを今から恐れないのかという問いに対して、董也は苦い顔から複雑な顔になり、渋面を作った後に、虚脱した。
一連の変面に、二人は見入る。
最後に董也は、何かを決意したように顔を引き締める。結局はいつもと変わらぬ生真面目で潔い顔。
「……ま、そうなったら、その時に考える」
簡潔な答えだった。実に彼らしい。
織麻は顔の硬さを解いて、大きな目を見開いた。青い水晶体に、彼が映る。
「起こってないことや目の前にいないことを考えるのは苦手なんだよ。先のことなんて誰にも分からないし、起こってもないことを怖がって萎縮するのも馬鹿らしいだろ」
「………あんたって、頭が良いのか悪いのか、豪胆なのか無頓着なのか、鷹揚なのか何も考えてないのか、よく分からないな」
清鈴の甘苦入り混じる評価に、董也は眉を寄せる。
「人間は元から多面的だよ。一つの性格で出来上がってない。だからちょっと見ただけで、そいつがどんな人間かなんて分からない。……ましてや、見てもいないんじゃ」
「……」
“想像”だけで人を評価するのは愚かだし、少し見えた面だけがその人間の全てだと思い込むのは短慮だ。
董也は、昨日これまで知りもしなかった一面を見せた、見知ったつもりでいた同級生を見る。知らぬ一面を知った今でも、彼らは今まで知っていた二人に違いない。それもまた事実。
「人間の都合の良い部分だけを見て、相手を見定める人間にはなりたくねえよ……」
ぼそりと、董也は言った。
その時に、学校全体に響く鐘が鳴った。
「予鈴だ。授業始まんぞ」
ごく自然にそう言って、董也は校舎へと足を進めた。
織麻はうん、と言って、彼に付いて行く。一瞬見せた強張りはない、いつもの朗らかな笑みだった。
上屋清鈴は、静かに歩む二人の後ろ姿を見て、その潔さに感服しながらも、どこかその姿勢に欺瞞も感じていた。
束川董也は、どんな脅威も起こる前から過剰に恐れないと言った。全ては起こってから、事態を見極めると。それは嘘ではないのだろう。実際昨夜、彼は自身の予想とは遥かに食い違う事態に彼なりに対処した。そしてそれを経てなお、明らか常人とは違う者を受け入れる度量がある。冷静で柔軟、鷹揚で寛容。──────その根本にあるのは、揺るぎない強靭さ。何事にも動じない、動じたとして、すぐに立て直せる強さがある。
つまりは、そういうことだ。
清鈴は少し振り返って、道端に供えられた花を見る。奪うことしか出来なかった少女が、初めて与えられたもの。……人に与えられるというのも、強者の証かもしれない。
あの少女は、集団になって一人を残酷に虐げたが、それが出来たのは彼女らが自制の効かない未熟な理性しか持たなかったこともそうだが、同時に、対象をそのように扱ってもいいと、漫然と思い込んでいたからだろう。虐げられていい人間など一人もいないと断言できるが、しかし、虐げられやすい人種というのはいて、他より何かが劣る者、かえって優れている者、そして違う者だ。
いじめ対象になったのはそんな人種だろう。恐らく、一般的な女子高生とは違った。周りに合わせなかったのか、話さなかったのか、単に今風ではなかったのか、何せ他とは違った。それがごく一般的な、普通の、今時どこにでもいる少女らの何かに障ったのだ。
“異質”への忌避は本能的なものだ。誰でも自分に似通った姿のものには愛着を持つが、それは同族への安堵であり、自身の共生者への無意識な依存だ。群れねば生きていけない生物の生存本能。そして自身に似ないものへの拒否反応はその逆。敵になるかもしれない者への攻撃性。それもまた生存本能。
そして、これに関しては、人間ならではなのかもしれないが、自分と違うものには何を言っても、どんな振る舞いしても許されると思っている。相手を別の生き物だと思っているから、人間同士の最低限の気遣いや遠慮がない。相手が、自分と同じように感じたり考えたりするものと思っていないのだ。そういう意味では、あの少女らがどこまでも自身の行いを悪いことと認識できなかったことも理解は出来る。彼女らにとって、相手は自分らの言動に傷付いたり苦しんだりする真っ当な感性を持つ、自分らと同等の存在ではなかった。
「……」
想像力の足らない、思考の巡らない馬鹿の愚行と言い捨てればそれまでだが、そればかりとも言い切れないのが生物の業だ。
相手を攻撃せねば生き残れない場で、相手の心情や事情を慮っていては生存競争に負ける。そう考えれば、これも本能の内かもしれない。自分と他人、同族の間にも境界線を引く。線の内側で必死に自分を守りながら、そこを侵食されまいと、向こう側を攻撃する。
……防衛線。これも“境界”。
それを引かずにいられるのは、結局は強い人間なのだ。線などなくても自身の立ち位置を認識できる。侵食されても自分を護れる、また相手に立ち向かえる、対処できると確信している人間。
異物を、他者を許容できる人間というのは、寛容とはつまり強さなのだ。強者の余裕、特権。
清く正しく在れるのは、結局は強い人間だけ。汚れるのは、弱者だ。
……ならば、この世の大概の人間は常に穢れの方に行く危険を背負っている。清も濁も、正も邪も、生も死も、境界線はあれど人は常にその真上を渡っていて、足先がどちらにつくかは本当に一重の差なのだ。僅かに揺れれば、安易に邪にも魔にもなる。
花は揺れている。風に煽られてゆらゆらと。屋上で見た、少女そのままのようだ。
視線を逸らし、校舎を見ると、生徒らが行くのが見える。授業の開始に向けて慌てて駆ける者もいれば、この状況でも悠々と歩む者、まるで動こうとしない者も。大勢の人間がいる。それぞれの意思や感情や思惑を持って動く。
長月第七高校は、三列の校舎が並行して、その中央を一本の廊下が貫く。あの少女は行き止まりで死んだが、そのすぐそばにはこの校舎の中心が、全ての道が行き交う、あらゆる人生が重なる場がある。
そこで時にすれ違い、ぶつかり、追いながら、本当に自分の歩みを守れている者は一体何人いるのか。揺らがず、流されず、立ち止まらず。
「………ここにいる何人が、本当の意味で正気なのかな」
そう言いながら、屋上を見た。一人の少女が生死を賭けた場所。生と死の明確な柵が並ぶ場所。あれは、目に見える形でも見えない形でも、あちこちにあるのだ。今も誰かが、その線の上に立っている。
時間を千切る鐘が、大きく鳴った。
だが、そんな彼女はある時、地上に向けて高速に落ちた。その最中、彼女はずっと自問していた。
─────どうして、こんなことにと。
彼女は、どこにでもいる少女だったのだ。親に愛され、友人らと親しみ、日々を楽しんで生きていた。なのに、何故こんなことに。
地面に顔の半分をめり込ませながら、まだかろうじて残る意識の中で、彼女は自問し続けた。
何故こんなことに、どうして────。
誰のせいで。
石畳に自ら流した血が広がっていくのを見つめながら、ただ問い続けた。
束川董也は夜の学校を一人で歩いていた。彼はこの長月第七高校の生徒会長で、他の生徒より早く来て、遅く帰ることが多かったが、それにしても今日は遅かった。窓の外はとっぷりと日が暮れて、水平線の向こうに僅かに赤い夕陽の残滓が残るのみで、殆ど夜。暗い中で廊下だけに灯りがともり、ぼんやりと浮き立つように光る様は何だか不気味だった。
だが、董也はその中を確かな足取りで歩いていた。彼は身長は平均程度だが姿勢が非常に良いので歩む様に妙に威厳がある。刈り込まれた黒髪、黒縁眼鏡の奥に、少し厚めの瞼に覆われたゆえに半眼に見えて些か目つきが悪く見えるが、それでも覗く黒い瞳に誠実さと平静さ湛えているから怖くは見えない。眉は平坦で面長の顔はのっぺりして、表情から一切の動揺は見えず、口は厳に引き結ばれて堅固な意志を感じる。
彼はある目的があって、もう人のいなくなった校舎に一人いるのだ。
「……」
ふいに、人の気配がした。ちょうど眼前にある曲がり角の先。彼の立ち位置からは見えないが、確かに人の足音がした。
「おいっ、誰かいるのか!?」
そう叫ぶと、足音が急に早く大きくなりだした。そこから駆け出したようだ。
「待てっ!!」
叫びつつ、董也も駆け出す。足音が二重になった。角を曲がると、校舎中央の階段を降りたらしい。三階のその場所から、董也も駆け降りる。決して運動神経が悪くない彼だが、眼前の人物はそれより数歩早く、踊り場に出る時にはもう階下にいて、姿を認めることが出来ない。軽い足取りでリズミカルに早く、階段を降りているようだ。────女の足か?と、董也は一階まで降りていた。すると今度は平面での追いかけっこが始まる。
「おいっ……、いい加減に……!」
苛立ちのまま足に力を込めて速度を上げる。距離が詰まるのを感じる。そして、中央の階段から真っ直ぐ伸びた廊下の終点、校庭と逆の樹木に覆われた校舎裏に面するそこは、夜の時間は真っ暗闇だ。そこに追い込む。董也は制服のポケットから携帯電話を取り出し、ライトを付けて暗闇で佇む人物を照らした。
その瞬間、黒縁の眼鏡の奥の吊り上がった目に映ったのは、真っ赤な毛並み。暗闇の中で一点に絞られた光の中で異様に輝いて見える赤色。
「……野茨か?」
董也が問う。すると赤毛に少女は少々気まずげに微笑んだ。その瞬間、廊下に灯りがつく。それに驚きつつも、眼前を見ると、そこにはやはり見知った少女が立っていた。クラスは違うが同級生。
二年生の野茨織麻。数多くいる生徒の中で、生徒会長とはいえ束川董也が彼女を知っていたのは、その少女が校内でもひどく目立つ存在だからだ。人目を引く真っ赤な髪。腰まで伸びたその髪は波打ち、少女の華奢な身体を覆うようだ。赤い穂波の中の顔は白く小さい。細い輪郭の中にくっきした眦の大きな目。その中央の虹彩は青く、やたらと白い肌といい筋の通った鼻といい、全体に彫りの深い顔立ちといい、一目で混血と分かる彼女は校内でも目立つ存在だ。二年生の中でも群を抜く美少女。それがこの長月第七高校の、野茨織麻に対する評価。
「……何やってんだ、こんな時間に」
普段から親しい間柄ではないが、それでも生徒会長の義務として、下校時間を過ぎて校舎にいる彼女の行動を咎める。単純に疑問でもあった。織麻は、校内では目立っても風紀を乱す存在ではない。成績も授業態度もまあ普通、友人関係、教師との関係も悪くない。ダンス部に所属する、極めて模範的な女子生徒である。
模範生、野茨織麻は気まずそうに微笑む。
「ええっと……。探検?」
おどけるような口調で返され、董也は瞬間的に眉間に皺を寄せた。
「お前か?最近夜に校舎うろついてるのは」
そう問われると、織麻は慌てたように手を振る。
「違う違う。夜来たのは今日が初めてで……」
「じゃあお前も妙な噂聞きつけて、肝試しでもしに来たのか。高校生にもなって、何やってる!」
怒鳴る生徒会長に織麻は肩をすくめる。
「……会長は、そういうのの取り締まり?」
「ああ、そうだよ。馬鹿な噂の真相と、それを間に受けて校内を嗅ぎ回る奴を見つけに来たんだ」
束川董也の目的はそれだった。この頃、長月第七高校には、妙な噂が立っていて、生徒らが浮き足立っていた。董也は生徒会長として、その収束のために動こうとしていた。
「高校生にもなって、噂を信じ込んで下校後に学校に居残ってたり、他校から進入者まで出た」
「ああ、知ってる。投稿サイトに上がってたね」
「すぐに消させたよ。はた迷惑な……」
ひどく忌々しげに周囲を見る。別段変わったところもない夜の学校。
「ああいう手合いを寄せ付けないために、根本を解決しないと」
「え?」
織麻が首を傾げる。束川は眉間の皺を更に深くした。
「噂の元になってる奴から聞き取りしたんだよ。そしたら、複数人から共通の目撃証言があった。それだけの証言があるなら、眉唾じゃない。何かしらある」
「……どう考えてるの?」
実に行動的な有能な生徒会長に問う。董也は黒縁の眼鏡の奥の目を険しくさせて答える。
「誰かの演出だろ。騒動起こして楽しんでんだ」
「なるほど」
「だから見回りしてたんだよ。人がいれば姿を現すかも」
「手伝うよ」
そう声を出したのは、織麻でも董也でもなかった。董也がぎょっとして、声の方を見る。すると、制服姿の男子学生が立っていた。先程電気つけたのは彼らしい。
「転校生……」
「上屋だ」
そう名乗った彼は、つい先頃この学校に来た転校生だった。そうだ、確か上屋清鈴といった。季節外れの転校生に関する情報を思い出す。
「……お前ら、二人で来てたのか?」
「あ、うん……」
織麻は頷く。学年は一緒でもクラスは違うこの二人に接点は見えないが、いつに間にそんなに親密になったのだろう。真っ赤な髪でいつも溌剌とした印象の明るい美少女と、黒髪を短く切り揃え、大きな瞳ではあるがいつも伏せ目がちであるゆえ切れ長に見えてやや冷淡な印象の、口を尖り気味に引き結びそこに細い顎の鋭角性も伴って、端正であるが親しみにくい顔つきの神経質そうな少年とは、どうにも合わない気がするのだが。
「別に変な仲じゃないよ」
「……今回の件に興味があって」
清鈴の発言に、董也は首を傾げる。
「心霊に興味でも?」
「そんなところ」
そんな印象は全くない同級生に、不可解な点を感じたが、しかし浮ついた感はない彼と、根は真面目と知っている織麻なら信用できると思った。
「そうだな。人が多い方が目立つし、釣りやすいかもしれない」
そう言って、改めて廊下を見据える。一階のちょうど端に来て、真っ直ぐ伸びる長い廊下が見渡せた。
「せっかくだ。ここから三階までしらみ潰しで行こう」
「おー」
「行こう」
そう言って、清鈴は壁に設置された電気のスイッチを全て押した。一階廊下が一気に明るくなって暗がりを照らし、闇夜との境界線がより目立って、その対比を際立たせた。
長月第七高校は、その名で設立されてからはまだ二年目である。しかし、校舎自体は十数年が経っており、それなりに年季が入っている。校名と校舎の歴史に食い違いがあることで分かるように、成り立ちがやや複雑であったが、基本的には平和な校風の中で近頃不穏な噂が流れていた。
曰く、夜な夜な女の霊が出て、通りがかった生徒の眼前で死んで見せると。
部活や自習で遅くまで居残っていた者が見たらしい。中校舎の屋上から制服姿の女性が飛び降りる様を。慌てて飛び降りた先に駆けつけると、そこには何の痕跡もない。一度なら見間違いで済むだろうが、そんなことが何度も起きた。女子生徒が飛び降りて、しかし地面には何もない。何人もがそれを見たと証言したから、こんな噂が立ったのだ。
昔自殺した女子生徒の霊が成仏できないまま彷徨い、何度も自身の“死”を繰り返しているのだと。
「馬鹿馬鹿しい」
束川董也は吐き捨てた。いかにも厳格な生徒会長の言いように、織麻は苦笑いした。
「言い切るな。人為的なもんだった確信してんのか」
心霊現象に全く感応がないらしい生徒会長に上屋清鈴が問う。黒縁眼鏡の奥から睨めつけながら、董也は答える。
「当たり前だ。自殺者の霊なんて、ある訳がない」
「根拠は?」
「今探してる」
廊下を進みながら教室を覗いて回る。トイレや用具入れまで確認した。だが、根拠は見つからない。
「異常なし……」
董也が険しい顔で溜め息をつく。その様を見て、清鈴は眉を寄せる。
「ずいぶん熱心だな」
生徒会長の職責としてもやたら力の入っている様子を訝しむ。董也は更に顔を険しくする。
「当たり前だろ。こんなタチの悪い悪戯、何度も……」
「何度も?」
董也の言葉に反応すると、織麻が苦笑いした。
「前にもちょっとあったんだよね、ネット関係で……。ほら、うちって成り立ちが複雑じゃない?元からネット社会の一部から注目されてて、それでまあ……変な情報ってか校内の動画が流出しちゃって、そこから一時期ひどかったのよ。イタズラ電話とか」
「まあすぐに収まったがな。ほんとにタチが悪い……」
憤慨する生徒会長に、清鈴は肩をすくめる。まあ何かしら前例があるなら、それを疑いたくなるのも分かる。しきりに周囲に目を光らす厳しい顔は、生真面目さと律儀さに満ちている。自身の考えが正しいと信じて、その行動が学校や生徒にためになると信じ、自らの役職に相応しい義務を果たそうとしている。今時珍しい真面目な高校生。だが、真面目な人間というのは裏を返せば頑固で偏狂でもあり、自分が見たものしか信じない。そこに以前の悪質な工作の事例もあって、今回のものもそれに倣うものと決め込んでいるようだ。
清鈴の視線を感じ取ったのか、董也はふいに振り向いた。いかにも現実主義的な理系の顔。眉間に皺が寄る。
「何だよ」
「別に」
更に歩を進める。人のいない校舎には、三人の足音だけが響いている。普段は喧騒に包まれる場に、いやに目立つ足音。廊下には影がくっきり見えるて、光の加減で二重三重にもなって、一つの影が別の影を追うようにも見えてぎょっと驚く。振り返っても誰もいない。だが、妙に不安が心にかかる。
野茨織麻が呟く。
「夜の学校って不気味……」
その言葉に、束川董也は眉をひそめる。
「別に必要以上に怖がることじゃない。時間と人数が違うだけで、いつもと同じ学校だ」
どこまでも冷静で現実的な物言い。やはり理性が強い。理屈抜きの本能的恐怖というものが少ないのだろうし、それを抱く他者に共感もしない。頼もしいとも言えるが、織麻はやや不満げである。
「会長ー。ホラー映画じゃそういうこと言う人からヤられちゃうんだから」
「やられるかよ。夜の学校でこそこそ生徒怖がらせてる愉快犯に負けるほど弱くない」
「……」
彼にとって、今回の件の真相はそれで決着がついているらしい。
その頑固さに呆れた視線を感じたか、生真面目な生徒会長はまた振り向いて、清鈴を睨む。
「だから何だ」
「現実的だなと思って」
「お前、幽霊とか信じてるクチか?」
超常現象として伝えられる今回の件をそうと捉えているのかと、堅そうな端正な顔に問うが、清鈴は無言のままだ。それを是と取り、董也は溜め息をつく。また背を向けて歩き出した彼に、清鈴が問う。
「逆にあんたは何で信じない?」
「見たことがない」
簡潔な答え。予想通りだ。
「あんたが見たことないからって無いとは限らない。あんたの視野が狭いだけかも」
「……見たことないもんを、どう信じろっていうんだ」
堂々巡りになりそうな言葉を吐き合う。清鈴は正論屋の理系を見つめる。
「それを言うなら、あんたが探す誰かだって、いるかどうか分からないだろ」
前例があるにしても、今回もそれとは限らない。探し求める先が見えないという点では、彼の意見もまた根拠がない。
董也の眼鏡の奥の、歳の割には光の据わった目が歪む。
「根拠はなくても、経験はあんだよ。伊達に生徒会長なんかやってない。」
そう言いながら、少し歩調を早める。それに合わせて、他の二人も早足になった。董也は真っ直ぐに階段を駆け上がり出した。脇目も振らない駆け足に、二人はやや戸惑うが、付いて行く。三階の更に上、生徒らの活動範囲を越え、階段しか無くなったその先に、小さなドア。董也は、その鍵穴に簡素なキーホルダーの付いた鍵を入れて回す。ひどく錆びついた音を立てて、ドアは開いた。
瞬間、湿った空気。六月も終わりの時期だった。本来は梅雨なのだろうが、昨今の気候事情ゆえか雨が少なく、それでも湿った空気は立ち込めていて、そこに早い夏の暑気が混じって、日中には耐え難い不快な空気に纏わりつかれることもあるが、今は夜半。しかも四階の高さの屋上は風も強い。湿り気と風と、ほんの僅かな冷気。まだらの空気の中で、野茨織麻は赤い髪を風の中で翻して、静かに言った。
「屋上に来たの初めてかも……」
「そうなのか?」
転校生の上屋清鈴が問うと、普段は立ち入り禁止だと董也が言い添える。
「だからこそ、鍵の複製なんか作られちゃ、やりたい放題なんだよな……」
この場への鍵は普段は職員室に保管されているが、そう厳重でもなく、持ち出そうと思えば出来るらしい。複製でも造られらたかも、というのが董也の意見らしい。
三人は周囲を見渡した。校舎全体の屋根の上にある広い広い空間。暗く寒く、今は三人しかない。
……ここが、件の“幽霊”が飛び降りるとされる場所なのだ。
三人、そこに歩む。ちょうど屋上の中央、胸元までの柵がある。
「ちょうど校舎の真ん中でもあるんだ」
手すりから視線を下ろし、織麻が呟く。ここは横に広がる校舎の中心でもある。そして、前面に校舎、後面にも校舎、縦に見ても真ん中だった。
長月第七高校の校舎は、90メートルほどの校舎が並行に三列並んでおり、その真ん中を渡り廊下が貫いている造りだ。南北に一棟ずつ。ここはその間。ちなみに南校舎の向こうには食堂や体育館、プールがあり、北校舎の裏はちょっとした林になっている。
「何か新鮮……。こんな角度から学校見ることなんてないし」
校舎を高い位置から真横に見る。確かに、滅多にあることではない。時折校舎の窓からぼんやり外を見やって、何となく対面の校舎を眺めているが、あくまで視界に入るのは一部だ。こんな高みから、校舎全体を俯瞰で見ることはない。三棟ある校舎の中で屋上があるのはこの中央棟だけなので、名実ともにここが校内で一番高い場所だ。
「おい、あんまり乗り出すな」
手すりの向こうの光景に魅入る織麻を、清鈴が制す。彼女はハッと気付いたように後ろに退く。
束川董也は、むしろ積極的に前のめりになって、柵の付近を確認している。
「……見た感じ、それらしい小細工はないな」
清鈴がどこか挑むように言う。董也は眉間を寄せた。
人を使って飛び降りを演出しているなら滑車、それ自体が映像ならプロジェクターでもあるかと思ったが、見当たらない。ただ錆びて古ぼけた暗褐色の柵があるだけだ。
「……他に隠してるかも」
まだ言う董也に、清鈴は肩をずり下ろす。
「まだ疑うのかよ。他の場所っていったって、さんざん探しただろ」
咎めるような言葉に、董也は鋭い視線を向ける。
「ここに来るまでの場所だけだろ。他の校舎も含めて、教室がいくつあると思ってんだ」
「……いくつあるの?」
織麻が聞く。
「普通教室で三十、特別教室が十五」
「……」
「そんなにあるの!?」
董也の言葉に驚く。自校だが、案外詳しい内容は知らない。改めて聞いてみれば、結構多い。
「うちは一学年5クラス。少子化時代にしちゃ多い方だが、昔はもっと多かった。その名残だよ」
「その計算じゃ、使われてない教室も多そうだな」
単純計算すれば、普通教室は半分余る。締め切られ、誰も足を踏み入れなくなった場所。
「誰かが隠れたり、何かを隠したりするには十分か」
「そういうことだ」
束川董也は踵を返して、扉に向かおうとする。その背に、上屋清鈴は声をかける。
「それが人外だっていう選択肢は?」
董也は胡乱げな目で振り向いた。その視線に構わず、清鈴は腰に手を置いて問い続ける。
「あんたの“経験”てのは、学校の間取りに詳しいことか?まあさすがは生徒会長だな」
一般の生徒より学校設備に詳しいのはさすがと言える。そこに何かがあるという確信には説得力がある。だが、その何かが何かまでは、彼の“経験”の中に根拠は見えない。
董也は眉間を寄せて、眼鏡の奥の眦を吊り上げた。我を譲らない男二人が見合う様を見て、野茨織麻はやや焦る。落ち着いてと言いかけたところに、束川董也はふいに表情を緩めて、小さく溜め息をつく。
その様子に、織麻も清鈴も目を丸くする。彼は言った。
「……確かにああいう場所には得体の知れないもんが湧くもんさ。……案外、人でないものもいるかもな」
「………」
先程までと真逆の言葉に、二人はますます目を丸くする。董也は俯いて深々と溜め息をつく。
「本当に、どうやって見つけるんだっていうぐらい、器用に人目を避けて湧く。………………校舎裏で煙草吸う不良」
「……」
「………」
「空き教室でイチャつくカップル、人通りの少ない階段の踊り場でゲーム、未使用倉庫で喧嘩、廃品置き場でひたすら寝てる奴………」
最後の方に怒気があった。恐らく日々彼を苛立たせている出来事なのだろう。……なるほど、これが“経験”か。
「場所を閉め切っても、また別の場所を見つけて、下手すりゃ忍び込んででも同じことをしやがる。……っその根性を他に向けろ、ていうか家でやれ!!」
「………」
「……学校でやるってのがいいんだろうね──」
董也の叫びに清鈴は眉を歪め、織麻は苦笑した。
少女の笑みに、董也は少し呼吸を整える。冷静な表情が戻って来る。
「何か一つ見つけたとしても、その時にはまた別の場所で別の何かが起こってて、その歯止めはない」
ましてや、と、董也は眉間を深く寄せる。
「それが机の下で操作されるスマホの中で起こってるんじゃ、そうそう見つけることも叶わねえよ」
「……」
忸怩たる響きがあった。董也はまた大きく溜め息をつく。
「調べたんだけどな。……確かに昔、校内で死んだ女子生徒はいた」
「え」
織麻、清鈴が目を見開く。
「結構前のことだが、今時ネット使えば昔の事件のことはいくらでも調べられる。……まあ、調査不足だが」
「原因は?」
「いじめを苦にした自殺」
「気の毒ね……」
織麻の呟きに董也は頷く。
「それを利用して騒動起こして、それをまたネットでの馬鹿騒ぎの燃料にしようとしてるなら許せない」
その声と表情には真摯な怒りがあった。
「もう話題が上がってるの?」
「ちらほらとな」
そう言いながら、董也は自分のスマートフォンを出して、SNSを開く。その中に、“長月第七高校”“幽霊”“女子生徒”“飛び降り”の文字がある。
「……これで動画でも上がろうもんなら大バズりだろうね」
織麻が引き攣った笑いを浮かべるが、董也は険しい表情のままだ。
「そんなことさせられるか。また学校の運営に影響が出たら困るし、……何より、遺族がどう思う」
その言葉に、織麻、清鈴は董也を見る。彼の顔はやはり険しく、真摯だ。
「昔って言っても、十数年前のことだ。まだ遺族は健在だろうし、身内の悲劇を面白おかしくネタにされたらたまったもんじゃない」
「そうだね……」
董也の言葉はどこまでも正しかった。学校のため、生徒のため、死んだ生徒、その家族。誰もが傷つかないように、今回の件を早急に解決しようとしている。
董也はスマホの画面を睨む。根拠のない推測や真贋の分からない情報が入り乱れている。それに反応して、また新たな推論が、情報が現れる。彼は忌々しげに言う。
「隠れてこそこそ悪さする連中の中で、こいつらが一番厄介だよ。つまみ出して怒鳴りつけることも出来ない」
「……だからこその悪さだろ」
清鈴が言うと、董也はまた小さく息を吐いて、スマホの画面を落とす。
この僅かな作業で断ち切れる世界は、しかしその簡潔さゆえに使用者に責任というものを感じさせない。簡単に開けて、簡単に言葉を入れて、その結果がどうなろうと、スイッチを切って画面を落としたらおしまい。その奥底でどんな暗雲が広がっているかなど気付きもしないし、気付いたところで責任を持つこともない。
「それでも始まりがここなら、ここで止めることは出来る。……向こう側に行かれる前に止めるぞ」
どれだけ向こう側が広く暗く深い世界でも、そこで広がっていくものが生まれるのはこちらだ。ならば止められる。
三人は屋上を歩み、校内の戻った。
最後、野茨織麻は振り向いて、柵の向こうの、開けた空を見上げた。日の暮れたそこは暗黒。高い位置から見ても、星も見えなかった。ただただ暗く広いそこには奇妙な引力があって、ひどく目と、心を奪われるようだった。
校舎の中をつぶさに見て回る。空き教室、滅多に開けない倉庫、校舎の隅の階段やトイレ。生徒数数百人を数えるこの長月第七高校でも、人通りの少ない場所は結構ある。
野茨織麻ははあと息を吐く。
「何か変な感じー。毎日通ってる学校なのに、知らない場所がこんなにある」
現在二年の六月。およそ一年半通った高校なのに、今日見るのは一度も立ち入ったことのない場所ばかりだ。
束川董也が二人を先導しながら言う。
「そりゃな。毎日通うって言っても、実際使う場所なんて限られてるだろ。自分のクラスの教室、部室、食堂や体育館、いくつかの特別教室。ほぼルーティン化してて、……お前、今すぐに一年一組の教室に行けって言われて行けるか?」
その問いに、織麻は目を丸くした後で少し考えて、首を振る。
「そんなもんさ。自分が関わらない限り、どこにどんな教室があるかも分からない」
学校と言っても、生活範囲はあくまでも学年内の授業範囲内。別学年、選択していない授業や活動の場は知らない。
「三年通っても、一度も足を踏み入れない場所もあるだろうな……」
校舎を見渡しながら、董也が呟く。その様を見つつ、上屋清鈴は小さく言う。
「まるで異界だな……」
彼は少し笑っていた。董也は目を見開き、織麻は静かに視線を寄せた。
「すぐ身近にあるのに、立ち入らない、触れない。線が引いてある訳じゃないのに、どうしてか行かない。そういう場所はあるもんだし、そういう場所がどうなってるのか人は知らないし、知ろうとしない」
無意識の向こうがわ。普段立ち入る場所がどこにあって何があるか常に意識に中にある。だがその隣にあったとしても、行かないなら、見ないならないも同然だ。完全に無意識の存在。
「壁一枚先は未知、一学年の差は無知、選択の外は無関心。知らないまま、意識しないままなら、ただそれだけだが、……時たま、何かのきっかけで無意識を意識した時に、人間は得体の知れない恐怖を抱くのかもな」
野茨織麻は笑う。
「まあ、考えれば学校の怪談って要はそういうことだもんね。昼間普段使いしてるものが、どうしてか突然怖いものになるんだもん」
日常が突然恐怖に。すぐ身近にあるものが、これは怖いものだと意識した途端に恐怖の対象になる。階段、ピアノ、トイレ、プール、貼り出されている絵。普通に見ていればそのままなのに、怖いように見れば怖い。恐怖とはそんなもの、と言うと、束川董也はまた生真面目な顔で溜め息をついた。
「そんなのただの無知とこじつけの賜物だろ。そりゃ立ち入ったことのない場所は怖いもんだし、日常のちょっとしたことを超常現象に結びつけようとすればいくらでも出来る」
いつも通りの平静そのものの声。二人は目を丸くする。
「階段がたまたま十三段になってることもあるし、音楽室の写真が傾いていることもあるさ。だからってその階段が処刑台への道だったり、音楽家の霊が夜な夜な飛び出してるなんて、さすがに飛躍しすぎだろ」
想像力には敬意を払うけど、とどこまでも生真面目に言う。
織麻は苦笑した。
「会長さ……。一応調査して、自殺者がいたことは知ったんだし、それが霊になってるって発想、一ミリも浮かばなかったの?」
何も前情報のない状態なら、霊など眉唾、と言い捨てることもあるだろうが、少しでもその根拠になる情報があれば、いくら現実主義者でも、僅かばかりの疑問は抱くものではないのか。
織麻のその言葉に、董也は少し考えた後、眉を歪めつつ首を捻った。
「……それ、前から思ってたが、理屈に合わないだろ」
「は?」
「何で自殺者が霊になる」
二人は眉を歪める。
「自殺ってのは、自分から進んで死んだんだから、この世に未練なんかないはずだろう。死ねて満足、さっさとあの世に行けばい」
「……」
「………」
何という簡潔かつ理性的な考え方だ。だがまあ確かに、理屈は合ってはいる。
自信ありげな生徒会長に、織麻は恐る恐る物申す。
「けど自殺する人って、この世の何かを、誰かを恨んだ結果死んだんでしょ。未練というか、悪意は残るんじゃない」
そう言うと、束川董也は心底複雑そうな表情を浮かべる。そして溜め息をつく。
「……確かにそうだろうよ。何かに苦しんで死んだ。……けど、本当にそれで死ぬほど苦しんでる人間ってのは、その苦悩を人にぶつけたりしないもんだ」
二人は目を見開いた。
「俺も立場上、そういう人間からよく相談を受けるよ。あれが辛い、これがしんどい、生きていたくない、死にたいってな。……けど」
そうやって死にたい死にたいという人間が、本当に死んだことはない、と束川董也は言い切る。
「苦しみを人にぶつけられる人間ってのはまだ余裕があるんだ。というか、口で言うほど苦しんでもいない。……まあそれはそれで良いんだ。何か悩みがあるのは確かなんだから。それを他人に話したり、誰かを恨んだりすることで解消出来てるなら、それはそれだ」
少し呆れたような口調になりつつも、苦悩者のそういう心情に一定の理解はあるらしい。だが生真面目な彼が本当に気がかりに思うのは、そうでない人種。
「本当に危ないのは、苦しいとも死にたいとも言わず、表情にも出さない奴。そういう人間は、本当に、ある時突然、まるで思いついたように死ぬ」
「……」
二人は静かに彼を見る。
「苦しみを他人にぶつけられない人間ってのはいるもんだ。そういう人間にとっては、苦しみを除く最大の手段が死ぬことなんだろう」
苦しみも悲しみも恨みも全て己の内に抱いて、誰にもぶつけず漏らさず、抱いたまま死んで、全ての苦悩を終わらせたのだ。その時点で、本当に全ては終わり。その先はない。何もかも消えたのだ。消えるために消したのだから。
「─────潔い」
董也は、視線を上向けて、そこにいる人間に敬服するように、言った。
「そんな風に全てを自己完結出来る人間が、死んでから誰かに恨みをぶつけたり、脅かしたりする浅ましい真似するもんかよ」
「……その苦しみを与えた当人にも危害は加えないと?この場合はいじめの加害者か」
怨霊の本懐は即ちそれだろうと、清鈴の言葉に、董也はまたも簡潔に言う。
「それをしたいと思うなら生前にやってるだろ。自分を殺す度胸があるなら、嫌いな奴を殴るなり刺すなり、いくらでも出来るだろ」
「……」
「………」
簡潔な上にやたら物騒な意見である。この生真面目な生徒会長、理性的なのか感情的なのか分からない。呆れ顔の生徒二人に、董也は言い募る。
「さっきも言ったが、人間、どれだけ辛い苦しいって言っても、いざ自分を殺す度胸はそう湧かないもんだ。自分で自分を殺せる奴っていうのは勇敢だよ」
その勇猛さがあれば、他人を攻撃することなど容易いと。織麻が可愛らしい顔を歪めた。
「……もしかして生徒会長、自殺に賛成するタイプ?立派な行為とでも?」
苦い問いに、董也は首を横に振る。
「そんな訳あるか。命を大事にしない奴なんてろくでもないさ。……ただ」
そこで少し言葉を切る。
「そんな行動が出来る度胸というか、思い切りの良さは認めるってことだ。そこに至るほどに苦しんだっていうことも」
厳粛な顔を少し緩める。
「自殺を賛美することは断じてしないが、苦しんだ末に死を選んだことを、恥だとは思わない」
「……」
自殺は逃避だと言う人間もいるが、束川董也はそうは思わない。本当の逃避者とは、現状の苦しみに対して自分にも他人にも何の行動も起こさず、口先だけで苦しみを垂れ流す人種だ。辛い苦しいと口を動かす元気はあるのに、その口で辛い苦しいと訴える人間の何とも滑稽なこと。それに比べれば、苦しみを終わらせるためにさっさと身体を動かす人間の潔いことだ。その行動が、生きて苦悩を取り除くためであれ、死んで苦悩から解放されるためであれ、董也は“行動”自体は称賛するかは置いておいて少なくとも認めるし、そういう人間が死んだ後になって人を害すような馬鹿げた真似はしないと確信している。
董也の理論は奇抜であったし、そう簡単に認めていいものではないだろう。だが、野茨織麻には、少しだけ同調できる部分があった。
「ま…確かに度胸はあるかもね。自分で自分を殺すって、思ってるよりずっと怖いよ」
そう言いながら、彼女は先程足を踏み入れた屋上を見つめた。今三人は例の屋上がちょうど見上げられる中央、北校舎の合間の屋外通路にいた。距離はあるが、高い位置にある屋上と、そこに並ぶ柵がはっきり見える。
それを見て、野茨織麻は静かに言う。
「飛び降りたってことは、あの柵を越えたんだよね」
その言葉に二人は目を丸くし、彼女に倣って、階上の屋上を見た。先程見た、風と静寂に満ちた場所。
「近寄って見てわかったけど、あの高さって本当に怖い。柵のこっち側にいても、下見たらぞくっとした。……それを、柵の向こうで見るってどんな気分なんだろうね」
「……」
建物として四階の高さ。10メートル弱とというところか。あの位置から見れば、地上では等身大のものたちが全て小さく、遠く見えた。その様を認めると、誰もが背筋に冷たいものを感じるだろう。ここからそこに行けばどうなるか、想像して身震いする。
あそこから飛び降りた人間は、その震撼を越えたのだ。
「それだけの絶望ってどんなものだろ」
青い目に暗くなった夜を写し、そこに茫洋と浮かぶ校舎、その最上階の規則的に並んだ金属の柵を見る。
あの柵も境界だろう、物理的な。柵のこちらがわとあちらがわを分ける。
意識とは違う、物理的な一線。あの柵の向こうもこちらも学校の一部だが、錆びた鉄柵一つで隔てられた向こう側はまさに異界だ。あちらは死、こちらは生。分ける世界はあまりに違う。
野茨織麻は束川董也を見る。
「人間って悩みが尽きないよね。会長にしんどい死にたいって言う人達も、その時には本気なんだと思うよ」
その言葉に、董也はぴくりと顔を揺らす。織麻は薄く笑った。
誰でも思い悩むものだし、時には死さえ望むこともあるだろう。その衝動のままふらふらと、あの屋上に彷徨い行くこともあるのかもしれない。だが、いざ飛ぼうとした時に、胸元に当たるあの柵が、一瞬歩みを止めるのだ。そしてふいに下を見て、瞬間、恐れに襲われる。その恐怖というのは生存本能。死から遠ざかるための感情。衝動的な行動を抑制し、冷静さをもたらす。そして、理性が衝動に勝てば、人はあの生死を隔てる柵から遠ざかる。死から遠ざかる。
……だが、その本能さえ打ち消して、柵を乗り越え向こう側に行く人間もいる。爪先で立って、片足を上げて柵に引っかける。乗せた手に体重を預けて、そのまま身を乗り出す。身長よりは低くても、それでも越えるには高い柵を越えて、それだけの動作を経て、敢えて、向こう側に行く。その間に一切の逡巡はなく、思い留まることもなく、柵の向こう側へ。それはもう衝動ではない。覚悟だ。阻むものなど何もないそこで、本当に一歩先に出れば全てが終わるそこで、その一歩を踏み出すことをもはや躊躇わなくなった覚悟と諦念、────絶望。
落ち行く瞬間は開放感に包まれているのかもしれない。そして地表に着いたその瞬間が、まさに全ての終わりの時。命と共に、全ての苦しみが終わる。
潔く終わらせた人間が、その後を望むだろうか。
「何か、行動と心理がちぐはぐって感じ。終わらせたいはずのことを何度も繰り返すって、それ……」
結果が不満か。……或いは、終わらせたくない。終わりというたった一つの結果しか望んでいないはずなのに。
霊現象そのものよりも、霊の心理状態に疑念を持ち出した二人に、上屋清鈴はやや焦燥を示す。
「お前ら、今はそういうことを言ってる場合じゃ……」
言いかけて、清鈴も視線を件の屋上に戻した。そして、視界の端にそれを見やる。
「現象の起源や理なんざ、どうだっていいだろ……。実際、起こってるんだ」
その呟きに、織麻、董也もまた屋上を見た。
「!!」
驚愕する。二人もまた、それを認めた。
暗闇の中で、相変わらず毅然と佇む校舎。その最上。暗闇に慣れだした目に、確かにそれが見えた。
遠目だが、確かに人間のシルエットだ。短いスカートは女子である証。肩まで伸びた髪も分かる。それらは風の中で揺らめいて、その揺らめきのまま、その女は体幹をぶれさせる。
「お、おい……」
さすがに董也が慌てる。
「……出た」
「ああ」
対して、織麻と清鈴は妙に冷静だった。静かに、高い屋上でゆらゆら揺れる少女を見つめる。その視線の先で、彼女は上半身を前にのめらせた。
「……っ!」
董也が駆け出す。
「ちょ……、待って」
織麻が制止するが、董也は聞かずに少女のいる校舎に向かって走る。ここでそうしても、もうどうしようもないが、それでも董也は走る。
「……偽物だと思ってるんじゃ?」
着いて来て並走する清鈴が皮肉っぽく言うが、董也は吐き捨てる。
「そう思ってるよ!けど、さすがに……」
どうやっているのかは分からないが、あれは明らかに危ない。屋上でゆらゆらと身体を揺らして、今にも落ちそうではないか。
「!!」
駆け寄る最中に、屋上の女子生徒は大きく上半身を前にのめらせた。そしてゆっくりと、頭から地上に落ちて行く。
「おいっ……」
焦燥を声に滲ませて、足を速める。今から屋上に駆け上がることは出来ない。彼女が落ちたと思われる校舎の足元に向かう。そこに行ったところでどうなるものでもなかったが、董也は人間の義務として駆けた。
そしてそこに辿り着く。目を剥いた。
「……え?」
少女が落ちたはずのそこ、悲惨な有り様が広がっていると思っていた場所には、何もなかった。思わず上を向く。屋上にも何もない。その途中にも。先程間違いなく目で見たはずの少女は、影も形もなかった。
「どうなって……?」
前後左右を見渡しながら戸惑う。見間違いか、それともやはり悪戯か。それにしても。あのゆらゆらと揺れる人影、転落のモーション、その動きに合わせて翻る髪にスカート。偽装には思えなかった。あまりに自然だった。
「……やっぱり幽霊かな?」
いつの間にか追いついて来ていた野茨織麻がどこか面白げに言った。
「いや、そんな訳……」
混乱したまままた上を向く。するとそこには、また彼女がいた。やはりゆらゆら揺れて、危うい足元で屋上に立っている。
「………っ!?」
「こりゃ、決まりだ」
清鈴が険しい顔で言う。
「そんな訳ない……」
「まだ言う?さすがに、私らのハズレだよ」
織麻が呆れ顔で言う。
「いやだから……」
言い合う内に屋上の少女はまた落ちた。真下にいる三人に向かって真っ逆様に落ちて来た。
「……おい!?」
慌てるが何も出来ない。立ち尽くしたまま、どんどん迫って来る少女を見つめた。猛スピードで落ちてくる。次第にその髪が、制服が、四肢がはっきり見えて来る。顔が見えそうになった。が、その瞬間に、彼女は消えた。三人の眼前まで迫って来て、地面にぶつかると思った瞬間、吸い込まれるように、消えた。
「……っ!?……!!」
董也は声を出せないまま、ただ彼女が消えた地面を見つめていた。
「……仕込みじゃないな」
清鈴が静かに言う。董也が彼を凝視する。今の光景を作り物と言えないことは、直に見た皆が分かった。
董也も、今のモノが見たことがないから無いと、宣言していたモノだと、そう認めざるを得ない。見てしまったのだ。もう否定出来ない。
幽霊。自殺者。死して生者の世界にいるモノ。自分が否定した存在が、今まさに眼前に現れた。その現実と、その事実に対する恐怖、混乱、そして同時に、董也はなおも納得はしきれていなかった。
「そんなはずは……」
なおも言い続ける董也に、清鈴は呆れた顔で溜め息をつく。
「いや、現実に見ただろうが」
「会長の調べた通りじゃない?自殺した女子生徒」
織麻も言う。だが董也は緩く首を振る。
「いやだから、そんなはずないんだって……。言っただろうが、調査不足だって」
清鈴と織麻、二人が目を見開く。
「自殺した女は首を吊ったんだ。飛び降りじゃない……っ」
「え」
男女が同時に言った。その、瞬間だった。三人の足元から、何かが出た。
「…………っ!?」
先程制服姿の女が吸い込まれた地面から。今度は何かが溢れ出て来た。それを視認することは出来ない。凄まじい圧で、何か煙のような、風のような、ガスのような何かが迫って来た。
「来たっ!」
「やっぱりじゃん」
「え」
清鈴は意気込み、織麻は面白がるようで、董也は戸惑った。
次の瞬間、溢れて来たそれを囲うように、今度は地面から蔓が伸びて来た。棘のついた太い蔓がたわんで、風圧をそのまま包み込んだ。
更に訳の分からない光景に、董也は目を剥く。
「やれそうか?」
「分かんない。結構強い」
混乱しきりの董也に対し、清鈴と織麻は妙に冷静である。そんな二人を驚愕の表情で見る。すると、球形になった蔓の一部が剥がれた。内から何かに押し出されているようだった。
「あら、思ったより強い」
「面倒だな……」
「おい…………」
なおも冷静な様子の二人に、董也はたまりかねて声をかける。二人はどこまでも平静な顔で、同級生を見てきた。
「あんた、ここを離れてろ」
「は」
「ごめんねー、会長」
織麻が笑いながら詫びた次の瞬間、董也の胴体に何かが絡んだ。見ると、彼の足元から生える蔓だった。棘もない細いそれは、見た目に似つかわしくない奇妙な力強さで董也を抱き込み、そして、浮かせた。
「お……」
何事も言えないまま、董也はその外力に従うまま身体を投げ出させた。瞬時に飛ばされ、その思いもよらぬ干渉を受け入れきれないまま、何とか残る冷静さで同級生二人を見た。だが、その姿は見えなかった。そこに至るまでの視界に、濁った幕が張られいたから。よく見るとそれは、水だった。噴水が湧き上がった瞬間に現れるものと似た水の壁がそこにあった。だが当然そこには噴水器も散水資材もない。完全に物理法則を無視した形で、水の壁が四方を囲み、二人と謎の現象を覆い隠していた。
「……」
束川董也は呆然として、眼前の非現実的な光景を見つめる。事実を咀嚼しきれないまま、慎重な彼にしては珍しく、無防備に自身の手を水の膜に伸ばした。触れた感触は確かに水。冷感と濡れた感触が指先から伝わる。しかし、妙に固い。本来ならすぐに通過できるはずの水面に奇妙な弾性があり、董也の指の圧力を拒む。今まで感じたことのない感触に驚き、思わず手を離す。
訳が分からなかった。今まさに目の前で起こっている全て。飛び降りて消える少女。地面から浮き上がる黒い何か。それにさほど驚きもしない同級生達。……董也は、あの二人のことを、少なくとも野茨織麻のことはよく知っているつもりだった。なのに、今見た二人の様相は彼の知見にはないものだった。何者だ、あの二人は。先程起きた現象と何か関係があるのか。伸びた蔓。眼前に聳える水の壁。
視線を上げると、ゆうに人三人分の高さある。越えられないし、くぐれないし、通ることも出来ない。この壁の中で、何が起こっているのか分からない。あの二人は、何をしようとしている。
不可解な出来事に、それに対して理解も解決も出来ない状況。混乱と共に、彼が本来持つ使命感や責任感から、無力感が湧き出す。何か尋常ならざることが起きているのに、自分は何も出来ない。そう思って拳を握ると、ふと、湿った感触があった。指先に、先程触れた水壁の雫があった。
「水……」
それはどう見ても感じても、ただの水だった。指先にはよくある濡れた冷たい感触。非日常な状況の中での、ひどく日常的な感覚。それが、束川董也にある種の冷静さを取り戻させた。
そうだ、理解不能な状況ではあるが、自身に緊急性の高い状況ではない。そして、この事態に対して、あの二人が何かしら対処しようとしていることは分かる。ならば。再び拳を握る。
長月第七高校の生徒らの長は、制服のポケットから携帯電話を取り出した。
水壁の中。
上屋清鈴と野茨織麻は、眼前の怪異に向き合っていた。地面から湧き上がり続ける禍々しい気流。二人には、それを構成する因子の一つ一つが見えていた。
「何か色々いるね────…」
「ああ。小妖魔どもの寄せ集めだ」
気流の中には色々いた。吊り上がった目で睨んでくるモノ、歯を剥いて笑うモノ、爪を剥き出しにして威嚇してくるモノ。どれも小さな異形の動物にようだ。
「どれも大した邪気もない小物だな。だが……」
「………大きいね」
目の前の怪異は、構成している一つ一つの要素は小さいが、それらが集まって、二人を見下ろすほどに大きい。家を逆立てた小動物のように、気を禍々しく燃え立たせている。
「………繋ぎはあれだな」
燃え立つ邪気の中に、一人の少女が認められた。地面に立ち尽くし、俯いている。先程屋上から飛び降りた少女だと分かる。制服姿の細い身体で、肩までの髪の毛。一見すると平凡な少女。だが、その身体のあちこちから禍々しい邪気の妖を生やしている。逆立つ邪気の根本を辿れば、彼女がいる。始まりは彼女。根源は彼女だ。
「小物どもを纏めちまったんだな。ここまでデカくなると厄介だぜ」
「……やっぱり自殺した娘なのかなぁ」
織麻が言うと、清鈴は首を捻る。
「会長殿の調査が正しければ、別口かもな。何にせよ、屋上から飛び降りて死んだ。……これだけの邪気を引くほどの悪心を抱いてな」
「……」
「マイナスはマイナスを引く」
膨れ上がった邪気を睨んで言う。
「しかも落ちた場所も悪い」
「え?」
「学校の中央から見た場合の、鬼門だ」
そう言われて織麻は目を丸くし、思わず周囲を見渡す。そして気付く。今怪異が現れる場所。恐らく彼女が飛び降りた場所は、三つ並んだ校舎の真ん中の棟で、極めて中央に近いがそのやや左寄り。そこから前にせり出して北、つまりは東と北の合間、北東、鬼門。────古来から、悪いモノが出入りする場所と言われる。
「おまけに“角”だ。校舎と廊下の交差する角地。……校舎の影になって陽も当たらず、人通りもなく目にもつかない。……ああいう場所は溜まる」
「……」
確かに、校舎の中央近くから真下に行けば、そこは三校舎の中央を貫く渡り廊下と、中央校舎が交わって出来る“角”。南側に高い校舎が建って陽を妨げ、常に影があるそこは、人通りもない。見られることもない。
校内に数多ある見える死角の一つだ。人々の意識の外の空間に彼女は居続け、邪を取り込み続けた。
「元から学校みたいな大勢の人間が集まる場所には色んな念が渦巻いてる。ここはその溜まり場でだ。こんな所で邪念を持って死んだら、この有り様だも納得だ」
「………ひどいね」
元はただの少女だったはずのモノの変貌ぶりを嘆く。
「ここまでになる邪念って何?」
「さあな。恨みや嘆きか……自殺者は恨んで化けないって、会長殿の推測は大外れかも」
「そうかなぁ……」
野茨織麻は、今もまだその推測には違和感があった。自ら死にに行く人間は潔い。そういう人間は、現世に恨みなど残さない、織麻はそんな生徒会長の推測に、不思議な納得を感じていたのだ。彼女は再び、変貌した少女を見る。すると、彼女と、目が合った。
「!!」
その場に、女の絶叫がこだました。俯いていた少女は弾かれたように首を振り上げ、凄まじい形相で、天に向かって咆哮を上げた。それと同時に、彼女から噴く邪気が一気に大きくなった。
「きゃっ……!」
邪気の塊が二人に向かって来る。それを二人は避けるが、避けた後の地面には、大きな邪気溜まり。それを見て清鈴は舌打ちする。
「弱い奴らも、寄り集まるとここまでかよ……っ」
呻きながら、更に向かって来る邪気に対して指を向ける。その指先に、水の球が生まれる。それは鋭い速さで飛び、邪気の塊にぶつかる。その瞬間、邪気が霧散した。
更に織麻も手を振る。それ合わせて地面から緑の芽が出て、一気に伸び、一本の蔓となって空を舞った。その一閃で、邪気は裂けた。
大きかった邪気は小さくなる。だが。
「なっ……」
それと同時に、また大きな咆哮が響いた。一段と大きく鋭い絶叫。それが発生する少女の口は限界まで開かれ、口角が引き裂けているようだった。その形相と身に纏っている平凡な制服がひどくちぐはぐで、その差異がかえって不気味だった。そしてその制服を纏った身体から、また異形のモノ達が湧き出て来る。
「………っ!?」
二人は目を剥く。
「まだあんなに……?」
一度縮んだ邪気がまた膨れ上がり、先程より大きくなった。それ合わせて異形の禍々しさも増し、妖魔の避けた口からは嘲笑うような笑い声が聞こえた。
「ありゃ、繋ぎというより、もう巣穴だな。どんだけ溜め込んでんだ……」
清鈴が呆れるように、恐れるように言う。織麻の目にもそう見えた。あの細身の少女から、どんどん異形の化け物が湧き出て、それが少女を中心にして纏まって、大きくなって脅威を増す。
「気持ち悪い……」
「だな。化け物どもが更に醜くなってる」
清鈴が嫌悪を込めて吐き捨てる。だが織麻は少し複雑な顔をした。
「そうだけど……。それだけじゃなく」
言い淀む織麻に、清鈴は怪訝な顔をするが、そこにまた邪気が襲う。圧力が先程より強い。
清鈴は水珠を出し、織麻も蔓を踊らせて、邪気を払うが、先程よりも効果が薄いのが分かる。まだ巨大な邪気の圧が、二人の迫る。
「面倒くせぇ……」
その攻撃を避けながら、清鈴が苛立たしげに舌打ちする。元は弱い妖魔らだというのに、寄り集まるとこうも厄介かと。清鈴は妖魔の発生源となっている少女を睨む。
「あれをどうにかしねえと。キリがない」
あの少女の亡霊が元凶だ。あれから湧き立ち、混ざって強くなっている。あれさえ無ければ、恐らく元の弱い小さい妖邪に戻る。それだけならばすぐに対処できる。
織麻も頷く。彼女も邪の中心となっている少女を見る。濃密な邪気の中にあって、その姿はもう朧げだが、間違いなく自分と同年代の少女だ。細い身体で、制服姿で、どこにでもいそうな女の子。そこに多くの弱く小さいモノが溜まって、奇怪な脅威となる。
「……」
織麻は、そうなったモノというより、そうなる事実がどうにも不気味に感じられた。
うろに溜まるような集団性。寄り集まって、個々の境目がわからなくなったような歪な密着。その上で肥大化する邪念。─────気持ちが悪い。
何だかそれは、彼女の本来の人間像とあまりにかけ離れているように感じた。やはり、どうも織麻には、董也の言葉が強く印象に残っていた。
“自殺者は恨まない”
苦悩も悲嘆も全て自身の身の内に抱いて、一人孤独に逝った少女の、行く末があれなのか。うじゃうじゃと集まった小物達。その中心にいる。
何かが、おかしい。しっくり来ないというか、噛み合わないような。ふと気付く。
「……ああ、あの子は違うんだ」
「は?」
次々来る攻撃を避けながら、ぽつりと言った織麻を清鈴が睨む。
「自殺した子じゃない」
「……」
清鈴は目を見開いた。彼も気付いたらしい。
そうだ、あの少女は話していた自殺者ではない。彼女は、恐らく誰も来ない場所で、一人首を吊った。徹頭徹尾、ひとりだったのだ。
あの娘は真ん中で────こんな人の行き交う大道で死んだ。
そして今も、多くに取り巻かれている。
あれは違う。
その瞬間、緊迫した状況のそぐわない間の抜けた電子音が聞こえた。
その正体をすぐに見抜いた織麻が、女子高生の習性としてポケットに手を入れ、自身のスマートフォンを取り出す。
おい、と清鈴は咎めるが、織麻は瞬時に画面を読み取って、少し目を見開く。
「………会長からだ」
清鈴も目を見開いた。
状況を半端ながら把握した束川董也は、とりあえず距離を取った。危険からは身を離すべしと、どんな状況であれ共通するだろう鉄則に従う。
渡り廊下の影に隠れ、状況を確認しつつスマホを取り出す。
不可解な状況。理解不能で対処不能。だが、そんな中でも自分にできることは。そう考えた末に辿り着いた答えが、“調査”。情報の収集と整理だった。
どうにも気になるのだ。あの屋上から飛び降りた女子生徒の幽霊───と、もう認めるしかないモノ。自殺した女生徒の霊と噂されていて、しかしそれには迎合できない。自身の事前調査によれば、自殺した生徒は首吊り自殺。あの飛び降りた女とは別物だろう。ならばあれは。別の自殺者か。……そうも思えない。どんな理由で命を絶ったにせよ、自ら死にに行く者が、ああも浅ましいだろうか。死を決意して飛んで、せっかく落ちて死んだのに、なのにまた戻って落ちることを繰り返す。その鬱陶しい反復行動には、“死”という結果が本当に欲しいのかと疑いたくなるいじましさがあった。
そもそもあの屋上でゆらゆらと揺れる、落ちるか落ちまいか躊躇うような、その逡巡を見せつけるような、わざとらしい、押し付けがましい、あのどっちつかずの動き。あれを見て一瞬抱いた苛立ち。覚えのあるあの感情。そうだあれは。よく抱く、辛い辛いと口では言いながら、現状を変える努力を一切しない、自身の前で突っ伏して、その隙間からちらちらこちらを覗いて来る相談者を前にした時のものと同じものだった。
束川董也は基本的には論理的な人間だが、この時だけは自身の直感を信じた。そして、その直感に根拠を添えようとした。恐らくはその結果が、あの亡霊の正体だ。
董也はポケットからスマートフォンを取り出す。そして登録してあった連絡先に電話をかける。
『────はい』
数コールで相手は出た。
「夜分にすみません。泰地先生」
礼儀としてまず詫びを入れる。
『いえいえ。どうしたの?』
相手は朗らかだ。泰地暁教諭。この長月第七高校の化学教師だ。まだ三十代前半の若手教師は穏やかで優しく、生徒らに親しまれている。こうして個人的に連絡先を交換するほどだ。
束川董也もこの話をしやすく、更に事情を把握してそうな彼ならばと連絡を取ったのだ。
「ちょっと聞きたいことが……。最近学校で流れてる噂なんですけど」
『ああ、幽霊が出るってやつでしょう。定期的に出るよねぇ、そういう噂』
教員としてそれなりに経験がある彼には、そういう眉唾の噂は慣れっこのようだ。
「……」
董也も何事も見なければ、ただの噂と吐き捨てた。或いは誰ぞの演出だと。だが、今はそうは言えない。
「………マジっぽいんですよ」
『え』
深刻な調子の董也の声に泰地教諭は一瞬静止したようだった。理性的な束川董也の口から出る言葉とは思えなかったのだろうが、だからこそ嘘ではないとすぐに確信したのだろう。
『……………本当?』
その疑問に董也は頷いた。電話越しに頷いても相手には分からないというのに、そんな反応をしてしまう程度には董也も冷静ではなかった。だが相手にしてみればただの沈黙でしかなかったその反応に、生徒をよく知る泰地教諭は真実を確信したようだった。
『見たの?』
「ええ……。けど変なんですよ。噂通り女子生徒なんですが、屋上から飛び降りたんです」
『……うん?』
董也の言葉に電話の向こうで相手が眉を寄せる気配がする。言葉の意味が分からないのだろう。
董也は相手に、自殺者の霊が出ると噂が出てから、自分なりに調べていたこと、過去に確かに自殺者はいたが、飛び降り自殺ではなかったことを語った。
『そうそう。確か、自分の家で首を吊ったんだ』
「知ってましたか……」
知っているだろう。事件があったのは彼が教職が就く前のはずだが、彼はこの校舎が長月第七高校となる前からここにいるのだ。
……そうだ。憐れな自殺者が逝ったのは、学校ですらなかった。だが実際にこの校舎の屋上には、執拗に死を繰り返す少女がいる。あれは、結局何なのだ。この教師なら知っているかもしれない。
「その自殺以外、何かなかったですか。生徒の誰かが屋上から転落した……自殺じゃないかも」
自身の直感と経験を信じて問うが、董也の緊迫感に反して、電話の向こうの若い教師は意外な答えを返してくる。
『ああ、あったよ』
「…………」
驚くほどあっさり返された。
「あったんですか!?」
勇んで問いただすと、うん、と相手はまたあっさり返してくる。
『逆に君の調査には引っ掛からなかった?』
「自殺者しか調べなかったので……」
『そう。その自殺に絡む話なんだけどね』
董也が眉を歪める。
『あんまり外聞の良い話じゃないから、事故ってことで記録には残したのかな』
「直近で自殺者出してる時点で、外聞も何も」
『まあそうなんだけど。その件は学校にとって、更なる恥の上塗りだったから。……それ以外の人間にとっては、案外愉快な話かもしれないけど』
「………何があったんです?」
人死にがえらく軽く扱われている気配に鼻白む。電話の向こうで溜め息が聞こえる。
『嘆いて沈めばいいのか、呆れて笑えばいいのか分からない話。……屋上から落ちて死んだ子は、自殺した子を殺した子」
董也の眦が吊り上がった。
『いじめの主犯格だった女子生徒だよ』
その事件は、言ってしまえばありきたりないじめ事件だった。あるクラスの女子生徒がクラスメイト数人から執拗な嫌がらせを受けた。揶揄われるとか仲間外れにされるとか、所持品を隠されるとか壊されるとか、段々エスカレートして密室に閉じ込められ、小突かれ、水をかけられ、挙げ句万引きを強要されそうになり。ひどい話だが、妙なことにそれらが明らかになったのは取り返しにつかない事態になってから。いじめられていた当人が自死し、自らが受けた所業をきっちり遺書に書き残して逝ってからだ。
これもまたありきたりな話で、悪質性の高い行為に死亡生徒の親も他の保護者も警察もマスコミも関係ない一般人も一気に騒ぎ出し、その追求に対し、当事者らも学校関係者も、そこまで深刻な事態だと認識していなかったと言い訳するのもまた、よくある話だった。よくあるその言い訳は、しかし事態をより悪化させ、騒ぎはどんどん大きくなった。
その騒音の矛先は、学校、教師、そして当然ながら、虐めの当事者達だった。集団になって一人の弱者を虐げていた少女達は、今度は虐げられる側に回った。死んだ生徒の親に、親族に、周りの生徒に、教師に、教育委員会に、マスコミに、全く関係ない第三者に責められ、無視され、笑われ、晒され、彼女らの家族も含めて生活は滅茶苦茶になった。それもよくある話だった。被害者や学校、関係者が与えた正当な罰以外にこそ痛めつけられる。当時は既にネット社会で、個人情報は容易に漏れ出た。もはや道を歩くことさえ困難になった彼女らはどんどん追い詰められ、その内の一人の母親が良心の呵責と世間からの非難に耐えられずに自殺未遂を起こすなど、もはや混乱の極みだった。
そうなるとどうなるかというと、内輪揉めが起こる。ついこの前まで徒党を組んで一人を虐げていた集団が、お互いに責任をなすりつけ合い、いがみ合った。いや正確に言うと、一部が纏まり、一部を離反した。要は、主犯格の一人を、それ以外で責めたのである。
だんだん話が見えてきた、と束川董也は眉を寄せた。
「いじめっ子がいじめられっ子に」
『まあ、よくあることだね』
呆れ笑いのような声が、電話の向こうで聞こえる。
『で、ある時ブチ切れた。授業中コソコソされて耐えられずに、奇声あげながら教室飛び出して、屋上に駆け上がったの』
電話の向こうの男性教師も、笑っているのか呆れているのか分からない声音である。実際、その後の彼女の行動はどう評価していいか分からない。屋上に行って、勢いのまま柵の向こうに渡り、追いかけて来た生徒、教師に向かって死んでやると叫んだ。そして、そのまま落ちて死んだのだ。
「…………自殺?」
『どうかな。その場にいた訳じゃないから。……ただねえ、君も分かるだろ。死にたい人間は騒がない」
「ですね」
そうだ。本当に死ぬ気のある人間は、死んでやると人前では言わない。奇声を上げて注目を引くようなことはしない。
「………“自殺未遂に失敗した”って奴ですか」
『正確に言うと、狂言自殺に失敗した、かな?………実態は今となっては分からないけど、まあ学校は事故ってことにしたんだろうね』
だから、董也の調査には引っ掛からなかった。彼は溜め息をついた。
「………そいつ、化けて出てるみたいなんですけど」
『おやおや』
電話の向こうの教師は笑っている。まあ分かる。生徒に死について笑うのは不謹慎だが、その点においてはもう笑うしかない。
自分の考えは間違っていなかったと董也は溜め息をつく。やはり自ら死にに行く人間は恨みを残して現世にしがみついたりしない。この世にしがみつくのは死にたくなかった奴。それなのに、死なされた奴だ。恨む理由は分かる。不慮の死は誰でも恨めしい。………だが今回に限っては、完全に逆恨みだ。
董也は教師に礼を言って電話を切る。そしてスマホ画面に文字を打ち込み始める。その文の送り先は野茨織麻。転校生の連絡先は知らない。
「……」
先程まで共にいた同級生らの顔を思い浮かべる。彼らの正体は知れないが、あの厄介な怪異に立ち向かおうとしているのは分かる。この行動が彼らの力になるかは分からないが、董也に出来るのはこれだけだ。
……これだけなのだが。
董也はふいに立ち上がって、相変わらず自分を締め出す水の膜を見やって、それを避けて校内に戻る。
その行動により何が出来るかは分からない。だが、何かやらずにはおれないのが彼だった。階段を駆け昇る。
彼女はずっと煩悶していた。あれ以来、周囲から訳の分からない悲鳴や嗚咽を聞かされて、その中心に自らがいる意味が掴めずにいた。
どうして自分はこうなっているのだろう。大勢の声に、視線に責められて、こんな辛い思いをしなければならないのだろうと。
ついこの前まで、彼女は本当に普通の少女だったのだ。親に愛され、友に恵まれ。どこにでもいる、ごく普通の。
普通でなかったのは、むしろあっちだったはずだ。教室内の華やぎにも騒々しさにも馴染まず、いつも一人で窓の外を見ていた女子生徒。彼女は他と違った。その違いが周囲に何か実害をもたらした訳ではなかったが、しかし、ただ何となく、気に障ったのだ。
最初は少し揶揄うだけ。だがそれに相手が何の反応も返して来ないと腹が立って、余計に揶揄ったり悪態をついたり、いつしか小突いたり椅子から引き摺り下ろすようなことをしても何も言わなかった。しかし、そうやって反応が返って来ないからこそ、ずぶずぶと入り込むように行動は激化した。だがそれにも何も返って来ない。行動は進む。その繰り返し。
そうなって来ると、その行為自体も特異でなくなる。まるで朝起きてから顔を洗うように、当然のように、あの娘を揶揄っていると、─────突然、結局何も言わず何もしないまま、あの娘は死んだ。その死に至る苦しみをわざわざ文書に書き残して。彼女達がしたあらゆる行為が苦しかったと。
その瞬間、世界の全てが敵になった。普通だったはずのは彼女は、途端に悪い子になった。
そのことに彼女は混乱した。何で。どうして。どうして皆責めてくるのだ。先生が怒る。あの娘の親には泣かれた。自分の親も泣いて、あの娘の親に詫びて、学校にも謝って、騒ぎ立てるメディアにも頭を下げて、挙げ句勤め先に迷惑がかかるからと辞めて、家に籠る生活を始めた。家の中では両親がお互いを罵り合って、娘がこんな人間に育ったのはお前のせいだとお互いに言い合っていた。
……─────こんな人間?自分は、親にとってどんな人間に育ったというのか。親の思う子供にはならなかったのか。でもずっと、親の言いつけは守って来た。遅くまで外にいちゃ駄目だとか、電気をつけっぱなしにしちゃ駄目だとか。そうやって教えられたことはやっていない。それなのに、親は我が子が良い子じゃないと言う。私の育て方が悪かった、死んでお詫びすると、勝手に死んだ。何とか命を取り留めた友達の母親は、長く入院することになって、どうしてこんなことになったのと、友達は泣きながら電話してきた。
…………………分からない。どうしてこんなことに。こんなことになるなんて、誰も教えてくれなかった。自分はただ、普通に過ごしていただけなのに。
何だか怒りが湧いて、何ヶ月かぶりに学校に行った。どこかやけくそで、投げやりだった。責めたければ責めろと、開き直りにも似たような心境で席に座って、しかし何も言ってこられなくて、ただ湿った視線が絡んで、囁く声だけだけが耳に届く。
鬱陶しい。どうしてこんな風に責められるのだ。何で今更。
今更。
彼らはずっと、この教室で行われていたことを、彼女らがしたことをずっと見ていたくせに、何も言わなかった。なのに今更になって。何故。
怒りが湧き、悲しみが湧いて、彼女は立ち上がって、叫びながら階段を駆け上がった。屋上の柵をまたいで、死んでやると叫んだ。私が死ねば満足なんだろう。なら死んでやると。何もかも私が悪いんだろうと。
ひとしきり叫んだ後で、漂ったのは、沈黙。
柵に乗りかかった彼女と、それを茫洋と見ているだけのクラスメイト達。
見ているだけの。
それを認めた瞬間、彼女の中の何かが冷えた。
高所での強い風吹き荒ぶ中で、彼女の足は震えた。不安定だった姿勢が、ぐらりと揺れた。
あ、と思ったのは一瞬で、その時初めて、観衆の口から声が漏れた。悲鳴、驚愕。本当に、誰も彼も、何かが起こってからじゃないと何も言わないししない。
…………どうして。彼女は地面い倒れ伏して、まだかろうじてある吐息の中で、地面に広がる血を見ながら自問し続けた。
何で、こんなことに。死にたくなったのに。死なせるつもりじゃなかったのに。誰も死ぬはずじゃなかったのに。何で、どうして、あの娘は、私は死ぬの。
どうして。
涙が伝って、地面に染みた。そこから、彼女の血と涙が染みた大地から何かが湧き上がってきた。小さな手、赤い舌、いやらしい触手。それらが彼女の身に入り込んで、彼女の混乱と悲しみと無念を食い荒らした。そしていつしかその魂を苗床にして、一つに大きな悪意になる。混乱と不安、嘆きと怒りは妖邪の好む人間の思念。暗い感情ほど、共感し合うものだ。………他者への攻撃性、蔑視、嫌悪。そして無関心も。彼女はいつも、そうした人間の中心にいた。そして、今もそうなのだ。
「………」
「……………」
野茨織麻、上屋清鈴の両名は、今しがた生徒会長から送られてきた情報と、眼前の事実を組み合わせて、状況を察した。
「……自殺じゃなかったね───」
どこか空寒い口調の織麻に、清鈴は深く溜め息をつく。
「自殺より馬鹿馬鹿しい……」
「……」
「……あの生徒会長殿の言葉は、結局いちいち正しかった訳だ」
束川董也の言葉を一つ一つ思い出す。
自殺者は恨まない。死んでこの世に残らない。自ら死んで、死を受け入れらえる者は愚かだが潔い。周囲を恨んでこの世に留まるのは、自分がそうされることに不満がある者だ。自分はあんな風に死ぬべき人間ではなかったと。どうして死んだのか、誰のせいで死んだのか、ぐずぐずと悩み恨み続けて、その負の感情で多くの邪を呼んだ。その内に、自らが邪になって、醜くおどろおどろしく、おぞましい姿になった。
「るつぼになって、くっついて膨れ上がって、他人を攻撃する。……まんまだね」
あの歪さ、気色悪さ、あれは恐らく、生前の彼女そのままだ。
清鈴が溜め息をつく。
「最後にはその報いが返って来るところもな」
黒い塊がまた迫って来る。二人はそれを避けて、高く跳び上がる。そして、その黒い邪妖を見下ろせる位置に上がる。
「……──────馬鹿は死んでも治らない」
冷たく言い捨てる。
織麻は憐れむように黒い塊を見ていた。
「元は普通の娘だったんでしょうに」
その呟きに、清鈴は織麻を凝視する。
織麻らが先程生徒会長から受け取った“彼女”の情報によれば、基本的には目立つ部分がない、家族関係、学校関係も問題なかった、ごく普通の女子生徒だった。
育ちにも問題なく、普通に両親に教育され、友人とも良い関係を築いてきた。
それが崩れたのはたった一つの過ち。それが致命的であったことと、何よりそれが致命的だと最後まで……というか、今に至っても分からなかったことだ。
自分の行動が、どんな風に人に影響を与え、どんな結果をもたらすか考えられない。
決して悪人でも、残酷な訳でもない。……ただ幼稚で、どうしようもなく馬鹿なのだ。
「一番タチ悪いだろ」
「だね……。今もなのかな」
また黒い塊を見る。
「まだ意識あるのかな。……今自分がどうなってて、何してるか分かってる?」
感情と衝動のまま邪気を膨らませて、暴れて他人を傷つけようとしている。自分の有り様を自覚しているか。
清鈴は舌打ちする。
「分かってないだろうし、分かったところで止めないし、止めようもない。……あそこまでになっちゃ」
苦い顔で視線を向ける。黒い塊りは更に大きくなった。そして高くにいる二人に迫って来る。より速く、より凶暴に。水と蔓で応戦するが、次々に湧いて出て来る。どれだけ凶暴化しても一撃一撃、対抗できないほど強くないのだが、とかく大きく再生が早いのできりがない。
それを見やって、織麻が言う。
「何にしてもやっぱり、あの娘をどうにかしないとね」
自主的に引かないなら、力ずくでも。織麻が清鈴に言う。
「“水牢”を作ってくれる?あの中に押し入んで」
清鈴が眉を寄せる。
「私、中に入るわ」
清鈴が更に顔を歪める。
「安全は保証できねえぞ」
「けどこのままじゃ埒があかないもの。ちょっと思い切った方向で行こう」
どこまでも穏やかな顔をしながら大胆なことを言う織麻に、清鈴は顔を顰めた後で、どこか諦めたように溜め息ついて、彼は両掌に水球を作り、それを細く引き延ばす。
それは、この現場を覆い、束川董也を拒んだものと同種だったが、それよりも更に小さく、その分幕がやや分厚い。それきれいな球体になって織麻の身体を覆う。
「内側の酸素がなくなるまでそう時間はないからな」
「分かった」
織麻は身構える。
「すぐ決めるよ」
そう宣言して、彼女はそこを飛び出した。文字通り、急速で場を離れ、黒く膨れ上がった邪気の中に突っ込んで行く。その瞬間、黒塊は霧散する。水に含まれた霊力が邪気を祓っているのだ。だが、祓われた先から邪気は膨れて、織麻を包む水球を巻き込んで行く。真っ黒な邪気に中に潜り込んで、徐々に姿を失って行く少女を見て、清鈴の胸中に焦燥が湧くが、しかしこういう土壇場で妙な力を発揮するのが彼女だ。
……そして、思い切りのいい行動に行こうとする彼女は、言い出したら聞かない。
「…………決めろよ」
信じながら、祈りながら、上屋清鈴は呟いた。
野茨織麻は、水の膜に包まれながら、黒い邪気の最中を突き進んでいた。邪気を押し広げるように進んでいたが、徐々に邪気が近くなっている。じわじわと、霊気を含んだ水膜を侵食している。
弾いても叩き付けても迫って来る。密度は大したことはないのに、この圧倒的な質量。数の力というのは恐ろしい。……これを発生させているのは、たった一人の少女だというのに。
じりじり脅威に取り巻かれているのを感じながら、織麻は前だけを見る。この肥大した悪意の足元。自身から黒い邪気を生やして、燃える最中に徐々に大きくなって、その先はもう自身で収めること叶わなくなった。非力な、ちっぽけ、ただの少女だ。
「………ねえっ!」
迫る最中、織麻は声を張り上げる。
「あなた、名前は?覚えてる?」
もはや意思や記憶があるかも分からない怨霊に声をかける。相手は答えない。織麻はそれでも語りかけ続ける。
「じゃあ、いじめた娘の名前は?どんな顔してた?」
答えない。
「……悲惨だね。名前も顔も覚えてない人間のために、こんなことになって」
少女は答えなかった。
「どうでもいい相手だってんでしょう。いじめたって言っても大した理由じゃない。ちょっと気に入らない程度?それで皆と一緒になって揶揄って、どれだけやってもそれぐらいのつもりだったんだよね。だから罪悪感もなくて、最悪の結果になっても自分が悪いと思えなかったのよね。そんなつもりでなければ、現実の行動がどうでもどこまでもそんなつもりじゃないもの」
少女が邪気の中で静かに漂っている。
「今更貴方に罪悪感持てなんて言わないよ。貴方は何も深く考えられない人だから、きっと今でも悪いことしたなんて思ってないんでしょ。……他人に対しては」
少女は何も言わない。ただ彼女から発生する邪気だけが、薄い水の膜を徐々に侵食して、織麻に迫っていた。
「自分のことは?……今の自分のことも分からない?」
織麻は畳みかける。
「馬鹿みたいだと思わないの?どうでもいい人間のために人生を壊して。……ろくな生き方もろくな死に方もせず、死んだ後もこの有り様」
水の膜が、極限まで薄くなっている。黒い塊が、赤い髪に絡み付こうとしていた。
「貴方の人生、何のためにあったの?何のために生きてた?何のために生まれて来たの?」
水の膜が弾けた。
だがなだれ込んでくると思っていた邪気は、その瞬間に霧散した。
大きく分厚く膨れ上がっていたが、散ればそれぞれはちっぽけな存在だ。織麻が瞬時に蔓を振り回すと、すぐに切り裂かれた。
「やったか?」
清鈴が寄って来た。大元を打てたかと問うが、織麻は答えないまま視線を彷徨わせた。
「……その前に自分でいなくなった」
「あ?」
清鈴が目を丸くする。邪妖らをつないでいた根本を叩いて、巨大化した低級邪物らを霧散させたのか思ったが、そうではないという。
あの少女は自ら引いた。
「かろうじて意識があったのかな」
自身の言葉に応えたのではないかと織麻は言うが、清鈴は渋面だ。
「だからって、急に改心でもしたって言うのか」
あそこまで拗らせておいて、と疑問を呈するが、それに対して織麻は悪戯っぽく笑って肩をすくめた。
「単にブチ切れちゃっただけかも……」
先程の織麻の発言を聞いていなかった清鈴は首を捻る。そして周囲を見渡す。そこここに、先程まであった巨塊の残滓が見える。小妖怪、低級霊。つなぎがなくなれば、本当にただの小物だ。清鈴は冷徹に水流で祓った。
「本丸は…いなくなった、てのは……」
「消えてはないよ。祓えてない。本当に、どこかに行った」
その言葉に、清鈴は顔を引き締める。
「どこだ。あれをちゃんとどうにかしないと。また繰り返すぞ」
「……」
焦る清鈴に対し、織麻は奇妙に平静だった。
彼女は静かに上を向く。
清鈴もそれに倣う。上向いた視線の先には、高々とある建造物、その頂点。暗い空を背景にした、鉄の柵の並び。
「あの娘の行くべき場所はあそこしかないよ。見てもらえるのは、あそこしかないもの」
確信があるようだった。清鈴も、不思議とそう思えた。
「ここは誰も来ない、誰も見ない行き止まりだもの。あの娘はこんなところにはいたくなかったはず。……だからこそ、何度もやり直してる」
ここに来る前の分かれ道。あの天頂こそが彼女にとっての選択の場だった。最後の最後に人生を賭けた。恐らく、一方的に。
彼女はまたそこにいた。風と無音だけがある、ぐらぐら揺れる足元と、その先にある遠い地面。そればかりの視界は、これで何度目だろう。もう思い出せない。
ぐらぐら、ゆらゆら。揺れるのは、身体か、頭の中か。記憶も意識も、何かも溢れ落ちそうだ。
どうして、こんなところにいるんだっけ。どうして、何度も、何度もここへ。
何もかも分からないまま揺らぎ続ける。この場所で一人。たった一人。誰もいない。誰も来ない。
─────ぎいい、と金属の軋む音がした。
彼女は、久しぶりに振り向いた。
「…────小林愛佳!」
束川董也が叫んだ。
屋上に駆け上がった彼は、ドアを開けた瞬間、行き合ったその怪異に対して、その名を叫んだ。先程教諭から授かった情報にあった死亡生徒の名。
小林愛佳、だったものは振り向いた。その姿は影のようで、表情は見えない。ただ、その陰影と髪の毛をゆらゆらと揺らしている。
その様を見て、董也は眉を寄せる。先程から見せるどっちつかず。行動の行き先を決め切れない、決めようとしない優柔不断。────苛立たしい。あれは、聞き飽きた、口だけの苦悩と同じ種類のものだ。
「────飛ばないのか?」
董也は低く言った。相手は、何も反応しない。反応しているのかもしれないが、見えない。こちらを向いたまま、しかし揺らぐのはやめてただ静止する。その様を見やって、董也は腕を組んだ。
「飛び降りないのかって。死にたいんだろうが。あと一歩前に行けば死ねるぞ」
挑発するように言っても、相手は微動だにしない。董也は溜め息をつく。
「うんざりなんだよなぁ……、お前みたいな奴。死にたい死にたい言いながらこっちをちらちら見て、死ぬな生きろって言われるのを待ってる奴。まあ立場上、言わなきゃしょうがないからそう言うが、……一度言ってみたかったんだ。お前には、言ってもいいだろ?」
死にたいならさっさと死ねと。そう言われた少女は、風の中ただ佇んでいる。
董也は鼻で笑った。
「こう言われたら死なねえんだろ。本当は死にたくなんかないんだもんな。お前は死ななきゃなんて思ってない。罪悪感も責任感も持っちゃないんだから。ただ周りに理不尽に責められて癇癪起こしてるだけ。恨みや嫌悪なんて上等なものじゃない。ただ拗ねて当たり散らしてるだけだ」
周囲の悪口雑言や白眼に耐えられずに、悲憤のあまりこの屋上に駆け上がったというが、彼女は本当に死ぬ気はなかった。ただ当てつけたかった。自分は周りのせいで死ぬほど苦しんでいると、だからこの死に対して責任を感じて、自分を止めろと、暗に訴えた。……結果は、沈黙。
やめろとも、生きろとも、死ねとさえ言われなかった。誰も何も言わず、ただ黙って佇んでいた。よく見ると、そこにいたのはクラスメイト全員でもなく、教師とかクラス委員、生徒会役員など、それが責務である人間だけだ。多くは、教室にいるまま。
「そんな有り様だってのに、何度もこの場面を繰り返してどうする。何度目かに、今度こそ誰かが止めてくれるとでも思ったのか?」
何度も繰り返せば、今度こそ。違う結果があるのではないかと。柵の内側に帰れるような、別の可能性。
「どこまでも人任せなんだな。他人の言動で自分の言動も決める。……いじめにしたって、周りの責任にしてるんだろ。誰かが止めてくれてればって。……確かにそうだ。皆知らん顔して、それが悪かった。けど、何でそうなったか分かるか?」
表情の見えない少女が、ほんの少し、反応したように見えた。
「どうでもよかったからだよ。お前もお前がやってることも。他の奴らには気にかける必要もないどうでもいい行為で、存在だった」
董也は、彼の人柄には珍しいほどの悪い笑みを浮かべて言う。挑発するように、嘲るように。
「お前はさ、悪いことしてるどころか、良いことしてる気分でもあっただろ。仲間内に娯楽を提供してやってる、クラスのはみ出し者を皆を代表して罰してやってるんだっていうくらいの気でいただろ。皆が喜んでくれてるって」
だからこそ、相手が死んで、全てが敵に回った状況が許せなかった。沈黙という同意のもと、彼女がクラスの厄介者を虐げる姿を密かに楽しんでいると、そう思っていた。だが、いざこれまで視線を向けていた少女がいなくなって、ゆっくり周囲を見渡してみると、……自分達を見ている者など、誰もいなかった。
「それが答えだ。お前が何をしようと、誰をいじめようと、死のうと、周りの奴は知ったこっちゃない。お前の行動もお前自身も、興味なんかない。自分達には関わりのない人間」
──────どうでもいい人間だったんだ。お前達は。
そう言い放つ。すると、目の前の影は、揺らめきでも翳りでもなく、明確に揺れた。そして、影になっていた顔がはっきり見える。
………どこにでもいる、普通の少女だった。彼女は、その顔を歪ませて、拗ねたような、いじけるような表情を浮かべて、唇を噛んで、顔を背けた。
そして、揺れることなく、真っ直ぐに、足を前に踏み出して、明確に、そちらがわに行った。自ら境界線を越えた。
そして、そのまま消えた。
束川董也は前に進んだ。彼女がいた位置に。
後に、野茨織麻と上屋清鈴もやって来た。三人、柵ににじり寄る。
下を覗くと、そこには何もなかった。小さく見える木や校舎だけがある。
織麻、清鈴は、そこに一切の怪異がないことを認めた。何度も落ちては鬼門を騒がせていた少女の怨霊は、完全に消えたようだった。
「……どうしたんだ」
先程までの荒れくれようを見ていた清鈴は不可解に呻いた。董也は溜め息をついた。
「終わったんだよ。……言ったろ、自殺者は恨まない」
そう言いながら、振り向いて柵から離れた。
「やっと自分で死んだんだ。自殺できたんだよ、あいつは」
静かに言って、彼は歩み去る。二人は、それに続いた。
織麻はまた、そこで振り向いた。そこにはやはり闇だけがあって、その暗さにはどうしてか引かれる。……あの娘も、そこに引き込まれたんだろうか。行き詰まった地べたではなく、広々した虚空に溶けることが出来たのか、やっと。
織麻は少しだけ笑った。そして虚空に背を向けて、風の中を去った。
校内の北東の日陰に、花と線香が供えられた。束川董也は、そこで手を合わせた。
「……そういう行動は、かえって霊を留めるぜ」
背後に、上屋清鈴、そして野茨織麻がいた。董也は彼らに向いた後で、また花の前で手を合わす。
「もう完全にいないんだろ」
「……ああ」
清鈴は周囲に視線を巡らせて答える。昨日はあれだけの騒乱があった場だが、今は静かなものだ。影らしく小さな邪妖が蠢いているが、無害なものだ。霊力を帯びる二人を見るとこそこそ逃げて行く。溜まれば威勢が良いくせにと呆れる。
「いないならいないで、無意味じゃない?」
織麻は語りかけるが、董也は涼しい顔だ。
「元からこんなのは自己満足だよ。死んでから花を見たって何にもならない」
小さな花束を足元に、そんなことを言う。
「誰かのために行動するなら生きている内にしないとな。……同情も労りも、死後に与えても何も救わない」
「……あの女の場合、生前であっても、何をしても無駄のように思えるけどな」
清鈴は侮蔑するように言う。あの女とは、今花を供えられている女。この場で怨霊となり、最後には空に散った愚かで憐れな女。
「最後まで理解不能だった。結局何がしたかったんだ」
「自分でも分かってなかったさ。ていうか、何もしたいことがないからこそ、ここでずっとグダ巻いてた」
そもそもいじめ自体、やることのない奴らの娯楽だと苦笑しつつ董也は言う。
「最後の最後まで、何がしたいか、何になれるか、何になりたいのか分からなかった。……あの女子、本当に普通の奴だったよ。成績も平均的なら、文化面、スポーツでも功績はない。家庭も普通。何の特異性もない。……個人を引き立てて証明するものが何もない奴だった」
普通の人間。裏を返せば、何も特徴のない平凡な人間だということだ。何者でもない。
「誰かを貶めて、無理矢理自分の立ち位置を上げて、大胆さや残虐さで集団の中で注目を集めても、結局は仮初だ。自分が何者でもないって現実は変わらない」
加虐というのは一種の承認行為だ。誰かに傷を与えることで相手に認識され、畏怖されることで自分が強くなったように錯覚できる。他人を下げることで自分を上げる行為はコンプレックスが強い人間がよくやることで、更にそれを集団でやることで団結と、そして集団内での力関係の指標にもなる。
「いじめでも何でも、悪さは集団で行われるもんだ。で、集団ってのは、大方似たような者同士で作られる。……この場合は同じ、取り柄のない、平凡な連中」
件の事件で加害者となった生徒らは、皆そんな評価だった。この一件以外、特に目立った悪点もない。外野から見れば、どうして彼女らがそんな大胆かつ悪質な事件を起こしたのか不思議にさえ思える。
董也には何となく掴めた。
「……つまんねえ奴らって、集団を保たせるのにも苦労すんだよ。共通の話題もないし、一緒になって打ち込むこともない。話す内容はすぐなくなって、同じ空間にいながら、各々でスマホの画面を覗き込んでいるような状況になる」
「そういう集団、結構見るけどね……」
最近多い気がする。同じ席で向かい合って座っているのに、視線はスマホ画面に向く。……何のために一緒にいるんだと聞きたくなるが、恐らく、他に行きようもないからそこにいるのだろう。
「だから無理矢理にでも皆で楽しめる内容を作るんだよ。ついでに、そこでの行為の過激さでもって、集団内の序列も決める」
行為をお互いに肯定し合った上で、より大胆で過激な行為をした者が集団の中でのイニシアティブを取るという認識が出来ると、上位を競って行動は更に加速し、時制の利かない段階まで進んでしまう。集団に属していないと自己を保てないのに、その集団の中で優位でありたいと願うのだから、人間の業は底知れない。
「救いようがねえな……」
「……何かおかしな話。他人を虐げるのに、その虐げる相手がいないと、立場や集団性を守れない訳?」
董也は肩をすくめた。
「だから、いじめの相手がいなくなったらすぐに瓦解したのさ。集団も周囲との関係も崩壊。そしてまざまざと思い知った。本来の自分の価値。集団内での地位も、弱者を虐げることで強制的に上げてた自分の価値も、全て幻だったってな」
本来の自分は、ただのつまらない人間だった。いじめという行為も含めて、丸ごと馬鹿にされていて、周囲には無価値な存在として捨て置かれていた。どうでもいい存在だと。
その現実に押し潰されつつある中で、あの屋上での狂言自殺はいわば最後の賭けだった。誰か一人でも自分を止めてくれたら、自分はまだ望まれている存在だと信じられた。だが止める者は誰もおらず、彼女は結局、自分が周りにとってどうでもいい存在なのだと自覚するしかなかった。自身を責めた社会を恨み、そしてその現実を受け入れたくないばかりに、何度もその絶望の場面を再現していた。
そして今、ようやく彼女は絶望を受け入れて、ちゃんと自殺したのだ。自身が生まれた価値はなかったのだと、その事実を刻みつけて。
上屋清鈴は溜め息をつく。
「馬鹿らしい……。そんなに自分の人生が嫌なら、他人を傷付ける前にさっさと死ねば良かったんだ」
「ここまで来ても、死んだ理由に相手が不在なのが凄いよね……。ていうか、その“絶望”って、相手の子も経験したことなのに、そこに共感することはないのかな」
「……そういう共感性や想像力があるなら、そもそも虐めはしてない」
理不尽に攻撃され、周囲に無視され、どうでもいいと見捨てられることは、そもそも最初に死んだ少女が経験したことだ。いじめっ子がいじめられっ子に逆転した現象は、まさにその経験の後追いだ。かつて自分が与えた痛みを自身で味わいながら、彼女は最後まで、相手に申し訳ないとは思わなかったのだ。
織麻の言葉には、董也も暗い顔をした。
「つっても、いわゆるサイコパスとかそういう上等なもんじゃない。……そこまで頭が働かないだけ。未熟なんだよ」
他人の心理や都合を慮る視野がない、自身の行動が他人にどんな影響をもたらすか想像する感性がない。行動には結果があり、結果には責任を取らねばならない。そんな当たり前のことさえ知らなかった。無知で愚かで、……幼い。どこまでも未熟で、子供なのだ。
「だからって行動が正当化される訳じゃない」
「それはそうだよ。どんな事情でもあいつのしたことは許されない。断罪されるべきだったし、今回のことは自業自得だ……」
そこは言い切る。だが、言葉尻はやや曖昧だった。彼は、足元の花を見る。その目元を窄めて、極めて複雑な、何とも言えない煩悶を浮かべた表情をする。
「………どうしてもな、憐れにも思っちまうよ。こいつなりに必死だったんだろうから」
「……」
確かに、必死ではあったんだろう。自分が何者であるか、何者になれるかを懸命に探し求めていた。それがどうしても分からなくて、とち狂った方法で何者かになろうとした。……そんな方法でしか自己を確認できず、そして何より、そのことに彼女自身が無自覚だったことが憐れというか、滑稽だった。彼女は自分が何かを欲していたことを 何かを成そうとしたかったことを、恐らく分かっていなかった。自身の行動や、その心理を自覚しないまま大きな責任が生じる事態を引き起こして、覚悟もないまま浴びせられた非難に耐えられず衝動で死んで、最後、ようやく自分の希求に気付いた時に、全てが取り返しがつかなくなっていた。
野茨織麻は複雑な笑みを浮かべた。
「何か、馬鹿とか幼いとかっていうより、そこが一番深刻かもね。……何にもなかった。からっぽだった」
その呟きに、董也も清鈴も小さく嘆息した。
あの大量の邪は、そこに入り込んだのかもしれない。彼女自身の邪念に引かれ、そのうろの中に巣食った。それであそこまで大きくなったのだから、その空虚の大きさは計り知れない。
「普通ってのが、一番怖いのかもね」
「……贅沢な話だよ」
織麻、そして董也が言い合う。その様を見て、清鈴は片眉を吊り上げる。
「凡庸であること自体は何の問題もないだろうが。……それに勝手に倦んで、かといって何もせず何も出来ず生み出さないまま、奪うばかりで、結局全て失ったのは自分の責任だ」
「ああ……」
清鈴の言葉に、董也は伏せていた目を上げる。
「何もかも自己責任だよ。何もかもこいつが悪い。……学ぶ機会はあったのに、最後まで何も学ばなかった」
そしてまた花を見る。
「けどさすがに今回は何かに気付いただろ。……もう、この先はないが」
─────もし今世の記憶を持って行けるなら、来世こそは、と。
そう言って、彼はその場を去ろうとした。
その背中を見ながら、織麻、そして清鈴は複雑な顔を見せる。
「………」
「ねえ、会長」
呼びかけられて、董也は振り返る。同級生二人が並んでいる。
「私らに何か聞きたいことないの?」
「……」
その言葉に、束川董也は目を丸くして、眉を寄せる。じっと、二人を見る。
いつもと変わらぬ制服姿で佇む、見慣れた、よく知っていると思っていた同級生。だが昨夜、彼女らは普段とはまるで違う姿を見せた。恐舞い飛ぶ水球と縦横無尽に踊る蔦は、恐らく彼らが発生させていた。そして怨霊と、得体の知れない何かに立ち向かっていた。それは普段の彼女らとも違っていたし、常人のそれでもなかった。
普通の人間ではない。その事実を、束川董也はその目で認めた。そこに恐怖や忌避はないのかと。一切そんな様子を見せず、常と変わらぬ会話をする董也を、織麻は不思議そうに見ていた。
彼は言う。
「ない」
「……豪胆だな」
清鈴は肩をすくめる。董也は彼を見据えて、挑むように言う。
「言っただろうが。俺は見たものしか信じない」
昨夜、彼らが常人でないことはよく分かった。この世には人外の怪異があり、彼らはそれに立ち向かい、そして打ち勝った。脅威の上を行く脅威。得体の知れない何かを越えた、得体の知れない何かだ。
と、同時に、彼らが自身には何の害ももたらさず、そして、校内の厄介ごとを解決してくれたということも、間違いない事実だった。
「今はそれでいい」
潔く言い切る。全く迷いもない。その姿に、清鈴は笑う。
「本当に腹がすわってる」
「そうでなけりゃ、長月第七で生徒会長なんて出来る訳ないだろ」
小さな溜め息混じりに言う。心労も見えるが、しかしその姿は、どこか誇らしげであり、楽しげだった。
「今更、変わり種が増えたところでどうも思わねえよ」
そう言い切る姿は実に潔い。本当に、心の底からそう思っているのだろう。この学府の全生徒の長である彼にとって、二人は自校に突如として現れた、しかしこれまでと変わらぬ見知った同級生であるらしい。
少なくとも今は。
彼はその意見を曲げる気はないらしい。結論の出た問題をいつまでも引きずる性格ではない。
……だが、そんな彼に、織麻は問うた。
「今はそうでも、その先は?」
董也、そして清鈴も彼女を見た。彼女は無表情で、しかし、その顔は相も変わらず可愛らしい。その柔さと、表情の硬さがひどくちぐはぐで、だがその乖離が妙に艶かしかった。
彼女は目元を真摯にしたまま、口元だけ笑ませて言う。
「これから私達が、貴方の脅威になるって思わないの?何か悪いことをするって」
今は良くても、これからはどうか。
董也は大きく目を見開いた後で、ひどく苦々しい目つきをした。
織麻の言葉が、全く響かない訳ではないのだ。今はそれでいい、と、彼自身が言った。……この先は、彼にとって未知だ。
それを今から恐れないのかという問いに対して、董也は苦い顔から複雑な顔になり、渋面を作った後に、虚脱した。
一連の変面に、二人は見入る。
最後に董也は、何かを決意したように顔を引き締める。結局はいつもと変わらぬ生真面目で潔い顔。
「……ま、そうなったら、その時に考える」
簡潔な答えだった。実に彼らしい。
織麻は顔の硬さを解いて、大きな目を見開いた。青い水晶体に、彼が映る。
「起こってないことや目の前にいないことを考えるのは苦手なんだよ。先のことなんて誰にも分からないし、起こってもないことを怖がって萎縮するのも馬鹿らしいだろ」
「………あんたって、頭が良いのか悪いのか、豪胆なのか無頓着なのか、鷹揚なのか何も考えてないのか、よく分からないな」
清鈴の甘苦入り混じる評価に、董也は眉を寄せる。
「人間は元から多面的だよ。一つの性格で出来上がってない。だからちょっと見ただけで、そいつがどんな人間かなんて分からない。……ましてや、見てもいないんじゃ」
「……」
“想像”だけで人を評価するのは愚かだし、少し見えた面だけがその人間の全てだと思い込むのは短慮だ。
董也は、昨日これまで知りもしなかった一面を見せた、見知ったつもりでいた同級生を見る。知らぬ一面を知った今でも、彼らは今まで知っていた二人に違いない。それもまた事実。
「人間の都合の良い部分だけを見て、相手を見定める人間にはなりたくねえよ……」
ぼそりと、董也は言った。
その時に、学校全体に響く鐘が鳴った。
「予鈴だ。授業始まんぞ」
ごく自然にそう言って、董也は校舎へと足を進めた。
織麻はうん、と言って、彼に付いて行く。一瞬見せた強張りはない、いつもの朗らかな笑みだった。
上屋清鈴は、静かに歩む二人の後ろ姿を見て、その潔さに感服しながらも、どこかその姿勢に欺瞞も感じていた。
束川董也は、どんな脅威も起こる前から過剰に恐れないと言った。全ては起こってから、事態を見極めると。それは嘘ではないのだろう。実際昨夜、彼は自身の予想とは遥かに食い違う事態に彼なりに対処した。そしてそれを経てなお、明らか常人とは違う者を受け入れる度量がある。冷静で柔軟、鷹揚で寛容。──────その根本にあるのは、揺るぎない強靭さ。何事にも動じない、動じたとして、すぐに立て直せる強さがある。
つまりは、そういうことだ。
清鈴は少し振り返って、道端に供えられた花を見る。奪うことしか出来なかった少女が、初めて与えられたもの。……人に与えられるというのも、強者の証かもしれない。
あの少女は、集団になって一人を残酷に虐げたが、それが出来たのは彼女らが自制の効かない未熟な理性しか持たなかったこともそうだが、同時に、対象をそのように扱ってもいいと、漫然と思い込んでいたからだろう。虐げられていい人間など一人もいないと断言できるが、しかし、虐げられやすい人種というのはいて、他より何かが劣る者、かえって優れている者、そして違う者だ。
いじめ対象になったのはそんな人種だろう。恐らく、一般的な女子高生とは違った。周りに合わせなかったのか、話さなかったのか、単に今風ではなかったのか、何せ他とは違った。それがごく一般的な、普通の、今時どこにでもいる少女らの何かに障ったのだ。
“異質”への忌避は本能的なものだ。誰でも自分に似通った姿のものには愛着を持つが、それは同族への安堵であり、自身の共生者への無意識な依存だ。群れねば生きていけない生物の生存本能。そして自身に似ないものへの拒否反応はその逆。敵になるかもしれない者への攻撃性。それもまた生存本能。
そして、これに関しては、人間ならではなのかもしれないが、自分と違うものには何を言っても、どんな振る舞いしても許されると思っている。相手を別の生き物だと思っているから、人間同士の最低限の気遣いや遠慮がない。相手が、自分と同じように感じたり考えたりするものと思っていないのだ。そういう意味では、あの少女らがどこまでも自身の行いを悪いことと認識できなかったことも理解は出来る。彼女らにとって、相手は自分らの言動に傷付いたり苦しんだりする真っ当な感性を持つ、自分らと同等の存在ではなかった。
「……」
想像力の足らない、思考の巡らない馬鹿の愚行と言い捨てればそれまでだが、そればかりとも言い切れないのが生物の業だ。
相手を攻撃せねば生き残れない場で、相手の心情や事情を慮っていては生存競争に負ける。そう考えれば、これも本能の内かもしれない。自分と他人、同族の間にも境界線を引く。線の内側で必死に自分を守りながら、そこを侵食されまいと、向こう側を攻撃する。
……防衛線。これも“境界”。
それを引かずにいられるのは、結局は強い人間なのだ。線などなくても自身の立ち位置を認識できる。侵食されても自分を護れる、また相手に立ち向かえる、対処できると確信している人間。
異物を、他者を許容できる人間というのは、寛容とはつまり強さなのだ。強者の余裕、特権。
清く正しく在れるのは、結局は強い人間だけ。汚れるのは、弱者だ。
……ならば、この世の大概の人間は常に穢れの方に行く危険を背負っている。清も濁も、正も邪も、生も死も、境界線はあれど人は常にその真上を渡っていて、足先がどちらにつくかは本当に一重の差なのだ。僅かに揺れれば、安易に邪にも魔にもなる。
花は揺れている。風に煽られてゆらゆらと。屋上で見た、少女そのままのようだ。
視線を逸らし、校舎を見ると、生徒らが行くのが見える。授業の開始に向けて慌てて駆ける者もいれば、この状況でも悠々と歩む者、まるで動こうとしない者も。大勢の人間がいる。それぞれの意思や感情や思惑を持って動く。
長月第七高校は、三列の校舎が並行して、その中央を一本の廊下が貫く。あの少女は行き止まりで死んだが、そのすぐそばにはこの校舎の中心が、全ての道が行き交う、あらゆる人生が重なる場がある。
そこで時にすれ違い、ぶつかり、追いながら、本当に自分の歩みを守れている者は一体何人いるのか。揺らがず、流されず、立ち止まらず。
「………ここにいる何人が、本当の意味で正気なのかな」
そう言いながら、屋上を見た。一人の少女が生死を賭けた場所。生と死の明確な柵が並ぶ場所。あれは、目に見える形でも見えない形でも、あちこちにあるのだ。今も誰かが、その線の上に立っている。
時間を千切る鐘が、大きく鳴った。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】
絢郷水沙
ホラー
普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。
下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。
※全話オリジナル作品です。


それなりに怖い話。
只野誠
ホラー
これは創作です。
実際に起きた出来事はございません。創作です。事実ではございません。創作です創作です創作です。
本当に、実際に起きた話ではございません。
なので、安心して読むことができます。
オムニバス形式なので、どの章から読んでも問題ありません。
不定期に章を追加していきます。
2026/2/9:『ゆぶね』の章を追加。2026/2/16の朝頃より公開開始予定。
2026/2/8:『ゆき』の章を追加。2026/2/15の朝頃より公開開始予定。
2026/2/7:『かいぎ』の章を追加。2026/2/14の朝頃より公開開始予定。
2026/2/6:『きんようび』の章を追加。2026/2/13の朝頃より公開開始予定。
2026/2/5:『かれー』の章を追加。2026/2/12の朝頃より公開開始予定。
2026/2/4:『あくむ』の章を追加。2026/2/11の朝頃より公開開始予定。
2026/2/3:『つりいと』の章を追加。2026/2/10の朝頃より公開開始予定。
※こちらの作品は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリスで同時に掲載しています。
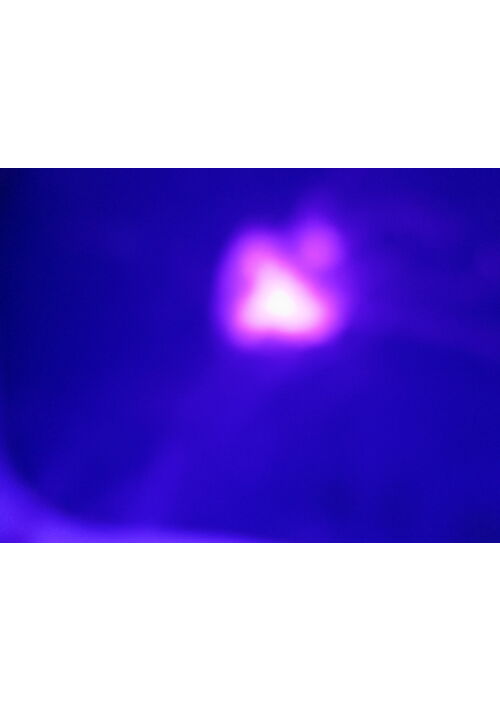
中古にまつわる怖い話と奇妙な話
夏の月 すいか
ホラー
人の想いや感情から怪異が生まれるのだとしたら。
中古品というものはそういったものが集まりやすいのかもしれません。
リユース、リサイクル品、店舗にまつわる怖い話、奇妙な体験です。

【1分読書】意味が分かると怖いおとぎばなし
響ぴあの
ホラー
【1分読書】
意味が分かるとこわいおとぎ話。
意外な事実や知らなかった裏話。
浦島太郎は神になった。桃太郎の闇。本当に怖いかちかち山。かぐや姫は宇宙人。白雪姫の王子の誤算。舌切りすずめは三角関係の話。早く人間になりたい人魚姫。本当は怖い眠り姫、シンデレラ、さるかに合戦、はなさかじいさん、犬の呪いなどなど面白い雑学と創作短編をお楽しみください。
どこから読んでも大丈夫です。1話完結ショートショート。
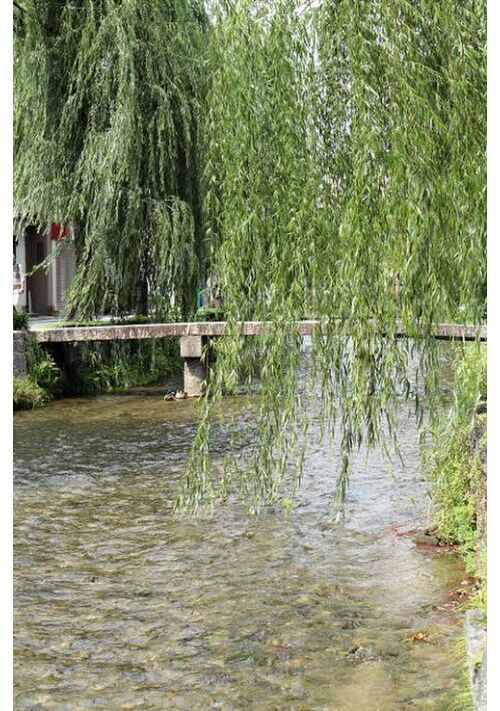

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















