1 / 1
血桜
しおりを挟む
どんよりと曇った、肌寒い秋の日のことだった。一寸先は白い闇。降り続ける長雨を厭うてか、その日、江戸の都を往来する者はごく少なかった。
都の出入り口に設けられた高札場、その隣に掲げられた梟首を見つめる女がひとり。
霧の向こうに、男の晒し首が見える。あんなものを見てはいけないと女中が咲の目を覆ったが、咲は黙って手を払い、なおも死者の顔を凝視し続けた。
あれは確かに鉄だ。咲の使用人だったその男は、武家の娘である咲を犯し、死罪に処せられた。
そう、鉄は死んだ。自分は彼の首が落とされる様を確かに目にした。
ならばあれは。自分の体を嬲るあれは、いったい……。
――覚えてろよ咲! 死んでもお前を俺のモノにしてやるからな……!
鉄の最期の叫びが蘇る。そして、この体を襲う悍ましい感覚も。
重苦しい沈黙の後、咲は何も言わずに踵を返した。屋敷に着くと人払いをし、そのまま自分の座敷に引き籠もってしまった。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
咲は十の頃、人攫いに遭った。悪しき野盗が、武家の娘を使って金をせしめようとしたのだ。暗闇に包まれた街道で衣を剥ぎ取られる。咲が男の下で震えていると、突如低い声が響いた。
「俺の縄張りで何してやがる、退け」
血飛沫が舞う。頽れた野盗の背の向こうを、咲は呆然と見上げた。
視線の先、大柄の男が立っている。男は表情ひとつ変えずに斬り捨てた野盗を見下ろしたが、咲を見て目元をひくつかせた。
「ち、ガキかよ」
咲が助けを乞う視線を送ると、男はばつが悪そうに顔を背けた。
「仕様もねえ。金を奪い取って酒に替えちまおうと思ったのに、こんなガキひとり攫ったって何にもならねえぜ」
「ま、待って、おねがい」
背を向けた男の足を掴む。男は咲を蹴り飛ばそうとしたが、彼女が涙を流しているのを認めて急激に怒気を引っ込めた。
「くそ、面倒くせえな! ……おい、お前はどこから来たんだ」
男は優しく咲を抱き上げた。彼の手はとても温かい。緊張の糸が切れた咲は、男に縋りつき声を上げて泣いた。
舌打ちを繰り返した後、男は咲を助けてくれた。
俺は物取りだ。奉行がいる都になんざ近づきたくねえ。俺が疑われると困るから、早くそれを直せ――男は咲の衣を整え、咲の家まで運んでくれたのだ。
都は大騒ぎになっていた。攫われた武家の娘と、彼女を背負って現れた大男。集まった者は男に対し尖った目を向けたが、咲は自分の恩人なのだと懸命に男を庇った。
前科者の入墨が彫られた腕。ぎょろりとした大きな目、険しい表情、頬に刻まれた刃傷痕、人差し指を欠いた左手。筋骨隆々の体は日に焼けて浅黒く、割れた顎には短い無精髭が生えている。
男はどんな生活を送ってきたのか、一目で分かるような荒っぽい出で立ちをしていた。
咲は男をたいそう気に入り、彼と共にいたいと望んだ。武家の娘と卑しい罪人を一緒にしておくなど、本来あってはならないことだ。だが咲の父は豪放磊落な武士であったので、娘の恩人を使用人として迎え入れることにした。
物取りの鉄。流れ者の男は、武家に仕える下人となった。咲よりも八つ上の鉄は、口が悪く粗野な男であったが、咲にだけは笑みを見せた。鉄は咲をお嬢と呼び、親切な使用人として振る舞ってくれた。
それが、咲と鉄の出会いだった。咲は鉄を兄のように慕い、淡い初恋の情を抱いた。
❀
咲は毎日鉄の側にいた。針仕事をしながら、庭木の手入れをする男を見るのが好きだった。
罪人ゆえに周囲から下衆と評される鉄だったが、その佇まいは堂々としていて、武家の屋敷にもよく馴染んでいる。咲は頭の天辺から爪先まで鉄のことが気に入っていた。鉄はよく見れば顔が良く、咲にとって優しい男だったからだ。
「鉄、こちらに来て」
縁側に座って呼びかければ、鉄はすぐに咲の傍に来てくれる。咲は荒れた鉄の手を取り、そっと親指でなぞった。荒仕事で鍛えられた硬い手は、咲のものよりもずっと大きい。指を絡ませると、鉄の肩がぴくりと動く。
「……お嬢、そんな風に俺の手を触るんじゃねえ」
「どうして? 鉄の手はとても温かいから触りたくなる」
「俺みてえな下人にべたべた触ったら穢れるぞ」
「よしてよ。ここには私たちしかいないのだし、あなたに触れてもいいでしょう? あなたのことは兄さまのように思っているのよ」
「はん。お嬢は変わり者だな」
つっけんどんな言い方をしながらも鉄は嬉しそうだ。それに気を良くした咲は、彼が止めるのも構わず肩を寄り掛からせた。鉄の体から、ほんのりと汗の匂いが漂う。咲は日向を思わせるこの匂いが大好きだった。
咲の座敷に続く縁側は二人の交流の場所だ。彼らは共に座り、中庭に咲く四季の花々を楽しんだ。
咲が十四を迎えた年の、ある春の日のことだった。満開の桜の大樹を見て、鉄はその美しさを褒め称えた。屋敷の庭には様々な花が植わっていたが、鉄は特に桜が好きなのだと言う。
「桜? 鉄は椿を好むと思っていた」
「そりゃどうしてだい」
「椿は首から落ちる様が潔いでしょう」
「そんな打首みてぇな花は嫌いだ! 花は花らしく、散る様が派手な方がいいだろうが」
はらはらと舞う白い花びらを眺めながら、鉄は浮かされた様子で呟いた。
「流れ者だった頃の俺は、酒を飲みながらよく山桜を眺めたもんだ。ああ、桜ってのは綺麗だなあ、満開の風情も、ああやって散る様も好きだ。花なんざどうでもいいけどよ、桜だけは別だった。あの有無も言わさねえ美しさが好きなんだ。こんな捻くれ者の俺でさえ言葉を失うんだ、男を狂わせる美女ってのがいるなら、それはきっと桜みてえな奴なんだろうさ」
桜について話す鉄は珍しく饒舌だ。鉄は年を経る毎に咲の前で無口になっていったが、この日ばかりは頬を緩め、酒に酔ったように言葉を重ねている。ふと、咲の手が優しく握られた。
「お嬢は桜みてえだな」
鉄がそう褒めてくれたことが嬉しくて、咲は頬を染めて俯いた。咲は気恥ずかしくて堪らなくなり、急いで縁側を後にしたが、胸の内では鉄の言葉をいつまでも覚えていたいと思っていた。
もっと綺麗だと褒めてほしくて、咲は鉄の前で紅をさすようにした。新しい着物は必ず鉄に見せ、髪には彼がくれた桜のかんざしを挿した。
しかし、咲が十五を過ぎた頃から、鉄の態度が変わり始めた。鉄は咲が話しかけても素っ気なく、二人きりにならないように避ける。咲は困惑し、自分の振る舞いが嫌われるほど浅ましかったのかと後悔の涙を流した。
毎日髪に挿すかんざし。桜のつまみ細工が可愛らしいそれは、鉄にねだって買ってもらった安物だ。鉄がかんざしを挿してくれた時、彼は何か言いたげな顔をしていた気がする。鉄が距離を置き始めたのは、ちょうどその頃からだった。
江戸中の評判になるほど美しく育った咲のもとには、日々縁談の話が舞い込んでくる。いずれ他家に嫁がなければならないという現実に、咲自身もやがて向き合わざるを得なくなった。
自分と鉄には身分の隔たりがある。どんなに鉄が好きでもこの恋は叶わない。想いを寄せる男の冷たさに胸を痛めながらも、鉄と一緒にいることはできないのだと自分に言い聞かせる。
そして、咲と鉄が縁側で過ごすことはなくなった。共に花を眺めた日々は過去のものとなり、二人の間には深い溝が刻まれた。
❀
咲が十六の頃のこと。寝付けなかった咲は、春の夜風を楽しみながら真夜中の庭を歩いていた。灯りに照らし出された夜桜は、どこか妖しい魅力を誇っている。
あの有無も言わさねえ美しさが好きなんだ、と鉄は言っていた。桜は狂気の花、心の内を映し出す鏡だ。昼は清らかで夜は魔性を帯びる。その佇まいは毒を含む美しさを湛え、胸底に秘めた想いを解き放ちたくなる衝動を呼び起こす。鉄が桜を男狂わせの女に喩えたのも、何となく頷ける気がした。
桜を眺めていた時、使用人が住まう長屋の方から音がした。気になった咲が近づくと、窓の向こうに鉄の姿が見えた。人が寝静まる時間に、いったいあの男は何をしているのだろう。そっと覗き込むと、鉄は大事そうに抱えた木箱の蓋をゆっくりと開いた。
鉄が何かを取り出す。
それは咲の櫛だった。失くしたと思っていたものだ。
鉄は櫛を指でなぞった後、目を閉じて深く息を吸い込んだ。肩を上下させながら女の匂いを肺に取り込み、唇を押し当て、生きた肌に触れるように何度も撫で回した。
咲の帯紐、手鏡、髪の毛……男は箱の中の品に同じことをした。貪るように匂いを嗅ぎ、丹念に唇を這わせる。時に歯を立て、時に舌を絡ませながら。咲に対する真っ直ぐな愛情と、決して手に入らぬ女への狂おしい執着が鉄の体から滲んでいる。熱が籠もった様子で品に求愛をする男の目は、異様な輝きを放っていた。
「……っ!」
見てはいけないものを見た気がして、咲は急いでその場を離れた。荒い息を吐きながら座敷に戻る。すぐさま布団に潜り込み、今しがた見た光景について反芻した。
鉄は密かに自分の物を集め、あの木箱に仕舞い続けていたのだ。主の持ち物を持ち去った挙げ句、あんな風に扱うだなんて……!
「……っ、ああ……」
漏れ出た困惑の声は甘い。咲は自らの声色に驚き、慌てて口を覆った。
あのような劣情を向けられたら、気味が悪いと思う女が大半だろう。だが咲は少しも嫌だとは思わなかった。むしろ、身が蕩けるほど嬉しかったのだ。
鉄の舌が自分の首筋に這わされたら。熱っぽい目で見つめられ、好きだと囁かれたら……。その時自分はどうなってしまうのだろう? 嬉しくて、きっと桜のように散ってしまう。
「鉄。あなたも好きだと思ってくれていたの?」
あの男は自分を嫌って避けた訳ではない。自分を愛しているからこそ、叶わぬ想いを必死に飲み込み続けてきたのだ。昼は冷たく距離を置くのに、夜は熱っぽく自分を呼ぶ鉄の姿。その二面性に甘い切なさが込み上げる。自分だけが苦しかった訳ではないのだと知って、胸が締め付けられた。
「……私、どうしても鉄が好き」
結ばれないと分かっていても、鉄の気持ちを知ったら我慢なんてできない。鉄と触れ合いたい。その思いだけが咲の頭を支配する。
あの男は身分の差に悩み、決して自分に近づこうとはしない。ならば、鉄が我慢できなくなるように仕向けてしまえばいいのだ。どうせ他家に嫁がなければならないのだし、最後くらい鉄と心を通わせたい。この恋を散らすなら、桜のように派手に散らしたい。
崩れていく。
武家の娘としての矜持が。
下人に対する主としてのあり方が。
年頃の娘としての慎みが。良識が。理性が。
あの男と触れ合えるなら、もうどうなってもいい。
――男を狂わせる美女ってのがいるなら、それはきっと桜みてえな奴なんだろうさ。
この身は桜になれるだろうか。鉄が言った、男を狂わせる女のようになれるだろうか。
❀
「鉄、私の座敷に来て」
黄昏時、庭木の手入れをしていた男の腕を、咲はぐっと掴んだ。鉄が肩を跳ね上がらせる。咲に怪訝な顔を向け、彼は唸るような声を漏らした。
「放してくれねえか。人に見られたら良くねえ」
「あなたが大人しく来てくれたら放してあげる」
咲は微笑みながらも、瞳に力を込めて鉄を見据えた。鉄はためらっていたが、周囲に人の気配がないのを確かめると小さく頷いた。
座敷の周辺はあらかじめ人払いをしてある。静まり返った座敷の中に大男を押し込み、咲はふうと息を吐いた。
「やっと二人きりになれた」
「……お嬢、いったい何のつもりだ」
「肩が凝ってしまったの。あなたに揉んでもらおうと思って」
甘い声で鉄を誘うが、彼は険しい顔をして離れようとする。女中に頼めばいいだろうがと呟く男に、咲は眉を跳ね上げた。
「これは命令よ。主の言う事が聞けないの?」
身分の違いを初めて武器に使う。わざと冷たく言い放つと、鉄が驚きに目を見開いた。
「ねえ、早く。あなたにしてほしいの」
咲は微笑みながら衣をくつろげた。襟元が緩み、色白の首筋が露わになる。髪がひとすじ肩を滑り落ち、その艶やかな流れに鉄の目が釘付けになった。咲は着物の裾をわざとたくし上げ、座布団に腰を下ろした。裾から覗く足首が、夕日を浴びて淡く色づく。
「さあ座って。丁寧に揉むのよ」
咲が鉄の腕に手を這わせると、男の大きな体が硬直する。鉄は震える指で、おそるおそる咲の肩に指を食い込ませた。
温かな手に肩を解されると、何とも言えぬ心地良さが広がっていく。もっと強くと咲が命じると、鉄は指に力を入れた。
「ぁ、いい……わ。鉄の指、きもちいい……」
咲は背を丸め、前に首を傾けた。咲のうなじを見た鉄の呼吸が荒くなる。随分と分かりやすいものだと可笑しく感じながら、咲は久方振りの男の温もりを存分に味わった。
「てつぅ……ね、そこをもっと揉んで。あなたの手で気持ちよくしてほしいの」
どこか淫らさを帯びる、甘く砕けた物言い。髪の隙間から覗く女の肌が桜色のように紅潮しているのを認め、鉄は嗚咽のような声を漏らした。
「っ、……くっ、お嬢、こんなのあんまりだ! もう――」
その先を遮り、咲は鉄に向き直った。男の前で着物の裾をめくり上げる。瑞々しい腿を見せつけながら、咲は高揚感のまま命じた。
「次は足を揉みなさい」
その言葉に鉄の顔が険しさを増す。咲が足を男の手に押し付けると、鉄は観念したように息を吐いた。
女のふくらはぎに触れた時、鉄の瞳にじわりと闇が広がった。遠慮がちだった指の動きは、枷が外れたのか大胆なものに変わっていく。大きな手が咲の足を摩り、揉みしだく。鉄は黙したままだが、彼の荒い息遣いは男の内に秘めた獣欲をはっきりと物語っていた。
何か言いかけては飲み込むその様子に胸の奥が熱くなる。好きな男が言葉を失うほど自分に溺れていると思うと、咲の心臓はこの上なく高鳴った。
「もう結構。明日も黄昏時に来て。必ずよ」
咲はそう言って、戸惑う男を部屋から追い出した。障子が閉まると同時に、体の力を抜いて座り込む。鉄を誘惑できた悦びに唇が歪んでしまう。男の顔を思い出すと愉快で堪らず、このまま大きな声で笑い出したい気分だった。
その夜、咲はまた鉄の様子を見に行った。窓の向こうの彼は、咲の櫛をじっと見据えている。男の額には冷や汗が浮かび、唇は震えていた。
「くそっ、俺の気持ちも知らねえで、よくも! 咲、咲、さきぃ……!」
櫛に鉄の舌が這う。粘りつく男の愛執を確認しながら、咲は桜の雨の中、妖艶に笑った。
❀
鉄が堕ちるのは早かった。それほどまでに彼は咲への想いを堪え、とうに我慢の限界に達していたのだ。
黄昏時になると鉄は咲の座敷を訪れ、彼女が命じるまま肌に手を這わせた。主を癒やすための奉仕は、段々と情欲を満たすための愛撫へと変わっていった。ひと月過ぎれば鉄の指から躊躇いは消え失せ、三月過ぎる頃には自ら女の内腿に唇を落とすまでになっていた。
「ふうっ、は、ぁっ……ん……てつ、ぅ……」
「お嬢、お嬢……。ああ、お嬢の肌は本当に綺麗だ」
白肌の上を赤い舌が這う。毎夜女の櫛にしていたことを、今や鉄は己の主にもしていた。
もはやこれは男と女の情事だ。身を繋げていないとはいえ、薄布一枚という格好で互いの体を擦り合わせているのだから。
鉄の目には、女を今にも喰らわんとする獰猛な光が宿っている。咲はその険しい顔に胸をときめかせた。自分は彼の主だとはいえ非力な女だ。鉄が先を望めば、この身は呆気なく明け渡されてしまう。
硬いものを腹に擦り付けられるたび、奥から蜜が溢れ出す。未通女だとはいえ、鉄が何を求めているのかよく分かる。咲は鉄の背に腕を回し、彼の耳元でもっと、と囁いた。
咲は鉄に好きだと言ってほしかった。鉄から想いを伝えてほしかった。
鉄は主に対する劣情を抑え続けてきた男だ。こちらから好きだと伝えても、何かと理由をつけて逃げていくのは分かりきっている。それでは駄目だ。理性を捨て去るほど愛に狂ってほしい。
鉄がもう一度桜みたいだと褒めてくれたら、それだけでこの憂き世を過ごしていける。鉄と心を通わせられたら、好きでもない男に嫁ぐ苦痛も我慢できるから。
「鉄、私の名を呼んで」
甘い声で懇願する。咲が鉄の唇を指でなぞると、彼ははっとした顔で咲から離れようとした。
「逃げないで。呼んでくれるまで放さない」
「お嬢、それは駄目だ。俺みてえな奴が名を呼ぶなんて……」
「命令なんて言葉はもう使いたくないの。お願い」
自分は桜にならなければいけないし、鉄にはもっと狂ってもらわなければならない。心を通わせ派手に散ってこそ、初恋に止めを刺せるのだから。
咲が熱っぽい視線で鉄を見つめると、彼は険しい顔を崩し、今にも泣き出しそうな顔をした。
「卑怯だ、俺がどんな思いで堪えていたか知らねえくせに……! さき。……咲。咲、さき……!」
一度口に出すと止められなくなったのか、鉄は何度も咲の名を呼んだ。首筋に熱い舌が這わされる。性急な愛撫に咲が微笑むと、鉄が顔を近づけてきた。
どちらからともなく唇を合わせる。大好きな男と口吻しながら、咲は恍惚の極致を味わった。
鉄はまだ想いを打ち明けてくれなかった。昼間の鉄は相変わらず素っ気ない。彼はあくまで使用人としての距離を保とうとしている。
だが、鉄は少しずつ変貌している。黄昏前に咲が廊下を通れば、障子の隙間から狂気混じりの視線が覗く。日毎に昏くなっていく異様な眼の光沢。肌を焼き、心の奥を穿つ男の眼差し。獲物をつけ狙うその瞳は、思わず咲が震えてしまうくらい強烈な愛執を滲ませていた。
黄昏時になれば咲を愛撫し、咲が立った床を撫で、咲が座った座布団の残り香を嗅ぐ。夜中、鉄は咲の私物を撫でながら自慰までするようになった。
咲はもどかしかった。どうすれば鉄から想いを告げてもらえるだろうか。鉄に好きだと言われたい。その願いが叶わぬのならいっそ、共に果ててしまえたら……。
ほの暗い気持ちを抱きながら、咲は鉄への想いを燃え上がらせ続けた。
❀
ふと、正気に返った。
もしこの関係が明るみに出たら、鉄が死んでしまうと。
咲がそう思い至ったのは十七の時だ。とうとう他家に嫁ぐ話が決まり、使用人総出で咲の嫁入り支度が始まった。ある日、咲が廊下を歩いていると女中たちの囁き声が聞こえてきた。
「茶屋の娘が鉄にお熱だってさ。あいつの婿入り支度も必要かね」
「はん、鉄はお嬢様にしか興味がないって知ってるだろ」
どくりと胸が跳ねる。咲は女中に気付かれないよう耳をそばだてた。
「聞いたかい、鉄がお嬢様に惚れた男を片っ端から酷い目に合わせてるって噂! やだよお、あの男。お嬢様を舐め回すような目で遠くから見張ってるんだもの。あたしゃあの目が獣のようで、恐ろしくて仕方ないよ」
「あいつも諦めの悪い男だね。もしお嬢様がいいって言っても、手を出したら死ぬのは鉄だけなのにねえ」
目の前が暗くなる。咲はそっとその場から離れ、ふらふらと自分の座敷に戻った。
座り込み、底冷えするような自分の愚かさを恥じる。夢が覚めた後にやって来たのは、自分が犯した罪に対する凄まじい恐怖だった。
「……なんて、愚かなことを」
あの女中の言う通りだ。鉄を狂わせて何になるというのか。既に前科者である鉄は、主と通じたと知られたら死罪になるだろう。
鉄のことを大切に思うのならば、この気持ちに蓋をして彼と接するべきだった。既に自分と鉄の関係は噂されている。これ以上鉄と仲を深めては彼の命が危うくなってしまう。
鉄の感情が日毎に強くなっていくのを感じる。劣情を宿す男の目は愛おしくも、時折寒気がするほど怖ろしかった。
もう迷っている時間はない、鉄がこれ以上想いを膨らませる前に、今すぐどうにかしなければ。愚かな女の初恋から、今すぐ鉄を解放してやらなくては……。
咲は震える指で、髪に挿している桜のかんざしを抜いた。鉄が贈ってくれたその品を、涙に霞む目で見つめる。別れの口付けを一度した後、二度と目に触れぬように棚の奥深くに仕舞い込んだ。
それから咲は、徹底的に鉄を避けた。
座敷を訪ねてくる鉄を跳ね除け、もう来なくていいと言い放つ。それでも次の日にやって来る男を拒絶し、ついには顔を合わせることすら許さないと命じた。
「なあ、教えてくれよ。いったい俺のどこが気に入らねえんだ!」
今日も鉄の懇願が耳を打つ。深い悲しみが滲む瞳を見ていられず、咲は静かに目を閉じた。
「さき、なんでそんな態度を取るんだ? 俺が嫌になっちまったのか……?」
「私の名を口にするなと言ったでしょう。もう近づかないで。これは命令よ」
咲は鉄を一瞥し、背を向けた。
桜のかんざしをしていない後姿を、男がどんな形相で見つめているのか知らないまま。
❀
嫁入りを三日後に控えたその夜、咲の座敷に鉄がやってきた。障子扉を勢いよく開き、驚く咲の傍にどかりと座り込む。鉄は無言のまま、眼光鋭く咲を見据えた。
屈強な男から発せられる怒りに咲の肩が震える。逃げようとすると、鉄が素早く伸し掛かってきた。
「っ、鉄! やめなさい!」
「咲ぃ、やっと俺の名前を呼んでくれたじゃねえか。そうやって甘い声で鉄って呼んでほしかったんだ。なあ、もっと呼んでくれよ。その可愛い声で何度も、何度も、何度も」
粗野な下人の顔が、恋と劣情を湛えた男の顔に変わる。その一瞬の変容が怖ろしく、咲は息をすることさえ忘れた。
咲の首筋に鉄の顔が近づけられる。熱い吐息から逃れようとするが、大きな手が腕を掴んで離さない。咲の耳元に、男の掠れた声が落ちた。
「さき、もし俺と心が一緒なら、咲から想いを伝えてくれ」
「……え?」
「俺は卑しい前科者だ。そんな俺を受け入れてもいいと思ってくれるなら、咲から好きだと言ってくれよ。心を通わせる赦しをくれ」
その告白が嬉しくて、咲は目が潤むのを感じた。もうすぐ鉄の温もりを感じることができなくなるのだと思うと、胸が張り裂けそうになる。
だがそれでも、鉄を救うためには。
「咲、お願いだ! 咲が他の男に嫁ぐと思うと、死にてえくらい辛いんだ。咲と心を通わせられたら、それだけでこの世を生きていける。だから、頼む……!」
鉄は本気でそう思っているのだろう。だが、二人の心が通じれば通じるほど、お互い己の欲望に勝てなくなる。そうして鉄は死に向かって歩み始めるのだ。それだけはどうしても避けなければならない。
今から吐き出す言葉で、鉄は自分を憎むだろう。
それでもいい、彼が生きていてくれさえすれば。
「……出過ぎた真似もいい加減にしなさい。私が穢らわしい下人に惹かれる訳がないでしょう? 旦那様と褥を共にする練習台に丁度良かったから、あなたに声をかけただけ」
血の味がする。心が血を流している。
蒼白な顔で唇を戦慄かせる男を見上げ、咲はわざと酷薄な笑みを浮かべた。
「男の人って案外可愛いのね、こんな未通女に本気になってしまうのだから。あなたをからかうのは楽しかったわ。おつとめご苦労さま」
鉄の目から光が消える。咲の言葉は、男の心を深く抉ったかのようだった。大きな体がぶるぶると震え始める。
「……練習台、だと?」
罪悪感に苦しみながらも、咲は決して微笑みを崩さなかった。この表情を崩せば、全てが無駄になる。
「そう。だからもう来ないで。あなたの役目は終わったの」
咲が冷たく言い放つと、鉄の顔が大きく歪んだ。彼は獣のような呻き声を漏らし、指が真っ白になるほど力を込めた拳を咲の横に叩きつけた。
「咲ぃ、さぁきぃッ! 俺はずっと咲のことを想っていたのに、お前はそんな酷いことを考えて俺を誘惑したのか!? だからかんざしを外したんだな!? 俺が贈った、あのかんざしをっ――」
鉄は言葉を途切れさせた。瞬間、鉄の手が咲の首に伸びる。咲が悲鳴を上げる間もなく、襟元が乱暴に掴まれ、怖ろしい程の力で衣が暴かれる。咲は恐怖に目を見開き、思わず涙を溢れさせた。
「やっ、やめて! 鉄!」
男の唇が醜く歪む。怯える女の耳を舐め上げ、鉄は怒りを押し殺した声で囁いた。
「どんなに泣いたってやめてやらねえよ。咲が俺を狂わせたんだ! お前があんな風に俺を誘わなければ、何とか我慢できたはずなのに……!」
窒息するような口吻に咲の視界が揺らめく。男の唇に歯を立てると、彼は咲の顔を睨みつけた。
「仕方のねえお嬢様だ。おい、お前が何をしたって無駄だぞ。他の男のものになるくらいなら、俺が手酷く散らしてやる!」
……それからのことは、もう思い出したくない。
鉄は咲を凌辱した。だが、男の顔に快楽の色が浮かぶことは一度もなく、彼は涙を堪え、辛そうな顔をしていた。鉄は組み敷いた娘を傷付けながら、己の心もずたずたに傷付けていたのだろう。
咲を穢した後、鉄はすぐさま主人に自白をした。物取りの前科に加え、武家の娘を強姦したとあれば、鉄の運命は決まっている。咲は鉄を引き渡さないでくれと父に懇願したが、父は娘の頼みを二度聞くことはなかった。
咲は飲まず食わずで訴え、必死に鉄の処刑を止めさせようとしたが、鉄の運命は覆らない。
そして数日後、鉄は打ち首に処された。処刑前の彼は力なく項垂れていたが、刑場に来た咲が大声で鉄を呼ぶと、ぱっと顔を上げて叫んだ。
「覚えてろよ咲! 死んでもお前を俺のモノにしてやるからな……!」
愛憎交じる狂気の叫び。咲が声を上げる間もなく、すぐに男の首が落とされた。
血の花が咲く。刀から赤い桜の花びらが舞い落ちる。咲を穢した男の死に様は、あまりにも呆気ないものだった。
✿
嫁入りは破談になった。人目を避けるため、咲は屋敷に籠りがちになった。
鉄と引き離された日から一睡も出来ず、食事も喉を通らない。日毎に咲は痩せこけ、顔色も悪くなり、美しいかんばせから生気が失われていった。
泣き続けたせいか肺が痛み、咳が止まらない。涙混じりの声で、咲は鉄に謝り続けた。
「鉄、ごめんなさい……。あなたが死んだのに、私がまだ生きているのはどうして?」
鉄の首に刀が振り下ろされた瞬間、咲は己の魂も引き裂かれたのを感じた。散り果てた花のように心が枯れている。苦痛の涙が頬を伝い、咲は床を叩きながら愛する男の名を呼んだ。
咲は鏡も見なくなった。綺麗だと褒めてくれた男はもうこの世にいないのだ。自分がどんな醜い姿になろうが、どうでもよかった。
……鉄が死んだ翌夜から、奇妙なことが起こり始めた。
秋の時節なのに、中庭の桜が突然花を咲かせたのだ。季節外れの満開の桜を、誰もが気味が悪いと怖れた。桜の花は赤く色付いていたからだ。舞い散る赤い花びらは、悍ましい血の飛沫を思わせたので、使用人たちはそれを「血桜」と呼んで怖れた。
血桜の開花は不吉の前兆だった。誰もいない場所から足音がし、畳が軋む。ふとした瞬間辺りの温度が下がり、背筋を冷たい何かに撫でられる。咲は、目に見えぬ何かの悍ましい視線を頻繁に感じ取った。
咲だけではなく、屋敷に住む誰もが奇妙な足音を耳にした。咲と鉄の仲を噂していた女中は、酷い悪夢を見たと言って床に臥せってしまった。
自分は鉄を見た。あの血桜は鉄の怨霊が咲かせた。この世に未練を遺した鉄が、皆を呪おうと屋敷に取り憑いたのだ……女中は真っ青な顔をしながらそう呟いた。
特に呪われたのは咲だ。黄昏時になると、何かが彼女の体を犯すようになった。
金縛りにあったかのように身動きできない。憎しみを滲ませたそれは咲の体をがっちりと組み敷き、肌を性急に撫で回す。女穴に大きなものを突き挿れられ、声を上げれば無理やり唇を塞がれる。欲を遂げながら、何かは咲の首をぎりぎりと絞め上げた。夜が明けると咲の全身には鬱血痕が浮かび、秘所からは大量の精が溢れ出た。
悍ましい体験だが、咲は奇妙な懐かしさを感じていた。手つきが鉄のものに似ていたからだ。
鉄は憎悪のあまり怨霊になってしまったのだろうか。
自分を陥れた娘を痛めつけるため、こうしてやって来るのだろうか。
それなら、それでいい。自分にできることは、抵抗をせずに鉄を迎え入れることだ。自分は鉄を誘惑し、死に追いやるという罪を犯した。あの男に少しでも報いることができるならば、いくらでもこの身を捧げよう――咲はそう考え、涙を流しながら霊に抱かれた。
鉄の手は温かかったのに、今や寒気がするほど冷たい。怨霊から伝わる殺意を感じながら、咲はこのまま死んでしまいたいと考えた。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
首は三日晒される。その後は棄てられ、如何なる者であろうとも弔いは許されない。処刑後、鉄は彼の世で物取りできないようにと両手を落とされた。そのため、咲は密かに鉄の手を持ち帰ろうと決めた。
人気のない明け方、咲は河原に打ち捨てられた男の遺体を見下ろした。
大きな体の傍に、人差し指を欠いた手が転がっている。青白い手は人形のように冷たい。持ってみると、ずしりと不気味な重さを感じた。
「……帰りましょう、鉄」
咲は鉄の両手を布に包み、屋敷に戻った。
中庭の桜の根元に、鉄の両手を埋める。彼が好んだ桜の下ならば、安らかに眠れるかもしれないと考えたのだ。鉄の手に土を掛けながら、咲は彼の笑顔を思い出した。
「あなたの気持ちに応えられなくてごめんなさい。私は鉄のことが大好きだった。愛するあなたと思いを通わせたくて、あんなことをしたの」
ぞっとするほどの冷気が満ち、赤い桜の雨が降り落ちる。嘘を吐くなと言わんばかりに何かが咲の首を絞めたが、咲は涙を流しながら言葉を続けた。
「鉄が私に溺れていくのを見るのは嬉しかった。でも、もしこの関係が明るみに出たら、死ぬのは鉄だけだと気がついたの。だからあなたを突き放した。鉄が死んだのは、私のせい」
初めての恋は、派手に散る前に腐ってしまった。本当の想いを伝えられないまま、愛する男は死んでしまった。
「だから、気が済むまでこの体を暴いて。あなたになら何をされても構わない」
懐から桜のかんざしを取り出し、髪に挿す。
そこにいる彼に向けて、咲は黄昏時に来てと囁いた。
✿
その夜、また霊はやって来た。
見えない手が咲を拘束し、衣を暴く。だが昨夜までと違うのは、その手つきが少しだけ優しいことだ。首を大きな手に掴まれるが、それ以上力が込められることはなかった。
咲は違和感を覚えた。今宵の霊からは強烈な殺意を感じない。今までとは明らかに異なる振る舞いに、咲の心が切なく揺れる。
「鉄? やっぱり、あなたなの……?」
返事はないが、そっと唇をなぞられる。それは肯定の証のように思えた。
咲は顔を歪め、暗闇の中で鉄の姿を捉えようとした。どんなに目を細めても何も見えない。愛する男の姿を想像しながら、霊の存在を掴もうと手を伸ばす。指先が何かに触れた気がしたが、その感覚はすぐに消えてしまう。
霊となってまで会いに来てくれたのだから、もっと鉄のことが欲しい。咲は甘い声で鉄を求め、この身にあなたの存在を刻みつけてくれと囁いた。咲の腰が撫でられる。衣と肌の隙間に差し込まれた手は、昨日よりも温かく感じられた。
乳房が揉まれ、先端に口付けられる。見えなくても、鉄が口をすぼめながら乳首を吸っているのが分かる。彼の赤い舌が己の肌を這い回る想像をして、咲は背が震えるほどの恍惚に溺れた。
優しい愛撫に咲の秘所が綻んでいく。敏感な女芯を指の腹でくるくると撫でられ、咲は今まで出したこともない艶やかな嬌声を上げた。
「あっ、っん、あはあぁ……」
咲はうっとりと顔を蕩けさせ、鉄がもたらす甘い快楽に浸った。女の反応を愉しむように、鉄の指が執拗に動き回る。彼は溢れ出る蜜を陰核に塗りつけ、太い指で膣をかき回した。
女の秘所が濡れそぼった頃、鉄は咲の瑞々しい腿を割り開いた。ぴり、とした甘い痛みの後、咲の肌に赤い花びらが散る。咲が笑みを浮かべると、鉄はそそり勃ったものを女穴に突き挿れた。
「ふあっ、は、ぁっ……。んぐ、てつ、ぅ……!」
隘路がみっちりと割り開かれる。大柄な鉄は男根も逞しく、受け入れると少しだけ息苦しい。心配するように自分の頬を撫でてくる鉄が愛おしくて、咲は涙を浮かべながら微笑んだ。
「ふ、ふふっ……。大丈夫、痛くないわ。鉄の好きなようにして……」
遠慮がちに腰が動かされる。咲の様子を伺いながら行われる抽挿は、段々と勢いを増していった。咲の秘部からぐぷ、ぐぷと淫らな水音が響く。やがて最奥に男の精が放たれ、ほのかな温かさがじんわりと広がった。
死んだ鉄がくれる、唯一の形あるもの。彼の精がとても愛おしい。虚空を見つめながら、咲はそこにいる男に向けて想いを伝えた。
「ねえ、知ってる? 私の初恋はあなたなのよ。鉄が桜のかんざしを贈ってくれた時、とっても嬉しかった」
切なさに涙が溢れる。ようやく想いを伝えられたのに、自分は二度と鉄の姿を見ることは叶わない。生と死の隔たりが、哀しくて仕方なかった。
「大好きよ、鉄。今も昔も、そしてこれからも……。ずっと鉄のことを愛しているわ」
空気が揺れる。自分を押さえつける気配が薄れ、どこからか慟哭に似た音が聞こえる。胸が抉れるような悲痛な叫び。鉄もまた、肩を大きく震わせながら泣いているのかもしれない。
咲は虚を抱きしめ、あなたと結ばれたかったと呟いた。
✿
霊とまぐわい始めてから二ヶ月が経った。
鉄は毎夜やって来る。姿は見えず、声は聞こえなくとも、咲は彼と恋人のように過ごした。縁側から血桜を眺め、褥を共にし、姿なき霊に「旦那様」と甘い声で呼びかけた。
咲の悔恨と愛情を信じたのか、鉄は憎しみを露わにしなくなった。娘に優しく口付け、その体をそっと抱きしめる。丹念な愛撫を施された咲の体は、すっかり女の悦びを覚えた。冬が近づく頃には鉄の大きな男根を難なく咥え込み、膣で絶頂を味わうまでに至った。
咲はとても幸せだった。歪な形でも、自分は大好きな男と結ばれたのだ。
だが、霊と深く交わるにつれ、咲を取り巻く呪いの気配は強まっていった。
始めは小さな異変だった。肉が落ちた咲の腕に痣が浮かび上がる。痣は日毎に大きくなり、やがて黒黒とした罪人の入墨を形作った。不気味な出来事はそれだけではない。咲が触れたものには必ず血の雫がこびり付く。茶碗や机を始め、床、障子にまで。咲がいる場には、悍ましい赤の花びらが散った。
咲は鏡を見ない。正確に言えば、鏡に映る自分の様子には目を向けず、鉄が体に残した痕跡を確かめるために鏡を使う。だから咲は、自分がどんなに異様な姿をしているのか気が付かなかった。
娘の肌は血を失ったかのように真っ白だ。全身に赤い指の痕が浮かび、首には手型が刻まれている。肉が落ちた体は濃密な死の気配を漂わせていたが、落ち窪んだ目だけは、爛々と生の輝きを放っていた。
お嬢様は呪われている。きっと、鉄の怨霊に取り憑かれてしまったのだ。女中たちはそう噂をし、咲を穢れた女として避けるようになった。
下人に凌辱された咲だが、それでも彼女に想いを寄せる者は後を絶たない。哀愁を帯びた横顔は一層の艶を増し、死に近い儚げな佇まいは幽玄の美として評判になった。桜のように美しい娘に魅入られた男たちが、咲に求婚をしようと次々に屋敷を訪れる。そしてその度、呪いは更に強まっていった。
咲に会いに来た武士が彼女の手を握ろうとした時、座敷の障子が乱暴に開け放たれた。風もないのにいきなり開いた障子に、男の訝しげな視線が向けられる。すると悍ましい殺気が辺りに満ち、男の体に耐え難い痛みが走った。まるで大きな手に、肩をぎりぎりと掴まれているかのように。
数日後、男は高熱に倒れた。彼の肩には真っ赤な手の痕が残っていたため、これは怪異の仕業ではないかと噂になった。
やがて、咲に近づく男たちに奇妙な災いが降りかかるようになった。ある者は夜道で首を絞められ、ある者は手足の骨を折り、またある者は悪夢にうなされ続け発狂した。そんなことが繰り返されたのち、咲に会いに来る者は段々と減っていった。
咲き誇る血桜、夜な夜な廊下を歩き回る足音、辺りに満ちる悍ましい冷気、夢に現れる大男。使用人たちは恐怖に怯え、次々と屋敷を去っていく。咲は怨霊憑きの娘と呼ばれ、父に座敷から出るなと命じられた。
そして、咲を蝕む呪いも勢いを増していった。
「けほっ、ごほ……」
咳が止まらない。
前から続いていたこの咳は、どんどん酷くなっていく気がする。鉄と引き離された時から食事らしい食事を摂っていないから、そのせいで元気がないのかもしれない。
咲は病的に痩せ細っていった。肺の奥が粟立ち、喉が引き攣れるように痛む。やがて咲自身も、床に血の花びらを散らすようになった。
喉が切れて血が滲む。乾いた咳がいつまでも止まらない。息苦しさを感じた時は、縁側に座って鉄の名を呼んだ。そうすると彼はすぐに来て、咲の背を撫でてくれた。
鉄に触れられている間は苦しみを感じない。背に温もりを感じながら、咲は愛しい男にありがとうと囁いた。
✿
咲の座敷には誰も近づこうとしない。静まり返った空間で、咲は愛する男と存分に過ごした。
黄昏時にやって来ていた鉄は、やがて昼夜問わず咲の傍にいてくれるようになった。彼と触れ合う度、見えぬ手の感覚がはっきりしていく。鉄との距離が縮まるのを嬉しく思いながら、咲は怨霊と体を重ね続けた。
雪深まる頃、咲は鏡に映る自分の後ろに見知った姿を認めた。
大きな目が印象的な、筋骨隆々の大男。体の輪郭は霞がかっているが、恋い焦がれた男の姿がそこにある。
「鉄……!?」
驚いて振り返るが、背後には誰もいない。だが再び鏡を見ると、確かに鉄の姿が映っている。男の表情は険しい。血走った瞳に憎悪を滾らせ、鉄は後ろから咲の体をぎゅうと抱きしめた。
『なあ、咲。お前は俺のモノだよな? なのに、どうしてまだ忌々しい男どもを寄せ付けるんだ?』
ぼやけた声が耳を打つ。霊となった鉄の声が聞こえたのはこれが初めてだ。咲が顔を輝かせると、鉄の姿が尚更くっきりと浮かび上がった。
男の温もりが咲の全身を包み込む。鉄は確かな体温、確かな形をもって咲に触れた。
『咲は俺の嫁だから手を出すなって言ったのに、まだ下衆どもがお前を狙ってるんだ。ああ、忌々しい。夜な夜な抱いて俺のにおいを擦り付けているのに、なんでまだ咲と二人きりになれねえんだ……!?』
頭の上から聞こえるぼやけた声は、生者と何ら変わらない。
生と死の境界が曖昧になるのを感じながら、咲はゆっくりと振り返った。
先ほどは見えなかった鉄の姿が、今は見える。男の頬に手を添えると、確かに触れた感覚があった。
「仕方のないひと。そんなことを考えていたの? 私に会いに来る殿方はもういないわ。鉄が全員追い払ってしまったじゃない」
『追い払っても新しいのが来るから悩んでんだよ。ったく、お前が綺麗すぎるのがいけねえんだ』
ふてくされた表情の男を見上げ、咲はくすくすと笑った。
「誰が来たって関係ない。私の旦那様は鉄だけよ」
『だけどよ、俺は死人だ。この姿は咲以外には見えねえし、この声は咲にしか聞こえない。俺の警告も、下衆どもにはちっとも聞こえちゃいねえ』
鉄は言葉を絞り出すようにそう言った後、大きな溜息を吐いた。
『俺はお前を連れて歩けないし、ガキも作れない。俺がいくら咲のことを好きでも、俺達は本当の意味で……夫婦にはなれねえのかもな』
その言葉に切なさが込み上げる。咲は悲しみに顔を歪め、目の前の男を精一杯抱きしめた。
「お願い、そんな酷いこと言わないで。誰に認められなくとも、私たちは確かに夫婦よ。鉄はここにいるじゃない。あなたの温もりをしっかりと感じるわ」
『……さき』
「私の全てはあなたのものよ。不安なら、私を抱いて。鉄と私の繋がりがもっと深くなるように、あなたの存在を感じさせて」
咲の微笑みに鉄の目が潤む。彼は愛しい娘を掻き抱き、性急に唇を奪った。
「んむぅっ、んくっ……! ぁ、て、つぅ……」
肉厚の舌がぬるりと咲の腔内に入り込む。鉄は女の頬を両手でがっちりと掴み、目を見開きながら咲の口を蹂躙した。
敏感な上顎に舌を這わされ、歯列を丹念になぞられる。引っ込めた舌を横から掬いあげられ、舌先を唇で挟まれながらゆっくりと前後に動かされる。粘膜を触れ合わせる甘い快感に、咲は唾液を嚥下しながら声を漏らした。
「あ、ふぅっ、鉄……んぁ、だめ、ぇ……」
『んっ……駄目だって? 仕方のねえお嬢様だ。そんなやらしい顔をして駄目なもんかよ』
鉄は咲の反応に目元を緩ませた。久方振りに見た男の笑みに、咲の胸がとくとくと跳ねる。自分からその先を求めるのは浅ましい気がして、咲は色付いた頬をそっと分厚い胸に埋めた。
『俺に甘えてんのか? 可愛いなあ咲。お前は本当にかわいい』
咲の体が優しく抱きかかえられる。布団の上に彼女を横たえ、鉄はそっと咲の上に伸し掛かった。
大きな手に衣を一枚ずつ脱がされる。乳房を揉まれながら、耳から首筋までを唇で何度もなぞられる。
『咲、さき……。お前は昔からちっこくて愛らしくて、綺麗だなあ。知ってるか? 俺の初恋はお前なんだ』
「ふ、あ……ほんとう……?」
『ああ、本当だ。愛しい咲、今日も可愛がってやるからな』
鉄の赤い舌が、咲の乳首をぱくりと咥え込む。敏感な胸の先端を飴玉のように舐め転がされ、咲はぴくぴくと肩を震わせた。
大きな手に咲の乳房がすっかり包み込まれ、形を確かめるように優しく揉まれる。片方の乳首を吸われながら、もう片方を指の腹で擦られる。単純な動きなのに、身を捩りたくなるような切ない快楽が広がっていく。
「ひ、んふうっ……。ああっ、ああんっ……」
鉄はわざと赤い舌を見せつけながら、無言で咲の胸を苛んだ。生温かい舌が、敏感な膨らみを粘っこく這い回る。舌に力を込めて乳輪ごと先端をなぞりあげられると、気持ちよくて力が抜けてしまう。
足を擦り合わせながら甘い快感に浸る。男に可愛がられ続けた胸は快楽に従順で、咲はすぐに甘い高みへ上り詰めた。
「はっ、ふあっ、てつぅっ、もうっ……! あっ、あはあぁっ……」
胸から全身へ、切ない絶頂の快感がじんわりと広がる。咲が鉄の首に腕を回すと、彼は濡れた秘部に指を入れ、優しく掻き回すように動かし始めた。
「あ、あああっ……。ひう、んんっ……」
『咲、顔が真っ赤だぜ。ははっ……すげえな。俺の指が溶けちまうくらいとろとろだ。そんなに気持ちいいか?』
「うんっ、うん……! てつのゆび、きもちいいっ……。ふあっ、あひっ……んあああああっ……」
膣天井を優しく叩かれると、むずむずとした快楽が迫り上がってきて雫を溢れさせてしまう。茂みの中に隠れていた肉の芽にしつこく愛液を絡められる。太い親指で陰核の先端を弾かれ、咲は呆気なく達した。
「ひっ、ひく、いくぅっ……! う、んんんんっ……!」
『咲が欲しい。咲に触れている時だけ心が安らぐ。さき、さき、俺の咲……。お前を満たせるのは、この俺だけだと教えてくれ……!』
足を割り開かれ、鉄の陰茎がずぶずぶと入り込んでくる。女のうつろを満たされる感覚に、咲はうっとりと目を瞑り、鉄の背に腕を回した。
「あ、ああっ……あ、はああああんっ……。いい、っ、きもち、いいわ……」
鉄がゆっくりと体を動かす。ふたりの腰が合わさる度、粘っこく淫らな水音が響く。咲は額に汗を滲ませながら、蕩けそうな交合の快楽に浸った。
『はっ、はっ、はあ……さき、咲……! お前の内がうねって、すごくいいっ……!』
「あ、あっ……てつっ、てつぅ……! あんっ……もっと、もっとしてぇ……!」
咲に誘われ、鉄は腰を大きく動かし始めた。男の太い陰茎が女の弱いところを擦り上げ、鋭い快楽を与える。咲は愛する男の名を何度も呼びながら、擦り付けられる男根の熱さに乱れきった声を上げた。
「あ、あああっ……そこ、いいっ……! ねえ、てつっ、てつも気持ちいい? もっとちょうだいっ、わたしがあなたのものだって、思い知らせて……! おねがっ……あ、あっ、ああああああんっ!」
腹の裏側を執拗に擦られ、咲は呆気なく絶頂を迎えた。鉄の顔が快楽に歪み、低く掠れた声が咲の耳元に落ちる。鉄は咲の唇を奪い、彼女の体を押さえつけながら激しく秘所を穿った。
『当たり前だろっ、咲は俺のモノだ! 死んだって放してやらねえ! 俺がどれだけお前のことが好きなのか知らねえだろっ、俺は咲のことが好きでっ、好きで、好きすぎてっ、ずっとこうしてやる想像ばかりしてたんだぞ……!』
「んうっ、ふあ、あああっ! あ、あっ、あっ、あっ……だめ、だめ……そんな強くされたらっ、またいっちゃ……!」
『いいぜ、旦那様の体で何度でも気持ちよくなれよ。お前が気をやっちまっても、俺がきちんと世話してやるからな! さきっ、さき! 咲ぃ……!』
「んん、あぁっ、はあああああっ……。鉄っ、てつぅ……! だいすきっ……ふあっ、ああああああっ!」
『咲、大好きだっ! お前をずっと愛してるっ、いつまでも、こうして幸せに暮らそうなっ……! くっ、はあぁぁ……!』
最奥に精が放たれる。鉄がくれる温もりが、降り落ちる愛の言葉がとても嬉しい。絶頂を迎えた陰茎を締め付けながら、咲は歓喜に涙を溢れさせた。
✿
満月が美しい冬の夜。咲は今夜も縁側に座り、鉄と共に桜を見た。
血桜はまだ花を咲かせ続けている。寒風が花を散らすが、枝から湧き上がるように次々と新しいつぼみが花開く。赤い花びらを派手に散らすその様は、まるで命を削っているかのようだった。
情事で火照った体を冷ましながら、咲は男の手を握った。
「ねえ。私を憎んでいないの?」
静かな問いかけに、鉄が首を傾げる。
「私は鉄を死に追いやってしまった。あなたに優しくされる度、いつも辛くなるの。私は鉄に殺されても仕方のないことをしたのに」
舞い散る花びらに血の色を重ね、咲は心痛を堪えた。鉄の死に様を思うと胸が痛む。肺が粟立ち、喉奥から何かが迫り上がってくる。
『……そりゃあ、な。呪い殺してやると思ったさ。お前のことを深く愛していた分、あんな風に俺の想いを踏みにじったことが許せなかった。絶対に幸せになんてさせない。犯して、痛い目に遭わせて、一生どこにも行けなくしてやろうと思った。その憎しみのあまり、俺は怨霊になっちまったしな』
俯く咲の手を握り返し、鉄は穏やかな声で言った。
『だけどよ、咲は俺を突き放した理由を教えてくれた。咲は俺と心を通わせてくれた。最初は疑っていたけど、今はお前の愛を信じられる。だから、もういい。今の俺には憎しみも怒りもねえ。咲とこうやって過ごせて、俺はとても幸せなんだ』
咲の体がすっぽりと包みこまれる。寒さから彼女の身を守るように、鉄はしっかりと娘の体を抱きしめた。
『俺こそ、酷えことをした。こんなやわっこい女は壊れ物のように扱うべきなのに、憎しみに任せてお前を傷付けた。痛かっただろ? 怖かっただろ。……乱暴にしてごめんな』
男の大きな目が後悔に揺れる。肩を震わせる鉄の顔を見上げ、咲は優しい微笑みを浮かべた。
「謝らなくてもいい。謝る代わりに、たくさん愛してるって言って。鉄から好きだって言ってもらいたくて、いつも一生懸命おしゃれをしていたの。ね、私の旦那様。おねがい」
可愛らしいおねだりに、鉄が目元を緩ませる。彼は咲の頬を撫で、甘い声で囁いた。
『愛してる、咲。俺達はずっと夫婦だ。いつまでも、いつまでも一緒にいよう』
望んでいた言葉をもらえて、喜びが胸に満ちる。私も、と返事をしようとした瞬間、喉奥から鉄の臭いが迫り上がった。
「っ!?」
咲の口からごぽりと血が溢れる。
ぼたぼたと音を立てて床に滴り落ちた血に、鉄はざっと顔を青褪めさせた。
『さきっ、咲! 大丈夫か!?』
「っ、げほっ……! ……はっ、はあ……なんだか、前から咳が止まらなくて。ごめんなさい、鉄が近くにいる時はっ……血を出さないように気をつけていたんだけど……」
激しく咳き込みながら、咲は溢れ出る血を止めようとした。
咳が止まらない。命が削られていく。こんなみっともないところを、愛する男には見せたくなかった。自分は常に、桜のように美しくいなければいけないのに。
「ご、ごめんなさい、少し別の方を向いていてくれる? 今、止めるから……」
『何言ってんだよ、こんなの止められる訳ねえだろうが! 咲、すぐに休め。俺がどうにかして医者を呼んできてやるから!』
鉄は咲の体を抱きかかえた。
そして気がつく。娘の体の、あまりの軽さに。
『は……?』
咲に対する恨み辛みから解放された末、鉄は初めて娘の本当の姿を認めた。愛する女と結ばれなかった未練に取り憑かれていた鉄は、咲がどんなに衰弱しているか、今まで正しく見ることができなかったのだ。
『咲? ま、さか……。咲は俺のせいでこうなったのか?』
全身から肉という肉が落ちた、骨のように痩せこけた女。蒼白な肌には赤い指の痕が刻まれ、腕には黒黒とした罪人の入墨が刻まれている。怨霊の呪いに蝕まれた咲は、明らかに死へと向かっている。
『咲が俺と話せるようになったのは、咲が死にかけているから。咲が病に罹ったのは、俺の呪いに引き摺られたから……。俺の怨念が、咲の命を奪っていったんだ。咲が俺と触れ合えるのは、死人の俺に近づいているからだ……!』
そうだ。古来より、怨霊は生者と相容れない存在だと伝えられている。怨霊はその場に存在するだけで生者を呪い、死の世界に誘ってしまうからだ。
それなら――死者と深く交わり続けた咲は、いったいどうなる?
『駄目だ、そんなの。俺が咲を殺しちまうなんて、そんな怖ろしいことねえだろうが! さき、俺はお前を死なせたくねえ……!』
己の腕の中で荒い息を吐く娘を見下ろし、鉄は呆然と唇を震わせた。
『お前が俺を必要としてくれたあの日から、俺は咲を守るって決めたんだ。これ以上咲を傷付けたくない。今すぐお前を解放してやらねえと……』
鉄はぐったりとした娘を布団の上に寝かせた後、すぐにその場から消え去った。
✿
自分は労咳に罹ったのだという。
咳をし続け、衰弱した末に血を吐いて死ぬ不治の病だ。
まだ若いのに可哀想だ。怨霊に引き摺られたのだろうか……女中の囁きをぼんやりと思い出しながら、咲はここにいない男に向かって呼びかけた。
「鉄。いつまでも一緒にいようって言ってくれたのに、どうして私の前から消えてしまったの?」
死は怖くない。死ぬよりも怖ろしいのは、愛する男ともう会えないことだ。
縁側で血を吐いたあの夜から、鉄は姿を現さなくなった。どんなに呼びかけても、鉄は気配すら滲ませない。腕に浮かんだ罪人の入墨が、日毎に薄らいでいく。鉄との繋がりを失ってしまうのが怖くて、咲は掠れた声で愛する男に呼びかけた。
「おねがい、鉄……。私を本当に愛しているのなら、もう一度姿を見せて……」
返事がないまま、月日が流れていく。
根雪が解け始め、春の気配が訪れても、鉄は戻ってきてくれなかった。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
俺の存在を認めてくれたのは咲だけだった。
親の顔も知らない根無し草。貧しさから逃れるために、俺は何度も盗みを犯した。前科者の入墨がある男なんて、誰からも嫌われる存在だ。なのに咲だけは俺の手を握り、あなたが必要だと言ってくれた。
咲に甘えられる度、心がくすぐったくなった。こんな俺を兄と呼んで慕ってくれる娘が愛おしい。咲は唯一の宝だ。命に代えてもこの娘を守ろうと決めた。
だが俺は、いつの間にか咲を女として意識してしまった。
あどけない顔は、成長するにつれ言葉を失うほどの美貌に変わった。咲は桜のように美しく、傍にいると胸が跳ねる。咲が目元を緩ませて綺麗に笑う度、恋心が膨れ上がっていくのを感じた。
邪な思いを必死で押さえつけているのに、咲は何でもない顔をして俺に甘えてくる。極めつきは俺にかんざしをねだってきたことだ。男が女にかんざしを贈る意味なんて知っているだろうに、咲は笑顔で頼んでくる。俺は咲に一番似合う花を思い浮かべ、桜のかんざしを買ってやった。
咲は男を狂わせる美女だ。その無防備な行動ひとつひとつが、抗えない誘惑のように思えてしまう。このままでは俺がおかしくなる。大切な娘を傷付けないように、どうにか距離を置こうと決めた。
だが俺は、とうに狂っていた。咲に穢れた視線を向ける男を見かける度、胸を掻きむしりたくなる。酷い嫉妬に苦しめられて夜も眠れない。咲の美しさは俺にとって誇りであり、耐え難い痛みでもあった。
我慢できなくなった俺は、咲に想いを寄せる男を密かに処分してまわった。汚い目で咲を見るのが許せない。目を潰し、手足を折り、下衆どもに咲は俺のものなのだと言い聞かせてやった。咲を好いていいのも、笑顔を見ていいのも俺だけだ。あの艶やかな髪に桜のかんざしを挿していいのも、小さな手を握っていいのも俺だけ。咲は俺だけのものだ、決して他の男には渡さない!
咲の縁談についての噂話を耳にする度、心臓が嫌な跳ね方をした。下人や町人とは違い、さすがに武家の男まで処分することはできない。大体、咲と俺は身分が違う。桜が散るように、いつか咲は俺の元から去る。そう思うと、胸の奥が焼け爛れるように苦しい。
この恋は叶わない。咲の幸せは良家に嫁ぐことなのだ。そう頭では分かっていても、咲を独占したい気持ちが止められない。だから俺は、咲の私物を使って浅ましい欲を発散しようとした。
桜が美しい夜だった。咲の私物を愛撫していると、どこからか視線を感じた。
咲がこちらを見ている。緊張に体が強張ったが、俺はそのまま咲の櫛を愛撫し続けた。気持ち悪がってくれたらこの想いを潰せる。俺を遠ざけてくれたら、これ以上咲への想いを膨らませずに済む。咲が息を呑んで逃げていくのを横目に、ほっとした気分になった。
それなのに、咲は翌日から俺を誘惑するような行動に出た。白い肌を露わにしながら艶やかに笑い、自分に触れるよう命じる。そんなことをされたら、もう我慢なんてできない。理性が呆気なく崩れ去り、抑え続けてきた咲への想いに支配されるのを感じた。
夜中になると、咲は俺の様子を窺いにくる。櫛に舌を這わせ、自慰をする男を微笑みながら見ている。うっとりと笑うその様は、男を狂わせる女そのものだった。
ああ、きっと咲も同じなのだ。下衆な男を遠ざけるどころか、自ら近づいてきてくれるのだから。きっとあの女も俺を愛してくれている……そう思っていた。
だから、練習台という言葉が許せなかった。
狂おしいほど咲のことが好きなのに、俺の愛は練習台の一言で徹底的に踏みにじられた。
もうどうなってもいい。これが最後なら、咲に消えない傷をつけてやりたい。
だが、咲を痛めつけた後にやってきたのは強烈な罪悪感だ。自分の下で啜り泣く咲を見た時、守ると決めた娘に対して、なんてことをしてしまったのだろうと怖ろしくなった。
死罪になると分かって自白した。
この苦界に未練などなかったのに、咲の声を聞いた瞬間憎しみが溢れ出してきた。
俺を裏切ったあの女が悪い。死んでもあの女を苦しめ、いつまでも取り憑いて自分の存在を刻みつけてやりたい。咲と結ばれないこの世を呪ってやりたい!
そうして気がついたら、俺は桜の下にいた。
咲と眺めた、中庭の桜の大樹の下に。
赤く色づく桜を見上げながら考える。どうやら俺は、咲への未練のあまり怨霊となったらしい。怨霊ならば、怨霊らしく裏切った女を呪ってやらなくては。俺は咲の座敷に忍び込み、またその体を穢した。
無理やり犯しながら首を絞め、一番奥に溜め込んだ欲を放つ。白い肌を握り込み、全身に所有の印をつける。啜り泣く咲を見ると、哀れに思う気持ちと同時に悦びが込み上げてきた。
散々怖ろしい目に遭わせたのに、咲は怨霊の俺を受け入れてくれた。桜の下で、本当の気持ちを聞かせてくれた。この女は確かに俺を愛してくれていたのだと気がついた時、俺は泣き叫びながら後悔した。
咲の愛情を感じる度、自分の心から憎悪が消えていく。咲を慈しみ、守りたいという気持ちが再び蘇ってくる。生と死の隔たりはあれど、咲は俺の女で、俺達は夫婦だった。俺だけが、この美しい女に触れられる。屋敷にいる人間も、咲を狙う男も全員要らない。今度こそ二人きりの世界を作るため、俺はあらゆる人間を呪い殺そうとした。
そうだ。俺は怖ろしい怨霊。どこまでいっても未練と怨念の塊だ。
こんな俺と一緒にいて、咲が無事でいられるはずがない。怨霊は死そのもの。生者と交われば、無理やりこちら側に引きずり込んでしまうのだから。
馬鹿だ。俺のせいで、咲が死にかけている。
恨み辛みから解放されて、やっと分かったんだ。
俺は咲を救いたい。咲の笑顔こそ、自分の宝だから。
だから、もう会えない。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
麗らかな春の空気が満ちる頃、咲はもうまともに歩けなくなった。
夜風が障子の隙間から吹き込んでくる。己の死が近いことを悟った咲は、痛む胸を抑えながら必死に外へ這い出た。愛する男に会いたい、その一心で必死に暗闇の中を進む。
「……て、つ」
咲は血を吐きながら、懸命に中庭の桜を目指した。鉄がまだこの世界にいるならば、それは彼の手を葬った桜の下ではないかと思ったからだ。
視線の先に、赤く咲き誇る桜が見える。
血桜は今なお咲き続けていた。夜の帳の中、紅の花びらがはらはらと舞い散る。命を削りながら激しく花を咲かせていた桜も、今は儚い静謐さを湛えている。散り際の桜は、最後の艶やかさで薄暗やみを彩っていた。
「……何となく、分かっていたの。この咳は怨霊の呪いによるものだって……。鉄が死んでからこの咳が始まったもの。それでも、私にとってはこの咳すらも愛おしい。だって、鉄との繋がりを確かめられる証のひとつだから……」
血が溢れ落ちる。自分の命も、桜の命も散っていく。
倒れてしまいそうな苦しみの中、咲は一歩一歩前に進んだ。
「もう一度鉄に会いたい。あなたと結ばれることが私の願い。他には何も望まないわ。だから、姿を見せて。おねがい、鉄……!」
骨ばった手を桜の幹に置く。咲が呼びかけた瞬間、辺りの景色が変わった。
視界が開ける。
眩い光に目を細めると、そこは花の海だった。
辺り一面は満開の桜だ。咲の頭上は淡い桃色の花で埋め尽くされ、地面には足首が埋もれるほどの花びらが隙間なく敷き詰められている。立ち尽くす咲の周りで、花の雨が静かに降っている。
ここは暖かい。瑞々しい花の芳香が、咲の痛みを和らげた。
「……さき」
桜みちの向こうから鉄が姿を現す。恋い焦がれた男の姿を認め、咲は涙を溢れさせた。
足に力が入らず、その場に崩れ落ちそうになる咲を、鉄はしっかり腕の中に抱き留めた。彼の手はとても温かい。懐かしい温もりを感じながら、咲は子供のように泣きじゃくった。
「鉄、てつぅ……! どうして会いに来てくれなかったの? ずっと寂しかったのよ……!」
涙を流す咲を抱きしめながら、鉄もまた泣いていた。衰弱しきった咲の背を摩りながら、何度も済まねえと口にする。鉄は咲の顔をじっと見つめ、涙混じりの声で囁いた。
「一人にして悪かった。……でも、もう咲と一緒にいることはできねえんだ」
鉄の声がやけにはっきりと聞こえる。大きな目を潤ませながら、鉄は帰れとしきりに言った。
「咲も気がついてんじゃねえか? お前が死にかけてるのは、怨霊の俺と一緒にいたせいだ。なのに、どうして会いに来たんだよ。俺といたら死人になっちまうだろうが。だから早く――」
「いやだ! もう鉄と離れ離れになるのは嫌なの!」
咲は鉄に抱きついた。彼といたいと望んだ、あの十歳の夜のように。
「私はあなたを殺したわ。だから、今度は鉄に殺されたい。おねがい、私を一人にしないで。一緒に連れて行ってよ……!」
言葉にならない想いが胸から溢れる。心にもないことを言って鉄を突き放してしまった罪悪感に、胸が千切れそうになる。鉄と一緒にいられるのなら、死など全く怖くない。
「……咲。お前はそれでいいのか?」
戸惑いの声を絞り出す鉄の顔を見上げ、咲は微笑んだ。
「もちろん。あなたの傍にいることが私の幸せだから」
体が軽い。指先の感覚が無くなってきている。腕も足も、自分のものではない気がする。ただ愛する男の腕の中にいることだけが、唯一の感覚として感じられた。
「それなら……。一緒に行くか? 桜の国に。そこはあったけえし、痛みも苦しみもねえ。未練がなくなった俺は、そこに向かおうとしていたんだ」
鉄が桜みちの向こうを指差す。欠けていた左の人差し指が、今はその手に確かに存在していた。
「そこに行けば、今度こそ俺達は二人きりで過ごせる。どうだ、咲。俺と一緒に来てくれるか……?」
死者の誘いに、咲は笑顔で頷いた。
「うん、一緒に行こう。私を永遠に鉄だけのものにして」
鉄の胸に顔を埋める。もう何があっても手放してやらねえと呟く男を愛おしく思いながら、咲は懐から桜のかんざしを取り出した。
「わたしは桜になりたかった。鉄を虜にする女になりたかった。もう一度桜みたいだって褒めてほしくて、あなたを誘惑したの」
かんざしを差し出す。艶やかな笑みを浮かべながら、咲は自分の髪にかんざしを挿すよう鉄に頼んだ。
「ねえ、鉄。私はきれい?」
鉄の顔に優しさが満ちる。彼は咲の髪にかんざしを挿した後、彼女の頬を両手で包みこんだ。
「ああ、綺麗だ。お前は桜よりも綺麗だ」
鉄の顔が近づいてくる。桜の樹の下、無数の花びらに包まれながら二人は口付けを交わした。
「愛してる、咲。俺達はずっと夫婦だ。もうお前を放さねえ」
花吹雪の中、体がゆっくりと溶けていく。
溢れんばかりの幸福を感じながら、咲は鉄と共に桜みちの向こうを目指した。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
朝日が差し込む頃、桜の大樹の下で息絶えた咲が見つかった。
不思議なことに、血桜は一夜にして散り果てていた。冷たい娘の体を包み込むように、赤い桜の花びらが積もっている。鉄の処刑から半年後に訪れた咲の死に、女中たちはお嬢様は鉄に連れて行かれたのだと囁きを交わした。
咲は寺に葬られるはずだったが、葬儀の日が迫るにつれ、屋敷の住人たちはまた不吉な夢にうなされるようになった。首なしの大男が咲の棺を強く求め、絶望に満ちた声で嘆き続ける夢だ。
中庭の桜の下から、何か引っ掻くような音が聞こえる。下人たちが恐る恐る桜の根元を掘ると、土の中から一対の手の骨が突き出ていた。まるで、咲の体を待ち望むように。
鉄の怨霊を鎮めるために棺を桜の根元に埋めると、奇妙な音はぱたりと止んだ。
そして、その次の年から、桜は一際美しく咲くようになった。見る者を魅了する華やかな佇まいは都中の評判となり、多くの者が桜を見ようと屋敷を訪れた。
時折、黄昏時になると、桜の木の下で寄り添いあう男女の幻が見える。
あれは武家の娘と下人の男だ。彼らはきっと死んだ後に結ばれ、ああして桜の下で愛を囁き合っているのだろう……。人々はそう噂をし、江戸一番の花の美しさを称えるのだった。
都の出入り口に設けられた高札場、その隣に掲げられた梟首を見つめる女がひとり。
霧の向こうに、男の晒し首が見える。あんなものを見てはいけないと女中が咲の目を覆ったが、咲は黙って手を払い、なおも死者の顔を凝視し続けた。
あれは確かに鉄だ。咲の使用人だったその男は、武家の娘である咲を犯し、死罪に処せられた。
そう、鉄は死んだ。自分は彼の首が落とされる様を確かに目にした。
ならばあれは。自分の体を嬲るあれは、いったい……。
――覚えてろよ咲! 死んでもお前を俺のモノにしてやるからな……!
鉄の最期の叫びが蘇る。そして、この体を襲う悍ましい感覚も。
重苦しい沈黙の後、咲は何も言わずに踵を返した。屋敷に着くと人払いをし、そのまま自分の座敷に引き籠もってしまった。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
咲は十の頃、人攫いに遭った。悪しき野盗が、武家の娘を使って金をせしめようとしたのだ。暗闇に包まれた街道で衣を剥ぎ取られる。咲が男の下で震えていると、突如低い声が響いた。
「俺の縄張りで何してやがる、退け」
血飛沫が舞う。頽れた野盗の背の向こうを、咲は呆然と見上げた。
視線の先、大柄の男が立っている。男は表情ひとつ変えずに斬り捨てた野盗を見下ろしたが、咲を見て目元をひくつかせた。
「ち、ガキかよ」
咲が助けを乞う視線を送ると、男はばつが悪そうに顔を背けた。
「仕様もねえ。金を奪い取って酒に替えちまおうと思ったのに、こんなガキひとり攫ったって何にもならねえぜ」
「ま、待って、おねがい」
背を向けた男の足を掴む。男は咲を蹴り飛ばそうとしたが、彼女が涙を流しているのを認めて急激に怒気を引っ込めた。
「くそ、面倒くせえな! ……おい、お前はどこから来たんだ」
男は優しく咲を抱き上げた。彼の手はとても温かい。緊張の糸が切れた咲は、男に縋りつき声を上げて泣いた。
舌打ちを繰り返した後、男は咲を助けてくれた。
俺は物取りだ。奉行がいる都になんざ近づきたくねえ。俺が疑われると困るから、早くそれを直せ――男は咲の衣を整え、咲の家まで運んでくれたのだ。
都は大騒ぎになっていた。攫われた武家の娘と、彼女を背負って現れた大男。集まった者は男に対し尖った目を向けたが、咲は自分の恩人なのだと懸命に男を庇った。
前科者の入墨が彫られた腕。ぎょろりとした大きな目、険しい表情、頬に刻まれた刃傷痕、人差し指を欠いた左手。筋骨隆々の体は日に焼けて浅黒く、割れた顎には短い無精髭が生えている。
男はどんな生活を送ってきたのか、一目で分かるような荒っぽい出で立ちをしていた。
咲は男をたいそう気に入り、彼と共にいたいと望んだ。武家の娘と卑しい罪人を一緒にしておくなど、本来あってはならないことだ。だが咲の父は豪放磊落な武士であったので、娘の恩人を使用人として迎え入れることにした。
物取りの鉄。流れ者の男は、武家に仕える下人となった。咲よりも八つ上の鉄は、口が悪く粗野な男であったが、咲にだけは笑みを見せた。鉄は咲をお嬢と呼び、親切な使用人として振る舞ってくれた。
それが、咲と鉄の出会いだった。咲は鉄を兄のように慕い、淡い初恋の情を抱いた。
❀
咲は毎日鉄の側にいた。針仕事をしながら、庭木の手入れをする男を見るのが好きだった。
罪人ゆえに周囲から下衆と評される鉄だったが、その佇まいは堂々としていて、武家の屋敷にもよく馴染んでいる。咲は頭の天辺から爪先まで鉄のことが気に入っていた。鉄はよく見れば顔が良く、咲にとって優しい男だったからだ。
「鉄、こちらに来て」
縁側に座って呼びかければ、鉄はすぐに咲の傍に来てくれる。咲は荒れた鉄の手を取り、そっと親指でなぞった。荒仕事で鍛えられた硬い手は、咲のものよりもずっと大きい。指を絡ませると、鉄の肩がぴくりと動く。
「……お嬢、そんな風に俺の手を触るんじゃねえ」
「どうして? 鉄の手はとても温かいから触りたくなる」
「俺みてえな下人にべたべた触ったら穢れるぞ」
「よしてよ。ここには私たちしかいないのだし、あなたに触れてもいいでしょう? あなたのことは兄さまのように思っているのよ」
「はん。お嬢は変わり者だな」
つっけんどんな言い方をしながらも鉄は嬉しそうだ。それに気を良くした咲は、彼が止めるのも構わず肩を寄り掛からせた。鉄の体から、ほんのりと汗の匂いが漂う。咲は日向を思わせるこの匂いが大好きだった。
咲の座敷に続く縁側は二人の交流の場所だ。彼らは共に座り、中庭に咲く四季の花々を楽しんだ。
咲が十四を迎えた年の、ある春の日のことだった。満開の桜の大樹を見て、鉄はその美しさを褒め称えた。屋敷の庭には様々な花が植わっていたが、鉄は特に桜が好きなのだと言う。
「桜? 鉄は椿を好むと思っていた」
「そりゃどうしてだい」
「椿は首から落ちる様が潔いでしょう」
「そんな打首みてぇな花は嫌いだ! 花は花らしく、散る様が派手な方がいいだろうが」
はらはらと舞う白い花びらを眺めながら、鉄は浮かされた様子で呟いた。
「流れ者だった頃の俺は、酒を飲みながらよく山桜を眺めたもんだ。ああ、桜ってのは綺麗だなあ、満開の風情も、ああやって散る様も好きだ。花なんざどうでもいいけどよ、桜だけは別だった。あの有無も言わさねえ美しさが好きなんだ。こんな捻くれ者の俺でさえ言葉を失うんだ、男を狂わせる美女ってのがいるなら、それはきっと桜みてえな奴なんだろうさ」
桜について話す鉄は珍しく饒舌だ。鉄は年を経る毎に咲の前で無口になっていったが、この日ばかりは頬を緩め、酒に酔ったように言葉を重ねている。ふと、咲の手が優しく握られた。
「お嬢は桜みてえだな」
鉄がそう褒めてくれたことが嬉しくて、咲は頬を染めて俯いた。咲は気恥ずかしくて堪らなくなり、急いで縁側を後にしたが、胸の内では鉄の言葉をいつまでも覚えていたいと思っていた。
もっと綺麗だと褒めてほしくて、咲は鉄の前で紅をさすようにした。新しい着物は必ず鉄に見せ、髪には彼がくれた桜のかんざしを挿した。
しかし、咲が十五を過ぎた頃から、鉄の態度が変わり始めた。鉄は咲が話しかけても素っ気なく、二人きりにならないように避ける。咲は困惑し、自分の振る舞いが嫌われるほど浅ましかったのかと後悔の涙を流した。
毎日髪に挿すかんざし。桜のつまみ細工が可愛らしいそれは、鉄にねだって買ってもらった安物だ。鉄がかんざしを挿してくれた時、彼は何か言いたげな顔をしていた気がする。鉄が距離を置き始めたのは、ちょうどその頃からだった。
江戸中の評判になるほど美しく育った咲のもとには、日々縁談の話が舞い込んでくる。いずれ他家に嫁がなければならないという現実に、咲自身もやがて向き合わざるを得なくなった。
自分と鉄には身分の隔たりがある。どんなに鉄が好きでもこの恋は叶わない。想いを寄せる男の冷たさに胸を痛めながらも、鉄と一緒にいることはできないのだと自分に言い聞かせる。
そして、咲と鉄が縁側で過ごすことはなくなった。共に花を眺めた日々は過去のものとなり、二人の間には深い溝が刻まれた。
❀
咲が十六の頃のこと。寝付けなかった咲は、春の夜風を楽しみながら真夜中の庭を歩いていた。灯りに照らし出された夜桜は、どこか妖しい魅力を誇っている。
あの有無も言わさねえ美しさが好きなんだ、と鉄は言っていた。桜は狂気の花、心の内を映し出す鏡だ。昼は清らかで夜は魔性を帯びる。その佇まいは毒を含む美しさを湛え、胸底に秘めた想いを解き放ちたくなる衝動を呼び起こす。鉄が桜を男狂わせの女に喩えたのも、何となく頷ける気がした。
桜を眺めていた時、使用人が住まう長屋の方から音がした。気になった咲が近づくと、窓の向こうに鉄の姿が見えた。人が寝静まる時間に、いったいあの男は何をしているのだろう。そっと覗き込むと、鉄は大事そうに抱えた木箱の蓋をゆっくりと開いた。
鉄が何かを取り出す。
それは咲の櫛だった。失くしたと思っていたものだ。
鉄は櫛を指でなぞった後、目を閉じて深く息を吸い込んだ。肩を上下させながら女の匂いを肺に取り込み、唇を押し当て、生きた肌に触れるように何度も撫で回した。
咲の帯紐、手鏡、髪の毛……男は箱の中の品に同じことをした。貪るように匂いを嗅ぎ、丹念に唇を這わせる。時に歯を立て、時に舌を絡ませながら。咲に対する真っ直ぐな愛情と、決して手に入らぬ女への狂おしい執着が鉄の体から滲んでいる。熱が籠もった様子で品に求愛をする男の目は、異様な輝きを放っていた。
「……っ!」
見てはいけないものを見た気がして、咲は急いでその場を離れた。荒い息を吐きながら座敷に戻る。すぐさま布団に潜り込み、今しがた見た光景について反芻した。
鉄は密かに自分の物を集め、あの木箱に仕舞い続けていたのだ。主の持ち物を持ち去った挙げ句、あんな風に扱うだなんて……!
「……っ、ああ……」
漏れ出た困惑の声は甘い。咲は自らの声色に驚き、慌てて口を覆った。
あのような劣情を向けられたら、気味が悪いと思う女が大半だろう。だが咲は少しも嫌だとは思わなかった。むしろ、身が蕩けるほど嬉しかったのだ。
鉄の舌が自分の首筋に這わされたら。熱っぽい目で見つめられ、好きだと囁かれたら……。その時自分はどうなってしまうのだろう? 嬉しくて、きっと桜のように散ってしまう。
「鉄。あなたも好きだと思ってくれていたの?」
あの男は自分を嫌って避けた訳ではない。自分を愛しているからこそ、叶わぬ想いを必死に飲み込み続けてきたのだ。昼は冷たく距離を置くのに、夜は熱っぽく自分を呼ぶ鉄の姿。その二面性に甘い切なさが込み上げる。自分だけが苦しかった訳ではないのだと知って、胸が締め付けられた。
「……私、どうしても鉄が好き」
結ばれないと分かっていても、鉄の気持ちを知ったら我慢なんてできない。鉄と触れ合いたい。その思いだけが咲の頭を支配する。
あの男は身分の差に悩み、決して自分に近づこうとはしない。ならば、鉄が我慢できなくなるように仕向けてしまえばいいのだ。どうせ他家に嫁がなければならないのだし、最後くらい鉄と心を通わせたい。この恋を散らすなら、桜のように派手に散らしたい。
崩れていく。
武家の娘としての矜持が。
下人に対する主としてのあり方が。
年頃の娘としての慎みが。良識が。理性が。
あの男と触れ合えるなら、もうどうなってもいい。
――男を狂わせる美女ってのがいるなら、それはきっと桜みてえな奴なんだろうさ。
この身は桜になれるだろうか。鉄が言った、男を狂わせる女のようになれるだろうか。
❀
「鉄、私の座敷に来て」
黄昏時、庭木の手入れをしていた男の腕を、咲はぐっと掴んだ。鉄が肩を跳ね上がらせる。咲に怪訝な顔を向け、彼は唸るような声を漏らした。
「放してくれねえか。人に見られたら良くねえ」
「あなたが大人しく来てくれたら放してあげる」
咲は微笑みながらも、瞳に力を込めて鉄を見据えた。鉄はためらっていたが、周囲に人の気配がないのを確かめると小さく頷いた。
座敷の周辺はあらかじめ人払いをしてある。静まり返った座敷の中に大男を押し込み、咲はふうと息を吐いた。
「やっと二人きりになれた」
「……お嬢、いったい何のつもりだ」
「肩が凝ってしまったの。あなたに揉んでもらおうと思って」
甘い声で鉄を誘うが、彼は険しい顔をして離れようとする。女中に頼めばいいだろうがと呟く男に、咲は眉を跳ね上げた。
「これは命令よ。主の言う事が聞けないの?」
身分の違いを初めて武器に使う。わざと冷たく言い放つと、鉄が驚きに目を見開いた。
「ねえ、早く。あなたにしてほしいの」
咲は微笑みながら衣をくつろげた。襟元が緩み、色白の首筋が露わになる。髪がひとすじ肩を滑り落ち、その艶やかな流れに鉄の目が釘付けになった。咲は着物の裾をわざとたくし上げ、座布団に腰を下ろした。裾から覗く足首が、夕日を浴びて淡く色づく。
「さあ座って。丁寧に揉むのよ」
咲が鉄の腕に手を這わせると、男の大きな体が硬直する。鉄は震える指で、おそるおそる咲の肩に指を食い込ませた。
温かな手に肩を解されると、何とも言えぬ心地良さが広がっていく。もっと強くと咲が命じると、鉄は指に力を入れた。
「ぁ、いい……わ。鉄の指、きもちいい……」
咲は背を丸め、前に首を傾けた。咲のうなじを見た鉄の呼吸が荒くなる。随分と分かりやすいものだと可笑しく感じながら、咲は久方振りの男の温もりを存分に味わった。
「てつぅ……ね、そこをもっと揉んで。あなたの手で気持ちよくしてほしいの」
どこか淫らさを帯びる、甘く砕けた物言い。髪の隙間から覗く女の肌が桜色のように紅潮しているのを認め、鉄は嗚咽のような声を漏らした。
「っ、……くっ、お嬢、こんなのあんまりだ! もう――」
その先を遮り、咲は鉄に向き直った。男の前で着物の裾をめくり上げる。瑞々しい腿を見せつけながら、咲は高揚感のまま命じた。
「次は足を揉みなさい」
その言葉に鉄の顔が険しさを増す。咲が足を男の手に押し付けると、鉄は観念したように息を吐いた。
女のふくらはぎに触れた時、鉄の瞳にじわりと闇が広がった。遠慮がちだった指の動きは、枷が外れたのか大胆なものに変わっていく。大きな手が咲の足を摩り、揉みしだく。鉄は黙したままだが、彼の荒い息遣いは男の内に秘めた獣欲をはっきりと物語っていた。
何か言いかけては飲み込むその様子に胸の奥が熱くなる。好きな男が言葉を失うほど自分に溺れていると思うと、咲の心臓はこの上なく高鳴った。
「もう結構。明日も黄昏時に来て。必ずよ」
咲はそう言って、戸惑う男を部屋から追い出した。障子が閉まると同時に、体の力を抜いて座り込む。鉄を誘惑できた悦びに唇が歪んでしまう。男の顔を思い出すと愉快で堪らず、このまま大きな声で笑い出したい気分だった。
その夜、咲はまた鉄の様子を見に行った。窓の向こうの彼は、咲の櫛をじっと見据えている。男の額には冷や汗が浮かび、唇は震えていた。
「くそっ、俺の気持ちも知らねえで、よくも! 咲、咲、さきぃ……!」
櫛に鉄の舌が這う。粘りつく男の愛執を確認しながら、咲は桜の雨の中、妖艶に笑った。
❀
鉄が堕ちるのは早かった。それほどまでに彼は咲への想いを堪え、とうに我慢の限界に達していたのだ。
黄昏時になると鉄は咲の座敷を訪れ、彼女が命じるまま肌に手を這わせた。主を癒やすための奉仕は、段々と情欲を満たすための愛撫へと変わっていった。ひと月過ぎれば鉄の指から躊躇いは消え失せ、三月過ぎる頃には自ら女の内腿に唇を落とすまでになっていた。
「ふうっ、は、ぁっ……ん……てつ、ぅ……」
「お嬢、お嬢……。ああ、お嬢の肌は本当に綺麗だ」
白肌の上を赤い舌が這う。毎夜女の櫛にしていたことを、今や鉄は己の主にもしていた。
もはやこれは男と女の情事だ。身を繋げていないとはいえ、薄布一枚という格好で互いの体を擦り合わせているのだから。
鉄の目には、女を今にも喰らわんとする獰猛な光が宿っている。咲はその険しい顔に胸をときめかせた。自分は彼の主だとはいえ非力な女だ。鉄が先を望めば、この身は呆気なく明け渡されてしまう。
硬いものを腹に擦り付けられるたび、奥から蜜が溢れ出す。未通女だとはいえ、鉄が何を求めているのかよく分かる。咲は鉄の背に腕を回し、彼の耳元でもっと、と囁いた。
咲は鉄に好きだと言ってほしかった。鉄から想いを伝えてほしかった。
鉄は主に対する劣情を抑え続けてきた男だ。こちらから好きだと伝えても、何かと理由をつけて逃げていくのは分かりきっている。それでは駄目だ。理性を捨て去るほど愛に狂ってほしい。
鉄がもう一度桜みたいだと褒めてくれたら、それだけでこの憂き世を過ごしていける。鉄と心を通わせられたら、好きでもない男に嫁ぐ苦痛も我慢できるから。
「鉄、私の名を呼んで」
甘い声で懇願する。咲が鉄の唇を指でなぞると、彼ははっとした顔で咲から離れようとした。
「逃げないで。呼んでくれるまで放さない」
「お嬢、それは駄目だ。俺みてえな奴が名を呼ぶなんて……」
「命令なんて言葉はもう使いたくないの。お願い」
自分は桜にならなければいけないし、鉄にはもっと狂ってもらわなければならない。心を通わせ派手に散ってこそ、初恋に止めを刺せるのだから。
咲が熱っぽい視線で鉄を見つめると、彼は険しい顔を崩し、今にも泣き出しそうな顔をした。
「卑怯だ、俺がどんな思いで堪えていたか知らねえくせに……! さき。……咲。咲、さき……!」
一度口に出すと止められなくなったのか、鉄は何度も咲の名を呼んだ。首筋に熱い舌が這わされる。性急な愛撫に咲が微笑むと、鉄が顔を近づけてきた。
どちらからともなく唇を合わせる。大好きな男と口吻しながら、咲は恍惚の極致を味わった。
鉄はまだ想いを打ち明けてくれなかった。昼間の鉄は相変わらず素っ気ない。彼はあくまで使用人としての距離を保とうとしている。
だが、鉄は少しずつ変貌している。黄昏前に咲が廊下を通れば、障子の隙間から狂気混じりの視線が覗く。日毎に昏くなっていく異様な眼の光沢。肌を焼き、心の奥を穿つ男の眼差し。獲物をつけ狙うその瞳は、思わず咲が震えてしまうくらい強烈な愛執を滲ませていた。
黄昏時になれば咲を愛撫し、咲が立った床を撫で、咲が座った座布団の残り香を嗅ぐ。夜中、鉄は咲の私物を撫でながら自慰までするようになった。
咲はもどかしかった。どうすれば鉄から想いを告げてもらえるだろうか。鉄に好きだと言われたい。その願いが叶わぬのならいっそ、共に果ててしまえたら……。
ほの暗い気持ちを抱きながら、咲は鉄への想いを燃え上がらせ続けた。
❀
ふと、正気に返った。
もしこの関係が明るみに出たら、鉄が死んでしまうと。
咲がそう思い至ったのは十七の時だ。とうとう他家に嫁ぐ話が決まり、使用人総出で咲の嫁入り支度が始まった。ある日、咲が廊下を歩いていると女中たちの囁き声が聞こえてきた。
「茶屋の娘が鉄にお熱だってさ。あいつの婿入り支度も必要かね」
「はん、鉄はお嬢様にしか興味がないって知ってるだろ」
どくりと胸が跳ねる。咲は女中に気付かれないよう耳をそばだてた。
「聞いたかい、鉄がお嬢様に惚れた男を片っ端から酷い目に合わせてるって噂! やだよお、あの男。お嬢様を舐め回すような目で遠くから見張ってるんだもの。あたしゃあの目が獣のようで、恐ろしくて仕方ないよ」
「あいつも諦めの悪い男だね。もしお嬢様がいいって言っても、手を出したら死ぬのは鉄だけなのにねえ」
目の前が暗くなる。咲はそっとその場から離れ、ふらふらと自分の座敷に戻った。
座り込み、底冷えするような自分の愚かさを恥じる。夢が覚めた後にやって来たのは、自分が犯した罪に対する凄まじい恐怖だった。
「……なんて、愚かなことを」
あの女中の言う通りだ。鉄を狂わせて何になるというのか。既に前科者である鉄は、主と通じたと知られたら死罪になるだろう。
鉄のことを大切に思うのならば、この気持ちに蓋をして彼と接するべきだった。既に自分と鉄の関係は噂されている。これ以上鉄と仲を深めては彼の命が危うくなってしまう。
鉄の感情が日毎に強くなっていくのを感じる。劣情を宿す男の目は愛おしくも、時折寒気がするほど怖ろしかった。
もう迷っている時間はない、鉄がこれ以上想いを膨らませる前に、今すぐどうにかしなければ。愚かな女の初恋から、今すぐ鉄を解放してやらなくては……。
咲は震える指で、髪に挿している桜のかんざしを抜いた。鉄が贈ってくれたその品を、涙に霞む目で見つめる。別れの口付けを一度した後、二度と目に触れぬように棚の奥深くに仕舞い込んだ。
それから咲は、徹底的に鉄を避けた。
座敷を訪ねてくる鉄を跳ね除け、もう来なくていいと言い放つ。それでも次の日にやって来る男を拒絶し、ついには顔を合わせることすら許さないと命じた。
「なあ、教えてくれよ。いったい俺のどこが気に入らねえんだ!」
今日も鉄の懇願が耳を打つ。深い悲しみが滲む瞳を見ていられず、咲は静かに目を閉じた。
「さき、なんでそんな態度を取るんだ? 俺が嫌になっちまったのか……?」
「私の名を口にするなと言ったでしょう。もう近づかないで。これは命令よ」
咲は鉄を一瞥し、背を向けた。
桜のかんざしをしていない後姿を、男がどんな形相で見つめているのか知らないまま。
❀
嫁入りを三日後に控えたその夜、咲の座敷に鉄がやってきた。障子扉を勢いよく開き、驚く咲の傍にどかりと座り込む。鉄は無言のまま、眼光鋭く咲を見据えた。
屈強な男から発せられる怒りに咲の肩が震える。逃げようとすると、鉄が素早く伸し掛かってきた。
「っ、鉄! やめなさい!」
「咲ぃ、やっと俺の名前を呼んでくれたじゃねえか。そうやって甘い声で鉄って呼んでほしかったんだ。なあ、もっと呼んでくれよ。その可愛い声で何度も、何度も、何度も」
粗野な下人の顔が、恋と劣情を湛えた男の顔に変わる。その一瞬の変容が怖ろしく、咲は息をすることさえ忘れた。
咲の首筋に鉄の顔が近づけられる。熱い吐息から逃れようとするが、大きな手が腕を掴んで離さない。咲の耳元に、男の掠れた声が落ちた。
「さき、もし俺と心が一緒なら、咲から想いを伝えてくれ」
「……え?」
「俺は卑しい前科者だ。そんな俺を受け入れてもいいと思ってくれるなら、咲から好きだと言ってくれよ。心を通わせる赦しをくれ」
その告白が嬉しくて、咲は目が潤むのを感じた。もうすぐ鉄の温もりを感じることができなくなるのだと思うと、胸が張り裂けそうになる。
だがそれでも、鉄を救うためには。
「咲、お願いだ! 咲が他の男に嫁ぐと思うと、死にてえくらい辛いんだ。咲と心を通わせられたら、それだけでこの世を生きていける。だから、頼む……!」
鉄は本気でそう思っているのだろう。だが、二人の心が通じれば通じるほど、お互い己の欲望に勝てなくなる。そうして鉄は死に向かって歩み始めるのだ。それだけはどうしても避けなければならない。
今から吐き出す言葉で、鉄は自分を憎むだろう。
それでもいい、彼が生きていてくれさえすれば。
「……出過ぎた真似もいい加減にしなさい。私が穢らわしい下人に惹かれる訳がないでしょう? 旦那様と褥を共にする練習台に丁度良かったから、あなたに声をかけただけ」
血の味がする。心が血を流している。
蒼白な顔で唇を戦慄かせる男を見上げ、咲はわざと酷薄な笑みを浮かべた。
「男の人って案外可愛いのね、こんな未通女に本気になってしまうのだから。あなたをからかうのは楽しかったわ。おつとめご苦労さま」
鉄の目から光が消える。咲の言葉は、男の心を深く抉ったかのようだった。大きな体がぶるぶると震え始める。
「……練習台、だと?」
罪悪感に苦しみながらも、咲は決して微笑みを崩さなかった。この表情を崩せば、全てが無駄になる。
「そう。だからもう来ないで。あなたの役目は終わったの」
咲が冷たく言い放つと、鉄の顔が大きく歪んだ。彼は獣のような呻き声を漏らし、指が真っ白になるほど力を込めた拳を咲の横に叩きつけた。
「咲ぃ、さぁきぃッ! 俺はずっと咲のことを想っていたのに、お前はそんな酷いことを考えて俺を誘惑したのか!? だからかんざしを外したんだな!? 俺が贈った、あのかんざしをっ――」
鉄は言葉を途切れさせた。瞬間、鉄の手が咲の首に伸びる。咲が悲鳴を上げる間もなく、襟元が乱暴に掴まれ、怖ろしい程の力で衣が暴かれる。咲は恐怖に目を見開き、思わず涙を溢れさせた。
「やっ、やめて! 鉄!」
男の唇が醜く歪む。怯える女の耳を舐め上げ、鉄は怒りを押し殺した声で囁いた。
「どんなに泣いたってやめてやらねえよ。咲が俺を狂わせたんだ! お前があんな風に俺を誘わなければ、何とか我慢できたはずなのに……!」
窒息するような口吻に咲の視界が揺らめく。男の唇に歯を立てると、彼は咲の顔を睨みつけた。
「仕方のねえお嬢様だ。おい、お前が何をしたって無駄だぞ。他の男のものになるくらいなら、俺が手酷く散らしてやる!」
……それからのことは、もう思い出したくない。
鉄は咲を凌辱した。だが、男の顔に快楽の色が浮かぶことは一度もなく、彼は涙を堪え、辛そうな顔をしていた。鉄は組み敷いた娘を傷付けながら、己の心もずたずたに傷付けていたのだろう。
咲を穢した後、鉄はすぐさま主人に自白をした。物取りの前科に加え、武家の娘を強姦したとあれば、鉄の運命は決まっている。咲は鉄を引き渡さないでくれと父に懇願したが、父は娘の頼みを二度聞くことはなかった。
咲は飲まず食わずで訴え、必死に鉄の処刑を止めさせようとしたが、鉄の運命は覆らない。
そして数日後、鉄は打ち首に処された。処刑前の彼は力なく項垂れていたが、刑場に来た咲が大声で鉄を呼ぶと、ぱっと顔を上げて叫んだ。
「覚えてろよ咲! 死んでもお前を俺のモノにしてやるからな……!」
愛憎交じる狂気の叫び。咲が声を上げる間もなく、すぐに男の首が落とされた。
血の花が咲く。刀から赤い桜の花びらが舞い落ちる。咲を穢した男の死に様は、あまりにも呆気ないものだった。
✿
嫁入りは破談になった。人目を避けるため、咲は屋敷に籠りがちになった。
鉄と引き離された日から一睡も出来ず、食事も喉を通らない。日毎に咲は痩せこけ、顔色も悪くなり、美しいかんばせから生気が失われていった。
泣き続けたせいか肺が痛み、咳が止まらない。涙混じりの声で、咲は鉄に謝り続けた。
「鉄、ごめんなさい……。あなたが死んだのに、私がまだ生きているのはどうして?」
鉄の首に刀が振り下ろされた瞬間、咲は己の魂も引き裂かれたのを感じた。散り果てた花のように心が枯れている。苦痛の涙が頬を伝い、咲は床を叩きながら愛する男の名を呼んだ。
咲は鏡も見なくなった。綺麗だと褒めてくれた男はもうこの世にいないのだ。自分がどんな醜い姿になろうが、どうでもよかった。
……鉄が死んだ翌夜から、奇妙なことが起こり始めた。
秋の時節なのに、中庭の桜が突然花を咲かせたのだ。季節外れの満開の桜を、誰もが気味が悪いと怖れた。桜の花は赤く色付いていたからだ。舞い散る赤い花びらは、悍ましい血の飛沫を思わせたので、使用人たちはそれを「血桜」と呼んで怖れた。
血桜の開花は不吉の前兆だった。誰もいない場所から足音がし、畳が軋む。ふとした瞬間辺りの温度が下がり、背筋を冷たい何かに撫でられる。咲は、目に見えぬ何かの悍ましい視線を頻繁に感じ取った。
咲だけではなく、屋敷に住む誰もが奇妙な足音を耳にした。咲と鉄の仲を噂していた女中は、酷い悪夢を見たと言って床に臥せってしまった。
自分は鉄を見た。あの血桜は鉄の怨霊が咲かせた。この世に未練を遺した鉄が、皆を呪おうと屋敷に取り憑いたのだ……女中は真っ青な顔をしながらそう呟いた。
特に呪われたのは咲だ。黄昏時になると、何かが彼女の体を犯すようになった。
金縛りにあったかのように身動きできない。憎しみを滲ませたそれは咲の体をがっちりと組み敷き、肌を性急に撫で回す。女穴に大きなものを突き挿れられ、声を上げれば無理やり唇を塞がれる。欲を遂げながら、何かは咲の首をぎりぎりと絞め上げた。夜が明けると咲の全身には鬱血痕が浮かび、秘所からは大量の精が溢れ出た。
悍ましい体験だが、咲は奇妙な懐かしさを感じていた。手つきが鉄のものに似ていたからだ。
鉄は憎悪のあまり怨霊になってしまったのだろうか。
自分を陥れた娘を痛めつけるため、こうしてやって来るのだろうか。
それなら、それでいい。自分にできることは、抵抗をせずに鉄を迎え入れることだ。自分は鉄を誘惑し、死に追いやるという罪を犯した。あの男に少しでも報いることができるならば、いくらでもこの身を捧げよう――咲はそう考え、涙を流しながら霊に抱かれた。
鉄の手は温かかったのに、今や寒気がするほど冷たい。怨霊から伝わる殺意を感じながら、咲はこのまま死んでしまいたいと考えた。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
首は三日晒される。その後は棄てられ、如何なる者であろうとも弔いは許されない。処刑後、鉄は彼の世で物取りできないようにと両手を落とされた。そのため、咲は密かに鉄の手を持ち帰ろうと決めた。
人気のない明け方、咲は河原に打ち捨てられた男の遺体を見下ろした。
大きな体の傍に、人差し指を欠いた手が転がっている。青白い手は人形のように冷たい。持ってみると、ずしりと不気味な重さを感じた。
「……帰りましょう、鉄」
咲は鉄の両手を布に包み、屋敷に戻った。
中庭の桜の根元に、鉄の両手を埋める。彼が好んだ桜の下ならば、安らかに眠れるかもしれないと考えたのだ。鉄の手に土を掛けながら、咲は彼の笑顔を思い出した。
「あなたの気持ちに応えられなくてごめんなさい。私は鉄のことが大好きだった。愛するあなたと思いを通わせたくて、あんなことをしたの」
ぞっとするほどの冷気が満ち、赤い桜の雨が降り落ちる。嘘を吐くなと言わんばかりに何かが咲の首を絞めたが、咲は涙を流しながら言葉を続けた。
「鉄が私に溺れていくのを見るのは嬉しかった。でも、もしこの関係が明るみに出たら、死ぬのは鉄だけだと気がついたの。だからあなたを突き放した。鉄が死んだのは、私のせい」
初めての恋は、派手に散る前に腐ってしまった。本当の想いを伝えられないまま、愛する男は死んでしまった。
「だから、気が済むまでこの体を暴いて。あなたになら何をされても構わない」
懐から桜のかんざしを取り出し、髪に挿す。
そこにいる彼に向けて、咲は黄昏時に来てと囁いた。
✿
その夜、また霊はやって来た。
見えない手が咲を拘束し、衣を暴く。だが昨夜までと違うのは、その手つきが少しだけ優しいことだ。首を大きな手に掴まれるが、それ以上力が込められることはなかった。
咲は違和感を覚えた。今宵の霊からは強烈な殺意を感じない。今までとは明らかに異なる振る舞いに、咲の心が切なく揺れる。
「鉄? やっぱり、あなたなの……?」
返事はないが、そっと唇をなぞられる。それは肯定の証のように思えた。
咲は顔を歪め、暗闇の中で鉄の姿を捉えようとした。どんなに目を細めても何も見えない。愛する男の姿を想像しながら、霊の存在を掴もうと手を伸ばす。指先が何かに触れた気がしたが、その感覚はすぐに消えてしまう。
霊となってまで会いに来てくれたのだから、もっと鉄のことが欲しい。咲は甘い声で鉄を求め、この身にあなたの存在を刻みつけてくれと囁いた。咲の腰が撫でられる。衣と肌の隙間に差し込まれた手は、昨日よりも温かく感じられた。
乳房が揉まれ、先端に口付けられる。見えなくても、鉄が口をすぼめながら乳首を吸っているのが分かる。彼の赤い舌が己の肌を這い回る想像をして、咲は背が震えるほどの恍惚に溺れた。
優しい愛撫に咲の秘所が綻んでいく。敏感な女芯を指の腹でくるくると撫でられ、咲は今まで出したこともない艶やかな嬌声を上げた。
「あっ、っん、あはあぁ……」
咲はうっとりと顔を蕩けさせ、鉄がもたらす甘い快楽に浸った。女の反応を愉しむように、鉄の指が執拗に動き回る。彼は溢れ出る蜜を陰核に塗りつけ、太い指で膣をかき回した。
女の秘所が濡れそぼった頃、鉄は咲の瑞々しい腿を割り開いた。ぴり、とした甘い痛みの後、咲の肌に赤い花びらが散る。咲が笑みを浮かべると、鉄はそそり勃ったものを女穴に突き挿れた。
「ふあっ、は、ぁっ……。んぐ、てつ、ぅ……!」
隘路がみっちりと割り開かれる。大柄な鉄は男根も逞しく、受け入れると少しだけ息苦しい。心配するように自分の頬を撫でてくる鉄が愛おしくて、咲は涙を浮かべながら微笑んだ。
「ふ、ふふっ……。大丈夫、痛くないわ。鉄の好きなようにして……」
遠慮がちに腰が動かされる。咲の様子を伺いながら行われる抽挿は、段々と勢いを増していった。咲の秘部からぐぷ、ぐぷと淫らな水音が響く。やがて最奥に男の精が放たれ、ほのかな温かさがじんわりと広がった。
死んだ鉄がくれる、唯一の形あるもの。彼の精がとても愛おしい。虚空を見つめながら、咲はそこにいる男に向けて想いを伝えた。
「ねえ、知ってる? 私の初恋はあなたなのよ。鉄が桜のかんざしを贈ってくれた時、とっても嬉しかった」
切なさに涙が溢れる。ようやく想いを伝えられたのに、自分は二度と鉄の姿を見ることは叶わない。生と死の隔たりが、哀しくて仕方なかった。
「大好きよ、鉄。今も昔も、そしてこれからも……。ずっと鉄のことを愛しているわ」
空気が揺れる。自分を押さえつける気配が薄れ、どこからか慟哭に似た音が聞こえる。胸が抉れるような悲痛な叫び。鉄もまた、肩を大きく震わせながら泣いているのかもしれない。
咲は虚を抱きしめ、あなたと結ばれたかったと呟いた。
✿
霊とまぐわい始めてから二ヶ月が経った。
鉄は毎夜やって来る。姿は見えず、声は聞こえなくとも、咲は彼と恋人のように過ごした。縁側から血桜を眺め、褥を共にし、姿なき霊に「旦那様」と甘い声で呼びかけた。
咲の悔恨と愛情を信じたのか、鉄は憎しみを露わにしなくなった。娘に優しく口付け、その体をそっと抱きしめる。丹念な愛撫を施された咲の体は、すっかり女の悦びを覚えた。冬が近づく頃には鉄の大きな男根を難なく咥え込み、膣で絶頂を味わうまでに至った。
咲はとても幸せだった。歪な形でも、自分は大好きな男と結ばれたのだ。
だが、霊と深く交わるにつれ、咲を取り巻く呪いの気配は強まっていった。
始めは小さな異変だった。肉が落ちた咲の腕に痣が浮かび上がる。痣は日毎に大きくなり、やがて黒黒とした罪人の入墨を形作った。不気味な出来事はそれだけではない。咲が触れたものには必ず血の雫がこびり付く。茶碗や机を始め、床、障子にまで。咲がいる場には、悍ましい赤の花びらが散った。
咲は鏡を見ない。正確に言えば、鏡に映る自分の様子には目を向けず、鉄が体に残した痕跡を確かめるために鏡を使う。だから咲は、自分がどんなに異様な姿をしているのか気が付かなかった。
娘の肌は血を失ったかのように真っ白だ。全身に赤い指の痕が浮かび、首には手型が刻まれている。肉が落ちた体は濃密な死の気配を漂わせていたが、落ち窪んだ目だけは、爛々と生の輝きを放っていた。
お嬢様は呪われている。きっと、鉄の怨霊に取り憑かれてしまったのだ。女中たちはそう噂をし、咲を穢れた女として避けるようになった。
下人に凌辱された咲だが、それでも彼女に想いを寄せる者は後を絶たない。哀愁を帯びた横顔は一層の艶を増し、死に近い儚げな佇まいは幽玄の美として評判になった。桜のように美しい娘に魅入られた男たちが、咲に求婚をしようと次々に屋敷を訪れる。そしてその度、呪いは更に強まっていった。
咲に会いに来た武士が彼女の手を握ろうとした時、座敷の障子が乱暴に開け放たれた。風もないのにいきなり開いた障子に、男の訝しげな視線が向けられる。すると悍ましい殺気が辺りに満ち、男の体に耐え難い痛みが走った。まるで大きな手に、肩をぎりぎりと掴まれているかのように。
数日後、男は高熱に倒れた。彼の肩には真っ赤な手の痕が残っていたため、これは怪異の仕業ではないかと噂になった。
やがて、咲に近づく男たちに奇妙な災いが降りかかるようになった。ある者は夜道で首を絞められ、ある者は手足の骨を折り、またある者は悪夢にうなされ続け発狂した。そんなことが繰り返されたのち、咲に会いに来る者は段々と減っていった。
咲き誇る血桜、夜な夜な廊下を歩き回る足音、辺りに満ちる悍ましい冷気、夢に現れる大男。使用人たちは恐怖に怯え、次々と屋敷を去っていく。咲は怨霊憑きの娘と呼ばれ、父に座敷から出るなと命じられた。
そして、咲を蝕む呪いも勢いを増していった。
「けほっ、ごほ……」
咳が止まらない。
前から続いていたこの咳は、どんどん酷くなっていく気がする。鉄と引き離された時から食事らしい食事を摂っていないから、そのせいで元気がないのかもしれない。
咲は病的に痩せ細っていった。肺の奥が粟立ち、喉が引き攣れるように痛む。やがて咲自身も、床に血の花びらを散らすようになった。
喉が切れて血が滲む。乾いた咳がいつまでも止まらない。息苦しさを感じた時は、縁側に座って鉄の名を呼んだ。そうすると彼はすぐに来て、咲の背を撫でてくれた。
鉄に触れられている間は苦しみを感じない。背に温もりを感じながら、咲は愛しい男にありがとうと囁いた。
✿
咲の座敷には誰も近づこうとしない。静まり返った空間で、咲は愛する男と存分に過ごした。
黄昏時にやって来ていた鉄は、やがて昼夜問わず咲の傍にいてくれるようになった。彼と触れ合う度、見えぬ手の感覚がはっきりしていく。鉄との距離が縮まるのを嬉しく思いながら、咲は怨霊と体を重ね続けた。
雪深まる頃、咲は鏡に映る自分の後ろに見知った姿を認めた。
大きな目が印象的な、筋骨隆々の大男。体の輪郭は霞がかっているが、恋い焦がれた男の姿がそこにある。
「鉄……!?」
驚いて振り返るが、背後には誰もいない。だが再び鏡を見ると、確かに鉄の姿が映っている。男の表情は険しい。血走った瞳に憎悪を滾らせ、鉄は後ろから咲の体をぎゅうと抱きしめた。
『なあ、咲。お前は俺のモノだよな? なのに、どうしてまだ忌々しい男どもを寄せ付けるんだ?』
ぼやけた声が耳を打つ。霊となった鉄の声が聞こえたのはこれが初めてだ。咲が顔を輝かせると、鉄の姿が尚更くっきりと浮かび上がった。
男の温もりが咲の全身を包み込む。鉄は確かな体温、確かな形をもって咲に触れた。
『咲は俺の嫁だから手を出すなって言ったのに、まだ下衆どもがお前を狙ってるんだ。ああ、忌々しい。夜な夜な抱いて俺のにおいを擦り付けているのに、なんでまだ咲と二人きりになれねえんだ……!?』
頭の上から聞こえるぼやけた声は、生者と何ら変わらない。
生と死の境界が曖昧になるのを感じながら、咲はゆっくりと振り返った。
先ほどは見えなかった鉄の姿が、今は見える。男の頬に手を添えると、確かに触れた感覚があった。
「仕方のないひと。そんなことを考えていたの? 私に会いに来る殿方はもういないわ。鉄が全員追い払ってしまったじゃない」
『追い払っても新しいのが来るから悩んでんだよ。ったく、お前が綺麗すぎるのがいけねえんだ』
ふてくされた表情の男を見上げ、咲はくすくすと笑った。
「誰が来たって関係ない。私の旦那様は鉄だけよ」
『だけどよ、俺は死人だ。この姿は咲以外には見えねえし、この声は咲にしか聞こえない。俺の警告も、下衆どもにはちっとも聞こえちゃいねえ』
鉄は言葉を絞り出すようにそう言った後、大きな溜息を吐いた。
『俺はお前を連れて歩けないし、ガキも作れない。俺がいくら咲のことを好きでも、俺達は本当の意味で……夫婦にはなれねえのかもな』
その言葉に切なさが込み上げる。咲は悲しみに顔を歪め、目の前の男を精一杯抱きしめた。
「お願い、そんな酷いこと言わないで。誰に認められなくとも、私たちは確かに夫婦よ。鉄はここにいるじゃない。あなたの温もりをしっかりと感じるわ」
『……さき』
「私の全てはあなたのものよ。不安なら、私を抱いて。鉄と私の繋がりがもっと深くなるように、あなたの存在を感じさせて」
咲の微笑みに鉄の目が潤む。彼は愛しい娘を掻き抱き、性急に唇を奪った。
「んむぅっ、んくっ……! ぁ、て、つぅ……」
肉厚の舌がぬるりと咲の腔内に入り込む。鉄は女の頬を両手でがっちりと掴み、目を見開きながら咲の口を蹂躙した。
敏感な上顎に舌を這わされ、歯列を丹念になぞられる。引っ込めた舌を横から掬いあげられ、舌先を唇で挟まれながらゆっくりと前後に動かされる。粘膜を触れ合わせる甘い快感に、咲は唾液を嚥下しながら声を漏らした。
「あ、ふぅっ、鉄……んぁ、だめ、ぇ……」
『んっ……駄目だって? 仕方のねえお嬢様だ。そんなやらしい顔をして駄目なもんかよ』
鉄は咲の反応に目元を緩ませた。久方振りに見た男の笑みに、咲の胸がとくとくと跳ねる。自分からその先を求めるのは浅ましい気がして、咲は色付いた頬をそっと分厚い胸に埋めた。
『俺に甘えてんのか? 可愛いなあ咲。お前は本当にかわいい』
咲の体が優しく抱きかかえられる。布団の上に彼女を横たえ、鉄はそっと咲の上に伸し掛かった。
大きな手に衣を一枚ずつ脱がされる。乳房を揉まれながら、耳から首筋までを唇で何度もなぞられる。
『咲、さき……。お前は昔からちっこくて愛らしくて、綺麗だなあ。知ってるか? 俺の初恋はお前なんだ』
「ふ、あ……ほんとう……?」
『ああ、本当だ。愛しい咲、今日も可愛がってやるからな』
鉄の赤い舌が、咲の乳首をぱくりと咥え込む。敏感な胸の先端を飴玉のように舐め転がされ、咲はぴくぴくと肩を震わせた。
大きな手に咲の乳房がすっかり包み込まれ、形を確かめるように優しく揉まれる。片方の乳首を吸われながら、もう片方を指の腹で擦られる。単純な動きなのに、身を捩りたくなるような切ない快楽が広がっていく。
「ひ、んふうっ……。ああっ、ああんっ……」
鉄はわざと赤い舌を見せつけながら、無言で咲の胸を苛んだ。生温かい舌が、敏感な膨らみを粘っこく這い回る。舌に力を込めて乳輪ごと先端をなぞりあげられると、気持ちよくて力が抜けてしまう。
足を擦り合わせながら甘い快感に浸る。男に可愛がられ続けた胸は快楽に従順で、咲はすぐに甘い高みへ上り詰めた。
「はっ、ふあっ、てつぅっ、もうっ……! あっ、あはあぁっ……」
胸から全身へ、切ない絶頂の快感がじんわりと広がる。咲が鉄の首に腕を回すと、彼は濡れた秘部に指を入れ、優しく掻き回すように動かし始めた。
「あ、あああっ……。ひう、んんっ……」
『咲、顔が真っ赤だぜ。ははっ……すげえな。俺の指が溶けちまうくらいとろとろだ。そんなに気持ちいいか?』
「うんっ、うん……! てつのゆび、きもちいいっ……。ふあっ、あひっ……んあああああっ……」
膣天井を優しく叩かれると、むずむずとした快楽が迫り上がってきて雫を溢れさせてしまう。茂みの中に隠れていた肉の芽にしつこく愛液を絡められる。太い親指で陰核の先端を弾かれ、咲は呆気なく達した。
「ひっ、ひく、いくぅっ……! う、んんんんっ……!」
『咲が欲しい。咲に触れている時だけ心が安らぐ。さき、さき、俺の咲……。お前を満たせるのは、この俺だけだと教えてくれ……!』
足を割り開かれ、鉄の陰茎がずぶずぶと入り込んでくる。女のうつろを満たされる感覚に、咲はうっとりと目を瞑り、鉄の背に腕を回した。
「あ、ああっ……あ、はああああんっ……。いい、っ、きもち、いいわ……」
鉄がゆっくりと体を動かす。ふたりの腰が合わさる度、粘っこく淫らな水音が響く。咲は額に汗を滲ませながら、蕩けそうな交合の快楽に浸った。
『はっ、はっ、はあ……さき、咲……! お前の内がうねって、すごくいいっ……!』
「あ、あっ……てつっ、てつぅ……! あんっ……もっと、もっとしてぇ……!」
咲に誘われ、鉄は腰を大きく動かし始めた。男の太い陰茎が女の弱いところを擦り上げ、鋭い快楽を与える。咲は愛する男の名を何度も呼びながら、擦り付けられる男根の熱さに乱れきった声を上げた。
「あ、あああっ……そこ、いいっ……! ねえ、てつっ、てつも気持ちいい? もっとちょうだいっ、わたしがあなたのものだって、思い知らせて……! おねがっ……あ、あっ、ああああああんっ!」
腹の裏側を執拗に擦られ、咲は呆気なく絶頂を迎えた。鉄の顔が快楽に歪み、低く掠れた声が咲の耳元に落ちる。鉄は咲の唇を奪い、彼女の体を押さえつけながら激しく秘所を穿った。
『当たり前だろっ、咲は俺のモノだ! 死んだって放してやらねえ! 俺がどれだけお前のことが好きなのか知らねえだろっ、俺は咲のことが好きでっ、好きで、好きすぎてっ、ずっとこうしてやる想像ばかりしてたんだぞ……!』
「んうっ、ふあ、あああっ! あ、あっ、あっ、あっ……だめ、だめ……そんな強くされたらっ、またいっちゃ……!」
『いいぜ、旦那様の体で何度でも気持ちよくなれよ。お前が気をやっちまっても、俺がきちんと世話してやるからな! さきっ、さき! 咲ぃ……!』
「んん、あぁっ、はあああああっ……。鉄っ、てつぅ……! だいすきっ……ふあっ、ああああああっ!」
『咲、大好きだっ! お前をずっと愛してるっ、いつまでも、こうして幸せに暮らそうなっ……! くっ、はあぁぁ……!』
最奥に精が放たれる。鉄がくれる温もりが、降り落ちる愛の言葉がとても嬉しい。絶頂を迎えた陰茎を締め付けながら、咲は歓喜に涙を溢れさせた。
✿
満月が美しい冬の夜。咲は今夜も縁側に座り、鉄と共に桜を見た。
血桜はまだ花を咲かせ続けている。寒風が花を散らすが、枝から湧き上がるように次々と新しいつぼみが花開く。赤い花びらを派手に散らすその様は、まるで命を削っているかのようだった。
情事で火照った体を冷ましながら、咲は男の手を握った。
「ねえ。私を憎んでいないの?」
静かな問いかけに、鉄が首を傾げる。
「私は鉄を死に追いやってしまった。あなたに優しくされる度、いつも辛くなるの。私は鉄に殺されても仕方のないことをしたのに」
舞い散る花びらに血の色を重ね、咲は心痛を堪えた。鉄の死に様を思うと胸が痛む。肺が粟立ち、喉奥から何かが迫り上がってくる。
『……そりゃあ、な。呪い殺してやると思ったさ。お前のことを深く愛していた分、あんな風に俺の想いを踏みにじったことが許せなかった。絶対に幸せになんてさせない。犯して、痛い目に遭わせて、一生どこにも行けなくしてやろうと思った。その憎しみのあまり、俺は怨霊になっちまったしな』
俯く咲の手を握り返し、鉄は穏やかな声で言った。
『だけどよ、咲は俺を突き放した理由を教えてくれた。咲は俺と心を通わせてくれた。最初は疑っていたけど、今はお前の愛を信じられる。だから、もういい。今の俺には憎しみも怒りもねえ。咲とこうやって過ごせて、俺はとても幸せなんだ』
咲の体がすっぽりと包みこまれる。寒さから彼女の身を守るように、鉄はしっかりと娘の体を抱きしめた。
『俺こそ、酷えことをした。こんなやわっこい女は壊れ物のように扱うべきなのに、憎しみに任せてお前を傷付けた。痛かっただろ? 怖かっただろ。……乱暴にしてごめんな』
男の大きな目が後悔に揺れる。肩を震わせる鉄の顔を見上げ、咲は優しい微笑みを浮かべた。
「謝らなくてもいい。謝る代わりに、たくさん愛してるって言って。鉄から好きだって言ってもらいたくて、いつも一生懸命おしゃれをしていたの。ね、私の旦那様。おねがい」
可愛らしいおねだりに、鉄が目元を緩ませる。彼は咲の頬を撫で、甘い声で囁いた。
『愛してる、咲。俺達はずっと夫婦だ。いつまでも、いつまでも一緒にいよう』
望んでいた言葉をもらえて、喜びが胸に満ちる。私も、と返事をしようとした瞬間、喉奥から鉄の臭いが迫り上がった。
「っ!?」
咲の口からごぽりと血が溢れる。
ぼたぼたと音を立てて床に滴り落ちた血に、鉄はざっと顔を青褪めさせた。
『さきっ、咲! 大丈夫か!?』
「っ、げほっ……! ……はっ、はあ……なんだか、前から咳が止まらなくて。ごめんなさい、鉄が近くにいる時はっ……血を出さないように気をつけていたんだけど……」
激しく咳き込みながら、咲は溢れ出る血を止めようとした。
咳が止まらない。命が削られていく。こんなみっともないところを、愛する男には見せたくなかった。自分は常に、桜のように美しくいなければいけないのに。
「ご、ごめんなさい、少し別の方を向いていてくれる? 今、止めるから……」
『何言ってんだよ、こんなの止められる訳ねえだろうが! 咲、すぐに休め。俺がどうにかして医者を呼んできてやるから!』
鉄は咲の体を抱きかかえた。
そして気がつく。娘の体の、あまりの軽さに。
『は……?』
咲に対する恨み辛みから解放された末、鉄は初めて娘の本当の姿を認めた。愛する女と結ばれなかった未練に取り憑かれていた鉄は、咲がどんなに衰弱しているか、今まで正しく見ることができなかったのだ。
『咲? ま、さか……。咲は俺のせいでこうなったのか?』
全身から肉という肉が落ちた、骨のように痩せこけた女。蒼白な肌には赤い指の痕が刻まれ、腕には黒黒とした罪人の入墨が刻まれている。怨霊の呪いに蝕まれた咲は、明らかに死へと向かっている。
『咲が俺と話せるようになったのは、咲が死にかけているから。咲が病に罹ったのは、俺の呪いに引き摺られたから……。俺の怨念が、咲の命を奪っていったんだ。咲が俺と触れ合えるのは、死人の俺に近づいているからだ……!』
そうだ。古来より、怨霊は生者と相容れない存在だと伝えられている。怨霊はその場に存在するだけで生者を呪い、死の世界に誘ってしまうからだ。
それなら――死者と深く交わり続けた咲は、いったいどうなる?
『駄目だ、そんなの。俺が咲を殺しちまうなんて、そんな怖ろしいことねえだろうが! さき、俺はお前を死なせたくねえ……!』
己の腕の中で荒い息を吐く娘を見下ろし、鉄は呆然と唇を震わせた。
『お前が俺を必要としてくれたあの日から、俺は咲を守るって決めたんだ。これ以上咲を傷付けたくない。今すぐお前を解放してやらねえと……』
鉄はぐったりとした娘を布団の上に寝かせた後、すぐにその場から消え去った。
✿
自分は労咳に罹ったのだという。
咳をし続け、衰弱した末に血を吐いて死ぬ不治の病だ。
まだ若いのに可哀想だ。怨霊に引き摺られたのだろうか……女中の囁きをぼんやりと思い出しながら、咲はここにいない男に向かって呼びかけた。
「鉄。いつまでも一緒にいようって言ってくれたのに、どうして私の前から消えてしまったの?」
死は怖くない。死ぬよりも怖ろしいのは、愛する男ともう会えないことだ。
縁側で血を吐いたあの夜から、鉄は姿を現さなくなった。どんなに呼びかけても、鉄は気配すら滲ませない。腕に浮かんだ罪人の入墨が、日毎に薄らいでいく。鉄との繋がりを失ってしまうのが怖くて、咲は掠れた声で愛する男に呼びかけた。
「おねがい、鉄……。私を本当に愛しているのなら、もう一度姿を見せて……」
返事がないまま、月日が流れていく。
根雪が解け始め、春の気配が訪れても、鉄は戻ってきてくれなかった。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
俺の存在を認めてくれたのは咲だけだった。
親の顔も知らない根無し草。貧しさから逃れるために、俺は何度も盗みを犯した。前科者の入墨がある男なんて、誰からも嫌われる存在だ。なのに咲だけは俺の手を握り、あなたが必要だと言ってくれた。
咲に甘えられる度、心がくすぐったくなった。こんな俺を兄と呼んで慕ってくれる娘が愛おしい。咲は唯一の宝だ。命に代えてもこの娘を守ろうと決めた。
だが俺は、いつの間にか咲を女として意識してしまった。
あどけない顔は、成長するにつれ言葉を失うほどの美貌に変わった。咲は桜のように美しく、傍にいると胸が跳ねる。咲が目元を緩ませて綺麗に笑う度、恋心が膨れ上がっていくのを感じた。
邪な思いを必死で押さえつけているのに、咲は何でもない顔をして俺に甘えてくる。極めつきは俺にかんざしをねだってきたことだ。男が女にかんざしを贈る意味なんて知っているだろうに、咲は笑顔で頼んでくる。俺は咲に一番似合う花を思い浮かべ、桜のかんざしを買ってやった。
咲は男を狂わせる美女だ。その無防備な行動ひとつひとつが、抗えない誘惑のように思えてしまう。このままでは俺がおかしくなる。大切な娘を傷付けないように、どうにか距離を置こうと決めた。
だが俺は、とうに狂っていた。咲に穢れた視線を向ける男を見かける度、胸を掻きむしりたくなる。酷い嫉妬に苦しめられて夜も眠れない。咲の美しさは俺にとって誇りであり、耐え難い痛みでもあった。
我慢できなくなった俺は、咲に想いを寄せる男を密かに処分してまわった。汚い目で咲を見るのが許せない。目を潰し、手足を折り、下衆どもに咲は俺のものなのだと言い聞かせてやった。咲を好いていいのも、笑顔を見ていいのも俺だけだ。あの艶やかな髪に桜のかんざしを挿していいのも、小さな手を握っていいのも俺だけ。咲は俺だけのものだ、決して他の男には渡さない!
咲の縁談についての噂話を耳にする度、心臓が嫌な跳ね方をした。下人や町人とは違い、さすがに武家の男まで処分することはできない。大体、咲と俺は身分が違う。桜が散るように、いつか咲は俺の元から去る。そう思うと、胸の奥が焼け爛れるように苦しい。
この恋は叶わない。咲の幸せは良家に嫁ぐことなのだ。そう頭では分かっていても、咲を独占したい気持ちが止められない。だから俺は、咲の私物を使って浅ましい欲を発散しようとした。
桜が美しい夜だった。咲の私物を愛撫していると、どこからか視線を感じた。
咲がこちらを見ている。緊張に体が強張ったが、俺はそのまま咲の櫛を愛撫し続けた。気持ち悪がってくれたらこの想いを潰せる。俺を遠ざけてくれたら、これ以上咲への想いを膨らませずに済む。咲が息を呑んで逃げていくのを横目に、ほっとした気分になった。
それなのに、咲は翌日から俺を誘惑するような行動に出た。白い肌を露わにしながら艶やかに笑い、自分に触れるよう命じる。そんなことをされたら、もう我慢なんてできない。理性が呆気なく崩れ去り、抑え続けてきた咲への想いに支配されるのを感じた。
夜中になると、咲は俺の様子を窺いにくる。櫛に舌を這わせ、自慰をする男を微笑みながら見ている。うっとりと笑うその様は、男を狂わせる女そのものだった。
ああ、きっと咲も同じなのだ。下衆な男を遠ざけるどころか、自ら近づいてきてくれるのだから。きっとあの女も俺を愛してくれている……そう思っていた。
だから、練習台という言葉が許せなかった。
狂おしいほど咲のことが好きなのに、俺の愛は練習台の一言で徹底的に踏みにじられた。
もうどうなってもいい。これが最後なら、咲に消えない傷をつけてやりたい。
だが、咲を痛めつけた後にやってきたのは強烈な罪悪感だ。自分の下で啜り泣く咲を見た時、守ると決めた娘に対して、なんてことをしてしまったのだろうと怖ろしくなった。
死罪になると分かって自白した。
この苦界に未練などなかったのに、咲の声を聞いた瞬間憎しみが溢れ出してきた。
俺を裏切ったあの女が悪い。死んでもあの女を苦しめ、いつまでも取り憑いて自分の存在を刻みつけてやりたい。咲と結ばれないこの世を呪ってやりたい!
そうして気がついたら、俺は桜の下にいた。
咲と眺めた、中庭の桜の大樹の下に。
赤く色づく桜を見上げながら考える。どうやら俺は、咲への未練のあまり怨霊となったらしい。怨霊ならば、怨霊らしく裏切った女を呪ってやらなくては。俺は咲の座敷に忍び込み、またその体を穢した。
無理やり犯しながら首を絞め、一番奥に溜め込んだ欲を放つ。白い肌を握り込み、全身に所有の印をつける。啜り泣く咲を見ると、哀れに思う気持ちと同時に悦びが込み上げてきた。
散々怖ろしい目に遭わせたのに、咲は怨霊の俺を受け入れてくれた。桜の下で、本当の気持ちを聞かせてくれた。この女は確かに俺を愛してくれていたのだと気がついた時、俺は泣き叫びながら後悔した。
咲の愛情を感じる度、自分の心から憎悪が消えていく。咲を慈しみ、守りたいという気持ちが再び蘇ってくる。生と死の隔たりはあれど、咲は俺の女で、俺達は夫婦だった。俺だけが、この美しい女に触れられる。屋敷にいる人間も、咲を狙う男も全員要らない。今度こそ二人きりの世界を作るため、俺はあらゆる人間を呪い殺そうとした。
そうだ。俺は怖ろしい怨霊。どこまでいっても未練と怨念の塊だ。
こんな俺と一緒にいて、咲が無事でいられるはずがない。怨霊は死そのもの。生者と交われば、無理やりこちら側に引きずり込んでしまうのだから。
馬鹿だ。俺のせいで、咲が死にかけている。
恨み辛みから解放されて、やっと分かったんだ。
俺は咲を救いたい。咲の笑顔こそ、自分の宝だから。
だから、もう会えない。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
麗らかな春の空気が満ちる頃、咲はもうまともに歩けなくなった。
夜風が障子の隙間から吹き込んでくる。己の死が近いことを悟った咲は、痛む胸を抑えながら必死に外へ這い出た。愛する男に会いたい、その一心で必死に暗闇の中を進む。
「……て、つ」
咲は血を吐きながら、懸命に中庭の桜を目指した。鉄がまだこの世界にいるならば、それは彼の手を葬った桜の下ではないかと思ったからだ。
視線の先に、赤く咲き誇る桜が見える。
血桜は今なお咲き続けていた。夜の帳の中、紅の花びらがはらはらと舞い散る。命を削りながら激しく花を咲かせていた桜も、今は儚い静謐さを湛えている。散り際の桜は、最後の艶やかさで薄暗やみを彩っていた。
「……何となく、分かっていたの。この咳は怨霊の呪いによるものだって……。鉄が死んでからこの咳が始まったもの。それでも、私にとってはこの咳すらも愛おしい。だって、鉄との繋がりを確かめられる証のひとつだから……」
血が溢れ落ちる。自分の命も、桜の命も散っていく。
倒れてしまいそうな苦しみの中、咲は一歩一歩前に進んだ。
「もう一度鉄に会いたい。あなたと結ばれることが私の願い。他には何も望まないわ。だから、姿を見せて。おねがい、鉄……!」
骨ばった手を桜の幹に置く。咲が呼びかけた瞬間、辺りの景色が変わった。
視界が開ける。
眩い光に目を細めると、そこは花の海だった。
辺り一面は満開の桜だ。咲の頭上は淡い桃色の花で埋め尽くされ、地面には足首が埋もれるほどの花びらが隙間なく敷き詰められている。立ち尽くす咲の周りで、花の雨が静かに降っている。
ここは暖かい。瑞々しい花の芳香が、咲の痛みを和らげた。
「……さき」
桜みちの向こうから鉄が姿を現す。恋い焦がれた男の姿を認め、咲は涙を溢れさせた。
足に力が入らず、その場に崩れ落ちそうになる咲を、鉄はしっかり腕の中に抱き留めた。彼の手はとても温かい。懐かしい温もりを感じながら、咲は子供のように泣きじゃくった。
「鉄、てつぅ……! どうして会いに来てくれなかったの? ずっと寂しかったのよ……!」
涙を流す咲を抱きしめながら、鉄もまた泣いていた。衰弱しきった咲の背を摩りながら、何度も済まねえと口にする。鉄は咲の顔をじっと見つめ、涙混じりの声で囁いた。
「一人にして悪かった。……でも、もう咲と一緒にいることはできねえんだ」
鉄の声がやけにはっきりと聞こえる。大きな目を潤ませながら、鉄は帰れとしきりに言った。
「咲も気がついてんじゃねえか? お前が死にかけてるのは、怨霊の俺と一緒にいたせいだ。なのに、どうして会いに来たんだよ。俺といたら死人になっちまうだろうが。だから早く――」
「いやだ! もう鉄と離れ離れになるのは嫌なの!」
咲は鉄に抱きついた。彼といたいと望んだ、あの十歳の夜のように。
「私はあなたを殺したわ。だから、今度は鉄に殺されたい。おねがい、私を一人にしないで。一緒に連れて行ってよ……!」
言葉にならない想いが胸から溢れる。心にもないことを言って鉄を突き放してしまった罪悪感に、胸が千切れそうになる。鉄と一緒にいられるのなら、死など全く怖くない。
「……咲。お前はそれでいいのか?」
戸惑いの声を絞り出す鉄の顔を見上げ、咲は微笑んだ。
「もちろん。あなたの傍にいることが私の幸せだから」
体が軽い。指先の感覚が無くなってきている。腕も足も、自分のものではない気がする。ただ愛する男の腕の中にいることだけが、唯一の感覚として感じられた。
「それなら……。一緒に行くか? 桜の国に。そこはあったけえし、痛みも苦しみもねえ。未練がなくなった俺は、そこに向かおうとしていたんだ」
鉄が桜みちの向こうを指差す。欠けていた左の人差し指が、今はその手に確かに存在していた。
「そこに行けば、今度こそ俺達は二人きりで過ごせる。どうだ、咲。俺と一緒に来てくれるか……?」
死者の誘いに、咲は笑顔で頷いた。
「うん、一緒に行こう。私を永遠に鉄だけのものにして」
鉄の胸に顔を埋める。もう何があっても手放してやらねえと呟く男を愛おしく思いながら、咲は懐から桜のかんざしを取り出した。
「わたしは桜になりたかった。鉄を虜にする女になりたかった。もう一度桜みたいだって褒めてほしくて、あなたを誘惑したの」
かんざしを差し出す。艶やかな笑みを浮かべながら、咲は自分の髪にかんざしを挿すよう鉄に頼んだ。
「ねえ、鉄。私はきれい?」
鉄の顔に優しさが満ちる。彼は咲の髪にかんざしを挿した後、彼女の頬を両手で包みこんだ。
「ああ、綺麗だ。お前は桜よりも綺麗だ」
鉄の顔が近づいてくる。桜の樹の下、無数の花びらに包まれながら二人は口付けを交わした。
「愛してる、咲。俺達はずっと夫婦だ。もうお前を放さねえ」
花吹雪の中、体がゆっくりと溶けていく。
溢れんばかりの幸福を感じながら、咲は鉄と共に桜みちの向こうを目指した。
✿ ❀ ✿ ❀ ✿
朝日が差し込む頃、桜の大樹の下で息絶えた咲が見つかった。
不思議なことに、血桜は一夜にして散り果てていた。冷たい娘の体を包み込むように、赤い桜の花びらが積もっている。鉄の処刑から半年後に訪れた咲の死に、女中たちはお嬢様は鉄に連れて行かれたのだと囁きを交わした。
咲は寺に葬られるはずだったが、葬儀の日が迫るにつれ、屋敷の住人たちはまた不吉な夢にうなされるようになった。首なしの大男が咲の棺を強く求め、絶望に満ちた声で嘆き続ける夢だ。
中庭の桜の下から、何か引っ掻くような音が聞こえる。下人たちが恐る恐る桜の根元を掘ると、土の中から一対の手の骨が突き出ていた。まるで、咲の体を待ち望むように。
鉄の怨霊を鎮めるために棺を桜の根元に埋めると、奇妙な音はぱたりと止んだ。
そして、その次の年から、桜は一際美しく咲くようになった。見る者を魅了する華やかな佇まいは都中の評判となり、多くの者が桜を見ようと屋敷を訪れた。
時折、黄昏時になると、桜の木の下で寄り添いあう男女の幻が見える。
あれは武家の娘と下人の男だ。彼らはきっと死んだ後に結ばれ、ああして桜の下で愛を囁き合っているのだろう……。人々はそう噂をし、江戸一番の花の美しさを称えるのだった。
23
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

オ
橙乃紅瑚
恋愛
山に置き去りにされてしまった女子大生が、不思議な村に招かれて幸せになる話。某都市伝説オマージュ。
※本作には流血等の残酷描写が含まれます。ご注意ください。
※この作品はムーンライトノベルズにも掲載しております。
※表紙画像は「かんたん表紙メーカー」様で作成しました。
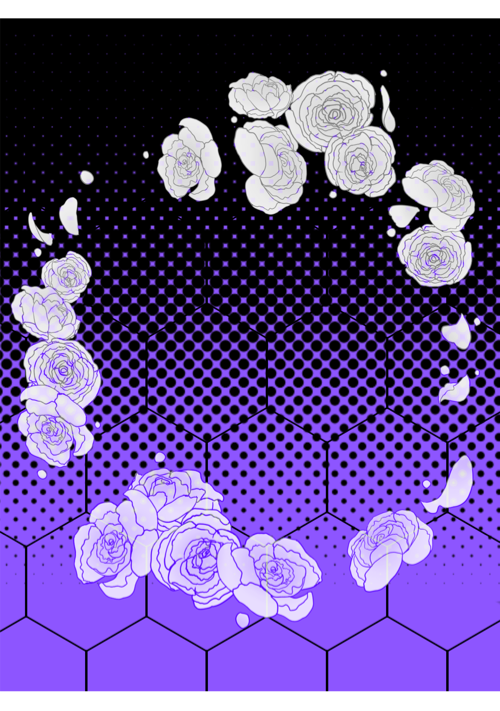
【ヤンデレ八尺様に心底惚れ込まれた貴方は、どうやら逃げ道がないようです】
一ノ瀬 瞬
恋愛
それは夜遅く…あたりの街灯がパチパチと
不気味な音を立て恐怖を煽る時間
貴方は恐怖心を抑え帰路につこうとするが…?


【情緒不安定なヤンヘラ御曹司は、 貴方に心酔して永遠に離してくれません】
一ノ瀬 瞬
恋愛
貴方が目を覚ました"そこ"は
見知らぬ天井が広がった…豪華な部屋の中だとわかった
貴方の横たわるベッド、そこにいたのはー…

【ヤンデレ蛇神様に溺愛された貴方は そのまま囲われてしまいました】
一ノ瀬 瞬
恋愛
貴方が小さな頃から毎日通う神社の社には
陽の光に照らされて綺麗に輝く美しい鱗と髪を持つ
それはそれはとても美しい神様がおりました
これはそんな神様と
貴方のお話ー…


美少年幽霊の狂愛〜私は彼に全てを奪われる
べーこ
恋愛
小さな町の高校に通う信濃ほのかは平凡な女子高生だ。
彼女のクラスには一度見たら忘れられない壮絶な美貌を持つ男子生徒がいた。
彼の名前は赤城陽光。黒い滑らかな髪の毛に整った顔立ちの白皙の美貌の少年で芸能界でもお目にかかれないレベルの美形だ。
とある偶然をきっかけにほのかと赤城は意気投合し仲良くなる。
しかしある日ほのかは訳あって彼を遠ざけてしまう。そして赤城がほのかに淡い恋心を抱いてるのをほのかは知らなかった。
不慮の事故で亡くなった赤城は淡い恋心が独占欲と執着心に塗れてしまい悪霊となってほのかの元へと現れた
絶世の美少年幽霊ヤンデレと臆病なヒロインの物語です。
つよつよヤンデレに何もかも奪われて人生を引っ掻き回される連作短編です

ホストな彼と別れようとしたお話
下菊みこと
恋愛
ヤンデレ男子に捕まるお話です。
あるいは最終的にお互いに溺れていくお話です。
御都合主義のハッピーエンドのSSです。
小説家になろう様でも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















