11 / 148
≪現在①≫
9 二人の食卓
しおりを挟む文香の真意など初めからまったく読めなかった。
だから、今更戸惑っても仕方がない。
そんなことを言い訳しながら、優はぼけっとキッチンで忙しなく動く文香の背中を見つめていた。
部屋中を漂うスパイスの匂いに口の中から唾が湧いて来るのが分かる。
文香は有言実行の人だ。
優が死ぬほど落ち込んだ前回。
それがどうしてこんな状況に転がったのか。
天国から地獄、地獄からまた天国と目が回りそうだ。
「偉そうなこと言っちゃったけど、本当は私もここ最近料理とか全然していないんだよね」
近くのスーパーのロゴが入った袋を軽々と抱えて文香は優の前に再び現れた。
事前に連絡が来たとはいえ、その気取らない態度に優はとにかくほっとして何も考えずに家に通した。
「元々、料理が得意じゃないの知ってるでしょ? マニュアル(レシピ)がないと何も作れないタイプだし、アレンジすると途端に不味くなるし……」
今日の文香は半袖の無地のカットソーに、細身のパンツスタイルだ。
髪を後ろにまとめているため、項がよく見える。
襟元が広いためか、細い項に、時折見える鎖骨を飾るシルバーのネックレスが優の目を惹きつけた。
髪を耳にかけるときに、ちらりと光るピアスにドキドキしてしまう。
一番優の心を落ち着かなくさせるのは、その細い腰に纏う紐……
優は文香のエプロン姿に震えそうなほど感動していた。
「まぁ、料理のリハビリも兼ねて結局カレーにしたってわけ」
文香は形から入るタイプだ。
学生の頃試験勉強を教えてと泣きながら縋り付いた優の家庭教師を引き受けたときも雰囲気を重視してわざわざ伊達眼鏡を購入した。
ウケを狙ったわけでもなく、真剣な文香に優は笑うこともときめくこともできなかった。
眼鏡姿の文香のせいで勉強にまったく集中できなかったという苦い過去である。
あのときの貴重な文香の姿を写真か動画に撮っておけばよかったという後悔もあった。
「カレーはいいよね。簡単だし、野菜もお肉もいっぱい摂れるし。どんな食材入れてもカレーになっちゃうし、本当懐が広いというか……」
そんな文香はキッチンに立つときは必ずエプロンをつけていた。
どこにでもある汚れが目立たない紺色のエプロンだったが、ただエプロンをつけるだけで普段は目つきがきついとよく言われる文香の顔立ちがなんとなく優し気に見える。
共働きとはいえ、文香の方が帰りが早く、優は仕事から家に帰るとキッチンから漂う料理の匂いとエプロン姿の文香に出迎えられた。
それが三年前の優と文香の当たりまえの光景だったのだ。
「材料を変えるだけで色んなバリエーションを味わえるし。ビーフカレー、チキンカレー、野菜カレー、シーフードカレー…… 今日は豚肉が安かったからポークカレーね」
それが三年の月日を経て再び優の眼前に蘇ったのだ。
感動しないはずがない。
そして、三年越しの今日の文香のエプロンは無地の赤だ。
以前愛用していたエプロンは捨ててしまったのかなと優は少し悲しくなった。
贅沢な悩みであると自覚している。
料理している間は適当に暇を潰してて、とテレビを適当に付けられた優はまったく画面を見ることなくずっと文香の背中を凝視していた。
何か手伝うことはないかと問いかけるという考えすら思いつかず。
テレビから流れ出る音などまったく耳に入らないまま、優はひたすら文香の奏でる小気味の良い調理音に集中していた。
初めて文香に料理を振る舞われたときは、その見るからに危なっかしい手つきや挙動不審さにハラハラドキドキしたものだ。
それでも何事もコツコツと学び知識や経験を積み重ねていく文香の料理の手際は徐々に良くなり、今のように一品目、二品目を同時進行で作れるようにまでなった。
料理に慣れると、今度は気づくと肉ばかりを食べる優の健康を考えてネットで健康レシピを探したり、姑に料理を教わりに行ったり、地道な努力をしていたそうだ。
地道に、優に悟らせないように文香は影で努力し、常に頑張っていた。
今思えば、頑張り過ぎていたのかもしれない。
「よし」
ぐつぐつ煮込まれた鍋の中身と市販のカレールーの箱の裏面を真剣に見ながら、文香はふと一息ついて額の汗を拭う。
そして、そのまま後ろを振り返ってにこっと優に笑いかけるのだ。
「好きでしょう? カレーライス」
その笑顔に優は反射的に頷いた。
文香は知らない。
確かに優はカレーが好きだ。
一番よく文香にリクエストしていた。
料理にまだ不慣れだった文香でもそれほど気を張らずに毎回美味しく作れるのがカレーだったからだ。
それでも初めの頃は何故か毎回味が微妙に違っていて口触りが良くなかったことを思い出す。
誤魔化すように途中でスープカレーになったこともあったが、いつの間にかそういうことも無くなった。
お世辞でも慰めでもなく素直に美味しいと言う回数が増えるたびに文香が照れたように、得意気に頬を染めてはにかんだように笑うのが好きだった。
カレーは確かに好きだ。
だが、厳密にいえば優は文香のその表情が好きなのだ。
カレーは、レアなその表情を見られる確率が高かっただけである。
そんなことを、優は思い出していた。
*
テーブルに並べられた食器。
湯気が立つカレーと白いご飯。
食欲が湧くのが分かる。
「はい。どうぞ、召し上がれ」
文香のその合図に、優は一瞬躊躇った後にスプーンを手に取った。
「……いただきます」
零さないように、口周りを汚さないように気を付けながら口に入れる。
火傷しそうになりながら、気づけば一口、二口と優の口の中にスパイスの味が広がって行く。
「スープとサラダもあるからね」
副菜も忘れないようにそれとなく注意する文香に優はこくこくと頷いた。
(……ちゃんと食欲はあるみたいね)
口に合うかどうか聞かなくてもその様子を見ただけで分かる。
人知れずほっと安堵の息を吐き出しながら、文香もまたテーブルに腰かけた。
少し手抜きしすぎたかと、自分が調理した三品を見て思う。
カレーとオニオンスープにポテトサラダ。
文香でも簡単に時間をかけずに作れるメニューばかりだ。
オニオンスープとポテトサラダなどはカレーの材料と被っていたが、優を見れば目を輝かせてそれらももくもくと食べている。
(……子供みたい)
喫茶店で再会したときの優は同い年とは思えないほど老け込んでいたが、今の優は初めて出会ったときのように無邪気で幼稚なオーラを垂れ流しにしている。
育ちがいいせいか、慌てて食べていても下品に見えないところが優らしい。
「どう? 味の方は」
「……美味しい、今まで食べたので、一番美味い」
不器用で痛々しい笑顔ではなく、再会後初めて見るであろう優の満面の笑みに文香はちょっと笑った。
「一番美味しい、ね……」
優の口元についているカレーを見て、またはその食欲を見て、過去一番美味しいと言われた自分自身がちょっとおかしかったのだ。
くすくすと食事中なのについ漏れてしまう笑いを抑えようとすればするほど耐えられなくなる。
そんな文香の上機嫌な様子に、優も嬉しくなった。
優が好きな文香のはにかんだような笑顔は見られなかったが、今は優の言葉で楽しそうに笑ってくれるだけで十分だ。
「そんなに気に入ったの?」
「ああ、とっても」
「私が今まで作ってあげた中で一番美味しい?」
悪戯っぽく笑う文香に、優は何も考えずに力強く頷いた。
「よかった」
まだ、おかわりあるからねと優しく目を細める文香を見て、優は今の時間が永遠に続けばいいのにと本気で思った。
こんな風にリラックスして、ごくごく自然体で文香と会話できることがまるで夢のようで。
途切れさせたくなくて、ついつい他愛のない話題を振ってしまう。
互いの現在の生活に踏み込む勇気はなかった。
必然的に文香が作ってくれた目の前の献立の話になる。
「隠し味とか入れたのか?」
「隠し味というか…… ただ市販のルウをブレンドしただけ。他はレシピ通りだよ」
「へぇ…… それだけでこんなに美味くなるんだな」
感心したように呟く優のコップが空になったのを見て、文香は無言で水を注いでやった。
* *
(今日のが美味しいんじゃなくて、ただ今までのが不味かったんじゃないの?)
と、いう言葉は呑み込んだ。
せっかく穏やかな空気が流れているのに、それをぶち壊す必要はない。
(そりゃあ、美味しいでしょう)
アレンジも何も。
ただ同じメーカーのカレールーを二種類ブレンドし、箱のレシピ通りに作ったのだ。
これで不味くなるはずもない。
ベストではなくともベターで美味しい味になっているはずだ。
作ろうと思えば誰でも作れる味である。
文香も一口二口食べて素直に美味しいと思った。
この味に辿り着くまで、数年かかった事実が悔しい。
そして、純粋に優に美味しいと言ってほしくて料理をあれこれ頑張っていた昔の自分を思い出す。
文香は自分に料理のセンスがないことを知っている。
だからなんでもレシピの通りに、無難に作ることを心がけていた。
下手にアレンジすると美味しいものが不味くなることを経験したからだ。
それでも、初心者向き料理代表であるカレーだけは拘っていた。
優のリクエストが一番多かったのと、一番反応が良かった料理だからだ。
定番中の定番であるカレーだったが、安定した美味しさに辿り着くのには苦労した。
文香がまだ優の奥さんであった頃。
カレーを作るときは市販のルウを使わず、小麦粉から作っていた。
優が時折舌触りに違和感を感じていたのはそのせいであろう。
手作りルウになんとか慣れて来てからは隠し味にチョコやソース、醤油に珈琲を入れてみたり。
ときには血迷ってスパイスを数種類揃えてみたりと試行錯誤を繰り返していた。
そのためなかなか正解のレシピが見つからず、味が安定しなかったのだ。
(今思うと馬鹿みたい…… 普通に市販のルウで十分に美味しいのに)
むしろ、十分すぎるほどだ。
(馬鹿みたいに拘ってたんだよね、あの頃の私は)
美味しそうに、幸せそうに文香の手作りカレーを頬張る優を一瞥する。
優はきっと文香がときに緊張したりはりきったりしながら毎回カレーに時間をかけていたことを知らない。
結婚当初、文香には固定観念というものがあった。
各家庭ごとにその家だけの『カレーの味』があるという思い込み。
つまりは我が家の味というものの代表がカレーであると信じていた。
だから、ありきたりな味では駄目だと、強迫観念染みたものを抱いていたのだ。
(……馬鹿みたい)
あの頃の文香は作りたかったのである。
自分自身で、見つけたかったのだ。
優と、文香の。
二人の『家庭の味』というものを。
だが。
それももう、昔のことである。
頑張っていたあのときの自分を笑って思い返せるぐらい。
文香にとっては、もう終わったことである。
そんなことに囚われている暇などない。
今の文香には、やるべきことがあるのだ。
* * *
優の皿を見て、文香はそっと立ち上がる。
「おかわり、する?」
優にはいっぱい食べてもらわなくてはいけない。
いっぱい食べて、いっぱい体力を付けてもらわなくては。
0
あなたにおすすめの小説


あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

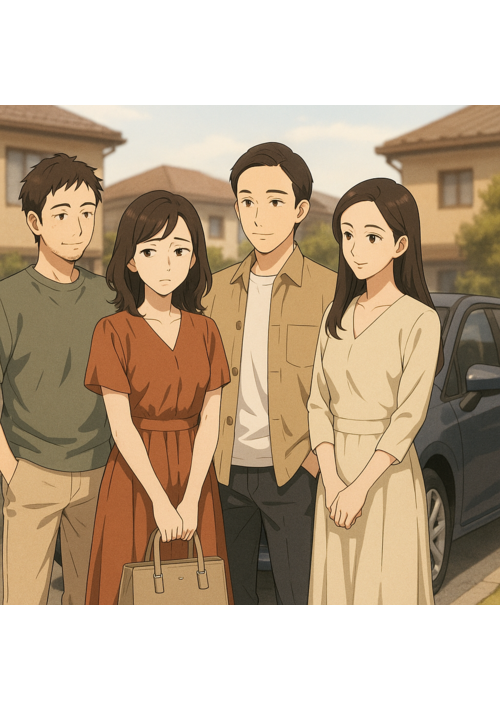


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















