1 / 6
プロローグ
しおりを挟む王都は、朝を迎えると同時に慌ただしさを増す。大通りには行商人の屋台がずらりと並び、客寄せの声が重なり合う。貴族の馬車が行き交い、その間を縫うように庶民が生活に必要な物を買い求めていた。朝日が城壁に差し込むころには、すでに人々の活気は満ち溢れ、王都特有の喧噪が広がってゆく。
そんな王都の華やかさの中心ともいえるのが、壮麗な王城だ。高くそびえる白亜の石造りの城壁は圧巻の一言に尽きる。中庭には季節の花々が彩りを添え、噴水が優美な音を立てて水を湛えている。庭師たちの手入れが行き届き、四季折々の美しさで来客をもてなすのだ。城内には常に多くの人々が行き交い、貴族たちは自分たちの派閥を象徴するように豪華な衣服を身にまとっていた。
アルタリア・カリスタ。
その名を聞けば、おそらく王都に住むほとんどの者が彼女の存在を思い浮かべるだろう。カリスタ伯爵家の令嬢でありながら、その美貌と聡明さから、社交界においては“王都の薔薇”と称えられていた。流れるような銀糸の髪をゆるく結い、伯爵令嬢にふさわしい気品を纏う姿は、他の貴族令嬢たちの憧れと嫉妬の的でもあった。その上、性格も穏やかで誰にでも分け隔てなく接するため、使用人たちからの評判も非常に高い。
彼女は、王国第二王子であるエリオット・イシュタール殿下の婚約者だった。エリオット王子は、第一王子の兄が既に王位継承権を得ているため、自らが王位を継ぐ可能性は薄い。しかしだからこそ、自由な立場で社交界を動かす人物として期待を集めていた。彼は堂々とした立ち振る舞いに加え、時折見せる優雅な微笑みで人心をつかむ魅力を持ち、王族の中では一際人気のある人物だ。アルタリアとエリオットが婚約を発表したとき、多くの貴族令嬢が落胆したという話は今でも語り草となっている。
もっとも、アルタリアはそのような周囲の羨望をただの噂話のように受け流していた。彼女にとって、婚約はあくまで家同士の結び付きの延長であり、そこに大きな恋愛感情があったわけではない。とはいえ、エリオットが示す気遣いには心を揺さぶられる瞬間もあり、将来的に“彼の妻”となる運命を受け入れ始めてもいた。胸が高鳴るような恋愛ではないとしても、穏やかに寄り添う関係を築くことはできるだろう――そう、信じていたのだ。
しかし、そんな安定と期待に満ちた未来が、ある日突然に崩れ落ちる。
その日は朝から小雨が降り続き、王城の回廊も外庭も湿った空気が漂っていた。アルタリアは通常であれば伯爵家のサロンに顔を出すところだったが、エリオット王子から「早急に話がしたい」との伝言を受け、急ぎ王城に足を運んだ。嫌な胸騒ぎを覚えつつも、彼がこんなにも急ぎで呼び出す理由がわからない。そもそもエリオットが彼女を直接呼び出すときは、たいていの場合、何らかの行事や儀式の打ち合わせである。だが今回ばかりは、周りの貴族や侍女たちにも詳しい説明がされていないようだった。
王城の奥、エリオット専用の執務室。高価な金細工が施されたドアをノックすると、控えめな返事が聞こえる。扉を開くと、部屋の中にはエリオットが一人、机に肘をついて座っていた。雨の影響で薄暗い室内に、彼の真紅のマントが鮮やかに映える。その横顔にはどこか強張った表情が見え、アルタリアの胸はさらにざわついた。
「失礼いたします。アルタリア・カリスタ、参りました」
そう告げると同時に深く一礼をし、息を整える。エリオットは彼女の様子をざっと一瞥した後、静かに立ち上がって窓際へと歩み寄った。開け放たれた窓からは冷たい風が吹き込み、薄いカーテンが揺れている。
「……ご足労だったな」
彼の声は低く、まるで懺悔をするかのように沈んでいた。アルタリアは嫌な予感を拭えないまま、口を開く。
「いえ。殿下が私を急ぎお呼びだったので、何事かと思い参上いたしました。どのような御用でしょう」
いつもであれば、エリオットは笑みを浮かべて「アルタリア」と下の名で呼びかけてくる。しかし今日に限っては敬称を維持したまま、まるで距離を取るような態度だ。
「率直に言う。私は……お前との婚約を破棄する」
そう言い放った声は、まるで王族の威厳を盾にするように響き渡った。アルタリアは一瞬聞き間違いではないかと耳を疑う。穏やかに育った彼女の人生で、こんなにも衝撃的な一言を聞いたのは初めてだった。
「――いま、婚約……破棄、と?」
アルタリアは何とか言葉を口にする。だが頭は真っ白で、うまく状況を整理できない。エリオットは再び視線を窓の外へ戻し、続けた。
「お前との縁組は、私の父上や周囲の貴族が取り決めたことだ。だが私は、新しい相手との結婚を望んでいる。これ以上、偽りの思いを抱えてお前と過ごすのは不誠実だと思ったのだ」
それはあまりにも身勝手で理不尽な宣言だった。けれどアルタリアは、婚約が政治的な結び付きであることを十分に理解している。だからこそ、当事者である自分を差し置いて、当の王子が一方的に破談を言い渡してくるなど、到底考えられない事態だった。
「なぜ、今になって……。私たちは、まだ正式な婚約発表をしてから日が浅いではありませんか」
「先日、私のもとに聖なる力を持つという娘が現れた。彼女は奇跡的な癒やしの力を示し、国中の注目を集めている。父上も、彼女を『新たな聖女』として歓迎すべきだと判断された。私はその娘を支えたい。……いや、正直に言えば惹かれているんだ」
胸を締め付けられるような痛みが走る。奇跡の力を持つ聖女の噂は聞いていた。だが、まさかそれが婚約破棄にまで発展するほどとは思ってもみなかった。王宮の中で優遇を受ける“聖女”という存在は、祈りや癒やしの力で国に恩恵をもたらすとされる。王族にとってその存在を手元に置くことは、政治的にも非常に有利だったはずだ。しかし、それがアルタリアとエリオットの関係を壊すほどのものなのか。
「殿下が……その方に惹かれるのは、お気持ちとしてはわかります。ですが、だからといって私との婚約を破棄するなど――。カリスタ伯爵家への影響も考えていただきたいのです」
「もちろん、伯爵家にはしかるべき補償を約束する。いかなる条件でも呑むと父上も言っている。安心するといい」
アルタリアは自分でも驚くほど冷静に、エリオットの瞳を見つめていた。裏切られた悲しみ、今後の先行きへの不安、そして怒り――さまざまな感情が渦巻いているはずだが、それらをすべて無理やりに抑え込み、外には出さない。それが貴族令嬢として培ってきた自制心と矜持だった。
「……ですが、殿下。私はあなたと婚約を結ぶにあたり、伯爵家は多大な労力と資金を投じて準備を進めておりました。私自身も、あなたの伴侶になる未来を受け入れて――」
「わかっている。だが、これはもう決まったことなのだ。もし納得できないのなら、ほかの貴族たちの前で正式に破談を発表しても構わない。王族の決定が翻ることはない。君がどんなに嘆こうと、私の意志は変わらない」
彼の言葉は残酷だった。かつてはアルタリアの存在を誇りに思い、彼女を守り抜くと誓っていたはずの男性が、今は冷然と自分を切り捨てようとしている。アルタリアは目を伏せ、声を震わせることなく微かに首を横に振った。
「……わかりました。私としては何も言えません。あなたが真に望む相手がいるのなら、どうかその方を選ばれるとよいでしょう。――ただ、これだけは言わせてください。伯爵家への正式な謝罪と補償の約束を、破棄しないでください」
「それは当然だ。私と父上が責任をもって対応する。……すまない、アルタリア」
最後に向けられた言葉は謝罪とも同情ともつかない曖昧な響きだった。エリオットはアルタリアを直視せず、視線を再び窓の外へと逃がしている。アルタリアはその姿に、もう何も期待できないと悟った。あれほどに理想的だった王子は、今や彼女にとっては“他人”でしかない。告げられたすべてを飲み込み、ドアへと向かおうとしたとき、まるで思い出したようにエリオットが言葉を投げかけた。
「……王城を出て行く前に、父上にも挨拶をしていってくれ。伯爵家に戻ったら、しばらくは穏やかに休むといい。いずれ手続きが終われば、再びこちらから連絡をする」
彼の声音に優しさはない。そこにあるのは、ただ“処理”としての婚約破棄を終わらせるための事務的な言葉のみだった。
アルタリアは一礼をして部屋を出る。廊下を歩きながら、激しい動悸に襲われた。自分の心を無理に抑え込んでいたせいだろう。王子の執務室を出て数歩進んだだけで、足ががくりと力を失いかける。だが、その姿を誰にも見せるわけにはいかない。いま、この場で弱音を吐けば、使用人や周囲の者たちが好奇の目を向けるだけだ。王族との破談はスキャンダルにもなりかねない。伯爵家とっても、そうした醜聞が広まるのは避けたいはずだった。
ただ、それでも動揺を隠しきれない。アルタリアは城を出る前に国王――エリオットの父であるヴァルデン国王への面会を申し出る。だが、侍従からは「陛下はご多忙につきお取り次ぎが難しい」との返答を受けた。結局、アルタリアは正式な挨拶すらできないまま王城を後にする。まるで追い出されるかのように、しとしとと降り続く雨の中を歩いた。
アルタリアが伯爵家に戻ったときには、既にこの話は父であるカリスタ伯爵の耳に入っていた。王族からの通達は速く、彼女が馬車から降りると同時に迎えに出てきた執事の表情が恐ろしく暗い。母である伯爵夫人もおろおろとしながら「いったいどういうことなの」と問いただしてくる。アルタリアが王城での一部始終を話すと、伯爵夫妻は激しく動揺した。
「そんなことが許されるのか! いくら第二王子殿下とはいえ、あまりにも我が家を軽んじている!」
怒りに震える父の横顔を見つめながら、アルタリアは申し訳なく思う反面、王族の言い分に抗えない現実を改めて痛感していた。カリスタ伯爵は王室にとって決して無視できない地位ではあるものの、最終的に国王や王子が下した決定を覆すことはほぼ不可能だ。ましてや、当の当事者であるエリオットが強固な意志を示している以上、どうにもならない。母も涙を浮かべながら、
「あなたの身は……私たちはどう守ればいいの? 伯爵家だって、殿下との婚約を前提にさまざまな予定を組んでいたのよ!」
「心配はいりません。殿下や国王陛下が、相応の補償を行うとお約束くださいました」
アルタリアの言葉に、伯爵夫妻はほとんど慰められた様子もなかった。そもそも、多額の金銭や領地を与えられたところで、婚約破棄の汚名を着せられた事実は残る。その事実が社交界でどう広まるか、それが伯爵家の今後にどれほどの打撃を与えるか――夫婦は目に見えない不安に苛まされている。
その後、伯爵家の使用人たちにも動揺は伝播し、屋敷内はバタバタとした雰囲気に包まれた。アルタリア自身、父母や使用人からの詰問を受けるたびに、エリオットの冷たい瞳を思い出す。まだ頭の中で整理しきれないまま、時間だけが過ぎていく。
そんな中、さらなる追い打ちをかけるかのように、王宮からの正式な通知――いわば“破棄の宣誓書”が伯爵家に届けられた。そこには、エリオット王子の署名とともに、「互いの合意のもとで結んでいた婚約を解消する」という旨が書き記されていたのだ。だが、アルタリアは一度も合意した覚えはない。むしろ拒否も抗議もしたかった。しかし、王族の決定を無視して反論することはできず、署名は彼女の意思に反して押し通された。
「これで……正式に破棄されたというわけですか」
アルタリアが震える指先で破棄の宣誓書に目を落とすと、父は唇を噛みしめながら悔しそうに拳を握りしめた。使用人たちも居合わせていたが、何も言えずにうつむいている。そこに、一人の侍女が駆け込んできた。
「お嬢様……外に、王宮の使者が来ております。『殿下からの命令で、アルタリア・カリスタ様の身を速やかに移動させたい』と……」
「身を移動? 何を言っているのだ?」
伯爵が眉間に皺を寄せると、侍女はおどおどしながら言葉を続ける。
「詳しくは私どもも……。ただ、殿下の命令で、お嬢様をこの伯爵家から退去させるとのことです。御用が済み次第、王宮へは戻らなくていいとも――」
その一言で、場の空気は氷のように固まった。アルタリア自身、驚きすぎて声も出せない。
破棄どころか、追放――。それがエリオットの真意だというのか。先ほどの婚約破棄だけでも衝撃なのに、その上さらに伯爵家からも出て行けとは。無論、伯爵家そのものを追い出すとは言っていない。あくまで、アルタリア個人を屋敷から退去させろという話らしい。だが、一族としての彼女の存在を否定するも同然の行為だ。
「それは……殿下は何を考えておられるんだ! アルタリアは伯爵家の娘だぞ!」
父の声は怒りで震え、今にも使者のもとへ乗り込まんばかりだった。しかし、相手は王族から派遣された存在。無闇に刃向かえば伯爵家に不利な状況を生むことにもなりかねない。母も憤りながら、アルタリアの手を握りしめる。
「こんな仕打ち、あんまりです……。アルタリア、あなたは絶対に何も悪くない。私たちが守るわ」
だが、アルタリアは母の手をそっと離し、悲しそうに首を振った。もし伯爵家が王宮と正面対立するようなことになれば、家そのものが危機にさらされる。婚約破棄による悪評だけでも大きな痛手なのに、国王や王子に逆らう形になれば、財産没収や爵位はく奪の恐れすらあるのだ。
「……お父様、お母様。どうか、私を守るために無茶をなさらないでください。伯爵家が潰されてしまっては困ります。私一人を切り捨てれば事が収まるのであれば、それで……」
「しかし、それではあまりにも……」
「大丈夫です。私なら……どこでも生きていけるように頑張りますから」
そう告げるアルタリアの瞳には、決意の光が宿っていた。涙をこぼすこともない。ただ、深く息をつき、その場にいる使用人たち一人ひとりへ穏やかな微笑みを向ける。誰もが言葉を失い、そして胸を痛めていた。
こうしてアルタリア・カリスタは、ほんの数日前まで“王都の薔薇”と呼ばれ、将来を嘱望されていた身ながら、一転して宮廷からも伯爵家からも疎まれ、ついには追放される運命を余儀なくされたのである。
――冷たい雨は夕刻になっても止まなかった。彼女がわずかな荷物をまとめ、伯爵家の門を出る頃には、空は灰色に覆われ、街の喧騒すらも弱まっているように感じられた。傘をさす手は震え、雨滴が彼女の頬を濡らす。涙と雨が混じり合っても、果たしてどちらがどちらか分からないほどだった。
外套のフードを深く被り、宿屋へ向かって歩き始める。貴族令嬢として育ってきた彼女に、外での生活は未知そのものだ。どのように身を立て、何を糧に生きていけばいいのか――考えは尽きない。けれど、ここから先は何者にも守ってもらえない自分だけの道だ。人生のすべてを自分の力で選び取っていかねばならない。
ふと、顔を上げると、雨の帳の向こうにわずかな月明かりが垣間見えた。
(私の人生は、あの人たちの思うままにはならない。こんなことで終わってたまるものですか)
泥濘んだ石畳を踏みしめながら、アルタリアは歯を食いしばる。誇りは失わないと決めた。追放された今だからこそ、彼女は自分が何を成せるのかを、これまで以上に真剣に模索し始める。
婚約破棄。追放。
嘆き悲しむだけでは自分を守れないし、未来を築くこともできない。いつか、この仕打ちを受けた分をそっくり返してやる――そんな強い意志を固め、アルタリアは雨の中を歩み続けた。
まだ見ぬ地で彼女が出会うものは、絶望か、それとも新しい希望か。それは誰にもわからない。けれど、少なくともアルタリアの心の奥底には消えぬ灯火がある。くすぶっていた想いが吹き上がるように、逆境の中で彼女は力を蓄えていくことになるだろう。
これまで穏やかで安定した人生を送ってきたアルタリアが、初めて自らの意思で未来を切り開いてゆく物語が、今、幕を開けるのだ。
1
あなたにおすすめの小説
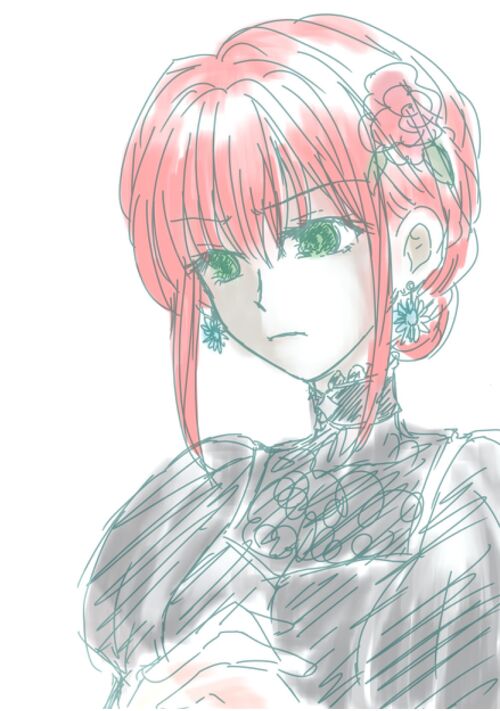
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

偽りの愛の終焉〜サレ妻アイナの冷徹な断罪〜
紅葉山参
恋愛
貧しいけれど、愛と笑顔に満ちた生活。それが、私(アイナ)が夫と築き上げた全てだと思っていた。築40年のボロアパートの一室。安いスーパーの食材。それでも、あの人の「愛してる」の言葉一つで、アイナは満たされていた。
しかし、些細な変化が、穏やかな日々にヒビを入れる。
私の配偶者の帰宅時間が遅くなった。仕事のメールだと誤魔化す、頻繁に確認されるスマートフォン。その違和感の正体が、アイナのすぐそばにいた。
近所に住むシンママのユリエ。彼女の愛らしい笑顔の裏に、私の全てを奪う魔女の顔が隠されていた。夫とユリエの、不貞の証拠を握ったアイナの心は、凍てつく怒りに支配される。
泣き崩れるだけの弱々しい妻は、もういない。
私は、彼と彼女が築いた「偽りの愛」を、社会的な地獄へと突き落とす、冷徹な復讐を誓う。一歩ずつ、緻密に、二人からすべてを奪い尽くす、断罪の物語。

不機嫌な侯爵様に、その献身は届かない
翠月 瑠々奈
恋愛
サルコベリア侯爵夫人は、夫の言動に違和感を覚え始める。
始めは夜会での振る舞いからだった。
それがさらに明らかになっていく。
機嫌が悪ければ、それを周りに隠さず察して動いてもらおうとし、愚痴を言ったら同調してもらおうとするのは、まるで子どものよう。
おまけに自分より格下だと思えば強気に出る。
そんな夫から、とある仕事を押し付けられたところ──?

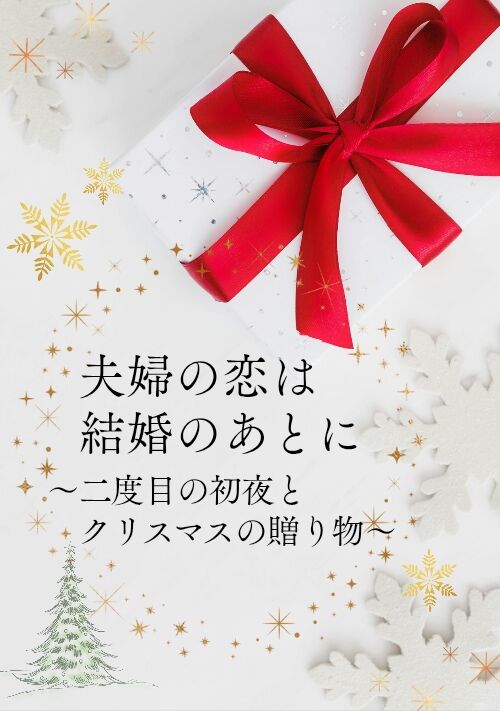
夫婦の恋は結婚のあとに 〜二度目の初夜とクリスマスの贈り物〜
出 万璃玲
恋愛
「エーミル、今年はサンタさんに何をお願いするの?」
「あのね、僕、弟か妹が欲しい!」
四歳の息子の純真無垢な願いを聞いて、アマーリアは固まった。愛のない結婚をした夫と関係を持ったのは、初夜の一度きり。弟か妹が生まれる可能性は皆無。だが、彼女は息子を何よりも愛していた。
「愛するエーミルの願いを無下にするなんてできない」。そう決意したアマーリアは、サンタ……もとい、夫ヴィンフリートに直談判する。
仕事人間でほとんど家にいない無愛想な夫ヴィンフリート、はじめから結婚に期待のなかった妻アマーリア。
不器用な夫婦それぞれの想いの行方は、果たして……?
――政略結婚からすれ違い続けた夫婦の、静かな「恋のやり直し」。
しっとりとした大人の恋愛と、あたたかな家族愛の物語です。
(おまけSS含め、約10000字の短編です。他サイト掲載あり。表紙はcanvaを使用。)

完結 愚王の側妃として嫁ぐはずの姉が逃げました
らむ
恋愛
とある国に食欲に色欲に娯楽に遊び呆け果てには金にもがめついと噂の、見た目も醜い王がいる。
そんな愚王の側妃として嫁ぐのは姉のはずだったのに、失踪したために代わりに嫁ぐことになった妹の私。
しかしいざ対面してみると、なんだか噂とは違うような…
完結決定済み

サレ妻の娘なので、母の敵にざまぁします
二階堂まりい
大衆娯楽
大衆娯楽部門最高記録1位!
※この物語はフィクションです
流行のサレ妻ものを眺めていて、私ならどうする? と思ったので、短編でしたためてみました。
当方未婚なので、妻目線ではなく娘目線で失礼します。

呪いを受けて醜くなっても、婚約者は変わらず愛してくれました
しろねこ。
恋愛
婚約者が倒れた。
そんな連絡を受け、ティタンは急いで彼女の元へと向かう。
そこで見たのはあれほどまでに美しかった彼女の変わり果てた姿だ。
全身包帯で覆われ、顔も見えない。
所々見える皮膚は赤や黒といった色をしている。
「なぜこのようなことに…」
愛する人のこのような姿にティタンはただただ悲しむばかりだ。
同名キャラで複数の話を書いています。
作品により立場や地位、性格が多少変わっていますので、アナザーワールド的に読んで頂ければありがたいです。
この作品は少し古く、設定がまだ凝り固まって無い頃のものです。
皆ちょっと性格違いますが、これもこれでいいかなと載せてみます。
短めの話なのですが、重めな愛です。
お楽しみいただければと思います。
小説家になろうさん、カクヨムさんでもアップしてます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















